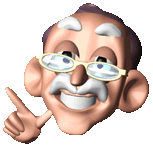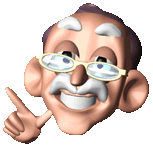|
|
幼時の遊びが趣味に
繋がっているか! |
幼児期の遊びが、その後の趣味になっていることは疑う余地もない。ただ、趣味として継続できない遊びも多くあることも事実である。自分の幼児期はテレビも無く、大自然のなかで、水や小鳥や魚を相手に遊びを探すと言う生活であったように思う。
幼児期の遊びで特に記憶に残るものは、
1) メジロの捕獲と飼育
ここ千葉地方では一年中人里近くで生活しているメジロ(冬には我家の庭にも頻繁に訪れるし、真名CCでは年中その美しい鳴き声を聞くことが出来る)が、鹿児島地方では海抜数百メートルの山で産卵・孵化し、秋になると成鳥となって里に下りてくる。夏に山に登って捕獲すると飼育しやすい幼鳥を手に入れることが出来るのだが、それは子供達にとっては容易なことではない。里に下りてきた後で捕獲していた。
この遊びでは、多くのことを学んだ。メジロを捕獲するための手段、長生きし良い泣き声を出すための餌の工夫、鳥篭の作り方、などなど幼い頭を多いに駆使した。特に、鳥篭の作り方はその後の工作への興味につながり、大袈裟に言えば大学で建築学を専攻することに繋がったとも考えられる。籠の製作に使ったナイフやキリまでも、その殆どが手製のものであった。
また、小鳥の捕獲は飼育が目的のメジロ以外のヒヨドリなどは食用にするための自然の材料を使った罠を利用して捕獲なども多いやったものである。
2) 魚釣り
これに関しては、「釣り」の項に記載したので参照。
3) 絵描き
これは遊びと言うべきか、否かは別として、幼いころにも絵は良く描いた。これも、「絵画」の項に記載した。
4) 海<海水浴と磯の貝採り>
小学校、中学校にはプールがない時代。水遊びの大部分は海であった。海で速くはないが長い時間浮いておれる泳ぎを身につけた。また、砂浜でのハマグリやアサリだけでなく、数キロメートルで磯にも行けて、そこでアワビやトコブシ、サザエなどの貝採りも遊びの一つとなっていた。
5) 木登り
放課後に友人たちが集まって、1時間、2時間またはそれ以上の時間を木の上で過ごすと言う遊びもよくやった。今思うと、サルの仲間かと疑いたくなるほどに木から木へと移動しながら長時間を木の上で過ごした。魚釣りや小鳥採りのような獲物を求める遊びではないが、何の道具も必要ない手頃の遊びだったと言うことであろう。
6) ベーゴマ、ビー玉、バッタなど
ベーゴマは、市販の金属製のものよりも、ばい貝という巻貝の殻を利用したものが主で、子供ながらも色んな工夫を加えて、戦いに強いベーゴマを作り上げていた。
<2008年1月 記>
|
ゴルフは何時まで
出来るか!

|
60歳を越したゴルファーにとっては、これから如何にスコアを良くしてHCを改善するかということよりも、何歳まで元気にゴルフが出来るだろうか、というのが最大の関心事になってくるようである。隠居にとっても、そのことは変わりない。
シングルHCになったのが61歳を数ヶ月過ぎたころであり、68歳直前の今でも大幅に力が落ちたという実感はない。周囲を見れば、73,4歳を境に急激に力が落ちてくる傾向が強いようにおもわれる。それまでには数年の猶予があり危惧することでもないが、個人差が激しいことも事実である。
隠居が所属する幾つかのゴルフの会での現役最年長プレイヤーは83歳、ほほ毎週2回のプレイをこなしており、まだまだ現役続行の可能性が高い。その他でも、病で他界した数少ない例を除いて、ここ数年の間に体力の限界を理由にゴルフを止めた人物は隠居の知人のなかでは皆無で、80歳代のプレイヤーの数も増えてきつつある。
今は亡くなったが、かって真名CCには「内田 祥三」という怪物と称すべき人物が在籍された。 同氏は、一日でプレイしたラウンド数の世界記録(ギネスブックに登録されていると言う)も樹立され、99歳で亡くなる1年前までは元気でプレイ(隠居も同伴したことがある)されていた。他に、100歳でプレイされる猛者もテレビで紹介されたこともあるが、これらの特殊の人達は例外として、平均的なプレイヤーでも病に見舞われなければ80歳くらいまではプレイできそうである。
このような環境を勘案すると、予期せぬ病の発症などのような突発事故のない限り、自分でも80歳までは何とかなるのか、と期待(と言うより願望と言うべきか)するようになってきた。最近10ヶ月間のブログのテーマをみてみたら「ゴルフ」が90回でダントツの1番で、2番の「花」の42回を大きく離しているように、ゴルフが最大の趣味(ゴルフ馬鹿と称されよう)となっている現状から、健康管理を兼ねたゴルフのプレイが何時まで続けられるかは、隠居の今の大きな関心事なのだ。
最近、一緒にプレイする機会が多い友人が狭心症の再発で血管バイパス手術をすることとなり、同病の経験者として些か気になることもあるが、特に気になるような症状もないので、先ずは75歳までは事無くプレイが楽しめるであろうと期待はしている。ただ、寒い冬場を注意して乗り切らねばなるまい。
<2008年1月 記>
|
釣りは生活の糧と
なり得るか!
 |
左記したタイトル(生活の糧になり得ることはないと分かっている)は別として、好きな釣りのことについて少し整理しておきたい。
釣りを始めたのは、家の近くの小川での幼児期の手長えびと鮒釣りからであると言えよう。終戦後の物資の乏しい当時は、釣具も満足に手に入れることは難しかったが、母親の縫い糸を柿渋などを浸み込ませて強くして釣り糸として使ったことは記憶している。釣り上げた獲物は、食糧難お時代でもあったので、囲炉裏の火で乾かして干物状にしてから、食用に調理した。
幼児期には、海釣りの経験は全く無い。海の魚は、もっぱら地引網ひき(祖父の兄に当る人が網元で、地引網用の船にも良く乗せてもらった)に参加して手に入れていた。このような環境に育ったので、海魚に不自由することは無く、また自ら魚をさばく術も何時しか身についていたように思う。
その後、大学時代には下宿の近くを流れていた川での「オイカワ」釣り、卒論のための実験を泊り込みでやった施設沿いにあった貞山堀や松島湾での「ハゼ」釣り、「カレイ」釣りなどが記憶に残っているが、頻繁に釣りに出かけてと言うことではない。
本格的に海釣りを始めたのは、会社に入って千葉に居を構えて数年が経ってからである。会社の同僚を仲間に引き込んで、今熱中しているゴルフには目もくれず、ほぼ毎週末に1泊2日のペースで、主として内房の富浦の「竹の家旅館」、外房の大原の「勇盛丸」、外川の「友丸」という船宿を基地として、マダイ、ハナダイ、イサキ、イナダ、カンパチ、ヒラメ、アイナメ、その他の五目など等を釣り歩いた。金曜日の夜に船宿に宿泊して土曜日に船釣りというパターンであったが、土曜日の釣果が思わしくないとさらに1泊して翌日も釣りに興じる(妻にはその都度、苦情を言われながらも)ということも何回かあった。会社の釣部の幹事役も何年も務めて、団体での釣行も企画したり、会社の文体会用の予算の獲得にも奔走したりと、釣りに関しては労を厭わなかった時期もあった。また、ある時期には、友人と共同で5馬力の船外機付のボートまで購入して釣りに使ったものである。
釣りでの一番の思い出は、神津島の磯での2夜連続のイサキ釣りであろうか。2夜寝ないでの釣りで、多少の危険も感じたうえに体力的にもきつかったが、持ち帰れないほどの釣果もあった。
このような釣り狂いの生活は1980年末頃まで続いた。釣りを止めてゴルフに転向したのは母と妻の強い要請があってのことである。郷里の近くの内之浦(人工衛星用ロケットの発射基地として知られている)の磯で関西方面から来訪する釣り人の遭難事故が多発していたこともあって、上記したような船釣りだけでなく、神津島などの磯での夜釣りなどもやるようになっていたので、遭難事故を危惧した母と妻の涙ながらの懇願が繰り返されることとなった。2,3年に亘って繰り返された懇願におれて釣りを断念して、ゴルフに転向することとした。
この時に釣具も総て処分したので、その後は全く釣りはやっていない。実際は、ゴルフに熱中するようになって、釣りとゴルフの両方を追いかけるだけの時間的な余裕がなくなったということかも知れないが。ただ、釣りに興味がなくなったということではなく、新聞や雑誌の「釣り情報」には、良く目を通すし、海岸や岸壁などで釣り人を見かけると暫し覗き込んでしまうことも度々である。そして、鹿児島地方の新聞である「南日本新聞」の週間釣り情報も、ほぼ毎週パソコンで覗き込んでいる。
いま、鹿児島など釣りの条件(多くの釣果が見込まれるなど)が整っている場所に移住することがあるとすれば釣りを再開したいという願望は煮えたぎっている。
<2008年1月 記>
|
庭いじり、盆栽は老人の
特許か!

鉢植えの藤
<1970年前後に鹿児島の実家から移植、鉢植えで育てている>
|
庭いじりや盆栽の手入れなどは老人のすることと思われがちであるが、そういうものでもない。これらは、自然に恵まれた田舎育ちの自分にとっては、幼い時期から興味をそそられるテーマであった。
特に、高校生及び大学生の頃の春休みや夏休みには、実家の庭の模様替えを庭師と一緒になって計画し、木々の植え替えなどの作業するなど、庭については執着した。当時、魚を飼うことも考えて、自分ひとりで「池造り」を何回か試みたが、水漏れを防止できずにこの試みは総て失敗に終った。とにかく、草花や木々を育てること、庭をいじることは生来好きであったようだ。
会社に入って間もない頃から、公団の賃貸住宅の1階に住みながら、ベランダはサツキ(自ら挿し木で増やすことも多かった)の植木鉢で溢れていた。初めて持ち家に住んだ1975,6年頃から、サツキを中心に、山野草や松なども加えて一時期には約400の鉢物を育てていたこともあった。国交回復後の1973年ごろに頻繁に訪問した中国出張時には、古い植木鉢を探して持ち帰る(妻に土産はいつも植木鉢と嘆かれた)ほどの熱の入れようであった。サツキの花後の手入れは、会社から帰った後の夜の仕事とで忙しい日々を過ごしたものである。
しかし、海外出張が多くなってきたことと、ゴルフが忙しくなってしまったことで、盆栽熱は徐々に冷めてきて鉢数は徐々に少なくなり、今はサツキ、松、藤その他で20鉢足らずとなってしまった。「隠居したら盆栽の復活を!」という思いは続いていたが、未だに実現はしていない。徐々に体力的なことも考慮しなければならないので、「ミニ盆栽」などが適していると考えるが、一日に何回も水遣りが必要で、旅行もままならないので容易に手が出せないのが実情である。
庭についても興味は薄れていない。初めて家を持った時も、転居後の今の家を購入する時も広い庭が確保(75坪の敷地の半分近くをオープンの駐車スペースと庭で活用)できることを条件にして、そこそこに庭いじるが出来る環境は整えてきた。最初の家では、水の浄化装置も備えた4,5平方メートルほどの池も作って鯉も飼ってみたが、病気の予防が上手くいかず、途中からは睡蓮用の池と化してしまうという失敗もしているが、退屈しのぎの玩具としての効果は十分にあった。
今の庭も、娘からみれば手入れや草取りに不満(隠居自信も十分に自覚している。ただ、有難いことに、娘は隠居と同行した2007年のニュージランド旅行で、草花だけではなく植木を中心とした庭造りも魅力的なことを知ったことを契機に、この庭に大きな関心と愛着を抱くようになった)はあるようであるが、隠居は元々からそこそこに満足している。
庭の植木は松や楓などの他に、花物はサツキ、ツツジ、石楠花、ギボウシ、えびね、あやめ、クレマチス、アジサイ、水仙、バラ、ヒマラヤ雪ノ下、百日紅、ツワブキなど、果実をつける木は大きな柿の木、びわの木、石榴の木、金柑の木など、実付き楽しむ小木はピラカンサ、南天、マンリョウなど、実に雑多な物が所狭しと植え込まれている。中でも、柿と石榴は、この地への転居時に前の住居から移植したものであり、強い愛着を抱いており、ここからの転居を考える時にその処置に頭を悩ます対象(転居を思い止まらせる効果もある)である。
ただ、柿、石榴、松などの高い場所での手入れは老人にとっては危険性も伴うことであり、ボツボツ難しくなってきており、何時まで続けられるか疑問ではある。これらを勘案して、2007年の年末頃に、特に柿も石榴も思い切って枝を切り落とした。
<2008年1月 記>
|
絵画は血筋か!

秋の実り
|
小学校の教師を勤めた母の一番下の弟が絵画の教育の面でそこそこの業績があったこと、母のすぐ下の弟の子供(隠居の従兄弟に相当)が美大を出て絵描きを本業としていること、などの環境からも絵画に対する興味とセンス(血筋か?)は幼いころからあったように思う。
しかし、それ以上に絵画に対する興味を強め、技術的にも進歩できたのは、服部(?60年以上前の話で名前は不確かであるが、ここでは服部としておこう)先生の存在である。服部先生は、本業は養蜂家で、春の「レンゲソウ」や「菜種」の花が咲くころに蜂を連れて当地を訪れ、2,3ヶ月滞在するという生活を数年続けていた。養蜂家との兼業画家であったのか、単なる趣味で絵を描いていたのかは知る由もないが、素晴らしい画家であったことは間違いない。先生の指導を得て、兄と共に画板を並べて、同じ場所の風景画を数年描き続けたことが我々兄弟の技術のレベルアップに大きく貢献した。
小学校時代には、地元紙の「南日本新聞」、「西日本新聞」、「読売新聞九州版」などの主催する展覧会も多く開催されており、それらに応募して度々入選・表彰されるという栄誉も頂いた。しかし、中学校の1年生頃を最後にこのような展覧会への応募の記憶もなく、従い入賞の栄誉の記憶もなく、高校時代にも「絵画部」に席を置いたりしたしたものの、これといった作品もないまま今に至っている。
ただ、絵画に対する興味を失うことはなく、その後も種々のテキスト(特に水墨画、水彩画)や、絵具や筆などを含めた画材の購入など、いつでも絵描きを再開できる準備は怠らないできたが、筆を手にせず数十年が経ってしまった。兄(油絵)と弟(水彩画)は、ここ数年意欲的に絵画に取り組んでおり、それぞれ美術展で入賞したり、個展を開いたりという状況にある。両人からも、「幼児期には、お前が一番実績があるのだからーー」ということで、筆を持つように勧められているが、気持ちはあれどもゴルフにかまけて手がついていないという状況は変わらない。
ようやく、2007年の後半になって、先ずはカルチャースクールできっかけをつくるべきかと思い、家の近くで開催される絵画教室を何回か見学させてもらったりしたほか、凄く簡単な2,3枚の水彩の静物画を描いてみたりしたのだが、本格的な絵画再開(あまりにも時が経ち過ぎているが)にはなかなか踏ん切りがつかないままに現在に到っている。まだ諦めたわけではなく、この春が最後のチャレンジとなりそうである。
<2008年1月 記>
|