チョコレートを君に
「じゃ〜ん!」
誇らしげにアリスが手にしているものを見て、思わず頭を抱えたくなった。
―いや、実際抱えたのだが。
くらくらとさえする頭を支えるようにして、こめかみを押さえると不思議そうな面持ちをしたアリスが首を傾げて覗き込んできた。
「なんや、火村?どないしたん?」
「…いや、アリス。それ…」
情けないことに指示そうと伸ばした指は、細かく震えてさえ居る。あまりの驚きに声も出せないとはこの事だな。などと、冷静を装ってみるも、無駄。無意識に一人問答をしてしまう俺の様子など、マイペースに話すアリスには気がつく筈もなく。
「あ、コレ?なんや、うれしかったんか?そんなに喜んでもらえると嬉しいなぁ。ネットで頼んでからずいぶん待ったんやで?よかったな!」
人の表情をどう履き違えたのか、溢れんばかりのほほ笑みを浮かべるアリスは、ん!と軽く顎をしゃくると小さな箱におさまったソレを差し出してくる。その、突き出された唇に吸いつきたくなる衝動を抑えると、大きくひとつ、息を吐いた。
アリスと過ごすようになって、もうずいぶんになる。
長い間の友人関係を経て、気がつけば誰よりも傍に居る、そんな関係になっていた。
―気がつけば…?
それは、間違っているかもしれない。なぜなら、少なくとも俺は、出逢ったときからおそらくはアリスに心を奪われていたのだろうから。でなければ、見も知らぬ赤の他人になど、自ら声を掛けたりしないからだ。今も、もちろん、学生の頃も。
あの階段教室で、隣に座っていたのが偶然だったと。アリスはきっと思っている。
偶然、では、無い。
すれ違いざまに、「有栖川」と、名前を呼ばれた華奢な男が、それはもう、底抜けに明るい笑顔で笑っていたのを見かけた事があった。陽の光を一身に浴びて、少し茶みがかった髪がきらきらと輝いて見えた。それから見かける彼の姿はいつだって同じだ。誰とでも馴染み合い、何処へいっても誰かが傍に居る。誰だって彼を知っている。きらきらと輝く光にさながら、虫が集まってくるように、彼の周りには誰かが居た。
ああ、自分とは違う、世界の違う生き方をしている人間なのだと思っていた。
その、彼が。
誰もいない、校舎の陰でなんの表情も載せず、呆けているのを知ってしまったからだろうか。話をしてみたい、と思って隣に腰をおろしたのは。履修、していない他学部の授業にもぐりこんでまで。
―気がつけば、親友と言われる位置に俺は居た。
いつからだろう、アリスに対しての思いが友情なんかじゃ無いということに気がついたのは。…長い、忍耐期間だったな。
紆余曲折を経て、今に至るというわけ………。
「…むら、火村!」
「あ、ああ…。なんだ、どうした?」
はっと顔をあげると、呆れたような表情で見つめるアリスのアップが目の前にあった。
「どないしたん?具合でも悪いんか?」
ああ、まずい。思考が遠くへ行っていたようだ。…アリスじゃあるまいし。
「いや、なんでもない。それより、コレを俺にどうしろと?」
差し出されたままの箱を指さして尋ねるも、当然といったように返ってきた言葉に不思議と乾いた笑いが漏れていた。
「は?食べるものや。なんや、君、ほんとに大丈夫か?」
「アリス、そんな事はわかっているが、どうしてそんな物があるんだって事だ。お前、それをどうした?」
リビングの中央あたり、ソファからも離れていたのだが、ソファまで移動する気にもならずそのまま腰を下ろすと、へたり、と器用に関節を折り曲げて座るアリスは白い指で箱の中身を一つぶ摘み嬉しそうに持ち上げた。
「ほら、見てみい!凄いやろ?ネットで注文しといたんや。前になんかでコレの特集してんの見てな、速攻で頼んだんやけど今になってもうた。なんや、人気あるんやな」
「…へえ。それはご苦労な事で。それがなんで俺なんだ?」
同じ目線で、指で摘まんだソレをかざしてアリスは悪戯っぽそうに瞳をキラキラさせて、箱にぎっしりと詰められた茶色い粒を床に並べる。
「ほら。見て、火村がいっぱいやで」
答えることなく、中身をすっかり取りだしたアリスは嬉々として、そのひとつの包装をはがして俺の口元へ運ぶ。
「ほら、あ〜ん、や」
唇を開け口に含むと、少し冷たいソレはすぐに溶けること無く、それでも確かな甘さを伝える。
「甘い…」
「当たり前やろ、チョコレートなんやから」
どこか懐かしいキャラメル包みの小さな粒チョコは、ほどなく溶けて無くなった。
床に並べられたチョコレートを見て、いささかげんなりする。箱で買った事に対して、だけではない。問題はもっと別のところにあるのだ。
「アリス、で?なんで、俺?」
「いやぁ…、ほんとはな?モモ達にしようと思ってたんや。ほら、そしたらきっとかわええやろ?でもなぁ…」
話しながらも意識は手元にあるようで、アリスはぺりぺりと包装をはがし、今度は自分の口へ含む。
「うん、懐かしい感じや。甘くておいしいなぁ。でな、思ってたんやけど、写真が無かったから仕方なく諦めたんや。そこで!手元にあった君の写真を送ったいうわけや。ほら、こっちのほうがおもしろいやろ?」
チョコレートを口に含んだまま、もごもごと話していたが、あっという間に食べ終えたのだろう、もう次の包装を破いている。
ソレは見事にひとつひとつに、俺の顔が印刷された粒チョコを。
「おもしろい、だと?写真が無かったのならアリス、お前の顔にすればよかっただろう!コレ、いつの写真だ?…ああ、夏に旅行に行った時のじゃねぇか。あ?ちょっと待て。旅行に行く前、下宿でモモの写真は撮ってたよな?」
「あ、バレた」
バレた、と言うものの、ちっとも悪びれた様子もなくアリスはまたひとつ、包装を開けた。
確信犯か…!
冷えていたチョコも室温で柔らかくなり始めているのだろう、摘まんだ指先に付いたチョコを舐めとる仕草が妙に艶めかしい。
「ほら、ハロウィンやし、ちょうどええやん?余ったら、研究室に差し入れでもする?」
「…アリス。お前は俺が他の人間に食べられてもいいんだな?」
「ん?」
先ほどまでと打って変わって落ち着いた声に顔をあげると、薄い笑いを口の端に乗せた火村がじっとこちらを見つめていた。なにやら、雲行きが怪しくなってきたような気がして、思わず上半身を引くと、追いかけるようにして火村が半身を乗り出してきた。
う、良くない顔をしてる気がする…。
アリスの不安をよそに、楽しそうにすら見える火村は、床に散らばったチョコを一つ摘まむと
印刷された写真をしげしげと見つめ、アリスの前にかかげて見せた。
「ほら、俺の顔が印刷されてる。つまり、他の誰かが俺を食べてしまうってことだろう?」
「…ん?」
じりじりと動く火村に押されるようにして逃げるも、いつの間にか被さる様にして反った身体の上に火村が覆いかぶさっていた。後ろ手に上半身を支える腕が痛い。
「アリス、お前はそれでもいいんだな?」
目の前で深い漆黒の色を湛える瞳に吸いこまれそうになりながらも、無意識に首を横に振っていたらしく、その動きに体重を支えていた腕が限界だった。
「…っ、あ」
かくん、と折れた腕に続いてくるであろう後頭部への衝撃を予想して、思わず目を閉じるも、思っていた痛みは無く、その代わりに柔らかく温かい火村の手のひらを感じた。どうやら落ちる前に受け止めて支えてくれたらしい。そのまま、ゆっくりと下ろされる。
「…それは、嫌、かも」
「だろ?だから、責任持ってお前が全部食べろよ?代わりに俺がアリスを食べてやるから」
「はっ?」
想定外の展開にあわてて身を捩るも、いつの間にか火村の手のひらはTシャツを捲り上げるようにして素肌に添えられている。
「な、関係ないやろ。って、火村!」
がっちりとホールドされた身体は少し捩ったくらいでは抜け出ることなく。煩そうに手を止めた火村は事もなげに言い放った。
「じゃあ、アリス。お前が「俺」を食べてくれるのか?そういうことなら、喜んでポジションチェンジするんだがな」
一瞬、火村の言わんとしていることが分からず、ポカンとしてしまったが、意図を理解した途端とんでもない羞恥に襲われ一気に頬が紅潮するのを感じる。
「…それは、無理、や」
あまりの恥ずかしさに、ぽそりと呟くと、火村は少し残念そうに眉を片方あげ、止めていた手を伸ばして床に散らばったチョコレートを摘み、口元へと運んだ。素直に唇に咥えると、甘い香りが鼻腔を刺激する。
「甘いだろ?アリス」
ん、と声にならない返事をすると、優しい火村の口付けが頬に落ちてきた。思わず、手を伸ばして背中に触れる。
それを合図のようにして、未だ溶け切らないチョコレートが口に残るキスをした。
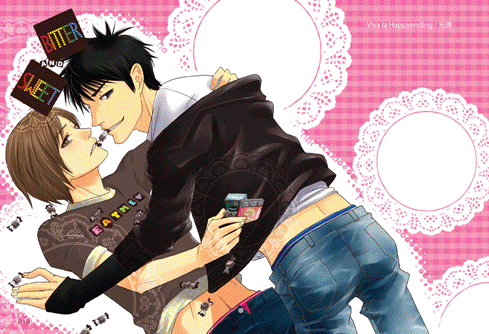
怪人館のMUTTA様に書き下ろして頂いた素敵な表紙で、2009年オンリーで発刊した「Bitter&Sweet」に収録したお話です。続きはR18ですのでご注意ください。 Author by emi