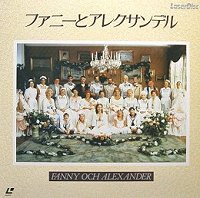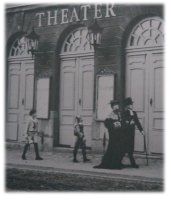| CinemaBox③ 特集:ファニーとアレクサンデル |
Fanny och Alexander
ファニーとアレクサンデル
ファニーとアレクサンデル
| 今回のCinemaboxは、スウェーデンの巨匠イングマール・ベルイマン監督の最高傑作にして最後の劇場作品『ファニーとアレクサンデル』の魅力について紹介していきます。 |
|Back|
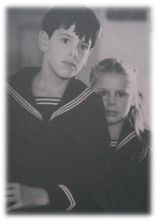 | 1982年作品 スウェーデン=フランス=西ドイツ合作 上映時間 310分 モノラル ヨーロピアン・ビスタ(1.66:1) |
| Index ■LD版ジャケット ■作品解説 ■キャスト/スタッフ紹介 ■物語解説 ■ベルイマン「ファニーとアレクサンデル」を語る ■受賞歴 ■DVD | |
| *本コンテンツの解説文は全て「ファニーとアレクサンデル」LD版に封入されている解説書を元に作成されています。 | |
| 注>物語解説は映画を観た後で閲覧する事を強くオススメ致します | |
|
|
||
| レーザーディスク版ジャケット画像、表(左)裏(右) [一番上へ] |
|||
作品解説
| スウェーデンの生んだ世界的巨匠イングマル・ベルイマン監督の大作である。この映画の完成後、ベルイマンはまだ64歳(83年当時)という年齢なのに、今後演劇活動は続けるが、映画は撮らないと宣言した。理由は「映画作りの面白さを味わいつくしたから」と、彼は語っている。したがって「ファニーとアレクサンデル」は、映画との訣別をこめて作られた、ベルイマン最後の映画作品ということになってしまった。 ベルイマンは、日本で公開されたオリジナル版(上映時間・5時間11分)で劇場公開を考えていたが、あるプロデューサーから、上映時間が長すぎて興行が難しいといわれ、結局3時間8分の短縮版を編集した。本国スウェーデンでは、82年のクリスマスに短縮版が公開され、オリジナル版は翌83年にTVで放映された。アメリカやヨーロッパ、その他の国でも短版で劇場公開され、アメリカ・アカデミー・最優秀外国語映画賞をはじめ、各国で多くの賞を受賞した。 ところが、83年ヴェネチア国際映画祭でオリジナル版が特別上映されるや、映画祭に集まっていた各国の映画批評家たちによって、短縮版よりもさらに高いその完成度がたちまち評判になった。こうしてある都市(ストックホルム、パリ)の劇場ではオリジナル版による再公開がおこなわれた。 このオリジナル版は、プロローグとエピローグをともなう全5部の構成。スウェーデンの古い大学町ウプサラ(ベルイマンの生まれた町でもある)の劇場のオーナーで、富裕なエクダール家の1907年の華やかなクリスマス・パーティーから話が始まる。そしてエクダール家の3代にわたる家族をめぐって、多彩な人物が登場、約2年間にわたるドラマが展開する。そこには、ベルイマン本来のテーマである男女の愛憎、宗教者に対する批判、さらには明らかにベルイマンの自伝的要素を思わせる部分や、芸術、演劇に対する愛好の念などが巧みに織りこまれ、さながらベルイマン芸術の集大成といった感がある。また、スウェーデン映画史上最大の制作費が投じられたといわれるだけの豪華なセットや、せりふのある役だけでも60人近い登場人物という、これまでのベルイマン映画には見られなかった、スペクタクルな映画でもある。
重要なエミリー役を好演したエヴァ・フレーリングは当時まだほとんど無名で、多くの新聞は「意外なキャスティングで、彼女には大変な好運だ」と書きたてた。しかし彼女は自分の才能をこの役で証明して、続いてベルイマン演出の舞台「リア王」でも次女リーガンという重要な役を演じている。 そのほかの出演者には、これまでのベルイマン映画でおなじみの俳優が多数出演している。「夏の夜は三たび微笑む」「第七の封印」「野いちご」「秋のソナタ」のグンナー・ビューンストランド、「女はそれを待っている」「叫びとささやき」「ある結婚の風景」「鏡の中の女」「秋のソナタ」のエルランド・ユーセフソン、「不良少女モニカ」「夏の夜は三たび微笑む」「叫びとささやき」のハリエット・アンデショーン、「夏の夜は三たび微笑む」のヤール・クッレ、「秋のソナタ」のマリアンヌ・アミノフ、「冬の光」「処女の泉」のアラン・エドヴァルなどがそうである。またクリスティーナ・スコウリーンは、かつてのスウェーデン美人女優の1人で、「天使なんかあるものか」(60)、「歓び」(64)など数本の主演作でわが国で知られている。アンナ叔母役のケービ・ラレティは本業はピアニストで、60年前後にベルイマンの4番目の妻であった。彼女は「秋のソナタ」などで実際のピアノ演奏を受け持ち、離婚後もなおベルイマンの協力者である。 スタッフはほとんど常連のいわゆる"ベルイマン一家"。スヴェン・ニクヴィスト(「道化師の夜」以来数多くのベルイマン映画の撮影を担当、世界的に有名になった)、アンナ・アスプ、、マリク・ヴォスは、この作品でそれぞれアメリカ・アカデミーの撮影賞、美術賞、衣裳デザイン賞を受賞した。 製作総指揮のヨーン・ドンネルは、「愛する」(64)などの監督で、早い時期にイングマル・ベルイマン研究の基本文献となった、ベルイマン評伝「悪魔の眼」(62)を書いている。 |
[一番上へ]
| ||
|
物語解説
プロローグ
大邸宅の一室でただ1人、人形芝居に興じる少年アレクサンデル・エクダール。夢みるような黒い瞳の彼は、実際に彫像が手を動かしたり、幽霊が現れたりするのを目撃することができる 幻視力の持主である。 傑作と言われる作品はオープニングからワクワクさせられるものですが、本作はその中でも最上級と言っても良いくらい魅惑的な映像世界を見せてくれます。最初に画面に映る穏やかな川面の描写(章の始まりには全てこの川面の映像が挿入されている)とバックに流れる優雅な音楽が早くも作品への期待を高めてくれます。そして画面は室内に移り、人形劇で遊ぶアレクサンデル少年が映し出されます。その大きくて黒々とした瞳はまさに男版アナ・トレントと言った感じの強烈な印象で、自分はここで一気に作品世界へと入り込んでしまいました。 暇を弄んでいたアレクサンデルは誰もいない部屋のテーブルの下へ寝そべり物思いに耽ります。すると・・・ここから映画は鮮やかな魔術を示し始めます。静寂の中時計の秒針音だけが聞こえ針がやがて3時を差します。するとオルゴールがそっと鳴りだし、時計に付いている仕掛け人形がゆっくりと回り始める・・・。何かを感じたアレクサンデルが辺りを覗います。暫く経つとシャンデリアに風が当たったのか、すぅーっと横に小さく揺れ始め、シャンデリアの装飾物が擦れてチリリチリリっと微かな音を立てる・・・。すると突然奥にある裸体像がゆっくりと動き出し、部屋の片隅には死神らしき異形の者が姿を現します。そしてそれはアレクサンデルのビジョンであることが分かります。彼は特殊な力を持った少年だったのです。・・・いや~あまりに素晴らしいので思わず詳細に説明しちゃいました(笑) まるで異空間に迷い込んだかのような不思議な感覚に襲われてしまうほど静謐と緩やかな時間の流れだけが画面内を支配する芸術的な映画演出!言葉ではとても言い表せない感動がこのシークエンスにはあると思います。メイドが暖炉に石炭をくべる音(かなり激しい音でビックリする)で観る者を一気に現実世界へ引き戻すところも実に心憎い演出です。 |
第1部
エクダール家のクリスマス
エクダール家のクリスマス
スウェーデンの地方都市ウプサラ。1907年のクリスマス・イヴ。富裕な俳優で劇場主のオスカル・エクダールは吉例のキリスト降臨劇を上演中である。妻で女優のエミリー、彼らの子供アレクサンデルとその妹ファニーも出演している。幕がおりるとすぐさま舞台にテーブルが運ばれ、俳優と裏方のためのクリスマス・パーティが始まる。席上、オスカルは「私のただ一つの取柄は、劇場というこのささやかな世界を愛していることだ。 この小世界は時に外の大世界を写し出し、そしてほんのひと時外の世界の憂さを忘れさせるのだ」と挨拶する。 そのあとエクダール一家は自邸に戻り、土地の名士や親しい友人を招いてディナーの会をひらく。その中心人物はアレクサンデルの祖母ヘレナで、彼女ももと女優であり、その長男で現在の家長のオスカルと同名で同じく俳優の亡夫オスカルが劇場とこの邸宅を買っておいたことが、今日の一家の繁栄をもたらしたのだ。彼らの三男、つまり現代のオスカルの弟でアレクサンデルの叔父、この土地一番の菓子店(喫茶店とレストランも兼ねている)の主人グスタフ・アドルフが料理と給仕を指揮している間、次男で大学教授のカールはすでに酔っている。エクダール家の習慣により、おもだった召使たちも主人と一緒に食卓につくが、ヘレナ係の昔風のヴェガとエステルとはこれでは落ちつかず、折角の食事の味もよく分らぬとこぼす。食後の踊りの間にグスタフ・アドルフは子供係の召使マイと密会の約束に成功する。 子供たちが寝室にひきとったあと、大人たちはカールの妻リディアの歌うシューマンの『あなたがくれたこの指輪』(『女の愛と生涯』から)を聞く。子供たちが寝室で幻灯を始めると、オスカルが入ってきて中国の王様のふしぎな椅子の話をしてくれる。 ヘレナは1人残ったユダヤ人骨董商イサク・ヤコビに息子たちの品評をして聞かす。彼女はオスカルとエミリーを信頼し、ほかの息子2人のことを心配する。ヘレナはまた、昔の事件を思いだす。当時イサクは彼女の愛人で、まさにこの部屋で密会中に夫オスカルに見つかったことがある。だが男2人はそれ以来逆に親友になったのだった。 マイの部屋のグスタフ・アドルフは若い彼女にすっかりのぼせ、菓子店を譲る証文を書き与えるが、彼女の「おバカさんね」という一言になぜか怒って自分の部屋に戻ってしまう。 カールの家計は実は火の車で、自分の部屋へ戻っても暖房用の薪もない。彼は大学での冷遇へのぐちを言い、ドイツ人のリディアがまだ完全なスウェーデン語ができぬのまで怒る。やや鈍感だが心からカールを愛している彼女は「自分も働く」と言うが、大学教授の体面がつぶれると一蹴する。さらに彼は彼女に子供が生まれぬのをなじるが、彼女は彼が自分に触れさえしないせいだと言いかえす。結局彼は彼女の膝に酔い崩れる。 こうして一同は、昨夜の客の1人ヴェルゲルス主教の主宰するクリスマス早朝礼拝に出かけてゆくのであった。 この第1部では、エクダール家で毎年行なわれる盛大なクリスマス行事を軸に、エクダール家とエクダール家に繋がりのある者達の織り成す一大人間模様が繰り広げられます。華やかで活気に満ちたディナーシーンから始まり、全員で家中を走り回る賑やかな行進と歌、赤を基調とした豪華な客間における大人達の静かな集いと子供たちの大ハシャギぶり(飛び散る羽毛のエモーション!)との対比の妙、そして奇妙な椅子の話で締める中盤、そこから一転して祖父ヘレナ、叔父であるグスタフとカール、それぞれに濃密で重厚な人間ドラマが展開されていく終盤まで全くと言って良いほど無駄のない構成が素晴らしいです。この第1部だけで上質のホームドラマを観終わった時のような充実感があります。俳優達も恐ろしいくらい巧みな演技を披露して、特に豪放で大らかなグスタフと知的だが神経質なカール、この2人の異なる人物造形の面白さ、存在感は抜群で、演じるヤール・クッレとボルイェ・アールステットも絶品の味わいでした。 |
第2部
亡霊
亡霊
年が明けて、2月上演の「ハムレット」を劇場でリハーサルしていたオスカルは、過労のため突然倒れ、家へ運ばれて「今なら亡霊役はもっとうまくやれそうだ」と悲しい冗談を残して死んでしまう。彼の葬儀はヴェルケルス主教の手で盛大に行なわれた。アレクサンデルは邸内で父オスカルの亡霊を目撃する。 この第2部は時間こそ短いですが、見所は実に豊富です。この章のテーマはずばり"死"そのもの。冒頭で「ハムレット」のリハーサル中、亡霊役を熱演していた父オスカルが突如倒れるくだりから既に死の匂いが画面中に充満しています。そして死が迫ったオスカルをアレクサンデルが見舞うシーン。アレクサンデルは執拗に怯え、なかなか父の寝室に行こうとしません。自分も小さい頃、母方の曽祖母が亡くなった時に恐くて遺体に近づけなかった記憶があります。この描写を観た時、あの奇妙な違和感がはっきり甦り思わずドキッとしました。ラスト、白いスーツに身を固めた父オスカルがピアノを弾く手を止めゆっくり後ろを振り返るシーンの静寂と緊張感・・・。この演出の何たる恐さ、美しさ!霊を表現するのに特殊効果は必要ないですね。それにしても・・・オスカルの死を冷静に受け止めているかに見えた妻のエミリーが夫の遺体の前で夜な夜な激しく慟哭するシーンの衝撃。それをドアの隙間から覗き見るアレクサンデルの表情・・・ベルイマン演出の凄まじさにまたも圧倒されるのでした。 |
第3部
崩壊
崩壊
オスカルの遺言により劇場はエミリーがひき受けて努力したが、不入り続きで、夫の死のちょうど一年後、彼女は自分が手をひくことを俳優たちに宣言する。エミリーは、夫の死後、いろいろと相談相手になってくれたヴェルケルス主教の求婚を受け入れようとしていた。 ある日、アレクサンデルが学校から戻ると、意外にもヴェルケルスが待っていて「人間はなぜ嘘をつくか」とたずねる。アレクサンデルは正直に「得になる事があるから」と答えるが、実はその質問は彼が学校で「自分はサーカスに売られたから、やがて曲馬を習って巡業に出る」と空想談を言いふらしたのを責めるための伏線だったのだ。 数日後、ファニーとアレクサンデルはエミリーにつれられて主教館を訪問し、主教の母ブレンダ、彼の妹ヘンリエッタ、病気で寝たきりの叔母エルサに紹介される。主教はエミリーに「衣服、友人、習慣など劇場の華美につばがる物はおいてこい。子供たちについても同じだ」と命じる。それが清い精神生活に入る道と考えた彼女は承諾し「私は舞台でいろいろな仮面を被ったけれど、私の神もそうだったの。本当の顔が分らないの。これからあなたを通して、すべてを知るのね」と告白する。 主教との結婚式は、その年の初夏、エミリーの住居で行なわれた。その最中、隣室に父オスカルに亡霊を見たアレクサンデルは、走っていって気を失う。主教館に伴われた子供たちは、15年前に溺死した主教の先妻とその2人の娘の形見の残る部屋へ入れられる。主教への反感を示すアレクサンデルを、エミリーは「主教様は「ハムレット」のクローディアス王じゃないのよ」と叱る。 冒頭・・・客足が遠のいてしまった劇場。芝居が終わり幕が下りるとキャメラは舞台裏を正面から捉えたショットになります。ここの演出が実にユニーク。エミリーや俳優達が舞台中央に集まって話し合いが始まるのですが、人やセットの動きがまるで演劇のように様式化されています。つまり映画の中の劇が終わり今度は映画を観てる人達の為の劇が始まる、と言ったところでしょうか。演劇狂のベルイマン監督らしい粋な演出でした。 |
第4部
夏の出来事
夏の出来事
翌年-1909年夏、近くの島のヘレナの別荘。夕立が、庭にちらばったままのおもちゃに降りそそいでいる。イサクからの近況見舞の電話のあと、グスタフ・アドルフの子をみごもったマイが久しぶりに訪ねてくる。グスタフ・アドルフの寛大な妻アルマは、生まれてくる子をエクダール家にひきとることにしていた。面目まるつぶれの彼は例の菓子店の贈与の実行を主張し、逆にマイを困らせているのだ。次にマイは三週間前にアレクサンデルからきた葉書のよそよそしさを案じる。 そのころ、主教館の子供部屋ではアレクサンデルが主教の死を祈っている。そこへ入ってきた召使ユスティナはお菓子で二人を手なずけようとし、ついでに「この家には幽霊が出る。私は突然ドアに手を挟まれた」と、皮膚がむけて血だらけの血を示す。それにつられたアレクサンデルも、主教の先妻と娘たちの幽霊を見たと言う。彼女たちは誤って水へ落ちたのではない。主教によって五日五夜食物を与えられずに監禁された彼女たちは、窓から逃げようとして夜の川に落ち、救おうとした母親も溺れたのであったと言う。ユスティナは早速主教に密告する。主教はファニーとアレクサンデルを呼びつけて作り話をしたことを叱責する。アレクサンデルは抗議するが結局屈服し、ムチで知りを10回叩かれる。ブレンダとヘンリエッタはそれを眺めながら平然と編物をしている。主教は「罰が理性を作る」と言い、ファニーの頭をなでようとするが、キッパリかわされて、思わずにぎりこぶしを作る。 別荘でまどろむヘレナのもとへオスカルの亡霊が現れれ、エミリーや子供たちのことが心配だとうったえる。そのあとへこっそりとエミリーが訪れ、結婚は失敗だったと悩むが、離婚して戻っておいでと言う義母には「夫が同意せぬかぎり法律上は家出とみなされ、子供たちはヴェルゲルス家にとられてしまう。それに私は主教の子を今みごもっている」と告げ、自分はここへ来なかったことにしてくれと頼んであわてて帰ってゆく。 体罰のあと屋根裏に一人で寝かされたアレクサンデルは、主教の娘たちの亡霊におびやかされる。妹エスメラルダをつれて現われたパウリーヌは「私たちは、クリスマス・プレゼントのスケートですべっている時に氷の割れめに落ちたの。あんたは父を悪く言ったから、いじめ殺してやる」と言って消える。そこへ戻ってきたエミリーに、主教は「この罰は愛のためだ」と言う。彼女の「あなたが愛の話?」という皮肉に彼は「私は欠点もある平凡人だが、主教という職にあるからそのようにふるまう」と宣言する。 この章でまず目を引くのがヘレナの別荘のシーンです。ヘレナの服も家の壁も家具も何もかもが白で統一された世界。外は雨。この静かで美しい部屋はオスカルの亡霊が現われる後半ではあたかも別世界のような不可思議な空間へと変化していきます。それは生者と死者の戯れ、まるで生と死の境が無くなったかのような幻想的な世界・・・。そして圧巻なのは主教とアレクサンデルの凄まじい確執。真実とは?愛とは?話せど話せど二人の溝は深まるばかり。ここは父親の宗教観に反抗し続けたベルイマン監督の過去が色濃く反映されているのでしょう。体罰のムチ打ちの乾いた音が恐かったです。 |
第5部
悪魔たち
悪魔たち
ヘレナの心痛を察したイサクは、主教館へきて「先日話のあった古い衣裳箱を買いにきた」と言って金を出す。主教が領収書を書きにいっている間に彼は合鍵でファニーとアレクサンデルを子供部屋からつれだし、衣裳箱に隠す。それを知らぬ主教は「子供たちに会おうとしたようだが、失敗したな」とイサクの首を締めあげる。駈けつけたヘンリエッタと主教が子供部屋を調べにいったあと、イサクは一瞬、すべてが失敗してエミリーが子供たちを殺す幻想におそわれて失神するが、皆が戻る前に急いで衣裳箱を外へ運びださせる。 イサクの家へ着いたファニーとアレクサンデルはイサクの甥のアーロンに紹介され、イサクの案内で、人形コレクションやミイラのある暗い広間の奥の小部屋にかくまわれる。イサクは、川と泉の源を探しにいった青年の話をしてやる。川や泉は、人間の夢や涙や恐れが凝縮した雲から降る雨でできたのだ。アレクサンデルは新しい幻想にふける。土煙の中を、修道僧たちやおのが身をムチで打つ上半身裸の信者たちが進んでくる。その中で、ユスティナが血だらけの手を見せる。突然情景が夜に変わり、何千本のロウソクの光の前で修道僧姿のエミリーが大きな杯をさしだす。それを受けたところで、彼は眼がさめた。 主教を訪問したカールとグスタフ・アドルフは賠償金で解決することをほのめかすが、法律によって子供たちの帰宅を要求し、その将来についてエクダール家の介入を認めぬと言う主教と、監禁虐待で親権は消滅したとするグスタフ・アドルフの議論はかみあわず、ついにグスタフ・アドルフは「お前は多額の借金のあることをバラしてやる」と怒るが、主教は冷然と「僧職者は物資から超然とした存在だから、そんな噂では破滅しない」と答える。そこへ現われたエミリーは、ややうつろな表情ながら、意外にも「私はここにいたい。子供たちも返して」と要求する。 夜ふけ、トイレに起きたアレクサンデルは父の亡霊に会う。亡霊は「お前たちが心配で眼が離せぬ」と語るが、アレクサンデルのほうは「見守ってるだけなら早く天国へ行ってよ。そこに神はいるの?」と言いはなつ。すると数体の人形が激しく揺れ始め「私は扉の背後の神だ。生きている者は顔を見るな」と告げるが、それはアーロンのいたずらであった。彼は「すべて神か、神の思慮の表現だ」と言うが、アレクサンデルは「神なんていない。いてもクズと同じだ」と反対する。アーロンも「ぼくは魔術師だから無神論者だ。超自然を求めるのは観客のほうだ」と同意し、弟のイスマエルに朝食を持ってゆくのにアレクサンデルを誘う。両親が早く死んだので二人は叔父イサクに養われているが、狂人のイスマエルは別室に監禁されているのだ。 カールたちが去ったあと、寝つかれぬ主教はエミリーに「私の仮面は一つだが、肉に食い込んで離れない。私は賢明で寛大で公平なのに、皆に憎まれる。私はアレクサンデルがこわい」と語る。そして彼は、自分が飲むつもりでエミリーが作っておいた睡眠薬入りの飲物を知らずに口にしてしまう。彼女は「この偶然を利用して、あなたが眠っている間にエクダール家へ戻る」と宣言する。彼は彼女のゆるしを乞うが、拒否される。 アーロンに頼んで三十分ほどアレクサンデルと二人きりになったイスマエルは「君とぼくとは同一人物かもしれない」と語り、主教が眠りの中で「神よ、なぜ私を見捨てるのか」と叫んでいるさまを幻視する。アレクサンデルは恐れて「やめて」と頼むが、イスマエルは「もう遅い。それにこれは君の祈りの成果なのだ」と首をふる。寝たきりのエルサが枕もとのランプを倒して、火だるまになって主教の寝室に駆け込む。そのため、主教も焼死する。このことは、夜が明けてからエクダール家にエミリーを訪ねた警部によって確認される。もちろん彼女に責任はない。 エミリーは懐かしい劇場を訪問し、グスタフ・アドルフの見当違いな経営に閉口している俳優たちの歓迎を受ける。 この章では他にも増してベルイマン監督の映像魔術が冴えを見せます。ユダヤ商人のイサクが一瞬垣間見る不吉な幻想、イサクの話の途中でアレクサンデルが見る奇妙な幻想、そしてイサク館の不気味な美術(世界中の人形やら骨董品やらが雑然と居場所がないくらい沢山置かれていて、さらに呼吸をするミイラまでいる^^;)や別室に監禁されている狂人のイスマエルなどまるで外の世界から隔絶された異様な空間と言った趣があります。イスマエルがアレクサンデル(表面上は嫌がる素振りをするが)に協力し、ヴェルゲルス主教を呪いによって焼殺してしまうシーンはこの章のクライマックスと言え、冷徹非道な主教のみならずアレクサンデルや果ては全ての人間が悪魔になり得るというベルイマン監督の辛辣なメッセージが感じ取れます。何故本章のタイトルが「悪魔たち」と複数形になっているのか・・・何とも興味深いです。 |
エピローグ
春になるころ、エミリーは女の子アウローラ、マイは同じくヘレナ・ヴィクトリアを生んだ。二人の洗礼の祝宴で、グスタフ・アドルフは「われわれの小世界もいつかは壊れるだろうが、運命は運命として、幸福な時は素直に楽しもう。それは恥ずべきことではなく、人生に必要な物なのだ。われわれはこの小世界にいるが、いつの日かアウローラとヘレナ・ヴィクトリアとがすべての世界の女王となるかも知れぬ」と演説する。 すべては昔に戻り、グスタフ・アドルフが新しい召使ローサに手を出しかけるところまで昔のとおりになったが、その夜、彼の長女ペトラとマイとは自活を求め、知人のエガマンがストックホルムで帽子店をひらくのを手伝いにゆくつもりだと言いだす。一方、邸内を歩いていたアレクサンデルはふいに首筋をつかまれた。それはヴェルゲルス主教で、主教は「逃がさないぞ」と言い捨てて戸口に姿を消した。そのころヘレナに会いにいったエミリーはもう一度劇場を経営してみるようにすすめられ、それならヘレナと二人で演じたいとストリンドベルイの新作「夢の戯れ」の台本をおいてゆく。ヘレナは台本を読み始める-「どんな事もあり得る。何でも起り得る。時間にも空間にも縛られず、想像の力は色褪せた現実から、美しい模様の布を紡ぎ出す・・・」。 揺り篭に入った二人の赤ん坊のアップショットからキャメラが上へとパンしていくと、大きな円卓を囲んで華やかな衣裳に身を包んだエクダール家の人々が賑やかに食事をしている。その奥では楽士隊が優雅な音を奏でている。そしてキャメラが切り替わり今度は楽士隊側の視点から上へとキャメラがパンしていって画面中央に「エピローグ」のテロップが挿入される。ん~お見事!この鮮やかなキャメラワークと豪奢な映像空間の宴。まさに最後を飾るに相応しい壮麗さです。そしてグスタフ・アドルフの演説。演じるヤール・クッレの何たる存在感!もうとにかく表情が豊かで観ているだけでワクワクさせられる俳優ですね。自然光による柔らかな色調が幸福感をより増幅させ、このまま映画はその壮大な人間ドラマに相応しい大団円を迎えるかに思えます。が、しかしそこはベルイマン監督、やはり一筋縄では行きません(^^; 宴が終わりいつもの日常に戻ったある日、ヴェルゲルス主教の亡霊がアレクサンデルの前に現われ彼に恐ろしい一言を浴びせます。その言葉は人間と宗教の関係、決して切り離す事の出来ない両者の因果を暗示しているかのようでした。最後の場面、台本を読むヘレナの言葉に静かに耳を傾けるアレクサンデル・・・そのまま画面はゆっくりと溶暗していき各章の最後と同様音楽のない赤地の背景にエンドクレジットが流れ出す。その無音の中でいつまでも映画の余韻に浸っていたいと願いつつ・・・。 |
ベルイマン「ファニーとアレクサンデル」を語る
| あれは1978年だったか、フォール島の自宅でくつろいでいた時、ふと一族の人たちのことを思いつくままに書き始めた。そのうち気がついてみたら、1本の映画にまとめられそうだった。だからこの映画は、ストーリーは私の創作だが、登場人物には多少なりモデルがある。アレクサンデルは私といっていい。少なくとも精神的肖像としては私自身だ。しかし、ことわっておくが、私の両親はこの映画に出てくるような非人間どもではない。歌も歌ったし、けっこう愉快な話もした。ただ、宗教に奉仕する者として、時おり急にタテマエ一点張りになる瞬間があり、そういう時は冷たくかたくなで、ほとんど偽善者的でいやだった。 私自身は劇場関係者の家に生まれたわけではないし、あんな豪華なクリスマス・イヴをやったこともない。子供のころに考えていたクリスマス・パーティ像を実際に描き出してみただけである。エクダール一家も、いわば私の夢の中の家族というわけだ。
この映画の製作には、私の生まれ故郷であるウプサラのロケも含めて1980年9月から82年3月までかかった。役らしい役のついた俳優だけでも60人近いし、制作費3100万クラウン(約9億3000万円)というのも、私としては最初で最後だ。最初はイギリスのプロデューサーが乗ってきたが、英語版をオリジナルとして製作してほしいというのでことわった。私はスウェーデン語の映画にしたかったのだ。長さも5時間のテレビ放映版(注=日本公開版)一つでいいと信じたが、西ドイツの出資者が「長すぎる。興行が難しい」と言うので、やむを得ず3時間8分の劇場版を作った。 多くの旧友の出演や協力に感謝するとともに、最初のつきあいだがエヴァ・フレーリングの魅力的で確かな演技にも満足である。リヴ・ウルマンも出たがったし、主役級で協力してもらう気だったが、契約のつごうでだめになった。娘のリンにはファニーを考えていたが、やはり実現しなかった。 |
受賞歴
|
■1983年度アメリカ・アカデミー賞 ・外国語映画賞 ・最優秀撮影賞 ・最優秀美術賞 ・最優秀衣裳デザイン賞 ■1983年ヴェネチア国際映画祭 ・国際批評家連盟賞 ■1983年度アメリカ・ナショナル・オブ・レヴュー ・最優秀外国語映画賞 ■1983年度ロサンゼルス映画批評家協会 ・最優秀外国語映画賞 ・最優秀撮影賞 ■1983年度ニューヨーク映画批評協会 ・最優秀外国語映画賞 ・最優秀監督賞 ■1984年アメリカ・ゴールデン・グローブ賞 ・最優秀外国語映画賞 ■1984年フランス映画批評家協会 ・最優秀外国語映画賞 ■1984年フランス・セザール賞 ・最優秀外国語映画賞 ■1984年イタリア・ダヴィデ・ディ・ドナテッロ ・外国映画部門 ・最優秀作品賞 ・最優秀監督賞 ・最優秀脚本賞 ※これらは全て3時間バージョンによる受賞です。 |
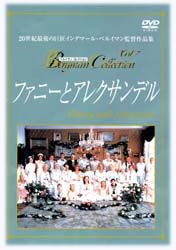 |
発売日 2000/12/21 発売元 ムービーテレビジョン/ビームエンターテインメント 商品番号 BBBF-1557 価格(税抜) 7,800円 仕様 片面一層(二枚組み) レターボックス・ビスタサイズ 収録時間 180分(劇場公開バージョン) 音声仕様 ドルビーデジタル・モノラル・スウェーデン語 字幕 日本語(ON・OFF可能) リージョン2 |
|Back|
| Copyright © 2004 Ginbanseikatsu. All Rights Reserved. email:ana48705@nifty.com |