第五部 第1章. 7千年前、5千年前の八丈島に、古代人はどのようにしてやってきたのか
第五部 第1章 目次
第1節 次の写真の花はなんという名で、どこからやってきたのか?
第2節 八丈島、7千年前の湯浜人、5千年前の倉輪人
鬼界カルデラ噴火
湯浜遺跡と倉輪遺跡
丸木舟による三宅島―八丈島間の航海の困難さ
第3節 湯浜人はどのように八丈島にやってきたのか、上陸の謎。
湯浜人はほとんど無一物で上陸した
湯浜人は漁撈を行わなかった
湯浜人は狩猟も行わなかった
湯浜人の持っていた神津島産の黒曜石は、彼らが本州中部から意図的・計画的に八丈島に南下したことの論拠にはならない
第4節 神津島産の黒曜石は本州中央部だけでなく広く各地で使われていた
旧石器時代から縄文時代へ、地層、遺跡、遺物
旧石器時代人の黒曜石を求める行動
縄文時代の黒曜石の分布
東海地方における石材利用と黒曜石の分布
瀬戸内技法・国府系文化集団の移動
「矢出川技法」による細石刃石器群の広がり
湧別技法集団の細石器刃文化の広がり
岐阜県の遺跡における石材利用と黒曜石
愛知県の遺跡における石材利用と黒曜石
三重県の遺跡における石材利用と黒曜石
南伊勢における神津島産黒曜石の出土と紀伊半島南岸への黒曜石分布の可能性
四国高知・太平洋岸の遺跡における石材、そして黒曜石分布の可能性
第5節 倉輪人の三宅島から八丈島への航海はどのように行なわれたか
海部チームの丸木舟・スギメの黒潮横断の実験航海
丸木舟で、三宅島から黒潮を横断して八丈島に渡る―計算
スギメの航海の分析
小学校教師らの手作りの丸木舟・からむしⅡ世号の航行速度
南洋諸島のアウトリガー付きのカヌー
旧石器人のカヤックは時速5㎞で航行できた?
「海民」であった倉輪人
三宅島から八丈島に渡る。事前の準備
三宅島→八丈島、計算
ヨットと丸木舟
古代に帆は存在したか
ムシロや帆布の代わりをするものはさまざまにあった
帆走丸木舟による航海、南西諸島のサバニ
丸木舟による三宅島―八丈島間の航海、具体的考察
三宅島で吹く風
黒潮の流路の変動を調べてみる
倉輪人が利用した潮流
まとめ:倉輪人の八丈島への移住と本土への帰還
第6節 湯浜人は黒潮に乗って西日本(東海地方以西)からやってきた
四国、南紀などから流され、八丈島に「漂着」できる可能性のある漂流
(1)黒潮が直接八丈島にぶつかる場合
(2)風による表面流に乗って八丈島に漂着する場合
江戸時代、多くの難破船が八丈島に漂着した
湯浜人はどうして漂流することになったのか
南海トラフ地震と西日本を襲う津波
津波により沖に流された―そのシナリオ
居住地を変えようと沿岸を移動中、誤って流された
第6節のまとめと第一章の結論
岐阜、愛知、三重の旧石器時代~縄文期遺跡の石器石材
【追加】ヤポネシア及び日本人の源流について
第5部目次へ戻る
第1節 次の写真の花はなんという名で、どこからやってきたのか?

クイズ:上の写真の花は何でしょう。
私はスマホを使っていない。初めて見た花だったので、まずWebの図鑑で調べてみた。いくつかの図鑑で、「カテゴリー」、「花の色」、「開花時期」など、様々な入り口から入って調べたが結局、これだというものは見つからなかった。
ところが、近所の山を歩いていてしばしば会うので仲良くなった植物好きの友達に写真を送って尋ねてみると、月桃(ゲットウ)ではないか、という。彼は10年ほど沖縄に住んでいたことがあるが、沖縄でよく見たという。そして、葉に殺菌力があるので、餅をその葉で巻いた菓子があった、という。
Webで月、桃と漢字を入れて検索すると、大当たり、間違いなく私が見たものと全く同じ花の画像が幾枚も現れた。
http://www.gettou.co.jp/hpgen/HPB/entries/1.html 日本月桃株式会社/有限会社月桃農園のHPによると
月桃には、月桃(シマ月桃)(Alpinia zerumbet)、タイリン月桃(Alpinia zerumbet var.excelsa)、ウライ月桃(Alpinia uraiensis)の3種類がある。
月桃は台湾から石垣島、宮古島、沖縄本島、奄美大島に分布し、北限が鹿児島県佐多岬といわれている。
タイリン月桃は沖縄原産の月桃と台湾北部原産のウライ月桃が交配して生まれた亜種月桃で、小笠原諸島、八丈島、大東島に分布する。
そして、ウライ月桃は台湾北部に分布する、という。
だが、「月桃の分布」<月桃インフォメーション>http://www.gettou.info によると、
学問的にはショウガ科ハナミョウガ属の植物で、沖縄近辺に分布する月桃は数種類あり、沖縄本島から台湾にかけて広く分布している月桃がいわゆる月桃で学名はAlpinia zerumbet var.zerumbet ---である、という。
これは月桃農園HPでいう月桃と同じものと思われる。大輪月桃とウライ月桃については月桃農園と同じ学名を記している。

また、上記、3種類のほかに、台湾南東の離島、フィリピン北東沖の離島に分布するアツバゲットウAlpinia glabrescens があるとし、
月桃を含むショウガ科の分類学については船越英伸の遺伝子レベルの調査の結果、月桃は同一の祖先が広まって現在に至っていることまで解明されている、といい
月桃の近縁種まで考えると、クマタケラン、アオノクマタケランなど、さらに数種類が沖縄を含む琉球弧に分布している、という。
こうした説明のほかに、船越から転用された右の「分布」図が載せてある。
〔なお船越は、大輪月桃をハナソウカ(花草果)と名付けたという。「総説:ハナソウカと月桃―分類から精油、DNAまで」『MEDICAL HERB』第43号 2018年3月 〕
オレンジの円内のBatanes Islandsはバタン諸島(フィリピン)、Lanyu Is.は蘭嶼島、ランショ島(台湾)でアツバゲットウの分布地、赤の円内は北大東島と南大東島、母島(小笠原諸島)、八丈島であり、タイリンゲットウの分布地。
次のように考えたくなる。一般に、交配は昆虫などによってもおこなわれるだろうが、渡り鳥などにより糞の中の種子が北から南へと運ばれることもあるだろう。
だが、また、フィリピン以南の東南アジアの島々の沿岸から流れ出た月桃の祖先種が、黒潮の流れに乗って、一部はバタン諸島、蘭嶼島、一部は台湾本島または琉球列島に流れ着き、そこで進化してアツバゲットウになり、また、月桃あるいはウライゲットウになった、のではないかと。
そして、台湾には月桃もウライゲットウもあるのだから、その交配種・大輪月桃もあり、その種子が海流で大東島、八丈島、小笠原諸島に運ばれたのではないか、と。
私が月桃の花を実際に見たのは2019年6月に、娘と一緒に八丈島に旅行した時である。上掲の写真もその時に撮った。私の八丈島旅行の主目的は、八丈富士とも呼ばれる西山と三原山(東山)に上ることであったが、初日は天気が悪かったので西山登山はやめ、島内を観光して回った時に、道端で見つけたのである。
また、島内観光の出発点であった町役場近くの「観光案内所」の隣の「歴史民俗資料館」 で私は、八丈島には5千年前、7千年前の古代人の遺跡があることを知った。
こうして、旅行の後、家に帰ってから、月桃について調べたり、Webの記事を読んで考える一方、私は、八丈島の古代遺跡に関する論文を読んだ。そして、古代人の八丈島渡来と月桃の分布に関連があるのではないかと、思った。
月桃は黒潮に乗って八丈島にやってきた。それと同様、八丈島の最初の住人もまた黒潮に乗ってやってきたのではないだろうか。
第2節 八丈島、7千年前の湯浜人、5千年前の倉輪人
小田静夫『八丈島の先史文化』国學院大學考古学資料館紀要 第21輯(「加藤有次博士追悼」特集号)2005.3.31 所収(pp.55-84) http://ac.jpn.org/kuroshio/hachijo2005/index.htm によると
小田(*)を含む、10数年に亘る東京都教育委員会を中心にした考古学調査により次のことが分かっている。
最古の住人は、7,000~ 6,500年前、八丈島に噴火が続き、西山(八丈富士)が形成途上にあった時期に、東山(三原山)地域に上陸し、「湯の浜」海岸の高台に生活の拠点を設けた。人骨は出土していない。上陸地点にちなんで「湯浜人」と呼ばれている。彼らの人口は15人程度、生活期間は数世代(100年以内)だった。
二番目の渡島民は、5,000年前の倉輪人で、同じ湯の浜海岸に上陸し、湯浜遺跡の西側高台、倉輪地区に集落を構えた。そして、彼らはたびたび縄文本土に渡航した「海の縄文人」でもあった。
三番目の渡島民は、八丈島の大きな噴火活動が終了し、ほぼ現在と同じひょうたん状の島形が完成した2,000~1,200年前(弥生~平安時代)、島の中央、八重根地区で生活した八重根人であった。
四番目の渡島民は、平安時代の火の潟人であった。
以上、現在までに確認された 4遺跡(湯浜、倉輪、八重根、火の潟)の発掘成果は、「八丈島先史時代」とも呼べる文献以前の出来事であった。 このように書かれている。
湯浜遺跡の年代に関して小田は、遺跡から出土した黒曜石の鈴木正夫(**)による分析で、産地はすべて神津島、水和層〔後述〕年代で7,100~6,400年前と出された、と書いている。
-----------------------------------------------------------------------
(*)小田静夫プロフィール
1942年東京生まれ。国学院大学卒業。明治大学大学院修了。総合研究大学で文学博士号。東京都庁に勤務。武蔵野の野川遺跡の発掘を通じ、旧石器から縄文までの文化層を明らかにし、その「武蔵野編年」は全国編年の基礎となった。旧石器捏造事件を、発覚以前に論文で鋭く指摘したが、逆に、強い圧力を受け、やむなく黒潮文化研究に方向転換し、黒潮圏の考古学を確立した。東京都庁を定年退職。日本第四紀学会員。元東京大学講師。
全国邪馬台国連絡協議会 第10回記念東京大会(2019年8月開催)講演会「考古学×DNA:日本人を考える」(小田静夫×斎藤成也***)チラシより。

(**)鈴木正夫は立教大学教授で、 2007年退職時の「最終講義「黒曜石学」の創生 」(応用社会学研究 2008 № 50 )で、黒曜石の産地を特定する様々な理化学的方法の説明を行い、最後に「黒曜石研究には、先史時代の人の 交流、物の移動、さらに文化圏の成立・変遷など を復元する客観的なデータを提供することができ る---のみならず、さらに、古気候変動の復元につ いても大きな可能性を秘めている---- など黒曜石だけが展開できる固有の世界がある」 として、「「黒曜石学」の創生を提唱する」と述べている。
また、国立国会図書館デジタルコレクション、https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10809108?tocOpened=1地質学論集、1973,(2)第8号,『フィッショントラック法による本邦新第三系の年代測定』西村進・笹嶋貞夫の論文のtable4には、鈴木らによるフィッショントラック法による10の産地からの黒曜石の年代が掲げられている。
フィッション・トラック法とは、 黒曜石内の原子核分裂片の傷-フィッション・トラック-を観察し計算することによって、その岩石の生成年代、つまり噴出年代を知る方法。 そのためには、鉱物中のウラン濃度を知る必要があり、このキズ跡とウラン濃度が、どの原産地の値に近いかをあわせて調べることによって、原産地を推定することができる。小田静夫「黒曜石分析から解明された新・海上の道-列島最古の旧石器文化を探る④-」による。
(***)斎藤成也(なるや) (***)斎藤成也(なるや)1957年生まれ、国立遺伝学研究所教授。総合研究大学院大学生命科学研究科教授、東京大学大学院理学研究科教授を兼任。様々な生物のゲノムを比較し、人類進化の謎を探る一方、縄文人などの古代DNA解析を進めている。『核DNA解析でたどる― 日本人の源流』(河出書房新社)の奥付、著者紹介による。
同書などによると、講演会「考古学×DNA:日本人を考える」における斎藤の講演のタイトル「ヤポネシア人(日本列島人)はどこからきたか」の「ヤポネシア人」という語は、南西諸島から九州、本州、北海道までの日本列島に住む人々の全体を指す。「日本列島人」と空間的にはほぼ同じ。
他方、日本という語は、大和朝廷で作られたものでそれ以前の時代には「日本」も日本人も存在しなかった。日本列島北部には(最近まで)アイヌ人、南部にはオキナワ人、中央部にヤマト人の三集団が住んでいた。大和朝廷成立以前からの日本列島に住む人々について考える場合には、<日本人>とせず、三つの地域に住む三集団を含む<日本列島人>とするほうが適切である。
ヤポネシアとする点については、ヤポ(ン)+ネシアでネシアは諸島、島々の意味で、ヤポンはヨーロッパ語(仏語:ジャポン、独語:ヤーパン、スペイン語:ハポン/シャポン)で「日本」の意味だという。
詳しくは、章末の 【追加】ヤポネシア及び日本人の源流についてを参照
------------------------------------------------------------------------
また、『八丈島の先史文化』で小田は、「鹿児島県鬼界カルデラから噴出した広域火山灰「鬼界-アカホヤ火山灰(K-Ah) 6,300~6,500年前」が、湯浜遺跡の遺物包含層中と隣接した倉輪遺跡(5,000年前、縄文前期終末~中期初頭) の遺物包含層下の風化火山灰層中から検出された」と書いている。
この文で、「鬼界アカホヤ火山灰」が湯浜遺跡の遺物包含層中から検出された」と言っている。
同じ論文の、少し後の箇所では遺跡の「環境と年代」についてもう少し詳しく書いている。
湯浜人が初めて八丈島に渡島した頃は、東山南西腹の側火山(八幡山)が噴火 (7,000年前)し火口を持つ噴石丘を形成していた。引き続きその南麓から大量の溶岩が流出し、斜面を南流し海食崖から海に滝のように流れ落ちた。
この溶岩流が、北西部に確認された倉輪遺跡(5,000年前)の基盤層を形成している。---八幡山の噴火後、早くて数年遅くて数百年後に、湯浜人がこの湯の浜に上陸したと思われる。----- 遺跡地は3~4メートルに及ぶ火山噴出物が堆積し、11枚の自然層に分層された。文化層は1枚確認され、同層中に鬼界―アカホヤ火山灰(6,500~6,300年前)が介在していた(杉原・小田1989,1990)
この文によれば、湯浜遺跡地の文化層中に「鬼界アカホヤ火山灰が介在していた」といっている。
「鬼界アカホヤ火山灰が湯浜遺跡の遺物包含層中から検出された」ということと、「湯浜遺跡遺跡地の文化層中に鬼界アカホヤ火山灰が介在していた」ということは同じことだと思われるが、それは湯浜人が八丈島に上陸後、鬼界カルデラ噴火の火山灰を被ったか、あるいは彼らが火山灰が降下した直後に上陸し、火山灰の積もった八丈島で暮らしたことになるように、思われる。
他方、同じ小田の『黒潮圏の先史文化 』(第 四 紀 研 究 (The Quaternary Research) 31 (5): 409-420 Dec. 1992)では、
湯浜遺跡から出土した「 厚手無文の丸 底土器 ・刃部磨製石斧 ・各種 の打製石器 に特徴的 な例が 認 め られた。 隅丸方形 の竪穴住居 を構築 し, 遺物包含層 の上 部 に は鬼界 ア カホ ヤ火 山灰 (K-Ah, 約6,300年 前) が堆積 していた。 この湯浜石器文化 の出自系統 は, い まだに不 明で あ り, 本土 の縄 文文 化 の変質 した もの か, 黒潮 の流 れる地域 や南方 からの伝播 かが論 じられて いる 」と書いている。
つまり、湯浜遺跡の「 遺物包含層の上 部 に は鬼界 ア カホ ヤ火 山灰 が堆積 していた」とされている。
この文からは湯浜人が八丈島に上陸し生活した時期は、鬼界カルデラ噴火の前だったということになると思われる。
私は、以下では、文意がはっきりしている『黒潮圏の先史文化 』にしたがって、湯浜人の来島は鬼界カルデラ噴火の前だった、と考えることにする。
鬼界カルデラ噴火
上の二つの論文では鬼界(キカイ)カルデラ噴火は6300年前から6500年前とされている。火山噴火の年代は、噴出物中の炭化物に含まれる放射性炭素の測定によって求められているが,その際、大気中のC14濃度が一定であるとして算出されている。実際には大気中の14C濃度は変化しており、最近は、樹木の年輪、サンゴ化石などの比較などにより補正曲線を作成して年代値を求めている。
鬼界火山の超巨大噴火は暦年補正された年代で7300年前とされているので、湯浜人の八丈島上陸は、7300年前以前ということになる。
他方、小田は、湯浜人の八丈島上陸は「八幡山の噴火(7,000年前)後、早くて数年遅くて数百年後」と書いている。そうだとすると、「鬼界カルデラ噴火前」とは300年以上の差があることになる。しかし、以下の議論では、この湯浜人上陸の年代は直接関係しないので、ふれないでおく。
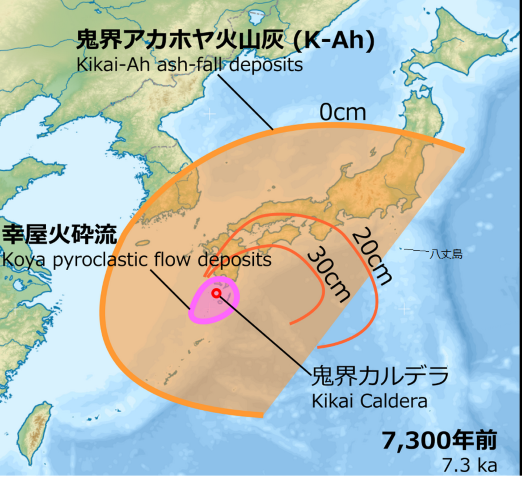 鬼界カルデラは、薩摩半島・枕崎から約50km南の硫黄島、竹島がカルデラ北縁に相当する。 東西約21km、南北約18kmの楕円形。約7,300年前、鬼界火山の超巨大噴火で形成された。
鬼界カルデラは、薩摩半島・枕崎から約50km南の硫黄島、竹島がカルデラ北縁に相当する。 東西約21km、南北約18kmの楕円形。約7,300年前、鬼界火山の超巨大噴火で形成された。火砕流が九州南端にまで及び、噴出した火山灰「鬼界アカホヤ」は四国、本州瀬戸内海沿い、および和歌山県で20cm以上堆積し、広くは朝鮮半島南部や東北地方にも分布 している。
Wikipedia「鬼界カルデラ」。
図中の㎝はアカホヤと呼ばれる鬼界カルデラ噴火の火山灰が積もった厚さを示している。
----------------------------------
『八丈島の先史文化』に戻ると
湯浜人が上陸したころ、八丈島には噴火が続いていたが、彼らの後、(今から)約5,000年前に上陸した住人である倉輪人は、本州の縄文文化を有した人々で、盛んに航海を行ったので、小田は「海の縄文人」と呼んでいる。比較的安定した200年間の定住生活が営まれていた、という。
その後、八丈島の大きな噴火活動も終了し、ほぼ現在と同じひょうたん状(まゆ状ともいう)の島形が完成した2,000年前以降、東山と西山の中間低地帯に、3回、本土から異なる集団が渡ってきた。干魚・燻製加工を専業にした弥生式文化を有した人たち、あるいは本格的な「鰹加工工場」を建設した人たち、さらに製塩作業を行った人たちなど、異なる文化層が3枚確認されている、という。
八丈島には、遺跡のあった場所の土がほかの場所に移されるなどして、出土状況が分からない土の中から見出され、「遺跡の年代などが全く分からない」 「もう一つ謎の先史文化が存在している」といい、小田は出土した石斧の説明も行っているが、省略する。
湯浜遺跡と倉輪遺跡
図は小田「黒潮圏の先史文化」第 四 紀 研 究 (The Quaternary Research) 31 (5), p414に掲載されている「図4」の一部である。なお、「第二期」の倉輪遺跡からの出土品のうち、18番の「の」の字型の垂飾品(垂らしてつけるアクセサリー)は、倉輪人についてのちに再度ふれる際に問題になるので、心にとめておいていただきたい。
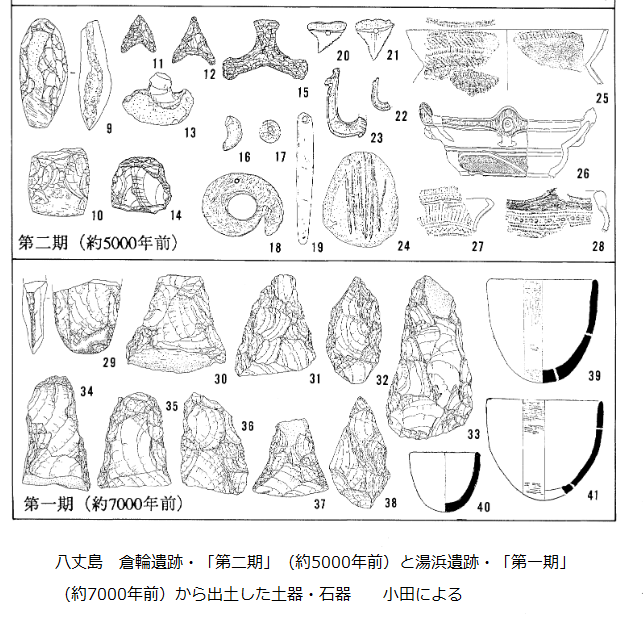
さて小田は、倉輪人を「海洋航海技術を熟達させ外洋を舞台にした縄文集団(海の縄文人)」と呼び、「倉輪遺跡からは、立派な本土の「縄文土器」をもった縄文文化が確認された」。
「イヌを連れイノシシの幼獣(ウリボウ)を携えて、丸木舟で黒潮本流を横切り八丈島に渡っている。イノシシは放牧され成獣にしたのち捕獲し食され、イノシシ祭礼儀式も行われていた。
彼らは円形の竪穴住居を数軒構築し、本土と同様の豊かな生活道具を使用し狩猟・採集活動を営んでいた。特に、釣針の製作技術は本土縄文人より優れていた。
また度々北部伊豆諸島や本土に出かけ、縄文土器や黒曜石(神津島)などを入手していた」といい、倉輪人の八丈島への渡島が、明確な、意図的・計画的航海によるものだったことを書いている。
これにたいして、湯浜人と本土との関係については、彼らの「出自系統は不明」とされ、彼らがどこから渡ってきたのかについて書いていないし、また、彼らの渡島が意図的なものだったかどうかということに関しても何も書いていない。
また、彼らの渡島が、黒潮本流 を越えることのできる渡航具と航行技術による、意図的航海によるものであるということを示唆するような、記述は全くない。
たとえば、台湾やフィリピンなど余所から漂着したということもないとは言えないかもしれない。だが、湯浜人がそうではなく、本土から渡ってきたのだと考えることができそうな証拠は、湯浜遺跡から神津島産の黒曜石が見つかっている、ということだけである。
しかし、湯浜人が神津島産黒曜石をもっていたことは、彼らが、北部伊豆諸島から南下し、三宅島/御蔵島から八丈島に渡ってきたことを必ずしも示す証拠にはならない。この点については後で触れる。
ところが、小田は『考古学からみた新・海上の道』南島考古 No.36 2017年では
「約7,000年前、日本列島の二つの地域から外洋に進出した縄文人集団があった。一つは本州島中央部から伊豆諸島の八丈島まで、もう一つは南九州地域から琉球列島の沖縄本島までの南下行動である。双方とも、黒潮本流(時速7.4km)を越えられるほどの航海技術を持った「海の縄文人」たちであった。」としている。
ここで言われている、「約7000年前」「本州島中央部から伊豆諸島の八丈島まで」南下した縄文人集団とは、湯浜人を指していることは明らかである。
また、前に書かれた1992年の『黒潮圏の先史文化』でも
「約6,500年 前 に 日本の二つの地域 で、 外洋 に進 出 した先史人 の足跡が確 認 されている。 一つは伊豆 諸島の八丈島へ の渡島で、 もう一つは南西 諸島へ の南 九州か らの南下行動 である。 両方 とも黒潮本流 を越えるほ どの航行技術 をもっていた」と書いていた。
「6500年前の外洋進出」が湯浜人の八丈島渡島をさしていることは明らかであるが、彼らは「黒潮本流 を越えるほ どの航行技術 をもっていた」とされ、外洋に出たのは意図的・計画的「進出」とみなされている。
つまり、1992年と2017年の論文では、湯浜人は「黒潮本流(時速7.4km)を越えられるほどの航海技術を持った「海の縄文人」」であり、本州島中央部から渡ってきたとされている。
これは、2005年の論文「八丈島の先史文化」で書かれていることとは違う。どちらが正しいのだろうか。湯浜人の渡島あるいは出自に関するあらたな事実が分かって、湯浜人の航行技術が倉輪人同様のものであった、というならば、それに類したこと及び新事実について述べた論文が、2005年から2017年までの間に書かれているはずだが、管見にして、知らない。
以下では、湯浜遺跡について、2005年の小田の論文で書かれていること以上の新しい事実の報告や研究はないことを前提に議論を進める。
丸木舟による三宅島―八丈島間の航海の困難さ
 なるほど、倉輪人は本土の土器などを持ち込んでおり、伊豆諸島北部と何回か往来した証拠があるというのだから、彼らの八丈島への渡島が意図的・計画的に行われたものであることには疑いがない。
なるほど、倉輪人は本土の土器などを持ち込んでおり、伊豆諸島北部と何回か往来した証拠があるというのだから、彼らの八丈島への渡島が意図的・計画的に行われたものであることには疑いがない。そして、八丈島への渡島は、それ以前の三宅島以北での縄文人の活動の蓄積を踏まえた、その延長上にある行動だと考えられるが、しかし、八丈への渡島は北部伊豆諸島の間の往来に比べまた一段と難しい。そのことをまず確かめておこう。
小田は「八丈島の先史文化」の冒頭で次のように書いて、三宅島―八丈島間の航海の大変さを指摘している。
八丈島は東京から約300キロ南、太平洋上に浮かぶ伊豆諸島南部の島である。島へは東京・竹芝桟橋から東海汽船が就航しており、この航海で「黒潮本流」を横断する約11時間の船旅が経験できる。
夜10時に出航した連絡船は、翌早朝三宅島に寄港する。三宅港を後に御蔵島を望見する辺りで、3,000トン級の大型客船が急に左右前後に大きく揺れ出す。これは地元で「黒瀬川」と呼ばれて漁民に恐れられ、江戸時代には流人の島抜けをも阻んだ航海の難所に突入したのである。
船は約3時間近くこの激流に翻弄されて、やがて八丈島・底土港に接岸し、黒潮本流横断の旅が終了する。先史時代人もこの黒潮激流を木の葉のような丸木舟を操り、八丈島に渡航したことを想像すると、その渡海能力の凄さに驚嘆させられる。----
さて、伊豆大島「大島町遺跡一覧」(東京都教育委員会)によると
伊豆大島には縄文早期から前期にかけてのものであることが確認されている三か所の遺跡がある。とくに、伊豆大島西部海岸の下高洞(シモタカボラ)遺跡は、奈良、平安時代にまで続いた遺跡の跡で、「平坂式」と呼ばれる土器が多数出土しているが、これらが大島にもたらされたのは、8000年前から9000年前と推定されている。
また「三宅村遺跡一覧」(同)によると三宅島には縄文早期(約1万2,000 - 7,000年前)の遺跡が4か所、前期(約7,000 - 5,500年前)の遺跡が5か所、このうち西原B・C地点は縄文前期から奈良、平安時代まで、伊豆岬A・B地点は弥生時代まで存続した。
これらはすべて三宅島の北部にある。北部は冬の季節風を受けるところで、南東部に比べて暮らしやすいところとは思われない。遺跡が北部に集中しているのは、北部伊豆諸島との往来の便利のためであることは明らかである。
倉輪人が八丈島から伊豆諸島の北部の島々に行き来した時に用いたのは丸木舟以外考えられないが、彼らはおそらく帆も つかっていただろうし(後述)、三宅島以北の島々の間をなんども航海し、またしばらくの間、三宅島か御蔵島に住み、二島周辺の海で漁をおこなうなどして、しばしば流路を変えて流れる黒潮を“読み”、適切な船出のチャンスをつかむことができるようになっていたと思われる。
とはいえ、倉輪人は八丈島に200年間しか生活できなかった。小田は「比較的安定した200年間の生活」と書いているが、三宅島以北の島々では(一時期噴火が原因で遺跡がほとんど途絶えている時期もあったが)人々の生活が長期にわたって続いていたのに比べ、倉輪人の次に、本土から人が渡ってきて八丈島(八重根地区)で暮らすのは、弥生時代(紀元前300年頃から西暦250年頃)の後期、紀元前後のころで、ほぼ3000年の長い空白期がある。
八丈島には、ほかに「石器時代」の所産であることは確かだが「謎の先史文化」と小田が呼ぶ、出土層が確定されずその年代が不明の石器群がみつかっている。この石器群は、 円筒片刃石斧に特徴があり、その形態から琉球列島(黒潮の道)や、マリアナ地域(太平洋の道)からの渡島文化の可能性が高いとされている。だが、この文化は伊豆諸島北部とは交流のない別文化だと考えられている。
ということは本土から5000年前(=紀元前3000年頃)に渡ってきた倉輪人は200年ほど八丈島で暮らしたが、彼らの渡島と島での生活は孤立事例であったということである。それは、本土人にとって八丈島との往来は、三宅島以北の島々との往来に比べ、格段に難しかったということの証拠であろう。
倉輪人は何度か北部伊豆諸島との間を往復したのだろうが、彼らは丸木舟で、凪で追い潮になるときには漕いで、潮が流れていないが風向きが都合のよいときに帆を使って、八丈島と三宅島の間を往来したのだろう。彼らが、操船技術及び、風と潮を読む力に関して、当時のほかの人々よりもすぐれた航海能力を持っていたことは確かと思われるが、やはり相当に冒険的でもあったはずである。
八丈町公式サイトの「八丈町の歴史」によれば、八丈島に統治機関がおかれたは室町時代の1338年足利氏の代官が在島したのが最初だという。倉輪人の時代から4千年以上たっている。
漁師など海に慣れた人々は、冬の冷たい海でなければ何時間でも泳ぎ続けることができる。丸木舟は転覆しやすいが、(海部プロジェクト―後述―で使われた丸木舟・スギメの漕ぎ手が言っていたように)慣れた人は転覆しても水に浸かったまま舟を起こすことができる。
海と船に慣れてない人を乗せて八丈島と北部伊豆諸島の間を往来できるようになるのは、丸木舟でなく大型の構造船が作られるようになってからのことで、それには4千年、5千年の年月が必要だったのだ。
後で、黒潮流速と舟の(静水での)速度を想定して、八丈島に渡る航海について具体的に考察し、丸木舟で、三宅島から八丈島へ黒潮を横断して渡ることの難しさを確かめる作業を行う。
第3節 湯浜人はどのように八丈島にやってきたのか、上陸の謎。
湯浜人はほとんど無一物で上陸した
後の倉輪人の場合には土器はすべて本土から搬入されたもので、石器も本土で使用されていたものと同じ種類のものだということが分かっていて、彼らが北部伊豆諸島を経て渡ってきたこと、本土との間で何回も往来があったことがはっきりしている。しかし、湯浜人の遺跡からは、数点の黒曜石以外、本土と関係のあるものは何一つ出土していない。石器も土器もすべて八丈島の石と土から作られている。
恐らく、意図した渡島であれば、最も近い三宅島か御蔵島からの出航と考えられ、その場合には5人乗りの丸木舟で、北からの追い潮で全力で漕げば早朝に出て日没までに到着可能である。ただし、相当にタフな航海である。このことは後で示す。
だが、このような航海は凪の日を待って行われたはずで、舟が転覆して、積み荷がすべて失われてしまう危険があるような時には決して行なわれることはなかった考えられる。(舟は転覆しても元に戻せる。)つまり、計画的になされた航海であったなら、航海の途中に荷物が失われたために上陸時にほとんど無一物になった、とは考えにくいのである。
また、島で使われていた石器が、木を伐り、土を掘るといった単純な作業を行うためのものしかなく、(黒曜石はあるのに)鏃は出土せず、狩猟や漁撈用の道具が出土していない。
だが、100㎞の海を漕ぎ渡る屈強な大人が複数いたとすれば、内地から持ってきた道具が航海中に失われたとしても、上陸後に様々な種類のおなじような石器を製作したはずであろう。しかし、そうではない。
また、土器類も本土で当時作られていたのとは全く異なるもので、しかも作りが稚拙である。
こうしたことから、倉輪人たちのように、大人たちが意図的・計画的に、北部の伊豆諸島を経て渡ってきたとは考えにくいのである。
湯浜人は漁撈を行わなかった
三宅島、あるいは御蔵島の住人が、小型の丸木舟に乗った夫婦船で漁労中に誤って流され、八丈島に着いた、というような可能性はどうか。漁撈を生業とする人たちなら、うっかりして流され(かかっ)たら、すぐに島に戻れるように舟を漕ぐだけの心得と体力があったと思われるが、仮に、流されてやむなく八丈島に接岸・上陸し、暮らすことになったとしてみよう。
かれらは、土器や石器などは積んでいなくても、網と錘(土錘)、そしてモリやヤスなどの漁具を積んでいただろうと思われる。そして、八丈島でも漁撈を行ったはずだ。
だが、湯浜遺跡からは漁撈を行うための道具は出土していない。彼らは「植物採集が主な生業」であるような生活を送った。三宅島や御蔵島の人たちの事故による意図せざる渡島だったとは考えにくい。
なぜ、湯浜人は漁撈を行わなかったのか。彼らが八丈島にやってくる前に暮らしていたところが山の中で、彼らは狩猟と植物採集しかやっておらず漁撈経験が全くなかったからだろうか。それにしては、鏃が出土しておらず、それは、彼らが弓矢を使った、本格的な狩猟は行っていなかったことを示しているように思われる。
湯浜人は狩猟も行わなかった
最も不思議なことは、石器の原材料として、非常に貴重な黒曜石を持っていたにも関わらずそれを使った形跡がないことである。そしてそれと関連することだが、石器は存在するが、森林の伐採や木材加工、住居のための掘削などに使用する道具だけで「彼らの労働用具は極めて単純な対象---だけのため」のものだった。槍の穂先や、(魚を突く)モリの出土も報告されていない。石器は「同年代に比定される内地の縄文時代前期の様相とは著しく異なっている」。
これらのことからは、彼らが漁網を編む技術も、先端を鋭く尖らせた石器(尖頭器)を製作する技術ももっていなかったと推測されるだろう。
また、土器は「いずれも脆く」また「器形は厚手の丸底深鉢形土器」で「無文」だといい、製作技術の稚拙さをうかがわせる。土器類が「本土の縄文文化には認められない土器群と考えられる」とされているのは、当時の本州各地の様式にしたがった製作技術を持っておらず、土をこねて形を作り焼く、という土器製作の基本的なことしか知らなかったからではないだろうか。
右の図は「丸底深鉢形土器」を示すために掲げたもの。

そして、これらのことから、さらに、上陸した者の中に、石の鏃や槍の穂先などをうまく作るだけの技術をもった大人が存在しなかったか、あるいは大人はいたが、けがを負っていたか病気で自らの手で道具を作ることができない状態にあり、石器も土器も子供たちが作ったのではないか、という推測が生まれる。
手を使えないか、体を動かせない唯一の大人に代わって、10歳程度までの子供たちが、大人の口頭での指示、指導にしたがって、これまでやったことのないことを初めて試みたとすれば、漁網を作ることができず、石器類も、木を伐り、土を掘るといった単純な作業を行うためのものしか作ることができず、土器は作ることは作ったが、脆弱で無文様のものしか作ることができなかったとしても不思議はない。
「野焼き(縄文土器の焼成)」 《わ!かった陶芸(明窓窯)》 https://blog.goo.ne.jp/meisogama-itaによれば、
土器は粘土で形を作った後、十分に乾燥させてから焼いて完成となる。縄文時代には窯がなかったので、「野焼き」といわれる焼成方法で焼き上げた。
温度が高いほど土器の強度は増し、壊れにくくなる。しかし急に温度を上げるのではなく、400℃程度までは、6時間以上かけゆっくりと焼く。その後燃料を増やして温度を上げる。
縄文時代には、おそらく水蒸気の出方を見るなどして温度を判断しただろう。
また、野焼きは、火災を避けるため、住居から離れたところで行なわれたはずだ、という。
だが、そうだとすると、唯一の大人が体を動かせない状態で、火加減を見てやることができなければ、適切な焼成はできなかっただろう、と思われる。
また、野焼きにはたくさんの燃料が必要で、そのために多くの人手が必要だった。「女子供だけでは無理なので、男手が必要だった」という。この薪を集める労働をできたのが子供だけだったら、焼成が十分になされなかった可能性がある。
こうしたことが、土器が「脆かった」ことの原因になったのではないだろうか。
また、彼らが狩猟を行なった形跡がないのは、槍や弓矢を製作できなかっただけでなく、上陸直後には、野生動物を追いかけ、あるいは待ち伏せて仕留めるだけの運動能力と体力を有するだけの年齢に達していなかったためではないかと考えられる。
しかし数年たって10代後半になっても、彼らはまともな狩猟具を手にすることも大人から狩猟方法を学ぶこともできなかったので、結局のところ、「植物採集が主」とされている生活に終始したのだろう。
かれらは縄文時代前期の親たちが有していた生活を支える技術を受けつぐことのできないまま、あたかも、旧石器時代の初期に逆戻りしたかのような状態におかれたと言えるだろう。
男女の混じったこどもたちであったとすれば、やがて子供もうまれたであろう。だが、住居跡が三つあるとしても、上陸後しばらくたってから子供が生まれて三つの住居が必要になったというよりも、はじめから、住居を三つ必要とする人数、例えば10人以上が上陸したとも考えられる。
そして、始めから10人以上が上陸したとすれば、彼らは丸木舟に乗ってきたのではなく、筏に乗ってやってきたと考えられる。丸木舟は5~6人しか乗れず、その後島で暮らしていて人口が15人程度まで増えたということは、彼らの栄養状態からして、難しかっただろう。
ジュール・ヴェルヌの『15少年漂流記』では、15人の少年たちは、漂着した島で 2年間すごすが、彼らが乗っていた船には、「2か月分の食料をはじめとして、ピストル、猟銃、散弾銃、信号弾、大砲などの武器、通信用ラッパ、望遠鏡、ゴムボート、寝具などが積み込まれていた。その他、大工道具、針や布、図書室の本がぎっしりと詰まっていた」ので、困窮することは全くなかった。
しかし八丈島の少年たちの生活は 縄文社会から、初期旧石器時代に逆戻りさせられたと同じことで、ゼロから道具を作って自然と戦わねばならなかった。 働けない大人に代わって子供たちが未熟なやり方で作った石器を使って、木を伐り、土を掘って、雨露を防ぐ掘っ立て小屋を作った。弓矢や槍などを製作することはできず、狩猟を行う道具も技術もないまま、植物採集でかろうじて飢えをしのぐだけの生活を送った。
十分な栄養を摂ることはできなかったから、子供が生まれても生育できた割合は低く、この集団の人口が増えたとしても遅々としていただろう。上陸時とあまり変わらないか、むしろ一人二人と人口を減らしつつ、「居住期間が100年以内」とされる、短命な歴史を残したのではなかろうか。
ただし、彼らが上陸してから数年ないし数十年後に、鬼界カルデラの超巨大噴火が起こった可能性がある。もしそうなら、噴火で生じたアカホヤ降灰で島の植物が少なくともその年は全滅し、一切、食料を得られなかったという可能性もあり、かれらは餓死してしまった、ということも考えられなくはない。
こうして湯浜人は丸木舟ではなく、筏で八丈島に着いたと考えられるが、筏は舵が利かない。筏で三宅島・御蔵島から八丈島に向かって、意図的・計画的に出航するということは到底あり得ない。つまり、湯浜人が筏で到着したとすれば、かれらは意図的・計画的に島に渡ってきたのではなく、偶然に漂着したのだ。
この節の最初の箇所で、八丈島の月桃は東南アジアを原産地とするもので、その種子が黒潮に乗って八丈島に流れついたとも考えられると述べたが、それと同様、八丈島に最初に到来した人間である湯浜人は、北部伊豆諸島を経由し、黒潮を横断して、意図的・計画的に渡島したのではなく、黒潮に乗って偶然に「漂着」したのだと考えられる。
そして、黒潮に「乗って」来たとすると、おそらく本土中央部ではなく、紀伊半島や、四国など西の方から、流されてきたのだと考えられる。しかし広い太平洋を漂流した後で、八丈島に流れ着く可能性はどれくらいあるのか。この点については、第5節で、黒潮の流路について詳しくみるので、そこで述べる。
筏による漂流ということについては、同じく第5節で、詳しく説明するつもりだが、たとえば、西日本の海岸に住んでいた人々が、津波に襲われ、住居ごと海に流された。近くに浮いていた漁撈用の筏に乗って助かったが、沖まで流され、黒潮によって八丈島まで運ばれた、あるいは何らかの理由で、住んでいた場所を変えようと筏を使って、岬の先端を回ろうとして、誤って沖に流されてしまい、やはり黒潮によって八丈島に運ばれた、というようなことが考えられる。
江戸時代200年間に御前崎から西の海上でしけに遭い、舵がきかなくなった大型帆船が、200隻も八丈島に漂着しているという事実がある。紀伊半島の南部を流れる黒潮は高い割合で八丈島を通過するのである。
第6節ではこうした黒潮の流路を調べ、本州島西部から漂流した筏が八丈島に漂着する可能性が十分にあることを示す。
湯浜人が神津島産の黒曜石を持っていたことは、彼らが本州中部から意図的・計画的に八丈島へと南下したということの論拠にはならない
ところで湯浜遺跡から出土したものの中にいくつかの黒曜石が存在し、いずれも神津島産であることが確かめられている。湯浜人が神津島産の黒曜石をもって八丈島に上陸したということは、彼らが八丈島への移住を目指し、移住先での石器製作のために、途中で神津島に寄った、ということを示しているのではないか。もしそうだとすれば、湯浜人が黒曜石を持っていたことは、かれらが意図的・計画的に八丈島に渡島したことの証拠になるように思われる。
だが、すでに述べたことだが、三宅島あるいは御蔵島から八丈島に渡るには筏では無理で丸木舟を使わざるを得ず、しかも凪の時に限られていて、上陸時に黒曜石を除いて無一物の状態だったことの説明がつかない。
もし、天候急変で丸木舟が転覆して、舟に積んでいた道具を失ったとするなら、黒曜石があったのにどうして上陸後に、鏃や槍などの道具を作らなかったのか、上陸した5,6名は屈強な漕ぎ手だったと考えられるが、なぜ彼らは狩りや漁に使う道具を作らず、植物採集の生活に甘んじたのか、が分からない。
湯浜人の遺物の中に神津島産の黒曜石が存在したからといって、それは、かれらの航海が八丈島への移住をめざした意図的・計画的ものであったことの証拠にはならない、と考えるべきである。
また、湯浜人が黒曜石を持っていたことは事実だとしても、必ずしも、彼らが、伊豆半島など本州中央部から出航し、伊豆諸島北部の島を伝って、計画的に八丈島に渡ってきたということを意味してはいない。というのも、神津島産の黒曜石は日本各地で広く使われていたからである。
第4節 神津島産の黒曜石は本州中央部だけでなく広く各地で使われてい
小田の2015年 『黒曜石分析から解明された新・海上の道-列島最古の旧石器文化を探る④-』によれば、「本州中央部山岳地の長野県矢出川遺跡の細石刃文化(約1万4,000年前)の黒曜石製石器に、200km以上も離れた太平洋上の神津島産(恩馳島)が多数確認され----ている」という。
そして、 武蔵野台地の旧石器時代遺跡から確認された神津島産黒曜石使用の最古の例は、東京都府中市武蔵台遺跡の立川ローム第Xa文化層(約3万2,000年前)の資料であり、
「縄文時代になっても、神津島産黒曜石は伊豆諸島の全島嶼遺跡や本州島に運ばれ、約5,000年前の縄文中期には関東・中部地方の太平洋岸を中心に、伊勢湾や霞ケ浦沿岸、さらに日本海側の能登半島へと本州中央部約200km範囲に分布した」という。
旧石器時代から縄文時代へ、地層、遺跡、
「立川ローム層第Ⅹa文化層」という語が出てくるが、この語の正確な意味が分からない。そこで少し調べた。
小田静夫『立川ローム第X層文化について―列島最古の旧石器文化を探る②―』2013.5、および小田静夫『考古調査ハンドブック⑨ 旧石器時代』ニューサイエンス社、平成26〔2014〕年5月によると、
武蔵野台地は基盤層の上部に「関東ローム」と呼ばれる火山灰層が厚く堆積しており、下から、多摩ローム(約40万~13万年前)、下末吉ローム(約13万~8万年前)、武蔵野ローム(約8万~4万年前)、立川ローム(約4万~1万5,000年前)の4つのローム層が堆積している。
『ハンドブック』図32「武蔵野台地の遺跡と編年」、図34「野川遺跡の層準と文化層」によれば、野川遺跡ではローム層の厚さは5mほどで、その下は武蔵野礫層という砂利の層になっているようだ。
「武蔵野台地の一般的な遺跡を発掘すると、表土(耕作土、近・現代)、黒色土(近世~古墳時代)、黒褐色土(弥生~縄文時代)という---遺物包含層が1m程度堆積している。そしてその下には、---「関東ローム層」が2m~3m近く堆積し、---基層である礫層や粘土層となっている。その中で旧石器時代の遺物が発見される層準は最上部の立川ローム層である」という。
また、1969・70年に実施された調布市、三鷹市、小金井にまたがる野川遺跡の発掘調査により、
第I層=表土(耕作土)、第Ⅱ層=黒褐色土で縄文時代までの遺物包含層の下、第Ⅲ層からが褐色の立川ローム層で、このローム層には第Ⅲから第ⅩⅢ〔13〕層までの13枚の自然層が重なっているが、
このうち第Ⅲ層から第Ⅷ〔8〕層までの堆積層中に10枚の文化層が存在し、旧石器時代の遺物・遺構が包含されていることが確認されたという。
そして小田は立川ローム層の年代を次のように推定している。左の竹岡俊樹『旧石器人の歴史』による図も参照

第Ⅲ〔3〕層:約13,000~14,000年前
第IV〔4〕層:約18,000~22,000年前
第V 〔5〕層:約23,000~24,000年前
第VI〔6〕層 : 姶良Tn火山灰層(AT)、約24,000~28,000年前
第Ⅶ〔7〕層:約23,000~26,000年前
第IX〔9〕層:約27,000~30,000年前
第X層上部は、約32,000~35,000年前
石器類がどの層から出土したかで、その石器文化の時代が分かるので、以下で、ローム層準で書かれた年代が気になるときには、ここを参照していただきたい。
なお、筆者には「ローム層Xa」がどこを指すのかははっきりしない。
「黒曜石の最古の例は3万2千年前」とされており、上記『ハンドブック』の図34、P134では、Ⅳ層が上から順にⅣa~Ⅳcという表記で細分されているので、X層の上部を指すのではないかと思われるが、不確かである。
なお姶良〔あいら〕Tn火山灰層(AT)とは、約2万9千年前に鹿児島湾(錦江湾)の北部姶良火山の超巨大噴火により噴出した火山灰が降り積もったもので、沖縄、朝鮮半島、青森県にまで及んでいる。
この火山灰が最初に丹沢山地で検出されたことから、姶良丹沢火山灰、あるいは姶良Tn降灰,AT降灰ともいう。Wikipediaなど参照。
さて、Wikipediaによると、人類は、猿人、原人、旧人、新人と進化した。(正確に言うと、そういう説がある。)
新人はホモ・サピエンス(現生人類)、旧人はすでに絶滅したホモ・ネアンデルターレンシス(ネアンデルタール人、デニソワ人)、原人はジャワ原人、北京原人などのホモ・エレクトス(直立する人)、ホモ・ハビリス(器用な人)、猿人はサルとヒトとの中間的な動物でアウストラロピテクスなどと呼ばれている。
ホモ・ハビリスは猿人と原人の中間段階とする説もある。このホモ・ハビリスが存在した時期(240万年前から140万年前)にヒト属は石器を使用し始めたようだ。
日本に原人が存在したことがあったかどうかは明らかではないが、旧人は存在したようである。(のちにふれる。)
日本では、2000年前くらいから鉄がつかわれるようになったが、それまでは石器が使われていた。
小田『ハンドブック』によって、以下概観する。稲田孝司『遊動する石器人』岩波書店、2001、も参照した。
旧石器時代の前期は約260万年前から約20万年前までの時期であり、打ち欠いた石の中心部(核)を使う石核石器を使用していた。
地域によって異なるが約200万年前から約5万年前までが中期旧石器時代、約5万年前から約1.3万年前までが後期旧石器時代である。
中期には原石周辺部を薄くはぎ取って二次加工して使う剥片石器が使われた。
日本の後期旧石器時代は、姶良火山噴火の時期をはさんで前半期と後半期に分けられ、前半期、3.5万年前~2.8万年前には石刃技法が発達した。 長さが幅の2倍以上ある薄く鋭い石の剥片を石刃(せきじん)bladeと呼び、あらかじめ円筒形ないし円錐形に調整し〔手を加え〕たサヌカイトや黒曜石などの石材から、剥片を連続的に剥がしとって、石刃を作り出す方法を石刃技法と呼んでいる。(稲田による)
 後半、2.8万年前から1.6万年前には、この石刃の様々な箇所に刃潰しを行なって調整したナイフ形石器が盛んに生産されたが、
後半、2.8万年前から1.6万年前には、この石刃の様々な箇所に刃潰しを行なって調整したナイフ形石器が盛んに生産されたが、調整の仕方にバリエーションがあり、東山型、杉久保型、茂呂型、国府(こう)型などと石器が出土した遺跡の名を取って呼ばれている。
1.6万年前~1.4万年頃の期間は、旧石器時代から新石器時代への過渡期(あるいは中石器時代)で、幅1センチ長さ5センチ以下の小さな石刃、すなわち細石刃の登場で代表される。
1.4万年前から1.1万年前の時期は、縄文時代「草創期」とほぼ重なる。「草創期」に続く6千年前ぐらいまでが「縄文早期」で、八丈島に湯浜人が漂着したのは早期の後半ごろ7千300年前頃である。
YouTubeで、研究者が黒曜石で製作したナイフ型石器で肉塊を切る動画をみたが、岩石を割って作った剥片が非常に鋭利で、現代の剃刀あるいは刺身包丁などと比べて少しも劣らぬ、鋭い切れ味を示していた。
こうした鋭い刃物を作るための石材として「黒曜石が代表的だ」と稲田は言う。
小田『黒曜石分析から解明された新・海上の道-列島最古の旧石器文化を探る④-』によれば、
酸性火山で作られる高温高圧のマグマが地表ないし地上近くで急冷するときに「黒曜石」が生じる。 黒曜石は火山ガラスで、割れ口が鋭く、また加工し易い美しい石材で、他の石材(チャート、砂岩、安山岩)に比べて群を抜いて優れた岩石である。
特に細かい整形を必要とする両面加工の尖頭器〔槍先〕や矢につける「石鏃(セキゾク)」、また鋭い刃が要求されるナイフ形石器、スクレイパーなどに多用された、という。
黒曜石の産地は日本中に80か所あるが、先史時代の遺跡がすべて黒曜石産地の近くにあったわけではない。
旧石器時代の人々が最初に石器を製作したときには、近所で入手できる石材を使ったに違いない。
ところが、上でふれたように、府中市武蔵台遺跡の立川ローム第Xa文化層(約3万2,000年前)から出土した黒曜石の資料11点を、X線分析法によって分析した結果、1点が神津島、7点が和田峠、1点が麦草峠の産であることが判明した。和田峠、麦草峠はともに長野県である。
すでにこの時代、武蔵野台の旧石器人は、直線距離で200㎞以上離れた場所の石材を使っていたのである。
そして、神津島産黒曜石は3万年以上前の関東地方で使われていただけでなく、
「約1万2,000年前の縄文時代になっても、神津島産黒曜石は伊豆諸島の全島嶼遺跡や本州島に運ばれ、約5,000年前の縄文中期には関東・中部地方の太平洋岸を中心に、伊勢湾や霞ケ浦沿岸、さらに日本海側の能登半島へと本州中央部約200km範囲に分布した」と、小田は言う。
旧石器時代人の黒曜石を求める行動
黒曜石ばかりでなく、ほかの石材も含め、旧石器時代の人々が石器づくりのために材料の石をもとめてどのような行動をとっていたかについて、稲田のいうところを聞いてみよう。
稲田によれば、南関東、千葉県北部に広がる下総台地上の遺跡からは、近くの河原などで入手できるチャート〔堆積岩の一種で、硬くて摩滅に強い岩石〕のほかに、信州産、箱根産、神津島産の黒曜石が見つかっている。旧石器時代後半には、黒曜石製の石器が半数以上占めるケースも目立つ。
また、伊豆・箱根の黒曜石産地に近い静岡県東部の愛鷹(あしたか)山から箱根山西山麓にかけての遺跡では、石器・剥片類の60%~80%が黒曜石で占められている。
蛍光X線分析法による原産地推定で、伊豆箱根系が92%で、残りの8%は100㎞以上離れている信州系であった。遺跡によっては90%以上が信州蓼科産で占められているケースもある。
つまり、愛鷹山山麓や伊豆・箱根地方の人々は、近くで黒曜石を入手できるにも関わらず、かなりの量の信州産黒曜石を併せて使っていたという。
同じ黒曜石といっても産地により少しずつ品質/性能が違っているようである。長期遊動の際に長野の原産地で発見したのだろうが、そちらの方がすぐれていたにしても、拠点の伊豆の野営地にまで運んでくる必要はあったのだろうか。
岩石は重い。中くらいの西瓜くらいの岩石でも30キロくらいあり、両手で持って10mも歩くのがやっとだ。
背負子のようなものを使うか、獣皮の袋に入れて肩にかけたかして、複数が交代しながら運んだのだろうが、薄い獣皮製の「靴」で道のないところを、山の斜面を上ったり、下りたりしながら運ぶのは大変な労力を要したはずだ。
稲田は、南関東の各集団が遊動中に伊豆・箱根地区で黒曜石を発見し、(再び)採集のために出掛けた折に、そこに暮らす人々に出会い、彼らから信州産を分けてもらうようになったのではないか、という。
つまり伊豆・箱根地区の人々は、自らも信州産を使っていたが、南関東の人々に譲渡すために、余分な量を信州から運んできていたと、いうのだ。おそらくそうだろう。
しかし、そもそもなぜ、彼らは、遠隔地で見つけた、(現代のハイテク機器をつかって成分を調べなければ違いの分からないような)性質・性能にわずかの差しかないものを、余分に本拠地まで運んだのか、そして、そこにたまたまやってきた南関東のよそ者にそれを分けてやることになったのだろうか。
稲田によると、天竜川沿いの磐田原台地の遺跡群では、信州や伊豆・箱根の黒曜石産地までの距離が武蔵野台地の人々とほぼ同じでありながら、ほとんど黒曜石を使っていなかった。
磐田原台地の人々は、北へ150㎞ほどの信州の黒曜石産地にも、また東へ100㎞ほどの伊豆箱根地区にもほとんど行かなかった。
稲田は「黒曜石の獲得は、自由な交換や交易に基づく経済行為の結果というよりも、押しなべて集団関係の結びつきの成果と言うべきだろう」と、磐田原台地の集団と伊豆箱根地区の集団との間の部族的関係が弱かったことが前者が黒曜石を手に入れることのできなかった原因だとしている。
稲田は、南関東では多くの河川が台地を開析〔侵食により地形面を細分化〕しているが、この小河川にそって複数の集団が遊動生活を送っていて、リーダー格の集団を中心に部族的関係を結んでいた、という。そしてこのような集団の間では黒曜石の入手、分配の仕組みが進んだというのである。
この考えには異論があるようだ。小野昭は「遺 跡分 布 か らみ た 旧石 器 時 代 の社 会―ナイフ型石器群を例とした分布の減少と実体」《第 四紀 研 究 (The Quaternary Research)》 26(3)January 1988 で、稲田の、(東京小平市にある)鈴木遺跡の黒曜石保有率が、野川流域の遺跡群全体に比べて高いことから、鈴木遺跡と他の武蔵野台地の集団の関係を主従関係にある とみなし、武蔵野台地の諸集団は単一の機構を形成していたという、想定に異を唱えている。
また、稲田は鈴木遺跡を100か所を越えるブロックからなる大集落・拠点集落と見るが、ブロックはひんぱ んな移動 あるいは定期的 回帰 の累積化 の結 果 と理 解 しなけれ ばな らない、という。
こうした異論の当否は別として、黒曜石の流通が、すべて、全く知らぬ者同士の偶然の出会いの際におこった交換の結果だと考えることもできず、普段の日常生活において多少でも交流のある人々(の集団)の間の関係を考えざるを得ないだろう。
磐田原台地の集団と伊豆箱根地区の集団あるいは信州の集団との間についてはそうしたつながりが薄かった、というのであれば、その通りだと思うが、しかし、それが磐田原台地の集団が黒曜石を利用しなかったことの説明になるのかと言えば、そうとも思えない。
黒曜石を利用しよう(したい)という動機が欠けていたから他の集団との結びつきをもとめなかった、とも考えられるからである。
むしろ、次のように考えられないか。集団によっては、黒曜石の優秀さを知ったとしても、それまで使ってきた石器による現在の生活にさほど不便を感じていなければ、あえて離れたところの他集団との関係を深める努力をしようと思わないだろう。
新しい物、新しい生活をとくにもとめない「保守的」な集団があり、また絶えず新しくすぐれたものを手に入れようとする「進歩主義的」な集団もあっただろう。集団が日常生活にたいして、また他の集団との関係に対して有する姿勢に、保守的か進歩主義的かの違いがある。
在地石材に黒曜石が存在しなかった場合、多少でも進歩主義的傾向があり、他の集団と関係を持つことに積極的な/消極的でない集団は、(同様に)敵対的でない/友好的な姿勢を持った他集団と出会った場合に、その人々が持っていた黒曜石に興味を示し、試しに使ってみたいと思い、何かと交換に少し分けてもらっただろう。
その黒曜石が優れていることがわかったら、その在処につれて行ってもらうように頼むか、時々あるいは恒常的に譲ってもらえるように交渉しただろう。
このような集団があちこちにあり、黒曜石の交換・交易の仕組みを発達させたと思われる。
こうした関係が何十年、何百年あるいは何千年か続く間に、神津島産あるいは和田峠・霧ケ峰産の黒曜石が本州中央部から、他の地域に広がったと思われる。そして、西のほうでは、東海、近畿にとどまらず、西日本全域に広がった可能性があると、私には思われる。
縄文時代の黒曜石の分布
ところで、稲田が、上で書いたような武蔵野台地など関東の集団や愛鷹山山麓、そして伊豆箱根地区の集団などの黒曜石に対する関わり方について述べているのは、立川ローム層のⅥ層ごろ(2万4千年前頃)のことである。
他方、湯浜人が八丈島に漂着したのは、縄文時代早期の終わりごろ、7千3百年前ごろのことであり、時期的に1万6千年~7千年の開きがある。このころにも神津島産の黒曜石は用いられていたかどうかが問題になるかもしれない。
 稲田(図66。p99)によれば、黒曜石の使用比率は立川ローム層第Ⅶ~Ⅵ(2.5万年前から2.4万年前)以降急増し、また第Ⅲ層上層(1.2万年前)以降、つまり、縄文時代草創期以降、急に減少している。(この本の刊行は2001年12月である。)
稲田(図66。p99)によれば、黒曜石の使用比率は立川ローム層第Ⅶ~Ⅵ(2.5万年前から2.4万年前)以降急増し、また第Ⅲ層上層(1.2万年前)以降、つまり、縄文時代草創期以降、急に減少している。(この本の刊行は2001年12月である。) 稲田は縄文時代についての黒曜石の流通や利用のされ方については触れてはいないが、この図からは縄文時代には黒曜石使用比率が(少なくとも関東では)大きく減少したように見える。
関東や中部地方など黒曜石産地の近くでの流通が減少すれば、近畿・東海などでも同じように減少するか、あるいはもっと減るだろう。その場合には、近畿・東海地方への神津島産黒曜石の広がりを予想することはできなくなる。
しかし、杉原重夫、小林三郎 「考古遺物の自然科学的分析による原産地と流通経路に関する研究-神津島産黒曜石について」(明治大学人文科学研究所年報,48,2008.2.28)では、むしろ縄文時代に黒曜石の利用が拡大した、とされている。
この論文によると、相模野台地、武蔵野台地、下総台地などの後期旧石器時代の遺跡から出土する黒曜石は箱根産、天城産、信州産が多く、「神津島産黒曜石を出土する旧石器時代の遺跡数は必ずしも多くない」。
他方、 神津島産黒曜石は「相模野・武蔵野台地とも,Ⅲ層段階〔1.4~1.2万年前〕で出土数がかなり多くなる」。「立川ローム層最上部〔=Ⅲ層〕で神津島産黒曜石の出土が著しい傾向は、下総台地でも認められる 」。
縄文時代の早期~前期になると、房総半島、三浦半島などの遺跡で、神津島産黒曜石は80%程度であった。
相模湾北岸地域では、縄文時代草創期〔約1万6000年~1万2千年前〕、早期、前期〔約7000年~5500年前〕の遺跡で「神津島産黒曜石の出土が目立ち、なかには全試料のほとんどが、神津島産黒曜石で占めるところもある」。
東京湾北岸地域では、縄文時代前期の遺跡に、「神津島産黒曜石の産出が著しい」。下総台地では、縄文時代草創期以降に神津島産黒曜石がみられるし、早期以降に神津島産黒曜石の優勢な遺跡が出現し、前期末では神津島産黒曜石の占有率が著しく高くなる」という。
また、杉原重夫・金成太郎 〈研究報告〉「静岡県、休場遺跡出土黒曜石製遺物の原産地推定一神津島産黒曜石の利用について」明治大学博物館研究報告 第15号、2010年3月 によると、
沼津市愛鷹山南麓に休場(やすみば)遺跡という、旧石器時代末期、およそ1万年前ごろつまり縄文時代早期の遺跡があり、黒曜石製の遺物が出土している。ここから出土した黒曜石製遺物551点のうち判別した479点の推定原産地は
神津島に属する恩馳島産が466点、信州和田峠系などが16点、伊豆柏峠産が2点で、97.3%が神津島産と判定された。
そして、この論文では愛鷹山南麓、相模野台地、武蔵野台地でほぼ時期を同じくして広く神津島産黒曜石が利用されるようになるとし、この時期に、それ以前の時代と比較して流通システムがより確立したと考えられる、という。
こうした杉原らのより新しい研究にもとづく説明によれば、縄文時代早期、つまり八丈島に湯浜人が漂着した時期には、神津島産黒曜石が少なくとも関東地方では広く流通していた。
池谷信之「旧石器時代の神津島産黒曜石と現生人類の海上渡航」安斎正人編『理論考古学の実線 Ⅱ実践編』同成社、2017によると
2000年以降に、愛鷹山麓で高速道路建設に伴う大規模な発掘調査が本格化し、多くの遺跡から神津島産黒曜石が出土したこと、またこのころから関東地方で「全点分析」が多くの遺跡で試みられるようになり、池谷らの蛍光X線だけでなく、より「分解能に優れた中性子放射化分析」による検証なども行われた結果、推定が正しいことが何度も確かめられた。
こうしたことから、神津島産の黒曜石が後期旧石器時代初期に海を越えて南関東に搬入されていたことは確かな事実と考えられている。(ただし、のちにふれる懐疑論もあるという。)
そして、池谷の調べでは、神津島産黒曜石の出土例は武蔵野Xa層からⅨ層段階に集中し、その後急激に減少するが、供給が完全に途絶えることはなく細石器段階(1.6万年~1.4万年前)に至るまで間欠的に、続いた、とされる。 そして、杉原らの調査結果からは、細石刃段階移行、縄文時代草創期から早期に神津島産黒曜石の利用は再び盛んになり、その後も黒曜石利用は続いたと考えられる。 稲田の『遊動する旧石器人』の刊行は2001年12月であり、杉原らの研究論文の発表は6年以上後であり、その間に研究が進んだのだろう。以下では、杉原らの説明に従って、縄文時代早期の黒曜石分布状況についての議論を進めることにする。
東海地方における石材利用と黒曜石の分布
さて、縄文時代早期、神津島産黒曜石の使用は関東地方では、盛んに広がっていた。では近畿から西の方ではどうだったか。 適当な参考書を見つけることができなかったので、岐阜、愛知、三重、3県の遺跡発掘調査報告書に当たって、石器の出土状況を調べてみた。
もし、湯浜人が伊豆半島など本州中央部から、伊豆諸島を伝って、八丈島に渡ったのではなく、太平洋岸に住んでいた人が何らかの原因で沖に流され黒潮に乗って漂流した結果、八丈島に着いたのだとすれば、そして彼らは神津島産の黒曜石を持っていたのだから、彼らが住んでいた地域に神津島産の黒曜石が広がっていたはずである。
神津島産黒曜石は本州中央部より西、少なくとも静岡県の西半分以西の、伊勢湾周辺、紀伊半島、そして四国、さらに九州の太平洋岸の地域のどこまで広がっていたのだろうか。
小田が何も言っていないのだから、おそらく、伊勢地方(三重)よりも西では神津島産黒曜石は(2.15年段階では)見つかっていない/いなかったのだろう。
だが、たとえば、岐阜県の西部で福井県、滋賀県と接する(揖斐川町)藤橋村地区戸入村平遺跡では長野県の霧ケ峰産の黒曜石の他に、神津島産と柏峠(伊豆)産の黒曜石が出土している。
しかし、そもそも直線距離にして2百数十㎞も離れた近畿地方にまで、神津島産黒曜石が広がったこと自体が不思議に思われる。
そして 大阪と奈良の県境の二上山(*)は、黒曜石に匹敵する石材であるサヌカイト産地である。そしてまた瀬戸内・香川の金山(かなやま)でもサヌカイトを産出する。実際、関西地方出土の石鏃の多くはサヌカイト製である。また島根の沖の隠岐諸島では黒曜石を産する。多くはないが隠岐産の黒曜石も使われている。
(*)二上山(にじょうさん/ざん)は、大阪平野と奈良盆地を隔てる生駒山地の南部にある。二上山の北西6~7kmのところには藤井寺市があり、市には次の節でふれる国府(こう)系文化・瀬戸内技法集団の残した国府遺跡がある。
そこで、奈良・大阪から西の地域では、滋賀と三重の間の鈴鹿山地、あるいはその南に連なる布引山地を越えて、東の神津島産黒曜石、あるいは信州産の黒曜石を手に入れようという動機が存在しなかったか小さかったと考えられる。
西日本では、神津島産の黒曜石も信州産の黒曜石も必要なく、したがって広がらなかったと考える人もあるかもしれない。
しかし、当時の人々は、現代人のように旅行の途中で店を利用して食事をしたり弁当を買ったりすることはできず、狩猟・採集によって食料を調達しつつ移動したのであり、そのための道具である石器とその補充のための石材を常に携帯する必要があった。
人々の移動があれば、それに伴って、必ず石器と石材も移動したはずである。場合によっては石器・石材の交易目的の移動もあっただろう。
また、行く先々で知らない集団同士が出会ったとき、場合によっては争いになったかもしれないが、仲良く応対することができ、持ち物の一部をプレゼントし合うというようなこともあっただろうし、東から西へと遠距離遊動する集団は、西の地域を通るときに、「通行料」代わりにするため、関東の優れた黒曜石を余分に携帯し、地元の集団にプレゼントしたかもしれない。
そして、実際、旧石器時代の末頃、様々な集団が、東日本から関西へと移動し、また関西の集団が関東へと移動している。
瀬戸内技法・国府系文化集団の移動
竹岡俊樹『旧石器時代人の歴史』講談社、2011年 によると、旧石器時代に大阪・藤井寺市の国府(コウ)遺跡をはじめとする多くの遺跡を残したホモ・ハイデルベルゲンシス〔日本型のネアンデルタール人〕集団が存在した。
彼らはAT降灰期(約2万9千年前~2万6千年前)以前からサヌカイトの一大産地である香川県の国分台周辺で、瀬戸内技法と呼ばれる方法で国府系ナイフ型石器を作って暮らしていたが、AT降灰期後、長期遊動・移動を活発に行い、国府系文化は、北は福島県にまで及び、西は九州に及んだ。
 左の国府型ナイフ型石器の写真は<Web風土記藤井寺>「国府遺跡」https://www.ne.jp/asahi/fudoki/fujiidera/06)bunkazai/2)kou-iseki/kouiseki.html による。
左の国府型ナイフ型石器の写真は<Web風土記藤井寺>「国府遺跡」https://www.ne.jp/asahi/fudoki/fujiidera/06)bunkazai/2)kou-iseki/kouiseki.html による。このHPの著者は 「瀬戸内技法の特徴は、〔第一工程で作った盤状の剥片を翼状破片に加工する〕第2工程にあります。翼状剥片を一定の厚みで連続的にはぎ取っていき、それをナイフの素材とするものです。---- 翼状剥片を連続的にはぎ取っていく技法は、サヌカイトという石が持つ独特の割れ方をよく知っていて確立された技術だと考えられます。---
サヌカイトの最大の特徴は、何と言ってもその堅さにあります。私もサヌカイトの塊を砕いた経験がありますが、なかなか大変な思いをしました。鋼鉄製のタガネを当ててハンマーでたたくのですが、簡単には割れません。尖っていたタガネの先がすぐに丸くなりました。
鉄器も無い時代に古代人はどうやってサヌカイトを割ったのだろうかと、思わず彼らの智恵を尊敬しました。サヌカイトが持つ独特の割れ方を知っていなければ、連続的に翼状剥片を作ることなどとても無理なことです。」
と書いている。同ページの他の図を参考にすると写真のナイフ形石器の長さは5センチくらいのようだ。
竹岡によれば、この瀬戸内技法集団は、移動先で出会った文化を取り入れ変容し、「類国府系文化」と呼ばれる先土器文化を各地で残した。また一部は時を経て再び瀬戸内地方に戻った、という。
この人々は移動先の文化(主に石器製作法である)を模倣・吸収したとされているから、関東地方では黒曜石も使用したに違いない。したがって「類国府系文化」を持つ一部の集団が関西地方に回帰したときに、黒曜石をもって来た可能性があるだろう。
「矢出川技法」による細石刃石器群の広がり
堤 隆「後期旧石器時代の石器群 と寒冷環境への適応戦略 」『第 四 紀 研 究(The Quaternary Research)』42 (3),2003によると
信州、野辺山の矢出川(やでがわ)遺跡の旧石器人は近くの八ヶ岳・麦草峠の黒曜石を用いたほかに、30㎞ほど離れたところにある和田峠などその他の場所の(より良質の)黒曜石を用いていた。
また、矢出川遺跡からは後期旧石器時代の最終末期に位置づけられる細石刃石核が出土しており、石器の中には200km離れた神津島産の黒曜石が多数ある。
この地域で製作された尖頭器(槍の穂先)は100km以上離れた関東地方の諸遺跡に搬入された。また、矢出川集団は、それまで一般的だった「原料補給型」ではなく、完成品または半完成品を移動の先々に持ち込むという「製品補給型のシステム」を作ったともいう。
後期旧石器時代の後半期末葉には列島全域において細石刃石器群が広がった。北海道から東北日本を中心に「湧別技法」による北方系の細石刃石器群が展開した。
他方、「湧別技法」と対峙するように 「矢出川技法」による細石刃石器群が 西南日本に広がった、という。
 堤にしたがうと、矢出川集団は和田峠周辺で製作した尖頭器などの石器を関東地方に供給しただけでなく、
堤にしたがうと、矢出川集団は和田峠周辺で製作した尖頭器などの石器を関東地方に供給しただけでなく、関東地方で展開したのと同様の新たな供給システムを作って、中部地方以西の西南日本へも細石刃石器群を供給したと思われる。
黒曜石で製作された石器もあり、出土した石材には信州産・和田峠系の黒曜石ばかりでなく、
神津島産の黒曜石も多数あったとされているから、神津島産黒曜石製石器の完成品あるいは半完成品が中部以西の地域に分布した可能性も十分にあると思われる。
湧別技法集団の細石器刃文化の広がり
稲田によれば「本州・四国・九州の細石器刃文化は約1万4000年前に円錐形・角柱形細石器核をもつ石器群が出現して始まる」。
そして「円錐形・角柱形細石器核を持った文化は本州北端まで波及したらしい。このあと北海道から湧別技法を持った細石器刃文化が南下し、結果として、〔湧別技法の〕北東日本・石器人文化と、円錐形・角柱形細石器核とそのあとに現れた船野型細石器核が主体となる南西日本細石器文化が、関東・中部地方を境にして対峙するような形勢になる」という。
だが、湧別技法集団の細石器刃文化は関東・中部地方の北東側に広がり、南西日本には及ばなかった。東海・近畿以西の西南日本には矢出川技法による細石器刃文化が広がった、というのではなく、湧別技法集団は日本海を主な植民領域としつつ、関東地方にも中部山岳地方にも進出した。
湧別技法集団は「長距離の回帰遊動を行ない」、さらに日本海沿岸部をたどって山陰地方から中国山地に植民領域を形成した。そして山陰地方の拠点となったのが岡山県の恩原遺跡1・2だ、と稲田は言う。
だが、円錐形・角柱形細石核の石器群は黒曜石あるいはチャートを主な石材とするが、湧別技法集団は、進出先においても、石器・剥片類の80%以上に最初の植民地であった東北地方日本海側特産の珪質頁岩を用いている、とされている。
すると、湧別技法集団の南西日本への進出があったからといって、ただちに、中部山地(信州)産の黒曜石が、そしてそれに交じって神津島産の黒曜石が南西日本に搬入されたと推定することができるわけでもないようだ。
ただし、中部山岳地域のいくつかの遺跡ではたしかに、湧別技法による黒曜石やチャートなど在地の石材で製作された細石器刃が出土していて、これら遺跡の場合には湧別技法集団は本拠地に回帰せず、在地石材に順応して住み着いたのだろう、と稲田は言う。
では、いったん在地石材に順応して住み着いた湧別技法集団は、もうそれ以上遊動・移動しなかったのだろうか。もし彼ら(の一部)が東海・近畿地方に遊動することがあったなら、信州や神津島産の黒曜石は関西にも搬入された可能性があるといえるのではないか。
そして実際、上峯篤史・大塚 宜明・金成 太郎 「滋賀県大津市真野遺跡の旧石器―湧別系細石刃核をふくむ資料群の発見」『旧石器考古学』82,2017は
琵琶湖南西岸の真野遺跡から出土した「細石刃核は黒曜岩〔=黒曜石〕製で、しかも湧別系の技術的特徴を備えていた。
これは近畿地方における細石刃関連資料に一事例を加えるだけでなく、湧別技法を携えた東北日本系細石刃石器群の南下と山陰地方への「植民」、近畿地方への遊動(稲田 1996)を物語る」という。
滋賀県の平成5〔1993〕年度から平成8年度にかけての調査で 縄文時代早期中葉を主体とする土器や石器が出土していたが、上峯ら執筆者がすべての石製資料をつぶさに観察した結果をこの論文にまとめた。
黒曜岩製遺物は細石刃核一点を含め12点あり、蛍光X線分析装置を用いた原産地推定で、11点は隠岐系または壱岐系で、1点は信州産、西霧ケ峰系または和田峠・鷹山系と判定された。
黒曜岩製以外の石器の多くはサヌカイト製で大半は二上山産だが、金山(*)産のものも混じっている。ほかにチャート製の石器もある。細石器刃石器群に属する資料は黒曜岩製及びチャート製の12点あり、湧別技法によるものである、という。
(*)金山(かなやま)は香川県坂出市南西部にある。この北東5~6㎞に瀬戸内技法集団の拠点、国分台がある。
一方、1981年頃、鳥取県境に近い岡山県北部の恩原高原で遺跡が発見されたが、その後、詳しい発掘調査の結果、3万年前にさかのぼる台形石器群、2万年以上前のナイフ型石器群とともに、18,000年~16,000年前の層から、湧別技法による細石器刃石器群が出土している。日本旧石器学会HP>「日本列島の旧石器時代遺跡>「恩原1・2遺跡」(執筆者は稲田。)
こうして、旧石器時代末期から縄文時代早期にかけて人々は、西へも東へも移動・遊動しつつ、行く先々の地で様々な石材を採取し、利用していた。
黒曜石の産地が存在しない近畿・東海地方で、盛んに中部・関東地方の黒曜石が使われており、神津島産の黒曜石を使っている遺跡も存在するなら、そして、岐阜・三重両県と滋賀県との県境をなしている伊吹山地と鈴鹿山脈―その鞍部に本州の東と西を分けると考えられている関ケ原がある―で本州の西と東が完全に分断されており、人々の往来・出会い・交流が全くなかったというのでないならば、この山地の西側にも神津島産黒曜石が持ち込まれた可能性がある、と私は思う。そして琵琶湖南東部の真野遺跡は、すでに関西地域に属する。
そこで 東海地方、岐阜・愛知・三重の3県(*)の遺跡で、どのような石材が使われていたのか、そして神津島産の黒曜石がそこにどれくらい入っているかを確かめてみた。
(*)東海地方というとき、普通は静岡を含むようだが、ここでは静岡は中部地方とする。また三重は近畿地方に数えられることもあるようだが、ここではこの3県を「東海地方」とする。)
<奈良文化財研究所>「全国遺跡報告総覧」により、県ごとに、「旧石器」&「縄文」などをキーワードにして検索した。調査報告書が刊行されている遺跡の数は非常に多いが、目を通すことのできたものは pdf 化されていてWeb上で閲覧できるものに限られている。
目を通した報告書は各県で10数点であり、ごく一部に限られているが、大体の傾向は分かったように思う。検索した遺跡調査報告書の抜き書きを末尾にまとめて掲げた。
岐阜県の遺跡における石材利用と黒曜石
「3県の遺跡地図」を参照していただきたい。図は、国交省中部地方整備局の「伊勢湾環境データベース」の地図を利用し、G1~M16など遺跡番号を書き込んだ。まず岐阜県から見ていく。
岐阜県は、北部の飛騨山地で、東の長野県、北の富山県に接する。この地域にある5つの遺跡(G1~G5:クリックで参照)では、出土している縄文早期の石器の素材は、下呂石、チャートが大半だが、黒曜石が15%ほど使われている。
チャートはいずれの遺跡でも近くで比較的簡単に採集できるようだが、下呂石を取るためには飛弾市付近から直線で50㎞以上離れた南の(下呂市)湯ケ峰まで行かねばならない。
黒曜石産地の分析は行われていないため、神津島産が混じっているかどうかは分からないが、多くは信州産と考えられる。黒曜石が採取できる和田峠周辺までは直線で100㎞ある。
岐阜県のほぼ中央部関市武芸川(むげがわ)町の岩井戸岩陰遺跡(G6)の出土石器の大半はチャート製で、前を流れる武儀川(むぎがわ)で調達可能。半径10㎞以内で採取できる安山岩・頁岩などが一定量出土している。 また サヌカイト製や下呂石製石器が少量出土している。下呂石産地の湯が峰までは直線で50kmくらいか。
サヌカイトは岐阜県内では産しない。少量の石を入手するために大阪と奈良の境にある二上山(直線距離で約140km)まで出かけたとは考えにくいので、産地に近いところをテリトリーにしている他の集団から譲り受けたのではないか。
下呂石は旧石器時代から利用されていたが、流通・交易が盛んになったのは縄文後期以降だという。(→川添和暁「縄文時代後晩期における剥片石器石材についてー尾張・三河地域の剥片石核類からー」愛知県埋蔵文化財センター研究紀要第17号、2016.5 )
福井、石川との県境にある岐阜県西部徳山ダム水没地区のはいずめ遺跡など3遺跡(G7、G8)では、チャート、砂岩など、近くで採集できる石材が主に使用されている。しかしいずれの遺跡からも黒曜石製品が1点ずつ出土している。
産地分析は行われてない。信州産ではないかと考えられるが、もしかしたら神津島産かもしれない。いずれにしても、ほかの集団から譲り受けたと考えられる。
だが、同じ徳山ダム水没地区にある戸入村平遺跡(G9)でも、石鏃349点のうち、徳山地域で手に入りやすいチャート製が312点で圧倒的に多いが、サヌカイト、下呂石、黒曜石など遠隔地の石材も少量ながら存在する。
この遺跡から出土したサヌカイトと黒曜石については藁科が分析を行っていて、11点の黒曜石のうち、信州産が9点(霧ケ峰が8点、和田峠が1点)、神津島産が1点、伊豆・柏峠産が1点だった。サヌカイト25点は、判別不可を除き、ほとんどが二上山産、2点が金山産だった。
調査報告書の著者は、黒曜石もサヌカイトも少量であり、「この遺跡に住んでいた人々が直截採取してきたとは考えにくい。何らかの交易によってこの地にやってきたものと思われる」という。
滋賀県との県境、関ヶ原町の小関御祭田遺跡(G10)は縄文中期の遺跡だが、1979年と1997年の2回調査が行われ、それぞれ225点、175点の石器が出土、チャートが89%と82%、サヌカイトは6.1%と2.8%、黒曜石は2回とも1.7%で、チャート使用が断然多いこと、黒曜石が数点あることがはっきりしている。1997年の調査で出土した黒曜石は藁科の分析で信州霧ヶ峰産と分かっている。
愛知県との県境にある野笹遺跡(G12)は縄文中期の遺跡だが、「使用石材は、下呂石229点(76.4%)、サヌカイト11点(3.6%)、黒曜石1点(0.3%)、チャート50点(16.7%)安山岩9点(3.0%)で、下呂石が圧倒的に多い」。
野笹遺跡を同じ時代の小関御祭田遺跡と比べると、下呂石を多く使っているのは、産地に30㎞ほどと比較的近いためだろうか。藁科の分析で、すべて下呂産である。おなじく藁科の分析で黒曜石はすべて信州霧ヶ峰産であった。
このように、岐阜県内の遺跡で出土した石器の石材の種類については大まか見たかぎりでは、各遺跡の近くで採れるチャートの使用が多いが、やや足を伸ばした所(50㎞程度)に行けば入手できる下呂石がかなりつかわれている。また、遠方(100㎞以上)の信州産黒曜石もある程度使われている。そしてごく少量だが、伊豆地方あるいは神津島産の黒曜石が混じっている。
徳山ダム水没地区の遺跡、また関ケ原地区の遺跡では地元産のチャートの他に、西と東の遠隔地のサヌカイトと黒曜石が使われていた。
この地の遺跡を残した人々は、すでにその地域にほぼ定住していたと考えられ、それら少量の石材を自ら遠隔地に出掛けて直接採取していたとは考えにくく、遺跡調査書の著者が述べているように、何らかの交易によって持ち込まれたのかもしれない。
だが、「交易」が石材の採取・運搬を専門に行う集団の存在を含意するとすれば(小田静夫「黒曜石分析から解明された新・海上の道」など)、必ずしも交易によるものではなく、東西に長距離遊動していた集団が、行く先々の地に住む人々との摩擦を避け、スムーズに通行・通過するための、「通行料」のようなものとしてプレゼントすることを前提に、携帯していた余分の石材や石器を、通過地域に住む人々に渡したこともあったのではないだろうか。
そして、細石器刃や石鏃など小型の石器や優れた石材の小さな礫はさほどかさばらず持ち運びに適していただろうし、黒曜石はわずか数グラムでも受け取った人々に宝物のように珍重された可能性がある。

例えば、次の節でふれる川向東貝津遺跡A1の発掘調査書 p197、図3-26「縄文時代の石器5-1」には、151番から164番までの黒曜石製石鏃の図が載っているが、
幅は1センチ程度、長さが2センチ以下、厚さは2~3ミリで、黒曜石の比重は2.4なので、重さは1個せいぜい1グラムで、1円玉と同じくらいの重さと思われる。
北海道で見つかった霧ケ峰産の鏃は0.8グラムだ。また高知県四万十市十和(とうわ)地区の遺跡から出土した矢尻は、0.1から0.2グラムだ。十和村埋蔵文化財発掘調査報告第6集、高知県幡多郡十和村 川口新階遺跡、轟遺跡、中亀越遺跡、小ノ田・カミヒラ遺跡、今成遺跡、上広瀬遺跡、広瀬遺跡」2004.3
100個くらいプレゼント用に余分に持って旅をしても負担にはならなかったと思われる。
愛知県の遺跡における 石材と黒曜石
愛知県の北東部に位置し、長野県と境を接する北設楽郡設楽町にある川向東貝津(かわむきひがしかいつ)遺跡(A1)では、2010年の調査に続く2015年の調査で、後期旧石器時代から縄文時代草創期の膨大な石器群が出土した。
後期旧石器時代の細石器文化として分類できる遺物が130点あり、下呂石(?)、チャート、溶結凝灰岩、安山岩などの石材に交じり、黒曜石も2点あった。
また縄文時代の石鏃21点は下呂石、黒曜石、安山岩、溶結凝灰岩で、石錐2点は黒曜石製。削器4点はチャート、安山岩、楔形石器は溶結凝灰岩、黒曜石など。
出土した黒曜石82点は、蛍光X線分析により、原産地の推定が行われ、ほとんどは長野県産であった。長野県には4か所の産地があるが、そのうちの和田峠系-2の産である。北設楽郡からは直線距離でほぼ120kmである。また神津島産が3個あった。
同じ設楽郡の市場口遺跡や上品野遺跡など3遺跡(A2~A4)からも、黒曜石製の石鏃、石錐、等が出土しており、産地分析の行われた3遺跡に関しては、何れも信州産であった。
また、設楽町に隣接する豊根村域にある茶臼山遺跡は、昭和 36・38(1961・1963)年に組織的に発掘調査された、愛知県を代表する後期旧石器時代遺跡である、という。
高見俊樹「茶臼山遺跡」(Communications of thePalaeo Perspective 旧石器時代研究への視座 Vol.2、2020)によると、「関東地方〔の岩宿遺跡〕以外で初めて発掘調査され、日本列島における旧石器時代の存在を確固たるものにした重要な遺跡 」で、「大量の出土遺物の多くは、黒曜石製の剥片である 」とされている。
産地の分析は行われていないようだ。川向東貝津遺跡出土の石器と同様、茶臼山遺跡出土の黒曜石の多くは信州産かもしれないが、そうだとすると前者の場合同様、いくつかは神津島産も混じっている可能性がある。
愛知県南東部、静岡県に接する新城(しんしろ)市にある、石座(いわくら)神社遺跡 (A5)からは、後期旧石器時代から縄文時代早期に属する遺物が多数出土している。
石鏃、石錐などの石材は熔結凝灰岩、凝灰岩21点、黒曜石、安山岩、下呂石、チャートなどである。エネルギー分散型蛍光X線分析装置による 分析結果によると、多くは信州産及び信州産?であるが、神津島産?が3個あった。?マークがついているのは被熱して領域が幾分ずれることによるものである。 また、伊豆・箱根系のものはなかった。
新城市、岡崎市の3遺跡(A6~A8)から多数の黒曜石製遺物(石器と剥片)が出土しているが、いずれも信州産であった。
岡崎市の車塚遺跡(A9)、豊田市の坂口遺跡(A10)出土の黒曜石は産地分析が行われていない。
豊田市の水汲遺跡(A11)から出土した石材は、3県の中でも最も多くの黒曜石をふくんでおり、 黒曜石205、安山岩1391、下呂石268、サヌカイト4、チャート1201、片麻岩34、溶結凝灰岩360、その他で計3516だった。(長田、第23表)
黒曜石202点の産地分析結果は星が塔192、小深沢6、神津島3、不明1だった。(同、第24表)
星が塔遺跡は信州下諏訪町。小深沢は国土地理院の地図にも地名が載っていないが、中村 由克「和田・鷹山地域の黒曜石河川礫の分布調査」<資源環境と人類 第 5 号> 2015 年 の図2によれば和田峠の西側、すぐ近くにある。
こうして、愛知県内の遺跡からも、黒曜石製の石器が出土しており、その産地は信州である場合が多いが、また時々神津島産も混じっている。そして、産地分析が行われていないケースも多い。分析が進めば、神津島産黒曜石の愛知への分布がより一層明らかになる可能性がある。
三重県の遺跡における 石材と黒曜石
三重県は私がWebで発掘調査報告書を直接閲覧できた14の遺跡においては、縄文時代早期の鈴山遺跡(M1)と宮の前遺跡(M5)の2遺跡以外、黒曜石出土はなく、石材はチャートかサヌカイトでほとんど占められていた。宮の前遺跡(報告書は1995刊)では、サヌカイト製の石鏃が4個、黒曜石の二次加工有剥片、ほかに黒曜石石核1点が出土しているが、この報告書の著者によると「縄文時代に黒曜石の三重県下への搬入は、無いことはないが極めて珍しい」 という。
しかし、宮の前遺跡より20年ほど後で調査の行われた菰野町の鈴山遺跡(報告書は2018年刊)では、石材の割合は、サヌカイトが大半を占め、次にチャート・下呂石・黒曜石の順に多い、としている。
石鏃1点の他16の薄片資料の黒曜石産地はエネルギー分散型蛍光X線分析装置による元素分析 で、産地の判明した12点は、いずれも信州産であった。
三重県の遺跡はほぼ北から番号順にならべてある。菰野町は三重県では岐阜県との県境の町いなべ市の南隣にあり、岐阜県境まで15㎞ほどと近い。このことが鈴山遺跡での黒曜石資料16点の出土を説明しているのかもしれない。
つまり三重県北部の地域は、岐阜県、および愛知県と接している。この両県の遺跡の多くでは、信州産の黒曜石が使われていた。したがって、三重県北部の遺跡の人々はこれら両県の人々と交わる機会があり、これらの人々を通じて黒曜石を入手することができた。(言うまでもないが、山や川は人々を遠ざける境界になったとしても、県境は、この時代の人々にとっては全く存在していない。)
あるいはまた、岐阜や愛知の人々は専門集団によらず、各遺跡ごとにあるいはいくつかの遺跡がまとまってチーム作って派遣、信州産黒曜石を自前で採取していた可能性があるが、鈴山遺跡でも自前で採取に出かけていたかもしれない。
ただし、中野山遺跡(M2、縄文早期)は四日市市北山町にあり、こちらは菰野町よりも岐阜と愛知に近いが、こちらでは黒曜石の出土はない。存続した時期が同じ「縄文早期」で、鈴山遺跡と同じころに存在していたならば、中野山遺跡の人々は「保守的」だったのかもしれない。
他方、県南部の櫛田川沿岸の遺跡(M9、粥見井尻遺跡)や、多気郡、度会(わたらい)郡など、三重県南部の宮川流域のいくつか遺跡では、宮川周辺で採取できるチャート製の石器がほとんどである。
だがまた、黒曜石製石器はないが、チャートの他にサヌカイトを使った石器を出土している遺跡も多い。 山籠遺跡(M5)から出土した石鏃10点はすべてサヌカイト製、松阪市の山添遺跡(縄文前期,M7)、 鴻の木遺跡 (縄文早期、M8)では、石鏃の大部分がサヌカイト製である。
西出遺跡(M6、安芸アゲ郡美里村、現在津市美里町)からもサヌカイト製品が出土している。三重県埋蔵文化財調査報告 92-4、「西出遺跡・井之広遺跡」1990によると、この遺跡の遺物は「段階の異なる押型文土器が混在状態で出土しており、一括性のある遺構の認定が行なわれていない」という。
だが、三重県HP「続・発見三重の歴史」第86話(2008/2/8)「広域交流の証しが出土―縄文時代早期の津市・西出遺跡 」(三重県史編さんグループ 田中喜久雄))によると、
西出遺跡は「押型文(おしがたもん)土器」が出土していることから「7,000年~8,000年前の縄文時代早期のものであることが分かる。---鏃(やじり)などの石器類はごく少量だったが、大阪・奈良県境の二上山(にじょうざん)産出のサヌカイト製のものが含まれていることも分かっている。地図で見ると、西出遺跡と神宮寺遺跡のある交野市との間は直線距離で約60㎞、二上山とは同じく 約60㎞の距離がある。おそらく木津川から服部川流域を伝って美里村に達したものと推測される」という。
西出遺跡から神宮寺式押型文土器が出土していることから、この形式の土器の製品が大阪交野(かたの)市の神宮寺から西出に運ばれたか、あるいは土器製作様式が西出に伝授されたかしたことが推測される、というのだ。
三重県内にはサヌカイト山地はなく、美里町に住んだ人々は「直線距離で60km」、川沿いに行ったとするとおそらく100㎞以上あったのではないかと思われる二上山まで行ってサヌカイトを採取していた。
他方、交野から二上山までは直線距離で30kmほどと比較的近い。神宮寺遺跡に住んだ人々も、当然、二上山に行ってサヌカイトを採取していただろう。
両地区の人々が、それぞれサヌカイトを採取するために同じ場所を訪れ、そこで出会ったことがきっかけになって、両地区の人々の交流が始まったのかもしれない。
あるいは二つの地区の集団は、この時期には離れた場所で暮らしていたが、もともと同じ祖先をもつ集団で、交流は以前からあったのかもしれない。
しかし、いずれにせよ、三重県側の西出遺跡の人々は二上山に時々出かけてサヌカイトを採集し(場合によっては、田中の示すような道で神宮寺に行き神宮寺の人々が余分に採集しておいたサヌカイトを譲り受け)、石器製作に用いていた。
西出遺跡の他にも、鈴山遺跡や松阪市の2遺跡(M7とM8)では、主としてサヌカイトが使われており、三重の人々が二上山に出掛けて直接採取していたか、あるいは、その付近の人々から譲り受けるかしていたことは確かで、三重に住んでいた人々は奈良・大阪から西に住んでいる人びととの出会い・交流の機会があったことは確かと思われる。
他方、内垣外(うちがいとう)遺跡(M10)は宮川中流域に位置し、出張(でばり)遺跡(M11)はその上流3㎞にある。この両遺跡では、数個のサヌカイトや頁岩製のものをのぞき、すべてチャート製であり、近くの川から採集されたと考えられる。
また伊勢市の万所(まんじょ)遺跡(M14)は宮川河口から9㎞上流の遺跡だが、やはり、チャート製石器と石核、剥片など合わせて20点近くが出土している。ほかには数点の砂岩、泥岩などの石器、2点のサヌカイトの剥片が出土している。
縁通庵(えんつうあん)遺跡とアカリ遺跡(M12)は櫛田川中流域の河岸段丘上にある。前者は石鏃17点のうち2点のみチャートで他はすべてサヌカイト。後者は石鏃16点のうち2点がチャート、1点が石英で、他はすべてサヌカイト、というふうに遠隔地産と思われるサヌカイトが多用されている。
以上は、私自身がWebで閲覧可能な発掘調査報告書(の一部)に当たって調べた、三重県の旧石器時代末から縄文時代にかけての遺跡における、石材使用のあり方及び黒曜石の有無に関する報告である。
三重県北部の一、二の遺跡では信州産の黒曜石が見つかっており、東の愛知・岐阜の人々とまた信州の人々との交流が想像された。サヌカイトも使用しており、関西との交流も推測される。
中南部の遺跡では宮川などで得られるチャートかまたは遠隔地の二上山のサヌカイトが使われていた。 西出遺跡では遺物の土器から、(二上山のサヌカイトを介して)大阪の人々との交流があったことがわかった。
他方、私がウェブサイトで発掘調査書に直接あたって調べた限りでは、三重県中南部の遺跡では黒曜石の出土は報告されていなかった。
しかし、愛知県の水汲み遺跡(A11)にふれたときに参照した長田、水汲み遺跡調査報告書の第Ⅶ章第3節「水汲み遺跡の位置付け」の「第24表 愛知・岐阜・三重における黒曜石分析一覧表」によれば
多気郡多気町の新徳寺遺跡、多気郡度会町の上ノ垣外(うえのがいと)遺跡、三重県志摩市の長尾遺跡 で黒曜石石鏃、剥片が合わせて38点出土しており、いずれも明治大学の杉原と金成により産地の分析が行われている。
それによれば15点は信州西霧ケ峰産、8点が神津島恩馳島産、3点が信州・星が塔産で、11点が判定不可だった、という。
この南伊勢おける黒曜石の出土に関連して、その搬入路の考察、および伊勢・志摩地方から熊野灘沿岸部への黒曜石分布の可能性について、節を改めて述べることにし、ここまでの岐阜県、愛知県、および北部三重県の遺跡における石材と黒曜石についてのサーヴェイのまとめを行っておきたい。
確かに、黒曜石は中部地方から岐阜、愛知、三重に広がってきており、一部は関西地方に数えられる滋賀県に分布していた。滋賀の真野遺跡では信州産の黒曜石が出土していた。
岐阜や、愛知の遺跡、そして三重北部の遺跡では、近くで安山岩やチャートなど石材が容易に手に入る場合にも、多くの遺跡で、近隣で採れる石材に満足することなく、サヌカイトや黒曜石など、遠隔地のものも含め、様々な石材を利用していた。
三重の遺跡では、北の愛知、岐阜に近い地域の遺跡(とすぐ後でふれる南の多気郡や志摩など一部の遺跡)で黒曜石が使われていたが、三重全体では、黒曜石はあまり使われていなかった。しかし、多くの遺跡で地元で採れるチャートに劣らずサヌカイトが使われており、奈良・大阪との交流が盛んにおこなわれていたことは確かだ。
黒曜石は、大部分、信州産のものであったが、そこには、しばしば、神津島産が混じっており、信州産黒曜石が東海三県にとどまらず、関西にも搬入されているとすれば、同じように神津島産の黒曜石がその中に交じって関西に分布している可能性がある。
以上が、岐阜、愛知、および北部三重の旧石器時代末から縄文時代早期にかけての遺跡から出土する黒曜石とそれ以外の石材の状況であり、またそこから言える関西への黒曜石の分布可能性である。
南伊勢における神津島産黒曜石の出土と紀伊半島南岸への黒曜石分布の可能性
しかし上で、愛知県の水汲み遺跡(A11)にふれたときに参照した、長田、水汲み遺跡の調査報告書の第Ⅶ章第3節「水汲み遺跡の位置付け」の「第24表 愛知・岐阜・三重における黒曜石分析一覧表」によれば、
多気郡多気町の新徳寺遺跡、多気郡度会町の上ノ垣外(うえのがいと)遺跡、三重県志摩市の長尾遺跡 で黒曜石石鏃、剥片が合わせて38点出土しており、明治大学の杉原と金成による分析で、15点は信州西霧ケ峰産、8点が神津島恩馳島産、3点が信州・星が塔産で、11点が判定不可だった、という。
縄文早期の北勢(北部伊勢)の遺跡では黒曜石が見つかっているが、亀山市(M4)、津市(M5)から南では見つかっていないか、「無いことはないが極めて珍しい」とされていた。
ところが、やや離れた、南勢の伊勢湾出口に近い志摩市や多気郡の遺跡で黒曜石が出土しているのだ。これらの黒曜石は、どうのような経路で搬入されたのだろうか。もし北部から陸路で搬入されたとすれば、途中の中部伊勢の他の遺跡からも黒曜石が出土しそうなものである。
水汲遺跡について長田は「豊川上流部での溶結凝灰岩や長野県産の黒曜石の利用」、「三河山間部との交流の深さ」、「長野県域との関係の深さ」について触れている。
もし、神津島産黒曜石を交えた信州産黒曜石の水汲み遺跡への搬入路の一部に豊川が使われていたとすれば、同じ舟で渥美湾から三河湾に出、渥美半島北岸を西に進み、伊勢湾出口を横断して伊勢市付近に舟を着け、荷の黒曜石を陸揚げしていたことも考えられる。
実際、長田友也は「東海地方における峰一合遺跡」(「下呂ふるさと歴史記念館開館 40 周年記念事業シンポジウム 縄文・峰一合遺跡の時代の再検討」2012)で、
縄文時代前期後半の住居跡と炉跡について、東日本地域に特有な諸磯式と西日本に特有の北白川下層式の区別を行ない、東海地方東部、岐阜県中津川市の遺跡などは諸磯式の影響が強いのに対して、西端の徳山ダム関連遺跡では北白川式の影響が強い。
だが「東海地方の南西部にあたる三重県南部ではやや異なった状況を示して」いる。松阪市山添遺跡では諸磯式住居形態を示しているとともに諸磯式の土器群が出土している。
また、装身具であるけつ状耳飾は岐阜県飛騨地方に集中しているのに対して、愛知・三重など東海地方南部では出土は低調である。愛知では三河山間部で出土し、三重では中南部の伊勢平野~志摩半島に集中している、という。
 (けつ状耳飾りはそれまで用途が不明であったが、藤井寺の国府遺跡から、人体骨とともに、頭部両側にこの飾りが一緒に出土したことによってはじめて耳に着ける飾りであることがわかったという。写真は前出<Web風土記藤井寺>「国府遺跡」)
(けつ状耳飾りはそれまで用途が不明であったが、藤井寺の国府遺跡から、人体骨とともに、頭部両側にこの飾りが一緒に出土したことによってはじめて耳に着ける飾りであることがわかったという。写真は前出<Web風土記藤井寺>「国府遺跡」)こうして長田は 岐阜・愛知の東部と三重南部との「海浜部を介した交流」「沿岸ルート」の存在を推定する。長田は具体的にその海浜部の名を挙げていないが、豊川河口付近から渥美湾に出て、伊勢湾口を横断する航路以外にないと思われる。
したがって、南伊勢における黒曜石の出土に関してもおなじように、渥美湾から沿岸ルートにより伊勢南部にもたらされた可能性がある。
さて、この黒曜石搬入路についての想定の当否はともかく、南勢に黒曜石が分布していたことが確かめられた。
すると、伊勢湾口を出て大王崎を回った熊野灘沿岸域にも、神津島産を含む黒曜石が伝わっている可能性がある、と思われる。
大王崎を回ってすぐのところに英虞湾があり、その最奥部の標高10mほどの丘陵上に「次郎六郎東遺跡」がある。三重県埋蔵文化財調査報告書145、1996。付近には旧石器時代から縄文時代にかけての遺跡が集中しており、海岸線には縄文時代の遺物散布地が点在している。
報告書著者は、付近の内陸にも遺跡が存在するが「海岸線に集中するのは、山と海の迫る志摩地域の海岸線地形が、食料の採取にとってより好都合であったためと考えられよう。このように、志摩地域、特に大王町域では、縄文時代以前にまで遡る人々の生活の痕跡を数多く見出すことができる」という。
ところで、海岸地帯に人々が居住し始めるのは旧石器時代末期以降のことである。それまでは山中で遊動しながら行う「狩猟採集生活」が主であった。
だが、縄文早期、およそ1万1千500年前から7千年前ごろにかけて、海面は50m以上上昇した。9千年前頃からでも20m以上、8千年前ごろからでも7千年前までに10m以上上昇し、もっとも上昇した時期には現在よりも5~6m高くなった。縄文海進である。左図参照。図はWikipedia「縄文海進」による。
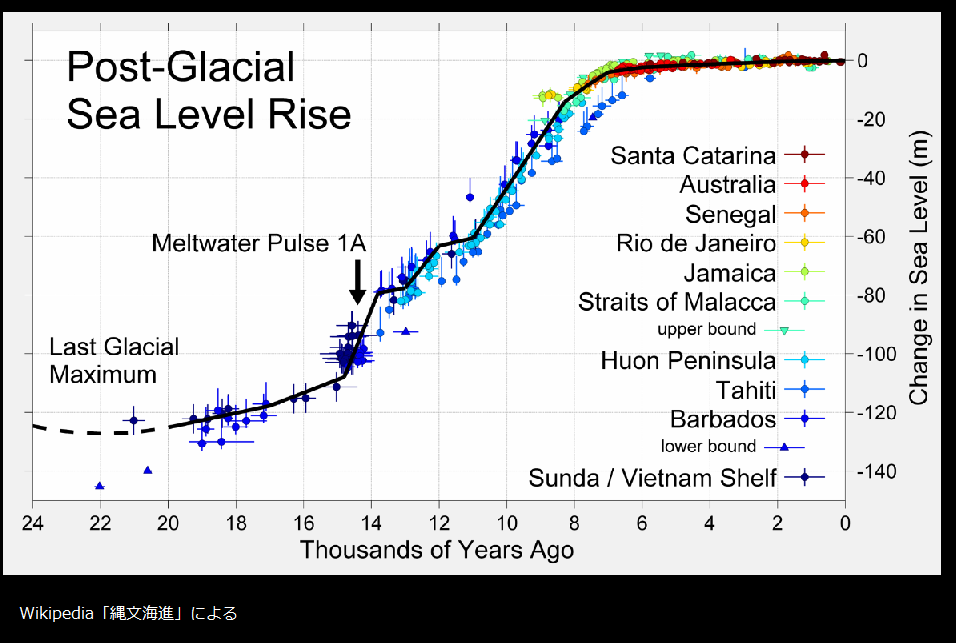 旧石器時代にも海辺に住み、漁撈で生活していた人々がいたことは確かで、縄文期にはそのような人々の数が増えた。
旧石器時代にも海辺に住み、漁撈で生活していた人々がいたことは確かで、縄文期にはそのような人々の数が増えた。縄文前期〔6千年前から5千年前、縄文早期の次の時期〕は気候が温暖化し海進がピークになる。
列島各地沿岸で漁場が形成され活発に漁撈が行われた。
前出、山添遺跡調査報告書(M7)では「縄文時代前期集落の傾向と特徴」という箇所で、安定した食料資源を背景に、前期以降に定住性の度合いが高くなる条件が整ったとし、三重県において確認された遺跡の数を時期ごとに分けて示している。
三重県では延べ、49遺跡が検出されており、草創期遺跡は1遺跡,2%、早期は7遺跡,14.3%、前期は3遺跡で6.1%、中期は17遺跡、34.7%、後期は16遺跡、32.7%、晩期5遺跡、10.2%である。
そして、三重県の近隣地域、近畿や東海地方においても同様の傾向であることがわかっている、という。
海岸に住んでいた人々はおそらく、たいてい標高3~4m程度のところで暮らしていただろうが、海進とともに海岸線は後退しただろう。
人々は海面が上昇するのにつれて次第により標高の高いところに住居を設けるようになっただろう。縄文早期末、約7,000年前に海岸にあった住居は、今は水深10mの海底に沈んでいるだろう。
英虞湾は、航空写真で見ると海底が見えるほど非常に浅い。次郎六郎遺跡付近の海岸線には多くの遺跡が存在するという。この英虞湾の中、そしてその少し沖の海底には縄文早期以前の遺跡が遠浅の海の中にたくさん沈んでいる可能性がある。
そして同じことが尾鷲付近のリアス式海岸地域に関して言えるし、また、紀伊半島南部、和歌山の新宮付近から田辺にかけては、湾の大小によらず、船をもやうことができ漁撈による生活が可能な湾・入江のある所では、同じように考えることができるはずである。
南伊勢への黒曜石搬入は(豊川を経て)渥美湾から船で行われた可能性がある。同じく海上ルートで、信州産黒曜石と神津島産黒曜石が南伊勢から紀伊半島南岸に分布した可能性があると私は思う。
ただし、Wikipedia「和歌山県」によると「縄文時代の遺跡が百数十カ所見つかっている。しかし、発掘調査はほとんど行われていない」という。
和歌山県南部に黒曜石が分布しているかどうかは当面は分からない。
後の第6節「湯浜人は黒潮に乗って西日本(東海地方以西)からやってきた」で、私は湯浜人は海岸地域に暮らしていた人々で、津波に襲われて沖に流されたか、居住場所を変えようと筏で移動中に誤って沖に流されたという考えを述べる。
ただし湯浜人は神津島産の黒曜石を持っていたという条件が付いている。これまで見てきたように愛知・岐阜・三重には神津島産黒曜石が分布していたことは確かめた。
したがってこの3県の海岸地域に住んでいた人々は湯浜人の候補である。また三重南部から熊野灘沿いの和歌山へも海上ルートでの黒曜石の分布が考えられるので、紀伊半島南部もまた、候補地である。
そして東の方では、渥美半島から御前崎付近までの海岸地区もその候補に入れられる。だが黒潮本流の流路から考えると、伊勢湾周辺と紀伊半島南岸の地域がはるかに有力な候補であると思われる。
そして、黒潮流路からすれば四国太平洋岸も、あるいは九州南東部も候補地に入れるべきだ。
四国高知・太平洋岸の遺跡における石材、そして黒曜石分布の可能性
関が原から西が関西圏とすれば、上では、滋賀県にまで、信州産の黒曜石が分布していること、つまり関西圏にも信州産黒曜石が分布していることを確かめた。そして岐阜や愛知などの遺跡で確かめたことだが、信州産黒曜石が出土しているところではまた少量ながら神津島産の黒曜石も出土しているということ、信州の黒曜石産地から伊豆・箱根方面及び南関東へと黒曜石が運ばれており、同じルートで逆に神津島産、伊豆箱根山の黒曜石が信州へと搬入されていて、信州から岐阜・愛知への黒曜石搬入には神津島産も含まれていることが多いことを確かめた。
また、旧石器時代の末期、類国府系集団が関東地方から瀬戸内地方へと回帰したこと、それに伴い関東地方の黒曜石が関西、瀬戸内海に搬入された可能性があることについて触れた。
そして、堤により矢出川集団の関西への広がりについて、また、稲田により湧別技法集団が日本海側から山陰を通って中国地方に「植民」した動きについて述べた。(滋賀の真野遺跡はその経路にあたっていた。)
では大阪平野や瀬戸内の低地からはどんな遊動・移動が見られるだろうか。
木 村 剛 朗「高知 県の縄文遺跡 とその文化」『第 四 紀 研 究 (The Quaternary Research) 31 (5)』1992、によれば、
高知 県における縄 文遺跡 は、 170ヵ 所が明 らかになっており、南西部に特に多い。 この地域は四万十川が内陸 山地 を貫流 し、 沿岸部 は リアス式海岸 を形成す るな ど、当時の人々にとって自然環境に優れていた。
四万十川流域 の河岸段丘上 や海岸 の海岸段 丘上 に見出されている遺跡からは、後期旧石器時代の石器、縄文時代草創期の土器、槍先型尖頭器、弓矢の鏃として使われたと考えられる小型有舌尖頭器が出土している。
 縄文早期にやや増加した遺跡からは、尖底土器や石鏃の他、多種の石器が出土しているが、石鏃には、チ ャー ト・サ ヌカイ ト・姫島産黒曜石が使われている。
縄文早期にやや増加した遺跡からは、尖底土器や石鏃の他、多種の石器が出土しているが、石鏃には、チ ャー ト・サ ヌカイ ト・姫島産黒曜石が使われている。姫島産黒曜石製石鏃の出土量 は南西部が圧倒的 に多 く、 足摺半島南端部に所在 する遺跡 は おび ただ しい出土量 を誇る。
この地域 が東九州地方や瀬戸 内地方 と盛 んに交流 を行 っていた ことが分かる、と木村はいう。
また、愛媛県愛南町の『愛南町史』(平成30年)によれば、愛媛県の南西端で高知県との県境に位置する愛南町では旧石器時代の6遺跡が確認されている。
僧都川下流に注ぐ和口川沿いの丘陵上にある和口西の駄馬遺跡には、瀬戸内技法による国府(コウ)型ナイフ型石器が多く出土していて、備讃瀬戸地域の人々の移住が推測されている。
和口西の駄馬遺跡の近くにはサヌカイトに似たホルンフェルス石材を産する。国府系集団が四国南西部に遊動した際に、近くの石材に注目し、ここに相当期間定着した、と考えられている。
すでに上でも述べたが、旧石器人あるいは早期縄文人の移動・遊動に際して、移動中の食料の獲得のために、あるいは行く先々で出会うそこに住む人々に通行料としてプレゼントするために、石器及び石材を携帯して移動したはずである。そして少量でも重宝される黒曜石はプレゼント用に好んで携帯されたと考えられる。途中で道具の作製にもプレゼントにも使わないまま残ることもあっただろう。
そして関東地方に遊動しそこの文化を取り入れて「類国府文化」を作ったのちに再び瀬戸内に回帰した人々があったこと、そしてその人々が関東から黒曜石を持ち帰った可能性があることにもふれた。
2.8万年前から1.6万年前には、石刃の様々な箇所に刃潰しを行なって調整したナイフ形石器が盛んに生産されたが、調整の仕方にバリエーションがあり、その一つに茂呂型のナイフ形石器がある、という。
竹岡俊樹『考古学基礎論』雄山閣、2019年によれば、茂呂型石器は、南関東では第Ⅸ層、第Ⅶ層、第Ⅳ~上層と、非常に長い期間に渡って、繰り返し出現が見られる、特殊な型をしたナイフ形石器である(p42)。
ところが第Ⅳ層(1.8~1.5万年前)の段階に、茂呂系ナイフに代わって切出し型石器を主体とする石器群が南関東に集中的にみられる。その理由は茂呂系文化に代わって国府型から変形した「疑似茂呂系ナイフ形石器」(=切出し型石器)を持つ文化が広く分布していたからだという(p68)。
当時、関東におけるナイフ形石器の素材には黒曜石が使われていた。→https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/18524/1/sundaikoukogaku_1_161.pdf.安蒜政雄「関東地方における切出し方石器を伴う石器文化の様相」『駿台考古学論集1』1975) 。
東進した国府系文化を持った人々は、サヌカイトを用いた瀬戸内技法を発揮できず、茂呂系ナイフ形石器を模倣して疑似茂呂系ナイフ形石器を作った。この疑似茂呂系ナイフ形石器が広く分布したのだという。
疑似茂呂系ナイフ形石器は、茂呂系石器に平面形は似ていても、機能的には後者よりも劣っていたという。
だが竹岡は模倣の理由はホモ・ハイデルベルゲンシス〔国府系の集団〕がホモ・サピエンスの持ち物には何らかの「呪術力」があると考えた結果ではないだろうか、という。p68
竹岡は同書のp134で、旧石器人にとって石器は単に物理的機能を持った道具であるにとどまらず、彼ら自身と一体化したものだったと言い、彼らは旧石器人に特徴的な環状ブロック群という遺跡を残しているが、そこに呪術的意味の込められた斧形石器を持ちこみ〔自分たち標識とし:須藤〕、このような環状ブロック群を自分たちが遊動した広い地域を囲むように、要所に残している。
彼らはこのブロック群で囲まれた広い領域を自分たちのものであると認識していた、斧型石器やその剥片には特別な意味があったのだ、という。
この箇所で言われている土地所有に関する呪術的観念については理解できる。しかし、茂呂系文化の模倣に関して、ホモ・サピエンスの道具をまねたのは呪術と関係があるという解釈は納得ができない。
国府系集団が、関東における素材の制限から茂呂型をまねることになった、という説明で充分理解できる。
しかし黒曜石の鋭い切れ味―これを彼らは利用できなかったようだが―は、その「黒い輝き」とともに、神秘的な魅力を感じさせたかもしれない。
http://www.hk-curators.jp/archives/2168、《集まれ!北海道の学芸員》松村愉文「黒曜石とトカチ石」【コラムリレー第43回】によると
黒曜石という語の登場は江戸時代の本草学者木内石亭が1801年に日本各地の奇岩をまとめた『雲根志』三編という書物にさかのぼる。「曜」は「耀」と書くこともあるが、ともに光り輝くという意味で、「黒曜石」には(黒く)光り輝く石という意味が込められていたと推定できるという。
また、黒曜石は北海道でアンチ(アイヌ語という)、トカチ石などと様々に呼ばれているが、黒水晶とも呼ばれていたという。
松浦武四郎は江戸末期から明治初期にかけ蝦夷地を探査し、北加伊道(のちに北海道)の名をつけたことで知られるが、『校訂 蝦夷日誌』二編には北海道内における様々な名をあげるとともに「石の裂目を見るに黒水晶の如し」と書いているという。
だが、すべての黒曜石が「黒く光り輝いている」のではなく、トカチ石は赤と黒のまだらである。(こちらの方が私には魅力的だと思われる。)
また薄墨色というか白みがかっているというか、漆黒ではないものも多くあるようだ。左の写真は、北海道の縄文前期の遺跡から出土したという長野県・霧ケ峰産黒曜石の鏃(左)と北海道産黒曜石の鏃である。どちらも「黒く輝いて」はいない。
 しかし、ある黒曜石製品販売店のHPのなかの「黒曜石の魅力に関する考察」というページに、「マニアの一人である私の私見」という文が載っていて、隠岐島の原石について「およそこのように美しく気高い石があるのかと、私はその原石に見入った。」と書いている。この人は「黒く輝く」黒曜石の強いマニアなのだろう。
しかし、ある黒曜石製品販売店のHPのなかの「黒曜石の魅力に関する考察」というページに、「マニアの一人である私の私見」という文が載っていて、隠岐島の原石について「およそこのように美しく気高い石があるのかと、私はその原石に見入った。」と書いている。この人は「黒く輝く」黒曜石の強いマニアなのだろう。そして私には1万数千年以上前の人々が黒曜石に呪術力を感じたということは大いにありそうだと思われる。
わたしは、瀬戸内に戻った類国府文化を持った集団は、普段は近くの金山などで得られるサヌカイトを使ったであろうし、時には隠岐産の黒曜石も用いたかもしれない。しかし恐らく、彼らが関東からもって帰った神津島産の黒曜石は使わずに「家宝」のように大切にとっておいたのではないかと思う。
そして、その子孫の中で四国へと移動・長距離遊動しようとするものがあらわれたときに、彼らの旅の成功を祈りつつ家宝の黒曜石の一部を持たせるということがあった、と想像する。
私の想像では愛南町和口西の駄馬遺跡は終着点ではなく、しばらくここに住んだが、その後さらに高知に向かって移動・遊動した。旧石器人はまだ定着することを好まずモバイルな暮らし方を好んだと思われるからである。
彼らは途中で他の在地の集団と仲良くなり、結婚も行い、縄文人の祖先となった可能性もある。その一部は四万十川の河口周辺で漁労を行なっていた。
黒曜石は「家宝」として礫のまま獣皮の袋に入れて柱にかけられていただろう。ところが、ある日大きな津波に襲われた。
かれらがいったんは津波に呑まれながら、どうやって死なずに筏に乗り、引き波によって沖合に流されたか、そして、黒潮によって八丈島に運ばれ、7,300年ほど前に初めて八丈島に上陸した「湯浜人」になったのか、については第6節で書く。
その前に、二番目に八丈島に上陸した人々、5000年前頃八丈島にやってきてほぼ200年間暮らしたことが確かな、倉輪人がどのようにして八丈島にやってきたのかについて書く。
第5節 倉輪人の三宅島から八丈島への航海はどのように行なわれたか
湯浜人を八丈島へと運んだ黒潮はどんな流れ方をしたかを示す前に、倉輪人たちの八丈島への渡島がどのように行なわれたのかを考察したい。彼らは本州から北部伊豆諸島を伝って南下し、三宅島からおよそ100㎞離れた八丈島に渡ったはずである。そして、彼らの航海は丸木舟で行われたことは間違いない。しかし丸木舟はどれくらいの速度で航走が可能だったのか。また海がどんな状態のときに丸木舟で100kmの航海が可能だったのか。海流の方向、また、波の状態、帆を使ったとも考えられるが、風の吹き方、など様々に、考えるべき要素がある。
丸木舟の構造については、遺跡から出土したものについての考古学者の研究があり、近代の丸木舟に関してもいくつか研究があって、大まかなことは分かる。
しかし丸木舟の操縦のしやすさ/むずかしさ、波を受けたときの安定性、速度などに関しては、沖縄など南西諸島で使われている小型船について書いたものは散見されるが、現存の5,6人乗りの大型の丸木舟について書かれたものは少なく、参考にすべきものが、見つからない。
以下では、主として、2019年7月に、国立科学博物館教授海部陽介を長とするプロジェクトチームによってなされた丸木舟の実験航海の報告を参考にする。この航海は「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」によって行なわれたもので、ほぼ100㎞の幅の黒潮を横断して、台湾から与那国島に渡った刳舟(丸木舟)による航海である。
海部チームの丸木舟・スギメの黒潮横断の実験航海
黒潮は、赤道の北側を西向きに流れる北赤道海流に起源を持ち、ルソン島にぶつかった北赤道海流が二つに分かれ、その一方が最速4kt(時速7㎞ほど)で北上するが、これが「黒潮」である。黒潮はルソン海峡Luzon Straitを越えたあと、台湾東岸に沿って流れ、 与那国島など日本の先島諸島とのあいだの100㎞ほどの幅の海峡を通って東シナ海へと流れ込み、東シナ海を北上してトカラ海峡から太平洋に入り、日本列島に沿って流れ、東北地方の三陸沖に及ぶ海流である。また、黒潮は日本の本州・東海地方の沖では主流が南北に500㎞近く変動するが、台湾付近と東シナ海では安定した流路をとっている。
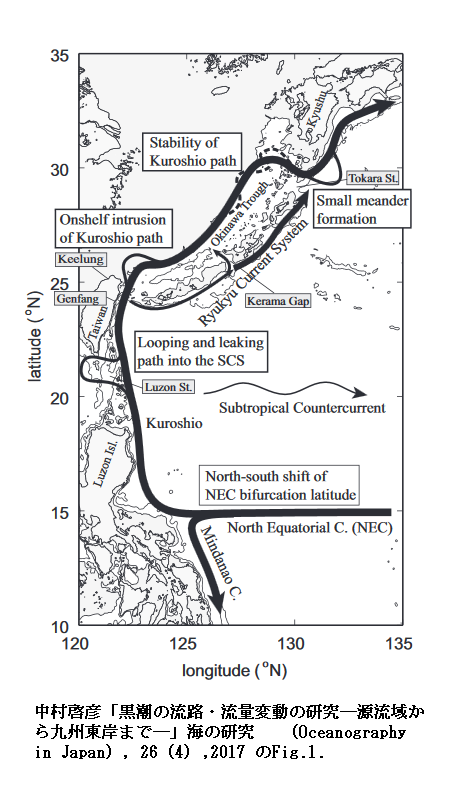 「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」では、杉の大木を刳り抜いて作った丸木舟・スギメによって、台湾から与那国島への、黒潮を横断する航海が行われた。
「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」では、杉の大木を刳り抜いて作った丸木舟・スギメによって、台湾から与那国島への、黒潮を横断する航海が行われた。当初は、ほぼ30時間ほどで与那国島に着くと見込まれていたが、実際には45時間かかった。
地図上の2点間を航行するときの舟の速度、おなじことだが、陸地に対する舟の速度を対地速度という。湖など静水における速度は対地速度と同じである。
他方、河川や潮流・海流のように、流れる水の上を走るときの水に対する速度を対水速度という。
対地速度=対水速度(ないし静水での速度) ± 川、海の水の流速 である。
台湾と与那国島の間の距離は約100㎞である。
スギメが、(対水速度で)平均時速3㎞~4㎞程度で走り続けることができれば、台湾東岸の最も近い場所から出航して、(海流が流れていなければ)25時間~33時間で与那国島に着くはずである。
実際には最高速度7.3㎞で黒潮が北に向かって流れている。
黒潮の速度が平均5㎞だとすれば、スギメは、25~33時間で100㎞東に漕ぎ進む間に125㎞~165㎞北に流される。
したがって、与那国島と同緯度にある与那国島から最も近い場所から出航するのでは、与那国島に到着することはできない。
こうしてスギメは、与那国島の真西から出航したのではなく、黒潮に流される分を見込んで、そこから170㎞ほど南のタイトン(台東)縣から出航したのである。航海時間が見込みより長くかかったのは、海がシケ気味で、スムーズに航行できなかったからではないか。
丸木舟で、三宅島から黒潮を横断して八丈島に渡る―計算
では三宅島―八丈島間の海を越えるためにはどのような航海が行なわれたであろうか。三宅島から八丈島に向かう時には、スギメの航海とは違い、黒潮に流される分を見込んで、その分、上流の場所から出航するということはできない。
黒潮の流れ方は非常に様々で、両島を包み込むように北から南に、あるいはその逆に流れることもあれば、両島の間を東西あるいはその逆方向に流れることもある。
だが、後で示すように、両島間を西から東に(あるいはもう少し正確に言うと南西から北東へと)流れることが多い。そしてこの流れ方の場合には、丸木舟を人力で漕ぐだけでは、横断はきわめて困難だと思われる。
これと比べれば、北から南に黒潮が流れている場合には、三宅島から八丈島に向かう航海は、かなり楽で、恐らく、倉輪人が最初に八丈島に渡った時には、この潮を待って渡航したと考えられる。
だが、丸木舟で伊豆諸島の北部の島々を飛び石伝いに南下しても、三宅島とその近くの御蔵島までは、比較的容易に行けるが、その100㎞先の八丈島に渡るのは、はるかに難しかったということを知るためにも、流れ方の頻度の高い、東西方向の流れの場合について、最初に考察してみる。
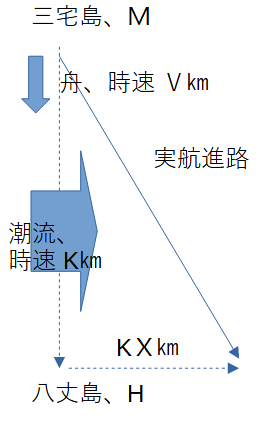
三宅島/御蔵島の南を黒潮が東に向かって流れていて、潮流の速度がK、舟の静水での速度(対水速度)をⅤとする。
八丈島までの航行時間をXとすると、X≒100÷Ⅴである。右図参照。
三宅島、Mから南にある八丈島、Hに渡ろうとしている。航行する時に、舳先を南に向かって走らせても、走行中に黒潮により流され、図のようにⅩ時間走った時点で、舟は島よりもKⅩ(㎞)だけ東の地点に行くことになり、島には到着できない。
スギメが、潮上にある場所(台東)から出航することができたのは台湾が大きな島だったからで、直径8㎞弱の三宅島ではおなじことはできない。出航地を選べないときにはどうするか。

流されるだろう距離だけあらかじめ潮上に向かい、それから舳先を南に向けて航行してもおなじことである。
台湾では出航地点をあらかじめ台東に決めていた。三宅島では、流されるだろう距離と同じだけ、西のPにまず走らせ、それから南に舳先を向けて、舟を走らせればよい。
MP=QH=KⅩだから、M→Pにかかる時間は KⅩ÷(Ⅴ-K)で、M→P→Qにかかる時間は、KⅩ/(Ⅴ-K)+Ⅹ=ⅩⅤ/Ⅴ-K である。
しかし、実際にこのように航海する人はいないだろう。MからまっすぐQに向かうだろう。MQとMHのなす角度をαとすると、
MからQの方向を目指して進み、MQ×cosα=MH、MH=ⅤⅩ、∴MQ=ⅤⅩ/cosα またMQ自乗=MH自乗+HQ自乗 MQ=√(MH自乗+HQ自乗)、あるいは、K/Ⅴ=tanα、などが成り立ち、
このMQを航走する時間YはMQ÷Ⅴ=ⅤⅩ/cosα÷Ⅴ=Ⅹ/cosα=√(Ⅹ自乗+K自乗)/Ⅴとなる。MHは「実航進路」であり、MH÷Y=実航速度という。
またこのように潮上に一定角度でむかって進むM→Qの進路により、Hに到達することが可能であるためには M→P→Qという進路も可能でなければならないが、それはV>Kを意味する。つまり、真横に流れる黒潮を横断することが可能であるためには、舟の速度は潮の流速より大きくなければならない、ということがわかる。
そこで、たとえば、Ⅴ=4㎞/hとし、K=2㎞/hだとすると、sinα=0.5,→αは30°、cosα=√3/2=0.866、実際に走る距離MQは MQ=MH÷cosα=MH×2/√3=100÷0.866 ≒115で、100㎞先の八丈島に向かう航海に実際に115㎞走らねばならない。
また八丈島までの航海時間は 100㎞÷4㎞/h=25時間ではなく、115÷4=28.8 つまり、およそ 29時間かかる。
しかし、速度4㎞/hで29時間もの間丸木舟を漕ぎつづけることは、非常にタフであり、また夜間も走行しなければならず、危険である。おそらく、倉輪人はこのような条件での航海は行わなかっただろう。
朝三宅島を出航して暗くなる前に八丈島に到着しようとすれば、航行時間は日の長い夏季においても15時間以下でなければならず、潮の流れの速度が加わった場合もしくは風を利用し帆走する場合の舟の対地速度が7㎞程度以上でなければならない。漕ぐだけでこの速度を得ることはたぶん不可能である。
北ないし北東からの風が吹き、帆を使うことができ、舟の速度として8㎞/hを見込めるならば、その場合には、K/Ⅴ=tanα=1/4=0.25→α≒14°、MQ=100÷cos14°=100÷0.97≒103、実航距離は3㎞ほどのびるだけで、航行時間は103÷8≒12.9(時間)となり、昼間だけの航海で八丈島に渡ることが可能となる。
倉輪人の航海について考察するに先立って、 「3万年前の航海徹底再現」プロジェクトで、台湾東岸から日本の先島諸島の与那国島まで漕ぎ渡った、丸木舟、スギメ(重量は350キロ)の航海実験を分析する。
スギメは、時速5㎞ほどの(対水)速度でほぼ16時間漕ぎ続けることで、黒潮の中心部を横断することができたようである。スギメの航海の報告を調べてみた。
スギメの航海の分析
『サピエンス日本上陸 3万年前の大航海』2020年3月、講談社; 『3万年前の航海の謎を解く』2019年11月、 徳間書店; 「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」報告会見 プロジェクト代表 海部陽介・国立科学博物館人類史研究グループ長 2019.7.18 などによると、スギメが台東県の烏石鼻(うしび)の浜を出航したのは2019年7月7日の14時40分ごろ。
出航後の30分間、15時10分までは、時速3.9㎞で漕いだ。
15時10分から16時までは、時速4.7㎞で漕ぎ、烏石鼻から6.1㎞地点に達した。ここまでは黒潮の影響はなく、速度は「対水速度」である。
16時からの10分間に、スギメの(対地)速度は時速4.7kmから6.6kmと4割増しになっていた。「黒潮に入ったのだ」。
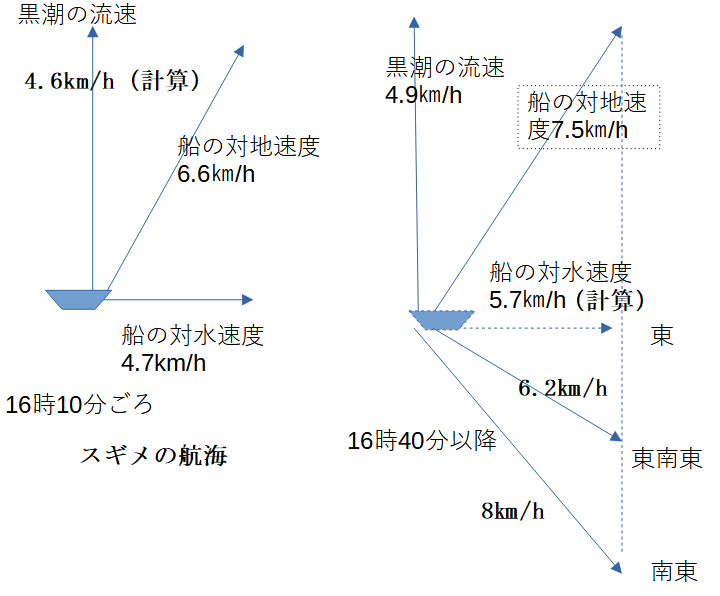 →舟の対水速度は変わっていないとする、この時の潮の速度は √(6.6の自乗-4.7の自乗)=√21.3=4.6㎞/h だった。
→舟の対水速度は変わっていないとする、この時の潮の速度は √(6.6の自乗-4.7の自乗)=√21.3=4.6㎞/h だった。 16時40分以降は対地速度は時速7.5km前後になった。この時点で「黒潮本流に入ったのだ」。潮の流れは時速4.9kmだった。
→「南東もしくは東南東に向かって漕いだ」という。真東に向かって漕いだとすれば、スギメの対水速度は√(7.5の自乗ー4.9の自乗)=√32.2≒5.7、で、スギメの対水速度は5.7㎞/hだったことになり、
南東に向かってこいだとすると5.7×√2≒8㎞/h、
東南東に向かって漕いだとすると、5.7÷cos22.5°≒6.2㎞/hだったことになる。
シケに対処しながらこいでおり、おそらくスギメの進路は南東ではなく東南東で、速度は最高で6.2㎞/h程度だったのではないか。
実験航海中の黒潮の最大速度は1.5m/s(時速5.4㎞)だった、という。
夕方から北風が吹き始め海は次第にシケてきた。風速は5mを越えた。潮流の方向と風が逆の時には波が立ちやすい。
北からくる波に舳先を向けて波を交わし、また向きを変えて東に進む。これを繰り返す。(舟が波の来る方向にたいして横向きになると、波にたたかれ転覆する。)また、たえず船内に入り込む海水をくみ出す作業を起こなわなければならず、すこしも休むことのできない航行がつづいた。
10時半ごろ、転覆の心配は薄らぎ、漕ぎ手は時々休憩を入れることができるようになった。出航から8時間、しけ始めてから6時間後だった。
図は記者会見で映された航海時のビデオ画像である。航跡のうち赤のところが昼間、水色のところが夜である。書き込みは須藤。

7月8日
仮眠をとっていたキャプテンの原が4時過ぎに目を覚ました時、舟が北向きになっていて、30分間誤って流されたと判断。東に向け漕ぐ。舟が北に流されたときには曲線が北に傾いている。
「6時半 時速8.2キロメートルという本航海での最高速度を記録したあと、30分後の午前7時には5.5キロメートル、そして8時以降は平均5.0キロメートル前後と、4割ほど落ちた。この時点で黒潮の中心部分を越えた」という。
黒潮の最高速度は時速5.4km程度だった。したがって、舟の対水速度は √(8.2の自乗―5.4の自乗)=√38.08=6.2㎞で、 6時半ごろから、短時間ながら、時速6.2㎞のハイペースで漕いだようだ。
海部は「スギメは、ついに黒潮本流の強力な流れを越えたのだ!ただ丸木舟の漕ぎ手たちにはこのことはわかっていない。この日も(交代で休みを取りつつ)漕ぎ続けた」と書いていて、図の軌跡の曲線が東に向かって傾いているのは、潮の速度ががくんと落ちたせいだろう。
その後軌跡の曲線の傾きが元に戻るのは、熱さのせいもあり、クルーに疲れが出て、午後14時ごろには漕ぐのを止め、海に入って体を冷やすなどしたためである。
その後夜に入るとウォッチ以外全員が眠った。そして運よく潮は与那国島に向かって流れてくれた、という。
日が落ちてから6時間ほどはかなりのしけと戦わねばならなかったが、それでも、速度を落とさず、漕いでいることは、ビデオ画像上の曲線の傾きがほぼ一定していることからわかる。
また夜が明けてまもなく本流を越え、潮の速度が落ちたにもかかわらず、しばらく時速5.7㎞以上の速度で東に漕いだようだ。この時は曲線がはっきり東に傾いている。
また、出航後20時間以上たった8日の昼前くらいには疲れが出て休みを取ったといっており、この時に航跡の傾きが縦になっており東向きの速度が落ちているのがわかる。
スギメは同じ速度でほぼ20時間漕ぎ続けることで、黒潮の本流を横断することができた。
結論: スギメは、30分ほどの助走ないしはウォーミングアップは時速3.9㎞だったが、その後の30分間に速度を4.7㎞に上げ、さらに16時40分以降はほぼ夜通し、およそ時速5.7kmから6.2㎞で漕いでいる。
翌朝も、本流を越えたことを知らないまま、日が高く上り暑さにやられてペースを落とす昼頃まで、交代で休憩を取りながら、同じように漕ぎ続けている。
これらのことはビデオ画像上の曲線の傾きの変化に現れている。
こうしてスギメのクルーは、20時間近くも時速5.7㎞以上で漕いだのだ。
このスギメのクルーは、カヤックで日本を一周したり、国際レースですぐれた成績を上げたり、あるいはアマゾンやアラスカの大河数千㎞を漕ぎ下ったり、という超一流の漕ぎ手である。他の例を調べてみよう。
小学校教師らの手作りの丸木舟・からむしⅡ世号の航行速度
隠岐諸島には黒曜石の産地があり、旧石器時代から縄文時代にかけて、中国地方や大阪付近に住んだ人々に利用されていた。 西川 吉光 「海民の日本史1」《国際地域学研究 19号 》 2016-03 URL http://id.nii.ac.jp/1060/00008257/ の(注9)に「1982 年に松江市内の小学校教師等が手作りの丸木舟「からむしⅡ 世号」(長さ 8.2 メートル、幅 64 センチ、重さ1トンの5人乗り)を用いた実験では、隠岐の知夫里島郡(こおり)港 から松江市美保関町の七類(しちるい)港まで 15㎏の黒曜石を1日で運搬することに成功した。郡港と七類 港の間は、直線距離で約 50 キロメートル。雨のち曇りで白波が立つ天候であったが、13 人のメンバーが交 代で漕いで、12 時間 43 分で七類港に到着している。」とある。
これによると、 からむしⅡ世号の「対地速度」は、50㎞÷12時間43分で、時速3.9㎞である。静水での速度(対水速度)はどれくらいだったのだろうか。計算して確かめ、スギメと比べてみよう。
 隠岐と対岸の松江との間には対馬海流から分岐した海流が西から東へと流れている。
隠岐と対岸の松江との間には対馬海流から分岐した海流が西から東へと流れている。右の画像は京都府農林水産技術センター海洋センターのHP>海況予測、「DREAMSコマンダー」による。九州大学応用力学研究所のサイトとのリンクによるものとされている。ただし2019年5月25日以降に限られている。
2019年と2020年の5月、8月、10月から無作為で6日選んで、海面下1mの流速を調べてみた。(閲覧とコピーは2020年秋に行なったが、2021年3月現在では見ることのできるマップは「若狭湾版」だけで「隠岐地方版」はないようだ。)
隠岐の北側の日本海の海流(対馬海流)は流れ方が様々に違っている。ところが隠岐諸島のうち一番南の知夫里島と対岸の松江市との間の潮は(冬を除き)ほぼ同じような流れ方をしていた。
右の、速度を色分けした帯の黄色とオレンジ色の中間くらい0.35m/s(時速1.26㎞)程度の潮が、知夫里付近から南東に向かい松江にぶつかるように流れているか、または、知夫里からの南東向きの潮は海峡の北半分だけで、海峡の南半分は東向きの潮になっているか、のどちらかだった。
前者の場合は全航路追い潮で、潮の速度は、ほぼ時速1.26㎞くらいだとして、知夫里島郡港から松江の七類港まで約50㎞を航行しておよそ12時間半だったとすれば、カラムシの(静水での)速度Vは
50÷(Ⅴ+1.26)=12.5 →Ⅴ=50÷12.5-1.26≒2.7 すなわち時速2.7㎞だったということになる。 後者の場合には、後半は西から東に流れる潮を斜めに横断する横断するように漕ぐ必要があり、前半での航行に比べ、時間がかかる。合計時間がどうなるかを念のために計算してみた。
 右図を参照してもらいたい。
右図を参照してもらいたい。△ABCは直角二等辺三角形、AC=CB=25㎞、CE=EB=DE=25÷√2=17.7㎞ とする。
カラムシはDまでは北西からの時速1.26㎞の追い潮で走り、Dからはほぼオレンジ色で秒速0.4m=時速1.4㎞で東に流れている海流を斜めに横断する。 海流を横断しつつ、実際にBに着くようなコースDBを走るためには、Bよりも潮上のQを目指す必要がある。
DQは、目指す方向が真南より角度αだけ東向き、という一種の仮想の航路。この方向を目指して走ると西からの潮の流れで(Qという単に想定された地点に着くまでの時間と同じ時間)横に流されて、実際にはBに到着する、と考える。
まず,Qの位置あるいはαを求める。ただしα<45°
EQ=DE×tanα 、DQ=DE÷cosα 、D→Qにかかる時間は、DQ÷Ⅴ=(DE÷cosα)÷Ⅴ、 この時間、潮流1.4㎞/hで東に流される。
→ 流される距離=QBは 1.4㎞/h×(D→Qにかる時間)=1.4×(DE÷cosα÷Ⅴ)
ところで EQ+QB=EB 、EB=DEだから DE×tanα+1.4×DE÷cosα÷Ⅴ=DE → tanα+1.4÷cosα÷Ⅴ=1
→ cosα+1.4÷Ⅴ= sinα → cosα- sinα= 1.4÷Ⅴ
そこで、 V=2の近くでたしかめると、
Ⅴ=3なら cosα-sinα=0.46666 →α≒25°、 cosα=0.906、 →DQ=DE÷cosα=17.7÷0.906≒19.5
Ⅴ=2.5なら cosα-sinα=0.56 → α≒21.5°、cosα=0.93 、 →DQ=17.7÷0.93≒19.0
Ⅴ=2なら cosα-sinα=0.7 → α=15°、 cosα=0.97 、 →DQ=17.7÷0.97≒18.2
などの値が得られる。
合計時間=ADにかかる時間+DQにかかる時間で、
V=3 ならば、25÷(3+1.26)+19.5÷3 ≒ 5.8+6.5 ≒ 12.3 、およそ12時間20分 、
V=2.5ならば、25÷(2.5+1.26)+19.0÷2.5 ≒ 6.0+7.6≒13.6 、およそ13時間40分 、
となる。
カラムシ2世の実際の航海は12時間43分だったから、前半は追いで後半は斜めに潮を横断する航路の場合の静水での速度は、時速 3㎞より少し遅い程度だったと考えられる。
カラムシ二世号の行程は50㎞、しかも13人が交代して漕いだ。ほぼ5人ずつの3交代で4時間ずつ漕いだ計算になる。他方、スギメは交代なしで、前半の20時間近くを時速5.7㎞で漕いだ。カラムシ二世号の2倍の速度である。
しかし、舟の重量が全く違うことを考慮すると、この差は縮まる。スギメの重量は350㎏、それに対してカラムシ二世号の重量は1トンある。
この重量差がどの程度人力だけで漕ぐ場合の速度にきいてくるかは分からないが、これを考慮せずに、学校の先生の即席チームとプロとも言うべき漕ぎ手から編成されたチームの差だと片づけることはできないだろう。
<中間地点の判断―山立て>
計算では、ABの中間点Dで仮想の針路DQを目指したが、クルーはD点にきたことをどうやって知るか。あるいは、どうやってQの方向に舳先を向けるか。GPSはもたず、また伴走船からの教示はないとする。
山立てで行なうことが可能である。ただし、既知の2点を見通す2本の線の交点として、自船の位置を決める通常の山立てはしなくてよい。知夫里港から出たら、松江まで見通す直線から外れないように、走り続ければいいのだ。
山立てしやすいのは目標物が10㎞程度までではないかと思うが、中間のD点からは知夫里島も松江も30㎞ほどとやや遠い。しかし知夫里島後方の西ノ島町には400mを越える山があり、松江の後方にも500mほどの山がある。(その東には標高が1729mの大山がある。)山立てには困らなかったのではないか。
AからDまでの間も、実際には、前方と後方の陸上の目標物を絶えず目視して、直線ABに沿って走る必要がある。
Dにきて、船が右(西)からの潮の中に入っても、横に押されてることは分からない。山立てをして初めて逸れていることが分かる。逸れていることがわかったら少し右に進路をとるようにする。細かく山立てを行ってその都度進路を微調整して進めばよい。
南洋諸島のアウトリガー付きのカヌー
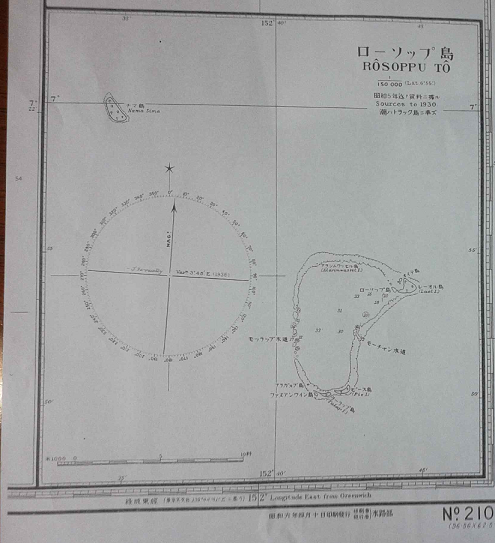 もう一つ参考事例を挙げる。2020年の秋から朝日新聞で連載されている池澤夏樹の小説「また会う日まで」の第225回に登場する、1934年、南太平洋のローソップ島で行なうことになった皆既日食観測隊の一員、地磁気の担当者、水路部の東中秀雄の話。
もう一つ参考事例を挙げる。2020年の秋から朝日新聞で連載されている池澤夏樹の小説「また会う日まで」の第225回に登場する、1934年、南太平洋のローソップ島で行なうことになった皆既日食観測隊の一員、地磁気の担当者、水路部の東中秀雄の話。ローソップ島は第一次大戦後、日本の信託統治領となっていた南洋諸島の一つで、トラック諸島(現在はチューク諸島Chuuk Lagoon(Wikipedia))の中心部から南東100㎞ほどのところにある。グーグルアースでは、地図にある緯度、経度に合わせて拡大しないと見えない。地図は国会図書館にコピーを依頼する。
東中はローソップ島から4海里ほど南にあるピース島へ行った。競走用という大型カヌーで、漕ぎ手の島民4人と観測関係者3人の計7人が乗った。 舷は低く海面すれすれ。逆三角形の断面の舳先はよく波を切って進んだ。
しかし、沖に出ると礁湖の中とは言え波は荒くなり、水が入ってくる。必死でくみ出すがずっと足が水に浸かっていた。スコールがあり、全身ずぶぬれになったが、出発から1時間ほどでピース島に到着した。
このカヌーは挿絵にあったように、おそらくアウトリガーがついていただろう。アウトリガーがついていれば安定性がよく転覆の心配は少ない。しかも外海ではなく礁湖の中の航行だった。
漕ぎ手は漕ぐことに集中できただろう。人を3人乗せていて、その分は速度は落ちたかもしれない。また舟自体は競走用だったとしても、競争におけるように全力で漕いだとは思われない。
しかし、この船は4海里の距離を1時間で航行した。舟の速度は1.85㎞×4=7.4㎞、つまり時速7.4㎞だった。
これは、スギメに比べるとずいぶん早い。競走用だというから、船体はスピードが出やすいものだったろうし、しかもたった1時間の航海でしかなかったことも関係しているだろう。
選りすぐりのカヤッカーからなるクルーが漕ぐスギメの、ほぼ20時間近く、かなりのシケの中を走って、時速5.7㎞というのは、恐らくどこの丸木舟にも負けない記録なのではなかろうか。
旧石器人のカヤックは時速5㎞で航行できた?
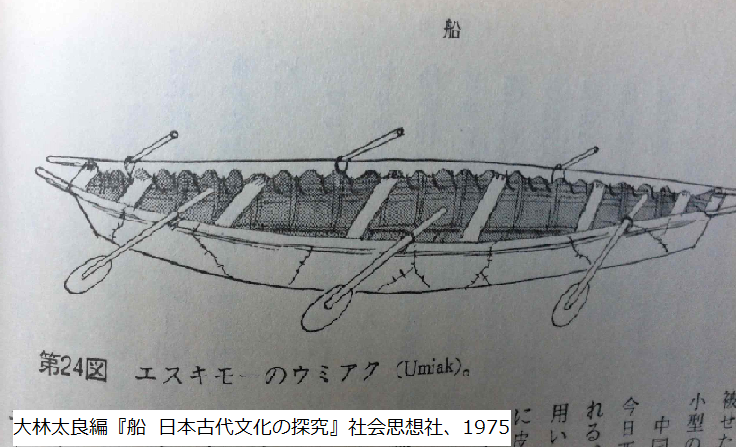 『黒潮を渡った黒曜石・見高段間遺跡』(新泉社)などの著書がある考古学者の池谷信之は、「世界最古の往復航海一後期旧石器時代初期に太平洋を越えて運ばれた神津島産黒曜石」『科学』No.9,vol.87 2017、岩波書店のなかで、
『黒潮を渡った黒曜石・見高段間遺跡』(新泉社)などの著書がある考古学者の池谷信之は、「世界最古の往復航海一後期旧石器時代初期に太平洋を越えて運ばれた神津島産黒曜石」『科学』No.9,vol.87 2017、岩波書店のなかで、海獣の革を使った極北地方のウミアック(大型のカヤック)が「軽量で速く,船底のフレームがキールの役割を果たすため,直進性にも優れている」という特徴にふれながら、
伊豆半島から神津島に渡った3万8千年前の旧石器人の乗った「船の巡航速度を」「仮に」「時速5㎞と速めに想定しても片道8時間を要する長時間航海になる」と書いている。
池谷は「旧石器時代の神津島産黒曜石と現生人類の海上渡航」安斎正人編『理論考古学の実践 Ⅱ実践編 』同成社,2017 では、スキン・カヤックの想定では、細石器によるフレーム構成のための木材の削り出し、縫製のための針や皮なめしの技術の存在を考慮した。しかし針の存在がそのまま漏水しない縫製技術の存在を意味しないこと、皮革の素材に何を想定するかといった点に課題も残している、と言っている。
古代人が神津島に渡ったのは夏季に限定されていたようであり、夏は多少足元が濡れることは問題ではなかったはずだ。しかし水がたまればくみ出す必要がある。
南方ではヤシの殻が、垢汲みとして使えただろう。日本ではどうだったか。ひょうたんを切れば味噌汁の椀と同じくらいのものが作れる。また直径が10センチ以上ある太い真竹の筒を2本並べて縛れば、同様に、垢汲みに使えたのではないか。
また皮革の素材については、恩馳島や式根島を繁殖地としていたニホンアシカの皮を使ったのではないかと思う。
私は、http://mishimasatoyama.web.fc2.com/page074.html 「三島里山倶楽部」HP>「神津島と海の道」で 恩馳島と式根島は、過去、ニホンアシカの繁殖地だったことを知った。
昭和初期までアシカ猟が行われていたが、今では見られないという。(Wikipediaによれば、アシカ島ないしアシカ岩という名の岩礁が太平洋沿岸にはたくさんあるが、ニホンアシカは近代になるまでは日本近海に多数生息していた。だが、日本海の竹島で1975年に数頭見られたのが最後で、その後は確かな目撃情報はなく、絶滅したと考えられている。)
このHPの編集長の長谷川は、神津島への渡航について、アシカの皮を使った浮袋をつけた木の筏を渡航具と考えているが、氷期の海退時にも、筏で伊豆半島から神津島に渡るのはむずかしかったのではないだろうか。
筏は何人かで漕いで動かせる。しかし、スピードは出ず、潮の流れのない湾内の短い距離の移動用には使えるが、目的地の定まった航海には向かない。筏は基本的に海上での作業、つまり漁撈のための道具である。
他方、クマなどの皮では無理でもアシカの皮を使ってカヤックを作ることはできただろうと思われる。
ちなみに池谷の趣味はカヤックであるといい、彼は海部の「3万年前の航海徹底再現プロジェクト」にも加わった。
倉輪人が八丈島に渡った丸木舟はどれだけの速度で走れただろうか。
「海民」であった倉輪人
倉輪人は、八丈島に渡っただけでなく、本州との間を何度も往復航海したことが分かっている。湯浜と倉輪の遺跡の調査を行ない、「八丈島の先史文化」を書いた考古学者の小田静夫は、古代に黒潮を横断して八丈島に渡るには高度な航海術を有してなければならなかったことを強調し、彼らを「海民」、「海の縄文人」と呼んでいる。
ところで、藤田富士夫『古代の日本海文化』(中公新書、1990)に、倉輪人に関する興味深い記述がある。
八丈島の倉輪遺跡から多くの装飾品が出土しているが、この中に含まれる「の」の字形をした垂飾品は、昭和30年代に富山県立山町の天林北(テンバヤシキタ)遺跡で、採集されたものと、大きさが少し違うだけで、どちらも蛇紋岩製で、形がよく似ているという。写真をみると確かに形がそっくりである。
 なお、第2節のなかで掲げた、小田による<八丈島の遺物の写真>も見ていただきたい。その「第二期(5000年前」とされる遺物のうちの18番がここに掲げている写真の右と同じものである。
なお、第2節のなかで掲げた、小田による<八丈島の遺物の写真>も見ていただきたい。その「第二期(5000年前」とされる遺物のうちの18番がここに掲げている写真の右と同じものである。藤田によると、倉輪遺跡出土品は幅6.07センチ、高さ4.87センチ、天林北遺跡出土品は幅約2センチ、高さ、1.85センチで、大きさは異なっている。しかし形はそっくりである。
「このような特殊な形態をした垂飾品が遠隔地にあって、無関係に生じたとは考え難い」と藤田は言う。(私ならこの二つの装飾品は同じ人の手になるものではないかといいたい。)
富山湾をめぐる地域には、耳飾りなどの装飾品の製作遺跡が集中的に発見されており、富山湾に拠点を置き、漁撈を行うとともに湾外に舟を繰り出して、 玉製品や海産物などの特産品を主とした広範な交易活動を行っていた海人集団がいた。
また、神津島産の黒曜石が出土した、石川県富来町のムカイヘラソ遺跡は「海民との深い関係が推測できる遺跡である 」ともいう。
そして藤田は「倉輪遺跡での北陸系の土器の出土や北陸と関係の深い垂飾品の検出は、北陸縄文人の黒曜石原石を求める行動の一端と解釈できるだろう。」と言う。
小田も倉輪遺跡の出土品には関東・中部地方、近畿・東海地方の土器が含まれていると述べており(「黒潮圏の先史文化」)倉輪人が本州各地で交易をおこなっていたことが知られる。小田によれば倉輪人は「海の縄文人」であった。
倉輪人の出身地が北陸地方だったと断定することはできないかもしれないが、かれらが北陸地方と縁が深く、日本海と東海地方および伊豆諸島を往来して交易を行なった「海民/海人集団」だったことは間違いないだろう。
かれらは日本海から瀬戸内海、そして関東地方を舟で回り、各地の沿岸住人と交易を行なうことを生業にしていたと思われる。
丸木舟に積める荷物の量は限られていたにせよ、土器や石器を陸路、歩荷で運ぶよりは、丸木舟を使って海路を利用して行った交易ははるかに有利だっただろう。
だが、かれらは、もしかしたら、交易を目的として本州各地を回っていたというよりは、舟によって本州沿岸の各地を訪れること、あるいは、新たな訪問地をめざして航海をすること自体を好んだ集団だったのではないだろうか。
竹岡俊樹『旧石器時代人の歴史』(講談社、2011年)は、これまでの通説を否定し、「生態系の変化に応じてヒトビトが道具を改良しながら文化が進化・発展していくという考え方は、私たち現代人のもつ発展史観を投影したものだ」という。
彼らは幼児のような精神構造を持った「ヒトビト」で現代の人間と違っている。「彼らの石器は機能性や合理性という概念とは無縁である」。石器製作の技法は異なる集団間で模倣されたが、それにより進化したわけではない。
彼らは日常的には広大な領域を回遊し、また時として日本列島を縦断するような移動を行っていた。前期旧石器時代にさかのぼる国府(コウ)系文化をもつヒトビトは、瀬戸内技法という世界的にも特殊な方法で石器を製作した集団である。
かれらは居住地の「瀬戸内地方から何度も遠い東日本地方にまで帰らぬ旅に出て行った」が、われわれ現代人が思いつくような、はっきりした目的があったとは限らない、という。
倉輪人が八丈島に渡ったのは後期旧石器時代の末期からでも1万5千年から2万年以上後のことである。しかし、彼らが旧石器時代のヒトビトのように幼児的な心性をもっていた可能性もある。彼らは航海が楽しかった、海が好きだったから航海をした。八丈島に渡ろうと考えたのも、そのためだったかもしれない。
本土から三宅島、御蔵島まで南下してくる以前に、その両島よりもはるか南に島があるということは聞き知っていて、そこへ渡ろうと考えながら三宅島にやってきたのかもしれない。
しかし、八丈島の存在は知らずに、伊豆諸島を南下し三宅島まで行ってみると更にその先に島があることを知って、そこへも渡ろうとしたのかもしれない。
いずれにしても、現代人なら、それを冒険とか探検と呼ぶかもしれないが、現代人が考える冒険や探検は「成果」を抜きにはあり得ない。しかし、倉輪人の場合には、無名の低山でも、山があれば登ってみるように、海があって島が見えれば航海して渡ってみようとしただけだったかもしれない。
人が住んでいるかどうかさえわからない遠くの島に、交易などの実益を目的に危険を冒したとは思えないからである。
彼らが八丈島にとにかく200年間ほど住み、暮らしたことは確かなのだから、かれらは数隻の丸木舟を所有し、家族を乗せた船団を組んで、航海をしただろう。本土では家族ぐるみで船上生活を行なっていた可能性がある。
近代の家船とは違い、安定性のよくない丸木舟では寝泊まりして暮らすのは無理のように思われるかもしれない。
しかし、湾の奥の波の立たない停泊地では、舟を2艘、3艘並べて、竹竿などを渡し、キヅタなどのロープ(あるいは動物の皮を石器で細長く切って作った皮紐、動物の腱を乾燥させて作った紐---小野昭『ネアンデルタール人、奇跡の再発見』朝日新聞出版、2012*)で縛って、安定性を持たせれば、その中で寝泊まりは可能だっただろう。
(*)この本は考古学初心者の私でも読みやすく、しかも胸が熱くなる素晴らしい本だ。
子供たちは生まれてから死ぬまで、ほとんど舟で暮らしたのかもしれない。
そして、かれらは三宅島までやってきて、八丈島を遠望し、とにかくそこに渡り、しばらく暮らしてみようと、航海の計画を立てたのだ。海の怖さは十分知っていたはずだから、航海計画は慎重にたてられただろう。
三宅島の南西側からは八丈島はよく見える。(南東側からは御蔵島の陰になって見えないところもある。)島に上がらなくても、海上の小舟からでも八丈島は見える。
三宅島から八丈島に渡る。事前の準備
八丈島は三宅島の南南東110㎞に位置し、同方向三宅島から約20㎞のところには御蔵島がある。
海上の船から、遠方にあるもの(船、灯台、島など)が見える距離には限界があるが、その距離を「海上視認距離」という。
その理論的な公式は 2.08×(√h+√H)マイル で表される。h 及び H は メートル。
http://arumukos.la.coocan.jp 「ちゅーやんのページ Chuyan's Page」>「生きていくのには不必要な知識」>「海上視認距離」による。このサイトはトランスパシフィック・ヨット・レースに参加した人が書いている。 丸木舟で座ったままだとすればh=50センチほど、Hに八丈富士の標高854mを入れて計算すると、視認距離は62マイル=114㎞なので、天気の良い日には、丸木舟に座ったままで八丈島は見える。
彼らはおそらく、三宅島か、御蔵島のどちらかの島に、少なくとも1,2年は住み、その近くで漁をして生活しつつ、それ以前の本州沿岸での航海では知りえなかったはずの、南部伊豆諸島を流れる海流や天候について調べただろう。
先住者から教えてもらうとともに、三宅島の周囲の海で舟を走らせ、また御蔵島との間を往復することで、潮の向き、流れの強さ、そして季節風の傾向を把握しただろう。
三宅島には縄文時代早期から人々が暮らしていた。また御蔵島にも、ゾウ遺跡という、縄文時代早期~中期にかけての遺跡がある。石鏃、土錘が出ているから狩猟、漁撈による生活がなされていたことが分かる。
本州からやってきた「海人」たちは三宅島にきて、黒潮がの流れ方を調べた、また風の向き、風の強さをしらべただろう。
八丈島まで丸木舟でどのくらいの時間がかかるかを調べてみよう。
海部プロジェクトでは、あらかじめ、大まかな潮の流速、与那国島の位置などがクルーの頭の中に入っていたにせよ、スギメは与那国島が全く見えないところから出航して、2昼夜に渡って航行した。半径50㎞ほどの島の可視圏に入らないまま通り過ぎ、東シナ海に流されてしまう恐れも十分にあった。
実際には、島の可視圏に入ることができ、島に到着することができたが、それにはつきもあったことを、海部もクルーも認めている。いざとなった場合に救助してもらえる伴走船なしではとてもできない冒険だった。
倉輪人は「海人」であったがやみくもな冒険は好まなかっただろうし、とくに八丈島への最初の航海では慎重を期しただろう。
ここにくる以前の本州沿岸の航海では、月明かりを頼りに、あるいは星の位置を見て、夜間航海をすることもあったかもしれない。その場合、予定した目的地に到着できなかったり、通り過ぎたりしても、どこかでいったん停泊し、翌朝を待って、航海することができただろう。
だが、八丈島に向かう場合には途中で夜になっても、停泊は不可能である。そして、暗い中で漕ぎ続け、島のそばを通過し、追い潮のため戻ることができずに太平洋の中へ遠くまで運ばれてしまう可能性がある。
こうした危険を避けるため、八丈島への航海は昼に行なうことにしたはずだ。
彼らは数字は使わなかっただろうが、私は数字を使い、中学生程度の数学を使って、考えてみた。
三宅島→八丈島、計算
さて三宅島から八丈島に向かった倉輪人の場合であるが、彼らは、島で暮らそうとしており、よい凪の日を狙い、3隻程度の船団で、子供も含め15人程度で八丈島に渡ったと仮定する。たくましい漕ぎ手だけの航海ではなく、また生活用具をある程度積んでいたと考えられるので、速度はスギメよりはだいぶ遅く、時速は4㎞程度としておく。
恐らく、海人たちは、八丈島への渡島に先立つ準備期間中に、生活のための漁を行って、三宅島と御蔵島の周辺の海を走り回ることにより、潮が、北からあるいはその逆に南から、あるいは東からまたその逆に西から、どれくらいの頻度で流れるか、一つの型の潮は流れははじめたらたらどれくらい続くか ある型の潮から別の型の潮へと変化するときの日数はどれくらいか、潮の速さが、多くの場合どれくらいであるのか、また最も早い場合にはどれくらいになるのか、等々のことを頭に入れただろう。また、1年を通しての風の強さや風向などについても体得しただろう。
彼らは少なくとも、最初の渡島時には夜間航行は避け、明るいうちに八丈島につけるような航海を行なおうと考えただろう。
かれらの舟の速度と望見する八丈島までの距離の見当から、追い風か追い潮でなければ、早朝に出港しても日が暮れるまでに八丈島に着くことはむりだと判断しただろう。
黒潮が北から流れている追い潮のときには、半日で八丈島に行くことはできるが、北からの潮がないときや、横に流れる潮、南からの向かい潮の時には潮がよほど緩くなければ、漕ぐだけでは渡航は困難だと考えただろう。そのような場合には、帆を使わねばならないと考えただろう。
数字を使って簡単な計算をしてみる。半日の、つまり、早朝から夕方までの航海で八丈島に着くためには、舟は時速8㎞以上の速度で航走する必要がある。100㎞÷8㎞/h≒13時間
この速度は、舟の(静水での)速度が4㎞/hとして、平均4㎞/h以上の速さの追い潮があれば可能となる。これくらいの速さの潮は時々流れただろう。
海洋産業開発機構JAMSTECのスパコンJcope2のデータ(後述)によれば、黒潮の中心部はほとんどの場合1.5m/s=5.4㎞/h程度で流れているからである。
黒潮の流路と強さは変わるが、突然一挙に変わるのではなく、本流(中心部)の流路が少しづつ変化するのにつれて、数日かけて徐々に変わる。そして、数日間程度は、同じような潮が流れることもある。後にこうした潮の変化も確かめる。
だが、必ずしも追い潮の速度が十分でないとき、あるいは潮が止まっているときに、帆を使って航海した可能性がある。
縄文の海人たちが実際に帆を使っていたかどうか、また帆を使ってどれくらいの速さで走れたのかを次に検討する。
ヨットと丸木舟
現代のヨットも帆を使って走る。ヨットはどれくらいの速さで走れるのだろうか。
船体を水に浮かべた時の水面ぎわの線を「喫水線または水線(water line)」という。船の積載状態や海洋の状況により喫水線の位置は変化する。 「国土用語の基礎知識 海事編」 www.wdic.org /dic/GEO/EMMARIN、による。
また、「MALU SAILING」 というページ(https://malu-sailing.com/archives/6271)によると、 ヨットは、「水線長」つまり水線の長さが長ければ長いほど速く走ることができ、 ヨットの巡航速度は「水線長(フィート)の平方根」にほぼ等しいと言う。
そして、23フィート(約7メートル)≒ 4.7ノット (時速8.7㎞)、26フィート(約8メートル)≒ 5.0ノット 、30フィート(約9メートル)≒ 5.4ノット ---40フィート(約12メートル)≒ 6.3ノット という数字が掲げられている。水線長はほぼヨットの「全長」とみなせるだろう。
「第86回ウォーターフロント研究サロン1.ヨットの魅力と楽しみ方」というページ(https://www.waterfront.or.jp/data_files/view/31/mode:inline)では、
ヨットで三浦半島から屋久島まで往復航海したベテランのヨッターの話 (講演記録)として
「この船は25フィート、7.7メートルと小さく、どんなにスピードが出ても5~6ノットぐらい、自転車程度です」と書かれてている。5~6ktは時速で10㎞から11㎞である。
こうして、ヨットの速度は時速9~11㎞程度と考えられる。山勘だが、丸木舟も帆走によってこの半分くらい、つまり時速4~5㎞程度の速力アップを図れたと考えられないだろうか。
古代に帆は存在したか
帆の起源ははっきりしていないが、古代エジプト時代の墳墓から出土した花瓶(紀元前4000年頃、つまり現在より約6000年前のものと推定されている)の絵柄に帆をもつ船が描かれていた。初期は、追い風の時のみに使用する補助的な動力源であったが、その後の改良により帆のみで航行可能な帆船があらわれた。(Wikipedia「帆船」による)
これまで日本で発見された最古の舟は市川市雷下遺跡で発見された7500年前の丸木舟であるが、これを含め「これまで発見された縄文時代の丸木舟は波よけ用に舷側を補強した跡や、推進力強化のために帆を使った形跡はない」という。日経新聞2015/2/23 <歴史博士>「歴史新発見 千葉県市川市の雷下遺跡」による。
また、これまでに出土した事例に見る限り、縄文人が航海に用いたのは一本の丸太を刳り抜いた丸木舟であったと考えられている。帆柱の跡やオール受けの跡は検出されていないため、(カイトセイリングのように帆柱を用いない形式での帆走を行った可能性は否定出来ないまでも)基本的には、櫂で漕ぐ、パドリングによる推進であった可能性が高い、という。 Wikipedia 「縄文人」>「縄文人の用いた舟艇」
6世紀の珍敷塚(めずらしづか)古墳(福岡県吉井町)の壁に描かれた船では、両舷に棒が立てられ、その間に帆が張られているという。帆に使用されたのは江戸時代までは基本的に筵(ムシロ)であった。江戸時代に帆布が開発され、全国に普及した。 Wikipedia「和船」による。
これらを見る限り、日本で出土している縄文時代の丸木舟で、帆柱に掛ける帆を使った形跡はない ようだ。
ムシロや帆布の代わりをするものはさまざまにあった
だが、すこし強い風が吹けば体が押されることは子供でも分かるし、川や海辺で漁撈を行っていた人々は、物や人を上に乗せた筏や小舟が風下に流されることは経験しただろう。したがって、乗り物の推進力として風を利用することは早い時期に思いつかれたはずである。
ツボや古墳の壁に描かれるようになったのは、大型の舟に筵ムシロなどの帆が広範に使われるようになってからのことで、それ以前にも小型の舟や丸木舟では、帆の役目を果たすものを用いて、風の推進力を利用したことがあったと考えられる。
湿地に生えるイネ科多年草・真菰マコモを編んで作るコモやイネ/稲藁を編んで作るムシロ以外にも風を受け止めることのできるものはいろいろある。

獣皮を第一にその候補としてあげることができるだろう。
左はWebのオークションに出品されていたヒグマの敷物である。この4本の足に紐をつけて手でつかめば、凧あげのタコのように風を受けることができる。
ブライアン・レイヴァリ著、増田義郎/武井摩利訳『舟の歴史文化図鑑―船と航海の歴史―』( 悠書館、2007)によると、ポリネシアで、アウトリガーカヌーにつけて1960年代まで使われていた「カニの爪」と呼ばれる帆があったといい、左の図を載せている。
 三角形をした蓆のようなものの頂点をカヌーの舳先に結び付け、残りの二つの隅に付けたひもを後方の船べりに結ぶかあるいは手で持つようにしている。
三角形をした蓆のようなものの頂点をカヌーの舳先に結び付け、残りの二つの隅に付けたひもを後方の船べりに結ぶかあるいは手で持つようにしている。図の中の説明を見ると、帆の裏側に「帆を支える円材」を当てて帆のふくらみを保つようにしているのが分かる。
だがこれほど、本格的でなく、紐の両端を舟縁に結ぶか手で持つかするだけでも十分な効果が得られただろうと思われる。
竹を編んで作るザルはムシロやコモを作るよりずっと簡単に作れ、ムシロやコモに比べ目が粗いようだが、風に対する抵抗は十分にある。
福井県の鳥浜貝塚は縄文時代草創期から前期にかけての貝塚で様々な種類の多くの遺物が出土しており、「縄文のタイムカプセル」と呼ばれることもあるという。
ここからは、漁網に用いられる縄文草創期の打欠石錘が出土しており(2002年時点で国内最古の出土事例とされている)、漁網がすでに存在したことが確かである。 Wikipedia「鳥浜貝塚」。
また、松永 篤知 「東アジア先史時代の編物に関する雑考―もじり編みと多経多緯式―」金沢大学考古学紀要 37 2015, 1-12 (https://core.ac.uk/download/pdf/196705123.pdf)によると、
もじり編みとは、「一方の条材に別の条材を絡め編んだもの」のことであるとされるが、からめる条材の本数や絡め方によって、何種類にも分類されるようである。
松永によると、鹿児島県三角山I遺跡で、土器の底部に絡め編み圧痕が残されている。この資料は縄文草創期のもので東アジア最古という。
また縄文時代早期の佐賀県東名遺跡 からは、もじり編みの実物、つまりもじり編みで編まれたかご類が出土している。さらに縄文時代前期に入ると、日本列島でも(もじり編みの布である)編布が確認できるようになる。こちらは実物資料・圧痕資料ともに認められる、という。
渡辺誠(『縄文時代の漁業』雄山閣、1973)によると、
竹や樹皮その他で製作したかご類は、その実物がすでに(縄文時代前期の)福井県鳥浜遺跡で発見されており、ムシロ、スノコ,編布などについても、熊本県宇土市の轟貝塚など、縄文時代前期にはすでにその圧痕があり、それらの存在は確か、としている。
日本最古の丸木舟が出土した、7500年前の市川市雷下遺跡の報告 <文化財センター速報>平成26年5月5月「市川市雷下かみなりした遺跡 」によると、同遺跡からは編み組製品も出土している、という。下は編み組のカゴの写真である。
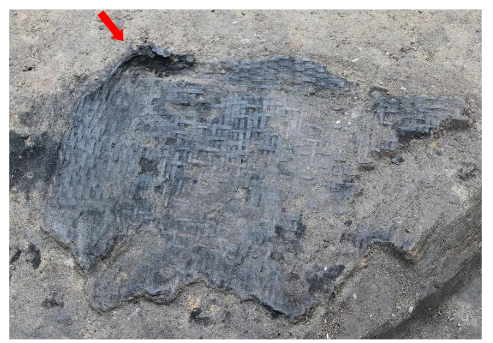
こうして、縄文時代早期(1万年前から6千年前)には帆として使うことのできるカゴや布が作られていた。
また漁網を袋にして、ソテツ、棕櫚の葉、(南方では)バナナの葉などを入れれば立派に帆の役目を果たしたであろう。
柳田国男「海南小記」には、14世紀ごろのことらしいが、琉球の舟が「蒲葵ビロウの帆をかけて支那の役人を驚かせた」という文がある。「柳田国男全集3」,p278。
蒲葵の葉を、おそらく網状のものの中に入れて使ったか、あるいは編んだものだったのではないか。 「蒲葵は沖縄ではクバといい、葉は扇や笠に利用し 乾燥させたビロウの葉で編んだクバ笠は、風通しが良いうえに撥水性があり、漁師や畑仕事をする人に重宝された」という。Wikipedia「ビロウ」。
また、出口晶子『丸木舟』<ものと人間の文化史>98(法政大学出版局、2001)は、17世紀、「日本人漂流民が乗せてもらった唐舟は、帆は竹で編んだかごの中に竹の葉を入れたものだった」と書いている。
目の詰まったカゴならそのまま風を受けられるはずだから、目の粗いかごに「竹の葉」(もしくは葉の着いた枝)を詰めたのだろう。
小型船では布であれ、獣皮であれ、帆柱を使わず、三角または四角の帆の三隅あるいは四隅に付けたひもを、手でつかんだり、船べりに引っ掛けるなどして、「タコ揚げ」のようなスタイルで風を受け、帆走することができる。これも、容易に思いつくことである。
関野吉晴 がグレートジャーニーの出発地にした南米最南端のナバリーノ島のカルデロンという老姉妹は、似たようなやり方で布を広げ両端のひもを手でもって帆走していた。関野は風の利用は誰でも考えるし、また簡単に風を受ける仕組みを思いつくこともできる、と言っている。

 写真右は普通のザル、左は箕(み)といい、穀物の選別、収穫物の運搬などに使用する一種のザルである。
ざるなら船の舳先の内側に立てて、四隅にひもをつけて、手で持てば、十分に帆の役目を果たすはずだ。
写真右は普通のザル、左は箕(み)といい、穀物の選別、収穫物の運搬などに使用する一種のザルである。
ざるなら船の舳先の内側に立てて、四隅にひもをつけて、手で持てば、十分に帆の役目を果たすはずだ。こうして、帆柱を備えた本格的な帆走は行われなかったにしても、獣皮、ザルや草の葉を入れた網袋やかごなどで風を受け、丸木舟の推進力を強化することができたはずである。
帆走丸木舟による航海、南西諸島のサバニ
<丸木舟で、三宅島から黒潮を横断して八丈島に渡る―計算>でおこなった計算では、東西に流れる黒潮の流速が時速2㎞、舟の速度が時速4㎞と仮定して、三宅島から八丈島までの航海には29時間かかった。これでは夜間の航行が必要になるので、倉輪人は、横に流れる潮の時にも航海したとすれば、補助的推進力を得るために帆を使ったであろう。
そして、帆走で舟の速度が時速8㎞であれば、13時間で航海可能だということ、つまり、三宅島を朝出発すれば暗くならないうちに八丈島に到着することが可能だということがわかった。ただし、これは風と海の状況が適当だった場合である。時速2㎞の潮流の速度は黒潮としてはかなり緩い方である。
橋口尚武、井口直司「伊豆諸島の生活技術」『黒潮の道』<海と列島文化7巻>で、橋口は
八丈島、三宅島間では---一年に二度ほど、安全に航海できる見通しの良い凪の機会に恵まれることもある。5月と10月の「ひよどり凪」のときである。
三宅島に住み着いた糸満出身の漁師が、大正13年、帆をつけたサバニを操って早朝に三宅島を出発し、午後の早い時期に、90㎞離れた伊豆の下田に入港したことがある、と書いている。


サバニは小(サ)舟(ブニ)の転用で、沖縄など南西諸島の、小型の丸木舟のことである。下野敏見「南西諸島の海人」『山民と海人』<日本民俗大系5.>
この糸満の漁師の帆をつけたサバニは、たとえば「早朝」4時に出て「午後の早い時期」1時に着いたとすると、9時間で90㎞走ったことになるから、(対地速度は)時速10㎞だったことになる。風はおそらく南風だっただろうが、潮はどんな潮の時だったのだろうか。
2017.1.15の潮流は、1m/s以上の速さで三宅島付近の西側を北もしくは北西へと流れている。
糸満の漁師がこれと同じような潮に乗って下田までいったとすれば、追い潮分の速度1m/s=時速3.6㎞を差し引いて、帆走時の速度は時速6.4㎞だったということになるだろう。後で示すが、南からの潮が流れることはかなり多くある。
だが、もしこの漁師が下田に行った日は、1.27のような潮況で、潮がごく緩いかほとんど動いていなかったとすれば、このサバニの速度は時速10㎞で、現代のヨットとほぼ同じくらいの速さだった、ことになる。
野口武徳「沖縄の伝統的舟について」大林太良編『船』<日本古代文化の探求>(社会思想社、昭和50年)には次のように書かれている。
「サバニは安定をとることが難しい。現在〔の舟〕より、さらに昔〔の舟〕はむずかしく、人が乗って重心をうまくとらなければ、帆柱を立てただけでも転覆したという。それだけ、バランスをうまくとる技術が乗り手に要求されるわけであるが、とくに注意しなければならないのは追い風が強いときで、ちょっとした油断でたちまちバランスを失うのであった。
上手な乗り手は手縄をやったりとったりして〔帆についている数本の横桟の一方の側についている縄を片手で持ち〕風の強弱に帆の向きを合わせる。〔また、他方の手で舵となる櫂を握る。〕〔帆柱は固定されておらず〕風が強い場合は帆柱を後傾させ---風の当たる面積を小さくして操縦する。順風に乗れば機械船にも負けないくらいのスピードが、平均して6~8ノットぐらい出る、と書いている。時速11.1~14.8㎞である。」
現在ではサバニの多くは板を張り合わせて作られる。そして重いエンジンを積むために胴が膨らみ船尾も大きくなっているが、昔は刳舟で、ずっとほっそりしたⅤ字型だったというから、安定性はよくなかったが、舳先は尖っていてスピードも出やすかったのだろう。そしてなによりも上記糸満の漁師は操船の技術に熟練していたに違いない。
丸木舟による三宅島―八丈島間の航海、具体的考察
しかし、縄文時代早期の刳舟は、帆を使ったとしても、その役割は補助的で、帆だけで走った場合には、現代の小型ヨットの4.7ノット(時速8.7㎞)と比べて、ずっと船足は遅かっただろうと思われる。上では、現代のヨットの半分くらいの速度を出せたのではないか、と書いた。倉輪人の乗った丸木舟はスギメと同じ5人乗りだったと仮定し、漕ぐだけで走る速度は時速4㎞だったと仮定する。
帆走する場合には、1人がかじ取りを行ない、3人が漕ぎ、そしてスギメと違い、1人が笊あるいは獣皮の帆につけた綱をもってコントロールしたと考えてみる。
この場合、帆で時速4㎞程度の速力アップができたと仮定する。それくらいの速力アップがなされたら、漕ぎ手が一人減って、漕ぐことによる速力は時速1㎞低下し、時速3㎞になるが、帆で速力アップしたことによって、合計時速7㎞で走ることができたことになる。そしてこの速度が可能だったなら、潮が止まっている状態で、北からの追い風のある時には、100÷7≒14.3(時間)で、三宅島から八丈島に行くことができたことになる。
だが、スギメ・クルーのキャプテンの原も言っていたように、丸木舟は不安定で、波があると、転覆しやすい。帆を使えばなおさらその危険は増すだろう。そして倉輪人の八丈島に向かう航海は、伴走船がついていて、いざというときには救助してもらえる「航海実験」ではなく、いわば真剣勝負だった。
彼らが、実際に帆走も行なったとすれば、三宅島に滞在した準備段階で、潮だけでなく、風についても、注意深く観察したことだろう。
風速に関して、19世紀イギリス海軍が定め(1964年には世界気象機関に採用され)たビューフォート風力階級表というものがあり、それによると、階級3の軟風Gentle breeze(3.4~5.4m/s)で、海上では「波頭が砕ける。白波が現れ始める」、階級4の和風Moderate breeze(5.5~7.9m/s)で「小さな波が立つ。白波が増える」、階級5の疾風 Fresh breeze (8.0~10.7m/s )で水面に波頭が立つ、とされている。
そして、この上の階級6では陸上で「木の大枝が揺れ、傘がさしにくくなる。電線が唸る」、海上では「白く泡立った波頭が広がる」とされる。
「FISHING JAPAN」https://fishingjapan.jp/fishing/4026によると釣り船に関して国が定めている出船中止基準があり、波高、視界の条件と並び、出航地の風速が10m/s以上になったら、中止という条件がある、という。現代の釣り船は大型で、相当なシケでも出船できる。しかし10mの風では出船しない。
一方、丸木舟は、舷側が低く、海面と船べりの差は30㎝くらいしかないので、波に弱い。スギメの航海中のビデオをみると、写真のような海況で、恐らく風速は4~5m程度だと思われる。小型のプレジャーボートでも、(宇和海で)これくらいの波であれば十分に釣りはできる。
だが、 海部は「16時ごろになるとそれまで微風だった北東の風が勢いを増し、風速5m以上で吹きつけるようになった。 そこここで白波が立ち始めた。北からうねりがはいってくるようになった。」と書いている。
キャプテンの原は「波がじゃぶじゃぶはいってきて、これはまずいなと思っていた。それまでの練習では、このような状況になれば、練習は中止していた」と言っている。
ちなみに、波の打ち込みを伏せぐために、舟の前後になめし皮と蒲葵の葉で、3か所に「ショウガ科のゲットウ」の葉で覆いをほどこしてあった、という。ゲットウについてはAlpinia uraiensisとAlpinia zerumbet のどちらだったかと聞きたくなる。( ´艸`)
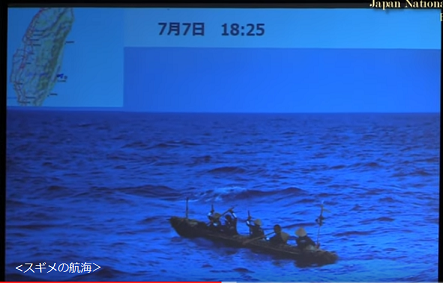
この日は、スギメは東に向かっており、潮は南から北に向かって流れていたが、風は北の風で風波が立ちやすかった。そして舟は北から大きめの波が来るたびに舳先を北に向け変え、波を横から受けないように操船する必要があった。向きを変えるのが遅れれば波が打ち込んできただろう。
潮が舟の進行方向と同じ追い潮で、風も同じく後ろからならば、操船は楽で、漕ぐことに集中できる。凧あげ式の帆の扱いもさほどむずかしくなかったかもしれない。
乗員の技術にかかることだが、操船不能になったり転覆したりする危険がない限り、風ははやいほど、帆走に有利であろう。
八丈島方向に向かう潮でなく、向かい潮であっても弱ければ、あるいは潮が止まっていても、北からの風が吹けば帆走することにより、短時間にあるいは楽に、八丈島に行くことができる。倉輪人も適当な風を待って出航することを考えただろう。
そこで、そこでまず、三宅島の風向・風速を気象庁のデータで調べてみた。風を知ることは2つの意味で必要だ。風が強く海がシケては、まず、航海が不可能である。強風でなくシケではないときに、帆走に適した風向と風速の日がどれくらいあるか。
三宅島で吹く風
三宅島で吹く風の様子を気象庁の統計資料で調べると、風速10m/s以上の風が吹く日数は、2019年~2020年2年間で347日ある。ほぼ1日おきに10m/s以上の強風が吹く。そして、2015年から2020年までの6年間の平均風速は5.1~5.7m/s だった。(ちなみに、西の宇和海に面した愛媛県宇和島では、同じ2年間で、10m以上の風が吹いたのは100日で、また同じ6年間の平均風速は2.6~2.8m/sである。三宅島では強風の日が断然多く、平均風速も断然強いことが分かる。)
丸木舟の出航に差し支えないと思われる一日の最大風速が5m/s以下で、追い風となる北北西から北北東までの間の風向の日がどれくらいあるか、2019年から2020年について調べてみた。
すると風向によらず最大風速が5m/s以下という日は2年間合わせて3日しかない。すこし判断基準を緩めて6m/s以下としてみると、2年間で合計57日である。しかし、そのうちで、順風の北北西から北北東の間の風の日は合わせて16日しかない。
海流は、多少は風向・風速の影響を受けるが、後でふれるように風による表面流の流速は風速の2~4%なので、丸木舟の航行にとっては無視できる。
したがって風が追い風であっても、向かい潮で時速が3㎞程度なら、舟の帆走の速度が時速8㎞とすると、八丈島に着くには20時間かかってしまう計算になり、航海は無理である。そして後で示すが、黒潮が三宅島から八丈島に向かって流れることは決して多くない。
とすれば、2年間に16日の順風のチャンスを待っているだけでは、渡航できない可能性が高いのである。
したがって、順風の日を待つのでなく、航海が危険でない限り、逆風であっても、潮が八丈島に向かって流れているときには、航路の全体を漕ぐつもりで出航した方がよいと考えられる。
もちろん、北からの順風が吹き、かつ潮が北からの潮であれば、倉輪人たちは出航しただろう。しかし、風向にかかわらず、凪なら、つまり最大風速が5m/s以下なら、追い潮で出航する方が渡島の可能性が高まる。
そこで、次に黒潮の流路を調べ、三宅島から八丈島方向に流れる頻度がどれくらいあるかを見よう。
黒潮は、その本流(中心部分)が三宅島とその南南東20㎞にある御蔵島周辺を、流れることが多い。
だが流路は変動し、流路の真ん中では潮は早く、流路の端では遅い。同じ場所で潮の速さは変化する。流路から離れたところでは潮は動かないこともある。分流が流れていて、本流とは反対方向に流れることもある。複雑な流れが見られる。
黒潮の流路の変動を調べてみる
黒潮は台湾東岸を北上したのち、東シナ海を通って、九州南部、トカラ列島で向きを変えた後、四国沖から本州の南を流れて房総半島の沖に至る。下は気象庁による黒潮の流路

黒潮の流路は、東シナ海では安定しているが、四国沖から房総半島沖までの流路は大きく変化する。
本州の南を流れるときの、黒潮の、比較的安定した流路が図の1,2,3で、
1と2は紀伊半島近くまではほぼまっすぐに流れる「非大蛇行」流路をとるが、その後、1は伊豆諸島の北部を通る「接岸」流路をとり、2は、紀伊半島潮岬付近から南下し、八丈島の周辺を流れる「離岸」流路をとる。
1は非大蛇行接岸流路、2は非大蛇行離岸流路と呼ばれる。
3は四国沖から南下し東海沖で北緯30度くらい(鳥島と同緯度付近)まで南下する「大蛇行」流路を取るが、その後、八丈島の西側を北上して、1とほぼ同様の接岸流路を取る、という。
図は、気象庁https://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/data/db/kaikyo/knowledge/kuroshio.html に島名を書き加えた。
他方、海洋研究開発機構・JAMSTECの美山は「典型的大蛇行」流路の他に「非典型的大蛇行」流路があるという。 (http://www.jamstec.go.jp/aplinfo/kowatch/?p=3007、黒潮ウォッチ2016-7-19)
 美山は、上の気象庁の図の1~3に加えて、
美山は、上の気象庁の図の1~3に加えて、非大蛇行離岸流路(2)の離岸が大きく発達した場合、非典型的大蛇行流路と呼ぶとしている。
離岸の大きさは黒潮が北緯32度線の南を通ることが基準になる。
非典型というのは、典型的な大蛇行は八丈島の北を通過するという特徴があり、それ以外は非典型的ということだ、としている。
気象庁によれば、黒潮大蛇行を判定する基準として、以下の2つの条件を設定している。
(1)潮岬で黒潮が離岸している。
(2)東海沖(東経136~140度)での黒潮流路の最南下点が北緯32度より安定して南に位置している 。
〔八丈島の南約65㎞にある青ヶ島の緯度は北緯およそ32.5度である。1975年から80年にかけての大蛇行時と2018年に始まった今回の大蛇行では最南下点が北緯30度である。鳥島の位置は北緯およそ30.5度である。〕
黒潮大蛇行は1965年以降5回発生している。そのメカニズムは分かっておらず、過去の大蛇行発生時の観測データはあっても、今後、発生する時期、継続期間、「最南下緯度」の予測はされていない。
2017年8月には、12年ぶりに黒潮大蛇行が発生し、2020年も大蛇行の状態が継続した。2020年12月には継続期間が3年5か月となり、1965年以降では2番目に長い期間の大蛇行となった。
次の図は気象庁>各種データ・資料>「黒潮までの距離」の図である。(島名など少し書き加えた。)

青の太い線は、1985年から2007年までの平均的な黒潮流軸(黒潮の中心部、ただし水深50m)の位置、破線は同じ期間の黒潮流軸の変動幅(流軸距離の標準偏差を平均値からのずれで表したもの)を示している。
この図によれば、2本の破線の間隔が大きいところでは黒潮流軸の変動幅が大きく、破線の間隔が小さいところでは変動幅が小さい。
したがってトカラ海峡以南では黒潮はほとんど同じところを通っているが、トカラ海峡を通過後、次第に南北に振れ、石廊崎沖、あるいは伊豆諸島付近では流路が大きく変わることを示している。この図では、八丈島は東経140度の線の近くで流軸の少し下に描かれている。
それでも、「標準偏差」の意味から、流路のおよそ、7割はこの破線の間にあることがわかる。
また、「平均」の意味からすれば、八丈島付近を流れる黒潮の頻度がもっとも高いとは言えない。(たとえば、仮に、ある期間、黒潮が、青い線(あるいは八丈島)の200㎞北側を、200日流れ続け、またその後200㎞南側を同じ日数流れ続け、八丈島付近には全く流れないというようなことが起こったとしても、結果は同じになる。2本の破線の間の幅は変わるだろうが。)
そこで、黒潮が日々、どのように流れているかを知る必要がある。
気象庁のホームページでは、上の図の「石廊崎」をクリックすると、最近5年分の石廊崎から黒潮までの距離の推移 を示す折れ線グラフ「石廊崎から黒潮までの距離」と、石廊崎からの距離を示す青丸の着いた直線の図(下)が表示される。
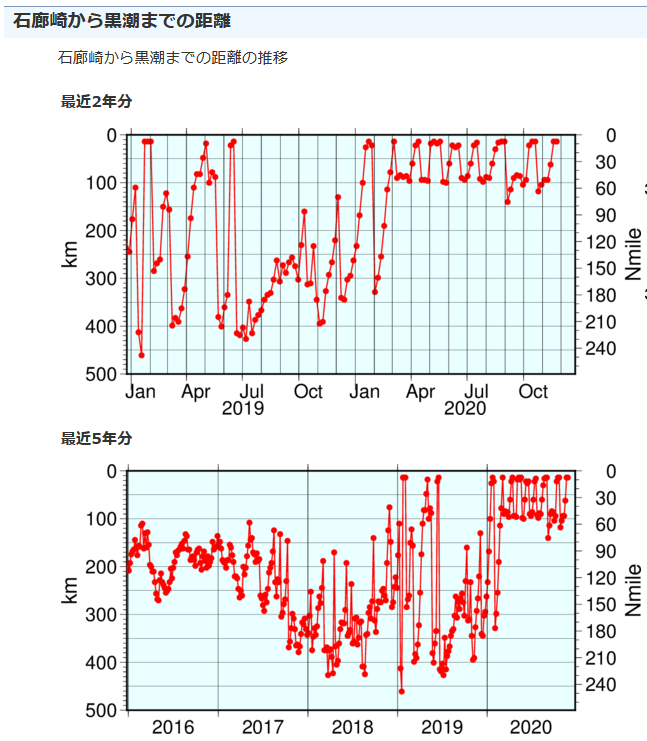
また、「海流に関する診断表、データ>日別海流」 のページで、海域ごとに、2019年1月1日以後の「前日の解析図」を見ることができる。
そのページでは、たとえば本州南の黒潮の本流は赤で示されて、よくわかるが、周辺の海域は流れの方向だけで、流速は分からない。また掲載されている分析図の期間は2019年1月以降に限られている。
私は、倉輪人の、三宅島と八丈島の間の航海を考えるために、伊豆諸島(伊豆海嶺)周辺の海流を詳しく見たい。他方、JAMSTECのサイトでは、伊豆諸島の近くの海域について、2015年1月からの海況を見ることができる。
そこで、以下では海洋研究開発機構JAMSTECのサイト「黒潮・親潮ウォッチ」を参照することにする。
JAMSTECのウェブサイトによれば、JAMSTECの中に「アプリケーションラボAPL」という、研究成果の社会応用を目的とした組織部門があり、ここでは高度なコンピュータシミュレーション技術を開発し、 季節予測や海流予測などの予測情報を提供している。「黒潮親潮ウォッチ」はAPLが掲載しているウェブサイトの一つである。
以下で、人工衛星の観測などを取り込んで計算するJAMSTECのスパコンJCOPEによる「黒潮親潮ウォッチ」の海況図とそのもとになった解析図を見てみよう。解析図の方が見やすいが2017年以降に限られているので、以前の海流については「黒潮親潮ウォッチ」の図を用いた。
倉輪人が利用した潮流
jcope2の毎日の潮況解析データの掲載は2017年1月から始まった。だが、この年の8月からは「大蛇行」が発生し4年以上続いている。大蛇行期になると黒潮の本流が潮岬沖から東経138付近まで南に向かって流れた後、大きく蛇行して、八丈島の付近(西側を通るのが「典型的」大蛇行とされている)を北上する。
最も南に下がる地点は変動し、本流の八丈島への当たり方は変化するが、それでも、八丈島の近くでは、おおむね潮が南から北に向かう。
したがって、大蛇行期には、八丈島から三宅島に向かうのに適した潮が流れることが多いが、三宅島から八丈島に向かうのに適した、北からの潮が流れる可能性は低い。
北からの三宅→八丈に適した潮が、どの程度流れるかを見るには、今回の大蛇行が始まる前のデータを見る必要がある。
「黒潮親潮ウォッチ」では、日々の海況を見ることはできないが、JCOPE-TDAによって、2015年の1月から毎週1回(金曜日)海況を解析し、それに基づき10日先の「短期予測」を行っている。私は(予測の図ではなく)黒潮の現況を示す図を参照した。
2015年春、黒潮は潮岬付近から北緯32度付近まで南下、八丈島の東、東経141度くらいのところを北上している。(南下の程度はあまり大きくないが「非典型的大蛇行流路」に分類できるだろう。)
北上する本流の西側が房総半島の沖で分岐して西に向かい、伊豆諸島付近から南に向かって流れている。
 ( 図では伊豆諸島のうち6つが示されている。上から伊豆大島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島である。)
( 図では伊豆諸島のうち6つが示されている。上から伊豆大島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島である。)4.11から5.16までの毎週の解析図は、三宅島付近では、北北東ないし北から、0.3m/s~0.5m/s位の潮が流れていることを示している。
このような潮は三宅→八丈島の航行に適した追い潮で、航海可能だったと思われる。(しかし、上で見たように、風が弱く、凪であることもまた、必要だが。)
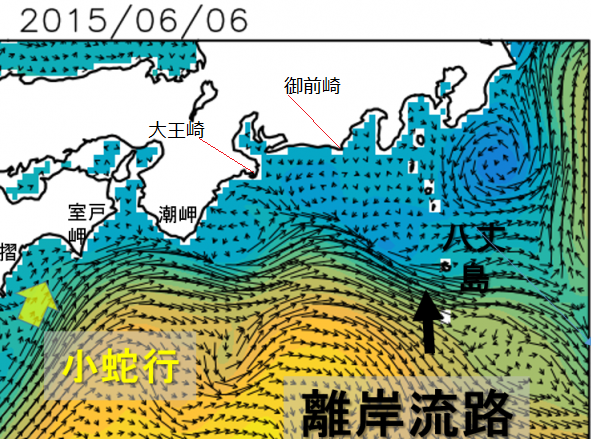
だが、5.23には、潮が御蔵島と八丈島の間を北東から流れており、5.30には、三宅島と御蔵島の間で潮が東から流れていて、このような潮では出航しなかっただろう。
しかし、6.6の図では、三宅島の近くでは北からの弱い潮(0.3m/s程度?)が流れているが、三宅島と八丈島の中間くらいから南では西から0.5m/s程度の潮が流れている。
この潮で三宅島を出航して八丈島に向かうと、航海の後半はかなり東に流されて、あぶなかったのではないだろうか。
だが、出航するかどうかは三宅島の近くの潮の流れ方を見て判断するしかない。八丈島の近くの潮の流れがどうなっているかはわからない。当時の航海には危険がつきまとっていたのだ。
6.13は航海可能だったが、6.20から7月いっぱいは北西からの早い潮が三宅~八丈間に流れ、その後は南からの潮に変わり、8月から9月中旬まではほぼ南南東ないし南東から流れ、またその後、10月17日までは東ないし北東からの潮で、三宅島→八丈島の航海には適さない潮が続いた。
 北東からの潮の場合、三宅を出航したらある程度の追い潮になると思われる。
北東からの潮の場合、三宅を出航したらある程度の追い潮になると思われる。しかし、潮の速度を舟と同じ時速4㎞とし、舟が南東に向かって漕ぐと仮定し、速度を東向きの成分と、南向きの成分に分けて、舟の速度と潮の速度を足し算すると、
舟の速度+潮の速度=(2√2, 2√2)+(-2√2,2√2)=( 0 ,4√2)で、南向きの速度は4√2≒5.6km/hになる。
しかし、100÷5.6≒18時間で、やはり、早朝に出港しても、八丈島に着くのは真っ暗になってからで、これはダメな潮だろう。
14時間以内に到着できるためには、舟の対地速度が時速7.8㎞以上である必要があり、2√2+Ⅹ≧7.8 となるのは、Ⅹ≧6、つまり時速6㎞以上の早い潮のときである。
しかし、その場合には潮の西向きの成分も6/√2で、舟の速度成分との和が6/√2ー2√2=√2となるので、舟は西に√2㎞で流されながらの航行となる。東向きにかなり漕がねばならない。そうとうにきついのではなかろうか。
私は、はっきりとした北東からの潮の場合には、倉輪人は出航しなかったのではないかと思う。おそらく、北東からの潮が流れ始めたとき、もう少し、もう少しと、潮が北になるのを待っただろうと思う。
ここに、初稿作成中に閲覧した(がコピーしておかなかった)2015年9月下旬から10月下旬までの間の海況図を1枚入れて、確認したいが、2021年6月現在jamstecのデータの公開が中止されていて、アクセスできない。 データの公開が再開されたら、ここに入れるつもりである。
次は、JAMSTECのデータ提供サービス停止中のお知らせである。
http://www.jamstec.go.jp/j/about/informations/notification_2021_maintenance.html
一部データサービス等の公開停止について
3/18付プレスリリースで既報の情報セキュリティインシデントへの対応により、一部データサービス等の公開を停止しております。ご利用の皆様にはご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
現在、以下のデータサービス等を停止しております。
現在、ご利用できないデータサービスは下記の通りです。
■各種データベース<>br ■各種お問い合わせ・相談・申し込み窓口及びフォーム<>br ■その他サービス (ウェブマガジン「#JAMSTEC」、「JAMSTEC研究者総覧」等)
さて、10月24日は北北東からの潮で、平均的な速度、時速4㎞程度で流れていれば、出航したであろう。31日は北からの潮で(八丈島付近では北西からの流れになっていたが)出航しただろう。その後は12月末まで三宅島で北西、西、ないし南西の潮になり、八丈島への出航はしなかっただろう。
この点に関しても、JAMSTECのデータが再度公開され次第、画像を入れて確認するつもりである。
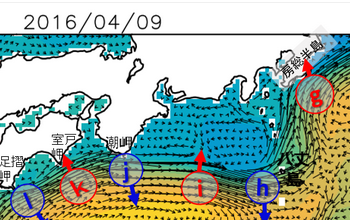 2016年は、1月から4中旬にかけて、潮岬付近からほとんどまっすぐに流れてくる黒潮本流の位置が駿河湾~伊豆半島の沖で、南北に変動しつつ、八丈以北の島々に潮が南西からぶつかるように流れている。
2016年は、1月から4中旬にかけて、潮岬付近からほとんどまっすぐに流れてくる黒潮本流の位置が駿河湾~伊豆半島の沖で、南北に変動しつつ、八丈以北の島々に潮が南西からぶつかるように流れている。4月下旬には、本流がさらに南下、八丈島の南を通って島の東側を北上、潮の一部が、南東から三宅島以北の島々に当たっている。
5月もほぼ同じ。潮岬からの本流が北上したり、また南下したりする。夏以降は、本流が八丈島から北の島々を西から直撃していた。
この1年間は、結局、三宅島から八丈島へと向かうのに適した北からの潮は流れないままだった。
したがって、JAMSTECのHP「黒潮・親潮ウォッチ」に掲載されている黒潮流路のデータの最初の2年間のうち、北北西~北~北東からの潮で、三宅島から八丈島に向かって時速4㎞程度の丸木舟で航行し、早朝に出て日が沈むまで、14~15時間で到着できるような、流速が時速4㎞以上の潮が流れていたことを確認できるのは、2015年の4.11、4.18、4.25、5.2、5.9、5.16、6.13、及び10.24の8日だけである。
ただし、海況図の掲載は週1回行なわれる。おそらく、4.11から5.16までの間はおなじような潮が流れていただろうと思われるので、凪であるか、風があっても北からの強くない風であったなら、この間はほぼ間違いなく出航できただろう。
しかし6.13と10.24はその直前の2~3日の潮(これはデータがなくわからない)の流れをみて、どうするか考えただけで、出発の判断はできなかっただろう。
まとめると2015年から2016年にかけての2年間は、出航チャンスのある潮は3週間ほどしか流れなかった。ただし、風は考慮していない。
三宅島の5月の卓越風は南西~西南西である。しかし2020年5月の1か月間の風を調べると、北東の風が11日吹いた。風速は、平均風速が9.5m/sという日が1日あったが他の日は、2.4、5.6、4.2、3.8、4.1、6.1、4.6、2.2,4.2,2.5m/sで、比較的穏やかな風である。
(すでに上でみたように、最大風速で5m/s以下という日は2年間でほぼゼロであり6m/s以下の日も数日しかない。)
北西~北~北東で5m程度の風が吹く日に、北からの潮が流れていれば、舟の(静水での)帆走速度を7㎞/h、潮の流速が4㎞/hだったとすると、9時間ほどで八丈島に到着できる。
しかし、南西~西南西の風であれば、北からの潮の時には、風速が5m/s程度でも、(スギメの航海同様)風波が立ちやすい。
倉輪人が高い航行技術を持っていて風波にうまく対処できたなら、向かい風が吹いていても、かれらは2015年4.11から5.16のような「良い潮」を生かして、八丈島に渡っただろう。だが向かい風を嫌って風が吹かない日を待ったかもしれない。
また三宅島では、秋には北東の風が吹く日が多い。海上が凪ならこの風を利用して八丈島に向かうこともあっただろう。このような航海ができたかどうかは、以下で、海況を詳細に見ることのできる2017年以降のデータを見ながら再度考える。
2017年からはjcope2の毎日の解析データを見た。
年初には、主流は八丈島と三宅島の間を通って、南西から北東へ流れる潮で、三宅島と八丈島の間の航海には、(どちらから出航するにせよ)不向き。

2017.1.15の潮流の図は<帆走丸木舟による航海、南西諸島のサバニ>で示した図を再掲した。
この潮で(風が北から吹いてなければ、あるいは南からの風だったなら)、イトマンの漁師のように、三宅島を出航し、北の下田に向かって航海すれば、よい(楽な)航海ができただろう。しかし、八丈島に向かうのは無理だ。
1.20には、秒速1m以上の速い潮が、石廊崎沖、北緯32.5度付近で北に向きを変え、八丈島の西側をかすめて北上している。
三宅島→八丈島は不可。(八丈島→三宅島は航行可。)

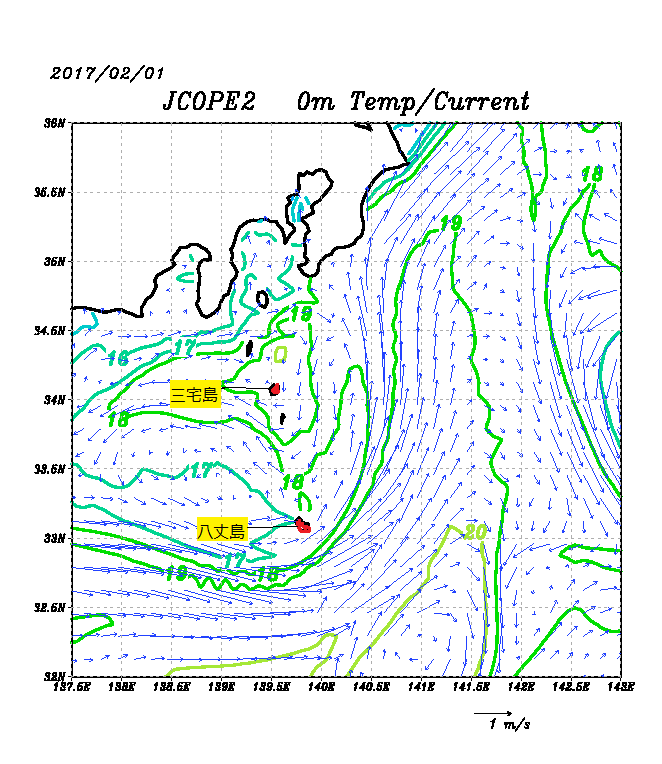
1.20には、八丈島付近で分岐ができ島の西側を強い流れが北上し、島の東側を弱い流れが北上する。
だが、 1.27になると流れが東に移り、八丈島の西側では流れが弱まった。
2.1には八丈島の東を北上した主流の西の端では主流と反対に0.3~0.5m程度の緩い潮が南に向かって流れている。
三宅島東岸でも北からの弱い潮が流れているので、この潮を見て出航したとする。しかし御蔵島に向かう途中で、潮が西に向かうのがわかる。
ここで引き返せば問題はないが、このまま進むと御蔵島より南では潮が強くなってやはり西向きである。
急いで北向きに漕ぎ、御蔵島の島陰に入って休んだだろうが、その後も潮は西向きに流れ続けたので、三宅島に戻るのに苦労しただろう。
出航に際しては(数日前からの)三宅島周辺の潮で判断するだろうが、八丈島までの航路全体の流れは分からない。
1月27日のような海況で潮待ちをし、流れ方の変化を見て、この2.1の潮がよい潮ではないと判断できたかどうか、不明である。出航しなかったとすれば、潮をみたためでなく風を見て判断しただろう。の
2月中は黒潮本流が八丈島の南を西に流れていたが、月末には流軸は南下しつつ、八丈島の南で次第に北東向きに方向を変えている。 (JAMSTEC のデータ公開を待って、次の3月中の海況とともに、再度チェックする。)
3月中八丈島の南を通った本流の一部が分岐し、八丈島と三宅島の間を東から西へながれている。
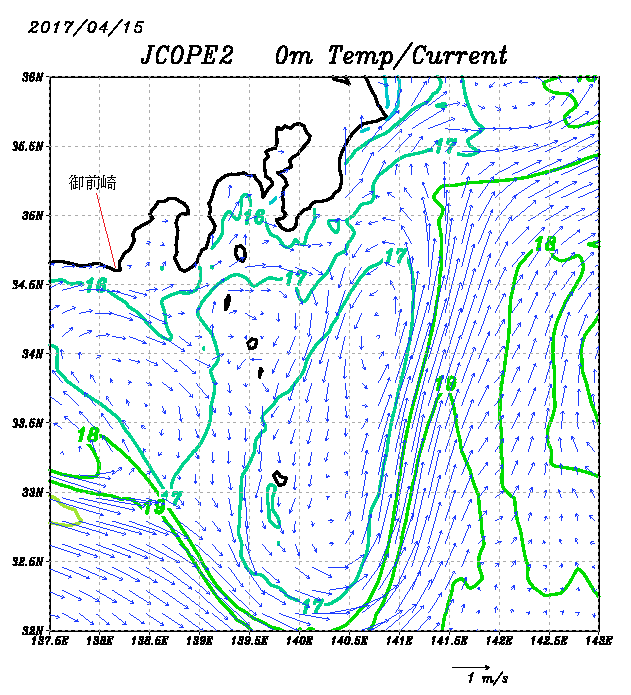 4月上旬には、潮岬から来る黒潮本流が八丈島の南で、北緯32度以南まで南下したのち、北東に流れる(非典型的大蛇行)流路を取っていて、北上する潮の一部が房総半島付近から南に向かって流れている。
4月上旬には、潮岬から来る黒潮本流が八丈島の南で、北緯32度以南まで南下したのち、北東に流れる(非典型的大蛇行)流路を取っていて、北上する潮の一部が房総半島付近から南に向かって流れている。→2017/04/15の図を参照。
また八丈島の西側には御前崎付近から南東に流れる分流があり、三宅島から八丈島にかけては0.3m/s~0.5m/s程度の二つの南向きの潮が合流するように流れている。
凪で、かつ北からの弱い風があれば、これ以上ない理想的な条件で航海ができただろう。
ほぼ同じような潮が5月上旬まで流れていた。 5月は比較的風が弱い日が多いので、5千年前にも、このような潮が4月~5月に流れたなら、風を待って渡島が行われた可能性が高い。
しかし、潮岬から来る黒潮本流が南に向かって流れる角度が変わって八丈島に近づき、中旬には八丈島にぶつかり、八丈島と三宅島の間を流れるようになる。
→2017/05/15の図を参照
こうなっては、八丈島に向かう航海は不可能である。
6月はほぼこれと同様の流れ方だったが、再び、潮岬から来る本流の南下の度合いが大きくなるとともに、最も南下した地点から蛇行する度合いが強まり、流れ方は複雑に変化するが、おおむね南から八丈島以北に向かって流れていて、三宅島から八丈島に向かうには適さない潮であった。

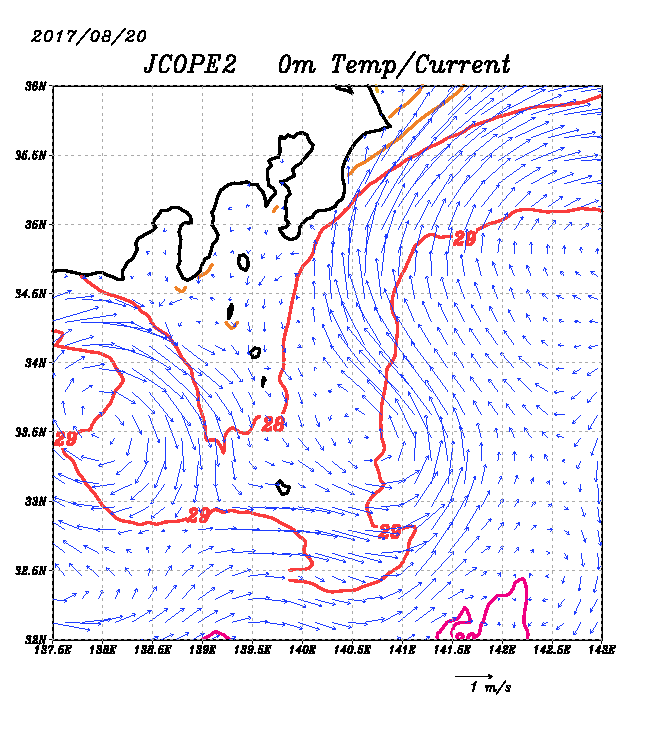
7月には、一時的に、三宅島~八丈島の間の海域が、その両側を北に向かって流れる潮の間の谷間のように、潮が弱い状態になることがあった。→7.25
また8月には御前崎方向から来る分流が三宅島から八丈島に向かって0.5m/s以下の速度で流れるということもあった。7.25及び8.20の海況図を参照。
 このように時々一時的に、航海が可能な潮が流れたが、8月以降年末に至るまで、黒潮は、おおむね、潮岬付近から大きく南下したのち八丈島の南から北に向かって流れ、三宅島から八丈島に向かう航海には適しない流れ方をした。黒潮の大蛇行が始まったのだ。→10月1日の海況図を参照。
このように時々一時的に、航海が可能な潮が流れたが、8月以降年末に至るまで、黒潮は、おおむね、潮岬付近から大きく南下したのち八丈島の南から北に向かって流れ、三宅島から八丈島に向かう航海には適しない流れ方をした。黒潮の大蛇行が始まったのだ。→10月1日の海況図を参照。 2018年3.30の図を見れば、主流が真南からまっすぐに北上して伊豆七島にぶつかっているのがわかる。
2018年3.30の図を見れば、主流が真南からまっすぐに北上して伊豆七島にぶつかっているのがわかる。大蛇行中は八丈島から三宅島に向かう航海のチャンスはいくらでもあったように思われる。
大蛇行以外の時にも、上の図でみたように、南から北に向かって流れる潮の頻度は低くない。本土に向かって航海するチャンスはかなり多いように思われる。
小まとめ:倉輪人の八丈島への移住と本土への帰還
大蛇行流路ではなかった2015年から2017年にかけて、風向き、また風速(したがって凪の状態)と関係なしに、潮の流れ方だけ見れば、三宅島から八丈島に向かって流れる有利な潮の日が時々あることが分かる。だが、<三宅島で吹く風>でみたように、三宅島では、そもそも平均風速が5m/s以下という日はほとんどなく、6m/s以下の日を数えても2年間で57日というふうに、べた凪の日を期待することは全くできない。
おそらく、倉輪人たちは、かれらの技で転覆せずに航行できると判断した、比較的波の穏やかな日に、思い切って出航したのだろう。
おそらく、かれらは夏季の、暖かい追い風の日に、獣皮かザルを使った帆の手綱を「やったり取ったり」しながら、ある程度の浸水に体を濡らしつつ、一瞬も休むことなく、航行をおこなったのではなかろうか。
彼らは本土から、多数の土器だけでなく、島で放牧して成長後に捕獲するためにウリボウ(イノシシの子)を運ぶなどのこともしており、かなりの量の物を運んでいる。「縄文の海人」言われるが、海を渡るすぐれた技術を有していたことは確かだと思われる。
なお、上では、八丈島から北の三宅島に向かうのに適した潮については、ついでにしかふれなかった。しかし、大蛇行期には顕著に、潮が八丈島の南から、北へと流れる傾向が強まる。
そして蛇行期でなくても、分岐した潮の一部が八丈島付近から三宅島方向へと流れることが時々あり、北に向かって航海するチャンスは、三宅島から南下して八丈島に向かおうとするよりははるかに多い。
三宅島から八丈島へと向かうのに適した潮が流れることは少なかったが、それは潮が南から北に向かって流れることが多いからであり、三宅から八丈島に向かうチャンスが少ないということは、とりもなおさず、八丈島から三宅島に向かうチャンスが多いことを意味しているといってもいいほどである。
結論を言えば、本土から伊豆諸島北部を経て、三宅島(あるいは御蔵島)から八丈島に向かうのは難しかった。
八丈島への移住は相当な冒険だった。だが八丈島から本土に向かうこと、あるいは八丈島での暮らしが楽でなく本土に戻りたいと考えた場合には、いつでも戻ることはできただろう。
倉輪人の集落は200年間存続(小田によれば繁栄)した。しかし、5千年前頃には数人の小規模集団に陥り、その直後に消滅してしまった、という。
小田はオセアニア地域に縄文土器と酷似した土器があり、彼らが八丈島よりさらに南の島々に移住したことも否定できないという。
しかし、小規模集団に陥り、集団としてのエネルギーが低下してから、本州から八丈島にむかうよりもはるかに遠い距離にある、見知らぬ島に移住するということは考えにくい。
これに対して、北の伊豆七島、そして本土は、彼らが最初に、八丈島に来る前に恐らく交易があった場所であり、またその後何度か通ったことのある場所で、知り合い、友人もいただろう。
物的、客観的根拠があるわけではないが、私は、彼ら倉輪人は、北部伊豆諸島もしくは本土へと帰還/(再)移住したのではないかと思う。
さて次に、湯浜人がどこからどのようにやってきたか、という問題に取り組みたい。
第6節 湯浜人は黒潮に乗って西日本(東海地方以西)からやってきた
湯浜人がどのように八丈島にやってきたのかについて書いている人は、著名な考古学者小田静夫以外、管見の私は知らない。小田は、すでに述べた通り、湯浜人は、彼らの2千数百年後に八丈島に移住し本土との間を何度も往来したことが確かな倉輪人と同じように、意図的・計画的に激流の黒潮を横断して本土から八丈島に渡った縄文の海人とみなしている。しかし、私は湯浜遺跡から出土しているものから推測される湯浜人の、上陸時の様態、上陸後の生活様態から、かれらの上陸は成人たちによる意図的計画的航海によってなされたものではなく、上陸後活動できる大人を欠いた子供たちが主であるようなメンバーの上陸であり、ほとんど無一物であったことから、予想外のできごとの発生により起こった漂流の結果だと考えるに至った。乗り物は人数と安定性とから丸木舟ではなく筏だと考えた。
予想外の出来事として、第一に考えられるのは、大地震による津波の発生であり、津波にさらわれ沖に流される場合である。津波の発生可能性については後述する。ほとんどの人は波に呑まれ命を失っただろうが、運のいい少数の人は何かにつかまるなどして沖に流され、黒潮に乗って漂流することになる。
問題は、偶然により起こった漂流で広い海の中の一つの島に漂着する可能性がどの程度あるのか、ということである。
「黒潮の流路」 の図にみるように、九州南部、四国沖までは黒潮はほとんど決まったルートでしか流れていないが、潮岬付近から東ではその流路は大きく変動する。南下して、八丈島付近を流れることも多い。湯浜人はそうした潮に乗って、東海地方以西から漂流してきた結果、八丈島に漂着・到着したと私は考える。
四国、南紀などから流されて、計算上、八丈島に「漂着」できる可能性のある漂流
次の図は、2004年3.31の本州の南の海況を示した図である。紀伊半島付近からほぼまっすぐ東に流れる「非大蛇行接岸流路」である。
紀伊半島以西の太平洋岸のどこかから沖に流された筏があり、このような潮に乗ったとしても、八丈島には漂着する可能性は非常に低い。代わりに伊豆諸島北部のどこかの島に漂着する可能性が高まるだろう。
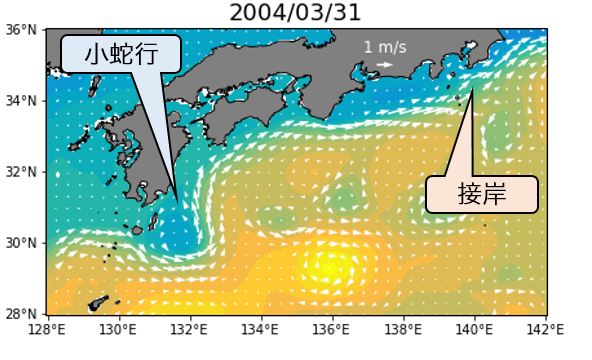
実際、『日本書紀』の飛鳥時代の記述に、推古天皇28年(620年)八月の条に掖玖(やく、現・屋久島)の人が「伊豆島」に漂着したとあり、
『日本書紀』には「伊豆島」、あるいは「伊豆嶋」に流刑に処せられた複数のケースが書かれていて、伊豆島とは伊豆諸島のことを指していると考えられる、という。Wikipedia「伊豆大島」
掖玖(やく)の人が漂着したという「伊豆島」は本州から最も近い伊豆大島である可能性が高いと思われる。
屋久島の人が伊豆島に漂着した時の黒潮は、この2004.3.31.の海況図と同じような、非大蛇行接岸流路をとっていただろう。
だが、 四国の太平洋岸あるいは紀伊半島の潮岬付近から、沖に流された筏は、黒潮が離岸流路をとって八丈島周辺を通る場合には、八丈島に漂着する可能性が高まる。
ところで、気象庁の「黒潮の流路」で典型的な流路とされる1と2(jamstec美山の図ではオレンジの非大蛇行接岸流路と青の非大蛇行離岸流路)に関して、黒潮は潮岬沖を通過後、1では東北東に向かって流れ、2では南東に向かって流れているが、大蛇行の場合(美山の水色と赤))ほどではないけれども、どちらの場合にも、本州の太平洋岸からはかなり離れたところを通っている。
潮岬から黒潮流軸(中心部)までの距離は平均50㎞ほどであるが、熊野灘の北部の大王崎からの距離は130㎞程あり、御前崎ではほぼ200㎞ある。 気象庁>各種データ・資料>「黒潮までの距離」参照
とすると、例えば伊勢湾沿岸で暮らしていた人々が津波にさらわれ、湾口までは流されたとしても、130㎞も沖を流れる黒潮に乗ることがあるかどうか、あるいは御前崎から西の渥美半島までの太平洋岸の人々が沖に流されたとしても、200㎞も南を流れる黒潮に乗ることがあるのかどうかが問題になる。

 しかし、次の海況図をみてもらいたい。
しかし、次の海況図をみてもらいたい。2020.8.16.14時の海況図では、黒潮本流は室戸岬沖付近から大きく南下し遠州灘の沖ではおよそ北緯31度(図の左側の数字)より南まで南下したあと蛇行。ほぼまっすぐに北緯33度付近まで北上し、紀伊半島にぶつかって東に向きを変え、遠州灘では太平洋岸に沿って東に流れ、それから再び南下して北緯33度付近の八丈島(図の青い円)にぶつかるように流れている。
このように黒潮が流れていれば、伊勢湾の湾内から湾口付近まで流されたものも、また御前崎から渥美半島までの大平洋岸から流されたものも、黒潮に乗って、八丈島付近へと運ばれる可能性がある。
また2016.9.10の海況図では、黒潮本流が潮岬付近から八丈島にぶつかるように、ほぼまっすぐ流れている。ところがその潮の西の端の方は石廊崎沖から大王崎に向かって流れ、さらに熊野灘沿岸を南西方向に流れて、潮岬から南下してくる本流に引き込まれるように流れている。
結局、この日のような潮の時には御前崎から西の太平洋岸、伊勢湾口付近、そして熊野灘沿岸から沖へと流されたものも、黒潮本流に乗ることになり、八丈島の近くへと運ばれるだろう。
このように、黒潮本流が太平洋岸に直接ぶつかるように流れたり、あるいは大平洋岸を流れる潮が、沿岸からは100㎞以上離れたところを流れている本流に引き込まれるように流れたりするケースは、「黒潮親潮ウォッチ」およびJCOPE2のデータを調べてみたが、多いわけではない。
しかし、このような潮の時なら、御前崎から西の太平洋岸で津波に襲われ沖に流されれば、本流から遠く離れていても、黒潮本流に乗る可能性はある。可能性は高くはないが、あることはあるといえる。
これに対して、四国の足摺岬から紀伊半島の潮岬までの太平洋岸から流された筏は、容易に黒潮本流に乗り、八丈島に向かって流される可能性が高い。以下ではそうしたケースについて確かめる。
(1)潮が直接八丈島にぶつかっているときにはその可能性が大きくなるが、(2)典型的大蛇行あるいは非典型的大蛇行の場合のように、潮流が八丈島から離れたところを通る場合にも、風による表面流によって、筏などの漂流物は島に漂着する可能性がある。
(1)黒潮が直接八丈島に直接ぶつかる場合
黒潮は2016年半ばから2017年半ばにかけて、50kmほどの変動幅をもって石廊崎沖ほぼ200kmのところを流れている。つまり黒潮は八丈島にぶつかるように流れている。筏が四国や紀伊半島の沿岸から沖に流されたとすれば、風が北東あるいは北からふいて黒潮の中心部に向かって押しやることがなければ、筏は黒潮の北側に乗って漂流することになる。風は無視しよう。
「黒潮親潮ウォッチ」では毎週金曜日に現況とその先の予測とを載せている。その現況を見ていくと
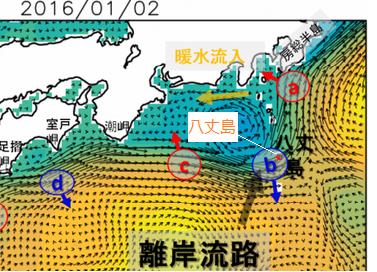
2016.1.2には、黒潮の真ん中が島にぶつかっている。このような海流は、4.9、4.16、4.23、7.9、7.16、7.23、7.30、9.24、10.23、11.20、12.16も同様。
10月はじめから12月末までは、黒潮が少し南下して、八丈島の南部をかすめたり、北上して島を直撃したりを繰り返している。
2016年中には八丈島に黒潮中心部がぶつかった日数は(週一回の観測で)合計15日あったので、1年間に15×7=105日あったと考えられる。つまり、紀伊半島付近から漂流したら、1年のうちの100日ほどは、八丈島にぶつかる海流に乗る可能性がある。
黒潮の幅は100㎞ほどである。八丈島の島の長さは15㎞。これに潮が45度の角度でぶつかるとすると島に当たる潮の幅は10㎞。したがって、この潮に乗って漂流している物は、10%の確率で八丈島に接岸する可能性があると考えられる。
105÷365≒0.29で、105日は1年の約30%を占める。30%の海流が八丈島にぶつかる。そして八丈島にぶつかる潮に乗った漂流物は10%の確率で、島に流れつく。
そうだとすれば、ある日偶然漂流した湯浜人の乗った筏は 0.3×0.1=0.03、 つまり3%の確率で八丈島に到着する可能性があるといえる。
3%の可能性は低いだろうか。しかし、もし、津波で100台の筏が流され漂流したとすれば、3台は八丈島に着くことになる。3%の漂着可能性は低いとは言えないだろう。
筏が紀伊半島や四国の沿岸から沖に流されたとすると、筏は黒潮の北側に乗って運ばれるだろう。そうだとすると、流れの中心部が島にぶつかるときには、筏の漂着の可能性はあっても、その可能性はあまり高くないと考えられる。
北ないし北東の風が強く吹いていなければ、筏が黒潮の流れの南側に乗ることは少ないと思われる。したがって、黒潮が八丈島の北側をかすめて通っているときには、筏が漂着する可能性は低いか、ほとんどゼロであろう。
だが、逆に八丈島の南部を黒潮の北側がかすめるように流れるときは漂着の可能性が大きくなるだろう。
もう一度海況図を調べると、 5.14、5.21.5.28には、黒潮は八丈島の南を、島から離れたところを通っているが、6.4、6.11、6.18、6.25、7.2では黒潮が八丈島の南部をかすめて流れている。
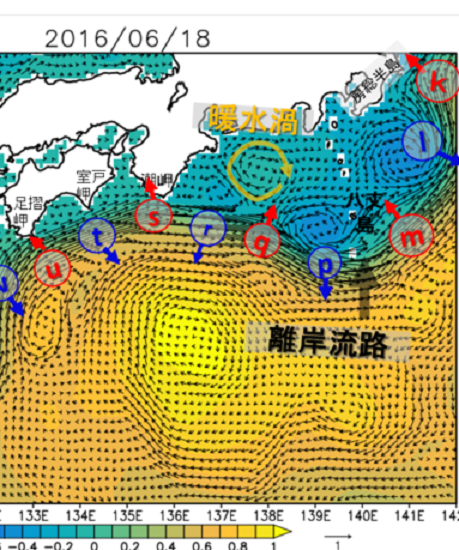
8.6、8.13には 黒潮は北上し、八丈と三宅の間を流れている。(筏は三宅島に漂着する可能性があるが八丈島への漂着可能性はない。)9月上旬まで同様。
9.10には、黒潮が再び南下してきて、八丈島の北部をかすめるように流れている。そして、その後は、八丈島を直撃する。
そこで、筏の八丈島への漂着可能性をつぎのように計算することもできるかもしれない。
「黒潮親潮ウォッチ」のデータで、週1回の黒潮の現況を1年間見たうち、直撃が15日、黒潮の北側が八丈島の南部にぶつかるか、かすめて流れる場合が10日あった。
黒潮中心部が八丈島にぶつかるときの筏の漂着可能性を0.1、黒潮中心部は八丈島の南をとおり、黒潮の北の端が島の南部にぶつかるか、かすめる場合の漂着可能性を1,それ以外の流れ方の場合にはゼロとして計算すると、
黒潮が、2016年のような流れ方をした年には、黒潮に乗って潮岬沖を通過した筏は、
(15×0.1+10×1)×7=80.5、したがって365日のうちの80日はほぼ確実に、八丈島に漂着する可能性がある、といえるのではないか。
二つの漂着確率/可能性に関する数字がある。一方の計算では、足摺岬付近から沖に流されて黒潮に乗った漂流物は、潮岬の沖を通過した後、10%の確率で八丈島に到着する。もう一方の計算では、1年間のうち80日、つまり約20%は八丈島に接岸する可能性がある。
この2つの数字はどのような関係にあるのかを、私は説明できない。しかし、とにかくこのように見積もることが一応可能ではないかと考え、このまま示す。どなたか説明をしていただければありがたい。
ここで述べたことは、漂流する筏が、流れの中心部かその一部が八丈島にぶつかるように流れる黒潮に乗っていた場合の、島への筏の漂着ないし接岸の可能性について考えられることである。
だが、黒潮が、かすめる場合も含め、必ずしも八丈島にぶつからず、島から離れたところを通る場合にも、筏が島に接岸・漂着する可能性がある。それを次に考える。
(2)風による表面流に乗って八丈島に漂着する場合
典型的大蛇行あるいは非典型的大蛇行の場合のように、潮流が八丈島からやや離れたところを通る場合にも、風による表面流によって、八丈島に漂着することがある。以下に、そうしたケースを検討してみる。潮流は深さによって流れが異なり、特に、風が吹いている場合には、潮流本体の流れの方向とは無関係(時には逆方向)に、表面から水深1,2mくらいまでは、風との摩擦によって水が風下へ引っ張られる。つまり潮が風下に流れる。
このような、風によって生じる海の表面の流れを吹送流と言う。流速は風速の2~4%とされる。ただし、吹奏流はまっすぐ風下に向かって流れるのではなく、風の方向に対して右へ30~40°の角度で流れる。
ブリタニカ国際百科事典小項目の解説;https://kotobank.jp/word/%E5%90%B9%E9%80%81%E6%B5%81-83019による。

地球上では、自転の影響で大気も水も、動くときには(北半球では)進行方向右向きの力を受ける。これをコリオリの力という。台風の中心に向かう風が、反時計方向に回転する渦巻きになるのもこのためである。
風によって生じる海水の流れ=吹奏流はエクマン輸送と言う。左の図を参照。 図はWikipedia「エクマン輸送」、日本語を書き加えた。
筏の上に人や物が乗っていれば、それらが帆の働きをして、風下に流される速度を増すだろう。風速が10m/s=時速36㎞とすると(それ以上は波が高くなって筏の揺れが大きくなり、乗っている人が海に落ちる危険がある)筏は
時速36km×0.02=0.7km/時 ~ 36㎞×0.04=1.4km/時で30~40°の角度で右斜め風下に流される。
風速が5m/sなら、その半分0.35㎞~0.7㎞/時で風下に流される。
①非典型的大蛇行流路(美山の図で水色の流路)、および②非大蛇行離岸流路(美山の図で青)の場合の二つのケースに分けて考える。ただし、以下ではコリオリ効果の分は、計算を簡単にするため、無視する。
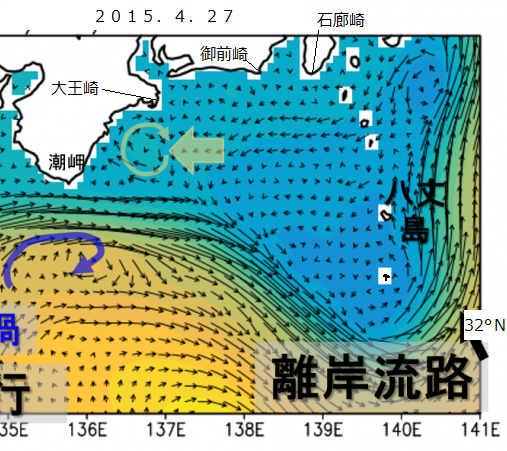
① 左図のような潮がある。
このような流れの時には、黒潮は潮岬沖ないし大王崎沖辺りから蛇行して南下するが、北緯31度~32度くらいのところから北上して八丈島の東側で島の近くを流れる。
黒潮が八丈島の東側を流れるときに東の風が吹けば、表面流は八丈島方向に流れ、筏があれば八丈島に吹き寄せられる可能性が高まる。
この流路の北側に乗って流されてくる筏が、北緯32度付近に来た時から2日か3日、風速10mの東風が吹いたとする。(緯度1度に相当する距離はほぼ100kmである。)
潮に乗った筏が北緯33度付近に位置する八丈島まで100km北上するのにかかる時間は、黒潮の速度が時速5㎞なら20時間である。この間に表面流に乗った筏は14㎞~28km西に流される。
したがって、黒潮の西の端が八丈島から東におよそ15㎞~30㎞程度のところを通れば、筏は吹き寄せられて島に接岸できる可能性があるだろう。
 ②
右の図は2015年6月13日の潮流の様子である。
②
右の図は2015年6月13日の潮流の様子である。この潮は遠州灘でいったん南下しかかった黒潮が御前崎沖で北上し、それから再び八丈島の西側を南下し、島の南側を通過してから北東ないし北へと流れている。
この潮流の(進行方向)左側の端は、石廊崎沖では東経138度30分、北緯34度付近(P)を通過した後、南下して八丈島の西側30㎞付近を南下するとする。また潮の流速は時速5㎞と仮定する。
Pから八丈島に最も近い点までの距離は140㎞程なので、ここに達するには28時間かかる。
10m/sの西風が吹いていれば、筏は0.7㎞×28~1.4㎞×28≒20㎞~40㎞東に流される。島は南北に15㎞ほどの長さがあるので、筏が島に漂着する可能性は十分に高い。
江戸時代、多くの難破船が、八丈島に漂着した
ところで、江戸時代には多くの船が遭難した。そして、220例に登る八丈島への漂着が報告されている。江戸時代の、弁才船また弁財船(ベンザイセンまたはベザイセン)と呼ばれた大型帆船は、少人数で操縦でき、大量の物資を運ぶことができたが、シケに遭うと舵が壊れやすい欠点があり、しかも帆柱を切るのが一般的な対処法で、遭難すると航行能力を失い漂流するのが常であった。そして経済活動活発化に伴う大阪と江戸の間の船の往来が増すにつれ、遭難、太平洋漂流が繰り返し起こった。
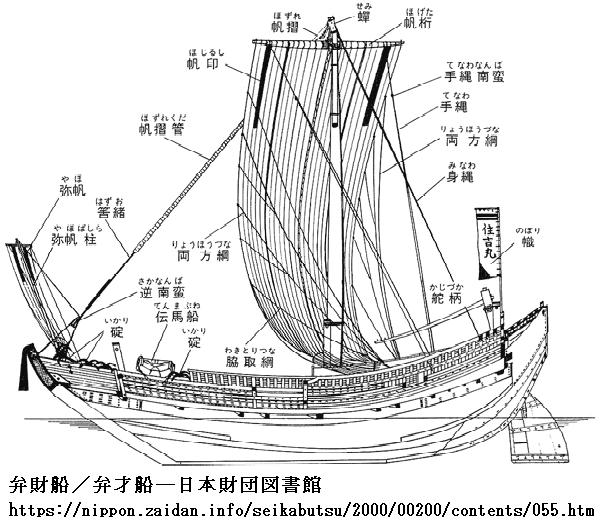
岩尾龍太郎『幕末のロビンソン』弦書房によると、和船は「鎖国体制の下、少人数で操れる一枚帆を巨大化し、積載量のみを増大させる定向進化をとげ」た結果、強風に弱い構造的欠陥を抱えていた。
小林茂文「漂流と日本人―漂流記に見る異文化との接触―」『漂流と漂着/総索引』<海と列島文化>別巻、1993、小学館
によると、江戸時代のおよそ200年間に、明らかになっているだけで、369件の漂流があった。そのうち200件は八丈島に漂着、次が中国への漂着40件、朝鮮への漂着が33件などだった。
「近世漂流船の漂着先と件数」(河合彦充『日本人漂流記』社会思想社 1967 に依拠、という。)
小林は「江戸時代には、大西風に吹き出されると、すべての和船が漂流船になる可能性があったといっても過言ではなかった」と書いている。
岩尾は、遭難した場合、北太平洋海流に乗ってアメリカ東岸へと流されることが多いが、ほとんどが漂着する前に沈没してしまうため、実際には無数の遭難事故があったはずだ、と言っている。
「369件」という数字は生還して報告がなされた限りの遭難/漂流の数で、実際に漂流した件数のごく一部に過ぎない、ということである。 したがって太平洋側で漂流した場合、八丈島への漂着可能性が200÷369=0.54、つまり54%あるということを意味してはいない。
だが、遭難件数が、実際には369件よりもはるかに多かったにしても、黒潮の流れる本州沿岸で漂流した場合、八丈島に流れ着く可能性は相当にあるということは言えるだろう。
こうして、航海術なしで、筏などで四国や紀伊半島から海に乗り出した/流されたとしても、うまく黒潮に乗れば、また風の吹き方によっては、八丈島に漂着する可能性が大いにあることがわかる。
【追加】
井上靖の小説に、下山事件を取材する新聞記者の『黒い潮』というのがある。この記者の妻は他の男と潮岬で心中した。灯台のある突端とは反対側の断崖下の砥端トバナという岩場からの投身自殺だった。潮岬の駐在所の巡査は、駆け付けた夫である記者に「砥端では場所が悪いです。死体はたぶん上がらんと思うんです。あそこのちょっと沖合で難破した船はあなた、八丈島へ漂着しますからね」と言っている。井上靖全集第8巻参照。
潮岬の近くを通る潮が八丈島に向かって流れることを示す一例で、作家が同様の心中事件を取材した際に知ったことであろう。
湯浜人はどうして漂流することになったのか
湯浜人の八丈島への上陸は7300年前の鬼界カルデラ火山の噴火よりも少し前だったと考えられる。この時代に海岸近くで暮らしていた人々が、なんらかの原因によって海に流されて漂流したという出来事はどれくらい起こっただろうか。
漂出―漂流の原因には、太平洋の島あるいは太平洋岸の居住地近くの火山の噴火、居住地の海岸への大きな津波の襲来、または環境悪化や他の集団との関係悪化などのために海沿いに移住しようとして、誤って沖に流された、などのことが考えられる。
縄文時代早期、1万1千500年前ごろから7000年前頃に、西日本にはどれくらいの数の人が海岸近くに住んでいたかをあらかじめ見ておこう。
小山修三*杉藤重信「縄文人ロシミュレーション」<国立民族学博物館研究報告> 9-1によると、
日本の先史時代の人口は全国的にみると、縄文時代の人口は早期(8000B.C.)から前期(5000B.C.)にかけてゆるやかに増加し,その後急速に増加して中期(4300B.C.)にピークに達するが,その後減少し,弥生時代からふたたび増加する。
また、縄文人口の分布を地域別にくわしくみると、西日本(九州,四国,中国,近畿)では人口量が時代をとおして少なく,かつ微増をつづけたとされる。
[表2a]は小山*杉藤「縄文人ロシミュレーション」による

 縄文時代早期に、大型の哺乳動物に代わってシカやイノシシなどの中・小型哺乳動物が狩猟対象の中心になり、弓矢が急速に発達したが、他方で、海面が上昇し(縄文海進)、沿岸部に好漁場が増えた結果、魚介類の利用が拡大し、北海道から沖縄まで各地で貝が常食された。
縄文時代早期に、大型の哺乳動物に代わってシカやイノシシなどの中・小型哺乳動物が狩猟対象の中心になり、弓矢が急速に発達したが、他方で、海面が上昇し(縄文海進)、沿岸部に好漁場が増えた結果、魚介類の利用が拡大し、北海道から沖縄まで各地で貝が常食された。
また土器あるいは石の錘(おもり)また(トカラ列島以南では)貝殻を錘とした網漁が行なわれ、ヤス、モリを使った漁も行われた。(Wikipedia「縄文時代」「貝塚」「日本の貝塚一覧」なども参照。)
九州などの海岸段丘にかなり大きな集落が成立し始めていたようである。海岸の平地(後に「浦」と呼ばれるようなった場所)にもいくつかの家族が集まって生活しており、周囲の山で狩りと植物の採集を行ないつつ、漁撈を主な生業とする暮らしを行っていた。河川の中流域の河岸段丘などにも人々が暮らしていた。
以下では、湯浜人が大津波に襲われた7300年前頃には、陸地での動物資源が減り海産資源の利用が必要になったため、全人口の半分ほどは海岸か海岸に遠くない場所に住んでいたと仮定する。
「縄文人ロシミュレーション」p22の地域区分の図によれば、静岡の西半部と愛知が「東海」で、岐阜の南部は「中部」の8分の1程度、三重と和歌山については近畿地方が7府県からなるのでその7分の2を算入する、四国については半分を算入する。
また7300年前頃の人口としては、早期と前期の人口の平均を取る。また沿岸地域に住んでいたであろう人々の数はさらにそれらの半分と見込む。
以上のようにすると、「東海」は(2,200+5,000)÷2÷2=1,800、岐阜南部=(3,000+25,300)÷2÷8÷2≒885、三重+和歌山=(300+1,700)÷2×2/7÷2≒143、四国=(200+400)÷2÷2=150 →合計2,978人、およそ3,000人が静岡県西部から四国にかけての太平洋岸に住んでいた人の人数である。
 旧石器時代の人々は、樹下で獣皮にくるまって寝たか、あるいは写真に見るようなテント状の差し掛け小屋を住居にしていたと想像されている。
旧石器時代の人々は、樹下で獣皮にくるまって寝たか、あるいは写真に見るようなテント状の差し掛け小屋を住居にしていたと想像されている。縄文時代早期にはもっとしっかりした住居で暮らしていたかもしれない。
海岸で漁労を主な生業にしていた人々は筏を持っていて、湾内で、漁網や錘、木蔦などのロープを積んで、漕いで移動したり、筏の上から銛で魚を突いたりしたと思われる。
【追加】 斎藤成也『核DNA解析でたどる―日本人の源流』(河出書房新社,2017)、および『日本列島人の歴史』(岩波書店、2015)によると、国立遺伝学研究所斎藤研究室のミトコンドリアDNA完全配列データを用いた推定結果では、4千年前~3千年前の人口は、中央値で80万人、誤差を入れて最低30万人と推定された。〔小山では75,800人である。〕「縄文時代の晩期の日本列島の人口は小山の推定より数倍大きかった可能性がある」という。 斎藤の推計に従い、早期~前期の人口を小山の推定の4倍~10倍だすれば、当時静岡県西部~四国にかけての太平洋岸に住んでいた人の人数は、12,000人~30,000人と見込まれる。
南海トラフ地震と西日本を襲う津波
Wikipedia「津波」によれば、津波は震源地が海底である大地震によって起こされることが多く、津波を引き起こす地震は海溝付近で発生することが多い。海溝付近では数十年―数千年の間隔で大きな断層を生じて、マグニチュード7―9の地震が起こり、大津波が発生する。
 東海地方から西の太平洋岸に大津波をもたらす地震として南海トラフ地震が考えられる。気象庁ホームページによると「南海トラフ地震は、駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界を震源域として概ね100~150年間隔で繰り返し発生してきた大規模地震」である。
東海地方から西の太平洋岸に大津波をもたらす地震として南海トラフ地震が考えられる。気象庁ホームページによると「南海トラフ地震は、駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界を震源域として概ね100~150年間隔で繰り返し発生してきた大規模地震」である。
内閣府「防災情報のページ」http://www.bousai.go.jp/jishin/tonankai_nankai/index.html >東南海・南海地震対策について によると、津波の高さは図のようになり、津波により「東海から九州にかけての太平洋岸を中心に約4万年棟」が全壊被害を受ける。
また「避難意識が低い場合」、死者数は8,600人と予想されている。もちろん縄文時代には、海岸近くで地震の揺れを感じて避難した人の割合は0%だったろう。つまり、図の緑色、オレンジ、赤で描かれた海岸の近くにいた人々のすべてが津波にさらわれただろう。
ただし、津波が襲来したときに、山に入って、狩りをしていたり、食料にする植物や果実を採取していたりした人は、津波に巻き込まれずに済んだだろう。海岸で暮らしていた人々のうちの半数の人が、海岸から離れたところにいた、と仮定する。
Wikipedia「歴史的な津波の一覧」に載っている奈良時代以降現代までの1300年間の大津波を数えると27回あり、ほぼ500年に10回、100年に2回の割合である。
7300年前ごろまでの100年間に2回の大津波が発生し、その都度、近畿地方~四国の太平洋岸に住んでいた3,000人(小山による)ないし3万人(斎藤による)の半分のおよそ1500人ないし1万5千人が津波にさらわれ、(6人家族で1台使っていた)500台から5000台の筏が津波で流され、そのうちの何台かに乗ることができて、かろうじて命のあった人びとが、八丈島の湯の浜に到着した、と考えられる。
津波により沖に流された―そのシナリオ
西日本の広範な地域の浦々が、大地震に続いて起こった大津波によって襲われ、人々は、住居の柱であった数本の竹や木、笊などの容器、獣皮を用いた(寝)袋、あるいは漁労用の筏、網や、キヅタなどで作ったロープなどと一緒に沖に流されたであろう。多くの人がおぼれて死んだ。しかし、近くにあった浮遊物につかまり溺死を免れた人も少数ながらあった。筏に乗ることができた者は、小さな浮遊物につかまっていた人が近づけば筏に乗るよう勧め、手を貸しただろう。大津波が発生したのは6月で、梅雨に入っていた。昼ごろだった。
もし夜間であったら、助かった人の数ははるかに少なかっただろう。また冬であれば海上を漂流する際に低体温症などで死亡する人が多かっただろう。また真夏の海はのどの渇きで数日の漂流にも耐えられなかっただろう。梅雨の時期なら、獣皮が一枚あればそれに水をためることができ、長い漂流にもたえることができただろう。
四万十川の河口付近に暮らしていた数十家族も大津波に呑まれた。
前出、気象庁の「黒潮流軸までの距離」によると足摺岬付近の黒潮流軸の平均位置は海岸から50㎞程である。黒潮の幅が100㎞ほどだから、四万十川河口から沖合に流されれば、黒潮の北側の端にのることは確実だろう。
潮岬をはじめとして紀伊半島南部の海岸から沖合に漂出した場合にも同様に黒潮の北端に乗っただろう。
また、すでに上で示ししたが、静岡県西部の太平洋岸、三重県の伊勢湾、熊野灘に面した海岸などから、黒潮本流までの距離は遠いけれども、いくつもの複雑な分流が発生し、海岸の近くの分流が八丈島に向かうことがあり、また海岸近くの潮流が遠くの本流に向かって引き込まれるように流れることもあり、いずれの海岸でも、津波によって沖に流されれば黒潮に乗り、八丈島に近づく可能性があった。
ある筏には津波にのまれたときに腕を骨折した大人の男と二人の子供が乗っていた。すぐ近くに流れてきた筏には男女4人の子供が乗っていた。
大人の指示で、二つの筏は、泳ぎの達者な少年によって、蔦のロープで結ばれた。また、子供たちは、周囲に漂っているものを可能な限り拾い集めた。中でもロープと獣皮は貴重品だった。筏には漁網が積んであったが、土錘(土で作った重り)がつけられていて波でさらわれた後沈んでしまい、回収できなかった。 現在とは違い、ごみの類は存在しなかった。
棕櫚や蒲葵の葉、葉のついた杉の枝もできるだけ集めた。夜が来た時、彼らはその枝を体にかけて眠った。流れていた獣皮の袋に入った木の実は7人の2日分の食料になった。
壊れて浮いていた小屋の柱の一本にしばりつけてあった獣皮の袋の中には黒曜石の小塊が入っていた。筏に乗った子供の1人が、自分の家にあったもので、その黒曜石を数世代前の祖先から、家族を守ってくれる力を持ったものだと教わり大切にしていたものだ、と言った。この筏の上では役に立つかどうかわからなかったが、失わないよう、しっかり筏に縛り付けられた。
こうして漂流が始まった。
翌日の昼頃陸に近づいた。高い崖が見えた。泳ぐことができそうな距離にみえた。しかし大人が「やめろ。海は流れていて、泳いでも流される。陸には泳ぎ着けない」というので、そのまま筏に乗り続けた。足摺岬から110㎞、室戸岬の沖、数百mのところだった。
次の日の夕方また陸の近くにきたが、同じように、泳いで上陸することは大人に止められ、あきらめた。足摺岬から260㎞の潮岬だった。
足摺岬付近から八丈島までは700㎞あり、黒潮の流速が時速5㎞なら6日間かかる。食料は2日で尽きたが、気温が高く体力の消耗は少なかった。
漂流の2日目に雨が降った。2枚あった獣皮を広げ、水を貯めた。壊れた差し掛け小屋の木材をロープで縛って木枠をこしらえ、水の入った袋を吊るした。
3日目から2日間食料なしで空腹に耐えた。ときどきウミガメや大きな魚が近くに来たがモリがなくどうしようもなかった。だが、5日目にトビウオの大群が通り、筏の中に数十匹が飛び込んできたので、これを食べて空腹を満たすことができた。そして7日目の朝、八丈島に漂着した。
この時の黒潮は2016年1月9日の時と同じ形だった。
東日本大震災の10年後、大津波で流された人の体験記が新聞に掲載されていた。「被災の地 流されて(上)」(2021.2.18、朝日新聞)によると、いったん波にのまれ、水面に浮かんだあと、畳につかまって沖に流された。周りには屋根の上に乗って流されている人もいて、互いに「がんばれ」と声を掛け合った。体は傷だらけになり手の爪が一部はがれていた、という。
また、実体験に基づいて製作されたという2021.3.7.夜9時~NHK・TVドラマの「星影のワルツ」では、壊れた自分の家の屋根に乗って沖に流される。主人公は寒さ、のどの渇き、そして空腹に耐えながら、2日間で30km流された。
大勢の人がおぼれて、あるいはいったんは何かに乗って漂流したものの水も食べ物もなく、低体温症などで死亡していった中で、少数ながら運のよかった人、また基礎体力のあった人は助かったということを知る。そして、大津波にのまれても、おぼれずに何かにつかまってそれに乗ることで助かる人があるが、引き波に持っていかれ沖に流されるということを知る。
7300年ほど前、太平洋岸に住んでいて、大津波で家ごと海にさらわれた1500人の人々の中に、漁撈用の筏につかまるなどしてかろうじて助かった、運のよい人たちがいた。どれくらいの人が、おぼれてしまわず、助かったのかはわからない。だが、彼らは、その後、沖に流され、黒潮に運ばれ、漂流する。そしてこの漂流を生き延びることができた人が八丈島に上陸して湯浜人となったと考えられるのだ。
居住地を変えようと沿岸を移動中、誤って流された
津波とは別の何らかの理由、食料にする周囲の植物や動物あるいは魚がとれなくなった、あるいは近くの他集団との関係が悪化したなどのことから、家族ぐるみで別の場所に移ろうとする何人かの人たちがいて、筏などで岬を回ろうとしたが、筏の操縦がうまくいかず沖に流されたという事故が、年に1、2回、したがって100年の間に100件から200件の漂流事故が起こって、太平洋に流されたと考えることは無理だろうか。
積んでいた道具類は、漂流中にシケに会い、黒曜石1個と獣皮(あるいは獣皮に包んで筏に縛り付けて置いた黒曜石)を除いて、全部流されてしまった。人が筏から落ちないようにするのが精いっぱいだった。
8人の子供はひもで体を縛り付けていて無事だったが、大人は一人しか残らなかった。しかも、彼は筏がぶつかった拍子に骨折などの大けがを負った。
こうして、①と同じように、八丈島に漂着したときには、黒曜石と獣皮しかなかった。
このケースでは、生活用具だけでなく、水や食料を積んでいたはずで、漂流に耐えることが比較的容易だっただろう。しかし、漂流の後半にシケに会い、上陸時にはほぼ無一物になっていた。
同じように筏の操縦ミスで沖に流されたケースの大部分はどこの島にも到着できず、海の藻屑と消えてしまったかもしれない。 だが、100年間に100回から200回起ったであろうこうした漂流事故で、一度も八丈島に漂着するとことはなかったと考えることは、江戸時代の漂流事件の例などに照らしてみて、むしろ、過小評価になるのではなかろうか。
最後に、火山噴火による避難で海に逃れたというケースはどうだろうか。気象庁の調べによると
本州中部より以西の火山は開聞岳、薩摩硫黄島、口永良部島、口之島、中之島、諏訪之瀬島、及び沖縄の硫黄鳥島の7つあり、そのうち5つは7300年前以前の500年間に噴火が起こった可能性がある。
しかし、神津島産の黒曜石をこの時期にこれらの島々の島民が持っていたとは考えられない。というのも、小田静夫「黒曜石研究の動向」<「小田静夫の公式ホームページ」《黒潮圏の考古学》(2019)によれば、
栫ノ原(かこいのはら)遺跡、ヘゴノハラ遺跡など九州南部の縄文時代草創期、あるいは早期出土の黒曜石は、いずれも、九州の山地からのものであることが分かっており、また、奄美・沖縄地方で出土する小型軽量剥片石器には貝殻が使われていて、黒曜石製はわずかで、理化学的分析がなされたものは 伊万里市の腰岳産であったとされている。
したがってトカラ列島の島々、沖縄の硫黄鳥島などの住民が神津島産黒曜石を持っていたとは考えられず、火山噴火で漂流した人びとがあったとしても、八丈島に漂着して湯浜海岸に上陸したとは、考えられないからである。
第6節のまとめと第一章の結論
海部は、「3万年前」のホモサピエンスの琉球列島への渡島は南の島々から漁労中の事故などで流され、黒潮に乗って偶然に漂着した結果だという従来からある考えを否定している。その根拠の一つに台湾の海洋学研究者の行った漂流ブイの実験記録を調べた結果をあげている。台湾の南部から、黒潮に乗せてこれまで多数のブイを流したが、すべて、台湾と与那国島の間の海峡を通過して東シナ海に運ばれ、その後は、琉球列島から遠く離れたところを北上し、琉球列島に漂着したブイは一つもなかった、というのがその結果である。
単なる漂流によっては、台湾から琉球の島々には来ることはできない。したがって、台湾と琉球列島西端の与那国島との間を流れる黒潮を横断する必要があり、そのために、意図的・計画的な航海を行ったはずだ、と海部は主張し、航海実験によってそれを実証するというのが、彼のプロジェクトの目的だった。
だが、日本の本州の南を流れる黒潮は、上でくわしくみたように、四国沖から潮岬沖へと流れたあと、いくつかの複雑なパターンの流路をとって、房総半島沖へと流れていた。
そして、それらのパターンのうち、確かに、非大蛇行接岸流路と呼ばれる流れの時には、潮は、八丈島から遠く離れた伊豆諸島北部をまっすぐに通過する。この潮に乗ってしまった筏は八丈島に着くことはあり得ないだろう。
だが、潮岬付近からまっすぐ八丈島にぶつかるように流れる潮流のパターンがあった。
また、直接八丈島にぶつかることはないが、八丈島の西側を南下して八丈島の近くを通過することがある。 また同じく西側を北上して通過することがある。これらの潮の場合、適当な時間、西風が吹けば、筏は吹送流で島に漂着する可能性がある。
また八丈島の南を通ったのち、島の東側の近くを北上することがあり、その場合には東風が吹けば吹送流で筏が島に漂着する可能性がある。
これらのことを上の計算で、具体的に示した。
また江戸時代には大阪―江戸間の沿岸航路で帆船の遭難がたびたび起こり、操縦不能状態で漂流したが、そのうち200件のケースが八丈島に漂着していた。四国から東海の沖を流れる黒潮の働きによるところが大きいと考えられる。
湯浜人の八丈島への渡島は、上陸時の持ち物や上陸後の生活の様態から考えて、意図的・計画的な渡航によるものではなく、むしろ、何らかの事故によって生じた漂流の結果と考えられた。
そして、黒潮の流路から見る限り、計算によっても、また江戸時代の遭難船の実際の漂着件数からも、漂流の結果八丈島に到着するということは十分にありうることが分かった。
こうして、私は、湯浜人は、意図的・計画的に、本土中央部から北部伊豆諸島を伝って南下し「黒潮を横断して」八丈島に渡ったのではなく、東海地方以西から、偶然、沖に流され、「黒潮に乗って」漂流した結果、八丈島に漂着したのだ、と主張したい。
もし、彼らの八丈島への到着が、三宅島からの計画的・意図的航海によるものだったと考えるなら、湯浜人が上陸時にほとんど無一物であったこと、彼らが上陸後に作った土器や石器が様式を持たない、粗末なものでしかなく、黒曜石を持っていたにも関わらず、鏃が作られず、狩猟が行われた形跡がなかったことなど、生活のしかたについて、上で私がおこなったのとは別の説明がされなければならない。しかしそうした説明は行われていないように思われる。
岐阜、愛知、三重の旧石器時代~縄文期遺跡の石器石材
「全国遺跡報告総覧」<奈良文化財研究所>→「遺跡(抄録)検索」のページで、「遺跡所在地」から「県名」、「遺跡種別」から「集落」(「散布地」という項目もあるが気が付かずチェックを入れなかった)、「主な時代」に「旧石器」と「縄文」にチェックを入れて「検索」。 表示される遺跡のうち、PDF版の調査報告書があるものをダウンロードして読んだ。ただし網羅してはいない。 以下はその抜き書き。岐阜県
G1 岡前遺跡 集岐阜県文化財保護センター調査報告書第20 1995, 吉城郡古川町(現飛騨市)岐阜県北部、高山市の北
縄文中期の遺物が中心だが早期のものもあり草創期末もわずかに含まれている。
出土石器総数は102点である。石材は、下呂石57点(55.9%)、チャート31点(30.4%)、黒曜石13点(12.7%)、その他1点(1.0%)である。石材の組成は、飛騨地方の他の遺跡と比較して、下呂石の比率が低く、チャートの割合が高い点が注目される、という。
分水嶺をはさんだ荒城神社遺跡では下呂石が74.5%、チャートが12.6%であり、また、当遺跡より北に位置する吉城郡河合村下田遺跡では、下呂石が69.0%となっている。
門前遺跡の近くにチャートの山地があるのではないかと推測。
G2 荒城(あらき)神社遺跡 調査報告書第16集、平成6年、1994
吉城郡国府町 縄文後期が主で中期も。
石鏃、372点、下呂石277,チャート47,黒曜石26、石核が43点、下呂石が24、チャートが8点、黒曜石が2点など。
石材別では、下呂石3,488点(44.9%)、玉髄2,485点(32.0%)、チャート1,599点(20.6%)、黒曜石195点(2.5%)。
黒曜石産地分析はない。
G3 ウバが平(ひら)遺跡 2010年、岐阜県文化財保護センター調査報告書 第112集 高山市上かみ切ぎり町
石材としては、剥片も入れて黒曜石が28点(石鏃が3点)、チャートが145,下呂石が1167(約8割)、黒曜石の産地分析はしていない
縄文早期の押型文系土器とともに石器も出土
G4「牛垣内遺跡」うしがいと遺跡、(大野郡丹生川町折敷地字牛垣内)、丹生川ダム水没地区(五味原遺跡群)第3集埋蔵文化財発掘調査報告書 1998 岐阜県文化財保護センター調査報告書 第44集
長野との県境に近い飛騨山地、丹生川ダム(高山市)地域
下呂市までは約50㎞
土器の種類から縄文早期から晩期
石鏃が333点、下呂石133点、チャート140点、黒曜石58点、頁岩2点など
石錐84点、下呂石39,チャート38,黒曜石6、凝灰岩1
削器が56点、下呂石9、チャート42,黒曜石4、凝灰岩1
掻器52点、下呂石9,チャート38,黒曜石4,頁岩1
両極に剥離痕のある石器23,下呂石11、チャート7,黒曜石5
使用痕のある剥片78、下呂石7,チャート47,黒曜石18、頁岩5など
石核12,下呂石3、黒曜石4,チャート4
包含層から出土した剥片類4976点、チャート2696,下呂石1514,黒曜石721など
包含層から出土した剥片類を別として、石器点数は554点、下呂石は171点、チャート278,黒曜石93,頁岩8である。黒曜石割合は16.8%
包含層から出土した剥片類4976点、チャート2696,下呂石1514,黒曜石721など、黒曜石割合は14.5%
黒曜石産地の分析は行っていない。
G5 カクシクレ遺跡 丹生川ダム水没地区(五味原遺跡群)第2集埋蔵文化財発掘調査報告書 、大野郡丹生川村折敷地字カクシクレ、下呂まで40㎞
A地点:石鏃23点(下呂石6.チャート9、黒曜石8)を含み86点の石器のうち、下呂石は30,チャートは26,黒曜石は26だった。
B地点、黒曜石の石鏃1点、
C地点 70数個の打製石斧(ほとんど凝灰岩)の他に、石鏃14点( 下呂石2、チャート6,黒曜石6)など。
黒曜石の産地分析はない。縄文中期以降の遺跡。
G6「岩井戸岩陰遺跡 」岐阜県のほぼ中央に位置する武芸川町、丘陵に固まれた武芸谷筋下流の町。 岐阜県文化財保護センター調査報告書第81集 、2003
第1期早期前半(押型文)、早期後半(条痕文)の土器に伴出 、10000~6000年前の石器、
石器はチャート製の河原石を素材とするものが大半であり石材は前を流れる武儀川で調達可能。また、半径10㎞以内の尾根を隔てた長良川 ・板取川流域で確保できる石材、安山岩・頁岩などが一定量出土している。
また 半径10㎞以外で採取された、少量ではあるが、サヌカイトや下呂石が出土している 。下呂石産地の湯が峰までは直線で50kmくらいか。下呂市金山(高山山本線「飛騨金山」)までは30㎞くらい。
サヌカイトはどこから採取したのだろうか。少量の石を採取するために二上山まで出かけたとは考えにくいので、他の集団から譲ってもらったのか。
G7「はいづめ遺跡」徳山ダム水没地区 埋蔵文化財調査報告書
岐阜県揖斐郡藤橋村大字戸入、平成元年3月(1988?)
縄文時代早期~晩期の遺跡 岐阜県西部。福井との県境。
石鏃17点チャート、9点砂岩、---黒曜石1点
G8寺屋敷遺跡・磯谷口遺跡 調査報告書35集
両地区は徳山ダム水没地区 揖斐郡揖斐川町
寺屋敷遺跡からは縄文、旧石器時代の遺構が出土 、磯谷口遺跡からは縄文の遺物が出土
寺屋敷遺跡から出土した縄文時代の石器のうち、石鏃9点は、7個がチャート、他は石灰岩と砂岩、錐は4点ともチャート、だった
G9「戸入村平遺跡」とにゅうむらだいら、揖斐郡揖斐川町
石器は全部で1万点以上が出土している。石鏃 は349点出土した。石材は、サヌカイト 23点、下呂石14点、チャート 312点で、徳山地域で手に入りやすいチャートが断然多いが、サヌカイト、下呂石、黒曜石などの搬入された石材のものも小量ながら存在する。
石錐は139点、石材はチャートが 133点、サヌカイトが 5点、下呂石が 1点である。
藁科による「岐阜県揖斐郡藤橋村徳山地区遺跡出土のサヌカイト、黒曜石遺物の原産地推定結果」では11点の黒曜石のうち、信州産9点(霧ケ峰が8点、和田峠は1点)神津島産が1点、伊豆柏峠産が1点だった。サヌカイトは25点、判別不可を除き、ほとんどが二上山産、2点が金山産。
G10「小関御祭田遺跡」、縄文中期、1997,
不破郡関ケ原町(岐阜県南東部、滋賀県との県境)
昭和54、1979年の(前回)調査では、石器は225点、チャート89%、サヌカイト6.1%、黒曜石1.7%、下呂石0.7%
今回は、石器総数175点、石鏃18点、---などで、石材は、主にチャート144点、82.2%、砂岩13点、7.4%、石英1点、そのほかにサヌカイト5点、黒曜石3点(1.7%)これは藁科氏によると霧ケ峰産だった
G11 船山北遺跡、報告集52 各務原市須衛 岐阜県南部、愛知との県境
後期旧石器時代のナイフ形石器1点、チャート製。
G12 野笹遺跡Ⅰ調査報告書第66集、2000年
美濃加茂市は木曽川、飛騨川が合流する、開けた盆地、愛知県に接する
縄文時代中期以降の遺跡
「使用石材は、下呂石229点(76.4%)、サヌカイト11点(3.6%)、黒曜石1点(0.3%)、チャート50点(16.7%)安山岩9点(3.0%)で、下呂石が圧倒的に多い。下呂石の内、表皮がほとんど風化していないきれいな石材を使用しているもの(下呂石黒)が58点で、下呂石のだいたい4分のlの割合を占める。」
第5章7節の藁科による「野笹遺跡出土サヌカイト製遺物、下呂石製遺物および黒曜石製遺物の原材産地分析 」が参考になる。
愛知県
A1愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第213 集、川向東貝津(かわむきひがしかいつ)遺跡。
愛知県の北東部に位置し、長野県と境を接する北設楽郡設楽町。平成22年度に調査された時点では縄文時代後期の埋甕が見つかったのみだったが、
平成27年度の調査で縄文時代中期の竪穴建物跡が確認され、さらにその下層で後期旧石器時代から縄文時代草創期の膨大な石器群が出土した。一躍、石器研究者の注目を浴びる遺跡となった。
後期旧石器時代細石器文化期の石器、細石器文化として分類できる遺物が130点あり、「ガラス質で良質な石材」下呂石?、チャート、溶結凝灰岩、安山岩などの石材に交じり、黒曜石も2点あった。
後期旧石器時代として分類できた石器は 45 点である。安山岩が多く片麻岩も混じるが黒曜石はない。 縄文時代草創期として分類できた石器は113点、溶結凝灰岩が多い。
縄文時代石鏃が21点。〔他の器種についての点数は省略する。〕
石鏃の石材は、下呂石、黒曜石、安山岩、溶結凝灰岩。石錐2点は黒曜石、削器4点はチャート安山岩、楔形石器は溶結凝灰岩、黒曜石など。
〔多数の石器、石材の説明があるが省略〕
出土した黒曜石82点は、蛍光X線分析により、原産地の推定が行われている。それによると、ほとんどは長野県産であった。長野県には4か所の産地があるというが、そのうちの和田峠系2の産である。北設楽郡からは直線距離でほぼ120kmである。神津島産が3個あった。
また、川向東貝津遺跡を中心に5㎞四方の地域に100か所を越える遺跡があり、設楽町に隣接する豊根村域には、茶臼山遺跡の所在が知られている。茶臼山遺跡は、昭和 36・38(1961・1963)年に組織的に発掘調査された、愛知県を代表する後期旧石器時代遺跡である。
高見俊樹「茶臼山遺跡」(Communications of thePalaeo Perspective 旧石器時代研究への視座 Vol.2、2020) によると、
「関東地方〔の岩宿遺跡〕以外で初めて発掘調査され、日本列島における旧石器時代の存在を確固たるものにした重要な遺跡 」で、「大量の出土遺物の多くは、黒曜石製の剥片である 」とされている。しかし産地の分析は行われていないようだ。
川向東貝津遺跡出土の石器と同様、茶臼山遺跡出土の黒曜石の多くは信州産かもしれない.そして、いくつか神津島産も混じっている可能性がある。
決して楽な旅ではなかっただろうが、使用されている黒曜石の量も多く、和田峠周辺の黒曜石は、この地域に住んでいた人々が自ら採集に出掛けた可能性が高いと思われる。
この設楽町や豊根村地域にある多くの遺跡に住んでいた人々は、恐らく何人かの「黒曜石採集隊」のようなものを結成して信州産黒曜石の採集に出掛けたのではないだろうか。
しかし神津島産黒曜石で作られた石器の数はわずかで、この地域の人々自身が神津島に行って採集したとは考えられない。おそらく他の人々から分けてもらったと思われる。
和田峠周辺には、箱根伊豆方面、愛鷹山周辺の人々が信州産の黒曜石の採集に出掛けていたことが分かっており(→稲田を見よ)、川向東貝津遺跡の人々は長野の黒曜石産地で、伊豆方面から来ていた人々と知り合いになり、彼らから神津島産黒曜石を分けてもらった可能性がある。伊豆方面からきていた人々は、信州産の石を採集するだけでなく、ほかの集団との交易を予想し、神津島産黒曜石を用意して信州に出掛けたのだろう。
愛知県埋蔵文化財センター研究紀要 第20号2019. 川合 剛・平井義敏・堀木真美子・川添和暁「市場口遺跡出土石器群の研究 」によると、
川向東貝津遺跡の近くにある市場口遺跡も後期旧石器・縄文時代の遺跡であるが、34点の石器が確認されており、2点はチャート、1点は根羽石でその3点を除いた31点が黒曜石製である。分析の結果31点すべてが和田峠系―2と推定された。
愛知県埋蔵文化財センター研究紀要 第17号2016.5 川添和暁 「縄文時代後晩期における ?片石器石材について 」 によると
下呂石は産地湯が峰に近い瀬戸市上品野遺跡などで後期旧石器時代以来から使用されてきた。
また黒 曜石は、瀬戸市上品野遺跡・岡崎市西牧野遺跡・設楽町半場口遺跡・豊川市駒場遺跡などの(遺跡で)、後期旧石器時代以降、----弥生時代に至るまで、継続して使用された石器石材である、という。
蛍光X線分析で確認された範囲では、すべて 星ケ塔(信州)産だ、という。
サヌカイトの利用は、下呂石とともに、東海地域でもかなり比率が高い。原産地としては二上山産が多いようであるが、金山産〔どこの〕もある程度流通している。後期旧石器時代初頭の上品野遺跡や縄文時代早期の瀬戸市八王子でもサヌカイトの利用が認められる。
A2上品野遺跡、愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第132集 、設楽郡
後期旧石器時代の11点の黒曜石製石器は、10点は諏訪・星ケ台、1点は和田・高松沢群域、また 10点のサヌカイト製石器については、二上山および春日山〔二上山の北西側枚方市〕と判定
A3西地・東地遺跡 報告書 211、2019年 設楽町、
縄文時代早期前半以降、繰り返し人が活動した、安定した集落のあった場所。
石鏃など50点他、剥片、礫を入れて2500点ほど出土。石材は、石鏃の2点が黒曜石、3点はチャート、下呂石、サヌカイト、
石錐26点のうち、黒曜石が21点、使用痕のある剥片35点のうち黒曜石が28点、等。
215個の石器、剥片等のⅩ線分析結果は、すべて信州・和田峠系であった。和田峠-1系統が14個、和田峠-2系統が199個
A4上の平遺跡 報告書 41、1992、設楽郡
18点の石鏃、その44%は黒曜石、 黒曜石の産地分析はない。
A5石座(いわくら)神社遺跡 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第189集 ,第一分冊、本文編
愛知県南東部で静岡県に接する新城(しんしろ)市、後期旧石器時代から縄文時代早期に属する遺物が多数出土している。
縄文時代の石器としては石鏃は 38点出土。石材は安山岩12点、熔結凝灰岩12点、黒曜石5点、凝灰岩3点、下呂石3点、チャート3点である。
石錐は 5点出土し 石材は熔結凝灰岩、黒曜石、安山岩である。
スクレイパーが58点、石材は熔結凝灰岩28点、凝灰岩21点、黒曜石3点、安山岩3点、下呂石1点・チャート1点、凝灰質砂岩1点である、等々の詳しい報告があり、
61点の黒曜石について、エネルギー分散型蛍光X線分析装置による 分析結果としては
最も多く検出されたのは和田峠系―2(和田村男女倉または同村星ケ塔) で、61 個のうち 36 個が該当する。弱被熱・和田峠系―2は 18 個、強被熱・和田峠系―2が2個である。神津島?が3個、月山系?2個である。3)神津島と月山系については?マークを付けてある。これらは被熱して領域が幾分ずれることによるものである。 また、伊豆・箱根系のものはなかった。
A6モリ下遺跡 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第196集、2015 、新城市
後期旧石器時代から縄文時代までに属するものは28器種516点、古代から近世に属するものが 2 器種 28 点である。
石鏃6点出土、2点は黒曜石、ほかの石器類は、安山岩、チャート、サヌカイトでエネルギー分散型蛍光X線分析装置による黒曜石分析で、石核と剥片も合わせてあわせて8点は何れも和田峠系-2と推定された。
A7 石岸(いしぎし)遺跡 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第195集 、新城市
剥片石核類で剥片720点、石核32点、二次加工のある剥片81点の計33点を確認。石材は安山岩746点、黒曜石8点、溶解凝結岩2点、下呂石1、チャート1、泥岩1、など
ネルギー分散型蛍光X線分析装置 による黒曜石産地の分析、石核と剥片ああせて8点はいずれも和田峠系と分かった。
A8西牧野(にしまきの)遺 跡 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第174集 、岡崎市
出土した黒曜石遺物 322 個を分析した結果、
222 個が和田峠系2(星ヶ塔・男女倉)で、風化した和田峠系2?と合わせて全体の約 75%に当たる。次いで、和田峠系1(西餅屋・東餅屋・小深沢)が 27 個あり、和田峠系1の風化したものも合わせると、全体の約 13%に当たる。全体の 88%がこの 2つの原産地に特定され、他の原産地のものはない。
A9車塚遺跡、岡崎市岩津町、報告書190
黒曜石製ナイフ型石器、石鏃:使用石材はチャートが多く、熔結凝灰岩・サヌカイト ? ・黒曜石・下呂石・安山岩も認められる。
黒曜石の産地分析は行っていない。
A10坂口遺跡、報告書46集、1993 豊田市保見町、伊保川が流れる谷間、伊勢湾まで30㎞
「根川古墳」(遺跡番号63075)・「伊保遺跡」(遺跡番号63074)・「坂口遺跡」(遺跡番号69022)
坂口遺跡からは打製石斧、磨製石斧、スクレーパー、石錐、石錘、石匙、石刀などがみられた。 石質については、ガラス質石英安山岩、安山岩、黒曜石、チャート、片岩、結晶片岩、塩基性凝灰岩、溶結凝灰岩、流紋岩質溶結凝灰岩、変成岩など。
24点の石鏃、うち2点が黒曜石。黒曜石産地の分析はない。
A11水汲遺跡、長田友也編「水汲遺跡」(豊田市教育委員会、2011)
水汲遺跡出土縄文土器 - 縄文時代前期~後期、豊田市郷土資料館所有。Wikipedia「豊田市」>考古資料>市指定有形文化財
長田友也「水汲遺跡の位置づけ」、
石材の分類では(永田23俵)黒曜石205、安山岩1391,下呂石268,サヌカイト4、チャート1201、片麻岩34、溶結凝灰岩360,その他で、計3516
黒曜石202点分析のうち、星が塔192,小深沢6,神津島3、不明1だった 星が塔、小深沢は、星糞峠遺跡、男女倉、東餅屋などと同様、(長野県長和町と下諏訪町の間にある中山道の峠)和田峠の近くの黒曜石産地だが、星が塔、小深沢の地名は地理院地図にはのっていない。小深沢については
<資源環境と人類 第 5 号> 2015 年 3 月Natural Resource Environment and HumansNo. 5.中村 由克 「和田・鷹山地域の黒曜石河川礫の分布調査」の図2にある。
中村の論文は、複数の河川が合流し、異なる場所の同種の石材が流入していて、蛍光X線分析では区別できない場合、石器に使われている石材がどこの原産地かを推定するための方法として、流れた距離に応じて礫の形状と大きさが異なることを利用することが可能であることを示した研究である。
長田、水汲遺跡の石材利用について
遺跡周辺で得られる石材としては矢作川で採集可能なチャートが使われているが、近くの矢作川河床からだけでは集めることはできず、一部は豊川や木曽川など、他地域から搬入した可能性がある。溶結凝灰岩は豊川上流など、近隣から搬入された。
黒曜石について、星が塔遺跡で多くの発掘遺跡が見つかっていること、そして「多くは関東地方に流入した」という。下呂石の使用量が多くない点について、チャート、溶結凝灰岩など近隣石材を積極的に利用し、下呂石自体の評価(利用しやすさ)とそれを入手するためのコストが合致していなかったものと考えられるとしている。
水汲み遺跡では矢作川河床ので得られる安山岩を用いて多くの石器製作が可能であるがやはり良質の刃器製作にはより珪質化の進んだチャート、黒曜石などの石材が適しており、黒曜石のような遠隔地石材をはじめとする石材が遺跡内にもたらされる必要があった。
下呂石より多くの溶結凝灰岩が利用されているがそれはこの石材を産する豊川上流部である三川山間部との交流の深さを示すと考えられる。
近接する矢作川河床の石材を目的に応じて多用しながらも、良質の石材については遠隔地に産する搬入礫をも用いるという、縄文時代一般の石材利用の在り方を示す。
第24表「愛知・岐阜・三重県における黒曜石分析遺跡一覧」
18の遺跡の、黒曜石分析数、計442のうち、霧ケ峰産は128、諏訪星ケ台44、星が塔198、西霧ケ峰15、和田峠4、神津島12、箱根鍛冶屋1、柏峠1,などだった。
黒曜石出土数が多かった遺跡は、岐阜県西が洞遺跡(早期~)16点、同上原遺跡第2(前期)17点、同第1・第3、20点、(これらは藤橋村)、野笹遺跡(中期~)60点、豊橋市洗島遺跡(前期~)26点
三重県では多気町新徳治遺跡、後期、1点、霧ケ峰;多気町上ノ垣外遺跡、早期、3点、西霧ケ峰;志摩市長尾遺跡(pdfファイル無し)期、34点、西霧ケ峰13点、神津島8点、星が塔3点、不可9
ここには三重県鈴山遺跡の発掘調査結果(2018年)は載っていない。
A番外1、八王子遺跡、瀬戸市豊田市の北、岐阜県との県境にある。
縄文時代早期~;剥片を除き、総数863点、石鏃が319点(約40%)など多数の石器を出土、多くはチャート(半分近く)、次いで下呂石、凝灰岩、石英だが、石鏃、スクレイパー、剥片に黒曜石も使われている。表4;第26図
エネルギー分散型X線分析装置による分析で、ほとんどは和田峠系ー2の男女倉5の原石と近い化学組成だった。
A番外2あり
三重県
M1「鈴山遺跡(第2・3次)発掘調査報告」三重郡菰野町、2018年 菰野町は四日市市の北西隣 縄文時代早期、中期の遺物を出土した。各遺構埋土の篩掛けにより、多量の剥片や砕片を検出した。
遺跡周辺で採取できる石材は花崗岩・流紋岩・砂岩・ホルンフェルス・閃緑岩である。一方、剥片石器(石鏃・石錐・削器等)は、サヌカイトや下呂石・黒曜石などという、他地域の石材を使用している。
石材の割合は、サヌカイトが大半を占め、次にチャート・下呂石・黒曜石の順に多い、としている。 黒曜石産地はエネルギー分散型蛍光X線分析装置による元素分析 で推定
石鏃1点の他16の薄片資料で、産地の判明した12点は、いずれも信州産であった。
分析結果末尾p119に長田友也「水汲遺跡の位置づけ」、長田友也編「水汲遺跡」(豊田市教育委員会、2011)への言及
M2「中野山遺跡」、四日市市北山町
遺物は押型文土器破片(縄文早期)、礫器、楔形石器(泥岩、砂岩)、敲石(砂岩)、石皿(流紋岩)などの早期の石器、
M3 「東庄内A遺跡(第2次)発掘調査報告 」 鈴鹿市(四日市市の南隣) 三重県埋蔵文化財調査報告301、2009
縄文時代早期の遺物は押型文土器のほか磨石、石皿があるが石 器はわずか。
M4「大鼻遺跡―本文編―」調査報告書100-5、「大鼻遺跡―本文編―」1994年
北勢(北伊勢)の亀山市(四日市市の南隣)にあり、鈴鹿川中流の河岸段丘にある。旧石器時代から室町時代まで及ぶ集落跡
草創期、早期の遺跡から出土した石器はチャート、サヌカイト製の石鏃、楔形石器などであった。黒曜石は出土せず。
http://kameyamarekihaku.jp/sisi/KoukoHP/dai1sho.html『亀山市史 考古編』によると
土器は草創期末の系統をひくと思われる表裏縄文土器、早期の押方文土器、が出土。石器は、尖頭器および石鏃はほとんどがサヌカイト、石錐、スクレイパーはチャート、楔型石器はサヌカイトとチャート、磨製石斧は砂岩とホルンフェルス、など
M5大古曽遺跡・山籠遺跡・宮ノ前遺跡発掘調査報告 三重県埋蔵文化財調査報告115-4 1995刊 三重県の県庁所在地である津市にある
大古曽遺跡(津市一身田)はテフラ、花粉などの分析で旧石器時代からの遺跡である。しかし出土した遺物は石器の破片などで器種などははっきりしてない。石材はチャートとサヌカイトという程度。
山籠遺跡〔弥生時代中期後葉〕(津市川邊町)からは石鏃が10点出土しているがすべてサヌカイト製
宮ノ前遺跡、津市長岡町「サヌカイト製の石鏃が4個、黒曜石の二次加工有剥片。ほかに黒曜石石核1点、「縄文時代に黒曜石の三重県下への搬入は、無いことはないが極めて珍しい。」
三重県埋蔵文化財調査報告 115-4 1995.3 「一般国道23号中勢道路建設事業に伴う 大古曽遺跡・山籠遺跡・宮ノ前遺跡 発掘調査報告」のp2にある
中勢バイパス建設計画の7.2㎞の工事区間内にある遺跡を示す図。大古曽遺跡は26番、山籠遺跡は31番、宮ノ前遺跡は34番
M6西出遺跡?井之広遺跡三重県埋蔵文化財調査報告92-4、1990
現在津市、 旧・安芸郡美里村
段階の異なる押型文土器が混在状態で出土しており、一括性のある遺構の認定が行なわれていない、という。
一方、そして、三重県HP「続・発見三重の歴史」第86話(2008/2/8)に「広域交流の証しが出土―縄文時代早期の津市・西出遺跡 」 と題する、三重県史編さんグループ 田中喜久雄の次のような文が載っている。----
M7山添遺跡(第4次) 松阪市 三重県調査報告書280、2007 松阪市山添町と安楽町にまたがる縄文時代前期の遺跡
300点を越す石鏃、ほとんどサヌカイトいくつかはチャート
その他の石器、石核も大部分はサヌカイト
石鏃ではサヌカイト使用が84%、チャートが14%、その他石材が1.8%(6点)
M8 鴻の木遺跡 (下層編) 松阪市明和町
大鼻式以前の押型文土器が多数出土、草創期末、
大川式=縄文時代早期の土器
石器出土総数1万点以上、尖頭器6、石鏃85--薄片・砕片9,300点ほど、
尖頭器はチャートとサヌカイト
石鏃凹基式54個のうち12個はチャート、1個は片岩、それ以外30個はサヌカイト、平基式10個のうち2個チャート、8個サヌカイト
一覧表をざっとみると大部分がサヌカイト製、そしてかなりチャート製がある。 サヌカイト産地の分析はない
M9粥見井尻遺跡 発掘調査報告1997年、三重県調査報告書156
三重県中央部飯南(いいなん)町、櫛田川中流の段丘上にある。松阪市は櫛田川河口にある。
無文土器とチャート製石器などが出土
「日本最古の土偶が出土」と話題になった(1996年)
炭化物の分析で、暦年較正年代は,およそ1万3,400年前で縄文草創期
剥片が1万1千点余、石器が183点出土。説明のある
石鏃54点のうち2点はサヌカイト、他はチャートであった。
サヌカイト産地分析はない。
M10内垣外(うちがいとう)遺跡発掘調査報告、 1997
三重県多気郡多気町相鹿瀬字内垣外に所在する。
総計479個のフレイク・石核?こぶし大の礫.砕片などが出土した。 数個のサヌカイトや頁岩製のもの以外、すべてチャート製である。
「環境」の説明として
現在の行政区画では多気町の南端にあたり、南は度会(わたらい)郡度会町・大宮町、東は同郡玉城町、西は多気郡大台町と近接している。地形的には、紀伊山地に源をもつ河川である宮川の中流域左岸に位置する。
宮川は、上流の山系は硬い砂岩と頁岩、チャートからなっており、それらは石器の石材として古くから流域で利用されてきた。ナイフ形石器や細石器などが数多く出土した東海地方屈指の旧石器時代の遺跡である大台町栃原の出張遺跡は、当遺跡の上流約3kmにある。
M11出張遺跡 日本旧石器学会HP>日本列島の旧石器時代遺跡 によると、
ナイフ形石器を主体とする後期旧石器時代後半期の石器群が大部分を占める。
ナイフ形石器200点は大部分がチャートで、表面が白色に風化した石材がそれに次ぐ。両者とも隣接する河川で採集されたものと考えられる。
M12縁通庵(えんつうあん)遺跡・アカリ遺跡 多気郡勢和村 三重県調査報告書171、1999
両遺跡は櫛田川中流域の河岸段丘上にある。
縁通庵遺跡は、縄文前期後半の土器類と、数百点の石器と剥片が出土。石器は石鏃17点、2点のみチャート、ほかはすべてサヌカイト製。ほかにサヌカイト製の石錐2点、砂岩製の磨製石斧1など。
アカリ遺跡
2個のチャート製ナイフ形石器、石鏃は16点あり、2点がチャート、1点が石英、他はサヌカイト、石錐など他数点もサヌカイト(産地分析なし)
M13 湯後遺跡」三重県調査報告書157、1997
多気郡宮川村 、縄文時代 宮川村は大台町、宮川の最上流にある。大台町は奈良県との県境の町 3点の石鏃、2点はチャート、1点はサヌカイト
湯後遺跡は出土数が少ないので除外して考えると、
三重県宮川周辺の遺跡から出土する石器は近くで手に入れられるチャート製がほとんどだった。
M14 「万所(まんじょ)遺跡」調査報告328、 2012年刊、伊勢市、辻久留3丁目
大台ケ原を源流とし、伊勢市の北東部の伊勢湾にそそぐ宮川の河口から約9㎞上流、標高約11m前後の河岸段丘上にある。
縄文早期の大鼻式土器などとともに、6点のチャート製石器と石核、10数点のチャート剥片、3、4点の砂岩、泥岩の石器、剥片、2点のサヌカイト剥片が出土している。
M15 中尾遺跡、鳥羽市岩倉町に位置する。縄文時代の遺跡で、サヌカイト石鏃・石錐が出土している。
長田「水汲み遺跡の位置付け」第24表「愛知・岐阜・三重県における黒曜石分布一覧表」によると 多気郡多気町の新徳寺遺跡、多気郡度会町の上ノ垣外(うえのがいと)遺跡、長尾遺跡、 これらは「報告書」あり。 新徳寺:石器は総計1,619点
石鏃55点、打製石斧 l点、台石3点、石皿17点、敲石34点、磨石24点、打欠き石錘80点、切目石錘83点、同未成品l点、石錘素材4点、磨製石斧4点、石匙 1点、削器16点、石錐 10点、楔形石器 4点、礫器 5点、二次加工有る剥片 3点、使用痕有る剥片 2点、剥片・砕片 1,269点、石核 4点である。
石鏃は 5点のチャート製品を除いて、サヌカイト製である。白色チャートを用いた第 79図 1118は 削器は、サヌカイト製が13点と多く、チャート製は 3点のみである。
石材全般では、下呂石が 1点もみられない。
黒曜石石材については書かれていない。文献として、田村陽一2010参照となっている。
上ノ垣外(うえのがいとう)遺跡、三重県度会郡度会町(縄文早期)からは同じく西霧ケ峰産黒曜石製石鏃が1点、判定不可2点、
志摩市長尾遺跡(縄文時代前期)からは石鏃掻器(スクレイパー)などが34点、うち霧ケ峰産13点、神津島産8点
カリコ遺跡、三重県度会郡玉城町世古地内、1995年10月~12月の調査で旧石器時代の遺跡、「カリコ遺跡発掘調査報告」書がある(奈良文化財研究所、全国遺跡報告総覧)が、webでは閲覧ができない。しかし、竹岡俊樹『旧石器時代人の歴史』p159によれば、チャートを用いた切出し形石器、サヌカイトを用いた一側縁加工のナイフ型石器などがみられ、「石材や石器の組成は南関東地方の類国府系文化の石器群に似ている。この地域では東日本地方に分布している有樋尖頭器が採取されており、長野県や関東地方の類国府系文化をもつヒトビトが、時を経て西日本地方に会えって来た可能性を示している」という。
三重県埋蔵文化財調査報告87-14、近畿自動車道(久居~勢和)、埋蔵文化財発掘調査報告,第3分冊 8 堀之内遺跡 C地区、1991・3 の
Ⅱ.5
「近畿自動車道に伴う発掘遺跡出士の黒曜石、およびサヌカイト製遺物の石材産地分析」 藁科哲男・東村武信 p31、第8表
黒曜石
上ノ広遺跡、松阪市広瀬町、時期不明、判定不明、フレイク、
焼野遺跡、一志郡嬉野町、縄文後期初頭、霧ケ峰、 〃
天保遺跡、 〃 、縄文晩期末葉、 〃、 〃
ほかに1点石鏃は下呂石、
堀ノ内遺跡、 〃 、縄文中期 、 〃、 〃
蛇亀遺跡、 〃 、 ? 、フレイク×12、和田峠1、ほかは霧ケ峰、石鏃1、霧ケ峰
サヌカイトの剥片が24点、山崎遺跡(多気郡多気町)、横尾遺跡(松阪市岡山町)、堀ノ内遺跡(17点)、ビハノ谷遺跡(縄文中期、5点)、から出土
他に、蛇亀遺跡からは下呂石剥片が2点、
三重県埋蔵文化財調査報告87-1、近畿自動車道(久居~勢和)、埋蔵文化財発掘調査報告,第1分冊 1 堀之内遺跡 C地区、1991・3 〔10の遺跡の報告〕
上ノ広遺跡からは
押し型文土器などとともに、尖頭器チャート製5点サヌカイト3点などチャートも多用されている。891点に上る、石器、剥片は、サヌカイトとチャートが半々くらい。その他には頁岩,凝灰岩なども、数点混じる
→5-1表~5-23表
三重県埋蔵文化財調査報告 264 2005 「戸井口遺跡・スブクリ遺跡(1次・2次)発掘調査報告」
「第1表 遺跡一覧」p5によると上ノ広遺跡の時代は「先土器・縄文・平安」となっている
三重県埋蔵文化財調査報告87-1、第一分冊 1
近畿自動車道(久居~勢和)周辺の遺跡について
この報告書にある10の遺跡は櫛田川中流域の中から低河岸段丘面にある。p10
櫛田川は、行政的には最上流に飯南郡飯高町から下流の松阪市まで1市4町1艘が流域に含まれる。
歴史環境として p13
先土器時代終末期から縄文時代初頭になると櫛田川中流域でも宮川中流域におとらず遺跡数は増加。有茎尖頭器、木葉型尖頭器が」代表的。神子柴型石斧も同時期。押し型文土器とともに出土。これらは宮川中流域では出張遺跡を中心にする地域。----
「歴史的環境」第3-1表 周辺遺跡一覧表1 p15には先土器時代から弥生中期までの100か所の周辺の遺跡が掲げられ、そのうち先土器時代遺跡が10か所、先土器末から縄文早期ごろまでの遺跡が23か所ある。
3-2表には弥生時代以降の100か所が掲げられている。この地域に上ノ広遺跡もある。
花の木(山崎)遺跡、多気郡多気町、早期~晩期の土器が出土、微量だが、少量の石鏃 櫛田川の中流 浅間山(せんげん山)遺跡花ノ木遺跡の南隣 微量、弥生時代
釈尊寺遺跡、同じ地区にある。弥生土器など
三重県埋蔵文化財調査報告94-2、平成2年度農業基盤整備事業地域 埋蔵文化財発掘調査報告 第2分冊では 北野遺跡、簔村大塚遺跡、中里遺跡、打田遺跡、伊勢寺遺跡の報告
長田友也(2011)水汲遺跡の位置づけ.長田友也編「水汲遺跡」:249-252,豊田市教育委員会. 豊田市北西部、矢作川河畔の遺跡
長田は「水汲み遺跡の主体的な時期(最も栄えた?)である縄文前期後半に焦点を当てて石器系列ごとに石材利用の在り方を概観」
押圧剥離(尖頭器、石鏃、石錐など)2694点、直接打撃(惰性石斧など)37,---合計3,516
剥片も入れて、下呂石製が268、安山岩製が1,391、サヌカイトが4,チャートが約1,201、溶結凝灰岩が360、黒曜石が206,
「押圧剥離系では黒曜石、下呂石、サヌカイト、チャート、溶結凝灰岩などを用いる。このうち遺跡周辺で得られる石材、すなわち矢作川河床で採集可能な石材として、チャートが上げられる。
矢作川上流----に供給源があるが、当遺跡で利用するチャートのすべてをもとめるのは無理。一部は豊川裕域や木曽川本流域〔豊田から西へ100㎞〕など他地域からの搬入石材である可能性もある。次いで豊川水系(南西へ90㎞)に産する溶結凝灰岩がある。」
黒曜石202点の産地分析で、192点(95%)が長野県、星が塔峠産、星が塔峠産の黒曜石の多くは関東地方へ流入した。
東海地方の黒曜石利用は関東に比べて「僅少」。18遺跡について産地分析がなされていて、第24表で、 分析された黒曜石点数の多いものは
水汲遺跡が205点;次が野笹遺跡=美濃加茂市が60点(藁科、55点が霧ヶ峰、不可が5);長尾遺跡=志摩市が34点(田村、西霧ケ峰13,神津島恩馳島が8、星が塔が3、不可9)、洗島遺跡=豊橋市 が26点(岩瀬他、縄文前・中期、18点が諏訪星ケ台、4点が神津島);20点が上原遺跡第1、第3=揖斐郡藤橋村(藁科、すべて霧ケ峰);17点が上原第2(藁科、すべて霧ケ峰);16点が西が洞遺跡=岐阜県白鳥町(霧ケ峰13、和田峠1群2)など
【追加】ヤポネシア及び日本人の源流について
ヤポネシアについて斎藤は『日本列島人の歴史』では、「政治の中心地」で時代をくぎる新しい時代区分を提唱。時代を現在から逆にさかのぼり、「江戸東京時代」(現在から1,600年頃まで)、「平安京時代」(1,600年頃から800年頃まで)、「ヤマト時代」(800年頃から200年頃まで)、「ハカタ時代」(200年頃から前3,000年頃まで)、そして「ヤポネシア時代」(前3,000年から前40,000年頃まで)の5つの時代に区分する。
「日本列島人の歴史」とは日本列島に確実に人間がいたと考えられる4万年間の歴史で、時代区分は「政治の中心地」で区切るとされているが、普通の日本史で行なわれているような、政治的有力者ないしは政権が存在した場所、都の所在地の変遷で区切るのではない。
この区切り方で、「ヤポネシア時代」と呼ぶ、農耕開始以前、採集狩猟だけが行われていた時代、おおまか3千年前より古い時代、考古学で言う弥生時代以前、政治の中心が存在しなかった長い時期が、日本列島人の歴史において占める重要性を強調している。
ヤポネシアという語は、沖縄の日本復帰以前の1960年代に、作家の島尾敏雄によっ造語された。島尾は戦後、奄美大島に長く住み、その経験をもとに日本列島の多様性を強調するために、日本、および島々を意味する外来語、ヤポンとネシアを用いて造語した。
斎藤は、「本書ではアイヌ人、ヤマト人、オキナワ人という三グループがむかしから住んできた範囲を日本列島ととらえ、同じ範囲を表すために「ヤポネシア」をつかうことがあります。」また、「本書では、国名がまだ存在しておらず、この列島が島の群れとしてのみ認識されていた時代にふれる叙述を中心にして、居住域としての島の群れを客観的に表したい場合に「ヤポネシア」を用いました」と、やや控えめに「ヤポネシア」の語を用いたとしている。
他方、 日本列島ないしヤポネシア南部に存在した琉球王国は、江戸東京時代には、列島中央部の政権により支配され、その後も中央部のヤマト人によるオキナワ人への差別・抑圧が続いたと指摘されている。〔1972年の「返還」後も続く沖縄への米軍基地の集中などは、本書では触れられていないが、同じ種類の問題である。〕
16世紀末には日本列島北部にはアイヌ人たちの社会が根付いていたが、ヤマト人との軋轢が次第に増し、17世紀以降、徳川幕府の下でアイヌ人が圧迫・支配をうけたことが指摘されている。
斎藤の「ヤポネシア」という捉え方には、日本列島は、単に、三つの異なる集団がもともと住んでいた地域であるというだけではなく、こうした列島中央部の集団による、南部及び北部の集団に対する差別、支配、抑圧の歴史に対する批判的な視点が含まれている。
 日本人の源流と「二重構造」説
日本人の源流と「二重構造」説では、もともとヒトの存在しなかった日本列島/ヤポネシアにどんなところからどんなヒトビトがやってきて、オキナワ人、ヤマト人、アイヌ人になり、そしてその子孫である現在の日本人になったのか。
斎藤によれば、1980年代までに、埴原和郎らにより定式化され、定説となっているのが「二重構造説」である。
旧石器時代の日本列島に移住して最初に住み着いたのは、東南アジアに住んでいた古いタイプの人々の子孫であり、彼らが縄文人を形成した。その後「ハカタ時代」(考古学で言う弥生時代にあたる、3,000年前頃からの約1,200年間)以降、北東アジアにもともと居住していた人々の一派が日本列島に渡来してきた。
このあたらしいタイプの人々は北部九州に始まって本州の日本海沿岸、近畿地方に移住を重ね、先住民である縄文人の子孫と混血を繰り返した。
しかし北海道にいた縄文人の子孫集団は、この渡来人との混血をほとんど経ず、やがてアイヌ人の集団につながっていった。沖縄を中心とする南西諸島の集団は、列島中央部から多くの移住があり、混血もあったが、列島中央部に比べると、縄文人の特徴をより強く残した。
こうして現代日本人の集団は、第一波の移住民の子孫である「土着縄文系」とハカタ時代以降の第二波移住民である「渡来弥生人」の二重構造を有している、というのが日本人の二重構造説である。
図はAnthropol. Sci. 人 類 誌,102(5),1994に掲載されている埴原の論文から引用したもので、非常にわかりやすい。なおこの論文は Hanihara, Kazuro (1991) Dual structure model for the population history of the Japanese. Japan Review, 2:1-33.1991 を著者自身が和訳したもの、という。
主に、歯や頭骨の形態学的な分析に基づいているが、尾本恵市などの遺伝学的研究ともよく整合しており、また、アイヌと沖縄の言語、世界観、信仰などの共通性、あるいは東日本と西日本で、土器の文様, 種 々の文化複合, 生 活形態 など文化現象ばかりでなく、身長, 頭顔 面 の形 態, 手掌紋 ABO式 な ど種 々の血液 型 , 血清 タンパ クや赤血球酵素の多型 などの身体 形質 に差があること、日本の東北部の犬が東南アジア系の遺伝子を持ち、南西部の犬が北アジア系の遺伝子をもつことなど、広範な事象が、「二重構造」つまり、東南アジアから移住してきた縄文人の住む日本列島に、弥生時代以降、北アジア系の人々が渡来してきたとすることで、よく説明できるという。
だが、この「縄文と弥生の二大要素の起源が問題として残る」。「弥生時代以降の渡来人は、考古学的・歴史学的な研究とも合致して、朝鮮半島や半島北部、あるいは山東(シャントン)半島などの地域に住んでいた人々の一派だと考えられる。
だが、旧石器時代から、縄文時代にかけてヤポネシアに渡来した人々の起源については、大陸のわずかな数の遺跡から発見された人骨の形態をもとに、東南アジアだろうとだけ言われており、遺伝学的データの解析からは、否定・肯定の両者が存在してきた、という。
この「縄文人はどこからやってきたのか」については、「第2章 国立科学博物館・海部陽介チーム「3万年前の航海徹底再現プロジェクト」は3万年前の航海を再現できたのか 」末尾の(注)を参照
(***)斎藤成也(なるや)に戻る