
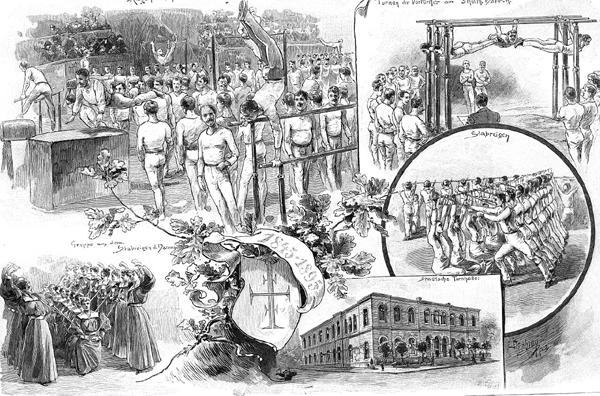
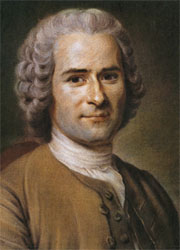
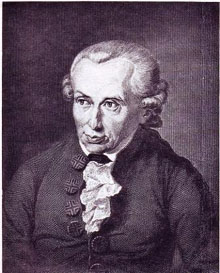

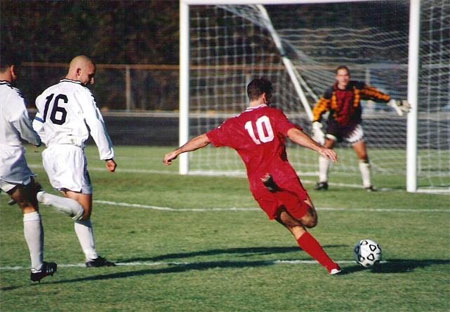


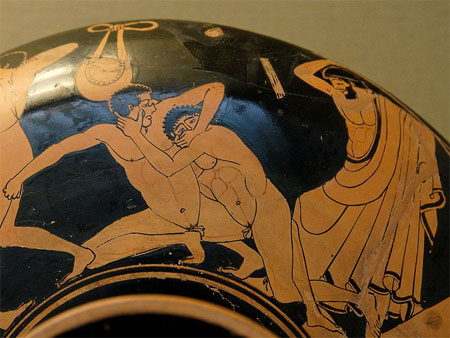
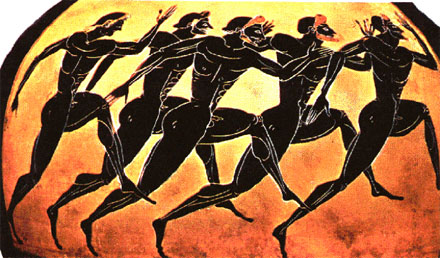

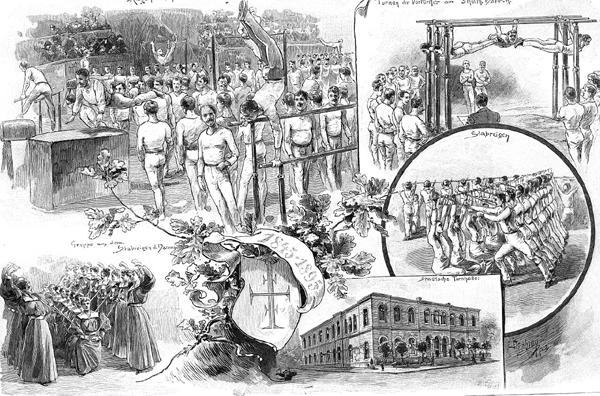
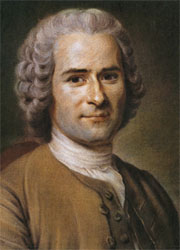
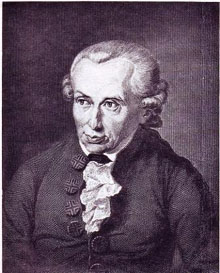

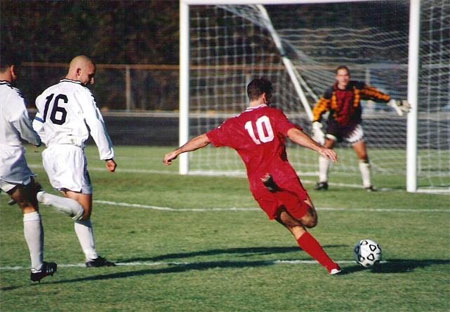


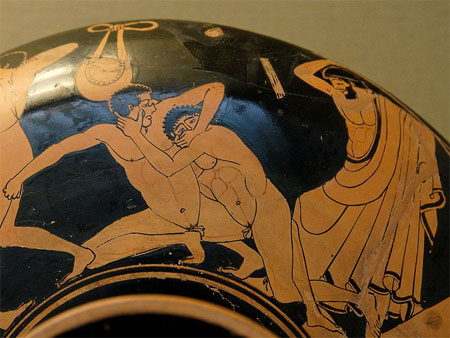
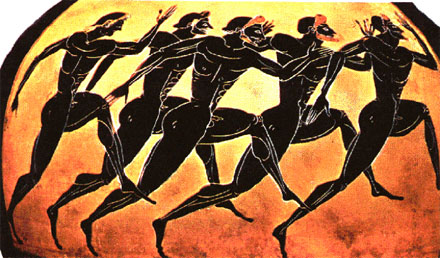



第一節 スポーツとは?
運動することの快楽。体を使う遊びがスポーツ?
釣りはスポーツではない?
スポーツの定義
スポーツと芸術の違い
イギリス型スポーツとドイツ型「体操」競技との違い、闘争型と自己鍛錬型
攻撃と防御は、体操の要素ではない
陸上競技は時間あるいは距離との戦いである
勝敗を競うよりも相互に讃え合うスポーツ
ゴルフはイギリス型のスポーツか
スポーツ事典の説明。スポーツとは
スポーツの「歴史性」について
スポーツの「遊戯性」について
プロ・スポーツにおける戦いの真剣さ
プロ野球ファン
プラトーンのイデア論とスポーツ概念
私の暫定的な意見、スポーツはいかなる活動か
第二節 スポーツの歴史、N.エリアス『スポーツと文明化』を読む
古代オリンピアの競技と暴力
英国中世のフットボール
「文明化」の過程
「文明化」は人間性の変化を意味しない
18世紀イギリスの議会主義化とスポーツの近代化
狩猟とは異なるスポーツとしての狐狩り
中間総括 近代スポーツの「スポーツ性」
釣りもまた体を動かすことにより生ずる「身体的快」をわれわれに与える。磯の上に立ち、竿を振り、リールを巻く。あるいは穏やかな波に揺られながら船の上から道糸を手繰る。身体的快がある。海に出たときに感じる「気持ちよさ」、爽快感は多くの要素から成り立っている。波に揺られたり、潮風が頬にあたることによって生ずる快の一部は、日頃の仕事から解放され、自然に包まれていることの意識によって生じる「精神的快」であろう。適度に体を動かし、運動するときに感じる「気持ちのよさ」も、「体を動かすことは健康にいい」、「スポーツはストレスの解消に役立つ」という現代の常識を背景に、自分が今体を動かしていることを意識することによっても生ずるだろう。だが、(船酔いをする人は別だが)体が揺れ動き、涼しい風が頬に当ることの快は、感覚によって直接的に感じる身体的な快であることも確かである。運動、スポーツにおける快は、一部は「こころ」あるいは「気持ち」で感じる快つまり精神における快であり、一部はまた直接、体に感じる快であると考えていいだろう。釣りには、じっと座って魚が来るのを待つという面もあるが、しかし囲碁や将棋、あるいは音楽を聴いたり小説を読んだりする楽しみとは違い、自然の中で体を使い体を動かすということがその魅力の大きな一部をなすということは確かだろう。
釣りは、体を使う遊びであるとすれば、スポーツだと考えられるかもしれない。 たとえば、永田一脩(カズナガ)『海釣り』(保育社、S41=1966年)という本では釣りをスポーツと見なしている1)。永田は『海釣り』の冒頭で、「釣りは健全な娯楽」で、「だからこそアメリカでもソ連でもあらゆるスポーツ、娯楽の最上位を占めている」と書き、スポーツと娯楽をひとまとめにして扱い、また釣りはスポーツの一種だということを当然のように前提した上で、「他のスポーツとはたいへんに違ったところがある」と言う。釣りと他のスポーツとの違いについては、第4章で、永田の説を紹介しつつ詳しく述べるが、私も、最初は彼と同じように、釣りはスポーツの一種だと考えた。
ところが、何種類かの「現代用語辞典」を読み比べ、また最近のものと30年ほど前のものとを比べてみても、釣りは「スポーツ」とみなされていないことが多い。釣りは「スポーツ」とは別の分野としての「レジャー・趣味」に分類されていたり、「観光・旅行、アウトドア、ホビー」のうちのアウトドアに分類されていたりする。大雑把に見れば、スポーツは、国体やオリンピックで行われている競技のような、そして多くはプロ化されている運動種目と同一視されている。だが、スポーツに関係する用語の説明はあるが、スポーツとは何かという定義も、スポーツとレジャー活動の区別の理由も、書かれていない。
身体運動性からすればスポーツと呼んでもかまわないと思われるのに、アウトドアとかレジャーとかと呼ばれ、スポーツとは呼ばれていない活動がかなりある。たとえば、ハンググライダー、ロッククライミング、ヴァンデルン(山歩き)、ジョギング、ウォーキング、海水浴、ダイビング、サーフィン、ウィンドサーフィン、カヌー、ヨット、などなど。これらはいずれも(ガイドやコンダクターを別として)職業化されていない身体運動である。職業にもなっている身体運動がスポーツで、職業化されていないものがレジャー活動なのだろうか。
野球、サッカー、テニスなど、現代スポーツの多くは「ゲーム」形式で行われ、勝ち負けを争うという意味で一種の戦いであるが、それは「単なるゲーム」であり、本当の「喧嘩」や「戦闘」ではないという理由で、スポーツは「遊び」だとも言われる。だが、また、一人で楽しむ遊び・ゲームと違って、「戦い」だからこそ、興行化され、プロ化される必然性があるとも思われる。誰もが競争や闘争を好むかどうかは別として、競争している様(さま)、戦っている様をみることは人を興奮させる。多くのスポーツは観客を集める力がある。プロ・スポーツの試合が面白いのは要するにハラハラ、ドキドキさせ、何かが起こる次の瞬間を見たいと感じさせるからであろう。ほとんどのスポーツは闘いであり、その展開が見る人を緊張させ、また興奮させる。ハラハラ、ドキドキさせる、遊びの戦いがスポーツなのだろうか。
だが、釣りでは、たまに行われる釣り具メーカーや渡船組合などによって主催される競技会や大会を除いて、他人と競争し、戦うことはない。そして釣りには運がつき物である。何時間も、あるいは一日中、釣れないこともある。基本的に釣りは「待ちのスポーツ」であり、したがって、緊張と興奮、スリルを求める人にとっては「退屈な娯楽」だということになろう。見るのはただであり、波止や防波堤で釣り人の姿が見えれば、散歩中の人は近寄って見物するであろうが、興奮したり声援を送るということはまずないだろう。 『広辞苑』では「遊戯・競争・肉体的鍛錬の要素を含む身体運動の総称」がスポーツだとされている。この説明が正しいかどうかが問題になるが、とりあえず、それに従えば、釣りは戦いではなく「競争性」に欠ける。「肉体的鍛錬」とまでは言いがたい。こういう次第で、釣りが身体を使う遊びでありスポーツに似ているにしても、やはり、スポーツとは言えないようにも思われる。
釣りは、山菜取り、家庭菜園、潮干狩り、磯遊び、狩猟、などと同様、収穫・獲物を得ることを目的にして行われる活動である。(アマの場合の)ゴルフやテニスあるいは野球やサッカーなど獲物を求めず「純粋な」楽しみを求めて行われるスポーツと比べれば、目的の有無という点で、釣りはスポーツと異なる。釣りは食料を獲得する活動、漁労から生まれたのであろう。だが、ゴルフやテニスあるいは野球やサッカーは生活のための活動から生まれたものではあり得ない。後に見るように、カイヨワは『遊びと人間』で、「遊びは純粋な消費だ」と言っている。スポーツは遊びとして誕生した。そして現代では多くのスポーツが商業化、プロ化されている。
こうして、はじめは釣りがスポーツかどうかが問題であるように思われたが、そもそも、スポーツが何であるのかも問題になる。ポーツとは何であるのかをもっと明確にする必要がある。そこで、遅まきながらスポーツに関する本をいくつか読んでみたのだが、そうするうちに、スポーツが、それまで自分が考えていたものと全く異なる、きわめて興味深い人間の活動の一つであることに気がついた。釣りがどんな遊びであるのかを語る前に、スポーツについて考えてみることにした。私は大学・大学院で倫理学を専攻し、大学の教師としては倫理学・哲学に関連した分野の科目を担当してきた。しかし、私は倫理とは意識の問題であると考えてきたために、たとえば、デカルトの心身二元論を考えたり、あるいは生命倫理の研究の中で臓器移植の問題を考えたりしたときなどを除き、身体そのものも、心身の関係も重要な研究対象と考えたことはほとんどなかった。また、運動やスポーツは個人的な好みの問題に過ぎないと考えていた。
釣りは、学生時代あるいは短いサラリーマン時代に少々やったマージャンやパチンコと同様の娯楽であり、学問や芸術のような「れっきとした」文化ではなく、また民衆の日常生活のなかから生まれたものであっても、ずっと前の時代から受け継がれてきた「伝統的文化」でもなく、単なる下位の文化・サブカルチャーにすぎないもの、というような偏見のもとに眺めていた。こうして、釣りをはじめとして体を使って遊ぶことは好きであったが、遊びやスポーツは私の知的な関心の範囲には入ってこなかった。
また、私はいつのころからか職業としての仕事に生きることが人生なのだとは考えなくなっていた。生きていくためには職業をもつことが必要であるが、これは個人的な利益の問題である。人は社会の中で社会という仕組みを利用しその恩恵を受けつつ生きていく。だが人は、自分の生活のためばかりでなく、困ったり苦しんだりしている人々のためにも行動すべきである、あるいは社会に働きかけ困窮している人を減らすよう努めるべきであると考えるようになった。そして実際、こうした考えに従い、「ボランティア的な」活動にも時間を使った。
他方で、生活のための職業上の仕事や家事育児の仕事、および「ボランティア的」な活動のほかに、遊びも必要であった。釣りが私の遊びであった。だが50代までは遊びの時間は思うようには取ることが出来なかった。そして私は還暦を迎えるのを機に、家族を含め生活の目処も立ったので、釣りをして遊んで暮らそうと考えた。しかし、釣りが人生にとって大きな意味があるということを人に向かって語る理由はないと考えてきた。自分の生活のための仕事であろうと「ボランティア的」活動であろうと、社会の中で行われる活動であり、他の人のために、他の人の必要に応えて、他の人による評価の下で行うという面が強く、義務と責任に縛られざるを得ない。だが、それら活動が必ずしも進んでやりたい楽しいものでなくても、それらをやる必要があり、またやるべき理由がある。
私が60歳で退職したのは、一面で、ほとんどが義務や責任の関係である他の人々との関係を大幅に断って、自分だけの世界にできるだけ閉じこもりたいためであった。何か困って助けを必要とした場合を除き、人に向かって積極的に語りかけること(教職とはそういう仕事である)はやめようと思った。仕事を辞めたもうひとつの理由は釣りをしたいということであった。釣りをしたいという理由は、それが好きだということにつきる。(その面白さは第4章、5章で書く。)「人に語りたい」、「人と話をしたい」のなら、退職後別な趣味もあっただろう。しかし、話すこと、語ることは釣りの要素ではない。黙って糸を垂らすだけで釣りはできる。
私は漁村に移り住み、ごく少数の地元の友人の助けを借りる必要があったことは確かだが、ほとんど話したり、語ったりする必要のない、釣り三昧の生活を始めた。時間はたっぷりあり、時化(シケ、=荒天)で釣りに出られないときには「釣日誌」を書いた。潮の流れ方や釣果についてばかりでなく、鳥の鳴き声など周囲の自然や人々の暮らしについても少しは書いた。つまり、日記をつけるようになった。釣り日誌、あるいは日記は釣りを少なくとも2回あるいは2倍楽しむ方法だということを第5章で書いている。だが、日記はあくまでも自分だけが読むものであり、自分で読んで楽しむために書く。
しかし、日記をつけることにとどまらず釣りとは一体何だろうと考え出したときに、釣りという遊び/スポーツに、知的関心がわいてきた。こうして、遊びとは何であり、スポーツとは何であるか。そして釣りが遊びであるとしたら、どんな遊びなのか、釣りはスポーツなのかどうか、ということを少し突っ込んで考えてみたくなった。そして若干なりとも、関連した書物を読んでみると、遊びやポーツについて考えることが、釣りをし、遊ぶことに匹敵するくらい、面白いことがわかってきた。そして以下のように考えた。
もっとも広いスポーツ理解では、娯楽や楽しみすべてがスポーツであるようだ。もともと18世紀くらいまでの英国では、disportとsportという二つの語が、ともに楽しみ、娯楽の意味で使われており、しかも、きちんとしたルールをもった近代的なスポーツは、18世紀頃まで存在しなかった。スポーツの歴史については、またあとで詳しくN.エリアスの研究を参照したいが、エリアスが、スポーツとは「するもの」と考えていないということをここで触れておこう。
エリアスによれば、スポーツとは、むしろ「見て楽しむ」ものなのである。サッカーや狐狩りは、ボールを蹴ってゴールに入れるゲーム、あるいは犬が狐を追いかけてかみ殺す「狩り」がそのスポーツの半分をなしているのだが、同時にそれを見て楽しむ観客あるいは犬の飼い主もそのスポーツの残りの半分を構成している。狐狩りではそれを楽しむジェントルマンは馬に乗って、狐を追う自分の飼い犬を追いかけながら見るのであり、相当に激しい運動を行なうが、目的は犬が狐をかみ殺すのを「見る」こと、それによって残虐な行為を自ら行なう良心のとがめを感じずに、興奮を味わうことにある。サッカーの観客が大声を上げて応援することは、私がこれまで述べてきたような「身体運動」ではない。観客はゲームを見て「楽しい興奮」を味わう。
エリアスのスポーツ概念では、自分で身体運動を行なうのでなく、ただ見ること、見て楽しむことが、身体運動により試合を行なうことと同様、スポーツである。観客もまたスポーツに「参加している」のである。
こうした概念に従えば、プロ野球やJリーグのサッカーのファンはもちろんのこと、競馬のファンも、明らかに、スポーツに参加している。賭ける場合には、いっそう、積極的に参加しているということになる。J.M.ミッチェナー/宮川毅訳『スポーツの危機―どこが間違っているか』(サイマル出版、1976)(原著名はSports in America)は最初の方で、実例を挙げて、スポーツの楽しさを説明している。1つは競馬で賭けること。競馬師はスポーツファンであるが、馬が走るのを見て楽しむだけの競馬ファンとは区別される。競馬に賭けることがスポーツだとされている。しかも、本物の競馬師は競馬場に行かないとさえ書いている。確かに競馬場に行かなくても、テレビやラジオで「楽しむ」ことが十分できる。ただし、この競馬師の賭けの勝率が高く、それで「食っている」のかどうかについては書かれていない。
もう1つの例は、仕事の注文をとるために客とプレーをし、わざときわどく負けたり、賭けゴルフをやって儲けたりもしているかなりの腕のアマ・ゴルファー。この例では、著者は「実益と趣味を兼ねて」ゴルフを楽しんでいると書いている。この人物は別に本業を持っている。健康のためにと考えてゴルフをはじめた。しかし、いまや、ゴルフは、この人物にとって、単なる趣味なのではない。実益も兼ねている。この全体が「スポーツ」なのである。アメリカでは、それで儲けることがあるとしても、世間で正規の職業とはみなされていないような、遊び半分である(としか分類し得ない)ような活動なら、スポーツだと考えられている。
また、楽しみ・娯楽がスポーツであり、身体運動の要素は関係がないとすれば、当然、チェスはスポーツであることになる。ただし、日本では、囲碁・将棋など知的なゲームはスポーツとは見なされていない。
シンクロナイズド・スイミングではartistic impressionも評価対象である(写真はWikipedia)

また、現代スポーツの多くは競技であるが、音楽演奏や舞踊においても「コンクール」(もとは「ともに走る」つまり「競走」を意味した。)において「勝ち負け」あるいは「優劣」が争われる。
舞踊に似た、体操やフィギュア・スケート、シンクロナイズド・スイミングなどの「スポーツ」では、技の「難度」や「正確さ」を競うのであり、細かく点数化された技量の優劣を競うのに対して、音楽や舞踊においては、正確さや難度といった技量だけではなく(というか、それらは必要条件に過ぎず)、それらを通じて表現される演奏や演技の「美しさ」が問題になるのだと思われる。
しかし、「スポーツ」とみなされているフィギュア・スケートにおける「プレゼンテーション」の評価が美しさ、優雅さなどとは別な「技量」だけを見るものだとはいえない。
2001年版『知恵蔵』によれば、フィギュア・スケートは「スピードだけに飽き足らない貴族たちが優雅さを求めてはじめたのがルーツ」であり、また、プレゼンテーションでは「表現」が評価される。ペアで行う規定演技であるコンパルソリーでは「正確に滑るテクニックと音楽のテンポに合ったステップや動作の協調性、姿勢や表現力などのタイミング・アンド・エクスプレッションで採点される」等とされている。だが、「滑る」ことを除き、同じことが舞踊でも言われるであろう。シンクロナイズド・スイミングについては「テクニカル・メリット(技術点)とアーティスティック・インプレッション(芸術点)の両方が表示され」、その合計点で順位が決まるという。
2012年ロンドン・オリンピック、体操の個人総合で優勝した内村航平は「美しい体操」を目指すと言っていた。体操でも優美さを重視する人が実際にいる。
「する」スポーツだけを考えれば、明らかに、強さや早さを競うスポーツと、見せるための「作品」をつくる行為である「芸術」とは異なる。しかし、スポーツの試合の全体は、人間を材料にして時間をかけてスタジアムというキャンバスcanvas(布地)ならぬキャンパスcampus(平地)の中に展開した作品であると言えないだろうか。もしそう言ってもいいなら、プロスポーツが中心であるような現代では、ゲームを「見せる」ために行われるスポーツは、戦う二つのチームが協力して作品を生産する活動だといえるだろう。スポーツと芸術を区別する指標のひとつが失われるといえないだろうか。
社会学者・井上俊は、芸術とスポーツの違いを前者が「表現」行為であることに見ている。だが同時に、上でふれた3種目のスポーツについて「どう考えるかむずかしいところ」だとも述べている。また、井上は、各種のスポーツに見られる運動や姿勢の美などもさることながら、しばしばスポーツの中に「ドラマや映画が決して直接示せないような劇的な緊張」を見出す。スポーツは「伝統的な意味での<芸術>ではない」としても、芸術と同じような機能を果たしている、とする説を紹介している。『スポーツと芸術の社会学』(世界思想社、2000年)第1章参照
しかし、一般的に、芸術とスポーツは異なる活動領域に属すると考えられている。芸術とスポーツを分ける理由は歴史的社会的背景---たとえば起源において、民衆の娯楽であったか、それとも権力者の装飾品とするために制作活動が行われたか、というような---のなかにあるとおもわれるが、それを調べる余裕はなかった。
芸術活動のいくつかは、身体を使う度合いにおいてスポーツにすこしも劣らず、また競技として行なわれているにもかかわらず、スポーツとは見なされていないが、逆に、もともとは性格がまるで異なり、始めは競技ではなかった別な種類の身体運動が、競技化されて、スポーツとして扱われるようになったものがある。私が言いたいのは、サッカーなど英国起源のスポーツ群とは異なる、ドイツなどで始まった体操・体育のことである。
サッカーや野球、テニス、あるいはレスリングなどでは、チームとしてあるいは個人として、選手は相手のチームあるいは相手プレーヤーと戦う。攻撃と防御がゲームの主要な要素になる。というよりも、攻撃と防御は同じ行動を異なる面から見て言う言葉にすぎない。こちらの得点は相手にとって失点であり、こちらの失点は相手の得点である。攻撃の成功とは相手側の防御の失敗であり、逆のことが言える。もし相手が攻撃をかけてもうまく防御すれば、相手の得点は生じない。こうして、最後に、得点と失点を差し引きしてプラスの側が勝ちなのである。
18世紀末から次第にきちんとしたルールが作られてイギリスから世界に伝播していったサッカーやラグビーなどの「スポーツ」は、のちに詳しく述べるが、もともとはルールがほとんどない「フットボール」という、本当の戦い(戦争や喧嘩)と区別できない「暴力」を伴った遊びのなかから生まれたものであった。遊びであるというのは、その戦いでは相手の身体の能力の破壊自体が目的ではなく、闘う者とそれを見るものが「楽しむ」ために行う活動だからである。現代スポーツのほとんどは勝敗を争う「ゲーム」であるが、出発点は、力と力がぶつかり合う馬上槍試合、(あとで見る古代ギリシアにおけるパンクラチオンを典型とする)レスリング や相撲など、格闘技における「勝ち負け」にある。チェスや囲碁・将棋は、本物の戦争を模して、貴人が宮廷で座って楽しめるようにと考え出されたものであろう。本当の戦いから「抽象的」に勝ち負けの観念だけを取り入れ、また戦いで必要な“策略”など知的要素だけを重視した遊びが、盤上の「戦い」であるゲームになったのだろうし、体力と身体能力を重視する遊びが現代のスポーツへと発展したのだろう。身体運動であるのかどうかの観点からは、サッカーと体操は「近い」といえるが、闘いであるのかどうかの観点からすれば、サッカーと体操の間の距離は、サッカーとチェスの間の距離よりも、むしろ大きいといえる。
ユリウス・ボフス/稲垣正浩訳『入門―スポーツ史』(大修館書店、1988年)によると、ナポレオン戦争で敗北した(領邦分立国家)ドイツにおいて、祖国救済を目的に、個人的な人格を開発するとともに国民的共同体に結合させることを目指し、一般的な義務教育の導入など、教育改革の必要を説く意見が強まった。知的教育や道徳的・社会的教育と同等に身体的教育を重視したペスタロッチの教育思想がこうした運動に大きな影響を与えた。ペスタロッチは古代ギリシアにおけるギュムナシオン(体育)に由来する語を用いて、身体教育をギュムナスティークと呼んだ。彼を崇拝するヤーンは、教育改革の中心を身体教育にあるとし、身体修練の新しいシステム=「トゥルネンTurnen」を提唱した。「トゥルネン」は、中世の貴族たちにより盛んに行われた、フランスに起源をもつ馬上試合・トゥルニールTurnier(英語ではトーナメントtournament)に由来し、古代フランス語のtornierは「馬を回す、むきを変える」ことを意味した。
1895年の全ライプツィヒ・トゥルネン協会創立記念祭の様子(ドイツ語版ウィキペディアによる)
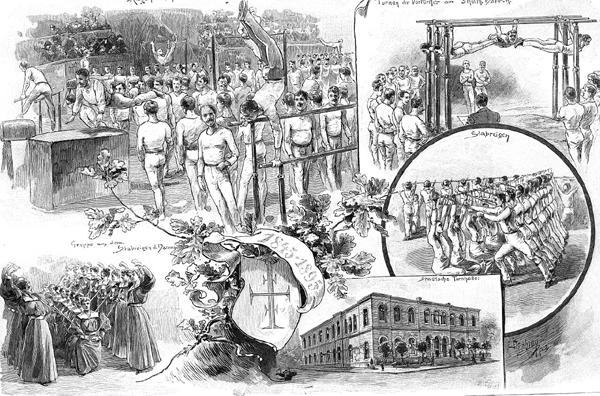
だが、19世紀に「創案」されたトゥルネンTurnenは、戦いではなく、狭い意味で器械体操、広くはギュムナスティーク、体操・体育を意味する。そして、トゥルネンを普及させるための組織、トゥルネン協会Turnengesellschaftが作られたが、20世紀におけるドイツ社会の複雑な政治的状況のなかで、トゥルネン協会の歴史も極めて複雑だったようで、現在の体育や器械体操の世界的普及にどのような役割を果たしたのかはボフスの著書からは読み取ることができない。だが、現代スポーツとしての体育・体操が今紹介したトゥルネンに起源を持つものであることは確かなことだと思われる。
また、ボフスがはっきり述べているわけではないが、体操、身体運動はヤーンにより突然考案されたのではなく、ボフスが述べている、17世紀の、君主の宮廷に集う貴族(青少年、男子)のための特別な学校である、騎士学校における、馬術、剣術、曲馬術などの訓練(そして、エチケット、作法、ダンスなどの優雅な振る舞いの訓練)のなかに、トゥルネンの原型があったと推測することができるのではないだろうか。というのは、ボフスは、騎士学校において、剣術をエペ、フルーレなど軽い武器で戦い、曲馬では木製の模造品をつかうなどし、軍事的様式でなく、動きの優美さBewegungseleganzが追求されただけでなく、平行棒、はしごなど練習のための特殊な器具が作られたと述べているからである。
ボフスは、18世紀後半の汎愛主義者による教育改革に触れて、この中で行われた体育授業における「授業の首尾一貫した方法化、過剰に高められた達成志向、抽象的な運動要素のなかでの〔への---須藤〕運動単位の細分化はつい最近に至るまでの体育に重くのしかかっていた」と述べているが、ある時期、ドイツのギュムナスティーク・体育が「競技スポーツ化」傾向を強めたのだろう。
トゥルネンにも陸上競技のような、競い合う種目が含まれていた。しかし、戦い・競争が中心であるような英国型のスポーツと明確に異なって、体力・身体能力の育成よりも、人格的な自己形成、しかもブルジョワ階級でも貴族でもなく「自由な」近代的市民である「ドイツ国民」を形成するという、実際にどの程度達成されたかは明らかではないが、文化的・精神的目標に重点が置かれていた。古代ギリシアのギュムナシオンは戦争、戦いのための身体訓練であったが、18世紀末から19世紀はじめのドイツのトゥルネンには、ナポレオン戦争で破れた相手国フランスに対抗する国民として、基礎体力の形成が目的の一部に含まれていたことは確かだが、直接的な格闘練習のようなものは含まれていなかったようだ。トゥルネンを「集団体操、行軍、走・跳・投の運動など、軍隊の集団行動の予備教育的な色彩が強いもの」だと見る研究者もいる。金芳保之/松本芳明『現代生活とスポーツ文化』(大修館書店、1997)第4章「世界のスポーツ」参照。しかし、「ナショナリズム」を背景にしたトゥルネンの「集団行動」的性格は、領邦国家に分立していた当時のドイツの特殊な歴史的状況を考慮すれば、私は、過大視できないと思う。2)
こうして、現在、同じくオリンピック競技になっているとしても、英国型の闘うスポーツ・競技スポーツとドイツ型の自己修練、自己形成的な「体育・体操」を異なるタイプのスポーツだと見ることができる。
古代ギリシャ、オリンピア競技会での短距離走。
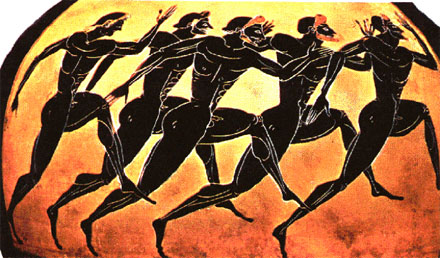 <>
<>
ゲームは相手がなければ、行う(遊ぶ)ことができない。チェスや囲碁・将棋なら、現代では、コンピューター相手に行なうことができるが、身体運動であるようなスポーツの試合、ゲームは一人では行なうことができない。瀬戸内海に浮かぶ愛媛県大三島の大山祇(オオヤマツミ)神社では毎年神事として「一人相撲」が行なわれるが、これは一人で相撲をしているのではなく、見えない神様と相撲をしているのである。普通、一人相撲は、自分だけで勢い込んで行う、むなしい行為をさす。一人では、摺り足や鉄砲などの稽古を行うことはできても相撲を取ることはできない。しかし、スキー・スケート、陸上競技では、計測さえすれば、自分の技量を測ることができるし、遊びとして、一人でも十分楽しむことができる。作家でかつ画家の玉村豊男は子供のときに一人遊びが好きだったという。彼は家の中で紐を張って高跳びをして楽しんだ。「体育の授業は嫌いなのに、ひとりで運動するのは好きな子どもだった」と書いている。毎日やっているうちに畳の根太が抜けて親に叱られたと付け加えている(愛媛新聞。2011.6.26「隠居志願」27)。(ただし、身体運動であるスポーツにおいても、近い将来、ボタンで強さやわざの程度を選ぶことのできるロボットが登場するだろうことは十分に予想できる。)
体操、陸上競技、スキーなどは、登山やロック・クライミング、ハンググライダー等の「アウトドア・スポーツ」同様、時間・空間、物、場所、自然と戦って、自己の身体の能力を楽しんだり、向上させたりしようとするスポーツである。それらは「競技」化されてはいるが、人間同士の「闘い」ではない。他方、イギリスの「フットボール」を元祖とするさまざまな球技などの「スポーツ」は体と体がぶつかり合う直接的な戦いという特徴をもった身体運動で、もともとは相手=敵を肉体的に圧倒して、相手ゴールにボールを入れることを目指す「遊び」で、ルールが設けられたのは近代になってからのことである。「フェアプレー」、「スポーツマンシップ」などはその遊びが人間同士の戦いであったがゆえに必要となった戦いの心構えである。体操や陸上競技、あるいは登山やスキーでは、戦う相手は自然である、あるいは自分である。ごまかすこと、インチキをすることは不可能である。
この十種競技においては、国際大会でも、2日目の最終種目1500mが終わると、優勝者だけでなく選手全員がビクトリー・ランを行い、劇や音楽会などのカーテンコールのように、選手が一列に並んで観客に向かって挨拶をするという。また最近の日本国内の大会では、優勝した選手をほかの選手みんなで胴上げをしたという。十種競技にはすさまじい体力を要求され、私の記憶では東京オリンピックでこれに出場した選手は「鉄人」と呼ばれていたと思う。(ただし「鉄人レース」と言うときには、水泳3.9km,自転車180.2km,ランニング42.195kmの計226.295kmを1日で行うトライアスロンを指すようである。DVD=ROM平凡社世界大百科事典)。 選手は自分の得点がほかの選手に勝(まさ)ったかどうかということではなく、身体の力の限りを尽して十種目の演技をやり終えたことに深い満足を感じ、互いに讃え合うのではないだろうか。優勝者はほかの選手を負かした最強者であるよりも、選手みんなのがんばりを象徴・代表する存在であると感じられているのではないだろうか。恐らく、私が記事を見つけることができなかった女性の七種競技も同様であろう。
スポーツの多くは勝敗を争う競技であり、格闘技のように闘いそのものでであるような競技も含んでいる。たとえば、後に見るように『ホモ・ルーデンス』の著者ホイジンハは、人間は本質的に他者との競争あるいは闘いを好むと言う。だが、山歩き、ダイビング、サーフィンなどのような、ひとりで身体運動を楽しむ、競技でも闘いでもないスポーツもある。十種競技やトライアスロンなどは競技であるが、どちらかというと他のアスリートとの闘い・競争であるよりも、自分自身への挑戦であり、記録を縮めるよりもゴールに到達することが目標であって、競技の完遂を互いに讃え合うような種目だと言えるだろう。
右はJeremiah Davison (1695?-1750?)により描かれた
The MacDonald boys playing golf(英語版Wikipedia, the free encyclopediaによる)

できるだけ少ない打数で打ち、ボールを穴に入れて、コースを回る遊びが「戦い」と関係あるのだろうか。ゴルフでは「パー」を基準にして、スコアーを数える。大会では多くの選手が参加して、それぞれの選手がコースを回って、あげたスコア(打数の少なさ)を最後に比較して、順位、勝敗が決まる。ストローク・プレーである。ゴルフは同じイギリス生まれのサッカー、ラグビー、クリケット、ポロ、ホッケーなど他のゲームとは違い、攻撃と防御を要素としていない。ゴルフはどちらかといえば、体操や陸上競技などと同じ種類のスポーツである。ただし、一緒にコースを回って、二人だけで勝敗を争うマッチプレーの場合には、「対決」、「対戦」であることがわかる。歴史的には、こちらが最初に始められたようだ。『知恵蔵2005』
ゴルフはサラリーマンのスポーツとして釣りと比較され、ゴルフは「社交」を重視したスポーツだと言われる。(釣りは社交にはあまり役だたない。『釣りバカ日誌』のハマちゃんとスーさんの関係は社交というよりも個人的付き合いである。これも「社交」ではあるが、相手が限定されている。)
社交に役立つばかりでなく、会社での付き合いや顧客の接待などのビジネスを目的に、仕事の延長としてゴルフが行なわれる。そのためにマッチプレーが役に立つ。相手と一緒にコースを歩きながら話ができる。これは「戦い」ではなく、ある種の友好のための活動である。一緒に遊んで親しくなるための「戦いの遊び」である。しかし、多かれ少なかれ友好と親善に役立つということは、一人で行うのではないゲーム(闘い)形式のすべてのスポーツの特徴でもある。国家間の友好親善のためにスポーツの試合が極めて有益であることはよく知られている。逆に、スポーツの試合から、国家間に反目が生じ、戦争にまで発展したケースもなくはないが。
ゴルフのマッチプレーは、一応、他のスポーツ同様、「ゲーム」の一種である。だが、得点を競う競技としては、(ドイツ型の)体操などと似ている。その勝敗の決まり方においては、直接に相手を倒すことを目指し、相手に失点を与えることが得点であるような他のイギリス型のスポーツとは異なる。(競走は世界中で行なわれており、イギリス特有のものではない。)
以上はたいしたスポーツ・ファンでなく、スポーツに全く詳しくない私の「オレ流」のスポーツ談義である。第一に「ルールに基づいて身体能力を競い合う遊びの組織化、制度化されたものの総称を意味する。言い換えれば、遊戯性、競争性、身体性、歴史性という4つの要素によって特徴づけられる文化形象である」という。とくに「歴史性」の要素はとりわけ重要で、それが得られるまでは「3つのほかの要素を満たしたとしても」、「スポーツ的活動であって、スポーツとは言えない」という。歴史性はすべてのスポーツ的活動がスポーツと認められるための必要(不可欠な)条件とされている。「ニュースポーツと称されるスポーツにも一定の歴史性が備わっている」という。この第一の意味でのスポーツには後で見るようにプロ・スポーツが含まれている。
第二に、ウォーキングやジョギングなど、「競争性や歴史性がなくても」、「非実利的な身体活動であれば」「健康保持や爽快感などを求めて行なわれる身体活動を指してスポーツと呼ぶことがある」という。
第三に「チェスや将棋」などの「知的な戦略能力を競い合う遊びを指してスポーツということがある」。「歴史的にも、産業革命前のイギリスではチェスもスポーツの一つとして捉えられていた。ただし、現代においてはあくまでも特殊な使われ方であって、スポーツの一般的な意味ではない」。「一般的」な意味、現代に通用し、適切な意味は、あくまでも第一の意味である、と服部は言う。
これらスポーツという言葉の三つの意味、つまりスポーツの三種の概念が包摂する活動の広さを最初に確かめておこう。
第二の概念は、ウォーキングのように競争性をもたない活動もスポーツと考える点では第一の概念よりも広いが、非実利性を要素としている点でプロスポーツを排除している、つまりアマスポーツのみをスポーツと考える点では狭い。良い悪いを別として、現代では、ニュース番組を見れば一目瞭然、プロスポーツがスポーツの主流であるから第二の概念は「狭い」概念である。
第三の概念は、身体活動性を「要素」とはせず、チェスや将棋のような「知的戦略を競い合う遊び」も「頭脳のスポーツ」として、スポーツだと考える3)。したがって、三つの中では、もっとも広い概念である。しかし、チェスや将棋のように「知的戦略を競う」ことは「賭ける」こととは違う。この概念は、先に見たミッチェナーの著書でいわれていたような、競馬や、賭けゴルフなどもスポーツと考える欧米の一般庶民のものと思われるスポーツ概念と比べれば狭い。
また、いずれの概念においても、スポーツは「する」ことだと見なされており、エリアスのように「見る」こともスポーツだとは考えられていない。服部の上げている三つのスポーツ概念はいずれも、欧米におけるスポーツ概念よりもせまく、必ずしも、十分に一般的ではないことがわかる。
そして服部の説明では、スポーツ概念に含まれている「歴史性」という要素が重要であることが強調されていて、第二、第三のスポーツ概念は、第一のそれとはただ別の概念だと言うのではなくて、特殊な概念、一般的でない概念だとされている。筆者の服部が第一のスポーツ概念に立っていて、自分の見方に基づいて他の概念を説明しているためではないかと疑われるのだが、客観的でない不公平な説明だという印象を与える。
第二のスポーツ概念は、プロスポーツはスポーツではなく、一般人が休日などに楽しみと健康増進などのために行う身体運動だけをスポーツと見なす。これはきわめて「特殊」だと考える人もいるかもしれない。しかし歴史的には比較的最近までこうした考えこそが主流であった。
後で再び取り上げるが、今から60年ほど前(昭和28年=1953年)に日本スポーツ振興会議が制定した「スポーツマン綱領」というものがある。そこでは「競技するものは、スポーツを行なうことによって、社会的名声や物質的な利益を得ようという考えをもたないこと」を定めている。金子藤吉『コーチのためのスポーツモラル』体育学講座14(逍遥書院、昭和52年、初版は昭和36年)に掲載されている。この時代には、「本来の」スポーツマンとはアマチュアのスポーツマンだけだという考え方があった。オリンピック大会への出場資格もアマチュアに限られていた。恐らく、現在も、「本来の」スポーツは、物質的利益を求めないものだと考える少数の人々がいるであろう。私はそれが「正しい」と思っているわけではない。しかし、服部はスポーツ概念の解説者としては、なぜ第一の概念のほうが、より適切であると考えられるのかを説明すべきであった、と私は思う。服部の説明には納得がいかないことが多いのでじっくり検討したいが、その前に、他の「事典」に少し当たって見てみよう。
エリッヒ・バイヤー編・朝岡正雄監訳『スポーツ科学辞典』大修館書店、1994では、1800字ほどで「スポーツ」という語を説明している。「スポーツという概念は、日常語では、非常に広い意味内容を持っているので、これを厳密に定義することはできない。この概念の適用範囲を科学的に分析しても、スポーツという概念で理解されている内容のほんの一部しか規定できない。その内容の全体は、日常的な使用法によって、さらには歴史の中で形成され伝承されてきた、スポーツと社会、経済、政治、法律との結びつきによって規定されている。この概念の理解は歴史の中で変化してきているので、それをあらゆる時代に対応するように固定することはできない。」という。そして、競争性が強いかどうかというような、異なる傾向をもったさまざまなスポーツが、さまざまな社会的な領域において、さまざまな視点・関心から、異なる性や年齢や職業のひとびとによって、行われていることを指摘している。私には、「スポーツという語の意味」ないし「スポーツの概念」についてのこうした説明のほうが納得の行くものであると思われる。
また平凡社DVD-ROM世界大百科事典の「スポーツ」(稲垣正浩)という項目では次のように書いている。「スポーツとは、競争を中心とする〈近代スポーツ〉、楽しさを中心とする〈ニュー・スポーツ〉、民族的なアイデンティティや儀礼を中心とする〈民族スポーツ〉、癒しや瞑想を中心とする〈瞑想系身体技法〉、健康を志向する〈体操・ダンス〉、自然との接点を求める〈野外スポーツ〉などの総称である」。言い換えれば、少しずつ異なる目的・性質のスポーツと呼ばれる様々な活動があるということである。
この説明に従えば、上でみた『最新スポーツ科学事典』で服部が言うスポーツの「第一の意味」は<近代スポーツ>に相当する。そして稲垣は「ニュー・スポーツには,フリスビーや風船バレーのような---,いわゆる〈軽スポーツ〉と呼ばれる,だれでもすぐに楽しむことのできるスポーツをはじめ,---セパタクローやブーメランのような民族スポーツをヒントにして簡易化したもの----がある」と、「歴史性」や「社会的認知」に言及することなく、ニュースポーツと呼ばれる活動がある事実を簡明に述べている。
瞑想系身体技法として、ヨーガ、坐禅、太極拳、少林寺武術(少林寺拳法)などをあげ、また、エアロビックス、ジャズ体操、ジャズ・ダンスなどもあげている。そして、「自然との接点を求める野外スポーツ」には、バードウォッチングなどの〈ウォッチング系〉のものをはじめ、ハイキング、登山、キャンピング、フィッシング、ハンティング、アクア・スポーツ、空の風と戯れながら楽しむ気球やハンググライダー、洞窟探検などのケービング、都心を離れてのサイクリングやドライブ、などがある、と言う。また,野外スポーツを楽しみながら、写真、スケッチ、俳句、短歌、寺社や名所旧跡探訪、なども同時に楽しもうという〈多目的スポーツ〉(マルチ・スポーツ)への道も開かれていると言い、結論的に、「以上のように、スポーツの概念もまた価値の多様化の時代を迎えて、多種多様な展開をみせている---。新しい時代の進展とともに、今後ますます多様化していくものと考えられる」と述べている。スポーツに関する客観的な説明で、私には納得がいくと感じられる。
普通の意味で歴史性とは、事柄の過去における事情、歴史的経緯、あるいは変化・変遷を言う言葉であろう。ある事柄の理解に、眼前の事実だけでなく、過去から現在に至るそれに生じた諸事情、歴史性の理解が大切な場合がある。私は歴史性と言う語の意味をこのように理解している。そして、一般的には古くからあるものは「歴史性」をもつ、と考えられる。
フリスビーや風船バレーなどニュースポーツと呼ばれているものは新しく始まったばかりである。「民族スポーツをヒントにして簡易化したもの」もあるとされるが、もとになった民族スポーツと現在の新しいスポーツとは別のスポーツであり、「ニュースポーツ」と呼ばれる一群の活動は、昔はなかった新しいスポーツであるはずだ。だからこそ「ニュースポーツ」と呼ばれているのだろう。ところが、服部は「ニュースポーツと称されるスポーツにも一定の歴史性が備わっている」と、新しいスポーツでも「歴史性」をもつことができる、と言っている。そうだとすれば、彼の言う「歴史性」は私が理解している「歴史性」とは異なる意味をもつだろう。
他方、第一の意味のスポーツが4つの要素を含むと述べた後で「歴史性については、遊戯性、競争性、身体的活動性の3つの要素を満たす活動が考案されたとしても、社会的認知を得るまではあくまでもスポーツ的活動であって、スポーツであるとは言えない」と、社会的に広く「認知」されていることが「歴史性」をもつことであるとし、またある活動がスポーツであることのもっとも重要で不可欠な「要素」であると述べている。こう述べられたあとで先ほどのニュースポーツについての文が続くのである。
「社会的認知」とはそのスポーツが広く社会に知られ、また実際に行われることを意味するだろう。フリスビーや風船バレーはそうしたことが当てはまるのかもしれない。それらの活動はスポーツに似ている(「スポーツ的」とはたぶんそういう意味なのだろう)が、最初は、たとえば、単なる遊びだとみなされた。しかし、あるとき以降、大勢の人がそれをスポーツだと認めたので、スポーツになったのだと。歴史性とは広く人々がそれをスポーツだと認めることだと。しかし、次のようなケースを考えてみると、この「要素」のおかしさがわかる。
ある「スポーツ的」活動が考案され、しばらく経って多くの人が行うようになり「社会的に認知され」た。しかし、人気は一時的で、その後は再びわずかな人の間でしか行われなくなったとしよう。この活動はある時期にはスポーツではなく、次の時期にはスポーツであったが、行う人が減った後では、再び、スポーツではなくなるのだろうか。その活動の中身が変わらないのに、それを行う人の数が多いか少ないか、つまり「社会的認知」の度合いで、その活動の分類のしかたが変わるということが起こるのだとすると、私にはたいへん奇妙なことのように思われる。
「スポーツという言葉の意味」あるいはスポーツの概念は、一般に、ある活動がスポーツなのかどうかを判断する際の基準になるであろう。つまり、ある活動はスポーツなのか、それとも宗教的行為なのか、芸術なのか、等々が問題となるときに、その判断基準となるであろう。そのとき、ある活動を指して「スポーツ的活動であってもスポーツではない」と言うとすればおかしなことであろう。スポーツとは、芸術的でも、政治的でも、宗教的でもなく、スポーツ的であるような活動、つまりスポーツ的活動であろう。私も含め、普通の人は「スポーツ的ではあるがスポーツではない」と言われても、まず納得しないであろう。そこでは「スポーツに似ているが、遊びに分類されるべきだ」というようなケースとは違う事態が問題になっているのである。活動の内容からすれば、単なる遊びではなくスポーツなのである。しかし、まだ、あるいはすでに、スポーツだと「認知されていない」がゆえにスポーツではないと言われているのである。
ある活動がほかの三要素を満たしているのにスポーツであると認められないことに不満を持ち「スポーツとは何か」と問うたとしよう。他の要素は満たされているから問題ではない。「認知」という要素だけが問題なのである。服部は「社会的認知と言う要素が重要なのだ。スポーツがスポーツであるのはそれがスポーツであると広く認められていることだ」と答えるだろう。
だがそれは「スポーツとはスポーツだと人々が考えているものだ」と言うのと同じことである。これは答えにはならない。りんごを知らない人が「りんごとは何か」、「りんごとはいかなるものか」と問うたときに「りんごとは人々がりんごと考えているものだ」と答えるのがナンセンスであるのと同じである。
それがナンセンスなのは、それがりんごの特徴にふれない、トートロジー(同語反復)の類の答えだからである。「社会的認知」がスポーツの概念の要素だとすれば他の要素についての考慮は不必要だからである。つまり異なる要素からなる複数のスポーツの概念が存在することについて考えたり言及する必要はないからである。「社会的認知」を不可欠な要素だと言い立てる第一のスポーツ概念は、スポーツとはスポーツであると人々が認めているものである、とスポーツを定義することである。
こうして、第一のスポーツ概念にたつならば、ある活動がスポーツであるのかどうかを判断したくても、できない。そこで、その活動がスポーツであるかどうかを知りたければ多くの人がどのように考えているかを調べるしかなくなる。しかし、尋ねられた人がまじめに答えようとすればスポーツの概念またはスポーツという語の意味にしたがって答えようとするだろうが、すべての人が「第一の概念」が「一般的」あるいは正しいと思い、それにしたがって答えようとするなら、その人たちも最初に尋ねた人と同じ困難に出くわすだけである。スポーツとは何かを知るために人々は、他の人々がスポーツとは何であると考えているかを知らねばならず、こうして無限後退に陥らざるを得ない。だから「歴史性=社会的認知」を概念の要素とすることは無理である。
ところで服部は説明の冒頭で、「スポーツという言葉には大きく3つの意味がある。第1に、スポーツとはルールに基づいて身体的能力を競い合う遊びの組織化、制度化されたものの総称を意味する」と言い、続いて「いいかえれば、遊戯性、身体運動性、及び競技性、歴史性と言う4つの要素によって特徴付けられる文化形象である」と書いている。この二つの文を比べると、彼が「組織化、制度化」と「歴史性」を同じ意味だと考えていることがわかる。
私は、すでに何冊かのスポーツ(の歴史)に関する本を読んでいたので、この二つの文に登場する言葉は知っていた(つもりであった)。だが、スポーツの「歴史性」という言葉は初めてであった。私の理解では、スポーツの組織化、制度化とは、19世紀ごろの英国ではじまった、各種スポーツに関する全国的な「連盟」や「協会」などの組織が結成され、統一的なルールが定められるとともに その組織による大会や競技会の管理・運営の下で、規格化された施設・用具を用いてゲームを行うようになった過程、歴史的事情を指す。
英国ではサッカー(1863年にフットボール協会を結成)やラグビーが(1870年ごろから)それぞれの統一ルールにしたがって行われるようになるまでは、それらに似ているが、それらよりもずっと荒っぽい、フットボールと呼ばれるスポーツ/球技が地方ごとに異なったルールで、パブリックスクールや近隣の町や村の間で行われていた。しかし、19世紀の半ば以降、ルールが次第に統一化され、また全国的な組織ができた。また、競技団体からは独立した審判が試合を公平に司る仕組みが作られ、ルール遵守が強化された。(N.エリアス『スポーツと文明化』、DVD=ROM世界大百科事典「サッカー」(松本光弘)、「ラグビー」(大西鉄之祐+綿井永寿)など)
日本の中学や高校の体育部などは「体育連盟」という組織に加盟している。あるいは成人のスポーツ団体の多くも何らかの組織に加盟しているであろう。しかし、そうした全国組織と関係ない、草野球や草サッカーチーム、ママさんバレーチーム、その他のスポーツ同好会のようなものもたくさんあるだろう。あるいはチームとはいえない、町内会やPTAの行事で臨時にメンバーを募って試合を行うような形式の活動、あるいはさらに、家族や友人で思い立ったときに公園のテニスコートなどを借りて行うプレー、これらさまざまな個人、団体の活動は一体なんであろうか。これら団体は「組織」には加盟していない。そして試合は、連盟公認の審判でなく適当にその場で選ばれた審判の下で、あるいは参加人数に余裕がなければ審判なしに行われるだろう。だが、「組織化・制度化」されていることが要件だということは、今言った草野球---等々の活動は、野球、サッカー、バレーボールなどのスポーツではなく、野球、サッカー、バレーボールに似た「スポーツ的活動」だということを意味しているのだろうか。
2014.1.14『愛媛新聞』「この人」に登場する、全国高校サッカー選手権で初優勝した富山第一高校監督の大塚という人は、法大でDFとして活躍し、日本リーグの古河電工に入社したが日本代表経験者がそろう強豪で芽が出ず、24歳で第一線を退いた。その後指導者ライセンスを取得するために英国留学したが、その際中に60歳くらいの人が集う草サッカーチームに参加して高校生を相手に対戦したときの試合の楽しさが忘れられない。大学や古河では苦しさのほうが先にたったが、欧州でサッカーは何歳でも楽しめるということがわかったと、言う。また、彼は高校サッカーで燃え尽きず、続けてほしいということを指導方針にしているという。この草サッカーチームは連盟に加盟していないから「草サッカーチーム」なのだろうが、連盟に加入すれば、そのメンバーは、単に「スポーツ的活動ではなくスポーツ」であるサッカーをすることになるのだろうか。
おそらく服部も、草サッカーがスポーツではないとは言わないのではないか。彼が言いたいことは、国際サッカー連盟 Federation Internationale de Football Association(略称FIFA))が認めた統一ルールに従って行われるのが、「本物」ないしは「正式」のサッカーで、審判がいなかったり、11人でなく、たとえば人数不足などのためにはじめから10人ずつであるいは10人対9人で行われたりすれば、それは「本物」のあるいは「正式」のサッカーではないということだろう。「正式」かそうでないかと言うスポーツの区別にも問題がないわけではないが、私はそのように言うことを否定しようとは思わない。だが、草サッカーと「正式」のサッカーの間に違いがあることを認めることと、サッカーとは「正式」のサッカーのことであり、草サッカーは「スポーツではない」と言うこととは全く別のことであろう。
英語版Wikipediaによると、英国ではsoccerはfootballの一種とされ、association footballの略称だという。
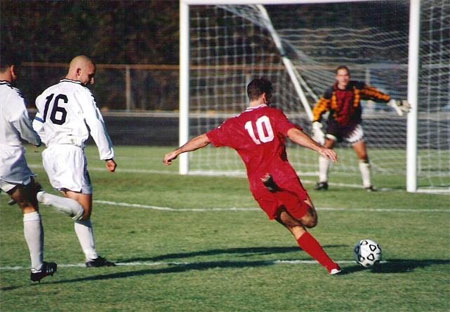
19世紀英国におけるスポーツの組織化・制度化の過程を簡単に振り返ってみよう。ラグビーとサッカーはどちらも中世から行われていた荒っぽい「フットボール」と呼ばれた球技にいくつかの新しいルールが設けられることによって19世紀半ばに誕生したものである。統一ルールが成立する以前、パブリックスクールと呼ばれる学校ごと、地方ごとに少しずつ異なるルールで試合がおこなわれていたにしても、それらのルールと統一ルールはよく似たものであったに違いない4)。
なるほど組織化・制度化により誕生したサッカーとラグビーは異なるルールを持ち、それらはまた「フットボール」とやや異なるルールで闘われる。だが、当時のラグビーもサッカーもともにフットボールに似た球技であったことは確かである。サッカー、ラグビーは以前のフットボールのルールの部分的な修正・変更によってうまれた。「組織化・制度化」を経たラグビーとサッカーはスポーツであるが、ルールが不明確なフットボールはスポーツではないと服部は言うのだろうか。
名称が変わり、明確なルールが作られて全国的な「協会」という組織ができたことは確かに「フットボール」とサッカー及びラグビーとの違いである。しかし、遊戯性、競技性、身体運動性というほかの要素に変化がないにも関わらず、組織化・制度化という変化によってスポーツではないものがスポーツになるという説明に納得できないのである。
ルールが一国内であるいは国際的に統一されているかどうか、また国内のあるいは国際的な統一組織が存在するかどうかによって、プレーの仕方、闘い方が相互に極めてよく似たゲームが一方はただの遊び、娯楽、もしくは「スポーツ的活動」であり他方は「スポーツ」だと言うよりも、一方は組織化・制度化が行われたスポーツないし娯楽であり他方は組織化・制度化が行われていないスポーツないし娯楽だというほうが自然ではなかろうか。実際に「正式」なルールによく似たルールでゲームが為されて、人々がゲームを行ったり観戦したりするのを楽しんでいるかぎり、草野球や草サッカーがスポーツではないと言えないのと同様に、一般に組織化・制度化されていない身体運動である遊び・娯楽をスポーツでないという理由がない。たとえば、柔道とは異なり、相撲には国際的な協会も国際ルールも存在しない。また日本の相撲に似たモンゴルや韓国の相撲が存在する。しかし、それぞれの国において一定のルールが存在し組織化制度化が行われている。この事実を国際的あるいは世界的に見て相撲はスポーツでないが、それぞれの国においてはスポーツである、と言うとすれば奇妙であろう。
服部の言う「スポーツという言葉の第一の意味」が、今検討し疑問を提出したようなスポーツの「組織化・制度化」を「不可欠の要素」とするものだとすれば、この概念を重視するのはスポーツの統合、管理・運営を重視する人々、たとえばオリンピック委員会の委員などではないだろうか。そして、もしかしたらその概念は主流であるのかもしれない。だが、私は、それはある特定の人々の持っているスポーツについての概念であるに過ぎない、と考える。
また「競技性」を要素とする、服部の「第一の意味での」スポーツ概念はマスメディアが持っている「スポーツ」概念と同じものだと思われる。競技性の高い、勝つことを第一の目的として行なわれるプロをはじめとする「組織化・制度化」された、スポーツ・マン、アスリートの戦いは「観戦者」にとって楽しい。マスメディアは多くの視聴者を獲得できるスポーツに注目することになる。その概念は「見られる」ことを重視したスポーツの概念である。
だが、草スポーツや草サッカー、あるいは海水浴やゲレンデスキーなど遊んで楽しむものとしてのスポーツあるいは身体運動、「する」スポーツでは、自らプレーを行い、自分で泳いだり滑ったりする人々の「身体運動性」と「遊戯性」の方が重要である。次にスポーツの「遊戯性」という要素についての服部の説明を検討する。
しかし、(日本の)剣道や(西洋の)フェンシングなどは遊びから生まれたスポーツではなく、武器を持って戦い暴力で物事の決着をつけることが当たり前であった時代の戦闘の技術が、後にそうした戦闘が行われなくなった時代に、さまざまなルールを設けることによって競技・ゲーム化されたものである。そこで格闘技の場合には、戦いではあるが本当の喧嘩や戦闘ではないという意味でしばしば「遊戯」であり、遊びであると言われる。
プロ野球やサッカーなどにおいても、選手たちは体を張って戦う。軍隊による戦闘行為とは異なり相手を殺したり戦闘能力を失わせたりすることは目指されていないが、プロスポーツではいずれも勝敗をめぐってはげしく争い、戦う。時には興奮した選手同士の殴りあいも生じる。それでもその戦いは「本当の戦い」ではない。怪我を減らすように配慮された、ルールの下での「遊びの戦い」である。
そこで、一般にある活動が遊戯、遊びであるかどうかが問題になるとすれば、レベルの違う二つの「遊戯性」の意味がある。ある活動が実用的目的からなされる仕事や労働ではなく、遊びであるという場合(広義の遊び)と、その遊びが特に戦う遊びであるときに、その戦いは本当の戦い、戦争や喧嘩ではないという場合(狭義の遊び)の二つである。だが、たとえば、同じ畑の耕作でも趣味・遊びとして行われることもあるし、生活のための仕事/労働として行われることもあり、耕すという活動形態、動作自体は遊びかそうでないかの区別はできないように、仕事/労働と遊びの区別は活動の形態、動作の違いによってきまるのではなく、その活動を行う人の意図・目的によってきまる。
したがって、たとえば漁師でない遊漁者の行う釣りは広義における遊戯であるが、小学生が休み時間に行う相撲は(喧嘩に発展しないかぎり)広狭両方の意味での遊戯である。スポーツの多くは勝敗を争う「闘う遊び」である。スポーツ愛好者は休日に、広狭両方の意味での遊びとして、スポーツを行って楽しむ。他方、プロの選手が行なうスポーツは観客を楽しませるために行なう職業労働、一種のサービス労働であり、仕事であって、遊びで行われるのではない。しかし、格闘技であっても試合=闘いは喧嘩ではなく、ルールに基づくプレー、つまり演技であり、ゲームである。プロ野球の選手は、狭義において遊戯である野球を仕事として行う。プロ野球選手は野球の試合を(広義の)遊びとして、つまり自分が楽しむことを目的にして行うのではない。これは手品師が遊戯である手品を仕事として行う人であるのと同じ、平明な事柄である。
スポーツの闘いは、虚構ではなくある種の本物の戦いである。だが同時に相手を叩きのめしたり殺したりすることを意図しない遊戯であって、本物の闘いではない。だからこそ、観客はスポーツを、本当の喧嘩や殺し合いに出くわしたときに感じるのに似た興奮を感じながら、同時にそれがスポーツの試合、つまり遊び・娯楽であるがゆえに、余裕をもって、「見て」楽しむことができる。スポーツのもつ遊戯性とはこのようなものである。
ところが、服部は「遊戯性」の定義を行わず、したがって、その二面を区別せずに、スポーツの「第一の概念」の要素として遊戯性、競争性、等々をあげたあと、「たとえば遊戯性について言えば、スポーツは本来自由な活動であり強制されたり義務的に行なわれるものではない。しかしプロフェッショナルスポーツや競技スポーツの世界では、勝利の重要性が強調されるのに反比例して、遊びの要素は重要ではないものとして扱われる。‐-‐競争性をあらわにして激しく競い合うことが歓迎される」と言う。
だが、プロが行なう試合は、労働契約・雇用契約、あるいはたとえばJリーグ規約のような規程に基づいて行なわれるもので、「強制や義務」を伴い、選手たちの私的で「自由な」楽しみのために行なわれるものではない。だから、プロ・スポーツについて「本来自由な活動であり云々」と言う言葉は無意味である。そして「勝利の重要性が強調される」ことに対する批判的ニュアンスの言及は、広義の遊びで行われる試合であれば、勝つということよりも、両チームの親睦、試合を楽しむことにこそ重点が置かれるべきだというもっともな考えが背景にあると思われるが、そこでは、遊戯/遊びと言うときに意味されるゲーム自体のもつ狭義の「遊戯性」と、活動を楽しむために行なう主体の目的としての広義の「遊び」とが区別されないままに遊戯性の語がつかわれているため、混乱を招いている。
プロフェッショナル・スポーツにおいては、選手は遊ぶこと、自らが楽しむことを目的にしてプレーを行なうのではない。闘いの遊び、というよりは遊びの闘いを真剣に行なうことによって、観客に楽しみを提供するという職業上の仕事を行なうことが、試合をする彼らの目的である。たとえば選手が暴力を振るったり監督が暴言を吐いた場合に、審判によって退場をさせられることがあるが、これは試合が何よりも勝利を重視するものであるがゆえに感情的になり喧嘩に発展することがあることをあらかじめ予想して作られた「ルール」にしたがって行われていることの表れある。(草野球ではそうはいかない。)つまりプロのスポーツでは喧嘩になるほど「真剣」に闘いが行われるのは当たり前のことなのである。友達同士で行われるスポーツの試合においては、相手を一方的に負かすことが目的ではないということはたしかであり、目的は二人が仲良く楽しむことだ。しかし、プロ・スポーツの対戦者の目的は相手と仲良くすることではない。観客は、真剣な、全力を尽くした戦いが見たいのである。プロ・スポーツの一つ、大相撲で、力士が本気で戦わず、相手を傷つけず自分も怪我をしないように気をつけながら戦ったなら、「無気力相撲」と見なされ、八百長の疑いをかけられてしまうだろう。なんであれ、プロ・スポーツの選手が戦いを「遊び」で行っていたら、たちまち観客からブーイングを食らい、そうした選手は首になるだろうし、遊びで試合をするチームはたちまち観客を失うだろう。
だから、「プロフェッショナルスポーツ---の世界では、勝利の重要性が強調されるのに反比例して、遊びの要素は重要ではないものとして扱われる」と、服部のように、ゲームが「本来、遊びである」ことを理由に、プロの選手に対して、勝利にこだわる態度を批判することは的外れである。勝利を追求することは、仕事が勝ち負けを競う遊びつまりゲームであることからくる、必然的な要請であり、それは、たとえば、画家が美を追求し、料理人がうまい料理を作ることを要請されているのと同じである。プロスポーツの選手に、八百長試合とは異なり、予想通りにあるいは筋書通りには決して進行しない、真剣勝負としてのゲームの勝利を重要なことではないと考えるよう求めることは、その代わりとして計算しつくされた演技(たとえばプロレス)を求めるのでもない限り、結局、仕事を真面目にやるなということと全く同じことである。
もちろん、勝利を追求するからと言って、ドーピングのような行為は不正をして勝ちを手に入れようとすることであるとともに自らの身体を傷つけることであり、決して肯定できない。それが勝つことにこだわる姿勢と密接な関連があることは確かだろう。しかし、ドーピングは勝つことへの不適切な、間違ったこだわりである。勝利への間違ったこだわりの存在を理由に、勝利へのこだわりを抑制しようというのは、たらいの湯と一緒に赤子を流すのと同じ愚を犯すことだろう。
不適切で、間違った行動を生むことにつながる勝ち負けに対する過剰なこだわりは、大会での順位やふだんの成績により決まる賞金や給料の格差が大きいということとも関係があるだろう。好成績をあげることのできる少数の選手だけに巨額の金を払い、J1や「一軍」以外の選手にはふつうの生活を送るにも困るような低い給料しか払わなかったり、成績の良くない選手を簡単に首にしたりという運営・経営の仕方が問題だと私には思われる。恐らく格差が人間のやる気をおこさせるという人間観・経済観から生じる労働問題であり、人権問題である。あるいは、他にも原因があるかもしれない。そうした問題を検討する必要があることは認めるが、しかし、「勝利の重要性の強調」自体をスポーツの「遊戯性」との関連で不適切だとすることは的外れで、間違っている。
プロ・スポーツが興行として観客を楽しませて稼ぐことができるためには、プレーヤーが勝利を目指して「競争性をあらわにして激しく競い合う」ことが効果的であることは明かであるように思われる。選手はプレーにおいて「遊ぶこと」を求めるのでなく、仕事に打ち込もうとする。工場労働やあるいは研究活動や他の職業の場合とは異なり、スポーツ労働は、勝利を目指し真剣に打ち込めば打ち込むほど、見る人々にとって、遊戯としての闘い=ゲームとしての面白さを生み出し、サービス業として成功することができるのである。
試合は地元でだけ行なわれるのではなく、そういつも応援にいくわけにはいかないだろう。だが、ファンは、損得抜きで、商売の売り上げを減らしてでも、ひいきのチームが勝ち、好きな選手が活躍するようにと、毎試合、夢中になって応援する。釣りをして暮らしている漁村の私の家には、テレビ放送のディジタル化以降、受像機はないし、家族の住む松山の家に戻った時も、私は、せいぜい、大相撲の結びとその前の二、三番を見る程度で、スポーツ観戦はほとんどしない。見ていれば、それなりに面白いと思うが、2時間近くなる野球をじっと見ていることはない。だから、夢中になって応援し、一緒に応援しないものにはけんか腰で対応するという気持は分らない。スポーツとは、またスポーツ・ファンとは不思議なものだと思う。だが、プレーヤーが本物の喧嘩のように真剣に闘うから、それに釣られてファンも応援しないものにけんか腰に対応すると考えれば少し分かる気もする。
プロではなくても、リトルリーグから高校野球まで、ゲームを楽しみながら「遊び」でプレーをしているものは、最近では、ほとんどいないのではないか。だから、現代のスポーツが遊戯性をもつというのは「する」スポーツとしては、休日の「草野球」や、臨時に参加者を募って行なわれる町内の地区対抗戦などを除けば、ほとんどあてはまらない。
しかし、私の理解では、イデアーつまり本質的概念は超越的なイデアー界にあるのではなく人間の脳の中にあるか、書き留められて書物の中にある。しかもそれぞれの事物や出来事に対応するイデアー・概念はリンゴやテレビのように明確に定義できる事物の場合のようにただ一つだとは限らない。つまり、日常用語で言えば、それぞれの事物や事柄についての概念は様々であり、「スポーツ」にもまたはっきりとした概念は存在しない。人々がスポーツと呼ぶ、時代ごとに少しずつ異なる活動が存在するだけである。私は、エリッヒ・バイヤー編『スポーツ科学辞典』で言うように、「スポーツという概念は、日常語では、非常に広い意味内容を持っているので、これを厳密に定義することはできない。」という説明が正しいと思う。
われわれはプラトーンではなく、アリストテレースに従い、地上に現実に存在するそれら活動が有する(それらに内在する)共通の性質(アリストテレースは主にエイドス・形相と呼んだ)から、スポーツとは何であるかを判断しなければならない。服部が「一般的」と言うスポーツ概念は、稲垣によれば、19世紀後半英国で始まった「近代スポーツ」を指すに過ぎない。ほかに、<民族スポーツ>、<瞑想系身体技法>、健康を志向する<体操・ダンス>、簡単にできてすぐに楽しめる<軽スポーツ>、<野外スポーツ>などのさまざまなスポーツが存在する。またプロスポーツをスポーツとはみなさず、ウォーキングやジョギングをスポーツに数え入れるスポーツ概念があり、あるいは身体運動性をスポーツの(不可欠の)要素と見なさず、チェスなどの知的競技もスポーツだとする概念が存在する。
しかし、スポーツにおいてはアマとプロとで、「すること」が自らにとって楽しみであるのかそれとも職業労働であるのか、言い換えると、自己にとっての快楽を生み出すのか、他者である観客にとっての快楽を生み出すのかというはっきりとした違い、分裂・対立が生じる。活動の目的が違ってしまう。スポーツ選手は、そのスポーツが好きだからそれを職業に選ぶ。とはいえ、彼が試合に出場してプレーを行うことは愛好者が休日にスポーツを楽しむのとは全く異なる。彼は楽しむために試合に臨むのではなく、職務を遂行し、給与を受け取り、家族を養うためにそうするのである。だから、プロのスポーツ選手は休日には他の遊びを行って気分を転換する必要がある。プロ・スポーツの選手にとって、スポーツは、楽しみのための活動、つまり「遊戯」ではない。もし、服部が言うように、楽しみのための活動である、つまり遊びであることが「スポーツの概念」に含まれるとすると、プロ・スポーツはスポーツではないことになる。(そしてそのように考える人もある。)しかし、定義として、プロ・スポーツはスポーツではないということにするのは、プロ・スポーツが極めて盛んになっている現在ではとうてい無理だろう。
他方、観客にとってプロ・スポーツは楽しみ、遊びであるが、しかし観客は「身体運動」はしない。大声で応援し、時には手を振り回したり跳び上がったりはするだろうが、チア・ガールの応援のような場合を除き、応援を「身体運動」とみなすのは無理ではないだろうか。身体運動性をスポーツの概念の要素として重視するなら、見るだけの参加はスポーツ活動ではないことになる。(そしてチェス・将棋もあるいは競馬でかけることもスポーツではないことになる。)これは日本におけるスポーツの常識に適った見方だろうと思われるが、私はそのほうがよいとは思わない。しかし、この区別はさほど重要なことではない。
プロ・スポーツもスポーツである、いやプロ・スポーツこそが主たるスポーツであるという現代の通念を前提にすれば、むしろ、スポーツの概念について遊戯性を要素と考えることをやめるのがよいのではないかと思う。スポーツを、「遊び」に中立的な、ルールにしたがって競争あるいは勝ち負けを争う活動と考えるのである。その場合には、スポーツを職業として行なう人もある。他方、休日にスポーツを楽しみとして遊びとして行う人もある。しかし、また、かなりの数の子供たちが、クラブに入るなどして、連日、一生懸命練習をしプロになることを目指す。塾で勉強して将来よい職に就こうと考えるのと同じように、スポーツは職業への準備として取り組まれる活動である。だから、スポーツ自体は遊戯であるとは言えないものである。
たとえばトランプ(カード)を用いる活動は、家族で行って楽しむこともできるが、占い師は職業にすることができるし、本物の賭けごとにもなる。あるいは手品もできる。トランプを使う活動はいろいろな目的で行うことができ、その活動がそれ自体遊びであるかどうかは問題ではない。スポーツ(ゲーム)をそれに似た性質のものと見なすのである。スポーツは遊びにも、プロの真剣勝負にも、あるいは「体育」の授業のためにもなる。スポーツが遊びであるかどうかは問題ではない。
学校における勉強は、P.ブルデューの言葉を使えば、将来の生活のための学歴と知識という文化資本を獲得するために行われる。(アダムスミスは、すべての人間を商人と見なしたが、ブルデューは「資本家」と見なすのである。)子どもたちは大企業に就職するため、有利な社会的な地位を手に入れるために、学校で「勉強」をする。学校での勉強の終点・目的は何らかの職業につくことである。(しかし、科目によっては学校の勉強が楽しいと言う子どももあるだろう。)
スポーツ・クラブや、中学校以上の部活のなかで子どもたちが行なうスポーツについて全く同じことが言える。(楽しいから通うと言う子どももいるだろうが。)子どもたちはいまやプロ・スポーツへの就職を目指してスポーツの練習に励むのである。勉強もスポーツも稼ぐための職業に就くことを可能にし、職業のなかで運用されて利益を生み出す、文化資本である。
エリアスはポーランド生まれのユダヤ人である。1920年代半ばに研究者としての経歴をはじめたがナチ支配下で教授資格を得ることは出来ず、33年以降はフランス、イギリスで亡命生活を送った。彼は母親をアウシュビッツで失った。
彼の主著は『文明化の過程』(上巻、赤井慧爾ほか訳、第一部「「文明化」と「文化」という概念の社会発生について」、第二部「人間の風俗の独特の変化としての「文明化」について」、1977年、下巻、波田節夫ほか訳、第三部「ヨーロッパ文明の社会発生について、まとめ 文明化の理論のための見取り図」、1978、ともに法政大学出版局)で、他にミヒャエル・シュレーター編/宇京早苗訳『諸個人の社会―文明化と関係構造』(法政大学出版局、2000年)、ミヒャエル・シュレーター編、青木隆嘉訳『ドイツ人論 文明化と暴力』法政大学出版局、1996などがある。
エリアスは亡命中の38年~39年に『文明化の過程』をバーゼルの出版社から刊行。英国では敵性外国人として抑留されるなどの苦労もあったが、54年に英国レスター大学の講師になった。69年に『文明化の過程』(第二版)と『宮廷社会』が刊行され、オランダ、及びドイツの大学で講義をするようになり、75年にアムステルダムに転居。77年80歳で、アドルノ賞を受賞。1990年死去。
エリアスは、競技や娯楽の活動を、それが行われていた社会のほかの諸活動やその社会の人々の価値観やものの見方、感じ方と関連付けてとらえ、スポーツの歴史を社会の歴史の一部、人間の諸活動全般の歴史的変化の一部として考察している。エリアスを通じてスポーツの歴史を知ることにより、単にスポーツの昔の姿を知るだけでなく、どうしてそれが現在のスポーツへと変化したのかについても知ることができ、また、スポーツの変化を通して人間社会の大きな歴史的変化を知ることができる。
私はもともと体を動かすことが好きで「する」ものとしてのスポーツが好きだったが、スポーツに対する知的関心はもっていなかった。だが、エリアスの著書を通じてスポーツに対する強い知的関心をもつことになった。また、だれでも、自分が生きている近代あるいは現代とはいかなる時代であるのかということは多少でも考えるであろうが、私は隠居後は釣りを中心としたせまい私的生活の瞬間瞬間の時間の流れに身をゆだねる毎日のなかで、歴史や時代を考えることをほとんど忘れていた。だが、エリアスを読むことで、改めて(スポーツだけでない)全体社会の歴史についても考えることができ、生活を豊かにすることができたと感じている。
エリアスは現代のレスリング(英語wrestleは「格闘する」ことである)と古代ギリシャのオリンピア競技の大会で行われていたパンクラチオンという格闘技を比べる。現代のレスリングでは、「フリースタイル」つまり規則が少なく自由に戦える様式のレスリングでも、試合時間、反則技が明確に決まっており、一人の審判、3人の審査員、時計係が試合を監督する。反則規定は相手に怪我を負わせる可能性のある暴力を禁止している。
だが、パンクラチオンでは、武器を使わないというだけで、あらゆる暴力が行使された。時間制限がなく一方が降参するまで続いた。眼をえぐりぬき、指、手足の骨を折り、噛み付くことが行われた。スパルタで行われたパンクラチオンでは頭、顔、耳を殴ってもよかった。この競技で何人もの男が殺されたという記録が伝わっている。一般に、殺されたり、重症を負ったり、生涯不具になることがしばしばあった。
噛み付いたり目をえぐりぬいたりすることは「慣例的には禁じられていたようだが、戦いの興奮に夢中になっている違反者を引き離さないうちに被害が及んだのだろう」とエリアスは言っている。初めてこれを読んで当時の「競技」のひどい暴力性に驚かない人はほとんどいないだろう。〔pancratium(英)の元のギリシャ語panはall、kratos,kratia(pl.)はstrength,mightの意味。したがってalmightyつまりあらゆるものに勝る(格闘)技、ないしはあらゆる力を行使してよい技を意味したと思われる。
前5世紀後半、スパルタとアテーナイがギリシャ世界を二分して戦った「ペロポネーソス戦争」を客観的・実証的に叙述したトゥーキディデース(ツキジデス)の『戦史』第5巻には、420年夏に「オリュンピア祭が催された。これはアルカイディア人アンドロステネースが第一回のパンクラティオン種目の優勝を得た年次である」というくだりがある。久保正彰訳『戦史』(岩波文庫)中、p319
パンクラチオンの壺絵
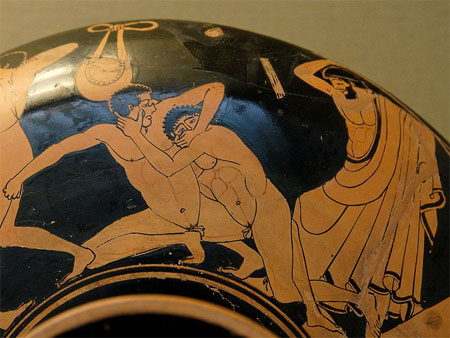 この写真では審判が選手(のどちらか)を鞭で打とうとしている。エリアスの述べている事からすれば、興奮している選手を手では止められず、通常、鞭で打ったのだろう。
この写真では審判が選手(のどちらか)を鞭で打とうとしている。エリアスの述べている事からすれば、興奮している選手を手では止められず、通常、鞭で打ったのだろう。
『驚異の古代オリンピック』(トニ―・ペロテット/矢羽野薫 訳 河出書房新社、2004年;『本で会いましょう』http://kaitekido.exblog.jp/18197392/ で紹介されている。)は、この絵の写真(元は壺絵であるがこれを平面に直したもの)を載せ、左の選手が相手の目を突く反則を犯して審判に鞭で打たれている、という説明を加えている。
確かにそう見えなくもないが、英語版Wikipediaでは逆に、右側の選手が相手の目をgaugeしようとしており、審判はこの反則のゆえに打とうとしている、と説明している。確かに右の選手が足を絡めて攻めており両手で相手の目を突こうとしているようにも見える。どちらの説明が正しいのだろうか。
エリアスによれば、肉体的暴力がほとんど規制されずに行使されたのは、「命をかけた戦いに屈しない肉体的強さを最高の美徳と考える価値観」と「暴力に対する当時の人々の一般的な感じ方」に関係がある。
古代ギリシアでは、美しい(見事な)肉体、強い肉体の能力が重視され、男性市民に勇気や忍耐力が求められた一方、人類史上にも稀な民主的な制度である(男性)市民全員参加の直接民主制を布いていたアテネにおいてさえ、身体障害者や高齢者が国の指導的地位につくことはなかった。虚弱な子供は放置され、死なせられた。肉体の美と強さ、忍耐力は人間の最高の卓越性をしめすものと考えられていた。オリンピアの競技会に出場する「運動選手の社会的地位は、現代の運動選手が維持している社会的地位とは全く異なっていた」。「オリンピア競技で優勝した人々のほとんどが彼らの彫像をオリンピアに、また時々彼らの故郷の町にも立ててもらった」。 他方、古代地中海世界では、同じギリシャ民族の都市国家間に戦争が起こった場合、勝った側は敵のポリスの男性をすべて殺し、女子供は奴隷にしたという。トゥーキディデース(ツキジデス)の『戦史』(アテネ中心の同盟とスパルタ中心の同盟の間の「ペロポネソス戦争」の記録)にもこうした皆殺しが報告されている。
都市国家内部においても暴力事件がしばしば生じた。近代以降の中央集権的国家においては、暴力行為を取り締まり、殺人や強盗などの事件が起こったときには裁きを下し処罰する強力な機関(警察や裁判所)が存在する。しかし、古代ギリシャ、都市国家内の「市民の生活防衛」は国家の「独占事業」にはなっていなかった。人々は個々の市民として、あるいは血族集団の一員として、私的な暴力を振るう機会と暴力を被る機会が多かった。誰かが殺された場合には、殺された側の血族集団が復讐を行ってかたをつけた。こうして、人々はポリス内部での喧嘩で、あるいは他のポリスとの戦争で、他者からの全く規制のない暴力にさらされたり、暴力の発生に直面したりする機会がいくらでもあった。
パンクラチオンをはじめとして、ゲームにおいて行使された暴力のレベルが現代に比べひどく高いことの背景には、日常生活の中で暴力を見たり行使したりすることが頻繁にあり、暴力に対する彼らの「道徳的反感、罪悪感のレベルはきわめて低かった」ことがあるとエリアスは言う。
古代ギリシャのパンクラチオンがレスリングの「原型」だとすれば、サッカーやラグビーなど近代スポーツの原型は英国中世の民衆の娯楽「フットボール」にある。英国における「フットボール」のスポーツへの変化はヨーロッパ世界の「文明化の過程」とともに起こった、という。
写真は英語版Wikipedia。folk/mob footballつまり民衆ないし暴民のフットボールだとしている。
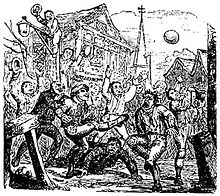
フットボールは、年中行事として設定されたゲームという楽しい形での、暴力の制度化されたはけ口、あるいは「半ば制度化された戦い」であった。社会の正常な年中行事としてのフットボールは聖人記念日や祝祭日に設定された。それは、「社会の基本構造に深く織り込まれたバランスの取れた種類の余暇活動」の一つであった。フットボールは宗教的な儀式の一つとして、伝統と一定の規則に従って行われたが、宗教的行為と世俗的行為の違いはあいまいで、教会の礼拝も「中世では現代の礼拝に比べてしばしば騒がしく、規律もなく、人々の日常生活に近かった」。
フットボールは近隣共同体の諸集団、地元のギルド、男女の集団、若い既婚、未婚の男たちの間で行われた。「若者たちは戦いたくてむずむずしていた」し、「フットボールは地元の集団間のわだかまった緊張をほぐすためのはけ口のひとつ」だった。
フットボールは時には「積もる恨みを晴らす機会として使われた」し、そうでなくても、しばしば「感情が高ぶったときには伝統的な慣例を破」ることも行われ、「いつ何時公然たる戦いに発展するかもしれな」いものだった。こうしたゲームを含む伝統的な習慣の「可変性」は、当時の人々の情緒性、つまり感情的で、気まぐれな性格と密接に関連していた。当時の人々は一般的に極めて感情的であり、子どもっぽく、衝動的に行動することが多かった。
暴力的なゲームは他にもあった。『スポーツと文明化』第8章で共著者のダニングが書いているが、ナパンというゲームは時々2,000人を超える参加者で行われた。数人は馬に乗って、しかも、雄牛や馬を殴り殺すこともできる太さの棍棒をもっていて、これで相手を殴った。このゲームには見物人はいない。というのも、見るだけの目的で来た人は、2,3発ぶん殴られて、ゲームに引き入れられたからである。
ルールや遊びの形式は、口で伝えられたものであり、また、地方ごとに異なっていた。そこには、観衆も、審判もゲームの規制者もなかった。民衆の興奮の高まりがあるだけであった。ダニングは「これら民衆のゲームは競い合っている集団の---相手に重傷を負わせたり、相手を殺したりすることがその本来の目的ではないという意味で、模擬戦であったのかもしれない。それにもかかわらず、民衆のゲームでは、公然たる暴力が示される割合が相対的に高く、相手に苦痛が加えられる機会がかなりあるということに、ゲームの楽しみの原因のひとつがあったのだろう」という。
中世においては貴族同士の決闘が認められていたし、また地方の有力貴族・領主が国王の命令に刃向かうこともしばしば起こった。だが、絶対王政が確立されるとともに、一般に暴力を行使すること、あるいは個人的な実力によって物事の解決を図ることは許されなくなり、暴力・強制力の行使は、その手段を独占する国家のみが行いうることとなった。実際には経済的な強制という形での暴力などいろいろの種類の暴力や強制の交じり合ったものが残存しているのだが、肉体的暴力は徐々に社会の日常生活という表舞台からは姿を消した、とエリアスは言う。
群雄割拠の戦国時代から家康による天下の統一を経た後、江戸時代にかけての日本においても、似たような社会の変化が進行したと言えるのではないだろうか。もともとは戦国大名で、徳川家の家臣となった藩主たちは、国王の宮廷、江戸城のなかで、暴力を行使することなく、礼儀正しい振る舞いをせねばならなくなった。こうして1701年、松の廊下で抜刀した浅野内匠頭長矩は切腹。また吉良邸に討ち入って主君のあだ討ちを行った47人も同じように処罰された。一般に暴力を行使すること、あるいは個人的な実力によって物事の解決を図ることは許されなくなり、暴力・強制力の行使は、その手段を独占する中央政府のみが行いうることになった結果だろう。
作家の有栖川有栖(ありすがわありす)は、江戸時代は「まじめ、勤勉」を良しとし、庶民の仕事、生活から文化・遊びの隅々まで、弾圧や締め付けを行いつつ取り締まり、「人々を管理したり支配したりした」時代だと言っている(2015.1.7.「朝日新聞」<オピニオン>)。これも「文明化」の進行と見ることができるだろう。
しかし、文明化は国家(の中枢機関)の権力の増大、権力の独占の動きと結びついて起こった、国家内部の過程であるに過ぎない。われわれは安全を保障してくれる権力の下にある限り、その内部集団に対する攻撃、暴力を控えようとする。しかし、一国(民族)の他国(民族)に対する暴力や攻撃を未然に防止し、諸国(民族)の安全を保障する上位の権力が存在しない国際関係においては、いったんことが起これば、暴力、攻撃が自制される保証はない。文明化によって、われわれが一般的に暴力を嫌い、生命その他の人権を大切にするような人間性を獲得したとは言えないし、「古代の野蛮な人々に優越している」などと考えることもできない、とエリアスは言う。
一般に国家の機能は、社会内部の個人や集団相互間の利害を調整し、紛争を押さえ、社会秩序を形成するとともに、外敵の侵入を防ぎ、それを保持していくことにあるとされるが、エリアスは、自国の生存を守るという国家の対外的機能を重視する。「生存単位」としての国家において人々は連合するが、その「連合の主たる機能は、ほかの集団による物理的破壊からの防衛、またはほかの集団の物理的破壊である」という。
こうしてエリアスによれば「文明化過程」において人々が同じ社会の構成員に対する暴力行使を嫌悪し、抑制するようになることは、その外の社会の人々に対する暴力行使を抑制する傾向を強めることにはなんら寄与せず、むしろ逆の結果を生む。他国、他民族との関係においては、いったんことが起これば、暴力や攻撃が自制される保証はない、と言う。人間のもつ攻撃的性格そのものがなくなったのではなく、人間性が根本から変化したわけではないと言う。
日本に関していえば、さきに見た江戸時代に進んだ「文明化」は、昭和における対外侵略戦争の過程での残虐行為を防ぐことには全くつながらなかったことに、その例証をみることができるかもしれない。
このエッセーを書く目的は隠居生活を楽しむことにあり、「戦争と平和」の問題を論ずることにあるのではないが、だからといって、イラク戦争以降の中東情勢や安保法制をめぐる日本の政治的動向に照らして、全く知らん振りを決め込んでいるわけにもいかないと感じる。だが不勉強でほとんど何も語ることができない。現在の論点に限っては、底なしの暴力の応酬にしかならない戦争は絶対に避けるべきであり、他国の戦争に巻き込まれること、他国を刺激したり他国との緊張を高めることにつながる政策を避けることに全力を尽くすべきであるといいたい。
大著『文明化の過程』第三部で詳しく説明されているように、中世ヨーロッパの国々では、貨幣経済の進展に伴い、貴族・戦士及び封建領主たちが没落した。とくにフランスでは、17世紀までに、国王による「物理的暴力の制度化された独占」と「課税権の独占」が進み、国王が他の諸階級、諸集団に対する絶対的な優位を占める絶対王政が打ち立てられ、大革命までの200年にわたって続いた。
だが、イギリスでは違っていた。17世紀、国王の支持者たちとピューリタンの非国教徒たちとの間に、血で血を洗う暴力事件が100年の間繰り返された。18世紀の多くの英国人は前世紀の内乱の再発を恐れた。彼らは「人間同士の暴力にうんざりしていた」。こうして、18世紀の最初の4半世紀くらいから、支配的な二つの党派は、以前なら政権交代がもたらしたであろう迫害、報復を抑制し、選挙による政権交代を穏やかに行なうようになった。そしてこの暴力を抑制する傾向の増大、すなわちイギリスの地主階級の議会主義化と相関して、かれらの娯楽のスポーツ化が進行した。
18世紀のイギリスでは、(ジェントリーと呼ばれる必ずしも貴族ではない)裕福な地主家族は、議会シーズン中はロンドンの家で数カ月を過ごし「都会生活の快楽―賭けごと、議論、社交界の噂話」に耽り、残りの時期を田舎で過ごすのを常としていた。こうした地主たちの生活様式はボクシングのような都会的見世物競技や、クリケットのような戸外の娯楽が「スポーツ」へと変化を遂げるのに役立った。
もうひとつ、政治における発展とスポーツの発展の関係を示す事情があった。専制君主国家のフランスでは国民の結社の権利が制限されていたが、イギリスでは紳士たちは自由に集まって自分たちの団体を作ることができた。「クラブ」制度はその権利の一つの表れであった。地方ごとに異なる伝統に従って行われていた狩猟や種々の球技のような娯楽は、紳士たちの自由な団体であるクラブによって規制されるようになり、クリケットはある場所からある場所へとチームが移動して行われいくうちに、地方クラブの統合が進んでいき、ある段階でメアリーレボン・クリケット・クラブMarylebone Cricket Club,MCCというロンドンのクラブが、国内全体の試合の効果的な統制権を受け継いだ。
18世紀半ばを過ぎたイギリスで生まれた政治状況は、いくつかの競合する支配的な集団間の適度に不安定な緊張のバランスだった。彼らは、「政権と権力の資源を暴力によって求めるのでなく、同意された規則に従って、言葉、投票、金銭によってのみ求めるという協定を」暗黙のうちに結んだ。この時期に、地主階級は「暴力を否定し、政府を規制したり、またとくに政府を交代させたりする議会の方法に必要な高度な自制の形態を習得した」。この時期、この階級は彼らの娯楽を「比較的穏やかで、より細かく調整された娯楽」であるスポーツへと変化させた。また議会における政権獲得競争は「楽しい緊張と興奮の機会を欠いていなかった」。「18世紀イギリスの政治制度の発展と構造と、同じ時期のイギリスの上流階級の娯楽のスポーツ化とのあいだには明らかな類似点があった」という。
では、それ以前の遊び・娯楽disportと区別されていなかったsportと、現在の「スポーツ」とはどこが違うのだろうか。あるいはsportという語はどのようにして現代的な意味をもった語として、それ以外の遊び・娯楽と区別されるようになったのか。
エリアスは近代スポーツのスポーツ性を、それ以前の「狩猟」とは異なる「狐狩り」を例にして説明している。初期のキツネ狩りは狩猟としてdisportであったが、18世紀にsportに変化した。狐狩りでも従来の狩猟でも動物を殺すことによる「わくわくする興奮」が追求される。だが、スポーツとなった狐狩りでは紳士たちは自分の手で狐を殺すのではなく、彼らの訓練された猟犬が狐を殺す。紳士たちは狩猟においては、追い詰めた動物を自らが殺すことによって快楽を味わうが、狐狩りのスポーツでは猟犬が狐を殺すのを見て楽しむ。狐狩りは暴力を行使することの「抑制の表現」なのだ。同時に、スポーツは「いささかも後悔しないで、つまり、良心の呵責なしに、闘争の興奮を楽しむ」形態であり、方法だ。そして、狩猟と違って狐狩りでは害獣を退治したりあるいは獲物を食べたりする実益は追求されない。実益を求める娯楽はスポーツではない。スポーツの本質は「楽しい緊張と興奮にある」。また、獲物を食べる楽しみがなくなった代わりに「すべてのルールは狩猟をあまり簡単にしないように、競技を長引かせるように、考案された」。こうして「競技に勝つことよりも競技そのものの長くて楽しい興奮に重点が置かれることへの変化」が起った。こうしたエリアスの説明を読むかぎり、古い楽しみ・娯楽の形態である狩猟と、新しいスポーツとしての「狐狩り」の違いは明らかである。では楽しみ・娯楽としてのかつてのフットボールは、それをもとに生まれたサッカーあるいはラグビーと全く異なったもので、スポーツと呼ぶべきではないものなのか。近代スポーツのスポーツ性はどこに求められるか。
2005年に施行されたキツネ狩り禁止法の緩和を求める動きを伝える2015年7月11日のThe Guardian紙(中道左派系とされる)の一面の写真

中世の娯楽「フットボール」、ナパンなどは現代のサッカーその他に比べ、ルールが明確でなく、審判もいなかった。そして流血の事態、乱闘が起こりやすかった。つまり暴力を抑制するための仕組みが整っていなかった。これは古代ギリシアのパンクラチオンなどの競技においても同じであった。そしてどちらの場合も、暴力手段を独占した国家機関が存在せず、日常生活において暴力が抑制されていない社会のあり方を背景に理解された。エリアスは旧い競技や娯楽の近代スポーツへの変化を「文明化の過程」の一部だと捉える。したがって、それ以前の競技や娯楽と異なり、スポーツでは選手の安全を主目的に作られたルールと、ルールを選手に強制する体制の構築とを伴っている点をエリアスはもっとも重視する。
文明化の過程において、「人生を通じて強い感情を抑制し、衝動や感情や情緒の規則的な自制を一定して続けることは、人間の内部に緊張をうみだすことにな」る。文明化による自然的衝動や感情の抑制だけがもし進んでいたら、いずれの社会においても人々はその抑圧が生み出す緊張に耐えられなかったであろう。スポーツは意図的、計画的に生み出されたものではない。だがうまいことに、スポーツという形で一定の枠の中でそれら自然的衝動や感情を発散する仕組みが生み出されたことによって、人々は緊張を適度に和らげ社会生活を続けることができた。あるいは社会は存続し続けることができた。スポーツは暴力や衝動的行動の抑制を求める文明化過程にある社会において、限定された仕方で暴力の行使が公認されている 「比較的穏やかで、より細かく調整された娯楽」である。
だが、それぞれの種目の暴力性の程度を基準にしてスポーツであるかどうかが決まるとエリアスは言うのではない。古代ギリシャのパンクラチオンや英国中世の「フットボール」では死者もでたというが、現在のボクシングでも死者はでる。暴力性の程度が異なるさまざまなスポーツないし娯楽が存在したし、今も存在するのであり、暴力性の違いを基準にするなら、「フットボール」がスポーツではないとすればボクシングはなおさらスポーツではないことになろう。
エリアスはパンクラチオンを説明しつつ、ルールが全然なかったわけではなく慣習的なルールは存在したという。しかし、近代になると暴力を抑制すること、生命の安全を確保することが重要だと考えられるようになった。こうして、どの種目のスポーツにおいても、選手の安全を最大限確保しようとする工夫に力が注がれるようになった。従来のすべての競技が文明化し非暴力的なゲームに変わってしまったとは言えないが、それぞれの競技において暴力の程度を減らすための工夫がなされ、その傾向が継続しているかぎり、つまり「文明化の過程」が続いているかぎり、それらはスポーツの特徴を有しているのである。
エリアスは、スポーツのもう一つの特徴として、勝利を急ぐのではなく試合を楽しむことが主眼になっている点を挙げる。ゲームである戦いを長引かせて「クライマックスに先立つ前快感を長く楽しむこと」がスポーツの特徴だと言う。だが、私はゲームの過程を楽しむことは古い娯楽にはない近代スポーツの特徴だとは言えないのではないかと思う。というのは以前の暴力的な戦いが主であった昔の球技でも勝ち負けは二の次で戦いそのものを楽しんでいたと考えられるからである。
フットボールは近隣共同体の諸集団、地元のギルド、男女の集団、若い既婚、未婚の男たちの間で行われた。「若者たちは戦いたくてむずむずしていた」し、「フットボールは地元の集団間のわだかまった緊張をほぐすためのはけ口のひとつ」だった。そして、フットボールは時には「積もる恨みを晴らす機会として使われた」という。もし、フットボールが本当の喧嘩であったなら、手っ取り早く相手をやっつけてしまうことに主眼がおかれることになろう。つまり勝ち負けが重要であっただろう。しかし、フットボールは社会の正常な年中行事として設定され行われた余暇活動だったのであり、戦いではあるが遊びの戦いであり、その戦いを楽しむために行われたのであろう。参加者はせっかくの楽しみを結果だけ求め短時間で終わらせずになるべく時間をかけて楽しもうとするのが自然だと思われる。
『スポーツと文明化』第10章、共著者ダニングによる「男性の領域としてのスポーツ」には1860年にラグビー校の卒業生が学校の雑誌に寄稿した文が引用されている。卒業生は軟弱になっている最近の試合を2、3年前のラグビーと比較している。スクラムを組んだときに彼の「仲間たちは---ボールが相手のすねを蹴るためのよい口実を与えてくれるとき以外は、ボールに目もくれなかった。---われわれはすでに5分間相手のすねを蹴っていたが、ちっとも十分じゃなかった。」
また、ダニングは、この卒業生の説明する初期のラグビーは「相手の一撃をよけたり、それを逃れたりすることを臆病ときめつけた---古代ギリシャのボクシングやレスリングを思い出させる。ラグビー校の卒業生は相手のハッキング〔すねを蹴る行為〕をかわそうとして、フェイントをかけたり、チームの同僚にパスしたりすることを「姑息」だとか「男らしくない」と考えた」と書いている。
要するに、初期のラグビーでも、ゲームの勝敗よりも、男として戦うことに重点が置かれていたのであり、選手たちはゲーム=試合の中に暴力を行使する快楽を見いだしていた。 ダニングはナパンなどの中世の民衆のゲームでは「公然たる暴力が示される割合が相対的に高く、相手に苦痛が加えられる機会がかなりあるということにゲームの楽しみの原因のひとつがあった」と言っていた。暴力行為が珍しくない社会においては、相手に重傷を負わせたり、相手を殺したりすることがその本来の目的ではないにせよ、暴力を行使することが楽しいことだったのだろう。
この観点に立てば、フェイントやパスを使って得点を挙げようとする近代的なプレーのやりかたは、ゲームの勝敗にこだわることであり、クライマックスを急ぐことであろう。初期のラグビーでは、楽しみの中身が後のラグビーの場合と違っていたが、後者と同様、初期のラグビーも、勝ち負けの結果ではなく、プレー自体を楽しもうとしている。初期のラグビーの選手たちも後の選手たちと同様「わくわくする興奮」を楽しむことを目的に戦いを行っていたのである。
それがスポーツと呼ばれようが昔のようにただの娯楽disportと呼ばれようが、余暇の楽しみにおいて人は時間が許すかぎり、時間いっぱい楽しもうとするのではなかろうか。仕事のように結果が問題であり、過程は結果に到達するための手段でそれ自体は重要ではないとするなら、出来るだけ早く結果に到達したくなる。しかし、遊び・娯楽は活動自体が目的である。競技スポーツが楽しみを求める活動だとすれば勝ち負けの結果を求めるよりもゲーム自体を楽しもうとするのは当然であるが、全く同じことがフットボールのような旧い競技についても言える。したがって、勝利を急ぐのではなく試合を楽しむことが主眼になっている、ということはエリアスの主張にもかかわらず、近代スポーツの特徴とは言えない、と私は思う。
次にエリアスは、狩猟に代わる狐狩りのスポーツの中にプレーヤー自身の暴力行使が減少する傾向とともに「見ること」により楽しみを得ようとすることへの重点移動が起こったことを示していた。つまり、スポーツにおいては観客とプレーヤーはともに参加者であるということがスポーツの三つ目の特徴とされていた。
しばしば死者も出た中世の「フットボール」やナパンにおいては、ジャッジもいないが見物人もいなかった。誰もがゲームに巻き込まれてしまい、関係者はすべてプレーヤーだった、とダニングは言っていた。また、街中でゲームが行われたときには、何百人という人がボールを追って目抜き通りを駆け回ったため、その並びの店舗や家屋は店を閉ざし、窓が壊されないように格子で遮られたともいう5)。つまり人々は「見物人」なしで、もっぱらプレーヤーとしてそれらゲームを楽しんでいた。
そうした事実からすれば、近代になって、見て楽しむことへの重点移動が起こることにより、スポーツ参加者の中にプレーヤーと観客の区別が生じたが、しかしその両者は参加形態・役割において異なるだけで、ともにスポーツの参加者であり、ゲームを楽しむという捉え方はもっともであるように見える。
しかし近代社会におけるスポーツと区別される、近代以前の社会における娯楽において、娯楽を楽しんだのは「行う人」だけで「見る人」、「見て楽しむ人」はいなかったのだろうか。あるいは現代社会において余暇でスポーツを楽しむ人々は同時に観客を持ち観客もそれに参加して楽しんでいるといえるのだろうか。すでにみたように「文明化過程の比較的後期の段階にある社会」つまり近代以降の社会では人々の暴力に対する感受性が変化し、ヨーロッパ中世における公衆の面前での絞首刑、猫の火あぶり、闘鶏などの娯楽は、暴力を不快だと感じる人が増え、次第に消滅した。
動物同士を戦わせたり、動物をいじめたり殺したりすることを楽しむアニマル・スポーツ6)では、動物をいじめる行為を行うプレーヤー(遊び手)だけでなく、見て楽しむだけの参加者、つまり見物人もいたであろう。見物人は動物の殺害に自らは加わらず、見て楽しむのだから、エリアスが「スポーツ」だという狐狩りのジェントルマンと同じである7)。また、見物人がはやしたてることにより、先頭にたって動物をいじめるプレーヤー(行う人)はいじめることに一生懸命になったであろう。
この構造は近代スポーツの試合における観客と選手の関係と同じである。盛んにとは言えないだろうが、闘犬、闘鶏、闘牛は現代の日本で行われているアニマルスポーツである。これらにおいては、キツネ狩りにおけるジェントルマンたちが飼っていた猟犬と同様に、飼育・訓練された犬、ニワトリ(シャモ)、牛がplayerであり、その飼い主は(ほかの観客とともに)「見る人」として参加する。これらは近代以前の社会で楽しまれた娯楽が今に続いているものである。また、伝統行事の中には虫を戦わせるものがあり、四国のニュースではしばしばジョロウグモがplayerである「クモ合戦」が取り上げられる。中国には唐の宮廷で始まり1200年の歴史を持つ闘蟋(とうしつ)と呼ばれるコオロギを戦わせる娯楽がある。大会が催され、闘蟋戦士の育成、管理、試合実施に使用される様々な容器、器具も発達しており、それらは伝統工芸品としても一大文化を形成している(「ウィキペディア」)、という。
これらアニマルスポーツは近代以前に始まった娯楽であり、スポーツと考える人は少ない。しかし、キツネ狩りと同じようにplayerだけでなく、飼育する人が「見る人」として参加しており、野球やサッカー、ラグビーと同様、ワクワクし興奮しながら戦いを楽しむ観客が「参加」している。 アニマル・スポーツがこのようなものである(あった)とすれば、プレーヤーと観客が共に参加者であるということを、とくに近代スポーツの特徴とすることはできないように思われる。
最後の、獲物や実益が無く純粋にプレー(遊び)を楽しむという特徴についてはどうか。
エリアスは18世紀末に書かれた、BeckfordのThoughts on Hare and Foxhuntingを引用している。ベックフォードはこの本のなかで、「釣りは退屈な娯楽で」あり、「狩猟は仲間を受け入れる余地があるが人は多くはいらない。できるだけ多くの人々が歓迎される狐狩りに比べて、両方とも個人的で孤独な娯楽である」と言っている。ほとんどの釣りは、(見る人が)馬を駆ってキツネを追いかけるキツネ狩りや、ボールがあちらこちらに飛び、選手の体と体が激突しあうラグビーやサッカーのように、観客を興奮させることはできない。また、魚を掛け、寄せようとしている釣り人は興奮していても、見ているだけで魚の引きをじかに感じることのできない観客を興奮させることはない。一般的には釣りや狩猟は「個人的で孤独な娯楽」なのである。〔ただし、幾分、大物釣りの経験がある私はテレビやYouTubeの動画で見たマグロなどの大物を釣る釣りは、漁師の釣りであれ遊漁船の客の釣りであれ、「興奮」を感じる。〕
他方、エリアスはスポーツは近代社会の文明化(礼儀正しさ、感情や衝動のコントロール、計画性などの重視)がもたらすストレスを適度に解消する機能をもつと捉え、スポーツにおけるワクワクする興奮、感情の発現を可能にする面を重視する。プレーヤーが獲物や実益なしに闘いに集中することがゲームを面白くし観客を興奮させることになるがゆえに、その点を、ほかの楽しみ・娯楽と区別された、スポーツの特徴とするのである。私も、楽しみ、遊びには様々な特徴をもったものがあるだろうが、スポーツの特徴をそのようなものとみること、あるいは、そのような特徴を持った遊び・娯楽をスポーツと呼ぶということには異論はない。
エリアスの説明に基づきつつ、それに多少の意見を加えた形で、私は近代スポーツのスポーツ性を以上のように総括しておきたい。
彼によれば「文明化の過程」は、科学技術の発展と工業化による自然の制御、議会制度や民主主義の発展に表れている人間相互の連関つまり「社会連関」に対する制御、そして個々の人間の自制つまり自己自身の制御という三つの側面からなる「制御」あるいは支配の度合いの増大として捉えられる。換言すれば、人間は文明化の過程を通じ、個別に自然に立ち向かって生きるのではなく、社会的存在として、社会を通じて間接的に自然に立ち向かうというしかたで生きる傾向を強めてきたが、このために、社会に適応し、社会が求める行動様式を習得し、この様式に従って自己をコントロールして行動する傾向を強めてきたのである。
産業化とともに、社会は次第に複雑化し、専門化された多数の仕事に携わる大勢の人々の間の相互依存の関係を生み出してきた。この相互依存の長い複雑な連鎖を通して多数の行為が無駄なく、期待された成果を生み出すことができるためには、その鎖の一つ一つに位置する人々の行為が一定の枠におさまり、パターン化された仕方で行われる必要がある。
社会の細分化、複雑化につれ「個々の人間は自分の行動をますます細かく、ますます均質的に、ますます安定性を持って規制することを余儀なくされる。その際この規制が意識的なものにとどまらないということ---、より安定した規制が幼少のときから個々の人間に自動的な行為として、意識の中で思っていても抵抗できない自己抑制としてますます叩き込まれるということが、文明化の過程における心理的装置に特徴的なのである」。法的規則の遵守は、それに違反し罰せられないように「正しく」行動しようという意識的な自己抑制である。他方、社会慣習に違反して行動することを「重苦しい不安という壁によって妨げようとする」「心理的装置」、「自動的な、盲目的に働く自己抑制装置が固定」化される(『文明化の過程』)。
「以前の戦士社会では、力と権力が十分に備わっていれば個々の人間は暴力を振るうことができたし、---おおっぴらに自分のしたいことをすることができた。しかしまた、代わりに大きな口を開けて待っている直接的な恐怖に襲われる機会も多いことを覚悟しなければならなかった。快感も不快感もより公然と、より自由に外に向かって発散することができた。しかし個人はその虜であった。個々の人間は自然の諸力に振り回されるように絶えず自己の感情にあっちこっちと振り回されていた。個々の人間が自己の激情を思いのままに操ることよりも、それらに操られることのほうがはるかに多かった」(同書)
国家によって暴力独占が形成されるとそこに平和な地域、普通の状態では暴力行為など起こらない社会的な場が生じる。実際には経済的な強制という形での暴力などいろいろの種類の暴力や強制の交じり合ったものが残存しているのだが、肉体的暴力は徐々に社会の日常生活という表舞台からは姿を消す。
「こういう社会では個々の人間は突然の襲撃や自己の生活が肉体的暴力によって衝撃的に侵害されることから広範囲に守られている。しかし同時にかれは自分のほうでも激情の発散や他人の肉体に攻撃を加えたいという沸き立つ心を押さえつけなければならない。----機能分担の進展に従って個々の人間が巻き込まれていく相互依存の編み合わせが密になればなるほど、----激昂や激情に身をゆだねる個々の人間はますますその社会的存在を脅かされるし、情感を抑制できる人はそれだけいっそう社会的に得をすることになる。個々の人間はそれだけになおいっそう幼いときから長い人間関係の連なりを超えて遠くまで自分の行動の影響や他人の行動の影響を考えざるを得なくなる」(同書)。
現代社会には、人々の行動を規制する「束縛の二重の輪」つまり、警察その他「法律とその代行者」による「外的束縛」と「良心や理性のような個人的抑制」つまり内面化された抑制が存在する。「自己の感情を絶えず規制し、作り変え抑圧しようとする」この「独特な習慣作り装置」により固定化されたものが「超自我」である。「そのおかげでわれわれは、相互依存のきわめて複雑な構造に従って、われわれの行動に方向を与え、かつ調節できるのみならず、それによってわれわれは、瞬間的な衝動の高まりから、よりいっそう解放され、〔適切な〕決定のためのより大きな余地を与えられることにもなる」8)。『スポーツと文明化』
エリアスは「慣例」を「他者との相互依存によって強要され、行為におけるかなり高度な規則性や着実さ、感情の抑制を個人に課し、他の行動の方向を、たとえそれがそのときの気分、感情、情緒的欲求ともっとよく一致していたとしても、阻んでしまうような周期的な〔習慣的に繰り返される〕行動の方向として」定義する。同書
慣例化は人々に対して、他者の欲求に答え、非個人的な仕事を遂行することができるように、感情や気分を抑制し、行動を一定の枠の中で行うよう求める一種の強制である。慣例に従い社会に依存して生きることによって人々は、独力で、自給自足で生活する労苦を免れることが出来る。だが「他人とともに生きている」がゆえに衝動や感情を抑えなければならない(「自分では抑えきれない感情の発作に支配されてひどく興奮する人々は病院か刑務所にふさわしい患者」として扱われてしまう)というだけでなく、「自分の衝動のなすがままに」他人を攻撃する子どもは、そのままでは「幼少期を過ぎて生き長らえることはできないし、偶然に生き残ったとしても、ほとんど人間的になることはなかろう」。
私は、子どもの頃ひどく「短気」で喧嘩しやすく、年上の子どもにも飛び掛っていったと母親から聞かされたことがある。どうのようにしてか中学生になった頃から喧嘩をしなくなった。男が家庭で妻や子どもに常習的に激しい暴力を振るうDVと呼ばれる事件が起こるが、こういう人は子どもの時の攻撃衝動をコントロールできないまま大人になってしまったのかもしれない。「自制を習得することは人間の普遍性であり、人間性の共通の条件だ」とエリアスはいう(同書)。こうしてエリアスは、一面では、人間が生きていく上で慣例化、自制の習得には重要な意味があることを指摘する。
自制を習得することによって人生は、「ある意味では危険の少ないものになるが少なくとも快感を求める心の直接的発散については情感や快感に乏しいものになる。以前、人間対人間の闘いの中で直接解消されていた緊張状態や激情のある部分が、今では人間が自分自身の心の中で押し殺さなければならないものになる」。そして、「もはや人間相互の関係の中に直接現れなくなった衝動や激しい情感が、今度は個々の人間の心の中でしばしば彼自身の監視している部分に対して、それに劣らぬ激しさで戦いを挑んでくる」(『文明化の過程』)。 エリアスは、社会生活における、枠にはめられパターン化した人々の行動のあり方を「慣例化」と呼ぶ。たとえば、時間を守ること、欠勤しないこと、感情に振り回されないこと、仕事に私情を持ち込まないことなどが「慣例化」された行動様式の例と考えることができるだろう。エリアスは文明化の進行する現代社会は「慣例」が人々の支配的な行動様式になっている社会だと言う。
また76年に書かれた<性の歴史>Ⅰ、『知への意志』においては、近代社会は国家が住民の健康を管理し、保護し、人口を調節するとともに、国家としての生存を確保するという目的のために国民を戦争に動員する、「バイオの権力」が支配していると言う。「バイオ」は生命、生活、生存を意味する。ただしフーコーの言う権力は、一部のグループが持っていて、他者を一方的に支配し服従させるために用いることのできる何かではない。権力(の関係)は網の目ように社会にひろがり、政府と国民、役所と住民、経営者・資本家と労働者などの間ばかりでなく、親と子、夫と妻、男と女、教師と生徒・学生、学校と父兄、医者と患者、等々、関係しあう人々の間で、力の配分を求めてなされる行為のすべてを貫いているものである。人々は何ものにも拘束されることなく自由に決断したり行動したりすることのできる「主体」(sujet)ではないが、同時に絶対君主に従属する単なる臣民(sujet)のような存在なのでもなく、交渉したり、抵抗したりして、力の向きを変えたり修正したりすることもできる。バイオの権力がすべての人々を貫いていることはよくわかる。渡辺守章訳『知への意志』新潮社、1986。 エリアスに即して言えば、「慣例化」=規律訓練は資本家の意向を体する政府=警察によって強制されているのでなく、職場や家庭などいたるところで、各人の性向により異なる「良心や理性」にしたがって、それらに進んで従ったり、批判的態度で抵抗したりする、権力の網の目(の一つ)をなしつつ行動することによって、強化したり弱めたりしているのである。

(2013年現在)28歳の息子はダウン症による知的障害者である。障害者自立支援事業を行うNPO法人が運営する事業所に週5日通い、大型公共施設に併設されたレストラン(「キッチン夢屋」)での接客サービスの仕事とゴミの分別およびマンションなどの清掃(「ハッピー・クリーン」)の仕事を1日おきに行う。1年間の見習い後、本雇いになって半年経つ。朝9時過ぎくらいまでに事務所に集まりそこから数人の他のメンバーやスタッフ(ジョブコーチ)と一緒に車で仕事先に移動する。事務所までは自転車でいく。
8時半に家を出れば十分に間に合うが、遅れると他の人を待たせることになる。事務所への到着が9時15分をすぎると「遅刻」で注意を受ける。家を出る1時間前に起きれはよいのだが、起床はいつも8時近くになる。私は6時前に起き、新聞を読んで、具沢山のサラダを作り、コーヒーを入れて、7時半には朝食をする。私はパン食だが息子はご飯食で別におかずを用意する(前日の夕食の残りということが多いが)。7時過ぎくらいからカーテンを引いて明るくし、ラジオの音を大きくし、7時半になると「そろそろ起きよう」と声をかける。最近では1、2回声をかければ自分から起きることが多くなったが、それでも時々8時近くまで起き(られ)ないことがある。持ち物などの準備は前の晩にできている。しかし、出かけるまでに30分か40分しか時間がないのに、顔を洗ってすぐに食べ始めるのではなく、まず新聞を読む。ETVの子ども番組、水戸黄門、名探偵コナン、ドラえもん---等々。声を出しながら10分以上かけて読む。それから10分くらいでご飯を掻きこみ、歯を磨く。
この30~40分がヤキモキすると言おうかなんと言おうか、息子の動きが非常に気になる。台所の時計を見ていることもあるので、針をこっそり10分ほど進めてみたが、結局、早すぎず遅すぎず、彼が最適と考える時間に事務所に着くように(彼は時々遅刻をするが他のメンバーも同様らしい)、家を出る「時刻」、あるいは「時計の針の位置」を決めているらしく、針を進めても数日のうちに「適応して」、その分(ぶん)遅く家を出る。私が我慢できず「もう時間がないよ」とか「新聞は帰ってきてからまた読めば」と言っても、馬耳東風。ゆっくりと新聞を読み、そしてご飯を少しも急がず、とはいえ10分ほどで食べ、またゆっくりと歯を磨いて、出かける。「急いで!」と言おうものなら、ますます動作を遅くするようにさえ感じられる。
写真は「ハッピー・クリーン」の作業着姿の息子
彼の時間に対する感覚は私と全く違う。彼は自分の身の丈に合わせて作った時間の衣服を着用している。私は時間にせかされながら行動することを嫌いつつ、いつも遅刻しないように、相手との約束の時間に遅れないように努力してしまう。私は近代の特徴である、時間による人間と社会のコントロールという窮屈な衣服、あるいは鎧を憎みながら自分のものとして身に着けてしまっている。
だからエリアスのいう自制と慣例化、フーコーのいう「規律・訓練」への「主体的服従」は現在の私の生活に対してきわめてリアルなあるいはアクチュアルな意味を持っている。生きるためには社会の構成員として働かないわけにはいかないが、働くことが生きがいであるかのように自分から進んで働こうと考える必要はないのだ。あるいは人々が規律正しく行動すること、また、世の中が整理整頓されていてきちんと管理が行き届いていることは、仕事の都合のためであり、それ自体、よいことでも立派なことでもなく、私は私であり、経済成長を目指して走り続けるための機械・機構の一部品になろうと努力する必要はないのだ、等々、私の頭はそのように言う。しかし、私の心と体は社会の「慣例」、「規律」に従うことへの要求の圧力を無視することができないでいる。一方でその圧力に反発し、ときおり、人並み以上に抵抗もするが、またその社会の中に拡散して働いている見えない権力に「主体的に」、「自発的に」従ってしまう自分がいる。息子が10分あるいは5分遅刻するのではないかと毎朝やきもきしている私の姿は、明らかに、こうした管理社会の要求に自発的に服従している「臣民」の姿である9)。
ロンドンの鉄道はよく遅れる。そして謝らない。現地で暮らし始めたころ、よく腹を立てた。ふとホームを見渡すと、イライラしているのは自分だけだった。事故を起こした運転士は事故の直前、たった80秒遅れただけで、「日勤教育」という名の懲罰を逃れることで頭がいっぱいだったと報道されたが、こうした背景を知った三宅さんは「日本でしか起きない事故だと思った」という。
英国では最終駅への到着時刻の遅れが、近距離なら5分以内、長距離なら10分以内であれば、「定時運転」とされる。日本では一分でも遅れると「定時」ではない。事故後JR西日本は各線でダイヤに余裕を持たせた。しかし50代の車掌は「事故後にあれだけ『もっとゆとりを』と言われたのに、利用客は相変わらず遅れに対して厳しい」と言う。「電車が2、3分遅れると、---「遅れた。謝れ」などと乗客に怒鳴られることがある」。
効率化、高速化に突き進み、社員を追い詰めていったJR西日本を、なぜ止められなかったのか、取材を進めながら考えた。「一つの方向に進みだしたら、異論を許さず、突っ走ってしまう社会も問われている」。英国では鉄道の高速化について賛否両論の立場から議論が盛んに行なわれているが「日本ではリニア〔モーターカー、リニア新幹線〕に水を差すような意見を言えば、「反日」とさえ言われかねない空気を感じる。タイトルの「Brakeless(ブレーキのない)」は日本社会も指している」。2015.4.25「朝日新聞」34面「宝塚線事故10年 答えは」
エリアスは『スポーツと文明化』「序論」で、1984年に書いたUber die Zeit(時間について)で行った社会的時間調節の長期的変化の研究が文明化の過程における社会的人格構造の長期的変化を裏付ける証拠(の一つ)となった、と述べている。時間を守ることが文明化過程と、そして慣例化に順応する人格構造とつよい関連があることはよくわかるが、日本ではとくに政府や企業その他の執行部などが提出する計画に賛成しないものを「抵抗勢力」と決めつけるなど、自由な議論、異論を抑圧する傾向が強いことが、いっそう、慣例化圧を強めている。日本は世界で最も「慣例化」の強い社会ではないか。
めん処・矢磨樹(ヤマキ)で働く大地

2016年3月追加:大地が現在のNPO法人の支援で仕事を始めてから4年たった。大地の常習的遅刻は変わらず続いている。
定期的に行なわれる事業所スタッフと保護者及び本人の最近の面談で、職場変えの提案があり、遅刻しても、車で仕事先に移動するメンバーを待たせないですむ、職場を提供してもらえることになった。集合場所であるNPOの事務所と同じ建物内にある、うどん店での仕事に変えてはどうかという提案である。
ここのうどん店は本来は、見習い期間の間だけ勤める場所である。本雇いになるとみな他の場所で働く。しかしここで仕事をすることになれば、9時15分の入社時刻に遅れても、車が出発する時刻を気にしなくてすむ。大地が慌てて自転車を走らせて交通事故に遭う心配もなくなる、とスタッフは言う。
大地の場合には、いったん身についた行動パターン、習慣を頑固に続ける。「時間を守る」、「スケジュールにしたがって行動する」というような世間の常識に従うように、彼を変えることは無理だと事業所スタッフは判断し、代わりに、事業所の仕組みを変え、大地に合う仕事(職場)を新しく作り出してくれたのである。事業所側の配慮を本人が理解したかどうかは怪しいが、私はとてもありがたいと思った。そして、障害者が働きやすいように職場の条件を整える今回の措置は、障害者の自立支援のために大いに好ましいことだと思った。
スタッフの一人は、時間厳守というのは健常者にとっても必ずしも簡単なことではないと、言っていた。近代社会、近代日本では10分、15分はおろか、1分、2分のちがいも許そうとしない。(最近のNHKのアナウンサーは、「ただいまの時刻は○時△分40秒を少し回ったところです」などと言う。放送局と同様に秒単位で世の中が動かなければならないと考えているようだ。)10分、15分のズレを気にしないで生きられる社会になれば、われわれが生きていく上で負う精神的ストレスの大半がなくなるのではなかろうか。
魚介類加工場で働く大地
エリアスは『ドイツ人論』で、ナチスの戦争政策を支持してつき従ったドイツ人特有の「国民性」、その背景をなす国家と社会の歴史、そしてナチス、国家社会主義者たちの特異な、宗教的ともいえる空想的な国家についての神話の信仰と人種思想についてきわめて具体的に説明し、その人種政策が「文明化の挫折」(エリアス)であるゆえんを詳しく述べているが10)、ホルクハイマーとアドルノは、ナチスの「非合理主義」、「むき出しの暴力」を、非常に抽象的なかたちで、人間の「理性」の働きの結果として説明する。日常的には「感情を抑えて理性的に事態を捉える」などと言うように、理性は衝動や感情とは別の、それらをコントロールする能力であると思われている。しかし二人によれば啓蒙あるいは理性とは、内容つまり行為や判断に統一性、あるいは首尾一貫性を与えるという単に形式的な働きをするものにすぎず、行為や判断の善悪を根拠づけるものではないという。『啓蒙の弁証法』の内容を紹介する。
二人は「知は力なり」の語で知られているF.ベーコンを啓蒙思想の代表例としてあげる。ベーコンは、知識あるいは「学問の真の目的と職務」は自然の支配、利用にあるという考えを明確に述べているが、そうした知識/学問は「一つの普遍的科学」でなければならない、つまり科学/学問の本質的な特徴はそれが統一的で体系的なものでなければならないと考えた。
また著者らは、カントの『純粋理性批判』を引用しながら、「理性が寄与しようとするのは体系的統一の理念、つまり堅固な概念的連関という形式的原理以外の何ものでもない」という。啓蒙は一般的には魔術や神話の世界から人々を解放したといえる。しかし、著書らによれば、神話によって「報告し、名付け、起源を言おうとする」行為は、とらえどころのない塊のようなものとして現れる自然・世界を、言語によって対象化し、人間の感覚や思惟〔概念〕の枠組みによって分類、整理、確認・説明する働きであり、理性の働きである。ユダヤ=キリスト教や古代ギリシャのゼウスを主神とする民族宗教も、それ以前の土着の宗教や神話や呪術を批判しつつ生まれたもので、それらも実は啓蒙的思惟の働きであったのだという。こうして啓蒙は人間が言語を使い始めたのと同じくらい古くからある思惟の活動の現われなのである。ところで啓蒙の目的は、自然に対する人間の恐怖を取り除くこと、自然による人間の支配から逃れること、自然をコントロールし支配することにあったと著者らは言う。
私は自然を理解し恐怖を取り除くことと、自然を支配し利用しようとすることとの間には違いがあると思う。哲学史的に言えば、アリストテレースの哲学を代表とする近代以前の哲学知scientiaにおいては自然・世界はテオーリアつまり観照し、理解し、説明することが目標であった。近代になってベーコンとほとんど同じように哲学の目的は自然の支配にあると言っているデカルトとベーコンにより学問が自然支配の道具、科学scienceと位置づけられた。そしてガリレオやニュートンらによる「科学革命」で実際にその一歩が踏み出されたと理解している。つまり理性(哲学的探求)は一貫して自然支配を目指す働きであったわけではないと考える。
しかしホルクハイマーとアドルノによれば、まだ神話と混じり合っているホメロスの『オデュッセイア』に描かれているように、「自然」、つまり良心の疚しさを感じずにセックスや食の動物的快楽に永遠に浸るという(清教徒=プロテスタントから見れば)おぞましい状態への「頽落」、甘美な幼年時代への退化の誘惑(セイレーンの歌声)に抗ってはじめて、人間は文明化され、進歩を遂げてきたのだが、 それは命令を下す支配者・管理者とそれにしたがって禁欲的に働く被支配者・労働者とに分かれて協力する分業の仕組みを通じて達成されてきた。つまり自然の支配は、より効率的、合理的=「理性的」な人間支配の仕組みを生み出すことによって達成されてきたのである。
だがその進歩は同時に人間性の退歩であった。なぜなら「支配の持続は生活が技術によって楽になってくる一方、より強い抑圧によって本能の硬直を引き起こすからである。創造力は萎縮する。--進歩の力への適応の中には権力の進歩が含まれており、そのつどふたたび退歩への営みが含まれている。つまりその退化は不成功に終わった進歩なのではなく、まさしく成功した進歩こそがじつは進歩の反対であることの証拠になる」ような退歩である。
啓蒙哲学者の一人とも言われるカントは、人々が、聖職者たちの教説や君主たちの命令に従って行動するのでなく、自らの理性にしたがって行動するべきことを説いた(『啓蒙とは何か』)。しかし彼の説いた理性は結局形式的なもので、統一性や論理的一貫性を意味するものでしかなかった。彼の掲げる道徳法則、「定言命法」は、相互愛と尊敬に基づく人間の共同体という理念を背景にしているがこの理念自体を基礎付けることはできない。定言命法は結局「理性の事実」であるような道徳法則への尊敬という「形式」にすぎないことが明らかである。こうして「倫理的諸力は---権力との融和へ向けられた場合にはたちまち非倫理的諸力へと転化する。---定言命法にそむいて11)、そしてそれだけいっそう深く純粋理性に同調しながら、ファシズムは人間を物として、---扱う」と著者たちは言う。
こうして人間は、啓蒙の理性、つまり統一性、論理的一貫性を求める理性に基づいて、とくに近代において、科学・技術的知識を発展させるとともに分業を発展させることにより、また労働者を管理・支配する技術を発展させることによって、そして初期プロテスタントたちのように勤勉・禁欲の倫理によって自己自身である自然、つまり自然的欲望や快楽への欲求を抑制するという仕方で生産・労働に打ち込むことによって、文明化、進歩発展を続けてきた。だがそれは人間の社会的な支配と隷属の関係を拡大再生産することであり「文明の一歩一歩」は野蛮への進歩であった、と著者らは言うのである。
古代ギリシャのアテーナイにおいては、一部の者、つまり男性で貴族を含む上層市民は、女性や身体的弱者、他国民、他の民族を犠牲にし、支配することによって、不自由のない暮らしをするとともに、近代的な異性愛にとらわれることなく性欲を満たし 、さらに政治的平等、スポーツや芸術や学問を満喫することができた。彼らは他者を犠牲にすることによって人間的な自由と幸福を享受することができたのだと言えなくはない。しかし、『啓蒙の弁証法』の著者によれば、支配者たちは、現代の資本家=経営者を含め、自然を支配するための道具である社会を担う主体として、社会的機能を果たしているにすぎない。支配される大衆、労働者が疎外された状況に置かれているのと同様、支配者たちも非人間的な野蛮状態にある。
「訳者あとがき」の徳永の文を引用すると「人間はさまざまの試練を克服しつつ、自らを支配する主体として自己を形成し、同時に他者を客体として形成することで世界を支配する。言い換えれば、人間は「外なる自然」を科学や技術によって支配し、「内なる自然」を道徳や教育によって支配することによって、さらにそれらを社会的に支配することによって、自己を主体として確立してきたのである」。そして、「〔いまや〕啓蒙は、現代に奉仕して、大衆に対する全体的な欺瞞へと転進する」という文が『啓蒙の弁証法』の全体をなす暗い基調を示している。しかし、訳者・徳永が言うように、単に理性の崩壊が描かれているのではなく、理性がそれを克服する「自己批判能力」を有することについての示唆と思われる箇所がなくもない。しかしあいまいで具体的な方向性は何も示されていない。人類の未来を楽観視する気分には到底なれない。
エリアスは人生を通じて「感情を抑制し、衝動や感情や情緒の規則的な自制を一定して続けることは、人間の内部に緊張をうみだす」ことになり、現代社会におけるような「慣例化」された生活の中では、人々のあいだに「抑圧の緊張が広がっている」。そして、諸個人の衝動規制の内面化は、「特別な欲求不満、多くの苦痛や苦悩」、「多くの病気を結果的に生み出すことは明らか」だという。
慣例化された社会では、人々は時間を守ること、欠勤しないこと、感情に振り回されないこと、仕事に私情を持ち込まないことなどに努力する。職場の同僚から仲間はずれにされることがあるかもしれない。上司からパワハラ等のイジメを受けるかもしれない。だが、怒りを呑み込み、冷静さの仮面をかぶって仕事を続けようとするだろう。また、家族があり自分が稼がねばならないという意識が必要以上のがんばりを生むだろう。結局こうしたストレスに耐えられなくなって、うつ病などにかかってしまう人がいても少しも不思議ではない12)。
エリアスは『ドイツ人論 文明化と暴力』において、ナチズムについて考察している。彼は、ナチスの運動の「独特の成功」を理解するためには、「1930年ごろの重大な経済的危機とかそのために激化した階級闘争」などの「特定の短期間の展開に着目する」のでは不十分で、ドイツの長期的発展をもとにして考察する必要があるという。大まかに言えば、エリアスは数世紀にわたる「分邦体制」つまり多数の領邦国家に分裂し対立を続けてきたドイツ、そして繰り返し他国との戦争で敗北し国土を蹂躙されてきたドイツの歴史を背景として重視する。そして、ドイツの統一を長期にわたって念願してきたにもかかわらず、近隣諸国のように中産階級の手で君主と貴族の古い支配を打ち倒し統一を成し遂げることができず、1871年の統一においても結局絶対君主国家プロシャの軍事力にたよらざるを得なかった中産階級の自らの無力感(法治国家および議会制民主主義主義への懐疑)とその裏返しとしての英雄待望論がナチス政権を可能にしたと分析している。
彼はドイツの歴史の一部として、20世紀はじめごろから、学生団体である「学友会」のあいだで行われていた「儀礼的決闘」について説明している。中産階級出身者は、貴族(宮廷貴族と軍人貴族とがあった)とは違い、大学教育を受けて初めて高級官僚となり上流階級に近づくことができた。大学による「純粋に学問的な教育を補」い、「国務に就くのに必要な性格を形成するため」の「準備段階」の役割りを「学友会」が果たしていた。当時は一般的には決闘は禁じられていた。しかし上流階級の決闘は黙認されていた。決闘は貴族が個人的名誉にかかわる争いを、国家の法律に従い裁判に訴えるのでなく自分たちの間で決着をつける権利であった。 貴族たちは、法律やその他の装置は大衆の間に秩序を維持する道具であるが、戦士であり支配者たる自分たちは国家秩序を維持する者である。自分たちは国家の主人なのであり、自分たちは自分たち自身が定めた規則にしたがって生きる。じぶんたちには国家の法律は通用しない、と考えていた。
学友会の学生を通じて、国家による暴力の独占(法治主義、議会主義)に反抗する、こうした支配階級のイデオロギーが中産階級の間に広まった。『ドイツ学友会の歴史』によると「祖国の政治的教育や学問的教育や倫理的教育や身体の訓練はなおざりにして、武装した学生の精神ばかりが前面に出て、外面的な事柄を気にする風潮がたいていの学友会に生まれた」という。それだけではない。
当時は学友会同士の強さを競う、対抗試合のような形で、決闘が行われた。下級生は上級生の命令にしたがって、スポーツの試合に出場する選手のように、決闘を行わなければならなかった。負傷の危険はもちろん命を落とす危険もあった。しかし、拒めば、全国的な組織を持つ、学友会から追放され、それはエリートへの道を放棄することあるいは人生そのものを否定することと同じであった。エリアスは言う、非常に形式化されていたにしても肉体的暴力をふるうことが人々の交際において許され求められさえする社会においては、肉体的に強いほうが相手に無礼を働いたり相手のうちに弱点をみつけたりしてそこに快感や喜びを感ずるような感じ方や付き合いかたが助長される。肉体的に強いものや巧みなもの、攻撃的人間や乱暴者や暴れ者に、他人を独裁的に支配して社会的に尊敬される機会を与える。決闘は、そういう集団では支配的な特殊なタイプの交際戦略の特徴であるとともに、人間の特殊な評価の特徴でもあった。
ここで培われた人格構造をもつ人間は次のようなものである。他者に対する同情をもたない。弱いことがわかったものには価値を全く認めない。自分より弱いものは殴って自分の優位と相手の劣っていることをすぐに明確に思い知らせるように振舞う。そうしないことは弱いということであり、弱さは軽蔑すべきものである。
このような「学友会」の決闘儀礼によって培われた上流階級のエートス、あるいは人格構造が、ナチスのむき出しの暴力を容認することにつながったとエリアスが言おうとしていることは確かだが、こうしたエートス/人格構造の持ち主がナチスの運動の直接の担い手だったとは言っていない。それは当時のドイツ中産階級が有した「国民性」の一側面であり、またそれはナチスの国民的成功の一要因に過ぎない。
ナチスは腹を立てるとすぐに部下を足蹴にしたという。強制収容所の看守の役は最下層の親衛隊員が行ったが、彼らは常日頃じぶんより目上の隊員から足蹴にされる腹いせに囚人たちをいじめたという。エリアスは、儀礼的決闘と下層階級における殴り合いとの違いについて次のように説明する。決闘では怒りや憎しみがわいてもとっさに対決するのではない。定められた儀礼が、まずはじめに敵意を完全に抑制して筋肉や行動から攻撃衝動を切り離すことを求める。社会的基準という外部からの強制が、きわめて強烈な自己抑制を要求する。つまり、上流階級の慣例化された形式を守る行動様式はかれらとナチスの衝動的で粗暴な行動との違いを意味するものであった。
第一次大戦で地位と職を失った軍人貴族を主要なメンバーとする義勇軍はヒトラーのもっとも重要な先駆者であり草分け的存在の一つであった。義勇軍の目的はおおくの点でヒトラーの目的と一致していた。「だが彼らは野生化しながらもその態度や心情には決闘を許された昔の貴族・ブルジョア社会の伝統、エリートたる将校の伝統が残っていた。ヒトラーはその伝統から解放され、---エリート特有の障壁を打ち砕き、大衆に広がることを妨げる限界を超えて、その運動を国民全体の運動に変えた。---ゲルマン人種の一員であることははるかに多くの人を参加させることができた」。
エリアスは、しばしば行われることがある「多少とも精神異常であるとか、特別に不道徳的人間の非合理な反ユダヤ感情によるものであるとか、ドイツ特有の伝統や特質に基づくものだ」とかいう説明は「説明になっていない」と言う。
アーリア人種の純潔を守るためにユダヤ人を絶滅し、帝国を樹立するというような国家社会主義者たちの信念は「非現実的」で「非合理」であるかもしれない。「言い換えればそういう信念の実質はまったく空想的なもの」であった。また「ヒトラーと彼の協力者たち---の言葉には大量の憎悪やたわごとや嘘八百が含まれていた」が、それは、「かれらが自分たちの信念の究極的な正しさを確信していたことと決して矛盾したことではなかった。国家社会主義では、政党の特徴に宗教運動に見られる多くの特徴が結びついていた。国家社会主義を一つの信念体系についての真剣な信仰に基づく運動としてみることこそ現実の出来事を捉えるための第一条件なのである。運動はセクトとして始まった。セクトの指導者は早くから、自分が救世主たる任務をもち、ドイツのための使命を帯びていると信じていた。それは彼の信奉者たちも同じであった」。〔オウム真理教はこれに似た現代における真正の宗教だったと考えることができるかもしれない。〕
定言命法は三つの形式で表現されており、上に示したものは「第一方式」である。それに従えば、自己矛盾が生じないことならばすべて格率として採用しうる。たとえば、ヒトラー国家の最高官僚で占領されたポーランド総督であったハンス・フランクは「総統が汝の行為を知ったとき、その行為を是認するように行為せよ、これが第三帝国における行為の定言命令であった」と書いているという(エリアス『ドイツ人論 文明化と暴力』(452)が、実際、下線部の「格率」=行為原則はカントの定言命法(第一方式)に反するものではない。
だが、定言命法「第二方式」では「汝の人格やほかのあらゆるひとの人格のうちにある人間性をいつも同時に目的として扱い、決して単に手段として扱うな」といわれており、全体として、各人が他者を人間として扱い、自己の道徳的完成と他者の幸福のために努めるべきだとされている(宇都宮芳明訳・注解『道徳形而上学の基礎づけ』(以文社、1998年)。またカントは『実践理性批判』において、彼の定言命法は聖書の中で昔から説かれてきたこと(「自分がしてほしいと思うように他の人にせよ」=「黄金律」)を厳密に述べただけだと言っている。黄金律では定言命法の第一方式の場合と同様に、行為(原則)の内容は未決定である。だが、イエスの教えの中心には隣人愛(普遍的な人間愛)がすえられており、それを踏まえれば、黄金律は愛の利他行を命じていると考えられる。カントの「定言命法」も同様に、(第一方式だけにもとづけばそう見える)単なる普遍性あるいは首尾一貫性を命じているのでなく、第二方式での人間愛、人間の尊重が「定言命法」の中心になっていると考えられる。こうして、ホルクハイマーとアドルノは、ヒトラー政府は「定言命法にそむいて、そしてそれだけいっそう深く純粋理性に同調しながら、---人間を物として、---扱う」と言うのである。
そして、人間は互いに愛し合わねばならず、殺しあってはならないということは多くの人が認めるだろうし、なんとなくそれが法律や倫理の根本原理だと考えているようにも思われる。しかしそれが正しいということは理性によってあるいは学問によって証明されているわけではない。ほとんどの人が暴力が日常的に罷り通る生活よりも、暴力のない平和な生活を望むからこそ、それが根本原理になってほしいと考えていることのあらわれと考えられる。
だが、また、近代社会はこのような慣例化を部分的に緩和する仕組みをうみだしてきた、とエリアス言う。その仕組みとは余暇活動のことである。「余暇活動は、ある程度の範囲内で、慣例化された部分から排除されている感情的な経験のための機会を提供する。余暇活動は、何よりも、感情の日常的抑制が公的に緩められ、社会的承認を得るような活動である」。人々は慣例化された生活のなかで「楽しい興奮」を必要としている。余暇活動は、「飛び地」で「興奮、緊張、そこからの解放、つまりカタルシス」を与えてくれる活動であり、「公認された興奮」によって慣例化を緩和してくれる活動である。人々は「戦いの興奮を求める」。フットボールのように暴力によって戦うことで人を興奮させ、また自然的感情や衝動を直接に表出することを可能にする活動であるスポーツは、「行う」にせよ「見る」にせよ、余暇活動の代表例である。余暇は、意図的、計画的に作られた制度ではないが、慣例化を緩和し、人々が精神衛生を保つことを可能する社会の仕組みである、とエリアスはいう。
以下では、『スポーツと文明化』「第1章余暇における興奮の探求」、及び「第2章自由時間のスペクトル」を中心に、エリアスの余暇論を検討したい。
私の生活経験に即して言えば、仕事(有給の職業としての仕事、無給の家事育児などの仕事、ボランティア的な社会活動としての仕事)があり、それと異なるものとして遊びや趣味の活動、つまり余暇活動がある。遊び、余暇活動はその活動が楽しいがゆえに、楽しむことを目的に行うような活動である。世の中には楽しみとして仕事を行う人もいるようだ。しかし仕事はふつう必要や、義務・責任感から行われる活動で、楽しみのために行われるのではない。仕事と遊びは対極的な活動である。仕事のなかで、ふつう、もっとも多くの時間を占めるのは職業労働である。そこで仕事を職業労働で代表させれば、遊びまたは余暇活動は職業労働の対極をなす活動である。
しかし、私は、日常的な経験を通じて獲得した遊びや趣味についての非学問的な、私自身の見方をまだ放棄しようとはしていない。文明化過程に関する統一理論に支えられ、「科学的」な事実として提出されている(そして、彼も完全だとは言っておらず検証のためにやるべき仕事は残っていると言っている)慣例化を緩和する機能としての余暇というエリアスの主張に対して「科学的な」反論を行おうと言うのではないが、彼の説は私の考えを排除・否定するものでもなく、私は自分の考えを維持することは可能であるとも思う。
エリアスの余暇論は、余暇活動が孤立した少数の事象ではなく多数の成員による活動であるがゆえに、それが結果的に生み出す社会的な効果・意義、つまり余暇活動の客観的・社会的な機能についての説である。私は、遊びや余暇の活動を、楽しみ・快楽を追求する個々人の主観的観点に即して捉える。つまり多数の人が行なう無数の活動が全体としての社会にどのような客観的効果をもたらしているかが問題なのではなく、人々は何ゆえに遊びたいと思い、余暇活動をしたいと考えるのか、余暇活動を動機づけるのは何であるのかを考えることに中心がある。
多数の成員の行動に関して主観的意図(動機)と客観的な結果(社会的機能)は一致することもあるが、一致しないこともある。私は個々人が主観的に追求している楽しみと社会的機能としての「非慣例化」作用とは個別のケースでは多くの場合一致しないように思う。しかし、だからといって、余暇は非慣例化機能であるとする説が正しいとしても、個々人は快楽を追求するために余暇活動を行なうのだとする私の考えを放棄しなければならないわけではない。また、私は、一般的に、労働は必要のためにやむを得ず行なう活動で、労働時間においてはしたくてもできない、スポーツや遊びや趣味の活動を、「自由時間」において行なうのだという常識的見解に立つ。遊び・趣味・余暇活動は労働のアンチテーゼだと考える。
また「余暇は労働の対極」説には、余暇活動を「仕事の緊張からの回復」とする傾向が広く見られる。そして、その傾向は「緊張」は何か否定的なものだという「仮説」に立っているが、それは「検証」を要する問題であると言う。また、緊張には余暇の模倣的催し物に含まれる楽しい緊張もあるが、それと不快だと考えられている仕事の緊張とはどう違うのかも明らかにされねばならない、という。
また、彼は、このような考え方の背景には、人間があらゆる活動においてあたかもただ一組の「規則」、規範によって支配されているかのごとく考える、社会観があると批判する。規範には範囲があり、余暇と非余暇において人は異なる規範に従って行動する、とエリアスは言う。
エリアスが考えているのはたとえば「プロテスタント」的か「カトリック的か」の違いはあれ、人々は働き方、遊び方、消費の仕方等々、生活の全分野における行動を単一の倫理(規則)に基づいて律していると、考えるような「人間観」、「社会観」のことであろう。余暇活動は代償行為、あるいはレクリエーションのための活動だという考えは、労働を最高の価値と見なす一つの規則(プロテスタントの勤勉・禁欲の倫理。あるいは労働とは自然に働きかけることによって自己を対象化し、自己実現することであり、人は労働に打ち込むべし、というような労働倫理。)にしたがって人間は生きているという、見方から生じたものにすぎない。
だが、エリアスはそうした「人間観」、「社会観」は間違いだという。余暇活動は労働あるいは非余暇活動とは異なる独立の規則に従う、異なった種類の活動である。利害を異にする複数の意思決定主体によって行われる行動はゲームと呼ばれる。仕事も一種のゲームである。「非余暇のゲーム〔=仕事〕における支配的な活動は目的志向である。それには一直線のベクトルの性格がある」。副次的には生活費を得たり、社会的承認を得るなど、自分のための満足も得られるが、「その基本的な機能は他人のための、「かれら」のための、あるいは会社や民族国家のような非個人的組織のための機能である」。これに対して余暇活動は各人が自分の満足が得られるような活動である。人間は異なる活動分野において、異なる規則にしたがって行動する。
またかれは余暇と仕事と言う「伝統的な」分極化においては有給の労働時間以外の時間が「自由時間」とされているが、「自由時間」において行う必要のある、家事や育児の労働など「多量の仕事」があいまいなままになっている。自由時間と余暇の関係をもっと明瞭に区別し、もっと明確に定義することが必要だと言う。家事労働をめぐる議論は余暇に関する議論と同じく、先進資本主義国が戦後経済成長を遂げつつあった1960年代以降に盛んになった。エリアスは「自由時間」に行われる諸活動を非慣例化の程度、換言すれば他人のためでなく自分のための満足の得られる度合の違いによってスペクトル状に配置し、自由時間と余暇の詳しい関係を実際に示す。
余暇活動は全般的な社会の慣例化を(部分的に)緩和する社会的な仕組み、機能である。その観点からは仕事つまり職業上の労働は慣例化された領域の一部であるに過ぎない。慣例化、感情抑制の習慣は人々の非職業的生活、たとえば友達づきあいやボランティア的活動などにも広く、深く行き渡っている。こうして余暇活動は仕事(職業労働)との関係においてではなく慣例化との関係においてとらえられるべき事柄だとエリアスは言うのである。
「映画、ダンス、---フットボールの試合など」余暇活動は「いくつかの点で非余暇的現実を思い起こさせる想像上の環境の中で」、「気分や衝動、感情や情緒が自由に生じることを許す」。だが、「模倣的」というのはそれらが「実人生の出来事の表象である」、つまり何らかのしかたで実人生を思い起こさせる、あるいは実人生に似ているところがあるという意味において言われているのではない。ルーレットで当たったり外れたりするような運や不運が実際の人生における運や不運に似ていると考えることにはほとんど意味がないであろう。
それが模倣的だというのは、余暇活動が観客に、彼らが「実人生」において経験するであろう感情に似た感情を喚起するからである。「余暇活動により喚起される感情こそ、たとえ模倣的催し物〔活動〕それ自体が「現実的」出来事と全く似ていないとしても、---〔現実の〕きわめて危機的な状況で経験される感情に類似している」のである。そして余暇活動において喚起される感情は、実人生におけるのと違って、恐怖、同情、嫉妬や憎悪であっても、「いわば別の調子に移しかえられ、---とげとげしさを失う。それらは「一種の喜び」と混じり合っている」。
実人生の中でかきたてられる興奮においては、人々は自制を失い、自分自身にとっても他者のとっても脅威になりがちである。だが「摸倣的な興奮は、社会的にも個人的にも危険のないものであり浄化的効果を持ちうる」。時に「いきりたったフットボールの観衆」、あるいは「手に負えなくなるポップスのファン」のように、「模倣的興奮が非模倣的興奮に移行」し、実人生においてひどい危機を招いてしまうということもないわけではないが、それは通例ではない。ほとんどの場合、人は模倣的活動における感情や衝動の表出、ないしはそれらの抑制の緩和を特定の限られた場所や機会、つまり「飛び地」の中で行うのである(114~116)。
おそらく、われわれは実人生において、楽しいことに出会ったときばかりでなく、悲しいこと、あるいは悔しいこと、きわめて腹立たしいことに出会ったときには、自分を傷つけたり他人に危害を加えたりというような攻撃的衝動に完全に身を委ねてしまうということは避けるべきだが、強く悲しんだり怒ったりし、もっと自然な感情を顕わにすべきであるのかもしれない。そうするほうが、それらの出来事が過ぎ去ったあとで、われわれが朗らかで平静な生活を送ることを可能にしてくれるかもしれない。
だが慣例化の進んだ現代社会に適応するように育てられたわれわれは感情を素直に表現できないし、衝動的行動を抑制してしまう。われわれは「抑制を緩めることは、異常であるとか、あるいは犯罪であるというふうに類別されがち」であることを知っている。われわれは強い悲しみや怒り、あるいは性的興奮などは抑え込んでしまう。模倣的催し物は実人生におけるのに似た興奮を喚起し、一定の枠内でだが、それら興奮を自由に外に表すことを許す仕組みであり、これによって多くの人が精神の健康、あるいは精神衛生を保つことが可能になるのである。
余暇活動にはさまざまなものがある。エリアスは休息も一種の余暇活動だという。一方でフットボールのような大きな身体活動性を伴うスポーツがあり、劇や映画、テレビを見ること、コンサートに行くことなど、身体活動性の比較的少ない余暇活動もある。さらに、他の人々といっしょにではなく、一人で室内楽曲など静かな曲のレコードを聴いたり、あるいは風景画や静物画を描くなどの余暇活動もある。これらさまざまな「模倣的催し物」あるいは遊戯的余暇活動のなかで、エリアスは、スポーツとりわけ戦いであるようなスポーツの重要性を強調する。彼は、人間は戦いの興奮を求めると言う。
また彼は、暴力を行使することに対して「人間が本能的で生来の抑制力を欠いているという事実」を想定することも可能だという13)。
だが、その場合には「人間が衝動規制を学んだり、自分自身やお互いを文明化するための自然の性質」を持っていると考えざるを得ないという。なぜなら、文明化の過程のなかで人間は攻撃衝動を抑制し直接的な暴力の行使を抑制する仕組みを発達させてきた。それは、現在までのところ国家の内部に限られている。しかし、その国家内部の社会においては確かに平和な社会生活が行われている。だが、人間の本性には抑制できない攻撃性があると想定し、しかも「衝動規制を学びお互いを文明化するための自然の性質」を持っていないとするならば、こうした社会生活は不可能であったはずだ、とエリアスは言う。
私は17世紀半ばホッブスにより著された『リヴァイアサン』を思い起こす。そこでは「自然状態」においては「人間は人間に対して狼」で、「万人の万人に対する闘争」が行われるが、各人が自己の暴力行使を控えて一人の主権者にゆだねることによって「国家」が成立すると説かれた。ホッブスにおいて人間は(生まれつき)暴力的存在であるが、同時に各人の暴力行使を放棄することで平和を達成することができると考える理性(知性)を持った存在であると考えられている。
エリアスも、人間はもしかしたら「狼」かもしれないが、しかし、衝動・暴力の規制をお互いに学び、文明化する性質を「生まれつき」もっている、と考える。だが「文明化」は理性や知性によって意識的に推進される過程ではない。人々はいわば本能的に平和を好み暴力を抑制する傾向を少しずつ拡大してきたのである。そしてそのために役立ったのが、遊戯・娯楽disportsを集団で楽しむことだった。なかんずく、一方で暴力を好む性質を満足させるとともに他方で暴力を抑え、安全を確保するルールを強めることによる娯楽のスポーツ化であった。
エリアスは、18世紀半ば過ぎのイギリスでは、地主階級が「暴力を否定し、政府を規制したり、またとくに政府を交代させたりする議会の方法に必要な高度な自制の形態を習得」したが、またこの時期に彼らの娯楽を「比較的穏やかで、より細かく調整された娯楽」であるスポーツへと変化させたと言っていた。また、彼は、議会における政権獲得競争は「楽しい緊張と興奮の機会を欠いていなかった」。「18世紀イギリスの政治制度の発展と構造と、同じ時期のイギリスの上流階級の娯楽のスポーツ化とのあいだには明らかな類似点があった」と言っていた。英国の地主階級は議会の建物内においても野外、田園においても、「楽しい緊張と興奮の機会」を与えてくれる活動を好んだのだ。こうして暴力の応酬が続いた17世紀前の英国社会は、一挙にではなかったにせよ、近代的な平和な社会へと移行していったのだ。
こうして、スポーツやそれに似た「楽しい緊張と興奮」を求める「生まれつきの」心性---むき出しの暴力を好む心性とも、理性・知性とも異なる---心性によって、人間は暴力の抑制を習得し、少なくとも一国内では、人々が平和な生活を行うことのできる近代国家を生み出す要因(の一つ)として機能した、と言っているのである。
18世紀の英国においては、紳士たちの政治的な争いは言論によって行われ始めていたが、まだ短剣や剣などの武器を用いた「決闘という正式なかたち」での命がけの戦いも行われていた。私なりに付け加えれば、この章の末尾でやや詳しくふれるように400年前の日本においては、武芸者たちが腕の強さ、つまり戦いの技を競って命がけの「立会い」を行っていた。しかし、どちらの社会においても、集権的な統治形態が発展するなかで全般的な物理的身体的暴力の抑制が進み、戦いは生命、身体の安全を守るルールにしたがって行われることになり、スポーツに変わった。そして、現在もスポーツは、本物の戦いで経験するのと似た経験を想像的環境の中でさせてくれる勝敗を争うゲームがほとんどなのである。
社会全体における文明化の進展という観点からすれば格闘技のような暴力的なスポーツが依然として存在し続けていることは不思議に思われるかもしれない。しかしエリアスによれば、「スポーツの中心をなす」のは「戦い」である。スポーツにおいては、ボクシングのように相手に苦痛と身体的ダメージを与えることを目指す競技でなくても、「あらゆるスポーツは本質的に競争的であり、それゆえ攻撃性と暴力性を喚起する。----二人の人間、二つの集団の間の「遊戯的戦い」、或いは「模擬戦」という形を取る暴力が重要な要素」(第8章「スポーツにおける社会的結合と暴力」ダニング)である。「競争性」といっても知的優劣や芸術的優美を競うのではなく、身体の強さ、あるいはルールの範囲内で行使される相手の暴力に屈しない強さを競うのである。野球でも、サッカーでも、プロや準プロのスポーツチームに交じって普通の人が出場すればたちまち大怪我をするか、下手をすれば命を失いかねない危険と暴力性に満ちていることは周知のことである。
もちろんその戦いがスポーツのなかで危険性を減らされた楽しいものであるから求められるのであるが、それでも人々は戦いを好むから、戦いであるようなスポーツを好むのである。こうして、余暇活動という形態での「飛び地」のなかでルールの枠内で暴力を行使することを許すスポーツは、戦いたいという欲求を満たしてくれ、結果的に、余暇の領域以外のところでの、とくに若者たちの暴力行使を未然に防ぐ役割を果たしているとエリアスは考えるのである。
しかし、余暇活動には暴力を行使したり見たりすることを楽しむスポーツ以外にも様々な活動がある。余暇活動は余暇に、通例「自由時間」と呼ばれる時間に行われる。
エリアスは自由時間においてなされる活動を、「慣例化」の浸透度合いのもっとも大きい(1)食事、飲酒、休息、睡眠、情事など「生物的欲求の充足」のための活動や家事・育児など日常的活動、(2)ラジオの組み立てのような「技術的な趣味」、「新聞・定期刊行物を読むこと、ためになるテレビ番組をみること」など、「主として、適応、および(または)自己実現、自己拡張に役立つ活動」、及び(3)慣例化の度合の最も少ない余暇活動の3つに大別し、さらにそのそれぞれをいくつかの細かなスペクトルに区分する。
(3)の「余暇活動」はa.「社交的活動」、b.「模倣的あるいは遊戯的活動」、c.「休暇旅行、気分転換のための外食、非慣例化を促す愛の関係、日曜の朝の朝寝坊、--散歩」など「雑多な余暇活動」に区分され、c.が余暇活動のうちでも非慣例化機能がもっとも大きいとされる。
c.「雑多な余暇活動」はスポーツのように身体運動性は大きくない。しかし、それは仕事上あるいは家族生活上の必要や義務から免れて、その時々の気分で行われる「衝動的」な行動である。こうしてc.は非慣例化機能が最大とされているのだと思われる。
b.「模倣的あるいは遊戯的活動」とa.「社交的活動」(結婚式、パブやパーティなど)とでは、前者のほうがより非慣例化の機能が大きいとされている。後者は仕事や家庭生活を通じた人間関係の中で行われるのに対して、前者は、仕事や家庭と無関係に行なわれるからであろう。
この前者、b.に含まれる活動は、さらに三つに区分され(ⅰ)は、「アマチュア演劇」やアマチュアのクリケット、フットボールなどを「行う」活動、(ⅱ)は「観客として参加する」活動、そして(ⅲ)は「団体に加わらずに行なうダンスや山登り」の活動であり、順に非慣例化機能が大きくなるとされている。 一般的には、身体運動を伴い、義務や責任から免れて自由な、楽しい興奮を享受するという自然的欲求を充足する活動は非慣例化機能をもつ。
(ⅰ)の「行う」活動と(ⅱ)の「見る」活動はどうして(ⅱ)の方が非慣例化機能が大きいとみなされるのだろうか。身体を使って自ら演技しあるいは競技するほうが、体を動かさずにそれらを見るだけの活動よりも、大きな緊張や興奮、つまり大きな非慣例化効果を得られそうである。だが、俳優として演じ選手としてプレーするためには一定レベルの技量が必要であり、そのための練習は慣例化の圧力を及ぼす。そしてスポーツの場合、試合の途中で興奮したとしてもプレーはルールに従ってなされねばならず興奮を抑えなければならない。フットボールのようなチームで行う競技であれば、他の選手と連携・協力して、プレーを行う責任がともなう。また、スポーツを継続的に楽しむためには、クラブその他の「組織としての活動」に参加する必要がある。これらは「慣例化」の要因である。同じことは演劇活動についても言える。(スポーツを行うことは戦いに対する欲求を満足させる機能をもつものであっても、慣例化を緩和する機能は必ずしも非常に大きいとは言えないのである。)
他方、観客として試合(あるいは劇)を楽しむのであれば、「運動性による非慣例化は比較的少ない」かほとんどないが、技術・技量(を養う練習)は必要なく、組織(クラブまたはチーム、劇団)の一員としての他者との関係における義務や責任を負うこともない。またエリアスはとくに「他人のため」の行動や配慮が慣例化の大きな要因だと考える。
こうして、団体の構成員として組織化された活動に参加することよりも、運動性は少ないが組織の一部とならず、「観客として活動に参加する」ことのほうが非慣例化が大きいとするのだと思われる。
また、(ⅲ)ダンスや山登りなど「それほど高度に組織化されていない」活動は、運動性に関してはフットボールなどを「する」ことと「見る」ことの両者の中間的大きさであるが、組織に加わって活動しないために、もっとも非慣例化機能が大きいということになるのだろう。
だが、(ⅰ)において、フットボール(やクリケット)と演劇を較べると、どちらもクラブに属し、playつまり演技は「チームワーク」であり「慣例化」の要素においては差が無い。だが、両者は身体運動性と興奮の度合はかなり違う。演劇の身体運動性はスポーツに較べてずっと低いだろうし、「戦いによる興奮」はほぼゼロで、演劇の興奮の度合はフットボールよりはるかに小さいはずである。どうしてこの二つの活動が同じ一つのスペクトルに属することになるのだろうか。
もし、演劇とフットボール(やクリケット)を一括しないとすると、b.に属する諸活動を、非慣例化機能の大きい順に並べれば (ⅲ)「団体に加わらずに行なうダンスや山登り」>(ⅱ)「観客として参加する」活動>アマチュアのフットボールなどを「行う」活動>「アマチュア演劇」ということになる。後の2者を一括しないとすれば「フットボールなどを行う活動」を(ⅱ)に移さなければならない。それでは観客とプレーヤーの非慣例化機能の程度が同じということになってしまい、不適切である。かといって、「観客」を(ⅲ)に移すのも無理であろう。結局b.の諸活動を三つのスペクトルに分けるという前提で(その理由は不明だが)、後の2者は一括されたのだと、考えざるを得ない。
余暇活動は「すべて公然と経験され、他者と共有され、かつ社会的承認を受け、安らかな心で享受される感情の楽しいたかまり、楽しい興奮の機会を与えてくれる」。だが、職業として行うスポーツも、試合のなかで「公然と」敵意をむき出しにして戦うことによって自然な衝動を充足させるという面があることは確かで、その点では他の筋肉労働者や事務労働者に比べて、仕事が人間の自然を抑制する程度は比較的軽いといえるだろう。
職業の一種としてのプロスポーツは子どもたちにとって、体を動かさず、机に座ったまま、計算したり文書を書いたりするデスクワーク、オフィスワークよりも、はるかに魅力的に映るだろう。学習塾へ行くよりはスポーツクラブに通うほうがずっと楽しい。こうして実際にプロのスポーツ・プレーヤーとして将来の生活を確保することがいかに困難であるかを大人から教えられないかぎり、大多数の子どもがプロスポーツ界を目指したとしても、何の不思議もないのである。
しかし、高い技術を獲得するためには、ときには休みたい、遊びたいという自然的衝動を押さえつけ将来を目指して努力を続けるという強度の「慣例化」に耐えなければならず、うまく就職できたとしても、労働契約に基づいて、上司である監督やコーチの指示や命令に従い、顧客である他者つまり、ファンたちの要求に応えるべく行動するのであり、エリアスの言うとおり、プロのプレーヤーのスポーツ活動は自らの「慣例化」を緩和するために行われる活動では全くないということも確かである。
政府は、オリンピックなどの国際競技に出場する選手の育成・強化や、練習場や競技場の整備などに力を入れているが、そうした動きの背景にはあきらかにナショナリズムの高揚効果を狙う政治的意図が働いている。また、現在の政府とそれを指示する財界のリーダーたちは、つぎのようなイデオロギーに立っている。つまり、競争は善であり(「規制は間違いだ」)、強い者、能力のある者が勝ち、成功するのは当然であるとともに、人々の能力や努力を引き出すために「格差」が必要だ。そして、富の偏りを是正することよりも経済成長によってつまりより多くの(物質的)富を生産することによって国民は豊かになるのであり、勤勉な労働によって豊かになれるのだ、というのがそれである。そこで、結論的に言えば、現在の日本の政治と経済のリーダーたちは不平等を放置ないし維持しつつ、国民をより多く働かせようと考えているのであり、労働時間を短縮し、より多くの自由時間を国民が享受できるようにしようとは考えていないのである。
私は、国民の多くが物的により豊になることではなく、労働を減らし、より多くの余暇活動を楽しみ、ストレスの少ない健康な生活を送ることの方が意味があり価値がある/幸福だと考えるようにならなければ、(少なくとも現在のような)労働重視社会のありかたは変わらないと思う。私は仕事/労働を人間にとって最も価値のある活動だという従来の考え方に反対し、遊びやスポーツ、芸術などの余暇活動に、仕事と同等のあるいはそれ以上の価値があり、仕事/労働をできるだけ減らすべきだと考える。エリアスは科学者として「余暇は労働の対極」つまりアンチテーゼではなく「慣例化のアンチテーゼ」だと述べているが、私は労働のアンチテーゼとしての余暇活動を増やすべきであると言う意見を述べたいと思う。
比較的自由に楽しく仕事をすることのできる少数の職業を別とすれば、自分自身の関心事とは関係なく、他者の意志にしたがって働かねばならない、多くの労働は楽しいものではない。それはやむを得ない労苦であり、できるだけ労働時間を減らし、労働の苦を減らしたい、より楽しく、幸福に生きたい、と考えるのは自然である。余暇活動は労働のアンチテーゼであろう。
人々は子どもの時期に慣例化した行動様式を習得する(させられる)が、だからといって家庭が、慣例化の震源地と考えることは出来ない。家庭における慣例化は、親が企業で働き、子どもも将来同じことを期待されて、必要な学力や学歴を身につけなければならないと思われているような家庭で、とくに親から子へと伝播するであろう。学校でも、進学校とそうでないところでは慣例化の度合は異なるであろう。慣例化圧力は家庭や学校の外部からやって来きて浸透し、子どもたちに影響を与えるのであり、それらは震源地ではない。震源地は企業や官庁など職業労働が行われる組織にある。
企業で働く場合には、労働者は賃金を受け取ることと交換に、仕事中には無駄口をきかないとか、持ち場をかってに離れないとかというような、どの職場でも要求される一般的な慣例化された様式したがって行動することを求められるだろうが、とりわけ管理機構が発達している大きな企業や官庁などでは、人々は慣例化された様式で働くことをよりつよく求められる。そこでは恣意や気まぐれ、感情を排し、先例を踏襲し、規則に従い、画一主義的に職務を遂行するという、官僚制が貫徹している。慣例化された行動様式の典型的な形態は官僚組織のなかで見出すことが出来る。
エリアスは相互依存の長く複雑な連鎖を通して多数の行為が無駄なく、期待された成果を生み出すことができるためには、その鎖の一つ一つに位置する人々の行為が一定の枠におさまり、パターン化された仕方で、つまり慣例化に従って行われる必要がある、としていた。行為者のこうした態度は、一言で言えば「計算可能、予測可能」な態度であり、M.ウェーバーが官僚制は合理的だといった意味で「合理的」態度である。
文明化の本来の意味は「礼儀正しさ」であり、国家の絶対的支配権を手に入れつつあった「宮廷」から外の社会へと広がって行ったといわれていたが、文明化の一面である慣例化も支配機構としての宮廷の官僚組織から外部の社会へ広がっていったのであろう。利潤の獲得を至上課題とするブルジョワジー(市民)の経営する資本主義企業では当然、計算可能性、予測可能性を重視した。こうして、再度、エリアスの言葉を用いれば、大勢の人々の相互依存の長い複雑な連鎖、あるいはネットワークのすべての場所で慣例化圧力が発生するというよりは、その中で大きな結節点をなすような場所、つまり大企業や官庁などの官僚制的な労働組織が慣例化の源としてつよい慣例化作用を発生し続けており、それが社会に放射され、伝播するのだと思われる。
まず、自由時間は労働時間によって決まる。その自由時間から家事育児、休息などの必要のための時間、さらに人によっては社会活動の時間を控除して、各人は余暇時間を作る。したがって余暇時間は、自由時間の長さ及び使い方によって決まるが、結局は労働時間によって限定される。目を覚ましている時間の大部分をまず職業労働が占める。その残りが自由時間であり、余暇活動に当てることができるのはそのうちのごく一部でしかない。
自由時間が労働時間によってきまることは現代の労働者だけに限られていない。農民は農繁期には一日中労働する必要があり自由時間はほとんどない。コルバンやボルストが示すフランス革命後の農民や中世の農民たち14)にとっては、祝祭日を除いて「自由時間」と「余暇」は存在しなかった。彼らの労働形態が彼らの「自由時間」を祝祭日に集中して持つことを強制したからである。
かれらは短期集中的にその場かぎりで楽しめる、練習を要しない活動、乱闘騒ぎに似たフットボール、牛や鶏などの家畜をいじめることを楽しむアニマル・スポーツ、見世物や大道芸の見物、賭け事などの娯楽を楽しんだ。クラブや団体に加わって、スポーツや演劇の活動を行うことはできなかった。余暇(活動)の種類は自由時間のあり方で決まり、自由時間は生産の様式、労働の行われ方によってきまる。
中世の農民の慣例化の度合い、つまり自然的感情や衝動的行動を抑制する度合は現代の労働者と比較してはるかに低かった15)。それでも彼らは遊び、娯楽を必要とした。このことも、遊び・余暇活動を労働との関係において捉えることが決して間違いでないことの証拠と考えることができるはずである。規則を重視する「近代スポーツ」は近代社会において発達した。だが、近代以前の社会の人々も遊び・娯楽、つまり余暇活動を行っていた。
人は生きるためには働かざるを得ないが、労働だけでは満足できず、遊びをあるいは余暇活動を必要とする。
(a)は「基本的には他人のための個人的(非職業的)な自発的労働」とされる。職業労働も幾分自分のための活動であるが基本的にはあるいは大部分は他人のための活動だとされている。わたしは社会活動については後でふれる。宗教活動についてはふれない。
(b)と(c)はエリアスにおいては、「基本的には自分のための活動」であるが、「余暇活動」とみなされていない。なぜなら、(b)は、それを行うためには、あらかじめ知識や技術を身につけておく必要があり、また衝動的行動を抑制し、根気よく、正確でていねいな作業を行なう態度が必要であるが、これらは職業をはじめとする慣例化された領域に適応するために必要な行動様式である。だから、その点から見れば工場における作業と大差ない。そこで「技術的趣味」の活動は、自分が好んで行なう活動であり、家事・育児などの仕事のように「他者」つまり家族のために行なわれる活動ほど慣例化されてはいないが、「余暇活動」ほど非慣例化(抑制解除)機能を持たない、「中間的」活動とされるのだと思われる。
ところが、趣味の活動であるかぎり作業(過程)と作業の結果である作品は連続していて手段と目的という区別が存在せず、作業が進行すると結果的にそれが作品となって結実するだけなのである。また趣味で製作される作品は、クリヤーしなければならない基準のようなものはもたない。作品の出来栄えは主としてあるいはほとんど、自分の目で見て満足できるかどうかという基準に従って判断される。もちろん自信があればコンテストに応募するなどして、他人の評価や賞賛という余分の快楽を享受しようとして構わない。しかし欲張る必要もない。確かに多くの人から作品が優れたものであると認められれば、快楽はずっと増えるだろうが、他者の評価を得ようとしてそれに失敗すれば、かえって楽しみが損なわれることになる。頑張ることや努力することはよいことだと反論されるだろうか。だが、それらが必要なのは社会により、他者により定められている基準をパスするためである。楽しみのために行なう趣味の領域においては、頑張り努力することは必要ではない。趣味は自分で楽しむ活動なのである。
したがって、趣味の活動における作業は、他人の指揮・命令によらずに行なわれるものでそれ自体楽しみであり、また、結果として生ずる作品に関しても、他人によって評価されねばならないという圧力は存在しないのだから、趣味の活動は「他者志向」でも「目的志向」でもない。趣味の活動を行なう人はもっぱら個人的な楽しみのために、根気よく正確にていねいに作業を行うであろう。作業形態が職業労働におけるのと同じであることをもって余暇あるい趣味の活動ではないと見なすことの不適切さは、家庭菜園における「農作業」をかんがえてみれば容易にわかることだ。
エリアスは技術的趣味を、天体観測、木工細工、切手集め、読書などとともに、「主として、適応、および(または)自己実現、自己拡張に役立つ活動」と言っている。少年時代に、就職に役立つ知識や技能を身につけようとして趣味の活動を行なっていたのならそれは一種の「適応」の意味をもつであろう。少年少女の活動でなく、仕事を持つ大人の自由時間における活動としてのそれら趣味は、「適応」のためとは考えにくく、「自己」を単に労働能力を持った存在として狭く捉えるのでない限り、「自己実現、自己拡張」と考えるべきであろう。
第3章のカイヨワについて述べた節でふれるが、カイヨワは機械的流れ作業の工場で働く工場労働者が「自己の技量と知性を発揮するという人間的な欲望」を満たすために、趣味でミニアチュアの模型の制作を行なうという事例について触れている。そのケースでは模型を作る活動は「適応」のために行なわれているのではなく「自己実現」活動であることは明らかである。
だが、自由時間のスペクトルの中で、エリアスが余暇活動の例として名前を挙げている(クラブに入って行う)演劇、フットボール、クリケット、あるいは(クラブに属さずに行う)ダンス、山登りはいずれも「自己実現、自己拡張」なのではないだろうか。エリアス自身は、これら余暇活動は非慣例化の活動だというのだが、それはともかくとして、すでに述べたように、技術的趣味や天体観測、あるいは切手集めや読書などは「他人志向」でも「目的志向」でもなく慣例化の要素は非常に少ない。これら趣味の活動を余暇活動と区別すべき理由がないように私には思われる。このように自由時間に行われる活動のスペクトル配列には、慣例化の浸透度合という点においても必ずしも適切とは思われない点がある。
だが、エリアスも必ずしも、余暇を精神衛生に役立つ非慣例化の機能を持つ活動とだけ捉えているのではない。彼は余暇の社会学的研究は「余暇の催し物〔余暇活動〕に固有の構造の規範」、それらの成功と失敗を区別する規範を与えることができると言っている。この文では非慣例化機能との関係におけるスポーツ、あるいは余暇活動を研究する意義について語っている。彼はこの文に続けて「さらに、われわれはそれぞれ、人々を啓発、教化してより多くの明敏さ、豊かさを授けてくれる余暇の催し物の発展をうまく想像することができる」とも言っている。
人々に「より多くの明敏さ、豊かさを授け」たり「人々を啓発、教化」することになるような余暇活動とはいかなる活動であろうか。エリアスは戦いであるようなスポーツとは異なる活動を念頭においてこの文を書いていると私は考える。つまり生理的興奮と同種の「面白さ」つまり興奮とそこからの解放=カタルシスを主要な内容とする活動とは別の種類の活動ではないかと思う。言い換えれば エリアスは、余暇活動のなかに、非余暇活動の領域でこうむる、人格を歪めかねない負の影響を減らすという、それ自体としては重要であるが、どちらかといえば消極的な機能を認めるにとどまらず、労働を主とする非余暇的領域のなかでは実現できない、人生にとって積極的な意味のある活動を行う自由を与えてくれる可能性を認めているのではないだろうか。
彼は、また、現在の国家による規制のありかたからすれば、スポーツも余暇活動も力で禁止されるようなことはないだろうが、他方で、スポーツ組織自体においても、スポーツにおける暴力行使をますますきびしく規制する傾向にあり、余暇活動全体のなかにおいても、戦いの興奮のような「本能的欲求」に訴えるものから、芸術のような「より複雑な組み合わせの感情的要求」に訴えるものへと比重が移動するだろうと、予測している。
次のことがわかる。文明化過程の初期の段階にあった人々は興奮を求めたが、その興奮状態を持続することには耐えられず、すぐにクライマックスに達してしまった。現代に近づくにつれ、人々はすぐに上り詰めてしまわず興奮状態を保てるようになった。見方を換えれば、その圧に耐えられる程度の興奮状態のなかで楽しみを見いだそうとするようになった。そして興奮圧を低く保つために快楽の「多様化」、分散化を行った。幾つもの低い「興奮圧」を複合的に楽しむことで、低い興奮状態に我慢しクライマックスに到達してしまわないでいる代償を得た。
また、古代ギリシャやローマ時代の民衆、中世の農民、19世紀の英国ジェントルマンたちを比較してみれば、暴力に対する感受性の高まり、つまり人々が激しい興奮とクライマックスを伴う暴力的娯楽を次第に好まなくなる変化が見て取れるが、それは快楽の多様化、複合化と同時並行的に起こったのだ。エリアスは「人間は戦いの興奮を必要とする」ことを発見したと言っていたが、彼はまた人間が次第に直接的な暴力を行使することも、あるいは暴力行使である戦いを見ることも好まなくなってきたことをも発見しているのである。
したがって、スポーツにおける暴力に対する規正がますます強まっている現代の傾向からすれば、人々は次第に暴力を行使し感情を爆発させるスポーツの替わりに非暴力的なスポーツを楽しむようになり、また知的ゲームや芸術的、文化的な活動など非慣例化機能(興奮とカタルシス)を主とするものではない活動に楽しみを見いだすようになる可能性はある、と考えてもおかしくはないだろう。
こうして、エリアスの考えに即しても、現在の余暇活動を慣例化に対する補償的あるいは治療的な効果を得るための活動としてのみ捉えるのでなく、仕事/労働の中ではできない、自分の好みに従う自由な楽しみの活動と捉えることが可能である。つまり、人々が仕事/労働の中で自分の能力を発揮することだけに満足を見いだすのでなく、さまざまな興味を広く追求し、自分が有する心身の能力、自己の可能性をさまざまなしかたで発揮することによって人生をより豊かにすることが可能になる、そのような活動として余暇活動を捉えることができると思われる。
だがエリアスはさらに、スポーツを代表例として余暇活動全般に関しても、その社会的機能は非慣例化にあると主張する。すべての余暇活動、催しものは、「模倣的」である。つまりそれらは、人生の中で人々が様々なことに出会い、経験するときに感じるであろう喜びや悲しみの感情に似た興奮を引き起こし「模倣的な」経験を与える。そして実人生においては慣例化の圧力により抑制されてしまうであろう自然的な感情の表出や振る舞いを無害な形で自由に表出、実現することを可能にする。こうしてスポーツばかりでなく、多かれ少なかれ「興奮とカタルシス」を与え「模倣的経験」を可能にする余暇活動も、その社会的機能は「非慣例化」作用であるとされる。
だが余暇活動、私の観点から言うと、楽しみで行なう活動には、慣例化の緩和に役立つと思われない種類の活動が多くある。たとえば、絵画や書道、あるいはその他の文芸を「自然的感情や衝動を自由に表出する活動」だとは言いがたい。また、囲碁や将棋などの知的・戦略的ゲームについても同じことが言える。
囲碁・将棋では、身体的競技と同様「勝ち負け」を争い、興奮することはあるだろうが、負けた場合に「健闘した」と自分を納得させるにしてもカタルシスを得られるとは言い難いように思われる。むしろ勝負中には内心ではまずい手を指したという後悔が渦巻いていたり、負けがはっきりとした場合には悔しさを感じるだろうが、それらを面に出さず、平然と静かに一礼して終るのが礼儀になっているのではないだろうか。知的戦略的ゲームでは行動(つまり指し手のことだが)において衝動的自然的振る舞いは禁物で、現在よさそうだと思われる手を指さず、なるべく先を読み、長期的視点に立って一手、一手を指すのではなかろうか。そしてこのような行動様式はむしろ「慣例化」した行動様式の特徴である。
第三章で見るが、カイヨワによると、古代の「中国人は、音楽、書道、絵画と並んで、囲碁、将棋を、知識人が実践すべき四つの技芸の一つにまで高めた」という。しかし、囲碁・将棋は「競争精神を擁護する傾向のゆえに求められたのではなく」、それらの遊びにおいて「闘争本能は沈められ、また、魂は静謐と調和と、可能なものについて沈思する喜びを学ぶ」と見なされたからであると説明している。「可能なものについての沈思」とは衝動的自然的行動とは正反対のものである。「沈思するする喜び」は「興奮がもたらすカタルシス」とはまったく別なものであろう。
またカイヨワは「中国における弓術の競技は、貴族の資格にとって必要とされたが、判定は結果によるよりも、むしろ矢を射るときの正しい動作や、敗者の慰め方などによるものであった」とも言っている。こうして、音楽、絵画、書道と並んで実践されたという、囲碁・将棋などの知的ゲームも、また身体を使う競技としての弓術も、古代中国においては、文明化による社会の慣例化を緩和する機能をもったのではなく、貴族、知識人を「文明化」(「廷臣化」)する方法の一つであり、むしろ「慣例化」機能をもっていたと考えることができる。
エリアスに従えば余暇活動が「興奮とカタルシス」を与えるものであるかぎりにおいて、人々は、慣例化を緩和するために、娯楽として余暇活動を求める。しかし、中世ヨーロッパにおいては、フットボールやあるいはアニマルスポーツなどのほかにも、それほど暴力的でない、ダンスや賭け事や見世物など様々な娯楽が、祭日などに行われていたことが知られている。
余暇活動を社会の慣例化と関連づけようとすれば、つまりふだん抑制されている自然的衝動を発散させ、興奮とカタルシスを得ることが余暇活動の主たる目的だとすれば、慣例化されていなかった中世の社会で余暇活動が行われた理由がわからなくなる。だが、人々は必要(あるいは隷属)ゆえの農業労働が主体の単調な日常性から脱出して、自由に遊んで楽しもうとしたと考えれば、中世の慣例化されていない農村社会においても、様々な余暇活動がおこなわれたことは、自然に理解できる。
「文明化」/「慣例化」という枠組みを否定しようというのではないが、余暇活動に関して、次のような見方が可能であるように思われる
人間は、いわば「自然・本性的に」、必要によって強制される仕事だけでなく、自由にさまざまな活動をやってみたい存在であって、労働によって生活の必要を満たす(苦を解消する)だけでは飽き足らず、身体、頭脳あるいは精神を用いた、競技や踊りや楽器の演奏、詩作、絵画、チェスあるいは将棋のようなゲーム等々、つまりさまざまな「遊び」を好む(多様な快を求める)存在であり、近代以前は、特権階層の人々や彼らをスポンサーとする才人たちをのぞいて、自由に遊ぶことはほとんどできなかったが、生産力の全般的拡大による「自由時間」の増大によって多くの人にそれが可能となった。20世紀後半の先進国の経済成長がそうした機会を大衆的規模でもたらしたのだ。
そこで、人々は、「スポーツ」の戦いの興奮であれ、静かな芸術的な愉しみであれ、各自が好む楽しい活動、遊びを余暇活動として行うのだ、と。そして、次のように主張することもできると思われる。すなわち、人々は、自己の生を労働の中に限定し、その中でのみ自己を実現しようと考えるのでなく、さまざまな余暇活動を行えるよう、できるだけ労働時間を減らし、多くの自由時間を獲得するようにすべきである(より多くの快を実現すべきである)と。
そして、そう考える場合には、余暇活動は非慣例化という社会的機能の大小にしたがってスペクトル状に配列することはできず、単に人々が好みにしたがって選ぶ様々な楽しく自由な活動があるだけだ、ということになる。
他方、「興奮する」ことの少ない余暇活動は上であげたようなものの他にも無数にある。エリアスが自由時間のスペクトルの中で言及している、ラジオや模型を組み立てる「技術的趣味」(最近では高校生などの間に「ロボ・コン」つまり自作したロボットのコンテストが流行っている)、あるいは天体観測や昆虫採集、写真、木工細工、切手集めなどの趣味も、暴力や興奮を伴う「非慣例化」機能は小さい。ではこうした余暇活動は何のためにあるのか。あるいはそれらにも社会的機能といったものがあるとすれば、それはなんであろうか。余暇活動を、それがもたらすかもしれないカタルシスないし非慣例化機能と関係づけずに、単に各人が楽しいと思う活動を自由に行うことであると捉えるときには、その価値はどこに求められるだろうか。
私は人間は楽しく幸福な一生を送ることが何よりも大切なことだと思う。私は、他国との平和な関係の下で、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(日本国憲法 25条1項)を保証され、衣食住に困ることのない生活を営みつつ、楽しく暮らすことが最高の価値なのだと考える。ある程度の仕事/労働は必要だろう。だが、自由時間をできるだけ増やしできるだけ多くの余暇活動を楽しむべきだと考える。各自が楽しいと思う活動を行うことが目的であり、余暇活動は何か他の目的をもっているわけではない。基本的に生存のために行う仕事/労働のために一生を終えるのでなく、可能な様々な活動を行い楽しむこと自体が価値であり、目的なのである。
具体的には、集団的熱狂や興奮とは関係なく、たとえば、非幻想的で非人工的な環境、つまり自然のなかで、時間をかけてゆっくりと山歩きや登山を楽しんだ人は、下山の際に、スタジアムの出口をでたサッカーファンのように直ちに「普通の市民」に強制的に戻らされることはなく、慣例化された日常生活に自動的に、無抵抗に戻ることはできないと考えられる。自然的な感情や衝動の表出を可能な限り減らして、仕事に必要なことがらのやりとりだけにコミュニケーションを純化する職業生活に簡単に復帰、埋没できなくなるのではないか。
次の章でふれるチクセントミハイは(趣味で)ロッククライミングを行う登山家の中には「社会についての解釈〔見方〕」が変わる経験をする者があり、転職するものもあると報告している。ただし、それには、クライミングの最中にフローという特殊な経験が必要だと言う。フロー経験とは、くわしくは次章で述べるが、注意集中を伴う高度な熟練を要する活動の中で、動作が、意識しなくても自然に/自動的に行なわれるようになると感じられる特殊な状態である。
だが、私は、そのような特殊な状態を経験しなければ、その人の世界観や生に対する態度の転換が生じないとは思わない。地球に戻って宗教家になった何人もの宇宙飛行士たちがいるが、全員が難しい船外作業を遂行しその祭にフロー経験をしたわけではなかろう。重要なことは、地上百kmを越える宇宙からはるかな下界を眺める経験あるいは、日常的な関係におけるのとは全く違った視点から世界や自分の生活を「眺める」経験だったのでないかと私は思う。一般的な山歩きにおいても町並みや人家から離れた山の稜線をゆっくり一歩一歩たどりながら遠くに重なる山々を眺めることはそうした経験に似たものを与えることになるだろうと私は思う。
丘陵地帯や森林の中をゆっくりと歩き回ったり、草の上に寝転んで、木の葉の間から透かして見える空を眺めたり、木の枝をゆする風の音にぼんやりと耳を傾けたりして活動と休息を楽しむ(これをドイツなどではヴァンデルンと呼ぶようだ)ときには、これまでの生活や生き方について振り返って考え、これから先の生きかたについて構想することもあるだろう。家庭菜園での耕作、山菜取り、釣りなどの場合にも、一日中、夢中になってそれを行うのでなければ、同じような機会をもつことになるだろう。このような休息を伴う活動によって得られる「非慣例化」効果は、つよい興奮とはっきりとしたカタルシスを伴うものではないから、穏やかなものであろう。けれどもその効果はその活動の後でも持続するということからすれば、決してその効果は小さいとは言えない。
要するに、闘争型のスポーツのように他のすべてを忘れて夢中になるのではなく、ゆったり時間をかけて自分のペースでのんびり活動することができ、現在の状態とふだんの「慣例化」された状態との違いを比べ、現在の状態の快適さを確かめながら楽しむことのできるような余暇活動を行う場合には、ふだんの生活に戻ったときにもその「非慣例化」効果は持続し、余暇活動中の「自然に、思い通りに振舞える自由さ」と慣例化された社会の仕事や規則に拘束された不自然で不自由なあり方との落差をはっきりと感じるとともに、慣例化にしたがって生きることに苦痛を感じ、抵抗感なしにそこに安住することはできないだろう。
時には、後者に対する衝突を生じ、転職を考える人もあるかもしれないし、その職場に止まって、慣例化を批判し、より緩やかなものに変えようと努力する人もあるかもしれない。競技場やあるいはスポーツ・カフェでの一過性の「団結」に興奮し満足するのではなく、職場で働く仲間との団結を作り出し労働条件の改善につなげようとする人もいるかもしれない。そうしたケースが増えれば社会的な影響もでてくるかもしれない。うまく行けば、たとえば、時間については英国並みに緩くするというような効果が生じるかもしれない。これら余暇活動は穏やかな「非慣例化」機能しか持たないが、代わりに、「反慣例化」機能、つまり社会における慣例化に抵抗し、その強化を阻止する可能性を機能としてもつと考えられる。
そのような「反慣例化」機能を伴い得る穏やかな「非慣例化」機能をもつ余暇活動は、自然の中で行われる、ゆったりとしたヴァンデルン型の活動に限らないことは明らかで、室内で行われることが普通であるような文芸活動なども同じような、穏やかな「非慣例化」効果を期待することが出来る、と思われる。
余暇にどのような活動を行なうか、遊びにおいてどんな遊びを選ぶか、退職後はどのような暮らし方をするか。これは、実際には、人々の性向=好みによって決まることであり、理屈、理論的態度によって決まることではないだろう。しかし(社会的に規定されたものであることは否定できないが)自己の人生観、人間観と社会観、職業観によって選び方が左右されるだろうし、また逆に遊び方により、人生観、世界観に多少の変化が起きるだろう。
たとえば後の第4節でふれることになるが、非常にスポーツが好きでプロの選手になることを望んでいるがそれに必要な高いレベルの技術をもっていないために、個人的にトレーニングを行う「プロ志願者」とも言うべき人々がいる。未婚者で、アルバイトをして自分で稼ぎ、残りの「自由時間」でトレーニングを行っている者もいるが、親のすねをかじっている者もいる。
私がテレビのドキュメンタリーで見たプロ野球選手の志願者の3人のうち一人は未婚者でアルバイトで稼いでいたが、二人は既婚者で、どちらも、妻が働いていた。また妻が食事を作るなど家事・育児を行っていた。つまりこれら二人の女性の余暇活動の時間はきわめて少ないように見えた。この二人の男性は、真剣にトレーニングに打ち込んでおり、遊んでいるのではないことは確かだが、しかし彼らは妻とは対照的に、少なくともその時点では、そしてプロとして稼げるようになるまでは(その可能性が高いのかどうかはわからなかったが)、ほとんど「自分のために」、つまり自分の好きなスポーツ(の練習)のために、多くの自由時間を使っていた。
この男女のアンバランスは一部は愛情によって説明されるかもしれない。しかし「慣例化の圧力の浸透」によっても説明されるだろう。男女平等は文明化過程が必ず生み出す慣例だとは言えないかもしれない。
ある社会で人々がそれにしたがって行動するよう内的に仕向ける一様で安定した枠組み、楽しいがゆえに好んでそうするのではなく、そうすることが生活に必要で、そうするほうが他の人との軋轢を生まないと思われるがゆえに選択されている、習慣的な行動様式はすべて「慣例」であろう。そして日本では、たとえばヨーロッパ諸国とは異なって、あるいはそれらより遅れて、男と女は異なっているがゆえに不平等であり、職場においては秘書、お茶汲みなどの補助的役割り、家庭においては家事・育児は女がやるものという「慣例」があって、それが家庭の中にも浸透しているのだと考えられる。
このような男女の不平等は、ともに普通のサラリーマンであるような共働き夫婦の場合にも、家事・育児労働の分担の問題として、広く存在する。つまり家庭内では「慣例化の圧力」は男女の平等を、したがって余暇の平等をもたらしているとはいえず、自由時間のスペクトルには男女差が存在するということである。この点についてエリアスは全くふれていないことが不満足感を与える。ただし、この男女の不平等が日本特有の問題だとすれは、エリアスに非があるわけではないということになるが。
a.は最近ではボランティア活動と呼ばれることが多い。私はエリアスのこの論文が1972年に書かれたものであることを考慮しても、労働運動、エネルギー・環境問題に関する運動、自然保護運動、人種差別や性差別に反対する運動などに参加する活動が全くふれられていないことに不満がある。これらは慈善活動とは違って「穏健」な活動ではなく、またスポーツの戦いのように「遊戯的」ではない、ある種の本物の闘争の要素がふくまれていることが、彼の平和を好む傾向に合わなかったからかもしれない。しかしこれら社会的活動がこのa.のボランティア的活動に含まれることは明らかである。これらの活動は、一般的には、行うか行わないかは各自の自由な意思に任されていると考えられており、行わないからといって社会的な非難を受ける性質の活動ではない。
共稼ぎで家事育児の必要のある既婚者の場合、これらの運動にかかわることは、私の経験を踏まえると、週1日であっても、相当に辛いことである。私の場合には、「主として自分のためでなく」家族のために仕事(職業と家事育児)を行うことは義務であると感じられたが、同時に社会という他人の集まりのために活動することも義務であると感じられた。私は農業のように直接自分で自然に働きかけることにより稼ぐ(生活手段を得る)よりも社会の相互依存の仕組みの一部を分担することで稼ぐことのほうが自分の「文化資本」を利用できて有利だと考えたからであるが、そこ(社会というインフラ)から一方的に利益を受けるだけでなく、より多くの人が平等/公正に利益を受けられるように社会を変えるための努力をすることは義務だと感じられた。
このa.すなわち「社会運動の活動」ないしボランティア的活動はb.ラジオや模型を組み立てる「技術的趣味」やアマチュア天文学など、c.アマチュアの写真、木工細工、切手集め、e.「新聞や定期刊行物を読む」などとは全く性質の異なる活動だと思われる。(d.宗教活動は除く。)エリアスはa.もb.c.e.もともに「自己実現、自己拡張」と特徴づけるが、後の三者は自分の都合と楽しみから行うスポーツ同様の「余暇」的活動であり、普通は「趣味」と呼ばれている。それらは一人でできる活動であり「慣例化」の圧力もスポーツに劣らず低い。これらは余暇活動に分類されてしかるべきだということは上で述べた。
これに対して社会運動、ボランティア活動は自分の都合は後回しにしなければならず、楽しみは活動への参加の動機にはほとんどならない。社会運動への参加は職業労働の場合の金銭のような、外発的報酬による動機付けは全く不可能で、また、大衆的に盛り上がった場合を別とすれば、行動の正しさに関する内的、主観的確信という倫理的な動機によってしか支えられていない。
一般の労働は種類によっては、何も考えず、手だけ動かしていればよいものもある。ある程度惰性でやれるものもある。しかし社会運動は惰性では継続できず、重力に逆らって上昇するロケットのように、燃料を燃やし続けなければ、直ちに止まり墜落してしまう。計画性、一貫性、約束の遵守など慣例化の圧力は職業上の仕事に劣らず強い。
自由時間が一定であれば運動への参加は余暇を減らすことである。慣例化は自己の自然的衝動の抑圧、自制つまり「禁欲」を主要な要素として含むと言えるなら、社会運動・ボランティア活動への継続的な関わりは、職業労働を行う場合よりもずっと厳しい自然的衝動の抑制と禁欲を求めるように思われ、きわめて強い慣例化圧力を及ぼす。(にもかかわらず、国の内外で、若い頃からほとんど一生をかけて、あるいは退職してから残りの半生を捧げて労働問題や貧困の問題に取り組んでいる、本当に尊敬すべき人々がいる。わたしも一時期不十分ながらこうした活動に関わった。だが退職と同時に社会へのボランティア的関わりもほとんどしなくなっている。私は余生あるいは人生の余暇を自分の好みにしたがってのんびり過ごしたいのである。)
だから余暇を自分のための模倣的あるいは遊戯的活動によって自然的衝動を充足する活動と考えるのであれば、職業労働と社会活動の両方を行う人にとっては、余暇の対極にある「慣例化」活動は職業労働ではなく、むしろ、社会運動やボランティア的活動だと見ることもできる。ところが、これらの活動は自由時間にしか行うことができない。しかし自由時間は、エリアスにおいては、幾分慣例化が浸透はしてはいるが慣例化活動の外部にあるものだと考えられている。だとすると、この自由時間のスペクトルの中に、職業労働以上に慣例化圧力の強い社会運動・ボランティアの活動を位置づけることは土台無理な相談だということになるであろう。
私はまず、生存の必要から職業労働を行う。(ただし「私」とは幸運にも十分な経済的あるいは文化的資本をもち、自分の好む職業につくことができ、職業の中で「慣例化の圧力」にさらされることが少ない、少数のエリートではなく、一般的な事務労働や筋肉労働を職業にする普通の人を指す。)残りが通常の意味での「自由時間」である。エリアスでは余暇は労働との分極化によって行われるべきではないとされながら、しかし、説明抜きで「自由時間」が前提された。しかし、「私」から出発すれば、「自由時間」とは生存のために使われなければならない、半強制的な職業労働時間を除く時間として定義される。
ここから家族のために使われる家事・育児の労働の時間が控除される。家事・育児の仕事は道徳的義務であるというよりも、楽しい共同生活を続けるために、あるいはそれを行わなければただちに生じるであろう多くの不都合、不愉快を避けるために行うことが必要な仕事である。職業労働も家事・育児の労働も私が快適な楽しい生存・生活を送るために必要な、あるいは苦痛・不快を避けるために必要な、換言すれば何らかの「強制」を伴った活動である。
残りが、私が生の必要とは別の、必要を超えた、自由な活動を行う時間である。積極的に自分だけでどう利用するかを決める時間である。というのは、通常私は自分のための楽しい余暇活動を行うこともできるが、また私はしなくても非難されない、社会に積極的に関わるボランティア的活動を自分から進んで行うこともできるからである17)。
余暇活動は積極的な快を与えてくれる。社会運動/ボランティア的活動は私よりも不利な条件の下で生活せざるを得ない人々、支援を求めている人々への援助を行わないことの後ろめたさを減らすために行われるともいえるし、無報酬で他の人々のために活動することは喜びを与えてくれるから行うのだともいえる。余暇活動は法律に違反したり、他者(通常は家族)に迷惑をかけることがない範囲で、大勢の人々とともに興奮を求めるのであれ一人で静かな活動を楽しむのであれ、全く自分の好みだけにしたがって行えばよい。非慣例化機能が大きいかどうかというのは政府や学者の観点からの問題で、余暇活動を行う個々の人にとっては全く関係がない。
の三つの機能があるとし、「余暇とは、個人が職場や家庭、社会から課せられた義務から解放されたときに、休息のため、気晴らしのため、あるいは利得とは無関係な知識や能力の養成、自発的な社会参加、自由な創造力の発揮のために、まったく随意に行なう活動の総体である」という。このまとめはほぼ肯定できる。
しかし、エリアスのいう余暇活動や遊びや趣味の活動の全体を含む「2.気晴らし」については「休息が人間を疲労から回復させるように、気晴らしは人間を退屈から救出する」とデュマズディエは言う。この説明では、「気晴」らしは活動である点で「休息」つまり不活動とは異なるが、やはり「心の疲労」とでもいうべき「退屈」(=恐らく単調な工場労働をさす)から「救出」してくれるものだとされており、積極的、能動的意味が認められていないように見える。他方、「気晴らし」と区別され、デュマズディエがもっとも重要だと考えている「3.自己開発」の機能は社会参加のほか「自発的な学習」つまり「知識や能力の養成」が主要な内容になっている。
また彼は余暇活動における、能動性と受動性を問題にする。余暇活動における能動的な態度とは、「社会的文化的活動への最適な参加を通じて、人間の潜在性の十全なる開花を可能ならしめるような、肉体的、精神的な構えの総体である」と言う。人々は流行に従うなど社会の支配的傾向に同調し、社会に受動的にかかわるのではなく、人間の潜在性〔諸能力〕の十全な開花」を可能にするような方向を目指す社会的活動に能動的・積極的にかかわるべきなのである。
彼は「多くの勤労者が、自分が従事している労働の場においてでなく、余暇活動を通じて、各個人は自分なりの生活様式〔生きかた〕を見つけ、育てる時間と方法をもつことになる。こうした生活様式は同調的な活動ばかりが目立つエネルギーに乏しい社会環境に対する反抗の態勢である」ということには賛成なのだが、社会的活動、社会運動などへの参加が余暇活動に含まれるとするのは、余暇活動への過剰要求のように思われる。私は「社会参加」は家事・育児と同様、「自由時間」の中で行われる活動であるが、余暇活動とは区別されることだと考える。
エリアスは、結婚制度は男女の性愛を慣例化された仕方で行なわせる仕組みだと、次のように述べている。家庭は「ひとびとの職業生活において要求される感情の---抑制に対抗する数々のバランスを提供することができる」。家庭は、都会化、産業化などの過程との関連でいくつかの機能を失ってきたが、たとえば、家族の安全・防衛、子供の教育などの機能とくらべれば、家庭は、「本能的、感情的欲求を満たすための社会的媒介のひとつとしての機能」を依然として保持し続けている、と言う。
しかし、「家庭だけでは他のところで抑制される欲求のすべてをみたすことはできない」。その理由のひとつは、上でもふれたが、家庭そのものが非常に慣例化されており、本能的、感情的欲求を抑制する必要についての意識が家庭内にも浸透していることである。もうひとつの理由は、その欲求の充足が「非常に強い、ほとんど逃れられない責任に関連している」ということである。夫婦は、その欲求充足がもたらす結果、つまり子どもに対して、あらゆる種類の外的、社会的圧力(「隣人、友人、法律」)によって、また、自分たちの責任感や良心という内的圧力によって、そして、「おたがいの愛情によって」責任を負う必要がある。
こうして、結婚は性行為への自然的な衝動を満たし、スポーツと同様、興奮を伴った快楽を社会的な承認のもとで享受することを可能にする制度であるが、同時に、外の社会で求められる他者に対する感情表出の抑制という慣例が浸透していて、抑制の緩和には限度がある。また当然のことながら、家族、とくに子どもに対するさまざまな責任を伴っており、外でのスポーツやその観戦などから得られる、責任なしで手に入れることのできる興奮・楽しみのように、ただ単に生を活性化し、楽しみを与えるだけの仕組みではないという。
こうして結婚は、十分には、性行為への自然的な衝動を満たしてくれず、慣例化を緩和してくれない。したがって、男女間の性愛の欲求は結婚の外においても起こる。だが、アバンチュールは「ひとが「火と戯れる」ように「規範と戯れる」ことを含んでいる。時々それらは度を越えることがある」とエリアスはいう。私が知っている限りでも、世界的大国の現職(当時)の大統領やプロゴルフの世界的スーパースターが、そうした「火遊び」によって世間の非難受けたり受けそうになったりし、「火傷」を負ったり負いそうになったりしている。有名人でない場合にも、浮気や「不倫」がばれれば、夫婦関係が悪くなり、離婚ということになるかもしれない。子どもがいなければどうということはないのかもしれないが、子どもがいる場合には、子どもが小さければ養育の点で苦労しなければならず、また子どもが事態を理解できる年齢に達していれば子供の心を傷つけることになる。子供にとっては両親が喧嘩をするのを見るのは辛いし、離婚ともなれば、相当なショックを受けるだろうことは間違いない。
慣例化の浸透による「新しい種類の緊張」も関係がないとは言えないが、結婚相手との関係がどこかの時点からうまく行かなくなり、家庭では十分に満たされないがゆえに、「ユニークで新しい愛着」を外で求めようとするのだろう。しかし、それがうまくいかず、しばしば取り返しのつかない「不幸な」結果を招くことになる。本当に仲の良い夫婦もあり、よい結婚に恵まれれば、その人は幸福だと言えるだろう。とはいえ、夫婦の関係が結婚当初と同じようにいつまでも良好であり続けるということはまれなのではないだろうか。それぞれの気質や性格、思想や、生活態度など様々なことが2人のあいだに亀裂を生み出す。結婚から時間が経ち、子どもができてから、あるいは大きくなってから、その隔たりがはっきりしてくる。
こうして、男女間の性愛の欲求は結婚の外においても起こる。しかし、結婚相手以外の異性との恋愛は社会規範によって公然とは認められていない一種の「火遊び」であるがゆえに、いっそう大きな「楽しい興奮」を与えることになるだろう。このように、結婚制度の外側で、その拘束から免れたアバンチュールとして行なわれる恋愛は、結婚相手との愛の行為と較べて(たとえ、それが夫婦間の単なる「慣例」に従ってあるいは義務意識にしたがって行なわれるのではない場合であっても)、非慣例化機能の度合いは大きいであろう。しかし非慣例化の機能が大きいとはいえ、「楽しい興奮」はそのまま快楽である、あるいは快楽を生むとは言えないだろう。
(狐狩りが禁止されるまでの)狐狩りにおける英国のジェントルマンたちも、球技場やコンサートホールに集まるサッカーファンやポップスファンも、良心のとがめをなんら感じることなく、周囲の目を気にすることなく、「楽しい興奮」十分に味わうことができる。
しかし結婚の外で行なわれるアバンチュールは、小説やテレビドラマのなかでは日常茶飯事のように行なわれてはいても、スポーツ観戦の場合のように、その自然的衝動、感情に従う行動が「当然」のことだと一般に見なされているわけではない。それはやはり「火遊び」なのである。それは、外的には、たとえば、不倫という社会的非難を浴びることであり、また、恋愛結婚こそが理想だという近代以降の結婚観や、愛に基づいて性交は行なわれるべきだという性愛思想、結婚相手以外の相手との性行為は結婚相手を裏切る行為であり、人格の誠実さの欠如を示すことである、あるいは、「自然的衝動」をコントロールできない意志の弱さの現れ、つまりカントの言う「道徳性」の欠如であるというような倫理観、などなどの内面的規制が働く結果、「良心のとがめ」あるいは後ろめたさを感じることなしには行ない得ない行動なのである。そして、これら内外からの規制は明らかに「苦」を生じる。これに対して結婚相手との愛の行為においては、何の心配もなく、性行為をゆったりと落ち着いて楽しむことができる。結婚外の恋愛は、強い興奮を伴った大きな精神的快楽をもたらすがまたそれは精神的緊張の苦をもたらす。私は、ヴァラン夫人との恋愛など強い興奮を伴う快楽に満ちた生活のなかでは見出すことのなかった大きな幸福を、孤独な散歩のなかで送る静かな生活に見出したルソーを思い出す。強い緊張と興奮を伴う快楽は持続的な幸福を与えないのである。第一章参照。
なお、以上の議論はエリアスの家族論についての見解に関連して述べたもので、エリアスは結婚も性愛も男女の間で行われることだと考えている。しかし同性間での性愛も結婚も存在する。私は性愛に基づく共同生活を結婚と考え、上で述べたことは異性間であるか同性間であるかにかかわらず、妥当すると思う。
第一章を読まなかった人の為に要約すと、エピクーロスの教説においては、人間は十分な勘考・思慮に基づいて快楽を最大にするように生きることが勧められていた。だが、彼は様々な快楽のうち精神の平静こそが最大の快楽だとしていた。彼に従えば、人々は生存にかかわる基本的な欲求を充足することができたら、食や性などの限度のない肉体的な欲求をコントロールし、哲学や自然研究などによって精神的な不安を解消し、精神の「平安」を達成するよう努めることが望まれるのである。恋の火遊びに伴う緊張、球技場でプロ・スポーツの観戦をするときのあるいは遊園地の機械に乗るときの興奮は、エピクーロスから見れば、精神の強い動揺、つまり苦であろう。「戦う遊び」であるスポーツを行ったり見たりすることによるショック療法的な慣例化の緩和というエリアス的 観点はエピクーロス的な快楽、持続的な精神の平静さの追求を主眼とする観点とは正反対といっていいほど異なる。
現代日本においては生存に関わる基本的な欲求はほぼ充足できている。問題は精神的な快楽にある。多くの人はエピクーロスが説くような「精神の平静」を究極目的にするような生きかたを好まないだろうし、エピクーロスのいう生きかたは求めても実現は難しいと考える。では、われわれはどのような快楽を求めるべきだろうか。
エリアスは人々がどのように行動すべきかを説くということはしないが、文明化過程の進展に伴い、次第に、単純で衝動的な活動への愛好が減り、より複雑な「洗練・純化」された活動が増えると予想している。この点はエピクーロスが望ましいと考えていると想像される方向と一致しているように思われる。興味深いことだ。
スポーツの多くは競技、つまり戦いの遊びである。戦いは、試合をするプレーヤーにとっても、応援の形で参加する観客にとっても、興奮を強めるスポーツの重要な要素である。スポーツ、それも暴力を行使する程度の大きなスポーツほど、人々に強い興奮をあたえる。そして、競技スポーツを始めとする体を多く使う活動、体を使って感情を表現することが可能であるような活動ほど、「精神の活性化」をもたらす働きが大きく、「非慣例化や緊張の緩和」の機能は大きい。つまり、芸術活動よりはあるいは知的なゲームよりは、スポーツのほうが「非慣例化」の機能は大きい。エリアスのスポーツについての見方をこのようにまとめることができる。しかし、また、彼によれば、文明化の過程はまだ続いており、暴力の抑制(ただしこれには国民国家という壁の内部という限界があるが)、自然的感情の表出や衝動的行動の抑制はよりいっそう進み、スポーツや余暇活動もまた洗練されていくという。以上が本章第3節でみたエリアスのスポーツについて説明の要約である。私の意見も少し述べた。
人間だけが持つ文化の一つ、スポーツを「より高く、より美しいものにするには、スポーツを行なうものの精神とそれを取り巻く環境の清らかなことが必要である。美しいスポーツマンシップはこのような世界に生まれ、やがて生活を導く基として社会のために貢献するであろう。ゆえにスポーツマンは競技場にあると同じ精神と態度で生活し、りっぱな社会人でなければならない。ここに真のスポーツがあまねくゆきわたり、すべての人のものとして、発展することを願いスポーツマン綱領を定めた」。
以下4か条の「競技するもの〔者〕」についての、そして1か条ずつの「競技を審判するもの〔者〕」と「競技を見るもの〔者〕」についての条項が述べられている。
最後に書かれている「競技を見るもの」、つまり観客についての条項では「感情にとらわれた応援をせず、美しい精神と優れた技をたたえ、スポーツのよりよい発展を願うこと」が求められている。4か条の「競技するもの」でも、似たような態度が求められているが、中核になるのは「競技するものは、スポーツを行なうことによって、社会的名声や物質的な利益を得ようという考えをもたないこと」だろう。エリアスのスポーツ概念はアマチュアのスポーツにもプロスポーツにもあてはまるものであったが、この綱領は、職業選手には明らかに該当しない。スポーツマンという語で考えられているのはアマチュアのスポーツマンだけである。
アマチュア amateur はラテン語の amator(愛好者)に由来する。スポーツにおけるアマチュアリズムとは,アマチュアは趣味としてスポーツを行い、それによって生計を営んだり賞金を得るなど、経済的な利益を追求してはならないという考え方である。
近代スポーツは19世紀、イギリスのクラブに寄り集まったジェントルマンたちが作り出した。1839年イギリスの第1回ヘンレー・レガッタで、参加規定に初めてアマチュアという名辞が使われ、66年にはイギリス陸上競技選手権大会で、さらにアマチュア規定が整備され、これがその後長くアマチュアリズムの規範となったという。初期には、アマチュアは〈ジェントルマン・アマチュア〉と呼ばれて、紳士と同義語とされ、〈工場労働者、職人、手工業者、召使〉はすべて、アマチュアではないとされたのが著しい特徴で、アマチュアリズムは労働者差別の身分規定でもあった。1894年創立のIOC(国際オリンピック委員会)はイギリスのアマチュアリズムをそのまま継承し、オリンピック大会は世界のアマチュアのスポーツ祭典と規定された。
参考:池田恵美子「ジェントルマン・アマチュアとスポーツ―19世紀イギリスにおけるアマチュアの理念とその実態」、望田幸男・村岡健司監修『スポーツ』<近代ヨーロッパの探求>⑧、ミネルヴァ書房、2002; 佐伯 聰夫「アマチュアリズム」『平凡社百科事典』など。
第2次世界大戦後スポーツの技術、施設、用具などが新たに開発され、世界的にスポーツの技能水準が急激に向上した。スポーツの一流選手は、アマチュアでも、生活時間の大半をスポーツにあてるようになっていった。こうしたなかで、62年イギリスのクリケット連盟がアマチュアとプロとの差別撤廃に踏み切り、68年には全英テニスがプロ選手の参加も認め、賞金制を導入した。1964年にオリンピック東京大会が開催されたころには、まだスポーツは主にアマチュアの選手によって行なわれていると考えられていた。しかし74年のIOC総会で、オリンピック憲章から〈アマチュア〉の字句は消え、オリンピックは〈世界のアスリートのスポーツ祭典〉となった。さらに82年、国際陸上競技連盟(IAAF)が、選手が賞金競技に出場することを承認し、アマチュアリズムは競技スポーツの世界では、まったくその存在理由を失うに至った。日本スポーツ振興協会の「スポーツマン綱領」が観客に求めていた「感情にとらわれた応援をせず、美しい精神と優れた技をたたえ、スポーツのよりよい発展を願う」という精神も意味のないものになった。
競技会の会場、競技場や球場、スタジアムは、興奮を求めて集まる観衆と、その観衆の大声援にこたえて体を張って戦うプロの選手たちとが一体となって、「良心の咎めなしに」興奮を楽しみ、感情を露わにする場所に変わった。トップレベルのスポーツ大会では強い興奮、集団的一体感が生み出される。競技場は「彼ら」に対抗する「われわれ」の集団との一体感を強める場になる。そして競技場でのこの興奮は、かつての社会における宗教的興奮に似たものを生み出している。スポーツが擬似宗教的活動になり、社会生活における宗教の衰退を幾分補足するはたらきをしている。スポーツは「世俗的宗教」になりつつある(『スポーツと文明化』)。こうした、エリアス/ダニングの議論は、マスコミを通じて知られる、最近の日本におけるプロ・スポーツの隆盛、スポーツ熱の高まりをよく説明してくれるように私には思われる。
21世紀の主流のプロ・スポーツにおいては、選手は、練習の時であれ、試合の時であれ、楽しんではいられない。多くの観客を集めるのに必要な、緊張に満ちた高いレベルの技術で戦いを展開することが必要だ。また種目によってはオリンピック大会への出場を目指し、あるいはスターとなって普通のサラリーマンが一生かかっても稼げない額を1年か2年で稼ごうとして、スポーツ選手は体を張って、スポーツに打ち込む。しかし、がんばってスポーツに打ち込むのは、プロのスポーツ選手だけではない。
企業のクラブチームの選手たちは、企業に勤め、社員として給料を受け取っているが、企業本来の仕事を行なうのではなく、ほとんどの時間をそのスポーツの練習に当てている。彼らは、会社の中で、他の社員が仕事に励むのと全く同様にあるいはそれ以上に、その会社の仕事としてスポーツに打ち込む。勤務時間以外の余暇、遊びでスポーツを楽しむのではない。彼ら準プロの選手は、会社が傾くなどして「解雇」されることがあっても、有名チームの場合、他の一般社員と異なり、クラブの一体性を保ったまま、他の会社に「移籍」する。
だが、子供同士の間のあるいは先輩のイジメや監督の暴力が原因で(しかも親の期待を裏切りたくないという思いも関係するなどして)、クラブに通うこと、部活を続けること(ひいてはその学校に通うこと)について悩み苦しんでいる子どもが相当にいる。朝日新聞2014年9月3日~5日、「子どもとスポーツ」第9部「やめる、やめない」で書いているように、 明らかに指導者に問題のあるケースもあるようだ。しかしそれは指導者の個人的な資質や性格などによると言い切れないところがある。朝日の記事では、競技志向の強まりを指摘する専門家もいる。闘うスポーツ、競技のなかに暴力の要素が含まれていること、つまり格闘技だけでなく多くの競技においては体力がつまり、肉体的な力で相手に勝ることが求められることと関係があるように思われる。子どもたちの間では結局イジメは体力に劣る弱いものに対して行われるのだろうし、指導者は言葉や論理的な説明にたよるのでなく、暴力によって自分の考え、方針を貫徹しようとする傾向があるのではないだろうか。
将来有名なスポーツ選手になるという目標の実現がすべてなのではなく、スポーツをやることを通じて子ども時代を楽しく幸福に生きることができ、また、大人になったとき、たとえプロあるいは準プロの選手になれなくてもスポーツを楽しみつつ生きていくことができるようになるためには、大人である指導者が指導をどのように行うべきかかについて、スポーツ界として意識的に取り組んで改革していく必要があると思われる。
プロスポーツが隆盛を極めているように思われるが、それでも、職業ないし準職業としてではなく、趣味で継続してスポーツを行う人もある。彼らは余暇に、あるいは退職後の自由な時間を使って、楽しむためにスポーツを行う。2013.1.20付け愛媛新聞では、スポーツ欄ではなく地方ニュースのページに 65歳以上の「ハイシニア」で作るソフトボールチーム「新居浜球友会」(24人)の話が、写真入りの記事で載っている。週2回の練習。ハイシニアの県内登録ソフトボールチームは16。新居浜旧友会は昨年の西日本大会で優勝。全日本大会でベスト8であった、という。
スポーツは余暇に(多くて)週に1~2回、遊び、娯楽、気分転換として楽しむことのできるものでもあるが、また、職業として、あるいは学生の部活として、子供たちのクラブでの練習として、毎日のように行なわれている。スポーツは日常の中に広く浸透している。学校で行なう勉強は(各生徒にとって)職業に就くための準備だ。学生が部活でスポーツに打ち込むのは、プロのスポーツに就くための準備である。勉強は必ずしも好きでやるのではないが、スポーツは好きではじめる。若者は勉学に努めるのと同様に真剣に、また、それ以上にスポーツに打ち込む。
小学生以上になると、学校で、教室の中で、ある種の厳しさを伴って、日常生活を送るのに必要な「知識」を学ぶとともに、将来の就職に役立つ事柄の基礎を「教科」として学ぶ。これを「学習・訓練」と呼ぶことができるだろう。体育系ばかりでなく文科系も含め、「部活」は教科以外のことがらの「学習と訓練」の場である。職業・仕事は大人が経済的自立のため、また、できれば自分の興味を満たし、才能を生かすための活動である。
現代人は、幼児のときにはともかくとして、子供、少年、若者のときに各時期の自己の生を気のむくまま思うままに自由に楽しむのではなく、大人になって仕事をするための準備にエネルギーを注ぐように仕向けられている。そして、しばらく前から、子どもたちは、学校で勉強するだけでなく、体を使うスポーツや舞踊や音楽の教育を早くから受けるようになった。
日本でスポーツの商業化、職業化が進むのは1970年代のようである。それ以前は、スポーツは娯楽、楽しみ、遊びの一種だった。子供たちは放課後や休日に、将棋や、五目並べ、そして、石蹴りや縄跳び、鬼ごっこやかくれんぼ、トンボ取りや魚釣りで遊び、相撲、野球(しばしば三角ベース)、ピンポン、バドミントンなどの「身体運動」、「スポーツ」で遊んでいた。しかし、商業化、職業化によって、スポーツは、アスリート、スポーツ選手たちによって演じられる、映画や歌謡などと並ぶエンターテインメント産業となり、観客を楽しませる、一種のサービス業、「仕事」になってしまった。スポーツは、一方で、行なって楽しむのではなく見て楽しむものとなり、他方で、科学者や技術者、医者や弁護士、あるいは銀行員のように、専門の技能や知識の習得を要求する職業となり、遊びや娯楽の活動ではなくなった。
そして見開きになった23ページには、プロ野球の結果が載っている。セリーグでは巨人が「光星学院・坂本の一発」でヤクルトを破り、パリーグではオリックスが「大阪桐蔭中田の連打」にもかかわらず日本ハムに負けた。中央に「OBハッスル、球児に負けない」という見出しがあり、坂本と中田がホームランを打った瞬間の大きな写真がある。(下に「タカ加速7連勝」の見出しとともに「タッチを交わすソフトバンクのナイン」の小さな写真がある。)なるほどと思った。私はもともと大したスポーツファンではなく、サッカーJリーグの勝敗などに全く興味がないし、野球もせいぜい「アンチ巨人」ファンで、「オレ流」の落合監督時代の中日が優勝するのを喜んだ程度であり、高校野球、甲子園大会にもほとんど興味がない。この年は、愛媛県代表の今治西高校が、相手の高校名は忘れたが、一試合22か23の奪三振記録を作った「マツイ」という好投手に抑えられて、緒戦で敗退したことを、連日、定時ごとにラジオから流れてくるニュースで聞かされて知っていた程度である。「コーセー学院」も「大阪トーイン」も聞いて知っているが、プロの中田や坂本がそれらの出身であることははじめて知った。新聞でスポーツが占めているスペースはふだんでも28ないし30ページのうちの4~5ページであるが、1週間か10日前、ロンドン・オリンピック大会開催中には、10ページ以上、新聞全体のおよそ半分がスポーツで占められていた。マスコミのこうしたスポーツの扱い方には、少々辟易しているほどで、熱心なスポーツ・ファンというには程遠い。

私が高校生であった頃、つまり50年ほど前には、(地方の公立)高校は大学に進学するために、あるいは、地元で就職するために行くところだと、中学生、その親、学校の先生は考えていたと思う。だが、上のニュース(の見出し)を見て、高校の中にはプロの野球選手になるために行く場所になっているものもある、と改めて思わせられた。たいていの高校は今でも、大企業や官庁に勤めるのに必要な知識・学歴(文化資本)を身につける機関である大学に行くために必要な/便利な場所である。医者や弁護士や科学・技術者になるためには「知識」が、そして一定の知識があることを証明するものとしての学歴・卒業証書が必要で、それらを獲得するには相当の時間が必要だ。時には司法試験に合格するために、大学卒業後、何年もかけて勉強するひともある。あるいは科学・技術者となるために、あるいは大学教員になるために、修士課程、博士課程で長いこと学ぶ。
これに対してスポーツには、「知識の量」に相当する「技量」だけではなく、体力が必要で、より早い時期、若くて身体的エネルギーに満ちているときに仕事に就く方がベターだ。こうして、スポーツ選手は、必要な技量を身につけることができれば、高校までで、ときには、中学まででも、国内のあるいは国際的な試合に出場する可能性を手に入れることが十分にできるのである。依然として、かなりの割合の若者にとっては、高校は通過点であるに過ぎず、最終学歴になるのは大学、あるいは大学院である。だが、スポーツで生きることを目指す多くの若者にとって、高校が最終的な訓練の場であり、そこを卒業すれば若者はひとり立ちし、大人となるのである。
面白いのは、知識を学ぶところである大学に「名門」があるように、高校にも「名門」があることだ。甲子園大会には同じ高校が県代表として繰り返し出場する。私学が多いが公立にもある。とくに私立では優遇制度を利用して能力のある選手が大勢集まって(集められて)きて切磋琢磨するから、名門校のチームに入れば、選手個人の成長も促進される。こうして同じ高校からプロ野球で活躍するプレーヤーが輩出されることになるのだろう。
だが、ちがう点もある。大学では学閥があり、名門に入れば、すでにそれだけで、就職への有利な道が開かれる。しかしプロのスポーツ選手になることを可能にするのは、スポーツの「有名高校」、「有名大学」のスポーツ部員になることではなく、あくまでも、本人の実力だけであろう。
「15号ソロを含む今季二度目の4安打」と「猛打」した中田がインタビューで、チームが「負けたので意味がないです」と言っている。日本では、選手が、試合における自分の成績よりも、チームの勝敗を重んじた発言をすることが多い。あるいはメディアがそのような発言を載せることが多い。また、高校野球の解説者が、チームの勝利に貢献することが大切だと語るのをしばしば聞く。試合に勝つためには、というのではなく、教育という目的と関係付けながらそう言われるのである。
なるほど、ほとんどの球児はふつうの企業に就職することになるが、その場合に企業というチームに貢献する精神が、確かに「高校野球」を通じて育つだろう。(しかし、監督や上司の判断が正しいときに、その命令に従い、たとえば、走者を還すために、長打を狙わずバントをするという行為が「チームに貢献する」ことになるのである。監督・上司の命令に従うことが常に「チームへの貢献」になるわけではない。単に「上司」の言うとおりに行動する社員が会社に本当に貢献することができるかどうかは極めて怪しい。)
だが、一般に、各選手がチームの勝敗を自分の成績以上に気にかけるのは、他のチームとの関係においてであって、彼がつねに同僚、チームメイト、他の部員を大切にし、彼らと仲良くしているかどうかは別の問題である。むしろ、同じポジションのチーム・メンバーはライバル関係にある。高校生の場合、プロ野球に就職できるかどうかはチーム力や学校名によるのではなく、個々の選手の力できまるであろう。全国約4千校の野球部に属する高校球児たちは、プロ野球に就職できるように、自分の力量を球団のスカウトたちに認められることを念頭に、日々、チームの力を利用しつつ、自分のために訓練を重ねているのである。野球の名門校といえども大学の学閥のような機能は果たしてくれない。
民俗学者宮本常一によれば、日本では明治時代を過ぎても、貧しい農山村の子どもは、小さいときから大人に交じって働かされた。宮本の郷里、山口県の周防大島から対岸愛媛の山村に樵夫や大工として出かけて行った者は、その地の貧家から子どもを託され、徴兵検査まで預かった。これが「伊予子」と呼ばれた。それが減ったのは大正の好景気の頃からである。大島の近くの好漁場に臨む情島では、漁師が潮流の速い海で釣りをするために、舟を流されないよう絶えず艪を押してくれる梶子が必要で、大正の好景気の時代、魚は高く売れたが、戸数80個あまりの情島でほぼ同数の「伊予子」が梶子として雇われた、という。
(宮本常一著作集第2巻『日本の中央と地方』(未来社、1967)、「2.島の暮らしと出稼ぎ」)
由良半島南岸の漁村を結ぶ、バスも通る現在の県道は彼の中学時代には存在しなかった。半島に点在する浦々の集落は当時は船で結ばれていた。浦々を結ぶ道は半島の尾根伝いの細い山道しかなく、そこは人一人が歩いて通るのがやっとで物を運搬することは不可能だった。彼の生まれ育った集落から、愛媛の宇和島と高知の宿毛を結ぶ(旧)国道に出る細い山道は自転車の通行も無理な急坂で、国道まで1時間以上かけて歩かねばならなかった。彼は、中学卒業後、大阪に出て働き、定年でUターンして郷里に戻った。これら数箇所の集落からなる内海村が真珠養殖で栄えるようになるのは昭和40年代以降である。源さんの子ども時代がそうだったように、ごく最近まで、日本においても、「山間または半島のさきなどの交通に恵まれない地帯」、宮本の言う「僻地」(同著作集第2巻「5.僻地性解消のために」)では子どもが小さな大人として、家族労働の一部を担わされていた。
ルソーの肖像画
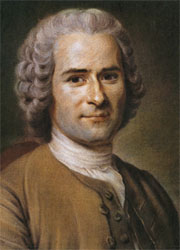
(今野訳、岩波文庫、また戸部訳<世界の名著>『ルソー』)
他方で、文科省が学校保健安全法で義務付けられている小中高校で毎年行う健康診断の検査項目を大幅に見直すことにした。2012年2月20日付愛媛新聞によると、戦前から行なわれてきたが、測定の必要性に疑問があるという「座高」の測定は止める一方で、新たに関節痛などのスポーツによる障害を早期に発見するための検査項目を導入する予定である。サッカーやテニスなど地域のスポーツクラブや部活動で体を酷使して骨や間接の異常を訴える子どもが増えているためだという。ここにはスポーツが脚光を浴び、子どもたちに魅力のある活動になったことに伴う負の面が現れている。子供たちは大人の職業選手と同じように、激しい練習に打ち込み、子どもの時から「職業病」にかかってしまうリスクを負うことになる。子どもたちはぎりぎり一杯に自己の身体を鍛え、使う。なかには持って生まれた身体能力を超えた訓練で体を壊してしまうものもいるということであろう。
精神的にはどうなのであろうか。子どものときからまっしぐらに、自己の生きる道を進み、真剣に自己実現を追求する。彼/彼女はわき目も振らずにひたすら専門的な技や芸を身に付け、磨くことに子ども時代と青春を過ごす。知識だけを振り回す頭でっかちも困るが、頭が空っぽな筋肉マン、「体育系」も敬遠されないだろうか。
かつて、自分の専門しか知らない、常識を欠いた学者・研究者を「専門バカ」と呼んだことがあった。この言葉を用いて誰かを非難することがもっともであるのは、その人物が何らかの権限や権力を行使する立場にあり、他者を圧迫したり弾圧したりすることの決定に関与していながら、その決定の適不適についての判断を行おうとせず、専門の立場に閉じこもり、無責任な態度を取っているときに、圧迫を受けたり弾圧されている側の人々がその人物を非難する場合である18)。 だが、他者に対する権力行使と関係のない個々人が、個人として、自分の専門にしか関心がなく、世間的な、あるいは一般的な常識を欠いているということがあるかもしれないが、それは全く別のことである。常識をたっぷり心得た、常識しか知らない人と比べるまでもなく、知的分野であるかスポーツの分野であるかに関わらず、狭いが深い専門に生きることの是非・善悪を簡単に論断することはできないだろう。
たとえば、小説家によって作られた像の影響があるかもしれないとはいえ、剣豪・宮本武蔵に、何か人間としての魅力を感じる人も多いと思われる。それは、彼が単に天下無双、最強の武芸者であったということによるのではなく、世の戦乱が収まり、武士が戦闘者から統治者に変わりつつあったにもかかわらず、あくまでも戦いにこだわり、ひたすら剣の道を究めようとした孤高の武芸者であったということによるのではないか。
いかなる道においてであれ、自分で追求する道を専門的に深く極めることで充実した人生を送ることができるかもしれない。専門家であることが社会に役立ち、より大きな社会的評価を受け、生きていくことに有利であるということが理由ではない。しばしば1世代か2世代後には変わってしまう社会的評価に従って自分の生き方を決めるのでなく、(他者にしわ寄せをしてはならないが)自分の本当にしたいことを見つけ、追求したい道に生きることが、充実した人生を送ることだと私は思う。多くの人が賞賛する人生はあっても、模範としてつき従うべき人生は存在せず、人間とはこういうものであり、人生とはこうでなければならないということは決して言えないと私は思う。
だが、スポーツがいくら好きでも、スポーツだけを一生続けていくことの出来る才能や運に恵まれた人はごく少数であろう。多くの選手が現役引退後は他の仕事をするか趣味を見つけ出すかしなければならないと思われる。
プロ野球引退時の選手の言葉をしばしば耳にする。好きなことに打ち込んでこられて本当によかった、野球人生に悔いはないという趣旨のものが多いように思う。(引退に際して、野球を選んだことに後悔しているという選手がいたとしても、それは新聞には載らないだろうが。)だが、現役引退だけで、人生についての判断を下すのは早すぎるように思う。多くのプロ野球選手は40歳前に引退する。この人たちが現役引退後も野球に関係した仕事を続けていくとしたら話はまた別だが、そうでない人は、野球以外のことをやりながら残りの30年近い人生を生きていく。どれほど自分の愛好するスポーツ一筋に打ち込んできたにせよ、その人がそのスポーツ以外何も興味をもたずに生きてきたとすると、後半生は退屈なものになってしまうだろう。これはスポーツに限らない。会社のなかで、仕事だけで生きてきた人にも同じようにあてはまることだが。
M.マートンは大リーグでもプレーし2010年に阪神タイガースに入団して、3度最多安打のタイトルを獲得した。彼は新聞の中で、「スポーツだけを続けて20代後半か30代でやめたら、〔その後の人生を〕どうやって生きていくのか」と問うている。彼は自分が卒業したジョージア工科大学の「トータル・パーソン・プログラム」(人格形成プログラム)を学んだ経験を踏まえ、やりたいことがたくさんあり、残りの人生を豊かにするために大学に戻って勉強したい、と言っている(2014.9.9朝日新聞)。大いに耳を傾けるべき意見である。
--------------- 注18)山本義隆『私の1960年代』(株式会社金曜日、2015年)に見られるように、1960年代末の東大では、自治会役員の学生らに対して当局が下した事実誤認を含む不当で一方的な「処分」に関連して、教授たちの中にこうした人物が多数存在した。ただし「専門バカ」は責任逃れのために装われた態度であったかもしれない。(2015年10月追加。)スポーツを選ぶ子どもは、学習塾に通う子どもとはちがい、将来の自分の幸福、満足のいく安全な生活のために現在を犠牲にするのでなく、今、自分の好きなスポーツに打ち込むという面が強いと思われる。そのような生き方を自分から進んで選んだのであり、親がそれを認めたのであろう。将来の職業という点からすれば、その子は学校での勉強が面白くないと感じて、あるいは一般的な庶民である親の日ごろの言動から、ふつうの職業が決して楽しいものでないことを予感して、普通に勉強する生き方を選択しなかった。親は子どもがふつうの勉強をし、ふつうの仕事に就くよりも、スポーツ選手として活躍してくれることを期待して、スポーツ・クラブに通うことを認めたのであろう。
ロンドン・オリンピック体操個人総合で金メダルを取った内村航平の両親はともに体操の選手で自分の家に練習場を設けて、子どもが小さいときから体操をやらせていたというが、このようにふつうの職業に対する評価とは関係なく、もっぱらスポーツに対する積極的評価にもとづいて、子どもにスポーツを選ばせるというケースは例外中の例外であろう。多くの場合に、ふつうの職業に対する親の消極的評価が原因となって、子どものスポーツ選択が可能になると私は推測する。単にマスコミなどによるスポーツ人気を見て、子どもの希望にしたがって、クラブに通わせる金持ちはそう多くはないと思う。
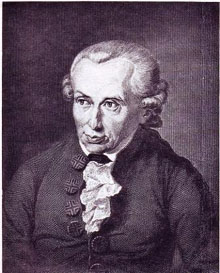 将来のオリンピックやワールドカップ、あるいは有名な国際大会に出場し活躍することを目指してスポーツに打ち込む子どもたちの生活には、ほとんど遊ぶ時間がなく、余裕がないということに疑いはない。ある程度のレベルに達した子どもは、ふだんは地元のクラブなどで練習を行い、学校が休みの時には、練習試合のために国内外を移動して過ごす生活に明け暮れるようだ。まるで武者修行で全国を旅する武芸者のような生き方である。このような、小さいときから訓練に訓練を重ねる人生には、遊び、余裕がなく、tolerance、つまりその子の「容量」のようなものによっては、酷使する体の部位だけでなくどこかに無理が生じるのではないかと気になる。
将来のオリンピックやワールドカップ、あるいは有名な国際大会に出場し活躍することを目指してスポーツに打ち込む子どもたちの生活には、ほとんど遊ぶ時間がなく、余裕がないということに疑いはない。ある程度のレベルに達した子どもは、ふだんは地元のクラブなどで練習を行い、学校が休みの時には、練習試合のために国内外を移動して過ごす生活に明け暮れるようだ。まるで武者修行で全国を旅する武芸者のような生き方である。このような、小さいときから訓練に訓練を重ねる人生には、遊び、余裕がなく、tolerance、つまりその子の「容量」のようなものによっては、酷使する体の部位だけでなくどこかに無理が生じるのではないかと気になる。
こうして、一見したところでは、子どもが自由に遊ぶのが自然で、子どものときから訓練を受けさせることは不自然、もしくは反自然であるように思われるが、しかし、子どもを単に好きなように遊ばせておくことが自然であり、そのようにすることが望ましい「人間」を育てることだとも言い切れない。そもそも「人間は教育によってはじめて人間になる。人間とは教育がその人からつくり出したものだ」(カント)という考えもある。
(カント/伊勢田耀子『教育学講義他』<世界教育学選集>、明治図書、1971年)
モーツァルトやエジソンやフィヒテなどの子どものときの逸話から知られるように、「天才」や「神童」は特別苦労して訓練を重ねなくても、一定の環境があればおのずとその特別の才能を発揮して、傑出した存在になる。そうでない、ふつうの、多くの子供たちは、意識的な学習や訓練によってはじめてひとかどの人物になることが出来る。だが、人より一歩か二歩前に出ようとして、小さいときから遊ばずに、スポーツクラブもしくは学習塾に通って訓練・学習を重ねることは、子どもが子どもであることを楽しむことを知らないまま、子どもの時期を飛び越して、ただの大人になってしまうだけのことではないか。しかし、人間は、子どものときから訓練・学習をおこなってはじめて自己の持っているものを開花させることができるのであり、子ども期の準備がなければ、大人になって自己の能力を発揮することはできない。人間とは、大人の人間のことであるとするなら「人間は教育が作り出したものである」というのもまたその通りだ。----いったい、どちらの考え方が正しいのだろうか。私にはどちらが正しいとも言えない。しかし、人間は、幼児であり、子どもであり、青年であり、そして成人の後には老人でもある。カントは人間が「大人」以外のさまざまなものであるということを軽視しているように思われる。
したがって、また、「大人」の後にやってくる老年期もまた人生においてその独自な意味を持つものではなく、子どもがまだ大人ではないものと見なされたのとは逆に、老人は人間の最高状態をすでに通り過ぎてしまった存在と見なされる。老人とは、かつては意義のある何かであったが今はそうではないもの、いったん完成したものがこんどは壊れたり擦り切れたりしつつあるもの、人間ではなくなりつつあるものである。
キケロー(第一章参照)のように、「肉体は老いるとも心は決して老いない」。「老年期においてむしろ知力、精神力が高まる」と見る人もある(中務哲郎訳『老年について』岩波書店、2005)。老年期について考えるのはまたあとで行うことにして、仮に、キケローの言うように老年期が完成状態からの単なる退化ではないと考えるにしても、人生の意味を何らかの能力の発揮に見出す限り、子どもの段階はその能力の完成に向かう最初の数歩、完成した老年期を含む「大人」に向かう助走とみなされる。そして、助走においては、途中で立ち止まり、休憩したり何かほかの事を楽しむことは許されず、開花=跳躍まで一気に走りぬかなければならない。 また、才能を開花させるということは、社会に役立つ何らかの機能を果たして社会に貢献すること、そしてそのことを人々に認めら、評価されることだと考えられているのではないだろうか。社会に貢献することが人生であり、人間はそのために生まれてくると考えられており、そのために子どものときから、訓練・学習に励むことが奨励されるのではないだろうか。
しばしば退職後の人生を指す日常的な言葉として、セカンド・ライフという言葉を聞く。たとえば『戦後史大事典・増補新版』(佐々木毅ほか篇、三省堂、2005)の「定年」という項目のなかには「セカンドライフを楽しむ」という小見出しがある。この言葉によって、退職前の人生があり、退職を境に第二の人生が始まると考えられている。老人の生の意義も認めている。だが、人生には第一のそれと、第二のそれの2つしかなく、人生には二段階しかないと考えられている。成人の時期が、前期と後期に分けられているだけであり、それとは別の未成年の時期、子どもの時期は人生における独自な段階だと考えられていないことが分かる。
全国およそ4,000の高校の硬式野球部が毎年甲子園を目指す。野球部員の総数は17万人近い。1年の時から続けている3年生部員の割合は約9割り(2015年6月30日朝日新聞P18)という。毎年、部員の3分の一が卒業すると仮定して、毎年、5万人以上の「球児」が、可能ならプロ野球の選手になりたいと考えるであろう。
プロ野球両リーグの12球団が契約することができる「支配下選手」の数は球団ごとに最大70人(そのうちの、28人が公式戦に出場できる「一軍」、残りは「二軍」登録となる)である。Wikipedia。したがってプロ野球選手の数は全部で最大840人ということになる。
選手の寿命はわからないが平均15年と仮定すると、プロ野球界全体で、年々、15分の1、つまり56人が新人で補給されることになる。選手寿命が10年なら、84人が新人の数になる。こうして大雑把にみれば、年々、高校球児の0.2%程度(56~84÷5万)しかプロ野球界に入ることはできない。残りの99.8%の高校球児は他の仕事に就くか、プロ野球とは別の、独立リーグなどに入って、野球を続けることを目指す。
プロ野球の球団は「支配下登録選手」のほかに3年間に限って契約することができる「育成選手」を擁している。年俸は最低240万円である。プロ野球規約は毎年のように変更されているようだが、球団が契約できる育成選手の数は(2013年春の時点では)「当面さだめられていない」。支配下選手はどの球団も制限数一杯に契約しているが、この育成選手に関してはソフトバンクのように20人を越えているチームもある一方で、日本ハム、千葉ロッテ、ヤクルトや中日のように、ゼロないし2,3人しかいないチームもあり、全体で60人ほどである。
青春を野球にかけた若者のほとんどは、資本を退蔵させて、ふつうのサラリーマンとして他の仕事に就く。彼らはうまくいけば仲間を見つけて休日に野球を楽しむことができるかもしれない。しかし、たぶん、かれらは野球を「する人」にはなれず、テレビやスポーツ新聞でスポーツを「見る」だけの人、時々はスタジアムで行われるプロの試合の観客として応援するというしかたで「スポーツに参加する」人になるのだろう。そしてふつうのサラリーマンと同様の人生を、たぶん、熱心なスポーツファンとして、送るだろう。
だが、高校を卒業したときに、スカウトから声がかからず、プロ野球の球団に入ることのできなかった元球児のなかには、野球選手として生きる道をあきらめず、日本野球機構とは独立の地方リーグの球団のテストを受けて、入団し、そこで自分の技術をみがき、プロ野球に挑戦することを目指す人もいる。独立リーグの歴史は浅く、最初に設立された四国アイランドリーグが2005年設立で、そのほかに関西地方にいくつか存在するが「構想は発表されたものの、金銭的な問題(スポンサーがつかないなど)、人材的な問題(審判やスタッフが不足、ひいては選手自体が集まらない)から構想が頓挫したり、プロ形態を断念し社会人リーグとして発足したものも多い」という。現存のリーグは、日本女子プロ野球機構をふくめ4つ程度のようだ。四国アイランドリーグは各県に一つずつの4チームで構成されている。こうして、独立リーグという「就職先」も多くの選手を吸収してくれるわけではない。
そして、これらマイナー・リーグの試合は、選手たちが生活をするのに十分な収入を上げるだけの観客を集めることが難しいため、選手たちは練習だけを行うのではなく、観客を集めるための宣伝活動をおこなったり、あるいはアルバイトをして生活費の一部を稼いだりしなければならないようだ19)。
新聞やテレビの報道などで知りえたかぎりのことだが、以下では、生活費の一部をサッカーや野球などの「マイナーリーグ」のチームに所属することで得、不足分をアルバイトで稼いでいる「半プロ」の人々、及び、ゴルフの大会に出場して賞金を稼ぐ(ことにより生活する)ことを目指して、アルバイトでほとんど稼ぎつつトレーニングを行っている「プロ志願」の人々などの両方を含めて、「半プロ」、あるいは「プロ志願」などと呼ぶことにする。
プロ野球球団の支配下選手に一度登録されても安定した選手生活が待っているわけでは決してない。テレビのドキュメンタリー番組で見たのだが、一軍の公式戦に出場した経験をもつけれども、成績が振るわず解雇された選手が、年に1回行われる「トライ・アウト」(実戦形式で行われる一種の選抜テストだが、そこでの活躍ぶりをみた球団から声がかかって、改めて球団のテストを受ける)に2回、3回と挑戦していた。そして、トライ・アウトで入団したある選手の1年目の給料は240万円だった。他方ドラフト会議で指名されて入団した選手は、2000万円を超えていた。入団できれば、給料の安さは我慢しなければならないが、練習はできる。しかし、入団もできない人は、方向転換を図るのでなければ、アルバイトで稼ぎながら20)、一人で練習をしなければならない。これは大変きびしいことであろう。スポーツ・ファンは選手がテレビで放映される公式戦に出場しているときの姿しか知らない。テレビに出てこなくなったスポーツ選手は、半年も経たないうちに、練習時間を減らしアルバイトをしながらでもスポーツを続けるか、それとも、スポーツと関係のない仕事に就くかを決めなければならないという、きびしい岐路に立たされているのである。そしてプロ野球選手として活躍できるのは、たとえ、怪我による故障がなくても、せいぜい40歳くらいまでではないか21)。捕手などは三塁から突っ込んでくる選手との激突がしょっちゅうあり格闘技並みのきびしさだ。二軍に落ちても解雇されず、選手生活を続けることができたと仮定しても、ふつうのサラリーマンに比べて仕事を続けられる時期は短いのだから、現役時代によほど活躍して高い給料を稼ぐことができる人以外、プロ野球選手の人生は、大変きびしいものだと考えてまちがいはないだろう。
プロのスポーツ選手としての成功は約束されたものではないということを知ってはいても、マイナー・リーグで戦うか、そうでなければアルバイトで稼ぎながら練習を続け、プロ野球公式戦の選手になることを目指すという生き方は、望んでいたものとはちがうのではないだろうか。若いときに、たとえ、ふつうの職業に就いている人に比べ、多くの時間を好きなスポーツに注ぐことができるにしても、他方で、金を手に入れるためだけにアルバイト仕事で稼がねばばならないというしかたで、残りの人生を生きていかなければならないとうことはやはり辛いことなのではないだろうか。野球が好きであったにしても、草野球チームに入り、余暇に楽しむことは可能だろうし、普通の企業に就職するほうが安定した生活を送ることができて、妥当な生き方だとは考えられないだろうか。
他方、一般の職業・仕事は、基本的には、生活の必要のために行なうものであり、なかには自分の適性にあった、全体としては満足できる職業もあるが、そのような場合でも行なう仕事のなかにはやりたくなくても我慢してやらなければならないことも必ず含まれている。一般的には職業としての仕事は楽しいものではなく、克己心を必要とする、きびしいものである。エリアスの語では職業としての仕事はもっとも「慣例化」された、つまり感情や衝動を抑制し、自分のためではなく他者のために行動しなければならない領域に属する活動である。つまり、一般の職業・仕事においては、何らかの意味で自己を犠牲にすることが求められ、それによって初めて満足のいく生活手段を得、生きていくことができる。職業・仕事は、それによって社会の中で生きることが可能となる活動であり、生きる手段として不可欠な活動である。そして、この観点からは、遊びとは、楽しむために好んで行われるものだが、それだけでは生きていけない活動である。そして、職業としてのスポーツには、この遊びと仕事の両方の要素があり、どちらの要求にも応えてくれるという性格がある。
しかし、スポーツを強く愛好しスポーツ選手として生きたいと願っているが、プロとして稼ぐことができないまま、アルバイトで稼ぎつつスポーツの練習を続ける「半プロ」スポーツ選手たちは、好きなことをやりながら同時に稼ぐのではなく、二つの異なる活動、単なる稼ぎの活動と、好きな、しかし、練習であり、決して遊びではなく、楽しいとも言い切れないスポーツの活動を別々に行なう。人によっては、スポーツをする者(男)と稼ぐ者(女)が二人一組でそれを行う。子どもの時には、学校で勉強し、放課後はスポーツクラブでトレーニングするという、二重の生活を送ってきたが、大人になってからもこの「半プロ」スポーツ選手、スポーツを強く愛好する人々は二重の生活を送ることになる。プロとして十分にあるいは全く稼ぐことのできないこれらスポーツ愛好者の場合には、限られた時間だけスポーツ、あるいはその練習を行い、残りの時間にそれと関係のないアルバイトをして稼ぐ。あるいは別の人がその人に代わって稼ぐ。 彼は生活の中心になるスポーツそのものが絶対的に気に入っている。スポーツが好きなのである。多くのふつうの人が、まず、ふつうの暮らしと、経済的な安定を考えて職業に就こうとするのに対して、スポーツを強く愛好する人々は、自分の本当に好きなスポーツを優先している。彼は産業社会のなかでの一般的な生き方とは異なる生き方、生活の苦労をすることは覚悟の上で自分の好きなことをやろうとする道をあえて選んだのだ。
多くの人が、何らかの才能を発揮し業績を上げることによって他者から評価されたいと考えるだけでなく、他の人々から「人間として立派な人」だと尊敬されるために、その時代の主流であるようなタイプの倫理を身に付け、その倫理に従って生きようとする。近代以降の社会においては、少し前まで、おおむね真面目に働いていれば、職業の種類を問わず尊敬された。定職に就いていない人、あるいは「無職」の人は(「住所不定」であればなおさらのこと)胡散臭い目で見られるか、遊び人として軽蔑された。定職を持ちまじめに働く人は、単に経済的に自立し社会的に有能であるというだけではなく、人格的に立派であると考えられていた。しかし、最近では、国の経済的豊かさが背景にあることは明らかだが、この勤勉・禁欲を旨とするタイプの倫理を尊重する人が大幅に減った。そして、立派な人格を有する、究極的な意味で「よい」人間として生きようとすることである倫理的態度と、そのような態度の一つである「勤勉・禁欲」的であることがほとんど同じものだと多くの人によってみなされていたために、「勤勉・禁欲」の価値低下に伴って、倫理そのものに何の意味も感じない人すら増えている。
だが、重要なのは、彼が経験・体験し、考え、喜び、苦しみ、悩み、悲しむことなのではなく、その人の社会的な業績である。その人の何であるかは、その人が仕事/労働によって生み出す生産物・サービスであり、業績、成果であり、客観的に評価できるものであると考えられている。
こうして、スポーツマンがスポーツを行うことは、本人がそれを愛好しておりそれが彼にとって楽しいからといって有意義であるのではなく、他の人々を楽しませることができる、あるいはエリアスが言うように、観客に興奮とカタルシスを与え、それにより「非慣例化」の社会的な機能をはたすことができる、その限りにおいて有意義であることになる。そうであればこそ、観客を集めるトップ・プロとしてスポーツを行なうことは、社会的に大いに有意義な役目を果たすことになる。
レギュラーとして活躍しているプロの選手は好きでスポーツをやっているだけではなく、稼ぎながらスポーツをしている。また彼/彼女はスポーツで名声をも手に入れている。プロのスポーツ選手の場合には、その仕事がどれほど気に入っているにせよ、スポーツは自己目的的活動ではなく、金と名誉を得るための手段として役立ってもいる。これに対して「半プロ」ないし「プロ志願」のスポーツ愛好家は、(アルバイトで稼いでいるにしても)スポーツではわずかしか稼いでいない。もちろん名声も得ていない。かれがプロの選手になれることが当分、あるいはもしかしたらずっと不確かである限り、スポーツは何かを得るための手段ではなく、目的そのものである。
アリストテレースは、「自己目的的活動」は他のものの手段とならないがゆえに、最終的で最高の部類に属する活動と考えたが、現代、産業主義社会においては、自己目的的活動は、それ自体として意味のあるものと認められていない。楽しむために行うスポーツが自己目的であると言われるのは、それが何か他の目的に役立つのではなく、それ自体として求められるものだからであるが、人間の価値は自分で働いて自立していることそして社会にも貢献することにあるのだとするならば、各人が自己目的的に打ち込むスポーツには意味や価値がないことになる。それは「単なる遊びに過ぎない」ことになる。
だが、次のように反論することができる。生きるために必要であれば、辛くても、楽しくなくても、一定量の労働を行なわなければならないことは確かである。だが、先進国では平均的な人々の生活はすでに十分豊かであり、労働時間を減らすことは可能である。(運の悪い生活困窮者には生活保護などの公的な援助が拡大されるべきだ。)ところが賃金が上がり生活はますます豊かになるが、労働時間は減らない。
それは金儲け、資本の蓄積を至上目的とする金持ち・資本家が社会を動かしており、彼らは自分では働かず、ほかの大勢の人間にたくさん働いてもらい、GDPを拡大してもらうことによって、自分の富をもっと大きくしたいと考えている。ふつうの労働者にとって、より大きな収入を得るということは、すでに豊かな国々では、決して楽しいものではない長時間の労働を続けるためのインセンティブとしては十分ではない。有意義だと信じられなければ、人々は、働くことをやめないにしても、働く時間をもっと減らすだろう。だからこそ職業・労働は、社会貢献、自己実現等々、有意義な活動だと強調され続けているのだ。「怠惰は悪だ。仕事(労働)に勤しみ、仕事の中でこそ自己実現を図るべきだ。仕事を通じて社会に貢献すべきだ。余暇は明日の仕事に励むことを可能にするレクリエーションのためにあるのだ」と。
私たちは、金儲けをしたいと考えている人々のいいなりになって、自分の愛好する活動を我慢し、従来の常識にしたがって、一日8時間、週5日の労働を行わなければならないと考える必要は全くない。資本主義社会は政治的には自由主義社会であり、他者を傷つけたり害したりしないかぎり、自由に行動して構わないのであり、戦前のように「国家・社会」に一身をささげることを義務付けられてはいないと同時に、また金儲けをしたいひとびとに親切にしてやらねばならないことはないのである。
私は、退職後は「半漁師」として、つまり漁業で稼いで暮らすのではないが全面的に釣りをして暮らすことに決め、海辺に移り住んで釣り三昧の生活を送っている。だが、早朝暗いうちの方が魚がよく釣れることは分っていても、朝寝坊の習慣を克服できない。また、熱中症に罹る恐れのある真夏には、あるいは寒く海が荒れる冬は、釣りは止めて何日も「休漁」する。私の生活から釣りを取るとほとんど何も残らないが、しかし、遊びの釣りであり、年齢のせいも多少あるが熱意、真剣さはプロ志願のスポーツに打ち込む人々の比ではない。彼らは、「衣食住」に関する常識的な満足を犠牲にして、眠る時間を削り、アルバイトでかせぎ、そして厳しいトレーニングを続けるのである。
このようなスポーツ愛好家は、スポーツに生きることこそが彼の人生だと思いを定めているのだと思われる。普通のサラリーマンのように平日8時間会社などで働き、休日にだけスポーツを楽しむという生活には満足できず、平日他の人たちが働いている時に、何よりも好きなスポーツをやる。スポーツ好きの普通のサラリーマンの場合には、働くことが第一であり、遊びは働いた後の「ごほうび」またはリフレッシュメントである。しかしこの半プロ、スポーツ愛好家にとっては、スポーツが第一であり、彼/彼女の生きることそのものなのである。彼らにおいてスポーツは単なる遊びとは決していえない。
だが、彼/彼女は独自な考えに基づいて、一人で、この非(反)勤勉禁欲倫理を選んだのではなく、彼/彼女が子どもだったとき、親が、楽しいことを後回しにして、ふつうの勉強を真面目にやるようにと子どもたちを説得せず、好きなスポーツを優先し学習塾よりもスポーツクラブに通うことを認めたからこそ、彼/彼女はこの道を選ぶことになったのである。この両親が、主流である勤勉禁欲の倫理に対して意識的にどのような態度をとったかは別として、ともかく彼らは、子どものしたいことをさせてやる、そのような寛容な育て方を行ったのである。そして、もちろん、このような子どもの育て方の背景には、社会が豊かになったこととスポーツ人気の高まりがあるだろう。 こうして、全体社会のスポーツ熱の高まりと、「スポーツ優先」の生き方に対する一般家庭における肯定的な考えがあり、それを背景にした、スポーツを中心にした人生を選ぶ若者たちが増えている。こうした傾向は、単に、社会のなかの特定の領域における変化を意味するものでなく、より深いところから社会が流動しつつあり、漠然とだが「近代」産業社会が別のものに取って代わられつつあることの表れと解釈することができるかもしれない。
親は、単に子どもが遊ぶのを容認したのではない。勉強して大学に行き、ふつうの職業に就く代わりに、スポーツ選手になって成功してもらいたいと考えているはずだから、子どもが練習に一生懸命取り組むことを求める。子供も、いやいやながら学習塾に通うのではなく、好きで自分から進んで始めたことであり、毎日のように、テレビでトップ・プロたちの晴れがましい活躍を目にするのだから、あんなふうにぜひなりたいとがんばるであろう。こうして、彼らは、身体的能力を最大限に伸ばそうときびしい練習を行い、遊びの時間を減らしてスポーツに打ち込む。この点からすれば、スポーツ少年たちは、放課後も熱心に塾に通って勉強し、少しでもよい成績をあげ、有名大学に進学しようとがんばっている勉強中心の子どもと同様、「勤勉・禁欲」的である。
ワールドカップやオリンピックの日本代表になった選手、あるいは、各種目で、世界中でわずか3人しかいないメダリストの一人になったような有名なアスリートは、もって生まれた特別な資質・能力とそれを伸ばすに足りる十分な環境とがたまたまそろっていたからこそ、それが可能になったのであろう。だが、多くの人は、これらトップ・プロたちの「途中でくじけそうになったことが何度かあったが、あきらめずに続けてきてよかった」、あるいはスポーツ評論家の「誰にも負けない豊富な練習量の賜物だ」というような言葉を素直に信じて、「勤勉・禁欲」のハード・トレーニングを長期にわたって積み重ねることが成功と栄誉の獲得を可能にすると考える。こうして、トップ・プロたちの活躍は、スポーツ少年自身にとって、またその親たちにとって、またアルバイトをしながらプロを目指すスポーツマンにとって、強い励ましになる。
しかも、かつてのスポーツ界とは異なり、「アマチュア規定」による制限は全く存在しない。トップ・プレーヤー、トップ・アスリートはつねに「トップ・プロ」である。つまり、スターであるスポーツ選手は「職業人」でもあり、彼らは働く人間の代表でもある。こうしてかれらの活躍、名声は、スポーツ少年、プロを目指すスポーツマンとその家族などだけでなく、ふつうの職業に就き、自分と自分の家族の生活のために、楽しくなくしばしば厳しく辛い仕事に耐えつつ、頑張って働いている人々にとっても、強い励ましになる。彼ら有名選手たちの言動は、一生懸命働くこと、一生懸命がんばって自分の職責を果たすことの大切さを人々に確信させることになる。スターであるトップ・プレーヤー、トップ・アスリートは、現代社会において「勤勉・禁欲」の倫理の大切さを鼓吹することに重要な貢献を行っている。
そして、アルバイトで稼ぎながらスポーツに打ち込む「半プロ」の無名選手は、そうしたスター・プレーヤーとはちがった仕方で、この勤勉禁欲の倫理を支えるのに貢献している。彼らは趣味・娯楽としてスポーツを楽しんでいるのでは決してない。彼らは、辛い現実に耐えつつ、プロになって稼ぐという目標に向かって、禁欲的に、労働・仕事と全く同等の活動として、スポーツに打ち込んでいる。
彼らは、この産業社会を支える勤勉・禁欲の倫理を、ふつうの労働者やサラリーマンよりもずっと多く体現した生き方を実践しているのである。ふつうのサラリーマンは、勤勉・禁欲の倫理が、安全安心の生活を手に入れる手段であることを知っている。倫理が重要なのでなく、その結果が重要なのである。しかし、無名の「半プロ」スポーツマンにとって、練習に打ち込む勤勉禁欲の生活は何も約束してくれない。初期のプロテスタントが、「勤勉禁欲の信仰生活を送れば救いが得られる」と考えてそうしたのではなく、超越神の絶対的な命令への服従として、その倫理的な信仰生活を送ったのと同じである。この「半プロ」スポーツ・マンこそ、勤勉禁欲倫理の原理主義者であり、労働、勤勉・禁欲を称える社会に生きる者の模範と考えられるかもしれない。
他方で、私も含め、労働・仕事が人間の使命だとは考えず、各人は自分のしたいこと、楽しいことをしてよいのだと考え、生活手段としての労働は最小限にとどめ、好きなことを最大限自由におこなうことができる社会が実現されるべきであり、したがって更なる「経済成長」、更なる「富の蓄積」に向け努力することには反対し、そうした努力を拒否しよう考える者もいる。この人々にとっては、遊びとは、遊んだあと次に仕事に戻ったときに、以前同様にあるいはそれ以上に集中して仕事に取り組めるようにすることが目的であるような、手段としての活動ではなく、仕事・職業から抜け出て、仕事以外の自分の好きなことを積極的に行う活動であり、それ自体が目的であるような活動である。したがって、遊びは仕事に従属的なものではなく、人生において、仕事と同等あるいはそれ以上に重要な意味を持つものである。
このように考えることができるとするならば、現代スポーツは、遊びと仕事の中間にある、またはその両方であるといえるだろう。遊びはいかなる活動であるのかについては次の章で詳しく考えたいが、たぶん、遊びの特徴の一つは「好き」で行う活動であり、したいことをしたいように行う活動だと考えられそうである。他方、職業としての仕事においては、ふつう、物を作るかサービスを提供することによって報酬を得るが、そこでは顧客の要求に応えるということがもっとも重要なことである。普通の職業においては、自分がよいと信じる物やサービス、自分が作りたい、提供したいと思う物やサービスを提供し、あるいは売ろうとするのでは、職業人として失格であろう。
ところが、プロ野球の選手は打率で3割3分をマークしホームランを30本打とうとするだろうが、それは観客・ファンを喜ばせるために、あるいはチームを優勝させるためにそうするのでなく、彼が強打者になり、ホームラン王になりたいからであろう。その結果、チームを優勝させ、ファンを喜ばせることになるだろうし、また年俸も上昇し、家族も喜ぶであろうが、それが目的なのではない。それは「結果としてついてくる」ことである。だからスポーツ選手は、基本的には、自分でやり遂げたいと思い、自分が設定する目標を達成することを考えて活動すればよいのである。(芸術家についても同じことが言えるし、研究者についてもほぼ同じことが言えるだろうが。)ファンが
求めるものと選手自身が求めるものは多くの場合一致するだろうが、選手は自分が野球ファンに示したいと思うものを止めてファンの要求するものに応えなければならないということはない。多くの他の職業とはその点で大きな違いがある。
スポーツ選手は自分のベストの成績を目指してプレーを行う。そうしなければファンの要求にこたえることもできない(職業であるかぎりそれは必要だ)。ところが、彼は自分のしたいことをする。自分のしたいことを最大限におこなうことがファン・サービスになるのである。自分の仕事を「他の人のため」ではなく、「自分のため」に行なうことができ、それでかまわないという点でスポーツという職業は遊びに似たところがある。彼らは子どもが遊びに夢中になるように、自分の仕事に全力で打ち込む。
遊びと違う点もある。これまでにも述べたが、遊びで行われるスポーツの試合においては、自分(のチーム)が力を最大限に発揮し、勝つということだけを考えていてはうまくいかない。試合の目的は相手(チーム)と一緒に楽しむことにある。しかし、プロの選手は相手(チーム)に勝つことだけを考えていればよい。プロの選手は自分(のチーム)ために、そして結果としてファン、観客のために、ただ闘って勝つことを目指せばよい。かれらは遊びとは違って、職業である「遊びの戦い」に思いきり打ち込むことができる。
無名の「半プロ」スポーツ・マンの場合はどうであろうか。自分が好きだという根本的な理由によって、プロ・スポーツ志願の選択を行った。しかし、「支配下選手」であっても一軍のレギュラー選手になれない限り、十分な収入を得ることはできず、自分と家族を経済的に支えることは難しいのではないか。トライ・アウトで入団した選手の生活、あるいはマイナー・リーグの選手の生活はアルバイトで稼ぐ必要があるだろう。かれは、たぶん、自由時間がわずかしかなく、遊ぶ余裕は経済的にも時間的にもきわめて乏しいだろう。かれは自分の「本業」であるスポーツのトレーニングの仕事に普通のサラリーマン以上の真剣さで取り組むであろう。しかしそれは稼ぎにならず、観客もファンもいないところで行われるのだから、「他人のため」の活動ではなく、愛好に基づく「自分だけのための」活動である。ということは彼の本業であるトレーニングという仕事(労働)は遊びに似た活動だということである。
つまりスポーツという職業は、実際にそれに就き、稼ぐことと名声を得ることに成功している人々にとっても、逆に、プロとなることを「志願」しているにすぎず、稼ぎも名声も得られないままトレーニングを行っている人々にとっても、同じように、遊びの性格を併せもつ特異な活動である。
スポーツマンとは、世間並みの生き方、普通の仕事に就き、平均的で安定した生活を送るのでなく、自分の好きな「戦い」に一生を賭けようとする生き方を選んだ者だと考えたとき、私は、どうしても、日本の戦国時代末期から徳川時代の初期にかけて現れた武芸者を思い浮かべずにはいられない。無名の「半プロ」スポーツマンだけではない。プロ野球界には、日本で一流の選手になったあと、こんどはアメリカの大リーグに挑戦し直すという選手もいる。中には、野茂やイチローのようにアメリカでも大成功を収める超一流の選手もいるが、日本では一流であっても、同じ結果がアメリカで出せるかどうかはわからない。彼らは武者修行に出かける武芸者のように大リーグに挑戦するのだろう。
2015年に日本に戻り、広島カープでプレーをしている黒田博樹について、3年前の新聞には次のように書かれていた。黒田は広島カープで10年間投げた後、大リーグ、ドジャースに移り4年間プレーした。2012年、ドジャースの戦力構想から外れ、フリーエージェントとなった。自分から選んだのではないから、解雇である。黒田の「気持ちは古巣の広島に傾いた。レッドソックス、ロッキーズ、ダイヤモンドバックスから好条件が提示されてもそれは変わらなかった。だが、ヤンキースが獲得に動くと心が揺れた。年俸ではヤンキースの提示を上回る球団もあった。より高いレベルで力を試したい思いが強かったのだろう。悩みぬいた末、広島に断りの電話を入れた」。「大リーグでのプレーについて「憧れていたわけではない。選手としてレベルアップするため」と言い切る黒田はワールドシリーズ制覇27度のヤンキースでしのぎを削る道を選んだ」。「黒田にとって野球は修行に近い。大リーグでの挑戦を「懲役」とまで言い、高年俸に見合う成績を上げようと毎年自分を追い込んできた。1年契約でドジャースに残留した昨季は重圧から不眠に苦しみ、病院で「強度のストレスが原因」と診断された。それでも自己最多の13勝を挙げた。常勝を求められるヤンキースでの重圧はこれまでの比ではない」(2012.1.15.愛媛新聞)。
黒田も、戦って勝つことにすべてをかけた武芸者の武者修行に似た、スポーツマン特有の生き方を示している。 2015年黒田は広島に復帰することになった。複数の大リーグ球団の申し出がある中で、日本で投げずに終わることに引っかかりを感じ、悩んだ末の決断だという。広島から毎年オファーをもらっていたことが決断を後押しする大きな要因になったようだ。(2015.1.17.朝日新聞)日本的な義理人情のようなものが黒田にあったのかもしれない。
剣豪宮本武蔵は、17世紀の始め頃、武士が戦闘員としてではなく、幕府という組織の一員として統治の職務を担当しつつあった時代に、あくまで一個の武芸者として廻国武者修行を行い、純粋な「剣の道」、戦いに勝つ技術である「兵法の道」を究めようとしながら生きた。彼は仕官すること、つまり組織に属して社会に役立つ仕事を行う(そして禄を得る)ことではなく、「個としての」独自の生き方を追求したのである。少し脇道に入ることになるが、宮本武蔵を代表例として、徳川時代の初期、すでに戦乱が遠ざかった社会で、あくまで武芸者であることにこだわって生きようとした少数の武士たちの生き方に目を向けてみよう。
依拠するのは、私の大学院時代の同窓生で、国際武道大学教授魚住孝至氏が書いた研究書『宮本武蔵―日本人の道 』(ぺりかん社、2002。以下では「日本人の道」と略す )および宮本武蔵[著]魚住孝至[校注]『定本|五輪書』(新人物往来社、2005)、一般向けに書かれた岩波新書『宮本武蔵―兵法の道を生きる』(岩波書店、2008。以下「兵法の道」と略す)である。
『宮本武蔵―日本人の道』は、最近新たに発見された諸資料も含め「これまでの資料すべてを資料批判した上で、----確かといえるもののみに基づいて」書かれた本格的研究書である。第一部では宮本武蔵の人物像とその時代が描かれ、第二部では武蔵の主著『五輪書』の思想が解説される。そして、430ページに及ぶ大著の後半、170ページを使って、関係資料全部が詳しい考証とともに収められている。武蔵の言葉は「 」で引用した。また、魚住の武蔵に対する見方、ないし論評に関する文も「 」で引用したが、それ以外の歴史的な事柄についての文も、ほとんど魚住の「要約」ないし「引用」である。しかし、読みにくくなることを避けるために、引用文に「 」をつけるのは省略した。
武蔵は30歳を越えてから、これまでを省みて、戦いには勝ったけれども「兵法至極してかつにはあらず」つまり兵法を極めたことによって勝ったのではないと考え、「なをもふかき道理を得んと、朝鍛夕錬し」た。そして「をのづから兵法の道にあふ事、我五十歳の比〔コロ〕也」、と『五輪書』の最初の巻、「地の巻」冒頭で書いている。
宮本武蔵自画像、Wikipediaによる

『五輪書』の執筆を始めたのは1643年、武蔵61歳の時であった。武蔵は、続く序論的な個所で、「武士の兵法をおこなふ道は、何事においても、人にすぐるるところを本とし、或いは一身の切りあいに勝ち、あるいは数人の戦に勝ち、主君のため、わが身のため、名を上げ身をたてん」とすることである、と書いている。魚住は、ここには「戦闘者として勝って武功を立て、名を上げ、立身出世せんとした伝統的な武士の精神が語られている」。「主君のため」とも言っているが、「これ以降の論には出てこないので、それほどの意味を持っておらず、単に伝統的な武士の通念---をそのまま書いただけのものであろう」(「日本人の道」)、あるいは「「主君のため」とは言いながらも、すぐ次に「わが身のため」が続くのであり、自らの実力で身を立てようとする個の武士の立場で言われている」(「兵法の道」)と言う。実際武蔵は一度も仕官していない。
武蔵は次の「水の巻」以下4つの巻で、戦闘者である武士の会得すべき兵法、つまり戦いの技法を詳しく述べるが、それに先立ち、この「地の巻」で、兵法の道を探求する武芸者がいかなる存在であるのか、兵法の道は他の道とどのような関係があり、どうちがうのかということについて述べる。武蔵は、まず、農、商、士、工の順で各職業の意義を論じ、戦闘者である武士の職分を、いざ合戦の非常時に備え、兵具を作り兵法を身につけ磨くことだとする。
武蔵は「武士をあくまで戦闘者として性格づけ、当時すでに主となっていた為政者や家産官僚としての性格は捨象している」(「日本人の道」)と魚住は言う。武蔵にとって、兵法は、統治者・為政者である主君に仕えるのに役立つ技法ではなく、「わが身のため」であり、他の武士に勝つためのものであって、個としての武士の立場で追求されるものであることからすれば、武士を社会の中で位置づけ武士の職分を規定するとき、戦闘者として規定することになるのは当然である。
したがって、また、武蔵は武士を全体社会の統治者とも他の三民の指導者とも見なかった。武蔵は「身分による差別観は何らなく---社会全体を広く見、その中における武士のありようを論じ」ている(「日本人の道」)と魚住は言う。
こうして、武蔵にとって、武士はあくまで戦闘者である。しかし、単に剣術、武術に励むだけでは、兵法の道を究めることはできない。道を究めるためには、他の道、他の職分からもまなぶべきである。たとえば、武士と言っても大将と仕卒ではそのありかたは異なるが、武蔵は武士を大工の棟梁と平大工にたとえながら次のように説いている。「棟梁が建物の基準となる「かね(矩)」を知っているように、大将は天下のかねをわきまへ---」ていなければならないという。〔「かね」は曲尺カネジャク/マガリガネをさすが、論語で「のり(矩)を越えず」といわれているように、規範、規矩のことである---須藤。〕そして平大工は日ごろから道具を磨き技を磨いておかなければならないと、比喩により、仕卒が日ごろから武具に親しみ鍛錬を積む必要があることを述べている(同書)。武士の兵法の道と、武士とは別の職分の大工のあり方とのあいだに共通する点があることが指摘されている。
武蔵はさらに、専門の道を追求する様々な人の中に学ぶべきもの、汲むべきものがあると言う。「道において、儒者、仏者、数寄者〔風流の愛好者〕---これらの事は武士の道にはなし」。しかし「道を広くし〔知〕れば、物毎〔物事〕にであうこと也」(「地の巻」第6条)。儒者、仏者、数寄者、等々の道は兵法の道、武士の道ではない。しかし、これらの人々は一般的な世の人々とは違い、物事を専門の道において深く探求しようとしている。兵法の道と一致するところ、重なるところがあるはずだ。武蔵は「拍子」〔調子やリズム〕を例に挙げながら、他の道を広く知ることが、兵法の道を究めることに役立つと述べている(「地の巻」第8条)。武蔵は、武芸者が武芸以外の諸芸の道に広く通ずることが必要だ、そう考えている。
こうして武蔵は、兵法の道の探求と他の諸芸における道の探求に交わるところ、共通するところがあるというが、他方で、「いずれも思い思いに稽古し、心こころにすくもの」であるが、「兵法の道にはすく人まれ也」と言ってもいる(「地の巻」序)。「すく」は「好く」であろう。気に入る、愛好することであろう。武蔵は、彼が説き、また体現していた兵法と生き方が、独自かつ特異なものであり、多くの人に理解され受け入れられるものではないということを十分に意識していたと思われる。
はじめに引用した文で「武士の兵法を行う道は、何事においても、人にすぐるる所を本とし、或いは一切の切合いにかち、或いは数人の戦に勝」つことだとされていた。「地の巻」末尾では、道の探求において、「手にて打ち勝ち、目に見ることにも人に勝ち、-‐-身にても人に勝ち、-----また心をもっても人に勝」つと述べる。手をはじめとする身体全体の使い方、身のこなし方において、また目の使い方、目のつけ方、物事の核心の見極め方において、結局、心身のはたらきすべてにおいて、人に勝つことの重要性を説く。また、武士の本分は戦うことにあるにせよ、大将になるかもしれず、また場合によっては政治ないし統治の仕事にかかわるかもしれないわけだが、そのような場合に関して武蔵は「大きなる兵法にしては〔大将としては〕善き人〔優れた人材〕を持つことに勝ち、人数をつかうことに勝ち、---国を治むることに勝ち、民を養うことに勝ち、---いずれの道においても、人に負けざるところをしりて、身をたすけ、名をたすくる所、是兵法の道也」と言う。
前に見たところでは、武芸以外の諸芸の道を広く知ることを通じて、兵法の道を深く究めることが重要だとされていた。そして、ここでは、「いずれの道においても」武士は「人に負けない」、「人に勝つ」ことが重要だと言う。そして、「人に勝つこと」、「戦闘者として勝って、武功を立て、名を上げ、立身出世する」ことを目指すのが武士だと唱えられている。魚住は「武蔵において自らの道を修し、どこまでも深く追求せんとする道の思想と、すべてにおいて人に勝たんとし、自らの実力によって身を立てんとした武士の精神が独特の形で結びついている」という(「日本人の道」)。
武蔵は30歳になるまでに60余度の勝負を行っていたが、ただ剣術を磨き兵法者として廻国修行を行っただけではなく、23歳のときに『兵道鏡』を書いたのをはじめとして、『兵法書付』、『兵法35か条』、『五方の太刀道』、『独行道』などを著し、最後に『五輪書』を書いた。こうして彼は、最晩年まで、著述しつつ兵法の「道」、武芸者として生きる「道」について思索した。
35歳ごろ姫路城下で行った立会いで強さが認められ、藩主は召抱えようとしたが、武蔵は仕官せず、客分にとどまった。40台半ばの頃、養子の伊織が出仕した明石・小笠原家の客分になり、また50歳ごろ小笠原家の小倉への移封の際、九州に移り、58歳の時には細川家の客分になって厚遇を得ているが、いずれにおいても仕官していない。(武蔵の著書や行動についてはすべて魚住による。)
武士は「戦闘者として、勝って武功を立て、名を上げ、立身出世する」ことを目指す。だが、武蔵の武者修行は、ただ戦って相手を打ち負かしてその強さを示すことを目的にしていたのでは
ないし、また、仕官、立身出世が目的でもなかったことも明らかである。魚住は、武蔵の武者修行は「仕官のためでも武名を上げるためでもなく、純粋に剣の道を追求するためであったのではないか」と言っている(「日本人の道」)。武蔵の場合には、「わが身のため」の兵法の追求であり、「個の立場」に立つものであるが、その「個」は世間的な利害心の主体としての個ではなかったということがわかる。
仕官する者は他者の判断によって自己の価値を知る。他者の評価と自己評価が一致すれば満足できるだろうが、それは不確かである。そして、他者の判断はあいまいであり、異なる複数の他者が異なる判断を下すかもしれない。しかし、兵法者は他者の判断を待つ必要がない。生死を賭した立会いによって、自己の価値、力量、実力を絶対的に知る。平穏に、あるいは楽しく生きることを求める人からは理解されないだろう。「武芸を好くものはまれである」。しかし、武蔵は「勝つこと」を目的として立て、他者の意見や価値評価を一切気にせずに、自分だけでその目的が実現できているかどうかを判断できる、個としての兵法者の純粋な「剣の道」を追求したと言える。
だが、武蔵ほど「純粋」ではなくても、やはり「剣の道」にこだわり、戦乱が治まっているにもかかわらず、武蔵と同様に廻国武者修行を行う武芸者たちがいた。魚住は、「むやみに勝負せんとする命知らずのものたち」と異なる、「武芸を磨く武者修行本来のあり様のもの」として真陰流疋田豊五郎と柳生兵庫助の名前を上げている。疋田は細川幽斉のもとで兵法師範を務めていたが、致仕(退職)して廻国武者修行に出、24度の立会いにすべて勝った。最後に西国武者修行で30人に勝ったという武芸者と立ち会って勝ち、「これは日本一」と言われたので最後にしたという。柳生石舟斎宗厳(ムネヨシ)の孫、柳生兵庫助は、加藤清正に招かれたが、1年で去り、真陰流三世を継ぐ前に3年以上廻国武者修行を行った(同書)21)。(注:追加へ)。魚住は柳生兵庫助に「武蔵に近いものが感じられる」と言っている(「兵法の道」)。
武蔵が60余度の試合の最後に立ち会った巌流小次郎も、そのような武芸者の一人であったのではないか。吉川英治が小説『宮本武蔵』を書く際に参考にした、江戸後期に書かれた武蔵の伝記等に書かれている、武蔵と「佐々木小次郎」の「巌流島における戦い」なるものは「実はさまざまな話を組み合わせた虚構、作り話であって、決して事実ではなかった」という(「兵法の道」)。資料批判を行った上で、最も確かだと魚住が言う武蔵と小次郎の戦いの記録は、武蔵の養子・伊織が、1654年、武蔵没後9年に小倉に立てた武蔵顕彰碑の文であるという。この文によれば武蔵と小次郎の勝負は、小倉藩が関与した「公式の勝負ではなく、武蔵と小次郎との私闘であった」。碑文(原文漢文)には「ここに兵法の達人岩流と名づくる者あり。彼と雌雄を決せんことを求む」と書かれている、という(同書)。こうしたことからすれば、小次郎もまた、仕官せずに廻国修行を行って「剣の道」に生きた武芸者だったと想像される。
他方、同じ頃、将軍家兵法師範柳生宗矩は『兵法家伝書』で、個々の武士の兵法は勝つも負けるも一人の「小さき兵法」。諸勢を手足のごとく使い、謀をして合戦に勝つのが「大将の兵法」。しかも国の機を見て乱れることを知って乱れる前に治めるのも兵法、すでに治まるときに、諸国に受領ズリョウ・国司を定めて国の守りを固くするのも兵法だと説いた。「治まりたる世」に必要なものは戦に勝つための「殺人刀(セツニントウ)」ではなく、人を活かす「活人剣」だとし、禅の教えを取り入れつつ、武士の人間形成に資するものでなければならないことを強調しているという。宗矩の考える兵法は、個々の武士の剣術の腕をあげさせるためのものではなく、世を治めることが職分であるような武士の心構えや態度の養成を目的としていた(「兵法の道」、『定本五輪書』p37、注4)
客観的に見れば、宗矩の兵法の考え方のほうが、当時の社会情勢に即したものだといえるだろう。徳川によって統一された世の中は、剣術の腕が優れている武芸者を求めていたのでも、「すべてにおいて人に勝る」こと目指す特異な兵法の道の探求者を望んでいたのでもなく、世の中をうまく治めてくれる集団としての武士を求めていたはずだ。
だが「武蔵は、---誰に臣従することなく、自ら節を高くして独り立ち、その生涯を兵法の道の追求で貫」いた(「兵法の道」)。「武士の独立不羈の精神を貫き、伝統や権威によらず、自らの経験によって、個として自由に生きた」(同書)と魚住は言う。武蔵の生き方は、独自で、特異なものであった。そして武芸者の中には、少数ながら、武蔵に近い精神的態度で兵法の道を追求し、「剣の道」に生きようとしたものもあった。彼らは、世の動向に従い統治階級としての武士の「安穏な」ふつうの生活を求めようとはしなかった。武蔵のように全く仕官しなかったというわけではなくても、統治者として、組織の一員としての役割を果たすだけでは満足できなかった。兵法者としての彼らの生き方は、広く世の中の役に立つものではなかったし、賞賛されもしなかった。武蔵は「兵法の道にすく人まれ也」と言っていた。兵法の道に生きること、大雑把に言えば「剣一筋に生きる」ことを「好む」者は少ないということを十分に知っていた。その上で彼らは、他の人々とは異なる、他の人の好まない生き方をあえて選んだのである。
小説『宮本武蔵』の読まれ方は一通りではないだろうが、多くの人は剣豪武蔵の超人的な戦いぶりのなかに読む快楽を見出すのではないか。とはいえ、利害を超えた剣の道一筋に生きる武芸者たちの生き方、また武蔵の特に求道的な生き方に心が惹かれる人も少なくないと思われる。彼らの生き方、武蔵の思想が世の一般情勢には合っていないということ、(少なくとも短期的には)世の中の動きに後れを取っているということは認めざるを得ないとしても、それでもやはり、そうした魅力を感じるという人がいるであろう。
こうして、プロのスポーツマン、あるいはプロとして稼げなければアルバイトをしてでもスポーツを続けようとする熱心なスポーツ愛好家と、武蔵やその時代の武芸者の生き方に共通するものをみいだすことができる。それは、一言で言えば、主流の生き方であるかどうかにかかわらず、自分の「好く」ところをあくまでも追求しようとする点である。すべての人は、仕事で稼いでいる者も、そうでないものも、自分の能力の範囲内で、その社会において可能な、自分の好む生き方をしていると言える。しかし、スポーツマンや武芸者は、世の中の多くの人が取る「安穏」で平凡な「好きな道」ではなく、きびしい道を選んだ。武芸者は命がけの勝負に生きる。スポーツマンは、生活の保証がないことに打ち込む。彼らは、生きるという、生物としての人間にとってもっとも基本的な欲求に反するか、それに役立たないことを主要な関心事として「生きている」。別な見方をすれば、どちらも、人の役に立つためにではなく、自己の能力を発揮するという個人主義的な意識に基づいて生き方を選んだのである。
武蔵が有名になったのは、足利将軍家兵法師範、吉岡一門との3度の戦いに勝ってからであるが、それ以前に、13歳と16歳のときに兵法者を倒し、それから28、9歳になるまでに60余度戦ってすべて勝ったと、『五輪書』に書いている。60人以上の武芸者が武蔵と戦って敗北を喫した。無傷なのは武蔵一人であった。碑文などの研究に基づき魚住が言うところでは、吉岡家の長男清十郎は「木刀の一撃でいったん絶息したが蘇り」門弟が板に載せて連れ帰った。「その後、薬や湯治によって漸く回復したが、もはや兵術を棄てざるを得ない身体になってしまった」。次いで戦った弟の伝七郎は武蔵に奪われた木刀で撃たれ、「地に倒れ、たちどころに絶命した」。武蔵が最後に倒した相手は「西国一」と唱えていた巌流の小次郎である。武蔵が遺した木刀とその他の資料から、魚住は、小次郎は長い木刀の一撃を頭に受けて倒れたという。おそらくその場で絶命したであろう22)。
私はこの文を書くまでは、無敵の剣豪・武蔵の観点からしか武芸者を考えたことがなかった。つまり、武蔵と戦って敗れた人々、武蔵の太刀を浴びて倒れた人々のことを考えたことがなかった。立会いに敗れて生き残った武芸者が気の毒である。彼らは大きな怪我を受けて体は不自由になり、また大怪我につきものの慢性的な疼痛に苦しみながら40歳か50歳になるまで、たぶん、ただ生きているというだけの、Q.O.L.のきわめて低い、つまり、生命ないし生活の質のきわめて劣悪な余生を送らなければならなかったであろう。温泉(湯治)が痛みに効くことは昔から知られていたようだが、湯治で慢性的な痛みが治ってしまうわけではない。そして慢性的な疼痛に対する治療は現代医学もできない。しかし、生活の不便さは社会的な仕組みで多少は軽減される。名門の出の吉岡清十郎の場合には、介護者つきで湯治をしながら暮らすことができたかもしれない。しかし、そのような家柄ではない武芸者はどのような生活であったか。私は、自分の一年ほどの腕と肩の痛み(→第一章参照)と比べて想像するだけだが、言うべき言葉を持たない。
現代の、スポーツ選手は、人生の盛りの時期、激しく生命を燃焼させ、輝かしく、興奮と感激にみちたきわめて充実した日々を過ごす。高給を受け、ふつうのサラリーマンではできない贅沢を尽くし人生の快楽を味わう人もいるだろう。しかし、その最高の時期は長くない。王や長嶋、金本のように、加齢による全身的な体力のゆっくりとした低下によって引退する選手はごく少数で、多くは、40歳まえに、使いすぎや怪我などによる脚や膝、肩など、体の一部の損傷による戦闘能力の喪失で引退する。現役を退いた後、健康を保持しつつ関連した仕事を楽しみながらやっていく人は少ないだろう。ほとんどは、関係ない領域に転職するか、預貯金で暮らすのだろうが、相当数が、怪我の後遺症である痛みを我慢しながら生きるのではないか。エピクーロスは自分の結石の痛みを忘れるため、過去の友人たちと交わした楽しい会話を思い起こした。スポーツマンは、過去の、自分の活躍、戦いの興奮、スタンドの大歓声、輝いていた時期の経験を思い起こすことによって痛みを忘れるのだろうか。それとももう一度戦い、興奮を味わいたいのにそれができず、からだの痛みに耐えて生きていかねばならないことを悔しく感じるのだろうか。スポーツマンが、他の人々に比べて際立って輝かしい生を味わったあとで、他の人々よりも苦痛に満ちた生を生きなければならないとするなら、かれらの生が「幸福」だということができるかどうか、私は怪しむ。しかし、いまやスポーツは、主に「見る」ものとして社会的に重要な役割を果たしている。スポーツは、エリアスの言う「慣例化を緩和する」社会的機能を果たすという文明史的観点からだけでなく、産業・経済的にみても、政治的にも、あるいは教育や文化という視点からも、芸術、文学などの領域、あるいは様々な他の職業と比べても、きわめて重要な社会的意味を持っていることは明らかであり、その重要性は今後しばらくは一層増して行くのではないかとも思われる。現代のスポーツマンはスポーツを取り巻くそうした社会状況のなかで彼らの活動を行なっているのであり、時勢に取り残されつつ生きていた徳川時代の武芸者とは全く異なる。武芸者たちは、時代の趨勢とは関係なしに、自己の「好き」を貫いた。現代のスポーツマンは、決して独自で、特異な生き方をしているのではない。スポーツマンは、メディアの脚光を浴び、世間の注目を受けつつ、あるいはプロとして成功し注目を受けたいと考えつつ、時代の先端で、「好き」な道に生きようとしているのである。
どちらも、人の役に、あるいは社会の役に立とうとして武芸あるいはスポーツを選んだのではなく、自分のために、自分のしたいことをして生きる道を選んだのである。だが武芸者は「自己の死を賭した立会いによって、自己の力量、実力を絶対的に知る」。勝者として生き残るか、敗れて死ぬかそれに近い目を見ることになる。世間、他人の評価は全く関係がない。他方、現代のスポーツマンは、スポーツ人気、スポーツに対する社会的な高い評価を背景に、しばしば資金力のあるスポンサーや協会組織などによって支えられながら、スポーツを行う。彼らは孤高の道を選んだのでもないし、特異な生き方をしているのでもなく、普通の職業人の多くが企業やさまざまな組織に所属して「他者志向」的に生きているのと同様に、あるいはそれ以上に他の人々との強い社会的関係の中で生きているのである。
第1節では、何がスポーツかについて、スポーツ事典の説明などを参照しながら考えた。そこで得た結論は、スポーツは時代によって異なり(たとえば、50年ほど前まではアマチュアによるスポーツだけがスポーツとされた)、国によって異なり(たとえば、アメリカでは競馬に賭ける遊びはスポーツだが日本では異なる)、人によって異なる(ジョギング、キャンプ、釣り、などもろもろの身体活動はスポーツかどうか)さまざまなスポーツ概念・理解があるということがわかった。
第2節では、近代以降、戦いであるようなスポーツ、競技がスポーツの主流を占めているとする、エリアスの説明に依拠して、戦いであるが相手を傷つけないための工夫、厳しいルールのあることが「近代スポーツ」の特徴であり、そのスポーツの変化が歴史における社会の「文明化過程」と関連があることが分かった。またスポーツは余暇活動の一つであり、余暇活動は文明化のアンチテーゼとして、非慣例化機能をもつものだとエリアスは説明していた。
第3節ではスポーツを含む余暇活動全般について考察した。ここでもエリアスに従い、「自由時間」に行われるさまざまな活動を慣例化の浸透度合/非慣例化の大きさの違いという観点から比較、考察した。私は余暇活動を行う人の(主観的)観点から、慣例化/非慣例化の度合の問題としてではなく、仕事・労働の「必要」から脱出して、自分の好きなことを自由に行うこととして余暇活動を捉える観点を提出してみた。
第4節では、スポーツマン、とくにプロになることを目指しトレーニングを行う「半プロ」スポーツマンの生き方を、勤勉禁欲のプロテスタント的倫理、職業を通じ社会の中で社会(他人)の要請に答えつつ生きることが人間の使命と見る考え方と対比して考えた。スポーツマン、半プロスポーツマンを、他者による評価を重要なものと考えず、非社会的に、自分の「好き」に生きる人間として捉え、戦国末期の武芸者宮本武蔵の生き方と比べて考えてみた。
私は次の章で、遊びについて考えたい。余暇活動の中に、競技中心のスポーツもあれば、身体運動ではない知的なゲーム、芸術、文芸、趣味などさまざまな活動がある。余暇活動の全体を仕事・労働と対比して遊びと考えることが出来る。釣りは身体運動と若干の技術を必要とする遊びであり、スポーツと考えることもできる。
しかし、(競技)スポーツを楽しむにはさまざまな制限がある。闘う相手が必要で一人では遊べない。野球やサッカーとなれば多数の参加が必要で、日程調整が求められる。年齢、体力、経験(技術)に差がある人が集まれば、プレーにレベルの差が生じて、各人がマイペースで楽しむことが難しくなる。また体育館、コート、グラウンドなど遊ぶための場所/施設が必要であるが、必ずしも十分ではなく、使用するために時間的な調整が必要だ。その場所/施設で遊びたいときにいつですぐに遊べるわけではない、等々、と言う具合に、競技スポーツを楽しみたいという人が大勢いたとしても必ずしもその望みが叶わない面がある。
ところがたとえば釣りは一人で勝手に遊べる。場所はいくらでも自由に選べる。技術は全く必要ないとは言えないが、どんなに下手でも自分なりのペースで遊べる。釣りは競技スポーツではなく、遊びの一種であるが、遊びは無数にあり、釣り同様、自由に遊べる活動がいくらでもある。
この章の始めに「釣りはスポーツか(それとも遊びか)」という問いを掲げたが、「そもそもスポーツが何であるのか」が問題になる、とも書いた。遊びの特徴が、(自由時間内であれば)自分の好みだけで、「他人」の意向、都合、体力、その他を気にすることなく自由に行うことが出来ることにあるとすると、行うために様々な条件を満たすことが必要で容易に楽しむことの出来ない(競技)スポーツは、極論すれば遊びではないとさえ言えそうである。
しかし、スポーツについての議論は今「まとめ」で書いたことで済んだことにしたい。遊びはいかなる活動なのか、次の章で、何冊かの本を読み、考えてみた。
------------------------------------------------------------------