
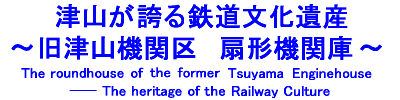
津山の扇形庫に眠る試作車両 DE50−1

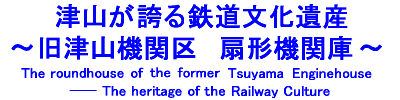
津山の扇形庫に眠る試作車両 DE50−1
| 2006/01/04開設 2006/10/08改訂 |
津山の扇形機関庫に眠る試作車両 DE50−1
('06年6月11日 機関庫見学会にて撮影)
旧津山機関区の扇形機関庫の中には、現在1両のディーゼル機関車が置かれています。
これはDE50形という形式の1号機で、昭和45(1970)年にこの1両のみ製造された試作車両です。
長年、岡山に置かれていましたが、平成14(2002)年に津山の扇形機関庫に移ってきました。
昭和61(1986)年に廃車となり、今では自力走行出来ない車両ですが、戦後開発された様々なディーゼル機関車の中で、 将来を期待されながらも1両しか製造されず、活躍することが出来なかった形式として貴重であり、 この地での末永い保存が期待されます。
▼ DE50−1号機について ▼
DE50形ディーゼル機関車(1号機)
(平成13(2001)年 岡山気動車センターにて撮影)
製造年 昭和45(1970)年 製造所 日立製作所 全長 15.95メートル 全幅 2.967メートル 全高 3.925メートル 運転整備重量 70トン 最大軸重 14トン 機関 DMP81Z 1基 連続定格出力 2000PS 燃料タンク容量 3800リットル 最高速度 95km/h
■ ディーゼル機関車の形式の表し方
(例) (表す内容) D E 50 ① 動力がディーゼル(Diesel)であることを表す ① ② ③ ② 動力の働く車軸の数を表す
B・・・2軸 C・・・3軸 D・・・4軸 E・・・5軸 F・・・6軸③ 最高速度または試作機等の別を表す
10〜39・・・最高速度85km/h以下 50〜89・・・86km/h以上
40〜49,90〜99・・・試作機、外国からの借入機関車
● 戦後のディーゼル機関車開発の背景
我が国に鉄道が開通して以来、特に昭和の戦前・戦後を通じて活躍した蒸気機関車は、 エネルギー効率が悪く、煤煙も多く出るため、戦後の経済が復興し成長してゆく中で、 鉄道における動力近代化の必要性が唱えられるようになりました。
また、終戦後の我が国のディーゼル機関車についての技術は、 アメリカなど各国に比べても大きな遅れをとっていました。
その中で、戦後の我が国におけるディーゼル機関車の開発は、遅れていた技術レベルの回復と、 電化の遅れている地方線区において、蒸気機関車からの転換を図るという役割を担っていました。
ディーゼル機関車は、ディーゼルエンジンを搭載し、そのエンジンからの動力で走行する機関車です。
エンジンの出力や車体重量、付属装置などの組み合わせによって、 幹線用や支線用、旅客用や貨物用など、様々な用途に応じたものが造られています。
また、エンジンからの動力を車輪に伝達する方式も、歯車で直接伝えて車輪を動かす機械式、 エンジンで発電機を回し、その電気で回したモーターで車輪を動かす電気式、 エンジンからの動力を液体変速機(トルクコンバーター)を通して車輪を動かす液体式、に分けることが出来ます。
こうしたディーゼル機関車の開発には、国内の技術だけでなく、海外企業の協力により行われるものもありました。
● DE50形の登場まで
昭和30年代、幹線用のディーゼル機関車としては、海外企業との提携によって開発された電気式のDF50形が活躍していましたが、 DF50形では大型の蒸気機関車に比べやや出力が劣り、なおかつ電気式は製造コストがかかるため、 これに代わるものとして、国内技術で開発した大出力エンジンを積んだ液体式のDD51形が昭和37(1962)年に登場しました。
DD51形は1100馬力のエンジン2基を搭載し、旅客用や貨物用など汎用性が広く、 この登場により各地で大型の蒸気機関車の置き換えが進みました。
しかし、2基のエンジンを搭載していることは車両保守や製造コストの面からは思わしくない、と見られていました。
DD51形ディーゼル機関車
片上鉄道のDD13形ディーゼル機関車
国鉄形と違う部分もありますが、基本は同じです。一方、幹線用以外のディーゼル機関車では、昭和33(1958)年には、 構内の入換用として国産の気動車用エンジンを搭載した液体式のDD13形が登場し、 全国に配備された結果、駅構内などで車両の入換に用いられていた蒸気機関車は置き換えられていきました。
また、DD13形は入換用にとどまらず、支線用としても用いられました。
しかし、このDD13形では車軸にかかる重量が重すぎ、線路規格の低い線区には入線出来ず、 また旅客用としては不向きだったため、これに代わるものとして、昭和41(1966)年に、1250馬力のエンジン1基を搭載し、 亜幹線・支線・入換用など万能タイプ的な機関車であるDE10形が登場します。
同じ年、DD51形の欠点をクリアする亜幹線用のディーゼル機関車として、 1820馬力のエンジンを1基搭載した液体式のDD54形が登場します。
このDD54形は山陰地方に集中投入され、寝台特急「出雲」も牽引しましたが、 故障が相次ぎ、また、エンジンを始め主要機器を海外企業の技術に頼っていたことが要因の一つとなり、 故障の原因を根本的に解決するには至らず、結局DD51形に置き換えられることになりました。
その後も1基のエンジンで幹線用として運用できるディーゼル機関車の開発は続けられ、 その結果、昭和45(1970)年に登場したのが、DE50形なのです。
DE10形ディーゼル機関車
● DE50形の特徴と登場後の運命
DD54形ディーゼル機関車 DE50形は、海外技術に頼ったDD54形の失敗を踏まえて全て国内技術で開発され、 2000馬力という大出力のエンジンを1基搭載した幹線用の液体式ディーゼル機関車です。
車体の形状は凸形ですが、車体中央部の運転台が中心よりも片一方の端側に寄っているセミセンターキャブ となっており、同じ形状のDE10形よりも一回り大きな車体です。
またエンジンも、DE10形のエンジンに改良を加えたパワーアップ型となっており、 DE10型の発展形とも言えます。
車両の特徴としては、国内最強とも言えるV型16気筒の大出力エンジンを搭載したことと、 勾配のある山岳路線での貨物用として設計されたことで、 連続する下り勾配での加速を抑制する装置として、液体変速機を利用した抑速ブレーキ (ダイナミックブレーキ)を初めて搭載したことが挙げられます。
試作機として製造された1号機は、まず愛知県にある稲沢第一機関区に配置され、 稲沢−四日市間で試運転の後、中央西線でテストが繰り返されました。
結果は概ね良好であり、幹線用の標準型の機関車として量産・増備が期待されましたが、 結局、増備は行われず、この1号機のみで製造は打ち切られました。
このDE50形が登場した頃には、DD51形やDE10形がすでに増備され、 さらに主要幹線の電化が進んでいたことで、既にある幹線用や亜幹線用のディーゼル機関車が余剰気味となり、 新形式の幹線用ディーゼル機関車を量産しても、活躍出来る場がなくなっていたことが原因でした。
その後、岡山機関区に配置転換されたDE50−1号機は、伯備線で使用されていましたが、 1両のみの異端な車両であったために車両保守や運転の面から敬遠され、あまり使用されることなく、 伯備線の電化前の昭和56(1981)年当時には既に休車状態となっており、 昭和61(1986)年には、ついに廃車となりました。
廃車後のDE50−1は、岡山気動車区(現 岡山電車区気動車センター)の留置線に置かれ、 露天で風雨に晒されて荒れるがままの状況でしたが、 平成13(2001)年に岡山の鉄道ファン有志が塗装をし直し、平成14(2002)年12月には 津山線経由で津山に移動の上、扇形機関庫に収容され、現在に至っています。
 |
 |
|
扇形庫の中のDE50−1(側面)。 ('06年6月11日 機関庫見学会にて撮影) |
扇形庫の中のDE50−1。 (津山駅ホーム西端から望遠で撮影) |
 扇形庫の中から、来る日も操車場や駅の移り変わりを眺めるDE50。 この地で末永く暮らせますように・・・。 | |
※このコンテンツ作成にあたっては、以下の文献を参考にしています。
『国鉄機関車全ガイド』 高橋摂 昭和57年
■当サイト管理人からのお願い(注意)■
DE50−1の収容されている扇形庫は、津山駅操車場の中(JRの敷地内)にあり、現役施設として使用されています。
JR津山鉄道部では、これらDE50や扇形機関庫・転車台等の操車場施設は原則非公開としています。
最近では、このDE50が書籍やネット上など各方面で紹介されているため、 この扇形庫内のDE50を観に訪れる方も増えています。
中には、津山鉄道部に無断で場内(敷地内)に立ち入って写真撮影等を行う人がいますが、 無断で立ち入るなどの行為は絶対に行わないで下さい。
無断で立ち入ると場内作業の支障となる場合があります。
また最近、機関庫背面(裏手)側では、 無断侵入者によるものと思われる窓等の損壊も増加しています。
こうした無断侵入や設備の損壊は、JRの方のご迷惑となると同時に、 今後の扇形機関庫のあり方にも悪影響を及ぼす場合があります。
また、扇形機関庫周辺は住宅地で駐車場もありませんので、 住民の方やJRの方のご迷惑にならないよう、節度を守りましょう。
