|
2014年6月20日: 「ヒマラヤのスパイ」を読む。 T.G. 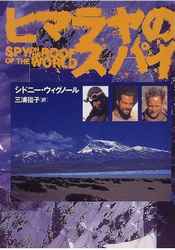
シドニー・ウィグノール著「ヒマラヤのスパイ」(文芸春秋社)を読む。原題は“Spy on the roof of the world”である。何気なく図書館で借りた本だが、これが滅法面白い。400頁を一気に読み通した。内容は中国人民解放軍チベット侵攻直後の1955年、ネパールから西チベットに入ったイギリスの登山パーティが人民解放軍に捕らえられ、厳しい取り調べを受けた後、命からがら脱出するまでの経緯を書いたドキュメンタリーである。同じようなチベットものでは、オーストリアの登山家、ハインリッヒ・ハラーが書いた「セブンイヤーズ・イン・チベット」が有名だが、リアルなドキュメンタリーとしてはこの方がはるかに優っている。 著者のウィグノール氏は山好きの海洋考古学者で、ウエールズで山岳会を組織する。自らが隊長になって西チベットの最高峰グルラ・マンダータを目指すが、途中仲間とともに人民解放軍に捕らえられる。アメリカCIAのスパイの嫌疑をかけられ、2ヶ月間にわたって過酷な取り調べを受ける。その間の尋問のスリリングなやり取り、劣悪な収容所生活、冬季のヒマラヤ越えの命がけの脱出行が描かれている。イギリス人特有のユーモアに溢れた記述の中に、取り調べを通じて分かった当時の人民解放軍の実態、中国の世界観、領土拡張意欲、チベット解放の実情が活写されていて興味深い。今に至るチベットの実態が、何ら正当性のない侵略に過ぎないことが分かる。 
当時のインドのネルー首相は、社会主義者であった。非同盟主義を掲げ、毛沢東中国との友好関係を信じていた。毛沢東の覇権主義、領土意欲を理解せず、国境警備を疎かにしていた。この理想主義者には、その後の中印国境で勃発した国境紛争など想像も出来なかったのだ。ネルーのインド政府は、中国との間で互いに諜報員(スパイ)を交換していた。実際取り調べの英語通訳をしたのはこのインド諜報員である。これに危機感を抱いたインド陸軍の将校が、登山隊長のウィグノールに近づき、当時西チベットで噂されていた人民解放軍の軍用道路の進捗状況、解放軍基地などについて、秘密裏の調査を依頼する。当時はチベット、インド、ネパールの国境線が明確でなく、ウィグノール等が登山用に持ち込んだ地図では判然としない。きちんと測量もされておらず、地形や山の標高もいい加減なものであった。それをいいことに、中国は勝手に領土を広げ、今の西ネパールや東のエベレストまで中国領内にあると主張していたのだ。 ウィグノールは積極的にスパイ活動を請け負ったわけではなかったが、山頂から西チベット方面をフィルムに収め、途中で行き会うチベット人などから情報を聞き込む約束をする。逮捕されたのは中国領ともネパール領とも判然としないヒマラヤ山中だったが、逮捕容疑は最初からCIAのスパイである。収容所での尋問はすべてこの嫌疑にかかわるものだった。当時の中国がアメリカにいかに不信感をもっていたか分かる。収容所では毎日の様に取り調べが行われ、毎回CIAのスパイであることを認める自白書にサインを求められる。その繰り返しが2ヶ月間続く。冬が迫った西チベットの、標高4500mの収容所の夜は零下30度まで下る。ろくな食事も与えられず、装備品はすべて没収され、過酷な毎日が続く。 
取り調べの尋問の様子が興味深い。狭い土間に引きずり出され、数人の取調官に囲まれる。椅子は与えられず、土間に座らされる。その周りに絶えず唾と痰が吐かれる。姓名、国籍などの質問から始まり、登山隊の目的などありとあらゆることが尋ねられる。何を答えても嘘だと言われる。本当のことを言えと迫られる。あきれ果てて口答えをすると、突然全員が立ち上がり、被告を指さして大声で非難する。中国語だから意味不明だが、罵詈讒謗を浴びせられているのは分かる。それがしばらく続くとまた尋問が始まる。その繰り返しである。後の文化大革命で紅衛兵が知識人達を人民裁判にかけたのはこれと同じ手法だろう。この国の裁判の原型なのだろう。被告にストレスを与え、罪を認めるまで弁護も反論も許されない。 傑作なのは登山という行為が彼らにはまるで理解できないことだ。「なぜ山に登るのか、目的は何か」と質問される。登山に関する永遠の問いである。「登りたいからだ」と答えると、いい加減なことを言うなと怒られる。からかわれたと思うらしい。山岳会の目的は何かと聞かれ、「山に登ることだ」と答えると、「そんなはずはない。毛沢東の教えでは組織には必ず政治的目的があると言われている。」と反駁される。登山という無償の行為が当時の中国人には理解できないのだ。それ以外にも彼らがまったく世界常識を欠き、盲目的に毛沢東の教義を信じ込んでいるのがよく分かる。当時の(今も?)人民解放軍の兵士は、プロパガンダ以外のきちんとした教育が行われていないのだろう。恐ろしいことだ。 尋問中に繰り返される拷問について書かれている。口答えや反抗的態度を取ると、銃で殴り倒される。最もきつい刑罰は、彼らが使うカラシニコフ銃にマガジンを詰め、額に銃口を押しつけて引き金を引く罰である。直前にマガジンを外すのだが、手違いと言うこともある。やられるたびに恐怖が湧き、夢でうなされる。帰国後もしばらくPSTDが残ったほどだという。かなり手慣れたやり方なので、人民解放軍の中で常套化されていた拷問なのだろう。 
そうまでもして彼らが欲しがったのは、アメリカCIAのスパイであることを認める自白書だった。いくら虐待、拷問が繰り返されても、自白書にサインするまでは命は奪われない。それが分かってから、ウィグノールらは逆の作戦に出る。出鱈目の自白である。世界中の山岳会はCIAの組織である。ヒマラヤ登山はチベットやウイグルの偵察が目的で、2年前のイギリス隊のエベレスト登頂は、酸素ボンベの中に小型原子力発電装置を組み込んだ偵察装置を頂上に運び上げるためだった、などである。この荒唐無稽の自白を彼らは信じ込む。よく自白したと大喜びで、その晩普段与えられないご馳走を食べさせてくれた。この自白はただちに北京に報告され、北京もそれを信じた節があるとウィグノールは言う。その証拠に、彼らが帰国したすぐあとに、人民解放軍の大規模なエベレスト登山が実行された。チベット側のロンブクまで軍用道路を通し、千人もの部隊を投入した大々的登山だったと言うから本気だったのだろう。 彼らが殺されなかったのは、逮捕を知ったインド政府がそんなことをしたら中国の国連加盟が認められなくなると忠告したからだとウィグノールは推測する。当時毛沢東中国の国連加盟をネルーが側面支援していたのだ。その中国が今は常任理事国として国連でふんぞり返っている。おかしな世の中だ。 本書の中でチベットとチベット人に対する人民解放軍の虐待、暴政が描かれている。基地や軍用道路建設にろくな賃金も払わず駆り出される。わずかな麦の収穫や、チベット人には必要不可欠なヤクや羊も取り上げられる。微妙な生態系のバランスで維持できているチベットが破壊されていく様子が分かる。それでも貧しいチベットの人たちはウィグノールらに親しく好意的に接してくれる。その雰囲気が全編にわたって書かれている。何年か前にラサからチベット奥地を旅行したが、その時の印象と何も変わっていない。中国が言うチベット解放は真っ赤な嘘である。侵略以外の何ものでもない。 物語の最後は、人民解放軍の兵士に追われながら、ろくな装備も食料ももたず、冬のヒマラヤ越えをする決死の逃避行である。どの登山記よりスリリングで面白い。国境越えの後の旅の描写では、当時のインド、ネパールの様な貧困国でも、自由のない中国に比べたら天国と言うことが分かる。現在のチベットウイグル地域の混乱を見れば、むべなるかな。 |