2013年1月22日: バスケット部高校生の死と言語能力 GP生
 昨今、大阪市立桜宮高校バスケット部の主将であった男子生徒の自殺が、新聞、テレビを賑わしている。 バスケット部顧問の男子教諭による体罰が原因と推定され大問題となった。昔から、学校の運動部での体罰は、熱血指導の一環として見過ごされてきたのは事実だ。 野球、バスケ、サッカー等で、強豪校として学校名が全国的に知られれば、監督や顧問等が指導に熱を入るのは自然の成り行きだ。
昨今、大阪市立桜宮高校バスケット部の主将であった男子生徒の自殺が、新聞、テレビを賑わしている。 バスケット部顧問の男子教諭による体罰が原因と推定され大問題となった。昔から、学校の運動部での体罰は、熱血指導の一環として見過ごされてきたのは事実だ。 野球、バスケ、サッカー等で、強豪校として学校名が全国的に知られれば、監督や顧問等が指導に熱を入るのは自然の成り行きだ。今回の問題は体罰を受けた生徒が、自殺にまでに追い込まれたことにある。 問題の顧問は部を強くするために、主将であるこの生徒に「しっかりしろと」気合を入れたのかもしれない。 しかし、20発、30発の顔面殴打に至っては、常軌を逸している。顔面は腫れ上がり、口内から出血までしている。愛の鞭の範囲を逸脱した行為であることは論を待たない。 百歩譲って、此の体罰により、殴られた生徒が主将の意識に目覚め、部をまとめ、部員のレベル向上に邁進したとしたら意義はあるのかもしれない。しかし、現実は、この生徒が主将の立場と体罰の恐怖と苦痛の狭間で立ち往生し、その解決を自らの命を絶つことに求めてしまった。
 高校二年生の未来ある若者が、自ら命を絶うと決意することは容易な事ではない。 彼の遺書には「死ぬ覚悟が出来たので死にます」と認められていたと言う。「それなら退部する道も、転校する道もあるではないか」と第三者は思うかもしれない。 人は悩み苦しみの中に閉じ込められる時、明るい道が見えなくなってしまう。 ましてや、高校二年生だ。 誰か彼の心の内に気付かなかったのだろうか。 子供の頃からバスケットが全てであった若者には、他の道が見えなかったのだろう。 彼の孤独な心情を思うと哀れでならない。自分の小学五年生の孫は野球部で活躍している。 彼の生活には野球しかない。使う用件でなくとも、グローブとボールの入ったザックを背負って出かけるのが常だ。 自殺した若者のバスケットにかけた情熱と孫の野球への熱い心が重なって見える。
高校二年生の未来ある若者が、自ら命を絶うと決意することは容易な事ではない。 彼の遺書には「死ぬ覚悟が出来たので死にます」と認められていたと言う。「それなら退部する道も、転校する道もあるではないか」と第三者は思うかもしれない。 人は悩み苦しみの中に閉じ込められる時、明るい道が見えなくなってしまう。 ましてや、高校二年生だ。 誰か彼の心の内に気付かなかったのだろうか。 子供の頃からバスケットが全てであった若者には、他の道が見えなかったのだろう。 彼の孤独な心情を思うと哀れでならない。自分の小学五年生の孫は野球部で活躍している。 彼の生活には野球しかない。使う用件でなくとも、グローブとボールの入ったザックを背負って出かけるのが常だ。 自殺した若者のバスケットにかけた情熱と孫の野球への熱い心が重なって見える。愛の鞭なら、一発で良い。 20発、30発連続に殴られれば、殴られた方は正常な思考など出来なくなるのが普通だ。 勿論、主将の責任の意識など湧くはずがない。 殴っている顧問にしても、殴っているうちに当初の目的意識は希薄となり、殴ることが目的化してしまう事になりがちだ。 暴力は人の思考力を奪うものだ。この顧問は他の部員にも、気合を入れると称して殴っていたようだ。 十数年に亘る顧問としての指導者生活で、殴ることが常態化し、不感症になってしまったのかもしれない。 周囲がそれに気が付いても、それ自体を大きな問題にせず、強豪校として名が知られることで良しとして来たようだ。 体罰の存在を知ってか知らずか、何れであっても学校長の責任はとてつもなく大きい。
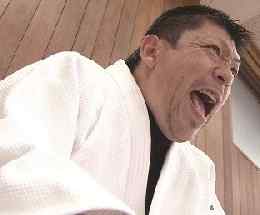 世の指導的立場にいる人で、部下や部員を殴ることで、彼らに立場をわきまえさせ、意欲を駆り立てる事が出来ると考える者は居ないだろう。家庭で父親が子供を躾けると称して、日常的に腕力を振っていたとしたら、間違いなく家庭崩壊となる。 乳飲み子の泣き声が五月蠅いとして、叩いて子供を殺したり、言うことを聞かない我が子を、長時間閉じ込めて死なせてしまった親の事例が多数報道されている。 腕力や暴力が子供を自分の思う方向に、コントロールできるとは思っていなくとも、相手の意思レベルに合わせた、言語能力に劣れば、暴力的表現になって終うのかもしれない。不幸なのは死んだ子供だけではない。 自らも人間としての未熟さ故に、長い後悔に苛まれることになる。
世の指導的立場にいる人で、部下や部員を殴ることで、彼らに立場をわきまえさせ、意欲を駆り立てる事が出来ると考える者は居ないだろう。家庭で父親が子供を躾けると称して、日常的に腕力を振っていたとしたら、間違いなく家庭崩壊となる。 乳飲み子の泣き声が五月蠅いとして、叩いて子供を殺したり、言うことを聞かない我が子を、長時間閉じ込めて死なせてしまった親の事例が多数報道されている。 腕力や暴力が子供を自分の思う方向に、コントロールできるとは思っていなくとも、相手の意思レベルに合わせた、言語能力に劣れば、暴力的表現になって終うのかもしれない。不幸なのは死んだ子供だけではない。 自らも人間としての未熟さ故に、長い後悔に苛まれることになる。部下を率いるにしても、部員を指導するにしても、指導者に求められるのは言語能力だ。教室で授業する教師が言語能力に劣っていたとしたら、授業は無味乾燥となり、生徒たちの学習意欲は減退するだろう。自分の中学、高校時代の授業を思い出しても、知識が豊富で、表現力の豊かな教師の授業は面白く、勉強にも熱が入った。 ダメ教師にはいじわるな質問をして、教壇に立ち往生させるぐらいがせいぜいだ。人格的にも、人間的にも優れた尊敬できる教師には、お宅まで押しかけて話を聞いたものだ。
 体育部は頭脳より、体の反復練習で身体機能を向上させるのだから、言葉は二の次と思われるかもしれない。 学校では、意識レベルの高いプロの選手を指導するのではない。 人間としても、スキルも未熟な少年達であればこそ、頭と身体両方の向上を促す指導が必要なのではないか。 理屈抜きの体罰指導が功を奏するとは思えない。 たとえ未熟であっても、目的を示し、それに至る手段を説明し、能力の異なる個人の特性を加味して、繰り返し教え諭す能力が高校運動部の指導者に求められている筈だ。
体育部は頭脳より、体の反復練習で身体機能を向上させるのだから、言葉は二の次と思われるかもしれない。 学校では、意識レベルの高いプロの選手を指導するのではない。 人間としても、スキルも未熟な少年達であればこそ、頭と身体両方の向上を促す指導が必要なのではないか。 理屈抜きの体罰指導が功を奏するとは思えない。 たとえ未熟であっても、目的を示し、それに至る手段を説明し、能力の異なる個人の特性を加味して、繰り返し教え諭す能力が高校運動部の指導者に求められている筈だ。主将、副主将であれば、人の上に立ち部員に信頼されるためには何を考え、何をすればよいかを教えるのが、顧問の仕事のはずだ。高校2年になれば、意識レベルは半分以上大人のそれだ。 47歳の顧問であれば、自らの人生経験、競技経験、教師経験のすべてを少年達に注ぎ込む義務がある。 勿論未熟な彼らが全てを理解し、実行できるわけではない。 だからこそ、繰り返し繰り返し、変化する状況に合わせ、手を替え品を変えて、教え指導しなければならない。 それが、指導者の姿だと思う。 暴力的体罰からは何物も生まれない。
問題の顧問教諭は、若い時にあるべき指導を大人から受けて来なかったのかもしれない。自分がかつて受けた指導のコピーをそのまま生徒にぶっけたのかもしれない。 顧問が少年だった時代と現在の少年たちの意識は異なるはずだ。 昔は正当な行為も、時代が変わり価値観が変われば、否定され唾棄すべき行為とされることは多々ある。 不易流行ではないが、学校の指導者は変えてはいけないものは厳に守り、換えるべきところは柔軟に対処する努力が求められる。
 如何なる時代、如何なる場合でも、指導的立場の人間に求められるのは、自分の意思と考えを、相手に間違いなく伝達できる言語能力だ。 これに劣れば、自分の想いを他に伝えられない。 相手が理解できず、あるべき行動が出来なければ、指導者自らが苛立ち、手が出て「俺の気持ちが分からないのか」となろう。熱血指導と謳っても、自らの能力不足をカバーしているのに過ぎないのではないか。
如何なる時代、如何なる場合でも、指導的立場の人間に求められるのは、自分の意思と考えを、相手に間違いなく伝達できる言語能力だ。 これに劣れば、自分の想いを他に伝えられない。 相手が理解できず、あるべき行動が出来なければ、指導者自らが苛立ち、手が出て「俺の気持ちが分からないのか」となろう。熱血指導と謳っても、自らの能力不足をカバーしているのに過ぎないのではないか。例え、言語能力に優れていてもも、人間力が薄っぺらでは、聞く人の耳に届いても、心には響かない。 その実例は、先の民主党政権に幾らでもある。例えば、菅直人は大震災に際し、周章狼狽し部下の官僚や東電幹部を怒鳴りつけ、挙句、福島第一に乗り込み怒鳴り散らし、現場の足を引っ張った。 昨年末の選挙では、吉祥寺の駅前で「脱原発」と書いた箱の上に立ち、大声でわめいていた。有権者に人間性劣悪を見抜かれ、見事選挙区落選と相成った。 しかし、当人は己の愚かさに対する自覚は無い。 政治家で、人間力が伴わない言語能力は百害あって一利もない。 問題の顧問にはどれだけの自覚があったのだろうか。
今回の事件でも、記者会見に臨んだ学校長の苦痛に歪んだ顔を見て、自分の責任を痛感し、自殺した生徒の冥福を祈り、嘆き苦しむ生徒の両親に詫びている様子には思えなかった。 「なんで、俺が校長の時に、こんな事件が起こるのだ。ついていない。」と思っている姿に見えて仕方なかった。大津市の中学生自殺の記者会見で、薄ら笑いを浮かべ動揺を隠そうとした、中学校長の顔と重なって見えたのは自分だけだろうか。
昨年来、教師の質の低下を正すべく、一部の地方自治体で動きが始まり、安倍政権でも日教組の影響排除の動きを加速させようとしている。 前政権では、参議院民主党を牛耳り、党幹事長の要職にある人間が、かって日教組のボスであったのでは叶わぬことだった。医者は人の命を担い、教師は子供の未来を担っている。自分の孫達の日常を見ても、担任教師達の影響の大きさは良く分かる。日本の将来の為にも、人間力に優れ、言語能力の高い教師が増えることを願っている。教育の質は制度もさることながら、教師の質に掛かっているのだから。