|
2012年11月26日: イザベラ・バードの「朝鮮紀行」を読む T.G. 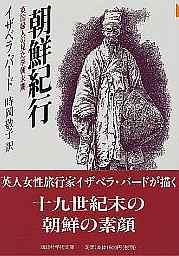
先に読んだ「日本紀行」に触発されて、イザベラ・バードの「朝鮮紀行」(講談社)を読む。日本紀行は明治11年だが、この朝鮮紀行はそれに遅れること約20年、明治27年(1894年)の旅行記である。この冒険好きなイギリス婦人が朝鮮滞在中に日清戦争が勃発している。当時の李氏朝鮮は清国の属国状態にあり、宗主国清と近代化を進めた日本との間に軋轢が高まっていた。彼女の目で見た当時の朝鮮は、李王朝末期の腐敗と暴政で疲弊しきっており、日本のような開国、近代化も進まず、維新直後の日本と比べても、はるかに貧しい文明未開の国であったようだ。彼女の歯に衣着せぬ直裁的な記述を幾つか上げると次のようである。 「北京を見るまではソウルこそこの世でいちばん不潔な町だと思っていた。首都であるにしては、そのお粗末さは実に形容しがたい。2階以上の家は建てられず、推定25万人の住民は迷路のような横町の地べたで暮らしている。路地の多くは荷牛と人間がかろうじてすれ違える程度の幅しかなく、おまけにその幅は家々から出た個体、および液体の汚物を受ける穴か溝で狭められている。悪臭紛々の穴や溝の横に好んで集まるのが土埃にまみれた半裸の子供達、疥癬持ちでかすみ目の犬で、犬は汚物の中で転がり廻っている。こういった溝に接する家屋は、一般に軒の深い藁葺きのあばら屋で、通りからは泥壁にしか見えず、時折屋根のすぐ下に紙を貼った小さな窓があって人間の住まいと分かる。」 「ソウルは商業という概念が行商人の商いに限られている。芸術品は全くなく、古代の遺跡は僅かしかない。公園もなければ、見るべき催しものも劇場もない。古い都ではあるものの、旧跡も図書館も文献もなく、宗教にはおよそ無関心だったため寺院もないし、いまだ迷信が影響力を奮っているため墓地もない。仏教は李王朝が創建される以前は千年にわたり大衆に好まれた宗教だったが、16世紀以来廃止されており、実質的に禁止されてしまった。3世紀前に仏教が廃止された時点で国家的信仰というようなものは一切朝鮮から消えてしまった。霊界に対して何らかの認識が存在したのは、主に祖先崇拝と中層、下層階級が信仰した一種のシャーマニズムである。」 
「通貨に関する問題は、当時朝鮮国内を旅行する者を例外なく悩ませた。日本円や外貨はソウルと条約港でしか通用しない。銀行や両替商は旅先のどこにも1軒として存在しない。 受け取ってもらえる貨幣は、当時公称3200枚で1ドルに相当する穴あき銭以外になかった。この通貨は数百枚単位で縄に通してあり、数えるのも運ぶのも厄介だった。たった10ポンド、百円分の穴あき銭を運ぶには、6人の男か馬が1頭要る。」 「道路事情は劣悪で、幹線道路すら粗雑な馬車道でしかないものがほとんどである。営業権を持ったアメリカ企業が、済物浦ーソウル間に鉄道を敷設し、1898年に開通する予定になっている。朝鮮を代表する大河である漢江は、日本海近くまで半島を横断しているが、全長にわたって橋梁は一つもない。ソウルからウォンサン(元山)には電信線が張られているが、送受信の回数は月に一度程度である。」 「朝鮮の言語は2言語が入り混じっている。知識階級は会話に漢語を使い、重要な文書は漢語で記される。とはいえ、千年も前の古い漢語で、現在清で話されている漢語とは発音がまるで違う。朝鮮文字であるハングルは、知識層からまったく蔑視されている。もともとハングルは女性、子供、無学な者のみに用いられていたが、1895年1月に、それまで漢語だけで書かれていた官報に漢語とハングルが混じった物が現れた。これは漢字と仮名交じりの日本語の文章と似ている。」 
維新当初の日本に比べても、はるかに貧しく、社会制度も国家インフラも皆無に等しい。バードが歩いた20年前の日本でさえ、法制度や金融や教育制度も、通貨や警察力も、ある程度全国に行き届き、古い封建体制から脱却出来ていたのだ。彼女がこれを書いた20年後の1894年には、日本ではすでに憲法が発布され、議会政治が始まっており、東海道線や東北本線などインフラも整い、釜石、八幡には大きな製鉄所が建設されていた。近代化された軍隊は大国清と一戦を交える実力に達していた。僅か20年でこの差がついた理由はどこにあるのだろう。彼女は「(ロシア領に移住して豊かになった朝鮮人を見るまでは)朝鮮人というのはくずのような民族で、その状態は望み無しと考えていた。」とまで書いている。 この旅行記の面白さは、19世紀末の格好の極東ウォッチャーでもあることだ。当時清国の属国であった李王朝末期の朝鮮は、宗主国の清と、力を付けた日本、隙あらばと狙うロシアが入り乱れて争う草刈り場になっていた。 その渦中に飛び込んだイザベラ・バードは、類い希な行動力と交渉術で朝鮮国王(高宗)や妃(閔妃)に取り入り、各国の要人らと精力的に接触し、見聞きした当時の極東情勢を客観的に記述している。幾つかを抜き書きすると次のようである。 
「現在朝鮮が国として存在するには、大なり小なり保護状態におかれることが絶対に必要であるのは明白であろう。日本の武力によってもたらされた名目上の独立(下関条約第1条のこと)も、朝鮮には使いこなせぬ特典で、絶望的に腐敗しきった行政という重荷に朝鮮はあえぎ続けている。かっては清が助言者、指導者としての役割を担っていたが、清国軍が撤退後は日本がその役目を請け負った。最も顕著な悪弊を改革する努力は、いくぶん乱暴に行われはしたものの、真摯であったことは間違いない。日本が着手した仕事は、(閔妃暗殺という手違いによる趨勢の変化から)ロシアが引き継がざるを得なくなった。」 バードは日本が進めた朝鮮近代化の努力を評価した上で、朝鮮は日清戦争の結果与えられた宗主国清からの独立を生かすことが出来ず、国王、妃の閔妃、国王の父親の大院君入り乱れての権力闘争と、支配階級である両班の腐敗と暴政に明け暮れ、独立はおろか、まともな国家運営が出来ない状態だったと言っているのである。頼まれてこの紀行記の序文を書いたウォルター・C・ヒアリー郷も、まったく同じことを書いている。 「政治的配慮はさておき、朝鮮は、列強のいずれかがこのような保護を行えば、国民の暮らし向きは大きく前進するはずである。それを何と呼ぶにせよ、何らかの保護、または監督なくしては、職権濫用、搾取、それに伴う窮乏の旧態へ退行してしまうのは必定である。」と。 
日本の指図を嫌った国王は、その後の閔妃暗殺の混乱に恐怖感を抱いてロシアの保護を求め、ロシア公使館に逃げ込んだ。自らロシアの傀儡になったわけだ。バードは集めた情報を元に、その経緯を詳しく書いている。朝鮮半島に勢力を伸ばしたロシアとの日露戦争の後、日韓併合に至る状況はこうして生まれた。日本は、独立の気概を欠き、大国の間を二股膏薬的に渡り歩く朝鮮に業を煮やしたのだ。その結果、日韓併合という愚行に走り、歴史の手痛いしっぺ返しを食った。この二股膏薬的生き方は朝鮮民族のDNAで、今の朝鮮半島にも脈々と受け継がれている。日本は重々心すべきであろう。 日清戦争の混乱を避け、ソウルから満州の奉天に避難したバードは、途中一時長崎に戻っている。その際の記述が興味深い。 「真っ赤な紅葉の燃えるように美しい長崎で、それまでとはがらりと変わった気持ちの良い一日を過ごした。清潔で、完璧なまでに治安が良く、道路には穴ぼこもゴミの山もない。 この小ぎれいな町は、清国のどの都市でも見られる吐き気を催すような不潔さやみすぼらしさとは胸のすく対象を示している。日本にいる清国人は支配民族の一員である雰囲気で長崎の通りを歩き回っている。彼らは憂さとはまったく無縁の様子で商売にいそしんでいる。同じ頃清国では、日本人が国外へ逃げ出し、人身、物品の危害を受け、はぐれた「倭人」が見つかろうものなら間違いなく殺されていたというのに。」 昨今の尖閣に端を発する反日暴動とまったく同じ構図である。今でも在日中国人は何ら危険を感じずに済むが、在中国の日本人や企業はそうではない。中国人と朝鮮人の日本嫌いは昔から筋金入りなのだ。日本人は中国、韓国に変な思い入れや過大評価せず、もう少し距離を置いて、客観的な見方をした方がいい。そうしないとまた同じ失敗を繰り返すだろう。1885年に発表された福沢諭吉の「脱亜入欧論」は、この煮ても焼いても食えぬ中華、小中華との無益な関わりの決別を促しているのだ。今日現在でも十分傾注に値する考え方である。 |