2012年3月23日: 芥川賞作品「共食い」、「道化師の蝶」を読む T.G.

文藝春秋3月号の芥川賞受賞作品を読む。昨年と同じく、今回も田中慎弥氏の「共食い」と円城 塔氏の「道化師の蝶」の2作品共同受賞である。これでは芥川賞の大盤振る舞いと言うか、大安売りではないか。昨年の西村賢太氏と同じように、今回も人を食った田中慎弥氏の記者会見が話題を呼んだ。彼が芥川賞候補に上げられたのは5回目だそうである。初期の芥川賞は、一度候補に上がった作家は受賞資格を失うのが決まりだった。第一回目の選に漏れた太宰治は、芥川賞が欲しくて堪らず、選者の一人、川端康成に短編小説「晩年」の原稿を送りつけ、取り上げてもらうよう懇願したが叶わなかった。今頃の芥川賞は候補者が列をなして順番待ちらしい。5回目でやっと順番が廻ってきた田中氏は、悪態などついていないで文春の商売上の変節に感謝すべきだろう。

この2作品を読んで、作品自体の巧拙とは別に、文学とか小説と言われるものはいったい何なのだろうと考えてしまった。文学に限らず芸術というものは、他者に対して何らかのメッセージを伝えることがアプリオリな目的である。そうでなければただのマスターベーションに過ぎない。それが美意識であったり、感性であったり、人間性であったり、思想や業や懊悩でも何でもいいが、作者が何かしら意図を持って伝えたいものがあって初めて芸術たり得る。バッハ演奏の第一人者グレン・グールドはきわめて奇矯なピアニストで、ある時を境に、死ぬまで人前で演奏しなかった。もっぱら無人のスタジオで録音機相手にピアノを弾いた。彼のレコードを聴くと、ピアノの音に混じって絶えず彼が発する、とても音楽的とは言えない唸り声が聞こえて来る。聴衆のいないスタジオでピアノを弾いていて、興に乗ると唸らずにはいられなかったらしい。演奏の素晴らしさとは対照的に、耳障りなこと甚だしい。彼はこういう一人勝手の演奏で何を訴えたかったのだろう。うなり声も彼の芸術的メッセージの一部だったのだろうか。
この両作品を読むと同じような感慨に囚われる。いったい何を訴えようとしているのか、いくら考えても分からない。文章が下手でメッセージ性が失われているわけではない。むしろ最近の芥川賞作品の中ではかなり文章力は高い方だ。こなれた完成度の高い精緻な文章は読みやすいし、読んでいて破綻がない。にもかかわらず、作者がこの作品で何を訴えようとしているのか判然としない。グールドの演奏はうなり声を捨象して聴けば実に見事なバッハである。へんてこで耳障りな唸り声にもかかわらず、そのことは歴然と伝わってくる。しかるに、この2作品については、どういう読み方をしても伝えることの意図が分からない。

田中氏の「共食い」である。女と性交する際、相手に暴力をふるって血が出るほど顔を殴りつけるとエクスタシーに達する変態性癖を持つ父親と、抗いながらもその性癖を受け継いでしまった息子の話である。いくら人それぞれとは言え、世の中滅多にある話ではない。その暴力性行為の直裁的な場面や、それを象徴する家の周りの下水と海水が入り交じった汚れきった川の風物が、全編を通じてこれでもかと言うほど猥雑に画かれる。文章力が勝っているだけに、実におどろおどろしい、やりきれない描写が延々と続く。シェークスピアのハムレットのような、一種のエディプスコンプレックスがテーマなのかと思わぬでもないが、そう言うメッセージ性は感じられない。もしそれがテーマだというなら、ここまで汚らしく表現せずとも、男の子なら誰しも持つ父親との相克は描けるだろう。作者が訴えたかったのかも知れない人間の業が、過度の汚らしさの前に薄らいでしまっている。この作者がお嫌いらしい石原慎太郎氏が57年前に書いた「太陽の季節」では、勃起したペニスで障子を突き破って見せた。おどろおどろしさは似ているが、テーマを見失うほどではなかった。
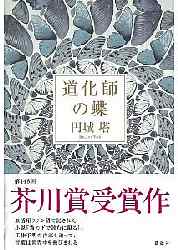
円城氏の「道化師の蝶」である。文章は整っていて平明である。読みにくさはいささかもない。すらすら読み下せる。しかしながら書いてあることに脈絡が無く、素直に頭の中に入ってこない。無意味で無内容な饒舌を聴かされているようだ。小説なら必ずあるストーリーも時制もテーマもない。ストーリーとテーマがないことがテーマなのかと思いたくなる。主人公もいない。「私」と言う一人称は出てくるが、同一人物かどうか判然としない。だから余計に話の展開が分かりにくい。文章に最低限必要な起承転結もない。この分かりづらさはどう説明したらいいのだろう。それをさらに倍加させるのは、いかにもペダンティックな描写と内容の非現実性だ。「観念の蝶を捕獲する補虫網」とか、「国際線の飛行機に乗り続ける乗客」とか、「“無活用ラテン語”で書かれた小説」などがごく当たり前のように登場する。だからといってSFでもなければファンタジーでもない。SFは書いてあることは荒唐無稽でも、論理的で明確なストーリー展開が不可欠だ。
この“一種の難解さ”は選者達も持て余したようで、その一人島田雅彦氏は難解文学の元祖であるジェイムス・ジョイスの「ユリシーズ」になぞらえ、「G.H.ウエルズはジョイスの試みを「分からん」と言ったが、そこまで「分からん」小説ではない。こういうやり過ぎを認める度量がなければ、日本文学は身辺雑記とエンタメしか残らない」と、褒めているのか貶しているのか分からない、いささか投げやりな選評をしている。他の委員からも、「小説になっていない」、「これを読んだ人たちの多くが二度と芥川賞を手に取らなくなる」と言う強い反対意見が出て選考は紛糾したという。そう言う意味では純文学のありように一石を投じた作品と言えなくもない。円城氏自身もインタビューで「難解」、「読者置き去り」を問われて、「当然全然読めないという人もいるだろう。それにはすみませんと謝るしかない。でもストーリーではなく、構造や部品そのものを面白がる小説があっていい」と、確信犯的な受け答えをしている。選者の石原慎太郎氏は、「再度の投票でも過半票に至らなかったこの作品が、どんなつもりか最後は半ば強引に当選作とされた」とぼやいている。商業誌の文芸春秋が意図して候補作に取り上げ、選者の反対を押し切って無理やり受賞させたと言っているに等しい。編集部贔屓の作品を、反対を押し切って無理やり受賞作にする。作品の出来不出来は別として、芥川賞特有のいやらしさ、いかがわしさが垣間見えるようだ。それもあってか、選者の黒井千次氏と石原慎太郎氏は今回をもって選考委員を退くという。