2011年6月27日: 日誌の効用 T.G.
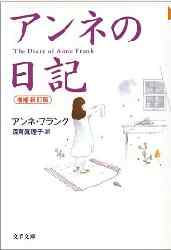 最近の伝蔵荘日誌はもっぱらGP生君と二人で書いている。 他の連中にも頼んでるのだが、一向に書いてくれない。 文章を書くことは人間にとって最も高度な知的活動である。 どんなに頭の良い人間でも、自分の頭で考えられる以上のことを文章には書けない。 文章はその人の知能レベルと全人格を表しているのだ。 だから文章を書き、文章力を向上させようと努めるのは、その人の知能レベルを高め、維持することに等しい。 思考能力や好奇心が衰え始めた老人にとって、文章を書くことは最も手っ取り早い老化防止策だろう。 日常的に文章を書くことは、おそらく認知症や老人性健忘症の最も有効な予防策なのではないか。 GP生君はそのことを理解して、この日誌の共同執筆者になってくれている。 最近奥方から「年を取っているのか若いのかわからない」とからかわれているそうだ。
最近の伝蔵荘日誌はもっぱらGP生君と二人で書いている。 他の連中にも頼んでるのだが、一向に書いてくれない。 文章を書くことは人間にとって最も高度な知的活動である。 どんなに頭の良い人間でも、自分の頭で考えられる以上のことを文章には書けない。 文章はその人の知能レベルと全人格を表しているのだ。 だから文章を書き、文章力を向上させようと努めるのは、その人の知能レベルを高め、維持することに等しい。 思考能力や好奇心が衰え始めた老人にとって、文章を書くことは最も手っ取り早い老化防止策だろう。 日常的に文章を書くことは、おそらく認知症や老人性健忘症の最も有効な予防策なのではないか。 GP生君はそのことを理解して、この日誌の共同執筆者になってくれている。 最近奥方から「年を取っているのか若いのかわからない」とからかわれているそうだ。以前勤めていた会社で自動翻訳を研究してる人に聞いた話だが、どんなに知能指数が高い人でも、修飾関係が7重以上に多重化した文章は理解できないのだそうである。 修飾の多重化とは英語の関係代名詞による修飾関係に当たる。 つまり関係代名詞が7重以上に輻輳した文章概念は、人間の知力の及ぶ域を越えていると言うわけだ。 だから文章を書く行為は、人間が頭をフル回転させて知的能力を最大限に発揮していることを意味する。 作文は最良の頭の体操なのだ。
だからといって修飾関係を重ねた複雑で難解な文章が良い文章というわけではない。 むしろ悪文である。 六法全書の法律文がその典型だ。 あの文章は普通の人が一読しただけではなかなか理解できない。 何度か読み直して何とか大意が掴めればマシな方で、とうとう分からないことが多々ある。 複雑な論理を、出来るだけ曖昧さを排除し正確に表現しようとするとこういう文章になる。 文章表現に求められる訴求性や情緒、感性などそっちのけで、法律で飯を食う連中にとっての実用性に徹するとああいう悪文になるのだ。 東大法学部出の三島由紀夫は、常々刑事訴訟法の文章を完璧で美しいと絶賛していたそうだが、彼のような美文家の言とは思われない。
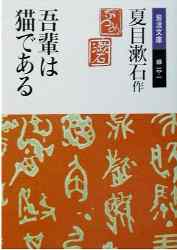 古今東西、名文と言われる文章は例外なく単純明快である。 複雑な文体の名文はない。 名文家はフレーズ同志の複雑な修飾関係を出来るだけ避け、より単純で短い文体で表現しようとする。 例えば夏目漱石の「吾輩は猫である。 名前はまだ無い。」などがその典型だ。 これ以上の単純明快さはない。 読んでいて内容が頭にすらすら入る。 文章力が劣っていると、凝ったつもりで「吾輩は猫であるが、名前はまだ無い。」などと、要らざる複合文にしてしまう。 これを英訳した“I am a cat, who have no name yet.”を、関係代名詞を憶えたての中学生に訳させたら、「我が輩はまだ名前がない(ところの)猫である」などと、さらに救いようがない悪文になってしまう。 英語の関係代名詞は接続詞と考えた方がよい。 夏目漱石のテンポの良い、流れるような文章は昔から大好きだった。
古今東西、名文と言われる文章は例外なく単純明快である。 複雑な文体の名文はない。 名文家はフレーズ同志の複雑な修飾関係を出来るだけ避け、より単純で短い文体で表現しようとする。 例えば夏目漱石の「吾輩は猫である。 名前はまだ無い。」などがその典型だ。 これ以上の単純明快さはない。 読んでいて内容が頭にすらすら入る。 文章力が劣っていると、凝ったつもりで「吾輩は猫であるが、名前はまだ無い。」などと、要らざる複合文にしてしまう。 これを英訳した“I am a cat, who have no name yet.”を、関係代名詞を憶えたての中学生に訳させたら、「我が輩はまだ名前がない(ところの)猫である」などと、さらに救いようがない悪文になってしまう。 英語の関係代名詞は接続詞と考えた方がよい。 夏目漱石のテンポの良い、流れるような文章は昔から大好きだった。文章力のもう一つの要素は慣用句を含めたボキャブラリーである。 ボキャブラリーが貧弱だと考えていることを的確に表現できない。 自分のボキャブラリーについて考えると、基本的な部分はほとんど中高生までの読書で獲得されたものだ。 それ以降、大人になってからは、専門用語、時事用語、業界用語など、文章力とは無関係の単なる語彙である。 “ボキャブラリー”には名詞、形容詞などの単語だけではなく、慣用句や格言、言い回し、引用句なども含まれる。 文章表現を豊かにするのはこちらの方だろう。 例えば、「蓼食う虫も好きずき」とか、「(悔しくて)切歯扼腕する」などという言い方は、他の表現に変えると、ニュアンスが異なり、まだるっこしい文章になってしまう。 この「切歯扼腕」と言う四文字熟語もおそらく中学生頃に読んだ本で憶えたものに違いない。 だから「せっしやくわん」と音読みが素直に頭に刻み込まれている。 正直言って、生まれてこの方「切歯扼腕」をATOKを用いず手書きで書いたことは一度もない。 それなのにごく自然に文章表現に取り込める。 子供時代の読書の賜物だろう。 だから義務教育の最重要科目は国語である。 英語なんか、二の次、三の次でいい。
作文が頭の体操によいと言っても、普通の人間はなかなかその機会がない。 せいぜい日記をつける程度だが、誰にも見られることのない日記は書き続ける動機や気力が薄れるし、文章に緊張感が無くなる。 「日記は誰かに見られることを意識しながら書くものだ」と喝破した人がいるが、けだし名言である。 伝蔵荘日誌はウェブ日誌だから、少数の読者がいることを前提に書いている。 読者が限られる非公開ホームページだから内容にそれほど気を遣う必要はないが、見られることを意識してあまりみっともない文章にならないよう気をつけている。 その最低限の緊張感が頭の体操の効用を高めている。 せいぜいこの日誌を書き続けよう。