2010年9月8日: 生病老死について考える。 K.O.
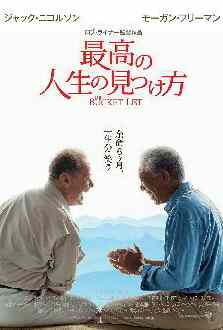 齢70歳を過ぎると人の死に接する機会も多くなり、肉体上の死について考えさせられることが多い。 今日も死亡通知を貰った。
齢70歳を過ぎると人の死に接する機会も多くなり、肉体上の死について考えさせられることが多い。 今日も死亡通知を貰った。亡くなられたのは、父の代からお世話になった公認会計士でテナントさんでもある。 行年82歳であるから男として天寿を全うしたとも言えるが、発病から死に至る経緯を考えるとそうとも言えそうにない。 老人健診で咽頭がんに気がついたのは今年の初めで、高齢でもあり、特にがん治療はせず、咽喉狭窄で食べ物が通らなくなる場合に備えて咽喉下部に穴を開け、器具を取り付けていた。
日常会話は多少不自由はあるものの、意思の疎通は十分可能で、事務所での仕事は通常通り行っていた。 ただ患部の除痰には苦労があったようだ。 今年の6月末、板橋の「帝京大学付属病院」に入院し、抗がん剤の治療を受けた。 抗がん剤で腫瘍を縮小させ、「除痰」の苦労を少なくする目的だとのこと。 会計士の娘さんから話を聞いたときには絶句した。
5日間連続をワンクルーとして、3クルーの投薬だという。 案の定、ワンクルー終了後副作用が激しく、抗がん剤治療は中止せざるを得なくなった。 これが7月中旬の話。 7月末にお見舞に行った時は思ったよりお元気で、話が弾み、帰るに帰えられず40分近く滞在してしまった。 「抗がん剤治療はもうやめ、副作用の症状が落ち着いたら退院するつもり」とのことで、明るい気持ちで帰宅した。 ところが9月2日に容体が急変し、死去されたとのこと。
信じられない思いであった。 私には咽頭がんによる死とは思えなかった。 入院病棟は14階で、新聞でも話題になった耐抗生物質菌の院内感染患者を5,6人出しているフロアーであり、一見お元気そうに見えても、抗がん剤により免疫組織がガタガタになっていたところに「院内感染」したと考える方が自然だと思う。 「痰」はがん組織との戦いの結果生じた「白血球」の死骸であり、自身の免疫組織は健全に機能していたと考えられる。 もし入院せず、抗がん剤治療を行わず、栄養条件・食事・睡眠・休養に留意し、定期的な除痰を行っていれば、まだまだ会計業務は継続できたと思う。 82歳の高齢者に抗がん剤を投与する医者のセンスに身震いを覚える。 長年の多量の飲酒と70代半ばまでの喫煙の結果であっても、82歳まで人生を全う出来たと考えられなくもないけれど。
自分の人生は自分だけのものにあらず。 中年以降の生き方・生活習慣が、老後の最後に来る死に大きな影響を与える。 思い立ったが吉日で、何歳であろうと自分自身の「天寿」を全うするために、「生病老死」について考えることは意味があると思っている