2010年6月1日: 「戦艦大和ノ最期」を読む。 T.G.
 今月の読書会のテーマ本、「戦艦大和ノ最期」(吉田満著、講談社文芸文庫)を読む。 リベラルな傾向が強い読書会にしては珍しい選書である。
この著書は数少ない戦艦大和の生き残りの一人、吉田満海軍少尉の有名な手記である。 「きけわだつみのこえ」的読み方を期待してのことだろうか。
今月の読書会のテーマ本、「戦艦大和ノ最期」(吉田満著、講談社文芸文庫)を読む。 リベラルな傾向が強い読書会にしては珍しい選書である。
この著書は数少ない戦艦大和の生き残りの一人、吉田満海軍少尉の有名な手記である。 「きけわだつみのこえ」的読み方を期待してのことだろうか。今時の子供は(もしかしたら大人達も)、戦艦大和といったら宇宙戦艦大和ぐらいしか思い至らないだろうが、大和はかって日本帝国海軍が作り上げた世界最大最強の超弩級戦艦である。 排水量7万2千トン、未だにこれをしのぐ巨大戦艦は造られていない。 理由は戦艦が近代戦にはほとんど役に立たないからだ。 大和に搭載された主砲46センチ砲の射程距離は、当時最長の30キロを超えたが、今なら小型艦の対艦ミサイルでさえ100キロは軽い。 戦艦が航空攻撃に弱いことは、第二次大戦中幾度も実証されている。 最初にそれを証明して見せたのは、日本海軍自身である。 大戦初期の1941年12月、マレー沖に進出した、当時世界最強のイギリス海軍が誇る巨大戦艦プリンスオブウェールズとレパルスを、日本海軍は航空機(九六式陸攻、一式陸攻)の雷撃及び爆撃によりあっけなく沈めた。 その事実に世界が驚愕した。 航空戦力の前には、戦艦が無力なことが世界で初めて実証されたのだ。 その4年後、戦艦大和は米軍艦載機の集中攻撃によって沈められる。 自ら学んだ教訓がまったく生かされていない。
後年よく知られるように、戦艦大和は大戦末期の昭和20年4月6日16:00、僚艦10隻を従え、航空掩護もなく、片道燃料だけを積んで、呉軍港から沖縄へ向けて特攻出撃した。 その翌日、鹿児島県坊の岬沖で、待ち受けていた米海軍の航空攻撃を受け、僚艦共々あっけなく沈められた。 著者の吉田満少尉は、東京大学法学部在学中に繰り上げ招集されたいわゆる学徒出陣士官で、出撃時は副電測士として大和に乗り組み、乗員3332名のうちわずか269名の生存者の一人である。 この書は、終戦直後、一晩で一気に書き上げたと著者は後書きで記している。 原文は当時の軍隊書式に準じて、「…敵艦隊トノ会敵ヲ予期セザルベカラズ。」といった漢字カタカナ混じりの文語体で書かれている。 占領軍の検閲と戦争賛美というリベラル左翼の非難に遭って、昭和24年に初出版したときはやむなく口語体に書き直したという。 その25年後の昭和49年に初めて原文のまま出版することが出来たという。
一読すれば分かるが、大和の特攻出撃の顛末を書いたこの著書の内容は、決して戦争美化ではない。 「きけわだつみのこえ」のようなじめじめした戦争批判でもない。 希代の大海戦の事実と経過を、極力感傷や主観をまじえず、22歳の学徒兵の目で、事実に沿って淡々と書いている。 無駄のないカタカナ混じりの文語調が、全体の緊張を引き締めている。 単なる記録にとどまらず、一種の戦争文学の域に達していると言えるだろう。 戦争反対の護憲左翼の人たちに言わせれば、これでも戦争美化と非難するのだろうが、解釈におかしなイデオロギーを持ち込んだら文学は成り立たない。
 著書の記述は出撃直前の状況描写から始まる。 毎日のようにB29爆撃機が頭上を通り、大和の動向の一部始終が偵察されている。 ハワイ出身の日本人二世の学徒出陣士官が乗り込んでいて、得意の英語で敵の暗号電文傍受に務めていたが、出撃後は暗号文ではなく、「敵艦隊南に向かう。 少なくとも戦艦一、駆逐艦多数」、などと平英文のママのだったという。 その頃の日本軍は制空、制海権を完全に米軍に奪われていて、手も足も出ない。 舐めきった米軍に狐狩りをされているようなものだったのだ。
著書の記述は出撃直前の状況描写から始まる。 毎日のようにB29爆撃機が頭上を通り、大和の動向の一部始終が偵察されている。 ハワイ出身の日本人二世の学徒出陣士官が乗り込んでいて、得意の英語で敵の暗号電文傍受に務めていたが、出撃後は暗号文ではなく、「敵艦隊南に向かう。 少なくとも戦艦一、駆逐艦多数」、などと平英文のママのだったという。 その頃の日本軍は制空、制海権を完全に米軍に奪われていて、手も足も出ない。 舐めきった米軍に狐狩りをされているようなものだったのだ。全170ページの内前半69ページは、出航から坊の岬沖での開戦に至るまでの比較的穏やかな状況描写である。 直前の出撃準備の様子や、彼の周りの人間模様、兵や士官の心境など、幾分情緒的な描写が混じる。 後に生還した吉田の知るところになるが、駆逐艦矢矧などなど10隻の護衛艦を従えた第二艦隊の司令長官伊藤整一中将は、大和特攻に関する「矢号作戦」に最後まで一貫して反対し続けていた。 海上戦力の大幅劣勢、航空機掩護なき出撃であることなどがその理由であるが、4年前にプリンスオブウェールズを自らの航空機が容易く撃沈した経験から、航空掩護のない単独での戦艦出撃が、まったく無意味であることを良く理解していたのだ。 沖縄に到達する前に、十中八九撃沈されると知っていたのだ。 そのことは兵や士官などもよく分かっていて、出航前に全員が家族や知人宛に遺書をしたためている。
最新の技術と資源を投入した大和にの建造には、当時の国家予算の3パーセント、現在の金額に換算して約2.5兆円もの莫大な費用が投じられている。 その“国家の宝物”と3332名の乗組員を、誰がどう考えてもまったく勝ち目がない死地に赴かせる。 なすところ無く海に沈める。 追いつめられた最後の土壇場での、この国家指導者の理性の無さは、戦前の軍部に限った特異現象か、はたまた日本民族固有の宿痾なのか、一考に値する。 誰が考えても現実性のない普天間国外移設を、最後の最後まで言いつのった現政権指導者を見ると、おそらく後者に違いない。
後半70ページ以降の戦闘開始から沈没、漂流の下りは凄まじい。 冗漫な修飾を排し、事実に即した淡々とした記述は、下手な戦争活劇映画が真似できない迫力がある。 「アワヤ寸前ニ魚雷ヲカワスコト数本、遂ニ左舷前部ニ一本ヲ許ス。」、「朽チシ壁ノ腰ニ叩キツケラレタル肉塊、一抱エ大ノ紅キ肉樽アリ。四股、首等の突出物ヲモガレレタル胴体ナラン。」、「他ノ8名ハ飛散シテ、屍臭スラ漂ワズ。」と言った調子である。 著者の吉田少尉は、戦闘開始に先立って艦内の見張り、報告、命令掌握を任務とする“哨戒当直”を命ぜられた。 艦橋で伊藤司令官の側にいて、司令官の一挙手一投足を目の当たりにし、命令伝達のため、戦闘中の艦内を駆けめぐった。 戦闘開始間もなく、米軍機に蜂の巣にされた大和は艦内通信網が破壊され、口頭での伝達しか出来なくなっていたのだ。 大和のような巨大な戦艦では、上級指揮官でさえ艦内全般の戦況を捕捉できないと言う。 哨戒当直を任務とした吉田少尉は、幸か不幸かそれが出来る立場にあった。 その結果、この著作が生まれた。
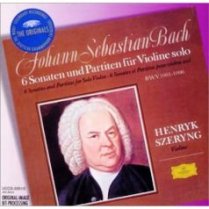 沈没して重油漂う海を漂流中、死を覚悟し、意識を失いかけた吉田少尉は、学生時代にしばしば聴いたバッハの無伴奏ソナタの旋律を耳にする。 ここのときの心境を、「フト思ウ。 貴重ノ時、真ノ音楽ヲ聴キ得ルハ、コノ時ヲ措キテ他ニアルベキカ聴クヲ得ベシ。」、「マサニシカリ、バッハの主題ナリ。耳馴レタルワガ心ノ糧ナルシ主題ナリ。 シカラズ、作為ナリ、幻聴ナラズヤ。」と記述している。 当時の学徒出陣士官はインテリだったのだ。
沈没して重油漂う海を漂流中、死を覚悟し、意識を失いかけた吉田少尉は、学生時代にしばしば聴いたバッハの無伴奏ソナタの旋律を耳にする。 ここのときの心境を、「フト思ウ。 貴重ノ時、真ノ音楽ヲ聴キ得ルハ、コノ時ヲ措キテ他ニアルベキカ聴クヲ得ベシ。」、「マサニシカリ、バッハの主題ナリ。耳馴レタルワガ心ノ糧ナルシ主題ナリ。 シカラズ、作為ナリ、幻聴ナラズヤ。」と記述している。 当時の学徒出陣士官はインテリだったのだ。大和沈没直前、伊藤司令長官は作戦中止、総員退去の命令を発している。 艦橋が傾きかけた大混乱の中、吉田少尉はその言葉を直接耳にしていない。 命令に従い、おそらく千人以上の生き残り兵士がそれぞれ海に飛び込み、脱出したのだろうが、そのほとんどが沈没による海流の渦に巻き込まれるか、海中で誘爆した火薬庫の大爆発によって命を落としている。 生きて僚艦に救助されたのはわずか269名。 大和のような巨大戦艦の轟沈が如何に凄まじいかが分かる。 その悲惨で壮絶な情景が細かく記述されている。
出撃前夜のガンルーム(士官室)で、天号作戦の成否と個々の死生観について士官の間で議論が沸騰する。 もとより必敗論が圧倒している。 特攻出撃が決まった後、死を覚悟した士官や兵の間では比較的自由な言論が許されていたようだ。 その際の結論となった哨戒長臼淵大尉の言は次のようだと、吉田少尉は書いている。
「進歩ノナイ者ハ決シテ勝タナイ。 負ケテ目覚メルコトガ最上ノ道ダ。 日本ハ進歩トイウコトヲ軽ンジ過ギタ。 私的ナ潔癖ヤ徳義ニコダワッテ、本当ノ進歩ヲ忘レテイタ。 敗レテ目覚メル。 ソレ以外ニドウシテ日本ガ救ワレルカ。 全員目覚メズシテイツ救ワレルカ。 俺タチハソノ先導ニナルノダ。 日本ノ新生ニサキガケテ散ル。 マサニ本望ジャナイカ。」
日本はこの大戦の大失敗の後、臼淵大尉が言う“私的な潔癖や徳義に拘らない、本当の進歩”をしたのだろうか。 はたして戦後日本は新生したのだろうか。 戦後65年もの長きにわたって続けられ、今も繰り返されている、地に足の着かない、あやふやで理性を欠いた防衛論議や国家安全保障政策を見ていると、大いに疑問だ。