■思い出話ーその3 T.G.
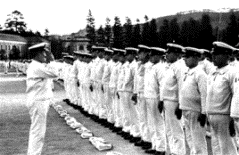
苦労した母も、大学3年生の時、52歳の若さで亡くなった。遠い街の大学にいて、死に目には会えなかった。夜行列車を乗り継いで、10時間かかって家に着いたときは冷たくなっていた。
思い出してみると、戦争未亡人としてさんざん苦労を舐めた母の口から、時々こぼす昔話以外に、恨みがましい反戦の言葉を聞いた覚えがない。それどころか、昔名古屋の女学生だった頃、バンカラな七高の学生さんや真っ白な制服の海軍兵学校生が憧れだったなどと、他愛もない思い出話をたびたび聞かされた。女学校の卒業の時、友達と色紙に“海軍兵学校”とか“若鮎”などと書いた話を聞かされたりした。もしかして好きな人でもいたのだろうか。色紙にちなんで自分の娘に鮎子という名前を付けたかったが、お父さんがさせてくれなかったとぼやいていた。長姉の次女、言うなれば母の二番目の孫娘が生まれたとき、自分の娘である姉に頼んで鮎子という名前を付けさせてもらって喜んでいた。その孫娘ももう50過ぎである。
もし母が反戦で凝り固まった戦争未亡人なら、戦前の忌まわしい記憶につながるそんな名前を付けるはずがない。今時のリベラル知識人の、地に足のつかないふやけた平和論議を聞いたら、気丈な女性だった明治生まれの母は何と言っただろうか。もう聞くすべはないが、お父さんは国や家族を守るために、仕方なしに死んだのだと思っていたのではないか。勝手な想像である。
藍より蒼き大空に、
たちまち開く百千の、
真白き薔薇の花模様、
見よ落下傘空に降り、
見よ落下傘空を征く。 (空の神兵)
最も過酷な戦闘を義務づけられる落下傘部隊は、どこの国の軍隊でも最精鋭である。今の自衛隊の空挺部隊もそうだ。真珠湾攻撃直前、シンガポール陥落の端緒となったマレー半島上陸作戦でも、先頭を切って敵陣深く降下したのは陸軍の落下傘部隊だった。周囲を敵に囲まれ、友軍の支援などまったく期待できない危険極まりない任務。この程度煽り立てねば、とてもそんな勇気は出ないだろう。
先日テレビのWOWOW番組で、スピルバーグ監督、トムハンクス演出による“Band of Brothers”という戦争映画を見た。日本語ならさしずめ「兄弟の絆」とでも訳すのだろうか。第二次大戦末期、志願兵で編成されたアメリカ陸軍の空挺部隊が、過酷な訓練を経た後、ノルマンディー上陸作戦に先んじて、ドイツ軍支配下にあるフランス領内に降下し、敵陣内で作戦を支援、友軍到着を待ってベルリンに向け進攻するという10時間に及ぶ大作である。リアルな戦闘シーンの凄まじさもあって、夜間B17輸送機の編隊から、打ち上げてくるドイツ軍の高射砲弾幕をかわしつつ、若い兵士達が次々にパラシュート降下する場面では、一種の感慨を禁じ得なかった。いざとなったら、今の日本の若者も同じことが出来るのだろうかと。国を守るためとは言え、着地前に半数が死んでしまうような過酷な任務を、自ら志願するだろうかと。そもそも国を守るなどという、当時の日本やアメリカの若者達が持っていて、今の中国や北朝鮮を含めた世界中の国々の若者達が持っている観念的価値観を、日本の若者達も持ち合わせているのだろうかと。
遅くとも2ヶ月後には民主党鳩山政権が誕生する。この混迷した世界情勢の中で、友愛だかなんだか知らないが、この育ちだけは良い党首の、国家安全保障に関するとりとめのない発言を聞いていると、この国は大丈夫かとつい心配になる。もう年寄りの出る幕ではないが。