2008年12月28日: 孫達の時代 T.G.
 二人目の孫が生まれた。 上の孫娘はもう3才だから三つ違いの弟だ。 1ヶ月検診で母子共に順調と聞いて安堵する。 息子夫婦は少し離れたところに住んでいるので、たまにしか会えない。 最近の一番の楽しみは、会うたびに可愛くなる孫を見ることだ。 自分の子供を育てているときは仕事も超多忙だったし、無我夢中であれこれ考えるゆとりはなかった。 どういう子供に育てるか、深く考えたこともなかった。 幸いにも高度成長期の上り坂に差しかかた時期だったので、大した苦労も失敗もなく育てることができた。 時代が幸運を授けてくれたのだろう。 昨今の世相を見ていると、この可愛い孫達が大人になる頃の日本はどうなっているのか、いささか気懸かりである。
二人目の孫が生まれた。 上の孫娘はもう3才だから三つ違いの弟だ。 1ヶ月検診で母子共に順調と聞いて安堵する。 息子夫婦は少し離れたところに住んでいるので、たまにしか会えない。 最近の一番の楽しみは、会うたびに可愛くなる孫を見ることだ。 自分の子供を育てているときは仕事も超多忙だったし、無我夢中であれこれ考えるゆとりはなかった。 どういう子供に育てるか、深く考えたこともなかった。 幸いにも高度成長期の上り坂に差しかかた時期だったので、大した苦労も失敗もなく育てることができた。 時代が幸運を授けてくれたのだろう。 昨今の世相を見ていると、この可愛い孫達が大人になる頃の日本はどうなっているのか、いささか気懸かりである。息子夫婦は共働きである。 嫁もキャリアウーマンなので、今は育児休暇中であるが、それが終わると孫達を保育園に預けて会社に復帰する。 保育園の送り迎えをしながらの仕事と子育ての両立はまさに獅子奮迅、はたから見ていても大変だ。 総合職だからどうしても残業や出張を避けられない。 熱を出したと急に保育園から連絡があっても駆けつけられない。 そのたびに我々老夫婦が緊急出動でお迎えに行くが、嫁の心配、気苦労も察するにあまりある。 専業主婦だった家人は、3才までの子育ては大事だから、その間仕事は辞めるべきと内心思っているが、口に出せずにおろおろしている。 しかしながら今は夫の給料だけで家族を養える時代ではない。 それが可能だった我々の頃とは環境が違う。 共働きを前提に会社の給与体系や税体系や年金制度が出来ている。 専業主婦対象の配偶者特別控除も今はない。 嫁自身が仕事好きなこともあるが、夫である息子の働きだけでは今の生活水準を維持出来ないのだ。 息子夫婦の住まいを見ても、我々の貧しかった新婚時代とはまったく違う。 洒落たデザイン、冷暖房完備、蛇口をひねればお湯が出る。 今では当たり前のこの生活水準を、我々の頃のすきま風が吹く貧乏アパート時代には戻せない。 しかし、ほとんどの子供達が乳幼児期に母親でなく保育園で育てられた30年後の社会はどうなっているのだろう。 いくぶん気懸かりではある。
 こういう豊かさが、はたして孫達の時代まで続いているのだろうか。 社会の豊かさは所得水準もさることながら、それなりの働き場所があることが条件だ。 高度経済成長期は、勤労意欲さえあれば誰でも仕事にありつけた。 今の時代、グローバリズムと景気低迷で仕事が先細りだ。 派遣社員の首切りが問題になっているが、仕事がないのだから仕方がない。 内部留保を吐き出して雇用を守れなどとバカなことを言う識者がいるが、仕事がないのに雇用は出来ない。 企業経営のなんたるかを知らない暴論である。 派遣というおかしな職業身分が生まれたのも根本原因は仕事が減ったからだ。 水は高きから低きに流れる。 二次産業に限れば人件費の安い中国やベトナムに仕事が流れるのは避けられない。 それで賃金や労働条件劣化を“国民承知の上で”派遣法が生まれた。 今頃文句を言っても始まらない。 嫌だというなら元に戻せばいい。 その代償に仕事も海外へ流れ出る。 どちらがいいか、難しい選択だ。 もうしばらく、中国の経済圧力は無くなりそうもない。 孫達の時代に、今程度の働き場所も無くなっている可能性は大きい。
こういう豊かさが、はたして孫達の時代まで続いているのだろうか。 社会の豊かさは所得水準もさることながら、それなりの働き場所があることが条件だ。 高度経済成長期は、勤労意欲さえあれば誰でも仕事にありつけた。 今の時代、グローバリズムと景気低迷で仕事が先細りだ。 派遣社員の首切りが問題になっているが、仕事がないのだから仕方がない。 内部留保を吐き出して雇用を守れなどとバカなことを言う識者がいるが、仕事がないのに雇用は出来ない。 企業経営のなんたるかを知らない暴論である。 派遣というおかしな職業身分が生まれたのも根本原因は仕事が減ったからだ。 水は高きから低きに流れる。 二次産業に限れば人件費の安い中国やベトナムに仕事が流れるのは避けられない。 それで賃金や労働条件劣化を“国民承知の上で”派遣法が生まれた。 今頃文句を言っても始まらない。 嫌だというなら元に戻せばいい。 その代償に仕事も海外へ流れ出る。 どちらがいいか、難しい選択だ。 もうしばらく、中国の経済圧力は無くなりそうもない。 孫達の時代に、今程度の働き場所も無くなっている可能性は大きい。その話と逆に、人手不足も日本の抱える大問題だ。 少子化対策で外国人労働者を千万人受け入れようなどと、おかしなことを言う政治家がいるほどだ。 仕事がないというのは都会の二次、三次産業に限った話だ。 その気になれば仕事などいくらもある。 最たるものは農業だろう。 日本の農業の最大の問題は後継者がいないことだ。 朝から晩まで汗水垂らして働いても収入はわずかだから、若い人がやりたがらない。 軽い気持ちで都会に出て、フリーターや派遣になる。 その仕事が無くなったからと泣き言を言う。 派遣フリーターはそもそもそう言う身分なのだ。 それが嫌なら、田舎へ帰ってオヤジさんの跡を継いで畑を耕せばいい。 余っている畑や水田はいくらもある。 食糧自給率が40%と言うことは、それを倍の80%に上げるだけで今の農業従事者数と同じジョブが生まれる。 農業以外にも介護労働など、人手不足の職場はいくらもある。 後は農業、医療政策と若者の勤労意欲の問題だ。 今のレベルの低い政治家や勤労を厭う若者を見ていると望み薄だが、そうも言っておれない状況だ。 30年後に孫達の仕事がちゃんとあるのだろうか。
一番の心配はこの国の安全保障だ。 この60年、多少の波風はあっても、日本社会にさしたる混乱は起きなかった。 外乱も被らず、社会秩序は安定し、飢えや寒さが死語に近い豊かな社会を享受出来た。 これから先はそうは行かない。 これまでの安定は東西冷戦による力の均衡の副産物に過ぎない。 それが終わり、巨大中国のプレゼンスが割り込んできたら、世界は一挙に不安定になった。 70年前と同じ状況だ。 歴史は繰り返す。 昨今の金融大混乱はアメリカの金融政策の大失敗だが、中国の急激な膨張がその一端を担っていた。 欧米は物作りを中国に丸投げして、金融立国に走る選択をした。 その歪みが形を変えて世界に波及し、テロが起き、イラクが壊された。 あげくに行き着いた先が百年に一度の金融大混乱だ。
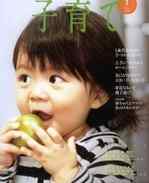 経済力を得た中国は軍事大国の道を歩んでいる。 歴史を見ても巨大化した軍事力は必ず出口を求める。 一衣帯水の所に出口を探す巨大軍事力がある。 この先心配なのは金融より安全保障問題であろう。 欧米、ロシア、中国の力関係の変遷でいろいろ摩擦が起きるだろう。 日本の隠れ蓑だった日米安保も影が薄くなっている。 10年後ぐらいに解消される可能性は小さくない。 その状況で中国の軍事圧力はますます増大する。
経済力を得た中国は軍事大国の道を歩んでいる。 歴史を見ても巨大化した軍事力は必ず出口を求める。 一衣帯水の所に出口を探す巨大軍事力がある。 この先心配なのは金融より安全保障問題であろう。 欧米、ロシア、中国の力関係の変遷でいろいろ摩擦が起きるだろう。 日本の隠れ蓑だった日米安保も影が薄くなっている。 10年後ぐらいに解消される可能性は小さくない。 その状況で中国の軍事圧力はますます増大する。そう言うことを想定した安全保障論議が一向に始まらないのが気懸かりである。 多母神前航空幕僚長が乱暴な方法で集団的自衛権問題に一石を投じたら、防衛大臣を始め、政府もマスコミも大慌てで封殺した。 最近、佐藤栄作元総理がアメリカのマクナマラ国防長官に核保有した中国への有事の核攻撃を求めた密約が明らかになった。 見損なったとか、ノーベル平和賞を返納しろなどと識者やマスコミは的はずれな非難をする。 表向き非核三原則を標榜しながら、東西冷戦の狭間でしたたかな綱渡り外交をした政治家という真っ当な評価をしない。 現実を直視しない平和ボケ日本の行く末が大いに心配だ。 間もなく中国との直接的な軋轢が始まるだろう。 オバマ等アメリカ新体制は手を引いて掛かり合わないだろう。 自主防衛能力を持たない日本の安寧が損なわれ、混乱が起きるだろう。 そうなった暁にも日本の平和主義者達は自主防衛でなく話し合いでなどと寝言を言うのだろうか。 そういう寝言の被害者は彼らではなく孫達なのだ。
あれこれ考えると、悲観的になる。 今より30年後の方がより豊かで安定している公算は大きくない。 我々が経験した戦前戦後の一時期のように、生活水準が劣化した世の中を孫達は耐えられるだろうか。 豊かな時代に育ち、飢えも寒さも知らない彼らがそれに順応出来るだろうか。 順応出来たとしても、その経過でいろいろな苦しみや不幸が生じるだろう。 我々に出来たことが孫達に出来ないはずはない、と願う他はない。 もう我々は何もしてやれないのだから。
年を取ったらもう少し楽観的になれた方がいいのかもしれない。