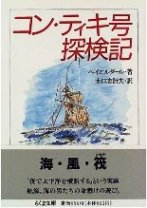 久し振りに本棚から「コン・ティキ号探検記」を引っ張り出して読み返す。この本は40年前の学生時代に一番町の丸善で買って読んだのが最初だが、その後幾度となく読み返した。読むたびに新鮮な感じを受ける。好きな本の五指に入る。
久し振りに本棚から「コン・ティキ号探検記」を引っ張り出して読み返す。この本は40年前の学生時代に一番町の丸善で買って読んだのが最初だが、その後幾度となく読み返した。読むたびに新鮮な感じを受ける。好きな本の五指に入る。1947年、ノルウェーのヘイエルダールという探検家が、ポリネシア人は南アメリカからの移住民だと言う学説を証明するためにペルーに渡り、そこに生えているパルサという巨木で筏を造り、友人6人とそれに乗り、風と海流に任せて6千キロの旅をする航海記である。理論の実証のために、古代人と同じ条件で十分な水も食料も持たず、動力もない筏で南太平洋を横断する。実際問題として危険極まりない航海なのだが、書かれている日常の描写が実に楽天的で好奇心にあふれていて、バイキングの子孫の面目躍如である。
太い竹の節を抜いて作った貯水タンクの真水はすぐに腐ってしまう。その後はスコールの雨水で航海を続けるが、それで十分だったと書いている。持ち込んだ食糧もすぐに尽きてしまうが、その後は手を伸ばせば魚がいくらでも捕れて食料にも困らない。それでもなにせ風任せの筏だから、ポリネシアの無人島にたどり着くのに97日間かかっている。航海の途中の出来事や事件も面白いが、何と言っても最後に筏が難破して漂着する珊瑚礁に囲まれた無人島の描写が素晴らしい。何度読んでも心が浮き立つ。ここを読むために読み返しているようなものだ。
『…私は暗礁を超して天国のような椰子島へ徒足で渡ったときのことを生涯忘れないだろう。日光に輝いた砂浜に行き着くと、靴を脱ぎ捨て、暖かい乾ききった砂に裸足のつま先を突っ込んだ。緑の椰子の実が椰子の葉むれの下に垂れ下がり、生い茂った茂み一面に咲き乱れた雪白の花は気の遠くなるほど甘い魅力的な香りを放っていた。二羽のアジサシが私の肩から肩へと飛び渡った。小さなトカゲが足下から走り出した。真っ赤なヤドカリがあちこちはい回っていた。ああ航海は終わったのだ。我々はみんな生きていた。小さな人の住まぬ南海の島に乗り上げたのだ。そして何と素晴らしい島だろう。ヘルマンが椰子の木によじ登って、大きな実をもぎ取ってきた。柔らかいてっぺんを南洋土人の刀でくり抜いて、甘くて冷たいミルクをゴクゴクと喉を鳴らして飲み干した。みなこの上なくいい気持ちで、砂浜に五体を伸ばして西の方に流れていく白い貿易風雲を見上げて微笑した。ベグントは正しかった。これは天国だった。…』
この後、この無人島でロビンソンクルーソーのような生活をするうちに、偶然カヌーで通りかかった近くの島の原住民に助けられヨーロッパに帰還するのだが、その間も好奇心丸出しの毎日で悲観的な様子はまったくうかがえない。スウェン・ヘディンと言いヘイエルダールと言い、北欧の人達の行動力と冒険心には頭が下がる。