 図書館で借りた福田和也著、「地ひらく、石原莞爾と昭和の夢」(文芸春秋社)を読む。 満州事変の首謀者として著名な陸軍参謀石原莞爾の生涯を書いたものだが、800ページにも及ぶ大著でなかなか読み進まない。 やっと盧溝橋に端を発する支那事変にたどりついたところだ。
この著書は石原莞爾の生涯を主題にしながら、同時代の日本と世界の置かれた状況を同時並行的に書き込んでいる。 戦後の一国平和主義に凝り固まった世の中で、誰も取り上げない石原莞爾と昭和史を克明に書いている点が面白い。 司馬遼太郎が「坂の上の雲」で明治史を書いた手法に似ている。 現在福田氏は文藝春秋誌で「昭和天皇」を連載している。 同じ様な書き方で毎号興味深く読んでいる。 昭和天皇を主題にすれば畢竟昭和史そのものにならざるを得ないからだ。
図書館で借りた福田和也著、「地ひらく、石原莞爾と昭和の夢」(文芸春秋社)を読む。 満州事変の首謀者として著名な陸軍参謀石原莞爾の生涯を書いたものだが、800ページにも及ぶ大著でなかなか読み進まない。 やっと盧溝橋に端を発する支那事変にたどりついたところだ。
この著書は石原莞爾の生涯を主題にしながら、同時代の日本と世界の置かれた状況を同時並行的に書き込んでいる。 戦後の一国平和主義に凝り固まった世の中で、誰も取り上げない石原莞爾と昭和史を克明に書いている点が面白い。 司馬遼太郎が「坂の上の雲」で明治史を書いた手法に似ている。 現在福田氏は文藝春秋誌で「昭和天皇」を連載している。 同じ様な書き方で毎号興味深く読んでいる。 昭和天皇を主題にすれば畢竟昭和史そのものにならざるを得ないからだ。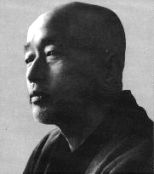 【石原莞爾の世界最終戦論】
【石原莞爾の世界最終戦論】石原莞爾は満州事変や満州国設立の立役者、首謀者として毀誉褒貶の激しい軍人であるが、彼の思想の集大成とも言える「世界最終戦論」は今の時代に照らしても合理的で説得力がある。 この論の主題は「アメリカとの最終戦争の後、世界に恒久的な平和が訪れる。」という実に壮大なスケールで、そのためにまず日本はアメリカとの持久戦争に耐えうる国力を蓄えるべきとした。 彼が知謀の限りを尽くして満州国を作ったのもその巨大な構想の一環である。
【石原莞爾と大東亜戦争】
石原を閑職に追いやった後、軍部の主導権を握った統制派の東条英機等は、国力も蓄えられない状況下で愚かにもアメリカに対して戦を挑み、見事に失敗した。 石原は殲滅戦の典型である真珠湾攻撃には終始一貫反対していたという。 それでは持久戦にならず、日本に勝ち目はないからだ。 よく知られている開戦直前の山本五十六など、一部海軍の単純な戦争回避論とは全く次元が異なる。 言うまでもなく殲滅戦はモルトケ以来、ヒトラーに到るまでのドイツ陸軍の伝統的兵法で、石原莞爾を除く明治以来の日本帝国陸軍が模範とした。 持久戦の典型的成功例はホーチミンが指導し世界最強のアメリカ軍を撃退したベトナム戦争であろう。
歴史にイフがタブーであることは承知の上で、もし東条英機ではなく石原莞爾が陸軍の主導権をとり続けていたならその後の世界史がどうなったか、興味があるところだ。 その可能性はなきにしもあらずだったし、満州事変の首謀者であった石原は、その後に起きた支那事変と戦火拡大には徹頭徹尾反対であったのだから。
【石原莞爾の国防国策大綱】
二・二六事件直後の昭和11年、平沼内閣の時に陸軍参謀本部作戦課長の要職に就任した石原のもとで帝国国防方針が作成された。 支那事変の直前である。 その骨子となった彼自身の「国防国策大綱」には冒頭次のように書かれている。
『皇国の国策は先ず東亜の保護指導者たる地位を確立するに有り、之が為東亜に加わるべき白人の圧迫を排除する実力を要す。 …。 先ず蘇国(ソ連)の屈服に全力を傾注す。 而して戦争持久の準備に就いて欠くる所多き今日英米、少なくとも米国との親善関係を保持するに非れば対蘇戦争の実行は至難なり。』
当時日本陸軍最高首脳の一人であった石原参謀は、日本の仮想敵はあくまでソ連であり、ソ戦と戦うためにはアメリカとの親善関係が不可欠と考えていた。 アメリカとの最終戦争はその後の段階である。
【戦争の勝敗】
クラウゼビッツの有名な「戦争論」によれば、戦争の勝敗は戦闘の勝敗ではなく目的を達したか否かで決まるとしている。 その論理からすれば、アメリカとの“最終戦争”の結果、目標通り欧米の植民地支配からアジアを開放した日本は“負けなかった”ことになる。 アメリカに対する殲滅戦とその敗北は、あくまで持久戦を主張していた石原参謀の責任の埒外である。 また戦後、昨今のテロ戦争など局地戦争はたびたび起こるものの、第二次大戦のような地球規模の総力戦か絶えたことも石原莞爾の目指した“最終戦争の後の世界恒久平和”と言えなくはないだろうか。 現在ある程度広範に行き渡った国連中心主義はその一つの形だろう。
風雲急を告げる開戦直前の昭和15年、東条等によって舞鶴要塞司令官という閑職に追いやられていた石原少将は「世界最終戦論」を刊行したと言う。 気力があったら読んでみたいものだ。