■合格る数学 (ウカルスウガク) ⅠA ⅡB ⅢC
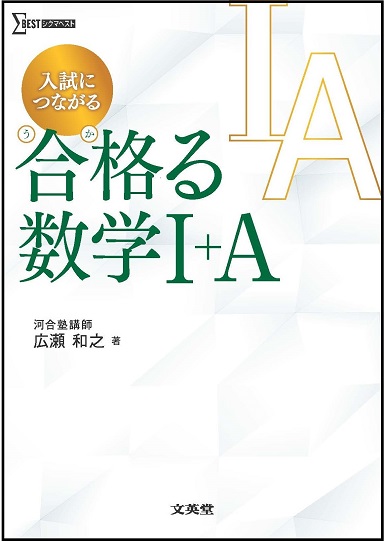 (文英堂Σベスト)
(文英堂Σベスト)
永きにわたり,数多くの受験生を支えてきた「理解しやすい」シリーズ(文英堂Σベスト)と後継という“重責”を担った書籍です.(流用等は一切ありませんが)
◇本書を「テキスト」とした
解説動画
◇
本書の
コンセプト
使い方
に関する動画を公開
◆概要
初学者向けの「学校教科書」と,受験学年生向けの「受験参考書」の機能を兼ね備えた書籍.だから
「基本原理」が,「入試問題解法」へ,つながる.
高校数学・大学受験・社会人学び直しの『学習ベース』(メリ・ハリのハリの方)とする書籍としては,本書の一択.決定版.
これまで30年超にわたって教えてきた生徒さんには,こうした書物を提供できなかったことを,土下座して謝りたい気分です...(授業数こなしながら書いたら,確実に命はなかったと思うが)
もちろん学校の授業と併用する“参考書”としても使うことも可能ですが,完全独学可能を旗印として書かれています.学校の進行を待たず,先行して自分で進めることもできると思います.
解説動画
もあることですし.
◆本書がフィットする人
上位大学(ここはワザとボヤかしとくね(笑))志望者.もしくは数学の本当の力を身に付けて,人生の財産としたい人.学ぶことの喜びを知っていて(またはこれから知りたいと思っていて),脳に負荷をかけてでも,一歩ずつ前へ進んで行きたいと願っている人.
<注>
ということは,「数学なんて受験のためだけにしょうがなくやるだけだし~,頭が疲れない楽な問題解法テクニックを沢山教えてよー」という人にはまったく適しません.本書をやると地獄だよ(笑).他を探しましょう.
<注>
ただし,「受験のためだけにしょうがなくやる」過程を通して,いつの間にか学ぶ喜びを知る人も沢山います!
◆正統的な数学の学び方
数学の学理・基本事項を『主体』とし,それを習得する“手段”として問題演習も行う.これが,普通の学び方です(大学に行くと,ますますそうなります.).
イメージが湧かない人は,本書のはじめにを読んでみてください.
数学の基本を丁寧に解説した書物として,「学校教科書」はとても優れています.筆者は,自身の受験生時代・予備校講師生活を通して手元に置いている本は常に教科書のみです.
ただし,教科書には弱点が2つあります:
(弱点その1)
“万人向け”に書かれているため,「高いレベルへの対応」は想定していない.
難関大学の「入試」まで“つなげる”ことはできない.
読者自身が“高いレベル”の人であれば,なんとかなってしまうが.
(弱点その2)
“初学者対象”に書かれているため,例えば「三角比」(数学Ⅰ)の記述において,後に学ぶ「三角関数」(数学Ⅱ)との関連情報が薄い.よって,「三角関数」を学んだ後に「三角比」を2度目に復習する際,「三角関数」の内容を取り込んでステップアップすることができない.
また,入試の“花形”である「分野を横断した融合問題」も扱うことができない.
これらの弱点を補うため,「学参」をプラスすることとなる訳ですが,別の書物で学ぶ宿命として起こるのが
「教科書の基本」と「学参の発展・総合演習」の乖離
という現象です.初学者のときは教科書をやり,受験学年時になると教科書には目もくれないでひたすら学参に載った問題の解き方を暗記して行く.これが,よくある“最悪の”学習スタイルです.せっかく,T大さんやK大さんが,あんなに教科書からの距離が近い問題を出してくれてるというのにね(苦笑).
数学が普通にできる人(滅多にいないよ)であれば,自分で教科書と入試レベルの問題解法をつなげられるので,学参を使う・使わないに関わらず大丈夫なのですが,ほとんどの受験生には,“つなぐ”のは無理です.
◆本書の特徴
という訳で,冒頭で述べた通り
「基本原理」が「入試問題解法」へつながる
ことを目指して書かれています.そのために・・・
1.
基本事項を一からみっちりと,教科書並みもしくはそれ以上に詳しく掘り下げて書きました.受験参考書にありがちな,教科書で基礎を学んでいるはずだからと“甘えた”申し訳程度の要約とは訳が違います.
基本事項解説こそ本書のメインコンテンツです.
2.
と言いながら,問題も充実しています.全662題 1).「問」なども入れるともっと多いです.
“無意味に”難しいものではなく,学んだ基本が役に立つ,言い方を変えると基本の習得に役立つものを主体としています.もちろん,上位大学入試問題レベルの問題も多数含んでいます.
3.
1.の「基本原理」と,2.に含まれる入試で“難問”と称されるものなどの「解法」がどのようにつながっているかを詳しく解説しています.
入試の難問が“自分で解ける”センセイはたくさんいますが,解く際に自分の頭がどう動いたかを[自覚→言語化→他者へ伝授]することはまったく別のスキルです.ここは,筆者の得意技です(笑).脳内の蠢 きを,包み隠さず書いています.(若干クドくて,たまに引かれます(笑).)
4.
「後に学ぶ分野との関連情報」
例えば数学Ⅰ「データの分析」は,数学B「数列」で学ぶ「Σ記号」を使わないことには埒が明かない分野です.そこで,「数列」未習者・既習者の両方を想定して,「○+△+□+・・・」と「Σ」の2通りの表記を併用しています.
このように,将来学ぶ内容も踏まえ,高校数学全体を視野に入れて記述しています.また,先々で学ぶ分野との融合問題もかなり取り入れています.(もちろん高1生はスルーしてよいですが.)
5.
読者の理解を促すためには,一切の妥協をしない.どんなに書くのが辛い所でも,決して逃げない・甘えない・妥協しない.そうした心構えのもと,2192個2)の図・表も筆者自ら描きました3).
昨今,原稿の「文字」だけを「コピペ」で楽~に書き,「図・表」などは(自身の労力およびデザイナーさんへの発注の手間・費用削減のため)サボる同業者を目にします.“指導者”として,失格です.
まとめると,要するにとても正統的で普通の本ですが,凄く丹精込めて書かれているということです.
高校1年生で初めて学ぶ時から,受験学年時まで,この一冊を使い続けてくだい.そうすれば,「基本原理」と「入試問題解法」がつながるはずです.
◆本書を「教材」とした動画サービス
それほどまでに丹精込めて書かれていてもなお,「文章」より「講義・動く映像」の方が伝わりやすい題材もあります.また,分野の全体像・概観とかも,文章より,画面でページを早送りしながら喋った方が伝えやすかったりします.そのような「動画提供する価値が高いもの」をラインナップしたサービスを提供します.
『渾身動画見放題』(笑うほど格安)に登録すれば,他のコンテンツともどもご利用いただけます.
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
もう,「うちは経済的に厳しくて・・・」なんていう言い訳=自己防衛は通用しません.あなたに「受かりたい」「学びたい」「昨日の自分を超えて行きたい」という揺るぎない意志があるなら,誰にも・どこにも引けを取らない教育環境が目の前にあるのですから.
◆現行課程・新課程
言うまでもなく,本書は2022年度高1→2025年度大学受験の「新課程」を想定して書かれています.しかし,2024年度入試までの「現行課程」と比べて,「ⅠA分野」の「入試に関係する部分」についてはそれほど大きな変更点はありません.4)
ⅠAの中で,
「数と式」
「2次関数」
「図形の性質」
は“今後の”学習において“土台”となる重要分野なのに,(単独では)“入試で出ない”ため,けっこうないがしろにされがち.
ⅠAが既習である現行課程生も,今後につながる大切なことを教わってない人が多いはず.本書で学び直しましょう.
また,合否を決める1題になる可能性の高い
「整数」
「場合の数・確率」
は,ちゃんと教えられる人の少ない分野です.既習である現行課程生も,本書で学び直しましょう.(既に出版した本との関係は,次の項目で.)
全般に,ⅠAはⅡB・ⅢCに比べて“クセ”が強い分野(データの分析など)が多く,執筆はダントツで一番困難です.それだけに,他書とは“モノの違い”が顕著に現れているはず.書店で手に取って比べてみて欲しいです.
「すでに○○ⅠAという学参買って持ってるから」なんて言う人は,価値判断のできない人(生涯収入変わるんだよ(笑)).現行課程生も買って損はない,というか,買うべきよ.
◆他の拙著との関係
(a).『合格る計算』
本書をベースに,(a)は計算練習量を補充する目的で使いましょう.同じ人が書いているので,“つながり”もわかりやすく,何に注意して計算するべきかもハッキリするずです.
(b).『合格る確率』
本書の方が基礎寄り.(b)の方が高度・発展問題の比重が高いです.
同じ人が書いているので,当然内容が重複する部分もあります.
(c).『ありのままのシンプルな整数』
上記(b)と同じです.
◆最後に著者の心意気
“攻める老後”へ狼煙を上げるべく,講師人生の集大成として全てを注いだ.もう,絞っても一滴も出やしない.おれの形見.今のところまだ向こうへ渡る予定はないが(笑).
**********************************
1)
661題自作・1題東大改題(→「利用報告書」提出).“自作”といっても,夥しい入試問題研究から抽出したエッセンスを自分なりに消化して,書籍の流れの中の各ポジションで読者の学力伸長に寄与する深度・ボリュームになるよう“調理”したに過ぎませんが(笑).
2)
本当に数えてくださった編集スタッフの方に感謝です.お疲れ様でした!
3)
これを実行できたのは,TeX用描画ソフト
「WinTpic」
のおかげです.作者の方に対して,感謝の気持ちでいっぱいです.
ちなみにこのソフトは,まるで
「作図」
(定規とコンパスによる)をするような感覚で図形が描けるという優れ物です.TeX本体とは切り離して単体で使うことも可能ですから,Windowsパソコンをお持ちの方は,一度試してみてください.使用法の
解説動画
が,広瀬教育ラボのYouTubeチャンネル内にあります.
4)
高校数学全体における「受験」に関係ある主な変更点:
・「数学A・確率」に「期待値」が追加.
・「数学B」に「統計的推測」が追加(ただしその影響は,とくに理系生にとっては未知数.)
他にもあったかな~.でも忘れた.その程度(笑).
当初は大改悪がなされたと世間で評判でしたが,けっきょくその後猛批判を浴びて(?)なし崩しになった模様(笑).入試での扱いには未知数な部分もありますが・・・
サイトトップへ
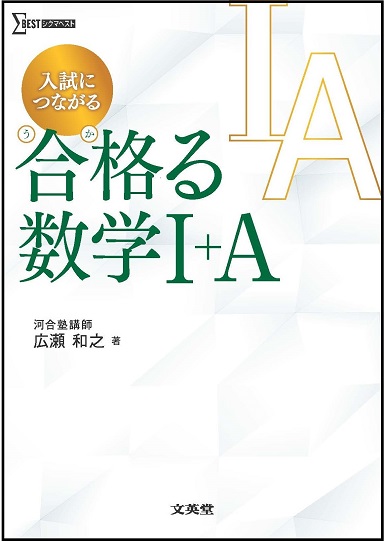 (文英堂Σベスト)
(文英堂Σベスト)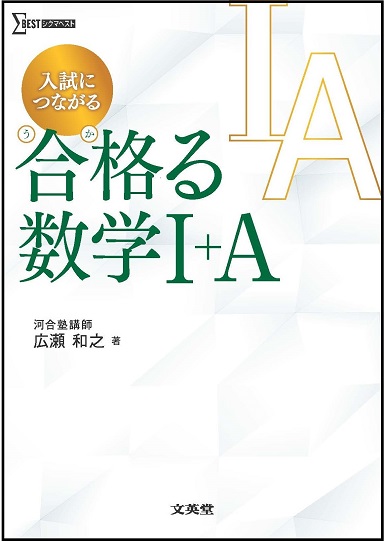 (文英堂Σベスト)
(文英堂Σベスト)