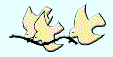 |
 |
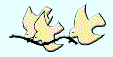 |
 |
支援する会・解散総会
松谷英子あいさつ
こんにちは。皆さまにはお忙しく寒い中を総会のため、ご出席いただきましてどうもありがとうござしました。
1988年12月10日、支援する会結成総会より12年間、全国の皆さまにご支援いただき最高裁で原爆症認定を勝ち取ることができた事に感謝申し上げます。
思い起こせば23年前、私は原爆症の認定の手続きをすることを知りませんでした。長崎原爆被災者協議会で一緒に働かさせていただいていた相談員の横山照子さんが、私の毎日の行動を見るうちに、原爆症の認定の申請をしてみようと言って下さいました。1977年、1回目を原爆病院の診断書や意見書を添えて申請しましたが却下され、あきらめかけていました。
10年後の1987年、横山さんが現在、私の主治医である山下先生に相談して、2回目の申請に頭部の断層写真等も提出していただきましたが、これも却下されました。
2回も却下された私は、原爆のためにこのような障害者になったことはまぎれもないことだし、却下されたことに憤りを覚えました。長崎原爆被災者協議会でも皆さんで話しあっていただき、2回却下されたらもう裁判しかないと結論が出ました。
しかし私は、裁判と聞いただけで戸惑いました。というのも私はこんな身体になってからは、引っ込み思案のうえに、人の前で話をすることすらできませんでした。そんな私でしたが、母に「原爆のための障害というのははっきりしているのだからやってみたら」と言われ、裁判をすることになりました。
裁判が始まってからはこの12年間、いろんな事がありました。
裁判を東京へ移そうとする厚生省への抗議に始まり、弁護団の先生方、科学者・医師・被爆者と証人として証言して下さったり、被爆直後の映像を収めたビデオの上映等、また裁判のたびの傍聴席はいつもいっぱいになり、報告集会を開いて裁判の内容を弁護士さんからくわしく説明してもらっていました。
福岡高裁になってからは朝早くで駅前に集合して貸し切りバスで福岡まで。バスの中で昼食をすませ、天神で署名行動して裁判の傍聴、報告集会会が終わり、長崎へ到着するのはいつも夕方になっていました。
最高裁へ移ってからは日本被団協をはじめ14団体で松谷裁判ネットワークをつくっていただき、裁判が開かれないため署名を集めて上申書と一緒に署名を提出に行き、書記官が対応されて私たちの意見を聞き、書記官はそれをメモするだけでした。
1993年5月、長崎地裁で、1997年11月、福岡高裁でそれぞれ完全な判決を勝ち取り、提訴から11年7ヶ月あまりの2000年7月18日、最高裁で勝訴が確定しました。
この勝利は決して私一人の勝利ではなく、被爆者全体の勝利であり、一緒にたたかっていただいた皆様の勝利だったのです。
この12年にわたり、各団体から代表者を選出して役員として活動され、会議や署名行動等の参加もよくしていただきました。また事務局員として頑張ってくださった皆様も昼は勤めながら、事務局会議や役員会、署名行動と頑張っていただき言葉では言い尽くすことができないことばかりです。本当にありがとうございました。
京都の高安さんも大阪高裁で勝利が確定し、認定書もいただいたとの事。一緒にたたかった1人としてうれしくてたまりません。これからは東京の東さん、札幌の安井さんの認定が一日も早く実現できるように一緒にたたかっていきたいと思います。
長い間ほんとうにありがとうございました。
12年間の私たちのとりくみ
I.私たちの運動の成果
私たちが「支援する会」を結成したのは、1988年12月10日、松谷英子さんが長崎地裁へ訴状を提出してから2ヶ月あまりたった、第1回口頭弁論(12月16日)の直前でした。
「支援する会」の結成総会のアピールで私たちは、「松谷さんの傷は、疑いもなく原爆の障害作用によるものです」「松谷さんのような方を、これまで放置してきた国の責任はきわめて重大です」と指摘し、「厚生省の不当な仕打ちに屈することなく、敢然と、厚生省を相手に訴訟を決意された松谷英子さんに敬意を表するとともに、勝利の判決を手にする日まで奮闘する」ことを誓いあいました。
1993年5月には長崎地裁で、さらに1997年11月には福岡高裁で、それぞれ完全勝利の判決をかちとり、提訴から11年7ヶ月余の今年7月18日の最高裁判決で松谷さんの勝訴を確定させました。
「厚生省は松谷さんに、がまんせよというのでしょうか」と結成総会で問いかけた私たちでしたが、最高裁へ提出した「上告理由書」の中で、厚生大臣は臆面もなく「戦争の被害は国民が等しく受忍すべき性質のもの」と主張、DS86と「しきい値」理論の機械的適用だけを頼りに、自ら行なった原爆症認定申請への却下処分を正当化しようとしました。
もともと最高裁の判例には「戦争被害受忍論」の考えと「原爆医療法の根底には国家補償的配慮がある」とみる二つの流れがありました。しかし最高裁は、今回の判決にあたって「戦争被害受忍論」の立場には立たず、DS86と「しきい値」理論の機械的適用を厳しく批判、厚生大臣の却下処分を取り消した高裁判決を支持しました。
最高裁を、このような立場に立たせたのは、まさに裁判支援運動の成果でした。長崎地裁、福岡高裁の法廷で、そして最高裁へ提出した「上告理由反論書」の中で、弁護団は執拗なまでに原爆被害の実相を明らかにすることに力を注ぎ、私たち「支援する会」も結成の当初から「原爆の被害をがまんすることは、核兵器を、そして核戦争を容認することにつながります。それは絶対に許せないことなのです。」という立場に立って支援の運動を推進してきたことが、勝利判決へと結びついたのです。
II.成果を生みだした私たちのとりくみ
私たちは、「この裁判は、ひとり松谷さん個人の救済にとどまるものではありません。核兵器、核戦争を許さない決意に燃えて、この裁判の勝利へむけ、ともに手をたずさえ、ともにがんばろうではありませんか」
と呼びかけた結成総会での声名を「支援する会」活動の原点として取り組み、運動を切り開いてきました。
III.残された課題
裁判に勝利し、松谷英子さんは原爆症として認定されました。さらに、京都の高安さん(ペンネーム)の原爆症認定訴訟も大阪高裁で勝利し、厚生省の上告断念により勝訴が確定しました。
しかし、すべてが終わったわけではありません。それは、厚生大臣が松谷さんへの謝罪をかたくなに拒み続け、最高裁が批判したDS86と「しきい値」理論に依拠した原爆症認定作業にあくまでも固執しようとしているからです。いいかえれば、国民をあの残虐な原爆被害にさらした責任を償おうとせず、被爆者行政への反省を拒んでいるからにほかなりません。
厚生大臣が、東京の東さん、北海道の安井さんのケースについても、「司法の判断を仰ぐ」と言ってることは、その証拠です。
これまで松谷訴訟を支援して下さった、全国の皆さん。それぞれの地域・職場・学園で、仲間たちと手をつなぎ、東京、北海道の原爆症認定訴訟を支援し勝利させましょう。
厚生省にたいしては、DS86と「しきい値」理論に依拠する現在の原爆症認定の仕組みに象徴される、政府の被爆者対策の抜本的転換を要求しましょう。東京の東さん、北海道の安井さんについては、ただちに原爆症と認定するよう要求しましょう。
松谷訴訟を支援して下さった全国の皆さん。そして、私たちの取り組みを温かく見守って下さった国民の皆さん。「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意」した日本国憲法の立場に立ち返り、「戦争被害受忍論」の払拭と、その背景となってい日本の核政策の転換を、日本政府に迫ろうではありませんか。
<アピール>
「支援する会」解散にあたって国民の皆さんに訴えます
原爆症認定を求める、被爆者・松谷英子さんが起こした裁判・長崎原爆松谷訴訟は、今年7月の最高裁判決により松谷さんの勝訴が確定し、松谷さんを原爆症と認定させました。
1988年9月の提訴以来、1993年5月の長崎地裁での勝利判決、1997年11月の福岡高裁での厚生大臣の控訴棄却の判決、そして今年の最高裁判決と、12年に及ぶ皆さん方の暖かいご支援にたいし、ここに改めて敬意を表し、感謝します。
この間に、弁護団は137名となり、全国で1万人が「支援する会」に結集し、地裁、高裁、最高裁へ寄せられた署名の総合計は120万に達しました。長崎原爆松谷訴訟は、このような国民的支援を背景とする多くの人たちのご奮闘により勝利したのです。そしてこの勝利は、京都の被爆者・高安さんの大阪高裁での勝利確定へとつながりました。
厚生大臣を相手とする裁判に勝利をし、松谷英子さんの原爆症認定を実現した私たち「長崎原爆松谷訴訟を支援する会」は、今日の総会で解散を決定しました。
しかし、私たちの課題のすべてが達成されたわけではありません。
第一に、厚生大臣、松谷さんの障害を原爆症と認定したものの、13年前の、あるいは22年前の、松谷さんの認定申請にたいする違法な却下処分についての謝罪をかたくなに拒んでいます。謝罪を拒むことは、これまでの原爆症認定のあり方を反省しようとしない証拠です。また厚生大臣は、これまでの被爆者対策背後に横たわっていた「戦争被害受忍論」についても撤回しようとしていません。このままでは、厚生大臣によって同じ過ちが繰り返されても不思議ではありません。
国民の皆さん。原爆の被害は、かつて最高裁が指摘したように「戦争という国の行為によってもたらされたもの」であり、政府がその責任を自覚し、原爆の被害を償うことは、ふたたび被爆者をつくらない決意の第一歩なのです。
私たちは、今日解散を決定しました。しかし私たちは、それぞれの地域で、職場で、学園で、再び被爆者つくらないために奮闘することを誓いあいました。
国民のみなさん。来たるべき21世紀を、核兵器も戦争もない世紀とするために共にがんばろうではありませんか。
2000年12月10日
長崎原爆松谷訴訟を支援する会・総会
「支援する会の解散」および残務処理委員会の設置について
「長崎原爆松谷訴訟を支援する会」は、裁判での松谷さんの勝利と原爆症認定を勝ち取ったことにより、会の目的を達成したことを確認しました。したがって、支援する会は、12月末日をもって解散をします。 なお、残った業務については「残務処理委員会」を設置し1月末を目処に取り組むこととします。
1. 「残務処理委員会」に付託される残務の内容
2. 残務処理のための事務局は、引き続き長崎原爆被災者協議会に置きます。
3. 残務処理委員会メンバーは、2000年度の代表委員、理事、監査、事務局員とします。
以 上