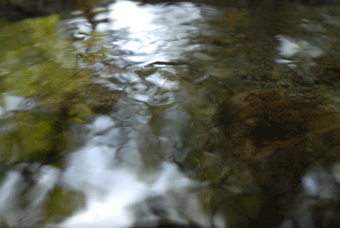
言葉本来の心の絆を取り戻すために、感動の音を求めて聖地を訪ね歩いてみました。出迎えてくれたのは、澄んだ空気とお日様を受けとめて輝く透明な水の働きでした。
覗き込むと、私自身の顔が映ります。背景には大空が広がり、夜のかなたに星が煌めきます。想像してみてください。無数の銀河の最果てに、この宇宙が開闢したその瞬間までもが水鏡に映りだされていることを。世界が開闢する前夜、その混沌のゆらぎの中で形もなく私たちは眠っていたのです。
こんな魔法の働きを持っている水鏡の写真を修め、そこから汲んできた水に音をともしていったのです。心の絆を取り戻すための感動の音、あからわをんまでの四十八音を授かりました。
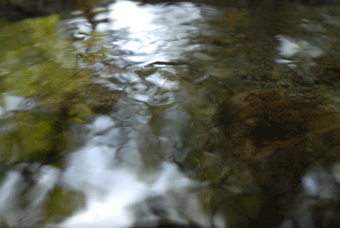
い
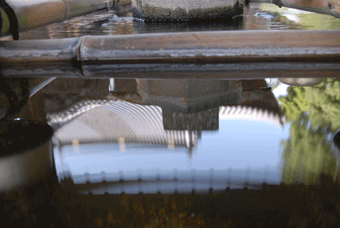
ん

り

よ
 ほたる川
ほたる川
る

か

け

や

に

も

す
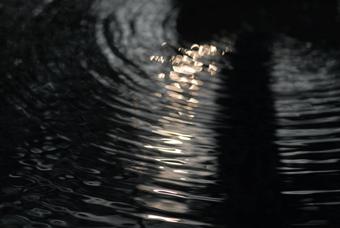
は

し

み

ゐ
ろ

こ

そ
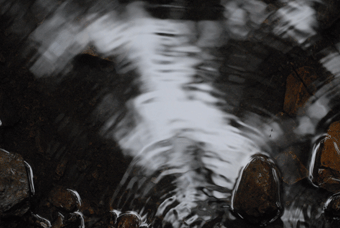 両崖山
両崖山
れ

ふ

ぬ
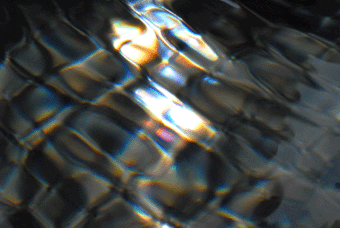
わ

き

ゑ

つ
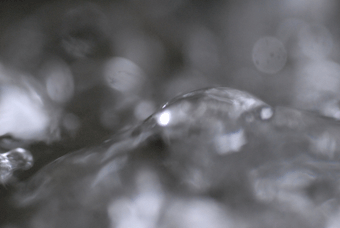
お

あ

な
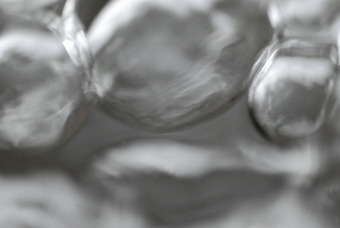
ほ

へ
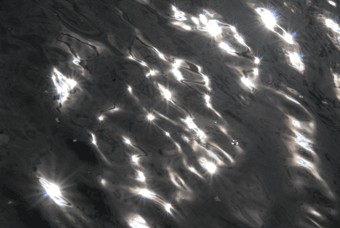
た

せ

む

ち

て
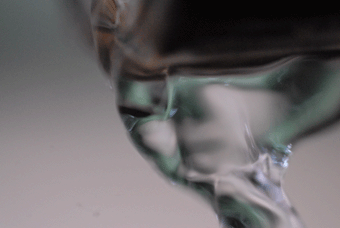
え

う

を

ひ

の
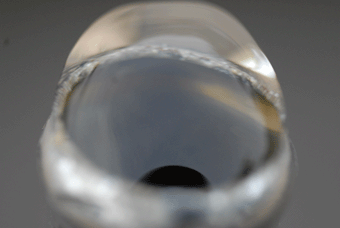
さ

ま

く

ゆ

ら
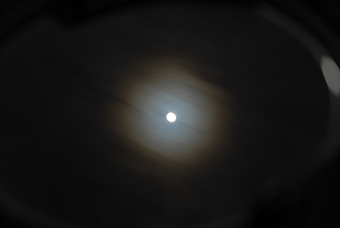
め
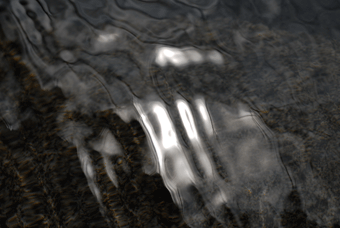
ね

と
音が融けている水にはどんな力が秘められているのでしょうか?祈りの雫を幾つか選んで音の融けた言霊水を創ってみました。
わそよみひ
ちあかみひほみ
さかひおりあわ
うすはわか
んくあわよに
たまちとく
かうるなみき
うすいかあわた
あもみことやは
かみふねたみか
かさつかるたね
さかしにしつき
この写真と水を使ったワークショップは「スサノヲの到来
―いのち、いかり、いのり」展の関連イベントとして足利市立美術館(2014年10月26日の午後2時から4時)とDIC川村記念美術館(2015年3月15日の午後2時から4時)で開催されました。
展示室と展示室を繋ぐ廊下や階段、ロビーや踊り場など四十八ヶ所に写真と水を配置しました。感動の音を求めて私が聖地を訪ね歩いたように、ささやかな巡礼を演出したかったのです。
いくら巡礼を演出したからといって室内の展示は、自然に身を委ねた時のように全身全霊で感じるようなわけにはいきません。感受性が視覚に限定されるのです。
では、観ることとはどういうことなのでしょう。言葉を創るという文脈から離れることなく考えれば「まなざし」という言葉に行き当たります。「真名差し」をこう書きますと真の名を表すことになります。未だならざるものに真の名を与えることが観るということなのです。真の名とはそのもの特有の働きのことですから、つまり、捉えた世界の本質を見極めることが観るということなのではないでしょうか。
配置した水鏡の写真を巡礼し、真名差しが融けている水を感じて歩きます。気になるものがあれば、小瓶に一雫、また一雫と音を採取して行きます。あちこちから採取した音が小瓶の中で響き合い真名の言の葉(言霊水)が生まれるのです。
こうしてできた音の連なりを別紙に記録し、言霊水の入った小瓶に巻きつけます。 それをキューピー人形の中に入れて持ち帰りました。
キューピー人形は、真の名を宿し、その働きを持って生まれる命のことを考えるために用意しました。