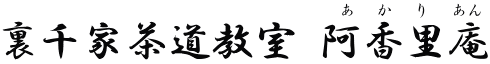
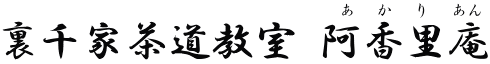
|
冬のお茶室は、あったかくいい香りに満ちて、幸せな気持ちになります。 エアコンやストーブと違って“炭”の熱は遠赤外線、体の芯から暖まります。 そしてお釜から立ちのぼる“湯気”もごちそうです。湯気を眺めているだけでほっこりします。 湯気が立ち上り始めてから沸騰するまでの間、お釜から音がします。煮え音です。 これは“六音(ろくいん)”といって六段階に分かれています。 松風(まつかぜ)という言葉は聞いたことがあるかもしれませんね。 さて年明けからの最初のお茶会、又はお稽古のことを“初釜(はつがま)”といいます。 お正月らしい様々な設え(しつらえ)があります。床のかざり、お道具類、懐石料理、お菓子などなど。 必ず使うのは“嶋台茶碗(しまだいちゃわん)”。楽焼の大きめのお茶碗で、内側が金と銀に塗られた二つセットの“重ね茶碗”で、お濃い茶を点てて皆さんでいただきます。 金銀が剥げてしまわないように、気を付けてそーっと扱います。 |
|
 |
 |
|
又、お薄茶を入れる“棗(なつめ)”、 これは大ぶりのものですが、私がお稽古を始めて最初に買い求めた、大好きな大事なお棗です。 |
|
 |
|
|
2月になりますと寒さが厳しくなるので、この時期だけのお点前として、 “筒茶碗”というものがあります。 ふつうのお茶椀より深く筒状で口がせまくなっていて、 お茶が冷めないようにとの心遣いのお茶碗です。扱いがちょっと大変です。 |
|
 |
|
|
3月。もちろん雛祭りです。大好きなお雛様を飾りました。 お雛様の前で、“誰が袖棚”とお雛様の絵の織部茶碗でのお点前です。 水指、建水も織部です。 お菓子は、扇の形の自作の器(逆さまにすると富士山)に、お団子とお雛あられです。 母、姉、私の三組のお雛様にも差し上げました。 (ブログを見て下さいね) |
|
   |
|
 夏バージョン(風炉) |
お茶のお稽古を続け茶道(ちゃどう)を学んできて“良かったなぁ・・”と思うことがたくさんあります。 日々の生活の中で、茶道で得られた知識や知恵がたくさん役に立っています。それは茶道が昔からの様々な日本文化と共に、というか取り込んで成り立っているからだと思います。 茶道の学びの中には、お茶を点ててお客様に差し上げるだけでなく、床(床の間)には掛け軸がかけられていて“書道”が、又その床にはお花があって“華道”が、お香をたくので“香道”が、着物と歩き方の基本は“能“から、そしてお客様への軽いお食事“懐石料理“は禅の修行が関係している・・ などなどたくさんあります。奈良・平安時代から育まれてきた日本文化を学ぶことでもあるのです。 そして何よりお茶の心は、相手を思いやる心“おもてなしの心“です。東京オリンピック・パラリンピックで世界中に有名になった “OMOTENASI” は日本の心、お茶の心なんです。 お茶室の様子は、5月と11月に変わります。 5月から10月までは夏バージョンの「風炉(ふろ)」、11月から4月までは冬バージョンの「炉(ろ)」となります。 炉に変わるときがお茶の世界のお正月「炉開き」でお祝いをします。私の所では毎年簡単なお茶事を行い“粟(あわ)ぜんざい”を頂きます。これが終るといよいよ冬だなぁと感じます。 |
 冬バージョン(炉) |
|