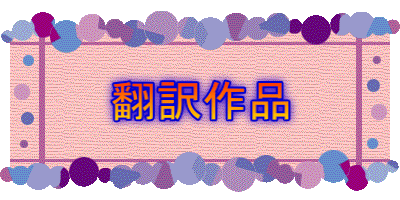
2010年に出版された自著の短編について、ささやかなコメントを。
天井桟敷のあの席へ
童話を書き始めた二十代前半、童話雑誌『MOE』の、ユア・ストーリーボックスという
コーナーに、原稿用紙10枚のメルヘンをせっせと投稿していました。その頃に
雑誌に採用された物語が、この作品のベースです。芸術家(ここでは、主人公の少年)
には、辛口で愛情深いパートナー(青いスカーフの少女)の存在が大きいのでは?
腹話術のからくり
一人で声色を使って、人形を操る様子が、とてもファンタジックなので、物語の素材に
使いました。幼い子どもを抱えて途方にくれる若いパパが、子どもより自分の夢を
優先させてしまう気持ちは、よくわかるけれど、最後はきっと、こんな思いに捉われる
のではないでしょうか。
ディ・ブレイク
就職先は、大手の印刷会社で、二百人近い同僚が、ワンフロアで働いていました。
営業開発をしていた私のとなりのセクションは、庶務課で、もくもくと仕事をこなす
課長さんがいました。その方が定年退職を迎えた日、花束を贈られ、去っていった
後には、何事もなかったように皆が仕事に戻り・・・。誰かが不在でも、変わりなく
過ぎていく人生を思ったときに、この物語のカトーさんが生まれました。
贋作鑑定師
本物かニセモノか、遠い時代の芸術品を鑑定する技術や知識は難しそうで、
作った本人に聞くのが一番、という発想から、この作品が展開します。
鑑定士は、今は“士”という字を使いますが、専門家という意味や、ラジィの尊敬する
師匠という意味で“師”を使っています。
藍色の夏
姪が小学生の頃、夏休みの自由研究で、私の住む町の染物屋さんを一緒に
訪ねたことがあります。夏真っ盛りの日に見た、古い古い染物工場での体験は
今、思い返すとひどく幻想的で、日常から切り離された時間だったような気がします。
クリーニングいたします
以前、PTAのママたちで集まったときに、「子どもは父方の母親より、母方の母親に
なついている」という話をよく聞きました。子どもを連れたママが頻繁に遊びに行くのは、
やっぱり気楽な実家だからでしょうね。それでも、それぞれのおばあちゃん、
おじいちゃんの良さがあり、子どもたちはよくわかっているんじゃないかと思います。
アリス川公園は、そのものズバリ、私の好きな麻布の有栖川宮公園のことで、公園内の
都立図書館には、昔、よく通ったものです。
たどり着いた場所
ニューファミリー新聞という地域紙に、千葉の風景を写真にとって、物語を付けると
いう連載をしています。どこでも好きな場所でいいので、JR八街駅の前に
落花生のオブジェがあると聞いて行ってみました。初めて歩く八街の町、“ぼっち”と
呼ばれる積み上げられたワラが、畑にいくつもあって、ミレーの絵のようでした。
その時に作った物語です。
あの子を探して
本のタイトルは、いくつか案を考えたのですが、最終的には、愛育社の伊東さんに
決めていただきました。ここに集めた短編には、「あの人は誰だったんだろう?」という、
謎めいた人物が出てきますので、このタイトルは似合うのではと思います。
この話も、ニューファミリー新聞のために作ったものです。夜のテントの中で輝く、
無数のおもちゃ宝石は、実は地元にあるロッククライミングの店の光景が,基になって
います。壁にはめ込まれた色とりどりの足場が、遠くから見ると、宝石みたいでした。
どれか、ほんの少しでも心に残る話になったらいいな、と思っています。
2010年 夏
エッセイへもどる