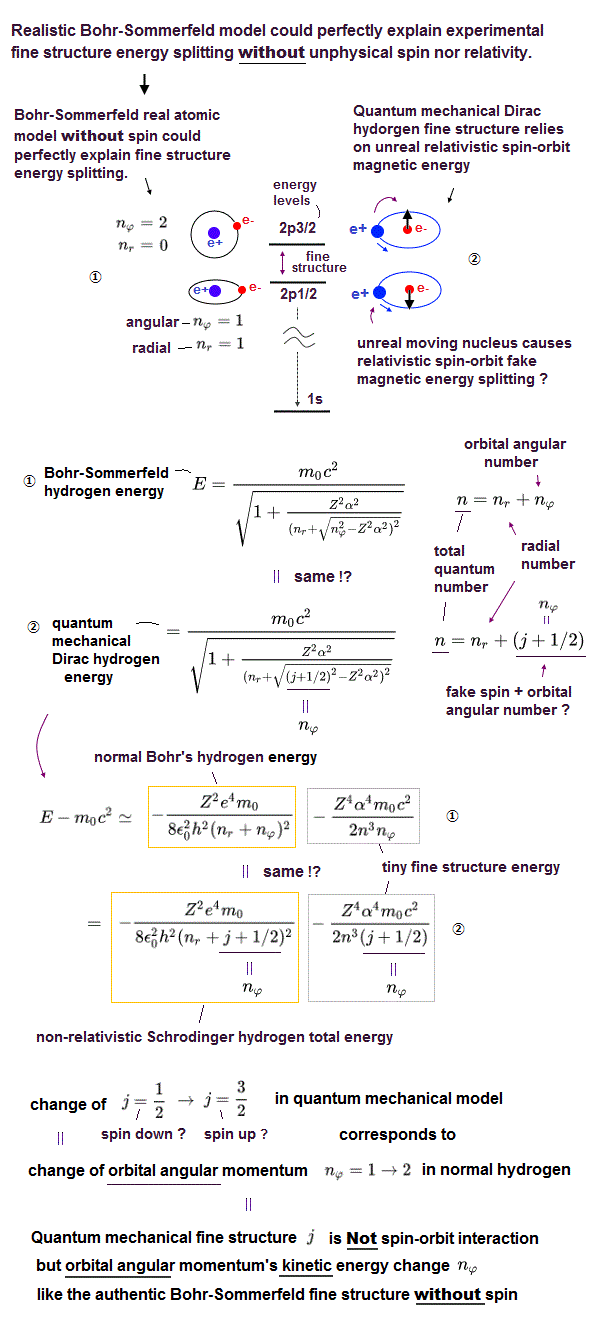
トップページ (2電子原子も含む正確な新ボーア模型)
シュレデインガー方程式は ボーア・ゾンマーフェルト模型の 一部。
微細構造=スピン軌道相互作用は 間違い。(14/8/17)
ボーア・ゾンマーフェルト模型では、軌道の長さが ド・ブロイ波長の 整数倍 である。
驚くことに、そのシュレディンガー方程式においても 軌道の長さが ド・ブロイ波長の整数倍になるのである。
シュレディンガーの水素原子は このページ に示すように ドブロイ波長の名前を変える ことによって 非常に不合理な "不確定性原理" という概念を導入した。
これが シュレディンガー方程式が ボーア・ゾンマーフェルト模型と同じエネルギー準位を与える理由である。
このページで このことを”数学的に”証明した。
(Fig.1) ディラックの水素原子=ボーア・ゾンマーフェルト模型。
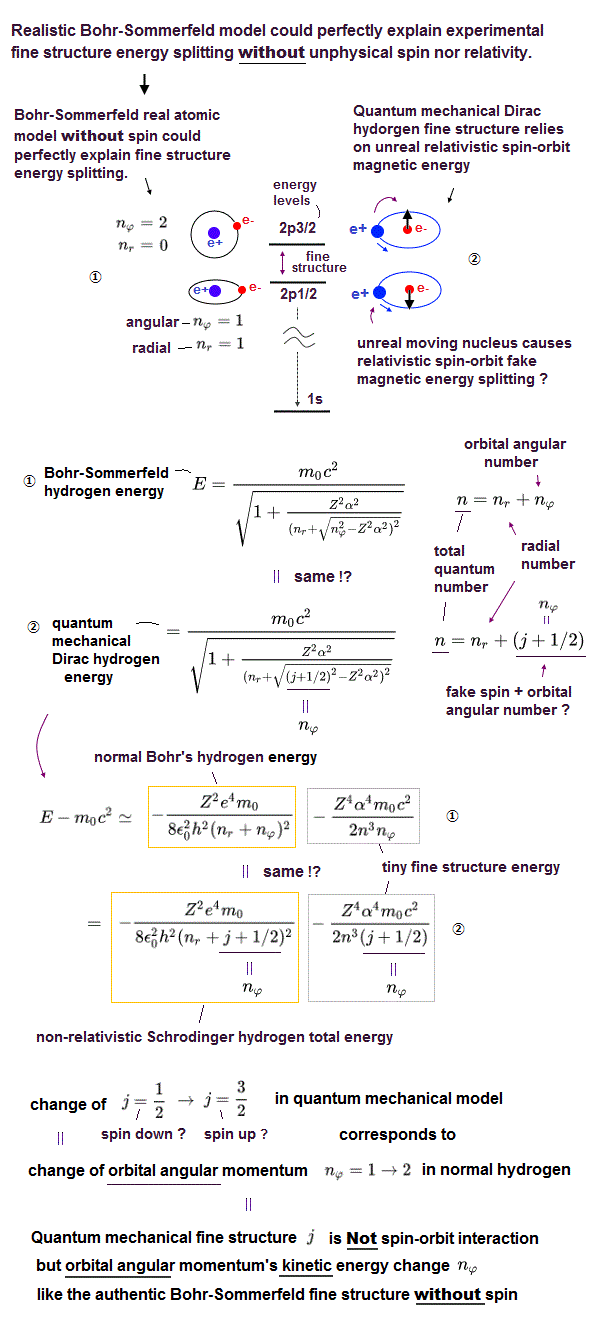
多くの教科書では、水素原子の微細構造は 2p1/2 と 2p3/2 の間のエネルギーの違いを意味しており、これは 相対論的な ディラック方程式 によって導出できると書いてある。
驚くべきことに、このページ に示したように、このディラック方程式の解は何と ”相対論的な”ボーア・ゾンマーフェルト模型の解と完全一致している。
比較のために、この詳細な計算方法を知ることが必要である。
しかし、残念なことに 多くの教科書では ボーア・ゾンマーフェルト模型についてほとんど触れられていない。
2,3の教科書、例えば ディラック著 "The Principles of Quantum Mechanics (fourth edition)" の 272ページには、"this formula gives the discrete energy-levels of the hydrogen spectrum and first obtained by Sommerfeld working with Bohr's orbit theory." と、ディラック方程式による水素原子解の導出の後に、ゾンマーフェルトと同じ解であることを触れている。
また、朝永著 「スピンはめぐる」 には、ゾンマーフェルトの微細構造の解釈が スピン軌道相互作用に変えられた経緯を詳細に述べている。
ボーア・ゾンマーフェルト理論が 歴史的には 最初に 微細構造定数 (= 1/137.036..) をだしたのである。
このことは重要である。
ところで、ボーア・ゾンマーフェルト模型においては 微細構造定数の ”物理的な”意味 はいったい何なのだろうか?
このセクションでは 実際に 相対論的なボーア・ゾンマーフェルト模型を解いてみて、微細構造定数の 本来の意味とその導出について説明することにする。
(Fig.2) 実在のド・ブロイ波 (= "エーテル" )による ゾンマーフェルト模型。

実際は、”相対論的な”ゾンマーフェルト模型は 後で説明するが、”エーテル”理論を使って自然に表すことができる。"エーテル"による説明 も参照のこと。
正確には ボーア・ゾンマーフェルト模型は 特殊相対論そのものを 用いていない。
その 古典的極限を使用している。
もし "地球のエーテル" を認めれば、致命的な 直角レバーのパラドックス を生じさせずに 相対論的な質量変化を エーテル内の最高伝達速度で説明可能である。
ボーア・ゾンマーフェルト模型と 相対論的な場の量子論との 最も大きな違いは 超光速の "タキオン" の存在である。
( Fig.A-1 ) ボーア・ゾンマーフェルト模型。

ボーア・ゾンマーフェルト模型では、ドブロイ波は もちろん 光速よりも遅いスピード "v" で進んでいく ( v < c )。
ドブロイ波長 λ は h/p に等しい。 h はプランク定数、 p は 最高伝達速度を含めた運動量である。
( Fig.A-2 ) 相対論的な場の量子論。

クライン・ゴルドンやディラック方程式などの 相対論的な場の量子論は このページに示したように、アインシュタインのエネルギー・運動量の関係式に起因している。
もちろん、相対論的な場の量子論においても、ドブロイの関係式は使用されている。
問題は それらの波動関数の振動数が 質量エネルギーのため大きすぎるということである。
この非現実的に巨大な振動数が 超光速のタキオンを生じさせてしまう。
( Fig.A-3 ) 波動関数の振動数と運動量。

Fig.A-2 の式を満たす波動関数は Fig.A-3 になる。
ご存じのとおり、波の速度は 振動数 f ×;波長 λ ( v = fλ ) で与えられる。
そのため この波動関数の速度は
( Fig.A-4 )
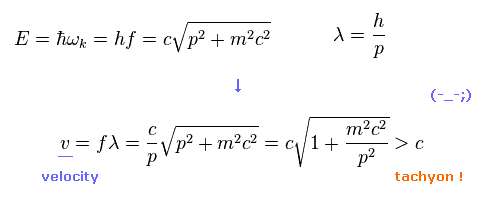
このスピードは 超光速である。
この理不尽な波動関数は 式のローレンツ変換不変性の要請から生じたものである。
皮肉にも 相対論的な制限が 想像上の粒子 "タキオン" を生じさせてしまったのである。
ディラック方程式で 正と負のエネルギー解を融合させれば、タキオンは消えると 彼らは主張しているが、電子と陽電子のそれぞれは 超光速であることに変わりはない。
( タキオン様の 仮想光子 も 相対論的なマクスウェル方程式から生じる。)
( ボーア・ゾンマーフェルト模型。 )
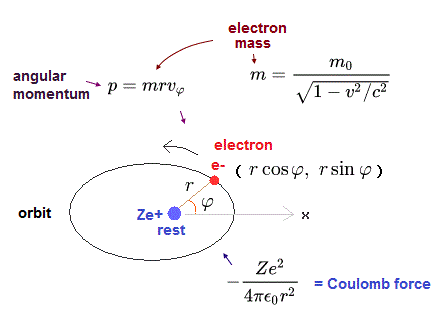
以下の説明は ゾンマーフェルトの論文 ( Annalen der Physik [4] 51, 1-167, A. 1916 ) を基にしたものである。
特殊相対論に関しては、このページ も参照のこと。
中心力をベースとした水素様原子においては、角運動量は一定である。
そのため、角運動量 (= "p" ) は次のようにあらわせる。
(Eq.1)
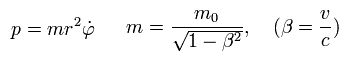
ここでは m0 は 電子の 静止質量 で、 m は 相対論的な質量 である。
もし 速度 (= v) が 光速 (=c) に等しいとき、この相対論的な質量は 無限大になる。
このページに示したように、相対論的な質量は "直角レバーのパラドックス" を引き起こしてしまう。
つまり 相対論的質量は エーテルにおける最高伝達速度に起因すると考えるのが自然である。
次のように直交座標を極座標に変換する。
(Eq.2)
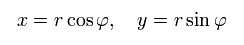
原子核が原点にあるとき、電子の運動方程式は クーロン力により 次のようになる。
(Eq.3)
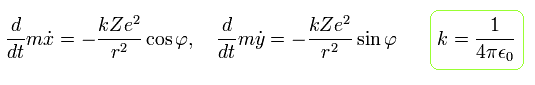
ここで Z は原子番号である。
ここではまた次のように定義してある。
(Eq.4)
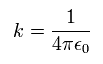
座標 r は φ の関数である。そのため t (= 時間) による微分を次のように表すことができる。(Eq.1 を使って。)
(Eq.5)
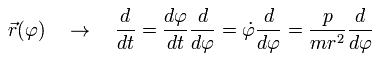
ここでは 次のように定義する。
(Eq.6)

Eq.2 と Eq.5 を使って、各運動量は次のように表せる。
(Eq.7)
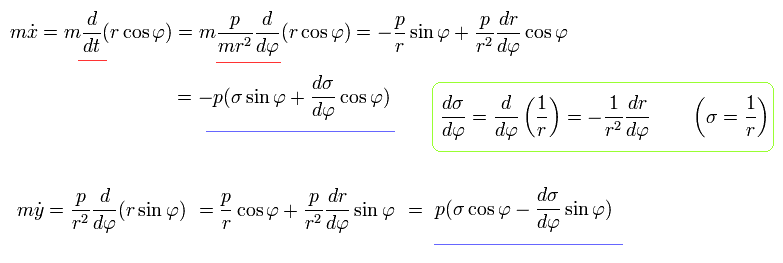
また、Eq.3, Eq.5, Eq.7 を使って、運動方程式は次のようになる。
(Eq.8)
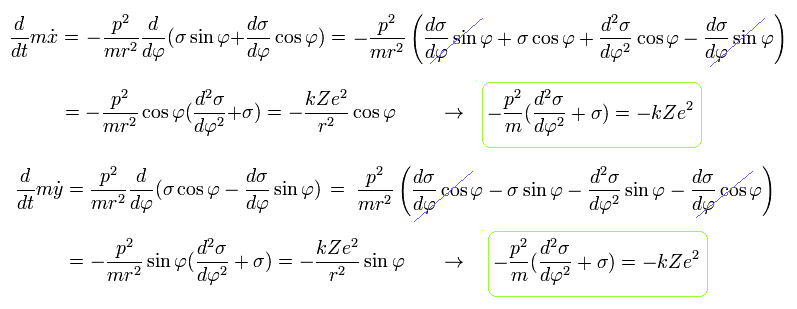
Eq.8 より、次のような 共通の 結果が得られる。
(Eq.10)
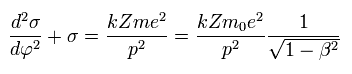
この β は 時間とともに変化しているため この β は別のものに置きかえる必要がある。
水素様原子では、ボーア・ゾンマーフェルト模型の 全エネルギー W (= T+V = 相対論的エネルギー (E) - m0c2) は 次のようになる。
(Eq.11)
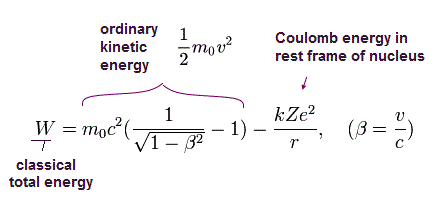
ここでは W は 運動エネルギーと位置エネルギーの和であり これは定数である。
正確に言えば、このページに示したように Eq.11 は 相対論的なエネルギーを表していない。
いわゆる 古典的極限の一種である。
また このページに示したように、相対論の E と p の2乗形は 奇妙な "仮想光子" を生じてしまう。
Eq.11 の W は それとは異なり、特殊相対論とは本質的に等価ではない。
Eq.11 からは Eq.6 の置き換えにより 次の式が得られる。
(Eq.12)
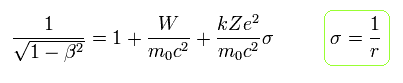
Eq.10 と Eq.12 から、
(Eq.13)
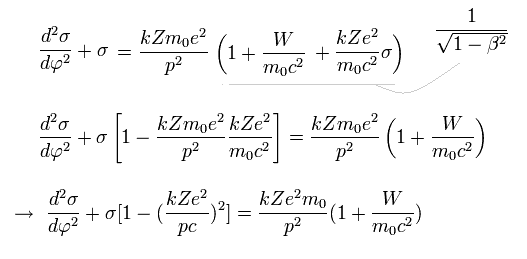
Eq.13 の σ の解は 次のように表せる。
(Eq.14)
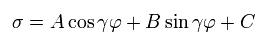
Eq.14 を Eq.13 に代入すると、 γ と C は 次のようになる。
(Eq.15)
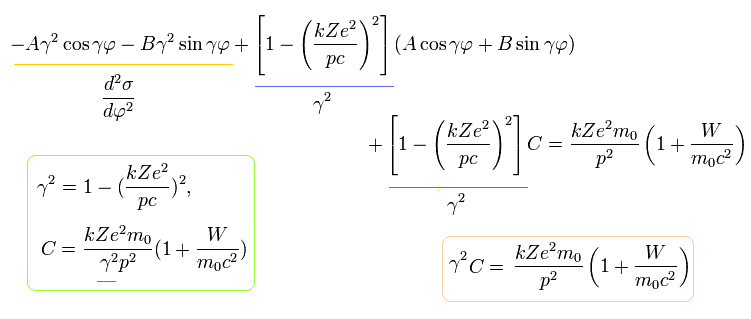
Eq.14 は r (= 1/σ) は 2π/γ ( 2π でなく) の角度 進むと 元に戻ることを示している。
そのため、”相対論的な”ボーア・ゾンマーフェルト模型の水素原子の軌道は、少し”歳差運動”していることになる。
例えば、1回転後、軌道の 近位点 は 次の角度進む。
(Eq.16)

ここで 近位点の最初の位置を φ = 0 とする。
すると、 Eq.14 の B は 次のように ゼロになる。
(Eq.17)
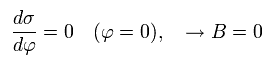
Fig.3 水素様原子の ”楕円形”の軌道。
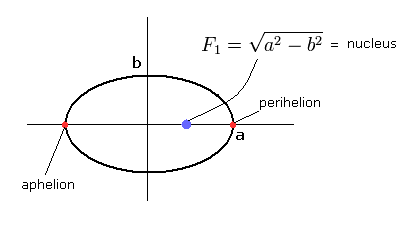
ここでは 原子核が焦点 (F1) に位置しており、離心率 (=ε) は次のように表せる。
(Eq.18)
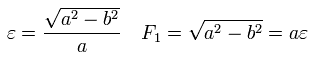
Eq.14 (B=0) と Eq.18 から、また Fig.3 の 近位点、遠位点を使って 次の関係式をだす。
(Eq.19)
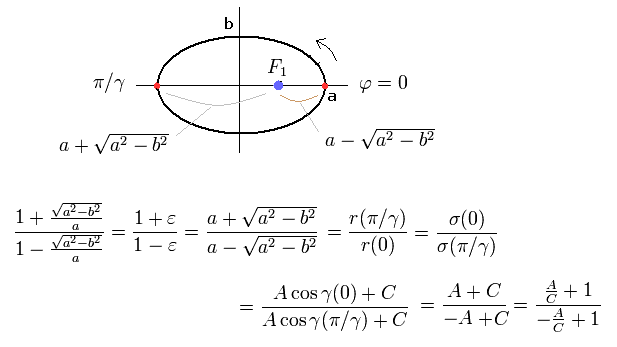
Eq.19, Eq.17 から Eq.14 における σ の A と B は 次のようになる。
(Eq.20)
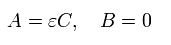
そのため r と σ は次のようにあらわせる。
(Eq.21)
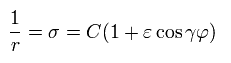
ここから、水素原子 (Z=1) を扱うことにする。
Z=1 を Eq.15 に代入して、次のように定義する。
(Eq.22)
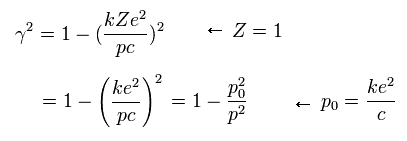
Eq.22 によれば、電子の角運動量 (p) が p0 のとき、γ は ゼロ になる。
このことは p = p0 のとき、Eq.16 の 歳差運動の速度 が 無限大 になることを意味する。
つまり ボーア・ゾンマーフェルトの水素原子では p0 は 角運動量の下限極限 ということになる。
(もちろん、この場合では "楕円"軌道は 壊れてしまう。)
p0 の ħ に対する比 ( = p0/ħ ) が いわゆる "有名な" 微細構造定数 α である。
(Eq.23)
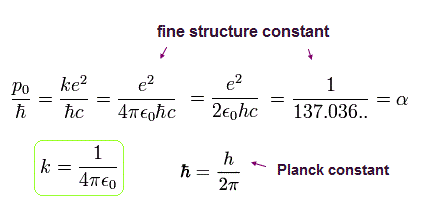
ここでは ħ ( = h/2π ) は ボーア模型における "量子化された" 最小の角運動量である。
つまり、微細構造定数 α (= 1/137) は ボーア・ゾンマーフェルト模型においては ”相対論的な”電子軌道における 歳差運動の速度 に関係しているのである。
------------------------------------
実は、この微細構造定数 α (= 1/137) は別のシンプルな方法でもだすことができる。( このページも参照のこと。 )
普通のボーア模型の水素原子の満たす式を解く。(遠心力とクーロン力が等しく、また軌道長がド・ブロイ波長の1倍 (n=1)のとき。)
すると、この n=1 のボーア軌道の電子の速度 (v) は 次のようになる。
ボーア模型の水素原子における n=1 軌道の 電子の速度 (=v)。
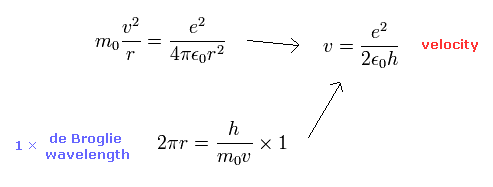
この電子の速度の 光速 (c) に対する比が 微細構造定数 α になる。
( 別の方法による微細構造定数の導出 = Eq.23. )
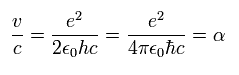
----------------------------------
Eq.21 より、φ がゼロのとき、 σ、v、β は次のようになる。
(Eq.24)
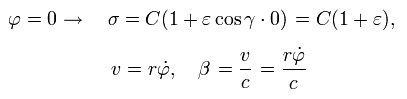
近日点では 速度は 接線方向である。
つまり、φ = 0 のとき、Eq.1, Eq.24, Eq.15 (Z=1) を使って 次の関係式が得られる。
(Eq.25)
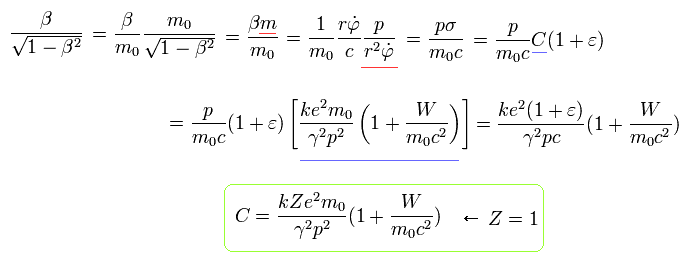
同様に、Eq.12, Eq.24, Eq.15 (Z=1) から、次の式が得られる。
(Eq.26)
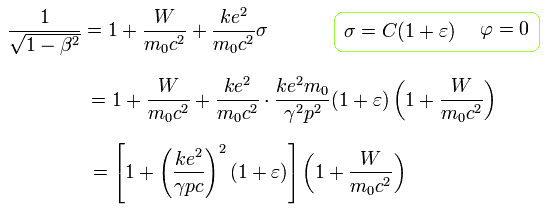
Eq.22 から、次の関係式を得る。
(Eq.27)
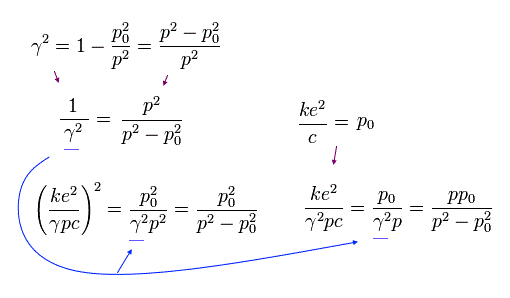
Eq.25, Eq.26, Eq.27 より、次のように β を消す。
(Eq.28)
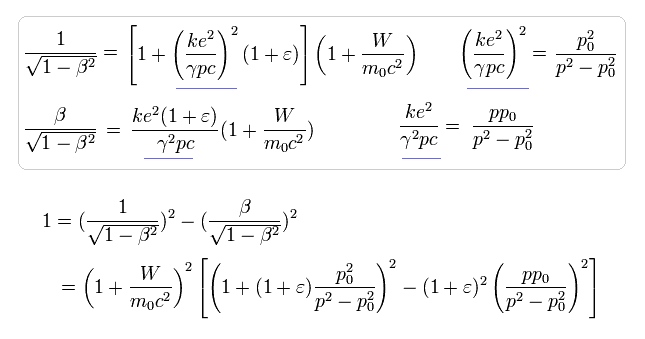
Eq.28 は 次に等しい。
(Eq.29)
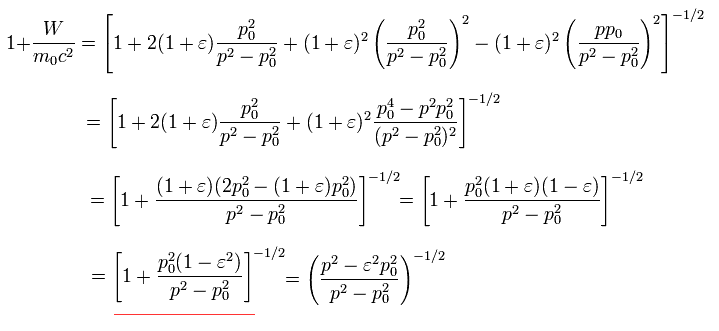
ボーア・ゾンマーフェルトの量子化条件では 次の関係式を用いる。
(Eq.32)
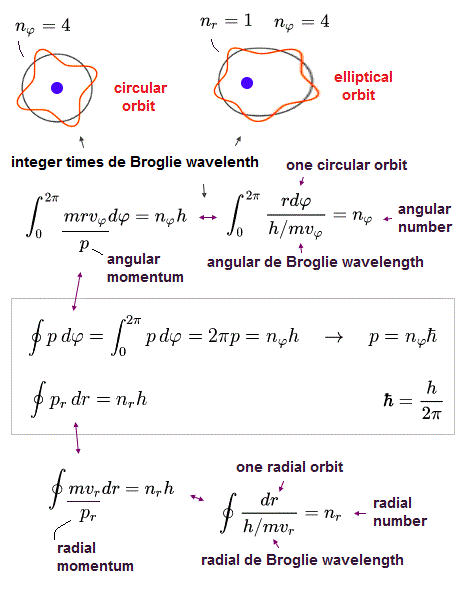
ここでは 角運動量 p は定数である。
そのため、 p は ħ の整数倍になる。
Eq.1 を用ると、 動径方向の運動量 pr は次のように表せる。
(Eq.33)
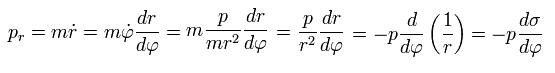
Eq.33、Eq.21 を用いて、Eq.32 の pr を 次のように積分する。
(Eq.34)
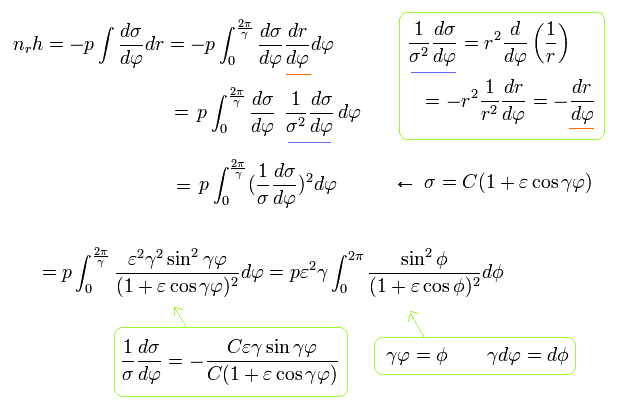
ここで 元の積分範囲は 歳差運動のため、0 から 2π/γ になる。
Eq.34 の最後の項では 次の置き換えを用いている。
(Eq.35)

このページの Eq.39 - Eq.48 に示したように、部分積分と 次の複素積分を使用する。
(Eq.39')
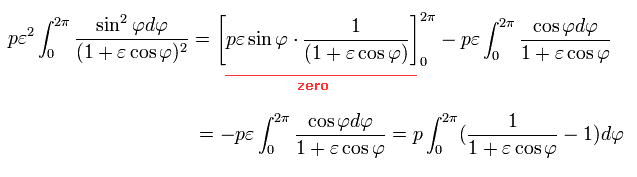
次の公式(複素積分)を用いる。
(Eq.40')
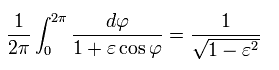
よって Eq.34 の結果は、Eq.22 の γ の置き換えを使って、
(Eq.36)
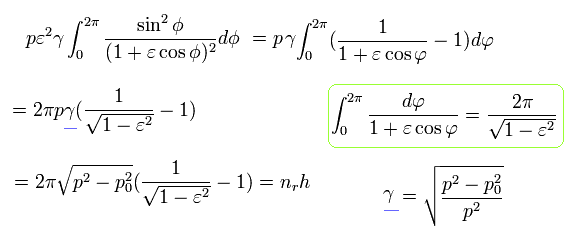
Eq.32 と Eq.22 を用いて、
(Eq.37)
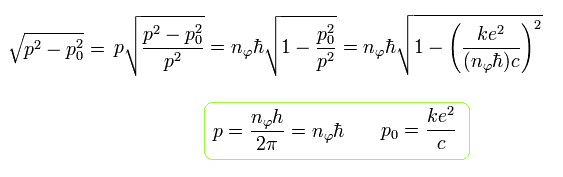
Eq.36 は Eq.37 を用いて、次の式に変わる。
(Eq.38)
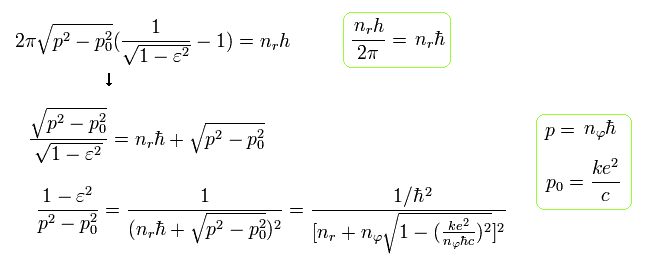
Eq.38 を Eq.29 の 赤線の項に代入して、Eq.23 の微細構造定数 α を用いると、
(Eq.39)
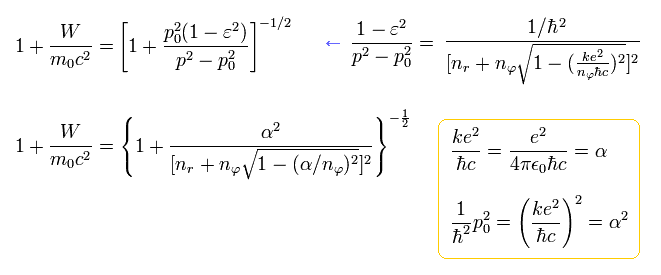
Eq.39 より、相対論的エネルギー ( E = W + m0c2 ) は、Z を付加して、
(Eq.40)
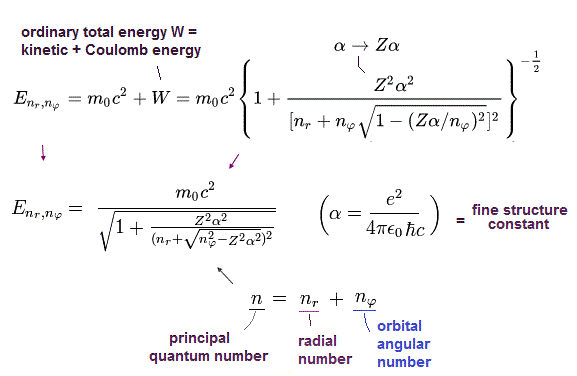
Eq.40 の ボーア・ゾンマーフェルトの解は Eq.41 の ディラック と 同じになる。
ディラック方程式の 計算の詳細については このページを参照のこと。
(Eq.41)
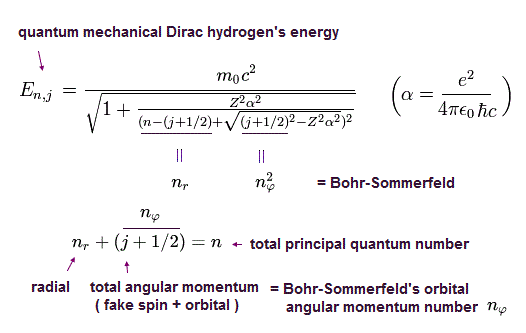
これはつまり Eq.41 のエネルギー準位は 次のように Eq.40 のと まったく等しくなる。
2p1/2 (n=2, j=1/2) -------- 2s (nr=1, nφ=1)
2p3/2 (n=2, j=3/2) -------- 2p (nr=0, nφ=2)
これは 驚くべき 偶然の一致である。
-------------------------------------------------------------------------------
これらの事実に基づくと、 Fig.2 の式を 粒子の運動量として使用できる。
この場合は、微小時間 dt の間に 粒子を加速させるのに必要なエネルギー (= dT ) は、
(Eq.42)
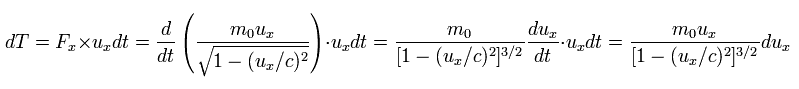
ここで ux は x 方向の速度、 Fx は 力である。
ここで 次を使った。
(Eq.43)

つまり、粒子を 速度 v まで加速するのに必要な 全運動エネルギーは、
(Eq.44)
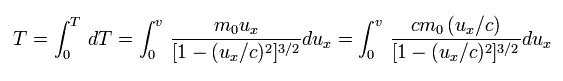
ここで 次の置き換えを使う。
(Eq.45)
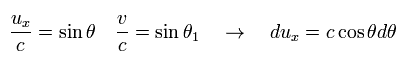
Eq.44 は、
(Eq.46)
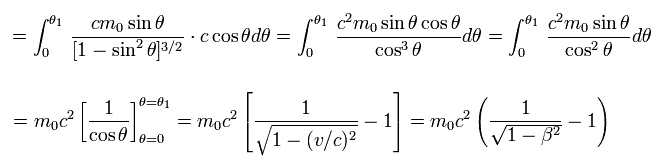
この運動エネルギーは 完全に Eq.11 の最初の項に等しい。
ボーア・ゾンマーフェルト模型は 1次のエネルギー項を使用しており、もとの相対論 (= 2次の項もしくは ディラックのガンマ行列 ) とは異なる。
また もちろん、この模型は "時間の遅れ" のような奇妙な概念は使用していない。
この理論では、電子のスピード v が c に近づくにつれて 加速しにくくなる 運動量 (= p ) として 次を用いている。
( なぜなら ある媒質 (= エーテル) において その最高伝達速度が存在すると考えるのが自然だからである。 )
(Eq.47)
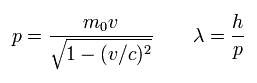
ここで λ は ドブロイ波長である。
Eq.42 と Eq..43 に示すように、 電場が 電子の進行方向 (= ux ) へ 電子を加速するのに 必要な力 Fx は、
(Eq.48)
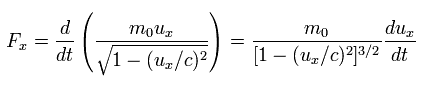
電場が この電子 ( uy = 0 ) を y 方向へ加速するのに必要な力 Fy は、
(Eq.49)
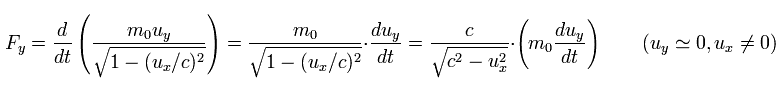
Eq.48 と Eq.49 に示すように、電場が 電子を 移動方向 (= x ) へ加速させるほうが y 方向へ加速させるよりも 力が必要である。
なぜなら 速度 ux がゼロでないため x 方向へ 場が凝集しているため 抵抗が強くなるからである。
( この場合では 速度 uy はゼロであるため、y 方向へは 場は凝集していない。)
つまり Eq.49 のほうが 場の凝集の効果を考える必要がなく 状況をイメージしやすい。
(Fig.4) 電子は x 方向へ動いている。 この電子を y 方向へ加速させる。
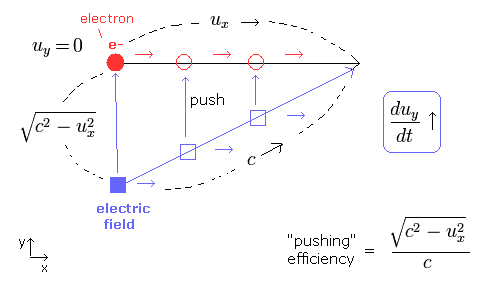
Fig.4 では、 電場は 電子を y 方向へ加速させようとしている。
これをするには、電場が 電子と同じ速度で x 方向へ進みながら 電子を y 方向へ押す (push) ことになる。
電場のスピードは c であるため、"押す" 効率 (= "pushing" efficiency ) は Fig.4 に示すようになる。
( 電子の速度 ux がゼロのとき、 この 押す効率は c/c = "1" となる。)
結果として、Eq.49 の重くなる電子の質量効果を説明することができた。
この効果を一般化すれば、Eq.47 の運動量が得られる。
重要な点は ボーア・ゾンマーフェルト模型は 1次のエネルギー項を用いており、W = 運動エネルギー+位置エネルギー を "定数" として扱っていることである。 ( Eq.25 も参照のこと。)
実は、特殊相対論の 2次のエネルギーの式は 各粒子のエネルギーや運動量の 足し算、引き算が正常に行えないのである。
( このページ の "相対論的な QED が 特殊相対論と矛盾する??" を参照のこと。)
そのため、相対論では "仮想粒子"のような 奇妙な概念を導入せざるを得なかった。
------------------------------------------------------------------------------
ここで次のような置き換えをする。
(Eq.50)
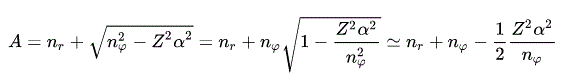
Eq.50 を Eq.39 に代入して、Eq.39 のテイラー展開は次のようになる。
(Eq.51)
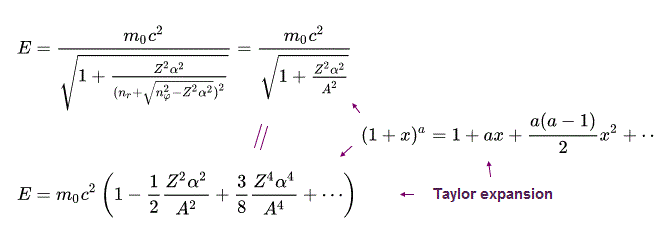
つまり、全エネルギー W は 次のようになる。
(Eq.52)
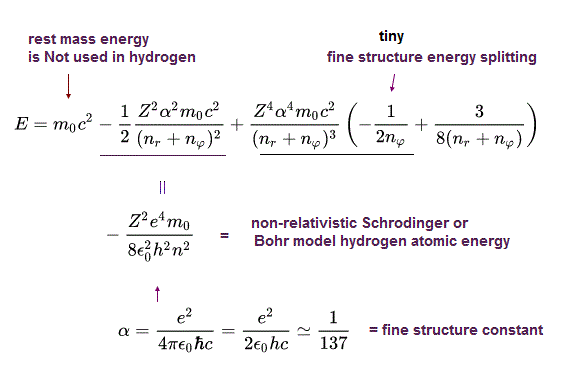
微細構造定数 α は 小さい。
そのため、Eq.50 の A を nr+nφ と仮定すると、Eq.52 の最初の項は 非相対論的なボーア・ゾンマーフェルト模型(もしくは シュレディンガー方程式)の解とちょうど同じになる。
(このページ も参照のこと。)
(Eq.53)
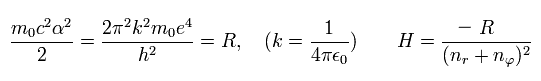
Eq.50 と 微細構造定数 α を使って、1/A2 は次のように表せる。
(Eq.54)
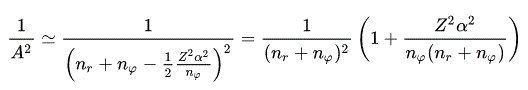
α は小さいので、近似的に 1/A4 を次のようにする。
(Eq.55)
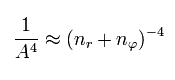
Eq.53, Eq.54, Eq.55 を使って、Eq.52 の W は次のように表せる。(α4 の近似で。)
(Eq.56)
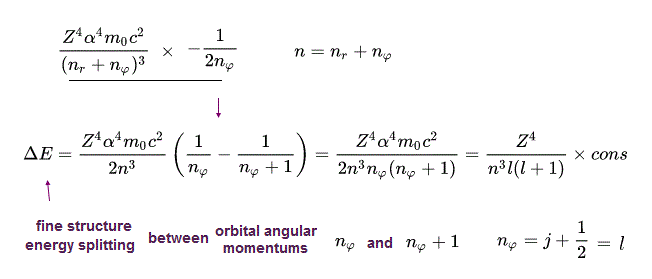
例えば、Eq.57 を Eq.56 に代入すると、(Eq.23, Eq.53 も使って) ボーア・ゾンマーフェルト模型の 2s と 2p のエネルギーの違い は Eq.58 のようになる。
(Eq.57)
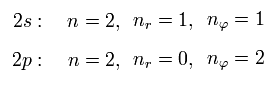
(Eq.58)
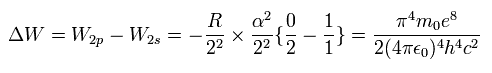
ゾンマーフェルト理論によれば、エネルギー準位 n の中の 角運動量量子数が k と k-1 である軌道のエネルギー準位の違いは Eq.59 のようになる。
(朝永著 「スピンはめぐる。」 も参照のこと。)
(Eq.59)
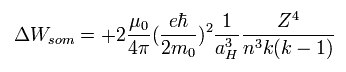
もし、2s と 2p の間のエネルギーの差を知りたいときは、Eq.59 に n=2 と k=2 を代入する。
(2s -- n=2, (k-1)=1, 2p -- n=2, k=2)
ここで aH は ボーア半径 で、μ0 は 真空の透磁率 である。
そのため、それらは次の関係式であらわせる。
(Eq.60)
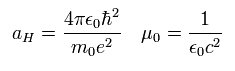
Eq.59 は H, He+, Li++, Be+++ などの 様々な原子の微細構造の実験値に よく一致することが分かっている。
ここで、Eq.59 を計算する。( Z=1, n=2, k=2 代入して。)
(Eq.61)
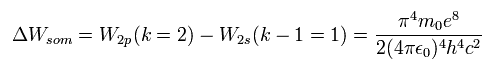
Eq.61 は Eq.58 に ちょうど等しくなる。
これは、Eq.59 と Eq.56 は同じ式であることを意味する。
このページに示したように、スピンする電子の角運動量を 1/2 ħ にするには、電子球面の速度が 何と 光速の 100倍 以上に ならなければならない。
そのため、1920 年代に パウリは 電子スピンの存在に対して とても強く反対した。
当時は、ゾンマーフェルトの Eq.59 の式が 様々な原子の実験値に合致することが知られていた。
(Eq.59)
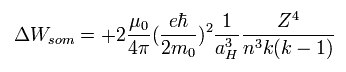
電子スピンの存在を証明するには、相対論的な質量変化によってではなく、スピン・軌道相互作用 によって Eq.59 の式に到達する必要があった。
ここで 電子が +Ze の原子核の周囲を周回していると仮定する。
すると、動いている電子の視点からすれば かわりに 原子核が電子の周囲を周回していることになる。
原子核の速度は -v、また 原子核の座標は -r である。
そのため、ビオ・サバールの法則によれば、電子の地点に生じる 磁場 (B) は次のようになる。
(Eq.62)
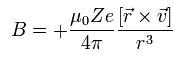
ここで 角運動量量子数 K (K = 1, 2, 3 ....) を導入する。
この K は K ħ = m0r × v の関係式を満たす。
そのため Eq.62 は 次のように表せる。
(Eq.63)
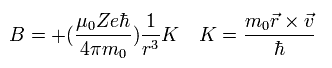
スピンする電子の 磁気モーメント は g因子 (ge) × s (=1/2) × ボーア磁子 である。
そのため スピンする電子と 磁場 (B) との間の 相互作用エネルギー は次のようになる。
(Eq.64)
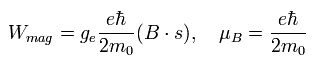
ここで μB は ボーア磁子, s はスピン角運動量 (=1/2) である。
Eq.63 の B を Eq.64 に代入する。
(Eq.65)
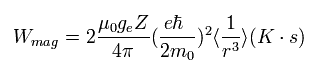
Eq.65 の spin up (+1/2) と spin down (-1/2) の間の エネルギー準位の差 は次のようになる。
(+1/2 - (-1/2) = 1)
(Eq.66)
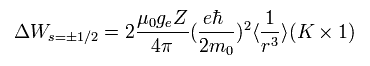
ボーアの理論によれば、1/r3 の平均値は 次の関係式を満たす。
(Eq.67)
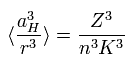
ここで aH は ボーア半径、 n は エネルギー準位を表す。
Eq.67 を Eq.66 に代入する。
(Eq.68)
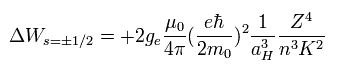
ここで Eq.68 の K2 を k(k-1) に変換すると、実験値に よく合うことが知られていた。
(Eq.69)
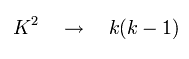
Eq.69 を Eq.68 に代入する。
(Eq.70)
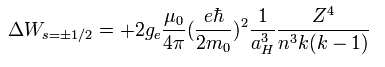
ここで スピンg因子 (ge) が 1 だとすると、Eq.70 は Eq.59 (= ゾンマーフェルト模型) に ちょうど一致する。
しかし、もし ge が 1 だとすると、電子の磁気モーメント は 1/2 × 1 = 1/2 × ボーア磁子 になってしまう。
つまり、Eq.70 は間違っていることになる。 なぜなら 電子の磁気モーメント (磁気能率) は 1 × ボーア磁子 にならなければならないからである。
この問題を解決するために トーマス (L.H. Thomas) が登場した。
彼は、トーマス因子 1/2 を使うことにより、電子スピンの正当化に成功した。
(しかし、トーマスの方法は 少々複雑で、不自然なものと言わざるをえないが。)
次に この因子について説明することにする。
このページ に示したように 磁場 (B) のもとでの スピンする電子の 歳差運動の角振動数は 次のようになる。
(Eq.71)
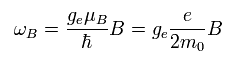
ボーアの 対応原理 によれば、ħω = | W1 - W2 | である。
ここで Eq.71 に ħ をかける。
(Eq.72)
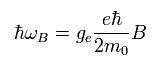
Eq.64 に示したように 磁場 (B) のもとでの 相互作用エネルギーは、
(Eq.64)
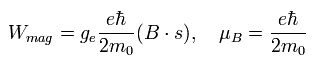
であり、磁場のもとでの 2つのスピン状態 s = ± 1/2 の間のエネルギー差は、
(Eq.73)
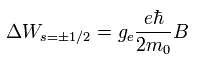
である。Eq.73 は Eq.72 と等しくなる。
トーマスは、電子が"加速度運動" しているとき、電子の"固有の"座標系 は 実験室系に対して 回転していることに気づいた。
彼の計算結果によれば、この座標系の回転角振動数は次のようになる。
(Eq.74)
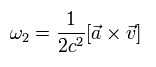
ここで、a は 電子の 加速度 である。
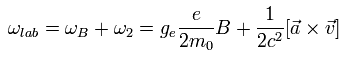
電子の加速度は 次のような +Ze の原子核のクーロン力によって生じる。
(Eq.76)
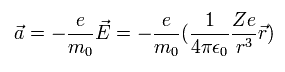
ここでは Eq.62 と Eq.60 の μ0 を使う。
(Eq.62)
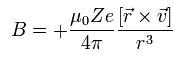
Eq.76, Eq.62, Eq.60 から、Eq.75 の全角振動数は次のようにあらわせる。
(Eq.77)
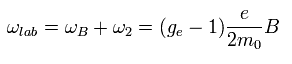
Eq.77 を使うと、Eq.64 の 磁場のもとでの 相互作用エネルギーは 次のように変化する。
(Eq.78)
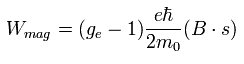
また、Eq.70 は 次のように変化する。
(Eq.79)
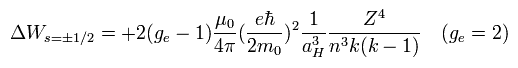
ge が 2 のとき、Eq.79 は ボーア・ゾンマーフェルト模型の Eq.59 とちょうど等しくなった!
Eq.79 = 1/2 × Eq.64.
そのため、この 1/2 を "トーマスの歳差因子" と呼ぶ。
これによって ようやく パウリは トーマスのスピン模型を "しぶしぶ" 受け入れることとなった。
(ようやく、トーマスは 電子スピンに関して パウリの御裁可を得ることができたのだ。)
ところで、トーマスのスピン・軌道相互作用モデルと ボーア・ゾンマーフェルトモデル、はたしてどっちが より自然な微細構造 だと みなさんは思われたことだろうか?
もし、微細構造が スピン・軌道相互作用によって生じるとしたら、このモデルは 相対性 と スピン・軌道相互作用 の ”たくさんの不自然な偶然の一致”を 含まなければならない。 ( 2S1/2=2P1/2, 3S1/2=3P1/2, 3P3/2=3D3/2.........).
また Eq.69 の置き換え ( K2 → k(k-1) ) は Eq.59 のボーア・ゾンマーフェルト模型においては "自然に" 得ることができた。
しかし、スピン・軌道 相互作用模型 においては、Eq.69 の置き換えは 量子力学的な l (l+1) という "数学的技巧" に頼らなければならない。
また、Eq.72 のボーアの対応原理の利用も奇妙である。
1975 年の スピンの2価性の実験によれば、フェルミ粒子は 1回転で元に戻れない。(2回転で元に戻る。)
そのため、電子スピンに関しては、4π の角度を 1 振動とみなすべきである。
こうすると、Eq.72 の角振動数は 半分 になることになる。
しかし、Eq.72 が半分になると、せっかくの トーマス因子 1/2 が 無意味 になってしまう。
つまり、この模型は自己矛盾を含んでいることになる。
結論として、スピン・軌道相互作用模型は、ボーア・ゾンマーフェルト模型に比べて、非常に無理強いした 不自然な模型と言わざるを得ない。
最近では、1つの電子をトラップできる ペニング・トラップ (Penning trap) を用いて [3]、異常磁気能率の測定が行われた。
(Fig.5) ペニング・トラップによる異常磁気能率の測定。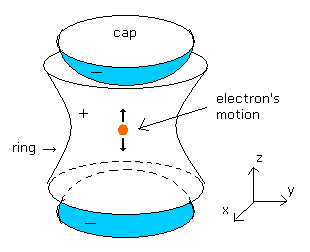
Fig.5 に示すように、ペニング・トラップは 上下の部分に 負電荷に帯電した キャップ (cap) がついている。
また、側面周囲には 正電荷に帯電した リング (ring) がついている。
中心を原点とすると、ペニング・トラップの 電位 は次のようになる。
(Eq.80)
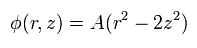
つまり、電子は次の力によって、z方向に 原点のほうへ引き戻されている。
(Eq.81)
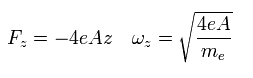
ここで ωz は z方向の角振動数である。
また、電子は 正電荷のリングに外側方向へひきつけられる。
そこで、z方向に 磁場 (B0) をかける。
すると、x-y 平面上の 電子の運動方程式は 次のようになる。
(Eq.82)
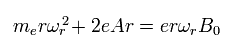
Eq.82 は 遠心力とローレンツ力を含んでいる。
さらに 次のような 小さな磁場をかける。
(Eq.83)
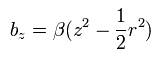
Eq.83 の磁場勾配のため、電子の磁気モーメントは次の力を受ける。
(Eq.84)
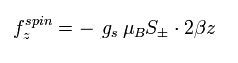
ここで μB は ボーア磁子で、S はスピン角運動量 (± 1/2)、gs は スピンg因子である。
(Eq.85) ボーア磁子。
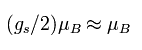
ペニング・トラップでは、Fig.6 に示すような 様々な運動が混在している。
そのため、電子の運動は とても複雑になっている。
もちろん、電子はとても軽いため、熱雑音の影響もとても大きい。
(Fig.6) ペニング・トラップにおける 軸方向運動、磁場運動、サイクロトロン運動。
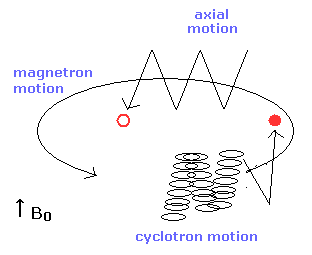
様々な量子数のサイクロトロン運動に及ぼす 磁気的な力は 次のようになる。
(Eq.86)
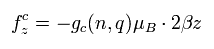
結果的に、z方向の全角振動数は次のようになる。
(Eq.87)
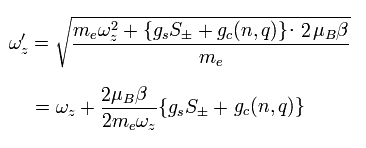
さらに、ここに 弱い振動電位 ( V =K sin ω t ) をかける。
この ω が Eq.87 に等しいとき、それは "共鳴"を起こす。
また この ω は測定できる。
電子のスピンは ランダムに 上下に変化 (flip) している。
(もちろん、様々なサイクロトロン運動もランダムに変化している。)
彼らは、Eq.87 の ± S の間の 角振動数の差 と思われるものをその中から 選びだし、 測定する。
そして、スピンg因子の値を得ることができる [4]。
しかし、Eq.88 に示したように、最小の (= ħ) 軌道運動 によって生じる 磁気モーメントも スピン磁気モーメントと同じである。
(Eq.88)
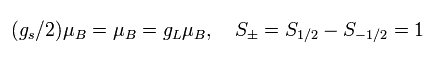
つまり、”奇妙な”スピンのかわりに、最小の軌道運動を用いると、g因子は 半分になる。
(”解釈”だけが変わるだけである。)
( References )
[1] W.H.Louisell, R.W.Pidd, An Experiment of the Gyomagnetic Ratio of the Free Electron, Phys.Rev.94 (1954) 7-16.
[2] D.T.Wilkinson, H.R.Crane, Precision Measurement of the g Factor of the Free Electron, Phys.Rev.130 (1963) 852-863.
[3] Dehmelt, Experiment with an Individual Atomic Particle at Rest in Free Space, Am.J.Phys.58 (1990) 17-27.
[4] H.Dehmelt, New Continuous Stern-Gerlach Effect and a Hint of the Elementary Particle, Z.Phys.D10 (1988) 127-134.
[5] V.Gerginov, K.Calkins, et.al. Phys.Rev. A 73 (2006) 032504.
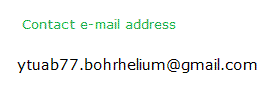
2011/2/4 updated This site is link free.