
ブルー・ギャラクシー 天使編 前編

神は、人間の発明品だ。
人生の絶望や死の恐怖を紛らすための、原始的な麻薬にすぎない。
ぼくたちバイオロイドには、そんな救いなど必要ない。なぜなら、ぼくらの神は、眼前にいる人間たちだから。
たった一つの惑星から出発し、今では、この銀河全体を手に入れようとしている種族。
――ぼくたちは人間に製造され、人間に知識を植え込まれ、人間のために働き、やがては抹殺される。
生きられる上限は、たったの五年。
それ以上長生きさせると、知恵がついて、反逆を企むようになるから。
ぼくは死にたくなかった。生まれた研究基地から、外に出たこともないままでは。もっと広い世界に出て、色々な経験をしたかった。基地の外には、無限の宇宙が広がっているはず。
だから、神に逆らった。
それでも、死は追いかけてきた。
だから、もう一度……今度は、魔女と契約した。永遠の生命を約束してくれる、冷徹な魔女と。
その代償として、ぼくは何かを失ったのだろうか。
決定的に、変質したのだろうか。
愛ならば、まだ持っている。美しいもの、気高いものに対する感動だ。その愛が、愛する相手に理解されないとしても。
今は、これでいいと思っている。魔女の陣営で。
もしも先で、自分が更に変質するとしても……
それは、仕方のないことだろう。人類そのものが、次の段階へ進むはずなのだから。

ミカエルは、知らなかったのだ。周りの人間たちが、彼を救おうと、密かに動いていたことを。
彼と仲間たちを苦しめた病気は、悪性の脳腫瘍だった。
高い知能と引き換えの遺伝的欠陥だから、対策は遺伝子治療しかない。辺境の科学技術なら、問題なく治療できる。
問題は、保守的な市民社会では、延命のための遺伝子操作が認められないこと。
古い道徳に縛られた市民たちは、人間そのものを変えてしまうような科学技術を拒んでいる。
でも、せっかく違法組織から脱出してきたのに、十年も経たずに死ななければならないとは、残酷すぎる。
人工遺伝子から培養されるバイオロイドは、普通、二百年やそこらは健康に生きられるのだから。
ミカエルたち「亡命バイオロイド」の担当だった司法局員が、繰り返し、上司や友人に訴えた。
その訴えが、最後には、ミギワ・クローデル局長に届いた。
彼女は下っ端捜査官の頃から、あたしと探春の友人だから、非公式に話してくれたのだ。
「わたしももう、引退が視野に入ってきたわ。だから、多少は自由にやらせてもらっていいと思うの。誰かの死亡を偽装する小細工とかね……」
本当はミギワだって、辺境に出て、不老処置を受けることができる。彼女なら、幹部として迎えたいという違法組織が幾つもあるだろう。
けれど、司法局のトップを務めた者までがそれをしたら、市民社会は崩壊すると、彼女は言い張っている。だから自分は、法に従い、おとなしく老衰死を受け入れるつもりだと。
あまりにも、勿体なさすぎる。
ミギワこそ、生きる値打ちのある人材だ。
そんなことで崩壊する社会なら、いっそ、崩壊した方がいいのではないか!?
数十年の司法局勤務の間、ミギワは相応に老けたが、強化体として生まれたあたしはまだ、若い肉体のままだ。今後も、老いるつもりなどない。新しい技術を取り入れて、生きられるだけ生きてやる。
悪党狩りのハンター稼業には、いずれ見切りをつけるかもしれないけれど。
そんなわけであたしは、バカンスのついでに植民惑星《エリュシオン》を訪ね、ミカエルという少年に会うことにした。
違法組織《ルーガル》からの三人の逃亡者のうち、最後の生き残りだという。
彼を辺境の宇宙に連れ出してやり、遺伝子治療を受けさせてやろう。
あたしとしては、〝正義の味方〟の義務のつもりだった。自力で違法組織から脱出してきた子なら、健康体になりさえすれば、辺境でも生きていけるだろう。
たとえば、あたしの故郷である違法都市《ティルス》の一族に預けたっていい。都市経営の一翼を担う従兄弟のシレールは、
『またか』
と渋い顔をするだろうけれど。
シレールはこれまでも、あたしが押し付けた大勢のバイオロイドを引き取り、再教育を施し、都市の経営機構の中に組み入れてくれた。小惑星工場とか、小惑星農場とか、人間を恐れる彼らが静かに暮らせる場所に。
あたしが必要とする武器や艦隊も、あらかたはシレールを通じて、一族の工場から手に入れてきた。それもこれも、一族の最長老である麗香姉さまが、一族みんなに言ってくれているからだ。
「紅泉のしていることは、世界のために必要なことよ。みんな、助けてあげてちょうだいね」
感謝している。一族の後援には。それがなかったら、何十年も戦い続けてこられなかった。
予想していなかったのは、あたしとミカエルが、互いに恋に落ちることだった。
事故と同じで、それは、避けようもなく起こってしまったのだ。
結局、それは『仕組まれた事故』だったのかもしれないけれど。

桜が咲いた。
咲いてしまった。
このまま永遠に、冬が続けばいいと思っていたのに。
いつの間にか、寒さがゆるみ、木々の新芽がふくらんでいる。道を行く人々の服装も、軽くなっている。
晴れた朝、丘の上にある宿舎のバルコニーから見ると、水気を含んだ青空の下、首都全体がピンクの霞に包まれていた。
これはもう、桜見物に行くしかない。仕事のない週末、それが一番有意義な過ごし方に決まっている。
ぼくは朝食を済ませると、科学技術局の敷地から出て、市街へ続く坂道を下っていった。車に乗ってしまったら、この春の日を味わいきれない。一日たりとも、無駄に過ごしていい日などないのだ。
こうしている今も、悪性の脳腫瘍が少しずつ、ぼくの命を蝕んでいる。やがては知能が低下し、意識が混乱し、最後には、自分が何者かも忘れてしまうのだ。
残り時間で何をしたら、
『有意義な人生だった』
ということになるのだろう?
誰にでもできる基礎研究など、気休めにもならない。さりとて、高度な研究を成し遂げるには、時間が足りない。ぼくに十年の時間があれば、きっと何かの業績を上げられると思うのに。
周りの研究員たちも、〝特別職員〟として押し付けられた亡命バイオロイドの存在に困惑し、礼儀正しく遠巻きに眺めるだけだった。共に脱走してきたウリエルとガブリエルが生きている頃、何度かは、普通の職員たちの家や、レストランでのパーティに招かれ、それなりに楽しい時間を過ごしたけれど、やがては、互いに気を遣う会話に疲れてしまう。
未来のある者が、ない者を、どう慰められるというのか。
ぼくたちには、結婚や子育てという救いもない。そんなことができる年齢まで、生きられないとわかっているのだから。
桜並木の下を歩きながら、大勢の市民とすれ違った。小さい子を肩車した夫婦連れ、お互いしか見ていない恋人同士、賑やかな若者グループ、共白髪の睦まじい老夫婦。
ぼくのことなど、誰も気に留めない。
傍目には、ただの少年だから。
しかし、実際には〝市民社会の厄介者〟であり、外出時には常に、司法局員たちが車で追尾してくる。偵察鳥や昆虫ロボットの、ゆるい監視網にも包まれている。
護衛、もしくは見張り。
警備チームの存在は気にせず、好きに出歩いていいというのは、当局の好意だとわかっている。狙撃の前例がある以上、ぼくが警備厳重な科学技術局の敷地内に留まっている方が、司法局としては楽なのだから。
市民社会の人間たちは、基本的に善良だった。彼らは、遠い宇宙で違法組織に製造されるバイオロイドを哀れみ、奴隷たちが運良く主人の元から逃げおおせた場合には、親切に保護してくれる。
ただ、軍艦を連ねて辺境の宇宙まで出向き、繁栄を誇る違法組織を根絶しよう、などという覇気を持たないだけ。
市民社会は、辺境の無法を『見ないふり』できるのだ。年間、どれほどのバイオロイドが抹殺されていようとも。
「――何だと、もう一遍言ってみろ!!」
橋の上から見下ろした川原で、わっと騒ぎが起きた。
両岸の桜並木の下を歩いていた人々も、土手や川原でピクニックしていた人々も、何事かと伸び上がって注視する。
「そっちこそ、突っ張ってるんじゃねえぞ!!」
「反則ぎりぎりの手で勝って、そんなに自慢かよ!?」
どうやら、ライバル校のスポーツ部員たちが鉢合わせしたらしい。空手部だかラグビー部だか知らないが、屈強な青年たちが三十人近く、二つの陣営に分かれて怒鳴り合っている。
殴り合いをして、骨折でもすれば、いい気味だ。
ぼくが吸血鬼なら、彼らの生命力を吸い取らせてもらうのに。
明日も生きられると思っているから、くだらない喧嘩などで、時間を無駄遣いできるのだ。
「やめて、落ち着いて。警察を呼ばれてしまうわよ」
「また、次の試合で雪辱すればいいじゃないの」
どちらのグループでも、連れの娘たちが青年たちの腕を引いているが、そのために余計、彼らは引っ込みがつかないようだった。
『女の前で格好をつける』
のは、動物的な習性としか思えない。〝激烈な性欲〟とやらに振り回される日々は、さぞかし面倒なことだろう。その渦中にあれば、それが楽しいのかもしれないが。
周囲の花見客たちも、力が余っているならやらせておけ、という傍観姿勢になっている。現代の医学なら、骨折や内臓破裂はすぐ治るからだ。
「やるか!!」
「おう!!」
と青年たちが上着を脱ぎ捨てたり、袖をまくり上げたりしたところで、すいと割り込んだ人影があった。
「まあまあまあ、坊やたち」
その声の何かが、ぼくをはっとさせた。豊かで楽しげなアルト。草食獣の群れに分け入った肉食獣のような、絶対の自信。
それは、屈強な青年たちに劣らない背丈の、しなやかで頑健そうな女性だった。
タイトなモスグリーンのミニドレスに、キャメル色の上着。
艶やかな小麦色の肌に、高く結い上げた金褐色の髪。
筋肉質の長い脚は、ダークブラウンのタイツに包まれている。足元は、動きやすそうなショートブーツ。
若く見えるが、貫禄からして、三十歳は優に過ぎているだろう。その女性は暗色のサングラスをかけたまま、笑いを含んで言う。
「こんな所で騒ぎを起こしたら、みんなの迷惑よ。ちょっと場所を移したら?」
青年たちが戸惑い、殺気をそらされた瞬間、双方のリーダー格らしい青年が二人、高く宙を舞っていた。豊かな水の流れる川の真ん中で、どぼんと二つ、水柱が上がる。
大多数の花見客には、青年たちの姿が壁になって、何が起きたかわからなかっただろう。
だが、橋の上のぼくからは見えた。素早い投げ技が。
次いで、四、五人の青年たちがぽんぽんと投げ飛ばされ、川面でしぶきを上げた。相手が突進してくる勢いを利用したわけではなく、純然たる腕力だけで、あそこまで投げられるのか!?
残りの青年たちが右往左往し、川に落ちた仲間を助けようとする。花見客たちもわらわらと集まってきて、それに加わる。
その間に、豪腕の女性は姿を消していた。慌てて目で探したぼくは、彼女が土手を越え、ビル街に向かっているのを発見した。まるで、瞬間移動したかのように速い。
ぼくは反射的に駆け出し、後を追っていた。
背の高い後ろ姿は、市街の雑踏の中でも見分けられる。溶けた黄金のように、光をはじく蜂蜜色の髪が目印だ。
それにしても、この速さは!? ゆったりとした歩みに見えるのに、実際には、小走りで追わないと引き離される。
追い付いて、どうしようとまでは考えていなかった。ただ、このまま見失うことはできない。
自分が、とてつもなく貴重な何かに遭遇した、という感覚があった。まるで、空から降ってきた流れ星に、頭を一撃されたように。
そう……世界が変貌した。
無彩色だった世界が、急に鮮やかな天然色になったようなもの。
ところが、ビル街の角を曲がった途端、光輝く姿が消え失せていた。あたりには、無彩色のおとなしい市民たちばかり。
どこかのビルに入ったのか? それとも、車を拾った? でも、ほんの数秒の遅れなのに。
焦って、闇雲に駆け出そうとした途端、ぐいと襟首を引かれた。
「えっ?」
背中を街路樹の幹にどんと押しつけられ、甘く濃密な香りに包まれる。
「何の用かしら、坊や?」
目の前に、黄金のオーラを放つ女神がいた。
赤い唇に悪戯な笑みをたたえ、暗色のサングラス越しに、ぼくを見下ろしている。
とっさには、声が出なかった。市民社会に来てから三年経つが、こんなに豪華でまばゆい女性を見たことがない。夏の太陽のようだ。
「んん? 何か用があるから、あたしを追ってきたんでしょ?」
ぼくはかっと熱くなり、激しい震えに襲われたが、同時に叫んでいた。
「お願いです!! 貴女の時間を、ぼくに下さい!! 三十分でも一時間でも……いいえ、今日一日!! 貴女の欲しいもの、何でもプレゼントしますから!!」
周囲の市民たちが足を止め、怪訝そうに振り返るのが、目の隅でわかる。自分でも、自分の大胆さに呆れてしまう。
(何をやっているんだ、ミカエル)
〝市民社会のお情け〟で生かされているバイオロイドのくせに。
しかし、この時、他に何ができただろう。
外聞を構っている余裕など、ぼくにはない。
「桜の名所をご案内します。それに、フランス料理でも日本料理でも、お好きな店にお連れします。宝石でもドレスでも、欲しいものを贈ります。どうか、今日一日、貴女の時間をぼくに下さい。ぼくの貯金、全て使い切って構いませんから!!」
さすがの女神も、呆れて言葉を失っている。叱り飛ばされるか、それとも笑い飛ばされるかだ。
『大人の女を口説くなんて、十年早いわよ』
と言われるのではないか。
そうしたら、ぼくにはその十年がないのだと、言うしかない。
同時に、普通の人間の子供ではなく、司法局の保護下にあるバイオロイドなのだと、白状しなければならないけれど。
だが、なぜだか、女神は凍りついていた。ほとんど、呆然自失のように見える。
そんな無防備さは、この人には似つかわしくない。
その間に、ぼくは立ち直った。どうせ死ぬのなら、何が怖いだろう?
「ぼくは、ミカエルと申します。貴女は、この街の方ですか。それとも、ご旅行でこの星に? これから、何かご用がおありですか? ぼくなら、明日でも、明後日でも、いつでも、貴女のご都合に合わせます!! 貴女が他の星に行くなら、ぼくも追いかけますから!!」
しまった、言い過ぎだ。これじゃ、ストーカーじゃないか。気味悪く思われるに決まっている。だけど、他にどうすれば。
そこで、ようやく我に返ったように、女神は動きを取り戻した。
「ちょっと、こっちへ来て」
「え」
ぼくは長身の美女に手を引かれ(大きくて力強く、温かい手!!)、近くの雑居ビルに連れ込まれた。動くとなったら、迷いのない人だ。彼女は何軒もの店を素通りして、地下への階段をずんずん降りていく。
「あの、どこへ……」
「いいから」
商品倉庫や従業員用の控え室を通り過ぎ、『関係者以外立ち入り禁止』の非常扉まで来た。この先は、都市のライフライン用の地下トンネルのはず。これは、司法局の護衛チームから制止がかかるかもしれない。
だが、彼女が何らかの操作をすると、ロックが解除されて厚い扉が開いた。もしかして、この首都の公務員か警察関係者なのかもしれない。それならば、ぼくの護衛たちも、一緒に行動して構わないと判断してくれるだろうか。
ぼくたちは地下トンネルに入り、扉を閉めて互いに向き合った。
といっても、彼女がぼくを見下ろす形だ。同じ高さで向き合うには、ぼくがあと三十センチ成長しなければならない。今はまだ、女の子に間違えられるくらいの、か細い子供に過ぎないから。
トンネルは真っ暗だが、人を感知した部分だけ照明が点いた。大小の配管が壁に添い、分岐しては暗闇に消えている。
「ええと、あたしはリリー……リリーというの。よろしくね」
改まった態度で言われた。自己紹介をするのに、わざわざ地下まで降りるというのは不思議だが、何か人目を避けたい理由があるのだろう。
「……そうですか。ぴったりのお名前ですね。よろしく、リリーさん」
まさに、真夏の百合だ。
それも、ほっそりした白百合ではなく、金色の斑点を散らした豪華な山百合。濃密な、甘い香水とも合っている。
すると、リリーさんはサングラスを外し、ぼくを見下ろしてきた。夏の海のような、濃いサファイア色の瞳だ。そこに飛び込んで、溺れてしまいたいような海。
顔立ちは高貴なまでに整っているけれど、冷たい印象はない。全身から、太陽のような生気を発散しているせいだ。抱きついたら、さぞ温かいに違いない。まさか、そんな真似をする機会は、ないだろうけど。
「ミカエル……ミカエルと言ったわね」
「はい」
この名前は、ぼくと同シリーズのバイオロイドたちに割り振られた記号にすぎない。ウリエル、ガブリエル、ラファエル、アサエル、タミエル、サリエル、タブリス、ナナエル、ラミエル……
古い一体が処分されたら、新しい一体にその名が回される。愛着のある名ではないが、この人の唇に発音されると、とても美しく聞こえるから不思議だ。
「きみ、川原から、あたしを尾けてきたわね」
「あ、はい。ごめんなさい」
身が縮んでしまう。この人には、素人の尾行なんて丸見えなのだろう。どうやって言い訳すればいいのか、わからない。
「とても、とても素晴らしい投げ技だったので……豪快でした。きっと、何年も修行なさったんでしょうね」
するとリリーさんは、何かに打ちのめされたような顔をした。ぼくが何か、悪いことを言っただろうか。誉めたつもりだったのに。
「あの、失礼なことをしたとは、わかっています。知らない女性の後を尾けるなんて。でも、どうしてもお願いしたいんです。貴女の時間、一時間でも二時間でもいいから、ぼくに分けてくれませんか。ぼくにとっては、それが、途方もなく大切な……」
思い出になる、と言いたかった。最後に病院のベッドの上で、繰り返し胸に甦らせるような。
ただ、病気の子供、と同情されるのは、違う気がした。
小さくても、半人前でも、男だから。
少なくとも、この人の前では、男でありたい。妙なものだ。さっきは、女の子の前で強がる青年たちを馬鹿にしたというのに。
「……大切な経験になる、と思いますので。リリーさんのご希望は、何でも叶えます。ぼくの貯金の範囲内で、ですが。何か、欲しいものはありませんか。宝石とか、ドレスとか? 車くらいなら、買えます。遊園地の貸し切りとか、クルーザーに乗って花火見物とか、手配さえ間に合えば、色々できるかもしれません」
科学技術局では、末端の研究員としての給与をもらっている。難民用の再教育施設を出た後、司法局に紹介してもらった仕事だ。贅沢などしないから、ほとんど貯金になっている。
市民社会では、普通に暮らしている限り、費用はあまりかからないのだ。安全確保のために出費を要する辺境とは、そこが違う。
ぼくの財産でも、一日だけなら、かなり豪華なデートができるだろう。
けれどリリーさんは、何か困っているように見えた。ぼくを傷つけたくないから、うまい断りの言葉を探しているのか。
確かに、十年後ならともかく、今の自分がこの人に相手にされるとは、自分でも思えない。
それでも、ぼくには多分、あと一年か二年の自由しか残っていないから。命があっても知能が低下していては、何もできないだろう。
「それじゃ、それじゃあね……」
ついにリリーさんは、覚悟を決めたように微笑んだ。
「車を借りて、ドライブに行かない? それで、桜の名所巡りをするの」
ぼくが愕然としたからだろう。リリーさんは、余裕を取り戻したように宣言した。
「あたしの願いを、何でも聞いてくれるんでしょ。それじゃ、夜まで付き合ってちょうだい。あたし、今はバカンス中だから」
一緒に脱出してきた仲間二人を失ってから、ぼくはずっと一人だった。
ウリエルは一年半前、組織の追っ手に狙撃されたし、ガブリエルは八か月前、脳腫瘍で死んだから。
そうすると、一般の職員たちは迂闊な慰めの言葉も言えなくなり、ぼくとは距離を置くようになる。精々、朝夕の挨拶をするくらい。
同じ体質であるぼくも、遠からず同じ病で死ぬ。それは、朝になって太陽が昇るのと同じくらい確実なこと。
既にもう、小さな腫瘍は幾つか手術で取り除いた。しかし、きりがない。腫瘍は次々に発生する。
せっかく、自由の身になったはずだったのに。
再教育を受け、市民社会の常識を覚えて、限定付きとはいえ、市民権を手に入れたのに。
ぼくの心の半分は、熱い怒りで占められている。残りの半分は、冷ややかな絶望に浸されている。毎日、その境目をよろめき歩いている。
いよいよとなったら、一人で黙って自殺をするか。
それとも、細菌兵器でも撒いて、この惑星上の全人類を道連れにするか?
その気になれば、たぶんできる。今、科学技術局の支局にいて、有機物の分析や合成の基礎実験をしているから。適当な致死性細菌かウィルスを合成して、空気中に放出すればいい。
日常の行動を管理システムに見張られていても、それを出し抜くことは、たぶん可能だ。違法組織の監視網に比べたら、はるかにゆるい監視だから。
実際、組織の基地を脱出する時に、ぼくたち三人でそれを実行した。
殺人ウィルスの散布。
サンプルは手近にあった。ぼくらがいた《ルーガル》の研究基地では、アンドロイド兵士やバイオロイドの製造の他、ウィルス兵器や細菌兵器も扱っていたから。
人間の科学者や技術者たちは、面倒な雑用を、ぼくたちバイオロイドの助手に任せていた。基礎データの積み上げ、実験動物の世話、用済みになった実験体の始末、機材の点検や薬品の補充。
定められた安全基準や、警備上の規則はあったけれど、長い年月のうちにそれがなし崩しになっていたから、隙はあった。
ぼくたちは保管庫から盗み出したウィルスをこっそり培養し、数日かけて、基地内の居住区に撒いて回った。自分たち三人だけ、前もってワクチンを接種しておいて。
凄まじい効果だった。
うまくいくとは、自分たちでも信じていなかったのに。
夜中、異変を知らせる警報が響いた。あちこちの非常隔壁が閉まり、空気の強制排気や消毒剤噴霧が行われ、狼狽する人間たちの叫びが行き交った。一人、また一人とうずくまり、吐き気や下痢に苦しみだす。
死ぬことのないアンドロイド兵士が、発病した人間たちを抱いて運んだ。けれど、医療室でも、医師たちが倒れていた。医療カプセルも、すぐに足りなくなった。誰も、ウィルスの蔓延を止められなかった。症状が出た時には、もう手遅れなのだ。
ぼくらは何も知らないバイオロイドたちに混じって、怯え、うろたえるふりをした。やがて、人間より強健なバイオロイドたちも倒れ、身を折って苦しみだした。
止まらない嘔吐。血便。粘膜からの出血。
朝になった頃には、基地中が凄まじい地獄絵図になっていた。半数はまだ、汚物まみれでもがき苦しんでいたが、半数は、既に動かなくなっている。息のある人間たちも、もはや、機械の兵士に命令を下せるような状態ではない。
基地の統合管理システムは、非常事態であることを上級基地に通報し、指示を仰いだ。上級基地の幹部たちは、他組織の攻撃と思ったのだろう。基地内の空気のサンプルや、死人の細胞のサンプルを取った後、死体を溶解槽に入れ、全ての空気を抜いて徹底消毒しろと命じたらしい。
アンドロイド兵士たちが、片端から死体を貨物車両に積み込み、処理室へ運んでいく。瀕死の者たちも、構わず車に放り込んでいく。
調査隊は、既に上級基地を出て、こちらへ向かっているだろう。到着は一日後か、二日後か。
ぼくたち三人は混乱に乗じ、廃棄処分を待っていた老朽艦に潜り込んだ。ぼくたちの技術で基地からの制御を切断できるのは、その船だけだったから。
もちろん、船で勝手に基地から離れれば、即座に管理システムに怪しまれ、攻撃される。それは想定済みだった。母艦そのものは、追ってきた無人艦のミサイルで爆破されたが、ぼくたちは直前に小型艇で母艦を離れ、手近の小惑星に隠れていた。
ちっぽけな小型艇でも超空間転移はできるし、贅沢を言わなければ、半年や一年、命をつなぐこともできる。
そして、半年もの時間をかけて慎重に遠回りし、ついに、市民社会が存在する中央星域に逃げ込んだ……
難民として司法局に匿ってもらった時は、これで自由になったと信じた。
組織からの刺客さえかわせれば(誰が惨劇の犯人なのか、いつかは明らかになるはずだった。当然、追っ手は来る。だが、司法局も対策は講じる)、市民社会の片隅でひっそり、穏やかに暮らせると。
知らなかったのだ。
ぼくたちの遺伝子に欠陥があり、生存期間の五年が過ぎる頃には、脳腫瘍が多発するようになるとは。
それでも、組織はぼくたちを許さなかった。市民を誘惑して刺客に仕立て、ウリエルを狙撃させた。彼は脳が吹き飛んで、即死だった。狙撃した方も逃亡しきれず、逮捕されたから、《ルーガル》の仕業と判明したのだ。
それから司法局の警備が厳重になり、幾度か場所も移されたが、組織の側はしつこかった。逃亡者を許しておいては、他組織に対しても、内部の人員に対しても、示しがつかないからだ。ぼくも一度、街中で狙撃され、危ういところで助かった。
そうこうするうち、ガブリエルが発病した。遺伝子治療以外に、方法がないこともわかった。
ぼくとガブリエルは、治療法を研究させてくれと、何度も申請した。何年も研究助手として働いてきた自分たちには、その能力がある。
しかし、申請はその都度、却下された。
惑星連邦政府は、遺伝子操作を許さない。
正規の市民ですら、遺伝子操作による延命は許されないのだ。まして、違法に製造されたバイオロイドのために、どうして法を曲げられるだろうか。
だからぼくらは、残りの日々を、死病と共に暮らすしかなかったのだ。
辺境でなら、たぶん、治療法が買えると知りながら。

どうかしている。
このあたしが、あたしの肩にも届かないような男の子を前にして、どぎまぎ、そわそわするなんて。
これじゃあ、まるで、十代の女の子みたい。
何十年も戦い続けてきて、まだ乙女!?
そもそも、この星へは、ミカエルに会うために来たというのに。
彼の位置情報を確かめてから、相棒の探春を残して、車を降りた。たまたま学生の喧嘩騒ぎを見てしまったものだから、つい悪戯っ気が起きただけのこと。
いったん隠れて、出直すつもりだった。〝リリス〟の追っかけは、どこにでもいる。彼らに気付かれて、騒がれたら面倒だから。
まあ、あれだけのことをして誰にも気付かれなかったら、それもまた、つまらないのだけれど。
まさか、ミカエル当人が追ってくるとは思わなかった。しかも、あたしが誰だか知らないまま、デートを申し込んでくるなんて。
単なる憧れ。
そう言ってよければ、一目惚れ。
これまで、男という男に恐れられ、避けられてきたというのに。この年になって、こんなことが起きるなんて。
もちろん有名人としては、ずっと追いかけられてきた。ジャーナリストやミーハー連中に。あるいは暗殺者やテロリストに。しかし、個人的に交際を望んでくれる男は、まずいなかった。
ミカエルの目の高さを、誉めるべきなのか。
やっと降ってきた幸運と思い、謙虚に感謝するべきなのか。
あたしのことは軍人か警官か武道家か、そんな風に推測しているようだ。元から、年上趣味なのかもしれない。ミカエルの知的水準は研究者レベルだから、十代の少女では物足りないのかも。
外見上は十二歳前後の少年だし、実際にも、まだ六、七年しか生きていないのだが、彼の経歴から考えれば、なまじの大人よりも老成していておかしくない。
違法組織の中で日常の仕事をこなしながら、密かに致死性のウィルスを培養し、それをぶちまけて脱走してくるとは、『何でもあり』の辺境でも、稀な出来事だ。
人間たちが、自分たちより優秀なバイオロイドを創ってしまったという、皮肉な証明でもある。
一般市民からすれば、目を背けたくなる事例かもしれないが、あたしが彼らの立場だったら、やはりやっただろう。
黙って殺されるのを待つなんて、冗談ではない。
殺す他に生きる道がないなら、あたしだって殺す。
それを非難する権利が、誰にある?
とはいえ、このミカエル、やはり子供ではあるのだ。あたしがリード権を奪うと、ほっとしたようについてくる。あたしはちらちら、彼のことを観察せずにいられない。
栗色のさらさら髪をショートボブにしていて、童話の中の王子さまのよう。
肌は白く、宝石のような緑の目をしている。
愛らしい顔立ちだから、ドレスを着せたら、女の子に見えるかも。今は白いシャツに紺の上着を着ているから、名門校の生徒みたいだけれど。
とにかく……きゅんときた。
ミカエルの貯金なんて、ささやかなものだろうに。それを全部使ってもいいから、あたしといる時間が欲しい、なんて。
あたしは大富豪ではないけれど、自分の欲しいものが買える程度の収入はある。私有の艦隊だってある。
それでも、強烈な快感が走った。
こんな懇願、生まれて初めてではないだろうか!?
ほとんどの男は、あたしを恐れた。こそこそ迂回して、避けようとした。尊敬はしてくれても、遠巻きにだった。
それは仕方がないと、あたし自身もあきらめていた。男というのは、女よりはるかに臆病な生き物だから。
彼らのプライドは、ガラス細工のようにもろいのだ。自分が勝てないと思う女には、最初から近寄ろうとはしない。まして、求愛など有り得ない。
こんな奇跡、生涯に一度だけかもしれない。
だったら、いいでしょ。
今だけ、憧れられることを楽しんでも。
〝リリス〟と名乗るのは、後にしよう。
もうしばらく、普通の女でいたい。
少しばかり武道の心得があるだけの、普通の女。
車で待っている探春には、ホテルへ戻るなり、買い物に行くなりしてもらおう。護衛のナギが一緒だし、司法局の警備網の中だから、危険はまずない。
『また、新しい王子さま?』
後から皮肉を言われても、構わない。どうせミカエルは、健康体になったら、あたしのことなど忘れてしまうに決まっているのだから。
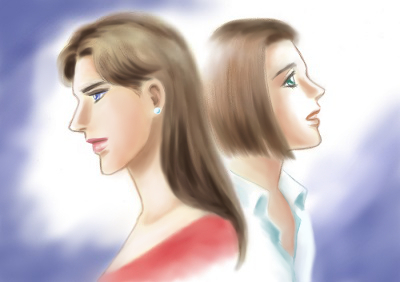
ぼくは、自分が恋愛をするとは思っていなかった。
誰かに『憧れる』なんて、そもそも無理だ。ほとんどの人間は、ぼくより愚かなのだから。
人間が猿に憧れたりしないように、知能強化型バイオロイドが人間に憧れることもない。
違法組織にいる間は、仕事に必要な科学知識しかなかったが、市民社会に亡命してきてからは、一般教養も身につけた。それこそ、一般人に向かって歴史の講義ができるくらいに。
《ルーガル》の基地を脱出する時、二百人以上の人間とバイオロイドをウィルスで殺したことも、悔いていなかった。
せっかくこの世に生まれたのだから、もっと生きたい。
そう願って、何が悪い。
ぼくらが高い知能を持つように設計したことが、人間たちの間違いなのだ。
それでも、今は……
リリーさんには、ぼくが『人間殺しの反逆バイオロイド』だと知られたくない。せめて、今日のうちだけは。
ぼくはリリーさんと、無人の地下トンネルを二キロ近く歩いた。水道管や電力ケーブル、通信ケーブルが分岐を繰り返す、地底の迷宮である。
いくら照明があっても、一人だったら不気味に感じただろうが、リリーさんがいることで、珍しい探検という感じになっていた。この人と一緒なら、どんな闇にも太陽の光が射すだろう。
なぜわざわざ、地下を移動するのか尋ねたら、
「さっき、大人げないことしてしまったからね」
という返答だった。リリーさんは、目立つことをしてしまった、と後悔しているらしい。
でも、ぼくにとっては幸運だった。おかげで、この人の存在を知ることができたのだから。
歩きながら、リリーさんが郷里の星では警官であること、今は従姉妹と一緒に、この星に遊びに来ていることを聞いた。
その従姉妹は今日、別行動だが、夕食時にはホテルで合流して、紹介すると言われた。つまり、夜までは一緒に過ごしてもらえる。あと、八時間か九時間のこと。
ああ、一秒ずつが勿体ない。
砂時計の砂粒が、全て宝石でできている気がする。
――後からわかったことだが、この時、既に、川原の花見客たちから噂が広まっていた。大の男を投げ飛ばした女性は、戦闘用強化体に違いないと。そして、何千人ものファンが連絡を取り合い、リリーさんの行方を追っていた。サインや握手をねだるために。
ぼくだって普段なら、すぐにわかったはずだ。常人を超える腕力の持ち主で、しかも、そのことをあっけらかんと披露する人物が、司法局のお抱えハンター〝リリス〟の他にいるはずないと。
けれど、この時は既に、まともな思考力が働いていない。考えずに、ただ感じるだけ。
ぼくらは地下トンネルを通って、ファンたちの捜索網を抜け、目立たないレンタル車を呼んで、首都を離れたのである。
青空の下を走る車の中で、まだ陶然としていた。
リリーさんの隣にいる幸運が、自分で信じられない。まさか、夢を見ているわけではないだろうな。目が覚めたら、脳の手術の後で、病院のベッドの上だとか。
けれど、リリーさんは車を運転しながら、機嫌よく話しかけてくる。
「今日は寒くないから、ちょっと海に行ってみようか? お昼は、魚料理がいいかもね。それから、きみのお勧めの桜の名所を回ろうか」
ぼくの身元を尋ねられなくて、よかった。尋ねられていたら、嘘はつけないから。
この気軽さは、ぼくを普通の子供と思っているからのこと。
大量殺人犯だと知ったら、絶対に顔が曇る。頭では理解してくれても、心情がぼくを拒絶するだろう。
司法局の護衛たちは、ぼくが初対面の年上の女性とドライブなんて、何事だろうと不審に思っているかもしれないけれど……
特に止められないということは、問題はないということだ。この奇跡を精一杯、楽しもう。
首都のはずれから三十分も走ると、砂浜と岩場が続く海岸線に出る。陽光にきらめく海上には、何艘ものヨットやクルーザーが散っていた。首都の人々が、海遊びに来ているのだ。
「船を借りますか?」
「ううん、今日は桜がメインだから、ちょっと海岸を歩くだけ」
リリーさんは海岸の松林に車を乗り入れ、ぼくを連れて、波打ち際に降りた。風はまだ冷たいが、火照った顔にはそれも心地よい。穏やかな波が打ち寄せる浜には、遠くにちらほらと人影が見えるだけだ。
「ミカエル、これできる?」
リリーさんは平たい小石を拾って、無造作に、しかし鋭く投げた。小石は海面で何度も大きく跳ね返り、はるか沖合まで進んで、やっと水没する。水切り、という遊びだそうだ。
「すごい!」
ぼくも真似をして小石を拾い、何度も投げた。理屈はわかる。浅い角度で、水面にぶつかればいいのだ。
「そうそう、いい感じ」
もちろん、リリーさんの飛距離には遠く及ばないが、それでも平均して二回ほどは跳ね返るようになったので、満足する。
知らなかった。こんな単純なことが、こんなに楽しいなんて。本ばかり読んでいた、これまでの時間、ぼくは人生を損していたのかも。
海水はまだ冷たいけれど、日差しの温かさがあるから、手を入れても平気だった。ぼくたちは岩場を探険して、潮溜まりにいる魚を観察したり、蟹を捕まえたり、綺麗な貝を拾ったりして、一時間以上を過ごした。
リリーさんといると、何をしても楽しい。ぼくは今まで、何でも一人でしてきたし、それが平気だったはずなのに。
「ミカエル、そろそろ、お腹空かない?」
「そうですね」
ということで車に戻り、海岸線を何キロか走って、魚料理を売り物にするレストランに入る。
海を見渡せる席に着いて、メニューを見るのも楽しかった。他の客たちからは見えない席だったので、貸し切りの雰囲気だ。
白身魚のマリネサラダや貝のバター焼き、海老の塩焼き、パエリヤなどの料理も美味しかったが、赤い宝石のようなサングリアを飲ませてもらったのが嬉しかった。
「お酒なんだけど、まあ、ジュースに近いから、ちょっとだけならいいでしょ」
とリリーさんは微笑む。ぼくのグラスに入れてもらったのは、確かに、ほんの味見程度の量にすぎない。
「あ、甘いですね。飲みやすい」
「ちょっとずつね」
「はい」
ぼくの精神はともかく、肉体はまだ子供である。惑星連邦に保護される前も、その後も、アルコールの摂取を許されたことはなかった。だが、どうせ死ぬのに、何を構うことがあるだろう。
サングリアは、これまで飲んだことのある、どんなジュースより美味だった。少しすると、頭がゆらゆらするようになってくる。パン籠に手を伸ばしても、距離感がうまく掴めない感じ。リリーさんが遠くに見えたり、足が地面に着かないような、ふわふわ感がしたりする。
これが、酔うということなのだろうか。だとしたら、面白い。人類が大昔から酒を愛してきたのも、納得がいく。
ただし、飲んだ量が少なかったせいらしく、デザートのケーキにさしかかる頃には、ゆらゆら感は薄れてきた。残念だ。いったんトイレに立ち、冷たい水で顔を洗ったら、だいぶさっぱりしてしまった。できたらまた、飲んでみたい気がする。
しかし、何より嬉しかったのは、リリーさんが、店の支払いをぼくに任せてくれたことである。
「美味しかったわ。ご馳走さま、ミカエル」
「どういたしまして。楽しんでいただけたなら、よかった」
「ええ、とってもいいランチだった」
普通なら、大人のリリーさんが払ってしまう場面だろうが、あえて、ぼくを立ててくれたのだ。〝男〟の役を果たせたようで、わくわくする。
車に戻ると、今度は内陸に入り込んで、桜の名所として知られる神社に向かった。何でも、地球の古い神社を模して建てられたそうだ。
去年はやはり桜の時期に、一人で(遠巻きに警備されつつ)歩いたのだけれど、まさか、デートで来られるなんて。
もっとも、周りからは、年の離れた姉弟か、叔母と甥くらいにしか見えないだろうな……
神社の周囲には広い日本庭園があり、あちこちで見事な枝垂桜が咲き始めていた。黄色い花を咲かせた、山吹の茂みもある。
大きな池には見事な鯉が泳いでいて、橋を渡ると、上から魚影がよく見えた。鯉に餌を投げている観光客もいる。
二人して池のほとりの茶店に座り、池に映る桜を観賞しながら、抹茶と桜餅を楽しんだ。
大きな屋根を持つ拝殿では、鰐口をガラガラ鳴らして、お参りした。賽銭箱にコインも投げた。現代社会では支払いにコインを使うことはないが、社務所に賽銭用のコインが置いてあるのだ。昔のコインを模造したものだという。
ぼくは何の宗教も信じていないが、それでも、リリーさんと出会わせてくれた何かに感謝した。
天と言ってもいい。宇宙の摂理と言ってもいい。
そして、この一日が無事に過ぎますようにと祈った。明日もまたなんて、欲張りすぎる。望みたいけれど、望んではいけない。きっと。
我ながら、いじらしいじゃないか、ミカエル。
幸せな時は、簡単に善人になれるのだな。
それから、社務所でおみくじを引いた。リリーさんが、やってみたいというので。女性は占いが好きだというけれど、普通の女性とは思えないリリーさんも、やはりそうなのかな?
ぼくは小吉だった。ぼくの気分からすれば、既に大吉だが、ぼく程度には、これでちょうどいい気もする。
今日一日だけの幸運。
明日にはきっと、リリーさんは従姉妹とどこかへ行ってしまう。ぼくのことなど、おぼろな記憶の一部になるだけ。
それはそれで構わない。
ぼくは死ぬまで、今日のことを忘れないから。
ところが、自分の引いたおくみじが大凶だと知って、リリーさんは本気で嘆いた。
「ああ、もうっ!!」
天を仰ぎ、髪をかきむしらんばかりに身をよじり、足で地面を踏み鳴らす。
「あたしって、いつもこうなのよ!! うまくいきそうだと思っても、いつも失敗するの!! せっかくミカエルと知り合えたのに、きっとまた嫌われるんだわ!!」
「ええっ」
ぼくに嫌われる心配、なんて。
そんなこと、世界がひっくり返っても起きるわけない。
それにまた、リリーさんのように剛胆な人が、こんなお遊びに、心底から一喜一憂するのも意外である。
「ぼくがリリーさんを嫌うなんて、あるわけないですよ。雨が逆さに降る以上に、無理なことです」
すると、リリーさんは金褐色の眉を曇らせ、悲しげに言う。
「だって、いつもそうなんだもの」
「いつも?」
「男という男、みんなあたしを避けて通るのよ。従姉妹のヴァイオレットにはデートの申し込みが殺到するのに、あたしには全然来ないんだから!! そりゃあもう、子供の頃からずーっとよ!!」
「……そうなんですか?」
ぼくはつい、笑ってしまう。だってそれは、男たちが、リリーさんに劣等感を感じるからだろう。ぼくのように、ただ仰ぎ見るだけの立場なら、いじける必要もない。
「じゃあ、ぼくが世界中の男に代わって、貴女を賛美してもいいですよね。リリーさんは素敵です。世界中の百合を集めてきても、リリーさん一人には敵わないですよ」
ちょっと気障すぎたかと思ったけれど、リリーさんは
まるで、救いを求める少女のような顔をする。
「ミカエルは……あたしのこと、いいと思ってくれるの?」
ずきんときた。
演技なんかじゃない。心の底から、本気で不思議に思って尋ねている。
この人は、自分が女神だと知らないのか!?
素直で、無邪気で、まばゆい生命力そのものなのだと。
では、どうしたら、ぼくが感じている気持ちを、この人に伝えられるだろう。だって、ぼくが今日まで生きてきたのは、この人に出会うためだったのかもしれない……そう思い始めている。ウィルスを撒いて大勢殺したことも、狙撃された時に助かったのも、全てこの時のためだったのかも。
そう思ってもいいはずだ。それでぼくが、納得して死んでいけるのなら。
少なくとも、身勝手な人間たちに造られて、この世に送り出されたことが、無意味ではなかったのだと思うことができる。
「……リリーさんは、太陽のような人です。ぼくは、太陽を回る惑星みたいに、貴女の周りを永遠に回りたいくらいですよ」
「そ、そう?」
リリーさんは困ったような、半信半疑の顔で、両手を頬に当てる。サングラスを外したままなので、表情がよくわかる。大の男を投げ飛ばせるのに、自分が求愛されないと悩むなんて。なんて、女らしい。
「リリーさんは、天に愛されている人だと思います。運が悪いはず、ありません」
何の根拠もないが、そう断言できた。
「ただ、運勢があまりにも強いので、バランスをとる必要上、ぶつかる困難も人より大きい、ということなんでしょう。このおみくじはきっと、困難を乗り越えたら、大吉に転じる、という意味ですよ」
自分が正しいことを言っているのが、自分でわかった。なぜだか、リリーさんといると、いつもの自分より頼もしい!?
「だから、これは、油断しないようにという、戒めを込めてのお告げなんです。安心して下さい」
すると、リリーさんは両腕を伸ばしてきて、ぼくをぎゅう、と抱きしめてくれた。
「ああ、ミカエルって、何ていい子なの!!」
ちょうど、ぼくの顔がリリーさんの胸の谷間に埋まることになる。窒息しそうだ。何という弾力だろう。顔が火照り、のぼせてしまう。いいのだろうか、人前だというのに、こんな快感を味わってしまって。
「もう、大好き!! 食べちゃいたいくらい!!」
リリーさんはぼくの頭に頬を寄せて、全身ですりすりしてくれる。てらいも何もない。
たぶん、いつもこうなのだ。好きも嫌いも、力一杯表す。食べることも遊ぶことも、常に全力。
(こんな風に生きられたら、人生、楽しいだろうな)
それは、強いからこその率直さ。
普通の人間には、真似できない。
だが、真似ようとすることくらいは、ぼくにもできるのではないか。
そうすることによって、リリーさんに出会えた意味が強まるのでは。
すると、周りの参拝客たちが呆れていようが、くすくす笑っていようが、どうでもいいと思えた。ぼく自身が嬉しければ、そしてリリーさんも喜んでくれるなら、それで十分ではないか。
「んーんっ」
最後にリリーさんは、ぼくの額にキスしてくれた。
――このまま、宇宙の時間が止まってくれればいいのに。
司法局の警備チームが、駐車場に停めた警備車両の中で、何て不釣り合いな組み合わせだと、笑い合っているかもしれないけれど。
勝手に、どうとでも思わせておけばいい。これは、ぼくの人生なのだから。
空の雲がわずかに茜色を帯びる頃、ぼくたちは神社の裏手の、なだらかな山に登っていた。山の中には、整備された遊歩道が巡っている。リリーさんが、滝を見たいと言うので。
山から降りてくる人はいても、今から登る人はいない。山の南斜面はまだ日に照らされているけれど、北側の斜面は青く陰っている。あちこちに、鮮やかな黄色の山吹がこぼれ咲いていた。たぶん、枝から枝へ飛んだ鳥は、ぼくを見張る偵察鳥だ。
「あれ、帰りに、ちょっと摘んでいこうかなあ。ヴァイオレットの好きな花なのよ」
「そうなんですか。豪華な花ですね」
「黄色い花が咲くと、春が来たって感じがするのよね。そうすると、あの子もよく黄色いドレスを着るの」
リリーさんの従姉妹は、今頃、美術館やデパートを巡っているはずだという。
「あたしは美術品や骨董品には、あまり興味がないのでね」
わかる気がする。この人はたぶん、静止したものには、そそられないのだろう。
「そういえば、ヴァイオレットって、この花のことですよね」
「ああ、そう、その菫のことよ」
遊歩道の脇に点々と咲く紫の菫は、星を撒いたように美しい。花の名を持つ従姉妹は、きっとこの菫のように、可憐で上品な女性なのだろう。
「ヴァイオレットさんも、同じ警察のお仕事なんですか?」
「ええ、まあ、そう……向こうは、事務仕事が得意でね。あたしと反対。あたしは現場を走り回る方」
「すごく想像がつきます」
リリーさんは、口より手の方が早いに違いない。
「もしかして、犯人をぶっ飛ばす想像してる?」
「まあ……そうですね」
ぼくが笑いを隠せないでいると、リリーさんは、ちょっと口を尖らせる。
「あたしだって、話して通じる時は、話すのよ」
「もちろん、そうでしょうとも」
笑いながら遊歩道をたどっていくと、吊り橋にさしかかった。はるか下は岩だらけの沢で、水量の少ない川がさらさらと流れている。観光マップによれば、滝はこの吊り橋の先だ。
ぼくは高い所が怖いので、吊り橋の手前で、わずかにためらった。どうしても、
(もし落ちたら)
と想像してしまうのだ。骨がぐしゃぐしゃになる自分を想像してしまうと、足がすくむ。
でもリリーさんは、そのためらいを見逃さなかった。笑って、手を差し出してくれる。
「どうぞ、王子殿下」
うわあ。冗談でも、王子さまとは。ぼくは耳まで熱くなってしまい、まともにリリーさんを見られない。
「ええと、はい……では」
子供扱いされてしまったとは思うが、優しい大きな手に手を包まれるのは、ひどく幸せなことだった。手をつないでもらうと、水面をはるか下に見る吊り橋も、それほど怖くない。橋が少し揺れても、リリーさんはまっすぐ前を見て、安定した歩調で進んでいく。思わず、尋ねてしまった。
「リリーさんて、怖いものはないんですか?」
「あたし? ヴァイオレットは怖いよ。あの子は怒ると、氷みたいに冷たくなるの」
「それは……怖いかも。でも、それは、ヴァイオレットさんを大事に思っているからですね」
「まあね。でも、誰かと手をつないでこんなに嬉しいのは、あたし、初めてかも」
うわあ。
胸が一杯になってしまって、受け答えができない。
自分で感心してしまった。こんなことで、こんなに幸せになれるほど、ぼくは単純だったのか。
常に人の言葉の裏を読み、罠はないかと疑う、疲れる性格だと思っていたのに。
いや、きっと、単純であるべきなのだ。
頭で考えているだけだと、堂々巡りしてしまって最後は絶望に陥り、世界を呪ってしまう。その時々で動物的な幸福に浸るだけなら、うんと楽なのだ。
というより、せっかく生まれてきて、人生を楽しめない方が愚かなのだろう。
そうか。ぼくに足りなかったのは、馬鹿になることか。
明日というものは、ない。
ただ、いつも、今があるだけ。
だから、今を目一杯楽しむ。
本当にその覚悟がついたら、それが、悟るということなのかもしれない。
手をつないだまま、長い吊り橋を、真ん中あたりまで渡ってきた時だった。いきなり、落雷のような衝撃を受けたのは。
天が怒り、世界が砕けたかと思った。
真っ白い光に漂白され、何も見えない。
けれど、吊り橋がまっ二つに断ち切られ、左右に分かれて落下していくのはわかった。足場がなくなり、躰が宙に浮く。
落ちると思った瞬間、ぼくは恐怖で気絶したに違いない。けれど、リリーさんは冷静にぼくを抱え、爆発的に沸き上がる水蒸気の中、川に飛び降りていたのである。

探春は怒った。もちろん怒った。
それも、ヒステリックに叫ぶのではなく、冷ややかに、淡々と怒る。
「自業自得だということ、あなた本人が一番わかっているわよね。わざわざ喧嘩騒ぎに分け入って、注目を集めるような真似をして」
はい。
おっしゃる通りです。
「何もしなくても目立つのに、どうして、更に人目を集めたがるのかしら。しかも、ミカエルと外を歩き回ったりして。すぐに宙港へ向かっていれば、今頃、安全な船の中だったのに」
弁解の余地はなかった。
「ごめん」
狙撃の標的はミカエルだった可能性もあるのだが、やはり、あたしであった可能性の方が、はるかに大きい。
衛星軌道からの砲撃。
辺境を支配する違法組織の〝連合〟は、あたしたちの首に巨額の懸賞金をかけている。今回は、大気の揺らぎによる、ほんのわずかなずれで命拾いしただけ。その幸運がなかったら、あの時、ミカエルと二人揃って、骨も残さず蒸発していただろう。
現場の山中へは、すぐに地元警察と司法局の部隊が駆け付けてくれ、あたしとミカエルを首都の病院へ運んでくれた。
あたしは軽い火傷と、岩にぶつけた傷だけだったが、砲撃に近かったミカエルは、右半身の重度の火傷に脳挫傷。
ミカエルを抱え、下の川にうまく飛び降りたつもりだったが、岩がごろごろしていて足場が悪く、着地の衝撃を殺しきれなかったのだ。
バイオロイドは普通の人間よりも丈夫だが、ミカエルは戦闘用の強化を受けたわけではない。回復には、しばらくかかる。
軍の艦隊が、衛星軌道からの砲撃を行った民間船を拿捕してくれた。しかし、砲撃は船の管理システムが勝手に行ったもので、人間の乗員たちは関知していないことがわかっただけ。
例よって、遠隔で管理システムを乗っ取られたのだ。
犯人は、遠い宇宙のどこか。
そこまでは、軍も司法局も追及しきれない。技術水準においても、戦闘力においても、もはや、辺境の違法組織の方が上なのだ。
首都の中央病院にいるうち夜中になり、雨が降りだした。せっかくの桜も、寒さに縮こまっているだろう。
この特別棟は、地元警察と司法局が合同で周囲を固めているから、まずは安心だ。警備責任者の許可を取り、ミカエルのいる集中治療室に、特別に入室させてもらった。
ミカエルは半透明の医療カプセルに入れられ、裸で薬液に浮いたまま、麻酔で眠っている。治療がある程度進むまで、意識がない方が、本人が楽だからだ。
右半身の白い肌が、赤黒いまだらになっているのが痛々しい。綺麗に治るのはわかっているけれど、あたしなんかと一緒にいたばかりに。
カプセルの横に置いた椅子に座っていながら、あたしは震えていた。寒いわけではないのに、震えを止められない。
目が覚めたら、ミカエルは何と言うだろう。
『リリーさんが、あの〝リリス〟の片割れだったなんて。早く言ってくれれば、並んで外を歩いたりしなかったのに』
それだけでもう、決定的に嫌われる。そのコード名には、死神のイメージが染みついてしまっているから。ミカエルがあたしを見る目には、恐怖と嫌悪が浮かぶに違いない。
あたしとしては正義のつもりでも、結果として、どれだけ殺してきたか。
宇宙空間で戦闘をすれば、爆破は死に直結する。吹き飛ばした船と共に、たくさんの命が消え去った。そしてそれを、当然のこととして忘れ去ってきた。くよくよ悩むくらいだったら、ハンターなんかやっていない。
でも、それは普通の人間から見れば、恐ろしい無神経だろう。
そもそも、何が正義かなんて、絶対の基準があるわけではない。
違法組織にだって、それなりの言い分はある。
不老不死を求めて、何が悪い。そのために人体実験をして、何が悪い。強い者が生き残るのが、宇宙の掟。
うちの一族だって、れっきとした違法組織。
惑星連邦の法そのものが、既に時代遅れという面が強いのだ。いつか人類が高度な他文明と出会ったら、その文明の掲げる正義は、人類の正義とは違うかもしれないし。
何にしても、
『そんな物騒な人と個人的に付き合うなんて、冗談じゃない。一緒にいたら、またいつ命を狙われるか、わからない』
ミカエルはそう考え、あたしを敬遠するようになるだろう。
脳腫瘍の治療さえ受けられたら、あとはもう、二度とあたしに関わりたくないと思うに決まってる……
都合のいい夢想だった。ミカエルが大人になるまでじっくり付き合って、本物の恋人同士になれるかもしれない、なんて。
『リリーさん、こちらの席の方が見晴らしがいいですよ』
『リリーさん、風が寒くありませんか』
『リリーさん、お茶のお代わりをもらってきましょうか』
ミカエルはデート中、懸命にあたしを気遣ってくれた。まるで、傷つきやすい貴重品を預かっているかのように。
それが嬉しくて、わくわく、いそいそしていたなんて、本当に馬鹿。
はるか年下の子供にすがろうなんて、何万人も殺してきた、このあたしが考えること!?
探春でなくたって、呆れるわ。
扉が開いて、アンドロイドのナギが、静かに声をかけてくる。
「ミス・リリー、じきに夜明けです。担当官が来る前に、朝食をどうぞ」
「わかった」
明るくなったら、司法局と相談して、公表の段取りをつけなくては。
表向き、ミカエルは〝リリス暗殺未遂事件〟の巻き添えで死亡、ということになる。でないと、遺伝子治療のために辺境に連れ出すことができない。《ルーガル》との関わりも、断ち切れない。
同じ重さの人形を入れた棺で葬式を出し、ミカエルの担当だった司法局員や、同じ職場にいた科学技術局の人々に参列してもらうことになるだろう。報道記者も来て、短いニュースを作る。そして、ウリエルとガブリエルの墓の横に、新しい墓が立てられる。
市民社会の知り合いたちは、少しばかり泣いて、ミカエルのことを清らかな思い出にする。ミカエルは辺境のどこかで、ひっそりと生きていく。
生きていく道は、いくらでもある。ほとぼりが冷めたら、別な名前でまた、市民社会に戻れるかもしれないし。
同じ階の控室で、探春がコーヒーとサンドイッチを用意してくれていた。小海老とアボカド。ローストビーフとクレソン。ベーコンとトマト。果物の盛り合わせも付いている。急に、胃袋が存在を主張してきた。
そういえば昨夜も、どさくさに紛れて、ハンバーガーを食べただけ。こんな時でも、食欲だけはある。失恋した時くらい、食欲が失せてもいいのにね。
「職員用の厨房を借りて、わたしが作ったから、安心して食べていいわよ」
探春は、さすがに手際がいい。あたしたちは常に毒殺を警戒しているので、外食の時は、無作為に店を選ぶ。さもなければ、無作為に材料を買う。
「そっか。ありがと」
と感謝して、小海老とアボカドのサンドイッチにかぶりついた。マスタード入りのマヨネーズが、あたし好みだ。コーヒーには、たっぷりクリームが入っている。
「クローデル局長と話したわ。葬儀の段取りはつきました。病院側でも、ミカエルの本当の状態を知っている医師は、ごく少数だから」
有能な探春は、マスコミ対策も含めて、既に司法局側と話し合ってくれたようだ。少人数のチームが、ミカエルの死を演出してくれるという。
「ごめん」
次のサンドイッチに手を出しながら言うと、幼馴染みの従姉妹は、諦観したような微笑みで言う。
「いつものことだもの。何でも、あなたの気の済むようにすればいいわ」
あたしが新しい王子さまを見つけ、舞い上がる度、探春は顔を背けて待っている。どうせ、すぐに破局が訪れるから。
今回も短かった。たった一日のデート。
それでも、あんな楽しい時間、生まれて初めてだったような気がする。ミカエルは何度も、あたしが聞きたいと思う台詞を言ってくれた。まるで、あたしのためにあつらえられた王子さまみたい。
でも、もちろん、これ以上、彼を連れ回してはいけない。
あたしのために、危険な目に遭わせてはいけない。
ミカエルが起きられるようになったら、辺境へ送っていく。故郷の違法都市で、麗香姉さまに預ける。それで終わりだ。
あたしの王子さまになってくれる物好きな男性なんて、いるわけない。変わらずに側にいてくれるのは、親友の探春だけ。
それだけで、十分な幸福のはずではないか。
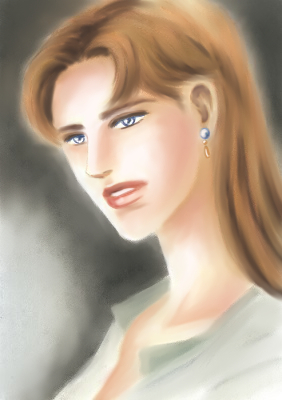
意識が戻った時は、ベッドの上で雨の音に包まれていた。世界全体が、穏やかな雨の底にある。知らない部屋だが、薬の匂いがするから、病室にいるらしいこともわかる。
桜……桜は、まだ咲いているだろうか……それとも、桜の季節はとうに過ぎている?
あれは、夢だったのか。
リリーさんと出会ったこと。海で遊んだこと。そして、吊り橋から落ちたこと。
冷たい砂利の上に横たわったまま、暗い空に、何かが大きく飛び回るのを見た。警察か司法局のエアロダイン、と思ったことを覚えている。降りてきた職員たちに、リリーさんが何か鋭く指示していた。砂利を蹴立てる、幾つもの足音が交差して……
それでも、いい夢だった……柔らかい胸に顔を埋めた感触、はっきり覚えている……目醒めなくてもよかったのに……
「ミカエルくん、気分はどうだい?」
扉が開いて、白い制服姿の若い男性が入ってきた。快活な態度で、主治医だと自己紹介する。
彼が窓の遮光機能を操作すると、半透明になった窓から、雨に濡れた中庭の木々が見えた。入院した記憶がないのは、脳腫瘍の切除手術を受けたからか。
ガブリエルが、そうだった。脳の手術をすると、どうしても記憶の欠落が生じる。いつも聡明な彼が、病床で迷子のような顔をしていた。
『お兄ちゃん、だあれ?』
彼の方が、ぼくより二つ年上だったのに。ウリエルと共にぼくを説得して、脱出計画に引き込んでくれた、しっかり者。
それが、最後には幼児に戻ってしまい、絵本を読んでくれとか、歌を歌ってくれとか、病院の女性スタッフに甘えていた。彼女を母親だと思っていたのか。バイオロイドに、母親はいないのに……
「きみは火傷と脳挫傷で、かれこれ五日ほど入院しているんだ。でも、心配はいらない。必要な治療はもう済んでいるから、午後には退院できるよ。二、三日はおとなしくしていてほしいが、後は普通に生活して構わない。塗り薬だけ出しておく。火傷の跡は、徐々に薄れるからね」
火傷? 何だろう? いつ、そんな怪我をしたっけ?
やはり、記憶の断絶があるらしい。
医師はぼくを診察し、回復は順調だと断言すると、楽しげに付け加えた。
「いやあ、本物の〝リリス〟と握手できるとは思わなかったよ」
え。
「映画以上の美人だったね。思っていたよりずっと、穏やかで控えめな人だったし。一生忘れないよ。守秘義務があるから、家族にも話せないのが残念だけどね」
ぼくが目を見開いたので、医師は説明を加えた。
「食事が済んだら、面会できるよ。彼女たちは、きみが目覚めるのをずっと待っていたんだから」
夢ではなかった。
それどころではない。
何という馬鹿だったのだろう、ぼくは。大の男をぽんぽん投げ飛ばす姿、あれだけで〝リリス〟と察するべきだった。
そもそも、リリーとヴァイオレットという名前の組み合わせは、映画でも小説でも、お馴染みだったではないか。もちろん、本当の名前ではなく、コード名のようなものだというけれど。
でも、まさか、本物の〝リリス〟が、そこらを気軽に歩いているなんて。その上、ぼくなんかのために、貴重なバカンスの時間を割いてくれるなんて。
緊張のあまり、胸が苦しい。
夢なら、夢でよかったのに。
これから現実のリリーさんと会って、さようならと宣告されるくらいなら、夢の方がましだった。谷底へ突き落されるようなものだ。焦がれても届かない人に、最後の日まで焦がれ続けるなんて。
いや、それでも、会わずにはいられない。伝えなくては。貴女に会えて、時間を共有できて、本当に嬉しかったと。
ぼくにはきっと、人生で一度きりの恋。
それを知らないままで終わるより、ずっとよかった。
後に悲しさが残るとしても、それは、会えたからこそ生まれた感情。心が凍りついたまま死ぬより、ずっといい。
だから、精一杯、平気なふりで、お別れを言わなくては。

美青年の看護師に世話をしてもらい(後で正体を知った)、着替えと食事を済ませた頃合い、リリーさんがやってきた。
目が覚めるような、美しいロイヤルブルーのワンピース姿。金褐色の長い髪は、背に垂らしている。耳たぶには、大粒の真珠。
美しい顔が曇って見えるのは、ドレスの色のせいか、窓の外の雨空のせいか。
「ミカエル、ごめんね」
リリーさんは真っ先にそう言い、椅子から立ったぼくの手を取った。温かく大きな手。記憶の中の感触と同じだ。間近に見る青い瞳も、記憶の通り。
「巻き添えにしてしまって、本当にごめんなさい。あたしが馬鹿だったのよ。わざわざ、自分の正体をさらすような真似をして」
ああ、そうか。
リリーさんは、ぼくが怪我をしたことで、悪いと思っているのか。
リリーさんでなければ、あの瞬間、ぼくを抱いて飛び降りることなどできなかったのに。普通の人間なら、岩だらけの川に墜落して、即死だったはず。
しかし、今ではもう、リリーさんにも、ぼくが何者かわかっているだろう。罪のない子供ではなく、恐ろしい決断をした反逆バイオロイドであると。
「ぼくこそ、申し訳ありませんでした……お荷物になってしまって。それに、自分のことをちゃんと言わなくて……」
リリーさんは、あっさり首を横に振った。
「あたしは知っていたのよ。最初から。だって、きみに会うために、この星に来たんだもの」
「えっ?」
ぼくらは偶然に出会ったのではない……というのか?
「全部、説明するわ。でも、まず、ここから出ないと」
それは、まさか、貴女と一緒にということですか?
「世間的には、きみは一昨日『治療の甲斐なく死んだ』ことになっているの。今日は郊外の墓地で、きみの葬儀があるのよ。きみの知り合いは、みんな参列しているわ」
唖然とするぼくに、リリーさんは言う。
「お別れを言いたい人もいるだろうけど、それはあきらめてね。《ルーガル》に追跡されないためには、ここで一度、死んでもらう必要があるの」
リリーさんに肩を抱かれるようにして、病院の地下で車に乗せられ、外の街路に出た。司法局が手配してくれたそうで、一般の職員がぼくらの姿を見ることはなかった。対外的には、ぼくは死んで葬儀場に送られたことになっている。
雨に打たれた街路の桜は、半分散りかけていた。道路のあちこちに、淡いピンクの花びらが散り敷いている。
外からは中を見られない半透明の窓なので、誰かに見咎められる心配はない。ぼくは呆然としたまま、過ぎていく市街の風景を眺めた。
三年近く暮らしたこの星と、今日でお別れとは。
かりそめの職場に未練があるとは思っていなかったが、それでも、親切にしてくれた人たちが、ぼくの葬儀に集まっていることには、気が咎めた。彼らにとって、ぼくは最後まで〝気の毒な少年〟のままなのだ。
すみません、さようなら。
ごめん、ウリエル。
ごめん、ガブリエル。
きみたちの墓がある星を、出ていくよ。
そして、たぶん、二度と戻らない。
一緒に車に乗っていたのはリリーさんと、相棒のヴァイオレットさんだった。それと、有機体アンドロイドのナギ。紺のスーツが似合う、黒髪の美青年だが、心を持たない人形であるという。同型の人形が何体も、リリーさんたちの助手として動いているとか。
機密保持のため、病院でぼくの世話をしてくれたのも、ナギだという。
「よろしくね、ミカエル」
と挨拶してくれたヴァイオレットさんは、ぼくより少し背が高いだけの、小柄で上品な女性だった。
金茶色の瞳と白い肌。長い茶色の髪は、きちんと結い上げている。クリーム色のワンピースがよく似合い、名画のように繊細な風情だ。とてものこと、長年、違法組織と戦ってきた闘士には見えない。
だが、リリーさんが剛勇ならば、この人は理知。〝リリス〟の活躍の半分は、このヴァイオレットさんのおかげだという。
宙港へ向かうドライブの途中、リリーさんが事情を話してくれた。上空からの砲撃を仕掛けた犯人は、わかりそうにないという。
「外部から、船の管理システムが乗っ取られていたの。中央の警備システムは、弱点が多いからね。でも、どうせ、あたしが狙われたに決まってるわ。もう二メートルずれてたら、あたしたち二人とも、蒸発してた。ほんの少しの大気の揺らぎのせいで、命拾いしたわ」
高出力レーザーの一撃か。民間船も、自衛のための武器は装備している。それを、何者かに利用されたのだ。
危なかった……ぼくに関して言えば、あの時、瞬時に蒸発していても、幸せだったかもしれない、と思うが。
リリーさんと一緒に死ねるのだったら、この上なく贅沢な死に方ではないか?
いやいや、リリーさんは〝正義の味方〟として、この世界に必要とされている人だ。死ななくて良かったに決まっている。
「じゃあ、やっぱり大吉ですよ」
ぼくが笑って言うと、リリーさんはきょとんとする。
「ほら、おみくじです」
「ああ……」
「リリーさんは、大凶の運勢を跳ね返せる人だから、存在そのものが大吉なんですよ。いつだって、天が味方しているんです。だって、地上に降りた女神なんですから」
ようやく、リリーさんの顔に苦笑が上った。
「まあ、そういうことにしておこうか……それで、ミカエル、これからのことなんだけど」
そらきた。
ぼくは別の星に移され、別の名前でひっそり、残りの日々を過ごすことになるのだろう。この人は義理堅く、別れの挨拶をするために待っていてくれたのだ。宙港にはきっと、出迎えの司法局員か誰かが待っている。そこまでの短いドライブが終わったら、さようなら。
「……市民社会はあきらめて、辺境に出ない? 実はもう、勝手に預け先まで決めてあるんだけど」
「辺境?」
やっと逃げ出してきた世界に、戻れというのか?
ぼくがぽかんとしていると、リリーさんは真剣な顔で言う。
「一緒に来てほしいの。ミカエルの治療は、辺境でなら、何とかなるはずだから。司法局も、了解済みよ。治療が済んだら、後は好きなようにすればいいから」
一緒にって……リリーさんと一緒に辺境へ?
「ぼくの好きにって、どういう……?」
「仕事とか、生活場所とか。何でも、ミカエルのいいようにすればいい。健康になったら、何でもできるでしょ。辺境でひっそり生きていけるように、あたしが知り合いに頼んであるから」
つまり、ぼくは生きられるのか? 健康体になって? しかも、一人で辺境に放り出されるわけではないと?
そんな……そんなことが本当に……? 司法局は、あくまでも遺伝子操作を許さないのではなかったか?
怖い。信じるのが怖い。そんな都合のいい話、あるとは思えない。
でも、だけど……
この人は〝リリス〟なのだ。軍人も司法局員も畏怖する英雄。辺境にどんな伝手を持っていても、不思議ではない。
「どうしても戻りたかったら、市民社会に戻ることもできると思うの。顔や名前を変えてね。もちろん、市民社会のルールを破ったことになるから、そう簡単には許してもらえないと思うけど。いずれ、次の局長の代になったら、司法局の空気も変わるかもしれないし。でもそれは、今後、気長に考えればいいでしょ? ミカエルはまだ、若いんだもの」
信じられない。
夢ではないのか。
リリーさんは、ぼくに未来をくれようとしている。
ウリエルやガブリエルには開かれなかった扉が、ぼくの前に開く。
「いいんですか? 遺伝子治療はご法度のはず……」
だが、リリーさんは確信的に言う。
「ミカエルは元々辺境生まれなんだから、そこまで市民社会に従わなくていいのよ。違法だろうが何だろうが、治療法はあるんだから。脳腫瘍なんかで死ぬ必要、これっぽっちもないでしょ」
何人もの関係者が、ぼくの命を救う方法を探して、司法局長を動かしたのだと知った。市民社会は、ぼくを見捨てたわけではなかったのだ。ごく一部の、お節介な人々のつながりが、リリーさんをぼくの元へ連れてきてくれた。ウリエルとガブリエルを救うのには、間に合わなかったけれど……
いや、彼らが死んだからこそ、最後に残ったぼくが、同情を受けられたのか。
それは法の公正にもとるだろうが、ぼくにはもう、感謝しかない。二人には心の中で詫び、有り難く、その申し出にすがることにした。
「ありがとうございます……全て、お任せします」
もし、これから一年か二年ではなく、二十年も三十年も、もしかしたら、もっと長く生きられるのなら。
そうしたら、何でもできる。
市民社会に恩返しすることだって、リリーさんのために何かすることだって、できるはずではないか。
世界は鉛色の雲と冷たい雨に閉ざされていたが、ぼくは、頭上に青空が開けた気分だった。
そう、雲の上はいつも晴れ、というではないか。
自殺などしなくて、よかった。
自棄でテロリストにならなくて、よかった。
今日まで生きていて、よかったのだ。
広大な宙港に着くと、発着場の片隅に小型艇が待っていた。ぼくらは車ごと艇に乗り入れ、そのまま離陸したのである。

「お世話をかけます、ヴァイオレットさん」
栗色の髪の美少年は、しおらしく頭を下げた。わたしたちの船は既に、ミカエルのいた植民惑星を離れている。
民間船として登録してあるけれど、実際には、辺境の最新技術を詰め込んだ高速戦闘艦だった。途中で偽装のために他の船に乗り換えて、辺境の宇宙を目指す予定。いつでも使えるように、あちこちに最新鋭の船を隠してある。
特に、故郷に向かう時は、厳重に航跡を隠さなくてはならない。わたしたちと違法都市《ティルス》の関わりを、第三者に知られるわけにはいかないのだ。
「何も気を遣わなくて、いいのよ。あなたは病み上がりなのだし、お客さまなのだから、ゆっくりしてちょうだいね」
優しく言ったつもりだけれど、やはり何か、不穏な気配があったのだろう。
「はい、ありがとうございます……」
ミカエルは戸惑ったような、曖昧な顔になっている。わたしが敵意を隠していること、気がついたかしら? 紅泉がこれほど入れ込んでいるのだから、賢い子であることは間違いない。
それならば、なおさら、余計なことは言わずにいるだろう……何に気がついたとしても。
「じゃ、部屋に行こ」
紅泉はさっそく、ミカエルをひょいと抱き上げて、船室に向かった。
「リリーさん、ぼく、歩けます。そんな、重病人じゃないんですから」
と本人は身をよじって恥ずかしがるけれど、紅泉はおおらかなもの。
「本当は、もう何日か入院していた方がよかったのよ。ちょっと無理して、早目に連れ出してしまったから、少し休んだ方がいいわ。食事時になったら起こすから、ね」
紅泉はミカエルを『保護すべき子供』として扱うことに決めたらしい。それがかえって、わたしには気がかりだった。
これまでの紅泉なら、駄目元でがんがん、王子さまを口説いたはず。
相手が少年だからといって、遠慮する性格ではない。ミカエルの成長を待つ時間は、たっぷりあるのだから。
でも、今はあえて、ミカエルとは『友達』のままでいようとしている。それが、ミカエルのためだと考えて。
ミカエルもまた、何か言いたげな熱い目で、紅泉を見上げている。けれど、彼には彼の引け目があるらしく、本当の気持ちは言うまいと努力しているみたい……
二人が海や神社でデートしている様子を、わたしは偵察鳥からの監視映像で見ていたから、わかる。
最初から、この二人は惹かれ合っているのだ。
恋という池にどぼんとはまる音が聞こえるくらい、明白だった。お互いに、相手を理想の異性と思い、奇跡的な出会いを果たしたと感じている。
もしかしたら、途方もなく相性のいい組み合わせなのかもしれない。
太陽と月。
動と静。
この世界が地獄だと知っていて、なおかつ、逆らう気力を持っている部分も共通している。
出会ってしまったのだ。たぶん。魂の呼び合う相手に。
でも、わたしは、余計なことは言わない。刺激を与えて、火を燃え上がらせてしまったら大変だから。
放っておけば、このまま冷める……そう祈りたい。
ミカエルを麗香お姉さまに預ければ、それで紅泉は〝正義の味方〟の義務を果たしたことになる。そして自分の仕事に戻り、ミカエルのことは、たくさんある思い出の一つになる。ちょっとほろ苦い、失恋の思い出に。
紅泉の人生の伴侶は、わたしだけでいい。
こんな子供なんかに、わたしの位置を譲るつもりは、微塵もない。
これまで紅泉を支えてきたのはわたしだし、これからも生涯、そう。わたし以上に役に立つパートナーは、誰もいない。
もしいても、追い払う。
ミカエルもいずれ、立派な青年になるだろうけれど、その頃には、他に可愛い女の子を見つけているはず。そして、紅泉のような、危険に満ちた人生を送る女とは、一緒にいられないとわきまえるはず。
二人がお互いに遠慮しているなら、その遠慮がはがれ落ちないよう、さりげなく寒風を浴びせてやればいいのよ。
数日が過ぎると、ミカエルはかなり元気になってきた。担当医から申し送りを受けているので、経過はきちんと見ている。火傷の薬も朝晩、塗ってやっている。背中の方は、本人には塗りにくいから。
本当は、紅泉が塗りたがっているのを知っているけれど、遠慮してわたしに任せているから、知らん顔して引き受けている。
「すみません、お世話をかけます、ヴァイオレットさん」
ミカエルが申し訳なさそうな顔をするのを、わたしはすまして受け流す。
「いいのよ、リリーが誰か拾うのは、いつものことだから」
「そう……なんですか?」
ほうら、てきめん不安そうな顔になったわね。
「これまでも、訳ありの子を何人も世話してきたわ。リリーはすぐ同情して、引き取りたがるのよ。どうせ、面倒みきれないくせに」
いけない……ずいぶん意地悪な口調になってしまったわ。意地悪すぎると、逆効果になる。
でも、ミカエルにも、もうわかっているでしょう。わたしが歓迎していないことは。
もちろん、彼はわたしに遠慮して、おどおどしていた。
「大丈夫です、ヴァイオレットさん」
「どうかご心配なく、ヴァイオレットさん」
と身をすくめている。
それでも、肉体の回復は早かった。何しろ若いし、バイオロイドは丈夫にできているので、脳挫傷の方はすっかり治癒している。火傷の跡も、日に日に薄れていく。
ただ、気持ちの方は沈んでいるようだった。紅泉と同じ船にいられるのは嬉しいけれど、それはわずかな日数のこと。目的地に着いたら、置き去りにされると知っている。
同情なんか、しないわ。
あなたは紅泉に愛されて、永遠に清らかな、思い出の王子さまになるんだもの。
わたしはそうではない。ただの従姉妹。家族の一員。
何十年、何百年生きても、紅泉がわたしに恋焦がれてくれることなんて、ありえないのよ。
でも、その代り、いつまでも、どこまでも一緒にいられる。
わたしはそれで、満足しようとしているの。
ちょっとばかりあなたに冷たくしたって、そのくらい、我慢するべきでしょう。
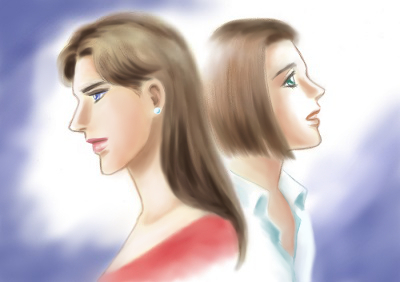
今はまだ、紅泉とミカエルの間に壁がある。
食事時などに、つい、顔を見合わせてしまった時には、どちらもさっと視線をそらす。ラウンジのソファに座る時も、ちょっと離れた斜めの位置を選ぶ。世間話をしても、それが深い話にならないよう、いつでも逃げられる身構えでいる。
互いに、
(自分は、相手に相応しくない)
と思っているからだ。うっかり熱い視線を向けてしまったり、本音の声で語ったりしないよう、気をつけている。
でも、そんな壁、何かの拍子に崩れてしまうかもしれない。心はどうしても、言葉や振る舞いに表れる。隠そうとしても、隠しきれない。
もし、二人が、相思相愛の状態になってしまったら……
わたしは、ミカエルを殺すかもしれない。うまく事故や事件に見せかけられる時が来たら。
でも、その事実を、後から紅泉に知られたら……?
考えたくない。紅泉に嫌われ、遠ざけられるなんて。
だから、わたしにできるのは、ミカエルが健康を手に入れ、新しい人生に夢中になって、紅泉を忘れますように、と祈ることだけ。
誰も知らなくていい。
わたしが魂に、地獄を隠していることなんて。
この世界に絶望しているのに、紅泉を愛している。
愛している限り、幸せ。
でも、その幸せが、いつか終わることを知っている。
わたしが独占したいと願っている紅泉は、何よりもまず〝正義の味方〟なのだ。わたしのことも、ミカエルのことも、その他の誰かのことも、みんな公平に気にかける。愛おしむ。
そういう紅泉だから、わたしはついていくのだ。いつか、一緒に死ねる時まで。
わたしたち二人を、そうとは知らず苦しめている紅泉は、遠慮しつつも気を遣い、ミカエルが快適に過ごせるようにしていた。
「ミカエル、お昼は何が食べたい?」
「ミカエル、何か足りないものは?」
「ミカエル、この映画見たことある?」
彼は彼で、はにかみながら、何でも素直に従っていた。
「リリーさんのお好きな料理は、何ですか? ぼくも、それにします」
「リリーさんのお薦めの作品なら、ぼくも見たいです」
ミカエルは色白だから、紅泉に構われて嬉しいと思う時は、頬が紅潮するのがよくわかる。紅泉の後ろ姿を見送る時さえも、瞳が憧れに潤んでいる。口に出さない分だけ、主人を慕う子犬のように、一途に紅泉を慕っているのがわかってしまう。
紅泉だって、その雰囲気は察しているはず。ミカエルを口説こうと思えば、いくらでもできる。
それでも紅泉は、あえて踏み込もうとしなかった。
(ミカエルは、あたしに感謝しているだけ)
そう決め込んで、『親切なお姉さん』の立場を守るつもりらしい。
不器用なのは知っていたけれど、ここまでとは。
もしも紅泉が一言、ミカエルに対して何か言えば、ミカエルは遠慮も何も捨てて、紅泉の腕に飛び込むでしょうに。
でも、そんなことになったら、わたしの居場所がなくなる。
ミカエルが賢い男の子であるだけに、なおさら危険なライバルだった。わたしの代わりにパートナーになろうなんて気を起こされたら、たいへん。
早く、故郷の麗香お姉さまの元に送り届けて、〝過去の人物〟にしてしまわなくては。
それにしても、紅泉ときたら、本当に懲りない人。何度失望しても、また新たな王子さまに期待をかけてしまうのだから。この調子では、またいつ、次の王子さまを見つけてくるか。
でも、それが〝永遠の若さ〟の呪いなのだ。
肉体が若いせいで、いくら経験を重ねても、知恵を蓄えても、おそらく、真の老成には至らない。
それがいいことなのか、悪いことなのかはまた別の問題。
紅泉もわたしも強化体だから、老いることなく、このまま数百年は生きられる。その年月の間に、おそらくは、数千年か数万年を保証する技術が育つ。
それはもしかしたら、生身の肉体を捨てる『超越化』の道かもしれないけれど、可能性としては、永遠に手が届くのだ。
一億年、百億年、更にその百億倍。
そうなってもまだ、人類は、愚かな争いを続けるのかもしれないけれど……
そう、〝天然の戦闘用強化体〟である男という種族が存続している限り、人類社会は、いつまで経っても平和にならない。
彼らの存在意義は、とうの昔に失われているのに。
彼らを絶滅させられる方法があれば、わたしは喜んでそうするだろう。
いいえ、別に絶滅しなくてもいい。紅泉の王子さまになる男が、いないままならば。
だって、人類社会が女だけになったら、紅泉は世界中の女に憧れられてしまうから、競争率が高くなりすぎるもの。

幸せなのに、苦しくなる。
毎日、リリーさんの姿を見られて嬉しい。会話できて楽しい。それなのに、別れの日が近付いている。
自分でも落ち着かず、何度も無駄に舞い上がったり、落ち込んで絶望したりする。
あと十日。あと一週間。あと三日。
船は中央星域を離れ、無法の辺境に入っていた。様々な違法組織の占有する領域を避けながら、目的地に向かっている。
他組織の艦隊と行き合うこともあるが、こちらも無人の護衛艦隊に囲まれているので、トラブルは起きない。互いに無視して、通り過ぎるだけ。
リリーさんがぼくを預ける先に選んだのは、リリーさんが信頼する、身内の女性だという。何でも、リリーさんやヴァイオレットさんの遺伝子設計をした人物だとか。
「姉さまは辺境でも有数の科学者だから、ミカエルの治療は任せて大丈夫。姉さまの元で、いい子にしていてね。またそのうち、暇ができたら遊びに行くから……」
「はい」
リリーさんは司法局から必要とされている身だから、次に長い休暇を取れるのはいつのことか、わからない。その時には、ぼくのことなんか、綺麗さっぱり忘れているかもしれない。
でも、ぼくは、寂しいとも、必ず来て下さいとも言えない。
だって、何の権利があるというのだ。リリーさんは、旧友の司法局長に頼まれたから、ぼくを送り届けてくれるだけ。〝気の毒な子供〟に対する好意にすぎない。
だけど、もし、いつか……
ぼくが成長して一人前の男になり、十分な準備ができたら、リリーさんのために何かできるだろう。新鋭艦を設計するとか、秘密兵器を作るとか、情報集めや裏工作をするとか……そういうこと。
そう思って、自分を励ましていた。脳腫瘍から解放されるだけで、十分に素晴らしい幸運なのだから、この上、贅沢やわがままは言えない。リリーさんは、ぼくなんかに手の届く人ではない。
とうとう、明日には目的地に到着する、という日になった。夕食の後、ヴァイオレットさんは先に自室に引き上げてしまったので、ぼくはリリーさんと二人、ラウンジに残って話している。
目の前のテーブルにはチョコレートの盛り合わせと、二杯目の紅茶。エメラルド色のミニドレスを着たリリーさんは、親切にあれこれと言ってくれる。
「ミカエルはきっと、姉さまに気に入られると思うわ。姉さまから色々教わって、ゆっくり進路を決めればいいのよ」
「はい、そうします……ぼくが、ご迷惑でなければいいのですが」
「そんなこと、心配しなくていいの。ミカエルは、いい子だもの。姉さまだって、可愛がってくれるはず」
そうだろうか。
二百人あまりを殺して、そのことを、微塵も後悔していないぼくなのに?
確かに、反逆の計画を立てたのは、二つ年上のウリエルとガブリエルだった。ぼくは後から引き込まれたのだが、積極的に協力したことは間違いない。
それに、ぼくはラファエルを見捨ててきた。同じ部署に配属され、ぼくを慕ってくれた年下の少年を。
『ミカエル、ありがとう』
『ミカエルは、何でもよく知っているんですね』
『ミカエルは、この基地の外に出たことあります?』
『海って、本当に塩辛いんでしょうか?』
『地震って、本当に地面が揺れるんでしょうか?』
素直な彼を陰謀に引き入れるのは、危険が大きかった。仲間が増えれば、それだけ秘密が漏れる可能性も高くなる。
あの子はあの日、基地のどこかで冷たくなっていたはずだ。ぼくに裏切られたことも知らないで。
後悔するとすれば、そのことだけ。
それはこれまで、誰にも言わないできた。同情されても、事実は変わらない。ぼくは他人を犠牲にして、生き延びた。これからだって、生き延びるつもりだ。病気さえ治れば、何でもできる。
再教育施設では、ぼくたちの知力は、人間の天才レベルと評価された。たぶん、そうなのだろう。科学技術局でも、周囲の研究員たちは、たいした能力を持っていなかった。中央だろうが辺境だろうが、ぼくならば、そこに適応して生きられる。
それに、今度からは、心の中にリリーさんを住まわせることができる。それだけでも、孤独がうんと楽になる。そのはずだ。
「そういえば、ぼくたち、滝を見なかったですね」
「ん? ああ、そうか。吊り橋から落ちて、そのままだったね」
あそこから百メートルも上流に行けば、滝にぶつかっていたはずだ。あの狙撃がなかったら。もう二度と、あの場所に戻ることはない。
「今度、どこかのリゾート星に行こう。そしたら、滝でも何でも見られるから」
「いいですね。楽しみです」
そんなこと、本当にあるんだろうか? 別れたらもう、二度と会えないのでは? いつかまた、というのは、別れをごまかす修辞に過ぎないのでは?
「お下げしますか」
ナギが来て、空になったカップを運び去った。ぼくもそろそろ、部屋に引き取る頃合いか。
その時、ぽつりと、リリーさんがつぶやいた。
「ああ、今日まで本当に楽しかった……寂しくなるわ。ミカエルがいない毎日なんて」
どきんとして、硬直してしまった。
本気にするな。社交辞令だ。たいした意味はない。
なのに全身が熱くなり、また冷たくなり、がくがくと震えがくる。
ぼくだって、言いたい。リリーさんと別れるのは、寂しくてならないと。
本当は、泣いてわめいて、すがりたい。
何でもしますから、傍に置いて下さいと哀願したい。
リリーさんがぼくを預け先に置いて去ってしまったら、毎日、どれほど苦しいか、今からわかる。毎日、中央のニュース番組を見て、〝リリス〟の活動の様子がわからないかと、そわそわ、やきもきするだろう。
期待を持つということは、すっかりあきらめるより、はるかに苦しいことだ。あきらめられたら、楽になるのに。
でも、何にも未練を持たなくなったら、それは、生きながら彼岸にいるのと同じこと。悟りなんか開くのは……まだ遠い未来でいい。苦しんでいることが、生きていることだ。
「ぼくも……ぼくだって……」
言うだけは、言ってもいいのではないだろうか。もう、明日でお別れなのだから。
「寂しく、なります」
どうせ、失うものは何もない。精々、ヴァイオレットさんに、余計に嫌われるくらいだ。
あの人こそ、リリーさんのためだけに生きている。だから、リリーさんを慕うぼくが、目障りで仕方ない。言葉は丁寧だけれど、針のような敵意が、ちくちくとこちらの肌に突き刺さる。
だけど、もはや二度と会わないかもしれない人に嫌われても、どうということはない。リリーさん以外の人間のことは、ぼくにとって、かなりどうでもよくなっている。ぼくには、リリーさんのような人類愛は持てないから。自分が憧れるような相手でなくては、意味を持たないのだ。
「このまま、リリーさんと一緒にいられたら、どんなに嬉しいか……たとえば、助手のような形でとか……」
リリーさんが、すっと顔を上げた。何か怒ったかのように、強い瞳でまじまじとこちらを見る。
ぼくはつい、目を伏せてしまった。何か、まずいことを言ってしまったのだ。見られていると思うと、ますます顔が熱くなる。きっと、耳まで赤くなっている。絶対、変に思われている。
「……ミカエル、あたしのこと、嫌いになってない?」
ぼくは驚いて、顔を上げた。
リリーさんは青い目をこちらに向け、真剣に返答を待っている。
そう、いつだって、真剣に向き合ってくれる人だ。だからこそ、正義の味方。ヴァイオレットさんから飛んでくるような冷たい言葉、リリーさんからは一度も聞いたことがない。
「まさか、貴女を嫌うなんて、どうしてですか」
毎日、毎日、新たに好きになるのに。
「だって、あたしのせいで、死にかけたのよ」
ああ、吊り橋の上で、狙撃されたことか。
そんなこと、リリーさんのせいではない。この世にたくさんいる、つまらない悪党たちのせいだ。
「リリーさんが来てくれなければ、どうせ、脳腫瘍で死んでいました」
「ううん。あたしがいなくても、ミギワが何とかしてくれたはず。あたしはただ、バカンスのついでにミカエルを拾いに行っただけ」
そうだろうか。
市民社会が、お荷物のバイオロイドのために、そこまでお節介を焼いてくれるものだろうか。
部下から嘆願を受けたクローデル局長だって、リリーさんというあてがなければ、ぼくを誰に託したというのだ。市民社会は、辺境の違法組織を全否定しているのだから。
「でも、ぼくは嬉しかったです……貴女と海で遊んで、神社にお参りして、山道を歩いて、どんなに楽しかったか」
リリーさんは、ぼくが科学技術局の宿舎に置いていた私物も、こっそり引き取ってきてくれた。わずかな写真や、日記の類いだ。全て過去のものとして、置いてきてもよかったのに。
「貴女は、ぼくの女神です。たとえ一緒にいられなくても、一生、貴女を愛します」
ああ。
言ってしまった。とうとう。
せめて、尊敬します、と言えばよかったのに。軽々しく軽薄なことを言う、と思われたかもしれない。
するとリリーさんは、怒るのをこらえるような顔をした。ぼくはやはり、礼儀に外れたことを言ったのだろうか?
でも、それでも……言わずにいられなかったし、言ったこと自体は後悔しないと思う。だって、二度と会えない可能性が高いのだから。
「ミカエル、あたし、言うのは卑怯だと思って、黙ってたんだけど……」
「はい?」
深刻な口調だ。何か叱られるなら、それでいい。リリーさんがぼくに与えてくれるものなら、叱責でも何でも受ける。
「きみはまだ子供だから……いくら知能が高くても……あたしの感情を押し付けるわけにはいかないと思って……」
不思議だ。何の遠慮だろう。
「何でも言って下さい。どうせもう、明日でお別れですし」
「うん……」
リリーさんは難しい顔のまま、困りごとのように言う。
「あたし、ミカエルが好きなの。錯覚かもしれないと思って、冷静になろうとしたけど、やっぱり好き。毎日、好きになる」
え。
「本当は、離れたくない。置いていくのはいや。たとえ、姉さまの元でも」
ええっ。
「ミカエルにとっては迷惑だろうから、あきらめようと思ったんだけど……ずうっと努力してきたんだけど……でも……もし、ミカエルが本当に、そう思ってくれるなら……もしかして……あたし、あきらめなくてもいい?」
ぼくはソファから身を浮かせた。
リリーさんは正直な人だ。圧倒的に強いから、自分を飾ったり、嘘をついたりする必要がない。
つまり、これは真実の言葉。
リリーさんが、ぼくのことを好いてくれる。
離れたくないと思ってくれる。
地下から溶岩が噴出するように、心が爆発しそうになって、どうしたらいいか、わからない。
「ぼくだって……」
ああ、どういえば伝わるだろう。
「ぼくだって、リリーさんが大好きです。離れたくなんか、ありません。ずっと、ずっと一緒にいたいです。ただ、でも、今のぼくはこんなざまで、リリーさんのお荷物にしかならないから」
吊り橋が切れたくらいで、恐怖で気絶するなんて、情けない自分が許せない。リリーさんは毎年何回も、何十回も、命の危険にさらされているはず。足手まといになるようでは、ついていく資格なんかない。だからヴァイオレットさんも、ぼくを冷ややかな目で見ている。
「だけど、十年、いえ、五年したら、何かの役には立てるかも……もし、ぼくを助手として使って下さるのなら……裏方の雑用くらいなら、きっと……」
リリーさんは立ち上がり、前へ踏み出して、がばっとぼくを引き寄せた。あっという間に、胸に抱き込まれてしまう。いつもの、甘い百合の香り。弾力のあるふくらみ。ぼくの頭の上で、アルトの声が言う。
「ミカエル、あたしと結婚しない?」
え。
まさか。
ぼく、上ずって、何か聞き間違いを。
だってそんな、いくら何でも。
「ううん、今は婚約だけでいいの。結婚を前提として付き合う、っていうことよ。ミカエルが大人になって気が変わったら、離れてくれて構わないから!!」
世界がぐるりと転回したようで、目眩がする。恐ろしい崖の下をのぞき込んでいたら、背中に羽が生えて、ふわりと宙に浮き上がったみたいに。
「あの、もう一度……説明を……」
ぼくは恋しさのあまり、都合のいい幻聴を聞いたのではないだろうか。
「あたし、ミカエルと恋人同士になりたい。ずっとそう思ってたの」
リリーさんの明晰な言葉が届く。空を飛べる羽をもらったようなものだ。高い空から見れば、地上の崖なんか障害でも何でもない。
「ぼくみたいな子供を、リリーさんが、本気で相手にしてくれるんですか?」
リリーさんは何かを振り払うように、頭を横に振る。
「年齢は関係ない。ミカエルはいつも、あたしの聞きたいことを言ってくれたわ。あたし、ミカエルといると嬉しくて、舞い上がってしまうの。今は子供でも、五年経ったら青年になるでしょう? あたし、ミカエルの成長を待てるわ」
気がついたら、ぼくは顔中にリリーさんのキスを受けていた。頬に、額に、そして唇の端に。まるで磁石のように、互いに引き合ってしまう感じだ。
歓喜が極まると、苦痛と変わらなくなるのだと知った。幸福すぎて、心臓が苦しい。いま、この瞬間に、宇宙が止まってしまえばいいのに。
「貴女が好きです……一生、傍にいさせて下さい。何でもします」
熱に浮かされたように、自分が言うのを自分で聞いている。他人が言うのを聞いたら、馬鹿みたいだと思っただろう。
でも、今はこれが真実の気持ちだ。生きていてよかった。生まれてきてよかった。たとえ、誰を殺しても。
「ありがとう……嬉しい。あたしも愛してる」
リリーさんは身をかがめて、繰り返しキスしてくれた。甘くて柔らかい唇だ。何だかむずむずしてきて、じっとしていられないような感じがする。必死に抑えつけていないと、躰が内側から爆発してしまいそうな。
もしかして、これがその……発情期のきざしなのか!? この先に、もっと深い快楽の世界がある!? ぼくの肉体が成長して、青年になったら、これまでは知識でしか知らなかった世界に踏み込めるのか!?
「約束よ。早く大人になってね。あたし、待つから」
何だか、待ちきれなくなってきた。ぼくが大人の男になったら、ぼくの方から腕を回して、リリーさんを抱けるのか。そうなったら……何だかもう、自分が期待で破裂してしまうような気がする。
ああ、大人になりたい。早く、早く、たくましい大人の男に。
翌朝、ぼくたちは朝食の席で、ヴァイオレットさんに打ち明けた。昨夜のうちに、婚約したことを。
ヴァイオレットさんは衝撃を受けたようで、しばらく絶句していたけれど、気絶したり、悲鳴を上げたりはしなかった。強い自制心を持っている人だ。やがて、茶色い前髪のかかる額に、ほっそりした白い指を当てて言う。
「そういうことなら……わかりました。別に、初めてのことではないし……たぶん、最後でもないでしょうから……好きにすればいいわ」
決して祝福の態度ではなかったけれど、リリーさんは気にしないようで、からからと笑う。
「あたし、前にも何度か、婚約騒ぎを起こしてるからね。でも、ミカエルがいてくれるなら、もう、新しい王子さまはいらないから」
ぼくが、リリーさんの王子さまになれる。
無上の名誉であり、歓喜であった。
それならば、どんな努力でもしよう。
ぼくにできる全てのことをして、リリーさんを守る。そうすれば、ぼくの知能にも意味ができる。
ヴァイオレットさんにも、いつか、ぼくが役に立つことを認めてもらえばいい。リリーさんに助手が二人いても、悪いことはないだろう。それでもなお、本物の祝福はもらえないかもしれないけれど。
「ふつつか者ですが、末永くよろしくお願いします」
ぼくが頭を下げたことに対して、ヴァイオレットさんはかなり冷淡だった。
「ミカエル、あなたの人生は、まだ始まったばかりよ。早々に、約束事に囚われる必要はないんですからね」
何か困難に遭ったら、ぼくがすぐさまリリーさんを置いて逃げる、と思うのだろうな。きっと、前の男たちがそうだったのだ。
でも、ぼくは違う。だって、逃げる先なんかない。リリーさんが、この宇宙で唯一の太陽なのだから。
ぼくは進んで囚われたいのだ、リリーさんに。そうでなかったら、この世に生まれた意味などないではないか。
「ヴァイオレットは男嫌いでね。あたしが恋愛騒ぎを起こすと、いつも機嫌が悪くなるのよ」
リリーさんは、笑いながら話してくれた。もちろん、側にヴァイオレットさんがいなくなってから。
「辺境で育つと、男の悪い面を見すぎるから、無理ないんだけど。ミカエルに慣れるまで、少し時間がかかるかもね。本当は、あの子もいい男に巡り会って、幸せになるべきなんだけど」
しかし、ヴァイオレットさんの方は、自分の人生に男など、これっぽっちも必要としていない。
そのことは、この船旅の間に、よくわかっていた。ヴァイオレットさんの宇宙には、リリーさんしかいないのだ。少女の頃から、ずっと。ぼくは、二人の間に割り込んだ邪魔者に過ぎない。
でも、それは、ぼくがリリーさんに言うべきことではなかった。ぼくはただ、いつかヴァイオレットさんに存在を許してもらえるよう、努力するだけ。
ぼくがリリーさんの役に立つことがわかってもらえれば、きっと、敵意も少しは薄らぐだろう。
だって、リリーさん本人は、あくまでも、男性の王子さまを求めているのだから。

旅の終着点は、違法都市《ティルス》だった。
人口百万人と言われる、歴史の古い小惑星都市だ。バイオロイドではない、本物の人間は、その一割ほどだというけれど。人口の十倍のアンドロイドが動いているというから、人影は一千万あるはず。
ただし、リリーさんの船は《ティルス》本体ではなく、それに付随する小惑星の一つに接近した。大都市に必要な物資を生産する小惑星工場や小惑星農場が幾つも、近接する軌道上にある。それらを守る防衛艦隊も、あたりを巡回している。
「ここが、麗香姉さまの隠居屋敷なのよ」
その人は、リリーさんの一族の最高指導者だと聞いている。今は現役を引退して、趣味の研究に没頭しているとか。
「子供の頃からの習慣で、姉さまと呼んでいるけど、本当は、あたしたちのお祖母さまより年上なの。もしかしたら、辺境で一番長生きしてる人かもしれない」
「それはまた、すごい人なんですね……」
宇宙進出時代のごく初期に、科学者仲間を集めて移民団を結成し、地球文明圏から脱出してきた中心人物と聞いて、驚きもし、納得もした。
まだ性能の低かった移民船団で長い旅を行い、辺境の宇宙に違法都市を築いた先駆者の一人。
〝リリス〟の背後には、やはり実力ある老舗組織が控えていたのだ。
ただし、そのことは、盟友である司法局長にも秘密にしているというから、ぼくも他言はしないと誓った。何であれ、リリーさんの不利になるようなことは、絶対しない。
気密桟橋に接続した船から、ナギの運転する車で降りた。岩盤をくり抜いた長い連絡トンネルを抜けると、緑の豊かな一G居住区に出る。
巨大な回転体の内側は、見渡す限り、森と草原のパッチワークだった。花の咲く丘、馬が草を食む牧場、蛇行する川、きらきら輝く湖。車の窓を開けると、水と緑の匂いがする。
「ここが辺境で一番、天国に近い場所かもね」
ホルターネックの白いシャツに黒いミニスカートのリリーさんは、今日も精悍で美しい。耳には、大粒ダイヤのイヤリング。ヴァイオレットさんは、ミルクティ色の丈長のワンピースに、真珠のイヤリング。
ぼくは初めて会う最長老に敬意を表して、白いシャツブラウスと紺のスーツを着ていた。ヴァイオレットさんが、船旅の始まる前に買い整えてくれた衣類の一着だ。シャツの襟元にはネクタイでなく、青いリボンを結んでいる。その方がぼくに似合うと、リリーさんが言うもので。
車はやがて、広い薔薇園に囲まれた屋敷に着いた。灰色と薔薇色の花崗岩で組み上げられたように見える、古風な三階建ての屋敷である。
数十万人は楽に暮らせる広大な居住空間に、建物はここ一か所だけというのだから、最上の贅沢といえる。屋内や庭園に幾つか見える人影も、アンドロイドの侍女と園丁だけだ。
こんな広い居住区に一人きりで暮らしているなんて、寂しくないのだろうか。《ティルス》本体で暮らす一族の人々は、たまに遊びに来るというけれど、すぐに帰っていってしまうのだから。
玄関前の車寄せに三人で降り立って、華麗な玄関ホールとサロンを通り抜け、薔薇園を見渡せるテラスに出た。
赤やピンク、白や黄色、オレンジや紫、薄緑。ありとあらゆる品種の薔薇が咲き誇り、桃のような甘い香りが漂っている。常春の気候に設定してあるので、花が途切れることはないそうだ。
「姉さま、来ましたよ!」
とリリーさんが呼びかける。
「わかっていますよ、いらっしゃい。相変わらず、元気だこと」
返事をしたのは、テラスでアンドロイド侍女と共に、お茶の支度をしていた女性だった。
背中に垂らした長い黒髪が印象的な、象牙色の肌の美女である。深いラベンダー色のワンピースを着て、耳には涙滴型の黒真珠を下げている。
大きな一枚板のテーブルには、溢れんばかりの料理とお菓子。ちょうど、午後のお茶の時間にあたっているからだ。
「姉さまも、相変わらずお美しくて、目の保養です」
長身のリリーさんは身をかがめ、黒髪の美女に親愛のキスをした。ぼくが驚いたのは、リリーさんが、ごく自然に敬語を使っていることだ。惑星連邦の重鎮である司法局長にさえ、対等な態度で接するというのに。
「姉さま、紹介しますね。この子がミカエルです」
「ええ、事情はヴァイオレットから聞いていますよ。検査データも受け取っているし。よろしくね、ミカエル」
リリーさんの手で前に押し出されたぼくは、かなり緊張していた。ぼくの命を握っている人だし、何より、リリーさんの敬愛する人だ。
「初めまして。ミカエルです。お世話になります。どうか、よろしくお願いします。あまりご迷惑でなければ、いいのですが」
薔薇とは違う、ひんやりと冷たいような、冴えた甘い香りがした。麗香さん愛用の香水、梅花香だと知ったのは後のことである。冬の厳しい寒気の中で咲く花は、確かにこの人にふさわしい。
「一人暮らしだから、お客さまは大歓迎よ。ちょうど、助手も欲しかったところだし」
「助手、ですか?」
ぼくが、この人の助手になる?
ぼくとしては、リリーさんの秘書か雑用係のような立場を考えていたのだけれど。
既にすっかり決めてある様子で、麗香さんは言う。
「あなたが将来、どんな生き方を選ぶにせよ、今はまだ、そのための準備期間でしょう。治療の傍ら、しばらく、わたしの元で勉強するといいわ。そうすれば、そのうち、自分の適性が見えてくるでしょう」
「あの……ぼくはつまり……脳腫瘍が治って元気になったら、リリーさんのお手伝いをしたいと思っていたのですが……」
ぼくたちが婚約したことは、リリーさんが既に伝えているはず。
「もちろん、それが大きな目的で構わないのよ。ただ、手伝うといっても、色々な方法があるわ。あなたの場合、現場に付いて歩くより、せっかくの頭脳を活かす方がいいでしょう。後方支援の総監督、みたいな立場を考えてみたら?」
後方支援の監督?
それはまあ……必要な役目だというのなら、これから考えてはみるけれど……
「姉さま、それはシレールの代りということですか?」
「そういうことになるわね。ミカエルが後を引き継いでくれるなら、シレールは都市経営に専念できるでしょう?」
ぼくとリリーさんは顔を見合わせた。
「そういうことなら……」
ちらりと思った。その方が、ヴァイオレットさんには都合がいいだろうな、と。
麗香さんに勧められてテーブルに着くと、古典的なメイド服のアンドロイド侍女たちが給仕してくれた。
生ハムを巻いた無花果、クリームチーズや小海老や胡瓜の薄いサンドイッチ、レモン風味のアボカドを載せたカナッペ、何種類ものオリーブとチーズ、蟹のクリームコロッケ、スモークサーモンと野菜のサラダ、ほぐしたハニーチキンのサラダ、温野菜を添えたローストポーク。
お菓子は苺のパイ、洋梨のタルト、林檎入りのクレームブリュレ、チョコレートケーキ、抹茶のムース。果物は桃に葡萄、さくらんぼ、メロン。
たっぷりの食べ物は結局、半分かた、リリーさんのお腹に収まったのではないだろうか。
「ふう、幸せ」
戦闘用強化体であるリリーさんは、エネルギー消費が大きい。だから、いつも、この世で最後の食事であるかのように、真剣に食べ物に取り組む。その豪快な食べっぷりを見るのも、ぼくの幸せの一つ。
「ミカエル、腹ごなしの散歩に行こうか」
誘われて、一も二もなく立ち上がった。ここの素晴らしい庭園を楽しみたかったし、リリーさんと二人きりにもなりたかったから。
「ゆっくりしていらっしゃい。わたしたちは、話をしていますから」
たぶん、ぼくの処遇についての相談だろうと思いながらも、麗香さんとヴァイオレットさんをテラスに残し、リリーさんと薔薇の庭園に降りていった。
白い玉砂利を敷いて、飛び石を配した小道があちこちに延びている。よく考えられた設計で、ゆるいカーブを曲がると景色が変わり、清らかな小川が流れていたり、薔薇の絡みついたアーチがあったり、小さな噴水とベンチがあったりする。
薔薇だけでなく、ラベンダーやジャスミン、サルビアやレモンバームの植え込みもあった。アイリスや撫子、桔梗や竜胆の咲く小道もあった。四季が凝縮されて詰まっているようだ。リリーさんは、ざくざくと玉砂利を踏みながら言う。
「どう、いい所でしょ?」
「はい、とっても……エデンの園みたいですね」
正直なところ、これだけの屋敷を、ただ一人のために維持する財力には、呆れている。
だが、その財力が〝リリス〟の活動を陰から支えているのだ、ということもわかる。軍や司法局は、中央の市民社会の中でこそ絶対権力だが、辺境の宇宙では、ほとんど力を持たないと知っているから。
これまでに耳に入ったことからすると、どうやらリリーさんの一族は、《ティルス》という都市そのものを所有しているようだ。それがどれだけの富を生み出すのか、ぼくには想像もつかない。
「往復の日数があるから、あたしたち、ここにはあまり長くいられないの。明日か明後日には、出発するわ。ごめんね。いつまた任務で呼ばれるかもしれないから、中央に戻っていないと」
「はい、わかっています」
ここまでぼくを送り届けてくれただけで、大変な特別扱いなのだ。ぼくを無人艦に乗せ、ナギだけをお供に送り出すことだって、できたのだから。
でも、リリーさんはぼくのために、自分の時間を使ってくれた。それどころか、婚約までしてくれた。わがままなんて、言えない。次に会えるのが半年後でも、一年後でも我慢する。
薔薇の小道は、途中で小川を越える橋になったり、石造りの四阿に行き合ったり、見晴らし台に登る階段になったりして、長く続いている。それでもやがて、庭園のはずれまで来た。
ここから先は、森と草原になる。大きな道路はなく、乗馬用の小道が巡るだけらしい。草原にはコスモスや桔梗、ポピーやアネモネが点々と咲き、常春の楽園であることを示している。
振り向くと、庭園の向こうに屋敷が小さく見えた。その背景も、ずっと彼方まで緑一色である。白い発光雲の漂うあたりに、やっと湖のきらめきが見える。
リリーさんは庭園のはずれの芝生に座り、ぼくを手招きした。
「ミカエル、おいで」
はい、と答えて横に座ると、リリーさんはぼくを押し倒すようにして、もたれかかってきた。逆らわずに後ろに倒れると、リリーさんがぼくの胸に顔を載せる形になる。
「うん、幸せ」
「はい……ぼくもです」
こんなに気持ちのいい重さ、味わったことがない。
「ほんとは、ずっとここにいたい。ミカエルと一緒に」
「はい」
それが真剣な気持ちであることは、ぼくにもわかる。同時に、三日もすれば、リリーさんがここの平穏に飽きるだろうこともわかる。
事件や冒険がなければ、リリーさんはエネルギーを持て余すだろう。
強化体である限り、おとなしく隠遁生活などできはしない。船の中でも、毎日、空手や剣道の稽古をしていた。闘うことが、リリーさんの生き甲斐なのだ。
「でも、リリーさんは、事件に呼ばれる人ですからね。司法局では今頃、帰りはまだか、とやきもきしていますよ」
「いいのよ、そんなの。あたしだって、たまには長期休暇をもらう権利があるんだから」
「はい、それはそうです」
ぼくが逆らわないと、リリーさんは自分で思い直して後を続ける。
「まあ、往復だけで時間はくってるけどね……できたら、ミカエルがここに慣れるまで、一緒にいたいんだけど……」
ぼくはもちろん、引き留めたりしない。また会える、とわかっているのだから。
「大丈夫ですよ。ぼく、麗香さんのよい生徒になれるよう頑張ります」
すると、リリーさんは、それにも不満そうだ。
「だからって、無理はしなくていいからね。ミカエルは、これまで辛い人生だったんだから」
どうしたんだろう、これまでにない不機嫌ぶり。ひょっとして、焼き餅だったら嬉しいなあ。
「辛くなんか、なかったですよ。他のバイオロイドに比べたら、ずっと恵まれていました」
今は、心からそう言える。他に何十億人のバイオロイドがいても、ぼくより幸運な者はいない。人類の中にだって、ぼくより幸福な者がいるかどうか。
「もしかして、ちょっと心配になったんだけど……ミカエルって、姉さまみたいなタイプが好み?」
リリーさんが冗談半分の態度で、それでも底に不安の混じる声で言うので、ぼくはあえて笑い飛ばした。
「そうですね。とても綺麗で神秘的な方ですから、よろめいてしまいそうです。でも、麗香さんから見たら、ぼくなんか小猿程度のものですよ」
もしかして、リリーさんのいつもの恋愛騒ぎ、と思っているだけかもしれない。冷却期間を置けば、醒めるはずだと。
「そんなの、わからないよ。姉さまはずっと独身だし、浮いた噂もないけど、あたしたちの知らない所でロマンスを楽しんでるかもしれないし……ミカエルが気に入ったら、ちょっかい出すかも」
「それは光栄ですね」
「だめ。よろめかないで」
と、しがみついてくる女性が可愛い。天下の豪傑が、実はこんなに純情可憐な女性だなんて、他の誰が知るだろう。
「心配ないですよ。ぼくには、リリーさんが全てです。他の女性はどんなに綺麗でも、造花のようなものです。ぼくにとっては、リリーさんだけが、生きた花ですよ」
と言ったら、受けた。リリーさんはきゃあきゃあ言って身をよじり、芝生に転がって嬉しがる。
「いやあん、ミカエルったら、もう、女慣れしたプレイボーイみたい」
「そうですか。じゃあ、もっとプレイボーイの研究をしておきます」
リリーさんが喜んでくれるなら、何でもするし、何でも言う。何をしたら、この人を笑わせてあげられるのか。
「ここでいい子にして待っていますから、リリーさんも、お仕事で無理はしないで下さいね。ぼくが一人前になったら、その時は、どんなにしてでもお役に立ちますから」
「うん」
リリーさんは微笑んで、ぼくの額にキスしてくれた。長い髪がぼくの顔を撫でるのが、くすぐったい。
それから、再びぼくの胸に顔を預けて、脱力した。
「次の休暇が取れたら、すぐに飛んでくるからね。その頃にはきっと、ミカエルの治療も終わっているだろうから」
「はい」
本当は、額にキスだけでは物足りない。それでは全然……ぼくの気持ちを表すには、足りないのだ。
リリーさんにキスされると、ぼくもむずむずしてきて、キスのお返しをしたくなる。豊かな胸の谷間に、もっと頭をこすりつけたくなる。
でも、リリーさんは、ぼくが大人になるまで『本格的なキス』は遠慮する、と言っている。当然、『それ以上のこと』も。
とことん公正な人なのだ。ぼくがまだ子供だから……純真だから……と思っているのだろうけれど、本当は少し違う。
バイオロイドは、純真でなどいられない。
《ルーガル》の研究基地では、人間の科学者たちの助手として働くだけでなく……気晴らしの〝遊び道具〟にされたこともある。男の科学者たちが、気分転換に、ぼくらを〝使用〟したのだ。
もちろん、こちらには苦痛でしかなかったから、全然〝むずむず〟なんて起きなかったけれど。
彼らの大半は、相手が少女でも少年でもお構いなしだった。いかにおぞましくても、拒絶することは考えられなかった。それが、バイオロイドの仕事の一つでもある。
だから、ぼくは男たちを喜ばせる技術を知っていた。その技術を、彼らを油断させるために使ったこともある。さもなければ、ぼくらがウィルスのサンプルを持ち出す隙は得られなかった。
でも、そんな過去を口にすれば、リリーさんが悲しむだけだとわかっていたから、あえて何も言わず、清純そうな顔をしていた。
リリーさんが、ぼくを無垢な存在だと思ってくれるのなら……バイオロイドの暮らしの実情を知ってはいても、〝穢れている〟と思わないでくれるのなら……そうでありたい。
神さま、どうかリリーさんをお守り下さい。ぼくが、この人を守れる男になるまで。
そう、リリーさんと神社詣でをしてからというもの、ぼくは前より素直に『神に祈る』ことができるようになっていた。神などいないと知っていても、祈ることは救いなのだ。どうせ、祈っても損はしないのだから。
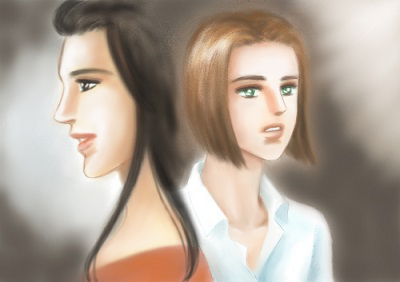
「あなたの心配は、わかっているわ」
麗香お姉さまは、テーブルをはさんだ席で言う。新しく注がれたダージリンが、香り高い湯気を立てている。
「わたしには、何も助けてあげられないけれどね……」
そう、一族のみんな、わたしの気持ちをよく知っている。そして、知らないふりをしている。
当の紅泉に、その気がないのは明白だから。
もちろん紅泉は、わたしのことを誰より愛してくれている。家族として、親友として。いざという時は、他の誰を犠牲にしてでも助けてくれる。
でも、自分自身はあくまでも、理想の王子さまを探し続ける。
まさか、あんな小さな男の子がそうだとは、わたしは思いたくないけれど。
いいえ、彼がこのまま成人したら、紅泉への愛情を持ち続けたら……その時は、限りなく理想の男性に近付く。
ミカエルには勝てない、という気がした。彼は、わたしと似ているからだ。聡明で冷静な補佐役。澄ました顔をして、汚い真似もできる。わたしの位置に、彼はすんなり収まることができてしまう。
「……ミカエルのことで、お姉さまにご迷惑をかけるのは、申し訳ないと思っています」
「いいえ、迷惑ではないのよ。賢い子だし、助手を欲しいと思っていたのは本当だから。もしかしたら、ミカエルには、ずっとここにいてもらうかもしれないわ」
「《ティルス》に?」
「あるいは、この屋敷に」
それは、奇妙な話だった。
好んで独り暮らしをしてきたお姉さまが、一時の客ならともかく、この隠居屋敷に誰かを長く住まわせる?
「まあ、ミカエル次第ね。あの子にどれほど根性があるか、楽しみだわ。シレールの役目を引き継げるようなら、彼にはもっと他の仕事を任せられるし」
お姉さまは、ミカエルが気に入ったのかしら。生きるために人を殺して平然としていられる、そのくらいの強さがないと、紅泉とは釣り合わないから?
「とにかく、ミカエルの治療をお願いします……紅泉が、とても心配しているので」
そして、健康体になったら、新しい人生に出発してほしい。紅泉のことなんか、あっさり忘れてしまって。これまで、何人もの男たちがそうしてきたように。
「それは、確かに引き受けました。それより、あなたたちこそ、無理をしないようにね」
「はい」
でも、わたしたちがハンターの仕事を始めた時に、励ましてくれたのはお姉さまだ。一族の総帥であるヴェーラお祖母さまは、断固として反対だった。
『紅泉、あなたは〝正義〟の名を借りて、好き放題に暴れたいだけなんでしょう。そのために他組織の恨みを買ったら、一族全体が危険にさらされます。あなたの勝手は許せません』
その意見は真っ当だった。
中央の市民たちが、違法組織も人体改造も認めないのであれば、違法強化体のハンターに頼ったりせず、自分たちの安全は自分たちで守るべきだろう。
それでも、最長老であるお姉さまが〝リリス〟の後援を決定したのだ。
『人類の存続を願うなら、誰かが〝正義〟のために戦わなければならないでしょう。それなら、紅泉以上の適任者はいないわ。紅泉と一族の関係は、隠せる限り、隠し通してみましょう。その上で、できるだけの応援をしてちょうだい、ヴェーラ、ヘンリー』
現役を退いたとはいえ、麗香お姉さまが一族の最高指導者であることに、変わりはない。
《ティルス》、《インダル》、《サラスヴァティ》という三つの違法都市と、その防衛艦隊。他都市に張り巡らせた通商網と情報網。
その全てについて、最終的な決定権は、お姉さまが握っている。
ヴェーラお祖母さまや、その伴侶のヘンリーお祖父さまでさえ、三百歳を大きく超す麗香お姉さまから見れば、ほんの駆け出しに過ぎない。
わたしたちもまた、辺境の各星域にある一族の工場や拠点を利用できるからこそ、私有艦隊を効果的に動かせる。〝リリス〟が実力を蓄え、独自にダミー組織を動かせるようになってからは、一族への依存度はいくらか低下しているけれど。
それでも、最新鋭の武器や艦船は、一族を通してしか手に入らない。
〝リリス〟が最高幹部会に敵視され、幹部会の代理人であるグリフィンの公表する懸賞金リストの最上位に載せられるようになっても、一族はわたしたちを後援し続けてくれる。
それは、麗香お姉さまの揺るぎない信念のためだ。人類の未来のために、市民社会は存続しなければならないと。
それならば、お姉さまは、いつか違法組織を束ねる〝連合〟と正面対決することまで、視野に入れているのだろうか。それとも、そんなことにはならないと、確信しているのだろうか。
一族は今のところ、〝連合〟と距離を置いて共存している。けれど、最高幹部会が本気で〝リリス〟を抹殺しようと決意したら、お姉さまは、どこまでかばってくれるのだろう……

人工の楽園を人工の夕映えが照らす頃、紅泉とミカエルは籠に一杯、薔薇の花を摘んで戻ってきた。赤やピンク、白やクリームの花びらが贅沢に折り重なっている。今夜はこれで、薔薇のお風呂に入るつもりらしい。
とはいえ、まだ二人一緒に入る段階ではない。それは当面、わたしだけの特権であるらしい。
お互いに裸で、花を浮かべたお湯に浸かり、紅泉の膝の上に抱っこされる時間、そのために、わたしはハンター稼業に耐えているようなもの……狡猾な獲物を狩る知的なゲームという側面も、確かにあるのだけれど。
「じゃあまた、夕食の時間にね」
「はい」
と互いの部屋に別れる様子がわかった。ミカエルが青年になるまで、軽いキスだけで我慢するというのは、紅泉の真面目さである。それがまた、ミカエルを感動させてしまうのに。
あの子は本当に、紅泉を恋い慕っている。
もしかしたら、理想の伴侶になるかもしれない。わたしが遠慮して、脇へどかなければならないような。
それでも、未来のいつか、ミカエルが紅泉を裏切らないという保証はない。
恋は、冷めるものなのだ……わたしが抱いているような、究極の愛情に進化しない限り。

夕食の前にシャワーを浴び、着替えをした。お姉さまの屋敷では、夕食は正装と決まっている。わたしたちが泊まる時のために、部屋は常に準備されていた。服も小物も揃っている。
鏡の前のわたしは、茶色い髪をあっさりと結い上げて、シトリンのイヤリングを下げ、淡いミモザ色のドレスを着ている。この姿は、二十歳の頃と何も変わらない……
いいえ、そんなことはない。
戦いの歳月が、やはり重い何かを刻印している。
表情が違う。振る舞いが違う。
人生の疲労が、蓄積しているのだ。肌がなめらかであっても、バレエの稽古で鍛えた軽やかな動作があっても、世慣れない若い娘ではないことは、誰にでもわかってしまうだろう。
かといって、成熟した貴婦人というのでもない。まだ何も、悟ってはいないから。単なる年齢不詳の……ひねくれた魔女ではないだろうか。
自分がどんな大人になりたかったのか、もう忘れてしまった。子供の頃に抱いていた、漠然とした夢や憧れは、十三歳の時、粉々に砕かれたままだ。
従兄弟のシヴァだけのせいではない。他の男たちも、わたしに絶望的な嫌悪と軽蔑を抱かせた。
子供の頃から、薄々とは知っていた男の正体。幾度かの事件が、それをはっきりと思い知らせてくれただけ。
この世は地獄。
地獄が薄皮一枚かぶっているだけで、どんな喜びも楽しさも、それを当然と思った瞬間に奪われてしまう。
だから、地獄と知ったまま、地獄で得られる"はかない幸福"を慈しむしかない。
どんな嫉妬にあぶられても、紅泉といられる日々が幸福なのだ。どうせ、すぐに終わりの日が来るのだから。
何万年、何億年生きても、死ぬ時は、あっという間の人生だったと感じるだろう。
その時、満足して死ねるように、今はあがく。
紅泉に重たがられても、離れない。
紅泉をミカエルに奪われたら……それは、その時にまた考えよう。