
ブルー・ギャラクシー 乙女の楽園編

「おはようございます。今日はみなさんに、新しいクラスメイトを紹介しましょう。もう、学校中に噂が駆け巡ったようですけどね。お父さまが再婚なさって、邪魔にされて捨てられたというのは、誰かの創作ですよ」
教室中にくすくす笑いが広まったけれど、すぐ静まった。
さすがは名門校。
生徒はみんな、若い淑女。
数学担当の三十代の美女、長い黒髪をきちんと結い上げ、ほのかに香水の香りがする吉田先生が、あたしの肩をそっと押す。
「ミス・ダイナ・マレーです。みなさん、仲良くしてあげて下さいね」
二十四人の女の子を前にして、あたしは淑やかに頭を下げた。
「どうぞよろしく、ダイナです」
精一杯にこにこして、無邪気な女の子を装わなくては。
もっとも、どう転んでも、あたしなんかが〝腕利きのボディガード〟に見えるはずはないけれど。
私立の名門、聖カタリナ女学院。
全寮制で、生徒はおよそ十二歳から十八歳までの三百人あまり。たまには、飛び級で来る十歳の子もいるとか。
あたしの入った学年は最高学年の一つ下で、十五歳から十七歳までの女の子が、二クラスに分かれて在籍している。
植民惑星《サリヌール》の中緯度地帯、なだらかな山地の中腹にある学校は、麓の町から切り離された別天地だった。
広い敷地を囲む二重のフェンス、無数の監視カメラとセンサー、女性警備員と番犬たちの巡回。
何でも、十数年前に一度、不祥事があったとかで、警備システムが強化されたらしい。それはあたしの任務には無関係ということで、詳しくは教えてもらえなかったけれど、不思議で仕方ない。
女の子が女の子を強姦したって、いったい、どういう事情だったの!?
そもそも、どうやってそんなことができるの!?
これから、生徒たちと親しくなったら、何か噂が聞けないかしら。
とにかく、それ以来、事件らしい事件は起きていないという。
ここを訪問できるのは、生徒の家族と、クラブ活動の交流試合などに来る他校の女子生徒の他、わずかな関係者のみ。
校長も教員も常駐の医師も、事務員も警備員も厨房担当者も、全員が女性。唯一、定期的に通ってくる男性は、社交ダンスを教える白髪のおじいちゃま先生だけ。
女の子を勉学に没頭させるには、最高の環境。
そして、あたしにとっては、生まれて初めての学校!!
これまでは一族の屋敷内で、育ての親であるシレール兄さまや、もっと年長のおじさま、おばさまたちに勉強やスポーツ、楽器の演奏や手芸などを教わるだけだった。同じ年頃の女の子なんて、車で繁華街を通った時、バイオロイドの娼婦や侍女たちを見かけたくらい。
辺境の違法都市には、あたしの他に、大事に守り育てられている女の子なんかいないのだ!!
(仕事なんだから、冷静に、冷静に)
と思っても、どきどき、わくわくが止まらなかった。
だって、教室中が女の子なんだもの!!
まるで、お花畑みたい!!
金髪、栗毛、黒髪、褐色の肌、黄色い肌、白い肌。
みんな、お揃いの白いブラウスにグレイの上着、グレイ地に深緑のチェックのスカート。もしくはトラウザーズ。タイツか靴下かは、かろうじて自由。靴も数種類の型に限定され、草履やハイヒールなどは禁止。
背の高い子もいれば、小柄な子もいる。細い子も、ふっくらした子もいる。全員の興味深そうな視線が、あたしただ一人に注がれている。
ああ、どうか、大きな失敗をしませんように。
無事、護衛としての任務を果たせますように。
くるくるの赤毛の癖っ毛を何とか梳かしつけ、真新しい制服に身を包んだあたしは、緊張一杯の自己紹介をした。
「母がいなくて、生物学者の父に育てられてきました。ずっと田舎の研究基地を連れ回されてきたので、学校に入るのは、今日が初めてです。犬や猿しか友達がいないのはよくないから、人間の友達を作りなさいと、父に言われてきました。集団生活に慣れていないので、何か失敗するかもしれませんけど、どうか大目に見て下さい。何が普通なのか教えてくれたら、その通りにします」
こう言っておけば、弱肉強食の辺境育ちのあたしが、中央の市民社会の常識に反する真似をしてしまっても、少しはごまかせるはず。

『おまえに、人の護衛が務まるとは思えないが……止めても無駄だろうから、仕方ない。手痛い失敗をすれば、少しは懲りるだろう』
違法都市《ティルス》の屋敷であたしを見送ったシレール兄さまは、あからさまに渋い顔だったけれど、あたしは気にしなかった。
兄さまはいつも、悲観的すぎるのよ。
ダイナ・マレーとしての架空の経歴は、司法局のハンター管理課が完璧に作り上げてくれた。無敵のハンター〝リリス〟の身内であるという事実は、あたしを抜擢してくれたクローデル局長と、特捜部のミン本部長以下の、ほんの数名しか知らない。
護衛任務をバックアップしてくれる司法局の担当班や、護衛庁の関係者たちは(政治家とその家族の警護は、普通、最高議会付属の護衛庁の仕事なのだ。でも、今回の任務だけは特別に、司法局との提携という形)、あたしをただの大学生だと思っている。司法局入りが内定している卒業予定者に、臨時任務を任せただけだと。
あたしにとっても、信じられない展開だった。まさか、司法局長じきじきのお声がかりで、市民社会の女学校に入れるなんて。
これには去年、従姉妹の紅泉姉さまと探春姉さまに連れられて、市民社会を旅行したことが伏線になっている。
わが一族の総帥であるヴェーラお祖母さまが、紅泉姉さまに『グランド・ツアー』の引率を頼んでくれたのだ。何でも地球時代、貴族階級の子弟には、教育の仕上げに外国を旅する習慣があったとか。

――大きな窓を持つ明るい教室には、目的のリーレン・ツォルコフもいた。素直な茶色い髪を紺のヘアバンドで押さえた、色白の可愛い子。大きな水色の目が印象的。
さらさらの髪というのは、本当に優雅でうらやましい。あたしの赤毛はくしゃくしゃもつれて厄介だから、いつも短くしているしかないのだ。
身長の伸びも、百六十センチ台半ばで止まってしまうだろう。おまけに、びっくり目の童顔だから、どう洒落てみても、赤毛の小猿という印象になってしまうのだ。
『あんたはあんたで可愛いよ』
と紅泉姉さまは慰めてくれるけど、あたしは姉さまみたいな、長身のかっこいい美女になるのが夢だったのに!!
……まあ、おかげで、どこへ行っても軽く見られ、警戒されないという利点はあるけれどね……せめて、中身だけは充実させなくちゃ……
「ミス・マレーは、ミス・モハマドカーンのお隣に座ってもらいましょう。慣れるまで、みんなで面倒を見てあげて下さいね」
あたしは教材や文房具のセットを胸に抱えて、指定された席に落ち着いた。途中、リーレンと目が合ったので、にっこりしておく。
昨日はシャルマ校長や担任の吉田先生との顔合わせ、護衛任務に関する打ち合わせ、敷地内の案内、荷物の整理などで終わってしまった。大食堂での夕食時と今朝の食事時、遠くからリーレンの姿を確認しただけ。今日、これからが護衛本番。
「では、授業に入ります。今日はちょうど新しい章ですから、ミス・マレーにもわかりやすいでしょう」
授業の内容は、あたしが既に《ティルス》の屋敷で習ったことばかりだった。シレール兄さまは厳しい教師なので、数学や物理から歴史、文学まで徹底的に叩き込まれている。勉強で苦労することはなさそうなので、一安心。公式の説明を聞くふりをしながら、教室内を観察するゆとりがある。
まあ、みんないい家庭のお嬢さまばかりだから、何も問題はないと思うけど……
リーレンの母親であるマダム・リーナ・ツォルコフが、連邦最高議会の若手有力議員であることが、女学校内での護衛を必要とする理由だった。
最近、議員の家族や親族、友人を狙う暗殺事件が続いているのだという。
議員当人にはプロの護衛官チームが付くけれど、家族や友人は、必ずしもそうではない。どこまでを護衛対象に含めるかが、難しいからだ。
両親や配偶者、子供や孫は明らかに対象だけれど、高齢の祖父母や曾祖父、曾祖母はどうか。離婚した元配偶者は。仲の良くない兄弟姉妹は。何年も会っていない旧友は。
無防備な親族や知り合いを狙う事件が続けば、議員当人は心が乱れる。また、違法組織からの脅迫に屈服しやすくなる。不幸にして誰かが殺されると、心が折れてしまい、そのまま引退してしまったりする。
硬派の議員が政界からいなくなれば、悪党どもにとっては万々歳だ。
そこで司法局としては、議員の家族・親族・友人に対する護衛を強化することになった。そして、警護の手を広げたために、人手不足に陥った。既に引退した者が呼び戻されたり、地元警察からの出向を頼んだり、軍や司法局を志願する若者を臨時採用したり。
だから、若いあたしがリーレンの護衛に選ばれても、司法局の一般局員は疑問を持たないでくれる。
あたしはこの任務を手始めに、少しずつ経験を増やし、実績を積んでいくつもりだった。
そうすれば、シレール兄さまもヴェーラお祖母さまも、あたしを大人として認めてくれるようになる!!
『一族の末っ子』として、叱られたり監視されたりするばかりの立場から抜け出せるはず!!
休み時間になると、リーレンの方からいそいそとやってきた。
「待っていたのよ、ダイナ。わたしがリーレンです。よろしくね。ダイナって呼んでいい?」
笑顔で握手を求められ、ほっとした。いかにも無邪気で、育ちのいいお嬢さま。
「ええ、もちろん。あたしも、リーレンて呼んでいい?」
「もちろんよ。仲良くしましょうね!!」
今回、本名のダイナをそのまま使ったのは、『偽名で暮らすのはややこしいよ』と、紅泉姉さまに言われたから。
あたしは初仕事だから、余計なストレスは少ない方がいいのだそうだ。もしも、次の任務を頼まれることになったら、その時、ふさわしいコード名や偽名を考えればいいと。
何にしようかなあ。紅泉姉さまはリリー、探春姉さまはヴァイオレットを任務用の通り名にしているから、あたしも花の名前がいいかなあ。ローズとか、デイジーとか……まあ、それはゆっくり考えるけど。
他の女の子もわいわい集まってきて、あたしは受け答えに大忙しだった。
「ダイナって、本当に学校行ったことないの?」
「お猿をペットにしていたの?」
「お母さまって、お亡くなりになったの、それとも離婚?」
何とか筋書き通りに答えたけれど、あまり細かく追求されるとぼろが出そう。どうやら転入生というのは、珍獣らしい。
次の授業が始まり、身元調査から解放されるとほっとした。女の子は注意力が鋭いから、用心しなくちゃ。
何しろあたしは、『普通の女の子』の振る舞い方を、本や映画で学んだだけなのだ。
お昼休み、再びわっと取り巻かれたけれど、リーレンが威張って言う。
「みんな、ちょっと遠慮して。ダイナはわたしの担当なの」
「何よ、それ」
「誰が決めたの、そんなこと」
という級友たちの抗議にもかかわらず、得意そうな顔。
「だって、うちのママから世話を頼まれてるんだもの。ママはダイナのお父さまとは、古い知り合いなんですって。だから、ダイナが慣れるまで、わたしが面倒みるわ」
独り占めなんてずるーい、という声は上がったけれど、とりあえず、あたしはリーレンの信託統治領になったらしい。甘い匂いのする包囲陣から逃れ出て、やっと深呼吸できる感じ。
これって、女の子酔い?
なんて贅沢なんだろう。辺境では、〝本物の人間〟の男女比は九対一くらいなのに!
だから女に飢えた男たちは、従順を植え込まれたバイオロイド美女を侍らせるのだ。彼女たちには選択の自由はなく、どんな厭な男にも黙って仕えるだけ。しかも、五年で廃棄処分に回されてしまう。
いつか、あたしが大物になったら、そういうバイオロイドの奴隷たちは全員、自由の身にしてやるんだから!!
「じゃあダイナ、お昼に行きましょ」
リーレンに腕を組まれて、はっとした。背丈が同じくらいだから、同じ高さで腕がクロスする。これが長身の紅泉姉さまだったら、あたしがぶら下がる格好になってしまうのだ。
シレール兄さまなんか、ここ何年も、あたしと腕を組んだりしてくれないし。
小さい頃は抱っこも添い寝もしてくれたのに、数年前から、はっきり突き放されているのだ。もう子供ではないのだから、べたべたするなと言われてしまっている。そのくせ、護衛任務など子供には無理だと決めつけるんだから、矛盾よね。
(ああ、そうか)
リーレンと腕を組んで歩くうち、納得した。
あたしは人生で初めて、『対等な関係』というものにぶつかったのだ。
これまでは大人の中の『みそっかす』だったし、去年の旅行で知り合ったルディは年下だったから、あたしは懸命にお姉さんぶって接したし。
花のような香りのする、柔らかい肌の女の子と寄り添って歩くのは、むずむず、ふわふわする不思議な気分だった。
リーレンは何とも思っていないだろうけれど、初めて会った相手を信用しきって、無防備に寄り添うなんて、辺境ではありえない。たとえ、誰の紹介でも。
それでも、あたしは自分が女の子集団に溶け込むのを感じていた。通路ですれ違う他学年の女の子たちは、
(ああ、転入生ね)
という確認の目で見ていくだけ。
下級生の女の子たちがふざけながら走ってきて、一人があたしにぶつかった時も(リーレンと腕組みしていると、とっさの身動きが制限されるとわかった。今度から、腕組みはさりげなく断るべきかも)、
「あ、ごめんなさい」
と普通に謝られただけ。
リーレンは上級生らしく、
「あなたたち、お行儀が悪くてよ」
と厳かにたしなめていたけれど、あたしは密かに感動していた。
(あたし、〝普通〟の仲間に入ってる!)
故郷の違法都市《ティルス》では、あたしは都市国家の王女さまのような立場である。広い敷地を持つ贅沢な屋敷の中で暮らし、正規の外出時には、周囲にアンドロイド警備兵の壁ができる。他人にぶつかられるなんて、ありえない。車で目的地まで運ばれ、専用駐車場で降ろされるだけ。
食事にしても買い物にしても、行く先は一族の所有する店と決まっている。しかも、その時間帯は貸し切りになっていて、他の客は閉め出されているという始末。箱入りもいいところ。
躾も厳しい。夕食時は正装と決まっている。うっかり礼儀に外れた言葉遣いをしたら、ヴェーラお祖母さまに刺すような視線を向けられる。
『ダイナ、いま何か言いましたか?』
屋敷の外は無法地帯なのに、なんで、細かいお作法なんかにこだわるの!?
シレール兄さまなんか、あたしが選ぶ服にも文句をつける。やれ派手だの、下品だの、流行に惑わされているだの。
(兄さまの言うなりになっていたら、あたしは一生、白い襟の付いたお嬢さまドレスだわ!)
……それで結局、あたしは黒いライダースーツに身を包み、顔をヘルメットで隠して、夜中にバイクで屋敷を抜け出すようになった。繁華街の裏通りを探険し、バイオロイドの娼婦たちに話しかけ、怪しげな店にも踏み込んだ。
紅泉姉さまも少女時代は、こうやって武者修行したそうだ。あたしは姉さまみたいに、自分からチンピラに喧嘩を売るなんて命知らずの真似はしなかったけれど。
ただ、喧嘩を売られるまで、街をうろうろしただけ。
最初はびくびくものだったけれど、次第に自信がついてきた。大抵の男は、喧嘩の度胸も技能も、あたしより劣るとわかったから。
アンドロイド兵を相手に単調な稽古を重ねるよりも、実戦の方がはるかに役に立つ!
とはいえ、チンピラではない、本物の強敵にはまだぶつかっていないから、その時はどうなるか、たぶん運次第……かな?
大勢の生徒で賑わう食堂では、リーレンが適切なアドバイスをしてくれた。
「ダイナ、料理より先にデザートを確保した方がいいわよ。校長先生って食べ物を無駄にしない主義だから、余るほどは出さないの」
それでも、料理はたっぷりあるように見えた。生徒の列に並び、お盆の上に好きな食べ物を取っていくのが面白い。
ハンバーグ、ローストビーフ、ポークソテー、チキンカツや白身魚のフライ、詰め物をした茄子の揚げ物、クリームコロッケ、何種類ものサラダとパン、スープ。揚げ出し豆腐、キムチに大根おろしに焼き魚、山菜ごはん、ナンを添えた豆のカレーもあった。
パンに好きな具をはさんで、サンドイッチにする子もいる。外で食べるのか、お盆を持って中庭に出ていく子もいる。デザートは季節の果物やヨーグルト、アイスクリーム、プリンやケーキ類。
「あー、チェリータルト、もうないわ」
「ねっ、その栗のムース、ちょっとだけ分けて。ちょっとでいいの」
「あら、甘いものはやめたんじゃなかったの?」
「それは明日からよ。今日は体育で走ったもん」
なんていう会話も楽しい。少女漫画の中に入ったみたい。いいなあ、女子校。
でも、内心でにやつくあたしって、女装して潜入した男の子みたい……?
それから突然、リーレンに驚き顔をされているのに気付いた。まずい! 他の女の子は、あたしの半分くらいしか料理を取っていない!
「ダイナって、いつもそんなに食べるの?」
これを食べたらもう一回列に並ぶつもりだったなんて、とても言えない。
「いえ、あの、今朝は緊張してて、ちっとも食べられなくて。やっとお腹が空いてきたものだから、つい」
大食いで正体が知られた、なんてことになったら、紅泉姉さまに大笑いされてしまう。
姉さまはあたしをこの星に送り届け、リーレンの警護担当班に引き合わせると、相棒の探春姉さまと共に、自分たちの任務に出発してしまった。大きな研究所に職員として入り、機密漏洩ルートを探るのだとか。
姉さまたちと離れるのは心細かったけれど、仕方ない。ここの女の子たちだって、家を遠く離れて、寮生活しているんだもの。
「いただきます」
幾つも並んだ大きなテーブルの一つに着いて、ざわめきの中で食べるのは楽しかった。周囲の会話も新鮮だ。厳しい先生の悪口、週末の計画、次の長期休暇まで会えないボーイフレンドのこと。
もちろんリーレンは、次から次に話しかけてくる。
「ダイナのお父さまって、ずっと独身なの? ダイナがいなくなって、お寂しいでしょうに」
あたしはつい、シレール兄さまを思い浮かべてしまう。年齢差からすれば、養父と言ってもいい人だ。でも、本人は遺伝子強化のおかげで若い姿を保っているので、幼い頃から『兄さま』と呼んで暮らしてきた。
あたし自身は最長老の手で遺伝子設計されて誕生したから、直接の親はいない。ただ、一族の遺伝子プールを利用して創られたという意味で、一族の末っ子なのだ。
シレール兄さまは、手を焼かせるあたしがいなくなって、やれやれと思っているかしら。それとも、少しは寂しがってくれている?
この任務を完了するまで、兄さまに連絡を取ることもできはしない……距離にして、四千光年は離れてしまっている……
「……パパは大丈夫よ。好きな研究をしていれば、それで十分な人だから」
兄さまには『一族の都市経営の一翼を担う』という、本来の仕事がある。最長老にあたしの世話を押し付けられのは、余計な苦労だったはず。
それは、兄さまが恋人を失って苦しんでいた時期のことだったという。最長老の麗香姉さまは(不老処置のおかげで、何百年生きても若くて美しい人なので、あたしたちは敬意を込めて"姉さま"と呼んでいる)、世捨て人のようになってしまったシレール兄さまを立ち直らせる意味で、赤ん坊だったあたしの養育係に任命したのだと聞いている。
兄さまは、慣れない子育てに悪戦苦闘するうちに、元気を取り戻していったのだとか。
あたしが物心ついた時には、もうすっかり、ベテラン育児人だったものね。
たまに、兄さまがぼんやり遠くを見ているのは、たぶん、亡くなった恋人のことを思い出している時。

最初の何日かは無駄に緊張してしまって、会話の受け答えもぎくしゃくしたけれど、慣れてくると楽なものだった。周りはみんな、善意の女の子なのだ。
「ダイナ、音楽室はこっちよ。楽器の準備、手伝ってあげる」
「このあたり、もう習ってる? 何だったら、宿題はわたしたちと一緒にしない?」
「教頭先生の授業は厳しいから、ちゃんと予習しておいた方がいいわよ」
「お買い物は週末にできるけど、お酒の持ち込みだけはしない方がいいわ。抜き打ち検査で発覚したら、退学になっちゃう」
「お部屋は防音だからいいけど、階段やバルコニーで話すと上下の階に筒抜けだから、気を付けて」
あたしはにこにこして、控えめな女の子でいればいい。当人たちが泣いたり怒ったりするような、些細な喧嘩やトラブルはあっても、第三者から見れば牧歌的なものだった。
まさに、清らかな乙女の園。
男ばかりの荒んだ違法都市から来ると、夢のような世界。
クラブ活動も見学した。テニス部に水泳部、園芸部に美術部、茶道部に華道部、ダンス部に料理部。馬術部は、近くの牧場まで遠征して馬に乗るという。
どこのクラブでもあたしを歓迎してくれ、親切に色々教えてくれた。みんな真面目で、先輩後輩のけじめが厳しく、でも和気藹々とやっている。とても楽しそう。護衛任務がなければ、順番に全部入りたいくらい。
一通り回った後、
「ダイナはどこに入るつもり?」
と案内してくれたリーレンに尋ねられたけれど、
「まだ考え中」
ということにしておいた。リーレンはどこにも入っていないから、あたしも自由な身でいた方がいい。
放課後はぴたりとリーレンにくっついて、宿題を教わるふりをしたり、学校に伝わる伝説を聞いたりして過ごし、夕食後に寮の部屋に引き取るまで離れない。仲良しの女の子たちは大抵、何をするのも一緒という協調行動をしているから、あたしの行動も目立たなくて済む。
それにしても、トイレまで一緒に行かなくてもねえ……?
そうして、初めて迎えた週末。
生徒の大半は外出許可をもらい、私服姿でバスに乗り、麓の町へ降りるというのに、リーレンは校内に残るという。
「あのね、今日、拳法部の親善試合があるのよ。首都にある姉妹校から、拳法部の人たちが来るの。それで、双方五名ずつの代表を立てて、試合するのよ」
可愛いシュガーピンクのツーピースが似合うリーレンは、なぜか恥ずかしそうに頬を染めて説明してくれる。恥ずかしいポイントは、いったいどこなのだろう?
「ちょっと意外。格闘技に興味があったの?」
もらった資料には書いてなかった、そんなこと。むしろ、スポーツは苦手で興味もないはずでは。
「ええ、まあ、ちょっと、見るだけ……」
別に構わない。あたしを同行させてくれさえすれば。護衛日誌には、ちゃんと記録しておこう。リーレンには、これまで見逃されていた趣味があるかもしれないと。
午後、リーレンと体育館に行くと、外出しなかった女の子たちが、二階部分の観覧席に鈴生りだった。学校全体の三分の一というところ。
土日は制服の着用義務がないから、みんな華やかな私服姿だ。あたしは動きやすさを優先して、地味なモスグリーンのシャツとスパッツ姿だから、花畑の中の雑草みたい。
実はあたしは、ちょっと前まで、シレール兄さまが繰り返し、
『赤毛の娘には、赤や黄色やピンクは似合わない』
と言うのに反発して、自棄のように派手な色の服を選んでいた。何色だろうが、気迫で着こなせばいいと思って。
けれど、近頃では少し思い直している。あたしの赤毛と白い肌には、やはり深緑や焦げ茶色、チャコールグレイの方が合うのかもしれないって。少なくとも、その方が上品で落ち着いて見えるのは確か。
だから今回は、吉田先生やバックアップ班の人たちに信頼してもらえるように、地味目の服だけ持ち込んだ。ぱっとお洒落するのは、任務を完了してからでいい。
「午前中は合同練習で、午後から代表選手の試合なのよ」
とリーレンが説明してくれた。
もちろん本日の来訪者については、バックアップ班から資料が来ている。首都の名門女子校の拳法部ご一行さま。引率のコーチも女性。特に怪しい部分はなし。リーレンが試合を見たがることだけ、あたしの予想外。
じきに、教頭のブッシュ先生の短いスピーチがあり(灰色の髪をきっちり結い上げ、角張った体格でお堅い紺のスーツを着込んでいる! 温和なおばあちゃま校長に代わって、生徒たちをびしびし取り締まっている憎まれ役!)、伝統の親善試合が始まった。
準備体操は既に終わっているので、双方のチームから選手が出てきて、中央に設置された試合用スペースで対峙する。
興味を持って試合を眺めていたあたしは、じきに、
(学ぶことはない)
と悟った。
こう言っては悪いけれど、あたしの目には、幼稚園のお遊戯と大差ない。拳法というより、拳法ごっこ。
でも、普通人なら仕方ないのよね。オリンピック級の選手だって、あたしから見ればとろいんだもの。そのあたしだって、紅泉姉さまには遠く及ばないのだし。
もしも、リーレンを狙う暗殺者が飛び道具持参でやってきても、この程度の力量なら何とかなりそう。
校内では銃こそ持ち歩かないけれど、制服のポケットにも私服のポケットにも、鉛の粒を入れてある。あたしの腕力で投げれば、これは、銃弾に匹敵する威力を持つのだ。
それに、腕の通話端末には超切断糸を仕込んである。接近戦なら、人体などまっ二つ。できれば、普通の女の子たちの前で、そんな真似はしたくないけれど。
敵に対して手加減など考えるのは無理、とわかっていた。
前に一度、死にかけたことがあるからだ。十四歳の時、《ティルス》の緑地帯で初めての実戦を経験した時のこと。
生存期限の切れた奴隷たちを、新米のバイオロイド兵たちに追わせて処刑させる〝兎狩り〟を指揮していた男と対決したのだけれど、勝ったと思った油断から、毒針を受けてしまったのだ。
こっそり尾けてきてくれた紅泉姉さまと探春姉さまが、すぐさまあたしの全身の血液を入れ換える治療をしてくれなかったら、どうなっていたか。
(わかってる。リーレンの安全が最優先。暗殺者が来たら、殺さず逮捕しようなんて思いません。殺してから、背後関係を調査してもらえばいいのよ)
最後の試合になると、見物の女の子たちから、これまでの何倍もの声援が飛んだ。どうやら、主将同士の対決らしい。
「ほら、あれが泉先輩よ!」
あたしがびっくりしたくらい、リーレンの声が上ずり、頬が紅潮していた。これまで見たことのない興奮状態。


夕食の時、待ち構えていて隣に座ろうとしたけれど、リーレンは素早く他の女の子の間に座ってしまった。あたしはあたしで他の女の子に囲まれてしまい、あれこれ話しかけられて身動きとれない。
「ねえ、ダイナって男の子と付き合ったことないの」
「今度の週末は、わたしたちと町に行かない?」
リーレンから離れないで済むよう、即興で用事をでっち上げなくてはならない。ほとんど、スパイの修行をしている気分。
夕食の後、素早くリーレンを追ったけれど、またしても自室に入られてしまった。扉を閉ざされてしまったら、それまでだ。しつこくドアを叩いたりしたら、学校中に、あの転入生は礼儀知らずの野蛮人と思われてしまう。寮の個室に鍵はかけられない仕組みだからこそ、主の許可を得てから入室するという手続きが大事なのだ。
翌朝は早く身支度して(あたしは毎朝ジョギングと空手の稽古をするから、元々早起きである)、リーレンの部屋の扉が開くのを待って捕まえたけれど、やはり、つんと顔を背けられてしまった。
日曜日だから、他の女の子は大抵町に遊びに行くけれど、あたしが誘ってもリーレンは応じてくれず、勉強するから、と自室に籠ってしまう。
あたしは途方に暮れてしまった。
女の子って、みんなこうなの?
機嫌のいい時は天使なのに、怒ったら小悪魔同然なんて、落差が激しすぎる。
あたしも女の子だけど、こんな風にしつこく怒り続けたことなんてない。だって、ヴェーラお祖母さまやシレール兄さまに叱られた時は、いくら腹が立っても、やっぱりあたしが悪かったんだものね。
月曜になっても、リーレンはあたしを避け続けていた。他の女の子たちから、
「どうしたの?」
と不審がられてしまう。やむなく事情を話すと、
「なんだ、そんなことで」
と笑ってくれる子が大半だったからよかったけれど、
「リーレンは泉さま一筋だから、これは長引くかもね」
という予言もあり、あたしはため息をついてしまった。どうしたら仲直りできるのだろう。
「手紙を書いたら?」
という提案もあったので、何人かから綺麗な便箋や封筒を分けてもらった。『お手紙の交換』というのは、伝統的な女の子文化なのね。
懸命に言い訳とお詫びを書き連ねて、教室のリーレンの机に入れておいたけど、読まれたのか捨てられたのか、まるで反応なし。
夜中、寮のベッドの上で天井を眺め、胸の中でつぶやいた。
(姉さま、この世に楽な仕事ってないのね)
箱入りのお嬢さまだと思って、リーレンを甘く見ていたのだと思う。自分はただの女の子じゃない、使命を帯びた身なのだと自惚れていたから、それが態度に出て反発を受けたのだ。
(これ以上、どうやって謝ればいいんだろ)
けれど、くよくよする自分を見下ろす自分もいる。毒針で死にかけたことに比べたら、こんなトラブルは可愛いもの。
紅泉姉さまなら、笑い飛ばすだろう。
自分が警護している大物議員でさえ、暗殺未遂犯を追う邪魔になれば、お尻を蹴飛ばして転がしてしまう人だ。
姉さまはそれでしばらく、その議員から逆恨みの厭がらせを受けたという。後日、別件でその議員の孫を助けることになって、仲直りできたそうだけれど。
そう、護衛としては、リーレンの命が無事なら、それでいいのだ。嫌われたままでも、護衛はできる。大幅にやりにくいけれど。

リーレン・ツォルコフという女の子のことは、そうと言われるまで、存在を意識していなかった。
ただでさえ、わたしのことをもてはやす下級生は大勢いる。こう言ったら悪いけれど、まるでメダカの群れ。
その中の一匹、いえ一人なんて、何か変わったことでもしない限り、判別できるはずがない。スカートで逆立ちするとか、イモリの黒焼きを差し入れに持ってくるとか。
でも、言われてから注意して見れば、対抗試合の時など、大抵観戦している。普段の稽古の後でも、差し入れを持って立っている。クッキーだったり、紅茶だったり、ポプリだったり。
お気持ちは有り難いけれど、わたしの部屋はもう、下級生からの贈り物で一杯。下手をすると、他校の女子からも手紙や贈り物が来る。
高価な品物のやりとりは学校側が禁じてくれているけれど、ささやかな品でも、量が集まると厄介だった。食べ物は拳法部の下級生に渡せばいいけれど、手作りのマスコット人形だの、手編みのマフラーだのは始末に困る。心(怨念?)の籠もった品を、人にあげられないし、迂闊に捨てるわけにもいかない。
だから、ある程度まとまったところで実家に送る。タオル類は実家の道場に通ってくる子供たちに使ってもらうし、引き取り手のない品はバザーに回す。どうしようもない時は、実家の近くの神社でお祓いしてもらい、焼いてもらう。
少女時代の一過性の憧れとはいえ、熱に浮かされたようなラブレター、ファンレターには寒気がした。
どうしてあの子たちは、同性のわたしを追い回すのだろう。
それより、自分の趣味や勉強にでも打ち込んだらどうなのだ。
それとも、打ち込む何かを見付けられないから、人の応援などで時間を浪費するのか。
(馬鹿馬鹿しい)
というのが本音だった。
わたしにとっては、自分が試合に勝てるかどうかは問題だけれど、たまたま同じ学校にいるだけの生徒たちには、関係ないことではないか。わたしが勝とうが負けようが、いちいち騒ぐ必要はない。
――わかっている。こういう考えが知られたら、たちまち友達がいなくなる。閉ざされた女子校の中では、あくまでも謙虚でいなくては。
いいえ、大学に進んでも、社会に出ても、若い女というものは、にこにこと愛想よくしていなければならない。わたしにだって、そのくらいのことはわかっている。
だから今日まで、礼儀正しい模範生でいた。
成績は常に上位を保ち、下級生への指導も親身に行う。他校のライバルとも、良き友人として付き合う。
でも、そんなものは猿芝居だ。
誰にわかる。わたしの限界までの努力が。その挙句の屈辱が。
いいえ、わかってくれなどと言うつもりはない。この世の真実がわかる者は、どこでも黙って耐えている。
それにしても、笑ってしまう話だった。違法組織というのは、どこから、そんなことを嗅ぎ付けてくるのだろう。誰にも明かしていないわたしの本心を、なぜ、見抜くことができたのか。
――市民社会を捨て、辺境の宇宙で生きる。
それ自体は、いいかもしれない。不老処置を受けられるし、実力だけの世界というのは、いっそ清々しい。
ひっかかる一点は、わたしはリーレン・ツォルコフに、何の恨みも憎しみもないということだ。
深い思慮もないけれど、悪意もない、ごく普通の女の子ではないか。母親が有力議員だからといって、見せしめに殺されるというのはひどすぎる。
どうせ殺すなら、わたしは自分の父を殺したい。世間では武道家として知られ、多くの弟子を育ててきた父を。
長女のわたしを道場の跡継ぎと定めて、幼い頃から厳しく仕込み、わたしが泣いても逃げても許してくれなかった。二つ年下の妹は、才能がないからと放置されていたのに。
わたしは早朝から叩き起こされ、厳しい朝稽古。学校から帰ると、また稽古。夏休みも冬休みもない。一年中あざだらけ。まるきり男の子扱いで、髪を伸ばすことも許されない。
いつも疲れていて、眠かった。友達と遊ぶゆとりも、滅多にない。おまけに、勉強の手抜きも許されない。文武両道でなければ話にならない、という正論。
父は道場を開くまで、医師として地元病院に勤務していた。道場に力を注ぐようになっても、週に三日の病院勤務は続けている。わたしもまた、何かの専門分野を持つように求められていた。学問と武道の両立を果たしてこそ、本物だから。
母は心配顔だったけれど、父には逆らえない人。たまに父方の祖母がわたしをかばい、今日は休ませてやれとか、友達と遊びに出してやれとか口添えしてくれた。
でも、何よりもわたし自身に、寄り道する心の余裕がなかった。父に示された目標に達しないと、自分がいたたまれないのだ。
父を尊敬していたから、わたしは耐えた。よくやった、とたまに褒められることが励みになったし、強くなる手応えもわかった。あちこちで公式試合に勝ち、年下の門下生に慕われることも嬉しかった。
わたしはやれる。
父の望む後継者になれる。
それなのに、あきらめていた男の子が生まれ、才能があるとわかると、
『もういい、おまえは好きにしろ』
だなんて。
父は弟にかかりきりで、わたしのことなど、もう忘れ去っている。やはり男でなければ、本物の武道家にはなれないと、母に言っているのも聞いてしまった。
本物って何?
誰が決めるの、それを?
家にいるのが辛くなったわたしは、祖母の勧めで、この学校に来た。郷里の惑星から二百光年。もう誰も、わたしに厳しい稽古を強いたりしない。
それでも、未練がましく拳法部に入ってしまったのは、子供の頃からの修行を無駄にしたくなかったから。
今はもう、人に評価されるためではなく、自分自身のために稽古している。登りかけた山なのだから、頂上まで登ってみたい。登りきれないとしても、限界まで努力した結果ならあきらめられる。
だから、父に対する恨みや反発は残っていても、殺意というほど強くはない。田舎道場の主なんか殺したところで、違法組織は褒めてくれないものね。
もちろん、彼らの甘い約束など、信用できない。リーレンを殺したら、わたしの脱出を手伝ってくれ、組織の一員として迎えてくれるなんて。そして、望みのままの不老処置、強化処置を受けさせてくれるなんて。
いくらわたしが小娘でも、違法組織の言葉を信じるほど、愚かではない。うかうか誘いに乗ったら、洗脳されて、駒にされるのが精々だろう。
でも、おかげで考えることになってしまった。
わたしはこのまま、市民社会にいたいのだろうか。
大学を出て何かの仕事に就き、結婚して母親になり、孫を持ち、穏やかに老いていく暮らしが望みなのか。
それで、満足して終われるのか。
いくら稽古を重ねても、父の言う通り、所詮は女の世界での強さ。骨格が弱い。筋肉も付かない。同じだけの稽古を積んだ男には、絶対に敵わない。男の弟子を指導するにも、限界がある。わたしは初心者クラス、女性クラスしか教えられないだろう。
道場を継ぐのは弟。
あの子はいずれ、体格でも技量でも、軽くわたしを追い越す。努力の量ではなく、生まれ持った資質で負けるのだ。
わたしは、男に生まれるべきだった。さもなければ、武道や修行などに興味のない、普通の女の子に生まれるべきだった。試合に出る側ではなく、無責任にキャアキャア応援する側に回っていればよかったのだ。
――卒業まで、残りわずか。
進学する大学も決まった。望み通りの理系コース。医師免許を取得した上で、生物学者を目指す。大学卒業後は、科学技術局か民間の研究機関に入りたい。
それでも、女子校から解放されたら恋愛しよう、とは思えなかった。子供の頃から、男の子を見ればまず、
(わたしより強いか、弱いか)
と考えてしまう。
強ければ悔しい。弱ければ興味はない。
こんな気持ちのまま、まともな恋愛などできるのだろうか。
スポーツマンや武道家はいやだ。負けたくない、と思ってしまうから。歴史学者とか芸術家とか、全く違う分野の人かいい。
でも、もしもそういうボーイフレンドができたら、拳法は趣味ですと言うのか。それとも、生き甲斐だと? もうこれ以上、強くなる余地なんてないというのに?
わたしは違法組織から勧誘を受けた事実を、惑星警察にも連邦司法局にも話していない。だから、向こうにしてみれば、まだ脈はあると思うだろう。
もちろん、わたしにはできない。何の罪もない下級生を殺すなんて。でも、そうしたら連中は、別の刺客を仕立ててリーレンを狙うだけ。
母親が邪魔者と見なされている限り、いつかは周囲の誰かが殺されるのだ。実行犯が逮捕されたところで、黒幕は辺境のどこか。軍も司法局も、辺境へは出ていかない。消耗戦になるだけだと言い訳して、中央に引き蘢ったまま。
ハンターの〝リリス〟だって、辺境の大組織には手出しできない。違法艦隊の総合力は、もはや惑星連邦軍を上回っているというのだ。
いずれ、この市民社会全てが、違法組織を束ねる〝連合〟の支配下に置かれる可能性だってある。
市民社会に未来がないなら、割り切って、違法組織の幹部を目指すという考え方もできるのだ。
『市民社会にいられなかった異常者や脱落者の集まり』というのは一面的な見方であって、『市民社会とは別の理念に従う独立国家の集まり』という見方もある。『正義がどちらにあるか』ではなく、『勝った者が正義を名乗る』だけではないか。
でも、こんな考えが人に知られたら、わたしは危険人物扱いされてしまう。せっかく今日まで優等生でい続けた苦労、無駄にしたくはない。
……毎年、何十万人かの市民が、自ら望んで辺境に出ていくというけれど、彼らの気持ちが、少しはわかる気がする。わたしも、ほんのわずかぐらついたら、彼らの仲間になるかもしれないのだ。
数日に一度、あたしは夜中の探険に出る。
短い睡眠で足りる体質だから、十時頃寝れば、二時か三時にはすっきり目覚められるのだ。
警備システムに特例扱いされているおかげで、暗い校内を好きにうろつける。教員用の宿舎を調べたり、温水プールで一泳ぎしたり、車庫に入っているスクールバスを点検したり、資材倉庫に入ったり、合間に厨房でエネルギー補給したり。
裏門からこっそり、敷地外に出ることもできる。その時は、敷地内に放されているドーベルマンやシェパードたちに、吠えないよう言い聞かせておく。
警備犬といっても、違法組織のサイボーグ犬ほど厳しく躾けられているわけではないので、買収は可能なのだ。まずは昼間、警備員の前で犬たちの頭を撫でたりして、あたしを覚えてもらっておく。夜間、犬たちが囲いから出されて敷地内に散ると、食料倉庫から失敬したステーキ肉を手にして(数量チェックで問題にならないよう、管理システムの記録を操作しておく)、一頭ずつ懐柔していく。それを、幾度も繰り返す。
そうすれば、あたしがフェンスを乗り越えても大丈夫。犬たちは戸惑う様子だけれど、やかましく吠えたりはしない。よしよし、いい子、いい子。
昼間はおとなしく振る舞っているので、あたしはエネルギーが有り余っていた。三人いる警備員たちも、夜間の見張りは機械任せにしているから、見咎められずに済む。夜更かしの誰かとぶつかりそうになったら、警備システムが事前に教えてくれるから、隠れてやり過ごせばいい。
部外者の侵入は、まず有り得ない。山越えの本道から外れて、この学校に通じる脇道に入ってくる車は、警備モニターに捉えられ、警備室でチェックされる。山道の途中で誰かが車から降りても、道に迷ったハイカーが来ても、すぐチェック。学校側で怪しいと判定して通報すれば、地元警察のエアロダインが飛んできてくれる。
ただ、遠距離からの狙撃だけは怖いので、あたしはバックアップ班からの指図に従い、リーレンをどこに立たせてはいけないか確認して回っていた。彼らも常に、不審者の監視をしてくれている。この学校を見下ろせる尾根などに、同じ市民が何度も車を停めていないか。
もちろん、はるか頭上の衛星軌道からの砲撃という可能性もあるけれど……それは、あたしの管轄外。連邦軍や司法局や航行管制局、惑星行政府がきちんと職務を果たしてくれるよう、祈るしかない。
あたしが泉と会ったのは、そういう〝うろつき歩き〟の後の明け方だった。
あたりが明るくなってきたら、堂々とジョギングのふりをすればよい。犬たちは朝の点呼のために、囲いに戻っていく。うっすらと白い霧がかかって周囲の景色を隠しているのも、いい風情。まるで、知らない世界に迷い込んだよう。
そうしてあたしは、敷地の外れに近い小道で、スポーツウェアの女生徒がうずくまっているのを発見した。
ちょうど銀杏並木の下で、黄色い落ち葉が厚く散り敷いているから、足を滑らせたのかもしれない。
「どうしたの? 捻挫?」
近寄りながら声をかけると、痛そうに靴を脱ぎかけていた彼女は、びくっとして振り向いた。まるで、世界に自分一人だと思っていたかのように。
「あら、泉先輩……でしたよね」
短い黒髪に、小麦色の肌の凛々しい少女。
あたしも少女なんだけど、この学校の女の子たちに対しては、つい保護者の気分になってしまう。
「滑った拍子に、足が攣ってしまって……」
苦痛のせいか、それとも霧のせいか、泉は顔色が冴えない。近くで見ると、直線的な眉の下は、涼しい一重の目。あたしは子供っぽい大きな目をしているので、切れ長の細い目はうらやましい。神秘的な雰囲気が出る。
「あら、大変。ちょっと失礼」
あたしは彼女が抱えていた左足を見せてもらい、骨折や捻挫ではないことを確かめると、靴を脱がせ、自分の膝の上に載せて筋肉マッサージを施した。まずは足の指をそらせてから、ゆっくりと筋肉の硬直をほぐしていく。対称位置にあたる右腕もほぐすと、全身のバランスが回復する。校医を呼ぶほどのことではない。
「あたしもね、やったことがあるんですよ。その時、マッサージしてもらって、楽になったから」
それは子供の頃、紅泉姉さまの後を追って走った時のこと。向こうは何しろ最高水準の強化体だから、飛ぶように走る。サイボーグ化された警備犬たちですら、追尾に苦労するほど。
でも、あたしも脚力には自信があったので、ついていけるつもりだった。そして、自分の限度を越えてしまったのだ。
木の根にひっかかって派手に転んだ拍子に、痙攣がきた。それ自体はたいしたことなかったのだけれど、何しろ初めてのことだったので、恐怖にひきつってしまった。姉さまが引き返してきて、笑いながらマッサージしてくれ、あたしをおんぶして帰ってくれたのである。
泉は最初、顔をしかめていたけれど、やがて眉間から皺が消え、放心した様子になってきた。
「気持ちいい……」
「よかった。もう少し我慢して下さいね」
霧が薄れ、明るい光が差してきた。鳥が飛び立ち、遠くで朝練の声もする。
「ありがとう。楽になったわ。もう歩けそう」
泉はにっこりしてくれた。
「あなた、転入生でしょ。うちのクラスにも、噂が流れてきたわ。猿しか友達がいなかったなんて、まさか、そんなことはないでしょうけど」
笑ってしまった。転入生は、やはり珍獣らしい。
「パパが再婚して、邪魔にされたって話もありました?」
「あら、お父さまに男性の恋人ができて、あなたが愛想を尽かしたという話だったけど」
そういうバージョンもあったのかと、感心してしまう。
「みんな、よく話を作りますね」
「女ばかりで、退屈しているのよ」
「まあ、楽しんでもらえたのなら、それでいいですけど」
あたしは泉が立ち上がるのを支えた。寮までは距離がある。
「先生に車を出してもらいましょうか?」
「いいえ、そんな大袈裟なことにしないで。もう大丈夫だから」
「じゃ、ゆっくり帰りましょう。送ります」
「あら、あなたはいいのよ。ジョギングの途中でしょ」
「でも、また攣るといけないから」
本当はおんぶしてもいいのだけれど、あたしが怪力女だなどという噂が流れては困る。泉の方が、あたしより身長も体重もあるのだから。
敷地を周回する小道をゆっくり戻りながら、当たり障りのない話をした。ここにはもう慣れたか。仲良しの友達はできたか。
この人は、見た目よりずっと女らしい、と感じた。言い方が優しく、作り物ではない思いやりがある。三人きょうだいの長女だというから、人の世話をすることに慣れているのだろう。実家の道場でも、年下の門下生の面倒をよく見てきたらしい。みんなに憧れられるわけだ。
でも、やはり、溌剌としている、という状態ではない。落ち葉の上で足を滑らせたのも、疲れているからではないのか。
「先輩、無理なさってるんじゃありませんか。練習のしすぎで」
学年は違うけれど、ほとんど同い年である。泉はいま十七歳、あたしはあと数か月で十七歳。
前から思っていた。十七歳というのは、人生で一番華やかで、危険な年齢ではないか。
十六歳だとまだ子供の部類だし、十八歳だとほぼ大人だから。
その間の、剣の刃の上でバランスを取っているような、不安定な年齢。
「そんなこともないけど……そうね、ちょっと焦ってたかな。今度の学生選手権、最後の大きな大会だから」
「最後って、大学生になっても選手権には出られるんでしょ?」
「そうだけど、わたしは他星の大学に行くから。この星では最後の大会」
「ああ、そうか」
「そういえば、あなたは何のクラブに入るの。あちこちから勧誘されたでしょ」
リーレンに付いて歩くのが仕事だから入らない、とは言えない。
「えーと、まだ決めかねていて」
「こんな早朝に走るくらいだから、運動系でしょ。拳法なんてどう?」
拳法部や剣道部はまだ見学していないけれど、それは、あえて避けたから。うっかり実力の片鱗でも見せてしまったら、厄介だもの。
「そんな怖そうなのは、とても。あたし、運動神経鈍いから」
「そう? そうは見えないわ。いい筋肉がついているし」
うひゃあ、観察されていたのね。話をそらさなくては。
「先輩は、背が高くていいですね。格闘技なんかやるには、ある程度、身長がないとだめでしょ。あたしはチビだもの」
すばしこいという利点はあるものの、破壊力では劣る。アンドロイド兵相手の稽古では、いつも悔しい思いをしてきた。紅泉姉さまのように、百八十センチを越す背丈とまでは言わないけれど、せめて百七十は欲しかったのに。
すると百七十センチを軽く越している泉が、悲しげに言う。
「わたしでも、まだ体格は足りないのよ。体格や素質に恵まれた人が、つくづくうらやましいわ。同じ稽古をしても、成果が全く違うのだから。それに、女子部で優勝したところで、男子のレベルとはまるで違うしね……軍や司法局に入れば、男女混合の訓練も多いでしょ。いえ、わたしはその方面に進むつもりはないけど」
よくわかる。
あたしたちの遺伝子設計者である、一族の最長老――麗香姉さまから、
『これまでで一番、調和の取れた強化になっているのよ。ダイナ、あなたは現時点では、わたしの最高傑作だわ』
と言われるあたしであっても、戦闘用強化体の男を相手にしたら、相当苦しい。精々、か弱いふりをして、相手の隙を狙うしかない。

朝食の時間、あたしはお盆に料理を山盛りにすると(真っ先に並んでサンドイッチやソーセージやパイを密封容器に取り、お昼までのおやつにする方法を覚えた。休み時間に、物陰で素早く食べるのだ。でないと、授業中にお腹がぐうぐう鳴ってしまう。もちろん昼食の時には、夕食までのおやつを確保しておく)、めげずにリーレンの横に座った。
返事がないのは覚悟の上で、冷たい横顔に一方的に話しかける。
「今朝、ジョギングに出たら、泉先輩と会ってね。銀杏並木のとこで、足が攣って、動けなくなっていたの。マッサージしたら、すぐよくなったけど」
ぴたり、とフォークを持つリーレンの手が止まる。
こちらを見てくれないままでも、聞いてはいるんだ、よかった。
「練習で無理してるみたい。最後の大会だから、どうしても優勝したいのね。寮まで戻りながら、色々話したの。それでね、強くなるのって、大変なことなんだなあって……」
会話の内容を一方的に話すうち、リーレンは抗議の顔であたしに向き直った。わあ、正面顔は久しぶり。
「ダイナ、ずるい!」
「えっ?」
「わたしだってまだ、数えるほどしか声をかけてもらったことないのに! この学校に来たばかりで、そんなにあれこれ話してもらえるなんて!」
あ、そういうこと。
あたしはほっとしたけれど、リーレンは悔しがってじれている。
「わたしたち誰も、身長が足りない悩みなんて聞いたことないわ! どうしてダイナが、そんなことまで話してもらえるの!」
ふうん、そんなに泉と話したいのか。
あたしとしては、リーレンと再び話せるようになったことが、とても有り難い。
「じゃあ、リーレンも一緒に走ろうよ。五時に起きて、校内一周するの。先輩も毎朝、その頃に走っているらしいから」
「………」
リーレンは絶句し、朝の接近遭遇をあきらめた。
無理もない。普通人なら、まだ寝ていたい時刻。それを起きて走るのだから、泉は偉い。
そんなに、頑張らなくていいのに。
どうせ普通人は、逆立ちしても強化体に勝てないのだから。
それよりも、学問や芸術に打ち込むとか、子供を指導するとかすればいいのだ。それこそが、真に価値のある仕事なのだから。
週末の外出許可は、その週に失点のなかった生徒に与えられる。提出物が期限に間に合わなかったとか、先生方に聞こえる所で下品な言葉を使ったとか、抜き打ち検査でご禁制の品(お酒や、いかがわしい本の類……何をいかがわしいと判定するかは、職員会議の結果次第)が発見されたとか、そういうのが複数回あったらだめ。
でも、ほとんどの生徒には許可が出る。そうしたらスクールバスで麓の町へ降り、買い物やお茶、ちょっとした冒険を楽しんで(地元の男の子たちにナンパされるとか、こちらからハントするとかね)、夕方のバスで戻ってくる。生徒たちは大抵、土日のどちらかで外出を楽しみ、もう一日は勉強や趣味の活動に充てるらしい。
その週末、リーレンはあたしと一緒に外出してくれるという。
「仕方ないから、ダイナに町を案内してあげるわ」
まだいくらか刺は残っているものの、とにかく、向こうから誘ってくれたのが有り難い。
「ありがとう」
と心から感謝した。
今度からは、地雷を踏まないようにしなくては。
……とはいえ、踏まない限りは、どこに地雷が埋まっているのか、わからないのよね。
もちろん、リーレンが町へ出るのは、危険を伴うことだった。どこに違法組織の回し者がいるか、わからない。地元の警官だって、喫茶店のマスターだって、違法組織に買収されていない保証はない。
それでも、まさか、卒業まで校内に籠もっていろとは言えない。狙撃や誘拐には用心し、スケベ目的の男の子からも守る。それが、あたしの役目。
そう覚悟して、よく晴れた土曜の朝を迎えた。
あたしは地味なモスグリーンのシャツと黒いワークパンツ、銃を隠すための褐色の厚手の上着。足元はスポーツシューズ。
色気も華やかさもないけれど、そんなものは後回し。
リーレンはサーモンピンクのミニのワンピースで、髪を三つ編みにしているのがとても可愛い。自転車に乗る予定なので、同系色のレギンスをはいている。足元もピンクのスニーカーで、大変結構。いざという時に、走れる格好でいてもらわないとね。
正門前の広場には、大型バスが待っていた。運転手は灰色の皮膚をした作業用アンドロイドで、女性警備員の一人が付き添い役である。
中に乗り込んで発車時刻を待っていると、ぎりぎりで飛び乗ってきたのは泉だった。グレイと青紫の横縞のTシャツに、年季の入ったジーンズという気取らない姿。キャメル色の革の上着を持っていて、あたしを見るとにっこりした。
「あら、ダイナ……この間は、どうもありがとう」
そして、あたしたちのすぐ前の席に座る。土曜と日曜の二日間、バスは町まで何往復もするので、車内はそれほど混んではいない。バスが正門を出ると、すぐさま自動で門が閉ざされる。徒歩で外出する女の子は、たぶんいないと思うけど。山中の道路を歩いて下ったら、それだけで一日終わってしまうもの。
「あれから、無理はなさっていませんか」
あたしが後ろの席から話しかけると、泉は身をねじって答えてくれた。
「ええ、少し怠けることにしたから大丈夫。でも、あなたは毎朝走っているみたいね。偉いわ」
「油断すると、すぐ太る体質なので」
これまで太ったことはないけれど、たぶんそうだと思う。いくら食べても細身でいられるのは、それだけ動いているからだ。
「ダイナ、あなたは運動向きよ。走り方を見ればわかるわ。かなり速度があるのに、まだ余裕があるでしょ。本格的に、何か始めたらどう?」
ううむ、観察されていたのなら、下手な言い訳はできないな。
「一人で走るのが好きなんです。人と競争するとか、試合に勝つとかは興味ないので」
「そうなの。勿体ないわね。他人と競争しなくても、自分の限界への挑戦という意味で十分なのに」
そこでリーレンが、あたしの袖をつんつん引く。欲求不満で爆発しそうな顔。あたしはすまして泉に言った。
「先輩、同じクラスのリーレンです。何度か先輩に差し入れをしているはずですけど、覚えてらっしゃいません?」
十中八、九、覚えていないと踏んでいた。だって、何十人という女の子がタオルだのレモンジュースだのサンドイッチだのを持って、泉の部活終了を待ち構えているんだから。どうせなら、もっと泉の印象に残るものを渡せばいいのに。子豚の丸焼きとか、イモリの黒焼きとか。それだと、間違いなく引かれるだろうけど。
でも、泉はにっこりした。
「いつか、胡麻風味のクッキーをもらったわね。あと、確か、ハーブティとオレンジケーキも。美味しかったわ、ありがとう」
「あっ、た、食べていただけたんですね。それだけで、もう……」
リーレンはすっかりのぼせ、頬をピンクに染めてしまっている。これも恋なのかな、とあたしは興味深く眺めていた。『本物の恋をする前の予行演習』のような気がするけれど、リーレン本人が幸せなら、それでいいわけだから。
「もちろん、差し入れは、いつもみんなで美味しくいただいているわ」
あ、クラブのみんなで分けただけなのか、とリーレンの肩が落ちる。でも、それが主将としての正しい対処だ。誰に何をもらったか覚えているだけでも、たいしたもの。
「リーレン、あなたは料理部なの?」
「いえ、時々場所を借りるだけで」
「じゃあ、あれはわざわざ、わたしのために焼いてくれたのかしら」
「はいっ」
バザー用のクッキーを、かすめ取ってきた場合もあると思うけど。
「そう、ありがとう。またお願いしてもいいかしら。下級生が楽しみにしているので」
「はいっ、もちろんですっ」
リーレンは目がとろけそうになっている。あたしはつい、横から言ってしまった。
「泉先輩、誰か一人を贔屓しちゃいけませんよ。他のみんなが泣きますからね」
「贔屓のつもりは……」
と泉は困った顔になる。憧れの王子さま(?)にされてしまう方も大変だな。しょせんは女学校を卒業するまでの代用品、なんだものね。また、もしそうでなかったら、それはそれで問題のような気がするし。
同性を愛することが悪い、というのではない。ただ、色々と難しいだろうなと思うだけ。
身近に実例がある。聡明な探春姉さまが、自分の本当の気持ちを絶対に口にしないのは――一族のみんなも、あえて知らんふりしているのは――熱愛されている当の紅泉姉さまに、その気がないからだ。
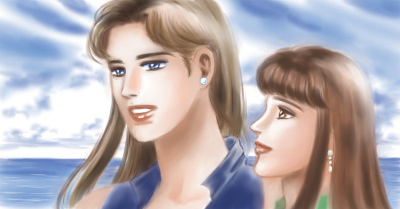
おしゃべりな生徒たちを乗せたバスは、赤や黄色に紅葉した山の中の道路を降り、明るい煉瓦色で統一された町に近づいていく。
森が切れると、畑や果樹園が広がった。ワインの醸造所や、牛や馬、羊のいる牧場も見える。平野部には川がゆったりと流れ、砂利の川原には犬や子供を遊ばせる人たちの姿がある。
バスはやがて、ささやかな町の中心街に入った。市場ビルや市民会館や雑居ビル。買い物の人、待ち合わせの人、散策の人。地元の公立学校に通う子供たちが、自転車やローラースケートで走り回っている。
あたしたちのバスは、中心街に近い小さな公園の駐車場に入った。私服でお洒落をした女生徒たちが、女性警備員に挨拶してから、ぞろぞろ降りて散っていく。
中には、泉の行く先を気にする女の子たちもいたけれど、何となくあたしたちが泉を占有してしまった形なので、あきらめたように離れていった。自転車にまたがった少年たちが、あちこちで女の子の群れを待ち受けている。
「ハイ」
「やあ」
照れたような挨拶が、あちこちで交わされた。七、八人の混合集団が幾つもでき、繁華街の方に移動していく。『節度を持ったグループ交際』なら、学校側も禁止したりしない。禁止する方が危険だから。
もちろん、『男性の危険な衝動』については、日頃から先生方がしつこく警告を繰り返している。男の子というものは、優しく見えてもシャイに見えても、いつ何時、理性を失うかわからない生き物ですからね。決して、二人きりになってはいけませんよ。
だから、グループ行動の中でチャンスを捉え、限りなく『二人きり』の状況に近付くのが、女の子たちの最大の冒険。同じクラスのサラや雪乃やマリアムたちから、そういう冒険譚のあれこれを聞いている。
いいなあ、ボーイフレンド。
あたしなんて、初デートの相手が、十二歳の男の子だったものね。
ルディはいい子だったけれど、あと十年は経たないと、恋愛対象にならない。あたしは『渋い大人の男性』が理想なんだもの。あたしが何かわがままを言っても、みっともない失敗をしても、ふっと笑って受け入れてくれ、頭を撫でてくれるような人。
そういう人にまとわりついて、思いきり甘えてみたい。シレール兄さまなんて、あたしを見たらお小言だもの……他人が見たら、優雅で理知的な『憂愁の貴公子』かもしれないけれど、ね。
「あの、先輩。今日はどちらへ?」
リーレンが手を胸の前で握りしめ、先にバスから降りた泉の背中に声をかけた。それだけでも、リーレンとしては大変な勇気だとわかる。振り向いた泉は、怪訝そうな顔をした。
「特に決めていないけど……」
「あのっ、だったら……ご迷惑でなかったら……わたし、わたしとダイナ……」
リーレンが上ずっているので、あたしが助け舟を出した。
「よかったら、あたしたちと一緒に遊びませんか。今日は、サイクリング公園に行こうって話してたんです。それから、郷土資料館」
泉は苦笑したように見えた。
「健全コースね」
子供っぽいと馬鹿にされたのか、とリーレンがしょげるのがわかった。それを見て、泉は励ますように言う。
「せっかくのお誘いだから、一緒に行こうかな。サイクリング公園て、どこにあるの?」
リーレンは歓喜のあまり、卒倒しそうだった。泉はこれまで、あまり町で遊ぶことがなかったらしい。あたしが説明した。
「この公園の管理所で、自転車を借りられます。それで走って、十五分くらい」
職務上、この町と周辺の地図は、およそ頭に入れてある。弾丸とレーザーの切り替えができる銃も、腰の後ろに差してある。火器は当然、公共の警備システムに探知されるけれど、あたしは護衛任務中の司法局員と登録されているので、問題なしと自動判定されるだけ。
もちろん、バックアップ班が車で追跡してきてくれる。あたしはたまに、トイレから報告を入れればいい。リーレンが知っているのは、自分が学校の敷地から出る時は、遠巻きの警護が付くということだけ。
それは政治家の娘としては当然のことだから、特に気にしていないはず。あたしが護衛とは、夢にも思っていないだろう。
それでいい。リーレンがそう意識してしまえば、行動が変わってしまい、それを暗殺者に探知されるかもしれないから。
ま、暗殺者がいるとすればね。
結局、三人で楽しく一日を過ごした。
コスモスの咲く広い公園で思いきり自転車を乗り回し、見晴らしのいい芝生で美味しいランチを楽しみ(あらかじめ、町のお総菜屋で買い込んだもの。泉も、あたしの食べっぷりには呆れていたみたい)、午後は、この町出身の芸術家の作品を集めた郷土資料館を見物した。
リーレンが一番はしゃいでいたけれど、泉も楽しそうだったし、あたしは何のトラブルもなくて一安心。
夕暮れ時、バスに乗って無事に帰還した。他の生徒たちも車内で新しい服や雑貨を見せ合ったり、男の子に声をかけられた自慢話をしていたり。これが、正しい青春というものよね。
寮に戻ってからも、リーレンは魂が抜けたような顔をしていた。それをいいことに、あたしもリーレンの部屋に入り込み、並んでベッドに座る。
「よかったね。泉先輩とデートできて」
リーレンは照れてつんとするけれど、お肌が薔薇色に照り輝いている。恋は美容にいいらしい。
「ごめん。あたしが一緒にいたら、デートにならないものね」
するとリーレンは、三つ編みを揺らして振り向く。
「ううん、ダイナがいてくれて、よかったのよ。わたし一人だったら、何を話していいか、わからなかったもの」
「それなら、よかった。また誘ってみようか。今度の土曜でも」
「そんな……そんなこと、図々しくない?」
一度ならともかく、連続となると、他のファンに許されないと思うらしい。
「泉先輩には、断る自由があるんだもの。あきらめるのは、断られてからでいいんじゃない?」
と言ったら、なぜか疑惑の顔をされてしまう。
「ダイナ、もしかして……」
「うん?」
「あなたも先輩が好きなんじゃない?」
つい吹き出しそうになったのを、何とかこらえた。女の子同士の恋愛遊戯に参加するつもりはない、なんて言ったら、また嫌われるだろう。
「安心して。あたし、渋いハンサムとの出会いを待ってるの。お姫さま抱っこをしてくれる人」
「それなら、いいけど」
いいのかなあ。
「リーレンは、王子さまを待っていないの? たくましい男性に、がばっと抱き上げてもらいたくない?」
「やめて、気持ち悪い!」
あれ?
「男の人って、気持ち悪い?」
「だって、だって……何だか、動物に近いような気がしない? 汗臭かったり、毛深かったりして……」
これが、乙女の清純というものだろうか。それとも、女子校暮らしの困った副作用だろうか。
「じゃあ……」
思わず、追求してしまいそうになった。
泉と本格的に交際したいの? キスしてもらいたい? それ以上のことも考えてる? それとも、退屈しのぎに騒いでいるだけ? 卒業したら、さっさと男性相手に切り替える?
あたしが泉だったら、やはり、迷惑度の方が強いだろうな。女の子の疑似恋愛に付き合わされ、卒業と同時に使い捨てられるなんて。
ふっと連想が湧いた。それは、紅泉姉さまも同じかもしれない。
無敵のハンターとして、世界中から尊敬と憧れを集めても、誰一人、立場を代わってくれる者はいない。
いつまでも、先頭に立って戦い続けなければならない。
紅泉姉さまの場合、好きで戦っている面が強いけれど、それでも幾度かは、うんざりして引退を考えたことがあるという。些細な落ち度でマスコミに攻撃されたり、救えなかった被害者の遺族に恨まれたりしたからだ。
ただ、新たに誘拐された人がいたり、ハイジャックされた船があったりすると、やっぱり要請に負けて、現場に出向いてしまう。そして、何とか事件を解決してしまう。
いつか、探春姉さまが言っていた。
『これは、紅泉が背負っている呪いなの。人より強い者は、人の分まで戦い続けるしかないのよ』
疲れるはずだ、いくら強化体でも。
だけど、あたしがいるから。
こうやって修行していけば、いずれそのうち、姉さまたちの重荷を分け持てるようになるから、期待して待っていてね。
次の週末は生憎の雨で、外出する者は少なかった。もちろん、濡れない場所でバスに乗り降りできるけれど、外遊びはできないものね。
「ああ、やあねえ、せっかくの週末なのに」
「仕方ないわ。勉強でもしましょ」
何度か雷がひらめき、一度はかなり近くに落ちた。裏の山かな。
「きゃああああっ」
と女の子たちの悲鳴が寮内に響くのも、あたしには面白い。
(そうか、女の子って雷が恐いのね)
また一つ、女の子の振る舞い方を覚えた。いつか、男性相手にこの知識を使うのが楽しみ。
女の子ってまず、堅い瓶の蓋が開けられないでしょ。蛇や蜘蛛や百足はだめでしょ。蜂が恐い、大きな犬が恐い、梯子に登れない。
可愛いふりをしたければ、方法は色々あるのだ。
バルコニーに出て外を眺めていると、薄紫の光がカッとあたりを照らし、空一杯にドドンと雷鳴が轟いた。宇宙空間の人工都市で育ったあたしには、惑星の大自然は感動ものだ。また光らないかな、とわくわくする。
土砂降りの雨も、遠くの山が霞む眺めもすてき。雨の匂いに土の匂いが混じって、肺の中までしっとりする。季節を、全身で味わうみたい。
「ねえダイナ、拳法部の稽古を見に行かない?」
リーレンが誘いに来たので、一緒に体育館に行った。今の時間帯は、拳法部とバレー部の割り当てらしい。体育館の半分では、ネットをはさんで、白いボールが行き来している。
あたしも思いきり飛び上がって、スパイクしてみたいな。
でも、それをしたら誰かに怪我をさせてしまうだろうから、運動音痴のふりが必要なのだ。
リーレンの〝お目当て〟は、白い道着に黒帯を締めて、下級生たちの稽古を監督していた。みんな懸命に、突きや蹴りを繰り返している。
何て痛々しい。あんなに華奢で、とろいのに、無理をして。
他の女の子たちと一緒に二階の観覧席から眺めていたら、泉が上がってきた。
「見に来てくれたの、ダイナ」
リーレンには目もくれず、あたしの手を取らんばかりにして誘ってくる。
「ねえ、ちょっと練習してみない?」
周囲の女の子の視線が集まってしまい、あたしは冷や汗をかいた。護衛は目立つものではない。
「そんな、とても無理です」
と尻込みしても、泉はあきらめてくれない。
「ちょっとでいいの。ちょっとだけ試してみて。あなたはきっと、適性があると思うのよ」
困ったことに、リーレンも横から勧めてくる。
「ダイナ、失礼よ。先輩がこんなに言って下さるのに。試すくらい、いいじゃない」
どうやらリーレンは、あたしが泉に引き立てられれば、自分も周囲をうろちょろしやすい、と計算したらしい。すると、他の女生徒たちも面白がる。
「ダイナって強いの?」
「何か経験あるんでしょ」
「なくても、やってみればいいじゃないの」
どうやら聖カタリナの拳法部では、泉一人が飛び抜けた強さで、自分の卒業後が心配になっていたらしい。
とうとうあたしは、予備の稽古着を借りて稽古に混じることになってしまった。見物人も釣られたように、二階からぞろぞろ降りてくる。
泉が付ききりで、立ち方、構え方から指導してくれた。夏休みなど、実家に帰った時に道場の子供たちを指導しているそうで、教え方は上手い。きっといい指導者になれる。
「そう、構えはこれでいいわ。まず、中段の突きからやってみましょう。わたしの真似をしてみて。腕ではなく、腰の回転で打つと考えてね。こう、肩が前に出れば、腕も自然に伸びるでしょ。そして、伸ばした腕をすぐに引くのが大事なの」
年に幾度か《ティルス》の屋敷に帰省してくる紅泉姉さまに、こうしてあれこれ教わったものだ。空手に剣道、射撃にナイフ。
姉さまが仕事に戻ってしまうと、後は一人で修行を続けた。どれだけの板を割り、アンドロイド兵をスクラップにしたことか。
それでも、初めての実戦では死にかけた。
正々堂々なんて考えたのが、あたしの身の程知らず。
どんなに卑怯でも冷酷でも、とにかく勝って生き延びなくては話にならない。
もしもリーレンを狙ってくる者がいたら、容赦しないと心に決めていた。政治家本人ならまだしも、家族を狙うなんて、卑劣すぎるもの。
「とてもいいわよ、ダイナ。今度は中段の前蹴り、いきましょう。こうするの。指先ではなく、指の付け根を使うのよ。指をまともにぶつけたら、骨折しますからね。まずはこのミットめがけて、軽く蹴ってみて。力は入れなくていいの。まず、正しい形を覚えてもらうから」
あたしは懸命に初心者を演じ、モタモタ振る舞ったはずなのに、しばらくすると、他の部員たちから言われてしまった。
「すごいわ、ダイナって才能あるんじゃない」
「初日でこれだけ綺麗に動けるなんて、たいしたものよ」
「もしかして、天才だったりして」
あああ、どうしよう。泥沼にはまってしまった。
おかしく思われても、さっさと逃げればよかったのに。
「確かに、センスがいいわ。あなた、どうして運動部に入らないの」
と泉は詰問口調に近くなっている。何だか、深く怪しまれているみたい。
「ダイナは心配してるんです。強くなったら、男性にモテなくなるって」
間近に立っている見物人の群れの中から、リーレンが言う。途端に周り中から、非難の声が上がった。
「そんなこと、あるもんですか。強い女が好きな男性も、いっぱいいるわよ」
「女にこそ、強さが必要なのよ」
「ダイナがモテないはずないわ。そんなの、余計な心配よ」
どうしても、この場から逃げられない雰囲気になってしまった。いったいどうして、こんなことに。
「それじゃ、軽く組み手をしてみましょう。さあ、ここに立って」
「でも、あたしそろそろ……宿題が……レポートが……」
「何よ、宿題はもう終わったって言ってたじゃない」
とリーレンが余計なことを言う。泉もどうやら、あたしがわざと実力を隠している、と思うらしい。組み手を始めると、段々、熱を入れて打ち込んでくるようになった。
どうしよう。こんな遅い攻撃、届くのを待っているだけで疲れる。
ただ突っ立っているわけにもいかないので、オタオタ受けていたら、泉の方が目に見えて疲労してきた。無理もない。彼女には、日頃の稽古の疲れがあるのだから。
「ごめんなさい。もうだめです!」
あたしはとうとう、半べそで叫んでへたり込んだ。
「あたしやっぱり、向いてません。こんな怖いの、もういや!! 勘弁して下さい!!」
周囲がみんな、ぽかんとしていた。泉は唖然としたままで、副将以下の部員たちが口々に言う。
「だって、あなた、ちゃんと受けているじゃないの」
「初めてとは思えないわ、たいしたものよ」
ええい、もう。
「それは、泉先輩が手加減してくれるからです。それでもあたし、厭なんです、こういうの。ひやひやして、寿命が縮みます!」
あたしがあくまでも恐がり通したので、仕方ないわね、とみんなあきらめた。
「ごめんなさい。無理強いするつもりじゃなかったのよ。ただ、あなたには才能があると思ったものだから……」
泉は謝ってくれたけれど、疑いは晴れない様子。
あたしはその場から逃げ、元の服に着替えてほっとした。一緒に寮の階段を昇りながら、リーレンが悲しげな様子で言う。
「ダイナ、あなた、うちの母の回し者なんじゃないの?」
あたしはぎくりとして、足が止まってしまった。幸い、あたりに人影はない。その態度で、リーレンは確信したようだ。
「やっぱりね。わたしにばかり親切にしてくれるから、おかしいと思っていたのよ」
「え、そうだったの?」
「そうよ。あなた、お勉強は余裕でできるのに、どこのクラブにも入らないし、他の女の子の部屋にも遊びに行かないでしょ。放課後も土日も、わたしと一緒。だからといって、わたしにお熱というわけでもないし。妙に冷静でしょ、ダイナって」
うわあ。
冷静なんて、初めて言われた。
シレール兄さまが聞いたら、天を仰ぐわ。
あたしは小さい頃から、蜂の巣を調べようとして蜂に刺されたり、木から木へ飛び移ろうとして墜落したり、ベッドの下で蛇の卵を孵して探春姉さまに悲鳴を上げさせたり、色々してきたから。
「自転車の乗り方もすごかったわ。他の人が何人も転倒していたでこぼこ斜面、すいすい下っていったでしょ。あそこ、競技用の練習コースなのに」
ひええ。
護衛しながら控えめに遊んだつもりが、大間違い。
それじゃあ、泉にも見られていたんだ、きっと。
「本当は、大学生なんじゃない? ママがあなたに頼んだんでしょ、わたしの護衛。きっとダイナは、武道の達人なのね。対象が学生の時、学生を護衛任務に就けることがあるって、聞いたことがあるもの。泉先輩には、それがわかったんだわ。だからむきになって、あなたを試してた……もしかしてダイナは、先輩よりずっと強いんじゃない?」
リーレンを騙すなんて、とても無理だと悟った。それで、やむなくあたしの部屋に呼び入れ、扉を閉めた。クローゼットの中からバッグを出し、中に隠しておいた銃を見せると、さすがに水色の目を丸くする。
「これ、本物?」
「もちろん。学校から外に出る時は、携帯するわ。言わなくて悪かったけど、あなたの考えた通りよ。あたし、大学を卒業したら、司法局に入ることが決まってるの。だから、ちょっと早めの実戦配備というところ」
まさか、『辺境生まれの違法強化体』とまでは打ち明けられない。中央の市民社会では、人体改造は禁忌だから。
悪党狩りのハンター〝リリス〟の活躍のおかげで、市民たちもだいぶ強化体アレルギーを薄れさせてはいるけれど、他の生徒に知られたら、父母も巻き込んだ大騒ぎになってしまう。
「でも、これはあくまでも、念のための用心だから。怖いことは、何も起こらないと思うの。もしも何かあったとしても、あたしが守るから。怪しい人とか、怪しい気配とか感じたら、すぐあたしに言ってね。外出する時も、あたしから離れないようにして」
しまった。安心させるより、怖がらせてしまっている。ベッドの端に座ったリーレンは、うつむいて涙をこらえている様子。
「ごめんね、怒った? 騙すつもりじゃなかったんだけど」
でも、茶色い髪の少女は、首を横に振る。さらさらの髪が揺れるのは、いい風情。
「ダイナは、わたしのために苦労してくれていたのね。それなのに、わたし、ひどい態度を取ってしまって」
あ、よかった。
これなら、警護が楽になりそう。
「まだ、たいした苦労はしていないから、大丈夫よ」
女学校生活、たっぷり楽しんでいるし。
「ううん。ダイナの大学生活を中断させてしまって、本当にごめんなさい。都会にいたんでしょうに、こんな田舎の山の中に来てもらって……」
「そんな、気にしないで。あたし、任務を与えられて嬉しいのよ。こういう仕事がしたくて、今まで修行してきたんだから」
「そうなの? 無理に押し付けられた仕事じゃない?」
「とんでもない。喜んで引き受けたのよ。ちゃんと報酬は出るし。これで認められたら、次の仕事も任せてもらえるし。大学の単位はほとんど取っているから、卒業も問題ないわ」
真実はちょっと違うけれど、そう大きな嘘ではない。自分の口座に自分で稼いだお金が入るというのは、とてもいい気分。町で買い物するのも、喫茶店に入るのも楽しい。自分の一族が管理運営する都市にいると、お金を使う場面すらないのだ。
「ダイナの迷惑でないなら、よかったけど……」
リーレンはあたしの横で、膝の上で組んだ指先を見ながら言う。
「ママがね、違法組織に狙われているのは知ってるの。グリフィンの懸賞金リストには載っていないけど、脅迫が来たことも何度かあるから」
懸賞金制度の管理責任者であるグリフィンの名前は、一般市民にも広く知られている。素顔も居場所も不明だけれど、違法組織の“連合”の頂点近くに位置する人物らしい。中央の政治家も官僚も、学者も実業家も、この暗殺リストに名前が載ったら大物だ。
「ママはわたしには何も言わないけど、そういう時は、警備が厳しくなるからわかるのよ。でも、議員の仕事は誰かがしなくちゃならないでしょ。悪い人たちを取り締まる法律を作るのは、とても大事なことなんだもの。パパからも、お祖父さまやお祖母さまからも、そう教わってきたわ。議員の家族は、その危険を共に引き受けるのが務めだって。わたしがこの学校に入れられたのも、お祖母さまの母校だからという以前に、やっぱり安全だからよ。首都の学校に通っていたら、誰でも狙えるもの。ここに来る前は、友達の家に遊びに行くのも警備付きだった。ここに来たからこそ、身辺警護がなくなったのよ。だから他にも、有名な学者の娘とか、資産家の娘とかいるでしょ」
政治家の娘には、やはり、それなりの覚悟があるらしい。
「わたし、ここでは護衛は要らないと思って、安心していたの。でも、あなたが来たということは、やっぱり、議員の家族の暗殺事件が増えているからなのね」
あたしがただの同級生だと思うのと、護衛だとわかっているのとでは、リーレンの日常の楽しさが違ってくるのだ。
「ごめんね。護衛だと知られないように、努力してたんだけど」
「ううん、それはもういいの。ダイナがわたしを守ってくれるなら、それは嬉しい。こんな素敵なボディガード、初めてだもの」
きっぱり言われ、あたしはほっとしたけれど、そこでまた、リーレンの視線が下がった。
「ただ、ほら、泉先輩がね。わたしのことなんか、最初から眼中になかったんだなって思って……先輩って、ダイナのことだけ、すごく意識してるんだもの。やっぱり、ライバル意識が湧くのね」
あきらめたような、寂しい微笑みを浮かべる。ちょっと、きゅんときた。
あたしが男だったら、肩を抱いて、頬にキスしてあげるんだけどな。元気を出せよ、きみはとっても魅力的だよって。
あ、だめ。ストップ。
そんなこと、考えるのはまずい。あたしも何か、変な方向に逸れてしまいそう。変と言ったら、探春姉さまに悪いけど。
あたしは絶対、渋いハンサムと大恋愛するんだもんね。女の子と疑似恋愛なんか、しない。
「ねえ、今度は町でボーイハントしない?」
と明るく提案してみた。
「ええっ!?」
「たまにはいいでしょ。男の子に声かけて、お茶するくらいは。あたしがいるから、おかしな真似はさせないし」
よかった。リーレンが笑ってくれた。
「ダイナったら、ずいぶん不真面目なボディガードね」
「真面目ですよ。男の子と付き合うのも、人生修行のうちだもの。こっちから男の子を選んで、主導権握っていればいいのよ。もちろん、先生方には内緒だけど」
「いいわ。男の子とお茶。ダイナがいてくれるんなら、試してみる」
あたしにとっても、それは大冒険。わくわくしてきた。相手が青年や中年なら、十二歳の男の子とデートするのとは、きっと大いに違うはず。
ところが、その夕方のこと。
部屋で腹筋や腕立て伏せをしていたあたしは(でないと、運動不足で気持ちが悪い!)、腕の端末に振動があったので、小さな通話画面をのぞいた。リーレンが自室から出た時には、振動で知らせるように設定してあるのだ。夕食にはまだ早い。誰かの部屋に、宿題の答え合わせにでも行くのかと思ったら、泉と一緒ではないか。
警備カメラ経由の映像は次々に切り替わり、リーレンの姿を追う。泉は長いコートを着て、その下に何か細長いものを隠していた。剣道の竹刀? なぜまた、そんなものを?
二人は寮の最上階を経由して、屋上庭園へ向かう。晴れならともかく、この雨の夕方に。
嫌な予感がして、あたしは部屋を出た。上着も持たず、Tシャツにスパッツだけの格好。
「あら、ダイナ、もう歴史のレポート済んだ?」
「え、ううん」
「ねえ、やっぱり文芸部には入らないの?」
「うん、ごめんね」
誰に呼び止められても最低限の返答で通り過ぎ、階段を上がる。屋上庭園に出る手前の空間に、二人の姿はない。外に出たのか。
あたしも屋上に出ようとして、ためらった。
もしかして、プライバシーの侵害にならないだろうか。
たとえば、リーレンが泉にラブレターでも出して、その返事を聞くとかいう場面なら。振られて泣くことになるのか、あるいは、あまりその可能性はないと思うけれど、ラブシーンになるのか。
別に、女の子同士で恋愛ごっこをしたって、構わない。何をしても妊娠することはないから、問題ないと言えばない。
ただ、頭に浮かんだのは昔の事件のこと。
女の子が女の子を強姦したというのは、いったい、どういうことだったのか。


これほど自分をぼろぼろにして、わかったことは一つきり。
――ダイナにとって、わたしは路傍の小石にすぎない。
誰もいない医務室の奥、医療カプセルの薄闇の中だった。
肉体は鎮痛剤のために麻痺しているけれど、精神は覚醒している。
頭の芯にあるのは、絶望的な執着心。まるで、叶わない片思いをしているよう。
これまで、ただの一度も、誰かを心底から羨んだことなどなかったのに。
――ダイナをこのまま、通り過ぎさせはしない。
ほんの一瞬でもいいのだ。ダイナを本気にさせたい。
だって、ずるいではないか。
わたしが欲しかったものを全て持っていて、なおかつ、ただの女の子のような顔をしているなんて。
もしもわたしが男なら、無理を承知でダイナにまといつき、しつこく口説いていただろう。振られても、永遠に憧れ続けることができただろう。
でも、女同士では。
わたしはダイナに、ライバルとして見てもらうことすら叶わない。ただ、通りすがりにちらと、軽い哀れみをかけられるだけ。
ダイナを見ていなければ、わたしはこのまま学園を卒業し、普通の大学生になり、普通の市民として一生を終えていたろうに。
この一件が、それほど大きな問題になるとは思っていなかった。シャルマ校長と吉田先生には、
『泉に、あたしの身分を知られたんです。挑戦されてしまって、やむを得ず』
と説明し、どうにか認めてもらったから。
でも、泉を気に入っている教頭のブッシュ先生は、シャルマ校長になだめられても、ぶつぶつ文句を言っていた。武道の高段者のくせに、手加減もできなかったのかと。
『手加減したからこそ、泉は医務室泊まりで済んだんです』
と、つい言ってしまったら、凍るような目で見られた。
『それはそれは、わたくしの生徒を病院送りにしないでくれて、どうもありがとう』
それからはもう一切、言い訳をしないことにした。泉の怪我自体は、たいしたことはない。校医の先生も言ってくれた。しばらくは痛むし、熱も出るけれど、休んでいれば治ると。武道家を志す者なら、打撲や骨折くらいは当たり前。まして、泉自身の望んだこと。
躰の回復を待つうちに、心の整理をつけてくれますようにと祈った。
泉の悩みなんて、本当は、たいしたことではない。
一番辛いのは、『誰かに勝てないこと』ではなく、『この世に、自分より強い誰かがいない』ことなのだから。

――けれど翌朝、食堂に入った瞬間にわかった。全校に、よからぬ噂が流れていることが。
あたしの姿を見た途端、食堂のざわめきが瞬間的に引いた。まるで、全員が息を止めたかのように。それからまた、おしゃべりが始まった。意図的に、あたしを排除して。
いつも声をかけてくれるサラや雪乃やマリアムたちが、揃ってあたしから顔を背け、目を合わせないようにしている。上級生も下級生も、あたしが近くを通り過ぎると、わざとらしく声を潜める。そのくせ、遠くからはあたしの一挙一動を見張っている。まるで、疫病の保菌者を監視するかのように。
あたしは耳がいいから、遠くのささやきもよく聞き取れた。
「ダイナって、本当はすごく怖い子なんだって……切れると、凶暴化するらしいわ」
「だからこれまで、学校に通えなかったのよ」
「前にも暴力事件を起こしているから、ここではおとなしいふりをしようとしていたらしいけど、結局はねえ……」
「ジャングル育ちで、まともな躾を受けていなかったらしいわよ」
あたしはターザンですか。確かに、庭の木に綱を渡して、ターザンごっこはしたけれど。
「やっぱり、退学になるんじゃない? 泉先輩、しばらく動けないらしいわよ」
「リーレンが屋上で泉先輩に迫ってて、それを見たダイナが逆上したらしいわ。竹刀で先輩に殴りかかったんですって」
「ほら、ダイナって、いつもリーレンに付きまとっていたでしょ」
「あれって、ただの仲良しじゃなくて……そういうことだったの?」
「リーレンてば、相当大胆な迫り方してたみたいよ。泉先輩は、リーレンのことなんか何とも思っていないのにね」
「先輩がお気の毒だわ。ダイナが勝手に誤解して、焼き餅やいたのよ」
「これじゃ、泉先輩、今度の惑星選手権には出られないかも」
リーレンが、今日は休むと言うはずだ。ベッドから出ないまま、風邪をひいたと言い張っていたけど、さぼりに決まってる。
居心地の悪さは、教室でも同じだった。みんな、あたしが存在しないかのように振る舞っている。
授業中はいつも通りに指名されたり、班ごとに化学の実験をしたりしたけれど、休み時間になると、誰もあたしに近付いてこない。そのくせ、あたしから遠い所では、尾ひれを付けた噂話に夢中。
もしかして、この事件が学園の新たな伝説になるのかしら。三角関係の挙句の決闘騒ぎって。
紅泉姉さまが聞いたら、お腹を抱えて笑うだろうな。すると、過去の強姦事件とやらも、実際には、たいしたことのない諍いが拡大解釈されただけかも……あたしがリーレンに熱烈な片思いだなんて、よくもまあ脚色してくれる。
でもまあ、護衛と悟られなかっただけ、ましなのかな。とにかく、任務さえ果たせれば、あたしの居心地なんて二の次、三の次なんだから。
放課後、リーレンの部屋にお見舞いに行った。部屋に入れてもらえないかも、と思ったけれど、
「どうぞ」
と言われたので、ほっとする。部屋に入ってドアを閉ざしてしまえば、興味津々の見物人たちは遮断できる。
リーレンはチェリーピンクのパジャマのまま、ベッドでクッションにもたれていた。いつものヘアバンドをしていないので、しどけない感じ。男の子が見たら、色っぽいと思うだろうな。
「風邪はどう?」
「うん、まあ……あの……本当は、さぼりなの」
「まあ、そうだと思った」
「だって、朝、ドアを開けたら噂が聞こえて……あんまりひどいから……ダイナは、ちゃんと授業に出たの?」
「出ましたよ。噂も仕入れてきたわ。あたしとあなたと泉とで、ありとあらゆる状況が設定されているみたい。でも、逢い引きなら、雨に濡れない場所を選ぶわよね。あんな所でいちゃついてたら、本当に風邪ひいてしまうわ」
厭味のつもりではなかったのだけれど、リーレンは顔を手で覆った。
「ごめんなさい。まさか、こんなことになるなんて……だって、泉先輩に、屋上で話したいって言われたから……それも、ダイナのことだっていうから……」
そりゃあ、泉が目的を持ってリーレンを釣ったのだから、リーレンが抵抗できるわけがない。
「みんな、退屈しているのよね。そこに話題を提供したんだから、あたしたち、いいことをしたのかも」
するとリーレンは、指の間からあたしを窺う。
「ダイナ、平気なの? だって、ダイナがまるで異常者みたいに……」
「ここまで言われると、いっそ笑えるわ。全部報告書に書くから、バックアップ班でも苦笑するでしょうよ」
女の子だけの学校には利点もあるけれど、歪みもあるのだと実感した。本当は、男女半々が自然なのだから。年頃の女の子だけを集めて閉鎖空間に押し込めたら、後輩いびりだって、疑似恋愛だって発生するだろう。
「ダイナって、大人なのね」
リーレンはため息をついた。あたしが『二十歳の大学生』だと信じているからだ。
「わたし、勇気がなくて。これまで、自分が人の噂をするのは平気だったのに。噂される側になるって、辛いのね……」
「それじゃあ、泉はずっと辛かったでしょうね。みんなの憧れで、注目の的になっていて、どこにも逃げ場がなくて」
リーレンは、はっとしたようだった。
「ダイナ、それよ。やっぱり、そこなんだわ」
うん?
「わたしたち、いけなかったのよ。いえ、あなたのことじゃなくて、この学院の女の子たちみんな。無責任にキャアキャア騒いで、まとわりついて、泉先輩を疲れさせていたんだもの。今年は三位じゃなく、優勝してほしいなんて……勝手な期待よね。自分たちは、見ているだけのくせに。先輩は内心でさぞ、うんざりしていたんだと思うわ」
まあ、それはその通り。
泉がミーハー娘たちにうんざりしていたのは、本当だろう。
でも、長年〝正義の味方〟をやっている紅泉姉さまは、人に憧れられても、逆に嫌悪されても、飄々としている。あたしも、ああいう風に振る舞いたい。
正直、今日は一日辛かったけれど、いい勉強になった。
あたしが違法強化体とわかったら、あんなものでは済まないはず。生徒の父母が学校に押しかけてきて、あたしは吊るし上げをくらった挙句、叩き出されるわ。
「まあ、そういう重圧に耐えるのも、修行のうちだから。泉だって、その覚悟があるから、厭な顔をせずに〝みんなの憧れ〟を務めてきたんでしょう。そこにあたしが現れて、ちょっとだけバランスを崩したんだと思うの。すぐにまた、冷静な泉に戻るわよ。昔は、オリンピックで優勝できなかった選手が、故国の人たちに申し訳ないって思い詰めて、帰りの旅の途中で自殺したりしたらしいけど」
しまった。余計なことを言ってしまった。
リーレンは水色の目を見開き、桜色の頬を両手で押さえた。
「たいへん。ダイナ、お願い、先輩のお見舞いに行って!! 何か励ましてきて!! いえ、わたしだって行きたいけど、わたしなんかじゃ、かえって迷惑になるだけだもの!!」
「まあ、確かに、今は噂の嵐だから……リーレンだって一応、風邪ひきの病人なわけだし……泉も人に会いたくないだろうから……」
「ううん、そういうことじゃなくて。ダイナ、わたしね、昨夜、眠らずに考えていたの。いえ、その分、昼寝してしまったから、全然偉くないんだけど。あのね、泉先輩から見たら、対等な競争相手はダイナしかいなかったのよ。わたしなんか、ほんとに、相手にする値打ちもない小娘だったって、よくわかったの……」
泉に『関係ない』と切り捨てられ、したたか傷ついたと思うのだけれど、リーレンは一晩でそこから立ち直ってきたらしい。
「今頃ようやくわかるなんて、ほんとに馬鹿よね。甘ったれの大馬鹿娘よ。ダイナみたいに、自分を鍛え上げて、なおかつ高い目標を持ち続けている人でないと、先輩に視線を向けてもらう値打ちすらなかったんだわ。わたしなんかが周囲をうろうろしたって、ただ目障りなだけ……」
いや、そこまで卑下しなくても。
「でも、みんなから応援されているのは、泉だって嬉しいと思うけど?」
「ううん、どうせ応援するなら、先輩の負担にならないようにするべきだったのよ。いいえ、それ以前に、先輩に振り向いてもらえるくらい、立派な自分にならないといけなかったのよ。わたし、これから色々頑張る。勉強でも何でも、もっと真剣にやってみる」
あれ、まだ泉のことをあきらめていないのか。
「今日はちょっと、臆病で授業をさぼってしまったけど……明日は、ちゃんと出るから。噂も気にしないようにする。毅然としていれば、そのうち消えてなくなるはずよ。それで、いつか、対等に向き合う値打ちのある人間だって、先輩に認めてもらえるようになる……いえ、なれないかもしれないけど、努力はしてみるつもり」
前向きだなあ。
まあ、いいことかも。あたしが紅泉姉さまに憧れるみたいなものだ。目標があれば、努力しやすい。
「わかったわ。何にしても、頑張るのはいいことよ。それじゃ、とにかく……今日のところは、あたしが泉の様子を見てくる。会えないかもれないから、期待しないで待ってて。会えたら、あなたが心配していること、ちゃんと伝えてくるから」
「ありがとう」
リーレンはようやく、安堵した笑顔になった。
「ダイナって、頼もしいのね。わたし、ダイナが来てくれて、本当によかったわ。くじけそうになったら、ダイナのことを思い浮かべるわね」
うひゃあ。
「そんな、あたしなんか、たいしたもんじゃ……」
ここで自惚れたりしたら、シレール兄さまに叱られる。
「ううん、ダイナはすごいのよ。だって、泉先輩を本気にさせたんだもの」
強化体だから、と打ち明けられないのが辛い。
あたしは自分がここに来てよかったのか、自信がなくなってきた。
泉やリーレンの学園生活を台無しにしただけで終わったら、どうしよう。
泉は校舎内の医務室から、寮内の自室に戻されていた。あたしは上級学年の暮らす最上階に上がり、すれ違う上級生たちの好奇の視線を浴びながら、泉の部屋にたどり着く。
面会を拒絶されるかもしれないと思ったけれど、ノックして名乗ったら、
「どうぞ」
という穏やかな返事。
よかった。泉もまた、何らかの悟りに到達したのかもしれない。
それとも、他の生徒たちの手前、平静を装っているだけ?
「あのう、ちょっとだけ、様子を見に……」
恐る恐るドアを開け、内部に滑り込んだ。室内には、薄荷のような薬の匂いが立ち籠めている。
短い黒髪の少女はあちこち保護シールだらけになって、ベッドにいた。リーレンの仮病とは違い、明らかに辛そうだ。それでもなおかつ勉強していたらしく、上掛けの上で数学のテキストを開いている。
「横になったままで、ごめんなさいね。少し熱があるの」
「あ、もちろん、そのままで。すぐ退散するから」
それでも泉は、あたしに椅子を勧めてくれた。自分は、ベッドの背にもたれた状態で対面する。
本人の地味なTシャツ姿と、何の飾りもない部屋が痛々しい。わずかな持ち物はきちんと整理され、所定の位置に収められている。まるで修道女の部屋のよう。
女の子の部屋は、もっときらきら、ふわふわしているべきではないのか。
といっても、下の階にあるあたしの部屋も、似たようなもの。護衛生活の今は、最低限の品物しか置いていない。
「熱がある時くらい、ゆっくり休めばいいのに……」
すると、穏やかな自嘲の笑み。
「貧乏性なのよ。何かしていないと、時間が勿体なくて」
少し安心した。冷静に話をしてくれそうだ。
「まだ痛そうね」
怪我をさせてごめん、とは言えない。あたしが、そうするべきだと思ってしたことだ。
泉も、恨み言を言うつもりはないらしい。
「少しはね。でも、集中治療してもらって、だいぶ楽になったから」
「それならよかった。選手権に出られないと困るものね。来月だっけ?」
泉は少し、妙な笑い方をした。
「それはね、もう、出なくてもいいかなって気がする」
優勝を狙うのはあきらめた、ということかしら。それとも、拳法そのものをやめるつもり?
「成績は気にしないで、自分の修行というつもりで出れば……」
「何だか、気が抜けてしまって。もう、どうでもいいような気がするの。こんな気分で出場したら、下級生にも示しがつかないし、他の選手にも失礼だわ」
これまで張り詰めていた緊張の糸が、切れてしまったのかもしれない。
でも、泉の場合、それは良いことの気がする。ずっと緊張しっ放しでは、保たないもの。
何年かのんびり暮らせば、またそのうち、修行の続きをしたくなるかもしれない。そうしたら、そこから先で、本物の強さに到達できるのではないだろうか。
「あのね。あなたがまた稽古したい気になったら、あたし、相手をするけど……ほら、みんなには内緒で、こっそり。リーレンの護衛に差し障りのない程度にね」
自分より弱い相手としか戦っていないと、鈍ってしまう、ということがある。泉の伸び悩みも、それが原因かもしれないし。
「ありがとう、ダイナ。あなたの親切は、よくわかっているの」
え、そうなの?
「わたしが無理を言って挑戦したせいなのに、あなたが悪者になってしまって、申し訳ないわ。校長先生にも教頭先生にも、そう説明したつもりなんだけど」
あたしは大いに安心した。泉はやっぱり理性的だ。
「大丈夫よ、お咎めはなかったから。あなたに挑戦されて、つい熱くなりすぎただけ、で済んだの。ほら、あたし、本物の生徒じゃないから、処罰の対象にはならないのよ」
「それならよかった。おかげでさっぱりしたわ。わたし、視野が狭くなっていたのね。考えすぎて、自分を袋小路に追い込んでいたみたい」
泉がそう思ってくれたなら、問題は解決だろう。あたしたちが仲良くなった様子をみんなに見せれば、おかしな噂も消滅するはず。
いや、そうしたら、今度はあたしと泉が『怪しい』とか言われるのかな。
まあ、何でもいい。泉とリーレンが、わだかまりなく付き合えるようになれば。
あたしはいずれ、任務終了でリーレンの人生から立ち去るけれど、残る一生、泉とリーレンは同窓の友人なのだから。
「泉はちょっと頑張りすぎて、疲れていたのよ。心も躰もね。しばらくのらくらしていれば、またそのうち、やる気が出てくるわ」
「そうかもしれない。のらくらって、いい言葉ね。やってみるわ」
リーレンは頑張るし、泉はのらくらする。いいことだ。
市民社会で、同じ年頃の女の子たちがどんな青春を過ごしているのか、遠い夢の世界のように思って漠然と憧れていたけれど、実際には似たようなことで悩んだり、落ち込んだりしているのだ。それがわかって、嬉しい。
「そうそう。リーレンがね、ひどく心配していたの。あなたに憧れて騒いだことで、余計な負担をかけたんじゃないかって。元気になって、そこらで会ったら、笑いかけてやってくれる?」
まだ数日は、リーレンを見舞いに来させるべきではないという気がした。下級生に会ってしまえば、泉はどうしても余計な気を張るだろうから。その分、回復が遅くなる。
「ええ、わかったわ。その時は、わたしからも謝っておく。昨夜は、ずいぶんひどい態度をとった気がするから」
「あれは、仕方なかったのよ。リーレンもわかってるから、大丈夫」
リーレンの失恋は間違いないけれど(だって、泉にはそういう趣味はないだろう)、今後はお互い、いい友達になれるだろう。
校内に広がった極彩色の噂のことを笑い合ってから、あたしは引き上げた。
あたしもまた、能天気だったのだ。
世の中、話せばわかることばかりではない。
もしもそうなら、世界はとっくにユートピアになっていただろう。
わたしが話した相手が、本物のグリフィンだったのかどうかはわからない。顔を見たわけでも、肉声を聞いたわけでもないからだ。
ただ、以前に接触してきた男が再度連絡してきて、グリフィンに回線をつなぐ、と言い出したのだ。
それが〝連合〟の頂点に近い大物であることは、誰でも知っている。
中央の要人たちに命の値段を付ける、闇の懸賞金制度の責任者。
拒絶する暇もなく、あの声が流れてきた。過去に何度も、新しい懸賞金リストを公開する時に、公共放送を乗っ取った人工音声。低く、錆びついたように不気味な声だ。もっとも、軽やかな声だった方が、余計に怖いかも。
『いいことを教えよう、泉。リーレンの護衛に付いた赤毛娘は、〝リリス〟の関係者だ。辺境生まれの違法強化体だが、司法局長が惚れ込んで後ろ盾になっている。クローデル局長は、ダイナを、新たなハンターとしてデビューさせるつもりだ。いつまでも〝リリス〟に頼るだけでは、司法局の権威も先細りだからな』

週末の外出日には、冷たい北風が吹いていた。赤や黄色に紅葉していた木々は、半分かた葉を落としてしまっている。空は低く鉛色の雲に覆われ、冬の予告編のような陰鬱さ。
でも、女の子たちはお気に入りのコートを着たり、手編みの帽子をかぶったりして、元気一杯、バスに乗り込んでいく。話題はそろそろ、冬休みのこと。
「新年は、お祖母ちゃんの家に行くのよ。ほんとの田舎で、牛と馬しかいないの」
「お兄ちゃんがね、大学から戻ってくるのよ。お友達を連れてくるんですって。素敵な人だといいなあ」
「今年は一家で、海岸のホテルに泊まるのよ」
「うちはスキーと温泉。一族大集合なの」
あたしとリーレンも、そのざわめきの中にいた。ただし、微妙に外された位置に。
リーレンはコーラルピンクのワンピースの上に白いコートを着て、とても可愛い。あたしはオリーブ色のシャツと黒いワークパンツ、褐色の革ジャケットという地味な格好。髪が赤いのだけが、唯一のアクセント。
「ダイナ、冬休みはどうするの?」
他の生徒の耳があるので、
「後で話すわ」
と言っておいた。
泉が悪い噂を打ち消すように振る舞ってくれたけれど、クラスのみんなまだ、あたしとリーレンに距離を置いている。あたしとリーレンがくっついて行動しているせいで、三角関係のこじれという疑いが払拭できないらしい。あたしが泉より強いことを証明して、リーレンを振り向かせたんだろうって……
みんな本当に、恋愛ネタに飢えているのね。
ここを卒業して大学に入ったら、女の先輩に憧れていたことなんか、遠い過去になってしまうのでしょうに。
町に着き、バスを降りて二人きりになってから、そっとリーレンに話した。
「司法局の方でね、あなたのママに、許可を取ってあるんですって。仲良しの友達ということで、冬休みはリーレンと一緒に過ごせるようにって」
ほっとしたことに、リーレンは喜んでくれた。
「休み中、ダイナと遊べるの! 嬉しい!」
いえ、あたしは仕事ですから、遊ぶふりをするだけですけどね。
リーレンは新年はお父さんの実家で過ごす予定で、母親のリーナ・ツォルコフ議員も、仕事が片付き次第合流するそうだ。
「パパの実家はね、この町よりもっと辺鄙な田舎町なの。農場と牧場しかないところ。でも、自転車で走るには最高よ。素敵な川や丘があるの。お弁当持って走りましょ」
「うん、楽しみだわ」
その時は、車で護衛が付いてくるけれど。
今日は寒いのでサイクリング公園には行かず、ささやかな繁華街をぶらついた。
ブティックやブックカフェ、宝飾店に骨董品店。もちろん高いものは買えないから、見るだけ。でも、十分楽しい。
同じ年頃の女の子といられるだけで、あたしには、パーティみたいなもの。
歩きながら、二人して男の子を物色したのだけれど、なかなか、手頃な相手に行き当たらない。背伸びして、三十歳過ぎの男性に声をかけたりもしたけれど、笑っていなされた。
「悪いね、これから奥さんと待ち合わせだから」
ですって。
他の男性には、
「聖カタリナのお嬢さん方には、近付かないことにしているんだよ」
と苦笑された。
まるっきり、危険物扱い。
もしかして、教頭先生からの脅迫が行き届いているのかしら? うちの生徒に手出しをしたら、責任を取っていただきますよ、とか何とか。
二十歳前後の青年を探そうにも、ここには大学がないから、その年頃の青年は歩いていないという事実に、ようやく気が付く始末。
同じ聖カタリナでも、もっと気の利いた女の子たちは、既にあちこちで、地元の男の子たちとグループデートしていた。六、七人でカフェテラスに座っていたり、雑居ビルの店を冷やかしていたり。
十七、八歳以下の少年ならいるのだ、確かに。それでも、めぼしい男の子は、みんな予約済みという感じ。
「わたしたち、出遅れているみたいね」
リーレンが笑って言う。『色々頑張る』の中には、男女交際の経験値を積む、というのも入っているのだ。泉にまとわりついて邪魔にされるより、成長して対等な存在になる方が先という決意は立派。
「まあ、そう簡単にはいかないか。あたしも恋愛初心者だし」
「そうなの? でも、ダイナだって、誰か好きになったことはあるでしょ」
ない。
だって、あたしの周囲の男性ときたら、身内のおじさま、おじいさまばかり。みんな、姿は若くても中身は老人。すっかり枯れている。
シレール兄さまなんか、(辺境においては)それほどの年齢でもないくせに、亡くなった恋人に操を立てて、他の女性には見向きもしない。

歩き疲れて、喫茶店に入った。聖カタリナの生徒が、よく利用する店だ。
ポット入りの紅茶を頼み、チョコレートケーキとチェリータルト、レモンパイと抹茶ムースをお供に、理想の男性について語り合った。
たまたま好きな俳優が一致したので、あの映画のあの場面がいいのよね、と盛り上がる。
「でもね、いくら憧れたって、現実には、スターとお知り合いになる機会なんてないのよ。ファンレターを出したって、読んでもらえるかどうか。いずれはみんな、美人女優とか美人作家とか美人実業家と結婚しちゃうんだから」
うちの姉さまたちは、司法局経由で届く子供たちからのファンレターを読んで、笑い転げているけどな。嫌なことがあって、もうハンターなんか辞めようと思っても、励まされるんだって。あたしもいつか、ファンレターをもらう身になってみたい。
「これから、美人政治家を目指すって手もあると思うけど」
と、からかったら、リーレンは憤然とする。
「いやあよ。護衛連れでないと、どこへも行けない生活なんか」
それから慌てて姿勢を正し、付け加える。
「いえ、護衛の人たちには、いつも感謝してるのよ。ほんとよ」
あたしは笑った。
「大丈夫、わかってます。大学に期待したら? きっと、かっこいい男性がいると思うな」
あたしもできたら、大学に行ってみたい。この任務をやり遂げたら、クローデル局長に頼んでみようか……半年でいいから、大学に在籍させて下さいって。
そこで、同じ店内にいる女の子たちが、あっという顔をした。外からふらりと泉が入ってきて、あたしたちの席に近付いてきたからだ。
あの事件以来、この三人が一か所に集まるのは初めてか。
泉はグレイのセーターと黒のパンツ、濃紺のコートというあっさりした身なりだった。唇の赤みと胸のふくらみがなかったら、華奢な美青年みたい。もしも赤やピンクのドレスを着て、イヤリングでも下げたら、華やかな美女になるはずなのに。
それとも、自分であえて、そうはなるまいとしているの?
「こんにちは。少し話してもいいかしら?」
リーレンは咄嗟に口が利けないようなので、あたしが答えた。
「ええ、どうぞ」
ただ、周囲のテーブルから好奇心の視線が集まっているので、ここではまずい。何を話しても、学校中に放送されてしまう。
「よかったら、場所を移しましょうか」
ケーキの残りを口に放り込み、紅茶で流し込んで、コートを取った。リーレンも慌てて立つ。
三人で外に出ると、夕方近い風は湿って冷たい。じきに、降り出すのではないだろうか。
「どこへ行く?」
と泉。リーレンに風邪をひかせるわけにはいかない。
「車にしましょう」
と提案し、手首の端末で無人タクシーを呼んだ。交通管制システムとリンクしているので、適当に走らせておくことができる。利用料はきわめて安い。
中央では、普通に暮らすだけなら、たいしてお金はかからない。辺境では、安全確保のために経費がかかるのと対照的。護衛兵の一団がいなくては、散歩にも行けないのだから。
三人でタクシーの後部座席に座り、向き合った。八人くらいは楽に乗れる車だから、余裕がある。リーレンは泉に正面から見られるのが恥ずかしいらしく、コートの裾を直したりして、もじもじしていた。やっぱり、どうしようもなく泉が好きらしい。
ささやかな商店街は、すぐに走り抜けてしまった。あとは、田舎スタイルの住宅が続く。それぞれの庭先には、実をつけた林檎や蜜柑の木、赤い冬薔薇、白い山茶花の植え込みが続いて、いい風情。道を歩く人たちは、もうほとんど冬支度。
「この間は、ごめんなさいね。改めて、お詫びを言うわ。変な噂を立てられて、迷惑だったでしょう」
「いえ、そんな。気にしないで下さい。ダイナも気にしてないし。そうよね、ダイナ」
リーレンは、すがるような目を横のあたしに向ける。
「ええ、もちろん」
理由はどうあれ、全校の憧れである泉を叩きのめしてしまったのだから、女の子たちから総スカンを食らうのは当たり前。
当の泉は、しごく平静に言う。
「ダイナにも感謝しているわ。あなたが本気を出したら、わたしは死んでいたもの。さすが、違法強化体は強いわね」
えっ?
「それも、あなたの場合、中途半端な改造体じゃなくて、最初から遺伝子設計された完成品なんですものね。辺境でも有数の強さなんでしょう」
あたしは凍った。
聞き間違いではない。
なぜ、どうして、そのことを。
泉はいったい、どうしたというの。たとえ推測したにしても、断定口調で言うなんて。
この前、泉を見舞った時は、こんな態度じゃなかった。あの時は、すっかり和解できたと思ったのに。
リーレンが、まじまじあたしと泉を見比べた。
「違法、強化体……?」
そして、人間に混じっていた吸血鬼を発見したような顔になる。
「どうして!? どうしてダイナが強化体なの!?」
泉は更に、涼しい顔で暴露する。
「ダイナの従姉妹のお姉さまたちというのが、ハンターの〝リリス〟なのよ。リリーとヴァイオレットの二人組」
うわ。
「もちろんそれはコード名であって、本当の名前ではないけれど。ダイナは子供の頃から、そのリリーさんに、直に教えを受けてきたんですって。二人は任務の合間に、しばしば《ティルス》の屋敷に戻ってきたそうよ」
恐怖でお腹が冷えた。
なんで知ってるの。そんなことまで。
司法局だって、姉さまたちの出身地や、本当の名前までは知らないのよ。まさか、まさか泉は……!?
数秒の沈黙。それから、リーレンが水色の瞳でまじまじあたしを見つめ、尋ねてきた。
「本当なの……?」
この顔で問われたら、嘘はつけない。手を合わせて拝んだ。
「お願いだから、みんなには黙っていて。知られたら騒ぎになって、もう、護衛役ができなくなっちゃう」
するとリーレンは、歓喜の顔で叫ぶではないか。
「すごおい!! ダイナって〝リリス〟の親戚だったの!!」
あっ、えっ……
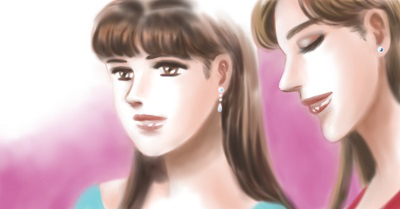

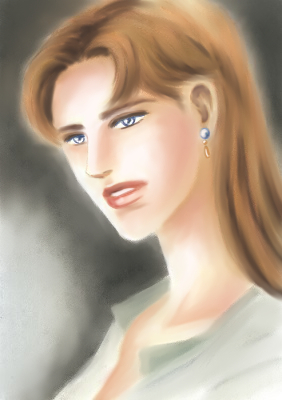
任務の切れ目でよかった。おかげで、惑星《サリヌール》の司法局支局から呼ばれた時、すぐに飛んでこられた。
医療カプセルの中で昏々と眠るダイナを見ながら、改めて思う。
――生きていてくれて、助かった。
この子が死んだら、あたしたちはシレールのことも失っていただろう。一度恋人を失っている彼にはもう、これ以上の喪失は耐えられないだろうから。
いや、一族全体が、がっくりと気落ちしてしまったはず。この子は探春に代わって、一族のアイドルになっているから。
何よりあたし自身が、後悔に耐えられなかっただろう。格闘技なんか教えるんじゃなかった、戦う心構えを持たせたりするんじゃなかったと。
本当は、わかっていた。ダイナを思う通り行動させておいたら、いつかは、こういうことになると。
今回は、まだ幸運だった。命があっただけで、奇跡のようなものだ。いかに優秀な強化体とはいえ、無敵でもなければ、不死身でもないのだから。
もちろん、こんなつもりではなかったのだ。リーレンの母親は、若手議員の中では有望株だというだけで、まだ大物というわけではない。その娘の警護なら、しかも山奥の女学校なら、たいした危険はないと思っていた。
ダイナが学校生活を楽しんでくれれば、という程度の『お試し任務』……こちらの認識が甘かったのだ。
いや、そもそも、あたしの覚悟が不十分。
ダイナを厳しく鍛えたいのか、それとも可愛がって甘やかしたいのか、いつも揺れ動いていた。
世界のためと考えれば、ダイナを冷徹な戦士に育てるべきだけれど、ダイナ自身の幸福を考えたら、それはどうなのか……せっかく、素直で可愛い女の子なのだから。
シレールの元で一族の仕事を分担するだけ、いずれはシレールとの間に子供を作って、優しいママになる。そういう人生だって、いいではないか。
もっとも、親友の探春はクールに言っていた。
『子供は勝手に育つわ。ましてや、ダイナですもの。周囲の思惑なんか、自分で打ち破るわよ』
迷いがあったのは、あたしだ。
あたしは自分の思い通りに『正義の味方』をやってきたけれど、何が正義かは、簡単に決められるものではない。おまけに、周囲に迷惑をかけまくっている。死なせてしまった軍人や捜査官、どれだけいることか。
こんな道を若い子に勧めるなんて、とてもできない。
敵も強大だ。『邪悪な誰か』ではない。『誰もが持っている邪悪』は、根絶できないからだ。
死にたくないという欲。
自分だけ得をしたいという欲。
それは、生命力そのものでもある。それが寄り集まって、〝連合〟という形になっているだけ。
これまでの数十年、『よく死ななかったな』と自分で感心するくらい、ぎりぎりの局面を幾度もくぐり抜けてきた。人の助けもあったけれど、あとは単なる幸運だ。幸運は、いつか尽きる。その時はあたしだけでなく、探春も道連れにしてしまう。
『好きであなたの相棒をしているのだから、いいのよ』
と探春は言うけれど、一緒に死ぬのならともかく、探春だけを先に死なせてしまったら、どうしよう。
それがあたしの最大の恐怖なのに、ダイナの命まで、とても背負えない。ダイナを一番に愛しているのはシレールだから、あたしは彼の命まで、崖っぷちに追いやったようなもの。
幼いダイナに憧れてもらい、慕ってもらうのはとても嬉しかったけれど、後ろめたくもあった。シレールからは常に、警戒の視線を向けられていたし。
彼には散々〝リリス〟の援護をしてもらってきたから、舞台裏を何もかも知られている。
無謀。気まぐれ。行き当たりばったり。
(あたしはそんな、たいしたもんじゃないのよ。金持ちの一族に生まれたから、援護してもらえただけ。手本になんか、しないでよ)
善意ではあったけれど、失敗もした。人も死なせた。いや、多くはこの手で殺したのだ。殺すしかないと判断した時は。その判断が間違っていたと、後からわかったこともある。
だから、ハンターなんかに憧れるんじゃない、汚れ仕事なんだから、と繰り返しダイナに説教した。実際の危険についても、説明した。それでも、ダイナが怖じ気ていないのを見て、誇らしくも心強くも思っていた。
あたしだって、あたしと肩を並べて戦ってくれる仲間が欲しい。探春は確かに頼れる相棒だけれど、あたしが戦うから仕方なく付いてきてくれるだけで、探春自身が積極的な闘士というわけではない。
ダイナが成長して、あたしに匹敵する戦士になってくれたらと……あるいは、あたしを超えてくれたらと……少しは期待していた。
勝手な期待だ。
それが危うく、ダイナを死なせるところだった。
(ダイナは、これで懲りるかな……)
ダイナ本人のためには、懲りて臆病になるのが一番だ。一族の領土に籠もって、地道な商売だけしていた方が長生きできる。
でも、懲りずにまた、次の戦いに出向いていくとしたら……世界は、新たな希望を手にしたことになる。
育ての親のシレールだけではない。あたしを含め、一族全員が、この子に希望を託しているのだ。
遺伝子設計者である麗香姉さまが、『自分の研究人生の集大成』と言うだけの優秀さ。いつか、あたしたちが〝連合〟と武力対決することになったら、その戦いを指揮するのは、ダイナかもしれないのだ。
「この子は懲りたりしないわよ。目を覚ましたら、けろりとして“お腹空いた”なんて言うはずよ」
共に病室に立つ探春は、微笑んで言う。
「紅泉、あなたが今になって後悔したって、手遅れよ。この子はもう、司法局にも期待されているんだから」
その通りだ。
ミギワ・クローデル司法局長も、部下たちにこう命じていた。
『いざという時は、リーレン・ツォルコフよりも、ダイナの命を優先して守りなさい。もちろん、あなたたちの命よりも優先です』
ダイナがリーレン警護のバックアップ班と思っていた捜査官たちは、実際には、ダイナの命を守るために待機していた。ただの少女にすぎないリーレンより(たとえ、将来にどんな可能性があろうとも)、中央と辺境の橋渡し役になりうるダイナの方が、はるかに貴重だから。
今回の任務はそもそも、ダイナに実務の経験を積ませ、捜査官たちと協力する練習をさせ、将来への布石にするためだった。長年、市民社会の防衛に務めてきた自分が第一線を退く時には、何とか新たな切り札を後に残していきたいと、ミギワは願っている。
考えてみれば、泉という娘も、気の毒なのだ。ダイナの輝きに目がくらみ、嫉妬と羨望に苦しんで、グリフィンの誘惑に負けてしまった。
まあ、グリフィンだって、駄目で元々という程度の、気軽な『お試し作戦』だったろうけれど。
ダイナにとって、これが『痛い教訓』になればいい。恵まれた者には、そうでない者の痛みは、なかなかわからない。そう、このあたしにも。
ダイナは人生の早いうち、人の恨みや憎しみを受けて、たっぷり悩むといいのだ……
意識を取り戻した時は、知らない部屋にいた。どうやら、医療ベッドの上らしい。
安心だとわかったのは、枕元に見慣れた姿があったから。
「お目覚めかね、お姫さま」
金褐色の髪を黒く染めた紅泉姉さまは、白いシャツに黒いミニスカートを合わせ、金のイヤリングを煌めかせている。長身と不敵な笑みで、いかにも〝謎の美女〟という感じ。
「もう大丈夫よ。治療は済んでいるわ」
茶色い髪を優雅に結い上げた探春姉さまは、クリーム色の上品なワンピースに、真珠のイヤリング。お姫さまみたいな愛らしさ。あちこちで一目惚れされるのも、無理のないこと。本当は筋金入りの男嫌いで、敵に対しては、紅泉姉さまよりも冷徹なんだけどね……
「ねえ、さま……」
かすれていたけれど、声は出た。
あたし、生きている。
左手を持ち上げてみたら、ちゃんと手がある。指も動く。
「もう、動かしても大丈夫。ただし、激しい運動はしばらく禁止だからね」
神さま、ありがとう。
あたし、まだ人生を続けられる。シレール兄さまに会える。
兄さまはきっと、『それ見たことか』と、冷ややかに怒っているわ……
リーレンも無事だと聞いて、ほっとした。検査のために一日入院したけれど、問題はなかったそうだ。今はご両親と一緒に、近くのホテルにいるという。
ここは首都の中央病院の、特別病棟。一般人は、立ち入り禁止。陽動の爆弾騒ぎでは、軽傷者が何人か出ただけだとか。
紅泉姉さまがあたしを支え、ストロー付きの容器で、甘いレモネードを飲ませてくれた。染み込むように美味しい。喉が潤い、声が戻ってくる。
「それじゃ、ウィルスは……」
「グリフィンは確かに、泉に本物のウィルス兵器を送ってきていた。でも、泉はそれを使っていない。あんたたちに見せたカプセルは、鼻炎用の噴霧薬だった」
それでは泉には、最初から、リーレンを殺すつもりは全くなかったのだ。蹴りさえも、加減していた。泉が本気だったら、リーレンには骨折や内臓破裂という被害があったはず。
それなのに、あたしは泉を殺してしまった。あの時は、自分が助かることしか考えられなくて。
「あたし、泉に撃たれたの?」
「いいや。狙撃手が川向こうにいたんだよ。サマンサ・ブッシュ。あんたの学校の教頭先生」
あの、謹厳の代名詞のようなブッシュ先生が!? 狙撃用の銃を持って、茂みに潜んでいたというの!?
「若い頃は、スポーツ万能だったらしいよ。射撃も名人級。持っていた銃は、学校の科学工作室で密造したものだった。彼女とお仲間たちは、司法局ビルで尋問を受けている。おかげでわかった。聖カタリナは、何年も前から汚染されていたってことが」
そうなんだ。
「有名人の娘が多いでしょう。グリフィンは何年もかけて、教師や生徒、出入りの業者を手先にしていたの。不老処置で誘惑したり、深層暗示で操ったりしてね」
「ただ、一度しか使えない罠だから、慎重に、相応しい獲物を待っていた。そこへ、あんたが飛び込んだわけ。〝リリス〟の血縁者がね」
「泉があなたの首を切断し、生命維持装置に入れて、川向こうのブッシュ先生に投げる予定だったの。あなたのバックアップ班が妨害されているうち、泉もブッシュ先生も、別々の脱出ルートで逃げる手筈だった。あなたが首の切断に耐えきれずに死んだとしても、生きているように装えば、わたしたちを脅迫できるものね」
あの時刻、地元警察も司法局支局も、陽動の爆弾騒ぎに気を取られていた。おまけに、あちこちにグリフィンの協力者が配置されていた。惑星警察、宙港、航行管制局、民間輸送船。あたしが泉を殺していなかったら、彼女たちの企みは成功していただろう。
「あたし、馬鹿だったわ。泉やリーレンに、余計なことをしゃべりすぎたのね」
穴があったら入りたい。
あたしが敵わない従姉妹の姉さまがいるというだけで、大きな秘密を洩らしたことになるのだ。
「そうだ、あたしたちの本拠地、向こうに知られているみたい」
グリフィンは、〝リリス〟が辺境に後ろ盾となる組織を持っていることを知っている。それがどこの組織か、突き止めようとしてきたはず。夜歩きしているあたしの姿が《ティルス》で撮影されていて、今回、重大な手掛かりを与えてしまったのかも。
もしや今頃、〝連合〟の大艦隊が《ティルス》を包囲しているのでは!?
ベッドの上からそう訴えると、椅子にかけている姉さまたちは、互いに顔を見合わせた。紅泉姉さまが、穏やかに言う。
「それは、気にしなくていい。たぶん、とうに知られていたことだと思うよ」
「えっ、そうなの!?」
「あたしだって子供の頃、散々、繁華街で暴れたからね。多少の偽装なんか、見抜かれていておかしくない。それでも〝連合〟がうちの一族に手出ししてこないのは、あたしたちを脅威だと思っていないからだよ。あたしたちがいくら小悪党を退治しても、六大組織はびくともしないんだから」
探春姉さまも、静かに言う。
「本気でわたしたちを殺すつもりなら、市民を手先にするのではなく、もっと確実な方法を採るはずよ。バカンス先の町ごと、核ミサイルで蒸発させるとかね」
「そんなことしたら、いくら大人しい市民たちだって、黙っていないでしょ」
本気で違法組織根絶に立ち上がる……あ、そうか。
そうなったら、本格的な戦争になってしまう。人類社会を二分する大戦争だ。どれだけの被害が出るか、わからない。
「だからよ。彼らは、市民社会を刺激したくないの。このまま、市民たちをぬるま湯に浸けておきたいのよ」
〝連合〟は現状で十分な利益を得ている、と姉さまたちは言う。
市民社会を包囲して、政治家や財界人や学者たちを密かに操る。世論を誘導する。有益な才能を発見したら、うまく誘惑して辺境に誘い出す。最先端の科学技術は、自分たちで独占する。
裏からの支配で足りているなら、あえて表に出る必要はない。
「市民社会を武力制圧しても、後の管理が面倒なだけでしょ。反乱を恐れて全員を洗脳してしまったら、無能な奴隷が増えるだけだし。市民たちには平和という幻想を与えておいて、実益だけ得ればいいのよ」
「ええと、それじゃ、あたしを誘拐して、姉さまたちをおびき出そうとしたのは……本気じゃなかったってこと?」
「成功したらいいな、という程度の軽い企みでしょう。グリフィンの点数稼ぎ、という意味もあるかもしれないわ。〝リリス〟に対して、たまには痛撃を加えないと、悪役として体裁が悪いから。どんな人物かは知らないけれど、最高幹部会の期待に応え続けない限り、いずれはお払い箱の運命でしょうからね」
と探春姉さまは分析する。
「ふうん……」
そういうものか。わかるような、よくわからないような。世界というのは難しい。
まあ、どちらにしても、あたしの存在なんて、〝リリス〟のおまけ程度のもの……よね。
「とにかく、ごめんなさい……あたし、普通人のふりが下手だったのね」
それは仕方ない、と紅泉姉さまはあっさり言う。何週間も一般人と一緒にいれば、どうしてもぼろが出てしまうものだと。
「正体が知られた時、それでも好意を持ってもらえるかどうかが、人間力の勝負なんだよ。あたしたちは、市民社会の中に味方を持たない限り、市民社会にいられないんだから」
それなら、あたしは失格だ。学校中から嫌われてしまって。
探春姉さまは、事務的に説明を続ける。
「学校関係者は全員取り調べを受けたから、大掃除になったわ。泉の他にも二人、汚染されている子がいたの。一人は美貌自慢で、永遠の若さを欲しがっていた子。もう一人は芸術家肌で、作品を描く時間が欲しくて不老処置を望んでいた子。どちらも未成年だし、まだ何の悪さもしていなかったから、収監されることはないけれど、違法組織の誘惑に負けたのは事実だから、成人しても市民権を制限されるわ。一生、監視される身の上ね」
知らなかった。
楽園に見えた学園に、そんな毒が沈潜していたなんて。
もちろん、不老処置を望むこと自体は、悪いことではないのだけれど。そのために、違法組織に頼るというのが……
といって、あたしたちも、違法組織の中で生まれ育っているからなあ。矛盾している。
「今度からは、抜き打ちの心理検査が繰り返されるから、違法組織は学校に手を出しにくくなるはず。リーレンのママが中心になって、法制化を進めているよ。その法案は、通ると思う。既に、自主的な心理検査を希望する学校が多いからね」
と紅泉姉さま。
それだけが成果なのね。あたしの任務は失敗だった。リーレンを守れず、怖い目に遭わせてしまって。
「あたし、もう、学校には戻れないのよね?」
探春姉さまは、気の毒そうに微笑む。
「あなたが護衛だったこと、生徒たちに知られてしまったから。マスコミが学校に押し寄せたし、生徒の家族も集まって騒いだので、校長先生は心労で倒れて入院なさったわ」
うわあ。ごめんなさい。どうしよう。
「でもね、それはあなたが心配しなくていいの。事件の後始末は、司法局の仕事ですからね。それから、リーレンは学校を辞めました。大学入学まであと少しだから、後は家庭教師を付けますって、ご両親から伺いました」
娘のせいで、他の生徒を巻き添えにしてはいけないという配慮。
「大学に入れば、成人の護衛が付いても目立たないからね。とにかく、あんたはご苦労さん。よくやったよ。おかげで、連邦中の学校で警備が厳しくなる」
紅泉姉さまに優しく言われ、却って落ち込んだ。
「……ごめんなさい。せっかく護衛を任せてもらったのに、こんな結果で。司法局の人たちも、呆れているでしょ」
「そんなことないよ。まあ、百点満点じゃないけどね。初仕事としてはよくやったって、クローデル局長からも言われてる」
うう。
あたしが重傷を負ったから、局長も姉さまたちも、大目に見てくれているんだ。自分が情けない。
「とにかく、誰も死ななくてよかったよ。あんたに何かあったら、あたしがシレールに呪い殺されるからねえ」
えっ。ちょっと待って。
小さな期待のかけらが、むくむくと大きくなる。
「あの、まさか、ひょっとして……泉は……死んでないの!?」
紅泉姉さまは、サファイア色の目をぱちくりする。
「ああ、殺したと思ってたのか。いやいや、助かったよ。命だけはね」
命だけは?
「出血が多すぎたんで、脳細胞がやられて、記憶の大半を失ったらしい。まだ治療中だけど、子供に戻ったような状態だってさ。十歳くらいの年齢に退行したって聞いたな」
ぎゅっと心臓がすぼまる気がした。それでは、あたしが泉の精神を殺したのと同じなのでは。
あたしと対決した泉は、もうこの世から消え去ってしまっている。残っているのは、重傷を負った子供だけ。その子は、自分がなぜこんなことになっているのか、自分でわからない。
「そうそう、これを預かっているわ」
探春姉さまが、ハンドバッグから淡いピンクの封筒を取り出した。上質の和紙で、いい香り。クラスのみんなからだ。内容を全員で考え、代表でサラが清書したと書いてある。
――事情は吉田先生と、リーレンから聞きました。何も知らないで大騒ぎして、勝手な噂を流したりして、本当にごめんなさい。さぞかし、幼稚な娘たちだと軽蔑したことでしょうね。心から謝罪します。
今後、記者たちに何と聞かれても、あなたのことは絶対しゃべりません。あなたが偶然写った写真も、みんなで探して廃棄しました。あなたの顔や特徴が世間に知られたら、次の任務の時、困るのでしょう?
どうか、お元気でご活躍を。
ただ一つだけ、お願いさせて下さい。もしも、どこかでまた会えたら、その時は、懐かしいお友達だと思っていいですか。もちろん、あなたの任務に障ると困るから、態度には出さないようにします……
あたしは気がゆるんで、途中から泣き笑いになってしまった。
この経験をしないより、した方がよかったんだ。
短かったけれど、楽しかった学園生活。そして、あたしを友達リストに入れてくれた女の子たち。
探春姉さまが、ティッシュを差し出してくれた。
「いい手紙? よかったわね」
「うん」
ただ一つだけ、泉のことが悔やまれる。あたしは、どうすればよかったのだろう。
その後悔を知ると、紅泉姉さまは長い脚を組み直して言う。
「あんたが泉の申し出を断ったのは、正しいよ。あんたを〝リリス〟に入れないのに、他の誰かを入れるはずないでしょ。だいたい、その時点では、泉はグリフィンの計画に首まで浸かっていたんだから、本気じゃなかったはずだ」
「最初に違法組織に誘惑された時、すぐ司法局に相談してくれればよかったのよ。それをしなかったというだけで、既に〝食い込まれている〟ということね。少しでもぐらつけば、違法組織は繰り返し接触してくるわ」
と探春姉さま。
司法局の調査によれば、それは、半年以上も前のことだという。道場の跡継ぎから外されて、泉は鬱屈していたらしい。進路面談でそれに気付いたブッシュ先生が、そのことを違法組織に告げた。また一人、誘惑できそうな子がいると。
ブッシュ先生自身は、仕事一途で独身のまま老いていくことを悔やみ、若返りを望んでいたという。四十代になり、虚しくエステに通ったり、宝石を買い漁ったりしていた頃、違法組織に勧誘されたらしい。いずれ何らかの役に立てば、辺境に脱出させて不老処置を受けさせると。
泉は彼女の網にかかった、三匹目の獲物というわけ。
「違法組織って、まめなんだ」
と感心した。常に市民社会を見張り、人材を吟味し、付け入る隙を狙っている。
「まあ、それが彼らの基幹業務なわけだから」
と紅泉姉さま。
ブッシュ先生は、取り調べ室で言っているそうだ。教育に捧げた人生を、悔いているのではない。ただ、他の人生を試してみたくなっただけだと。
「姉さま、あたしそれはわかる……わかる気がする。若返って、別な人生を試してみたい気持ち。不老処置を禁止している市民社会の方がおかしいって思うの、無理ないと思う。あたしだって、普通人じゃなくてよかったって思うもの」
この肉体、学校の女の子たちに比べたら、百倍くらいタフだもの。今回、体力の差はとてもよくわかった。
「でも、泉の気持ちはわからない……最初は違法組織の誘惑を拒絶したのに、なぜ今度はグリフィンの手先になったのか……強化体になりたいだけなら、半年前に簡単にリーレンを殺して、中央を脱出できたのに……」
姉さまたちは、しばらく沈黙した。どう説明していいか、と迷うように。
「あのねえ、ダイナ……」
紅泉姉さまが、どこか気の毒そうに言う。
「あたしは治療中の泉をちらりと見ただけだから、これは勘で言うんだけど、たぶん泉は、あんたと同じ高さに立つために、グリフィンの誘いを受けたんだろうな」
あたしと同じ高さ?
探春姉さまが、付け加えて言う。
「時間のかかるまともな道ではなくて、ショートカットの道を選んでしまったのは、若さ故の焦りというものでしょうね。若者には、若さの価値がわからないのが普通だから……」
あたしが理解していないと見て、紅泉姉さまは苦笑した。
「泉はね、心のバランスを崩してしまったんだよ。手の届かない夢を、目の当たりに見せられてしまったから。何とか手を伸ばそうとして、転落してしまったわけ」
手の届かない夢?
「紅泉、この子にはわからないわよ……」
探春姉さまの顔は穏やかだけれど、目は笑っていない。
「この子は自分がどれだけ恵まれているか、本当には理解できないわ」
そんなことない。ちゃんとわかってる。感謝している。兄さまに守り育てられて、こうして姉さまたちがいてくれて……
「あなたも紅泉も、自分自身が太陽だからよ。その光に目がくらむ者がいること、強烈な光が辛くて闇に隠れてしまう者がいるなんてこと、永遠にわからないわ」
そんな、そんな言い方。
まるで、あたしに世の中が見えていないみたいに。
でも、長年、紅泉姉さまの補佐をしてきた人の言うことだけに、無視できない重みがある。
「多くの人は、光と闇の境目をよろめき歩いているの。光に憧れるけれど、闇の誘惑にも負けてしまう。わたしだって、もし紅泉に何かあったら、どう変質するかわからないわ。たとえば、もしも市民社会が〝リリス〟に対する感謝を忘れて、紅泉に石を投げるようになったとしたら……」
うう、それ、とっても怖いんですけど。
もしも探春姉さまが紅泉姉さまを失い、その恨みで魔女と化したら、〝連合〟より怖い。紅泉姉さま、絶対に死なないでよね。
その紅泉姉さまが、ふっと息を吐いた。
「まあ、あたしも恵まれてるから、わかりきれてないかもしれない。苦痛で歪んでしまう者の気持ちはね」
それから探春姉さまを引き寄せ、ふっさりした前髪の上から、額にキスをする。
「あたしは簡単には死なないから、大丈夫。それに、あたしが死んでもダイナがいれば、人類の未来は明るいよ」
ひええ。そんな大きな話をしないで。あたしなんかに、紅泉姉さまの後継は荷が重いですう。お願いだから、いつまでも長生きしてえっ。
「とにかくダイナ、師匠として、一応は言っておく。あんたはね、現時点では世界最高の……理想的な超人なんだよ。それを自覚しておくこと」
はあ? 超人?
「泉にしろ誰にしろ、あんたを間近で見たら、羨望でおかしくなっても不思議じゃない。だから、覚悟を持ちなさいよ。これからも、妬み、そねみを山ほど受けるってね」
なに、それ。
姉さまったら、あたしを励ますにしても、大袈裟な。
「単純な護衛任務も満足に果たせなくて、どこが超人なの? シレール兄さまが聞いたら、笑うわよ」
でも、紅泉姉さまは真面目な顔のまま。
「あたしやシヴァは体力だけの戦闘馬鹿だし、探春やシレールは頭でっかちで神経質でしょ。その点、あんたは文武両道でバランスがいい。それも、最高水準でのバランスだからね」
最高……?
「頭脳の方は、既に大学卒業程度の中身が詰まってる。分野によっては、博士クラスだし。シレールがあんたに与えていた数学や物理の問題には、専門家でも未解決の難問が織り込まれていたんだからね。あんたは何日か何週間かでそれを解いていたけど、ただの練習問題だと思っていたでしょ?」
え、難問? 未解決の?
「だって、中央の大学入学に必要な水準の問題と言われたから……解けなければ恥だと思って……」
「よく解決してくれたよ。その成果は、一族の研究機関に送ってある。いずれ、応用分野が広がるはずだ。射撃も格闘技も、あたしが基礎を教えただけで、あとは勝手に達人の域に達したからね」
達人……?
「シレールはあなたを甘やかすまいとして、あえて厳しくけなして育てたけれど、本当は天才級の頭脳なのよ。何でもできるわ。もし研究者の道を選ぶとしたら、麗香お姉さまを超えられるかもしれない」
うそ。うそ。
あたし、そんな大層な存在じゃない。
聖カタリナで勉強に苦労しなかったのは、兄さまに厳しく仕込まれた成果。そんな、あたしを突き放すようなこと、言わないで。
「達人なんかじゃないよ。だって、紅泉姉さまには勝てないもの……」
「そりゃ、あたしは、あんたが生まれるずっと前から戦ってるんだから、技術はあるよ。経験からくる知恵もある。でも、そんなものは、あんただってそのうち身に付けられる」
だけど、身に付ける前に、死ぬかもしれないじゃない。
「いつもシレールから、あんたの練習風景の録画を送ってもらってたんだよ。悪い癖がつくと困るから、間違ったことをしていたら、早目に矯正しようと思ってね。でも、あんたは自力で正しい修行法にたどり着いていた。途中で迷うことがあっても、結局は正しい方向を選んだ。同じ年齢で比較すれば、あたしより強いし有能だよ。あたしと探春を二人合わせたくらいの力は、今でも持ってる。おまけに、これからまだまだ伸びる。いずれ、あたしたちを追い越すはずだ」
そんな……まさかそんなことは……姉さまを追い越すなんて……それより姉さま、仕事の途中でもあたしのこと、気にかけてくれていたのね。
「おまけに見た目は、ごく普通の女の子ですものね。どこへ行っても、そこに溶け込めるでしょう。市民社会の側に立ったら、最強だわ。グリフィンの側にすれば、手に入れるか、殺すか、どちらかということになるわね」
と探春姉さま。
何だか、怖くなってきた。ずっと憧れだった姉さまたちに、真顔でそんな風に言われるなんて。道案内なしで、荒野に放り出されたような気分。
「あんたを〝リリス〟には入れないと言ったでしょ。それは、あんたには、あたしたちの跡なんか辿ってほしくないからだよ。小悪党退治なんか、あたしたちだけでたくさん。あんたには、あたしたちのできなかった仕事をしてもらわないと困るの」
……小悪党退治……
「でも、姉さま、あたし、わからない。そんなこと言われたって、これからどっちへ行けばいいのか……」
「あたしにだって、わからないよ。未来は誰にも見えないんだから、あんたの将来なんて、あたしには指図できない。自分で考えて、自分で何とかして。できるでしょ。もう、子供じゃないんだから」
ものすごく怖い。お師匠さまに突き放されるって、何て怖いことなの。
それが自立なら、あたし、まだ自立なんかしたくない。シレール兄さまに叱られる、子供のままでいたい。誰かに指図されるって、何て有難いことなんだろう。
……ああ、そうか。だから人は、組織に入るのか。誰かに従うのか。自分で判断し続けることは、あまりにも大変だから。
探春姉さまが、いささか冷淡にまとめた。
「わたしとしては、泉がこうなって、よかったと思うわ。本来の泉のまま〝向こう側〟に行っていたら、きっと、厄介な敵になっていたはずだもの」
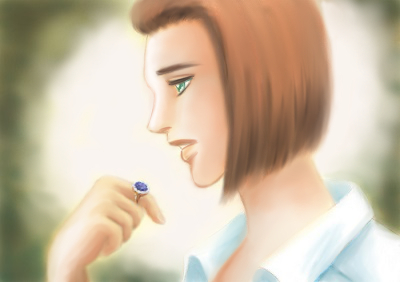
「今回はやはり、ちょっと怖かったですね……ダイナさんを死なせたら、リリーさんは、ぼくを許してくれなかったでしょうから」
炉を切った和室でお茶を点てながら、栗色の髪の少年が微笑んで言う。
雪見障子の向こうには、池と築山を配した日本庭園が広がっている。松と躑躅と桜、楓。植え込みには桔梗、撫子、都忘れ。
ミカエルが自分の趣味で建てた別邸は、とことん日本趣味に貫かれている。
お茶の作法はわたしが教えたのだけれど、もうすっかりさまになっていた。わたしが教えたことは何でも吸収し、更に自分で工夫を重ねる優秀な弟子。
最初は怖々だったグリフィンの職務も、今では当たり前の顔でこなすようになっている。
「ぎりぎりの試練でないと、試練の意味がないわ。もしもダイナが切り抜けられなかったとしたら、失敗例の一つになっただけのこと」
紅泉も探春も、そしてこのミカエルも、幾多の試練をくぐり抜けて生き延びている。
わたしが手塩にかけた、珠玉の作品たち。
「そうですね……ぼくは、泉が勝つかと思いました。惜しい素材です。しばらく治療の様子を見て、使えるようなら再利用してみます。数年分の記憶を失っても、魂の質は変わらないでしょうから」
「挑戦者の魂ね。あなたの思うようにすればいいわ……」
わたしはミカエルに対して、細かい指図はしない。彼はわたしの意図を理解しているから、大筋で間違うことはない。
権力の根源は、わたしがしっかりと握っている。
人類の未来のために何より大切なことは、『男に権力を持たせない』こと。それは、わたしが若かった頃、この身で痛いほど学んだ真理。
だから、シヴァに替えて二代目グリフィンの座に据えたミカエルにも、『永遠の少年』でいることを求めた。
成人男子の肉体を持ってしまったら、男の性に振り回される。
権力欲、支配欲。
ミカエルもそれを理解し、受け入れた。愛する紅泉を守りたい一心で。
少年の純真さを保つ限り、彼の愛情も続くはず。グリフィンに陰から守られて、〝リリス〟の活躍も続く。
わたし自身は、誰にも愛される必要はない。恐れられれば、それで十分。人類はこのまま、わたしに導かれていればいいのだ。もっと成長して、わたしを倒せるようになるまでは。
未来のいつか、わたしに刃向かってくるのが誰かなのか、まだわからない。
あるいは、わたしが育てた子供たち全員が団結して、わたしに立ち向かってくるのかもしれない。
そういうことが起きるのならば、それも楽しみだ。それは、わたしの子育てが成功した証拠なのだから。
誰も反逆してこないのならば、それでもいい。これまで通り、わたしが人類を支配し続けるだけだ。
そして、繰り返す実験の中から、新たな種が生まれる。今はまだ、おぼろな想像しかできないような、優れた生命が。
あたしは問題なく退院し、姉さまたちと近くのホテルに移った。司法局の警護もあるし、姉さまたちの使う有機体アンドロイド、ナギも数体付いているから、まずは安心。
翌日、リーレンの一家がお見舞いに来てくれた。濃紺のスーツが似合うハンサムなパパと、ベージュのスーツを着た知的な美人のママ。
淡いオレンジ色のワンピースを着たリーレンからは、サーモンピンクの薔薇の花束と、大きなケーキの箱をもらって、
「もうすっかり元気なのね、さすがは強化体!」
と感嘆され、
(恨まれていないんだ)
と安心した。
何といっても、泉を記憶喪失の状態にしてしまったのだもの。
ナギがお茶を淹れ、みんなでお土産のケーキを食べた。もちろん、議員一家も厳重な警護付き。あたしはホテル内外に散ったプロの護衛チームを見て、ほっとする。もう、あたしがリーレンの安全を心配することはない。
「それにしても、まさか本物にお会いできるとは」
リーレン一家は、揃って〝リリス〟のファンだそう。ことにリーレンのパパは、姉さまたちと握手できたことで感動していた。
「一生の記念になります。もう、この手を洗いたくないですよ」
と上ずり気味。もちろん、妻と娘が横にいては、さすがの紅泉姉さまも、自分に好意的なダンディを口説けない。
「喜んでいただけて、光栄ですわ」
と、にっこりするだけだった。
あたしもご両親に繰り返し感謝され、恐縮してしまう。
「よく、娘を守ってくれました。ありがとう、ダイナさん」
本当は、もっと巧く戦うべきだったのに。
泉に悪意があれば、リーレンの命はなかった。罪のない下級生を殺さなかったのは、泉のプライドだ。
「あの時は、ダイナが死ぬかと思って、すっごく怖かったんだから! だって、噴水みたいに出血してたもの! あなたの銃は、警護対象者にも撃てるようにしておくべきだったのよ!」
というリーレンの指摘は、ごもっとも。警護対象が成人だったら、きっとそうしていた。
「まさか、リーレンにかばってもらえるとは思わなかったわ。銃を持って立った時、すごくかっこよかった。ありがとうね」
と感謝すると、リーレンは照れ隠しに難しい顔をし、えへんと腰に手を当てる。
「わたし今度から、射撃練習を始めることにしたの。護身術も習うわ。いざという時、わたしがパパやママを守ることになるかもしれないもの」
この分では、将来、ママに負けない大物になるかもしれない。
ただし、泉のことについては、リーレンは華奢な拳を握って怒った。
「絶対許せないわ! ダイナをグリフィンに売り渡そうなんて! よくも、あんなひどいことができたものよ! ダイナは自分が悪役になってまで、泉の挑戦に応えたのに!」
もう、先輩とは呼ばないつもりらしい。でも、リーレンに泉を憎んでほしくはなかった。あんなに憧れていた相手なんだもの。あたしが出現しなかったら、泉が道を踏み外すことは、きっとなかった。
「あたし、泉のお見舞いに行くけど、何か伝言は?」
と尋ねたら、リーレンは意外そうな顔をする。
「だって先輩は……いえ、あの人は、もう記憶がないんでしょ? ダイナに会っても、誰だかわからないんじゃないの?」
そう、子供並みの知的能力しか残されていない。だから、特殊施設での長期療養になった。
再教育を受け、成人の知性を取り戻しても、市民権は制限される。つまり、残りの一生、前科者として警戒され続ける。
公職には就けない。旅行も制限される。新たな泉にとっては、身に覚えのない罪で人生を制限されるわけだ。そのことを、将来の泉がどう受け止めるのか。
「子供時代の泉に戻ったらしいけど、断片的な記憶は、まだあるかもしれないって」
「そうしたら、ダイナは名乗るの? あなたと戦った相手だって」
「それは、しないようにって、司法局の人に言われてる。今後の心理治療に差し支えると困るって。だから、他人のふりで接触するだけ」
リーレンは迷う様子だったけれど、別れ際、言ってくれた。
「わたし、もう、あの人に会いたいとは思わないけど、でも、祈ってるわ。今度はちゃんと、普通の幸せを手に入れてくれますように」
「ありがとう」
泉に代わって感謝した。本来の泉なら、平凡な幸せなど、却下したかもしれないけれど。
山奥の隔離施設へは、首都から車で半日のドライブだった。特殊な病気の患者や、犯罪被害者のリハビリなどに使われている施設だという。
姉さまたちと一緒なので、半分は物見遊山だった。途中で温泉に入ったり、山菜料理を楽しんだりしたので、目的地に着いたのは、午後のお茶の時間になってから。
山地の南斜面に広がる施設では、面会を周到に準備してくれていた。あたしは施設のスタッフの制服を借りて、さりげなく泉に近づいたのである。
泉はサーモンピンクの部屋着を着て車椅子に座り、眺めのいいサロンで、本物のスタッフに絵本を読んでもらっていた。普通人は、重傷状態からすぐには回復しないのだ。
事件の知らせに別の星系から飛んできたご両親は、いつまでも道場や、泉の弟妹を放置できないからと、数日前、引き上げていったとか。泉を可愛がっていたお祖母さまは、心労で寝込んでしまったという。ご両親はきっと、『わたしたちの育て方が悪かったのだ』と後悔しているだろう。
本当は、誰が悪いというのではなく、ただ、巡り合わせだったのだと思うけれど。
「泉ちゃん、わたしはちょっとおやつの支度をしてくるから、ご本を読むの、このお姉ちゃんと代わっていいかしら?」
本物のスタッフは、うまくあたしに相手役を振ってくれた。泉は何も疑いを持たない様子で、
「うん、いいよ。じゃあ、このページからね」
と、あたしに絵本を差し出してくる。
それは、元気なお姫さまが活躍する名作絵本だった。あたしも小さい頃、シレール兄さまに繰り返し読んでもらったものだ。あたしが読み聞かせをする側に回るなんて、何だか不思議。
泉はあたしのことを何も覚えていないらしく、単純に絵本を楽しんでいた。ほっとしたような、がっかりしたような。
本来の泉だったら、こんな可愛い部屋着を着ることもなかっただろうに。
これから再教育を受けて五年後か十年後、成人の知能を取り戻した泉は、自分の過去をどんな風に振り返るのだろう。馬鹿なことをしたと悔やむのか、それとも、懲りずに再び辺境を目指すのか。
お願いだから、今度は平和な道を選んで。あなたに憧れていた女の子たちも、みんなそう願っている。
接触は長くても三十分、と施設側から言い渡されていた。絵本を読み終わったら、わずかな時間しか残されていない。
「そうだわ、泉ちゃん」
あたしは持参したお土産を、袋から取り出した。薔薇色のドレスを着た、赤ん坊サイズの可愛い抱き人形である。白い肌、栗色の巻き毛、緑の瞳。
「この子、これまであたしのお友達だったんだけど、お姉ちゃんはもう大きくなったから、要らなくなったの。よかったら、泉ちゃんのお友達にしてくれないかしら?」
すると泉は顔を輝かせ、人形を受け取ってくれた。
「ありがとう、お姉ちゃん。この子、なんて名前?」
しまった、それは考えていなかった。
「ええと、今度からは泉ちゃんのお友達だから、泉ちゃんが決めてくれる?」
「それじゃあ、ダイナがいいわ。よろしくね、ダイナ」
あたしは危うく、しゃっくりを起こすところだった。
偶然だろうか。
それとも心のどこかに、あたしのことが残っていたのか。
「あのう、ええと、誰か、そういう名前のお友達がいるのかしら?」
「ううん。でも、好きな名前なの。ご本に出てきた猫の名前。とっても可愛いでしょ」
「そう……そうね。いい名前だわ」
猫の名前とは。どっきりした分だけ、気落ちした感じ。
本来のスタッフがおやつを持って戻ってきたので、あたしは挨拶してその場を離れた。泉は楽しげに、もらった人形の紹介をしている。
心の中で祈った。
ダイナ、あたしの代わりに泉を見守って。未来の泉がどんな道を選ぶにせよ、行き止まりの道ではありませんように。
元の服に着替えて、斜面の庭園を散歩していた姉さまたちの所へ行った。
「もういいの?」
「うん、ありがとう。気が済んだから」
「それじゃ、所長さんに挨拶して、引き上げましょうか」
空はまだ青いけれど、冬の太陽はもう山の向こうに隠れてしまっている。じき、夕焼けが始まるだろう。
ナギが運転する車は、幾度もカーブを曲がりながら、山を下っていく。曲がる度、深い谷間や、吊り橋や、底を流れる川が新たな表情を見せる。いい景色だけれど、人家は一軒もない。泉はあと何年も、もしかしたら何十年も、この山奥から出られない。
やがて紅泉姉さまが、ぽつりと言った。
「ダイナは、泉が好きだったんだね」
「えっ?」
自分で驚いた。
これまで、そんな風に意識したことはなかったから。
「でなかったら、わざわざ、記憶のない相手を見舞いに行かないでしょ。面会の許可が下りるのを、半月近くも待ってさ」
それも、姉さまたちが司法局と交渉してくれたから、許可されたのだ。向こうはそもそも、あたしが泉に面会する必要なんて認めていなかった。マスコミに所在を知られないうち、辺境に引き上げて欲しいと言われたもの。面会待ちの期間に、校長先生のお見舞いもできたから、よかったけど。
もう二度と、この星に来ることはできないかもしれない。司法局の依頼がなければ、あたしは市民社会に入れないのだ。女学校に在籍することも、たぶん、二度とない。
思い返すと、宝石のような日々。声援を浴びていた泉の勇姿は、光の結晶の中に閉じ込められている。一緒に自転車を走らせたことも、お昼を食べたこともあった。最初に話をしたのは、銀杏の並木の下だったっけ。あの時は、護衛任務が嬉しくて張り切っていた。
「そうかも……あたし、泉と友達になりたかったのかもしれない……」
あのタクシーの中で、もしも、あたしが別な態度をとっていたら、泉はグリフィンのことを打ち明けてくれ、〝こちら側〟に戻ってきてくれたかもしれない。そうしたら、あたしが憧れていた〝親友〟に……泉が、なってくれたかもしれないのに。
紅泉姉さまが、黙ってあたしを脇に抱え込んでくれた。強い大きな手が、あたしの髪をくしゃくしゃにする。誰かに守られて泣けるって、幸せなこと。
探春姉さまは、素知らぬ顔でナギに話しかけている。
「夕食は、どこでしようかしら。宙港に着く前に、お腹を落ち着けておきたいわ」
もし、いつかまた、司法局から新たな任務を頼まれたら、あたしは引き受けるだろう。でも今は、屋敷に帰れることが嬉しい。あたしを心配しながら、冷淡なふりをするシレール兄さまの元へ。
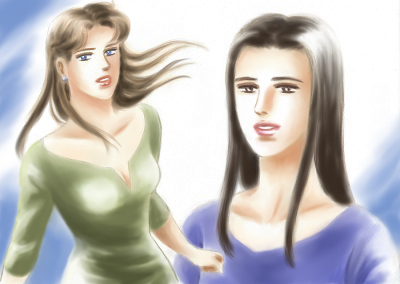
ダイナが《ティルス》の屋敷に戻ってくる前日、最長老の訪問を受けた。
麗香大姐と呼ぶ人もいる。ミス麗香と呼ぶ人もいる。マダムと呼ぶ人もいる。
だが、その存在を知る者自体、きわめて少ない。
外宇宙植民時代の初期に地球脱出を果たした一族の第一世代の、最後の生き残りである。わたしは畏怖と敬意を込めて、大姉上と呼んでいた。対面している時には。
実務から退き、専用の小惑星に籠もっている人が、猥雑な違法都市の中にある屋敷まで出向いてくるとは、珍しい。
むろん、屋敷そのものは広大な敷地内にあって、厳重に守られているが、ここへ来るには、チンピラやバイオロイドで溢れた市街を通り抜けてこなくてはならないのだから。
外周桟橋で船から降りた最長老の車は、いったん繁華街の一つに入り、適当なビルの地下駐車場から、一族の屋敷へ通じる地下通路に潜った。違法都市の地下深くに張り巡らされた迷路のような通路は、紅泉やダイナがバイクで冒険に出掛けた日々の脱出路でもある。
わたしは屋敷の地下駐車場で、彼女の車を出迎えた。護衛のアンドロイド兵に付き添われ、優美な姿が降り立つ。
「ようこそ、大姉上」
不老処置を繰り返しているため、彼女の見た目は若い。長い黒髪に象牙色の肌をした、神秘的な美女である。上品な青紫のドレスと、二連に巻いた真珠の首飾りがよく似合う。
単純な紅泉などは、子供の頃から『姉さま、姉さま』と慕っている。だから、紅泉の弟子であるダイナも慕う。
しかし、わたしは昔から、彼女を見ると、山奥の深い沼を連想してしまうのだ。緑色に濁った沼の底には、幾つの白骨死体が眠っているかわからない。一族の繁栄の基盤を築くまでに、この人は、どれだけの敵を葬ったことか。
「シレール、久しぶりね」
「大姉上も、お変わりなく」
同じ屋敷で暮らす総帥夫妻ではなく、わたしに話があると言うので、二階にあるわたしの書斎で向き合った。やはり、ダイナのことだという。
「お騒がせして、申し訳ありません」
と頭を下げた。一応は、まだわたしがダイナの監督責任者である。
わたしは中央のニュース番組も見たし、紅泉たちからの報告も受けていたから、事態をよく知っている。
学校内の汚染を暴いて、市民社会に大騒ぎを引き起こしたのは仕方がないが、自分自身は撃たれて死にかけたくせに、しばらく遊んでから帰ってくるという能天気ぶり! わたしが眠れぬ夜を過ごしたことなど、あの子は全然わかっていない!
「いいえ、シレール、あなたが謝る必要はないのよ。ダイナはよくやりました。誉めてあげるといいわ」
とんでもない。ただでさえ怖いもの知らずのお転婆なのだから、厳しく叱ってやらなくては。
しかし、アンドロイドの侍女が運んできたお茶を前にして、最長老はゆったりと言う。
「ダイナが帰ってきたら、ぼちぼち、一族の仕事をさせてみましょう。ヴェーラの秘書役がいいわ。そうすれば、都市経営というものがわかるでしょう。足りない知識は、実務の中で学べるはずだし」
そうか。そういう話か。
では、ダイナはわたしの手を離れる。
まだあと半年か一年は、手元で教育の仕上げができるかと思っていたが……未練だったな。
「その後は、わたしの元で、研究助手をさせてもいいわ。あの子なら、研究者としても立てるでしょう。防衛艦隊の指揮官もやらせてみたいし。艦隊戦の実戦も、経験させておかないとね」
「そうですか……お任せします」
何でもご自由に。
わたしはわずかな期間、教育係を任されただけのこと。
あの子は好きな場所へ飛んでいき、わたしのことなど思い出しもしなくなる。わたしが選んだ上品なドレスは、ダサくて嫌だと言うのだから。
「ダイナには、幅広い経験をさせておきたいの。中央に友人を作るのも、大事なことよ。紅泉たちが、クローデル局長という友人を持っているようにね。それがいつか、役に立つ日が来るでしょう。わたしはあの子を、次の総帥に指名するつもりだから……」
ぎょっとした。
あの子に、そんな大役を。
「マダム・ヴェーラという立派な総帥がいるのに、ですか!?」
「もちろん、何十年かは先の話よ。でも、ヴェーラ夫妻にいつまでも重荷を背負わせておくのは、よくないわ。肉体が若くても、精神の疲労は溜まるものです。といって、紅泉たちは中央に入り浸りだしね。もちろん、その時は、あなたがダイナの補佐を務めてくれるでしょう? あの子の伴侶としてね。そうと決まっていれば、ヴェーラもヘンリーも、大幅に気が楽になるはずよ」
微笑んで言われ、愕然とした。
伴侶だと。
顔に血が集まってしまい、言葉が出ない。
それでは、わたしの本心は、他人には丸見えだったのか。探春の気持ちが、紅泉以外の者にはくっきり見えているように。
しかし、まさか、ダイナ本人には悟られていないだろうな。
『へーえ、兄さまって、お堅いふりして、あたしにメロメロだったんだ。じゃあ、あたしがいなくて寂しかった?』
などと面白がる顔で言われたら、どうすればいい。これまで懸命に気を張って、厳しい教育係を演じてきたというのに。
いや、もしかしたら、もうその演技は終了してもいいということか? 薔薇の花束を抱えて、ダイナに求愛する?
それこそ、大笑いされそうだ。
「そんなこと、こちらで勝手に決めても、あの子がどう思うか……」
何かを押し付けられたら、ダイナは猛然と反発するはずだ。可愛い顔には似つかぬ強情者。
しかし、最長老は見通したように言う。
「ダイナも今は、外の世界に憧れているし、劇的な恋愛を夢見ているでしょう。でも、いずれ気が付くわ。自分を一番愛してくれるのは、誰なのか。色々冒険しても、最終的には、あなたの元に落ち着くはずよ」
そうだろうか。
そんな、甘い期待をしてもいいのだろうか。
確かに、ダイナを愛することにかけては、わたしが世界一だという自負は持っているが。
しかし、ようやく腑に落ちた。この人がどうして、ダイナを誕生させたのか。最長老が第四世代の子供を創ることはもうないだろうと、皆が思っていた頃に。
「そのために、あの子を設計したのですね……一族の未来を託すために」
強い好奇心と向上心、明るく素直な性格。
確かにダイナなら、立派な指導者になれるだろう。
わたしや探春では悲観的すぎるし、紅泉では剛直すぎる。ましてや、家出したきりのシヴァなど論外。
第三世代の伯父や叔母たちは、マダム・ヴェーラの指揮に慣れすぎて、自分から率先して動こうとはしない。〝リリス〟の後援をしながら〝連合〟と付き合うのは、神経のすり減る綱渡りだ。英傑であるマダム・ヴェーラにしても、最長老という心の支えがなければ、とうに潰れていたかもしれない。
「人材を育てるのが、わたしの役目ですからね。これからもまだ、新しい子供たちを創りますよ。でも、それには時間が必要です。考える時間がね。次の世代は、もう人間の形をしていないかもしれません」
人間の肉体にこだわらず、人間らしい弱点を持たない第五世代か。
それはもう、人間ではない別の種だろう。
自分がそういう未来に適応できるかどうか、はなはだ怪しい。違法都市で暮らしてはいても、わたしは保守的な人間なのだ。
だからこそ、ダイナを育てていた歳月、この上なく幸せだった。料理をすることも、ダイナの服を選ぶことも、絵本を読んでやることも。
「わかりました……わたしはダイナの補佐を、生涯の仕事と覚悟します」
ダイナが困難な道を選ぶことは、もはや覚悟している。そして、その道が正しいこともわかっている。
渋々ながら〝リリス〟の補佐をしてきた歳月のうち、わたしも思い知った。この先、たとえ一族が〝連合〟と深刻な対立をすることになっても、この銀河を捨てて逃げるというのは、現実的な選択肢ではない。逃げても必ず、人類社会の膨張に追い付かれるからだ。その時は、主流から外れていた分、今より不利な立場に陥るだろう。我々は厳しい闘争のただ中に残り、切磋琢磨を続けるしかないのだ。
「あなたや紅泉たちのおかげで、ダイナは理想的に育っているわ。シレール、もう少しだけ、あの子の良い教師でいてちょうだいね。あの子がすっかり大人になったら、口説いて構わないから」
最長老が立ち去った後、わたしはしばらく虚脱していた。甘い未来を期待しながらも、心の半分では、
『えーっ、やだあ!! 兄さまと結婚なんて!!』
というダイナの叫びを予期している……
あの子にとって、わたしは育ての親だ。堅苦しい教育係だ。結婚を前提に交際を、などと言ったら、
『兄さま、何考えてるの、気持ち悪い!! あたし、身内の男なんて男と思っていないから!!』
と宣言されてしまうかもしれない。
落ち着こうとして、中庭に出た。しんと冴えた空気の中で、香り高い冬薔薇が咲き誇っている。白、ピンク、赤、オレンジ。
小惑星都市に本物の季節や陽光はないが、我々が人工的に調節して、冬の午後を創り出している。
何年か前、ダイナが毒針に刺されて倒れた時も、こうして、この花の中で祈ったものだ。わたしの元から飛び去ってしまっても、他の男を愛しても構わない。ただ、生きてさえいてくれればいいと。
そう、わたしに選択の余地はない。
ダイナを死なせないために、できることを何でもするだけだ。
ダイナに伴侶として選ばれなくても、それには耐えられる。たぶん、きっと。
そうだ。今日のうち、あの子の好きな苺のミルフィーユでも作っておこう。それから、チョコレートケーキに林檎のタルト。レモンパイ。
ダイナを送ってくる紅泉と探春は、どうせすぐ次の任務に行ってしまうのだから、好きな料理で迎えてやろう。海老とムール貝入りのパエリア、蟹のサラダ、ローストビーフに白身魚のマリネ、煮込みハンバーグにクリームソースのパスタ。
ダイナの負傷について、師匠たる紅泉に言いたいこともあるが、それはこらえることにする。紅泉もまた、自分ではない誰かのために戦っているのだから。