
ブルー・ギャラクシー ミオ編


サンドラが早めのお昼をすませ、武装トレーラーで船から出ていった後、わたしはヴァイオレットさんと二人で留守番していた。
ヴァイオレットさんも、戦闘が予期される場合には、少し離れた位置で待機するのが普通だという。
「わたしたちが危険な位置にいると、サンドラが余計な気を使うことになるから。間違ってわたしたちが人質になったりしたら、それこそおしまいだし」
小惑星の外周桟橋に停泊する船の中で待っていられるのなら、これからもついていけると思って、ほっとした。
いつものように髪を結い上げたヴァイオレットさんは、美しい薄紫のミニドレスに真珠のイヤリングという、およそ戦いとは関係なさそうな姿をしているもの。スカート丈が短いのが、唯一、アクションの心構えかも。
わたしも別に、戦闘服を着ろなんて言われていないから、この赤いワンピースでいいのよね?
サンドラが、わたしには赤が似合うと言うの。自分では、白が似合うと思っていたのだけれど。
足元はサンドラに言われた通り、いつでも走れる、足首固定型の丈夫なサンダル。どんな靴でもブーツでもいいけれど、いざという時にダッシュできるものを履いていなさい、と言い渡されている。
でも、競り市に出掛けていったサンドラは、一人で大丈夫なのかしら。護衛の兵士たちがいるといっても、命令者がいなければ役に立たない、単なる機械人形なのだし。
「違法組織の幹部とかが、大勢来るんでしょ?」
と尋ねてみた。ヴァイオレットさんは、ソファに座って何かのデータファイルを眺めている。各都市から上がってくるという、《ナギ》からの報告書なのかもしれない。
「だから、会場の警備は厳重よ。そこで騒ぎが起こることは、まずないわ。そうしたら、開催者が責任を問われるから」
法律はないにしても、揉め事を最小限に押さえるための慣習は、違法都市にもあるのだという。
その慣習を破る者は、死を覚悟しなければならないという点では、法律より厳しいと言える。
「本当に、さらわれた人たちが、そこで売られるんですか」
映画では見たけれど、本当は映画の制作者だって、違法都市の現場で取材したわけではないでしょう。
「科学者や技術者の場合は、まず自分の組織内で働かせるけれど、人員が足りている場合はよそへ売るわ。あと、あなたのような可愛い女の子だったら、やっぱり高く売れるわね」
この場合の『可愛い』は、別に誉め言葉ではなくて、『外見しか取り柄がない』という意味だと思う。
それは、ヴァイオレットさんの声の調子で判別できる。
サンドラが『可愛い』と言ってくれる時は、見かけも中身もひっくるめて、全て肯定してくれるのが、よくわかるもの。
「処女だったりすると、びっくりするような値段がつくこともあるのよ。高級娼館の目玉商品にしたり、特殊な映画の撮影に使ったりするの」
ヴァイオレットさんが、静かに微笑んで言うのが怖かった。これまでさんざん、そういう現場を見てきたらしい。
若く見えても、二人とも、実はかなりの年齢なのだ。だって〝リリス〟が世間に登場してから、もう半世紀以上経つのだもの。それ以前にも、無名の状態で戦っていたのだろうし。
マレーネが、永遠の若さを手に入れるために、せっせと〝遣り手婆〟の真似をしていたことを思うと、皮肉な気がした。それを取り締まる側に、不老の英雄がいるなんて。
マレーネの気持ちも、今なら少しはわかる。
『だって、いい仕事もいい男も、みんな若い子に取られるのよ!!』
と取り調べ室で叫んだという。
モデル業界は、確かに年齢勝負。年輩になっても需要はあるけれど、よほど個性がある人でなければ、ギャラは大幅に低下する。マレーネのような美人だと、余計に凋落が辛いのだろう。
その焦りを、パーシスがうまく利用したのが悪いのだ。
わたしがまた、何も考えず、気楽に人の噂話をしたのも悪いと、今では思う。わたしがマレーネのことを、お金持ちの男性が好きみたい、なんてパーシスに話したのがいけないのよ。
今はまだ、マレーネと仲直りする気にはなれないけれど、以前のような、吐き気を伴う嫌悪は薄れていた。
もう、精神安定剤がなくても平気。
いずれ、手紙でも書けるかもしれない。不幸な事件だったけれど、お互いに、これからの人生を大切にしましょうって。
わたしも今では、過去の事件より、先の方を心配しているのだった。このまま五年、十年過ぎたら、わたしの方がサンドラよりも老けてしまう。
それは悲しかった。
いつまでも、可愛い女の子でいたいと思ってしまう。
でないと、サンドラに甘えられないわ。しわのある顔で若い女にすがりつくなんて、どう想像しても醜悪だもの。人間、年をとったら、甘えられる側に回るのが義務よね?
でも、もしもサンドラに頼んで不老処置を受けさせてもらえたとしたら、その時は、二度と市民社会には戻れないことになってしまう。
中央では原則として、延命のための遺伝子操作は許されない。難病の治療の場合でさえ、厳格な制限をかけられる。許可なく遺伝子操作をした者は、すなわち犯罪者。
サンドラたちのように、特殊な貢献をするのでない限り、中央に踏み込むことも許されない。
パパとママにも、タケルにも会えなくなる。
残りの人生を辺境のどこかで過ごすなんて、あまりにも荒涼としているわ。
それとも、本格的な戦闘用の強化をして、サンドラと肩を並べて戦えるようにする!? わたしに、それだけの覚悟がある!? いえ、覚悟はつけても、適性があるとは思えない。
あれこれと考えていたら、ヴァイオレットさんが席を立って、お茶を淹れてくれた。
「ずっと緊張していると、保たないわよ」
と言ってくれる。
でも、もしかして、わたしがお茶の支度に立つべきだったのかしら。
サンドラだったら、あれが欲しい、これは要らないとはっきり言ってくれるから、その通りにすればいいのだけれど、相手がヴァイオレットさんだと、まだ調子がつかめない。
とりあえずは、
「ありがとう、いただきます」
と言い、二人で居間のテーブルについた。クッキーやチョコレートの盛り合わせと、ブランディを垂らした熱い紅茶を楽しむ。
戦闘艦の艦内といっても、1G居住区は柔らかい淡色のインテリアでまとめられていて、居心地がいい。
ナギやアンドロイド兵士が雑用に動くのを別にすれば、暮らしているのは女だけだから、椅子の背にかけられたカーディガンも甘い色、ティーセットも繊細な薄手の磁器、薔薇模様の刺繍のリネンも優雅で、女の城という感じ。
お茶を途中まで飲んだところで、
「それ、毒入りよ」
ヴァイオレットさんが言ったので、むせそうになった。
まさか、嘘よね。
好かれていないのは、重々承知しているけれど。
「安心して、すぐには死なないわ。十年か二十年かけて、じわじわ効いてくるから」
にっこりされた。ただの意地悪だと思うのだけれど、返事に困る。
「年をとる薬なの。十年経ったら、皮膚がたるんで、小じわが出てくるわ」
そういうこと。わたしがいつまでも、サンドラの側にはいられないと、思い知らせるつもりなのね。
開き直って、わたしは逆襲した。
「どうして、はっきりサンドラに言わないんですか。わたしを追い払ってって。目障りだからって」
本当は、聞くまでもない。サンドラに、心の狭い意地悪女と思われたくないからに決まっている。
一緒に何日も過ごすうちに、わかってきた。ヴァイオレットさんは、自分の気持ちを告げるつもりがないのだ。今のまま、ずっと親友の位置を守っていこうとしている。
だから余計、堂々とサンドラに甘えるわたしが憎いのだと思う。
それに、薄々はわかっているのではないかしら。サンドラが、ただわたしを抱きしめるだけではなく、それ以上のことをしてくれていること。
サンドラが、わたしをたっぷり可愛がってくれた後、
『これだけは内緒だよ』
と念を押して言うのは、ヴァイオレットさんが潔癖症だと思っているから。知られたら軽蔑される、と心配している。サンドラにとっては、わたしの治療の一環に過ぎないのに。
でも、本当はヴァイオレットさんこそ、サンドラに抱いてほしくて苛々している。それを言えない分、鬱屈してわたしに当たるのだ。
「言えばいいのに」
ついにわたしは、真正面から宣言した。
「きっとサンドラは、ちゃんと受け入れてくれますよ。通りすがりのわたしにも、これだけ優しくしてくれるんだもの。ヴァイオレットさんのことなら、なおさら愛してくれるわ」
でも、テーブルの向こう側に座る女性は、苦痛をこらえるかのように、細い茶色の眉をしかめている。
「わたしは、サンドラの負担になりたくないのよ」
あなたのようには、という意味ね。
「でも、不健康だわ。ヴァイオレットさんがそうして我慢していたら、それは結局、別な形でどこかに出るんじゃありませんか。それより、あなたが満足してにこにこしている方が、サンドラだって嬉しいと思いますけど」
はるか年下の小娘の分際で、生意気なことを言っていると思う。
でも、恋愛という戦場では、年は関係ない。
わたしは親友でも従姉妹でもないのだから、全力でぶつからなければ、サンドラの側にいられないのだ。
ヴァイオレットさんは苦笑した。
「サンドラは、あなたのことをいたいけな女の子だと思っているけれど、実はどうして、なかなか押しが強いのよね。うらやましいわ。迷惑もかえりみず、好きなだけ甘えられて」
真珠が似合う上品な美人であるだけに、こうして冷たく振る舞うと、とことん冷たい印象になる。
この人のことは、一生、苦手なままだろう。
でも、迷惑をかけているのは事実なので、反論できない。
「わたし、本当に運がよかったと思います。あの日、階段でサンドラに助けられて」
そのことを、後からどれだけ感謝したか。事件に巻き込まれたことすら、サンドラに会うためだったのなら、受け入れられる。サンドラに出会わなくても、パーシスには利用されていたのだもの。
「そうね」
茶色い髪を結い上げた美人は、小さな唇からほっと息を吐く。
「わたしがあなたを苛めても、意味がないのよね」
わたしはやや、意外な気がする。自分でも、虚しい行為だと思っているのかしら。
「わかってはいるのだけれど、つい、あなたがうらやましくて。いままで、ライバルになりそうな相手は、なるべく追い払ってきたのよ」
ああ、やっぱり。
「でも、あなたの場合は、サンドラがすっかり同情してしまって」
ぐさりときた。
確かに、同情だとは知っている。やっぱり大人の女性だわ。意地悪にも、年期が入っている。
殴るとか蹴るとか、引っ掻くとかなら証拠が残るけれど、言葉は消えてしまうものね。
自分がどんなに冷たい皮肉を言っても、わたしがサンドラに言いつけないことを知っているからだ。
わたしだって、サンドラに、嫉妬深い面倒な女と思われたくないもの。わたしの口からヴァイオレットさんの悪口なんて、絶対言えない。
誰か悪いとしたら、それはやはり、横入りのわたしなのだし。
「ごめんなさい。でも、サンドラが好きなの」
言い訳はそれしかない。
「ええ、わかっているわ。どうしようもないことよね」
ヴァイオレットさんも、静かに言う。まるで、悲劇の舞台の台詞のよう。
「わたしにも、どうしようもないの。これからも、あなたに意地悪をしてしまうと思うけれど、それは謝らないわ。悔しかったら、やり返してちょうだい」
悲愴な顔をされてしまうと、わたしも悲しい。女同士で傷つけ合って、何になるだろう。
「男が悪いんです」
わたしは言った。
「あんな事件がなければ、わたしもまだ、結婚や何かに夢を持っていられたでしょう。でも、今はもうだめ。人類の半分が、信用できないんだもの」
それはわかるわ、とヴァイオレットさんも同意してくれた。
「彼らは何万年も昔から、女を獲物としか見ていないのよ。文明が進んでも、本質は変わらないわ」
女を〝モノ〟にして、仲間の男たちに自慢する。
それが若くて美しい女であればあるほど、仲間内での地位が上がる。
「彼らにとって、女を愛するというのは、所有し、支配することなの。男同士の競争に勝つためには、自慢できる獲物が必要なのよ」
学校の授業でも習った。長い進化の過程で、雄と雌は違う淘汰圧を受けてきたのだと。
子孫繁栄という至上命題において、雄と雌の利害はしばしば対立する。
多くの雌に、多くの子供を生ませたい雄。
優秀な雄を選び抜いて、少なく生みたい雌。
だから、男と女は、決して本当には相容れないのだとヴァイオレットさんは言う。
そうなのかもしれない。
父や祖父たちはもちろんわたしを愛してくれるけれど、他の男たちは全員(異性愛である限り)、まずわたしの外見を見る。
わたしを可愛い、綺麗だと思えば、お世辞を言ってまとわりつく。贈り物をしようとする。
でも、二十年後、三十年後、彼らがわたしに同じだけ優しいかといえば、そんなことは絶対ありえない。
いっそ女というのは、醜く生まれた方が楽なのかもしれない。そうしたら、うるさい男たちは寄ってこない。
もしも誰か近づいてくるとしたら、それは、心を愛してくれる人でしょう。そんな男性、あんまりいそうな気はしないけれど。
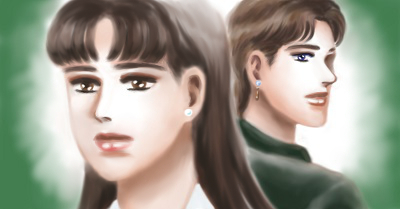
昨日、あれだけ笑わせたことだし、探春は機嫌よくミオと留守番してくれるだろう、とあたしは思っていた。
船から車で降りると、街を流しながら、こっそりメッセージ通信を送る。麗香姉さまの隠居所にいるミカエルに。
かつて、あたしが惚れ込んだ薄幸の美少年は、違法組織から脱走してきた、知能強化型のバイオロイドだった。脳腫瘍ができやすい体質で、そのままでは長く生きられないはずだったが、今では治療を済ませ、永遠の少年として幸せに生きている。
醜悪な〝男〟にならず、清らかな〝少年〟のままでいることを選んだのだ。
そして、姉さまの研究の助手をしたり、あたしが依頼した新兵器を作ってくれたり、ダミー組織の管理を手伝ってくれたりする。
『今回は方角が違うから、会いに寄るのは無理だけど、いずれまた遊びに行くからね』
簡単なメッセージだが、ミカエルには通じるだろう。
辺境に出る都度、なるべく立ち寄るか、メッセージを送るようにしている。通話して長く話し込まないのは、傍受が心配であることと、探春に知られたくないからだ。
あたしがミカエルに熱を上げ、婚約指輪まで交わしていた時期、探春は冷ややかな顔をして張り詰めていたが、やがてミカエルが自分から身を引くと、またにこにこするようになった。
ミカエルは、そういう探春に遠慮したのだ。
『あなたにとって、一番大切なのは、ぼくではなく、ヴァイオレットさんでしょう。ヴァイオレットさんが不幸になったら、リリーさんこそ、不幸になってしまう。それならば、ぼくは友人でいる方がいいんです』
家族と恋人は違う、三人で暮らせるはずだ、とあたしは言い張ったのだけれど、ミカエルは婚約指輪を外した。そして、
『あなたのことは大好きですが、ぼくは戦場についていくより、安全な隠れ家にいて、後方支援を引き受けた方がいいと思います』
と言って、姉さまの元に身を寄せることを選んだのだ。
それにまた、大人の肉体になることを嫌って、少年の姿でいることに決めたというのだから、あたしが無理に押し倒すわけにもいかない。
違法組織の基地で、大人の男の餌食にされてきたことが、ミカエルにそういう選択をさせたのだ。
今はただ、ミカエルがこの世に生きていてくれる、そのことに感謝するしかない……
あたしはため息をついてから、神経を仕事に切り替えた。
競り市は市街の一角、あるビルの中で開かれる。
あたしはダミー組織の幹部として、黒い制服を着せたアンドロイドの護衛兵を連れ、そこを訪れた。頭にはショートカットの赤毛のかつらをかぶり、派手なメイクをし、おまけに黒いゴーグルをかけて。
これまでずっと髪を長くしていたから(あえて女の格好をしていないと、どんどん男っぽくなる自分が怖い)、イメージが変わってちょうどいい。
衣装はここぞとばかり、肩と胸の露出度の高い、派手な金色のつなぎである。動きやすいが、柔らかい生地なので、セクシーな印象のはず。
それに、ダイヤとルビーを嵌めた、金細工の豪華なジュエリーを合わせている。垂れ下がるイヤリングに、重いネックレス、揃いの腕輪に指輪という満艦飾。
普段のあたしは、女物を着ているとはいえ、だいたいシンプルな格好をしているので、こういう変装の時は、思いきり派手に装って楽しむ。もしかしたら、いい男が目を留めてくれるかもしれないし。
いや、まあ、どんな男でも、ミカエル以上にあたしを愛してくれることはないと思っているけどね……
それは、あたしの勝手な思い込みかもしれないけれど……そう思っていられることで、救われるのだ。
劇場のような摺鉢形の会場には、何百人かの暇人たちが集まっていた。
趣味のいいスーツを着た男に、いかつい護衛たちが付き添うグループが大部分。
本物の女は、数えるほどしかいない。それも大抵、男に連れられた愛人風の女である。甘い色のドレスに、赤やピンクの唇、きらきらする装身具。
あたしのような、自分自身の部下や護衛を従えた姐御風の女は、ほんの片手の指ほど。
裏の世界は、ほとんど男のものなのだ。暴力や陰謀が得意なのは、男が多いからである。戦うことが楽しくなければ、辺境では生きていけない。
強面ばかりの会場に彩りを添えているのは、扇情的なロングドレスを着た、バイオロイドの美女たちだった。あちこちで、飲み物のサービスをして回っている。
それを気軽に受け取る男もいれば、用心深く拒絶する者もいた。自分の持ち船やビルから出たら、一切飲み食いしない者も多い。かろうじて信用できるのは、同じ系列に属する組織くらいか。
あたしもまた、探春によく戒められていた。中央ですら毒殺の用心をするのに、まして辺境の違法都市で、迂闊に飲み食いするはずがない。
美女の勧めるカクテルを断り、中ほどの席から舞台を見下ろして待った。喉が渇いた時には、護衛の兵に持たせてある水筒の水を飲む。《ナギ》は常に、あたしたちが吸う空気、飲む水、料理の素材などを点検しているから、そういう面では安心していい。
ほどなくライトが舞台に集まり、客席が暗くなって、競りが始まった。主催者の簡単な挨拶の後、まず売りに出されたのは、中央の美術館や金持ちの屋敷から盗まれた、古典絵画や彫刻、骨董品。
これは気楽に見られる。
いくら高価だろうが貴重だろうが、どうせ品物だ。
美術館には精密な走査データが残っているはずだから、客には完璧な複製品を見せられる。現代の技術では、本物そっくりの複製品がいくらでも作れるのだから、歴史的価値を重んじる学者でない限り、本物かどうかにこだわるのは、ただの趣味といってもよい。
どこかの物好きたちが、それぞれ結構な値段で落札していった。好きにすればいい。
次は痛かった。子供ではないか。
長い栗色の髪をした、五つか六つの女の子だ。
誕生パーティのような、オレンジ色のひらひらドレスを着せられ、スーツ姿のバイオロイド従業員に付き添われているが、何が起きているのかわからない様子で、既に半泣きである。彼女の目からは、男たちの陣取る暗い階段客席は、ただの不気味な洞窟だろう。
進行係が説明した。中央星域から、親子で脱出してきた本物の市民。父親は科学者で、ある違法組織に加わるはずだったが、待遇面に不満があり、他組織に乗り換えて逃げようとした。しかし失敗して囚われ、洗脳され、ただの奴隷に成り下がり、子供のことなど忘れてしまったという。
その子供がいま、売りに出されている。
どうぞ身元をお確かめくださいと言われ、多くの客たちがそれぞれ、中央のデータベースにアクセスした。
あたしも自分の端末を通して確認したが、本物である。野心家の父親を持ったばかりに、わけもわからず辺境に連れ出された少女。わずか六歳のジャスワント・フォーゲル。
これを見過ごしていいのか。
この子を買うのは、どうせ悪趣味な変態野郎に決まっている。さんざん弄んで、挙句はSM行為で死なせるか、飽きてよそに売り飛ばすか。
次に買われた先では、特殊なウィルスか何か感染させられて、生物兵器に作り変えられてしまうかも。子供は適応力が高いから、人体実験の素材にはもってこいなのだ。
――ああもう、だから辺境は嫌いなんだよ。すぐこうして、かっかと腹を立てることになるんだから。
もちろん、今回のあたしの仕事には関係ない。違法都市では、こうして毎週、誰かが売り飛ばされている。
あたし一人で、全部救って回るわけにはいかないのだ。だから、なるべく中央でバカンスを過ごす。余計な悲惨は見たくないから。
しかし、見てしまったものはどうなる。この子はミオやタケルより、もっと悲惨ではないか。
ええい、司法局には関係ない。あたし個人の金で買ってやる。それほど高値にならなければ、だけど。
困ったことに、物好きが何人もいた。すぐに値段が吊り上がる。サクラが混じっているのかもしれないが、それはあたしには知りようがない。
『あなたはすぐ短気を起こすんだから、熱くなっちゃだめよ』
いつも探春に言われることは、あたしもよくわきまえている。でも、この子を助けてやれなかったら、後々思い出しては暗くなるだろう。
二百以上もある違法都市の中で、繰り返し開かれているオークションの一つで、たまたま行き合わせてしまったのだ。これはやはり、縁というものだろう。
ついに、あたしが落札してしまった。予想外の出費になり、ほっとするやら、がっくりするやら。手元の端末からビットするので、誰が何を買ったか、他の客には知られない仕組みだけれど。
次は大当たりだった。舞台に引き出された男は、奪回してほしい科学者リストの第一位。ツァオ・カイル。
まだ三十代の大学教授で、理論物理学の分野では、気鋭の一人だそうだ。違法組織にくれてやるには惜しい人材、とミン局長が言っていた。やはり、あちこちの組織の幹部たちが落札しようとする。司法局が認めた予算の範囲内で、うまく取り戻せるかどうか。
くそ、だめだった。
さっきジャスワントに使った金があれば、上乗せして落とせたと思うのだけれど。
あたしたちは確かに、そこそこの資産を持っているが、それは基地や艦隊や資源惑星という形で蓄えてあるので、すぐに換金できるわけではない。また、任務でいちいち私財をはたいていたら、すぐに素寒貧になってしまう。それでは、生き延びられない。
仕方ない。
ツァオ教授は一人前の大人なのだから、たとえあたしが後で救い出せなかったとしても、自分の身は自分で心配してもらおう。
どうせ彼は、洗脳などされない。そんなことをしたら、せっかくの高価な頭脳を曇らせることになるからだ。
優秀な科学者であればあるほど、違法組織の側も、待遇に気を使う。
科学者によっては、拉致されたとしても、喜んで違法組織に居着くくらいだ。いや、そうなる者は少なくない。
適切な不老処置を受けられ、ずっと好きな研究が続けられると思えば、辺境でも楽しく暮らせる科学者は多い。市民社会から、こっそり伴侶や恋人を呼び寄せることもできる。
中央のように、研究内容にいちいち法的な制限をかけられることもない。けち臭く、成果を急かされることも少ない。そこそこの組織なら、基礎研究の重要さは、ちゃんとわきまえている。
特に男性の場合、柔順なバイオロイド美女が何人も世話係につけば、それですっかりいい気になってしまう。
自己主張の強い本物の女より、言いなりになる奴隷女の方が楽だというのだ。まったく情けない。
ジャスワントの父親だって、待遇に不満など持たなければ、そこそこ快適に暮らせたはずなのだが。娘を一緒に連れてきたのは、きっと不老処置を受けさせてやりたいためだったのだろうに。
次もまた、リストにあった科学者の一人だった。
ハンス・ベルデン。
しかし、順位は確か十番目以下だったぞ。
人間の価値に順位をつけられるはずもないが、司法局特捜部としては、違法組織に渡った場合の危険度によって、奪回の優先度を決めるしかないのだ。
こちらは博士号とりたての二十代、まだ業績らしい業績がないので、将来性を見込んでの買い物ということになる。ツァオ教授より、だいぶ低い値段から競りが始まる。
さあ、どうしよう。こいつのために金を使うべきか。それとも次に、もっと優先度の高い科学者が出てくるのを待つか。
市民社会で行われるオークションなら、あらかじめ、出品される品物を知ることができる。
しかし、違法都市では、あたしのような当局の回し者がいるため、商品は舞台に出る瞬間までわからないのだ。
事前にわかるのは、噂程度のもの。それが情報屋や駐在員を通して、司法局にキャッチされる。
えい、買おう。
こいつを見逃して、次にリスト上位の科学者が出てこなかったら、後悔する。
このベルデン博士は値段が上がらず、うまくあたしが落札できたので、よかった。たとえツァオ教授を救えなくても、手ぶらで帰らずにすむ。
その後も何人か、科学者や技術者の売り物があったが(新規に誘拐されたのではなく、潰れた組織からの流出品)、それは任務外だし、予算も足りないので見送った。長生きを祈るしかない。
今回は、これからツァオ教授の奪回を試みるだけで手一杯。
同時に拉致された他の研究者たちは、今日のオークションに出されなかった。次回に回されるのか、それとも既に別の都市で売られたのか。あるいは、拉致した組織の内に留められているのか。
いずれにせよ、それはもうあたしの任務ではない。改めて追跡を依頼されたら、その時はまた考えるが。
オークションが終わると、濃い薔薇色のドレスを着たバイオロイド美女に、別室へ案内された。あたしの〝買い物〟が二人、片方は泣きべそで、片方は不安顔で、それぞれ手錠をかけられて待っている。
「おやおや、情けない顔をして。鬼に食われるとでも思ってるの?」
黒いゴーグルに顔を隠したまま、燦然たる姿のあたしは二人をからかった。
「大丈夫、大金を出して買ったんだから、大事にしてあげるわよ。元を取るまではね」
支払いはもう《プラチナム》の口座を経由して済んでいるので、護衛兵にジャスワントを抱えさせ、苦い顔の青年科学者を引き立てて外へ出た。待たせておいた武装車が来て、あたしたちを乗せる。
適当に車を走らせておき、あたしは《ナギ》からの報告を待った。
客に紛れて、やはりダミー組織の幹部に仕立てた有機体アンドロイドを三組、護衛兵つきで会場に入れておいたのだ。入場料さえ払えば、入るのは簡単なこと。いずれも《ナギ》のプログラムで動く人形で、ミオにはただちに怪しまれた水準だが、他の客と会話しなければ、十分〝人間〟で通用するだろう。
彼らがそれぞれビル内の通路やエレベーターをうろうろし、ツァオ教授を連れ出す者を確認するはずだった。
もしも確認できなければ、それでおしまい。あたしも万能ではないのだから、できることしかできない。
けれど、幸い、ツァオ教授を買った違法組織の幹部は、それほど用心していないようだった。堂々と彼を連れて、地下駐車場から武装トレーラーに乗ったという。
尾行の手筈はついていた。無数の偵察虫を撒いてあるし、車も配置している。拠点となるビルや船がわかれば、攻撃計画を立てられる。
「あんたはどこの組織なんだ?」
あたしの買った若手科学者、ハンス・ベルデンは、幅広の手錠をかけられたまま尋ねてきた。その間も、幼いジャスワントを腕の中に抱えて慰めているのは感心。
周囲にはずらりとアンドロイド兵がいるので、もちろん逃亡はあきらめている。間延びした顔をしていて、それほど好みのタイプではないが、それでも若い男。
「さあ、どこでしょうね。大丈夫、いい子にしていれば、悪いようにはしないから。そうねえ、たまに、あたしの足でもマッサージしてもらおうかしら」
金色のサンダルを履いた足で、彼の膝をこすってからかったら、露骨に、
(ごめんだ)
という顔をされた。まあ、覇気があってよろしい。
あたしは車をでたらめに走らせた後、あるビルの地下駐車場に入れて、扉部分を連結させた別のトレーラーに乗り換えた。むろん、体重の移動分は兵士や荷物の重量でごまかす。でないと、後から、道路のあちこちにある荷重センサーの記録を検索されるかもしれない。
それから、それぞれの車が別方向に走り出し、じきに、ダミー組織の持つビルや倉庫を通り抜ける。その際、もちろん、あたしたちは別の車に乗り換える。
これを数回繰り返せば、たとえ追跡してくる者がいても、完璧に撒けるはずだった。
〝連合〟はあたしの体格データを傘下の組織に流しているから、いつ、どこで、誰に狙われるかわからない。船に敵を連れ帰らないための、いつもの用心。
「さて、ベルデン博士」
曇り顔のジャスワントを膝に乗せて、あれこれあやしている青年に、あたしは言った。
「無人船を貸すから、あんたはお嬢ちゃんのお守りをしつつ、先に中央に帰ってもらう。あたしには、ツァオ教授を救出する仕事があるから。こう見えても、司法局の上級捜査官なんだよ」
青年科学者は、口をぽっかり開けた。しばらく金魚のようにぱくぱくしてから、やっとで言う。
「それならそうと、早く言ってくださいよ!! てっきり、どこかのサド女に買われたんだと思ってましたよ!!」
正直な奴である。それでも、心底からほっとしたようで、
「ああよかった、助かった」
と繰り返す。故郷には、結婚を控えた恋人がいるそうで、
「もう二度と会えないかと思って、真っ暗だったんですよ」
と照れ笑いで言う。事情のわかっていない少女にも、
「よかったね、お家に帰れるよ。お祖父ちゃんとお祖母ちゃんのいるお家だよ」
と親身に説明する。
それでようやく、褐色の目をした少女の顔が明るくなった。
「お祖父ちゃんのお家に行けるの?」
「そうだよ。中央に入ったら、通話して、迎えに来てもらおうね」
設計士である母親は、どこかの建設現場で運悪く事故死しているそうだけれど(だから父親は、未練なく市民社会を捨てたのだ)、祖父母は二組とも健在だから、ジャスワントはちゃんと保護者に引き取られる。今日はこれで、二人の人生を救ったことになる。
「でも、まさか、ぼくたちだけで中央へ帰れっていうんじゃないでしょうね? 途中、何かあったらどうすればいいんです?」
「大丈夫、船には優秀な管理システムがあるし、護衛艦もつけるから。途中、この子の世話をよろしく。同僚に連絡しておくから、中央の外れで出迎えがあるはずだ。言っておくけど、スケベな悪戯はするんじゃないよ」
するとハンス・ベルデンは、まず唖然としてから、次に憤然とした。
「そんなこと、するわけないじゃないですか!! ぼくは成熟したグラマー美人が好きなんです!!」
と拳を握って力説してから、慌てて少女を見下ろし、愛想笑いをしてみせた。
「きみも可愛いよ、ジャス。将来はとってもすてきな美人になること、間違いなし」
よろしい、幼い女の子の心を傷つけないよう、そうして気を遣うのならば。
「健全な趣味でけっこう」
あたしもにっこりして言った。たとえ彼がトチ狂ったとしても、あたしの船は、どれも《ナギ》が制御しているのだから。もしも彼が幼女に何か悪さしようとしたら、ただちに麻痺ガスを吹きつけて拘束する。
もちろん、あたしも彼はまともだと思うけれど、それでも男だから、一応、釘を刺しておかないと。
探春の男性不信に与するわけではないが、ほんの数百年前まで、男たちは、実の娘さえ平気で犯していたのだ。学校の教師たちも、しばしば女生徒を餌食にしていた。この現代でもまだ、その手の卑劣な男は絶えていない。
そうして二人を別の車に乗せ、予備の船に向けて送り出した。あとは《ナギ》が、無事に中央まで送り届けてくれる。
そこで尾行班から連絡があり、ツァオ教授の連れ込まれたビルがわかった。《ケルベロス》という中規模組織の拠点。
繁華街ではなく、緑地の中に孤立するドーム施設だった。施設の規模や車の出入りからすると、この都市でのメイン施設らしい。
それなら、しばらく他所へ移される心配はないだろう。
(どうでもいいけど、みんなギリシア神話が好きなんだな)
いったん外周桟橋の船に戻ると、
「お帰りなさい!」
赤いミニドレスのミオが、飛び立つようにして出迎えてくれた。いつもなら、探春が抱きついてくるところだけれど。
あたしはミオを軽く抱きしめ、額にキスして、
「まず、何か食べさせてくれる?」
と頼む。
「はい!」
ミオがいそいそ厨房に去ると、次は探春を抱きしめて、やはり額にキスをする。
甘く冷涼な花の香りがして(麗香姉さまが作った梅花香だ。あたしたちの香水は、あらかた姉さまから分けてもらったもの)、きちんと結い上げた髪に、真珠のイヤリングがよく似合う。男だったら、食べてしまいたくなるだろうな、と思ういい女。
「これから一つ、ドンパチだ。ツァオ教授を落札し損ねたのでね」
パンプキンパイやツナのサンドイッチ、マロンケーキやポテトサラダ、ミオがあれこれ並べたテーブルで、あたしは二人に今日の活動を報告した。ミオは、小さな女の子を助けた話に、いたく感動したようである。
「よかったわ!! よかった」
と、わがことのように喜んでいる。
でも、あたしは探春に謝る必要があった。
「ごめん。予定外の散財をしてしまって」
ハンター稼業で司法局から得た賞金は、あたしと探春の共同財産である。大きな買い物をする時には、必ず探春の承諾を得るようにしていた。それを今回、独断で、かなりの額を使ってしまったのだ。
けれど、探春は怒らなかった。
「貯金は、またできるわ。小さい女の子を助けたんですもの、いいことをしたのよ」
優しく言われて、ほっとする。やはり、理想のパートナーだ。
ところが、コーヒーを飲んでいるうちに、《ナギ》の人工音声が報告してきた。ツァオ教授の連れ込まれた孤立施設から、四台編成のトレーラーが出て、外周桟橋へ向かっているという。
他に出入りしている車は都市内の移動だから、行く先だけ確かめておけばいいだろうが、船で出航されるのは困る。
「まずいな、都市外へ逃がすのは」
無関係な幹部の出立か。それとも、教授の移送か。外からは、厳重にシールドされた車内の様子はわからないのだ。
「よし、桟橋で仕掛ける。もしも教授が乗っていなかったら、その時は、メイン施設にも奇襲をかけるから」
あたしが席から立ち上がると、探春が言う。
「サンドラ、桟橋での攻撃はよくないわ。他組織の車や船を巻き添えにしてしまうもの。都市の管理機構にも睨まれるでしょ。余計な恨みを買うと、離脱が面倒になるわ。船が管制宙域の外に出てから、仕掛けるべきよ」
ま、それはそうだけど。
二か所で戦う場合、戦闘現場が遠く離れてしまうのは、やりにくい。
「あなたは、船の方を追えばいいわ。わたしは街で待機するから。そちらが空振りだったら、ドーム施設の襲撃を指図します」
探春は簡単そうに言うが、あたしは不安を覚えた。
「それはちょっと」
探春はもちろん、あたしと組んで何百回という戦闘を経験してきているが、大抵は後方支援の位置にいた。
実際の突入は機械兵やアンドロイド兵がするが、回線を通じた指示が必要になることもある。
その場合、敵に指揮者の位置を悟られる危険があるのだ。それに、船が攻撃された直後だと、ドーム基地でも警戒を強めるだろう。
「大丈夫よ、ドームに突入するのは《ナギ》の部隊だけだから。中継用の鳥や虫は広範囲に撒いておくし、必要がない限り、余計な通信はしないもの。教授が船にいれば、こちらは何もしなくていいわけだし」
迷ったが、結局、そうすることにした。あたしの方で教授を確保すれば、それで済むのだ。
「じゃ、気をつけて」
探春とミオを船に残し、あたしは別の船に移動した。それから、先に出港した船を追う。
標的の船は、護衛の艦隊に囲まれていたが、全部で八隻にすぎない。こちらは、その数倍の戦力を配置している。
数時間後、船団が《ヴァンダル》の管制宙域を出てから攻撃をかけた。
こういうことは、先に仕掛けた方が有利である。
向こうが超空間転移した直後を狙い、強襲艇を何十機とぶつけて、レーザーと核ミサイルで大破させ、抵抗力を奪ってから、指揮艦に機械兵部隊を突入させる。アンドロイド兵やバイオロイド兵の抵抗は、物量で押し破る。
しかし艦内には、離れた星区の基地へ帰還する、中級の幹部がいるだけだった。
手早く尋問したが(薬の効きにくい強化体だったので、原始的に暴力と恐怖で吐かせた)、ツァオ教授はまだビル内にいるという。
あたしは探春に連絡した。
「これからすぐ引き返すから、あたしが行くまで何もしないで、見張りだけにして」
探春の知性や判断力を疑うわけではないが(頭のよさでは探春の方が上だ)、戦闘には勘というものが重要なのだ。それは、好きで戦いを繰り返した者しか身につけられない武器である。
悪党狩りを趣味にしてきたあたしには、その勘があるが、探春にはない。
そして、探春もそのことをわきまえている、はずだった。
「大丈夫よ。どうせ攻撃するなら、早い方がいいわ。教授を他所へ移されたら、また面倒だもの」
という反応は、予想外である。
「ちょっと待って!!」
けれど通話は切れ、あたしは凝然とした。再度かけても、応答しない。無視しているのだ。
信じられない。
いつもなら、当然あたしを待つはずなのに。
あたしは全速で《ヴァンダル》に戻りながら、いやな予感に襲われていた。何かが狂っている。ミオを連れてきたせいだろうか。
準備段階では意見を言っても、実際の戦闘が始まれば、探春はあたしの判断に従ってきたのに。
不安は現実になった。《ヴァンダル》を内部に収める小惑星の、外周桟橋の一つに接岸した途端、通告が来たのである。
「初めまして、ミス・サンドラ。わたしはディーン。《ケルベロス》の幹部と言えば、おわかりだろう」
顔はわざと見せないが、気取った男の声である。
「そちらが〝リリス〟だということは、もうわかっている。突撃部隊に命令を出していた女性たちを捕まえたのでね。片方は薬物に耐性があるが、片方は普通人なので、知っていることを総てしゃべってくれたよ」
これ以上悪い事態は、想像できない。
二人とも、裸同然の格好にされ、手錠や足枷をはめられて、冷たい床の上に転がされているのではないか。
命はあるだろうが、どんな脅しや暴力を受けているかわからない。探春はともかく、ミオの神経が保つかどうか。
「わたしは今、きみたちに壊されたドーム基地を出て、別な場所にいる。幾重にも包囲してくれたらしいが、ここは突き止められないと思うよ。非常用の地下通路を利用したのでね」
たぶん、事実だろう。
違法都市の市街の地下には、複雑なトンネルが四通八達している。半分以上は生活用水や電力・通信ケーブル、物資配送のためのサービストンネルだが、残りは極秘の移動用だ。
トンネルの存在そのものは探知できても、その内部の移動までは、なかなか把握できない。
むろん、ビル周辺の地中にも探知虫を潜らせてはいるが、トンネル内で複数のダミー車両を走らされたりすると、もういけない。
トンネルの全貌と、その利用者の行方がわかるのは、その都市を建設した支配組織だけだ。
そして、そこに間借りする中小の違法組織は、それなりの金を払えば、一時的にその地下通路を利用することができる。
「どうだい、取引をしないかね」
ディーンと名乗った男の声は、機嫌がよい。あたしが捕らえた仲間の幹部のことなど、気にもとめていない。同じ組織内の他幹部というのは、単なるライバルにすぎないからだ。誰かが始末してくれるなら万々歳、というところだろう。
「五百億クレジットで手を打とう」
何だって。
何だ、その巨大な金額は。
「こちらの指定する口座にそれだけ入金してくれれば、二人とも、生きたままで返そうじゃないか。無理だというなら、構わんよ。彼女たちは、六大組織の最高幹部会に引き渡す」
胸が冷えた。いったん〝連合〟の中枢に囚われてしまったら、おいそれとは取り戻せない。うちの実家より、はるかに巨大な組織の集まりなのだから。
もし、公開処刑などということになってしまったら。
「ヴァイオレット嬢はきみの助手らしいが、それでも〝リリス〟の片割れだろう。最高幹部会にとっては、仇敵だ。どちらか一人でも、きみたちにかかった懸賞金の全額を保証するという公約がある」
いきなり、そんな大金が用意できるものか。
もちろん、あたしたちの持つ基地や艦隊、資源惑星を売り払えば、金はできる。しかし、それは買い手があればこそ。それに、こちらが焦っているとわかれば、たちまち買い叩かれる。
だいたいこいつ、金を払ったからといって、素直に人質を返すタイプじゃない。探春を餌にしてあたしも捕まえ、最高幹部会に引き立ててもらおうという計画ではないか。
「わかった、金を用意する。でも、すぐには無理だ。三日待って」
と言ってみた。すると、面白がる声。
「ほう、その間に、わたしの居場所を突き止めるつもりだね」
もちろんだ。
最悪、街中に小型ミサイルを撃ち込んでもいい。混乱を引き起こしておいて、ありったけの兵士や偵察鳥を使い、探春たちの居場所を突き止める。
いや、しかし、こいつが既に、船で街を離れている可能性もある。通信はいくらでも迂回させられるから、発信源を逆探知するのは、ほとんど不可能だ。超空間通信なら、タイムラグはほとんどない。
「それは無理だ。わかってる。あんたは、慎重に隠れてるはずだからね。あたしは、二人さえ戻ればいい。強盗してでも金は作るから、それまで、二人に手出ししないで」
「何もするなというのかね。こんな美女を前にして」
顔が見えなくても、ほくそ笑む気配はわかる。
「うちの部下たちが、そわそわしているよ。これまで、バイオロイドの女しか相手にしたことがないのでね。本物の人間の女性、しかも一人は〝リリス〟の片割れとは、わたしだって興奮する」
何だと、こら。
「二人の身が大切ならば、期限は、今から十二時間後だ。それを過ぎたら、彼女たちは最高幹部会に引き渡す。その前に、ちょっと楽しませてもらって、映画に撮らせてもらうがね。出演者がいいから、高く売れるだろう」
あたしを怒らせ、焦らせるための台詞だということは、よくわかっていた。だからあたしは、きわめて冷静に罵倒した。
「このクズ野郎、よく聞けよ。二人を取り戻した時、無事でなかったら、生まれてこなきゃよかったという目に遭うからな。まだ生きていたければ、粗末な代物はパンツの中にしまっとけ!!」
通話を終えると、あたしはたまたまそこにあった、罪のない陶器のティーポットを壁にぶん投げた。ガチャンと派手に砕ける音で、少しはガス抜きになる。
「片付けてよろしいですか?」
隅で待機しているナギが、微笑んで尋ねてくるのは、もはやブラックユーモアだ。だけど、機械に同情されるよりはいい。
「ああ、そうして」
それから、すぐさま実家に連絡した。普段はなるべく甘えないようにしているが、探春の命がかかっているとなれば別である。通話はもちろん暗号化しているから、傍受されても、解読までには何年もかかる。
「すみません、助けてください」
苦手のヴェーラお祖母さまに、あたしは頭を垂れてすがりついた。
「何事ですか」
と青い瞳の、冷ややかな視線が返ってくる。お祖母さまにとって、あたしは『困ったおてんば娘』にすぎないのだ。
しかし、探春は『掌中の玉』である。
きっと力を貸してくれる。
貸してくれないと困る。
普段ならともかく、今のあたしには、落ち着いて考えを巡らせる余裕がない。探春が横にいてくれ、静かに微笑んでいてくれなかったら、落ち着きようがないのだ!!
「いま《ヴァンダル》にいるんですけど、ここの支配組織と取引できませんか。通話記録から、通話元を確かめたいんです。探しているのは、《ケルベロス》という組織の幹部で、ディーンという男です」
うちの一族は、古い違法都市である《ティルス》を支配している。他に二つの姉妹都市も持っている。違法都市同士は相互に連絡を取り合い、互いの商売が円滑にいくよう協力するものだ。
もちろん、事情を聞いたお祖母さまは、いつにも増して厳しい顔だった。金髪をふんわりとショートカットにした美女だが、金茶色の眉を険しくひそめたままで言う。
「そんなことをしたら、うちと〝リリス〟のつながりつながりを悟られるかもしれないでしょう。脱出に地下通路を使った時点で、《ヴァンダル》側が興味を持っていたら、そのディーンという男の通話、傍受されている可能性があるわ。《ヴァンダル》は〝連合〟の領土です。あなたたちのために、一族全員を危険にさらすことになるのよ」
ごもっとも。
お祖母さまも、意地悪でそう言うのではない。
探春を何とか救いたいと、白い額の奥であれこれと計算しているのがわかる。既にあたしと探春の両親は遠くへ去り、期待をかけたシヴァは行方不明のまま。これ以上、一族を失いたくないのだ。
その時、お祖母さまの注意が脇にそれた。別口の通話らしい。しばらくそちらに耳を傾けてから、あたしに言う。
「麗香お姉さまの所にいるミカエルが、既に動いているそうよ」
あ。
「任せてよいとお姉さまがおっしゃるので、そうします。それじゃあね。いい報告でなければ、聞きたくありませんからね」
通話はあっさり切られ、別の通話に切り替わった。緑の瞳に白い肌、栗色の髪をボブにした美少年が現れる。
「リリーさん、今朝、メッセージを送ってくれましたよね」
ミカエルと知り合った時、あたしは『リリー・ベイ捜査官』の身分で動いていたので、彼は今でもあたしをその名で呼ぶ。
「あれから、ぼくなりに《ヴァンダル》の内情を調べています。競り市の様子も確認しました。何かの時は、お手伝いしようと思って」
と静かに微笑んで言う。
あたしから事情を聞くと、ミカエルは頷いた。
「ぼくの管理しているダミー組織から、《ヴァンダル》の支配組織にアクセスできます。幹部同士の対立があるので、そのへんで隙があると思います。ディーンという男の居場所を探ってみますから、少し待ってください」
ミカエルは、できないことは言わない。あたしは黙って待った。ミカエルに突き止められなければ、あとは都市ごとひっくり返してやる。
三十分としないうち、連絡があった。市街区のコンドミニアムの一つにいる確率が高いという。
「もし、そこから移動していたら、厄介ですが」
「よし、まず当たってみる。ありがとう」
ミカエルは控えめに微笑んだ。
「他組織の幹部たちも入居しているビルなので、破壊は最小限で済ませてください」
「わかった、そうする」
あたしは画面の少年に投げキッスをした。
「今度会ったら、じかにキスするからね」
そのくらいなら、探春も大目に見てくれるだろう。年に一度か二度の、短い逢瀬。それが、あたしとミカエルの心の支え。
「ええ、楽しみにしています」

敵の居場所さえわかれば、戦闘はあたしの得意科目である。十二時間どころか、二時間しないうち、あたしは都市内にあるコンドミニアムの一棟に奇襲をかけていた。
中小組織の幹部たちが、月単位で各階を借りている。
まず、中距離と遠距離に配置した武装車から、ビームとミサイルの一斉攻撃をかけさせた。
近場に配置した車からは、煙幕用のガス弾を撃ち込ませる。
たちまち、十六階建てのコンドミニアム周辺は、白い電離気体の霧に包まれた。周囲の緑地が広いので、他のビルへの影響は少ない。
また、地下トンネルからは、機械兵の攻撃部隊を進ませていた。
都市の管理組織は、金払いのいい客には便宜を図ってくれるのだ。都市内戦闘に対する迷惑料をたっぷり払ったので、都市の警備部隊を出動させるのは、しばらく待ってくれるという。
個々の組織が戦い合うことには、関与しないのが違法都市の常識である。片方が〝リリス〟と知ったら、また別かもしれないけれど。それは今回、なかったようで助かった。
むろん、ビルの防衛システムがレーザーや小型ミサイルで反撃してくるが、限度がある。
こちらは武装車の十台や二十台失っても、どうということはない。予備はいくらでも配置してある。包囲戦になれば、固定施設の方が不利なのだ。
やがて、炎と煙に追われ、逃げ場を失った人間たちが、地下の駐車場から武装トレーラーで飛び出してきた。
包囲を強引に突破しようとするが、そうはさせない。片端から粘着弾を浴びせて動きを止め、機械兵たちが一台ずつ中を調べた。
その中には、手錠つきのツァオ教授もいた。しかし、探春とミオは乗っていない。ビルを制圧した部隊からも、二人は見当たらないとの報告。
どういうことだ。
移動されてしまったのか。
ツァオ教授には、ゴーグルをかけたまま〝リリス〟と名乗り、安心してもらって、話を聞かせてもらった。
「ええ、さっきまでは、ディーンという男が一緒にいましたよ。ぼくを組織内の研究所で働かせると言っていました。いえ、女性の姿は見ていません。でも、そういえば、地下の車に誰か〝お客さん〟がいる、というようなことを言っていました。攻撃が始まる三十分くらい前に、ぼくを残して出ていきましたよ」
頭をかきむしりたくなった。せっかくミカエルが工作してくれたのに、わずかに遅かったのだ。
ああもう、だから、辺境は嫌いなんだよ!!

わたしたちは服をむしられ、下着姿にされて、中型トレーラー内部に監禁されていた。
寒いという温度ではないけれど、下着姿では心細い。
サンドラに見てもらうために、毎日、優雅なレースの下着をつけているから、みすぼらしくないのはよかったけれど。
ヴァイオレットさんも、象牙色のシルクの優美な下着。ただし、胸のふくらみはひかえめと言うべきね。その点では、わたしの方が勝っているわ。というより、勝てるのはそこだけかも。
手首には頑丈な手錠をかけられているし、裸足の足首は、座席の脚部に手錠でつながれている。おトイレに行きたい時だけ、兵士が足枷を外してくれる。
――軽い夕食をすませた後、ヴァイオレットさんが《ナギ》の制御する部隊に、ドーム施設の奇襲を命じたのだけれど、なぜだかわたしたちの位置が敵に知れ、あっという間に捕まえられてしまった。
わたしは薬を打たれ、朦朧としているうち、質問されたことに全て答えてしまったらしい。サンドラたちが〝リリス〟だということの他は、たいしたことは何も知らないのだけれど。
わたしときたら、いまだにサンドラの本当の名前すら教わっていない。
ヴァイオレットさんの本名らしき名前は、幾度かサンドラがぽろりと洩らしたけれど、忘れるように努力した。尋問の時、知られないで済んだかしら。
ディーンと名乗った男は、わたしたちを餌にしてサンドラを捕まえるか、ヴァイオレットさんだけを最高幹部会に渡して懸賞金をせしめるか、状況次第だという。浅黒い肌に黒髪の、痩せた中年男。闘士というよりは、策士という感じ。
「もしも〝リリス〟の主力を捕まえられたら、六大組織の幹部の座も望めるだろう。まあ、うまくいけばだが」
と言う態度は、謙虚ですらある。
違法組織の幹部というのは、欲に狂った自惚れ屋ばかりだと思っていたけれど、案外と冷静なのね。
ヴァイオレットさんには〝リリス〟の片割れとしての価値があるけれど、わたしはおまけに過ぎないから、人質の役が済んだら、売り飛ばすか、映画の撮影に回すかするという。
本当なら、しくしく泣いてもおかしくない事態だけれど、わたしは自分でも意外なほど平静だった。
売り物にされるのも、下劣な撮影に使われるのも、もう経験済みではないか。
それにまた、ヴァイオレットさんが、やはり下着姿で静かに座っているからだ。
あきらめているのか、それとも助けを信じているのか。あるいは、なるようになる、と悟りを開いているのか。
華奢な人なので、白い薄手の下着姿で、手首に太い手錠をかけられているさまが、痛々しい。
それでも、わたしのことなど、もう別世界の住人のように無視している。きっと、サンドラのことしか考えていないんだわ。
人のことは言えないけれど、怖いほどの執着という気がする。こんなに美しいのだから、その気になれば、いくらでも男性を手に入れられるはずなのに。
そんなもの、手に入れてもしょうがないと思っているのね。
それは、わたしも同感。
とにかく、ヴァイオレットさんが平静なら、わたしも負けられない。みっともなく泣きわめいたりしたら、
『やっぱり、この世界は無理でしょ、あなたには』
と言われてしまう。
車内にはアンドロイド兵だけでなく、生身の肉体を持つバイオロイド兵もいるけれど、強姦されるような気配はなかった。
ディーンという男も、同じ車内の前方にいるけれど、それどころではない、と思っているらしい。どこからか報告を受けたり、部下に指示を下したり、さもなければ、じっと考え込んでいたり。
伝説のハンターを敵にした、という緊張がありありと背中に見えた。少しでも気をゆるめれば、自分の負けだと思うらしいのだ。
それにしても、ただ座って変化を待つだけというのは、退屈なものだった。自白剤のせいでわずかな頭痛が残っているけれど、あとは別に何事もない。どうかすると、眠くなってくる。
いま何時かしら? さっき軽い夜食を勧められてから(ヴァイオレットさんが断ったので、わたしもそうした)、何時間経っている?
端末は取り上げられているし、わたしたちのいる後部区画には窓はなく、外が見えない。今夜中にはもう、何事もないかもしれない。
それなら、眠っておく方がいいわ。サンドラが来てくれた時、明晰な頭でいられるように。
「毛布をくれる?」
見張りのアンドロイド兵士に言ったら、案外親切に、棚から二枚、取り出してくれた。一枚は、近くの椅子のヴァイオレットさんに渡される。
「わたし、少し眠ります。おやすみなさい」
と断って椅子の背を倒し、暖かい毛布にくるまった。足枷のせいで姿勢は制限されるけれど、周囲の照明も絞ってもらったし、何とか寝られるわ。
ヴァイオレットさんは、毛布をかけはしたけれど、端然と座ったまま。細く見えても強化体だから、体力があるのね。
うとうとしかけた時、突然、車を突き上げる震動があった。小惑星都市に、地震はない。爆発の連続だ。サンドラかもしれない!!
「やられた。さすがに早いな」
とディーンが部下に話すのが聞こえた。攻撃されているのは、さっきまでいたコンドミニアムらしい。ここは、そのコンドミニアムのすぐ裏手のビルの地下。ディーンは用心深く、わたしたちを貨物の配送チューブで移したのだ。
それなら、もう少しの辛抱だと思った。サンドラはきっと、ここも探り当ててくれる。
やがて、ディーンは車を出すよう命じた。他の組織の車が逃げ出すのに混じれば、特に怪しまれないということらしい。トレーラーは、ビルの地下から外の道路に出た。戦闘はもう終わったようで、何の騒ぎも伝わってこない。
サンドラには、わたしたちの居場所がわからないの!?
このまま、またどこかの地下に潜ってしまったら、発見してもらえないまま、都市外へ連れ出されてしまうかも。
焦って腰を浮かせていたら、いきなり轟音がして、車が横転した。わたしは椅子に繋がれたまま全身を打ち、息ができなくなる。毛布を巻いていただけ、まだましだけれど、頭を打ったかもしれない。
痛みで朦朧としているうち、誰かがわたしの足枷を外した。そのまま腕をつかんでわたしを引きずり、車の外へ連れ出していく。裸足の足裏に、路面が冷たい。
毛布を失ってしまうと、寒さで鳥肌が立った。ヴァイオレットさんも、やはり連れ出されたのかしら。でも、頭に傷を作ったらしく、血が流れ込んできて目が見えない。
「援護しろ!!」
「予備の車を!!」
という声と、周囲を走る足音、交錯する銃声。
左右のどこかで、何かが爆発したような衝撃も感じた。刺激のある、煙の臭いに包まれる。あちこちで、どさりと重い音がするのは、護衛の兵士が倒されていく音ね。
やがて、裸足の足の下に、草と石ころを感じた。車道から外れたらしい。手錠をかけられたわたしの腕に、自分の腕をからめて抱き込み、盾のように押し出していく男は、わたしの頭に、何か堅いものを押しつけてくる。
「下がれ、道を開けろ!! 近寄ったら、こいつも死ぬぞ!!」
ディーンの声。明らかに、恐怖でひきつっている。囲まれているんだわ。
「構わないよ、撃てば。次の瞬間、あんたも死ぬだけだ」
空中から、少しくぐもったサンドラの声が応じる。偵察虫を経由した放送らしい。溶けるような安堵で、膝から力が抜けてしまう。
「その子を放して、降参おし。そうすれば、命は助ける」
虫が宙を飛び回りながら、そう告げる。
でも、ディーンにはそうする気はないようだった。荒い息をしながら、躰の前面でわたしを押して歩かせていく。彼もどこか、怪我をしたのかも。周囲を見たいと思ったけれど、血のせいで目が開かない。
「あっ」
足が何かにひっかかり、躰が前に泳いだ。その瞬間、
「あぐっ」
と変な声がして、わたしを抱え込んでいた力がなくなった。倒れ込んだわたしの全身に、びしゃりと生暖かいものがかかる。むっとする鉄錆の匂い。ディーンが、どさりと崩れ落ちる気配。
次にわたしに触れた誰かは、聞き覚えのある声をしていた。
「もう大丈夫です。手当てしますから」
《ナギ》の操る美青年アンドロイドの声だった。では、助かったのだ。
顔に流れる血をぬぐってもらい、切り傷には保護スプレーをかけてもらった。目を水で洗って、ようやくあたりが見えるようになる。
近くにビル群の明かりがある、暗い野原だった。わたしたちは、林に入りかけた所にいる。
すぐ横手の道路に何台もの武装トレーラーが停まり、こぼれる明かりで野原が照らされていた。あちこちで爆破の痕跡らしい薄煙が上がり、わたしは血で真っ赤に染まっている。わたし自身の出血は、たいしたことがないのに。
振り向くと、左腕を付け根から失ったディーンが縦に切断されて、木々の間に倒れていた。切り口から内臓がこぼれ、大量の血が流れている。銃を握ったままの右の手首も、近くに落ちていた。
映画で見た通り、超切断糸の仕業に違いない。わたしには一筋の傷もつけないまま、ディーンの肉体を三度、糸が通過したのだ。
赤毛のかつらのままのサンドラが、戦闘服姿で近くに立っていた。静かだけれど、こちらから声をかけるのが怖いほどに厳しい顔で、あたりの兵たちに指示を出している。生存者の確保、撤収の準備。
たぶん、これが本来のサンドラなのだ。
両方の手首にある銀色の腕輪、あれに超切断糸が隠されている。だから、お風呂の時でも、眠る時でも外さない。
道路上で横転したトレーラーの方を見ると、数体のアンドロイド兵が、ヴァイオレットさんを運び出したところだった。盾として連れていくなら、わたしの方が簡単だとディーンは判断したのだろう。
周囲は装甲服の兵士や機械兵で一杯で、わたしたちはすぐ、別の武装トレーラーに運び込まれた。走りだした車内で、サンドラが、ようやくこちらに来てくれる。
当然、優しくいたわってもらえるものと思った。
抱いてくれて、キスしてくれるわ。可哀想に、怖かったでしょうと。
ところが、サンドラは血まみれのわたしを素通りした。まるで、目にも入らないかのように。
そして、すぐ後ろで、ビシッと鋭い音がした。振り向くと、ぶたれたのはヴァイオレットさんだった。
「待てと言ったでしょう!! 自分は戦闘向きじゃないと知ってるくせに、どうして無茶をするの!!」
ヴァイオレットさんは躰を傾け、黙ったまま頬を押さえている。サンドラは怒りで息を荒くしたまま、手を開いたり握ったりして、パートナーをみつめている。
わたしは声もなかった。
任務でなくても、自費で小さい女の子を助けた人が。
しつこく甘えるわたしを、辛抱強く受け止めてくれた人が。
初めて、冷たい実感に浸された。
サンドラが本気で心配するのは、この人のことだけなのだ。
わたしがこんな風に怒られることは、きっと、ない。わたしには、何も求めず、期待しないから。
わたしがじっとしていると、サンドラはようやく振り向いて、静かな声で言った。
「ミオも、無事でよかった。怖い目に遭わせて、悪かったね」
サンドラの正直さは、残酷を通り越して、笑えるほどだ。
たとえ薄闇の中でわたしを愛撫してくれても、それは〝心の治療〟であって、恋愛感情に変わることは、決してない。
それは、ヴァイオレットさんに対しても、そうかもしれない。だからこそ、ヴァイオレットさんも苦しんでいる。
でも、ヴァイオレットさんは、それ以前にサンドラの〝半身〟なのだ。そこにわたしの入り込む隙間は、ない。
たぶん、他の誰であっても、ないだろう。
「中央に引き上げるよ。ツァオ教授も回収できたから。そこのシャワー室で、汚れを落としてくるといい。そしたら、本格的な手当をしよう」
お湯で血の汚れを落としながら、一緒に涙も洗い流した。わたしも、あんな風にぶたれてみたかった。サンドラに、本気で相手にしてほしかった。
でも、わたしはきっと、六つの女の子と同じなのだ。泣いている子供を放っておけないから、抱っこしてあやすだけのこと。
永遠に、恋人にはなれない。
本当は、自分でもわかっていた。二人きりの夜、サンドラはわたしを愛撫して、夢中にさせてくれたけれど、わたしが同じことを返そうとすると、
『しなくていいよ』
と下着姿のまま、冷静に言うのだもの。
安全な船内に戻り、《ヴァンダル》を離れて一息ついてから、あたしは探春の部屋へ行ってみた。
探春はまだ、助けられた時の下着姿のまま、ベッドに横たわっている。大きな怪我はないのに、着替える気力もないというのか。
「シャワーもまだなの?」
黙ってこちらを見た白い顔は、涙で濡れていた。片方の頬には、まだ赤い跡がついている。
加減したとはいえ、あたしの力でぶったのだから、痛かったはずだ。
子供の頃、ふざけていて、うっかり探春を階段から突き落としてしまったことがあったが、あれ以来の暴力かも。あの時は、平身低頭して謝り、骨折した探春に、笑って許してもらったものだ。
「ぶったりして悪かった、と言いたいけど、あたしは怒ってるんだよ。なんで、あたしの帰りを待たなかったの」
科学者の奪回なんて、探春の命に比べたら、どうでもいいことだ。それは探春だって、よくわかっているはず。
幸運だったのは、ディーンが徒歩で逃げる時、ミオを盾にしたことだ。おかげであたしは、冷静に対処できた。
あれが探春なら、奴の指が間違って引き金を引かないかどうか、心底から怖かったはず。切断糸を振るう腕も、緊張で、思うように伸びなかったかもしれない。
探春は、動けない人形のように、ベッドに横たわったままである。あたしはその横に座り、泣いている顔を見下ろした。
「言いたいことがあるなら、ちゃんと言って。でないと、あたしは鈍感だからわからないよ」
しばらく待つうちに、探春は目を閉じた。そうすると、また新しい涙が溢れ、頬から耳元へ、枕の上にこぼれる。
「ミオを家へ帰して」
低いささやきだが、はっきりと言う。
「あの子がいると、わたし、辛いの」
ミオを連れ歩くことに賛成していないのはわかっていたが、それがこれほど探春の負担になるとは、驚きだった。
ただの無邪気な居候ではないか。
しかし、探春はぎりぎりまで我慢する性格である。それが、泣いてこう言うからには、本当に限界なのだ。
このままでは、おそらく、次の仕事でも何かやらかす。あたしたちの命が危なくなるようなことを。
「わかった、そうする」
あたしは探春の肩と膝の下に手を入れ、そっと抱き上げて、あたしの膝に座らせた。そして、ぎゅっと抱きしめ、乱れた髪を撫でる。
「ごめん、あたしが悪かった。ミオを《ベルグラード》で降ろして、別の星に遊びに行こう。それでいい?」
探春は無言のまま、あたしにしがみついてきた。ただ、静かに泣き続けている。それでも、安堵しているのが伝わってきた。
ミオのことは、切り捨てよう。ミオに泣かれても、恨まれても、やむをえない。
ミカエルのことも、あたしはあきらめたのだ。あたしを真剣に愛してくれる、最初で最後の男性だったかもしれないのに。

ミオに話した。ヴァイオレットが嫌がるので、このまま連れ歩くことはできないと。
ミオはきっと泣いて抵抗すると思ったのだが、なぜか静かだった。涙だけははらはらこぼしたけれど、口では、
「わかりました」
ときっぱり言う。
やけに聞き分けがいいではないか。続けざまに怖い目に遭って、もう懲りたということなのか。
「ごめんね。こんな半端なことになってしまって」
あたしが謝ると、涙を流しながら、首をはっきり横に振る。
「サンドラには、最大限、優しくしてもらったから。今日まで、本当にありがとう。あの振り袖は、一生、宝物にしますから」
そういう態度をとられると、こちらが辛い。本当にいい子なのに。
「親切のつもりだったんだけど、かえって悪いことをしたね。怖い思いをさせただけで」
すると、ミオは口許をゆがめた。笑っているのか。
「サンドラって、本当、わかっていないのね」
「え」
何か、間違っただろうか。
「いいの。そういう人だから、好きだったの」
と過去形で言う。何か、急に大人になったようだ。ということは、結果的に、これでよかったことになるのだろうか。
「楽しかった。本当よ。少しの間だったけれど、夢を見られて、幸せだったわ」
そして、泣き濡れたままでにっこりした。
「わたし、農場を作るから。これまで、自分の貯金だけで何とかする計画だったんだけど、こうなったら、両親や祖父母に援助を頼んでもいいと思うの。いずれ、お返しをすればいいんだもの。タケルが退院できたら、大学に戻るかもしれないけど、それが無理だったら、そこで一緒に働いてもらおうと思うの」
そうか、そういうことを考えていたのか。
「自然の中で動物の世話をしていたら、きっと心がなごむわ。それに、あちこちの学校に声をかけて、子供たちの体験学習の場にするつもりよ。卵を集めたり、ミルクを絞ったり、チーズやバターを作ったり。グループごとに、ハムやベーコンを作ってもらうのもいいわね」
驚いた。ミオはすっかり前向きだ。
「うん、すてきだね。きっとタケルも元気になるよ」
あたしはそう言ったけれど、泣いてすがってもらえないのが、やや残念な気がした。この子に慕ってもらえたのは、あたしの勲章だったから。
「パパとママにも、安心してもらわなくちゃ。わたしがしっかりしないとね」
ミオは涙をこすり、にっこり笑って言う。
でも、その農場に、あたしたちを招待するとは言わなかった。あたしも、訪ねて行くとは言わなかった。もう、二度と会わない方がいいのだ、きっと。
待たせておいた《エスメラルダ》に乗り換えて中央星域に戻り、ツァオ教授と、捕まえた《ケルベロス》の構成員たちを、出迎えの司法局員たちに引き渡した。違法組織の人間からは、色々と有益な情報が得られるだろう。
先に帰した青年と少女は、無事にそれぞれの居場所に落ち着いたというので、一安心。
また、探春が手紙を送った女性捜査官からも、感謝の返事が託されていた。
『わたしは今まで自惚れの強い、傲慢な性格でしたけれど、痛い目に遭って、ただの弱い人間だということがわかりました。でも、弱いなりにできることがあると思うので、これからも頑張ります。先輩たちも、どうぞご健勝で』
という手書きの文章を読んで、探春と二人、にっこりした。女はタフでないとね。
それから、ミオを故郷の《ベルグラード》に送り、額にお別れのキスをした。ミオは少し泣いたけれど、それでも努力して微笑んだ。
「お世話になりました。さようなら。どうか、いつまでもお変わりなく」
そう言われたあたしの方が、なぜか捨てられたような気分になる。ミオはもっと何年も、あたしといたがるもの、と思っていたから。
やっぱり、本当の正常な恋愛ではないから、冷めるのも早かったということなのか。また、自分よりも弟の方が傷が深い、と思うせいなのか。とにかく、ミオが家へ帰る決意をしてくれて、よかったのだけれど。
ミオを司法局員に託した軌道ステーションから船を離し、あたしと探春は再び二人きりに戻った。探春は放心したような顔をして、居間のソファに座っている。
「大丈夫?」
あたしはつい、その前に膝をついて尋ねてしまう。正直、今回は怖い思いをした。何か余計な負担がかかったら、すぐに壊れてしまう程度の危うい状態だったのだ。あたしたちのペアは。
もう二度と、探春を追い詰めてはいけない。ミカエルのことでも、心に負担をかけたのだから。
「ええ、平気」
口ではそう言うが、まだ目の焦点が合っていない。南の島でバカンスを過ごしたら、少しは元気になってくれるだろうか。
探春はおそらく、あたしを疑似的な恋人にして、かろうじて精神のバランスを保っているのだ。それなら、それを続けるしかない。従姉妹が幸せでなければ、あたしもまた幸せではありえないのだ。
「ね、抱っこしてもいい?」
尋ねてから、そっと探春をあたしの膝に乗せた。その状態でしばらく、ニュースを見たり、バカンス先で何をするか話したりする。ダイビング、ウィンドサーフィン、島巡りのクルーズ。
予約したホテルのある島で、真珠の養殖もしていると観光ガイドにあったので、そこで真珠を買う約束をする。
「もう、ネックレスも指輪もイヤリングも、たくさん持ってるわ」
真珠好きの探春は言うが、似合うのだから、いくらあってもいいだろう。
「好きな粒を買って、違うデザインを考えればいい。そうだ、真珠のティアラは持ってないでしょ?」
「だって、そんなもの、どこへつけて行くの」
そこらのレストランへ行くには大袈裟すぎる、と言う。あたしは笑った。
「どこかのホテルを借り切って、仮装パーティでも開こうか。近所の大学で宣伝して、客を集めるとか。そうだ、パーティ券を売ったら、いい商売になるかもね。そしたら、かわゆい男の子をひっかけられるかもしれないし」
「まあ」
「探春は、ティアラをつけてお姫さまの格好をすれば。あたしは海賊の扮装でもするから。そう、髭と傷をつけてね」
「それでは、〝かわゆい男の子〟は寄ってこないわよ」
「それもそうか。じゃ、クレオパトラにでもなろう」
少しずつ、探春がほぐれて、笑みが浮かぶようになってきた。
ミオには悪いことをしたが、あの子には両親もいるし、夢もあるし、守るべき弟もいるから、きっと大丈夫だ。
その晩は、探春を抱えるようにして眠った。どうして世間には、探春やミオを安心させてやれる男がいないのだろう。
いないわけではなくて、まだ会っていないだけだ、と思いたい。
それとも、いつも探春が言うように、男と女は、しょせんは相容れない種族なのだろうか。シヴァの馬鹿も、簡単にあきらめないで、しつこく探春を口説き続ければよかったのに。
ミオは土地を買い、作業ロボットを助手に農場を始めた。やがて、学校を卒業したタケルが手伝いに加わり、仲間も集まり、うまくやっているらしい。
あたしはそれを確かめて満足し、会いに行こうとは思わなかった。市民社会には、深入りするべきではないのだ。しょせん、あたしたちは異邦人なのだから。