
レディランサー アイリス編5

迷った末に、フレンチスリーブの、白いミニドレスを着てみることにした。野戦服のズボンがはけない以上、仕方ない。
薔薇模様のレースの下着も、ブラウンの薄いストッキングも、ストラップ付きの華奢なサンダルも添えてある。いずれも上質な素材で、肌触りがよく、しっくり馴染んだ。自分まで、高級品になったみたい。
もしかして、着る物は大事なのかもしれない。美しい下着やドレスで、こんなに気分よくなれるのだったら。
浴室にある鏡で全身を確かめ、感動した。
あたし、綺麗に見える。ドレスのデザインがいいから、貧弱な胸でも、ちゃんと曲線になっている。
もしかして、人生で初めてなのか。女物のドレスを着るのって。
子供の頃に着ていたのは、腰の後ろでリボンを結ぶ、お子様向けのワンピースだったものね。
意識して男になろうとしてから、かれこれ三年、いや、四年に近い。
学校時代、同級生の女の子たちが、学校の行事やあちこちのパーティで、華やかなドレスを着ている時も、あたしは精々、簡素な紺のスーツで済ませていた。
お洒落をしたいとか、遊びに行きたいとか、そんなことで、気を散らせてはいけないと思っていた。一日でも早くパイロット・ライセンスを取ろうとして、ひたすら単位を取りまくり、あとは空手の修業をして。
(いいのかな、こんなもの着てしまって……)
《エオス》に乗ってからはなお、質実剛健を貫いてきた。オリーブ色やグレイのシャツ。厚地の作業服、作業ブーツ。
言葉もきつく、態度は挑戦的に。
何か叱られたら、三倍は言い返す。
そうでなくては、年長の男どもに張り合えない。
でも、今は、そういう突っ張りに疲れた、という気がする。本当は、こういう美しいもの、優雅なものに飢えていたのかも。
やっぱり、あたしは男じゃない。
男になろうとするのは、無理がある。
ふと思った。エディがこの姿を見たら、何と言うだろう。リナ・クレール艦長には遠く及ばないとしても、少しは可愛いとか、綺麗だとか、思ってもらえたかも。
……ううん、そんなことは今、考えない。考えたら、力が出なくなる。何とかして、ここから脱出しなくては。
ベッドにどさりと座って、あれこれ思い巡らせた。23 号が昆虫の群れを操れるのだったら、次はどうするだろう。
シドは援軍を呼び、迎撃の態勢を整えた。もう、同じ手は通用しない。《エオス》が戻ってくるまで、あと二日。でも、たった一隻で、違法艦隊とまともにやり合うなんてことは、到底不可能。パトロール艦が来てくれても、蹴散らされるだろう。
だったら《エオス》が来る前に、シドの艦隊がこの星系を立ち去ってくれる方がいい。いや、その前に、シドを何とかできれば。
突然、部屋の扉が開いた。まだ、昼時ではないのに。ベリルとペトラが、まるで葬式のような顔で入ってくる。

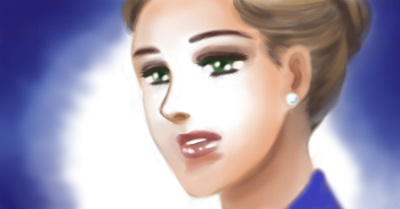
昼時になると、ベリルが昼食のワゴンを押してやってきた。金髪をきちんと結い上げて、ニンフのような美しさ。
「後で、お怪我の保護シールを貼り直しましょう。火傷の跡は、痛みませんか」
と事務的に言う。さっきのことには、触れないつもりらしい。
それなら、あたしも知らん顔していよう。内心では、抑えきれない悔しさと、恥ずかしさに焦げついていても。
給仕されて、食事をした。サーモンのクリームパスタ、子羊のグリル、ハーブとラディッシュのサラダ、ダークチェリーのタルト。
ベリルは熱い紅茶を注いでくれ、空になった食器を下げてくれる。食べる間、あたしは考えていた。侍女の二人を殺したくないとすれば、味方にするしかない。男の兵士たちもそうだけれど、好きで違法組織に生まれたわけではないのだから。
「ねえ、あなたたち」
平静なふりで、話しかけた。
「あなたとぺトラのことだけど。空いた時間があったら、ここへおいでよ。中央のことを、話してあげるからさ。亡命したら、普通の市民に混じって暮らせるんだよ。何年か施設で再教育を受けたら、自由になれるんだから。仕事も紹介してもらえるし、友達もできる。あなたたちだったら、ボーイフレンドもすぐできる。五年で死ぬ必要なんか、ないんだから」
ベリルは、意味がわからない、という顔だった。
「わたしたちは、どこへも行けません」
「シドが生きている限りはね。でも、あたしがシドを殺したら、もう組織に縛られる理由はないでしょ」
「そんなこと、あるはずが……」
「あるよ。あたしは絶対、生きて自由になる。だから、あなたたちも……」
そこで、ベリルが手を滑らせ、金属製のポットが床に落ちた。残った紅茶が流れ出す。
「申し訳ありません」
ベリルはエプロンのポケットから小型のタオルを取り出し、床を拭きにかかったが、ぽろりと落ちたものがあった。真ん中を縛った、細長い小袋のようなもの。
何だろうと覗き込んで、ぎょっとした。使用経験はないけれど、知識はある。これって、使用後、男の側が引き取るものではないの。
ベリルは落とし物に気づくと、のろのろと手を伸ばし、それをポケットに戻した。別に、慌てて隠せとは言わないけれど、床を拭いた時の迅速さと比べて、やけにだるそうだった。まるで、急に鬱状態になったかのように。
「……あのさ、嫌だったら答えなくていいけど、それは、シド?」
と恐る恐る尋ねた。
「いいえ、これは……違います。非番になった兵たちが、順番に来るので」
あたしは衝撃を受けた。
しばらく、口もきけないほど。
初めて理解した。なぜ、この現場に、非戦闘員である彼女たちが、連れて来られているのか。
シドの世話よりも、何十人もの兵士たちの〝慰労〟が、主要な役割なのだ。
それでは、バイオロイドの女たちには、何の救いもない。同じ奴隷の立場の兵士たちまでが、彼女たちを〝利用〟するのなら。
焦点の合わないベリルの目を見ただけで、その辛さがわかる。この世に生まれて数年で、疲弊しきって。
だから彼女たちは、五年で処分されてしまうのだ。肉体は若くても、心が疲れきり、生きた死人になってしまうから。それではもう、男たちの役に立たないから。
あたしの胸に溢れてきたものは、単純な怒りではない。
もっと何というか、そわそわする、もどかしさのようなもの。
いいのか、これで。
真実を見たくない一般市民はともかく、このあたしは。
いや、これまでだって、自覚しているつもりだった。重犯罪者や、その後ろ盾になる違法組織とは、戦わなくてはならないのだと。
でも、戦いを決意した直接の動機は、両親を守りたいということだった。それにまた、自分自身が生き延びたいということ。
辺境のバイオロイドの運命まで、本気で心配していたわけではない。
でも、今ここで、放っておけない悲劇を見てしまった。もう、見る前の状態には戻れない。
「あの、あのね」
考えがまとまらないうち、口を開いてしまっている。
「あたしだったら、あたしがもしボスだったら、あなたたちにそんなこと、させない。それはあんまり、ひどすぎるもの」
そんな仮定、全然、意味はないけれど。
「もちろん、新しいバイオロイドは作らせないし、前からいる者は、寿命まで生きられるようにする。いや、その前に、自分の道を選ばせる。組織に残るか、それとも市民社会に助けを求めるか」
きょとんとした顔のベリルに、続けて問いかけた。
「ねえ、考えてごらん。市民社会では、自分の好きな人とだけ、そういうことをすればいいんだよ。嫌いな男とは、手も握らなくていい。何も、ぼろぼろになるまで我慢しなくていいんだから」
本当に、この女たちの我慢ときたら、あたしなんかの比ではない。
あたしはシゴキだ何だと文句を言いながら、結局、ジェイクやバシムたち、軍や司法局の人たち、周りのみんなに守られてきた。守られることが、当たり前だった。
バイオロイドには、一切の人権が認められないのに。
けれど、ベリルはまだ、ぼんやりと曇ったような瞳でいた。あたしの言うことが、ちゃんと脳まで届いているだろうか。それとも、そんな現実味のない話なんか、聞く意味はない?
「ジュンさまは……」
「うん?」
「恋人だったのですか、あの人は」
不意打ちだった。エディのことだ。あたし、大泣きして暴れたからな。
「違うよ。でも、そうだったら、よかったな」
素直に認めてしまったら、何だか、胸のあたりで詰まっていた水路が開通したような気分。
悲しいけれど、その悲しさに、出口が見つかった気がする。
エディに対する好意を認めまい、認めまいとしていたから、あんなに苦しかったんだ。
「お好きだったのですか」
「うん」
楽しかった。厨房を手伝うのが。お茶を淹れて、おしゃべりするのが。銃や装甲服の整備さえ、エディと一緒なら苦にならなかった。
「……でも、恋人にしてもらうのは、無理だったろうな。あたし、エディに嫌われることばかりしてたから」
《エオス》から降りろなんて言って。山の中に置き去りにして。
「どうして、そんなことを?」
「ほんと、どうしてだろうね」
と笑ってしまう。
「自分でも、馬鹿だと思うよ。ひねくれていたんだなあ。あたし、エディのお母さんに、何て言えばいいんだろう……」
バシムから聞いたのだけれど、エディが《エオス》に仮採用になってから、親父が、エディのお母さんに連絡を取ったのだそうだ。危険な職場で恐縮ですが、息子さんをしばらく預かることになりました、と。
エディのお母さんは、喜んでくれたそうだ。息子が何かする気になっただけで、とても嬉しいと。少しでも、皆さんのお役に立てることを祈っています、と。
それなのに、あたしときたら。
でもベリルはまだ、納得しない顔をしている。親も兄弟姉妹もいない身では、家族の情なんて想像できないのだろう。自分を五年で殺す主人しか、すがる相手がいない。その心細さは、いったいどんなものなのか。
「あなたたちは、シドが好きなんだよね。人工的に植え込まれた気持ちでも、好きなものは仕方ないよね」
と認めた。認めないことには、話が進まない。
「でも、それでもね……もしもシドが先に死んだら、その後はどうする? シドの後を追う? それとも、殺した相手に復讐する? たとえば、あたしに? 復讐を果たしてしまったら、それからどうする?」
ベリルは唖然とした様子である。そんな未来、考えたこともないのだろう。
「シドさまは、永遠に生きられます。不老処置を受けているのですから」
「それでも、いつかは誰かに殺されるよ。他組織に滅ぼされるか、部下に裏切られるかして。ちゃんと考えた方がいいよ。そうしたら、自分はどうしたいのか」
あたしはこの女たちを、揺り動かさねばならない。あたしの味方になってくれないなら、殺すしかないからだ。
「ジュンさま」
ベリルは眉を曇らせ、頭痛をこらえるかのように尋ねてきた。
「さっきわたしは、覚悟していました。舌を入れたりしたら、噛み切られるかもしれないと。でも、ジュンさまはそうしなかった。どうして、最後まで我慢なさったのですか? 途中で、わたしたちに反撃できたのではありませんか? 手錠を外した後でも?」
意外な問いだったけれど、いい傾向だ。疑問を持ち、質問してくれるのは。
「女同士は、助け合わないといけないんだ。でないと、いつまでも、犠牲者の立場から抜け出せない。それは、中央でも同じなんだよ。昔の市民社会では、男が女を奴隷にしていた。地球時代のことだけどね。でも、その女たちが立ち上がって戦ったから、男たちも変わったんだ。女も対等な人間だって、認めたんだよ。女が自由になって、幸せになれば、男も幸せになれるって。辺境だって、これから変わるよ。あたしたちで、変えていけばいいんだ」
おお、偉そうなことを。
自分でも驚くくらい、正論ではないか。
あたしがこの星に来て、シドにぶつかったのは偶然だけれど、ある意味、必然でもあったのかもしれない。ママは違法組織から逃げてきたけれど、逃げただけでは、問題は解決しないんだ。
次の世代のあたしは、戦いを先に進めるべきなのではないか。
違法組織の解体。
中央の理想を、辺境へも広めること。
あたしの世代だけで無理なら、次の世代が引き継いでくれる。
いいぞ。なんか、戦う気力が湧いてきた。あたしはやっぱり、謙虚に落ち込んでいるより、かっかと燃えている方が自然なんだ。
「黙って耐えていたって、いずれは廃棄処分だ。だったら、生きる方に賭けても損はないよ」
この会話がシドに聞かれていても、構わない。
「世界は、《ゼラーナ》の外にも広がっているんだ。それを見るためだけでも、生きる値打ちはあるよ」
ベリルは困惑した顔のまま、ワゴンを押して立ち去り、あたしは床に座って、ストレッチを始めた。いざという時、身軽に動けるように。
見ていて、エディ。
できるだけのことは、してみるから。
運が尽きたら、あんたに会いに行く。だからそれまで、ママと一緒に見守っていて。
肉体はできた。ごく一部だけがわたしの細胞で、あとは、エディ自身の細胞を利用している。
ただし、目立たない程度に、骨格と筋肉を強化した。エディ本人よりは、何割か強いはず。
暗い洞窟の中で、エディから取り上げておいた服を着た。胸に焦げ穴のある戦闘服だ。
いかにも病み上がりらしく、よろめき歩いてみせよう。野山を歩いていれば、いずれ警備衛星か偵察鳥が発見してくれる。
わたしの細胞を入れた兵たちが、指揮官に対する反乱を成功させてくれればいい。そうでなければ、わたしの出番。
違法組織の弱点は、組織がピラミッド型であることだ。指揮官さえ倒せば、いくらでもやりようはある。彼らがこの星に核ミサイルの雨を降らす前に、勝負をつけなくては。

夕方、アンドロイド兵士が二体迎えに来て、あたしに手錠をかけた。今度は、躰の前側で。
連行されて司令室に入ると、壁の大画面には、相変わらず、捜索の状況が映されている。当直の兵たちの緊迫度からすると、23号は未だ発見されていないらしい。
グレイのスーツを着たシドが、あたしを奥のテーブル席に招いた。
「客人を放っておいて、すまないね」
「どういたしまして。あんたも、虫刺されで大変だったでしょ」
と言ってやったら、苦笑する。今はシドの顔にも手にも、わずかな赤い跡しか残っていないけれど、ショックで死んだ兵もいるのだから。
「確かに。狩りの途中で油断はよくないと、身に染みた。ところで、そのドレス、よく似合うじゃないか。見違えたよ」
そうら、きた。
「どうもありがとう。あたしの趣味とは、ちょっと違うけど」
裾の短い、白いドレスのあたしは、つんとして言った。こういう態度が、シドを喜ばせるらしいから。そうでないと、あたしは長生きできないことになる。
「しかし、その上着は脱がないかね。ドレスと不釣り合いだよ」
あたしはしっかり、戦闘服の上着を着込んでいる。そうでないと、無防備すぎて。
「手錠付きでは無理だね」
「そうだな。キス一回と引き換えで、しばらく外してやろうか」
シドがあたしの手を取ろうとしたので、ぴしりと払った。
「狩りの途中で、油断はしないはずでしょ」
彼は苦笑し、手を引っ込める。
「ふむ。では、夕食を一緒にどうかね」
「それならいい。あたしも退屈してたんだ」
ストレッチと腹筋、スクワットに腕立て伏せだけでは、そう長い時間は保たない。上空の母艦のライブラリーは利用できたが、娯楽番組を見る気分ではないし。
夕食が運ばれてくるのを待つ間、シドはテーブル席の向こうから言う。
「ところで、お嬢さん。きみはこの艇内に、反乱分子を育てようとしているらしいね。女たちは、だいぶきみに懐いているようだ」
ふん、隠し撮り野郎が。
「あんたが真人間になれば、反乱は必要なくなる。そうしたら、あたしも友達になってやるし」
威張って言ったら、シドは据え付け型の椅子の背にもたれ、楽しげに笑った。
「では、わたしに、中央へ戻って、刑を受けろと言うのかね」
惑星連邦に死刑はない。不完全な人間が、人に死を宣告する権利はないからだと学校で教わった。最高刑でも終身隔離だ。それも、刑罰というより、危険人物から社会を守るため。囚人とはいえ、快適なホテル暮らしと変わらない。反省を強要されることもない。精神は自由だ。法はただ、物理的な自由を制限するだけのこと。
犯罪者が自首して出た場合は、過去にどれほど殺していても、数年の隔離で済むだろう。そんな物好き、滅多にいないらしいけど。
市民社会では、不老処置の更新はできないからだ。いったん不老不死を目指した者には、馬鹿馬鹿しい結末であるに違いない。
「別に辺境にいたって、組織を率いていたっていいよ。部下の人権を守ってやれるなら」
辺境で暮らすことが、犯罪なのではない。不老不死を目指す挑戦が、悪いわけでもない。無法地帯であることに安堵して、ありとあらゆる非道を繰り返すことが悪いのだ。
「人権?」
シドはわざとらしく、目を丸くしてみせる。
「ベリルやペトラたちは、ずいぶんひどい目に遭ってるようじゃない」
ポケットから、ぽろりと、ああいうものが落ちるような生活だ。
「ふむ。まあ、そうかもしれない。しかしね、男の兵士には、息抜きが必要なんだ。恐怖を紛らすためにも、興奮を鎮めるためにもね。地球時代の軍隊も、しばしば娼婦の集団を連れ歩いていた。港町には、娼館が立ち並んでいたものだ」
勝手な理屈。
考慮されるのは男の都合だけで、女の都合は無視されている。
「だったら、男なんか絶滅すればいいんだ。世界中の女がほっとする」
「お嬢さん、きみの父上も男だぞ」
「女に暴力を振るわない男なら、存在してもいい。言っておくけど、洗脳して従わせるのも、暴力だからね」
シドは苦笑した。
「きみと話していると、本当に退屈しないな。下劣な男は滅びるべき、か。いやはや、きつい」
何も本気で、男が滅びた方がいいとまでは、思っていないけど。悪質な違法ポルノの流通を見ると、男の愚劣に呆れ果てるのは事実。
「しかし、野蛮な男がいなくなって、腑抜けた下僕男ばかりになったら、それもつまらんだろう」
「ふん。野蛮な男だって、実体は腰抜けなんだから、同じだよ」
この世に、強い女はいても、強い男はいないのではないか。
親父だって、ママが死んだ時には、暗い部屋で一人、いつまでもしょぼくれていた。
ジェイクだって、仕事仲間の女性に捨てられて気落ちして、腑抜けていたところを《エオス》に拾われた。子供の頃、最初に見たジェイクは、誰かに死なれたばかり、みたいな顔していたもの。それでも、あたしに向かって、お義理のお愛想を言ったりしてさ。
「あんたみたいな男が威張っていられるのは、相手が、自分より弱い立場にいる時だけじゃないさ。それに、女は、男を奴隷にしようなんて思ってないよ。紳士でいてくれれば、それでいいんだから」
「おやおや、そうかね」
なに、その厭味な言い方は。
「あの金髪の坊やは、どう見ても、きみの奴隷だったがね。気の毒に、きみに好かれようとして、懸命に尻尾を振っていた」
むっとした。
あたしのことならともかく、エディを侮辱するようなことを。
「エディは紳士だったから、あたしに気を遣って、優しくしてくれただけ。あんたのひねくれた見方では、どう見えたのか知らないけど」
「わたしのひねくれた見方では、彼は、きみに惚れていたね。きみは、気づかなかったというのかい? それとも、彼を振り回して楽しんでいたのか? まったく、女というのは、残酷だからな」
あたしはしばらく、開いた口がふさがらない。ちょっと偵察映像を見たくらいで、いい加減なことを。
「エディには、好きな人がいたんだ。あたしなんかとは、比べものにならない人」
喉が詰まった。写真でしか知らない美女。あの人が生きていれば、エディが《エオス》に来ることもなかった。
「ほう、そうかね。男というのは、次々に何人でも愛せる種族だが」
「そうじゃない男もいる。親父は、ママを忘れていない。他の女の人になんか、見向きもしない」
「それは、きみに軽蔑されるのが怖いからだろう。何しろ、普通の五倍くらい、きつい娘だからな」
きついことは認めるが、その数字の根拠は何だ。
「きみもそろそろ、父親離れしたらどうだ。船長は男盛りだというのに、きみが張り付いていては、美女とデートもできまい。きみは、わたしと楽しく過ごせばいいんだから」
失礼な。あたしはただ、しょぼくれ親父の保護者になってやっているだけ。
何か辛辣なことを言ってやろうとした時、料理のワゴンを押して、短い赤毛のペトラがやってきた。
「お待たせいたしました」
運動でもしてきたかのように、色白の肌が上気して、灰色の目が楽しげに輝いている。まるで、大輪の薔薇のよう。昨日の火事の中では、ずいぶん疲れて見えたのに。
「昨日の傷はどう?」
と尋ねたら、テーブルに料理の皿を並べながら、にっこりする。
「もう大丈夫です。ジュンさまが撃たないで下さったので、いま、命があるんです。生きているって、いいことですね」
あっと思った。ちゃんと通じていたんだ、あたしの気持ちは。それならよかった。昼間の一件なんか、何でもない。
でもシドは、あたしとペトラの心の交流が、気に入らなかったらしい。
「ジュンが好きなら、今後もずっと、ジュンの侍女になるか?」
と冷たく言う。いいえ、わたしにはシドさまだけです、という答えを期待して。
ところが、ペトラは華やかに微笑む。
「はい、そうできたら嬉しいです」
あたしより、シドの方が驚いたようだ。奴隷女は、自分だけを一途に慕い続けると思っていたのか。休日も、私服も与えないくせに。
「ふむ。女同士の連帯というやつか。では、こういうのはどうだ」
シドは太い指で、割れた顎を撫でる。
「お嬢さん、きみがわたしの言うことを聞いて、いい子にしていれば、この女たちを無事に生かしておく。しかし、きみがわたしに逆らったら、その都度、この女たちの指を、一本ずつ切り落としていく」
何だって!?
「最初は足の指、次に手の指だ。指が全部なくなったら、次は手足かな」
ペトラは恐怖で顔を伏せてしまい、そのまま凍りつく。あたしは唖然として、シドの顔を見つめたまま。
こいつ、気の利いた冗談でも飛ばしたつもりか。
それとも、本気。
あたしなら、脅されたっていい。怒りがあれば、恐怖にも屈辱にも立ち向かえる。でも、抵抗する力を持たない女たちに。
「謝れ。悪質な冗談を聞かせて悪かったって、ペトラに謝れ」
通信席の兵たちは聞かないふりをして、手元の画面に視線を落としたまま。それが、奴隷の心得。でも、肩がこわばっている。彼らはそれぞれ、ベリルかペトラに〝慰安〟してもらったはずだ。
「冗談だ、ということにしたいのかね? この女たちのために、自分の貞操を犠牲にしたくないから?」
シドはにやついて言う。胸がむかついた。自分の卑劣を、あたしの卑劣に置き換えようというのか。
「それで当然だな。たかがバイオロイドのために、本物の人間が犠牲を払う必要はない。この女たちは、人間が快適に暮らすための道具だ。どんな使い方もありうる」
シドは言い切った。ペトラや、バイオロイドの兵士たちがどう思うかなぞ、はなから問題にしていない。いや、それとも、自立心や反抗心の芽を摘むために、わざと言うのか。
「昼間は、きみも楽しんだだろう、お嬢さん」
え?
「おかげで、いい表情が撮影できた。相手が女なら、それほど嫌なことではなかったらしいな。ずいぶん我慢していたようだが、最後の一声はよかった。実に切なくて、風情があったよ。お次は、指を二本にさせようか?」
その瞬間、氷と液体が辺りに飛び散った。あたしが椅子から立ち、グラスに入った金色のジャスミンティを、シドの顔面にぶちまけたからだ。
怒りで頭が白熱していて、先がどうなるかまで、心配していられない。どのみち、あたしを怒らせて楽しみたいのだ、こいつは。
しかし、シドには予想外の反抗だったらしい。顔や髪からぽたぽた雫を垂らしながら、唖然としている。
当直席の兵たちは揃って腰を浮かせ、腰の銃に手をやった。壁際にいたアンドロイド兵たちが、銃口をあたしに向けて前に踏み出す。神聖不可侵のボスに対しては、許されない冒涜だったらしい。
「動くな!! わたしが処理する」
シドは兵たちを手で制してから、ペトラが差し出したタオルで顔や肩を拭った。
「わかったよ、お嬢さん」
不気味に穏やかな声で言う。
「きみはまた、わたしに吊るしてほしいんだろう。あのお仕置きが、気に入ったんだな」
あたしは一気に血が引いた。
あれは。あれだけは。今度はたぶん、もっとひどいことになる。
シドはあたしの恐怖を見てとり、優位の笑みを浮かべた。
「わかっていて反抗したのだから、ご期待に応えよう。どうせ、追加の映像が必要になる。きみの調教記録を、大々的に売り出すつもりでいるのだよ」
調教……記録?
「だいぶ撮り溜めた。川での水浴び、逆さ吊り、女奴隷による悪戯。わたし一人で楽しむには、勿体なさすぎる。有名人の娘というだけで、見たがる男はたくさんいるからね」
足がすくんだ。そんなものが世間に出回ったら、たとえ生きて自由になれたとしても、二度と町中を歩けない。きっと、人の視線が怖くなる。指差されるのが怖くなる。
「次は、どうするかな。裸で、蛇の浴槽に放り込むか。いやいや、脱がせるのは最後だな。着衣のまま縛った方が、風情がある」
だめだ。そんな映像、親父が知ったら耐えられない。あたし本人より何倍も苦しみ、脳内出血か心臓発作でも起こすのではないか。
殺す。
こいつ、殺すしかない。
頭が白熱して、それしか考えられなかった。あたしは床を蹴り、シドに飛びかかった。
しかし、手錠付きではやはり遅い。目玉を狙った突きは軽く払われ、投げ飛ばされる。あたしは床に転がり、受け身を取って起き上がった。そこに、蹴りをくらう。
骨折するような鋭い蹴りではなく、胸全体を靴底で押された。体重差があるから、かなりの衝撃。
押し飛ばされ、背中を打ち、息が詰まった。横隔膜が、応えてくれない。転がって苦しみ、仰向けになったところで、シドの足でぐっと踏み付けられる。喉を、まともに。
「いい子だ、ジュン。可愛いらしく、泣いて謝ってごらん。それが、女の子の武器ってものだ。普通なら、わたしに危害を加えようとした者は、即座に処刑だぞ」
気道が潰れる。息ができない。
だけど、泣いて謝ったところで、調教とやらから逃れることはできない。どうせ人間、死ぬのは一度きり。
耐え続けて、気絶寸前、ふっと足の圧力がゆるんだ。急いで横に転がり、必死で息を吸い込む。
「強情なところが可愛い。軽いお仕置きにしよう。鞭で打たれたことがあるかな、お嬢さん」
あるわけない。だけど、それなら、浴槽一杯の蛇よりましだ。
「手加減するし、服の上からなら、そう痛くないはずだ。痛かったら、泣いて謝ればいい。ごめんなさいと言ったら、そこで許してやろう」
あたしは引き立てられ、手錠を外され、上着を脱がされ、左右の手首を一体のアンドロイド兵士に握られて立たされた。兵士の堅い胸板に、顔をすりつける格好だ。
シドはあたしの背後に立ち、床を叩いて鞭を鳴らす。
「きみのために用意した鞭だ。出番があって、嬉しいよ」
そんなもの、用意するな、変質者。
打撃を数えていたのは、幾つまでだろう。最初は、たいして痛くない、と思った。ただ、背中に重い衝撃を受けただけ。
四撃目あたりから、はっきり痛みになってきた。いったん痛みだと認識すると、それは二度と、意識の外に追いやることはできない。
しかし、まだ耐えられた。空手の稽古で骨折したり、ナイフを使った格闘術で切り裂かれたりする方が、ずっと痛い。
「わかっていたことだが、根性のあるお嬢さんだな。こちらも、調教のし甲斐がある」
シドは、笑いのこもった声で言う。あたしは、昔のサーカスの動物じゃないぞ。今は動物だって、権利を保護されている。
六撃かそこらで、ドレスの布地が裂けた。皮膚が露出したところに、次の打撃が来る。反射的に、叫んでしまった。
痛い。きっと、背中が裂けた。生理的な涙がにじむ。
「おお、可哀想に。これは効いたな。どうだ、降参するか?」
しない。でも、自信がない。あと何撃、耐えられるか。
次の一撃がきた。精一杯こらえたけれど、涙が止まらない。足が震える。立っていられなくなる。ただ、アンドロイド兵に両手首を握られているから、倒れられないだけ。
「まだ頑張るか? ごめんなさいと言えば、それでいいんだぞ」
言わない。まだ。
「よし。代われ」
シドは、誰かに鞭を譲ったらしい。兵に代わり、あたしの腕を握って立つ。
あたしの腕を、自分の背中に回すようにして固定した。あたしは、シドと抱き合って立つ形になる。どうやら、あたしが打たれた瞬間の震えや、身もだえを楽しむつもりらしい。この変質者。
「軽く打ってやれ。女の力なら、たいした怪我にはならん」
すると、鞭を持つのは、ベリルかペトラか。
後ろを見られないのでわからないけれど、彼女は鞭を持たされてから、しばらくためらっていたようだ。シドに命じられたことなら、何でもするはずなのに。
ためらってくれただけで、十分。だから、打ってもいいよ。打たなければ、あなたたちが罰を受ける。
あたしは、そう言うべきだった。でも、言葉が出ない。もうこれ以上、一撃も受けたくない。何でもするからやめて、と叫びたい。どうしてあたしが、こんな目に遭わなきゃならないの。
「どうした、ベリル、できないのか?」
シドに催促されて、ベリルは慌てて鞭を振ったらしい。打撃が、あたしのお尻に当たる。
あたしは思わず叫び、身をそらせた。それが、シドに腰をすりつける結果になる。おう、と喜ぶ声。こいつには、こんなことが楽しいのか。
「おいおい。尻や脚はよせ。椅子に座れなくなるのは可哀想だ」
それ以前に、もう、ベッドに仰向けに寝られないと思うけど。
ベリルは狙いをつけやすいよう、やや前に出て振ったらしい。次は、背中に当たった。生地の残りが裂け、背中に新たな傷が走る。
あたしは無言のまま身悶えし、シドの腹に胸をすりつける状態で涙を流した。悲鳴をこらえようとすると、どうしても息が荒くなる。
「可哀想に、まだ頑張るのかね?」
泣いて謝れば、この場はそれで助かるのだろう。でも、また次がくる。こいつは、あたしをぼろぼろにするまで、こうやって遊ぶつもりだ。
まだ、耐えられる。
あたしはずっと、耐えてきた。
《エオス》に乗る何年も前、母娘二人で暮らしていた頃ですら、商店の棚の陰で、学校行事の講堂で、休日の公園で、ひそひそささやく人たちはいたのだ。
あれが例の亡命者、殺戮用の〝生きた兵器〟だと。
議会や司法局はなぜ、あんな化け物を、町中で暮らさせておくのか。
英雄の妻だからといって、特別扱いするのか。
また暗殺未遂でも起きたら、周りが迷惑なのに。
どこかの山奥にでも引っ込んで、他人と関わらずに暮らせばいいじゃないか。

また一撃。
あたしは無言のまま震え、シドの胸に顔をこすりつけ、涙を流した。もし、エディがいてくれたら。エディにすがりついて、大泣きできたら。
「立派だよ、お嬢さん」
シドの声が、頭上で言う。
「これまで、女を痛めつける男というのは、ただの精神異常者だと思っていた。しかし、必ずしもそうではなかったらしい。屈服しない女を、何とかして屈服させようとする。精神と精神の戦い。それが、こういう行為の本質らしい」
そんなこと、改めて悟るようなことか。
おまえたち男が、大昔からやってきたことじゃないか。
女を脅し、殴り、強姦した。
そして、屈服しない女は殺してきた。
歴史で習ったぞ。本も読んだ。いつの時代、どこの国でも、おまえたちはそうしてきた。女たちが立ち上がり、世界規模で手を結ぶまで。
シドの声が、遠くで笑っている。
「きみは全く、値段のつけようがない貴重品だな。まだ子供のくせに、よくもここまで意地を張る」
おまえに誉められても、嬉しくない。
「よし、次だ」
ヒュッと新たな鞭が飛び、あたしの頭上を通過した。髪をそよがせる感覚で、それがわかる。
「何をする!」
シドが叫んで、あたしの腕を放す。後ろへ飛び退いたらしい。
あたしは床に膝をつき、前へ倒れた。もう、立てない。このまま気絶したい。
けれど、背後で誰かが殴られ、床に倒れるのがわかった。
「きさま、わたしの目を狙ったな!! ジュンに忠義立てしたつもりか!!」
薄れそうな意識が、かろうじて戻った。ベリルが、シドの目を狙った!? それでは、反逆行為だ。しかも、無駄な反逆。
「この不良品めが!!」
これまでダンディを気取っていた男が、本音の声で叫び、ベリルを蹴りつけた。床に倒れて頭を抱え、身を縮めていた女を。
あたしは肘をついて、上体を起こした。シドの堅い靴先の当たった場所で、骨が折れる不気味な音がする。
「やめて下さい!!」
身を投げ出してシドの脚にすがりついたのは、ペトラだ。
「どうか、お許し下さい。ベリルは、手元が狂っただけです。わたしたちがシドさまに逆らうなど、絶対にありえません」
ところが、シドはそのペトラを振りほどき、蹴り倒した。顔面をまともに蹴られた女は、顔を手で覆って倒れ臥す。白い指の間から、たちまち血が流れ出る。あれは絶対、鼻が折れた。
やっぱり、こいつは屑だ。
大物ぶっていても、すぐメッキが剥がれる。
シドが向きを変え、またベリルを蹴ろうとするので、あたしは叫んだ。
「いい加減にしろっ!!」
二体のバイオロイド兵に引き起こされ、腕を取られ、床に引き据えられていたけれど、口は塞がれていない。
「バイオロイドだって、いつかは人間になるんだよ!! 洗脳なんて、いつまでも続きゃしないんだから!! 腐った男なんか、本物の忠誠を得られるわけないだろっ!!」
シドはあたしを振り向いた。精神の動揺が顔に表れ、肩で息をしている。
たっぷり数秒経ってから、ようやく息を鎮め、あたしに問いかけてきた。
「こいつらの命乞いか? それとも、口先で偉そうなことを言うだけか?」
仕方ない。
「その二人を殺さないで。許してやって。その代わり……あたしが何でもする」
言ってしまった。とうとう。
だって、この二人はあたしをかばい、仲間をかばったのだもの。その気持ちに応えなくては。人間がみんな、シドのように腐ってはいないことを、知ってもらわなくては。
シドは無言のまま、しばし考えた。立ち直りの早さは、さすがだ。再び口を開いた時には、冷徹な統率者に戻っている。
「その提案は非常に魅力的だが、それでは、組織全体に示しがつかないのだよ、お嬢さん。人間に逆らう不良品は、ただちに処分しなければ」
あたしの馬鹿。
あたしのせいで、この二人が殺される。
「この女たちを……」
シドが言いかけた時、当直席のバイオロイド兵が声を上げた。部屋中が振り向くような声を。
「シドさま、鳥が妙な人影を捉えました!!」
一拍おいてから、シドが大画面の方を振り向いた。
「妙とは、どういう意味だ」
不機嫌な声に、兵士はひるんだけれど、報告はしなければならない。
「これです。殺したはずの男が、ここに……」
心臓が止まるかと思った。拡大された空撮画面の中に、エディがいる。木々にすがりながら、ふらついて歩いている。
夜の闇の中での映像だけれど、補正されているから、色彩もわかる。戦闘服の胸が焦げ、周囲に血の染みがついているのは、撃たれた跡だ。
シドもさすがに、驚きを隠せなかった。
「即死のはずだぞ。どうやって生き返った!?」
――ああ、神さま。
銃の出力不足だったのかもしれない。安堵のあまり、気が遠くなりかけた。でも、シドの台詞ではっとする。
「捕まえろ。23号が化けているのかもしれん。細胞検査だ」
あれが偽者なら、のんびり気絶している場合ではない。偽者が着ているのは、《エオス》の備品である戦闘服。つまりそれを、エディから奪ったということだ。じかに会って、エディの生死を聞き出さなくては。
遠い山中でエディを捕まえた兵たちが、小型艇で戻ってきた。
あたしとベリル、ペトラは医療室で手当を受けた上で、手錠をかけられ、三人一緒に、司令室の隅で兵たちに見張られている。
せっかくの夕食は片付けられてしまって、あたしたちは空腹のまま。シドの根性悪め。鞭の恨みより、食い物の恨みの方が恐ろしいぞ。
鎮痛効果を持つ湿布のおかげで、背中の痛みは和らいでいた。ベリルも、あちこちの骨折を保護するギプスをはめられ、どうやら起きていられる状態。内臓破裂を起こしていなくて、幸いだ。ペトラは綺麗な顔の真ん中に、厚い保護シールを貼られている。
「こんなことになって、ごめんね。あたしをかばってくれて、ありがとう」
そっと言うと、二人とも、痛そうに微笑んでくれた。
「女同士は、助け合うんでしょう?」
あたしも笑った。
「そうだよ。それで、世界を変えていくの」
男が暴力に走る阿呆ばかりなら、女がしっかりしなければ。
結局は、三人とも、シドに殺されるだけかもしれないけれど。
それでも、心が通じたことは嬉しい。もしも、辺境中のバイオロイドたちが互いに励まし合って、立ち上がることができたら。辺境では、ごく少数の人間が、圧倒的多数のバイオロイドに取り巻かれているのだから。
(あたしに、この先も命があれば)
と、ひりつくように思った。そうしたら、〝リリス〟のような活躍は無理だとしても、何かはできるだろうに。
「シドさま、移送中に、捕虜の身体検査をしました。全身八箇所で細胞を採取したところ、そのうち五箇所までは人間のものです。残りの三箇所、脳幹部分と、撃たれた胸から背中にかけて、人工細胞に置き換わっています」
部下から報告を受けたシドは、厳しい顔をした。
「23号に助けられたということか? ただの親切ではあるまい。ここへ連れてこい」
偽者ではなくて、エディ本人なの? 23号に、何かされたの?
手足に手錠をかけられたエディが、兵たちに連行されてきた。具合が悪いらしいのに、司令室の真ん中の床に、乱暴に突き倒される。
「わたしがわかるか、小僧。この《ゼラーナ》の統率者、シドだ」
左右に護衛兵を従えたシドが、尊大に名乗った。あたしの機嫌を取る時とは、大違いだ。
「どうやら、23号に会ったらしいな。どんな奴だったか、話せ。後はおまえの態度次第で、わたしの部下に取り立ててやってもいい」
エディを洗脳して、使うつもりか。
「あたしが聞く。あんたなんかに、エディは何も言うもんか」
五メートルほど離れた兵の垣根の中から、あたしは呼びかけた。
「エディ、しっかりして。あたしがわかる? こっちが見える? エディ?」
エディが床の上で上体を起こし、ぼんやりした顔でこちらを見た。視力はあるらしいが、あたしを見ても、その顔は曇ったまま。
エディじゃない、と悟った。
エディなら、あたしを見て、何か反応するはずだ。怒りにしろ、喜びにしろ。
あたしの顔を見て、シドも何か悟ったらしい。
「おまえたち、そいつを……」
シドが命じかけた瞬間、エディの偽者が飛び上がった。糸で吊られたように。
見張りの兵たちが、銃口を向けた。四方の壁や天井からも、蛇の鎌首のような銃口が現れ、パルスレーザーを発射する。
まだ空中にあるうち、偽者の肉体はずたずたに撃ち抜かれた。片方の腕がちぎれ飛ぶ。顔面が消滅する。脳が飛び散る。膝が砕かれる。腹に大穴が開く。
それでも、その男の残骸はシドに飛びついた。そしてシドの口に、無事な方の手を突っ込んだ。
後で知ったことだが、指の先端が変形して伸び、シドの喉の奥を突き破り、脳幹と小脳に達していたのだ。
アンドロイド兵たちが、急いでシドを助けようとする。
その時、なぜかバイオロイド兵の一人が、自分の銃でシドの胸を撃ち抜いた。それから、左右にいた仲間の兵たちを撃ちまくる。生身の男たちは、ひとたまりもない。もっとも、その反逆兵も警備レーザーに撃ち抜かれたが。
あたしが唖然としているうち、ペトラが飛んだ。倒れた兵士の手から落ちた銃に飛びつき、くるりと回転して撃ち放す。警備レーザーの砲塔が幾つも潰される。
左右の手首をつなぐ手錠と、ひらひらするスカート姿にもかかわらず、訓練された兵士のような動き。
異変を知って、通路から駆け込んできたバイオロイド兵たちが、それぞれぺトラに頭を吹き飛ばされた。ぺトラは冷静に、残った警備レーザーも始末する。
(うそっ。これがペトラの実力!?)
あたしを追って、よたよた山の中を走って来た時は、絶対こんなじゃなかった。すると、もしや!?
心を持たないアンドロイド兵たちが、反逆兵(既に何箇所も撃たれているのに、まだ動いている)とペトラに向かって、淡々と銃撃を加える。あたしとベリルは、流れ弾に当たらないよう、床に身を伏せているのが精一杯。
反逆兵はついに頭を撃ち抜かれて倒れたが、ペトラはうまく通路に逃れた。アンドロイド兵たちが、それを追う。
司令室内は、嘘のようにしんとした。ただ、幾つもの死体が転がり、破壊された機器が火花を散らすだけ。
あたしはそろそろと、頭を上げた。艇内の遠くで、叫びと銃声が聞こえたけれど、それもすぐに止む。
室内に残ったアンドロイド兵たちは、なぜか、彫像のように動きを止めていた。数体は、倒れたシドの回りにしゃがみこんだまま。数体は、あたしとペトラを囲んだまま。
そうっと、灰色の皮膚をした兵の胸を押してみた。二メートル級の兵は、マネキンのようにぐらりと揺れ、どすんと倒れただけ。管理システムの制御が失せているらしい。
次には、艇内の照明が消えた。ただ、床や壁のあちこちに発光パネルが使われているので、真の闇ではない。
「ジュンさま、これは……」
ベリルもそろそろと身を起こして、あたしの後に続く。シドはエディの偽者と折り重なったまま、床に倒れていた。目を見開き、偽者の手を口に入れられたまま。撃たれた胸からは、どくどく血が溢れている。
エディそっくりだった偽者はもう、見分けもつかない残骸だ。
大画面からも光が消え、空調のような基本機能まで止まっていた。外部との通信も、絶たれているようだ。
「艇の管理システムが、死んだんだ。外部からの乗っ取りでないとすれば……シドが完全に死んだからか……」
管理システムが、シドの脳死を確認した。そして、かねてからの指令に従い、自分自身を停止させたのだろう。唯一無二の主人が死んだら、何をするべきか、なさざるべきか、人格のない管理システムには、もはや一切判断できないから。
おそらく他の艇も、上空の母艦も全て、動力を切られてしまっている。独裁が普通の違法組織では、こういうこともあるのだろう。
シドは自分の死後、誰に組織を譲るとも、決めていなかったのだ。もし、組織を継ぐ者が勝手に出現するとしたら、混乱は自分で何とかしろ、という意地悪なのかもしれない。
「シドさまが……お亡くなりに……?」
「おめでとう。自由の身だよ」
あたしは落ちていた銃を拾い、呆然としているベリルの手錠を壊した。ベリルに方法を教え、あたしの手錠も壊させた。
二人で銃を構え、そろそろと、暗い艇内を歩きだす。
そこここで、アンドロイド兵が床に座り込み、あるいは仰向けに、もしくはうつ伏せに倒れていた。管理システムの末端である彼らは、機能停止の信号を受けて藁人形同然だ。撃たれたバイオロイド兵の死体も、十体以上あった。
けれど、艇の奥では、生きて動いている者たちの気配がある。
そこではっとして、ベリルを押し、物陰に隠れた。エアロックの一つを、誰かが外側から開こうとしている。もはや、艇内外の砲塔に狙われる心配がないからだ。
二重扉の外側が開き、内部扉に手がかかった。内部扉は半透明なので、外の暗闇から入り込んできた者が見える。
裸の女? 他の艇にいた侍女だろうか? 兵士に〝奉仕〟させられていた最中だったから?

二時間あまり後、再び明かりがついた。再起動した管理システムは、今度は23号……アイリスを新たな主人として認識しているという。
エディが説明してくれた。この司令艇が真っ先に復旧したので、ここから他の艇や、上空の艦隊に指令を出すことができたと。
「上空の艦隊も、シドの死亡信号で機能を止めたままだった。浮かぶ棺桶状態だね。上の連中も復旧を急いでいたようだけど、こちらがスピードで勝ったから、警備システムとアンドロイド兵を使って、艦内に麻痺ガスを流しておいた。後はアイリスの仲間たちが乗り込んで、片付けてくれる」
さすがはエディ。見事なお手並み。
「おかげで助かったわ。上の連中が先に再起動に成功していたら、厄介なことになっていたでしょう」
アイリスは裸のまま司令席に座り、あちこちに指示を飛ばしていた。復活したアンドロイド兵たちは、アイリスの命じるままに働いている。銃撃戦による損傷の修理、負傷者の手当て、死者の埋葬。
生存者にはアイリスの細胞を植え込み、アイリスの仲間として復活させるそうだ。考えようによっては、非常に恐ろしいことなのだけれど、この際はやむを得ない。
ペトラのように、既にアイリスの細胞を植えられている者たちは、それぞれ無駄なく働いていた。上陸艇で各地に飛び、アイリスの仲間たちを集めて回ったり、上空の艦隊を占拠したり。
諸々の手配が一段落すると、アイリスがエディに言った。
「あなたは、輸血を受けた方がいいわ。そして、一眠りなさい」
エディはアイリスの仲間たち――山猫や鳥やリス、猿や鼠や昆虫などの混成軍団――と共に周辺の野山に潜んでいて、管理システムが停止した瞬間、この停泊地に一斉攻撃をかけたのだという。
外で巡回していたバイオロイド兵たちは、みな倒された。装甲服を着ていても、ボディに取りつかれて気密ロックを解除され、隙間から昆虫に侵入されたら、それで終わり。
あたしはエディと一緒に医療室に行き、世話をした。人工血液の輸血、あちこちの怪我の手当て。大きな怪我はなかったけれど、野山の移動や乱戦の中で、あちこち傷を負っている。
何より、銃撃で心臓を吹き飛ばされたのは、本当だという。アイリスがいなければ、その場で死んでいたはずなのだ。
危なかった。
もう二度と絶対、エディをこんな目に遭わせない。
ベリルは、隅の医療ベッドの患者に付き添っている。喜んでいいのか、悲しむべきなのか、決めかねている顔で。
上半身裸のシドが、やはり輸血を受けていた。アイリスが自分の細胞を植え、復活させるという。
「脳細胞が死滅しきらないうちに、血流を再開させたから、記憶を保ったまま起き上がるでしょう、主基地を掌握するためには、シドがいた方が便利なのよ」
それがいいことなのか、悪いことなのか、あたしにはわからない。シド本人にとっては、間違いなく災厄だろう。
けれど、アイリスにとって、自分の細胞をこの世に広めることは、当然の権利なのだ。たとえ、他人の肉体を苗床にしても。
命を助けられたあたしは、それに文句をつけられない。人間だって、牛や豚を食べている。生きることは、常に他の生命を犠牲にすること。
そもそも、人類とは異なる種族に対して、人類の道徳を押しつけることはできない。
だとしたら、これから先は、あらゆる知的種族が参加できるような、ゆるやかな同盟を作るべきなのかもしれない。人類自体が二つに分裂している状況では、まだまだ遠い目標だとしても。
「夜食を持ってきたわ」
ペトラは元気一杯で、メイド服から戦闘服に着替えていた。
「ありがとう。かっこいいね、それ」
と食べ物を受け取って言うと、白い顔がにっこりする。
「ありがとう。わたしもそう思うの」
とりあえず、皆で栄養補給をした。あたしとベリルとペトラ、アイリス。エディは輸血を受けながら眠ってしまったから、また後で。
ハムとレタスのサンドイッチ、タラとポテトのフリット、グリーンピースのポタージュ、フルーツケーキ、ジャムを載せたクリームチーズ、熱いコーヒー。
食べながら、話した。アイリスと仲間たちは、手に入れた艦隊を使い、《ゼラーナ》の基地を全て乗っ取るつもりだという。
「主基地ではまだ、この異変に気づいていないわ。作戦終了まで、余計な連絡は絶っているから。シドの姿を使えば、組織の掌握は問題ないでしょう。それから落ち着いて、次を考えるわ」
《ゼラーナ》一つで満足するか。他組織も乗っ取り、勢力を広げていくか。それとも、この銀河を出ていくか。
「ペトラはどうする? アイリスと一緒に行く?」
「それがいいでしょうね。中央に亡命しても、生体実験の材料にされるか、こっそり抹殺されるかでしょうから」
とアイリスは言う。
「でも、あたしのママは……」
「逆改造しなければ、一生、隔離施設から出られなかったのでしょう。わたしはごめんだわ」
とぺトラは言う。
そうだ。ママは本当には、市民社会に受け入れられなかった。普通人は、辺境産の強化体や実験体を恐れる。古き良き時代を終わらせる、大津波の先触れだから。
「わかった。あなたたちのことは、あたし、誰にも言わない。親父にも内緒にする」
と約束した。存在を知る者が少ないほど、アイリスたちは安全なのだ。
「ありがとう。助かるわ」
アイリスは、ママそっくりの顔でにっこりする。見慣れてしまうと、裸でいられても、どうということはない。
人類が衣服を必要とするのは、虚弱だからだ。アイリスたちは人類を超える、新たな種族。人類の文化には縛られない。

ここは、どこだ。
俺はどうして、こんな所に寝ている。
長い夢を見ていたような気がするが、目を開けたら、消えてしまった。ベリルが俺に取りすがって、泣き笑いしている。その後ろに、ジュンと裸の女が立っている。
赤毛の女は、ペトラか。侍女の分際で、なぜ兵士の服など着ている。鼻の骨を砕いてやったはずだが、顔の保護シールはもうないし、傷跡もない。そんなに、長い時間が経ったのか?
俺はそろそろと起き上がり、あたりを見回した。司令艇の医療室らしいが、壁際のアンドロイド兵は、俺が来いと合図しても無視している。なぜだ。
他のベッドには、バイオロイド兵たちが寝ている。奥のベッドには、金髪の青年。これが、本物の忠犬坊やなのか?
「おまえが、23号か」
俺が声をかけると、白い髪を裸の肩に散らした女は、不敵に俺を見返してくる。
「ようやく会えたわね。満足かしら」
どうやら俺が〝席を外している〟間に、勝手に話が進んだらしい。王子さまが白い魔女に助けられて、お姫さまを救出に来たという図だな。俺が悪役か。これでも昔は、傷つきやすい純情青年だったのに。
「シドさま、お水を」
ベリルに助けられ、水を飲んだ。ようやく、頭がはっきりしてくる。だが、喉や胸に違和感があった。ひきつれたような、しびれているような。
「あなたの体内に、わたしの細胞を入れたの。じきに馴染むわ。心臓も再生したし」
この化け物の細胞が、俺を生き返らせた!?
言われてみれば、全身がむずむず、ざわざわするような、妙な感覚がある。まるで、思春期に戻ったような。
では、やはり、あの虫の襲撃だ。あの時、兵たちもペトラも、体内に、こいつの細胞を入れられていたのだろう。そうでなくて、侍女が俺の脚にしがみついたりするものか。
「俺を、実験材料にしたな」
「それは、お互いさま。今はわたし、アイリスと呼ばれているの。あなたも、そう呼んで。この姿には、その名が似合うそうよ」
何がアイリスだ。人間のふりはしていても、怪物ではないか。女ですら、ない。
いや、待て。
俺も、怪物の仲間になるのか!? 心まで、変化していくのか!?
ペトラは腕利きのガンマンのように冷然と構え、事態を面白がる顔だ。こいつはもう、すっかり怪物らしい。
だが、ベリルは心配げな顔だ。ギプスのままだし、何かに怯えている。ということは、まだ怪物に乗っ取られていない。
ジュンは? 面白がるような、気の毒がるような顔だ。ただ、ベリルと違って、怯えてはいない。
「きみはどうなる」
と尋ねたら、幸福そうに微笑む。
「《エオス》に帰るよ。エディと一緒にね」
俺の胸がいくらか痛んだのは、嫉妬のせいか。あの青年が生きていたことで、そんなに満足そうな顔をするとは。
「あんたはアイリスと一緒に、《ゼラーナ》の基地に帰ることになる」
「化け物に、基地をくれてやるためか」
「その化け物が、欲しかったんでしょ? 望み通りになったじゃない。あんたは、アイリスの力を手に入れたんだよ」
「力だと……?」
「何か覚えていない? シドのものではない記憶が、浮かんでこない?」
何を言ってる。俺が、何を覚えているというんだ。
「空を飛んだでしょう。空から、ジュンを見たはずよ」
と白い女が言う。
「空から、何を見たって……」
俺は眩暈を感じた。この記憶は何だ。高い位置からの俯瞰。リュックを背負って雪の上を歩く、防寒服の少女。砂漠のオアシスで枯れ枝を集めて、火を焚く少女。
俺はそれを、はるか上空から見下ろしたことがある。空から降りてきた者を、交替で監視したのだ。そして、害はないと見極め、空の彼方へ引き上げる機体を見送った。俺はそれ以前から、鳥の姿で、大陸中を飛んでいた……
いや、違う。これは、23号の記憶だ。23号は、以前からジュンを見知っていた。その記憶が、俺の脳内に植え付けられた!?
「大地を走ったでしょう。四つ足で」
四つ足? そうだ。そんな夢を見ていた。俺は狼になり、山中を疾駆していた。仲間と協力して、大きな鹿を仕留めた。獲物にかぶりつく快感。甘い血の味。骨を砕く歯ごたえ。湯気の立つ臓物の匂い。獲物の苦痛は感じるが、それを上回る歓喜があった。
「俺は……」
おかしい。なぜ、狼に戻りたい、大地を走りたいなどと思うのだ。ただの夢ではないか。
夢ではないとしたら……これは、単なる洗脳にすぎない。
俺はシドだ。人間だ。
脳を乗っ取られてたまるか。わずかでも俺の意識がある限り、こいつらの好きにはさせない。
アイリスが、親切な医師のように言う。
「あなたの脳内で、わたしの神経細胞が、新たな回路を作りつつあるわ。もう一度眠って目覚めれば、だいぶわたしに近づいているはずよ」
神経細胞の新たな接続。励起される神経電流。固定される記憶。この星で暮らしてきた、アイリスの記憶。
そうだ。こうやって、多くの生命を取り込んできた。そのことを覚えている。自分の体感として。
人間たちが移植した動植物を食らい、一体となり、この星の上で増え広がってきたのだ。空から、新たな敵が降りてくるまでは。
その敵の親玉は、大柄な人間の男だった。兵士たちを指図して、無数の動物を狩らせていく。自分の分身も、そうでない動物も。
だから、虫の姿で彼らを襲った。殺すためというより、我々の細胞を植え付けるために。
俺の記憶に、アイリスの記憶が重なっている。明日になったら、俺は、シドの記憶を持つ化け物なのか?
ベッドから降りようとした俺は、よろめいて、ベリルに支えられた。骨折のために、ベリルは俺の体重を支えきれない。反対側を、ペトラに支えられた。
「どこへ行くの?」
と尋ねたのはジュン。
「部屋で寝る。ここはうるさい」
俺は女たちに左右から支えられ、通路へ出た。今ははっきりわかる。俺の体内で、何かが新芽のように伸びている。俺は、一秒毎に作り変えられていく。俺の感じ方が、浸食されていく。
もう、止めることはできない。あと何日かすれば、俺は、『シドだった記憶を利用するアイリス』になってしまうだろう。
輸血が効いたようで、目覚めた時は、だいぶ楽になっていた。枕元の時計表示を見たら、じき夜明けだ。
ジュンが片隅でアイリスと話し込んでいる隙に、そっと起き出し、医療室を離れた。
ジュンは、お母さんそっくりのアイリスに夢中だ。小さな女の子に戻ったようで、アイリスにまとわりついている。わずかな時間でも、甘えておけばいい。
ぼくは通路をたどり、シドの部屋を探した。この星を離れる前に、〝落とし前〟をつけておかなくては。
ジュンのあの大泣き、ただごとではない。
それに、背中の傷。
奴を、このまま放免するわけにはいかない。いくらアイリスの細胞が入ったとはいえ、まだ九割方はシドのはず。
遅まきながら、ぼくはようやく、男であることの本質がわかったと思う。
――好きな女のために戦って、何が悪い。
――俺の邪魔をする奴は、みんな殺してやる。
いざという時に、腹の底から湧いてくる、凶暴な衝動がそれだ。原始的だからこそ純粋で、強烈な陶酔を伴う。
ただ文明社会では、その衝動をストレートに出せない。法律や良識に押さえ込まれているうちに、男は野生を忘れてしまう。すると、何のために生きているのかも、わからなくなってしまう。
ぼくがそれを思い知ったのは、アイリスに付いて、この停泊地に乗り込んだ時だ。見張りの兵たちに、小動物や昆虫たちが攻撃をかけた。その騒ぎに、艇から新たな兵たちが飛び出してきた。ぼくは、奪った銃で彼らを撃った。アンドロイド兵は機能を停止していたから、バイオロイド兵ばかりだった。
慌てたせいだろう、装甲服も着ていない、生身の男たちだ。急所を外す余裕はなかった。向こうも、恐怖に駆られて撃ちまくってくる。
ぼくは血に酔ったような興奮状態のまま、彼らを次々になぎ倒した。生きた的を仕留めることが、勝ち続けるゲームのように気持ちよかった。アイリスの援護もあったが、気づいた時には、十数名の兵士を撃ち殺していたのだ。
あの時のぼくを、ジュンが見たら、血に飢えた殺人鬼と思ったのではないか。
事実、ぼくは殺戮に酔っていた。
いくらでも殺せる。もっと来い。
もし、あの勢いでジュンに会っていたら、その場で押し倒し、服を引き裂き、むしゃぶりついていたかもしれない。
本能の解放。
それが、あれほどの快感だとは。
だが、ジュンがアイリスにすがって泣いているうち、ぼくの血は冷め、いつもの分別が戻ってきた。
あれは危険だ。
快感だからこそ、普段は、封じておかなくてはならない。
癖になったら、それこそ、辺境の違法組織で生きるしかなくなってしまう。
普通の市民と重犯罪者の溝は、多分、そんなに深くないのだ。
ぼくはシドの個室にたどり着くと、中に声をかけた。
「起きていますか? エディ・フレイザーです」
入れという返事があったので、入った。広くはないが、茶と深緑でまとめた、趣味のいい一室だ。シドは新しい服を着て、大きな椅子に沈み込んでいる。奥にあるベッドだけは、不愉快な連想が湧くので、見ないようにした。
「何かね、坊や」
偉そうな態度に、ますます反感が湧く。

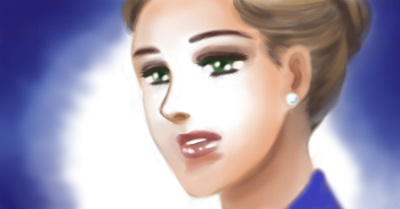
自由というのが、こんなに寂しい、心細いものだなんて、知らなかった。
わたしは、どこへ行けばいいの。
それを決められるほど、世界のことを知らないのに。
上陸艇の並ぶ草原には、大きな焚火が幾つも燃え上がっていた。たくさんの星が輝く紺碧の夜空に、濃い煙が立ち昇っていく。
死んだ兵士たちを、焼いているのだ。使える死体は、アイリスの細胞を植えるために運ばれていった。不要と判定された死体は積み上げられ、化学燃料をかけられて焼かれている。
わたし以外には、誰も立ち会わない葬儀。
わたしは内心でずっと、彼らの欲望をおぞましいと思っていた。できるものなら、全員死んでくれないかとも思っていた。
でも、こうなってみると、哀れなのはどちらだったか。
わたしとペトラには優しいジュンも、死んだバイオロイド兵のために、泣いたりしない。好きな青年が無事だったので、歓喜している。
それは彼女のために喜べるけれど、わたし自身は。
シドさまはもう、元のシドさまではない。元から遠い人だったけれど、もっと遠くなってしまった。
それでもなお、付いていこうとするならば、わたしも〝怪物の仲間〟になるしかない。アイリスの細胞を植え込まれたら、ちっぽけなわたしの心など、圧倒されて消え去ってしまうだろう。
できるなら、ジュンに付いていきたかったけれど、それはアイリスに禁じられた。わたしが今、《エオス》に保護されるのはまずいという。当局に、アイリスの存在を知られてはならないのだ。
市民社会に保護してほしければ、いったん辺境に出て、記憶を消す操作を受けてからにしろという。でも、そうしたら、今ものを考えているわたしとは、違うわたしになってしまうのでは!?
赤い炎の前で草地に座り込み、ぼんやり考えた。
いっそ、一人で、この星に残ったらどうだろう。町の廃墟で、静かに暮らせるかもしれない。野菜を育てて、魚を取って。
ああ、でも、アイリスの大部分は、この星に残留する。これまで通り、鳥や獣や昆虫の姿で。シドさまの艦隊に乗れる〝仲間〟は、ごく一部にすぎないから。ここにいたらいずれ、わたしもアイリス一族に取り込まれてしまうだろう。
そこへ、草を踏んで歩いてきた者がいた。すっかり戦闘服が馴染んだペトラ。炎に照らされた顔は、綺麗に回復している。
アイリスから、追加の細胞を注入してもらったのだという。わたしはまだ、骨折の痛みをあちこちに抱えて、ぎくしゃくしているのに。
「あなた、まだそれを着ているの? 寄越しなさい」
ペトラはわたしからエプロンを外すと、炎の中に放った。白い布は炎に食われ、煙になっていく。ポケットに入っていた潤滑クリームも、コンドームも。
「もう奴隷じゃないのよ。母艦に戻ったら、好きな服を着ることね」
「でも……」
「大丈夫。あなたまで、アイリスの苗床になる必要はないの。今のままでいられるように、わたしが守るから」
びっくりした。
あまりに驚いて、まじまじペトラを眺めてしまう。
ペトラが、わたしを守る!?
「アイリスは、基地の人員を全て、自分の仲間にするつもりよ。でも、わたしはまだ、奴隷だった自分のことを忘れていない。もう二度と、誰かの奴隷にはなりたくない。だから、そのうち、アイリスたちとは別れるわ」
辺境のどこかへ、一人で旅立つというのだ。そんなことが許されるのかと疑ったけれど、アイリスの了解は取ったという。
「アイリスの一族も、これからは、たくさんの亜種に分岐していくはず。わたしが離れることは、裏切りではなくて、繁栄のための分家なの。わたしは、自分の道を探してみる」
ペトラには、自由が喜びになっているのだ。炎に照らされて、髪も肌も赤銅色に輝いている。まるで、燃え立つ花のよう。
「強くなったのね……」
「それは、アイリスのおかげ。でも、わたしはアイリスのコピーじゃない。まだ、ペトラとしての記憶が強いの。わたしたち、先のない奴隷だったでしょ。だから、その気持ちがわかる者を同志にしたいの」
そして、じっとわたしを見る。
同志って、もしかして、わたしのこと!?
「でも、わたしには、何の力もないのよ。それより、アイリスの細胞をもらった兵たちの方が……」
「いいえ、彼らはしょせん、アイリスの一部として取り込まれるだけ」
男である限り、他人に負けない強さを求めて、細胞の追加を望むはずだからと。万能細胞が多ければ、それだけ元の人格の寄与は薄れるという。
「アイリスは人間じゃない。分身同士で精神が通じ合うから、本当の孤独も知らないし、絶望することもない。無限に増殖するアメーバだわ。でも、わたしはまだ人間だから、人間の仲間が欲しい。それも、男でない方がいい。男はやはり、女を餌食にする生き物だもの」
ペトラの意志ははっきりしていた。でも、わたしは後込みしてしまう。
「わたしでは、あなたの役に立てないわ……何の力もないんだもの」
「これから勉強できるわ。二人で一緒に。全員が、アイリス一色に染まらない方がいいの。それではいつか、集団で道を誤るかもしれない」
ペトラはもう、ずっと先まで考えている。その上で、わたしに来いと言っているのだ。
「順調な時は一人でいいけど、困った時には支えが要るわ。わたしの支えになってくれない?」
熱い手で手を引かれ、腰を抱かれた。わたしの骨折に障らない程度に優しく、でも明確な意志を込めて。
肌が触れ合い、甘い香りがする。ジュンもそうだったけれど、女の肌は柔らかで気持ちいい。バイオロイドに母親はいないけれど、どこかで母親の記憶というものが、遺伝子に組み込まれているのかも。
「さあ、わたしと来るとおっしゃい」
笑いを含んで、耳元でささやかれた。何だか、酔ったような気がする。わたしはもう、独りではない。これからは、ペトラに付いていけばいいのだ。

アイリスとの別れの時刻が迫っていた。この先、二度と会えないかもしれないのだから、いま、言っておかなくては。
「あのね、お願いがあるの。《ゼラーナ》だけでなく、他の違法組織も全て乗っ取って」
司令室でアイリスの側に座り、あたしは訴えた。逃げ場のないバイオロイドたちの苦しみを。
尽くす一方の女たちも辛いけれど、戦いに押し出される男の兵たちも辛い。現にアイリスの奇襲によって、この停泊地を守っていた百人近い兵が死んだ。アイリスの細胞を注入されて蘇る者はまだいいけれど、他の者は死に損だ。彼らの無念は、実験動物扱いされていたアイリスなら、よくわかるはず。
「違法組織を端から乗っ取って、無駄な殺し合いをやめさせて。バイオロイドたちを解放して。新たな奴隷は創らないで。できたら、ベリルのように、そのまま解放してやるのが一番いい」
アイリスは面白そうな顔をしている。
「わたしの意識が、この銀河を支配することになってもいいの?」
「それが望ましい状態だとは思わないけど、少なくとも、もっと邪悪な奴らに支配されるよりはいいよ。あなただったら、他の種族が生きる余地を、残しておいてくれるでしょ?」
すると、アイリスは不敵に微笑んだ。
「その方が望ましいと、判断したらね」
生きた戦闘兵器。
人類を超える新しい種族。
でも、共存はできるはずだ。ママは、人間社会に溶け込もうとした。戦闘力や寿命と引き換えにしてもいいくらい、人間社会の何かに焦がれていた。
人類には、可能性がある。
アイリスも、〝自分〟だけに頼らない方がいい。
アイリスの細胞を入れられても、シドやペトラのように、元の自分を色濃く残していたら、純粋アイリスとは違う感じ方、考え方をするだろう。
そういうことを訴えると、アイリスは白い腕を伸ばし、あたしの頭を撫でてくれた。
「大丈夫、わかっているから。人間の本で学んだわ。〝多様性こそが、生命の繁栄を約束する〟のだものね。わたしたちは、融和によって仲間を増やしていくわ。あなたも中央で生きて、〝繁殖〟しなさい」
苦笑してしまった。アイリスなりの、好意の示し方だ。
「いつか、あなたたちが人類と対立することになったら、できる限り仲裁するよ。その時までに、一生懸命仕事をして、仲間を増やしておく」
アイリスは微笑んだ。
「それでこそ、マリカが生きた意味があるというものだわ」
ママの命があたしにつながったように、アイリスとの間にも、何かの流れが通じた気がする。無限の連鎖。星が燃え尽き、爆発して、生成された元素が宇宙に撒かれる。それを原料にして、新しい命が誕生する。その大きな流れの中に、人類の文明が誕生した。いずれは、この宇宙の運命すら変えるかもしれない文明が。
「あのう、アイリスのこと、あたしの叔母さんだと思っていい?」
遠慮しながら尋ねた。宇宙規模の命の連鎖に比べたら、けちくさい願いのように思ったので。
でも、アイリスは快く認めてくれた。
「わたしも〝姪〟に会えて、よかったわ」
あたし、もしかして、宇宙で最強の叔母さんを持っているのかも。
夜明け前、ちょっとした事件が起きた。人が死んだ事件を、〝ちょっと〟と表現していいものならば。
いきなり銃声が響き、あたしは驚いて司令室から通路に出た。もう、艇内に敵はいないはずなのに。
アンドロイド兵たちも、事件が発生した場所へ駆けていく。兵たちの控え室の前で、一人のバイオロイド兵が頭を撃ち抜かれていた。あたりに、血と脳漿が飛び散っている。
撃ったのは、ペトラらしい。ハンドガンを手に、平然と死体を見下ろしている。その後ろで、ベリルがすくんでいる。
「どうしたの!?」
ペトラは確信犯の静けさで答えた。
「この男、わたしたちのどちらでもいいから、やらせろと言ったの。断ったのに、無理強いしようとするからよ」
でも、この男にも、アイリスの細胞が入っていたはず。互いに感応できるのに、なぜ殺し合いになるのだ。ペトラの怒りを感知した時点で、この男が引けばよかったではないか。
「面白いわね」
アイリスが現れ、実験結果を分析する科学者のように言う。
「多様性を認めると、こういう〝利害の衝突〟が起きる」
それからアンドロイド兵に命じた。
「医療室へ運んで、ここを掃除して」
同時に、兵の肩から飛んだリスがぐにゃりと変形して、男の頭部の穴に潜り込んだ。エディの心臓も、こうして再生されたらしい。
エディが撃たれたのが、頭でなくてよかった。外見はエディでも、中身はアイリスというのでは、悲しいもの。エディはこの世に、たった一人しかいないのだから。
「もう一度蘇生するから、問題ないわ。今度は、もっとわたしに近くなっているから、トラブルは起こさないでしょう。この話が他の仲間に広まれば、彼らも用心するはずよ」
ペトラはそれを聞くと、銃をホルスターに納めた。
「それなら結構」
もう、歴戦の闘士みたい。この調子でいくと、どこまで強くなるか、計り知れないものがある。
「処罰は……?」
まだ不安顔のベリルが、誰にともなく尋ねた。もしかして、ペトラは、ベリルに教えるために撃ったのか。ベリル自身はまだ、自分たちに、男の要求を拒絶する権利があるとは思っていないから。
「処罰なんか、ないよ」
あたしは断言した。あたし自身が恐怖と屈辱に泣いた後だから、はっきり言える。
「これから先、あなたたちに暴力を振るおうとする男がいたら、こうやって射殺して構わない。それが、女の権利というものだから」
ベリルは緑の目を見開いた。そこへちょうどエディが来合わせ、あたしの言葉を聞いて恐怖の色を浮かべたので、まずかったと反省した。エディを脅すつもりではなかったのだ。
「大丈夫、何でもないよ。ちょっとした行き違いがあっただけ」
と微笑んでみせた。男というものは、紳士であれば、女を恐れる必要はない。女はそういう男には、ちゃんと優しさで報いるのだから。
「でも、今度からは、いきなり射殺でなく、まず警告を与えるのが穏当だね」
とベリルたちに向かって付け加えた。偉そうな態度かもしれないが、今はまだあたしの方が〝この世の先輩〟だから。
「あれはつまり、あなたの細胞が入っても、元の男の意識や本能が、強く残っていたということでしょ」
とアイリスに確かめた。
「そういうことね。個体ごとに、わたしの細胞を植え込む量や、部位を変えているから」
アイリスの意識と、他人の意識の混合の割合によって、どんな『種の分化』が起こるか、実験中だという。これまでは動物相手の実験だったから、アイリスの意識が圧倒的だった。でも、人間相手では、相手の個性との格闘になるらしい。
「そうすると、これから先は、アイリスとしての統一がとれなくなるね」
「それでいいのよ。この先、どんな敵にぶつかってもいいよう、わたしたちは多様な変種に分岐しているべきなの。市民社会から見れば、〝怪物の増殖〟にすぎないでしょうけど」
あたしは人類と、アイリスの仲間が殺し合う未来は見たくない。中立的に言った。
「それなら、人類がこの銀河に広まったこと自体、〝生物学的な汚染〟かもしれないよ。いつか人類が、もっと高度な異星文明に〝駆除される〟可能性だってある」
アイリスには通じたが、エディは困惑したようだ。普通の家庭で育ったエディは、人類中心主義を疑わずにきたのだろう。
「それでは、わたしたちの旅立ちも祝福してもらえるわね。分岐の一枝として」
あたしは驚いて、迷彩柄の戦闘服のペトラと、彼女にすがりつくようなベリルを振り向いた。ベリルは瑠璃色のメイド服のままだが、エプロンはもうない。
「そういうことになったの?」
「ええ。しばらくアイリスの元で暮らして、それから独立するわ」
それなら、それでよかった。ペトラが短時間にこれだけ変貌したことを考えれば、二人の未来は明るい。
「もし、あたしで役に立つことがあったら、連絡してね。必要なら、助けに行くよ」
「ええ、ありがとう」
あたしたちが握手するのを、エディは何か、怖いものでも見るように見ていたけれど。
「ジュン、あなたはどうなの?」
ペトラに尋ねられて、あたしは戸惑った。
「え、何が?」
「アイリスの細胞をもらって、超人になるつもりはないの」
あ、それか。
確かに、そうしたら便利だろうな。怪我をしてもすぐ治るし、変身したり、仲間同士で遠隔感応したりできるんだから。たぶん、寿命も延びるだろう。分裂できることを考えたら、不老不死と言ってもいいかも。
でも、あたしはそういう能力が欲しいだろうか。
不思議なことに、否、である。
あれほど、強くなりたいと願っていたくせに。
「ほら、お腹一杯のところに、ご馳走出されても、もう食べられないでしょ。それと同じ。あたし、いま幸せだから、このままでいいんだ」
生きているエディ。これ以上の贈り物はない。
「いつか、その気になったら、中央を脱出して、あなたたちの仲間になりに行くかもしれないけど。今はまだいいよ」
アイリスは、わかっている顔で微笑んだ。
「よかったわね」
ベリルもペトラも、笑顔になっている。あたしは、ぽかんと突っ立っているエディに尋ねた。
「あんたはどう? 追加の細胞もらって、超人になりたい?」
するとエディは急いで首を振り、辞退すると言う。
「命が助かっただけで、十分に満足だから。できる限り、平凡な人生を送りたいよ」
嬉しかった。エディがあたしと一緒に、人間の世界に戻るという結末で。
わずかな雲がピンクと菫色に染まる頃、あたしとエディは元の戦闘服姿で、取り戻したリュックを抱え、朝露に濡れた草地に降り立った。遺体を焼いていた火は消え、痕跡には土がかけられている。いずれすっかり、草に埋もれてしまうだろう。
他の上陸艇はとうに離陸し、上空の戦闘艦の群れに戻っているから、地上に残っているのは司令艇と、あたしたちの上陸艇のみ。
あたしたちはアイリスたちと、別れの挨拶を交わした。
「きみを愛人にできなかったのが、心残りだ。野兎ちゃん」
しゃあしゃあとしたシドの挨拶には、笑ってしまった。見た目も態度も、元のシドと変わりない。
「もしかして、あんたの愛人暮らしも、悪くなかったかもね」
けれど、ぐいと引き寄せられて、まともにキスされてしまったのは、まずかった。横にいたエディが、瞬時に激怒したから。
「ジュンに触るな、この変質者!!」
みんなで引き離さなければ、乱闘になるところだった。エディが女たちの手で引き止められているうち、シドはさっさと司令艇に引き上げていく。
「落ち着いてよ。ただの冗談なんだから。だって、もうアイリスが混じってるんだから」
となだめたけれど、エディはしばらく肩で息をしていた。でも、エディも怒るんだとわかって、ちょっと安心したかな。人がいいだけでは、この先、困るもの。
お次は、戦闘服姿のベリルとペトラが、頬にキスしてくれた。驚いたことに、ベリルは髪をばっさり切って、軽快なボブにしている。これまでは規制があって、髪も自由に切れなかったそうだ。
「よく似合うよ。すてき。元気でね」
「ジュンさま、いえ、ジュンも元気で」
最後にアイリスが、あたしと抱擁を、エディとは握手を交わした。
「それじゃ、有性生殖に励んでね。せっかくパートナーを取り戻したのだから、もう横取りされないように」
それから裸の背中を見せて、司令艇の中に消えていく。
有性生殖の……パートナー?
残されたあたしたちは、顔を見合わせてから、苦笑で視線をそらせた。アイリスってば、人間の機微がわかっていない。エディはリナ・クレール艦長を忘れていないし、他の女性に目を向ける時が来ても、あたしを選ぶとは限らない。
それにしても、もし、あたしが子供を作るとしたら、エディの遺伝子はよさそうだけどなあ。
金色と薔薇色に輝く朝焼けの下、大型艇は圧縮空気を吹いて浮上した。一定の高度になってから、プラズマ推進に切り替える。
ぐんと速度を増した機体は、小さな輝点となって藍色の空に消えていく。
あたしとエディはそれを見送り、涼しい風の中に立ち尽くした。
《エオス》は明日、この星系に戻ってくる。アイリスたちの艦隊は、痕跡を残さず彼方に去っているだろう。あたしの背中の傷と、エディの胸の傷跡は、二人で協力すれば、何とか隠しおおせるだろう。世界が、アイリスの存在を知る時まで。
エディが咳払いして言った。
「ジュン、今のうち、これを飲んでほしいんだけど」
振り向くと、何か深刻な顔をしている。掌に載せて差し出してきたものは、ラミネートされたカプセル薬だ。
「痛み止め?」
背中の傷は手当てしてあるから、別に要らないんだけど。
「いや、その……」
エディはためらってから、視線を外したままで言う。
「アフターピルなんだ。これさえ飲んでおけば、もしもの悲劇は防げるから」
ピル? 悲劇?
数秒経ってから、やっとわかった。エディってば、余計な心配を。確かに、人に言えないようなあれこれはあったけど、その心配だけは必要ないのに。
だけど、そういうことはなかった、と言って、信じてもらえるのか。シドのあの態度では、無理があるかもしれない。
そもそもアフターピルなら、あたしも前から持っている。コンドームとセットで、バシムに渡されたものだ。そして、万が一の場合は、
『男に媚びろ、哀願しろ』
と教えられた。腕力で勝てない相手に襲われた時は、あきらめたふりをしてコンドームを差し出し、これをつけてくれるように頼めと。
『泣くふりでも、媚びる真似でも、何でもしろ。男が油断したら、急所を握り潰してでも、蹴り潰してでもいいから、逃げろ』
それでも逃げ切れなかったら、事後にアフターピルを飲めと。
幸いにして、これまで、そういう極限状況はなかった。今回もまあ、何とか無事だったし。
「それ、必要ないから」
と短く言ってみた。すると、エディは頑固に言い張る。
「ジュン、これを飲むだけでいいんだ。飲んでくれたら、今後一切、このことは口にしないから」
うわあ、やっぱり、思いきり誤解してる。この思い込みを正しておかないと、この先、一生、見当違いの同情を持たれてしまう。
(ぼくのせいだ、ぼくが守れなかったからだ)
だなんて、無駄な後悔をさせ続けてしまうかもしれないし。
仕方ない。
あたしは覚悟を決め、エディに言った。
「ついて来て」
《エオス》から乗ってきた上陸艇に入り、荷物を降ろした。艇内の医療棚から、消毒された手術用手袋を取り出す。他の男なら(医師は別として)、こんなこと絶対許さないけど、まあ、エディだからね。
まだ理解していないエディの右手に、薄い手袋をはめさせた。それから、自分のズボンを下に下ろす。エディはショックを受けた顔で後ずさり、壁に背中をぶつけてしまった。
「ジュン!!」
泣きそうな顔をするから、あたしは逆に安心できる。
「自分で調べていいよ。指を入れたら、わかるでしょ。指一本しか、通らないってこと。あんたの指だと、小指でもやっとかもね」
友達はそろそろ、処女膜の除去手術を受けて〝その日〟に備えるようになっているけれど、あたしはまだ、先の話だと思っていたから。
エディは巨人の手にはたかれたかのように、がばっと床に伏せた。あたしが止める暇もなく、土下座して叫ぶ。
「ごめん!! 悪かった!! もう二度と言わないから、ごめん!!」
どうやら、通じたらしい。
「納得した?」
「した!! しました!! ぼくの誤解です!! とんでもない間違いでした!!」
本当のところ、エディがもし、実際に確かめようとしたら……あたしは、エディの顔面に蹴りを入れていたかもしれない。
だって、そんなことは、あたしのプライバシーでしょ? シドとの間で何があろうがなかろうが、本当は、エディが口を出す筋合いではない。
「ところで、あたしから、一つ聞きたいんだけど」
ズボンを上げて、身なりを整えながら尋ねた。これは、《エオス》に戻る前に確かめておきたい。
「あのさ、エディは、もう懲りたよね?」
「え、何が?」
ぴっちりの手袋を苦労して外したエディは、涙目のまま、不思議そうに振り向いた。
「こんな目に遭ったの、《エオス》に乗ったせいだもの。三か月経ったら、《エオス》を降りるよね?」
エディは不思議なことを聞いたような顔をし、それから、にっこりした。
「そういう意味なら、懲りてはいないよ。たまには、事件にぶつかるのもいいかもしれない……生きてることの有り難さが、よくわかるから。親父さんが本採用にしてくれたら、ぼくはずっと《エオス》にいたい。きみの相棒になりたいから」
甘えてはいけないと思うのに、やはりほっとしてしまった。八割がた、エディが去っていくことを覚悟していたから。
「じゃあ、よろしく、相棒」
と右手を差し出したら、エディも微笑み、握手を交わしてくれた。大きくて、温かい手だ。この手がこれからも、あたしを支えてくれる。
「よろしく、先輩」
笑ってしまった。
「それはもう、いいってば」
ちょっとだけ、エディに甘えてもいいことにしよう。あたしももっと成長して、エディの役に立つ相棒になればいいんだから。
その晩、あたしたちは、本来の目的地である山の中腹の湖にいた。夜風は寒いほどに涼しく、空には満天の星。
上陸艇を湖岸の草地に停めておき、外で焚火をしてお湯を沸かし、持参した食料の残りや、艇内の保存食料を食べた。もう、この星で狩りをする気にはなれなかったから。
初日にあたしが殺した兎には、アイリスの細胞は入っていなかったと聞いたけれど(だったら簡単には殺されないわ、とアイリスは笑っていた)、もうこれ以上、この星の生き物を殺したくない。生き残った動物たちは、すぐにまた増えるだろうから、ここは残留したアイリスの仲間たちの天国になる。
焚火の炎に照らされながら、向き合って熱い紅茶を飲んだ。エディはあたしに、打ち明けることがあると言う。
「これまで、怖くて誰にも言えなかった。親父さんにも、ジェイクたちにも話してない。でも、きみにはもう、何も隠す必要がないと思うんだ」
まあ、既に大きな秘密を共有してしまったからね。
これからは、運命共同体。
「というか、きみには是非、聞いてもらいたい。今度、何か事件があったら、言えないまま死んでしまうかもしれないからね」
エディはそう前置きして、《トリスタン》でのことを語ってくれた。亡くなったリナ・クレール・ローゼンバッハ艦長から、軍を変革するための誘いを受けたこと。おそらくは、その決起計画のために、艦が爆破されたこと。そして、事件の調査委員会から、守秘義務を課されたこと。


わたしは、人類を甘く見てはいない。
個々の人間はひ弱だが、集団になった時の力は侮れない。彼らもまた、群体を作る種族なのだ。
おまけに、二百億以上の個体数があり、この銀河に広く散っている。
戦って勝てないとは思わないが、共存の方が理に適っている。いずれは、市民社会を手を結べるかもしれない。
「その時は、ジュンの父親の名声が役に立つというわけだな」
とシドが言う。精神感応でも通じるのだが、あえて声に出すのは、同じ司令室にいるベリルを仲間はずれにしないためだ。
「ええ。そのために、母親を思い出させる態度をとったの」
ジュンがわたしを慕う気持ちは、利用できる。
また、わたしの能力を恐れるエディには、繰り返し〝安心感〟を投射しておいた。シドに対する嫉妬も望ましい。ライバルがいれば、男は戦闘意欲をかきたてられる。
エディには、ジュンを守ってもらわなくては。もしも今後、彼が大きな負傷をすれば、わたしの細胞が活性化して命を救うはず。長い年月のうちには、彼も少しずつ進化していく。
「全て、計算ずくなのね」
隅の席で読書していたベリルが、反感の声で言う。
「人間の言葉で言えば、それが、友情を結ぶということよ」
シドも彼女に言う。
「我々との共存を当然だと思う、若い世代が育っていけばいいんだよ」
パイロット席で航法の勉強をしていたペトラが、ベリルに笑顔を向けた。
「生活が落ち着いたら、どこかの地球型惑星に降りて、海水浴に行きましょう。わたしたち、本物の海を知らないんだものね」
この娘たちは、好きに暮らしていい。どうせ、監視はつける。
他組織を吸収し、拡大し、いずれは〝連合〟とも手を結ぶか。それとも敵対するか。
もしかしたら、もう一人の姉妹である19号とも、どこかで会えるかもしれない。もしも彼女が、人間を畏れることを学んで、生き残っていれば。

ぼくの胸に残されたアイリスの細胞は、これまでのところ、何の悪さもしていない。《エオス》に戻ってから、ジュンと二人で何度もこっそり検査したが、異変はなかった。
『もし、何か変化があったら、すぐあたしに言うんだよ』
とジュンが言ってくれるので、心強い。ぼく一人だったら、うじうじ気に病んで、ノイローゼになっていたかもしれない。
ジュンの背中の傷は無惨なものだったが、あれこれ理由をつけて一週間ほど空手の稽古を避け、ぼくが毎日薬を塗っているうち(背中といえど、素肌を見せてくれるのは、大変な信頼だ!!)、綺麗に治ってきた。若さの回復力である。
共有する秘密のせいで、ぼくらは緊密な仲良しになった。男に生まれて損をした、と思っていた時期もあるが、今では、男に生まれたことが誇らしい。
ジュンはまったく、素晴らしい女の子だ。シドとの間に何があったにせよ、それは少しもジュンを損ねていないのだ。だったらもう、気に病む必要はない。
ただ、ぼくには一つ宿題があった。これを済ませないことには、ジュンの相棒になる資格はない。
それで、平穏な航行中のある日、先輩たちとラウンジで一緒になった時に、覚悟を決めて宣言した。
「あのう、聞いて下さい。ぼくは今後一切、違法ポルノを見ないことにしました。だから、鑑賞会には呼ばないで下さい。ジュンにわかる所で上映するのも、やめて下さい。決して、いい子ぶって言うのではありませんが、やはり、全ての女性に対して、言い訳できない罪だと思うので」
先輩たちは、唖然としたらしい。ぼくがいきなり、何を言い出したのかと。
「そりゃ、自慢できることじゃないのは、わかってるが」
「タルいだろ、合法ポルノは」
「俺たちが見るのをやめたところで、世間には、変わらず出回ってるわけだし」
予期できた反論である。そもそも、上映の主目的は、ジュンに対する『免疫療法』であったわけだし。
「先輩たちにまで、見るなとは言いません。個人的に見るのは、自由です」
本当は、個人的にでも拒絶するべきだと思うが、自分の好きな女性が被害に遭いでもしなければ、ものを考えないのが、男という生き物だ。
ぼくもまた、《タリス》でシドに嘲られた時、初めて、自分の卑劣を本当に自覚したのだと思う。アイリスがいなかったら、ジュンが強姦される場面が、違法ポルノとして、世界中に撒かれていたかもしれないのだ。
そんなことにならなくて、本当によかった。
だが、そういう目に遭った女性が、他にはたくさんいる。
自分の好きな女性を守りたいと思ったら、まず、世界中の女性や子供が守られる状況を作っておかなければならない。人間でも、バイオロイドでも。
「ただ、ぼくは、ジュンに対して恥ずかしいことをしたくないので。撮影に使われた女性にとっては、映画を作る男も、それを見る男も、等しく加害者だと思うんです」
ちょっと、きつい言い方だったかもしれない。もしも、目の前に傷ついている女性がいたら、先輩たちはきっと、助けようとするはずだ。
だが、間接的な加害まで意識しなければ、違法ポルノを根絶することはできない。ぼくはまず、この考えを、周囲に広めていかなくては。
「それに、ジュンももう、十分にわかっていますよ。男が下劣な生き物だってことは」
すると、エイジが言ってくれた。
「おまえの言う通りだな。俺も見習うことにしよう」
ルークもジェイクも、やれやれ、という感じで苦笑した。
「しょうがねえ。他の船の連中にも、言っておくよ。もう、新作を回してくれなくていいってな」
ジェイクがぼそりと、嬉しいことを言ってくれた。
「このくらいでないと、ジュンに付いて行くのは無理なのかもな」
というわけで、《エオス》からは(表面上だとしても)、違法ポルノが消えた。それをジュンに説明することはしなかったが、いずれ、雰囲気で伝わるだろう。
自分が前よりましな男になった、と思えるのは嬉しいことだ。それもこれも、ジュンという灯台が行く手を照らしてくれるから。
七月に入るとジュンの誕生日が来て、無事に十六歳になった。ぼくは特大のケーキを作り(ブランディ浸けの果物をたっぷり飾った、重量級チョコレートケーキ)、可愛い蝋燭を立てて、ジュンに吹き消してもらった。
大きな薔薇の花束も渡した。赤やピンクだと、何か深読みされるかもしれないので(ジュンは花言葉など気にしないだろうが、親父さんは警戒するだろう)、あえてオレンジ色の薔薇を選んで。
ジュンはとても喜んでくれ、
「エディの誕生日には、あたしがお祝いするからね」
と約束してくれた。絶対、その日まで生きていなくては。
そうこうするうち三か月が過ぎ、ぼくは正規の乗員として採用してもらうことができた。
「これで、ずっと一緒だね!」
とジュンが手を取って喜んでくれるのを、親父さんは、複雑な顔で眺めていた。ぼくにこれといった失点がなかったので、追い出す理由がなかったのだ、というのがバシムの解説である。
後はひたすら、ジュンの番犬、下僕を務めるだけだ。いや、本当は騎士と言いたいのだが、まだ、そこまで威張れたものではないと思うので。
「おーい、エディ、飲みに行くぞ!」
長い航行の後、《エオス》が母港に入港すると、先輩たちがぼくを誘ってくれた。それはいいのだが、首にがしっと腕を回され、
「さあ、今日こそ、優しいお姉さんの所へ行こうな」
と決めつけられるのは、まずい。誰も、そんなことは頼んでいないのに。
「おまえの話をしたら、是非とも相手をしたいって希望者が、何人もいるんだよ」
「有り難く、可愛いがってもらえ」
「誰かがオトナになるのを待ってたら、あと何年かかるかわからんだろう」
「それまで、おまえはおまえで、男の修業をしておけばいいんだよ」
先輩たちの親切心はわかるのだが、そんな話がジュンに聞こえたら大変だ。
「結構です、遠慮します」
逃げようとしても、エイジに襟首を捕まえられ、ずるずる引きずられてしまう。
「往生際が悪いぞ。女の方から、お呼びがかかってるんだ。行かなくて、どうする」
「駄目です、勘弁して下さい!!」
ぼくが壁の手すりに掴まって、じたばたしていると、凛然たる声が響いた。
「こらっ!! 嫌がる者に無理強いするな!!」
ジュンが腰に手を当て、勇ましく仁王立ちになっている。ぼくはエイジの手を振りほどき、ジュンの後ろに逃げ込んだ。
「飲みに行くなら、あんたたちだけで行けばいいでしょ! エディは真面目なんだから、変な場所に誘わないで!」
「別に、変な場所じゃねえよ」
「船乗りが溜まる、普通の店だよ」
先輩たちはぶつくさ言いながら、それでもジュンには逆らわず、居住区を出ていった。ジュンはぼくを振り返り、にっこりする。
「もう大丈夫。今度から、あたしが守ってあげるからね」
「ど、どうも」
純粋な好意が嬉しい。何か、話が逆な気がしないでもないけれど。
「ねえ、エディ、気にしなくていいんだよ。いい歳をして〝未経験〟なんて、男仲間では、笑われるのかもしれないけど」
ぼくは後ろへのけぞり、壁に背中をぶつけた。
ど、ど、どこからそんな話が。
いや、確かに、
『これまで、真剣に付き合った女性はいない』
とジュンに語った気はするが、それでも、学生時代に何度か、軍にいる間も多少、双方が納得ずくのアフェアはあったのに。ぼくは女性からは、安全で手頃な相手に見えるらしく、お誘いそのものはたくさんあるのだ。何か、美しく誤解されているのでは。
ジュンはやはり、聖母のように言う。
「あんたは、クレール艦長に操を立てているんだものね。偉いよ。あいつらの真似をして、遊び人になったりしなくていいんだから」
み、み、操!?
なぜ、どこから、そういう発想が!?
「やっぱりエディには、年上の、しっかりしたお姉さんが似合うよね。大丈夫だよ。真面目に暮らしていれば、いつかそのうち、相性のいいお姉さんと会えるから。その時は、天国のクレール艦長も、きっとわかってくれるでしょう」
返事のしようがない。ジュンはぼくの腕に、すんなりした腕を絡めて言う。
「さ、遊びに行こ。今度から、上陸休暇はあたしと過ごせばいいんだから」
とにかく、こうしてぼくは、生きる場所を見つけた。そして、困難ではあるが、誇りを持てる道を歩みだしたのである。