
レディランサー アイリス編3

植民惑星《タリス》。
ただし、現在の人口はゼロ。
ここに人間が住んでいたのは、数年前までだという。せっかく開発局が海を広げ、地球型の動植物を定着させたのに、移民たちは、わずかな年月で撤退してしまった。
元々、必要性の薄い、強引な開発計画であったらしい。
「確かに、位置的には不便ですよね」
ラウンジの大画面に映る青い惑星を見上げて、ぼくは言った。他にいくらでも便利で快適な惑星があるのに、わざわざ田舎星区に住む必要はないのだ。
地球ただ一つに、百億近い人間がぎゅう詰めになっていた時代とは違う。現在は、一つの植民惑星に、最大でも二億人程度なのだから。
「開発局の悪あがきなのさ。新規開発がなければ、開発局自体も縮小されるだろ。役人たち、自分の椅子がなくなるのは、嫌いだからな」
と縞シャツ愛好家のルークが言う。たぶん、微妙に異なるブルー系の縞シャツを、何十枚も持っている。口マメで、向き合う女性をいい気分にさせるのが、ルークの得意技だ。
「軍でも、ここらに一つ、核になる市民居住地が欲しかったらしい」
クルーの制服である、淡いラベンダー色の上下を着たジェイクが言う。彼は、制服があれば、私服の組み合わせを考えなくて済む、というタイプだ。
もっとも、精悍な長身だから、何を着てもかっこいい。金茶の髪と同じ色の無精髭も、男臭くていい風情だ。どこの寄港地でも、大抵、ガールフレンドが待っている。
「そうすれば予算が付いて、パトロール艦隊を増強できる。違法組織の侵入に対して、外壁を強化することになるわけだ。しかし、普通の市民は〝盾〟になんか、なりたくないからな」
もっともだ。どうせ暮らすなら、便利で安全な地球寄りの星区がいいに決まっている。
「といって、〝中央〟が縮小するのも困るがな。現在の境界線を守らないと、市民社会は、辺境に飲まれてしまう」
そう言ったのは、厨房から出てきたエイジだ。深緑のシャツに、制服のズボンという組み合わせ。だいたい、茶系統か緑系統の渋い服を好んでいる。それがまた似合っているから、渋好みの女性にもてる。


――迷彩柄の野戦服に、防水のリュック。護身用の銃と弾丸、エネルギーパック。ナイフや調理器具や医薬品など、最低限の装備を詰めて、身支度は完了した。素早い身支度は、軍で叩き込まれたことだ。
リュックを背負って格納庫に向かおうとしたら、白い開襟シャツを着たバシムに呼び止められた。
「エディ、これを持っていけ」
「薬なら、もう入れましたが……?」
渡された小袋を見て、ぎょっとした。コンドームとアフターピルの、避妊セットではないか。アフターピルは、避妊に失敗した時に、女性が使う予備薬だ。本来のホルモン環境を乱す劇薬なので、滅多に使うものではないと教わった。
「あの、まさか、そんな、ぼくは」
ぼくの頭の中の妄想が、他人には丸見えだったのだろうか。
しかし、バシムは悠然として言う。
「何も、それを使えと言っているわけではない。あくまでも、非常用の備えだ。いわば、男のたしなみだな」
「でも、そんなこと、絶対にありません。手も握っていないんですから。こんなもの、要るわけないです、絶対に」
「ほう。そういう可能性を、考えたこともないと?」
ぼくは、耳まで真っ赤になったと思う。
ジュンのあの、細い腰を抱いてみたい。
なめらかな頬に、手を添わせてみたい。
さくらんぼのような唇に、キスしてみたい。
しかし、そういう願望は、慎重に押し隠していた、つもりだ。せっかく、下っ端同士の連帯感が生まれてきたところなのだから。
「それなら、これから考えてみることだ。わたしは何しろ、学生のうちに、子持ちになってしまったのでね」
「えっ」
「学生時代の後半は、双子の片方を腹に抱えて、もう片方を背中にくくりつけて、試験勉強したものだ。結果的には、子供を授かったことは、素晴らしいことだったがね。人生の予定が、大きく狂ったのも事実だ。女が〝大丈夫〟と言う時は、絶対に信用してはいかん。父親になる覚悟があるなら、別だがな」
哲人のようなバシムに、そんな若い頃があったのかと驚いた。しかし、個人的な話をしてもらえたのは嬉しい。
今では、双子の息子さんたちは社会人。奥さんのルカイヤさんは、地元惑星で議員をしていて、ずっと別居結婚だという。
たまにしか会えない船乗りは、忙しい女性には、ちょうどいい夫であるらしい。学生のうちに、好きな男の子供を産んでおくというのは、ルカイヤさんの側の、周到な作戦であったわけだ。
「これは、もらっておきます。ありがとう」
と感謝して別れた。ジュンがぼくに、大丈夫だからと言ってくれるなんて、天地が逆さになっても、ありそうにないけれど。
「それじゃ、しっかりな」
「幽霊によろしく」
面白がる顔の先輩たちに見送られ、ぼくとジュンは上陸艇で《エオス》を離れた。青紫のオパールのような惑星は、すぐ眼下に広がっている。
大気圏に突入すると、艇は銀灰色の翼で滑空し、白い雲の層を抜けて、無人の大陸に降下していった。目的地は大陸の温帯地方、ほぼ真昼時である。
ぼくたちが無事に、大陸西岸の山脈地帯に着陸すると、《エオス》は衛星軌道から離れていった。この星系全体、探知ブイと警備衛星に守られているから、何か異変があれば、軍のパトロール艦隊が急行してくれる。近くを通りかかった民間船も、救援に来てくれる。
それに、《エオス》が従えてきた無人の護衛船二隻のうち、一隻は星系外縁に残される。たぶん、その船に助けを求めるようなことは、起きないと思うけれど。
ぼくたちは外気の確認をしてから(移民が去った後、目立つ変化は起きていないが、念のため)、上陸艇のエアロックを開けた。
水と緑の匂いがする、甘く香しい空気。
千五百メートル級の、なだらかな山地の中腹である。この着陸地点は、昔のキャンプ場の跡地だという。
ここから徒歩で山越えして(それも、ハイキングコースの跡だ)、反対側の中腹にある湖を目指すというのが、予定のコース。
ジュンが前に降ろされたという、砂漠や吹雪の山地に比べると、きわめて安楽なコースだ。それだけ、ぼくが頼りなく見えたのだろうか。軍でもサバイバル訓練は積んだから、どこに落とされても、最低限の装備さえあれば、生き延びられるつもりだが。
アンドロイド兵や医療カプセルを積んだ上陸艇は、ここに置いていく。途中で足をくじいたとか、風邪をひいて熱を出したとかいう程度のトラブルなら、この艇を呼べば十分だ。
「いい天気でよかった。雨だと、厄介だからね」
ジュンは自分のリュックを背負い、地図で方向を確認した。
空は青く晴れ、白い積雲を浮かべている。気候はちょうど、春から初夏に移るあたり。白い太陽が、広大な緑の山野を照らしている。
「じゃ、行こうか」
ジュンが先に立ち、何の気負いもない様子で、草の茂った尾根道を歩いていく。ぼくは五、六メートル後ろに付いた。このくらいが、ジュンに不安を与えない適度な距離だろう。
空では、大きな鳥が円を描いて上昇気流に乗り、地上では、木々の幹を素早いリスが走る。若葉を茂らせた桜の木には、赤い実がなっている。
草むらには白や黄色の花が咲き、野生化したハーブがあちこちに茂っていた。ディルやミント、バジルやレモンバーム。
「ジュン、ちょっと待ってくれる?」
ぼくは持参の袋を広げ、ハーブやさくらんぼなどを摘んでいった。ジュンも、採集に協力してくれる。
「エディ、いい匂いがするんだけど、これも食べられる?」
「ああ、それは、よもぎだよ。草餅なんかに使うんだ」
ぼくはハーブや野草に詳しい祖母から直伝されているので、わかるだけ答え、ジュンを感心させた。
「へえ、これも薬草なの。ヘンルーダかあ」
「タンポポは知ってたけど、ナズナも食べられるんだ」
「これが毒草なの? 綺麗だね、イチリンソウって」
そうして話しながら歩いていると、ハイキングそのものだった。日差しは強く、汗ばむほどだが、木陰をたどって歩けば、風が気持ちいい。こんな場所をジュンと二人で歩けるというだけで、天に感謝する気持ちになる。
――見ていてくれますか、艦長。ぼくはまだ、生きていていいんですよね。ぼくがいることで、ジュンが一度でも余計に笑ってくれるなら。
歩きやすい尾根を伝い、場所によっては薮をかき分け、岩の斜面をよじ登った。それでも大体は、昔のハイキングコースをたどっている。
たまに止まって水筒の水を飲み、方角を確かめた。いずれは川に降りて、水を補給しなくては。
夕方近くになって、前方の茂みから何かが飛び出した。
途端に白い光が走り、その動きを止める。運の悪い野兎が、ジュンの投げたナイフに仕留められたのだ。
ジュンはナイフを引き抜いてから、改めて野兎の喉をかき切り、血のしたたる哀れな生き物を、逆さにしてぼくに差し出す。
「はい、今夜のごはん。料理頼むね」
さすがの腕前。
しかし、即座にナイフが飛び出す用心深さは、いささか痛々しくもある。ぼくといる時は、もう少し気をゆるめてくれてもいいだろうに。
ぼくの顔を見てどう思ったのか、ジュンは生真面目に言う。
「可哀想だけど、あたしたちも食べなきゃね」
「うん、わかってる」
狩りをするのも、課題の一つだった。携帯食料も少しはあるが、それは悪天候や、不慮の事態に備えて取っておく方がいい。
「それじゃ、そろそろ野営の支度をしようか」
「そうだね。暗くなる前に、寝る場所を決めないと」
ぼくらは、木々の間に見え隠れしていた谷川に降りた。
大きな岩と玉砂利の岸にはさまれて、豊かな川が流れ下っている。
ジュンが枯れ枝を集めて火を焚く間、ぼくは持参の検査キットで、川の水質検査をした。開発局が責任を持っていた頃と違い、上流で崖が崩れて、有毒な重金属が流れ出しているという可能性もある。
大丈夫とわかってから、料理にかかった。
(ごめんよ。無駄にせず、綺麗に食べるから)
野兎に心の中で謝りつつ、皮を剥ぎ、内臓を取り出した。母に田舎の農場で鶏の解体を習ったし、父にサバイバルキャンプを強制された過去もあるから、野外での料理でも、特に困ることはない。
料理の腕のおかげで《エオス》に乗せてもらえたようなものだから、まさしく、『芸は身を助ける』わけだ。
山道で摘んだハーブや木の実を、兎の腹の中に詰め、表面に塩をすり込み、大きな木の葉にくるんで、熱くした石の間で土をかぶせ、蒸し焼きにした。
肉が焼き上がる頃には、空にたなびく雲は、見事な紫と茜色に染まっている。それが暗い青灰色に沈み、一番星が輝きだす。
さすがに、空気が冷えてきた。周囲に闇が忍び寄ると、ささやかなオレンジ色の炎が、この上なく頼もしいものになっていく。
「美味しい。こんな美味しい肉、初めて」
切り分けて木の枝に刺した肉を、ジュンが夢中で食べてくれたので、嬉しかった。
「外で食べると、何でも美味しいんだよね」
小鍋に内臓と野草を入れて煮込んだスープも、いい味である。日程に余裕があるので、早目に料理に取りかかれたのがよかった。
「何といっても、きみの腕前がすごかったよ」
「たまたま、目の前に飛び出してくれたからね」
ジュンは謙虚に言うが、たまたまなどではない。エイジやジェイクに仕込まれたせいもあるだろうが、元からの覚悟が違うのだ。賞金首の父親を持つ娘は、強くならなければ神経が保たないと、バシムが言っていた。
だったらせめて、ぼくといる時くらいは、少し心をゆるめてほしい。この五日の間に、どうか、僕に対する信頼が増しますように。
その晩はよく晴れて、星が美しかった。地上に人家の明かりがないので、夜空は怖いほど深い。
天の川を背景にして、白い流れ星が幾つも、鮮やかに落ちていった。宇宙で見る星はしんとして冷たいが、地上から大気の層を通して見上げると、柔らかくにじんで、優しくまたたく。
風情のある星空だと言うと、ジュンも同意してくれた。
「宇宙では、生命維持が最優先だもんね。ゆっくり星を見るのは、地上の方がいいね」
持参した紅茶のパックでお茶を淹れ、焚火の炎をはさんで、ジュンと話をした。
「すごいな、もう二度も行ったの?」
「うん。親父がね、ママに地球を見せたいって、結婚してすぐ、申請しておいたんだって。あたしが生まれた時にも、あたしのためにね」
人類の故郷である地球は、惑星全体が貴重な文化遺産として保護されていて、観光客の入星を厳重に制限している。普通は、申し込んでから、何年も待たされるのだ。親父さんの場合は、特例として、優先的に枠を回してもらえたのかもしれない。
「順番が回ってきたのは、あたしが五歳の時と、九歳の時。楽しかったな。お城にピラミッドに、万里の長城……島巡り……京都の桜も見たよ」
そのお母さんは、ジュンが十二歳の時に亡くなっている。映画では、英雄に助けられた美女は、その後もずっと、幸せに暮らせるはずだったのに。
その映画を撮ったチャン監督も、親父さんを狙う暗殺者に利用され、爆死したという。その話になると、さすがにジュンの声が湿る。
「遺族からは、責められたよ。賞金首が、のうのうと街を歩くなって。でも、親父に助けられた人たちが、反論してくれた。みんなのために戦う人を排斥したら、それは、自分たちの首を絞めるのと同じだって」
そうだ。今ならわかる。ぼくはクレール艦長に、積極的に協力するべきだった。
〝連合〟が殺しきれないくらいの速度で、同志を増やす。
それしか、方策はなかったのだ。みんなが震え上がって逃げてしまったら、世界は悪党の思うがままになる。
「ママはね、寿命だったの」
ジュンは揺れる炎を眺めながら、ぽつぽつと話す。
「わかっていたんだ。ママは、特殊なバクテリアとの共生体だったから。外皮を剥がしただけでは、まだ足りなかった」
外皮を、剥がす!?
そんな、壮絶な処置が必要だったとは……
映画では、もっと人間に近い姿で描かれていたから。
「そのバクテリアを除去しない限り、隔離施設から出られなかったんだ。別に、他人に感染するものじゃなかったんだけどね。法律上は、そうなる。でも、それをしたら、中央の技術では、そう長くは保たないだろうって……」
薬品治療だけでは足りなかった。ジュンのお母さんは、骨がもろくなって背丈が縮み、髪の毛が抜けて、皮膚が乾ききり、最後の数週間で、百歳の老人のようになっていったという。
「毎日、病院に寄るんだけど、あたし、学校帰りだから、お腹空いてるでしょ。ドーナツやケーキを買っていって、ママと一緒に食べるんだけど、それも最後にはもう、一口しか受け付けなくなっていてね。それでも、あたしが二人分食べるのを、嬉しそうに見てたよ。あたしが元気なのが、ママには一番嬉しいんだって」
ジュンは微笑んでいるが、ぼくには慰めの言葉もない。
せっかく違法組織から逃げてきても、改造された肉体のままでは、市民社会に受け入れてもらえなかったのだ。
だったらいっそ、辺境のどこかで、強健な怪物のまま、長生きしていた方が……とも言えない。ジュンのお母さんは、自分で『平凡な家庭の幸福』を選んだのだから。
「大変だったね」
ぼくにはそれしか言えないが、ジュンはにっこりする。
「もういいの、大丈夫。終わったことだから」
ぼくとしては、お母さんの最後の日々、せめて親父さんの両親が《キュテーラ》に来て、痛ましい母娘に付き添ってくれればよかった、と思うのだが。
親父さんは今なお、故郷の一族とは絶縁状態だという。あの穏やかな親父さんが、そうまでして、自分の思いを貫いたのか。
もしかして、親父さんも、雷に打たれたのだろうか。だから、そう言ったぼくを(少しは)信用してくれた?
ジュンはしんみりしたことに照れたのか、口調を変えて、明るく言った。
「この《タリス》が本当に幽霊惑星なら、あたしは、ママの幽霊に会いたいけどね。エディは誰か……」
言いかけて、口を押さえる。
「ごめん。何でもない」
気を遣ってもらったらしい。初対面の日からしたら、だいぶ優しい扱いになっている。
「《トリスタン》のことなら、普通に話してくれて、大丈夫だよ。《エオス》に拾ってもらってから、だいぶ気が紛れてるんだ。亡くなったみんなも、きっと許してくれると思う。ぼくがこうして、生きていることを」
するとジュンは、口先だけの慰めではない様子で言ってくれる。
「もちろん、生きててよかったんだよ。誰か一人でも助かって、あんたの仲間は喜んでるよ」
他人のことなら、ぼくだって、そう言うのだが。
でも、ジュンの慰めは嬉しかった。ジュンは、自分の気持ちに反することは、言わない子だから。
焚火を強くしてから、ブーツを脱いで、寝袋に入った。偵察虫を飛ばしてあるので、大型獣が来たら警告してくれる。焚火の火がどこかに飛んでも、警告してくれる。
ぼくらは焚火を挟んだ位置で、おやすみと言い合った。寝袋にくるまり、頭の部分の防虫ネットを降ろせば、快適に眠れる。
程よく疲れていたので、たちまち、深い眠りに引き込まれた。幽霊も出ず、狼の群れも現れなかった。
おかげで翌朝は、早く目覚めた。森はまだ暗いが、空の星は薄れている。空気はひんやり冷たく、草木は清浄な露を帯びて、平和そのものの朝。
焚火の向こうの寝袋は、空っぽだった。ジュンは起きて、火を焚き直してから、どこかへ行ったらしい。さすがは十代の若さ。
ぼくも起き出し、小鍋に水を入れて火にかけた。昨日の肉の残りと、これから新たに摘むクレソンで、簡単なスープを作ろう。昨日の夕方、川縁でクレソンの群落を見つけたのだ。
それから、顔を洗いに水辺に降りた。丸い大岩の群れに挟まれた川は、うっすらとした曙の光の底で、滔々と流れている。
水筒に水を補充してから、ふと考えた。躰を洗ってもいいのではないか。ジュンの側に寄った時に、汗臭い奴だと思われたくない。
あたりを見回してから、野戦服を脱いだ。下着は速乾性だから、洗ってもすぐ乾く。下着を岩に干してから、清冽な流れに身を沈めた。頭まで水に潜ってごしごしやり、昨日一日の汚れを落とす。
躰が水の冷たさに慣れたので、調子に乗って少し泳いだ。流れに逆らい、上流に向かうように泳いでも、たいして移動はできないのだが。
ふと岸を見て、ぎょっとする。
ジュンが、大岩に腰かけていた。服は着ているが、裸足の足に、靴下を履こうとしている。ブーツやタオルが、横に置いてあった。髪がまだ濡れているということは、彼女も水浴びしたのか。
危なかった。もう少し早かったら、裸のジュンと出くわしていたかも。そうしたら、打ち首ものだ。
それから、はっとして川に身を沈めた。もしや、今、背泳ぎの状態の時、ジュンに核心部分を見られたのでは。
「お、おはよう、早いね」
自然に挨拶したつもりが、声が上ずっている。ジュンはぼくの慌てぶりをどう見たのか、素っ気なく答えた。
「おはよう」
それから靴を履き、タオルを持って、すたすた行ってしまった。ぼくは顎まで水に浸かったまま、ため息をつく。
本当は、ジュンの水浴びを見られなくて、残念だった。想像するに、その姿は、小麦色の人魚だろう。可憐な胸はきっと、ぼくの掌にすっぽり収まるくらい……
いかん。
自分の顔を、ぴしゃりと叩いた。急いで引き返して、服を着る。まさか、水浴びを覗こうと企んだ、などと思われてはいないだろうな。
クレソンを摘んでから焚火に戻ると、ジュンは鍋に残り物を入れて、スープを作ってくれている。
「朝ごはん、こんなでいい? 適当だけど」
落ち着いたさまに、まずほっとした。
「十分だよ、ありがとう。これだけ、ちょっと加えるね」
クレソンを入れて味を整え、スープを完成させた。ジュンは近くの茂みから、木苺も摘んできている。ぼくはもう何年も、木苺なんて見ていなかった。懐かしい。サバイバルキャンプとしては、非常に贅沢な朝食だ。
「あのう、さっきはごめん。びっくりさせただろうね」
食後、貴重な紅茶を飲みながら、ぼくは恐る恐る切り出した。
「たまたま偶然、躰を洗ったついでに、ちょっと泳ぎたくなって」
「うん、偶然はわかってる」
ジュンは静かに言ってから、にっこりした。
「見ちゃった、エディのお尻」
「えっ」
ぼくが狼狽すると、けらけらと笑う。
「大丈夫、水面下で、ちらりと見えただけだから。エディって全身、白いね。日焼けしないタイプなんだ」
快活に言われて、ほっとした。どうやら本当に、痴漢の疑いは持たれずに済んだらしい。ジュンが晴れなら、ぼくも晴れなのだ。
食事を終えると、手分けして鍋や食器を洗い、火の始末をした。荷物をまとめ、出発の準備をした時、ジュンが言う。
「せっかくだから、もう一回、木苺を摘んでこようかな。この先にまだ、あるかどうかわからないし」
それがいい、とぼくも認めた。
「じゃ、ぼくはクレソンを摘んで来るよ。すぐ戻るから」
そして荷物を置いたまま、やや下流の水辺に降りて、クレソンを採集してきた。ついでに、目についたハーブも摘んで、水を打って小袋に入れておく。
あとは何か、獲物を仕留められれば完璧だ。猪か鹿を捌くとしたら、大仕事になるが。
鼻歌混じりに元の川原に戻ると、ぼくのリュックだけが残っていて、ジュンの荷物がない。
妙だな、とあたりを見回した。でも、必要にかられて、リュックを持ったまま、用を足しているのかもしれない。とすれば、探してはまずい。待つことにしよう。
日は高く昇りかけ、空は青く晴れ渡っている。木々の梢にちらと見えたのは、猿だろうか。蝶や蜜蜂も飛ぶ。まさに、この世の楽園。
そのうち、不安が湧いてきた。遅すぎる。ジュンはもしや、足でもくじいて、動けなくなっているのでは。負けず嫌いだから、ぼくに助けを求められないのかも。
「ジュン? 今どこ?」
手首の通話端末で、声をかけた。上空の通信衛星が生きているから、この惑星上、どこでも通じるはず。やはりすぐに、元気な返答がある。
「エディ、悪いけど、ここからは別行動にさせてもらう」
ぼくはがん、と頭を殴られた気がした。
なぜ、どうして。
まさか、リュックの内ポケットに隠しておいた避妊セットを、見られたわけではないだろう。
「待って、ジュン、一人歩きは危ない。さっきのは本当に、偶然なんだ。そもそも、きみが水浴びしてるのも知らなかったし……」
しかし、通話画面の中のジュンは、くすくす笑っている。
「別にエディは、何も悪くないよ。ただ、競争させてもらおうと思っただけだから」
「競争?」
「そう。どっちが先に湖に着くか、勝負」
「でも、これは、二人で協力する訓練では……」
「こんな楽なルートで、協力もへったくれもないでしょ。あんたはあんたで、山越えして。あたしはあたしで、勝手に行くから」
そんな、冷たいことを。さっきまでは、あんなに機嫌よく……
いや。あれは、ぼくを油断させるための演技だ。
「あたしが勝ったら、あたしを先輩として立ててもらう。今後、偉そうな顔はしないでもらうからね。それじゃ」
通話は切れた。向こうの位置情報も消える。ジュンが、自分の端末の電源を切ったのだ。
しばし、呆然としてしまった。
偉そうな顔って、何のことだ。卑屈と言われるなら、まだわかるが。
そもそも、ジュンとは下っ端同志、仲良くなれたと思っていた。あれは、ぼくの勝手な思い込みで、本当は嫌われていたのか?
真っ暗な穴に落ち込みそうだったが、とにかく、無人惑星上で別行動はまずい。険しい山ではないが、崖から落ちて気絶するとか、熊に出くわすとかいう危険はある。せめて、ジュンの姿を視界に入れる位置までは近づかないと。
どうせ、山越えには、このハイキングコース周辺しかないのだ。急げば、追いつける。ぼくはポケットから偵察虫を出し、
「人間を発見しろ」
と命じて飛ばした。ジュンなら虫を撃ち落とすかもしれないので、残りの虫は温存しておこう。
尾根道を急ぎ足で昇り、ジュンが電源を切った位置に到達した。もちろん、姿はない。ずっと先に進んでいるに違いない。
ぼくは額の汗をぬぐい、早足で山道を登っていった。どうして、うまくいかないのだろう。ぼくはジュンに、ぼくを頼ってほしいだけなのに。

「何という、可愛い小兎かね」
固定式の椅子に深く腰かけて、わたしは含み笑いをしてしまう。
周囲の兵たちは独り言と判断して、何も言わない。元々、バイオロイドは口数が少ないのだ。我々人間が、そのように躾けている。
地上基地として使っている、大型上陸艇の司令室だった。偵察鳥が送信してきた映像を、手元の画面で鑑賞したところだ。
早朝の川で水遊びをする、短い黒髪の乙女。
人間に飼育される、ひ弱な兎ではなく、野山で跳ねる野生の兎だ。引き締まった肢体には、一グラムの贅肉もない。
若い二つのふくらみに、細い腰回り。
わたしにはロリータ趣味はないと思っていたが、熟れた女にはない魅力があるのは確かだ。手足に青痣の名残りがあるのは、格闘技の稽古のためだろう。報道からすると、たいした闘士らしいから。
是非とも、この娘が欲しい。
こんな所で出会うとは、やはり縁があるのだ、わが《ゼラーナ》とは。
我々はこの《タリス》に四十機ほどの上陸艇を降ろし、数千のサイボーグ鳥を飛ばして、23号の捜索をしていた。
十五隻の戦闘艦隊は、この星系内の数箇所に分散して、待機している。
何年もの時間をかけて、ここまでの経路に存在する当局の探知ブイや中継ブイを、こちらの用意した偽物にすり替えたのだ。そうすれば、軍にも開発局にも、我々の動きを知られずに済む。
二十年前の、一連の事件が始まりだった。わが《ゼラーナ》の二箇所の研究施設から、計三体の実験体が脱走したのだ。職員を殺し、他の実験体まで一緒に吹き飛ばして。
同型の遺伝子セットから培養した13号、19号、23号。
それぞれ違う処置を施したので、成長後の形態や能力は異なるが、同じ土台から出発したという意味では、姉妹といえる。
この不祥事は皮肉なことに、実験の成功のためだった。何十年もの人体実験の結果、ようやく、知能が高く、攻撃力の強い完成品に到達したからだ。
だが、そうなると、反逆の能力も持ってしまう。
当時の統率者は、ただちに艦隊を派遣して追わせたが、三体とも逃がしてしまった。
そのうち、13号の運命だけはわかっている。彼女は中央に亡命し、自ら望んで高度な戦闘能力を捨て、普通の市民に混じって暮らし、数年前に病院で死んだ。一人の娘を残して。

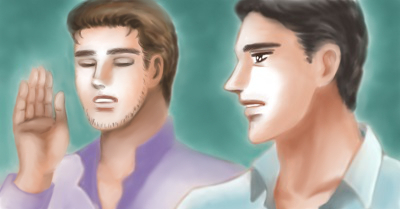
黒髪の渋い中年男は、苛々とラウンジを歩き回っていた。コーヒーを飲んでも、ニュース番組を見ても、少しも落ち着かないようなのだ。
そこまで心配なら、《タリス》に降ろすのは、エディだけにしておけばよかったのに。
公平ぶって、ジュンにまで、サバイバル訓練を課すことはなかったのだ。あいつはもう二度、苛酷な訓練を乗り越えているのだから。
俺たちは、あえて知らん顔していた。親父さんも少し、娘離れすればいいのだ。ジュンとエディなら、似合いのカップルではないか。強気と弱気、足して二で割ればちょうどいい。
もっとも、エディの奴、俺たちと対決した時は、弱気どころではなかった。やはり男は、女がからむと度胸が出る。
「あー、ジェイク」
ついに、哀れな父親は俺の所へやってきた。
「今回のサバイバル訓練、なぜあのコースなのかね。砂漠でもなし、高山でも密林でもない」
「親父さん、エディの根性がまだわからないのに、あまり危険なコースへは送れませんよ」
と答えた。
「あいつは屋内では有能ですが、樹上から蛇が降ってきたら、卒倒するかもしれない。軍のサバイバル訓練なんて、生ぬるいですからね。奴がジュンの足手まといになったら、困るでしょう」
ジュンの訓練担当は俺たち三人だから、親父さんも、俺たちの決定には滅多に口を出さない。
軍の訓練が甘いのも、本当だ。この現代、本当に苛酷な訓練など課したら、新兵は全員逃げてしまう。俺のように、必死で軍にしがみつく者など、滅多にいない。

――俺の場合は、父親が犯罪に走ったからだ。
司法局員という立場にありながら、懸賞金のかかった政治家を暗殺しようとして失敗し、辺境に逃亡した。
残された母親もまた、阿呆と釣り合う、見栄張り馬鹿女。
その屈辱を晴らすために、俺はエリート街道を目指した。親が自慢できないなら、自分を誇れるようになるしかない。
だが、それもまた、虚しい努力だった。
現在の軍には、市民社会を防衛する意志もなければ、能力もない。
本気で治安を守るつもりなら、〝連合〟と正面対決しなければならないのに、その現状を認めることさえしない。
市民の大多数が、表面上の平和に馴れてしまっているからだ。辺境の違法組織など、半端なはぐれ者の集まりくらいに思っている。
自分たちが、彼らの管理する牧場の羊だという苦い現実は、最後の最後まで、見ないようにするだろう。
その点、親父さんはわかっている。一市民でありながら、自ら戦う手本を示し、市民社会への呼びかけを続けているのだ。
この現実に目覚めよ、と。
娘を溺愛するという弱点くらい、あってもいい。
その娘がまた、困った頑固娘だが……
「それに、ジュンにとっては、年の近い相手と協力するのは、いい経験ですよ。今までは、俺たちから一方的にしごかれるだけでしたからね」
と説得を続けた。
「心配ないですよ。何かあれば、ルークが三十分で駆け付けますし」
星系外縁に残したレンタル船には、ルークがいる。初回は俺が、二度目はエイジが、《タリス》を見張りながら、こっそり待機していた。過保護親父が、ジュン一人を無人星系に残していくなど、有り得ない。
もちろん、ジュン本人には、陰の見張りのことは教えていない。知ったら気が抜け、甘えが出る。
「いや、わかった。ちょっと聞いてみただけだ。気にしないでくれ」
過保護親父は、しょぼくれた背中を見せて立ち去った。娘を持つ父親というのは、報われない永遠の片思いをしているようなものだ。俺にはまだ子供どころか、決まった女もいないから、他人事だが。
しかし、エディはいい拾い物だった。一度どん底に落ち、そこで何かを悟ったのだ。《トリスタン》の事件がなければ、きっと今でも、呑気なお坊ちゃん軍人のままだったろう。
(せっかく送り出してやったんだから、何とかしろよ)
と俺たちは内心、エディに呼び掛けている。
もし、ジュンが間違って妊娠、などということになったら(バシムが、エディに避妊セットを持たせたというが、そんなもの、頭に血が昇った時には、思い出しもしないだろう)、親父さんは卒倒するかもしれないが、願ってもない間違いではないか。
エディなら、生涯、ジュンのいい番犬になるだろう。
俺だって内心、少しは苦いものを感じているが……それは、妹を奪われる兄の気分だからだ。ほとんど、男の子と見分けがつかないような妹だが。
エディが息を切らせて坂道を上がっていく間、あたしは、そっと下流方向に離れていた。川向こうに渡ってから、ゆっくり山を登っていけばいい。勝負の勝ち負けではなく、エディから離れることが目的なのだ。
――一緒にいたら、甘えてしまうだけだもの。
エディは優秀すぎる。そして、あたしに親切すぎる。
困るのは、その優しさなのだ。
『ああ、重いものはぼくに任せて』
『夕食はハンバーグにしようか、それともロールキャベツ?』
『この映画はお勧めだよ。お茶を淹れるから、一緒に見ない? バナナケーキもあるよ』
一緒にいると心地よくて、つい、ぼうっとしてしまう。自分が溶けてしまって、輪郭がなくなりそう。
あえて闘争心をかき立てないと、あたしは、一人で立てなくなってしまう。
誰かに甘えるなんて、恐ろしいことだ。だって、いつまで一緒にいられるか、何の保証もないんだもの。
そもそも、エディの中には、亡くなった女性が住んでいる。
リナ・クレール・ローゼンバッハ大佐。
エディの部屋に予備の寝具を届けた時、荷物に紛れていた写真を見てしまった。栗色の髪をショートカットにした、理知的な美女。毅然として、しかも温かみのある微笑み。
気になって、軍の記録やマスコミの記事を調べてしまった。まさに、軍人の手本のような人。《トリスタン》の乗員たちの写真もあったけれど、それは何かの行事の時の集合写真で、大佐の写真だけ別になっているんだもの。
もしかして、エディは毎日、写真に語りかけているのではないか。親父が部屋でこっそり、ママに話しかけているように。
それを考えると、あたしは力が抜ける。今の親父にとって、あたしが一番だというのはわかっているけれど、それは、一位が退場したための『繰り上げ当選』にすぎない。
どんな気分だろう。男の人に、最優先で愛される、というのは。
その人には、どんなわがままを言っても許され、可愛いと思ってもらえるのだろうか。
うらやましいけれど、でも、だめ。
あたしには、することがある。
親父の首に懸賞金が懸かっている限り、うっとり、ほんわかなどしていられない。エディがあたしに腹を立て、冷たくなってくれるくらいの方がいいのだから。
あたしは川幅の狭い箇所を選び、岩から岩へ飛んで、向こう岸へ渡った。尾根の向こうに出れば、エディの飛ばした探査虫にも発見されないだろう。
ところが、川岸の斜面を登るうち、虫がわんわん飛び回っている場所にさしかかった。深い草むらの中に、何頭もの動物の死体が散っている。
鹿、山羊、猪、狼、熊。
全て、レーザーで胴体を撃ち抜かれていた。腐り方からして、精々、ここ一週間以内の出来事。水場に降りる途中で狙われた、あるいは、死骸に引き寄せられたところを狙われた、という感じ。
ただ、なぜなのか、即死させてはいない。頭部と心臓部は、避けて撃っている。
苦しませるために、あえて急所を外した?
昔の移民は、もう一人も残っていない。ここへ立ち寄った船も、最近は《エオス》だけのはず。
非常にまずい。エディと合流しよう。軍に通報する方がいい。
その時、空から黒い影が舞い降りた。あたしの横を、矢のようにかすめ飛ぶ。
猛禽型の偵察鳥とわかった時には、顔をかばった手の甲に、何本もの微細な針が突き刺さっていた。抜こうとするとポキポキ折れて、針が体内に残ってしまう。たぶん、溶解性の毒針。
猛毒ではありませんように、との願いも空しく、急速な麻痺がきた。あたしは草地に膝をつき、前にのめる。支えようとした手に力が入らず、頭が地面にぶつかった。視野が暗くなる。
――あたし、まさか、こんなところで死ぬの。
だったら、あたしの方こそ、化けて出てやるんだから。
ぼくは疲れはて、リュックを背負ったまま、涼しい風の通る尾根道に座り込んでいた。
どうやら、偵察虫を飛ばす方向が間違っていたらしい。有機素材でできた虫は、時間が経てば、鳥に食われたり、蜘蛛の巣にかかったりして、失われていく。頭上の衛星からも、森の中に隠れた人間を発見するのは難しい。
ぼくには全然、女心がわかっていないのだろう。ぼくを励ましてくれる先輩たちだって、男だからな。誰か、女性の助言者がいればよかったのに。
その時、さわさわいう葉擦れに混じって、低いささやきが聞こえた。
――逃げなさい。
――逃げて、狙われている。
はっとして頭を上げ、周囲を見渡した。明るい陽光に、きらきら輝く緑。杉や檜、桜や楓、樫や椿の混合林。斜面の下には、さらさらと流れる川。
今のは幻聴か?
まさか、真っ昼間から幽霊なんて。
怪しんでいるうち、頭上から何かが急降下してきた。反射的に懐の銃を抜き、レーザーモードで撃つ。どさりと落ちてきたのは、褐色の羽を持つ猛禽だ。開いた口の中に、銀色の砲口がのぞいている。
警備用のサイボーグ鳥だ。
こいつ、ぼくを撃つつもりだったのか!?
次の鳥が、高い梢から急降下してきた。明らかに害意がある。走りながら、身をひねって撃ち落とした。
ぼくらの上陸艇には、サイボーグ鳥など積んでいない。移民たちが残したものでもない。市民社会では、サイボーグ鳥の飼育に厳しい規制があるからだ。
こんな時に、ジュンと離れ離れとは。
また別の鳥が来たので、林の中へ逃げた。手首の端末から、艇に緊急信号を送る。これは上空の衛星にもキャッチされ、軍に通報されるはず。
だが、もし、中継ブイが破壊されていたら。あるいは、パトロール艦の到着までに、手遅れの事態になったら。
川原に出る手前で、愕然とした。川向こうの尾根の更に向こうに、見知らぬ小型艇が降下していく。
ジュンはあそこだ、と悟った。
あの艇は、ジュンを収容するために舞い降りたのだ。
ぼくは砂利の上にリュックと水筒を捨て、予備の弾倉だけリュックのポケットから抜き取ると、岩を踏んで川を飛び越えた。銃を弾丸モードに切り替え、大型獣のために持ってきた炸裂弾を使うことにする。
しつこい鳥がまた襲ってきたが、それを撃ち落として走った。鳥程度のものは、この弾丸に遭えば、微塵に飛び散る。
斜面を駆け上がり、尾根の上に出た。若葉の茂った木々を透かして、谷間の平地に着陸している小型艇を見つけ、そちらに走る。
艇の周囲に、灰緑色の制服を着た兵士たちが散っていた。六体か七体。背丈の揃った屈強な体格、灰色の皮膚、黒いゴーグル。心を持たないアンドロイド兵だ。
中の一体が、ぐったりしたジュンを抱いて運んでいる。他の兵が、ジュンのリュックや水筒を下げている。
目を閉じて顔を仰向け、だらりと手を落としたジュンを見た瞬間、かっと脳が煮え立った。普段はぐじぐじ悩む性格のくせに、自分にあれだけの兵を倒せるかという、最低限の計算すらしなかったのは、呆れたものである。
ぼくは撃ちながら、木々の茂った斜面をじぐざぐに駆け下りた。手前にいた兵が、胴体を大きく吹き飛ばされて倒れる。銃弾の破壊力は十分だ。
ジュンを抱いた兵は、他の兵にかばわれて、艇へと向かう。他の兵は散開し、木や岩の陰から撃ってくる。
ぼくの後ろで、細い木が幹を砕かれ、絡んだ蔦を引きずって倒れた。怖いと思うゆとりすら、ない。連射で、立ち木ごと兵を吹き飛ばし、回り込んで艇を目指す。
次に立ち塞がった兵を吹き飛ばした後、足が木の根にひっかかり、躰が前へ泳いだ。その途端、ドンという衝撃を受ける。
何が起きたか、わからない。
ただ、取り返しのつかない凶事と感じた。
そのまま前へ倒れ込み、木の枝で顔を切ったと感じたのが最後で、すぐに、全てが闇に包まれた。

兵たちは、意識のない少女だけを連れて、上陸艇で飛び去った。金髪の青年は、斜面の草むらに放置されたまま。
死んだ、とみなされたのだ。心臓直撃では、無理もない。
わたしは迷ったが、ほんの一瞬のことだった。どうせもう、このまま隠れ続けるのは無理だ。追い詰められて核兵器で焼かれるか、あるいは、毒ガスで根絶やしにされるか。
わたしは飛んだ。木の枝から、小鳥の集団として。
そして、動かない青年の背中や、その周辺に舞い降りた。幸いなことに、もう敵の偵察鳥はいない。
小鳥の一羽が変形し、青年の傷口に潜り込んだ。それでは足りないとわかり、もう一羽が、やはり変形して潜り込む。
心臓と主要な血管を修復し、脳への血流を再開させるのだ。失われた骨と筋肉、肺や皮膚の再生はその後。幾度も動物たちで実験してきたことだから、手順は覚えている。
青年の肉体と一体化するのは、膨大な〝わたし〟のごく一部。
この大陸中に散った、何十万もの小鳥やリス、猿や山猫たちが、みな、わたしの精神と万能細胞を受け継いでいる。
〝わたし〟のネットワークが、既にこの星を覆っているのだ。
そこへ、うかうか降りてきた者たちこそ、袋のネズミ。
〝わたし〟だけでも戦えるが、せっかくだから、この青年も利用しよう。
この星から去った移民たちは、超空間航行ができる船を残してくれなかったのだ。自力で小型船を組み上げても、隣の星系まで一万年かかるようでは、意味がない。
わたしが自由を得るためには、人間の造った船が必要なのだ。それも、できれば、違法組織の技術が詰まった新鋭艦が。

飛行する機体の中で、目が覚めた。
静かな飛行だが、それでも、飛んでいることはわかる。
横の窓から、外の青空と、ホイップクリームを落としたような白雲の群れが見えた。上昇ではない。水平飛行だ。
(あたし、どうしたんだっけ)
しばらくぼんやりしてから、座席に、シートベルトで固定されていることを理解した。ベルトはロックされていて、外れない。
おまけに、両手首に、幅広い手錠がかけられている。内側が柔らかい素材なので、痛くはないが、左右の手首が十センチしか離れない。もちろん、左手首にあった通話端末は、取り上げられている。
あたしの座席は、何列かある乗客席の一番前だった。二メートルほど前方の、二つ並んだ操縦席には、誰かいる。背もたれが高いから、肘しか見えない。
咳払いして、喉の具合を試してから、あたしは吠えた。
「あんたたち、どこの誰!? ふざけた真似をすると、ただじゃおかないよ!!」
負け犬の遠吠えだとしても、黙って屠殺される趣味はない。
「お静かに、お嬢さん。貴女に危害は加えません」
片方の兵が、振り向いて言った。感情のない灰色の顔と、平板な合成音声で、アンドロイドとわかる。やはり、どこかの違法組織だ。
「これが、危害じゃないっての!? あんたたちの主人は、どこ!?」
すると、機内の通話システムから声が流れた。
「元気がいいな、お嬢さん」
深い響きを持つ低音で、自分の優位を楽しむ気配があった。こんな時でなかったら、セクシーな声だと思うところだ。監視モニターを通じて、あたしの様子を見ているのだろう。
「我々は、違法組織《ゼラーナ》だ。まあ、〝違法〟と呼ぶのは市民の側の思い上がりで、我々としては、独立国家のつもりだが」
がんと殴られた気がした。
「《ゼラーナ》だって……?」
それは、ママが逃げてきた組織ではないか。あたしの意識の中では、とうに完結した昔話である。
違法組織から脱走してきた母は、《エオス》で輸送船稼業を始めたばかりの父と仲間たちに出会い、救われた。市民社会に加わって、幸福な結婚生活を送り、そして死んだ。早すぎる死ではあったけれど、母の物語は幕を閉じた……はずだ。
反射的に、防衛本能で訴えた。
「あたしは実験材料じゃない!! ママの遺伝子は、もらってないんだから!!」
「わかっている。連邦は、実験体の繁殖を認めないからな。しかし、きみが13号の娘であることは、世界中が知っている。わたしにとっては、価値ある獲物というわけだ」
恐怖で身内が冷たくなった。こいつ、あたしをどうするつもり。
怒りを鎧にして、内心の怯えを隠したつもりだけれど、男は見抜いたらしい。不気味に優しげな声で言う。
「心配しなくていい。きみは若くて、可愛いからね。洗脳したり、切り刻んだりなどしないよ。そんな勿体ないことは、とてもできない」
鳥肌が立った。別の意味で怖い。それにまた、本筋の懸念もある。
「あたしを人質にして、親父を捕まえるつもりだな。懸賞金が目当てだろ」
あたしのせいで、親父が殺されたりしたら、あたしだって、生きていられない。
「いいや、金には困っていない。今回、きみの父上に用はないよ。ここへ来たのは、昔、うちの組織を脱走した実験体を探してのことだ」
そうか。昔ここにあったのは、《ゼラーナ》の施設だったのか。では、移民たちを怖がらせた幽霊話の元は、その実験体だったのかも。
「動物を殺したのも、あんたたち?」
「そうだ。その実験体、23号は変身能力を持っているのでね。どんな動物の姿をしているのか、わからない」
「だからといって、この星の動物を全部殺して回るつもりじゃ……」
「必要があれば、そうする。その艇は間もなく、わたしの元に到着する。じかに会えるのを、楽しみにしているよ」
通話は切れた。ママは、こういう奴らから逃げてきたのだ。そして、永久に追っ手の届かない場所へ去った。でも、現世にいるあたしたちは、戦わなくてはならない。
(そうだ、エディはどこ!?)
この機内に囚われているのか、それとも、山中を逃げ回っているのか。
《エオス》に連絡しようにも、中継設備が乗っ取られている可能性が高い。遺棄された植民惑星なんか、訓練の場所に選んではいけなかったんだ。
機体は、山地の麓の草原地帯に着陸した。周囲には大小の上陸艇や強襲艇が七、八機、新製品の展示場のように並んでいる。見張りの兵士たちも、あちこちに立っている。ここが前線基地というわけか。
あたしはその中の、最も大きい機体に案内された。要所は、アンドロイド兵とバイオロイド兵の組み合わせで警備されている。
「初めまして、お嬢さん」
司令室で待っていたのは、白い服を涼しげに着こなした、大柄な男だった。
オールバックにした黒髪に、細い灰色の目、太い眉、存在感のある鼻、大きめの口、割れた顎。全体として、重量級の伊達男という印象。
「わたしはシド。《ゼラーナ》の代表者だ」
複数いる幹部の一人ではなく、頂点に立つボスということか。
年齢は四十代に見えるが、実は二百歳かもしれない。辺境の人間は不老処置を受けているのが普通なので、実年齢は見当がつかないのだ。
「《エオス》が戻ってきて、大事な娘が行方不明とわかったら、英雄の船長殿はどうするかな。楽しみだ」
高い位置から悠然と見下され、手錠付きのあたしは奥歯を噛み締めた。
「やっぱり、そうじゃないか。親父を最高幹部会に売り渡して、賞金をせしめるんだろ」
「それも悪くはないが、わたしとしては、23号の方が、いい商売になりそうな気がしている。まだ生きているのなら、是非捕まえたいね。いま、体重三十キロを目安にして、大型獣を撃たせている」
部屋の壁の大半を占める大画面には、惑星全土の地図が投影されていた。それに重なる小画面に映るのは、密林、氷河、高山、湖、大河、草原、砂漠、極地。
そして、そこに倒れている、たくさんの動物たち。ライオン、象、サイ、キリン、虎、熊、猪、野牛。
まるでゲームのように、偵察鳥たちがビームを吐き、動物たちを射殺していく。そして、倒れた動物の上に舞い降りては、爪を突き刺して、細胞を検査する。反応がネガティブだと、また舞い上がって、次の獲物を狙う。
撃たれて死んだ母イルカが波間を漂い、子供のイルカが、その躰を鼻先でつついている映像もあった。ママ、どうしたの。どうして、起きてくれないの。
あ、だめ。
こういうのを見ると、涙腺が刺激される。
映画でも特に、親子の別れの場面に弱い。作り物に泣かされるなんて恥ずかしいから、悲しい映画は絶対、人と一緒には見ないけど。
「これだけ殺して、まだ見つからないの。下手なやり方だね」
と軽蔑を込めて言った。シドは動物に感情移入はしないらしく、淡々と言う。
「あるいは、よほど巧く隠れているのか。それとも、こちらの予想外の姿をしているのか。とうに死んでいるか、この星から逃げている可能性もある。当時の担当者が死んで、詳しい資料が残っていなくてね。組織内でも、色々あったし」
そこで、彼はにやりとした。
「当時のボスは、わたしが倒したんだ。それで、こういうことになっている」
なるほど。違法組織の内部では、常に権力闘争があるわけだ。
「とにかく、ありとあらゆる温血動物を狩らせている。海中にも主要な湖にも、サイボーグ鮫を放った。洞窟の奥、極地の氷山の下も調べさせている。強酸性の火山湖の中までね。まさか、植物には化けていないと思うが。まあ、立ち話も何だ。ここにかけたまえ」
あたしは奥まった位置の、テーブル席に座らされた。作戦会議をするための席だろう。シドはあたしの斜め前に座り、にやついて言う。
「たとえ捜索が空振りでも、わたしとしては、きみを捕まえられただけで満足だ。可愛い野兎ちゃん」
何だって。虎とは言わないけれど、せめて、山猫に喩えたらどうだ。
「きみを飼ったら、さぞ楽しいだろうな」
は?
「そう、ピンクのドレスを着せてね。それとも、真っ赤なチャイナドレスがいいかな。腰までスリットが入ったやつだ」
かっと顔が火照った。からかわれている。あたしにドレスなんて、絶対似合わない。ママが死んでからは、顔が険しくなる一方だもの。髪の毛だって、邪魔にならないよう、短く切ってあるだけだし。
「ピンクは嫌いなの。似合わないから。赤の方がまし」
つんとして言ったら、シドは咳き込むように笑った。何がおかしい。
「あたしみたいな黄みの肌に、純粋ピンクは似合わないんだよ!」
と言ったら、なおも笑いむせんでいる。まるで、百年も楽しいことがなかったみたい。
「……いやあ、勇敢なお嬢さんだ。素晴らしい。きみが一人いたら、バイオロイドの女百人より、はるかに楽しめるな」
楽しまれてたまるか。
隙があればいつでも逃げてやるけれど、室内にも通路にも、見張りの兵がいる。決して油断することのない、機械の兵士。
もちろん、壁や天井には、警備兵器が据えられている。レーザー砲や電磁ネット。
捜索状況を映す大画面の前には、濃紺の制服を着たバイオロイド兵が四人。各地に散っている仲間に、低い声で指示を流している。彼らはそれぞれ小麦色の皮膚だったり、褐色の皮膚だったりするから、灰色の皮膚の機械兵とははっきり区別がつく。
辺境では人口のほとんどが、培養された人工奴隷――バイオロイドだ。推定で、二十億から三十億とか。
彼らは心を持っているけれど、人間に対する絶対服従を植え込まれているので、おとなしく警備や雑役をこなすだけだ。
余分な知恵や反抗心が育つのを防ぐため、五年で処分されるという。本当なら、優に百五十年は生きられるはずだというのに。
奴隷にするために命を創るなど、市民社会では有り得ない。それどころか、遺伝子操作による不老化や延命処置も、認められていない。
もしも認めてしまえば、世界は超人や怪物で溢れかえり、人類の文明は(少なくとも、これまでのような文明は)崩壊すると恐れられているから。
だから、不老不死を望む野心家たちは、市民社会を捨てて、何でもありの辺境に出ていく。そこでは、ごく一握りの、優秀かつ冷酷な者しか生き残れない。このシドは、その希少な勝ち残り組というわけだ。
「あんたもやっぱり、五年で彼らを殺すの?」
聞こえよがしに言ってやった。シドは迷惑そうに、苦笑する。当直のバイオロイド兵たちは、ちゃんと背中で聞いているからだ。
いくら心理操作を受けていても、生存本能はあるだろう。あたしの味方に引き込むことは、不可能ではないはず。あたしと一緒に脱出すれば、当局の保護を受けられ、市民社会で長く生きられるのだから。
「反乱を煽るつもりかい、お嬢さん? 無駄だね。管理システムが常に、全員を見張っている」
「わかってる」
違法組織の基幹機能は、短期間ならば、基地や戦闘艦隊の統合管理システムと、その末端である機械兵だけで十分にカバーできるはず。
「でも、できることは何でもするよ。あたしは生きて、自由になりたいから」
シドは、何かを隠した薄笑いで、あたしを見ていた。
「きみは実に、いい性格をしているなあ。父上に鍛えられたのかね」
「ママが教えてくれたんだ。市民一人一人が戦う覚悟を持たなければ、中央の文明は、いずれ違法組織に滅ぼされるって」
ただし、大多数の市民は、手遅れになるまで、それを認めようとしないかもしれないって。
ママの元の能力を考えても、違法組織の科学力、技術力は侮れない。制限なしの開発競争は、どんな危険な兵器でも作り出す。
だから、親父は、機会があるごとに訴えている。市民社会が、強大な違法組織に包囲されている現状を。
「そうか。しかし、それは違うかもしれないぞ」
「どこが?」
「市民社会には、人材を育てるという役目がある。最高幹部会もそれをわかっているから、中央に対して武力侵攻などはしない。まともな家庭でなければ、まともな子供は育たないからね。新しい人材が供給されなければ、辺境の文明も停滞してしまう」
へええ。意外に、筋道の通ったことを言うではないか。
「違法組織に捧げるために子育てするなんて、馬鹿馬鹿しい。〝連合〟が市民社会を守り続けるなんて、期待する奴は阿呆だね」
と、あたしは決めつけた。
「完璧な不老不死の技術が完成すれば、新しい人材は必要ないでしょ。あんただって、自分の跡継ぎを育てることなんか、考えてないはずだ。自分自身が永遠に生きるつもりなら、跡継ぎなんて必要ないもんね。違法組織っていうのは、そうやって閉じていくんだ。不老不死のボスの周りには、おとなしい奴隷だけが残る。反抗する気力のある人間の部下は、端から殺されるか、洗脳されるかだからね」
これはまあ、親父やバシムの受け売りだけど、あたしもそう思う。
「ボスはいずれ〝裸の王様〟になって、自滅していくよ。でも、それにはまだ何百年か、何千年かかかる。それまでに、市民社会が滅ぼされてしまったら困るんだ。だから、戦えるうちに戦わないと」
シドはまじまじ、珍獣でも見るかのように、あたしを見た。
「お嬢さん、歳は幾つだったかな?」
なんでそんなこと、と思ったけれど、別に秘密ではない。
「十五。もうすぐ十六。来月、誕生日だから」
でも、来月まで生きられるか、怪しくなってきたな。
シドは破顔した。
「素晴らしい。その年齢で、それだけ言えるのは、たいしたものだ。やはり、両親が偉かったんだな」
何をぬかす。逃亡したママたちを捕まえて、殺そうとしたくせに。
「あんたに感謝しろっての? ママを創ったから」
「13号を創ったのは、今はもうこの世にいない、前のボスだ。彼に感謝するとしよう。おかげで、こんな素敵なお嬢さんに会えた」
その時、あたしのお腹がぐうう、と盛大に鳴った。シドはきょとんとしてから、笑い出す。
「失礼した。きみは、朝食を食べたきりだったね。何か運ばせよう」
ほっとした。食べられる時に食べておくのが、戦士の心得だ。
「好き嫌いはないけど、デザートにはケーキを付けて。できたら、チョコレートケーキ。飲み物は紅茶がいい」
と要求した。シドが警備兵に指で合図すると、それが他の部署に伝わったらしい。十分ほどで、白い襟のついた瑠璃色のメイド服を着たバイオロイド美女が、料理のワゴンを押して現れた。
長い金髪をきっちり結い上げ、耳には小粒の真珠のイヤリング。あたしたちに一礼してから、黙々と立ち働く。
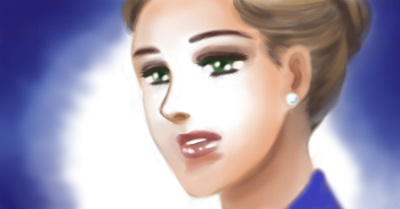
最初、あたしは信じなかった。でも、現場で、兵のゴーグルを通して撮影された映像を見せられた。エディがあたしを取り戻そうとして戦い、転びかけた瞬間に胸を撃たれて、斜面に倒れ込むさまを。
間違いない。ほとんど即死だ。すぐに医療カプセルに入れられればともかく、山中に放置されては。
あたしは泣いた。
わめいた。
シドを罵倒し、手錠付きのまま荒れ狂った。
「人殺し!! 悪魔!! エディを返せ!! 返せーっ!!」
最初は面白がっていたシドも、あたしが食器やカトラリー類を彼に投げつけると、閉口して兵に命じた。
「連れていけ」
あたしは同じ艇内の一室に押し込められ、手錠のまま放置された。狭いベッドに身を投げて、わあわあ泣きわめく。
どうして、どうして、こんなことに。
あたしのせいだ。つまらない意地を張って、エディを撒いたりしなければ、二人一緒に捕まっていたのに。
無意味に死なせてしまった。ようやく放浪生活を切り上げて、新しい生活を始めたばかりのエディを。
エディの家族に、何て言い訳すればいいの。お母さんは、エディが仕事に就いたことを、あんなに喜んでくれたのに。あたしにまで、手作りのクッキーやジャムを送ってくれたのに。あたしが切腹したって、何の役にも立たない。
ごめん、エディ。
ごめんなさい。
あなたはただ、船内のみそっかすに、親切にしてくれただけなのに。あたしがひねくれていて、素直に感謝できなくて。
そうして何時間、断続的に泣き続けたのだろう。いつしか、疲れきって眠っていた。
目を覚ましたら、手首の手錠がない。ブーツを履いていたのに、それも脱がされて、ベッドの下に揃えてある。
窓がないので、外の様子はわからなかったけれど、通話画面に時計表示があった。この地域では、夜明け前。あたしの体内時計とも、合っている。元々、連邦標準時に合う時間帯の土地に降りたからだ。
もう眠る気はしなかったので、着たきりだった服を脱いだ。付属の浴室に入って、熱いシャワーを浴びる。
気持ちよかった。文明生活の有り難さだ。下着も洗って、温風乾燥にかけた。短い髪も、すぐに乾く。
棚にバスローブがあったので、それを着た。裸足のまま部屋に戻って、ベッドに座る。
自分の運命や23号のことよりも、今はまだ、エディのことしか考えられない。フルーツグラタンを作ってくれたエディ。勉強を教えてくれたエディ。点検作業を手伝ってくれたエディ。ハーブの名前を教えてくれたエディ。
エディが一緒だと、山の中のキャンプも楽しかった。あたしに裸を見られたくらいで、あんなにうろたえて。ほんと、純情なんだから。
それなのに、もう二度と、エディの料理を食べることも、焚火をはさんで、おしゃべりすることもない。
ママが死んだ時だって、こんなに苦しくなかった気がする。あの時はむしろ、安堵が強かったから。
でも、エディの人生は、まだまだこれからだった。せっかく《トリスタン》の事件を生き延びたのは、こんな風に死ぬためじゃないはずだ。
やはり、責任はあたしにある。本当は、怖かったのだ。エディのいたわりが、目眩がするほど心地よかったから。それに引き込まれてはいけない、と思った。あたしは〝女〟になってはいけないのだ。戦えなくなったら、《エオス》にいられないから。
実際には、女であることと、戦士であることは、両立するのだろうけれど。ハンターの〝リリス〟や、多くの女性軍人や、知り合いのおばさま船長たちのように。
でも、あたしはまだ、そこまで大人ではない。突っ張って生意気な口をきくのが、あたしなりのバランスだった。
エディが悪いのだ。そんなことを何も察せず、横から急に現れて、あたしを女の子扱いするから。
だから、エディから離れるつもりだった……嫌われた方がましだと思った……まさか、こんなことになるなんて……
やがて、通路に面した扉が開いた。
「ジュンさま、失礼します」
昨日のバイオロイド美女が、食事のワゴンを押して入ってきた。扉が閉まる前にちらりと見えたが、通路では灰色の顔の兵たちが、銃を構えて見張っている。
「朝食をご用意しました。お気に召さないようでしたら、他のものを用意して参ります」
まだ朝早いのに、きちんと身支度している。瑠璃色のメイド服に白いエプロン、結い上げた金髪、宝石のような緑の瞳。中央だったら、女優かモデルになれる美貌だ。それが辺境では、五年で使い捨ての奴隷とは。
「これで十分だよ」
と答えた。平静な声が出せたことに、自分で呆れる。おまけに、食事をするつもりだ。蜂蜜とジャムを添えたパンケーキ、中身が半熟の見事なオムレツ、蒸した野菜のサラダ、厚切りのハム、ヨーグルト、果物。
昨夜、夕食抜きで眠ってしまったあたしは、狼のように空腹だった。手狭なテーブルに並べてもらった食べ物は、端から、あたしの胃の腑に消えていく。
金髪美女は用済みの皿を下げ、オレンジの皮を剥いてくれ、コーヒーのお代わりを注いでくれた。ひっそり静かなのに、必要なことは手際よく行う。
「ごちそうさま、美味しかったよ」
「足りましたでしょうか?」
「うん、これで十分」
あたしはようやく、目の前の女性に興味を向けた。バイオロイドと向き合って話をするのは、初めてだ。いや、亡命して市民社会で暮らしているバイオロイドもいるから、知らない間に知り合っていたかもしれないけれど。
辺境の工場で大量生産される、人造人間。
人間の遺伝子を元にした人工遺伝子から創られるので、あくまでも人間のうちである。知能が高く、身体強健だから、人類の改良種と言ってもいい。それが、奴隷の立場から抜け出せないのは、教育が制限されているからだ。
「あなた、名前は?」
すると、向こうはびっくり仰天している。何か、無理難題でも投げられたかのように。
「どうしたの、名前がないの?」
「いえ……あの……ベリルと申します」
「緑柱石か。目が緑だからだね」
あたしが言うと、ますます呆然としている。何だろう、この反応。
「もしかして、自分の名前の意味、考えたことないの?」
「ええ、あの……名前に、意味があるのですか?」
工場で培養されるバイオロイドにとって、名前とは機械的に割り振られるもので、番号と大差ない、ということか。
このベリルの〝型〟の場合、宝石から取った名前を順に付けられるだけなのかも。では、お仲間は、ルビーとかパールとか、アンバーとかいうのだろう。
あたしの名前は、日本語の『純粋』から付けられた。親父の家系は、日本の血が濃い。だから、漢字で書く時は、その字を使う。現実には、『単純』の純かもしれない。あたし、頭が悪すぎる。
ベリルにあれこれ質問して、ようやくわかった。彼女が、囚人であるあたしを怖がっていることが。
シドの侍女であるベリルは、これまで『本物の人間の女性』と話したことがほとんどないという。組織にも女性の幹部や技術者はいるが、ベリルの行動範囲では、親しく接したことがないらしい。
おまけに昨夜、あたしが滅茶苦茶荒れ狂ったものだから、すっかり『凶悪生物』と思われている。
見た目は二十歳前後の成人女性に見えるが、実際には、培養カプセルを出てから、わずか数年なのだ。つまり、年下の少女だと思うべきなのである。
「あのね、エメラルドってわかる?」
かしこまって立つ美女に、あたしは小学校の先生の気分で尋ねた。
「宝石……ですか」
「そう、緑色の宝石。ベリルというのは、そのエメラルドの仲間なの。て言うか、ベリルの中で上質のものを、特にエメラルドって言うのかな。とにかく、あなたの名前は緑柱石という意味で、とても綺麗な名前なんだよ。あなたは素晴らしい緑の目をしているから、その名前、よく似合ってる」
ベリルは、少し納得したようだった。
「綺麗な石の名前……なんですね」
バイオロイドには最低限の教育しか与えられない、という意味がわかった気がする。表面的な日常知識はあるけれど、その深部に広がる、系統立った科学知識や歴史知識までは与えられない、ということだ。あくまでも、下働きに必要な知識だけ。
「それでね、ベリル、急ぎの用がなかったら、少し話相手になってくれるかな」
と頼むと、
「はい」
と素直に言う。座るように言うと、なんとスカートを広げて床に正座した。
たった一つの椅子には、あたしが座っているからだけど、あたしはベッドに腰掛けてくれ、と言ったつもりだったのに。
手を引いて彼女を立たせ、改めて、ベッドの端に座らせた。さあ、どこまで答えてくれるものか。
「あなたたち、この星にはいつ来たの。母艦はどこにいるの。この星に上陸した部下は、何人くらい?」
尋問か、とベリルは困惑した様子。けれど、シドに説明を禁じられていなかったためか、首をひねりながらも、訥々と話してくれた。組織の基地について、構成員について、商売について、艦隊について。
もちろん、侍女の立場では、知らないことの方が多い。それでも、おおよそは掴めた。二流どころの中規模組織だ。これは、決して馬鹿にできる相手ではない。ママが脱走できたのは、本当に幸運だった。中央の外縁で、たまたま親父の船に出会ったことも。
「ありがとう。引き留めて悪かったね」
あたしが質問攻めから解放すると、ベリルはほっとしたようで、ワゴンを押して立ち去った。やはり、扉の外では、兵たちが警戒している。脱走を試みるのは無理。
あたしはベッドに転がって、今聞いた情報を整理した。23号が発見できてもできなくても、シドはあたしを辺境の基地に連れ帰る。《エオス》が《タリス》に戻ってくる前に。基地からの逃亡は、まず不可能。ならば、この星にいる間に、シドを殺すしかない。
そうすれば、判断力のないバイオロイドの部下たちは混乱する。シドはこの星には、バイオロイドの部下しか同行していないから。
星系内に潜伏している艦内には、人間の部下がいるらしいけれど、彼らも、シドの後を継ぐ者が決まらないと、どう動いていいか困るはずだ。
永遠に生きるつもりのシドは当然、後継者など決めてはいない。有力な部下たちの跡目争いになれば、あたしのことなんて後回しになる。
ごめん、エディ。
あたしはまだ生きる。そのために努力する。
あたしが死んだら、親父がどうなるかわからない。ママが死んだ時、あれほど打ちのめされていたんだもの。
もしも、生きて《エオス》に戻れたら、あんたのご両親に会いに行く。そして、あんたを死なせたことを謝る。許してもらえるとは思わない。でも、伝えるよ。エディがどんなに誠実で、働き者で、みんなに好かれ、期待されていたか。
ようやくわかった、と思う。《トリスタン》で、ただ一人だけ生き残ってしまったエディが、どんな思いで、半年も放浪していたか。
こんな、心にたくさんの石ころが詰め込まれたみたいな気持ちでいたんだ。
重くて冷たい、硬い石ころで、あたしの胸は、ぎっちり塞がれてしまっている。息をしても、ものを食べても、全身が重苦しい。
顔で笑っても、心までは笑えない。
法的な責任は問われなくても、自分を責め続ける、魂の生き地獄。
この先、何十年生きても、あたしはもう二度と、偉そうな態度なんかとれない。エディはあたしなんかより、ずっと上等な人間だったのに。
……もしかして、みんなそうなの?
人生のどこかで、取り返しのつかない間違いをしてしまったら、残りの年月、ずっと心に石ころを詰め込んで、重苦しく足を引きずって生きるもの?
自分には幸せになる権利はないとばかり、謙虚に頭を垂れて、隅っこで身を縮めて暮らすもの?
でも、待って。それも違う。
自分に罪があろうがなかろうが、それとは関係なく、怒るべき時はあるんじゃないの?
たとえば、シドが動物たちを大量に虐殺させているのを見たら。23号を捕まえて、再び実験動物にしようとしているなら。そして、ベリルのようなバイオロイドたちを、五年で廃棄処分し続けるというのなら。
どこかで、水の音がする。
静かな水面に水滴が落ち、波紋を広げるような音。音が籠もって反響しているのは、閉ざされた空間だからだ。
冷たいものがぽつんと頬に落ち、耳に流れた。ぼくは驚いて目を開けたが、真っ暗で何も見えない。
数瞬、盲目になったかと思った。しかし、目が慣れてくると、不規則な岩壁の輪郭が見え、洞窟のような場所であることがわかる。
なぜか、自分は裸だ。下着もなければ、ブーツもない。手首にはめていた端末も、やはりない。そして、覚えのある寝袋の中にいる。
起き上がろうとして、胸から背中にかけて違和感を覚えた。痛みというよりは、筋肉や皮膚が引き攣れるような感じ。
それにまた、体重がいつもの何倍にもなったかのようだ。わずかな動きなのに、息が切れ、目眩がする。
これは、病気なのか。
ぼくはどうして、こんなことに。
これまで、風邪くらいしか、病気の経験はない。それも、母の作ってくれた熱いスープやリゾットを食べ、ぐっすり眠れば、すぐ治った。
姉のアリサが、笑ったものだ。
エディ、あんたって、本当に恵まれているわ。体力も頭脳も、手先の器用さも。ないのはただ、情熱だけね。
そうだったかもしれない。学生時代、ただの一度も、本気の恋愛をしなかった。たいして好きでもない女の子と付き合って、振り回されるのが煩わしかった。付き合うのは簡単でも、別れるのは難しいからだ。
たぶん、途方もなく、理想が高かったのだろう。それも、自分の身の程を、わきまえていなかったからだ。
少しばかり優秀だと思って、自惚れて。
だから、ジュンにも嫌われる。夏の野に咲く白百合のような、誇り高い美少女に……
ようやく、記憶が蘇った。ジュンがさらわれたのだ。謎の一団に。
ぼくは……撃たれた?
なぜ、生きているんだ。即死でも、おかしくなかったのではないか。
「目が覚めたのね」
静かなアルトの声がした。ぎょっとして頭を巡らせると、闇の中に、白い人影が浮き上がっている。
ぼくは目を疑った。
石筍の群れの向こうに、青白い燐光を放つ、裸の女性が立っているのだ。ゆるくカールした白っぽい髪を、大理石のような肩にこぼしているだけで、豊かな胸のふくらみも、引き締まった下腹部も、なだらかな曲線を描く脚も、何も隠さずに。
