
レディランサー アイリス編2

今朝からどうも、鈍痛がある。昨日のパフェのせい? それとも、夜中に毛布を蹴飛ばしていたせい?
何度目かのトイレで初めて、
(あ、そうか)
と思い出した。
毎月、律儀によく来るな。あたしはどうせ、妊娠も出産もしないのに。
それでも、初めての生理の時は、ママが喜んでくれ、母娘で正装して最高のレストランに行き、一番高いコース料理を注文して、ジュースで乾杯したものだけれど。
その母が死んだ時、あたしは『普通の女の子』をやめた。少なくとも、そう振る舞うことをやめにした。長くしていた髪を切り、赤いリボンも、フリルのワンピースも封印した。
元々、母が望むから、そういう可愛い格好をしていたのだ。ひらひらのスカートなんて、駆けっこにも、木登りにも向かないのだから。
それでも、母にとっては、やっと手に入れた『普通の生活』だったから、あたしは、母の望むことなら何でもした。一緒にケーキを焼くことも、庭に花を植えることも。
学校が休みの日には、二人で買い物に行き、眺めのいいカフェテラスで、パフェやケーキを食べた。
外からは、どこにでもいる、普通の母娘に見えただろう。母はプラチナブロンドに青い目、白い肌。あたしは黒髪に黒い目、黄色い肌。ちっとも似ていない母娘だったけれど。
普通と違っていたのは、違法な実験体である母がいつか死ぬと、子供の頃からわかっていたことだ。
寿命を削ることを承知で、母は『逆改造』の苛酷な処置を受けた。それを受けない限り、一生、僻地の隔離施設から出られない運命だったから。
何回もの手術とリハビリ、一生続く投薬と、病院通い。それでもなお、体力の低下は避けられない。
まして、妊娠や出産という負担を引き受けたら、更に命を縮めることになる。
それほどの犠牲を払って手に入れた『普通の家庭生活』は、幸せなものでなくてはならない。
あたしは物心ついた時には、誰に説明されたわけでもないのに、わかっていた。
(ママは大変なんだ。あたし、いい子でいなきゃ)
もう一人の実験体と共に、辺境から逃亡してきたという事情は、もっと後になってから知ったこと。
母にはあたしと父の他、誰もいないのだ。
いや、亡命者の苦労を理解してくれる人も、支援してくれる人もいたけれど、それでも母は最後まで、市民社会の異端者だと感じていただろうから。
違法組織の実験施設で培養された『戦闘兵器』。
名前の代わりに、番号で呼ばれていた。13号と。
唯一の仲間であった19号は、共に組織の基地から脱走し、追っ手と戦った後、母と決別したという。
『人類の時代は、もう終わり。これからの世界は、わたしたち超人類のものよ』
そう言い残して、宇宙のどこかへ去ったと聞いている。
それとは反対に、古い人間たちを信じようとした母は、結婚相手の家族から、魔女のように忌み嫌われた。息子をたぶらかした怪物、と。
一度でも会ってもらえたら、怪物などではないと、わかったはずなのに。
その母が、半年あまりの入院生活の終わりに力尽きた時、あたしは枕元で、枯れ枝のようになった手を握って約束した。
『後のことは心配しないで。大丈夫。あたしがちゃんと、パパの面倒見るからね』
当時はまだ、『親父』ではなく『パパ』と呼んでいた。小さく枯れ縮んでしまった母は、涙の下から微笑んでくれた。
『ダグと会えて、あなたを授かって、本当に幸せだったわ。ありがとう』
《エオス》で遠くを飛んでいた親父は、臨終に間に合わなかったけれど、それでよかった。あたしは一人で遺体に付き添い、心ゆくまで泣けたから。
泣きながら、深いところでほっとしていた。何年も笑顔を作り続けて、疲れていたのだ。
母の衰えに気がつかないふり。
入院すれば元気になるよ、という分かりきった嘘。
その母が死んで、途方もない重荷がなくなった。暗い密林から抜けて、青空の下の大砂漠に出た気分。
もう学校帰り、毎日、病院に寄る必要もない。その日の出来事を、面白おかしく脚色して話さなくていい。
これからは年齢相応の、わがままな子供になって構わないのだ。パパには、あたしを甘やかすくらいの度量はある。
ところが、葬儀が済むと、その父の老け込みぶりに気がついた。真っ黒だった髪に、白いものが混じっている。
弔問客がいるうちは、何とかお義理の笑顔を浮かべているけれど、誰もいなくなると、暗い部屋に座ったきり。あたしが無理に食事をさせないと、お酒しか飲まないで寝てしまったりする。
あたしは悟った。
自分には、まだ役割があるのだと。
親父が《エオス》での仕事に戻ると、あたしは保持する意味のなくなった家を出て、学校の寮に入った。
ここなら、あたしに付く警備の人たちも、仕事がやりやすい。親元を離れて寮にいる子供はごく少ないから、あたしは誰にも邪魔されず、ガリ勉できる。
もはや、弱音を吐く相手もいない。一番の仲良しだったリエラは、お父さんの仕事の都合で、遠くの星に引っ越してしまった後だし。
あたしは単位を取りまくって、人より早く学校を卒業し、パイロットのB級ライセンスを取って、強引に《エオス》に乗り込んだ。
『あたしがライセンスを取ったら、乗せてくれる約束だったよね』
と、子供時代の口約束を盾にして。
今度は、父を支える息子になるのだ。
《エオス》で実務経験を積んだら、商業船の船長に必要な、A級ライセンスにも挑戦できる。
ジェイクたち〝鬼軍曹〟にしごかれたおかげで、今では操船も、上陸艇の修理も、機械兵部隊の指揮もできる。素手の戦いはともかく、武器を使えるなら、そのへんの男になんか負けやしない。
――それなのに、毎月、これだけは来るんだからなあ。
男にはなれないと、繰り返し、宣告されているようなもの。
寝込むほどひどくはないけれど、泥のようにだるくて、しつこい眠気があって、重苦しい痛みが続く。
この期間は、空手の稽古など、怖くてできない。間違ってお腹に蹴りが入ったら、きっとショック死してしまう。水で一杯の風船を、下腹部に抱えているような感じ。
あたしは鈍痛を抱えて医療室に行き、医学雑誌を読んでいるバシムに、生理が来たことを伝えた。
「そうか、わかった」
あとは、彼がジェイクたちに伝えてくれる。空手の稽古や、きつい整備作業を五日間、免除してもらうためである。
あたしとしては悔しいことだが、仕方ない。子供時代に通っていた道場でも、女性の先輩たちに言われていた。
『女性の肉体は、本来、荒事には向いていないの。強くなろうというのなら、なおさら、限界をわきまえないとだめ』
ことに、生理日の無理は禁物。打撃を受けたり、強い振動にさらされたりすることは、絶対によくない。
昔の女子スポーツ選手は、生理が止まってしまうほど、苛酷な練習をしていたというけれど、そんなのは本末転倒だと教わった。健康な人生のために、スポーツがあるのだからと。
ただ、あたしの場合はまず、生き残るために強くなる必要があるのだけれど……

温かい飲み物を求めて、厨房に行く途中、ひょいとラウンジを覗いて、ぎょっとした。
いつもニュース番組を見る大画面に、あえいでいる裸の女が大写しになっている。
しかも、金属製の狭い檻に入れられ、その躰に、大きな蛇が何匹も絡み付いている。
生きた蛇ではなくて、精巧な作り物のようだけど、その蛇の舌が、チロチロと女の乳首を甞めている。女の顔は、恐怖と快感で混乱しているように見えた。檻の周りでは、人相の悪い男たちが、にやついて眺めている。その上、蛇の頭が、女の脚の間に潜り込んでいく!!
あたしは息を止め、足音を忍ばせて、その場から遠ざかった。心臓が鼓動を速め、怒りと反感と、恐怖がごっちゃになっている。
(……あの連中、また!!)
画面に向き合う半円形のソファに、四つの頭があったのはわかった。男同士の団結のためだとかほざいて、時々、違法ポルノの上映会をするのだ。私室でやればいいものを、共有のラウンジで堂々と。
合法ポルノなら、強姦や拷問を〝娯楽として〟描くことはできない。法で規制されている。だから、あの手の描写があるのは、辺境で作られた違法ポルノと決まっている。
しかも、今日はふてぶてしい三十代トリオに、エディまでが加わっていた。
ぽかんと口を開けて、違法ポルノを見ているなんて、信じられない。
しおらしげな態度をしていたくせに、もうすっかり、うちの連中に馴染んでしまったのだ。
これだから、男ってのは。
あたしは厨房を素通りして、温室に向かった。奴らが違法ポルノを見ている隣の部屋で、のんびりココアを飲むことなんて、とてもできない。
気づかれて、たまるか。
このあたしが、怯えている、なんて。
同時にまた……刺激されている、なんて。
温室では、バシムが趣味で花を育てている。二重扉をくぐって暖かい空間に入り、緑の匂いにほっとした。時々、あたしが昼寝をしたり、読書したりするのに使う、ささやかな芝生の上に座り込む。
あたりには四季咲きの薔薇が茂り、甘い香りを漂わせていた。その奥には、レモンやオレンジの木も生えている。バジルやミント、レモングラスやカモミール、ラベンダーやローズマリーの区画もある。
少しずつ、気持ちが収まってきた。
(見なかったことにしよう)
あいつらが、これ見よがしにああいうものを上映するのは、半分、あたしに当て付けているのだと知っている。
(違法組織に捕まったら、こういう目に遭うかもしれないんだぞ。おまえだって一応、女なんだからな。怖いと思ったら、船を降りろ。女子大の寮にでも入れ)
という意味だ。
冗談ではない。
親父を置いて、逃げられるものか。
それに、惑星上で司法局の護衛に囲まれていたって、無事で済むとは限らない。
子供時代に、何度も誘拐されかけた。どの時も、運良く助かったけれど、もし、あたしが人質にされていたら、親父はおびき寄せられて、殺されていたはずだ。あるいは、懸賞金制度の元締めである、グリフィンに差し出されていた。その後は、公開処刑されていたか、それとも洗脳されて部下にされていたか、わからない。
親父をモデルにした映画を撮った、ミハイル・チャン監督はどうなった? 親父の暗殺を企む者たちに捕まり、催眠暗示をかけられて、人間爆弾に仕立てられたではないか。
親父と同郷の先輩だったチャン監督は、二年前、親父と歓談していたホテルのバーで吹き飛んだ。体内に一定量のアルコールが入ると、化学反応で爆発するよう仕組まれていたという。
周囲にいた一般市民、十数名が死傷した。親父が軽傷だけで助かったのは、たまたま別の知人に声をかけられ、柱の陰に回り込んでいたからだ。
賞金首の父を持つ限り、あたしは戦う覚悟を持って暮らすしかない。《エオス》を降りて、行きたい場所なんか、あたしにはないんだから。
(それにしても、あいつら)
まだ、あたしが目障りなのか。何とかして追い出そうと、あれこれ工夫してくれるものだ。
必要のない整備作業なんかを命じてくるのはいいけれど(こっちも、整備の勘所はわかってきた)、本当には、おしゃべりの相手にもしてくれない。いい加減、仲間として受け入れてくれてもいいだろうに。
(男のエディなら、すぐに受け入れたくせに……)
あたしが子供だから、じゃない。
女だから、なんだ。
温室の二重扉が開く音がした。慌てた様子でやってきたのは、エディだ。厨房の主になって以来、エプロン姿でいることが多い。今日は白いシャツの上に、大きなポケットの付いた、紺のエプロンを
重ねている。
エディはあたしの近くの芝生に膝を着くと、祈るような動作で言った。
「ジュン、ごめん!! 変なものを見せてしまって!!」
へえ。
あたしが廊下を通り過ぎたのが、わかったの。
画面に夢中で、気がつかないかと思ったけど。
「何でも、勝手に見れば? 外に言いふらすつもりは、ないから。そんなことしたら、親父の恥になるもの」
冷たく言い捨てたら、エディはおろおろ弁解する。
「いや、あの、先輩たちに、社会勉強だと言われたものだから。まさか、ああいうものの上映会だとは思わなくて……」
「ふーん、そう」
市民社会では絶対に許されない、悪質な違法ポルノが――演技ではなく、本物の強姦や獣姦を撮影したものが――違法都市では、大量に売られている。その一部は、市民社会にも流れてくる。
違法組織にとっては、安定した資金源だ。
映画に使われたバイオロイドの女子供は、数回の撮影で、心身共にぼろぼろになって、廃棄されるという話。
よくも、そんな映画を〝楽しめる〟ものだ。まあ、合法ポルノより、ずっと強烈なのはわかるけど。
「あたしのことなんか気にしないで、好きなだけ、お勉強すれば?」
ああいうものにお金を出すということは、紳士面した市民社会の男も、つまりは、違法組織の男と『地続き』だという証拠。
ところが、エディは全力で否定する。
「いやっ、ぼくは別に、見たくないから!! ただ、その、新入りとして、断れなかっただけだから!!」
何なの、その力み方は。
「へえ? そお? 普通は、見たいものでしょ?」
見たくないと言ったら、嘘つきだと判定するぞ。
あたしだって、合法ポルノなら何度も見た。学校時代、女の子だけの誕生会とか、パジャマパーティとかで、誰かが持ってきたものを、みんなでキャアキャア言いながら鑑賞した。
『えーっ、嘘お、ホントにそんなことするの!?』
『信じらんない!!』
『いやあん、ゼッタイ無理!!』
『うそうそ、彼に頼まれたら、するでしょお?』
『しないってば!!』
なんて、じたばた、きゃあきゃあ、笑い転げながら。
それは、実際に男の子と付き合う前の予習だから。大抵は、誰かのお姉さんや、女性の先輩から推薦された作品だった。
『あんたたち、口説かれたからって、簡単に許しちゃだめだからねっ!! 男ってのは、仲間に自慢したいために、とにかく経験値を上げたがるんだからっ!! あいつらの口説き文句なんか、本気にするんじゃないわよっ!!』
という、有難い忠告付き。
だから、男連中も同様の上映会をするのは、別に構わない。それが、誰も傷つけずに製作されている合法ポルノなら。
「そ、それはその、ぼくだって、合法の奴なら、たまにはお世話に……いや、その、だからっ!!」
エディは一人でうろたえ、冷や汗をかいているみたい。何もそんなこと、あたしに言い訳しなくていいのに。
お上品な合法ポルノは『かったるい』と言う男たちが多いのは、知っている。アニメや合成映像で満足すればいいものを、小さな女の子を使った実写の映像が見たい、という奴もいるらしい。ハードなSMを実写で見たい、という要望も根強いとか。
そういう要望に応えられるのは、違法ポルノだけ。
違法ポルノを一度も見たことのない男なんて、市民社会でも、少ないんじゃないだろうか。
だから当局も、本気では取り締まらないのだと聞いている。違法ポルノを見た男を、片端から逮捕して回ったら、市民社会はフリーズしてしまうから。
「とにかく、ごめん。不愉快な思いをさせて。今度から、先輩たちには、個室で見てもらうように言うよ」
へえ。
何だろう、紳士ぶりたいのかな。
エディはどうやら、親父に憧れているらしいから。親父の前では、目に見えて、ぎくしゃくするものね。
軍にも司法局にも、時々いる。ハンターの〝リリス〟に憧れて志願しました、とか、英雄のヤザキ船長に憧れて、とか言う奴。

その午後、自室でレポート書きをしているあたしのところに(大学の通信講座を幾つも取っていると、かなりの勉強量になる)、エディがやってきた。
「あのう、ジュン、よかったら」
と、精一杯の様子でにこにこする。大きな朱塗りの盆の上には、大盛りのチョコレートパフェと、グラスに差した白や紫のパンジーの花。
いったい、何を考えているんだろう。
エディは確かに料理係として試験採用されたが、おやつは契約外だ。それは各自、これまで通りに、好きなものを食べればいい。食糧倉庫には、山ほどの備蓄がある。
おまけに、パフェに花が付いてくるのは、どういう意味?
「あのね……」
あたしは言葉を探した。パフェは好きだが、生理の時は内臓が収縮するため、ただでさえ、お腹を下しやすいのだ。そこに冷たいものなど入れたら、どんな悲惨なことになるか。
けれど、それをわざわざ、男に説明する義理はない。
「パフェは好きなんだけど、今日は欲しくない」
と言ったら、エディは殴られたような顔をする。そのまま、後ろに倒れるんじゃないかと思ったくらい。
「ご、ごめん。そうだよね。冷やしちゃいけないんだ。気がつかなくて。外側の温度しか、考えてなかった。出直すよ。何か温かいもの……」
やや気の毒になった。午前中の映画のことを、まだ気にしているのかもしれない。どうせエディは、中年三人組に誘われただけなのに。
「待って」
去りかけたエディの背中に手を伸ばして、引き留めた。盆の上の花を差して、
「これも食べ物?」
と、念のために尋ねた。だって世の中には、薔薇のジャムも、菫の花の砂糖漬けも、菜の花のお浸しもあるでしょ。食用のパンジーというのも、あるのかもしれない。
でも、エディは戸惑ったようだ。
「これはただ、ちょうど温室で咲いていて、綺麗だから……」
そうか、観賞用か。
「じゃあ、これだけ、もらっておく。ありがと」
とパンジーのグラスを取り上げたら、エディは青い目を見開いて、固まっている。
やっぱり、変な奴。
あたしに、花は似合わないとでもいうのか。
あたしだって、ママと暮らしていた頃は、ささやかな一軒家の庭で、たくさんの花を育てていたんだぞ。
「まだ何か?」
あたしが問うと、エディは急いでしゃべりだす。
「あの、今夜は薬膳料理、どうかな。躰を温める料理を作るよ」
まるで歩く料理本のように、朝鮮人参だの、クコの実だの、生姜だの、大蒜だのと、薬効を並べ立てる。
「とりあえずは、参鶏湯かな。大根と牛肉とナツメのスープもいいかも。生姜と羊肉のスープというのもあるけど、どうかな?」
どうかと言われても。
「適当に作ってよ。美味しければ、何でもいいよ。好き嫌いはないから。でも、躰を温める料理というのは、嬉しいな」
するとエディは、ほっとしたような笑顔になる。
「わかった。これから毎日、きみの体調に合わせた料理を作るからね。食べたいものがあったら、ぼくに言ってくれればいい」
あたしは急に、眩暈を覚えた。
変だ。
熱がある時のように、力が抜けて、頭がくらくらする。
あたし、エディがこの船に来た時、さっそく、ひっぱたいているんだけど。
あれはもう、気にしていないのだろうか。
翌日、エディが謝りに来た時も、つんけんして、何か屁理屈言った気がするんだけど。
『あたしが怒ったのは、あたしの感情であって、あんたが自分の主義を変える必要はない』
とか何とか。
好意のはずがない。
エディに好意を持たれるようなことは、何一つしていない。
もしかして、あたしが凶暴だから、手懐けておかないと危険だと考えて?
たぶん、それだ。
「あのね。あんたは、この船全体の料理人でしょ。あたしだけじゃなくて、みんなの希望を聞いて、メニューを決めるべきじゃないの?」
と一応、良識を示してみた。ところがエディは、やけにきっぱり断言する。
「いいんだ。きみの希望が最優先。ほら、育ち盛りだからね。きみが一番、栄養を必要としているわけだし。きみの躰にいいものは、他の人間にもいいに決まっているし」
そうだろうか。四十代の親父やバシムには、十代のあたしとは違う好みがあると思うけど。
でもまあ、いいか。
あたしにも、たまには少しくらい、いいことがあってもいいはずだ。エディがあたしに脅えているための親切なら、やや気の毒な気はするけれど。
「それじゃあ、一つ頼んでいい? 何か、あったかいおやつ」
「わかった。フルーツグラタン、どうかな。カスタードクリームのやつ。すぐ作れるよ。それに、熱い紅茶を添えて」
というわけで、あたしは甘くて温かいおやつにありつき、夜は夜で、躰にいい薬膳料理をたっぷり食べたのだった。
これって、なかなかいい。
まるで、お抱えシェフを持つ大富豪みたい。
レストランを持つお母さんの元で修業したというだけあって、エディの腕は確かだった。軍人であるお父さんからは、武道のスパルタ教育を受けたそうで、あの強さも納得というもの。
もっとも、
「軍を辞めた時点で、父には勘当されているんだ。この根性なしの、腑抜け息子ってね」
と笑って言うのには、びっくりした。
笑い事なの、それ。
夕食の片付けを手伝いながら(それも、下っ端であるあたしの仕事のうち)、つい、あれこれ尋ねてしまう。
「じゃ、帰りたくても、家には帰れないの? お母さんにも会えないの?」
あたしだったら、親父から勘当されるなんて、この世の終わりみたいなものだ。その時はきっと、親父もそう感じるだろうけど。
ところが、エディはあっさり言う。
「帰ろうと思えば、いつでも帰れるんだよ。父が勘当と言い張っても、母と姉が味方してくれるから」
ああ、そうなんだ。
「だいたい、ぼくが育った家は、母の持ち物だしね。喧嘩したら、追い出されるのは父の方だよ。母と姉がスクラムを組んだら、父は勝てないし。父もそれがわかっているから、余計、男の沽券にこだわるのかもしれないね」
へええ、とあたしは感心する。
「お母さんの方が、強いんだ」
「大抵、どこもそうじゃないかな。表向きは、父を立ててるけどね」
「喧嘩することも、あるの?」
「たまにね。父が、母の誕生日を忘れた時とか」
そんなことで、喧嘩になるのか。よその家庭の話は、不思議だ。うちの場合、ママには誕生日なんてなかった。気がついた時は、組織の実験室だったんだものね。
綺麗に片付けた厨房の、カウンター席に座って、エディとお茶を飲んだ。熱いミルクティ。お供は、あたしの好きなオランジェット。オレンジピールとチョコレートは、よく調和する。
「うちは、親父が留守の時が多かったから、ほとんど母娘二人だったよ。ママには親戚もいないし、ママを怖がる人もいたしね。逆改造して攻撃力は減ったといっても、男三人分くらいの腕力は残っていたし」
「でも、市民権はちゃんともらえたんだよね?」
「うん。限定つきでね。旅行する時は、許可が要るの。でも、親父がまとまった休暇を取った時は、よく旅行したよ。ママは、本物の空や海が好きだったから」
宇宙空間の小惑星都市は、清潔で快適だけれど、しょせんは箱庭だ。川や湖はあるけれど、海はない。制御された雨は降るけれど、嵐は来ない。地震も、火山の噴火もない。
だから、本物の地球型惑星の大自然は、あたしにも感動だった。台風、地震、落雷、オーロラ、氷河、山脈、ジャングル、砂漠。
「でも、船乗りの基地としては、小惑星都市の方が便利だからね」
何週間も船に閉じ込められていた後の上陸休暇は、ものすごく楽しい。親父と市街地のホテルに泊まって、街を歩いたり、話題のレストランで食事したり、美術館をのぞいたり、観光牧場で馬に乗ったりする。もちろん、遠巻きの護衛は、いつも付いているけれど。
それは、あたしたちを守るためが半分。あとの半分は、万が一の場合、一般市民の巻き添えを最小限にするため。
ママが生きていた頃の家は、あたしが基礎教育課程を修了し、市民権を手にした時、家具ごと売ってしまった。それは、親父が家を、あたし名義にしておいてくれたから、できたことだけど。
あたしが《エオス》に乗れるのなら、もはや、《キュテーラ》に家を維持しておく意味はない。ママの遺品など、捨てられないものだけ、貸し倉庫に預けてある。
今では《エオス》が、あたしたちの家。それも、悪くない。船内の個人空間が限られているから、荷物はあまり増やせないけれど。
「あのう、ジュン、ええと」
エディは何か言いたいらしく、隣の椅子の上でもぞもぞする。
「ええと、今度、その、よかったら」
あたしがじっと続きを待っていると、ため息をついて、
「ごめん、何でもない」
と横を向く。
やっぱり、変な奴。
でも、船内でこんなおしゃべりができるのは、確かに嬉しい。ジェイクたちには、子供扱いで叱られてばかりだし。
船に仲間が増えるのは、いいことかもしれない。エディがこのまま、繊細な、はにかみ屋でいてくれるなら。
エディは本当に毎日、あたしの食べたいものを作ってくれる。
煮込みハンバーグ。海鮮ピラフ。スパゲティ・ボンゴレ。チーズカツレツ。餃子に春巻き。海老のチリソース。豚肉入りのちまき。チキンカレー。茄子の挽肉はさみ揚げ。
あたしの知らない料理も、次々に披露してくれる。海老と百合根のバター炒め。山芋の豚肉包み焼き。大蒜とマッシュルームのサラダ。つくしのお浸し。白身魚と貝の蒸し焼き。鰻のソテー。アスパラガスのビスマルク風ソース添え。
おまけに、あたしが言いつけられた銃の手入れや、装甲服の調整、貨物の点検なども、いそいそ手伝ってくれる。
「いいよ、あんたは食事の支度があるでしょ」
と断っても、にこにこして言う。
「もう下ごしらえは済んでいるから、大丈夫。きみはやっと手が治ったばかりなんだから、無理しないで」
自分だって、最初は、骨折抱えていたくせに。あたしが頼む前に、さっさと工具箱を運んでくれたり、堅いネジをゆるめてくれたり、重い迫撃砲を支えてくれたりする。
それでまた、あたしは、くらくらしてしまう。
なんで、こんなに親切なの。
あたしが凶暴化するのを防ぐため、ばかりとは思えない。だって、いかにも楽しげなんだもの。
あたしは不安になって、つい、ジェイクやルークの反応をうかがってしまう。
『こら、てめえの仕事を人に押しつけるな』
と叱られるかもしれないと思って。
ところが、それがない。エディがあたしの仕事を、ほとんど半分片付けてくれるのを見ているはずなのに、文句をつけてこない。
これは、どういうわけ。
あたしを《エオス》から追い出すための嫌がらせは、もうあきらめたというの。
それとも、これは新種の嫌がらせ?
そうかもしれない。エディの優秀さを、あたしに見せつけたいのかも。
『こんなにできる奴が入ってきたんだから、おまえはもう要らないよ。よくわかっただろ』
そう言われたら、反論できない。
そもそも、悪いのは、エディをあてにしてしまう自分なのだ。最近では、何をするにも、まず、エディの姿を探してしまう。
いったん甘える味を知ってしまったら、堕落するのは簡単だ、と思い知った。
(もしかしたら、わざと)
という考えすら浮かんだ。つまり、親父以下、みんなの共謀なのかも。
あたしがエディに頼るように仕向けておいて、それに慣れきった頃、がくんと支えを外すつもりでは。エディに一切の手伝いを禁じるとか、エディを去らせるとかして。
そうしたら、あたしはショックのあまり、《エオス》を降りるかもしれないから。
それなら、なお、このままではいけない。何とかしなければ。

あたしが悩んでいる間にも、《エオス》は雑多な貨物を積んで、寄港地から寄港地へ、宇宙空間を飛んでいた。
船体の大部分を占める倉庫区画には、たくさんのコンテナが詰まっている。
建設作業用重機、屋外作業用ロボット、金属精錬や加工用の大型プラント、有機物合成プラント、化学燃料合成装置、医療カプセル、気象観測衛星、警備衛星、大型トレーラー、海中探査船、通信中継ブイ。
いずれも、各星系の研究基地や探査基地に必要な品である。
それらを輸送中、非破壊検査にかける。必要なら、分解検査もする。もちろん、ちゃんと組み立て直す。荷主側がそれを認めなければ、最初から輸送の契約をしない。
滅多にないことだけれど、中に密輸品や危険物が隠されていたら、運んだあたしたちも、責任を問われるからだ。
間抜けな船長だと、貨物コンテナに密航者が隠れていても気がつかない、ということもある。
密航者ならまだしも、誘拐された被害者だったりしたら、大変だ。
また、もしかしたら、親父を殺すために、爆発物やウィルスなどが仕掛けてあるかもしれない。
貨物の点検作業の責任者はルークだけれど、エディという助手ができたので喜んでいるし、手伝うあたしも心強かった。
エディは《トリスタン》で痛い思いをしているだけに、こういう点検作業の重要性をよくわかっている。しつこい検査をするという評判がまた、あたしたちを守っているのだ。
「これ、このままエックス線かけていいの?」
「あ、その前に、超音波検査をしよう」
「こっちの消毒、真空曝露で足りる?」
「その後、マウスで表面検査をしよう」
「このコンテナ、何気圧で窒素充填しとく?」
「そうだね。0.2気圧でいいと思うよ」
何を尋ねても判断が的確だし、労力を惜しまない。エディを失って、軍は大損しているぞ。
そう感心してから、はっとして、自分の頬を叩く。
あたしも、これくらい役に立たなきゃいけない。するとやっぱり、通信教育だけでなく、きちんと大学へ行った方がよかっただろうか。
でも、それだと、何年も、親父の傍を離れることになるし。放っておくと、部屋でぶつぶつママの写真に話しかけて、一人で暗くなってるんだもの。
あたしはやっぱり、《エオス》にいたい。バシムやジェイクたちが、いくら頼れる男であっても、家族とは違う。いざという時、親父の盾になれるのは、あたしだけなのだから。
《エオス》に乗って早々、ぼくがびっくりしたのは、禁制の映画の上映会ではない。上映自体は、すぐ終わった。エイジが、
「いま、ジュンが通ったぞ」
と指摘した時に。
ジュンに知られたら終了、というのがルールなのだ。ジュンにはきっと理解されないと思うが、一種のゲームなのである。刺激的な映像に、どれだけ平然と耐えられるか、という。
「それに、男がどれだけ下劣か知ってた方が、あいつのためだ」
とも言われた。だったら、するなとは言わないが、ぼくを巻き添えにしないでほしい。
その映画の前に、先輩たちの間で交わされた会話の方が、ぼくにはショックだった。
「あ、そうだ。バシムから伝言。あいつ、来たとさ」
「そうか、もう月末だったな」
「了解」
「誰が来たんですか?」
話の見えないぼくが問うと、あっさり答えられた。
「ジュンの生理だよ」
ぼくはぎょっとして、後ずさった。
「な、なぜ、そんなこと、話題にするんです。ジュンのプライバシーじゃありませんか」
すると、ルークが難しい顔で言った。
「手加減するためだ。生理中に無理させるなって、前に、バシムに叱られた。たまたま生理中に、きつい整備作業やらせちまって」
「あ、それで……」
「あいつも、具合が悪い時はそう言えばいいのに、黙って無理するから、後で寝込んだりするんだよ」
「その期間中、冷えは厳禁だとさ。きつい稽古も無理。だったら、ルールとして明文化しておいた方がいいだろ」
と武道指南役のエイジが言う。
ぼくも、母と姉のアリサの会話を漏れ聞いたことがあるから、多少はわかる。治療が必要なくらい、症状の重い女性もいるらしいのだ。ジュンはそれほどではないというが、さすがに、格闘技の稽古は無理だろうし。
それにしても、ジュンにとっては、辛い話ではないか。毎月、男たちに、そんな報告をしなければならないとは。
「俺たちだってな、あいつの扱いには、苦労してるんだ」
と伊達男のルークが、苦い顔で言う。
「何も好きで、女の子を殴ったり、蹴ったりしているわけではない」
と空手家のエイジも、重々しく言う。
「まさか、本当に殴っているんですか!?」
「人聞きの悪いことを言うな。稽古の時だけだ。手加減はしているが、たまには、止めきれずに当たってしまうんだ」
まあ、武道の修業をしていれば、仕方のないことではある。
軍の女性たちも、男女混合の訓練では、体格の不利で苦労していた。それでも、最後には総合力の勝負になるから、精神面で強い女性たちが優位に立つことも、少なくなかった。
「最初のうちは、厳しく当たれば、泣いて船を降りると思ってたんだ。しかし、それはなさそうだと、わかってきたよ」
と、うんざり顔のジェイク。
「やっぱり、親父さんが大好きなんですね」
世間では毎年、『理想の男性』リストのトップ10に挙げられるくらいの人だ。娘から見たら、他の男なんか問題外なのだろう。
「筋金入りのファザコン娘だからなあ」
「いつになったら、父親離れすることやら」
「まあ、おまえは気長に頑張るんだな」
もちろんだ。日々、ジュンの傍にいられるだけで(たとえ、便利な下僕としか思われなくても)、世界の他の男たちより、はるかに有利なのだから。
《エオス》船内の仕事には、すぐ慣れた。輸送する貨物の目録と、実物の突き合わせ。装甲服や小型艇の整備。機械兵を使っての戦闘訓練。物資の補充の手配。
そういう仕事は軍でもしてきたから、経験を生かせる。時間的にも体力的にも、余裕があった。
一番大切なのは、ジュンに信頼してもらうことである。
ぼくがいくら、ジュンを守りたいと思っていても、それがジュンに伝わらなくては、効果が生じない。
違法ポルノの鑑賞会に加わっていたことをジュンに知られたのは、痛恨の大失点だったから、それを挽回するためにも、ぼくは必死で、ジュンの行く先につきまとった。
「装甲服の整備なら、半分受け持つよ」
「あ、それは重いから、ぼくが運ぶ」
「今日の晩ご飯、何がいい?」
「歴史のレポートなら、資料集めを手伝うよ」
「ちょっと休憩して、甘いものでもどう?」
ジュンは最初、露骨に迷惑顔をしていた。
「構わないで。あたしの仕事なんだから」
ぼくが、おべっかを使って、取り入るように思うのだろう。
「あたしが船長の娘だからって、気を遣ってくれなくていいんだから」
とも言われた。
「でも、ほら、下っ端同士だし、色々と協力し合う方が合理的だろう?」
女の子だから、見るからに痛々しいから、かばいたいのだ、などと言ったら、ますます怒られるに決まっている。
「一緒にしないで!! あんたの方が年上だけど、《エオス》では、あたしの方が先輩なんだからっ!!」
「あ、それはもちろん、よくわかってる……わかってます、先輩」
「わざとらしい呼び方、しなくていいからっ!!」
「あ、ごめん。じゃあ、ジュンでいい?」
「いいに決まってるでしょ」
「よかった、ありがとう」
有難いことに、ジュンは、何かで怒っても、後をひかない。毎日、仕事と勉強と格闘技の稽古で忙しいので、過ぎ去ったことなど、どうでもいいようだ。

「どうだね、エディは?」
航行中のある日、わたしが尋ねると、ジェイクは苦笑した。
「毎日、せっせと、誰かのご機嫌を取ってますよ。どうせなら、もっと楽な相手に惚れればよかったのに」
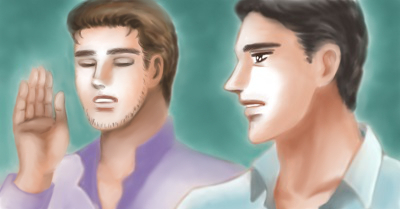
わたしはこれまで、ジェイクたちがジュンに苛酷な課題や業務を負わせ、その合間に、わざと下品な猥談を聞かせたりすることを、胃が痛む思いで、見ないふりしてきた。
違法ポルノの上映さえも、黙認してきた。うちで禁止しても、他の船では流通しているからだ。刺激を求めるのは男の本能で、禁じれば、地下に潜るだけのこと。
『ジュンを箱入りにするより、俗悪に免疫をつけてやらないと』
『いつも、俺たちが守れるとは限りませんからね』
という彼らの言い分にも、一理ある。
ジュンが、男という生き物の低俗さに呆れ、身を守る意識を高めてくれればいい。
とにかく、ジュンが《エオス》を降りてくれることが一番だ……と最初は思っていた。司法局の護衛に守られ、どこかの大学の寮で暮らしてくれればいいのだと。
しかし、ジュンはわたしの片腕になり、わたしを守ると言い張る。
母親が死んだ時、それが自分の新しい役割だと、思い定めてしまったらしいのだ。そんなこと、マリカは望んでいなかったはずなのに。
だが、マリカの葬式後、ジュンは長かった黒髪を、ばっさり切り落とした。可愛いワンピースは、一切着なくなった。言葉もどんどんきつく、短くなっていった。まるで、男になろうと決めたかのように。
『親父さん、ここは一喝して、追い出すべきですよ』
『ここは親父さんの船なんですから、子供は乗せないと言えばいいんです』
とジェイクたちに幾度も言われたが、わたしは結局、ジュンがこの船に居着くことを認めてしまった。
勝てるはずがない。たった一人の娘なのだから。
毎日、その姿を間近で見られることが、どれほどの喜びか。
それに、ジュンはマリカに似て、芯が強い。マリカの血は引いていないが、強靭な精神は受け継いだと思う。
これはできるか、あれはできるかと試しにやらせているうちに、操船技術も銃の扱いも、馬鹿にできなくなった。戦闘用装甲服を着せると、体格のハンデがなくなる分、目覚ましい働きをする。
若いうちに徹底して鍛えるということは、恐ろしいことなのだとわかった。もう数年したら、我々が戦闘指揮を受ける立場になるかもしれない。
バシムなどは、笑って言う。
『ダグ、いずれおまえは、ジュンの父親、という注釈で紹介されるようになるぞ』
いずれはジュンが、次の船長かもしれない。本当は、ジェイクに任せる方がいいのだろうが……彼もまた、これまでのクルーのように、結婚して、船乗りをやめるかもしれないし。
ジェイクもやはり、一種のはぐれ者である。エリート部隊である軍の情報部に納まりきりれず、辺境に出て、重犯罪者狩りのハンターになった。彼の経験こそ、映画にするべきだろう。いつか機密保持の期限が切れたら、わたしが映画会社に掛け合ってもいいくらいだ。
その時のパートナーだった女性に、いかなる理由でか去られてしまい、気力を失っていた時期に、バシムが《エオス》に勧誘した。今ではすっかり、頼もしい副長になっている。
ルークもエイジもきわめて優秀な男だが、大組織の歯車でいることに耐えられず、自由を求めてやってきた。
軍を辞めて放浪していたエディも、ここで人生を立て直してくれるといい。立ち直ってから《エオス》を出て行くのは、彼の自由だ。
それにしても、わたしだけではないのだな。女を見て『雷に打たれた』せいで、人生の針路を変える者は。
――二十年前、最初に宇宙空間で出会った時は、直立歩行するカブトムシの怪物のような姿だった。
黒い装甲皮膚に守られ、電磁波を感知する触覚を生やした、実験体13号。
仲間である19号と共に、自分たちの育てられた研究施設を破壊し、職員たちを殺して、脱出してきたのだ。
発狂レベルの殺人音波を発生する特殊器官。人間の十数倍の怪力。空を飛べる折り畳み翼。真空にすら耐えられる外皮。光さえ浴びていれば、長期の絶食にも耐えられる発電細胞。
普段はもの静かで理知的だが、いったん戦いを始めれば、まさしく黒い悪魔。追っ手の戦闘員たちが、片端からなぎ倒された。
だが、彼女の心は人間だった。人間社会に交じり、平和に暮らしたいと願っていた。
独立心の強い19号は、追っ手から奪った船で宇宙の彼方に去ったが、13号は亡命者として、惑星連邦政府に保護された。
そして、苛酷な逆改造の処置を経て、人間の姿になりきったのだ。
いや、普通よりはるかに美しい、白い天使。
わたしは隔離施設の面会室で、見舞いの花束を取り落とした。柔らかいプラチナの髪、青い目をした、この女性は誰だ。
仕事でしばらく離れていたので、その間の変化を知らなかったのだ。白いワンピースの美女は、首をかしげて微笑んだ。
『わたしの姿、おかしい?』
その声だけは、聞き覚えがあった。13号に間違いない。わたしは彼女を番号で呼ぶのが心苦しかったので、マリカという名前を進呈していた。
『いや、あの、髪……もう、そんなに伸びたのかと』
『これ、かつらなの』
マリカはすっぽり、かつらを外した。ほんのわずかな和毛が、卵のような頭に生えてきている。
『いずれは、こうなるはずですって。その頃には、町へ出られるそうよ。付き添いがいれば、好きに歩いていいんですって。買い物したり、パフェを食べたりできるのよ』
『そうか。よかったね』
わたしも笑ったが、同時に、身内が熱い涙で満たされたような気がした。
異形の怪物の中に隠されていた、可憐な淑女。
普通の人間になりたいがために、自分を創った組織と望まぬ戦いを始め、数千光年の距離を、苦労しながら逃げてきたのだ。
彼女が望む幸せを、わたしが与えたい。たとえ、この世に遺伝子を残すことを許されない、違法な人造生命であっても。
障害があるからこそ、余計に燃え上がったのだろう。マリカが結婚を承諾してくれるまで、がむしゃらに押しまくった。
彼女は、わたしの友情に感謝してくれたが、結婚までは望んでいなかった。そんなことは、自分には無理だと、最初からあきらめていた。ただ、市民社会の片隅にいられればいいと。
そういう女だからこそ、余計に愛しい。
家族や親戚がこぞって反対しても、言い争った勢いで絶縁することになっても、あの頃のわたしは平気だった。仕事があり、仲間もいて、そこに愛する女性が加わる。何の不足があるだろう。
やがてジュンが生まれ、幸福は完璧になった。ジュンとマリカは、血のつながらない母娘だが、強い絆で結ばれていた。長いわたしの留守、二人で笑い合い、励まし合って過ごしてくれた。
マリカを失った今でも、わたしにはジュンがいる。だから、自分は他のどんな男よりも、幸福だと思っている。
たとえ〝連合〟の懸賞金リストに載せられていても、ジュンさえ無事に育ち、幸せになってくれれば。

「――それにしても、エディの女神が、ジュンとはな」
わたしは自分の部屋で、毎日のように、マリカの写真に話しかける。
「いくら崇拝されたところで、あのジュンが、ふわふわ恋愛なぞするものか。そんな娘なら、苦労はないよな」
すんなりした白い腕に、幼いジュンを抱いている懐かしい姿。この頃はジュンもまだ、髪に赤いリボンを結んで、白いワンピースを着ている。現在の殺伐たる姿と比べて、泣けてくる。
写真のマリカは、ややカールしたプラチナブロンドを長く伸ばし、青いリボンで束ねている。青い目に、青いドレスがよく似合う。
(ジュンにはずっと、苦労をさせたわ。可哀想に、親を心配するのが、自分の務めだと思っているのよ)
わたしには、マリカの言いそうなことがわかる。だから、こうやって会話を続けられる。
「そうだな。年頃の娘が、男ばかりの輸送船になど、乗る必要はないのに」
(あなたが悪いのよ。本当は、あなたがジュンに甘えているの)
「すまない。反省している」
それでも、ジュンに、船から降りろとは命じられない。今となっては、わたしが、その寂しさに耐えられないだろう。
本当は、マリカが衰弱して入院していた最後の半年、わたしも《エオス》を降りて、一緒に付き添えばよかったのだ。船は、ジェイクたちに任せられたはずだ。
なのに、仕事を言い訳にして、たまにしか帰港しなかった。耐えられなかったのだ。枯れ縮んでいくマリカを、間近で見続けることに。
見ないでいれば、回復するかも、という幻想が持てる。
短い通話だけなら、演技で笑顔を保てる。
つくづく、卑劣だった。たった十二歳のジュンに、一人で母親を看取らせるとは。マリカも内心では、わたしの卑劣を恨んでいたかもしれない。
今でも、英雄と呼ばれる都度、ひるむ自分がいる。勇敢なのは、追っ手と戦うことを決め、逆改造の処置を望んだマリカであって、わたしではない。
せめてこれから、少しはましな父親にならなくては、マリカに顔向けできない。
そう思うそばから、エディのような青年が現れると、ジュンのために喜ぶどころか、ピリピリと身構えてしまうのだから、情けない。
もしかしたら、大人になるのは女だけであって、男というのは、最後まで真の大人にはなれないのかも。
(エディ君のこと、わたしはいいと思うわ。ジュンにも、甘やかしてくれるボーイフレンドが必要よ)
「しかしだな、同じ船で寝起きしていて、危険じゃないか?」
若い男の頭の中など、知れている。自分がそうだったから、よくわかるのだ。すぐ隣の部屋に好きな娘が寝ていたら、どんな妄想が湧き起こるか。
妄想だけで済めばいいが、実際に何か行動を起こしたら、どうするのだ。
しかし、写真の中のマリカは依然、笑っている。
(ジュンがエディ君を気に入れば、それでいいのよ)
女親は平気かもしれないが、男親としては、胃がねじれるような気がする。
「ジュンに何かよからぬ真似をしたら、射殺してやるぞ」
(あらあら、困った人ね。いつまでも、小さな娘じゃないのよ。いつかは恋人ができないと、ジュンが不幸じゃないの)
わかっている。
はねっ返りの頑固娘でも、もうじき十六になるのだ。
これからも次々、男が寄ってくるだろう。一人や二人、射殺したところで、状況は変わらない。いずれ、誰かがジュンの心を射止めてしまう。
つい、ため息をついてしまった。
「マリカ、きみがいてくれたらな……」
そうしたら、ジュンが巣立った後、二人で呑気な隠居暮らしに入れただろう。
「幽霊でもいい。出てきてくれないか」
未練がましく、わたしは写真に頼む。マリカは微笑んでいる。
(わたしは生きたの、十分に)
だが、あんな無理な逆改造をしなければ、きみはもっと長生きできた。きみ本来の肉体は、宇宙空間でも活動できる、強靭な戦闘兵器だったのだから。
きみが市民社会で暮らすには、〝黒い悪魔〟めいた装甲皮膚を剥がし、体細胞に共生している特殊なバクテリアを、薬剤で強引に除去するしかなかった。
その結果が、わずか十五年の余生。
きみたちを創った組織《ゼラーナ》は、まだ存続しているはずだ。
命を弄ぶ連中に、いつか、天の裁きが下ることはあるのか。
それとも、悪は栄えるのが、宇宙の摂理か。他者を打倒していく強者を、悪と呼ぶのだとすれば。