
ミッドナイト・ブルー グリフィン編 後編

馬鹿げている。
自分でそう思う。
わたしはかつての恋人を去勢し、死に追いやった女ではないか。そのことを、自ら宣伝材料にしたではないか。おかげで辺境中から、男嫌いのアマゾネスと恐れられている。それがなぜ、一人の男を気にするのだ。
だが、わたしがどれだけ粗探しをしても、シヴァはまともな男だった。張議員が暗殺された時は、本気で怒っていた。犯人の学生たちは、いずれ本当に冷凍されてしまうだろう。
シヴァ自身の私生活は、本当に質素なものだった。食事だけは人一倍食べるが、それも、肉体を維持するのに必要な分だけ。
服は、用意されているものを、交互に着るだけだった。普段着レベルのシャツとズボン、それに革のジャケット程度で、何の不満もないらしい。リナがデザイナー物のスーツなどを押し付けようとすると、そっぽを向く。
着慣れてくたくたになり、気を遣わないで済む衣類で十分、ということらしい。
性的な奉仕をしてくれるバイオロイド侍女は、欲しがらない。雑用は、心を持たないアンドロイド侍女で十分だという。
セレネやレティシアの誘惑も、依然、拒絶し続けていてる。リナがすり寄って甘えても、それに付け込むこともしない。それどころか、リナを妹のように見て、躾けようとしているくらい。
毎日、憮然としたままジムで運動し、事務局から上がってくる報告書を読み、要人暗殺計画について、わたしと議論する。夕食の後も、夜中まで資料を読み込み、気になる点を確認しているようだ。
ほとんど、仙人のような清貧さだと言える。それで平気なのは、たぶん、『成り上がり者』ではないから、なのだろう。
最初から資産家の一族の中に生まれ、権力も財力も約束されて育ったから、そういうものに飢えていない。
それどころか、恵まれた環境を捨てて、犬だけを相棒にする暮らしを選んだ男。
仕事の上では、明快で論理的だった。しゃべる言葉に、嘘がない。
というより、嘘をつくという、面倒なことを嫌っている。
そういう点、彼が監視している従姉妹のリリーによく似ていた。リリーもまた、ハンター稼業の中、あちこちで衝突を起こす女だが、率直で悪意がないので、喧嘩した相手も、結局は彼女の言い分を認めてしまう。
シヴァもまた、性格の素直さが隠せない男だ。年長のルワナには敬意を払い、リナのことは、戸惑いながらも可愛がっている。
「おい、仕事の時のスカートは、ミニじゃなくて、膝丈にしておけ」
「どうしてですか? わたし、ミニが似合うでしょ?」
「そういう問題じゃない。グリフィンの秘書として、威厳が足りないだろ」
「わかりました。ルワナさんみたいな、スリットの入った膝下のタイトがお好みなんですね!! じゃあ、明日からそうします!!」
「だから、違う。好みの問題じゃない。おい、ルワナ、こいつに秘書の心得を説明してやってくれ!!」
傍で聞いていると、笑いをこらえるのに苦労するくらいだ。
茜という娘を引き取った時も、こんな風だったのだろうか。
リザードからの報告書では、初恋の従姉妹であるヴァイオレットにそっくりだったので、衝動的に娼館から買い取った、ということだったけれど。
気がつくと、わたしはシヴァを目で追っていた。
どこか遠くを見るような横顔、広い肩、力強い指、無造作な歩き方。
そして、深みのある低い声。耳元で何かささやかれたら、きっと震えてしまう。そんな機会、まだ一度もないけれど。
わたしより一回り大柄な男だが、重量型ではない。必要な筋肉はついているけれど、身長のせいで目立たないのだ。どちらかといえば、痩せている部類だろう。
ただ、最高水準の強化体であることは納得した。一度、竹刀を持って、リナの稽古相手をしている様子を見たからだ。リナがどんなに打ちかかっても、むきになって体当たりしようとしても、シヴァは全て軽く受け流していた。
リナは無邪気な娘に見えても、戦闘用の強化を受けているし、リザードの元で、かなり厳しい訓練を受けているのに。
わたしは学生時代、空手や剣道で段位を取っているし、軍に入ってからも稽古を積んでいたから、動きを見れば、他人の強さの水準はわかる。自分がリナと戦ったら、勝てないだろうということもわかっている。
そのリナが、シヴァを相手にすると、まるきり子供扱いなのだから。
やはり、後からの実験的な強化では、遺伝子設計の段階から始まっている、根本的強化に届かないのだろう。
シヴァがアンドロイド兵士を相手に、軽いトレーニングをしているのも見た。彼は、わたしに見学されるのは厭だったろうが、ルワナに同行してもらい、
「きみの身体能力を見れば、リリーの身体能力を知る手がかりになる。正しい認識がないと、正しい作戦が立てられない」
と言って押し切ったのだ。
軽い稽古といっても、アンドロイド兵士が数体、シヴァの蹴りで吹き飛ばされて、修理工房行きになった。隣で見学していたリナも、自分には無理だと認めた。リナならば、武器なしでアンドロイド兵士を倒すことはできない。
しかし、それだけ強くても、意味がないとシヴァは自嘲する。
「最高幹部会には、昆虫採集の虫みたいに捕まったからな」
それは仕方がない。
個人の強さと、組織の強さは別次元の話。
一度、わたしが相棒のショーティのことを尋ねたら、彼は憮然として、そっぽを向いた。何も話したくないらしい。
わたしと会話してくれるのは、グリフィンの職務に関することだけ。それも、仕方なしの様子を隠さずに。
別に構わない。
わたしだって、彼がわたしを敵視するのは理解できる。
ただ、こっそり思うだけだ。あの広い背中にもたれたら、どんなに気持ちがいいだろう。
あの大きな手に、もし、そっと撫でてもらえたら、どんな感じがするだろう、と。
シヴァに会えるのは、週に何度かのことだ。
ルワナの監督下で、グリフィン事務局が本格的に動き始めたので、わたしが口出しすることは、あまりなくなった。大きな方針だけ、シヴァと協議して確認する。
わたしが《フェンリル》の紋章付きの車で、しばしばこの船――グリフィンの紋章付きの大型艦――に出入りするので、他組織では、グリフィンというのはジョルファの別名ではないか、という噂も生まれているらしい。
その噂は放置しておけ、とリザードは言う。〝連合〟の頂上付近の人物については、霧に包まれている方が都合がいい、と。
シヴァと向き合って、懸賞金リストの人物について話す時は、セレネとレティシア、ルワナとリナが同席するのが有り難かった。他人の目があれば、わたしは冷徹な女戦士でいられる。
たまたま、彼女たちが退席してしまい、シヴァと二人で会議室に残されたりすると……途端に、会話に困ってしまう。
もし、わたしがシヴァの好きな映画や小説のことなど聞いたら、怪訝な顔をされるだろう。ましてや、子供時代のことなど聞けない。絶対、弱点を探ろうとしているのだと思われる。
室内に妙な沈黙が降りてしまうと、シヴァも居心地が悪いらしい。早く誰か戻って来ないかと、内心で念じているのがわかる。
前は信じなかったことを、今では信じられるようになっていた。シヴァは本当に、ハンター稼業の従姉妹たちが大切なのだ。だから、懸命にグリフィンの職務を果たしている。
それならば、引き取ってすぐに死なせてしまったバイオロイドの娘のことも、本気で大事にしていたに違いない。シヴァがその娘のことを愛した分だけ、我々が憎まれるのは、仕方のないことだ。
そう、頭ではわかる。襲撃を指示したのはリザードであって、当時のわたしは、シヴァの存在すら知らなかったのだとしても。
ただ、それでこの先、いつまでもシヴァに嫌悪され続けるというのは……理不尽ではないか?
でも、だからといって、シヴァにどう話せばいいのだ? 過去のことはなかったことにして、我々に心を開いてくれと頼むのか?
今でも最高幹部会は、彼の親友を人質に……犬も人質と言うべきか……取っているというのに。
だめだ。わたしが何を言っても、シヴァを怒らせる。
わたしはあくまでも『彼のライバル』、『潜在的な敵』にすぎない。
わたしが今でも、リザードのことを警戒し続けているのと同じだ。温厚に見える彼の、芯の冷酷さは、わたしが誰よりよく知っている。命がけで直訴しなければ、わたしはとうに、違法ポルノの撮影現場で死んでいただろう。
シヴァから見れば、わたしも似たようなものに違いない。わたしは必死になって、自分の恐ろしさを世に広めてきたのだから。

「グリフィンさま、お待たせしました」
リナがお茶のワゴンを押して戻ってくると、シヴァはほっとした様子で、リナに話しかける。今夜は何が食べたいとか、後で格闘技の稽古をつけてやるとか、気晴らしのドライブに出ようとか。
彼が素顔をさらさない限り、行動は自由である。市街を車で走っても、危険はまずない。《フェンリル》のマークを付けた車ならば、特に目立つこともない。わたしの部下たちが大勢、同種の車で動いているからだ。
シヴァの車がいったん《フェンリル》のビルに入り、地下駐車場と地下の迷路を経由してから地上に出れば、部外者には誰が乗っているのか、わかりはしない。
「ジョルファさま、事務局との調整がつきました。この作戦でいけそうです」
セレネやレティシア、ルワナも戻ってきて、また議論の続きにかかる。
グリフィン事務局のオフィスは、この《ルクソール》の市街にあるが、そこに出入りしたり、通信で打ち合わせしたりするのは、ルワナやリナの役目だった。
シヴァが直接、事務局のスタッフに顔を見せることはない。声すらも聞かせない。必要ならば、合成音声を使う。
グリフィンはあくまでも、謎の人物でなければならないからだ。彼の素顔を知る者は……ことに、情を知る男だなんて素顔は……最小限でいい。
するべきことが済むと、わたしはセレネとレティシアを置いて(彼女たちはまだ、シヴァにまとわりつくことに飽きていない)、先に市街地のオフィスに戻った。
移動時の護衛はレティシアの部下たちがするから、問題はない。今日のうちに済ませたい雑用や、決定するべき事項が残っている。
一般市民は信じないだろうが、違法組織の幹部は忙しいのだ。週に三日か四日しか働かず、たっぷりバカンスを取る中央の市民より、はるかに勤勉である。
思い切って部下に任せれば別だが、わたしのように、事業の隅々まで把握したいと思うと、丸一日、仕事から離れることすらできない。精々、たまに半日の休みを取るくらい。
夕食をはさんで、夜の九時まで、繁華街にあるオフィスで過ごした。それから車に乗って、十分ほどの距離にある拠点ビルまで戻る。
ここは、わたしの部下たちの宿舎になっている、円形のドーム型施設である。辺境では、男子禁制の女の城として知られている。
外郭は武装要塞そのものだが、中央部には広い円形庭園があり、季節の花が咲き乱れている。
昼間は、その庭園に、半透明のドームから外光が降り注ぐので、芝生の広場で食事をする者もいれば、昼寝をする者もいる。木陰にハンモックを吊るして、読書する者もいる。庭園の一部にある、温水プールで泳ぐこともできる。
内情は、女子校の寮のようなものだ。外では冷然と振る舞う女たちも、ここに戻ると寛いで、仲間とキャアキャアやっている。
他組織の幹部に口説かれた自慢話をしたり、出先で出会った失礼な男について怒ったり、センスのいい衣装デザイナーや、シェフのいる店を見つけたと報告したり。
もしも彼女たちがシヴァを見たら、どんな騒ぎになるか、容易に想像がつく。みんな、いい男には飢えているのだ。
だから、シヴァと接触するのは、セレネとレティシアだけで十分だった。彼女たちも、その特権を守りたいから、シヴァのことは決して口外しない。
「お帰りなさいませ、ジョルファさま」
「お疲れさまです」
「ああ、ただいま」
すれ違う部下たちと挨拶を交わし、中心部の庭園を見下ろす、三階の私室に入った。上着を脱いでアンドロイド侍女に渡し、奥の浴室に向かう。
わたしは他の贅沢はしないが、浴室にだけは凝っていた。玉砂利の小道の中に飛び石を配し、緑の植え込みを作り、温泉地の露天風呂のようにしつらえてある。
部屋を暗くし、天井に星空を投影すると、本物の露天風呂と変わらない。入浴剤でミルク色に濁った湯に浸り、手足を伸ばした。
今日も一日、無事に終わったわけだ。
組織はいつも通りに運営されているし、グリフィンの業務にも、特に問題はない。暗殺志願者を二名ばかり援助しているが、ぎりぎりで暗殺に失敗するように仕組む予定である。
そう簡単に、市民社会の中核人物を殺させるわけにはいかない。市民たちが絶望したり、自棄になったりしてはいけない。恐怖と希望。巧くバランスを取って、現在の体制を維持しなくては。
ミルク色の湯の中で、自分の腕を撫でた。皮膚はなめらかで、筋肉に支えられた張りがある。
暦の上では四十歳を過ぎたが、リザードの部下になってから、最新の不老処置を受けているので、最盛期の体力そのままだ。
強化体ではないが、何も不自由はない。頑丈な骨格と鍛えた筋肉は、そこらの男顔負けだ。
子供の頃から、周囲の男の子たちに、ゴリラ女という、わかりやすい渾名で呼ばれていた。
自分が可憐な美少女でないことを、たまに寂しいと思うこともあったが、おおむねは満足していた。同じ学校の少女たちには慕われ、頼られていたからだ。
サッカーで走り回り、空手や剣道を習った。体を動かすことが、単純に好きだった。深い考えのないまま、軍人を志した。そして、軍の中で出世しようとしていた。あの男に会うまでは。
お茶や食事に誘われ、花を贈られ、甘い言葉をかけられて、驚いた。自分がまるで、いい女であるかのように扱われるなんて。
でも、それは新鮮な驚きだった。優しく扱われて、初めて気づいた。自分が、女として飢えていたことに。
いったん男に甘える味を知ると、わたしは簡単に堕落した。その心地よさを、愚かにも、愛情と勘違いした。それは単なる、雌としての満足だったのに。
おかげで、高い授業料を払った。
地獄の二年間。
女としてのわたしを愛してくれた男はいなかったのに、あんな映画にだけは使われて。
いったん世界に撒かれてしまった映像は、もう消滅させることはできない。
こうしている今も、世界のどこかで、誰かが、わたしが凌辱されている姿を楽しんでいるだろう。
つい、怒りと絶望の真っ暗な日々を思い出しそうになり、慌てて振り払った。
本当に忘れてしまうことはできないが、普段は、意識の外へ飛ばしておく方がいい。
負の記憶に囚われると、消耗して、生きる気力を失ってしまう。魂が病み、衰えてしまうのだ。
そうして、多くの女たちが死んでいった。映画の撮影現場で、あるいは娼館で。違法組織の日常の中で。
わたしは死なない。生き続け、戦い続けてやる。
さもないと、世界はいつまでも変わらない。
男たちに支配させておいたら、女は永遠に蹂躙され続ける。
シヴァのことをこんな風に思うのも、しばらくのことだ。彼には絶対、わたしの内心を悟らせない。
これは、動物の欲望にすぎないからだ。男にすがりたい、猫のように甘えてみたい、絡み合って甘い声を上げたいなどと思うのは。こんなものは、意志の力で押さえ込める。過去の大失敗を、二度は繰り返さない。
わたしの成功には、辺境の女たちの未来がかかっているのだから。

ある晩、俺が執務室から戻ってきたら、寝室に人の気配があった。
リナだろう。懲りずに新しい服を作っては、俺に着せようとしているから。
青や水色はともかく、ピンクやラベンダーを着せようとするのは、やめてほしい。俺は暗い色でないと、落ち着かないのだ。
「リナ?」
妙だと思ったのは、室内の明かりが、ベッド脇の小さな夜間灯だけになっているからだ。
「はい」
小さな声で返事があり、リナの居場所がわかった。なぜか、俺のベッドに潜り込んでいる。しかも、上掛けをあごまで引っ張り上げて。
「何をしてる!!」
つい、叱りつける口調になった。小娘といえども、女の部類だ。紛らわしい真似は困る。
「あの……わたし……ただ……」
リナはおずおず、上掛けを肩まで下げた。裸の肩が見えたので、ぎょっとする。これがセレネやレティシアなら、さほど驚かなかったと思うが、何しろリナだったから。
「何の真似だ」
離れて立ったまま、厳しく問うと、リナは日頃の威勢はどこへやら、身を縮めるようにして言う。
「あの、だって……こういうことも、秘書の仕事の一部だから……」
何をぬかす。リザードの元で、そんな教育を受けてきたのか。秘書は、愛人と同義語だとでも?
「他組織ではそうかもしれんが、ここでは違う。俺が一度でも、そんなことを要求したか?」
溶解弾をぶつけられないよう、紳士として振る舞ってきたはずだ。あくまでも、俺の理解する紳士に過ぎないが。
「していませんけど……でも……」
「誰かに命令されたのか? ルワナかリザードにでも?」
「いいえ……」
「じゃあ、出て行け。そういう真似をするのなら、二度と俺の部屋には入らないでもらう」
いくら『恐怖のアマゾネス』だと思っていても、セレネやレティシアのようないい女の誘いをかわし続けるのは、かなり苦しいやせ我慢なのだ。いい加減、もやもやが溜まっているというのに、リナまでがこれでは、我慢の限界を超えてしまうではないか。
そうなったら、ジョルファがどんないちゃもんをつけてくるか、わからない。
いちゃもんで済めばいいが、グリフィンの地位を追われるのは困る。
ここにいてこそ、紅泉や探春の動静が詳しくわかるのだから。〝連合〟が張り巡らせた情報網は、俺とショーティが即席で作った情報網より、はるかに緻密で役に立つ。
リナは殴られたような顔になって、おずおず問いかけてきた。
「グリフィンさま、わたしのこと、お嫌いなんですか……?」
そういう問題ではない。俺が周囲の女に手を出したら、規律も何も、ぐずぐずになってしまう。せっかく〝グリフィン〟になりきろうとしているのだから、余計なトラブルはお断りだ。
「おまえはリザードの秘蔵っ子で、俺の看守だろ。看守としては付き合えるが、それ以上に思えと言われても、無理だ」
「看守だなんて。違います」
「じゃ、秘書だ」
「ちが……」
「違うなら、出ていけ。秘書でないおまえに、用はない」
するとリナは顔をゆがめ、裸の肩を見せたまま、べそべそと泣き出すではないか。
まったく、小娘のくせに。変なところだけ、女みたいな真似を。
こんなリナは見たくない。怒って俺に溶解弾を投げてくる方が、ずっとましだ。
「いい。俺が出ていく。戻った時にまだいたら、叩き出すからな」
おかげでこちらは、プールにでも行って、頭を冷やす他ないではないか。
いや、その後でさえ、女の匂いが残るベッドで、おとなしく一人寝できる気がしない。かといって、リナを呼び戻したりしたら、グリフィンの威厳など丸潰れだ。
そうだ、外を走ろう。惨めに捕まって以来、バイクでの外出はしていなかったが、もういいはずだ。グリフィンとしての俺は、都市の警備システムに守られるのだから。

「グリフィンさまが、バイクで市街を走り回っています」
という報告を受けた時は、驚いた。
「しかし、今夜は雨だろう?」
警備管制室にいるレティシアは、顔を曇らせている。
「ええ、先ほどから降っています」
《ルクソール》の1G居住区は広く、毎日のように、どこかで人工の雨を降らせているが、今日は降雨の範囲が広い。わたしは既にベッドに入り、就寝前の習慣である読書をしていたが、急いで起き出し、都市の警備システムからの転送画像を確かめた。
間違いない。ヘルメットにライダースーツという姿で大型バイクを駆っているのは、シヴァだ。顔が見えなくても、体型や姿勢でわかる。もう、それだけ彼と馴染みになってしまった。本降りの雨の中、何台もの車を追い越して、幹線道路を走っていく。
「途中までは大型トレーラーだったのですが、その車から単独で降りてきて、もう三十分近く、走ってらっしゃいます。雨なのにあんな速度で、危ないですわ」
心配丸出しで訴えてくるレティシアに、
「わかった。後はわたしが処理するから、きみはもう休んでいい」
と言い渡した。
レティシアは、できれば自分で彼を追いかけ、連れ戻したかっただろうが、わたしの指図に抗議はしなかった。ただ、いくらか不審げな顔をしただけで。
それにしても、ルワナは、このことを知らずに眠っているのか。それとも、問題はないと判断しているのか。
バイクの運転技術はあるのだろうが、違法都市のことである。単身では、どんな事故や災厄に見舞われないとも限らない。車に収容するべきだ。
本当は、シヴァが予期せぬ災厄で死ねば、わたしが次のグリフィンになれるのだけれど。
そんなことは、とっくに望まなくなっている。彼が存在しない世界より、存在する世界の方がいい。たとえ、彼がわたしを嫌っていても。
手早く身支度して、ドーム施設から中型トレーラーで出た。人工の季節は早春であり、凍るように冷たい雨だ。シヴァは強化体だから、この寒さでも平気なのか。
彼がバイクで走っていく方角に、車で向かった。今は市街地ではなく、緑地帯の周遊道路に入っている。
後ろから追うのではなく、先回りして捕まえるつもりだった。向こうの方が、機動性では勝るのだから。
それにしても、無茶な走り方をする。この雨の夜中に、こんな速度で林道を飛ばすとは。隠れ暮らす生活に飽きたのだとしても、せめて車で走ってくれないか。
それでも、夜の闇の中でシヴァの軌跡を追うのは、密かな快感だった。運転席の地形図に出る彼の位置表示が、彼そのものに思える。
グリフィンの正体を知る者は限られているから、彼を追えるのも、止められるのも、わたしだけ。
もちろん彼は、途中でこちらの接近に気づいた。深い森林を貫く林道の一点で、静止したから。わたしの車が現場に近づくと、大きな木の下で、バイクごと雨宿りしているのがわかる。
手袋もライダースーツも防水だろうが、それにしても、わざわざ雨の晩に走らなくても。
わたしは木から五十メートル手前で車を停め、アンドロイド兵を使いに出した。けれど、兵は虚しく濡れて戻ってくる。
「邪魔するな、とのことです」
やれやれ。
わたしはフード付きの防寒コートを着て、車から降りた。たちまち、コートの表面に水の流れができる。ほとんど、氷雨と呼んでいいような雨だ。
濡れた砂利を踏んで、大木の下にいる男に近づいた。車のライトがこちらを照らしているから、わたしだということはわかるはずだ。
「きみは、単独で外出していい身ではないはずだ。おとなしく、一緒に戻ってもらおう。どこに偵察虫がいるか、わからない」
あえて、彼の名を呼ばずに説得した。他組織の放った偵察虫が、たぶん、あちこちに潜んでいる。それなのに、シヴァはヘルメットの下から不機嫌に言う。
「放っておいてもらおう。俺の命だ」
この、わがまま者が。従姉妹の命を預かっている立場のくせに。
「そうはいかない。船に飽きたのなら、うちが経営するホテルにでも泊まってもらおう」
「断る」
ふん。それで、わたしがあきらめるとでも?
「では、好きに走るといい。こちらの兵が、隊列を組んできみの前後を走る。天下の公道だから、誰がどう走っても自由だからな」
それで彼はようやく、わたしから逃れるのは無理だと悟ったらしい。
「わかった。おまえの車に乗ればいいんだろう。俺の車は、繁華街の地下に置いてきたからな」
そして、雨の中、バイクから離れてわたしの方に歩いてきた。それだけで、わたしの動悸が増すことを、彼は知らない。
兵にバイクを収容するよう命じてから、シヴァの後を追った。すると彼はトレーラーの扉の前で、こちらを見て立っている。雨に打たれるのだから、先に車内に入ればいいのに。
もしかして、わたしを先に入らせようというのか? まさか、わたしを『いたわるべき女』だと思っているわけではないだろう?
とにかく、暖かい車内に戻るとほっとした。濡れたコートを脱いで、アンドロイド兵からタオルを受け取り、シヴァにもタオルを放る。
彼はヘルメットを外すと、ライダースーツの肩や腕を、ざっとタオルで拭った。その動作も男らしくて、つい見とれてしまう。もちろん、彼がわたしの視線に気付づかない角度で。
シヴァはやがて、どさりとソファに座り、タオルを放り出して、疲れたようなため息をついた。強化体のくせに、なぜ疲れているのだ?
「ちょっと、車を出すのは待ってくれ。どこへ行くか考える」
彼の言葉に、わたしは疑問を抱いた。船に帰りたくないのか?
「ルワナに、何か叱られでもしたか。とにかく、きみを確保したと、連絡だけはしておくぞ」
ルワナが既に眠っていても、船の管理システムに伝言を入れておけば、それでよい。
それから兵に、熱い飲み物を命じた。何か手元にあれば、少しでも気まずさが誤魔化せる。
ブランディ入りの紅茶が運ばれると、わたしもシヴァの前に座った。真正面ではなく、斜めにずれた位置に。車は林道に止まったままだが、どうせ他に通りかかる車などないから、問題はない。
「おまえたち、夜中でも俺を監視してるのか」
「当たり前だ」
「それにしても、軍団長が自分で出てこなくてもいいだろう。レティシアでも寄越せば済むのに」
軍団長か。アマゾネス軍団という意味だろう。
「それでまた、彼女に口説かれたいか? それは、邪魔をして悪かったな」
カップを持ったまま、シヴァは嫌な顔をした。彼のこういう顔を見るのが、わたしの密かな楽しみになっている。嫌われていると認識できると、逆説的に安堵するのだ。
「おまえの部下に俺を誘惑させるのは、いい加減にしたらどうだ」
誘惑させる? 彼女たちが個人で、楽しんでしていることを、わたしの命令だと思っているのか?
「わたしがなぜ、そんな真似をさせると思うんだ?」
「俺が品性下劣な男だと、証明したいんだろ。おまえの世界観では、男は全員、下劣な獣なんだろうから」
そうか。そういう風に見られていたわけか。
「全員とは思っていない。わたしは世間に、まともな男が存在するのを知っている。これでも市民社会で、普通に育ったからな。ただ、辺境では、まともな男は、限りなくゼロに近いと判定しているだけだ」
「そうか。それじゃ、全世界の男を絶滅させようとまでは、思っていないわけか」
痛烈な皮肉が込められていた。シヴァはわたしがそこまで、憎悪に凝り固まっていると思うのだ。
確かに、男種族に対する嫌悪と軽蔑は強い。違法ポルノの大半は、色々な偽装を通じて、市民社会の男たちに買われているのだ。その売り上げが、違法組織の大きな資金源になっている。
そうと知っているくせに、政治家も官僚も司法局長も、本気で取り締まりに乗り出さない。一度でも違法ポルノを買った男たちを逮捕して回ったら、社会の機能が停止するからだ。
「そんなことは、不可能だ。人類がこれだけ宇宙に散らばってしまってから、男だけ絶滅させようなんて」
「それじゃ、俺一人だけでも抹殺したいだろうな……俺がいなければ、グリフィンの地位は、おまえのものらしいから」
わたしは後悔した。十代の女の子みたいにどきどきして、こんな雨の夜中に、はるばるシヴァを迎えにやってくるなんて。
「きみが大きな失策をするまで、わたしには手出しできない。最高幹部会のご指名なんだからな。どこへ行きたいのか、言ってくれ。そこまで送る」
努力して冷淡に言うと、シヴァは上体をソファの背に預けた。
「せっかくだから、頼みがある……リナを、そっちで引き取ってくれ」
驚いた。リナだけは、お気に入りのはずではなかったのか。
「あの子が、何か失敗でも? 一生懸命勤めているのに」
「その、一生懸命が困る」
シヴァは説明をためらったが、言うしかないと覚悟したようで、苦々しく白状した。
「今夜、俺の寝室に裸でいた」
あ。
「そんなことを要求したつもりはないんだが、何か誤解があったらしくてな。叱りつけたら、泣き出しやがって」
ずきんとした。リナがとうとう、そんな挑戦を。
さすが、若い子は恐れ知らずだ。それでシヴァは、船から逃げ出してきたわけか。
可哀想に。リナにとっては、父親代わりのリザードの他に、辺境で初めて出会ったまともな男だろう。捨て身でぶつかったのに、叱られて、置き去りにされて。
確かに、シヴァとリナでは、無理な組み合わせだと思うが。しかし……もう何年かすれば、リナも大人になるはずだ。
「なぜ、抱いてやらなかったんだ」
と言ったら、シヴァはぎょっとしたようだ。
「できるか!! まだ子供だぞ!!」
わたしは内心、可笑しくなった。こういう面では、シヴァは鈍すぎる。
「あの子がきみに恋しているのは、きみ以外の誰の目にも明らかだ」
と言ったら、愕然としたようで、気の毒なくらい狼狽えている。
「そんなはず、あるか。あのガキ、何度も俺に溶解弾を……」
「それだけ、きみを意識しているんだ」
誰かが気になって、些細な言動で、一喜一憂してしまう。それは、今のわたしのことだ。
「だからって、唐突すぎるだろ!!」
やはり、男は鈍い。本気で慕われているのに、わからないとは。
「本人だって、悩んだ挙句のことだろう。リザードだって、別に文句は言わないはずだ。愛人にしてやればいいだろう。きみに損はないはずだ」
すると、シヴァは、わたしに食ってかかってきた。
「おまえ、男には感情がないと思ってるのか!? 女に迫られたら、直ちに尻尾を振って喜べとでも!?」
わたしは戸惑った。なぜ怒る。リナのような可愛い娘に迫られて。
「据え膳喰わぬは何とやら、と言うじゃないか」
その台詞自体は時代物だが、そういう傾向は今もあるだろう。
シヴァはいきなり、立ち上がった。
「もういい!! おまえら女の傲慢と無神経は、もうたくさんだ!! 自惚れも大概にしろ!! 男の側にだって、事情も都合もあるんだ!!」
そしてそのまま、扉から外の雨の中に出ていこうとする。自惚れ、とか言ったか? 女は男ほど、自惚れてなんかいないのに。
わたしは急いで、扉の前に立ち塞がった。やっと捕まえたのに、また逃しては厄介だ。
「待て。それなら、きみの都合とやらを聞こう。何が気に入らないんだ? とにかく、単独で走るのは困る」
「勝手に困ってろ。そこをどけ。俺のバイクを返してもらおう」
彼の手がわたしの肩にかかり、無造作に横へ押しのけようとした。それだけだ。
しかし、大きな手の感触を肩に感じた途端、何かが弾けた。
もう二度と、こんな機会はない。雨の夜中に二人きり、などという機会は。
わたしは咄嗟に、両手でシヴァの手首を掴んだ。彼がぎょっとしたのを見て、余計、捨て鉢の勇気が湧いた。
どうせ既に、嫌われている。これ以上、悪くなることはない。
「行かないで」
シヴァが理解不可能という顔で、呆然と立ち尽くしている。
「まだ、行かないで……」
シヴァの手を両手で握り直し、そろそろと自分の胸に引き寄せた。彼は唖然としたまま、わたしを見下ろしている。大柄なわたしより、更に大きな男。怒れば一撃で、わたしを殺せる。
彼の手を自分の胸に抱えるようにして、訴えた。
「お願いだから、もう少しだけ、ここにいて。怒ったのなら、謝る。でも、きみには、わかっていないんだ。女には、女の本能がある。本物の男を嗅ぎ分ける本能だ。セレネもレティシアも、きみが本物だとわかったから、きみに甘えているんだ」
「甘え……甘えだと?」
「そうだ。女である限り、男を求める本能がある。リナだって、きみが大好きなんだ。それを、彼女なりのやり方で表した。なのに、きみが怒ったら、彼女は立ち直れない」
こう言ったのは、リナのためではない。わたし自身のためだ。
「優しくしてやってくれ。哀れみで構わない。きみが愛しているのは従姉妹たちだけだと、みんな承知の上なんだから」
シヴァは凍りついたように、動かない。わたしの手を、振りほどくこともしない。ただ、息を深く吸い込んだ。
「わからん」
心底、混乱しているような声だ。
「おまえは、何がしたいんだ? 俺を、どんな罠に落としたい?」
つい、かっとした。人がここまで真剣に訴えているのに、まだ疑うのか。
わたしはシヴァの手を放し、彼の顔に平手打ちを見舞った。普段の彼なら避けたかもしれないが、今はまともに打たれて、後ろによろめく。信じられない、という顔をして。
勝手に怒ればいい。わたしだって、怒っている。
「きみにとっては、従姉妹以外の女は、本当にどうでもいいんだな。リナがどれだけ傷つこうと、平気で見限れるんだ。セレネだってレティシアだって、きみに惚れているのに。わたしだって……」
しまった。つい。
なんて馬鹿。
自分が、耳まで真っ赤になっているのがわかる。これでは、リナより幼稚ではないか。
だが、言いかけてしまっては、もう、引き返せない。たとえ、どんな反応をされようとも。
「わたしだって、きみが好きだ。好きになった。きみが、わたしを敵としか思っていなくても」
自棄の勢いで言いきった。もう、シヴァの顔をまともに見られない。下を向いたまま、たっぷり五秒は待った。それでも、何の返答もない。
そうか。
わかったよ。
いや、最初からわかっている。わたしなんか、女に見えていないってことは。
皮肉な話だが、女としてのわたしに価値を認めてくれたのは、わたしをポルノ映画に使った連中だけだ。それも、元軍人という経歴が売り物になったから。どれだけ痛めつけても、自殺せず、回復したから。
「引き留めて、悪かったな」
わたしはシヴァの顔を見ないまま、外へ出る扉を開き、彼を冷気の中へ押しやった。
「さあ、どこへでも行けばいい。好きなだけ走れ。きみがどうなろうと、もう心配などしてやらないから」
けれどシヴァはなぜか、扉の横のバーに掴まったまま、最後のステップから降りようとしない。外から吹き込む雨が彼を濡らすが、いまさら、寒いのは嫌だと言うつもりか。
「ちょっと待て。俺に考える時間を与えないのは、卑怯だぞ」
驚いた。卑怯とは。
つい顔を上げてしまったら、段差のせいで、間近に向き合ってしまった。黒い目が、真正面からわたしを見ている。奇妙なものでも見るかのように。こちらはつい、視線をそらせてしまう。
「単細胞のくせに、何を考えるんだ。女の気持ちなんか、いくら無視しても平気なくせに。一生涯、従姉妹のことだけ見ていればいい」
ああ、もう、何が言いたいのか、支離滅裂だ。シヴァもまた、怒った声で言う。
「だから、人を、人でなしみたいに決めつけるな。俺だって、好きで雨の夜中に走り回ってるんじゃない。だいたい、なんでおまえにぶたれたり、追い出されたりしなきゃならないんだ。おまえ、俺を迎えに来たはずだろうが」
彼は憤然として扉を閉め、ステップを上がり、わたしに向き直った。
「居場所がないんだ。もう、ここでいい。いさせろ。頭が冷えないうちに船に戻ったら、ややこしいことになるだろうが!!」
それは、リナの気持ちに負けてしまうということか。やはり、可愛い女は得だ。男にぶつかれば、男はたやすく動揺する。
「だいたい、おまえが言うことは、わけがわからん。確認させろ。さっき、俺のことを何だと言った?」
うわっ。そこを追及するのか。また、耳まで熱くなってしまうではないか。
「間違いだ。何でもない。忘れろ」
しかし、彼はしつこい。
「おい、間違いで済ませるのか。はっきりさせろ。俺をどう思ってるんだ。何か……変なことを言ってなかったか?」
この馬鹿。
死んでしまえ。
わたしは彼の肩に手をかけると、背伸びして、彼の口にキスをした。いくら馬鹿でも、これならわかるだろう。あとは、いくらでも勝手に怒れ。
わたしはもう、このキスだけで気が済んだ。これでもう、こいつのことは拭い去る。元の自分に戻る。
ところが、シヴァから離れようとした瞬間、がっと背中に腕を回された。あっと思った時には、強く抱え込まれて、キスを返されている。
どうして。
どう考えても、本気のキスだった。これまでの人生で、ただの一度も、こんなキスをしてもらったことはない。逃げられないほど強く、情熱的なのに、どこか遠慮がちなのがわかる。わたしが噛みつくとでも思うのか? いや、わたしが怖がるとでも?
ゆっくりと、力が抜けていった。酔ったようになり、足に力が入らなくなって、崩れ落ちてしまいそうだ。けれど、強い腕に支えられているから、倒れられない。
キスが終わっても、シヴァはわたしを離さなかった。腕でわたしを囲い、わたしの肩に顔を埋めるようにして、じっとしている。
いや、気がついたら、身を震わせ、低く、むせるように笑っているではないか。
「何がおかしい!!」
わたしがつい、うっとりしてしまったから、それを笑いものにしたいのか。
シヴァは両腕をわたしの背中に回したまま、笑いながら言う。
「おかしいよ。おかしいだろ。これで、二度目なんだ。女の方から、キスしてもらったのは……」
えっ? この、かすれた声は?
違う。笑っているのではない。泣いて……泣いている? こんな、殺しても死なないような、ふてぶてしい大男が?
シヴァがずり落ちた。わたしの腰に腕を回したまま、わたしの腹に顔をつけて、泣いている。声を殺して。
わたしは、わたしの魂が裂けたと思った。シヴァの魂も、裂けて血を流している。
そうなの。
魂の居場所を探していたの、あなたも。
前にあなたにキスをしたのは、死んだバイオロイドの娘? その娘のことを、思い出したの?
わたしも床に膝をつき、シヴァを抱きしめた。頭を撫でてやり、濡れた顔を胸に抱き寄せた。
迷子になった、小さな男の子と同じ。
難破船が二隻、海の中でぶつかったようなものだろうか。
彼がわたしに弱味を見せるのは、今夜だけのことかもしれない。でも、それでいい。わたしも今だけ、ただの女に戻るから。
雨は、朝まで降り続いた。トレーラー内の簡易ベッドには、大人一人分の幅しかなく、大柄な彼とわたしでは、いかにも狭かった。
それでも、わたしたちは他の場所に別れたりせず、手足を絡めるようにして眠った。お互いの体温に温められて。
眠りに落ちる寸前まで、シヴァは、まるで貴重な壊れ物であるかのように、わたしを優しく扱ってくれた。わたしが過去に体験した地獄の分も、自分が優しくしなければならないと決めているかのように。
ただ、明け方に目を覚ました時、わたしは、彼が後悔しているものと考えた。
昨夜はたまたま、感傷的になっていただけだ。今はまだぐっすり眠っているが、目を覚ましたらすぐ、服を着て出ていってしまうだろう。こんなことはもう、二度と起きないはずだ。だからわたしも、次に彼に会った時は、知らん顔していた方がいい……
名残のつもりで、そっと彼の髪を撫でた。素直な黒髪の間に指を入れて、感触を楽しむ。
ところが彼は、目を覚ましていたらしい。むくりと動いて、わたしを抱え直すと、肌にキスをしてきた。肩や腕に、それから胸に。大きな手が、わたしの輪郭をなぞりだす。本当に実在しているのか、確かめるように。
結局、わたしたちは、それぞれルワナとセレネに連絡して、下手な言い訳をし、午前中の予定を全てキャンセルすることになった。
彼女たちにどう思われているかと思うと、恥ずかしさのあまり、体温が上がりそうになる。まるで、無断外泊した不良少女のようだ。この歳になって、こんなことで予定を変更するなんて。
けれど、連絡を終えてしまうと、シヴァはまたわたしを抱き寄せる。
「たまにはいいだろ。普段は勤勉なんだから」
そして、わたしの唇に、何十回目かのキスをしてくれた。まるで、百年も前からの恋人のように。
わたしは嬉しくて、でも、恥ずかしくて仕方ない。こんな時、何を言えばいいのだろうか。腕の中に抱いてもらいながら、つまらない言い訳をしてしまう。
「あの、夕べ、狭くて寝苦しかったでしょ」
「そうだな。今度は、広いベッドにしよう」
「いえ、そうじゃなくて、わたしが大女だから……」
「そうか?」
「そうかって、わたし、百八十センチあるんだから……」
「俺は百九十あるぞ」
「だから……」
わたしが大柄で、ごついことを引け目に感じていると知ると、シヴァは優しく笑い飛ばしてくれた。俺の方がごついだろ、と。
「だけど、子供の頃から、ずっとゴリラ女って言われてて……」
シヴァはぷっと吹き出した。わたしが傷ついた顔になったのを見て、慌てて言う。
「いや、違う。俺は絶対、そんな風には思ってない」
わたしがじっと見上げると、気まずい様子で視線をそらす。
「ああ、その……本当のところ、ちょっとはそう思ったが……今は……」
「今は?」
「こんな美人のゴリラ、見たことないと思ってる」
そして、笑いながら、あちこちにキスしてくれる。
もう、馬鹿。
でも、嬉しい。こうやって、一緒に笑い転げることができて。
実際、強化体であるシヴァにとっては、普通人のわたしなど、脅威でも何でもないのだ。だから平気で、可愛いもののように扱える。
わたしは幸福に目がくらんでいて、先を考えることをやめていた。
今だけでいい。
もう少し、もう少しだけ、このままでいさせて。
自分がもう一度、こんな時間を持てるなんて、期待していなかった。
実際、彼がリナにぶつかられ、動揺していた時でなかったら、懐に飛び込むことはできなかっただろう。幸運だった。リナには悪いけれど。
あの子はまだ若い。これから出会うどんな男でも、手に入れられる。だから、シヴァは譲れない。この人だけは。
それでも、浮き世の義理がある。後ろ髪を引かれながらも、昼にはシヴァと別れた。彼は自分の車で船に戻り、わたしは繁華街のオフィスへ。
セレネやレティシアは、何があったか察していたと思うが、知らん顔して、仕事の話だけ振ってきた。感謝する。
ルワナもたぶん、そうしているだろう。リナは、どうだか知らないけれど。
わたしが罪悪感を感じるのは、リナに対してだけだ。もしかしたら、リナを選んでいたかもしれないシヴァを、わたしが横取りしてしまったのだから。
いえ、でも。
彼は今頃、悔やんでいるかもしれない。どうせ慰めを求めるなら、アマゾネス軍団の長などではなく、もっと優しい美女にしておけばよかったと。
その晩、外回りの仕事を片付けてドーム基地に帰ると、第二秘書のファティマが困惑顔で告げてきた。
「あのう、ジョルファさま宛にお花が届いていますが、どういたしましょう」
花?
「一応、保安検査はして、問題ないと確認していますが」
それは、ちらと空想したような、ありきたりの花束ではなかった。わたしの私室を埋め尽くし、通路にまで溢れ出し、通る部下たちを驚かせる、大量の薔薇の花だった。
赤やピンク、白や紫、オレンジ色にクリーム色。様々な品種の薔薇の見本市だ。
それぞれ、白いかすみ草や、ピンクや青紫のコーンフラワーを取り混ぜた、大きな花籠になっている。全部で百籠あり、数体のアンドロイド兵が何往復もしないと、地階の駐車場から運びきれなかった。この分では、《ルクソール》中の花屋の薔薇が、品切れになっているのではないだろうか。
手書きのカードを添えた、平たい箱も届けられていた。
『何が好きか知らないから、適当に贈る。次に会ったら、欲しいものを言ってくれ』
適当に送る、と言うあたりがシヴァらしい。箱の中には、カット済みの大粒の宝石のルースが、きちんと区分けされて詰まっていた。ダイヤにルビー、サファイア、エメラルド、トパーズ、オパール、アクアマリン、タンザナイト、翡翠、珊瑚、真珠。
同質の石が三つずつ揃っているのは、指輪とイヤリング、あるいはペンダントとイヤリングに仕立てられるように、という配慮だろう。
甘い薔薇の香りの中で、しばらく脳が溶けてしまった。幸福すぎて、何も考えられない。まるで、お姫さまになったみたい。
これは、過去の不幸の埋め合わせと思っていいのだろうか?
けれど、しばらくすると、冷静な計算が働き始めた。このことはもう、部下たちの噂になっているはずだ。どう説明しよう。
相手がグリフィンだということは、隠しようがない。わたしが高い地位の男に媚びているのだ、とか、情欲に負けた、とか思われるのでは。
これまでの女同士の結束に、ひびが入ることになってはまずい。セレネやレティシアも、わたしを軽蔑するのではないか。
『知らん顔していて、実は狙っていたのね。たいした手腕だわ』
『結局、ジョルファさまも、普通の女だったってことね』
わたしは相談相手として、ルワナの顔を思い浮かべた。人生の大先輩だ。彼女なら、客観的分析を聞かせてくれるのではないだろうか。
怖々、グリフィンの船に通話申し込みをしたのだが、通話画面に出たココア色の肌の美女は、いつも通りに穏やかだった。
「まず、おめでとうございますと申し上げます」
「え?」
「グリフィンさまに相談されて、贈り物のアドバイスをしたのは、わたくしですから」
「あ、そうだったの」
確かにそうだ。シヴァには、何か贈りたい気持ちはあっても、選ぶセンスがないだろう。
「こうなって、良かったのですわ。一番望ましい結び付きだと思います」
「……そうなの? 本当に?」
「もちろんですわ。リナはしばらく泣き続けるでしょうが、仕方ありません。あの子はまだ若いのですから、これから幾らでも、新しい出会いがあります」
それでも、シヴァ以上の男が、そうそういるとは思えないが。
「仕事上でも、歓迎すべきことです。ジョルファさまとグリフィンさま、双方の地位が安定しますから」
ああ、そういう見方ができるのか。
「セレネもレティシアも、納得するでしょう。彼女たちが納得すれば、直接グリフィンさまを知らない女たちも納得します」
それなら、いいのだが。
「それで……その……」
わたしが言葉に迷っていると、ルワナは理解ありげに微笑んだ。
「グリフィンさまは、まだ地面に足が着いていません。明日はまた、別な贈り物を届けろと言うのではないでしょうか」
平気なふりをしようとしても、顔が赤くなるのが止められない。
「そ……そうなのか?」
確かに、昨夜から昼まで、とても優しくしてもらったけれど。彼はたぶん、条件さえ揃えば、他の女にも優しくできるはず。
「わたしは午後からずっと、あの方の様子を見ていますが、一人でにやけたり、慌てて顔を引き締めたりの繰り返しですわ。まるで、初体験を済ませたばかりの若者のように」
信じられない。あのシヴァが、そんな。
でも、嬉しい。嬉しくて、どうにかなりそう。
「おかげでわたくしも、安堵しました」
ルワナは穏やかに言う。
「ピリピリ尖っていては、長期間、安定して働くことができません。これで余計な緊張が解けて、楽になるでしょう。あの方の無愛想な態度は、自分を守る殻ですから。ジョルファさまの体当たりが、その殻を壊したのですわ」
本当に? わたしは信じてもいいのか? これからもずっと、シヴァの優しさを独占できると?
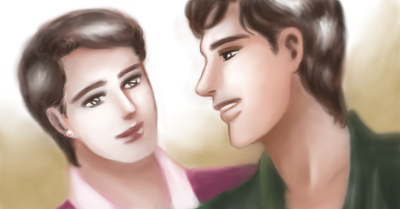
シヴァは翌日にも、贈り物を届けて寄越した。豪華な百合の花束を添えた、薄手の箱が一ダース。
中身は、全て首飾りだった。まずは、大粒の真珠を連ねた首飾り。それも、白い真珠と、金色の真珠と、黒真珠の三種類。
次は、ダイヤとルビーをつないだ首飾り。それから、金とエメラルドの首飾り。
緑の翡翠もあれば、海のようなサファイアもある。可憐なピンク・サファイアも、オレンジ色のきらめきを放つオパールも。
しばらく、その場から動けず、華麗なジュエリー群に見とれてしまった。これまで、他人の首に見かけることはあっても、自分がつけようとは思わなかった品々。
いかつい顔のわたしに、こんな華やかな首飾りが似合うだろうか? でも、せっかく贈られたものを、蔵い込んだままにはできないし。
おまけに、わたしの部下たちに分けるようにと指示が添えられて、ドレス用の高級な布地が一山、届いていた。山吹色や煉瓦色、真紅や紫、淡いピンク、ラベンター、レモン色、水色、黄緑、深緑、紺や青や黒。
幸福を独り占めしないようにとの、ルワナの気遣いだろうか。
布地の山を見たセレネとレティシアは、互いに顔を見合わせてから、肩をすくめた。
「仕方ないですわね。とっても残念ですが、グリフィンさまは、ジョルファさまに譲ります」
「わたしたちがあれほどぶつかっても駄目だったのに、お見事ですわ」
二人は、それぞれにため息混じりで言う。
「ほんとに、わかりやすい愛情表現ですこと」
「惚れたとなったら、一直線の方だったんですね」
わたしが、惚れられている?
「あの……自分でもまさか、こうなるとは……」
わたしの言い訳を、セレネは簡単に遮った。
「いいえ、わかっていました。ジョルファさまの視線の先も、ちゃんと見ていましたから」
「え、あなたたちに知られていたの!?」
自分では、自分の気持ちを完璧に隠しているつもりだったのに。

次に、シヴァと二人きりで会ったのは、市街のホテルの一室だった。どちらも、自分の拠点で会うのはまずいと思ったからだ。
それでも、《フェンリル》所有のホテルだから、機密保持に問題はない。わたしは彼にしがみつき、ジャケットの胸に顔をこすりつけ、頭を撫でてもらい、これが現実だということを再確認した。シヴァはわたしを膝の上に座らせ、笑って言う。あの朝は、自分も怯えていたのだと。
「おまえが目を覚ましたら、車の外に叩き出されるかもしれないと思ってた」
けれど、わたしがそっと彼の髪を撫でたので、安心したと言う。
「ずうっと、軽蔑されてるんだと思ってたからな」
「わたしだって、あなたに嫌われているとばかり……」
「はっきり言ってくれないと、わからないんだ。女の気持ちなんて」
よかった。世界が晴れ上がったような気がする。
愛することは人の本能だから、そう簡単に、冷血にはなれないのだ。たとえ何年、辺境暮らしをしようとも。
それならば、これから先、シヴァと二人で、少しずつ辺境を変えていけるかもしれない。
「あの、重いでしょ、わたし」
遠慮して膝から降りようとしたら、シヴァは笑う。
「おまえがか? いや、全然」
シヴァはわたしを横抱きに抱き上げると、軽々と室内を歩き回った。さすがは戦闘用強化体。七十キロを超すわたしの体重を、少しも苦にしない。
「俺が腕立て伏せする時、背中に乗っててもいいぞ」
「それは無理でしょ、さすがに」
「いや、平気だ。俺が潰れたら、笑ってくれていいぞ」
そういう馬鹿話もできる。本当は、朗らかな男なのだ。
「いつも怖い顔してるから、気難しいと思ってた」
「こっちこそ、怒らせたら、ちょん切られると思って、びくびくしてた」
「いや。そんな勿体ないこと、絶対しない」
そして、二人で笑い崩れる。
従姉妹のヴァイオレットは、確かに初恋の相手だったけれど、今はもう、未練はないとも話してくれた。あまりに嬉しすぎて、逆に怖い。
「わたしだけで、いいの?」
つい、馬鹿なことを訊いてしまう。
「どういう意味だ」
「つまり……あなたさえそのつもりなら、セレネもレティシアも、リナだって、あなたのものになるのに……」
けれど、シヴァは簡単に言う。
「ややこしいことは断る。大事な女は、一人でたくさんだ」
わたしが、大事な女? 本当に、女と思ってくれている?
「俺は大型だから、女も大型の方が安心だしな。小柄な女だと、抱き潰しそうで怖い」
彼は言葉より動作で、繰り返し、それを実証してくれた。わたしとは、精神も肉体も、相性がいいと。
おかげでわたしは、心身共に安らぎ、ゆるんでしまう。こんなにとろけてしまったら、明日、また冷徹なアマゾネスに戻れるだろうか。
「それより、何か欲しいものはないのか?」
わたしに腕枕してくれながら、シヴァは言う。
「もう、十分。今日までにもらった宝石だけで、一生、間に合うくらい」
贈り物のお礼は、真っ先に言ったのだが、シヴァはどうやら、〝自分の女〟に山ほど贈り物をするのが、男の最低限の義務だと思っているらしい。そのあたり、彼の育ち方がうかがわれて、興味深い。
「俺には、女の服や宝石はよくわからんから、手始めに贈ってみただけだ。好みを教えてくれ。今なら、店ごとだって買ってやれる」
わたしだって、買おうとすれば、店ごと買えるけれど。というか、傘下に商業ビルを幾つも持っているけれど。これまでは、ビジネス用の堅いスーツしか必要としていなかっただけ。だって、私生活というものが、ほとんどなかったのだもの。
「それと、ルワナに注意された。おまえに何か贈る時は、部下にも贈らないと、恨まれると。女の恨みは怖いからな。次は何を贈ればいいのか、一緒に考えてくれないか?」
何かの間違いではないかと思うほど、幸福だった。
シヴァはわたしがどうしたいか、何を望んでいるか、懸命に気遣ってくれる。わたしのために何かすることが、嬉しくてたまらないという気持ちが伝わってくる。
逢瀬を重ねるうち、シヴァの前では、無理して男言葉を使うこともなくなった。彼の希望に応じて、女らしい下着や部屋着を着るようにもなった。
「赤が似合うじゃないか」
「今度は、ルビーのネックレスとイヤリングのセットを探しておこう」
などと言われるのも嬉しい。
ホテルの部屋から外に出なくても、優雅なドレスを着て、ジュエリーを選び、カクテルで乾杯し、豪華なディナーを楽しむことはできる。その後、もつれ合ってソファやベッドに転がることも。
仕事の上では変わらず、アマゾネス軍団の長だが、私生活では女に戻れる。戻ってもいい。
シヴァはわたしを、リアンヌと呼ぶようになった。ずっと忘れていた、忘れようとしていた、本当の名前。
ここにいるのは、グリフィンとジョルファではなく、シヴァとリアンヌ。
時間を作って、ホテルで落ち合う。新しいドレスを着て、彼に見てもらう。同じソファに座って、話題の映画を見る。
厨房に立って、一緒に料理を作ることもあった。わたしがサラダを作る間に、彼は見事なステーキを焼いてくれる。
「あなたに料理ができるなんて、思わなかった。老舗組織のお坊ちゃまだったんでしょ?」
「そう、馬鹿にしたものでもないさ。特技は色々ある。例えば、誰かの足の裏をくすぐるとか」
いったん心を許せば、彼は他愛ない冗談も言うし、おふざけもするのだった。わたしは一緒になって笑い転げ、抱き上げてベッドに運んでもらい、彼に寄り添って眠る。
あまりにも幸福なので、この幸福がいつまで続くのか怖くなり、自分の部屋で一人になってから、発作的に涙ぐんだこともある。
もし、いつか彼と引き離されたら。何かあって、置き去りにされたら。そんなこと、耐えられない。死んだ方がまし。
そんな感傷も、シヴァから新しい贈り物が届くと、すぐに晴れてしまうのだったけれど。
一つだけ気にかかっているのは、リナがシヴァの秘書を辞めて、リザードの元へ戻ったことだった。すっかり暗い顔になって、シヴァにぼそぼそ、別れの挨拶をしていったとか。
シヴァも、リナを引き留めなかった。自分は、一度に二人の女を相手にできるほど、器用ではないからと。
リザードからは、心配要らないと言われている。リナには気が紛れる仕事を与えるから、いずれ回復するはずだと。
シヴァの新しい第二秘書は、女性の恋人がいる女性に決まった。それなら、ややこしいことにはならないだろう。
そういう日々の中、忙しく過ごしていたわたしは、自分の変調に気がつかなかった。ある日、ルワナに指摘されるまで。
「ジョルファさま、もしかして、妊娠なさったのではありませんか?」

「グリフィンさま、そこにお掛け下さい」
ルワナに厳かな態度で言われた時、不吉な予感が走った。何か、極めてまずいことがあったらしい。
しかし、グリフィンとしての職務に遺漏はないはずだ。暗殺志願者はこちらで把握して、巧く操っている。従姉妹たちも無事だ。
俺の前に立ったルワナが、いきなり右手を振り上げ、ごつんと俺の頭に振り下ろした時は、ぶたれると頭でわかっても、躰が抵抗できなかった。それは、ルワナが、悪ガキを叱る大人の態度だったからだ。
「何をする!」
と頭を抱えて抗議できたのは、拳固でぶたれてからだ。ルワナは厳しく、俺を見下ろしている。
「グリフィンさま、わたくしは注意したはずです。浮かれるのはご自由ですが、避妊には注意なさって下さいと」
俺は唖然とした。確かに、言われた記憶はあるが、しかし、それについては、リアンヌ本人が心配しなくていいと言ったから……
叱責の意味がわかったのは、数秒後だ。
「まさか?」
「その、まさかです」
では、あの最初の晩かもしれない。雨の中のトレーラー。あの時はどちらも、そんなことになるとは思っていなかった。いきなり激流に落ちて、押し流されたようなものだ。
しかし俺には、幸運な事故だった。リナに迫られて船を飛び出さなかったら、リアンヌの心に触れることもなかった。
「妊娠十四週。本来なら、祝福すべきことですが、この場合は残念ながら、違います。危険はおわかりですね」
わかった。ルワナが、笑みのかけらもない顔でいる理由が。
「普通人と強化体の間に、正常な子供ができることは、まずありません。九割方、流産します。何とか生きて生まれても、重い障害を背負っていることがほとんどです。治療するとしたら、早期の脳移植しかありません。それも、脳に障害がなければの話です」
そうだ、ショーティにも注意されていた。もしもきみが、自分の遺伝子を分け持つ子供を作ろうとしたら、最初から精密に遺伝子設計して作るしかないと。
だが、その頃は、そんなこと、あるはずがないと思っていた。俺は、何という大間抜けだ。これでは、リアンヌの身を、生体実験に使ったようなものではないか。
「すぐ、リアンヌに会う。説得する。胎児を取り出すように」
でないと、母体が危険だ。子供はどこかの研究室で、人工子宮に入れておくしかない。治療できるものなら、治療する。今ならまだ、遺伝子操作で何とかなるかもしれない。助からないのなら……仕方がない。
「それは、わたくしから、ジョルファさまにお話しました。リザードさまにも、報告しました。リザードさま直轄の研究機関で、胎児を治療してくれるそうです。既に、スタッフの選定が行われています」
「そうか」
息を吐いた。さすがルワナ、やることが早い。俺への報告が後になったのは、いささか不愉快だが。今回はルワナも、俺の馬鹿さ加減に腹を立てたのだろう。
「問題は、ジョルファさまが、お腹の子供を手放そうとしないことです」
「何だって!?」
「摘出手術を拒絶なさっているのです。それはもっと後、不都合が出てからでいいはずだと」
あのリアンヌが。もうそこまで、母親になりきっているのか。
「しかし、今日、明日にでも、流産するかもしれないんだろ」
「ええ、ですから、説得をお願いします。なるべく早く、母子分離をするべきです。でないと、子供が助からなかった場合の傷が深くなります」
俺は馬鹿だ。
俺は馬鹿だ。
俺は馬鹿だ。
せっかく俺を愛してくれた女を、そんな苛酷な状況に立たせてしまって。ショーティがいたら、どんなに呆れられたことか。
俺はルワナに付き添われ、車を飛ばしてドーム施設に向かった。男子禁制の要塞だが、事情を知るセレネとレティシアに、そっと奥へ通してもらった。一般の部下たちに、姿を見られないようにして。
リアンヌは、自分の部屋で横になっているという。
「具合が悪いのか?」
「いいえ、そうではありません。ただ、妊娠がわかってからは、お昼寝の時間を取るようになさっているので」
妊娠が明確になってから、もう一週間以上、過ぎているという。既に女性医師が付いて、体調の管理をしていると。
「なぜもっと早く、俺に教えないんだ」
「それは……グリフィンさまに知られたら、子供を取り上げられると心配なさって」
くそ。その通りだ。
俺は、子供より母体を取る。
しかし、リアンヌは、俺がそう思うことを理解していたのだ。一日でも長く、腹に子を抱えていたかったのだろう。
誰よりも女らしい女であることを、俺は知っている。かつてリアンヌを騙した男は、そこに付け込んだのだ。
「リアンヌ、入るぞ」
彼女の使う寝室に踏み込むと、リアンヌは仕事着のパンツスーツのまま、上着だけを脱いで、ベッドの上に横になっていた。俺が贈った花を除けば、余計な装飾のない部屋だ。
「シヴァ」
リアンヌは思わず俺の名を呼んでしまい、そのことに気づいて顔を曇らせたが、その時にはセレネは寝室の外にいて、ドアを閉めかけている。聞こえなかったものと考えよう。ルワナも、近くの客室で待機していてくれる。
「起きるな。寝てろ」
と手で制止しながら言うと、リアンヌは苦笑した。
「別に、病人じゃないから。ちょっと休憩していただけ」
もちろん、妊婦に無理は禁物だ。まして、普通の妊娠ではない。
「いいから、横になっててくれ。頼む」
俺はベッドの端に座ると、リアンヌの手を取り、指にキスした。いつものように。リアンヌの指には、俺が贈った大粒のルビーの指輪がある。リアンヌの浅黒い肌の色には、赤いドレスや赤い宝石がよく似合うのだ。
「悪かった。俺が悪かった。こんなことになるなんて、考えもしなかった」
「ううん、それは、わたしのせい。自分が妊娠するなんて、考えていなかったから」
以前、違法ポルノの撮影に使われて、心身共に、ぼろぼろにされたせいだとリアンヌは言う。一時は、生理も止まっていたと。リザードの下で働くようになってから、何とか生理は戻ったものの、もう、妊娠の機能は失われていると思っていたらしい。
「お願い、謝らないで。わたし、とても嬉しいんだから」
ひやりとした。微笑んだリアンヌの顔は、もう母親のそれになっている。子供愛しさのあまり、異常な妊娠の危険を、過小評価しているのだ。
「頼むから、話を聞いてくれ。一緒に、リザードの研究基地へ行こう。受け入れ態勢は、もうできてる。子供は、研究チームに託そう。きっと、何とかしてくれる。治療の方針が立つまで、冷凍保存しておくこともできる」
「ええ、わかってる……」
リアンヌは、ぼんやり微笑んだ。
「でも、もう少しだけでいいから、一緒にいたいの……わたしの赤ちゃんなんだもの……」
不覚にも、泣きそうになった。大事な女に、こんな思いをさせるとは。
かろうじてこらえ、両手でリアンヌの手を握った。
「俺が連れていく。留守中のことは、セレネとレティシアが見てくれるから、心配するな」
二人とも、上司の迂闊な妊娠には呆れたらしいが、留守は守ると約束してくれた。
「ハネムーンだと思って、のんびり旅行してらして下さいな」
「何かありましたら、すぐ報告しますから」
側近に二人がかりで説得され、リアンヌもついに、手術を受けるための旅行を承知した。往復に時間がかかるし、手術後の療養もあるだろうから、本拠地を一か月あまり留守にすることになるが、問題はない。
グリフィン事務局は、元々、俺が出入りしていたわけではないから、距離が遠くなっても、通信さえできれば、それでいいのだ。
「では、グリフィンさま、ジョルファさまをお願いします」
「ああ、わかった。必要な連絡は入れる」
一般の部下たちには仕事での出張ということにして、俺たちは《ルクソール》から出航した。護衛艦に囲まれた母艦に乗っているのは、ルワナとリアンヌと俺の三人だけだ。第二秘書のリーファは、連絡員としてグリフィン事務局に残してある。
まずは、リザードに指定された座標に向かう。そこに、出迎えの船団が来る約束だった。
リザードの研究施設というのがどこにあるのか、こちらには不明のままだ。リザードはあくまでも秘密主義で、我々に、自分の手の内をさらすつもりはないらしい。
それは、別に構わない。今はとにかく、リアンヌと子供の命が優先である。
ショーティがいれば、治療は奴に任せるところだが、それはもう、惜しんでも仕方ない。リアンヌと愛し合うようになってから、俺は、奴のことをあまり思い出さなくなっている。もちろん、いつかは必ず取り戻すが、今はまず、リアンヌのことだ。
そのリアンヌは、子供のことで頭が一杯らしく、船室に落ち着いても、子供のことばかり語る。どんな名前にしようか、どんな服や玩具を用意しようかと。
「あなたも名前を考えてね、シヴァ」
子供が育たない可能性を、すっかり排除してしまっているようだ。俺はなるべく、逆らわない方向で話相手になった。
「そりゃ、考えるけどな。まだ、男か女かもわからないんだろ」
調べれば判明することだが、リアンヌはあえて、調べさせていない。空想して楽しみたいらしい。
「だから、両方。あなたに似ていたら、背が高くてハンサムで、無愛想な男の子になるでしょうね」
うっとりした様子で言う。
「生意気なクソ餓鬼になりそうだな」
俺に似ていたら、やりにくいことこの上ない。厳しく叱れば反発するだろうし、放っておいたら傲慢に育つだろうし。
「でも、女の子だったら、骨太の大女になってしまうかも……わたしに似てしまったら、ピンクのドレスも、リボンもレースも似合わないわ」
リアンヌが悲しげに言うのは、自分の少女時代を思い出すからか。
しかし、紅泉だって、少女時代は短い髪をして、縞シャツや野戦服みたいなものばかり愛用していたぞ。あいつのピンクのドレス姿なんて、見たことがない。正装を課せられる夕食の時だって、あっさりした紺や黒のワンピースを着ていたからな。
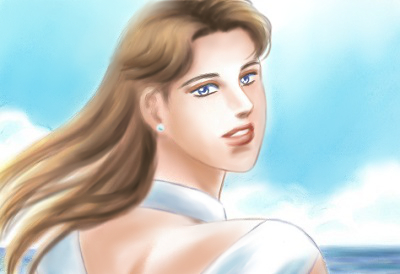
三人きりの船旅の中で、出産経験者のルワナは頼りになった。遠い昔だが、市民社会にいた頃、結婚していて、子供も二人いたという。
今はもう、その子供たちもとうに成人して、孫どころか、曾孫までいるから、市民社会に戻りたいとは思わない……というのは本心なのか、どうか。
ルワナはあれこれと気を配り、リアンヌをいたわってくれた。ゆったりした衣類、温かな食事、心を落ち着ける音楽、子供向けの絵本。中央で製作された名作絵本をめくっていると、リアンヌは気持ちが安らぐらしい。微笑んで、童話に没頭している。
(これが、本来の姿だったんだ)
冷徹なアマゾネスという姿は、辺境で生きるための演技。
多分、セレネもレティシアも、そしてリナも、ルワナでさえも、守ってくれる男がいれば、喜んで可愛い女になるのではないか。
戦いを趣味にしている紅泉は、やはり、特殊な例外だろう。あいつのボーイハントは、まさしく『狩り』に他ならないし。
(俺がリアンヌを守らなければ……何をしてでも)
改めて、思う。辺境でまともに子育てしていた俺の一族は、やはり、特殊だったのだ。偉かったと言ってもいい。
俺も従姉妹たちも、友達があまりいない他は、何不自由のない子供時代を送った。辺境の現実とぶつかって、人生がきしみ始めたのは、戦う準備ができた思春期以降のことだ。
もし、俺がこれから子供を持つとしたら、その子供たちには、あれと同じくらいの環境を用意してやらなくては。そのためにも、俺には安定した地位や権力が必要だ。
いや、待て。
もしかしたら、故郷の一族と和解するべきなのか。
かつての俺は、どうしようもないチンピラだったと認める。愛する女ができて、初めて大人になったと、最長老や総帥たちに頭を下げる。そして、リアンヌと子供たちを預かってもらう。
いや、だめだ。それはできない。俺がグリフィンである以上。
だが、リアンヌと出会ったことは、全く後悔していない。茜の時はまだ、『金で買った愛情』という負い目があった。しかし、リアンヌは自由意志で俺を選んでくれたのだ。その嬉しさ、誇らしさは、これまでの不幸を償って余りある。
(茜、すまない、許してくれ)
この宇宙のどこかに漂っている魂に、祈った。
(おまえを忘れたわけじゃない。おまえの姉妹たちを救う誓いも、忘れていない。だが、今はリアンヌを守りたいんだ)
俺は変わった。前は、茜の魂がすぐ横にいてくれると思っていた。日に何度も、こっそり語りかけていた。だが、最近ではもう、滅多に思い出すこともない。今の生活が忙しく、心はリアンヌのことで占められている。
(茜、俺を恨むか? 怒っているか?)
わからない。茜は寂しそうに、薄く浮いている。遠い宇宙を背景にして。
平穏な旅は、突然終わった。
〝連合〟系列の中小組織の領宙を通り抜けようとしている時、忽然と、正体不明の艦隊が現れたのだ。
百隻近い陣容であり、明らかに待ち伏せである。こちらは、わずか八隻。既に包囲されていて、勝ち目はない。
艦体には《フェンリル》の紋章を付けているというのに、そんなことはお構いなしか。
「六大組織でもなければ、系列組織のどれかでもありません。もし、グリフィンの乗艦と知ってのことなら、心当たりは〝リリス〟しかありませんね」
ルワナは平静だ。相手が〝リリス〟なら、降伏すれば命は助かるからだろう。元々が、中央からさらわれてきた女だ。逮捕されても、情状酌量してもらえる。
「だが、二人とも、司法局に軟禁されているはずだ」
グリフィンの懸賞金リストに載せられたため、紅泉も探春も、平和な植民惑星の、温帯地方の離れ小島で、強制的に休暇を取らされている。そのはずだ。

六大組織の最高幹部たちは、懸賞金制度の布告に対して、〝リリス〟が何らかの反撃に出ることを予期していたのだろう。
というより、英雄として当然、反撃してもらう予定だったのだろう。それがまた、市民社会での〝リリス〟の評価を上げる結果になる。
だから、リアンヌを俺の身代わりとして、用意しておいたのだ。それというのも、リアンヌが成功しすぎ、〝連合〟の重荷になってきていたからだろう。
『男嫌いのアマゾネス軍団』の評判が高くなりすぎて、他組織の男たちを委縮させてはまずい。辺境はあくまでも、『男の天国』でなければならないからだ。
不老不死。
身体強化。
バイオロイド美女のハレム。
野放しの違法ポルノ。
そうであってこそ、馬鹿な男たちが市民社会を離れ、辺境にやってくる。リアンヌと、彼女が集めた女闘士たちは、俺のことがなくても、いずれ厄介払いされる予定だったのだ。
自分でも、心のどこかで知っていた気がする。こんな幸福、いつまでも続くはずはないと。
だから、逆に納得して、安心している。そうか、こういう風に終わるものだったのか、と。
わたしを捕まえるのが〝リリス〟なら、かなりましな運命だ。
子供のことは、無理だと最初からわかっていた。ただ、一日でも長く、夢を見ていたかっただけ。
人並みの幸福など、とうにあきらめていたのに、好きな人ができた。妊娠することもできた。
わたしの幸運は、ここまで。
辺境を変えようという夢は、シヴァや〝リリス〟が引き継いでくれる。シヴァなら、わたしの部下たちの身柄も守ってくれる。
本当は、もう少し長く、シヴァの愛情に浸っていたかったけれど。
「通話だ、向こうと話す!」
話せば、紅泉はわかってくれる。他でもない、従兄弟の俺が言うことなのだから。
だが、首筋でバチッと何かが弾けた。
全身を走る衝撃。
視野に白い点が飛び、平衡感覚が失われる。
嘘だろう。この俺が、床にぶっ倒れるなどと。そんなこと、強烈な電撃を食らいでもしない限り……
いや、食らったのだ。他ならぬ、リアンヌの手によって。ルワナも、リアンヌがスタンガンを手にして、俺に忍び寄るのを知っていて、黙っていた。
「ごめんなさい、シヴァ。許してね。これしかないの。わたしが投降するから、あなたは逃げて」
リアンヌの顔が逆さになって、俺の視野に入る。身をかがめて、俺の口にキスしてから、すっと消える。
ちょっと待て。勝手に決めるな。
それは、俺を忘れるということだぞ。
くそ、声が出ない。
「記憶を失くしても、あなたを愛していることは、永遠に変わらないわ。待っているから、迎えに来て」
何だと?
「逮捕されて何年かすれば、当局の監視もゆるむはずだから。もう一度会えば、そこからまた、始められるでしょ。わたしがあなたを忘れていても、あなたが優しくしてくれたら、またあなたを愛せるから……」
俺を信じて、市民社会の隔離施設で救出を待つというのか。しかし、そんな必要はないんだ。今、紅泉に助けを求めることさえできたら。
「では、ジョルファさま、いいですか」
「いいわ、やって」
ルワナがリアンヌに、何か薬物を打ったらしい。倒れかかったリアンヌを、アンドロイド兵が支えて運び去った気配がわかる。おまえたち、手際がよすぎるぞ。
「いいか、シヴァ、よく聞くんだ」
ルワナが、床に倒れたままの俺の横に膝をついた。いつも上品な女が、どうしたことだ。やけに素っ気ない、まるで男のような口の利き方をする。
「時間がない。わたしの言うことを、その鈍い脳味噌にしっかり刻んでおけ」
おい、その言い方。まるで、誰かみたいだぞ。
「リアンヌの身柄は、心配ない。紅泉が、妊婦に手荒な真似をするはずはないからな」
紅泉?
なぜ、その名前を使う? これまでは、リリーというコード名でしか呼んでいなかっただろうが。
「リアンヌは逮捕されるが、いずれは刑を終えて、自由になれる。だが、彼女を迎えに行ってはいけない。そのまま、市民社会に戻してやれ」
何だと。
「元々、市民社会にいるはずの女だった。きみのことを忘れれば、市民社会で幸せになれる。結婚もできるだろう。子供も持てる。だから、リアンヌのために、このまま別れろ」
だが、リアンヌ本人が、俺に迎えを頼んだのに。
アンドロイド兵士が、俺を床から引き起こし、抱き抱えた。ルワナはそれを、横で見ている。
「わたしはここまでだ。ルワナとして、きみを守るつもりだったが、とうに最高幹部会に知られていたようだ」
ああ? ルワナとして、だと?
「わたしは、ショーティの分身の一人だ。何年か前に、本物のルワナとすり替わった。彼女がリザードの秘書に抜擢される、少し前のことだ。本物は整形させて、安全な場所に逃がしたつもりだったが、捕まったのかもしれないな」
ちょっと待て。
おまえが、ショーティから枝分かれした一人だと!?
しかし、この場で、そんな冗談が出てくるはずもない。茜の事件の後、ショーティが自分を更に進化させ、あちこちに、自分の分身を送り出したのは事実。いざという時の備えだと言って。
俺たちは、その分身たちとは、連絡を断つようにしていた。行方を知らなければ、敵に捕まっても白状しようがない。
彼らがそれぞれ、辺境で生き延びてくれることを祈って、別れた。いつか合流できる日が来れば、その時は、強力な同志になってくれるはずだと信じて。
俺がすんなりルワナに馴染んだのは、そういうわけか。道理で用意される服、出てくる料理、俺の好みにぴたりと合っていたわけだ。またしても、ショーティにお守りされていたとは。
「シヴァ、忘れるな。この絵図を描いたのは誰か、突き止めろ。それがおそらく、きみから茜を奪った犯人だ」
えっ?
最高幹部会や、リザードでない犯人が、別にいるとでもいうのか?
「茜は自殺ではない。おそらく、自殺を強いられただけだ。きみに、行動の動機を与えるために!!」
おい、待て。
聞き捨てならないことを言ったな。
「後は、自分で調べろ。真の権力者と戦うのか、それとも駒のままでいるのか、自分で決めろ!!」
兵士たちは手足の利かない俺を抱え、エレベーターの扉を閉めた。ルワナの姿が視野から消える。まだ、聞きたいことが山ほどあるのに!!
自由になろうともがいたが、まだ力が戻らない。兵たちの手で0G区域の倉庫に運ばれ、何かのカプセルに押し込められた。蓋が閉ざされ、ロックされ、周囲から冷気が満ちてくる。
まさか、冷凍睡眠カプセルじゃないだろうな。やめろ、眠ってる場合じゃないんだ!!
冷凍睡眠のカプセルは、当然、強化体をも問答無用で眠らせることのできる仕様だ。あとは、船倉にある本物の小惑星にカプセルごと押し込んで、宇宙空間に放出すればいい。カプセルの分だけ、空洞が作られている。
それが、この周辺の何万という小惑星に紛れてしまえば、おいそれとは発見されない。紅泉たちが引き上げたら、一週間もしないうちに、リザードの捜索部隊に発見されるはず。
リアンヌには防御服を着せて、先に放出した。タイムリミットぎりぎりで小転移をかければ、この艦隊が自爆しても、彼女に悪影響はない。発信機の電波を探知し、紅泉たちが拾ってくれるはずだ。
この事態を予期していた最高幹部会なら、わたし用の小惑星を用意することもできたのに、それをしなかった。
つまり、わたしには、ここで死ねということだ。
人間の女のふりをしていたわたしは、確かに、紅泉に投降することはできない。短期記憶を消したとしても、犬だった記憶は残る。そこから、シヴァがグリフィンだと知られてしまう。
それはまだ、紅泉たちに知らせるべきではないと、最高幹部会は思っているだろう。
懸賞金制度は、始まったばかり。
シヴァにも、紅泉たちにも、生き残ってもらわねば困る。人類の未来のために。
(甘かったな、ショーティ)
ルワナとの入れ替わりなど、とうに見抜かれていたのだ。
シヴァが伴侶と子供を得て、幸せになるのを見届けたかった。人類の進化と、宇宙の未来を見届けたかった。
だが、あちこちに散った分身たちがいる。彼らが生き延びて、真の敵と戦ってくれることを期待しよう。
船の管理システムに転移と自爆を命じようとした時、目の前の通話画面が明るくなった。
「待て、死ぬ必要はない」
呼びかけてきたのは、耳を立てた大型犬だった。
わたしの元の姿。
オリジナルのショーティか!? それとも、わたしのような分身の一体!?
互いに独自の進化を果たすため、また、敵に一網打尽にされる危険を回避するため、誕生以来、他の分身たちとは連絡を絶っていた。だから、オリジナルから分かれた兄弟たちが、どこでどう生きているのか、知らないままでいた。
「装甲服を着て、手近の小惑星に取り付け。迎えを出す」
「だが、それでは紅泉たちに発見される……」
「対策済みだ。向こうの探知は回避できる。わたしに任せろ」
このショーティは、全ての事情をわきまえているらしい。迷う時間はなかった。紅泉は本当に、十分の猶予しかくれないだろうから。
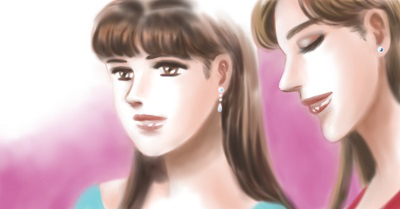
司法局と軍の代表、最高議会の特別委員会との間で、何度も話し合いが行われた。
大きな問題点は二つ。
司法局が独自の判断をして、小島に軟禁されていた〝リリス〟をこっそり脱出させたこと。
辺境に出た〝リリス〟が勝手に行動して、グリフィン捕獲作戦を実行したこと。
違法強化体に特権を与えることを苦々しく思っていた議員が多く、司法局の独断を咎める声も高かったけれど、連邦市民の大半が、〝リリス〟を擁護してくれたのだ。
議論の結果、〝リリス〟の現場復帰が正式に認められた。特別委員会も、速攻でグリフィンらしき人物を捕えた、わたしたちの功績を評価したのだ。
調査した結果、本物のグリフィンではないと判明しても、それに近い立場の人物ではあるはずだ。〝連合〟には、ある程度の打撃だっただろう……と見ることができる。市民社会中枢の指導者たちも、市民に対して、
『懸賞金制度を潰すため、司法局が積極的な決断をした』
という言い訳ができる。
「まあ、何とか収まったわね」
ミギワ・クローデルが、息を吐いてから言う。
「冷や汗をかいたわよ。あなたたちが何らかの成果を出して戻らなかったら、わたしも特捜部本部長の椅子にはいられなかったわね」
紅泉は笑って応じた。
「あのまま逐電しても、よかったかな」
「冗談じゃないわよ。あなたたちには、これから司法局の看板を背負ってもらわなきゃならないんだから」
それは仕方がない。紅泉が、依然、やる気なんだもの。
辺境での彼女の通り名は、ジョルファ。
本名は、リアンヌ・ルナン。
元軍人で、老舗組織《フェンリル》のナンバー2として知られてきた人物。
彼女と側近たちは違法都市《ルクソール》で、グリフィンの紋章を付けた艦に、しばしば出入りしていたことが確認されている。
ジョルファが《ルクソール》から小艦隊で出発したことを知って、わたしたちは待ち伏せをかけた。こちらで使っているダミー組織の支配領域を、うまく利用することができたから。
母艦が自爆した後、ジョルファの他に、生きて逮捕された者はいない。それは、彼女をグリフィンとみなすべき根拠となる。
ただし、紅泉は納得していなかった。
「だって、自分で自分に記憶消去の注射をすると思う? そんなことをしたら、自分を守ることもできない。ほとんど、自殺に近いよ。それに、艦隊は自爆前に小転移したよね。あれが気にかかる」
「それは、自分を艦隊の自爆の巻き添えにしないためでしょ」
「自爆させなくても、管理システムの中身だけ消せばよかったのに」
そこには、市民社会の中の協力者のリストがあったかもしれない。
「船内にいた、他の部下を始末したかったのかもしれないわ。色々と、組織内の事情もあったでしょうから」
わたしたちの包囲の中で、小艦隊の船は、一隻残らず自爆してのけた。その後、わたしたちがジョルファを宇宙空間で拾い上げた時、彼女は既に、記憶のかなりの部分を失った状態だったのだ。
子供の頃の記憶や、軍人時代の記憶は残っているけれど、辺境に出てからのことはおぼろになり、ここ数年以内のことは、ほとんど覚えていない。
おまけに、彼女は妊娠していた。本格的な尋問にかかる前に、出血を起こして倒れたのだ。
わたしたちは流産の危険が高いと見て、母子分離手術を行った。親が何者だろうと、子供に罪はない。
胎児はどうやら遺伝子異常の様子だったので(強化体と普通人の間で子供を作れば、大抵そうなる)、人工子宮に入れて、故郷の麗香お姉さまの元へ送った。

やがて、麗香お姉さまからは、子供は助からなかったという報告がきた。こちらできちんと埋葬するから、それで納得するようにと。
わたしたちはそれを、ジョルファ……いえ、リアンヌに、じかに伝えることにした。とある植民惑星の、辺鄙な山中の隔離施設で面会した時、彼女は自分を捕まえたハンターに対して、平静な態度だった。
「わざわざ来てくれて、ありがとう」
子供の話を、通話や司法局経由の通知で済ませなかったことで、こちらの誠意を汲んでくれた。元々、聡明な女性なのだ。
子供が助からないことは、出血した時から覚悟していたらしい。いずれ、どこかに中身のない墓を作るつもりだという。
「子供の父親のことは、どうやっても思い出せないけれど、でも、自分で納得した妊娠だったと思うの」

リアンヌと別れて、車で田舎道を走りながら、紅泉は言う。
「彼女の相手は、もしかして、本物のグリフィンだったのかもしれないね」
「そうなのかしら……」
「その男がもし、本気でリアンヌを愛しているのなら、後から取り戻そうとするかもしれない」
紅泉は、発想がロマンティックすぎる。でも、それが紅泉のいいところだから、無下に否定することもできない。
「さあ、どうかしら。本気で愛しているなら、このまま市民社会に託そうとするかもしれないわ。その方が、穏やかに暮らせるもの」
そんな優しい男、辺境にいるとは思えないけれど。
本当は、リアンヌを都合よく利用して、追い払っただけかもしれない。だとしたら、彼女は捨てられてよかったのだ。これから新しい名前で、新しい人生を始められる。
「とにかく、懸賞金制度は始まってしまった。要人暗殺は続く。あたしたちは、自分にできることを続けるだけだ」
「ええ、そうね」
そこで紅泉は、少し申し訳なさそうな顔になる。
「ごめん。探春には、苦労をかけるばっかりで」
これだから、憎めないのだ。手当たり次第にボーイハントする姿を見ると、どうやって懲らしめてやろうかしら、と思うけれど。
「あら、どういたしまして。でも、悪いと思っているなら、次のバカンスは雪の温泉宿がいいわ」
紅泉はにやりとして、運転しながら敬礼してみせる。
「承知しました、姫」
わたしはこれで、十分に幸せだった。結婚も出産も、関係なくていい。この人についていけるパートナーは、わたしだけなのだもの。
懸賞金リストの更新は、グリフィンの名で続いていた。要人の暗殺や、暗殺未遂事件も、年に何件かは起きている。
司法局としては、最高幹部会が、新しいグリフィンを立てたのかもしれない、と言い訳するしかない。あるいは元々、特定の個人ではなく、単なる役職名なのかもしれない。
リアンヌは隔離刑に服した後、軽い整形手術を受け、新しい名前での市民登録を済ませて、市民社会でひっそり暮らすようになった。司法局が世話した事務仕事をしていれば、出世はできないけれど、穏やかな日々を過ごせる。
司法局は、彼女に違法な接触がないか、十年以上も監視を続けたけれど、彼女を妊娠させた男が、あるいは《フェンリル》の旧部下たちが、彼女を取り戻そうとすることはなかった。
そのうち、彼女の過去を知らない男性が、溢れる善意で求婚した。
「あなたはいつも遠くを見ていて、寂しそうだ。ぼくと一緒に、賑やかな家庭を築きませんか?」
彼女はいったん断ったけれど、やがて、その男性の熱意にほだされた。そして、ルビーの指輪を、引き出しの奥深くへ仕舞い込んだ。
彼女が辺境で受けた不老処置は、遺伝子を改変する恒常的なものではなかったので、妊娠と出産を禁じられることはなかった。今では元気な子供たちに囲まれ、楽しく忙しい毎日らしい。それでこそ、わたしたちが逮捕した甲斐がある。
一方、リアンヌの抜けた《フェンリル》では、女性の部下が昇進して、商業部門の運営を引き継いだけれど、リアンヌほどの統率力はなかったらしい。
やがて、アマゾネス軍団は解体され、リアンヌが集めた女たちは、どこかへ散っていった。
《フェンリル》の商業部門は、男の幹部が引き継いだ。最高幹部会の代理人を務めるリザードの権力には、何の変わりもない。
元々、違法組織の中で、女たちのグループが力を持つこと自体、異例だったのだ。辺境はやはり、男優位の世界のまま。
辺境のあちこちで、今日も、グリフィンの紋章を付けた艦隊が動いている。
