
ミッドナイト・ブルー グリフィン編 前編

俺は想像もしなかった。この世界に、俺を誘拐しようと企む者たちがいるとは。
女ならともかく、男なんか誘拐して、何の役に立つ!?
俺が目障りなら、ただ殺せばいいだけではないか。
たぶん、もう真夜中近い。
怒りの発作が幾度も押し寄せ、虚しく過ぎ去った後だ。まだ絶望しきってはいないが、甘い期待は失せている。
象どころか、大型恐竜でも破れないような特殊合金製の、二重の檻の中にいるのだ。しかも素裸に剥かれ、腰にバスタオル一枚を巻いただけという、情けない姿。
ライダースーツもブーツも銃も予備の弾倉も、通話端末もナイフも偵察虫も小型爆弾も、所持品は全て取り上げられている。
ここは、どこかのビルの地下倉庫だろう。片隅に古いコンテナが幾つか積み上げてあるだけで、長らく使われた形跡がない。
俺を拉致してきたトレーラーは、ひしゃげた俺のバイクを積み込んで、既に立ち去っている。一ダースはいた見張りのアンドロイド兵士すら、俺をこの檻に押し込めると、どこかへ引き上げてしまった。誰かがビルの警備管制室にいれば、それで十分というわけだろう。
外界の物音は、一切届いてこなかった。凍死するほどの寒さではないが、暖かいとはいえない。俺は強化体だから、裸でも風邪はひかないが、ずいぶんな待遇ではないか。
はるか頭上の街は、クリスマスの飾りで燦然ときらめき、華やかなバイオロイド美女を連れた盛装の男たちが、シャンパンで乾杯しているというのに。
左右の足首には、爆弾入りの枷がはめられていた。俺がこの枷を外そうとしたり、何らかの方法で脱走しようとしたりすれば、即座に、膝から下を失うと警告されている。
どのみち、この檻は特別に頑丈だ。試しに揺さぶってみたり、蹴りを入れたりしてみたが、びくともしない。俺の腕力を知っている者が、念を入れて用意したのだろう。
そもそも、倉庫の四方の壁と天井には、警備レーザーの砲塔が何十と据えられ、俺の動きを追尾している。いくら強化体でも、数千度の熱線を浴びせられたら、消し炭だ。
(いずれ、誰か人間が来るだろう)
と覚悟して、待ちの態勢に入っているが、不可解だった。
俺を誘拐して得をするのは、いったい誰だ。
これまでに殺した誰かの身内から、逆恨みでもされているのか。
しかし、辺境の違法都市で暮らすチンピラや小悪党に、そんな情の濃い身内がいるとは思えない。
(まさか、身元を知られた上での誘拐か)
俺自身ははみだし者にすぎないが、故郷の一族は資産家だ。《ティルス》、《インダル》、《サラスヴァティ》、繁栄する三つの小惑星都市を建設・運営し、その上がりで優雅に暮らしている。
その一族から、身代金でも取ろうという企みか。
しかし、俺は若い頃の家出以来、一族とは連絡を絶っている。出来損ないの不良息子の命など、一族の側が、平然と無視するかもしれないだろう。
(ああ、わかってるよ、ショーティ)
俺が悪かった。
危険だからバイクはやめろ、単独の外出はするなと幾度も言われていたのに、無視した報いだ。
だが、船やビルの中で隠れ暮らすことにうんざりすると、無性に外を走り回りたくなるのだ。
ヘルメットで顔を隠していれば、特に注目されることはないと思っていた。違法都市の街路には、たくさんの車やバイクが行き交っている。
ほんのたまの気晴らしだったのに、いつから狙われ、罠を張られていたものか。
――昼間、バイクで市街を走り回っている時だった。繁華街の中の大通りだというのに、道路前方にいきなり、金属製の大型ネットが立ち上がったのだ。
ブレーキも急ターンも間に合わず、飛び越えることも不可能で、俺はバイクごと金属ネットに突っ込んでしまった。
丈夫なヘルメットと緩衝材入りライダースーツのおかげで、深刻な怪我こそしなかったが、バイクがひしゃげ、ネットが大きくたわんだところに、粘着弾の集中砲火をくらった。
そして、バイクと一体化する形で、ネットに張り付けられてしまった。トリモチにかかった虫同様だ。
すると、通りの左右のビルから、所属不明のアンドロイド兵士が十体以上、即座に湧き出してきた。そして、ネットを大きく切断し、彫像化した俺を貨物トレーラーに担ぎ込んだのだ。
その間、大通りへの他の車の流入は、阻止されていた。
ネットが出現するまで、俺の前後を走っていた車は、俺が罠に気づかないように誘導する、サクラだったに違いない。俺の他に、車やバイクでネットに突っ込んだ者はいなかったからだ。
前もって、都市の管理機構に許可を得ていた捕獲作戦だ。関係者に金さえ払えば、違法都市では何でもできる。
俺を積み込んだトレーラーは、複雑な迷路になっている地下通路を、二十分ほど走り回った。
一般車両の入れる連絡用通路と、都市機能を維持するためのインフラ用トンネル。そして、許可を得た者しか通れない秘密通路が、複雑に交錯している立体構造の迷路だ。
ショーティの操る警備用の偵察鳥や偵察虫は、俺の様子がわかる距離にいたはずだが、そいつらにも、地下トンネルの奥までの追跡は無理だ。尾行しても、センサーで発見され、レーザーで焼却されたことだろう。
俺を乗せた車に張りついた偵察虫がいても、おそらく発見され、処分されている。ショーティが車の行方を突き止め、救援を寄越してくれる可能性は、きわめて低い。
そうして降ろされたのは、ここだ。
まずは、空気に触れて硬質化した粘着材を、専用の薬剤で乱暴に溶かされた。襟の中まで、刺激性のある薬剤が侵入してくる。
そして、全身に絡みついたどろどろの残滓を、高圧ホースの冷水で、容赦なく洗い流された。泥付きの芋だって、もっと優しく扱われるだろうに。
それから、裸に剥かれて檻に押し込まれた。与えられたのは、バスタオル一枚きり。速乾性だから、濡れた躰を拭いても、すぐ乾いたのが救いだが。
(最悪、闇から闇だな)
怒りもあるし、恐怖もあるが、何より、阿呆らしかった。
(俺の人生、こんなもんか)
自分の組織を拡大して力を蓄え、いつか〝連合〟を倒して世界を変えてやる、と意気込んでいたのに。
これなら、一族の中にいた方がましだったのではないか。たとえ年長者たちに監視され、従姉妹の探春に軽蔑されながらでも。
(いや、だめだ)
聡明で優美な従姉妹の、
(死ねばいいのに)
という冷淡な視線には、とても耐えられなかった。
俺には冷たいくせに、親友の紅泉には、無限に優しい視線を向ける。あいつが何をしでかしても、苦笑で後始末してやる。紅泉こそ、俺なんかより、はるかに無茶な奴なのに。
もしも一族内にいて、その格差を日々味わっていたら、俺はいずれ爆発し、無駄に荒れ狂い、事態を余計にこじらせていただろう。
そうなる前に、外へ飛び出すしかなかった。
以来、一族に頼らず、自分の知恵と度胸で生き延びてきたつもりだ。途中からは、知能強化に成功した、相棒のショーティに頼りきりだったかもしれないが。
(茜、笑ってくれ。これで終わりなら、俺もしょせんは野良犬だったんだ)
檻の中で胡座をかいたまま、いつも頭の中にいる女に語りかけた。
(おまえを失った時、もっとましな男になると誓ったのにな)
あれからできたことは、他の中小組織を幾つか乗っ取り、多少、勢力範囲を広げたことくらいだ。
それも〝連合〟にマークされないよう、洗脳した人間や、ショーティの操る有機体人形を表に立てて。
辺境で使い捨てられている大勢のバイオロイドたちを救いたいという願いは、依然、遠い目標のままだ。
かろうじて、自分の組織内でのみ、バイオロイドたちの待遇改善を実現できただけ。
彼らを五年で殺す必要など、そもそもないのだ。ちゃんと遇してやれば、彼らが人間の主人に反逆を企むことはない。
本当は、彼らを独立させ、自分の道を自分で決めさせるのが筋なのだが……
現実問題として、彼らの労働力なくして、組織の維持は難しい。いくらショーティが、無数のアンドロイド兵士を巧みに操ってくれるとしても。
広大な辺境の宇宙に、本物の人間は、わずか数億人しかいない。
その十倍ほどの人数のバイオロイドが、便利な下働きとして利用されている。ろくな教育を与えられず、人権も認められないままに。
本当は、人類の改良種である彼らこそ、これからの文明の主役かもしれないのに……
そこで、動きがあった。車両用の大扉ではなく、人間用の扉が開き、たくさんの足音がやってきたのだ。
二重の檻の中に座ったまま、俺は唖然とした。
パーティ帰りのような、きんきらした連中だ。
いや、実際に、クリスマス・パーティの途中でやって来たものか。
十名ほどの男たちは、黒やシルバーグレイのタキシード姿。数少ない女たちは、華やかなドレスを着て、宝石をきらめかせ、絹や毛皮のストールを羽織っている。
彼らの周囲には、制服を着たアンドロイド兵士の壁があった。その制服は、紺や深緑や黒など、何種類もある。
俺は、兵たちの徽章を目で確認した。いずれも六大組織のものだ。《黄龍》、《アスタルテ》、《ティアマト》、《エンプレス・グループ》、《キュクロプス》、《ヘカテ》。男優位の辺境で、なぜか組織名に女神の名が多いのは皮肉だが。
まさか、この連中は!?
「あらあら、野生の狼さんが可哀想に」
「いい格好だ。記念撮影してやろうか」
「やめた方がいいぞ。恨まれる」
「どうせなら、タオルなしで鑑賞したいわ」
「それは、個人的に口説かれたらいかがです?」
「噛みつかれそうねえ」
総勢で十五、六名の男女が、談笑しながら檻を取り囲んだ。俺はまさか、競売にかけられるんじゃないだろうな。生体実験の素材として。
あるいは、ローマ帝国時代の見せ物のように、闘技場で剣を持たせ、人造の怪物と戦わせるつもりとか。
すると、パーティの余興が、俺の人生の終着点か。
「やあ、シヴァ」
胸にカトレアを飾った恰幅のいい金髪男が、気安い態度で俺に呼びかけてきた。
なぜ、俺の本当の名前を知っている。その名前は、ここ二十年あまり、俺とショーティの間でしか使っていないのに。
いや、わずかな期間だけ、茜も俺をその名で知っていてくれたが……ついに、茜の声を聞くことはなかった。手話と文字が、茜の表現手段だった。
「少しは、頭が冷えたかね。じき、きみの相棒も届く頃だ」
何だって。
まさか、ショーティまで捕まったのか。
それでは、もう何の望みもない。俺たちは、俺たちの他に頼る者を持たないのだから。
「悪いが、きみたちの組織も、全て接収させてもらった。代理人に運営させていたダミー組織まで、一つ残らずだ。したがって、きみに残っているものは、その身一つだけということになる」
ダミー組織の名前を幾つも挙げられて、ようやく得心した。
もう間違いない。子供の頃、一族の中で習った知識の通り……こいつらは、最高幹部会だ。
辺境の宇宙を支配する、最高権力者の集まり。
この金髪男は《黄龍》のトップ、デュークと呼ばれる男だろう。
栗色の髪をした色白の美男子はナルシス、《アスタルテ》の大幹部。
プラチナブロンドに白いドレスの、豊満なマシュマロ女は《キュクロプス》のメリュジーヌ。
深紅のドレスの、すらりとした長身の金髪女は《ヘカテ》のリュクス。
黒い長髪を一つに縛った、浅黒い肌の男は《エンプレス・グループ》のハヤテ。
他もそれぞれ、普通なら、姿も拝めない大物たちだ。そいつらがなぜ大集合して、俺なんかの前に現れる。
そこへ、アンドロイド兵士に押され、台車に載せられた透明カプセルが登場した。俺は思わず立ち上がり、内側の檻の太い金属棒を握ってしまう。
ショーティだ。
強い麻酔をかけられているらしく、カプセルの底面でだらりと舌を垂らし、ぐったり横になっている。
知らない者が見れば、ただの大型犬にすぎないが、俺には唯一無二の親友だった。
人間を凌駕するほどに育った奴の知力があればこそ、俺たちは、今日まで生き延びてこられたのに。
「見ての通りだ。きみは、我々の言う通りに働くしかない。我々というのは、〝連合〟の頂点たる最高幹部会のことだがね」
呼吸を鎮めるのに、数秒かかった。
「……つまり、俺に、おまえらの犬になれと?」
「断るのなら、きみもショーティも冷凍保存だ。新たな使い道ができるまで、何十年でも眠っていてもらうことになる。出番がなければ、そのまま永眠かもしれないな」
デュークはそれを、何の悪意もない、温和な説明口調で言うのだ。いや、俺の無力を憐れんでさえいるかもしれない。
燃えるような激しい怒りの発作が、俺の体内を駆け巡った。
叫びたい。暴れたい。
檻を打ち壊して、こいつらをぶち殺したい。
だが、俺の中には、それを止める俺がいる。
――感情に流されるな。また後悔するぞ。
もう六、七年前になるのか。茜を失った時、一生分くらい、のたうち回って苦しんだのだ。せっかく愛してくれた女を、俺は守れなかった。絶望する必要のないことで絶望させ、自殺させてしまった。
あれから何年も、ただ息をするのさえ苦しかった。茜の遺品を見ることすら、耐えられなかった。
他組織の乗っ取りを繰り返し、ひたすら勢力拡大に打ち込むことで、ようやく、息がつけるようになったのだ。
そしてその頃、偶然に、幼馴染の従姉妹たちの消息を知った。俺が自分のことしか考えていなかった頃、彼女たちは、もっと高い理想を追っていたのだ。
彼女たちの前に出られる自分ではないが、今なら、少しは役に立てるかもしれない。
そう思って、ショーティと共に、あれこれの工作を行ってきた。従姉妹たちの命がかかっていると思えば、知恵も湧く。市民社会の不満分子を、手先として利用することも覚えた。
そういう経験のおかげで、少しは賢くなっている。俺とショーティが生き残るには、どんな屈辱にも耐えるしかない。
「……何をさせたいんだ」
やっとのことで、言葉を絞り出した。すると、デュークは満足そうに言う。
「それは、この男が説明する。紹介しよう。《フェンリル》の代表者、リザードだ。きみの身柄は当面、彼に預けることにする」
俺はぎょっとして、前へ出てきた細身の伊達男を注視した。
七三分けにした金髪。極地の氷山を思わせる、アイス・ブルーの目。白い肌に整った顔立ち。洒落たグレイのスーツに、白いポケットチーフ。
知らない者が見たら、作家か大学教授と思うのではないか。それが、静かに会釈して言う。
「よろしく、シヴァ」
奴だ。
俺の船にチンピラ連中を送り込み、茜が死ぬ原因を作った男。
いや、このリザードが主犯でなかったことは、今わかった。あの一件もまた、最高幹部会の差し金だったに違いない。
おそらく、俺に対する試験だったのだ。俺がどんな性格で、何が弱点で、どこまでやったら爆発するか。
そのために、俺とショーティは、無人の売りビルにおびき出された。船で留守番していた茜は、侵入者たちに強姦され、自分の頭を銃で撃ち抜いて死んだ。いったん〝汚れて〟しまった以上、あとは俺に見捨てられるだけだと、一人で絶望して。
そんなことくらいで、俺が嫌うはずはない、捨てるはずはないと、あの時の茜には、わからなかったのだ。
俺が娼館から〝新品〟の茜を買い取って、たった三か月。
バイオロイドには何の権利もない、五年で廃棄される道具にすぎないという、培養時の洗脳が、まだ抜けきっていなかった。
せめて、もう三か月、一緒に暮らしていれば。茜は心底から、俺たちの愛情を信じてくれたはずだ。どんな目に遭っても、絶望して死ぬ必要などないのだと、わかってくれただろうに。
「では、後はお任せを」
リザードが大物たちに一礼すると、彼らは満足したようで、潮が引くように引き上げていった。
「ここは寒いわ」
「上で飲み直しましょう」
「新年は、どちらで過ごします?」
「実は、新しい別荘を手に入れてね……」
呑気なざわめきが遠ざかり、扉の向こうに消えた。たぶん、最高幹部会の定例の会合を、今回は、この都市で開いていたのだろう。ショーティの入ったカプセルも、一緒に運び去られてしまった。
後に残ったのはリザードと、その秘書らしき青いスーツの女、護衛らしきダークスーツの男。それに、一ダースほどの迷彩服のアンドロイド兵士。むろん、兵たちの銃口は俺に向いている。
「暴れないと約束してくれるなら、そこから出そう」
中肉中背のリザードは、穏やかな観察者の視線で、檻の中の俺を眺めていた。抜け目ない商売人というよりは、研究対象を見る学者のようだ。俺は、捕獲した大猿か?
「約束する。足首が吹き飛ぶのは、ごめんだからな」
俺が怒りをこらえて言うと、リザードは、横にいたダークスーツの護衛に言った。
「出してやってくれ。すぐにルワナが来る」
その護衛の男は――いや、待て。
これは女だ。
褐色の髪を短く整え、骨太で筋肉質の大柄な体格を、堅いミッドナイト・ブルーのスーツに包んでいる。だが、胸と腰に、隠しきれない厚みがある。
黄みがかった浅黒い肌をして、化粧気はまるでないが、顔の造作が男より柔らかい。耳たぶには、小さな金のイヤリングが光っている。
飾りといえば、それだけだ。それなりに見られる顔立ちをしているが、美人というよりは、質実剛健と形容するのが相応しい。
(そうか、こいつがジョルファだ)
リザードの右腕として、組織の商業部門を統括している女。
茜の事件の後、《フェンリル》については調べ尽くしたから、覚えている。
そうでなくても、辺境では元から有名人だ。『自分を裏切った恋人を、去勢した女』として。

このジョルファは、直属の部下を、女ばかりで固めている。他組織の乗っ取りや取り潰しを繰り返し、自分の権勢を増してきた。
逆らう者や裏切った者は、幾度も公開処刑にかけていることから、『男嫌いのアマゾネス軍団の長』として、辺境中から恐れられている。
男優位の辺境で、女ばかりの集団が畏怖されているのは、稀有なことと言っていい。
俺が戦慄したのは、ジョルファの褐色の目に、明らかな敵意と軽蔑がたぎっていたからだ。
俺個人に対する敵意、だけではない。
この女は、世界中のありとあらゆる男を憎み、軽蔑している。
かろうじて、その憎悪から逃れているのは、彼女を『違法ポルノの撮影現場』という生き地獄から救い出した、リザードだけだろう。
もっとも、彼女は何年も、そのリザードのおかげで、組織の最底辺の地獄に沈められていたわけだが。
元は、惑星連邦軍の軍人。
本名は、確か……リアンヌ。
リアンヌ・ルナンだったか。
図体に似合わない可愛い名前だったので、改めて資料を見た時、意外に感じたことを覚えている。
彼女の〝主演した〟……いや、〝主演させられた〟映画を見たのはもっと前のことで、その時は、名前など気にしなかった。
軍人として、普通に勤務していたリアンヌは、ある時、恋人だった男に誘われて、軍の練習艦を盗み、一緒に辺境に出てきたという。
無論、その男は、リアンヌを愛してなどいなかった。ただ、辺境で生き残るために、戦闘指揮のできる相棒が必要だっただけだ。
だから、男に免疫のなかった純情なゴリラ女をたぶらかし、自分の用心棒として利用した。
愛されていると思えば、女はせっせと男に尽くす。
若い頃のリアンヌも、戦闘についてはプロだったが、男を見る目は育っていなかったらしい。
二人は何年もかけて、自分たちの組織を育てた。部下を集め、商売を工夫し、輸送船団や護衛部隊を充実させた。
ところが、組織が育ってくると、男の方が、中堅どころの組織にスカウトされた。既存の組織はそうやって、若い組織を取り込んでいく。
大抵の場合、若手は都合よく利用されるだけだが、男は、自分が認められたのだと勘違いした。
手堅く運営されている中堅組織の幹部になれるのなら、もはや個人的護衛は必要ない。そもそも、リアンヌがいては、バイオロイド美女の愛人も持ちにくい。
不用になったリアンヌは、一服盛られた。そして意識不明のうち、他組織に売り飛ばされた。
辺境では珍しくもない、裏切りの物語である。
そうして売られた先が、《フェンリル》だったわけだ。
違法組織は大抵、娼館経営や違法ポルノ製作で稼いでいる。彼女はそこで何年も、残虐な違法ポルノの撮影に使われた。
中央の市民社会では決して許されない、悪質な実写映画だ。輪姦や獣姦は当たり前。拷問に近い強姦が繰り返され、撮影される。そういう作品には、根強い需要があるのだ。
普通の女なら、一本か二本の撮影で心を病んでしまうような、苛酷な撮影現場だという。肉体の傷は治せても、心の傷は治せない。
本人の短期記憶を抜くことはできるが、それを繰り返すと、痴呆化してしまい、新鮮な素材ではなくなってしまう。
だから大抵は、安く手に入るバイオロイドの女子供が撮影に使われ、ズタボロにされて、廃棄される。殺す場面まで、しっかり映画に取り込むのだ。
『本物の人間の女』をそういう撮影に使うのは、あまりにも高くつくので、リアンヌのような頑丈な女を、〝主演女優〟として繰り返し使えた監督は、さぞ喜んだことだろう。
俺も、好奇心でその映画を見た。元軍人の、本物の女が使われているという宣伝だったので。
茜と出会う、何年も前のことだ。言い訳させてもらえば、最初の一本で辟易した。したがって、シリーズ化された後の作品は見ていない。確か、十数本は作られたのではないか。
抵抗する力を持たないバイオロイドの女より、必死で逃げたり、全力で反撃したりする『本物の女』の方がいいという連中が、かなりいるのだ。
特に、このジョルファの場合、身一つで野山に落とされ、武器を持った男たちの一団に追われても、知恵と力の限りを尽くして、最後まで抵抗するという姿勢が……演技ではない、本物の抵抗ぶりが……その後の強姦の場面を盛り上げるということで、評判が高かった。
だが、俺は楽しめなかった。
探春が聞いたら信じないだろうが、俺は元々、女子供が痛めつけられる映画は好きではない。
それよりもっと、物語性の豊かな、ロマンティックな作品が好きだ。ショーティに知られて、からかわれるのが厭だったので、中央製の恋愛映画やソフトポルノは、自室でこっそり見ていただけだが。
とにかく、その手の映画は、辺境で売られるばかりではない。市民社会に何億人といる、密かな愛好家の元へも届く。
表向きは紳士然とした男たちが、妻や娘には内緒で、女子供を犠牲にする違法ポルノを楽しんでいるわけだ。
当局が取り締まっても、違法組織の側は、あらゆるルートで作品を売りさばく。彼らにとって、手堅い収益源だからだ。
元軍人という、毅然とした女闘士が、大勢の男たちに追い回され、狩り立てられ、抵抗を封じられ、徹底的に陵辱される姿を、どれだけの男が楽しんだことか。
おかげで、リアンヌの魂には、男種族全体に対する、冷酷な憎悪が染み付いたのだろう。
彼女は自殺も発狂もせず、希有な体力と精神力で、その数年間を耐え抜いた。そして、たまたま撮影現場を視察に来たリザードに、体当たりで直訴したという。
自分には、もっとましなことができる。それをポルノにしか使わないのは、大きな無駄だと。
リザードは、彼女の生命力と、強い闘志を評価したのだろう。彼女にジョルファという新しい名前を与え、組織内で引き立てた。
地獄から這い上がった者は、強い。
彼女は猛烈な勢いで働き、あっという間に、組織内での地位を固めたという。
それから数年後、十分に出世した後で、ジョルファは、自分を裏切った元恋人を探し出し、捕まえた。
元恋人の方は、引き抜かれた先の組織で、下っ端暮らしに甘んじていただけのようだ。元は技術者だったというが、しょせん、女の手を借りてしか、辺境に出られなかった男。その組織も《フェンリル》に比べれば、はるかに格下だったので、彼を救う者は誰もいなかった。
ジョルファは彼を、自分が担当するようになった映画部門で、撮影に使った。皮肉にも、彼女がリザードから任された商業部門には、違法ポルノの商売も含まれていたのだ。
その映画は、森の中で迷子の少女を捕まえて乱暴した男が、少女の庇護者であるアマゾネス軍団に捕まって、報復を受けるという、歴史ファンタジー仕立てのポルノだった。
アマゾネスの女たちは男を必要とせず、女だけで楽しむ。捕まった男は奴隷として、女たちの快楽に奉仕させられるだけ。
映画の最後で、男は女たちに去勢される。
切り取られた肉塊は、血まみれのまま黄金の皿に載せられ、女たちの崇める、戦いの女神に捧げられる。この儀式の場面が、映画のハイライトだ。
その切断場面は特撮でも何でもなく、本物の実写だった。
いや、俺は怖くて見ていないが(見たら絶対、うなされる!!)、そういう筋立てだそうだ。
ジョルファはその映画を派手に宣伝し、世界中に撒いた。辺境にも、市民社会にも。
そうして、自分がおとなしく泣き寝入りする女でないことを証明した。映画と同様に、アマゾネス軍団を率いて、辺境に睨みを効かせるつもりだと。
その男は去勢された後も、しばらく違法ポルノの素材として飼われていたが(女を犯すことはもうできないから、惨めな役回りばかりだったらしい)、後日、ロケ現場で見張りの隙をついて、自殺したという。
無理もない。
辺境中の男たちが、密かに同情したのではないだろうか。
今では、ジョルファの監督下で製作される違法ポルノは、女同士の絡みがメインだ。男は添え物にすぎず、撮影でバイオロイドを責め殺すこともないという。
それはそれで、固定ファンが付く。ショーティが調べてくれた限りでは、きわめて人道的な撮影現場になっているらしい。
つまりは、筋の通ったアマゾネスだ。おそらく紅泉ならば、ジョルファのことを、自分の同志だと思うのではないだろうか。
そういう〝伝説の猛女〟と間近に向き合った俺が、真っ先に感じたのは、急所が縮み上がるような恐怖である。
(まさか俺も、ちょん切られるんじゃないだろうな!!)
嘘だろう。
勘弁してくれ、それだけは。
確かに俺は、女に尊敬されるような男ではない。娼婦を買ったこともあるし、それ以前に、従姉妹を強姦するという事件も起こした。
しかし、あれは片思いが嵩じた結果だ。
悪意ではなかった。
何と言い訳しても、探春本人が許してくれないのはわかっているが、その後悔があったからこそ、茜には精一杯優しくしたつもりだ。
しでかしたことについては、深く反省している。
二度と絶対にしない。
だから、去勢だけはしないでくれ。
まして、その場面を撮影され、世界に公開されるなどということになったら。自分が生きていられるかどうか、確信がない。
俺は内心の恐怖と動揺を、深く押し隠しているつもりだったが、リザードには見抜かれたらしい。哀れむように微笑まれた。
「彼女はわたしの片腕、ジョルファだ。これからは、きみと協力して働いてもらうので、仲良くしてくれたまえ」
冗談ではない。
ジョルファ本人は仲良くどころか、明らかに、俺を下劣な下等動物と見なしている。
俺について、どれだけの予備知識があるのか知らないが、凍るような目付きで一言、冷ややかに、
「よろしく」
と言っただけだ。
わたしに迷惑をかけるな、隙があったらいつでも殺す――と宣告されたに等しい。
「何について、協力するというんだ?」
俺が用心しながら尋ねると、ジョルファは馬鹿を見下すような顔で言う。
「きみが職務を遂行できるよう、必要な助力を行う。きみが不適格とわかれば、きみに代わって任務を遂行する」
つまり、俺の監視役ということか。
どんな職務が課せられるのか知らないが、こんなゴリラ女に背後から監視されていたら、それだけで手元が震えて失敗しそうではないか。

ジョルファの指図で、俺が兵たちの手で檻から出されると、じきに車両用の大扉が開いて、大型トレーラーが倉庫内に進入してきた。こちらに横腹を向けて停止すると、前部と中部の扉が開いて、《フェンリル》の紋章を付けた、黒と銀色の制服姿のアンドロイド兵士の群れが降りてくる。
その中にちらりとオレンジ色が見えたのは、兵たちを指揮する人間の女らしい。
合計、二ダースほどの兵士が、俺の護送に当たる。用心深いことだ。無数の銃口に狙われた上、足首に爆弾が付いているのだから、下手に暴れるつもりはないのに。
「詳しい話は、明日にしよう。今夜はもう遅いし、きみも、その格好では落ち着かないだろう。車に乗りたまえ。我々の船へ招待する」
リザードはそう言って俺に背を向けると、女秘書やジョルファと共に数体の護衛兵に囲まれ、トレーラーに向かった。三人とも、前部扉から車内に消える。
タオル一枚で立つ俺の前には、なめらかなココア色の肌をした、すらりと背の高い美女が残っていた。
柔らかくカールした短い黒髪、優しげな黒い瞳、上品な鼻筋、色っぽい厚めの唇。
威圧的なゴリラ女を見た後では、なおさら好ましく思える、優美な女だ。淡いオレンジ色のドレススーツを着て、揺れる金のイヤリングを下げている。
「わたくし、ルワナと申します」
響きのいいアルトの声で名乗り、淑やかに一礼する。ふわりと、甘い香りまで流れてきた。
「これまでは、リザードさまの秘書室におりましたが、今日からはシヴァさま、いえ、グリフィンさまの第一秘書になります。どうか、よろしくお願いいたします」
不機嫌な裸の囚人を前にしながら、大企業の重役室にいるかのような落ち着きだ。
「グリフィンだと?」
「シヴァさまの役職名のようなものです。今日からは、そうお呼びしますので、お慣れになって下さいね」
俺の役職名?
確かに、シヴァという本来の名前で活動するのはまずいから(一族、もしくは従姉妹たちの耳に届いたら、どうなるか)、偽名は必要だ。
「リナという第二秘書もおりますが、今は別の役目を果たしていますので、後日、お引き合わせいたします」
何もかも、勝手に決められている。この分では、いつ寝て、いつ起きて、何を着て、何を食べるかまで、全て指図されるのではないか。
俺はルワナに連れられ、裸足のまま冷たい床を踏み、トレーラーの中部扉から、暖かい車内に乗り込んだ。無論、俺を見張る兵たちも一緒だ。
こういう大型車はしばしば、移動オフィスとして使われる。拠点を持たない駆け出しの若者など、ずっと車内で暮らすこともある。したがって内部には、ラウンジや執務室、厨房や洗面所、寝室などが巧みに配置されている。
前部扉から乗ったリザードたちは、そのまま、運転席のある前部区画に落ち着いたようだ。俺とルワナが入ったのは、後部区画である。
車はすぐ走りだし、都市の地下に広がるトンネル網に入っていく。
「まずはシャワーを浴びて、暖まって下さい。着替えと軽食を用意してありますから」
俺はルワナの勧めに従って寝室区画に入り、熱いミストシャワーを浴びた。冷えた皮膚に、心地よい刺激が走る。静脈を通して、体内深部に熱が伝わる。それからようやく、筋肉がほぐれてくる。足首の爆弾は、当然、濡れたくらいでは何ともない。
温風乾燥してシャワーブースから出ると、俺の体格と趣味に合う、まともな衣類が用意されていた。銃や通信端末は返してもらえないようだが、仕方あるまい。靴を履けただけで、かなりましだ。
それからラウンジのソファに移り、厚いハンバーガーと塩気の効いたフライドポテト、野菜サラダとアップルパイ、クリームたっぷりの濃いコーヒーで人心地ついた。飢えていては、考え事もできはしない。
その頃には、車は、回転円筒内にある1G市街区を離れ、0Gの長い連絡トンネルに入っていた。
回転体を守る厚い岩盤を通り抜け、小惑星表面に出ると、そこには、さまざまな船が停泊する桟橋地帯が広がっている。
俺とショーティの船も、その一画に停泊しているが、そこへ戻ることは、もう永遠にないのだろう。
奴はカプセルに入れられたまま、どこへ移送されていったものか。いくら賢くても、有能でも、冷凍睡眠にかけられたら、手も足も出ない。
ルワナはソファ席の俺にシートベルトを勧め、自分も俺と向き合う席でベルトをかけた。食事の残骸は兵士が片付け、固定されていない品物は全て、扉付きの棚に収納される。立ったまま警戒している兵たちも、壁の手すりやシートベルトで身を固定している。
「今夜のうち、概略だけ説明しておきますね。でないと、グリフィンさまも、安心してお寝みになれないでしょうから」
ルワナの穏やかな語り口、行き届いた世話ぶり、兵たちへの無駄のない指図、まるでベテランの女教師だ。もしかして、俺がこういうタイプを苦手にしていると知った上での人選か。
「グリフィンさまは、最高幹部会の新たな代理人として、年明けに世界デビューすることになります」
ああ!?
世界デビュー!?
「辺境では、最高幹部会からの公式発表ということになりますし、中央でも、公共の放送回線を乗っ取って全市民に通告します」
俺は唖然とした。
さらりと言ったぞ、何か途方もないことを。
「おい、何だ、その話は。年明けって、もう半月もないぞ。俺を、全世界のさらし者にするってことか!?」
「いいえ、グリフィンさまの素顔を、外部にさらす必要はありません。本当のお名前を知る者も、ごくわずかしかおりません。放送用の映像は、既にできています。〝最高幹部会の代理人〟たるグリフィンさまのお名前で、あるリストを公表するだけのことです。グリフィンさまが映像をご覧になって、細部の手直しをなさる分には構いませんが、大筋はそのままでお願いします」
おい、待て。
話が一方的すぎる。
「グリフィンというのは、最高幹部会の……直属の代理人という格付けなのか?」
「はい、そうです」
俺にとっては驚天動地のことでも、リザードの秘書であったルワナには、普段の職務の延長にすぎないらしい。リザード自身がそもそも、最高幹部会の代理人の一人だからだ。
リザードも他の代理人たちも、自分の組織を率いる傍ら、最高幹部会からの任務を請け負い、系列をまたぐ組織間の抗争の調停や、難事件の解決などに飛び回っているという。
「ご存じのことと思いますが、最高幹部会の代理人というのは、〝連合〟に属する、あらゆる組織に命令を下せる、辺境の超エリートです」
誰でも知っている。中央製の映画や小説では、よく敵の黒幕として登場するからな。
「現在、直属の代理人として活動しておいでの方は、二十名ほどですが、グリフィンさまも、そのお一人ということになります」
すると、リザードに近い立場だ。無論、新米の俺が、古株のリザードほど信用されるはずはないが。奴はおそらく、二百歳近いだろう。
それでも、超エリート階級の一員に加えてもらえるわけか。他の男なら、ひれ伏して感謝するところかもしれない。
だが、茜を殺したのは、奴らの無造作な冷酷。
ショーティは今後何十年でも、俺に対する人質として冷凍されたまま。
奴らは、俺の怒りと憎しみを知っていて、なお、俺を便利に使えると思っていやがる。
腹の中を灼く炎を感じながら、俺は尋ねた。
「つまり、俺を名目だけの責任者に据えて、何か厄介な仕事をさせようっていうんだな。おまえが俺の手足を操って、思い通りのダンスをさせる傀儡師か」
ルワナは子供をあやす乳母のように、にっこりした。
「名目だけ、ではありません。グリフィンさまは、実質的な権限をお持ちです」
「へえ、そうかい」
「わたくしには、グリフィンさまに命令する権限など、ないのですよ。ただ、リザードさまの意向をグリフィンさまにお伝えし、現場からの報告をまとめて、リザードさまに上げるだけの役目です。中継役と思って下さい」
俺の監視役、その二だな。
「そのリザードさまも、最高幹部会からの委託で動かれているに過ぎません。大きな決定は常に、最高幹部会でなされているのです。グリフィンさまも他の代理人の方々も、その枠内での行動が認められているだけです」
ああ、あの華麗な連中が、真の権力者であることは知っている。
噂では、最高幹部会すら誰かの操り人形だという話もあるが、それは、都市伝説のようなものだろう。人間を超える存在――超越体は、まだ実際に確認されたことはない。
「それじゃ、ただの人形でも、椅子に座らせておけばいい。俺のすることなんて、何もないんだろう」
「いいえ、そんなことはありません。これからグリフィンさまのお考えで、直属の事務局に細かい指令を出すのですわ」
ふん。無理難題命じられる、中間管理職か。
「事務局の人員は当面、百名ほどを予定しておりますが、そこから何千、何万という人間に指令が渡ることになります。実務がきちんと果たされるかどうかは、グリフィンさまの采配次第ですわ」
俺はどうも、この女に、幼稚園児扱いされている気がする。
ジョルファのような憎悪と軽蔑の視線も何だが、幼児扱いも……なぜか非常に懐かしい気がして、逆らいにくい。まるで、ショーティにお守りされているようで。
俺がどれほど怒ろうと、むくれようと、この女は淡々として受け流し、にこやかに俺を操るだろう。
「何の指令だ? 何のリストを公表すると言った?」
「市民社会の要人を三十人ほど列挙した、懸賞金リストです」
何か、非常に厭な言葉を聞いた気がする。
「懸賞金?」
「はい。政治家、高官、軍人、科学者、財界人、学者やジャーナリストなど、いずれも、選び抜かれた高潔な人物ばかりです。市民社会の柱となる人々ですね。誰であれ、これらの人物を暗殺した者に、最高幹部会から懸賞金を支払うという宣言です」
しばし、唖然とした。
市民社会の柱となる人物を、暗殺せよと奨励する!?
優雅な美女の口から、何という凶悪な企みがこぼれ出るのだ。
「要人の暗殺リスト……グリフィンというのは、暗殺を司る役職なのか!?」
「その理解で、間違いないと思います」
何ということだ。
よりによって、この俺が。
これまで、何十万という違法組織を束ねる〝連合〟は、辺境の宇宙でこそ、好き勝手に暗殺や闘争をやらかしてきたが、中央星域の市民社会に対する直接攻撃はしなかった。
水面下で要人の暗殺や、洗脳や誘拐は企んでも、公共放送を乗っ取ったりはしなかったし、軍に追われれば、反撃せずにさっさと逃げた。
つまり、『人類文明の正統』である市民社会に対して、自分たちは『裏の存在』であると自己規定して、遠慮のポーズを取っているはずだったのだ。
その方針が、大きく変わったというのか。
自分たちこそ『人類社会の本流』だと、ついに名乗りを挙げる!?
そして、市民社会を実質的に支配する!?
「できれば、懸賞金リストと呼んで下さい」
ルワナは、単なる呼称の問題であるかのように言う。これは、文明の転換点になりうる行為だとわかっているくせに。
ショーティが聞いたら、人類の暗黒時代の始まりだと評するのではないか。
「グリフィンというのは、この懸賞金制度の運営責任者のことです。グリフィンとしてのあなたの仕事は、これから市民社会の各地に現れるだろう暗殺志願者と連絡を取り、彼らに武器や情報、逃走用の船という、実務的援助を与えることです。要人の暗殺に成功した者は、〝連合〟のどこかの組織に、幹部待遇で迎え入れることになるでしょう」
それが、俺の仕事。
「そして、望む通りの不老処置や強化処置を受けさせる、か」
「ええ。辺境に出てくる者の目的は、ほとんどがそれですから」
それならば、餌に釣られて要人暗殺を試みる馬鹿が出てくるだろう。いくらでも。
人類の科学技術は、肉体の乗り換えによる若返りや、遺伝子操作による身体強化、薬品による延命などを可能にしているが、市民社会では、そういう行為につながる研究は禁忌とされている。
いったん不老処置や人体改造を認めれば、ありとあらゆる不死の怪物が誕生し、人類文明は取り返しがつかないほど変質するだろうと、恐れられているからだ。
だが、絶対の自由を是とする辺境では、多くの違法組織が総力を挙げて、不老不死や究極の進化を目指す研究に取り組んでいる。
市民社会でおとなしく老いていくことに耐えられない者たちは、家族や故郷を捨てて、辺境を目指す。
だが、特殊な才能があるとか、まとまった資金があるとかいう者でなければ、辺境で生き延びることは難しい。
この制度は、若さの他には何も持たない若者や、もはや失うものがない老人をそそのかす効果を持つのではないか。
「もちろん、細かい実務はグリフィン配下の事務局が行います。グリフィンさまは、大きな指示を出して下さればいいのです。どの暗殺志願者を援助し、どの標的を狙わせ、成功後はどの組織に受け入れるか、などですね」
それは、かなり面倒そうな仕事に聞こえるぞ。細かい情報を網羅しないと、判断がつかないことになりそうだ。これまで、厄介事はみなショーティに押し付けてきたが、今はもう、それができない。
「懸賞金システムに関連することならば、グリフィンさまは、〝連合〟に所属する全ての組織に指令を出すことができます。資材や艦隊はもちろん、市民社会の中に隠れている〝協力者〟を差し出すことも命じられます。最高幹部会から、それだけの権限を委託されているのです」
改めて驚嘆した。
ちょっと考えただけでも、すさまじい権力ではないか。
辺境には、大小百万を越す違法組織が散らばっていると言われているが、その上位半数は、あらかた〝連合〟に組み込まれている。
ことによったらグリフィンは、古株の代理人たちより、優位に立つこともできるかもしれない。
いずれは〝連合〟を倒そうという野望を持っていた俺でさえ、地位の高さにくらくらする。
下手をしたら、その地位に酔ってしまい、骨まで腐り果ててしまうかもしれない。
「とりあえず、事務局長は、わたくしが兼任いたします。ですが、適任者が見つかり次第、その職務は譲りますので。わたくしはあくまでも、グリフィンさまの個人秘書が本務です」
何でも勝手に言ってくれ。どうせ、全部決まっているんだろうから。
車は桟橋区域に出て、小惑星表面に張り巡らされた気密トンネルを走り抜けていく。
トレーラーの内壁の一部には、外部の光景が映されていた。トンネルの上半分を覆う透明天井の向こうに見えるのは、接岸した船の群れと、星を散りばめた暗黒の宇宙だ。入港する船、出航する船が、標識灯を灯して、蛍のように行き交っている。
俺たちの専用艦も護衛艦も、この桟橋のどこかにあるのだが、それはもう、接収されてしまったというからな。
あらゆる基地、あらゆる商売、あらゆる財産が全て取り上げられた今、俺にはもう、自分の命しか残っていない。
人間やバイオロイドの部下たちは、ボスが交替しても、組織の方針が変わっても、すぐそれに慣らされてしまうだろう。
慣れない者は、処分される。俺たちがこれまで築き上げてきたものは、全て無になる。
トレーラーはやがて、気密桟橋に停泊する船の一隻に吸い込まれた。車体が船内格納庫に固定されると、まず、リザードたちが前部扉から降りたようだ。それから、ルワナが俺を案内して降り、船内の通路をたどっていく。
アンドロイドの警備兵は、わずか数体が付き添うのみ。船の警備システムが俺を追尾しているから、それで充分なのだ。
リザードが移動用に使う船だそうで、さすがに広く、贅沢な居住区を持っていた。高い天井、緑の植え込み、あちこちに飾られた絵画や彫刻、金と白とクリームでまとめた上品な内装。
俺たちの船と違って、戦闘にさらされることなど、はなから想定していない。動く豪華ホテルというところか。
航行時には、強力な護衛艦隊が付くという。もちろん、『神狼のシルエット』という、有名な紋章付きの艦隊に、手を出す愚か者はいない。
「この船はじき、《ルクソール》に向けて出航いたします。そこに、《フェンリル》の商業部門の拠点がありますので。今夜はもう遅いので、お休み下さい。明日、朝食が済んだ頃に、お迎えに上がります」
俺を船室に導いたルワナは、戸口で一礼すると、後をアンドロイド侍女に任せて去っていく。警備兵は、扉の外に立つだけだ。
居間と客間、食堂と寝室、書斎や控えの間まで揃った、最高級の客室だった。まさしくVIP待遇。
何という変転だろう。つい半日前には、ショーティと冗談を言い合ったり、一人で気ままにバイクを飛ばしたりしていたのに。
居間の壁際に立つ女たちは、お揃いのエプロンドレスを着てはいるが、心を持たない、灰色の皮膚の機械人形だ。いざという時は、俺を捕縛するだけの戦闘能力を持っている。
「ウイスキーはあるか」
「はい、お好みの銘柄を取り揃えてございます」
あのルワナのことだ。準備に抜かりはないのだろう。
手近のソファに座り、表情のない侍女に氷と酒を持ってこさせ、厚手のグラスに入れて、ぐいとあおった。
飲んでも酔いはしないが、飲みたい気分だ。
この俺に、暗殺事業の監督をしろとは。
市民たちが、自分たちの代表者を自分たちの手で殺すようになったら、おしまいではないか。
多くの市民は誘惑されないと信じたいが、大金や不老処置に釣られて動く馬鹿どもは、必ず出る。十万人に一人でも馬鹿がいれば、市民社会全体では、無視できない危険因子になる。世界は確実に、悪い方に転がっていくだろう。
だが、なぜ俺なんだ!?
それだけの権限を持てる職なら、他にいくらでも、やりたがる奴がいるはずだ。
あのジョルファだって、自分がグリフィンになりたいんじゃないのか。だからあんなに、敵意を持った顔で俺を見るんだろう。
そこで、初めてはっとする。
もしかして、奴らは知っているんじゃないか。悪党退治のハンター〝リリス〟が、俺の従姉妹たちだと。
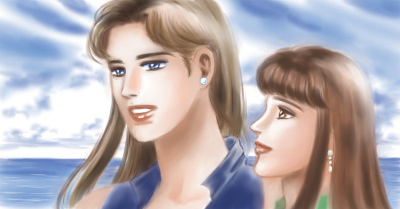
翌朝、強健な俺は、早く目覚めた。
広いベッドの上で、自分がどこにいるのか思い出すと、げんなりとしたが、とりあえず起き出して、軽い運動をする。
足枷は鬱陶しいが、ストレッチや腕立て伏せくらいで爆発はしない。
俺の動きを感知すると、アンドロイド侍女たちがやってきて、あれこれと世話を焼く。
熱いシャワーを浴びて、身支度した。強化体は基礎代謝が盛んなので、汗臭くなりやすい。運動も必要なので、一日に何度でもシャワーを浴び、着替えるのが習慣だ。
まして、これから、複数の女と顔を突き合わせるとなれば。
食堂で朝食を食っていたら、ルワナが現れた。今朝は象牙色の上品なドレスを着て、水仙のように涼しげだ。
「おはようございます、グリフィンさま。何か足りないものはございますか?」
涼やかな花の香りを漂わせて、秘書の見本のようだ。
「特にない」
着替えは寝室のクローゼットに詰まっていたし、食事も満足のいくものだ。米飯に味噌汁、出汁を入れて焼いた薄甘い卵焼き、大根おろしを添えた焼き魚、何種類もの漬物、素揚げした野菜と焼いたハム、温野菜を添えた醤油味のステーキ、緑茶、果物。
昔、《ティルス》の近傍にある最長老の隠居屋敷で育てられていた頃、よくこういう食事をしていた。茶の作法も教えられた。俺の育ての親は、地球から、自分の文化を運んできていたから。
だが、俺が地球を訪れることは、生涯ないだろう。地球は、中央星域の市民社会のど真ん中にあるからだ。
「九時になりましたら、リザードさまの執務室にご案内いたします。それまで、何かご質問がありましたら、どうぞ」
ルワナは俺に、静かな黒い目を向けていた。静けさの底に隠されているのは何なのか、まだわからない。
「一つ確認したい。懸賞金リストを見せてくれ」
ルワナは自分が持っていた紙製ファイルを、俺に差し出した。やはりだ。大物たちの名前の最後に、司法局の専属ハンター〝リリス〟の名前がある。
電子ファイルでないのは、これがまだ機密事項だという意味だ。
「実は、昨夜は大事なことを一つ、あえて言い残していました。それを聞いたら、お眠りになれないだろうと思いましたので」
「それは、気を遣わせたな」
皮肉で言っても、むろん彼女は動じない。
「いま、改めて申し上げます。最後の欄にある名前、司法局の専属ハンター〝リリス〟ですが……他の政治家や要人たちはほんのおまけで、この懸賞金制度の主眼は、〝リリス〟に市民たちの注目を集めることにあります」
覚悟していたつもりだが、やはり、腹にずしんとくる衝撃だった。そらとぼけるのは、時間の無駄。
「もう、知ってるんだな」
「はい。このお二人が、グリフィンさまにとって、大切な存在であることは」
そうだろうよ。
悪党どもは、人の弱みに付け込むのが得意なんだから。
――ここ数年ほどの話だが、俺とショーティは、物陰からこっそり、従姉妹たちの活動を見守ってきた。
そして、可能な限り援護してきた。
彼女たちを狙う敵艦隊を、横から奇襲して壊滅させたり。彼女たちの立ち回り先に、調査の手掛かりを撒いたり。彼女たちが気付かずにいる毒物や爆発物を、こっそり無力化したり。
最初はもちろん、驚き呆れた。根っから闘士の紅泉はともかく、おとなしい探春までが、悪党退治の仕事に乗り出すとは。
だが、事実は事実。
暴れすぎて、故郷の違法都市《ティルス》を追放され、あてのない武者修行の旅に出た紅泉に、親友の探春が付き添ったのが、ことの始まりらしい。
たまたま別の違法都市で、活動中の捜査官を助けたことで、司法局とつながりができ、市民社会の側に立つ仕事を引き受けるようになったのだ。
誘拐犯の追跡、拉致された被害者の奪回、要人暗殺犯の逮捕、違法組織とつるんだ民間企業の内偵など、仕事はいくらでもあるらしい。
市民社会でおっとり育った、お上品な捜査官たちにはできないような過激なやり方が、違法組織がらみの事件では、大きな成果を上げたのだ。
俺たちが彼女たちの活動に気づいたのは、たまたま取引のあった組織が、サイドビジネスで市民誘拐を企んだからだ。
現役の科学者や技術者は、違法都市で高く売れる。子供は、生体実験用に売れる。大人より、適応力や回復力が高いからだ。
その結果、その組織は、被害者救出に来た紅泉たちに叩き潰された。それを知った時、こちらは血の気が引いたものだ。
(冗談じゃない。そんな仕事、やめてくれ。命が幾つあっても足りないだろうが!!)
しかし、既に〝リリス〟は十五年以上も実績を積み上げてきたと知って、あきらめた。
彼女たちが違法強化体なので、司法局は〝リリス〟の存在も業績も、一般市民から隠そうとしているが、紅泉はそれで構わないらしい。たぶん能天気に、
(あたしの天職)
とでも思っているのだろう。
俺たちにできることは、陰からの援護しかない。そう覚悟して、ショーティと共に、報われない手助けをしてきた。
こちらの関与を従姉妹たちに知られることは、あってはならない。
紅泉はともかく、過去の傷を抱えたままの探春は、俺に助けられることなど、拒絶するに決まっているからだ。
――最高幹部会の奴ら、よりによって、この俺に〝リリス〟を狩らせようとは。
俺がまだ罪のない少年だった頃、彼女たちもまた無邪気な少女だった。笑いさざめいて、きらきらとまぶしく、生きた宝石のように美しかった。活発な紅泉も、淑やかな探春も。
違法都市という特殊な環境ではあったが、俺たちは一族の大人たちに守られて、まっとうな道徳心を育てていた。
紅泉は今もまだ、あの頃のままだ。そうでなくて、〝正義の味方〟などやっていられるわけがない。どんなに苦労して悪党を退治しても、一般市民には知られず、褒めてもらえず、司法局内でも異分子扱いされるのだから。
(こん畜生)
深く息を吐き、密かに拳を握った。
それでは、俺が何としても、グリフィン役をやり遂げるしかないではないか。
そして、〝リリス〟暗殺を妨害し続けるのだ。
他の誰かがグリフィンになったら、喜んで〝リリス〟抹殺の計画を練り、成功させるだろうから。
「……あの、一つ、誤解なさっていると思いますが、グリフィンさま」
「何をだ」
俺がじろりと見ると、ココア色の肌の美女は、柔らかく言う。
「最高幹部会は、あなたに〝リリス〟を守らせようとしているのですわ」
何だと。
意味がわからない。
「〝リリス〟は正義の側だぞ。悪の帝国から見れば、敵だろうが」
楽しいことを聞いたかのように、ルワナは微笑んだ。正義とか、悪とかいうのは、幼稚な区分だと思っているのだろう。
それはそうだが、少なくとも紅泉は、本気で正義を実行している。あいつの信じる正義を。
「〝悪の帝国〟から見れば、ハンターごとき、敵ではないのです。むしろ、利用価値があるのですわ。詳しくは、リザードさまからお聞き下さいませ。ご案内いたしますから」

「おはようございます、ジョルファさま」
リザード専用艦内の豪華な大食堂に行くと、わたしの秘書のセレネと、護衛隊長のレティシアが顔を揃えていた。
「おはよう。わたしにもコーヒーを。砂糖はなしで、クリームだけ入れて」
控えているアンドロイド侍女に、指示を出した。リザードやルワナは自室で朝食を済ませるらしく、晩餐会ができるくらい広いテーブルには、わたしたち三人だけ。
「今日はいよいよ、グリフィンと対決ですわね」
とセレネは興奮気味だった。長い金髪を優雅に結い上げた、白い肌に青い目の美女である。今朝は若葉色のスーツに、金とエメラルドのイヤリングという、優美な秘書スタイル。
「少しはましな男でしょうか。それとも、鼻持ちならない自惚れ野郎かしら」
とレティシアは面白がっている。こちらは短い黒髪に褐色の肌、黒い瞳の、精悍な筋肉質の美女だ。
セレネが北国の湖に浮かぶ白鳥なら、レティシアは南国の密林で獲物を狙う黒豹だろう。愛用する迷彩柄の戦闘服を着て、腰にはホルスターを吊るし、背後にアンドロイド兵士を並べている。
それでも、ほんのりと珊瑚色の口紅を塗り、金のイヤリングを付けているのは、グリフィンがいい男だった場合に備えての〝用心〟らしい。わたしと違って、二人ともまだ、男というものに多少の期待を残している。
それは女の本能なので、咎めるつもりはない。
アマゾネス軍団としては、厳しい規律を保っているが、部下たちの私生活にまで、干渉するつもりはなかった。
世間ではそれを知らず、男嫌いの歪んだ女たちの集まりと思っているようだけれど。
勝手に怯えているがいいのだ。その怯えも、わたしたちが利用する。
「さあ、まだわからない」
とだけ答えた。彼女たちは昨夜、この船で待っていたので、裸で檻に入れられていた、怒れる男を見ていない。
シヴァという男は、自分を捕えたのが最高幹部会だとわかってからも、臆した様子は見せなかった。わたしが誰なのか悟った時は、さすがに、恐怖と反感を隠しきれなかったけれど。
当然、わたしの経歴を知っているのだ。違法ポルノの素材にされていたことも、自分を裏切った男を去勢して、自殺に追いやったことも。
憎まれて結構。
恐れられたら、なお結構。
この辺境で好き勝手している男たちを、少しでも牽制しなくては。
奴らが不老不死を望むのは、別に構わない。わたしも数年前から、若さを保つ処置を受けるようになっている。そうでなくては、組織を維持・拡大する激務を続けていくのが大変だから。
許せないのは、彼らがバイオロイドの女子供を、使い捨ての道具として扱うことだ。
工場で培養される人造人間といえども、人間の遺伝子を元にしているのだから、赤い血が流れているし、愛する心や恐れる心を持っている。
それを娼婦や侍女や小姓として便利に使い、最後は殺すというのは、あまりにも非道すぎる。
男としてはかなりましなリザードでも、部下の男たちが女を使い捨てにするのを黙認しているし、リザード自身、バイオロイドの美少年を身近に侍らせているのだ。
それ自体は、まだいいだろう。バイオロイドを奴隷として使っても、労働条件さえ改善すれば、そう惨めな生活ではなくなるはずだから。
最大の問題は、いかなるバイオロイドも五年以内に処分せよという、最高幹部会の暗黙の威圧だ。
それがあるから、権力に弱い男たちは、平気でバイオロイドを使い捨てる。その不文律に、疑問を持つこともしない。
過去に幾度も、バイオロイドの反逆事件が起きたための対応策だというが、それならばまず、バイオロイドの待遇を改善するべきだろう。
彼らに人権を認めれば、彼らだって、鎮圧されることがわかっている反乱を起こしたりしない。
とはいえ、わたしも組織内にいる身。表立って、その方針に逆らうことはできない。わたしの地位は、リザードが認める限りにおいてしか保証されないのだ。
だからわたしは、自分の監督権が及ぶ範囲内でのみ、バイオロイドたちの待遇を改善してきた。
これ以上何かしたかったら、それこそ、リザードを倒して組織を乗っ取り、最高幹部会に立ち向かうしかない。
だが、それは不可能だとわかりきっている。彼らは数百年かけて、辺境の支配体制を固めてきたのだから。
「わたしも昨夜は、顔を合わせただけだ」
グリフィンの威信を守るため、彼が裸で檻に入れられていたことは、あえて言わないでおく。
彼に関しては、シヴァという名前を含め、セレネにもレティシアにも語れないことが色々あった。違法組織では、地位によって、許される知識の範囲が異なるのだ。
それでも長い間には、噂によって、真実が少しずつ洩れていくものだが。
「で、どんなタイプでした? 秀才風? 野性的? 渋いハンサムだと嬉しいですね」
と期待顔のレティシア。
男の中身など、どうせたかが知れているのだから、外側が見目良い方がまだまし、と思っている。何らかの劣等感でひねくれた男より、能天気に自惚れて育った男の方が、いくらかは扱いやすいというわけだ。
「まあ、野性的……だろうな」
苦み走った長身のハンサムで、中央の映画スターでも滅多にいないくらいのいい男……とは告げなかった。熱狂されては困る。
いや、どうせ後で会うのだから、熱狂するなと言っても無理か。
プライベートでなら、いくら熱狂しても構わない。わたし自身はもはや男を必要としないが、セレネやレティシアは健康な女だ。彼女たちの下にいる、数百名の部下たちも。
彼女たちには、私的に交際する男がいてもいい。万が一、その男に騙されたり、利用されたりして、組織に損害を与えることになったら、どう責任を取るかは、わきまえているはず。
「ジョルファさまがそうおっしゃるなら、期待しますわ」
セレネはヨーグルトであえた果物を食べながら、楽しげに言う。
「最高幹部会に抜擢されるくらいなんですもの、切れ者に決まってますし」
「まあ、馬鹿ではないだろう。少なくとも、自分一代で、そこそこの組織を築いた実力はある」
長い伝統を持つ老舗組織の中に生まれながら、そこを飛び出して、独力で生きてきたという男。
生まれながらにして、最高水準の強化体。
他人を信用しないらしく、相棒は何と、自分で知能強化した犬だという。
眠らされた犬を見た時の彼の動揺は、演技には見えなかった。いくら人間並みに賢くても、犬に頼るとは問題ありだと思うが、リザードの説明によれば、もっと奇妙なことがある。
かつてシヴァは、娼館から買い取ったバイオロイドの娘を本気で愛していた、というのだ。
当時、最高幹部会の指示を受けたリザードが、試しの攻撃をかけた時、シヴァは、茜と名付けたその娘を失った。彼にとっては、しばらく立ち直れないほどの打撃だったという。
本当に本気の愛情だったのかどうかは、怪しいものだ。男たちはしばしば、独占欲や支配欲を愛情と呼ぶ。
とにかく、それ以来、シヴァは《フェンリル》を自分の敵と見なしているらしい。報復の隙がないか、あれこれ調べて回ったようだ。
けれど、実際には、何の手出しもできなかった。
多少は勢力を伸ばしたとはいえ、彼の組織はまだ弱小だ。百年以上の歴史を持つ《フェンリル》に正面から挑むなど、自殺行為でしかない。
もっとも、これからグリフィンとして力を付けたら、何か企むかもしれない。それは、警戒しておくべきだ。
「楽しみですね。彼が不適格とわかれば、ジョルファさまが、グリフィン役を引き継ぐのでしょう?」
とオレンジを食べながらのレティシア。
「そう簡単に、失策はしないだろう。そのために、ルワナが付いている」
「ルワナさんて、あちこちの組織を経由してきた、大ベテランなんでしょう?」
というレティシアの問いに、年長のセレネが答えた。
「三年くらい前に、下部組織から引き抜かれて、リザードさまの秘書室に入っているわ。今では、秘書室の中でも中堅の扱いよ」
現在は、わたしが組織のナンバー2の地位にあるが、もし、わたしが大きな失敗をして失脚しても、ルワナは、リザードの信頼厚い秘書であり続けるだろう。それならば、実質的な地位は、わたしより彼女の方が上かもしれない。
「その人を秘書に付けたんだから、リザードさまとしても、本気でグリフィンを応援するおつもりなんでしょう」
とレティシア。
「もちろん、我々もグリフィンに協力する……彼が無能とわかるまでは」
だが、実際には、彼自身の能力や適性など、ほとんど関係ないだろう。大抜擢の理由の八割方は、彼が、司法局の秘密兵器と言われる〝リリス〟の従兄弟だからだ。
彼女たちもまた、違法都市《ティルス》と、その姉妹都市を建設した富裕な一族の中で生まれた、最高水準の戦闘用強化体だという。
だが、それは、セレネとレティシアには告げられない。シヴァと〝リリス〟の関係、及び出身地は、最高レベルの機密事項なのだ。
ジャムを添えたパンケーキとベーコンエッグ、空豆のスープと野菜サラダと果物の朝食を済ませ、コーヒーを飲みながら中央のニュース番組を見ていると、ルワナがやってきた。
「おはようございます、ジョルファさま」
今朝はホワイトベージュの服に、翡翠のネックレスとイヤリングを合わせて、存在そのものに品格がある。元は教師だったと聞いているが、生徒に慕われる、優秀な教師だったはずだ。
それが、開発局の輸送船で辺鄙な任地に赴任する途中、違法組織の船に襲われ、そのまま辺境へ拉致されたという悲劇。
ルワナもまた、自分の運命を受け入れ、辺境の人間になりきるまで、様々な葛藤を乗り越えてきたはずだ。リザードに引き抜かれるまで、あちこちの組織の分裂や併合を経験してきているという。
「おはよう」
とわたしが答えた後、
「おはようございます。ルワナさん」
と声を揃えて挨拶したのは、わたしの側近たちだ。二人とも、ルワナのことを業界の大先輩と認識している。
「おはようございます、ミス・セレネ、ミス・レティシア」
とルワナはにっこり受けた。
「ジョルファさまだけ、わたくしと一緒に来て下さいますか」
取り残されるセレネとレティシアは不服げだったが、組織内では序列は絶対である。ルワナはわたしより下だが(それも僅差だ)、セレネたちよりは上位にある。二人は、おとなしく待つしかない。
「やあ、おはよう、ジョルファ」
居並ぶ警備兵の前を通って、リザードの書斎に入ると、シヴァは既に仏頂面で、デスク前の椅子にかけていた。地味な暗緑色のシャツと褐色のズボンという、くだけた姿。
彼はわたしを見ても立ち上がらないし、挨拶もしてこない。それでわたしも、グレイのスーツを着て、デスクの向こうに端然と座っているリザードにだけ挨拶した。
「おはようございます、リザード」
わたしは彼に、敬称を付けない。彼も、わたしにそんな虚礼は求めない。最初に出会った時、わたしが彼に喰ってかかった時から、そうだった。
『わたしを、こんな違法ポルノの撮影で使い捨てにするつもりか!! わたしなら、あんたの部下よりもっとましな仕事ができる!!』
リザードは、二年あまりの生き地獄で、自殺も発狂もしなかったわたしの生命力、捨て身の度胸を買ってくれた。現場から引き上げて、下級幹部の地位を与えてくれ、あとは正当に働きを評価してくれたのだ。
リザードには、感謝している。
彼の冷酷さはよく知っているから、甘い期待はしないが。
辺境の男たちが持つ欠点の多くを、リザードはほとんど持っていない。既に十分な出世を果たしているせいか、権力執行には淡泊だ。美少年好みではあるが、特定の美少年にのめり込むこともない。もしかしたら、女から性転換した男ではないかと疑うくらい、稀有な平静さを保っている。
ルワナも含めた四人で、ティーテーブルを囲んだ。紺の制服を着たアンドロイド侍女が、紅茶を給仕して回る。
「昨夜のうち、ルワナから概略は聞いたと思うが、何か質問はあるかね、シヴァ」
リザードは学生を前にした指導教授のような態度だったが、シヴァは露骨な警戒顔のままだった。
「なぜ今、懸賞金制度が必要なんだ? 要人の暗殺なら、これまでだって成功してきたじゃないか」
そう、〝連合〟に都合の悪い要人は、暗殺されたり、密かに洗脳されたりしてきた。
市民社会において、現在、どれだけの要人が洗脳され、操り人形にされているのか、誰にもわからない。最高幹部会のメンバー同士でさえ、互いの手の内は、可能な限り隠しているだろう。
リザードは穏やかに答える。
「惑星連邦の一般市民に、広く知ってもらう必要があるからだ。市民社会にとって、誰が真の重要人物なのか」
ルワナは無関係のような顔をして、紅茶を飲んでいる。リザードが直々に話すのなら、ルワナの出番はないからだ。
「グリフィンが公表するリストには、本当に価値のある人物しか載らない。いくら有名でも、正しい展望や信念を持たない人物は無視される。つまり、これからは、グリフィンのリストに載った人物こそ、真の大物だと認知されることになる。当然、当局の警護も手厚くなるし、社会の中でも、より一層重く扱われるようになるだろう」
シヴァは、よくわからん、という顔をしている。そんなことをして、〝連合〟に何の得があるのかと思うのだろう。
わたしも、最初はそう思った。リザードから、最高幹部会の意図を解説されるまで。
「人物の重要度を〝連合〟が判定するのか?」
「その通りだ。〝連合〟というよりは、グリフィンだがね」
「俺に、判定の権限があるのか?」
「そうだ。最初の三十人こそ、最高幹部会の意向を受けて、わたしが選定したが、今後はきみの裁量になる」
「リストを更新していくのか?」
「その通り。老いて引退した者、堕落した者はリストから外すし、暗殺された者も当然、名前がなくなる。その代わりに誰を入れるか、きみがルワナやジョルファと相談して、決定すればいい。わたしには、公表前に報告してくれればいい。不満があれば、その時に言おう。どのみち、ルワナが定期的に報告してくれる」
シヴァはわたしと、ルワナの顔を見比べた。どちらがより危険か、測っているかのようだ。
「俺と、彼女たちの意見が対立したら?」
「懸賞金制度の責任者はきみだ。きみに決定権がある。もちろん、何か失敗があった時の責任者もきみだ」
シヴァはふっと苦笑した。
瞬間、わたしはどきりとする。
悟った顔――責任を引き受けた顔だったからだ。潔く、崇高ですらある。男の顔に、この表情を見ることは珍しい。男は普通、真っ先に責任逃れを考えるからだ。
「いいだろう。俺が、リスト入りする人物を決める。全ての責任も、俺が負う」
いい度胸だが、どのみち、彼に逃げ道はない。最高幹部会の決定なのだから。まして、彼が従姉妹たちを愛しているのなら。
わたしとて、この世に本物の愛が存在しない、とまでは思っていない。
わたしは市民社会で普通に育ち、両親にも祖父母にも愛された。三つ年下の弟もいて、喧嘩と仲直りを繰り返した。男性の善良さも、純情さもよく知っている。
ただ、子供の頃から体格のよかったわたしは、同年代の少年たちにゴリラ女とからかわれ、敬遠され、自然と、他の少女たちのボディガード役に回っていた。
身内の男性を除けば、誰もわたしに、綺麗だとか可愛いとか言ってはくれなかったのだ。
だから、勉強とスポーツだけに打ち込み、恋愛に免疫のないまま成人してしまった。もう少し女としての知恵が育っていれば、あんな見え透いた誘いに乗ることはなかっただろう。
彼はわたしを愛したわけではなく、ただ、一人で辺境へ出るのが怖かっただけ。そして、上位の組織からの誘惑に、勝てなかっただけ。
長生きしたいだけが目的の、つまらないチンピラだった……そうわかったのは、彼に裏切られ、売り飛ばされてからのこと。
けれど、それはもう、済んだことだ。
彼は死に、わたしは地位を得た。大事なことは、これから何をしていくか。
目の前では、シヴァがリザードに疑問をぶつけていた。
「だが、そこに〝リリス〟を加える意味はあるのか? 単なる賞金稼ぎだぞ。しかも、辺境出身の違法強化体だ」
長身の闘士リリーと、小柄な頭脳派のヴァイオレット。
これまでは、司法局が彼女たちの存在を秘匿していたせいで、いくら事件を解決しても、一般市民にはほとんど知られていなかった。共闘した軍人、捜査官や事件関係者から、わずかに噂が流れていた程度。
「大きな意味があるのだよ。リスト入りすることによって、彼女たちは有名になる。チンピラに命を狙われる危険は増すが、それゆえに一層、市民社会の英雄になっていくだろう」
「違法強化体が!? ちょっとくらい活躍したからって、保守的な市民に受け入れられるとでも!?」
シヴァには、わかっていないのだろうか。いつまでも若く強健でいられる肉体に、一般人がどれほど憧れているか。
ただ、市民社会に満ちる同調圧力が、本音を言わせないだけのこと。
本心では、誰だって、不老不死に惹かれている。
不幸なことに、現代では、それが犯罪と結びついているから、拒否しなければならないだけ。
「受け入れられる」
リザードは断言した。
「彼女たちが活躍を続けることによって、市民たちの人体改造アレルギーが薄れていくだろう。違法強化体が、必ずしも怪物ではないという認識が広まる。そのことによって、中央と辺境の垣根が低くなる。中央から辺境に流れて来る者が増えれば、〝連合〟の陣容が厚くなる」
シヴァはまだ、理解に苦しむ顔をしている。
「だが、グリフィンというのは、暗殺を推進するんだろう」
リザードは、穏やかに訂正した。
「表面上は確かに、暗殺志願者を援助する役だ。だが、正確には、援助するふりで妨害するのが、きみの職務だ。したがって〝リリス〟を狙う暗殺志願者は、片端から返り討ちに遭うだろう。そうすれば、〝リリス〟は無敵の英雄ということになる」
シヴァは疑う顔でいながら、身を乗り出した。
「本当に、二人を守っていもいいんだな」
リザードは淡々と話す。
「他の政治家や学者たちについては、たまに殺されても構わない。暗殺成功者には、きちんと約束の報酬を支払ってくれたまえ。支払ったことが、全世界に納得されるようにだ」
今後、どれだけの人材が、無駄に殺されることになるのだろう。ただ一組の英雄を押し上げるために。
「それがまた、次の暗殺志願者を励ますことになる。せっかくの良質な人材、惜しいのは確かだが、すぐにまた、次の人材がとって代わるから、大きな問題ではない。しかし、〝リリス〟の代わりはまずいない。いずれは〝リリス〟に憧れる子供や若者が、軍や司法局を目指すようになるだろう」
シヴァが苛立つ声を出した。
「なせだ!? なぜ、わざわざ祭り上げる!? 彼女たちは、〝連合〟傘下の組織を幾つも潰しているじゃないか!!」
リザードは微笑んでいた。
「二流以下の中小組織など、いくら潰されても構わない。彼らも少しは、怯えた方がいいのだ。そんなことより、市民に希望を持たせておく方が大切なのだよ」
あっ、とシヴァの顔に理解の光が走った。リザードは辛抱強い教師のように、説明を続ける。
「最高幹部会は、市民社会の安定を望んでいる。市民たちが明日に希望を持ち、真面目に働いて、子育てをしてくれることを。健全な子供は、健全な家庭で育つ。そして〝連合〟は、常に新しい人材を補充していかねばならないのだ」
違法組織の要所には、教養と判断力を備えた本物の人間が必要だった。そういう人材が一人いれば、数十人から数百人のバイオロイドを監督することができる。
そして、現在のところ、そういう人材は、中央の市民社会からしか供給されない。
しかし、望んで違法組織に加わるのは、市民社会に適応できないはぐれ者、欲望が病的に肥大した者、不老不死を得るためなら何でもする卑怯者が多い。腐った人材だけでは、違法組織も腐っていく。
逆説的だが、違法組織にこそ、誠実で有能な人材が必要なのだ。
リザードがわたしを引き立てたのも、わたしが理想を捨てていないからだろう。
男たちの横暴を許しておかない。そのために、女が力を持つべきだという信念。
わたしは何年もかけて、あちこちの組織から、まともな女たちを引き抜いて回った。セレネ、レティシア、ファティマ、ユーリ、ジュナ、トリシア、マグダ、アレクサンドラ、マーヤ……
そして、アマゾネス軍団と言われる集団を作った。
辺境全体が男優位である現状は変わっていないが、少なくとも、わたし直属の部下たちはどこでも恐れられ、敬意を払われる。
これが百年続けば、少しは辺境を変えられるはずだ。悪質な組織は淘汰し、ましな組織を優遇するようにしていけば……
「新たな人材の供給源として、市民社会を存続させておきたいんだな」
「そうだ。わたしにしてもジョルファにしても、市民社会で普通に生まれ育ち、成人後に辺境に出てきた人間だ」
リザードの過去については、誰も何も知らないけれど。
「ルワナなど、誘拐されて辺境に連れてこられた被害者だ」
ココア色の肌の美女が軽く頭を下げると、シヴァは驚きながらも、納得という顔になる。
「望まずに違法組織に加わった者こそ、望ましい人材だといえる。きみや〝リリス〟のように、辺境でまともに育つ者の方が珍しいのだ。今後、きみが中央を監視していて、これはと思う人材を発見したら、こちらで誘拐なり脅迫なりして、引き込めばいい」
「〝連合〟としては、今後もずっと市民社会を守る……そういうことか」
シヴァの緊張が、かなりゆるんだようだ。リザードは苦笑してみせる。
「そうかといって、市民社会が力を付けすぎても困る。それでは、我々が退治されてしまうからな。現状維持が一番いい。わかりやすい〝正義の味方〟が活躍していれば、市民たちは安堵して、思考停止する。わざわざ法律を改正して、軍や司法局を強化しようなどとは思わない。全市民の深層心理検査を、定期的に繰り返そうとも思わない」
シヴァは太く息を吐いて、椅子の背にもたれた。
「そうか。そのために、彼女たちを祭り上げておくのか……」
「そうだ。華麗なる正義の看板だよ。従兄弟のきみなら、本気で彼女たちを守れるだろう。過去数年間、そうしてきたようにね」
シヴァは頭痛でもしたかのように、片手で額を押さえた。その口元は、堅く引き締められている。
「グリフィンは、憎まれ役だ。きみは紋章付きの艦隊であちこちに出没し、要人暗殺計画を援助し、市民たちの恐怖と怨嗟の的になればいい」
片手を下ろすと、シヴァは苦笑した。その顔にはようやく、安堵に似た表情が表れている。
「そういうことなら、了解した。グリフィン役、務めさせてもらおう」
そして、黒い目でわたしを見据えた。
「悪いが、この役は譲らない。いくらおまえが、俺の失脚を待っていてもな」
わざわざ、ライバル宣言か。
「では、精々、大きな失敗をしないように気をつけることだな」
と言い返した。リザードには、あらかじめ告げられているのだ。シヴァが大きな失敗をしたら、次は、わたしがグリフィンだと。
リザードの艦隊は、わたしたちの拠点がある違法都市《ルクソール》に向かっていた。
その艦隊中の一隻で、わたしは毎日、シヴァと話し合いを重ねている。
まず、繰り上げ候補者のリストが必要だった。最初の三十人に欠員が出た時、誰をその代りにリスト入りさせるか。
その場合、その人物の周辺で、こちらの手先として使えそうな人物も、目星をつけておかなくてはならない。標的の人物の暗殺を手伝わせるか、それとも妨害させるかは、場合による。
基本的には《フェンリル》のデータベースを使えるが、それで足りなければ、他組織の持つ情報や人脈も利用する。手先として目星をつけた人物に、あらかじめ、こちらから働きかけておくか。それとも、どうしても必要になってから接触するか。
「場合によっては、リストの人数を増やすこともあるな」
「堕落した者が出たら、それをすぐに発見して、リストから外さなければ」
「相当、細かい監視が必要になりますね」
基本方針が定まったら、細かい部分はグリフィン事務局に引き渡すが、その事務局の人選もまだ途中である。
六大組織とその系列組織から、有能と思われる人材を引き抜いてあるが、誰をどの役職に就けるかは、我々が最終決定することになる。三十チームがそれぞれの標的を担当しつつ、次の候補者の監視もすることになるので、各チームの人材の組み合わせも大切だ。
毎日、ああでもない、こうでもないと、テーブルをはさんでシヴァと議論した。セレネとレティシアも、わたしの補佐として、データ分析や議論に加わっている。
もし、グリフィンの役職がわたしに回ってきたら、この二人には、全面的に助けてもらうことになる。今から、細部まで把握しておいてもらわないと。
シヴァもわたしたちを警戒しつつ、仕方なく、相談相手として受け入れている。
「おはよう」
と言えば、
「ああ」
と返す程度の反応はするようになった。いかにも渋々、嫌々だが。
計算外だったのは、セレネとレティシアが、本気でシヴァにのぼせたらしいことだ。
いや、まあ、多少は予測しないでもなかったが、これほど燃え上がるとは。

「何だって!?」
シヴァがグリフィン事務局の人員を、全員女にしろと言ってきた時、わたしは、すぐには理解できなかった。
彼が懸賞金リストの順位や、賞金額に文句をつけてきた時は、それなりに配慮したが、今度は何だ。
事務局の人員の半数は、既に系列組織から引き抜いて《ルクソール》に呼び集め、残り半数の選定にかかっているのに。
「公私混同はやめたまえ。きみのハレムじゃないんだぞ」
しかし、彼は譲らない構えだ。
「俺には、自分の部下を選ぶ権限があるはずだ。男の部下は欲しくない。おまえだって、自分の部下を女だけに限っているだろうが」
「それは、チームワークのためだ。男が混ざると、統制がとりにくい。きみのは、個人的な願望だろう」
「そうじゃない。男はどうしても、奴隷女を必要とするからだ。俺は極力、そういう意味でバイオロイドを使いたくない」
えっ?
わたしは耳を疑った。
辺境で生まれ育ち、自分の組織を持っている男が何を?
「きみの組織だって、バイオロイドを使っているだろう……」
「前からいる者だけだ。新しいバイオロイドは増やしていない。男の部下には、女を買うなら一生責任を持てと命じてきた。バイオロイドを買って、飽きたから捨てる、なんてことは許していない……いなかった。今はもう、自分の組織はないが」
本当に?
「他組織を乗っ取った時は、バイオロイドの待遇を改めている。五年で殺すこともしていない。無用なストレスを与えなければ、バイオロイドはもっと長く使える。男の餌食にされるのは、バイオロイドの女にとって、最大のストレスだ。それをなくすためには、最初から、男の部下を使わないことだ。そうすれば、組織内の女たちは安心して働ける。人間の女でも、バイオロイドの女でも」
信じられない。
男が、わたしと同じ考えを持っているなんて……?
「彼は本気なのか?」
わたしは後で、こっそりルワナに確かめた。
「本気だと思います」
ルワナは見通した態度で言う。
「事前の調査を担当しましたが、あの方の組織では本当に、バイオロイドの人権を守っていました。他組織を併合した場合も、そこで働いていたバイオロイドたちは、きちんと保護していました」
調べればわかることだ。シヴァの組織は今、リザードの部下が管理している。いずれシヴァがグリフィンになりきったら、接収した組織は返却する予定だそうだから。
「彼らに教育を与え、長く使っていることは事実ですわ。人間の男の採用は、最小限に絞っています。ジョルファさまも、報告書はご覧になったでしょう?」
「見たが、しかし……」
シヴァに関する調査資料は膨大なもので、わたしはさして深入りせず、ざっと一読しただけだった。それに、彼は単に、バイオロイドを長生きさせることが経済的だと計算しただけかもしれない。
だが、ちょうどいい。
前から、ルワナに聞いてみたかったことがある。
「彼が、以前……娼館から買ったバイオロイドの娘を愛していたという話だが……きみは信じたか?」
ルワナは少し意外そうな顔をし、それからにっこりした。
「それはわかりません。買い取った事実は追跡調査できましたが、それをした彼の心情は、他人には見えませんから」
なるほど、ルワナらしい言い方だ。
「でも、ジョルファさまが、そういう疑問をわたしにぶつけて下さったことは、嬉しいと思います。これまでずっと、わたしを警戒していらしたでしょう?」
そうだ。ルワナは、わたしの部下ではない。リザードが目をつけ、下部組織から引き抜いた女。
「わたしは、きみの過去を知らないからな。警戒して当然だろう」
市民社会から誘拐され、売り飛ばされたのは本当でも、その後はあちこちの組織を渡り歩き、何十年も生き延びてきたという。それだけで、したたかさは保証付きだ。
もしも、わたしが何か失策をしたら、わたしの後を引き継ぐのは、この女かもしれない。
「バイオロイドを守れる男なら、従姉妹たちのことも本気で守る。最高幹部会は、そう判断したのでしょう」
そうかな。
彼らが、そんなことを判断材料にするのだろうか。
姿を見たことはあっても、直接には、ほとんど口をきいたこともない天上人たちだ。最高幹部会のどの人物も、脳移植や不老処置を繰り返して、何百年も生きてきた怪物だと聞いている。彼らがどんな考えを持っているのか、こちらの常識では推し量れない。
「シヴァさまが期待外れなら、その時はあなたの出番ですし。ジョルファさまはきっと、〝リリス〟と通じるものをお持ちですわ。立場は違っても、同じ目的に向かえるでしょう」
この世界を、少しでもましな場所にする。
それが、わたしの生きる理由だ。
わたしが体験した地獄を、他の女たちに体験させることはない。
そして、同じ考えを持つ女たちを集めてきた。
それなのに、セレネとレティシアは、シヴァに熱を上げている。男など、強い者に媚びるだけの、卑劣な生き物のはずなのに。

航行の途中で気がついた時には、リザードは艦内から消えていた。忙しい彼は、他の艦に移乗し、自分の仕事を片付けに行ったという。
リザードは組織の軍事部門と研究部門を統括していて、ジョルファですら正確には知らない基地を、あちこちに隠し持っているらしい。
違法組織というのは、組織内でも秘密主義なのだ。さもないと、いつ部下に寝首を掻かれるか、わかったものではないからな。
グリフィン事務局の人選については、ジョルファが折れてくれた。
「既に集めた人材うち、女は残すが、男たちには元の場所に戻ってもらうことにしよう。改めてスカウトをやり直すが、元々、違法組織に人間の女は少ない。時間はかかるが、それは承知の上だろうな」
「ああ、わかってる。人が足りない分は、俺が働く」
書類仕事は得意ではないが、必要があれば、集中して片付けることはできる。
疲れ知らずの体力があるということは、その気になれば、何でもできるということだ。
科学者になれと言われても、軍人になれと言われても、必要な基礎は既にある。
だから、懸賞金制度の運営も、まあ、できるだろう。それが、従姉妹たちを守るために必要なことならば。
「その男たちには、無駄足させて悪かったと、リゾート惑星の招待券でも渡しておいてくれ」
とルワナに頼んだ。市民社会なら、謝罪した上、違約金を払うところだ。違法組織だからこそ、ろくな説明もなく振り回しても、表立って文句を言われないで済む。
「かしこまりました」
そういう実務は、ルワナがきちんと片付けてくれる。
事務局を女だけにするという案も、ルワナが認めてくれたから、ジョルファも追認してくれたのだろう。
リザードからも、特段の非難はなかったようで、助かった。茜に言い訳できないことは、極力したくないからな。
半月の航行で、違法都市《ルクソール》の管制宙域に入った。
二百年前ほど前に、この小惑星都市を建設したのは、六大組織の一つ《エンプレス・グループ》だという。現在では、人口百万を超す一級都市だ。
違法組織《フェンリル》の商業部門を統括するジョルファは、ここにアマゾネス軍団の拠点を構えている。数百名の女が暮らす、要塞のようなドーム型施設だ。
本物の人間の女がこれだけ集まる施設は、他都市でもまずないので、街の男どもには、下心の混じった好奇の視線を向けられている。
といっても、俺がそこへ顔を出すことは、絶対にない。《フェンリル》内で俺の顔を見ていいのは、リザードとルワナの他は、ジョルファと側近二人だけだそうだから。
そして、その側近たちも、俺の本当の名前は知らない。俺が、どんな背景を持っているのかも。
「当面、この《ルクソール》を、きみの居場所にしてもらう。わたしが、きみと連絡を取り合う都合上だ」
とジョルファに言われた。
グリフィンの事務局も、ここの市街のビルに用意されている。スタッフの宿舎と、オフィスの機能を兼ねたビルだ。職員たちは外に出なくても暮らせるようになっているし、外出する場合には、ダミー組織の偽装をすることになっている。いずれ手狭になったら、他の場所を探すことになるだろう。
俺自身は都市内ではなく、桟橋に停泊させた船内で暮らせということだ。
「たまになら街に出ても構わないが、くれぐれも、素顔を目撃されないよう用心してくれ。どこに〝リリス〟のスパイがいるかわからない」
とジョルファに言い渡された。
グリフィンという名前だけは一人歩きするが、実体の俺は、これまでと同様、船や車の中で隠れ暮らすことになるわけだ。以前は一族や〝連合〟の目から隠れ、これからは、従姉妹たちの目を恐れて。
もしも、俺がグリフィンだと知ったら、紅泉は俺が〝連合〟の軍門に下ったと思って、激怒するだろう。
だが、探春ならば、別に何とも思うまい。彼女ははるか昔に、俺という存在を、自分の世界から削除してしまっている。
「連絡というよりは……おまえが俺を見張る都合上、だろう?」
「そう思いたいのなら、そう思っても構わない」
ジョルファというのは、いつもむっつりして、可愛くない女だ。まさに、鋼鉄ゴリラ。こいつに言い寄った男は、どんな企みのためとはいえ、あまりにも命知らずだった。
逆に、セレネとレティシアは色気過剰だ。隙さえあれば、俺にすり寄ってくる。
これはこれで、始末が悪い。なまじ美人なだけに、こっちの肉体が反応しそうになって、困るのだ。
「ここなら、ちょくちょくお会いできますわ、グリフィンさま」
「わたしたち、仕事の合間に遊びに来ますから」
来なくていい、と何度言っても、彼女たちはひるまない。
どうせ、ジョルファの命令で、俺の弱点を探り出そうとしているのだろう。
そんなもの、従姉妹たちと犬の他には、残っていないというのに。
その《ルクソール》に入港する少し手前で、俺たちは《フェンリル》の艦隊から、グリフィンの紋章を付けた艦隊に移ることになった。
六大組織の一つ《黄龍》の工場で建造された、最新鋭艦隊だという。ざっと資料を見ただけで、本当に最新鋭なのだとわかった。
これに比べたら、これまで俺とショーティが持っていた艦隊は、時代遅れもいいところだ。権力の側に付くと、いいことがあると納得した。後で早速、航行演習や戦闘演習をしてみよう。
「わたくしには戦闘方面はわかりませんので、それは、グリフィンさまのお好きなように」
ルワナはおっとりと言う。しかし、ジョルファは元軍人だけあって、戦闘にも一家言あるらしい。
「演習なら、わたしも付き合うぞ。グリフィン艦隊の実力を知っておきたいからな」
つまり、俺の指揮能力を計っておきたいのだろう。いずれ、俺と闘う時のために。
「好きにしてくれ。俺を追い払った後は、おまえがグリフィンになるんだろうからな」
と言うと、嫌な顔をする。俺に、世辞でも言ってほしいのか。自分こそ、最初から喧嘩腰のくせに。
忙しいジョルファが側近を連れ、はるばる他都市まで俺の出迎えにやってきて、同じ艦内で半月も一緒に過ごしたというのは、つまり、そういうことだろう。
それは構わない。彼女たちとあれこれ議論する中で、俺自身もずいぶん、考えが深まった。
どんな経緯であれ、こういうことになったのだ。グリフィンの仕事は、きっちりこなしてやる。ジョルファが残念がるように。
ルワナと二人で小型艇に乗って移動し、俺の居住用だという大型艦に入ると、《黄龍》の工場からの曳航を担当したという、短い黒髪の小娘が待っていた。
真新しい紺のスーツを着て、目一杯力んだ顔をし、背筋をぴんと伸ばしているが、スカートはかなりのミニ丈だ。
「初めまして。グリフィンさまの第二秘書の、リナと申します。これからグリフィンさまの身辺のお世話をいたしますので、どうかよろしくお願いします」
勢いよく、ぺこりと頭を下げたのはいいが、しゃべり方が切り口上で、いかにも子供っぽい。
改めて顔を見たら、すべすべの小麦色の頬に、丸い黒い目をして、まるっきり、学校出たての新入社員だ。どう多めに見積もっても、二十歳を過ぎているようには見えない。
「おまえ、幾つだ」
と尋ねたら、リナは心外だというように、むっとした顔になる。
「十八歳になりました。もう子供じゃありません。リザードさまの秘書室で、見習いをしていました」
俺は内心、がっくりきた。
リザードめ。俺にはこの程度でちょうどいいだろうと、みそっかすの小娘を選んで寄越したな。
「子供じゃないと言い張る者は子供だっていう、世界的法則を知らんのか」
と指摘したら、リナはむきになって言う。
「そんな法則、初耳です」
「じゃ、覚えとけ。おまえはあと十年経たないと、一人前になれない」
「どうして十年なんですか!! その年数の根拠は何ですか!!」
「そうやってすぐ、金切り声になるからだ」
リナははっとして、口を押さえた。横から、ルワナが微笑んで言う。
「グリフィンさま、リナはこれまで、リザードさまの元で基礎教育を受けてきました。本格的な任務に就くのはこれが初めてですが、わたくしが指導しますので、どうか気長に育ててやって下さい」
「おい、俺が育てるのか!?」
初仕事のガキを!?
「組織の長としては、新人の育成も業務のうちですわ」
「ふん。違法組織も人材不足なんだな」
リナは反抗心溢れる顔で俺を睨んでいたが、ルワナがにこやかに説明した。
「この子はいざという時には、グリフィンさまの護衛にもなります」
俺は唖然とした。それから失笑した。
俺の肩に届くかどうかという、細い小娘が護衛だと。ずいぶん甘く見られたものだ。
「いざという時は、おまえの陰に隠れればいいわけか?」
「リナ」
ルワナが視線で合図すると、次の瞬間、壁際に立っていたアンドロイド侍女の一体が、身を折って崩れ落ちた。その腹から、しゅうしゅう白煙が上がり、刺激的な異臭が漂う。
常人には見えなかっただろうが、リナが、隠し持っていたカプセル弾を投げたのだ。小指の先ほどの大きさだが、衝撃で破裂し、溶解液を撒き散らす。普通人なら、即死か重傷だろう。
「この子は、グリフィンさまほどではありませんが、それなりの戦闘用強化を受けています。戦闘全般の訓練も受けています」
とルワナが言う通り、リザードの元で、多少は鍛えられてきたようだ。
「なるほど。いざという時には、俺の処刑人になるわけだな」
すると、リナはまたしても怒った顔をする。
「どうして、そんな言い方するんですか!! わたしが受けた命令は、グリフィンさまのお世話と護衛です!! 遠い先のことはわかりませんけど、今はそれを一生懸命やりとげます!!」
本気で言っているらしい。頭痛がしてきた。無邪気な殺し屋というのは、とてつもなく怖い。
「わかった。とにかく……その命令が撤回されるまでは、頼りにすることにする」
「そうです。頼りにして下さい」
おい、今のは皮肉だよ。
とにかくリナは、上司であるルワナの指示には従うよう、リザードにきつく言われているらしい。
「グリフィンさまをお部屋にご案内して、お食事を差し上げなさい」
と年上の女に言われると、素直に俺を船室区画へ案内した。
予想していた通り、豪華な続き部屋だ。寝室に居間、食堂に書斎にジム。
広いジムには、俺が愛用していたのと同じサンドバッグや、鉛入りの木刀などが揃っている。最高幹部会の情報収集力はさすがだ。たぶん、俺のことなら何でも知っているのに違いない。中央製の恋愛映画が好きなことも。
映画や小説は、現実逃避だ。俺の実生活は殺伐としているから(唯一の親友まで奪われて!!)、正反対の楽しみが必要なのだ。現実に立ち返った瞬間、虚しさに襲われるとしても。
「グリフィンさま、お夕食はこちらでなさいますか。サロンの方に、大食堂もありますけど」
「ここでいい」
正装で正餐にしろ、などと要求されなくて助かった。リナが合図すると、すぐにアンドロイド侍女が料理を運んでくる。
何種類もの前菜、グリーンピースのスープ、きのことベーコンのパスタ、白身魚のグラタン、厚いステーキ、たっぷりのサラダ、冷えたワイン。リナが吟味して用意させたということで、質、量共に申し分ない。デザートの果物とババロアまでで平らげて、満足した。
問題は、食事が済んだ後もリナが室内をうろうろして、酒だの着替えだの、先回りして世話を焼くことだ。それは秘書の業務というよりは、侍女の業務だろうに。
「おい、もう自分の部屋に帰っていいぞ」
「そうはいきません。グリフィンさまがお休みになるまで、控えているのが仕事です」
そういうものか?
ショーティは大抵、俺のベッドの足元か、精々、隣の部屋あたりで寝そべっていたが。あれは、犬時代からの習慣だったからだ。
「もしかして、おまえも、俺を誘惑しろって命令されているのか?」
と軽い気持ちで尋ねたら、
「えっ」
と驚いて、壁際まで飛び退り、かちんこちんに固まっている。その顔があまりにも間抜けだったので、つい、からかってしまった。
「それじゃ、ストリップでも見せてもらうかな。見せるほどの胸があればだが」
その途端、リナが怒りの形相になり、手首の端末から溶解カプセルを抜いて投球モーションに入ったので、慌てて避けた。
俺の後ろで壁に穴が空き、しゅうしゅうと白煙が上がる。常人なら直撃間違いなしだ。
しかもリナは、
「そういう下劣な冗談は、二度と聞きたくありません!!」
と叫ぶ。リザードは、どういう教育をしているのだ。これでは、秘書も護衛も務まらないだろう。上司がしょっちゅう、即死してしまうではないか。
「おまえ、俺が普通人だったら死んでたぞ!!」
抗議しても、リナは悪びれない。
「だけど、強化体でしょ。わたしより強いんでしょ。ちゃんと無事だったじゃないですか」
「だからって、怒ったら、いちいち溶解弾を投げるのか!!」
「わたしに手出ししようとしたら、また投げます!! 本気ですから!!」
本気はよくわかった。この娘が本当は、俺を警戒して、ピリピリしていることも。
セレネやレティシアのような、経験を積んだ大人の女とは違うのだ。
「あのな、俺は手出しなんてしてないだろ。ただちょっと、おまえをからかっただけだ」
納得させておかないと、こちらの命が危ない。足首の爆弾は、既にルワナの手で外されていたが(こういう艦内にいる限り、警備システムに見張られているからだ)、こいつに殺されたら、笑い話にもならない。
リナはつんとして言う。
「わたしはグリフィンさまにお会いしたばかりなんですから、それが本気なのか冗談なのか、判別できません」
ああ言えばこう言う。
「とにかく、俺を殺そうとするのは、俺が本気でおまえに襲いかかった時だけにしてくれ。冗談を言って殺されたら、たまらない」
「あら、グリフィンさまが本気だったら、わたしが勝てるわけないじゃありませんか。やっぱり、危険を感じた時には、即座に反撃しないと」
何が危険だ。
危ないのはこっちだ。
「わかった。安心しろ。何があっても、絶対、おまえに手出しはしない。たとえおまえが、人類最後の女だったとしてもだ。だいたい、おまえみたいな小便臭いヒステリー娘は、趣味じゃないんだ」
うっかり正直に言ってしまったら、火吹きドラゴンのように赤くなって怒る。
「そういう言い方は、女性蔑視です!! ちゃんと、礼儀を守って下さい!! わたしはしっかり、お役に立つつもりでいるんですから!!」
俺は、はなはだ分が悪い。
「わかった。よくわかった。紳士として振る舞えばいいんだな」
するとリナは、腰に手を当て、憤然と顎をそらす。
「そうです。最初から、そうなさればよかったんですわ。グリフィンさまが紳士でいて下さるなら、わたしも淑女でいられます」
どこが淑女だ、まったく。
とにかく、俺はこうしてグリフィンになった。なるしかないのだ。犬一頭と二人の従姉妹、彼らの運命が、俺の努力にかかっているのなら。

わたしたちは、ある大手企業に、社員として潜り込んでいた。
辺境の違法組織と裏取引している疑いがあり、怪しい重役も浮かんでいるのだけれど、内偵に入っていた司法局員が、先月、不審な死に方をしたのだ。
複数の蜂に刺されてショック死という、事故とも他殺ともつかない死に方だった。誰かが、蜂毒を仕込んだロボット虫を飛ばした可能性はある。
公開捜査に踏み切る前に、もう少し的を絞りたいというのが、特捜部の考えだった。
一斉に網をかけると大騒ぎになるから(関連企業まで含めると、数万人の取り調べを行うことになる)、混乱に乗じて、こちらでマークしていない者が逃げたり、肝心な人物が口を封じられたりする可能性がある。
そこで、『殺しても死なない』ハンターの出番。
いえ、紅泉だって不死身ではないけれど、普通人の捜査官より、はるかにタフだから。
紅泉は他企業から出向の技術者として、わたしは社長秘書室の補充要員として、先週からこの本社ビルに通っている。
わたしたちの正体を知る者は(それもハンターではなく、普通の司法局員と信じている)、社長以下のほんの数名だけ。
毎日、仕事のふりで社内をうろついて、無邪気そうに質問したり、噂話を拾ったり、資料を漁ったりして過ごす。
勤務時間中は、互いに姿を見ることもないので、昼休み、社員食堂で紅泉に会えた時は、ほっとした。自慢の金褐色の髪を黒く染め、地味なパンツスーツを着ていても、強い生命力を発散しているから、どこにいても人目を惹く。
それなのに、紅泉ときたら、ちらとわたしに微笑を投げてきたきり、あとは熱心に、若い男性社員を口説いている。
「ねえ、休みの日は何しているの? 今度、あたしとドライブしない? いい温泉ホテル、知ってるんだけど」
誘うのはいいけれど、坊やの手を、テーブルの下で、自分の太腿に誘導しているのはやりすぎよ。通りすがりに頭の上で、料理を載せたお盆をひっくり返してやろうかしら。
その時、広い食堂にざわめきが走った。それまでローカルニュースを流していた壁面の大画面が、真っ暗になったのだ。番組の切り替えにしても、長過ぎる。
と思ったら、黒字に金で描いた有翼獅子の紋章が現れた。
「なあに、映画の宣伝?」
「どこの会社のマークだっけ?」
社員たちの注目の中、肉声なのか、合成なのか、判然としない男の声が流れた。
「――〝連合〟を代表して、全世界に通告する。わたしの名はグリフィン。辺境の秩序を維持する、最高幹部会の代理人である」
グリフィンですって!?
そんな代理人、初めて聞くけれど。
放送局の宣伝や、悪ふざけではない。回線を乗っ取られたのだ。〝連合〟ならば、技術的に可能だろうけれど、これまで、こんな真似はしたことがなかったのに。
「本日から、最高幹部会が、市民社会の中核となる人物の首に、懸賞金をかける制度が始まる」
何ですって――暗殺予定リスト!?
「懸賞金リストに載せられた紳士淑女諸君は、誇りに思ってくれていい。市民社会の最重要人物と認定されたのだ」
離れた席にいる紅泉と、黙って視線を交わした。
紅泉のサファイア・ブルーの瞳はそのまま。わたしは茶色い髪を金髪にし、金茶色の目に緑のカラーコンタクトを入れている。整形をしなくても、女は衣装や髪型、化粧で雰囲気を変えやすい。
「リストの人物を暗殺しようと考える者は、グリフィンに連絡せよ。武器や逃亡手段など、可能な限りの援助を行う。要人暗殺に成功した者は〝連合〟で歓迎し、《プラチナム》の口座開設の形で懸賞金を支払う」
それは、辺境の決済機構である。辺境での組織間取引や個人の買い物は、ほとんど《プラチナム》を経由する。
続いて、グリフィン事務局へのアクセス方法が説明された。もちろん違法アクセスだけれど、当局が取り締まるにも限度があるから、どれかの方法で連絡が可能になるだろう。
それから、要人の名前と顔写真、賞金額が並んだリストが出た。
有力政治家、司法局の局長と特捜部本部長、軍の実力者、財界の大物、信望の厚い学者や思想家など、三十人。
あたりのテーブルの社員たちは、しんと静まっていた。多分、他のフロアでも、他の会社でも、学校や家庭でも、この放送を見た者は、みんな凝然としていることだろう。
惑星連邦の歴史上、初めてではないだろうか。裏の世界が、表の世界に公然と挑戦してくるなんて。これまで違法組織は、実力こそあるものの、自分たちを陰の存在と規定してきたはずだから。
頭の中で、計算を始めた市民もいるに違いない。あれだけの賞金が手に入ったら、辺境で何ができるかと。
リストの最後に、『司法局の専属ハンター〝リリス〟』という欄があった。
ぎょっとしたけれど、顔写真はない。身体的特徴が、文章で説明されているだけ。
百八十センチ級の筋肉質の女と、百六十センチ弱の小柄な女のペア。どちらか片方だけでも、懸賞金は全額支払われるという注釈付き。
凍りついていた社員たちは、ここでようやく、ざわつき始めた。
「こんなハンター、いるのか?」
「ハンターなんて、映画でしか見たことないわ」
「ハンター制度って、まだ続いてたんだ」
「これが、市民社会の重要人物だって?」
「他にいくらでも、政治家や学者がいるじゃないか」
さすがの紅泉も、唖然としている。
いえ、呆れているけれど、心底では面白がっているわ。新たな戦いの章が始まった、という感じ。
でも、笑い事ではない。これに煽動されて、あちこちで暗殺事件や、暗殺未遂事件が頻発したら。
軍人や司法局員、警官など、暗殺を防ぐ立場の者からも、裏切り者が出るかもしれない。市民社会は信頼で成り立っているのに、それが崩壊してしまう。
これは、武力制圧よりも悪質だわ。
リストにかぶさり、グリフィンと名乗った男の声が流れた。
「市民諸氏は、辺境を無限闘争の地獄と思っているかもしれない。確かに法律はなく、安全の保証もない。だが、無限の可能性がある。百歳の老人であっても、適切な処置を受ければ、若い頃の気力と体力を取り戻せるのだ。おとなしく老衰死を迎える前に、辺境への脱出を考えてもらいたい。〝連合〟は、新たな人材を歓迎する。その際、手土産があればなお結構だ。グリフィンは、あらゆる提案を待っている」
放送自体は、ほんの十分ほどだった。画面が元のローカル番組に戻ると、すぐさま当局のテロップが入る。
『ただいまの放送については、軍と司法局で事実関係を調査中です。市民の皆さまは、冷静に調査発表をお待ち下さい』
もちろん会社全体が、蜂の巣をつついたような騒ぎになった。
司法局や地元警察、あるいは知り合いの議員に問い合わせる者。ネットで関連情報を調べる者。上司や同僚と相談する者。家族と連絡を取る者。
「世も末だよ、公共放送が乗っ取られるとは」
「軍が〝連合〟を退治できないの?」
「無理だって。辺境は広すぎるんだから」
「政治家や高官はわかるけどさ。なぜ、賞金稼ぎのハンターなんか? チンピラを捕まえて、小遣い稼ぎしているだけだろ」
「でも、これだけの大物と並んで、リスト入りしているのよ。すごい腕利きなんじゃないの?」
「司法局の公開データ、どうなってる?」
「あら、〝リリス〟って、情報公開されてない。名前以外、機密扱いよ」
「A級機密ってことは、存在していることは確かなんだ」
「A級機密の閲覧許可って、誰なら得られるんだ?」
わたしと紅泉は、さりげなく席を立った。わたしたちの顔写真が出なかったのは、向こうに情報がなかったからではなく、《ティルス》の一族に対する警告の意味ではないだろうか。
『そちらの迷惑娘を引退させろ。さもないと、次は容赦せず本拠地を叩く』
ということなのでは。
〝連合〟の最高幹部会が、うちの一族の自主独立路線を認めているのは、うちの技術力に一目置いているからだと、ヴェーラお祖母さまに聞いている。金の卵を産む鶏は、腹を裂くより、快適に過ごさせる方が得だから。
でも、わたしたちの、正確に言えば紅泉の暴れぶりが、とうとう我慢できなくなったのかも。
たぶん、特捜部のミギワ・クローデル本部長から、新たな指示が来るだろう。このまま隠密任務を続けるのか、それとも、どこかに避難するのか。
もう数時間すれば、過去にわたしたちが接触した人々から、情報が洩れ始める。ひょっとしたら、写真や動画の流出があるかもしれない。髪を染める程度の変装では、もう逃げられない。
(今度からは、迂闊に外を歩けないわ)
わたしはともかく、紅泉は身長だけで目立つ。その上、輝く美貌に派手な言動ときては、関わった人々に忘れられない印象を残す。
明日にはきっと、連邦中の市民が、謎のハンターのことを話題にしているだろう。

わたしはずいぶん長く、うとうとしていたのだろう。
何かが、鼻先をくすぐった。目を開けたら、白い蝶がひらひら、わたしの鼻先から飛び立ったところだ。蝶は野草の花をかすめ、小川の向こうに渡っていく。
周囲はぐるりと、針葉樹と広葉樹の混合森だった。空には白い雲がかかり、世界は柔らかな間接光に満ちている。
(ここは、いったい?)
わたしはさらさらと流れる小川のほとりの、暖かな草地にいた。懐かしい、水と緑の匂い。
わたしはなぜか、この場所を知っている。
深く馴染んでいる、と言ってもいい。この土地の匂いは、なぜかわたしを安心させる。
頭がぼんやりしたまま、クローバーの草地から起き上がった。子犬の頃に戻った気分で、よたよたとあたりを歩き、嗅ぎ回る。ヨモギ、タンポポ、葛、ドクダミ。
小鳥や兎、山猫やリスのような小動物はいるが、大型の獣はいないようだ。森の中には、人が踏み分けたような小道が続いていた。いや、馬の蹄の痕も残っている。
それをたどっていくうち、記憶の引き出しが開いてきた。
わたしは前にもこうして、この道をたどったのではないか。あの時は、そう、前方を駆ける少年を追いかけて。
その少年はするすると大木によじ登り、ターザンのように隣の木に飛び移った。そして、笑いながらわたしを呼ぶ。木登りできないわたしは、地上を走って彼を追いかけた。どこまでも。
ここは、まさか。
森を抜けると、なだらかな丘陵を見渡せる場所に出た。手入れされた草地と花畑と森林が、はるか彼方まで繰り返されている。
景色が遠くで迫り上がっているのは、ここが小惑星内部の人工空間――回転居住区だからだ。そして、その一角に、灰色と薔薇色の石造りの屋敷がある。見事な薔薇の庭園に囲まれて。
もう、間違いない。
ここは、わたしが子犬時代を過ごした場所。そして、少年の頃のシヴァと駆け回った場所。
どうしてか知らないが、わたしは故郷へ連れ戻されたのだ。
花畑の間の小道をたどり、三階建ての屋敷に向かった。あそこにはおそらく、シヴァを育てた最長老がいるはずだ。
彼女がいれば、わたしに説明してくれる。なぜ、わたしがここにいるのか。シヴァはどこなのか。
そう、思い出した。バイクで出掛けたシヴァが、拉致されたのだ。恐ろしく手際のいい、組織的犯行だ。
追跡を手配した記憶はあるが、そこから先が途切れている。
シヴァをさらった連中が、わたしのことも捕まえたのか。それならば、わたしはなぜここにいる。何の拘束も受けないままで。それとも、体内に爆弾でも埋め込まれたか?
一年中、花が途切れることのない薔薇の庭園を抜けて、何年も暮らした屋敷のテラスの下に出た。
砂利の小道から石の階段を登れば、テーブルや椅子を置いた広いテラスに上がれる。あの片隅が、子犬時代のわたしの寝床だったのだ。
時には乗馬用の馬を追って走り、時には単独で森を探険した。そして、戻ってきては餌をもらい、シャンプーやブラッシングをしてもらった。あまりにも懐かしいので、苦痛を感じるほどだ。
シヴァはここで、子供時代を過ごした。わたしは彼の手で世話してもらい、彼が遊びに出掛ける時には、必ずお供をした。彼がわたしの世話を怠った時は、最長老に厳しく叱られていたものだ。
彼が十歳を過ぎて、この隠居屋敷から、一族の本拠地である《ティルス》の屋敷に移された時は、わたしも一緒だった。
そこで、少女時代の紅泉と探春に出会った。一族の、他の人々にも。
現役世代を統率する総帥、マダム・ヴェーラ。その夫で、補佐役のヘンリー。ヘンリーの兄のマーカスと、その妻のサラ。女闘士のサマラやヴァネッサ、サーシャ。子供たちの教師役のシレール。
一族の者たちはそれぞれ、都市経営や研究組織や対外交渉を受け持ち、他の姉妹都市との間を行き来して暮らしていた……
「お帰りなさい、ショーティ」
長い黒髪を背に垂らした貴婦人が、テラス奥の室内から姿を現した。
わたしの記憶のままだ。象牙色の肌、物憂げな黒い瞳、膝下までの優雅な薄紫のワンピース、上質な真珠のイヤリング。
わたしが態度を決めかねて、彼女を見上げていると、微笑んで言う。
「しゃべっていいのよ。あなたたちのことは、全て知っています。シヴァが今どうしているかも、説明するわ」
では、わたしが〝ただの犬〟のふりをする必要はないのだ。
彼女はテラスに通じる階段に腰掛け、砂利の小道に伏せたわたしに、淡々と説明してくれた。
シヴァが最高幹部会の監視下に置かれ、グリフィンという名で呼ばれるようになったこと。《フェンリル》のリザードが、シヴァの目付役になったこと。要人の懸賞金リストが、グリフィンの名で世界に公表されたこと。市民の注目の的となった〝リリス〟が、連邦最高議会の要請で、軟禁状態に置かれていること。
何ということだ。
わたしは、何も察知していなかった。
進化したつもりが、とても足りなかったのだ。
茜を失い、シヴァの悲嘆を見てからは、自分にかけていた制限をあれもこれも取り払い、自分を拡大して、可能な限りの挑戦を繰り返してきたつもりなのに。
だが、わからないのは、この人だ。
なぜそんな、〝連合〟の内奥まで知っている。
シヴァの一族は、〝連合〟とは距離を置いてきたはずではなかったのか。それとも、それは擬態にすぎなかったのか。
「なぜ、わたしがここに、こうしているのですか?」
用心しながら尋ねた。黒髪の麗人は、静かに言う。
「いったんは冷凍したわ。少しの間、眠っていてもらうためにね。でないと、あなたは、シヴァを取り戻そうとして、あれこれ余計な真似をしたはずだから」
それでは、この人は?
「でも、懸賞金制度はもうスタートしたわ。邪魔をするには手遅れ。それに、あなたにも、役目を用意してあるの。これからは、わたしの下で働いてもらいます。現在の支配体制を続けるためにね」
あたりには、甘い薔薇の香りが満ちていたが、真冬のようにしんとして、胸が冷えた。
そうなのか。
ようやく見えてきた。
〝連合〟に加盟していないシヴァの一族が、なぜ何百年も、辺境の宇宙で無事に繁栄していられるのか。〝連合〟と敵対している〝リリス〟を後援していて、なぜそのことを〝連合〟に発見され、咎められないのか。
こうなったらもう、遠慮する必要はない。疑問は全てぶつけよう。ぶつけても、これ以上悪くなることはない。
「つまり、あなたが〝連合〟の支配者なのですね。それならば人類社会の、陰の支配者と言ってもいい。シヴァを育てたのも、紅泉たちを育てたのも、あなたの大きな計画の一部だったのですね」
最高幹部会というのは、この人の代理機関にすぎないのだろう。真の権力者の存在を隠すための、衝立のようなもの。
その衝立の中を覗かせてもらえる者は、この人に選ばれた忠実な臣下のみ。
黒髪の美女は、にこやかに言う。
「ええ、そういうこと。あなたもまた、その計画の一部なのよ」
わたしが?
「ただの犬のわたしが、ですか?」
少しばかり知能強化されても、到底、人間社会の深淵には届かなかったのに?
「あなたはもう、ただの犬、なんかではないでしょう。シヴァがあなたの知能強化を決めたのは、確かに彼の決断だったけれど、当時の彼の技術では、あなたをここまで育てることはできませんでした」
ぞくりとした。
まさか。
「そう。わたしがこっそり、手を貸したのです。シヴァの船の管理システムを通じてね。適切な時期に、適切な投薬。必要な刺激。シヴァが使おうとした人工細胞と、より望ましい細胞とのすり替え……そういったことで、あなたの知能強化を援助したの」
そういうことか。
わたしは深い納得と、敗北感に打ちのめされた。人間に負けないほど進化したなどと、途方もない思い上がりだったのだ。
それなのに、シヴァに偉そうな説教などして。穴があったら入りたい、というのはこのことだ。
「我々は、あなたの掌で飛び回る、孫悟空だったのですね」
孫悟空は慈悲深い釈迦に導かれたが、この人は? 慈愛の女神なのか、それとも、暗黒の魔女なのか?
「でも、無邪気な孫悟空は、この世に必要だわ。そうでしょう? それは、人々に夢と希望を与える存在だもの」
だから紅泉と探春は、正義の味方として、宇宙を飛び回ることを許されているのか。いつか、不要と判定される時まで。
「どんな夢を、人類に与えようというのですか。あなたが」
「世界は、理想郷に向かって進歩している、という夢かしら」
それはシヴァの夢であり、わたしの夢でもあった。だが、こうなってみると、それには大きな障害がありそうだ。
「でも、あなたは、その夢を認めていない?」
「個人の幸福と、人類全体の存在意義は、別次元の問題だわ。個人を甘やかしていたら、人類は停滞してしまうもの」
なるほど、そういう考えか。事件があろうと悲劇があろうと、それが社会を進歩させるなら、それでよいというわけだ。
「あなたが目指す方向とは……あなたの計画とは、どんなものですか」
「そうね。無限の進化……というところかしら。進化の果てがどうなるのかは、わたしにも想像がつかないわ。だから、進んでみたいの」
無限の進化とは、気が遠くなるような話だ。
「わたしには、シヴァとわたしの幸福が最優先でした」
「ええ、これまではね、それでよかったわ。でも、もう、それでは済まないのよ。あなたは進化して、普通の人間をはるかに超えたわ。だから、わたしの片腕になってもらいたいの」
わたしでは、この人の片手の指一本にも足りるまい。
「あなたは……市民社会と辺境が、どちらも存在した方がいいと思っているのですね。市民社会には、人材育成を任せる。辺境の違法組織には、新たな挑戦をさせる。そして、その挑戦の結果、人類全体が進化する……いや、人類の中から、新しい種族が誕生する。人類を超える種族が」
そうなった時には、人類は不要となる。
動物園の動物のように、幾つかの惑星に閉じ込められ、記念品のように残されるだけではないのか。あるいは、更なる実験の素材として使われるのか。
「さすがね、ショーティ。よくできました」
黒髪の女性は子供好きの教師のように、にっこりしてみせる。
つまり、わたしは、この人の作品の一つ。これまでは好きに行動させておいたが、それは修業期間だったからで、これからは本格的に役に立ってもらう、ということらしい。
「そういうことなら、貴女に逆らうという選択肢はないのですね」
「ええ、あと数百年か数千年して、あなたがそれだけの実力を備えるまではね」
残念だが、そうなのだろう。あと何年、わたしが生きられるかは、わからない。その間に、この人を超えられるかどうかは、なおわからない。
「あなたに従いましょう。わたしは、何をすればいいのです?」
今は、おとなしく軍門に下るしかない。そして、反撃の機会を待つ。
シヴァは絶対に、誰かの掌で満足したりはしないだろう。
「とりあえず、わたしの助手という地位で、幾つかの仕事を受け持ってもらいましょう。シヴァに悟られないように彼を助ける仕事も、その中に含まれます。あなたが傍にいると知ったら、彼に甘えが出ますからね」
それならば、よかった。シヴァの安否がわからないままでは、わたしが落ち着かない。
「その仕事なら、喜んでさせてもらいます」
「そう言ってくれると思ったわ。望んでする仕事の方が、成果が上がりやすいものね」
だが、以前から抱えてきた重荷が、もう一つある。それは今日まで、一つの仮説にすぎなかったが、ここにこの人が現れたことで、その仮説に真実味が加わった。
「せっかくですから、この機会に、一つ尋ねたいことがあります」
とうに人類を超えたらしい女性を見上げ、わたしは慎重に問いかけた。
「なぜ、あなたは茜を殺したのですか?」

彼女は、何も動じなかった。断定口調の質問を、疑問に思うふりすらしなかった。
それで、わたしは確信した。シヴァが茜を見つけたことも、愛した後で失ったことも、全て、この人の計画の内だったのだと。
あれは、茜が死んでから、一年ほどが過ぎた頃だ。
わたしは彼女の遺品を整理しようと思い、基地に置き去りにしていた、古い船に入った。そして、クローゼットの奥に蔵ったまま、忘れていた着物を発掘した。
紫の地に、白い花模様の絹地の着物。赤い帯。シヴァが娼館で茜を見た時に、彼女が着ていたものだ。他の女たちは、みな肌を露出するドレスだったのに。
(なぜだ?)
初めて、疑問が湧いた。あまりにも、偶然が過ぎないか。
たまたま、シヴァが立ち寄った先の歓楽街で、初恋の従姉妹にそっくりの顔をした女が、たまたま、従姉妹を思わせる着物姿で座っていたとは。
わたしは、その娼館にバイオロイドを納品した製造元の工場を調べ、その時期、茜と同型のバイオロイドが三百体あまり、付近の娼館に納入されていたことを知った。全て、しゃべれないように細工されて。
しかも、調べがついた限り、その女たちは、似たような絹の花模様の着物を着せられていた。ドレス姿の女たちの中で、嫌でも目立つように。
その指令は、相互に付き合いのない複数の組織にまたがって発令されている。そして、確実に実行されている。
残念なことに、茜の姉妹たちは、ほとんど生き残っていなかった。娼婦の暮らしは、彼女たちに多大な消耗を強いる。だから、生存率が低いのは当然なのだが、それでも、あまりにも死亡率が高すぎた……わずかな生き残りも、どこかの誰かに買われていて、わたしには追跡しきれなかった。
わずか一年で、三百人が、残らず消えてしまうとは。まるで、わたしに引き取らせまいとするかのように。
わたしは疑惑を深め、その指図をした何者かを探ろうとした。だが、調査はそこで壁に突き当たった。何か、大きな力が働いている。それは《フェンリル》なのか。それとも、その背後にある、より大きな組織なのか。
今は納得した。命令の源はこの人だ。
「わかりません。なぜ、シヴァを幸福にしておいてから、地獄へ突き落とす必要があったのか」
すると、黒髪の美女はうっすら微笑んで言う。
「あら、あなたはもう、自分で説明をつけているのでしょう。その説明を聞きたいわ」
わかってきた。この人のやり方が。冷酷な教師。教え子を、千尋の谷に突き落とす。這い上がってこられなければ、それまで。
「あなたはシヴァに、試練を与えたかった。シヴァがちっぽけな成功に安住して、大きな野心を忘れかけていたから。あるいは、野心を無限に先延ばししていたから。あなたは、シヴァが愛する女を得れば、真剣に未来を考えるだろうと思った。しかし、シヴァが茜と二人きりの幸福に安住してしまうのは、望ましくない。あなたは彼を、〝リリス〟のための裏方に据える予定だったから。シヴァが従姉妹たちのために真剣になるには、茜が邪魔になる……」
語りながらわたしは、それが正解であることを確信した。この人は、わたしをも試験したのだ。その真実に辿り着くかどうか。
「麗香さん、あなたはわたしに、何をさせたいのです。わたしを、あなたの敵にしたいのですか。このことを知ったら、シヴァは絶対に、あなたを許しませんよ」
「ええ、シヴァが知ったらね……でも、あなたが話さなければ、彼には知りようがないわ。そうでしょう? 彼が余計なことを探ろうとしたら、あなたが妨害してくれればいいのよ」
何ということだろう。わたしは、シヴァに言えない秘密を抱えてしまったのだ。
わたしが真実を話せば、彼は本気で怒る。だが、この人に戦いを挑んでも、勝ち目はない。
だから、わたしはシヴァに真実を話せない。そして、これから先、ますます話せないことが増えていくだろう。
わたしと彼の間に、渡れない川が生じてしまったのだ。この人の思惑通り。
いずれは、大きな敵と戦わねばならないと覚悟していたが、敵の正体がわかった瞬間、その懐に取り込まれてしまっている。
ここで逆らえば、記憶を操作されるか、存在ごと抹消されるかだろう。それでは、シヴァのために何もできない。
「いいでしょう。わたしは、シヴァに生きていて欲しい。だから、あなたの部下になります。遠い将来の保証はできませんが、当面は、あなたの指図に従って動きます」
美女はにっこりした。聖母のように。
「ありがとう。そう言ってくれると思っていたわ。遠い将来、あなたがシヴァと組んで、わたしに反逆するのなら、それは構いません。その頃には、わたしももっと進化して、力をつけていますからね」
今、わたしが見ている女性の姿は、巨大な知性体の、ほんの末端なのだとわかった。
この人はおそらく、超越化に成功している。
人間の限界を超えた、超知性体。
超空間ネットワークを通じて、存在を広く分散しているはずだから、弱点になる中枢というものはない。
したがって、簡単に滅ぼすことはできない。
わたし自身が超越化に成功し、自分を大きく進化させなければ、この人に追いつくことはできないだろう。今のわたしはまだ、この犬の肉体に依存している。ここから手足を延ばしても、中枢はまだここにある。それでは弱すぎるのだ。
いや、何をしたところで、差は広がるばかりなのかもしれない。
だが、それでも。
かろうじて、意地を示した。
「あなたの理想とわたしの理想、どちらがより大きな力を持つか、試してみることにしましょう」
この人はわたしのことを、自分が育てた実験動物の一体だと思っている。どう成長しても、創造主たる自分には敵わないと。
そうかもしれない。だが、世界は広い。どんな出会い、どんな出来事が生じるかわからない。
わたしは、それに賭けよう。
そして、それまでシヴァを守ろう。
たとえ、彼がわたしを忘れてしまっても。あるいは、わたしを敵と思うようになっても。

やられた。やりやがった。
まさか、こんなに早く、暗殺の成功例が出るとは。懸賞金リストを公表してから、たった一か月ではないか。
やってのけたのは、学生だ。男二人、女一人の三人組。母校である大学に講演に来た政治家を(まともな人物で、しかも二児の母親だったのに)、毒殺しやがった。
護衛官たちも、聴衆や大学職員たちは警戒していたが、講演会を企画した若い学生のことは、疑っていなかったのだ。軍と司法局、議会に付属する護衛庁、地元警察の間で、警備要員の相互乗り入れがあったせいもある。
その学生三人組は、張議員が演壇で喉を潤すための水に、特殊な微生物を仕込んだのだ。そして、講演会が終わってから、グリフィン事務局に要求してきた。脱出の手配をしてくれと。
微生物が彼女の体内で増殖し、致命的な毒物を分泌するまで、一日か二日はかかるという。それは、大学の付属研究所から盗んだ微生物だというから、まったく、中央の警備体制はなっていない。
俺は最初、張議員の治療ができないかと考えた。当局に情報を漏らしてやれば、治療が間に合うのではないか。
しかし、ルワナに止められた。
「いけません。リザードさまに禁じられています。そんな通信はさせられません。グリフィンという存在を、甘く見られてしまいます」
俺がグリフィン艦隊の主人だとはいえ、真の決定権を握っているのは、遠隔地にいるリザードだ。リザードが認めない行動は、艦隊の管理システムに拒否される。
やむなく、複数ある惑星脱出ルートの一つを使い(〝連合〟傘下の組織が協力者のために用意していたものを、横取りしたのだ)、彼らをいったん民間企業の倉庫に匿ってから、コンテナに隠して宇宙空間に脱出させた。
張議員が翌日、オフィスで倒れ、病院に運ばれる前に絶命してから、大慌ての捜査が始まったが、その頃には、三人の学生たちは遠くへ運ばれている。複数の企業の輸送船を利用し、中央の外れで、違法組織の船に出迎えさせる手筈を整えたのだ。
俺は自分の仕事の汚さにむかむかしたが、通話画面で話したリザードは、涼しい顔だった。
「最初の成功例だ、派手に歓迎してやればいい。その様子を見たら、次の跳ね上がり者が現れるだろう」
まだ社会に出てもいない学生のくせに、母校の大先輩を殺して、その報酬でぬくぬく暮らそうとは。
何という、腐りきったガキどもだ。
通話を終えてから、ルワナの前で怒鳴り散らしてしまった。
「そんなに辺境に出たいのか!? 不老処置を受けたいのか!? 永遠に、闘争し続けなきゃならないんだぞ!! 大体、よくもグリフィンなんて、得体の知れない奴を頼ろうなんて思ったな!!」
ルワナは自分のデスクで書類の整理をしがら、穏やかに言う。
「若いうちは、何でもできると思っているのですわ。優秀な若者は、天井知らずに自惚れているのが普通です」
口の中に、苦いものを感じた。
俺も、以前はそうだったかもしれない。
ちょっとばかり体力があるくらいで、自分は特別だと思い込み、いつかは大物になれる、あれもこれも夢を叶えられると思っていた。
だが、実際には女一人、守ることもできなかった。親友は今も、どこかで冷凍カプセル詰めだ。
自分の無力を知ることが、大人になるということか。
「いいだろう、派手に宣伝して歓迎してやる。有力組織に迎えて、幹部に据えてやろう。だが、ちやほやするのは半年程度だ。その後は、俺の好きにさせてもらう」
ルワナは平静だ。
「どうなさるおつもりです?」
「三人とも、凍結保存だ。十年ばかり寝かせておいてから、司法局に送り届けてやろう」
ルワナは首を傾げたが、反対はしなかった。十年後、俺がこの地位に残っているかどうかわからないのだから、当然だ。言うだけ言わせておいても害はない、と思うのだろう。
もちろん、俺だって綺麗な身ではない。だが、人を殺したとしても、これまでは、対等な戦いの結果だった。殺さなければ殺される、というぎりぎりの場面をしのいできただけだ。
暗殺の幇助は、後味が悪い。不安も強い。
もし、〝リリス〟を暗殺しようと企む奴が、こちらの知らないうちに、独自の計画を進めていたら。
(頼むから、事前に連絡してきてくれ)
と祈った。暗殺計画に最初から関与できるなら、効果的に妨害できる。性能の劣った武器を渡すとか、狙撃の邪魔をするとか、爆弾の爆破タイミングをずらすとか、当局に密告するとか。
グリフィンをあてにする、腐った犯人の方が、望ましいのだ。
「グリフィンさま、お茶の時間です。軽食をお持ちしました」
リナがにこにこして、ワゴンを押してきた。おかげで、殺伐とした気分が薄れてしまう。
リナはすっかり、第二秘書になりきっていた。俺の好みも把握して、毎日、至れり尽くせりの世話焼きだ。
コーヒーには濃いクリーム、ハンバーガーには玉ねぎとピクルス、フライドポテトには強めの塩味、アップルパイはレーズン入り。
「ルワナさんには、紅茶とクッキーです」
「あら、ありがとう」
「わたしは、バナナパフェをいただきまあす」
態度は相変わらず能天気だが、この娘もこれで、事情を抱えているのだ。
ルワナから、リナの経歴を聞いた。子供の頃、両親と共に中央の客船から拉致され、他の数百名の船客と同様、競りにかけられ、別々に売り飛ばされたのだ。
売られた先の組織をリザードが潰して、生体実験の材料にされていた子供たちを手に入れた。何人かはそのまま継続して実験に使い、死なせたが、リナは運良く生き残った一人だという。
利発で負けず嫌いであり、反抗心が強かったので、リザードに気に入られ、手元で幹部要員として鍛えられたのだとか。
聞いてしまえば、哀れな話だ。
本人はもう、子供時代の記憶を失い(生体強化の実験台にされ、色々な薬品を使われた結果だ)、リザードのことを父親のように慕っている。彼にとっては、道具の一つに過ぎないというのに。金では買えない忠誠心を、子供時代から育てることによって、手に入れただけのこと。
もし、この娘のことを本気で心配してやる者がいるとしたら、それは、俺くらいのものではないか。
それで、ルワナがいない時を狙い、そっとリナに問いかけてみた。
「リナ、おまえ、中央に帰りたくないのか。本当の家族が恋しくないのか」
すると、リナは黒い目を見開いて、きょとんとしている。
「だって、何も覚えていませんから……」
「だが、おまえの一族は、おまえを待ち続けているはずだ。売られた両親はもう死んでいるかもしれないが、故郷の星には、祖父母も親戚もいるはずだぞ」
俺に権限があれば、この子を中央に送り届けてやれるのだが。
リナは少し考えたが、首を横に振った。
「無駄です。わたしの乗った船が襲われても、軍は助けてくれませんでした」
「それは、間に合わなかっただけだ」
「いいえ。違法都市で売られても、実験台にされても、ずっとずっと、助けは来ませんでした。軍も司法局も、被害者のことを未解決事件のファイルに入れて、忘れてしまいました」
俺はつい、反論に詰まる。
確かに、軍や司法局は、違法組織がらみの犯罪には及び腰だ。辺境は広すぎ、違法組織は数多い。だからこそ、紅泉たちのようなハンターを利用する。正規の軍人や捜査官は法に縛られるが、灰色のハンターなら、当局は成果だけを受け取ればいい。
「市民社会にいても、安全ではないってことでしょう? 戻ったところで、また誘拐されるかもしれないじゃないですか。だったら、有力な違法組織にいた方がましです。ここから更に誘拐されることなんて、まずないんですもの」
皮肉な話だ。市民社会にいるより、大手の違法組織の一員でいる方が安心とは。
「しかし、ここにいて楽しいか。こんな戦闘艦の中で暮らして」
「あら、そうですね」
リナはなぜか、笑いをこらえる顔をした。
「少なくとも、セレネとレティシアは、わたしをうらやんでくれます。わたし、グリフィンさまの秘書になれて、ラッキーかな」
何をぬかす。
「俺を殺しかけておいて、言う台詞か?」
「あら、わたしは本気じゃありませんでした。グリフィンさまだって、余裕でかわせたじゃありませんか」
「本気で怒ってたように見えたぞ」
すると、リナはころころ笑う。
「グリフィンさまって、女心が全然おわかりにならないんですね。男の人だから、仕方ないですけど」
何が女心だ。まだ小娘のくせに。
だが、そう言ったらまた、リナはぎゃんぎゃん反論してくるだろうから、口には出さない。
それにしても、だ。
俺はあっという間に、リナにも甘く見られるようになってしまった。小娘にも恐れられないグリフィンで、いいのだろうか。
問題は色々あるものの、優秀な女たちに補佐されて、俺の仕事は巧く回っていた。ジョルファは週に二回程度、セレネとレティシアを従えて、俺の暮らす船にやってくる。そして、俺の指図したことのあれこれに、細かく難癖をつけてくる。
「この男には、もう一段階、見張りを付けた方がいい。この性格からして、予想外の行動をとりかねない」
「この援助はやりすぎだ。無駄な死人が増える。与える武器は最小限でいい」
「この妨害工作は露骨すぎる。もっと遠回しにするべきだ。後で司法局にたどられてしまう」
言い返せることもあれば、できないこともあった。向こうも馬鹿ではない。資料をよく検討して、計画の穴を突いてくる。それもまた、悪くはなかった。議論しているうちに、もっといいやり方が見えてきたりする。
用件が済むと、ジョルファはすぐ引き上げていくが、セレネとレティシアは一時間かそこら、余計に残っていくことが多かった。そして、何だかんだ俺にまとわりついてくる。
「グリフィンさま、お忍びでドライブに行きません?」
「人目を気にせず、のんびりできるホテルがありますのよ」
どちらも熟れた美女だが、背後にジョルファがいると思うと、俺はひたすら怖い。どんな罠が待っているか、わからない。間違っても、ちょん切られるような羽目に陥りたくない。
だが、近頃では、リナが俺の盾になってくれる。腰に手を当てて、冷然と言うのだ。
「お二人とも、無駄ですわ。グリフィンさまは、そういう私的な外出はなさいません。もし外出なさる時は、わたしがお供します」
すると美女二人は、冷ややかな笑みを浮かべる。
「あら、リナ、お子様は引っ込んでいていいのよ。わたしたち、あなたは誘っていないんだから」
「誘われなくても、グリフィンさまのいらっしゃる所にはお供します。わたし、護衛ですから」
「まあ、一人前の口を利くようになったわね。ついこの間まで、リザードさまに甘えていたくせに」
「リザードさまが恋しくて、夜中にべそをかいているんじゃなくて?」
むろん、セレネもレティシアも、背伸びしているリナを可愛いと思い、先輩としてからかっているのだが、リナは本気で憤然とする。
「今は、グリフィンさまの秘書です。お二人とも、ジョルファさまのお側にいなくていいんですか。お役目怠慢ですよ」
「ジョルファさまにはちゃんと、わたしの部下が付いているわ」
「わたしたちにだって、自由時間くらいあるのよ」
俺はその間に、こそこそ逃げる。ルワナは我関せずで仕事しているので、彼女の執務室に隠れたりする。
「女同士で仲良くすればいいのに、なぜ、ああなるんだ?」
「いいんですのよ、あれで。セレネもレティシアも、グリフィンさまが誘惑に乗らないのはもう納得していますが、意地があるから引けないんです」
「何の意地だ?」
「女にとって、殿方を魅惑できることは、大きな自信になるんですわ」
誘惑ゲームか。ろくでもない。
「女ってやつは、世界中の男が、自分の奴隷にならないと気が済まんのか?」
「あら、何も、世界中の男性でなくていいんですのよ。自分が狙いをつけた殿方だけで」
「俺が、グリフィンの地位にあるからだろ?」
一文無しの負け犬の俺だったら、彼女たちは洟もひっかけないだろう。
「その認識ができる点、グリフィンさまは、まともでいらっしゃいます。大抵の男性は、自分の魅力と、自分の地位の魅力を混同していますからね」
褒められたのだろうか。それとも、あやされたのだろうか。
そこへ、リナがやってくる。
「グリフィンさま、しつこい方たちは引き上げました。お夕食が済んだら、お忍びでドライブに行きませんか? よろしければ、ルワナさんも」
「いえ、わたしは結構。二人で行ってらっしゃい。けれど、迂闊に姿をさらしてはいけませんよ。どこに〝リリス〟のスパイがいるか、わからないのだから」
紅泉たちは、ほとんどの違法都市に、有機体アンドロイドの助手を配置している。それもこちらで把握しているつもりだが、見落としている部分があるかもしれない。
「はあい、わかってます」
《フェンリル》の組織力を後ろ盾に育ったリナはお気楽だが、まあいいだろう。この子が機嫌よくしていると、俺はほっとする。何か、置き忘れてきた大事なものを取り戻したような気がして。
女の子は本当は、これくらい無邪気でいいはずなのだ。世間の荒波と戦うのは、もっと後でいい。
いや、そうではない……それは違う、か。
この子は家族から引き離され、身体強化の実験台にされ、記憶を奪われた。この明るさは、虚無に通じている。おそらくは、絶望からきた開き直りのようなもの。
だからこそ、せめて、俺の元では安心させてやりたい。この生活がいつまで続くものか、俺にもわからないが。

みんな、あたしを馬鹿だと思っている。
一族の総帥であるヴェーラお祖母さまも、従兄弟のシレールも、司法局員にしては物分かりのいいミギワ・クローデルも、そして親友の探春でさえも。
思い立ったらすぐに飛び出す軽はずみ、反省を知らない能天気、と言うのだ。
いちいち反論はしないが、あたしだって、少しはものを考える。
いいのか、このままで。
〝リリス〟が懸賞金リストに載せられたのは、これまでの活動の結果だから、仕方ない。違法強化体であるあたしたちを、市民社会の要人たちと並べてくれたのだから、感謝してもいい。
〝リリス〟というのは、あたしと探春のペアのことだが、戦いの主役はあたしである。あたしがいなければ、探春は、一族の領宙から出ることはなかっただろうから。
その〝リリス〟が世間の注目の的になったからと言って、おとなしく隠れ暮らしたままでいいのか。
快適なホテルとはいえ、いつまで籠もっていれば済む?
司法局はあたしたちに任務を続けさせたがったが、連邦最高議会から横槍が入ったのだ。市民社会に違法強化体をうろつかせるのはまずい、マスコミも騒いでいるし、しばらく謹慎させておけ、と。
もしかすると、このままお役御免かもしれない。司法局では二度と雇ってくれず、市民社会への出入りも禁じられるかもしれない。
探春は、平和な植民惑星で過ごすバカンスを愛しているのに。
かといって、故郷の違法都市《ティルス》へ戻っても、あたしは座敷牢行きかもしれない。お祖母さまは元々、ハンター稼業には反対だったから。
『そんなものは、あなたの自己満足でしょう、紅泉。小悪党を退治したところで、〝連合〟の支配体制は変わらないわ』
という冷淡なご意見。
この懸賞金騒ぎで、ますますお怒りなのではないだろうか。
一族の最高指導者である麗香姉さまも、今度ばかりは、あたしをかばってくれないかも。
それは困る。一族の支援がないと、必要な艦隊を維持できない。
司法局からの賞金だけで、何年も違法組織と戦い続けられるものか。最高議会の連中、〝リリス〟への報酬が高すぎるなんて、辺境の現実を知らないのだ。一回まともな戦闘をやったら、船や装備の補充に、いくらかかると思ってる。
一族の造船工場に実費で頼んでいるから、何とかやりくりがついているだけだ。
そのあたしが、報酬目当てのハイエナだって? 冗談ではない。ボランティアと言ってもいいくらいだ。
あれこれ思い悩んでいると、むかむかしてくる。最高幹部会の思惑通り、〝リリス〟は行動を封じられてしまったのだ。
あたしがいなかったら、他に誰が、はるばる辺境まで、凶悪犯を追っていく?
そいつらとつるんでいる違法組織を、どうやって壊滅させる?
もしも、そんな奇特な闘士が現れたとしても、しばらく活躍したら、その人物まで賞金首にされてしまう。
政治家だって学者だって、目立つ活動をしたら懸賞金リストに載せられると思えば、自己規制してしまうだろう。つまり、市民社会は無力化する一方だ。
「紅泉、おかしなこと考えないで」
探春が、あたしの背中にそっと顔を寄せてきた。蜂蜜のような、甘い香水の香りがする。
あたしたちはホテルの中庭を見下ろす窓辺にいるが、バルコニーには緑の植え込みがあって、目隠しになっているから、中庭に面した他の部屋からの視線を気にしなくて済む。
惑星首都の一角にありながら、プライバシーが守れる作りのホテルだった。作家や映画スターなどの有名人が、便利な隠れ家として愛用している宿らしい。
つまり、あたしたちも有名人になってしまったわけ。
グリフィンの放送までは、軍と司法局のわずかな関係者にしか知られていなかったから、あちこち素顔で出歩けたのに。
「わたしたちは、指示通り、隠れていればいいのよ。懸賞金制度にどう対応するかは、連邦政府が決めることだわ」
「ないよ、対策なんか」
「えっ?」
「政府の機能なんて、とっくに骨抜きだ。惑星連邦自体が、虚構みたいなもんだ」
議員や高官、学者や財界の有力者のうち、誰が〝連合〟の操り人形になっているか、わかりはしない。
多くの市民は、汚染がどこまで進行しているか、その実態を知らないのだ。
連邦軍の艦隊など、とうの昔に〝連合〟の大艦隊の敵ではない。まともにぶつかれば、いや、ぶつかる前に遠隔で制御を乗っ取られる。既に、それだけの技術格差がついてしまっている。
市民たちはこのまま未来永劫、羊の群れでいるつもりか。
真の飼い主は、最高幹部会だ。市民たちは、彼らに捧げるために、子供を育てている。
「だからって、わたしたちに何ができるの? こうなったのは、市民たちが長いこと、辺境の無法状態から目を背けていたからよ」
「ま、そうなんだけどね」
普通の人間は、自分の生活の安泰を真っ先に考える。だから、彼らが辺境を無視していたことは、責められない。まともな市民は、自分たちの暮らす植民惑星を理想郷にすることに忙しかったのだ。
その間に、辺境の宇宙へ出た開拓者たちは、組織を作ってバイオロイドの部下を培養し、互いに勢力争いを繰り返していた。その争いの中で、戦術も科学技術も急速に磨かれた。
研究に制限がないのだから、進歩は速い。使える資源とエネルギーは、無尽蔵だ。
そうして、多くの市民が気づいた時、辺境の違法組織は、大きな連合体になっていた。人口からすれば小さな集まりだが、科学技術では、市民社会を大きく引き離している。
〝連合〟はその優位を保つため、市民社会から有能な研究者を引き抜き、まともな対策を立てられる政治家や官僚たちを、次々に洗脳したり、暗殺したりしてきた。
このままでは、辺境の優位はいつまでも続く。
このホテルに押し込められてから、あたしはずっと考えていた。何か一つでいい。最高幹部会に、打撃を与えてやれないか。
たとえば、あたしがグリフィンを仕留められたら。
最高幹部会は次の誰かを立てるだろうが、そうしたら、そいつも倒す。誰も、懸賞金制度の責任者になりたがらなくなるまで。
「ねえ、屋敷に帰らない?」
探春は、あたしの背中に顔をすりつけたまま言う。
「もうハンターとして、十分に戦ったわ。〝リリス〟が引退すれば、誰も追ってこないわよ。何年か、屋敷でのんびりしてから、また何か、新しい活動を考えればいいじゃない」
探春の気持ちはわかる。あたしは元々、勝ち目のない戦いをしているのだ。〝連合〟はもはや、市民社会を包囲し、内部にも浸透している。
しかし、戦いをあきらめたら、何が残る?
何より、自分で自分を軽蔑してしまう。
戦うこと、抵抗し続けることに意義があるのだ。少なくとも、あたしの場合はそうだ。
最初から、負けを認めて縮こまっているなんて、生きているといえるか。
――ああ、まったくもう。
壁にぶつかると、あいつのことを思い出す。二つ年上の従兄弟。シヴァがいたら、一族の守りを託し、探春を預けておけるのに。そうしたら、あたしは、もっと思いきった動きができる。
今はあたしが行く所、どこにでも探春が付いてくるから、本当の危険は避けるしかないのだ。
あたしが絶対に失えないものは、この従姉妹だけ。
故郷を出てから二十年近い戦いの日々、ずっと探春があたしを支えてくれていた。あたしが背後を気にせず戦えたのは、探春のおかげ。
あたしは他の誰が死んでも平気だが、探春を失ったら、きっと耐えられない。
「離していいよ。勝手に逃げたりしないから」
身をねじって言うと、細い腕があたしの胴体から離れた。
「ごめん、苦労ばかりかけて」
すると、白い顔が花のように微笑んだ。
「そう思うなら、いたわって。わたし、ダンスがしたいの。ワルツを踊ってちょうだい」
いいですとも。
探春と踊る時、あたしはいつも男役なので、すっかりそれに慣れてしまっている。たまに女役で踊ると、女の感覚を取り戻すのに手間がかかり、相手の男性の足を踏みそうになる。
たぶん、一生、あたしは女役になれない。あたしを女役にしてくれるような男が、この世にはいないから。
肉体的にあたしより強いシヴァでも、駄目だった。あいつは少年の頃からずっと、探春だけに憧れの視線を向けていた。
嫌われたからといって、自棄になって家出したりせず、探春が振り向いてくれるのを待てばよかったのに。
時間をかければ、男嫌いの探春にだって、通じていたはずだ。シヴァの不器用な好意が。
この世には、男と女しかいないのだから。互いに、いたわりあって暮らすしかないではないか。