
ブルー・ギャラクシー 再会編

超越体になって、得たものは多い。
地位、権力、知識、仲間、部下。
しかし、失ったものもある。
その筆頭は〝眠り〟だ。
ミカエルの〝一部分〟が休息することはあるが、総体としては常に活動を続けている。
グリフィンの名で、あるいは別名で何百という艦隊を展開させ、各星区からの報告を受け、他の超越体との情報交換を行い、特定の人物の監視や警備を指揮し、様々な分野の調査研究を遂行する。


人間の肉体に宿るミカエルは、時々、麗香さんの隠居屋敷の地下に降りる。そこをゆっくり歩くと、過去に麗香さんがどんなことを考え、どんな実験を行ったかが実感できる。
光合成をすれば、人間は他の生き物の命を奪わずに済み、幸福に暮らせるか。
太陽の光で発電ができれば、余計な欲を持たず、平和に暮らせるか。
手が四本あれば、便利になるか。
眠らない肉体なら、どうなるか。
真空中で生きられるのなら、どうか。
数百年の試行錯誤の証拠である何千もの実験体が、凍結されて保存されている。
そこを歩きながら、ぼくは麗香さんの思考をたどる。
地球を捨てて辺境の宇宙に出てきてから、自分の率いる一族をどのように守り、進化させ、外敵と戦ってきたか。
今のあの人はもう、そういう試行に飽きているのではないか。
彼女から見れば……いや、もはや性別など超越しているだろうが……人類など、池に漂うミジンコ程度の存在にしか思えないのでは。
ぼくたち超越体は、精々、小魚程度。
ならば彼女は、その池から飛翔しようとしている鳥か。
麗香さんならば、この銀河を捨てて遠くに旅立っても、何の不安も不自由もないだろう。
もしかしたら、この宇宙を捨てて、新たな宇宙に乗り出すことすら、計画に入っているかもしれない。
別の物理法則に従う、全く別の時空間。
ぼくには到底、ついていけないし、ショーティたちにしてもそうだろう。
ぼくらはここに残り、人類の世話役として活動していくことになるはずだ……少なくとも、向こう数百年か数千年。
あるいは数万年。数十万年。
自分たちが、人類に見切りをつけるまで。
それは麗香さんが、ダイナとシレールの総帥夫妻に告げたことからも、うかがえる。
「わたしはもう、一族の子供を遺伝子操作で作ろうとは思わないの。あなた方の世代で、人間としては、理想の姿に到達したのではないかしら。だから、これから先は、普通に子供を作ればいいわ。もし、それで不足なら、あなた方の考えで改造すればいいでしょう。わたしはもう、一族の人数に制限をかけようとも思っていません。シヴァの子供たちのように、わたしの管理を外れて生まれた子供もいるのだし」
ダイナとシレールは、顔を見合わせた。
最長老の方針が、変わったのだ。
それは、一族にとっての大きな方向転換になるのか。
それとも、一族そのものが枝分かれし、大きく分裂していく始まりなのか。
ともかく、その結果、彼らには普通に子供が生まれ……それは男と女の双子だったが……二人で子育てを楽しんでいる。
リリーさんとヴァイオレットさんも、《ティルス》に戻ってきた時は、一緒になって子供たちと遊んでいる。
少し遅れて、シレールと泉の間にも子供ができた。その子たちは、ダイナの子供たちとは異母兄妹として、共に転げ回って遊んでいる。
どの子にもシレールがたっぷりの愛情を注いでいるから、誰もひねくれたりせず、健やかに育っているのが嬉しい。
主に中央で活動しているリリーさんとは、年に一度か二度、《ティルス》への帰郷の機会に対面していた。そのくらいの時間なら二人きりになっても、ヴァイオレットさんは黙認してくれる。
ぼくたちは隠居用小惑星の草原や林を歩きながら、話をする。離れていた間に、何をしていたか。事件、冒険、新たな発見。研究組織に勧誘した、才能ある若者たち。

しかし、本当に疲れたら、死ねばいいのだ。
その選択肢があるからこそ、耐えられる。物理的な基盤が消滅すれば、超越体も死ねるのだ。
死ねない方が、残酷だ。
もし、この宇宙から脱出できないとして、星々の輝きが消え、老いて死んでいく冷たい宇宙に、ただ一人で取り残されたら……
そんな想像、試すだけで心が冷える。
ぼくはまだ、生命の溢れる世界にいたい。悩んだり心配したりして、生きていたいのだ。
「今はまだ、無限に生きる心配なんか、できないな」
ヴァイオレットさんに渡す花を摘みながら、リリーさんは笑っていた。撫子、竜胆、桔梗。
「明日まで生きていられるか、その保証もないんだし。それより、次の食事が楽しみだよ」
今のリリーさんは、まだ百年も生きていないのだから、辺境の基準からいえば若者の部類である。まだ、生きることに飽きてはいないだろう。
――貴女のことは、ぼくが守りますよ。少なくとも、ぼくが超越体として生きている限り。
でも、それはまだ言えない。
リリーさんは、辺境には既に高度な超越体が存在するだろうと思っているけれど、その元締めが麗香さんだとか、ぼくが子分の一人だとかは、夢にも思っていない。
ぼくはただ、〝成長を止めた子供〟として、哀れまれている。
「それじゃ、もし世の中が平和になって、〝リリス〟としての仕事がなくなったら、どうしますか」
ぼくが暮らす桔梗屋敷を遠くに眺めながら、聞いてみた。するとリリーさんは少し考え、笑って言う。
「学校を作って、子供たちに戦い方を教えるかな。だって、好戦的な異星文明が攻めてくるかもしれないし」
リリーさんは、とことん戦士なのだ。戦いや挑戦がなければ、すぐに退屈してしまうだろう。
「もし、その心配もないとしたら?」
とりあえず、この銀河には、人類が脅威に感じる異文明はなさそうである。そんなものがあれば、とうに、どこかの艦隊か調査船がぶつかっているだろう。
もし、人類が存在を察知できないほど異質な、あるいは高度な存在なら、争いを心配しなくてもいいだろうし。
だが、ぼくらが教えを請えるような……そんな都合のいい先進文明があることは、期待できない。その逆は、あるかもしれないが。
人類は、単独で宇宙と向き合うしかないのだ。
「うーん、畑でも耕して暮らすかな。犬を飼って、鶏を飼って。まあ、探春に聞いてみるよ。探春がしたいようにすればいい」
日頃、ぼくがリリーさんから遠く離れて暮らしていることで、ヴァイオレットさんは安心している。だから、こういう時、自分は屋敷で留守番して、ぼくらを二人きりにしてくれる。夜は麗香さんの屋敷に泊まり、リリーさんだけをこの屋敷に泊まらせてくれるのだ。
「いつか、そういう時が来るといいですね」
人類はバイオロイドを奴隷にし、さんざん搾取してきた。脅迫しておきながら、愛情や誠実を要求するのだ。
ぼくも奴隷として暮らしたし、脳腫瘍で死ぬ恐怖にも怯えたが、リリーさんに出会ったことで救われた。もう、人間たちを恨んではいない。
寂しい人間たちが、望んでも得られない愛情の代わりとして、バイオロイドの奉仕を求めたのだ。
今は、辺境にも新たな波が広がっている。そう遠くない未来に、バイオロイドの製造はなくなるだろう。既に生まれた者は、人間と同等に扱われるだろう。
そのための布石は、麗香さんが打ってくれた。
ジュン・ヤザキの管理する違法都市《アグライア》と、ハニーとシヴァが作った女たちのネットワーク《ヴィーナス・タウン》が、辺境で勢力を広げ、有機的に結びつけば、今の最高幹部会は力を失っていく。
そのことは、最高幹部会のメンバーも既に納得している。納得しなければ、麗香さんの計画を阻害する者として、排除されるとわきまえているからだ。
今後、まだ数十年はかかるとしても、市民社会の道徳が、辺境にも浸透していくだろう。
そうなれば、悪党狩りのハンター〝リリス〟も役目を終える。
リリーさんは学校を作ってもいいし、他の銀河の探険に出てもいい。そうしたら、ミカエルの〝一部〟が護衛として、こっそり付いていく。
超越体の仲間も、少しずつ増えていくはずだ。
やたらと数を増やしては厄介なことになるが(どんな超越体になるか、必ずしも予測できるわけではない)、一人ずつ、ぼくらの審査に合格した人間を仲間にすればいい。
元司法局長のミギワ・クローデルも、いずれ市民社会から脱出させるつもりだ。彼女の意志と能力は、このまま老衰死させるには惜しい。
辺境で若い肉体を手に入れ、第二の青春を楽しめば、そのうち飽きて、超越化に興味を持つかもしれない。そうしたら、ぼくか他の超越体が手引きをすればいい。
読めないのは、麗香さんの内心だ……
ぼくの推測が、当たっている保証はない。
ジュン・ヤザキを子供の頃から(もしかしたら、彼女の両親が出会う以前の段階から)見守っていたのは麗香さんだし、シヴァをハニーと引き合わせたのも麗香さんだ。
シヴァは、最長老の隠居所である薔薇屋敷の地下に、本物の茜が凍結保存されていると知ったら、怒り狂うだろう。
彼がショーティと共に船を離れて上陸した隙に、麗香さんは、茜を同型のバイオロイドとすり替えさせたのだ。それから、自殺を演出して、シヴァを絶望の底に叩き込んだ。
真実を知ったシヴァが、激怒して反逆するという未来も考慮した上で、麗香さんは、ぼくに薔薇屋敷への出入りを認めてくれたわけだ。
実際には、シヴァが何もしなくても、現在の〝連合〟の支配体制は崩壊していくはずだが……
その先は、どうなるのだ?
自由を求める野心家たちは、道徳の押し付けを嫌い、この銀河から逃げていくだろう。
彼らが行く先に、どんな地獄が新たに生まれるのか?
それとも、麗香さんは、その地獄にこそ期待しているのか?
もし、そこに恐ろしい怪物が育つとしたら……ぼくらは今から用心し、戦いの備えをしておかなくてはならないだろう。
麗香さん本人に尋ねても、答えてはもらえない。あの人は、ぼくらが依存心を持つことを望んでいない。
権力の一部を分け与えてくれたのは、ぼくらに未来を考えさせるためなのだ。
子供を持つと、以前は見えなかったものが見えるようになる。
今にして、わかる。
父は、わたしを見捨てたのではなかった。
娘のわたしに、あえて重荷を背負わせることはない、と考えただけなのだ。道場を継ぐなら、息子で十分だと。息子がそれを望まないなら、道場は弟子の誰かに委ねてもよいと。
ただ、それをうまく伝えられない人だっただけ。わたしが違法組織の誘惑に負けるくらい苦しんでいるなんて、想像もしなかっただろう。
それでも、わたしは家を捨て、故郷を捨て、ここまで来てしまった。辺境の違法都市に。
ダイナに出会ったことは、大きなきっかけだったけれど、それがなくても、いつかは辺境を目指したのではないだろうか。わたしは、偽善的で頭の固い市民社会に満足してはいなかったから。
それならば、ここで幸せになるしかない。
いつか、孫の顔を両親に見せることができればいいのだけれど。
生きて、無事でいることだけは、シレールの助けを借りて、そっと伝えた。でも、居場所は教えられない。わたしは市民社会から見れば、我欲で殺人未遂を犯した犯罪者なのだから。
子供を持つと、朝から忙しい。
自分の身支度をしながら、ぐずる娘を起こし、あやしながら抱き上げ、身支度させて、食堂へ連れていく。
わたしたち母娘の暮らす西棟から、短い渡り廊下でつながれた本館の食堂へ行くと、東棟からは、ダイナが自分の子供たちを連れてやってくる。
双子の兄の春と、妹の夏。
わたしの娘の梢は、双子より半年ほど遅く生まれた。
毎日、同じ屋根の下でもつれあって育っているから、子犬が三匹いるようなもの。遊んだり、喧嘩したり、仲直りしたり、一緒に悪さをしたりして、騒動の起きない日はないくらい。
春と秋は、ダイナとシレールが〝自然に〟作った子供で、特に遺伝子操作はしていない。二人とも、同じ制作者の手になる強化体なので、それで問題はなかったのだ。
けれど、強化体のシレールと普通人のわたしでは、普通の妊娠・出産は難しい。もし何とか子供ができても、後で病気や故障が起こる可能性が高い。
そこで、彼の一族の最長老……科学者である麗香女史に、シレールとわたしの生殖細胞を託して、強化処置を施した受精卵を作製してもらった。
おかげで梢は強健な肉体を持って生まれ、頑丈な春や秋と遊ばせても、命の危険はない。
わたしから見ると、高い木によじ登ったり、屋根の上から飛び降りたり、走りすぎて壁に激突したり、取っ組み合いのプロレスごっこをしたりして、はらはらする毎日だけれど。
「あたしもあんなものだったから、大丈夫よ」
というダイナの言葉を信じて、何とか耐えている。
アンドロイド侍女が用意した食卓に子供たちを座らせ、食べさせている合間に、自分たちの食事も済ませるのが、いつもの流れ。
誰かが何かこぼしたり、グラスを倒したり、喉を詰まらせたりして、なかなか落ち着いて食べられないけれど、それも成長と共に、ましになっていくはず。
本館の主であるシレールは、一足先に自室から降りてきて、自分の食事をあらかた済ませているので、子供たちの食事の世話を、かなり引き受けてくれる。
「春、そんなに急いで詰め込まなくても、時間はあるよ」
「夏、その手をちょっと拭かせてくれるかい」
「梢、お替わりが欲しかったら、そう言いなさい。人のお皿に手を出してはいけないよ」
アンドロイド侍女にはそういう躾はできないから、そこは親が教えなければならない。
子供たちの世話をしているうちに、完璧に整えたシレールの髪や服に、様々なべたべたが付いてしまうけれど、それはもうすっかりあきらめているようで、苦笑で言ってくれる。必要なら、また着替えるから大丈夫だと。
「今日も元気だな。いい子で留守番しているんだぞ。パパたちは、夕方までお仕事だからね」
夫が一人で妻が二人という家庭は、市民社会から見れば変則かもしれないけれど、子供たちは最初からこの環境で育っているから、これで当たり前と思ってくれている。
いずれ成長して、よその家庭は違うとわかれば、そこで考え込むかもしれないけれど。
でも、個人の自由が最大限に認められるのが、辺境のいいところ。
性転換も、無性体や両性体になることも、女同士や男同士で暮らすことも、男性がハレムを持つことも、各人が自由に選んでいる。
とはいえ、もしもダイナがわたしを拒めば、わたしと梢は、別な場所に家を持つことになっただろう。
ダイナが正妻であり、わたしは愛人にすぎないという見方も強かったのだ。シレールの一族の間では。
でも、ダイナは自分とわたしを対等に扱うように、シレールにも一族の皆にも言ってくれた。
その結果、本館をはさんで左右に別棟を造り、こうして穏やかに暮らすことになっている。
子供たちにとっては、どの棟も自分たちのものだ。鬼ごっこや隠れんぼで、隅々まで駆け回っている。家具や食器の破損は、いつものこと。
もう数年して、子供たちが自分の腕力や、わがままを制御できるようになったら、犬や猫を飼おうと話している。乗馬も教える、とダイナは言う。
「みんなで遠乗りしたら、きっと楽しいわよ。焚火を焚いて、キャンプもいいわね。ここじゃなくて、麗香姉さまの小惑星なら、何の心配も要らないし」
こんな幸せ、少女時代には想像もつかなかった。家庭を持って、母親になれるなんて。
妊娠を期に、わたしは元の組織から、ダイナ一族の組織に移った。円満な移籍になるよう、ダイナとシレールが手を尽くしてくれた。リザードもまた、それを認めてくれた。リザードにとっては、わたしはまだ〝持ち駒〟なのかもしれないけれど。
今は、一族の総帥の座を引き継いだダイナの元で、都市の管理機構の一員として働いている。道場主を目指していた少女のわたしが見たら、何と言うだろう。
「おはよう、おちびちゃんたち。お祖母ちゃまですよ」
「お祖父ちゃんもいるよ」
食事が済む頃、ヴェーラとヘンリー、前の総帥夫妻が揃って来てくれる。汚れても構わない、動きやすい格好で。
ダイナとシレール、そしてわたしに仕事の大部分を譲り渡したので、二人は時間に余裕が出来、子守りを引き受けて下さっている。とても有り難い。読み書き計算を教えることから、ままごと、積木遊び、食事、おやつ、外遊びまで、すっかり二人にお任せしている。
あとは夕方まで、わたしたちはそれぞれの職務に励む。
都市内で活動する他組織の監視。もめ事の仲裁。
商売上の交渉。
ビルの補修や新設などの工事の管理。
小惑星工場での研究・開発への目配り。
組織内の人員への仕事の割り振り、新人の採用、研修。
研究・開発部門に関しては、麗香女史からミカエルへと引き継ぎがなされているので、わたしたちはおおむね、彼からの報告を聞く程度のこと。
一族の一人、アスマンもまた自分の研究施設を持っているけれど、こちらは基礎研究が主なので、何らかの成果が出るには、百年、二百年の歳月がかかるのではないだろうか。
こういう地道な研究に取り組む余裕があるのも、一族の本業で十分な利益が出ているからこそ。これからも三つの違法都市を繁栄させていくのか、わたしたちの責務。
いずれ子供たちが育てば、都市経営の責任を分け持ってくれるはずだ……と期待している。
もしかしたら、〝リリス〟が市民社会に出ていったように、子供たちもまた、違う道を選んで、出ていってしまうかもしれないけれど。
夕方は、仕事が一段落した者から帰宅して、子供たちと遊ぶ。総帥夫妻はやれやれと苦笑しながら、自分たちの屋敷に引き上げる。
夕食はまた、無事に済むまで一仕事。
でも、子供たちが手を焼かせるのも、わずかな年月のこと。彼らもいずれ、一人で大きくなったような顔をすることだろう。
わたしたちは、いつかきっと、この喧噪を懐かしく思い出すはずだ。
夜、娘をベッドに潜らせて、お話を読んでやり、寝顔を見守るひと時が、一番平和な時間だ。
シレールの端正な面差しを受け継ぐ、黒髪の可愛い娘。
わたしが望んでも得られなかった、屈強な戦士の肉体も備えている。
それが本当にいいことなのかどうかは、まだわからない。活力を持て余し、〝リリス〟のように、戦いを求めて銀河を飛び回るかもしれないから。
どうか、無事に大きくなりますように。
そして、いい男性と巡り会いますように。
できれば、わたしのような、家庭の幸福を得られますように。
娘を持っていると、世の中の危険のあれこれが、ひたひたと心に押し寄せる。
誘拐、暗殺、脅迫、暴行、破壊、汚染。
事故や事件の報道を聞く都度、あるいは実際に後始末に駆け回る都度、そんな不幸が娘に降りかからないよう、自分にできることはないかと考えてしまう。
地位や権力があるということは、嬉しいことでもあるが、責任も重い。財力に甘えて安楽に過ごそうとすれば、それもできてしまうから、自分が弛緩しないよう、常に自戒しなければならない。
もちろん、わたしにはダイナという盟友がいるから、ダイナに遅れをとらないようにと意識するだけで、自分を律することになるけれど。
子供たちが安心して出ていける世の中になるように、少しでも手を打っておきたい。
悪質な組織は《ティルス》や姉妹都市から退け、良心的な組織が伸びるように。
それは、ダイナにもシレールにも共有されている願いだから、わたしたちは、チームとしてうまくやっていた。
いずれ子供たちが大きくなったら、興味や適性に応じて、職務の一部を譲っていくことになるだろう。それが無理でも、新たな人材を求め、権限を与えていくことはできる。子供たちが、他所で優秀な伴侶を見つけ、連れて戻るかもしれない。
この都市は、そうやって継承されてきた。
自分がその大きな流れの中に迎えられたことが、とても嬉しい。ここに落ち着いてようやく、人生の本番を始められた気がする。
もし、時を超えてメッセージを贈ることができたら、少女時代の自分に言ってやりたい。
そんなにピリピリしなくても、生きていけるのよ。
将来は、素敵な男性と出会えるのよ。
もっとゆったり構えて、自分を許してもいいのよ。
でも、不安と苛立ちに責められていた時代こそが、今のわたしの土台を作ったのだといえる。
学業と拳法修行の双方で、心身の限界まで努力してきたから、違法組織に入ってからも、さして辛いと思わずやってこられた。
それならば、苦しむことも、いいことなのだ。ある程度までは。
できるなら、自分の娘には、そんなに苦しんでほしくないと思ってしまうけれど……
この子には、どんな未来が待っているのだろうか。
もし、外に出て傷ついたら、戻ってきてほしい。
わたしはいつまでも、変わらずに愛しているのだから。
子供たちは遊び疲れて、芝生の上で、てんでに寝入ってしまった。一緒に駆け回っていた子犬たちも、近くで丸まったり、母犬に甘えたり、水を飲みに行ったりしている。
強化体の子供たちを、ここまで疲れさせることができたのは、紅泉だから。
わたしは屋敷からタオルケットを持ってきて、子供たちにかけて回った。建物に囲まれた中庭は暖かく、安全だから、このまま一時間やそこら、寝かせておいて問題はない。
子供といっても、既に個性ははっきりしてきた。
遊びながらも周囲に気を遣う、慎重な春。三人の中でただ一人の男の子なので、自分が妹二人を守らなくては、という責任感も育っている。
双子の片割れ、お転婆で挑戦好きの夏。わたしとしては、子供時代の紅泉の暴れ方を思い出してしまう。この子が将来、どんな冒険に乗り出すか、今から親たちは心配だろう。
泉の娘である梢は、パパが大好きな甘えっ子だ。人をうまく使う、ちゃっかり型のお姫さま体質でもある。
「誰に似たのかしら」
と泉は不思議そうだ。泉自身は、武道家の父に厳しく仕込まれ、甘えることができずに育ったらしいから。
一族の年輩者たちも、交替で子供たちと遊びにやってくる。ダイナ以来、待ちこがれていた新世代だ。それぞれ得意分野を教えようと、手ぐすねひいている。
「あなたはどうなの、探春。そろそろ、子供を作ったら」
と尋ねられることはある。でもわたしは、自分自身で子供を持つ気はなかった。
わたしにとっては、紅泉が〝大きな子供〟のようなもの。
紅泉としては、自分の方が、わたしを守っているつもりでしょうけれど。
その紅泉は、全身についた葉っぱや土ぼこりを払い落としながら、テラスに向かう。
「もうそろそろ、格闘技の手ほどきも始めたいな」
きちんとした体さばきや護身の技術を教えた方が、無用の怪我は減るはずだから。それに、技術があれば、意図せず人を殺してしまう事故も防げるだろう。
「姉さま、お疲れさま。お茶をどうぞ」
仕事を早目に切り上げて帰宅したダイナが、アンドロイド侍女に命じて、テラスにお茶の支度をさせている。
「泉とシレールは、夕食には帰宅しますから。今のうち、休憩しておいて」
子供たちが目覚めたら、また大騒ぎだろう。
小さい子は可愛いけれど、わたしは泥まみれになって一緒に遊ぶ気はしない。もう少し聞き分けができる年齢になったら、ピアノやバレエ、手芸の基礎は教えたいと思うけれど。
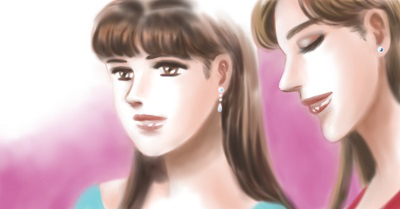
それでも紅泉が子供たちと遊びたがるから、この子たちが生まれてからは、仕事の合間に、まめに帰郷するようにしていた。
子供はすぐに大きくなってしまうから、今の時間が貴重なのは確か。
自分が子供だった時代は、遠い昔になってしまった。わたしと紅泉が育った屋敷は、シレールたちが暮らすこの屋敷から、ほんのわずかの距離にあるのだけれど。
今ではヴェーラお祖母さまたちが、毎日のように子守りに通ってきている。ヘンリーお祖父さまも、長年の苦労から解放され、ほっとしているようだ。
都市の運営は、その分、ダイナやシレール、泉たちの責任になっている。第二世代、第三世代のおじさま、おばさまたちも、徐々にダイナに判断を預けるようになっているらしい。
ミカエルもまた、麗香姉さまの後継者として、問題なく研究部門を統括している。
一族の未来は、心配しなくてよさそうだと思う。
わたしたちには、アスマンと梨莉花もいるのだ。シヴァを愛した女性が、シヴァに内緒で作った子供たち。
ミカエルの管理下にあるとはいえ、彼らは自分たちのささやかな研究所で独自に活動しているから、いずれそちらからも、何らかの成果が出てくるだろう。
物理や数学の基礎研究なので、その成果が実際に応用できるようになるまで年月はかかるだろうけれど、構わない。一族には、それだけの余裕がある。応用ができなくても、人類の知的領域が広がることは望ましい。
アスマンは、リザードの元にいる母親のリナとは、たまに面会しているようだ。それでも、あちらの組織に戻るつもりはないと言っている。アスマンにとっては、今も紅泉が師匠だから。
中央の大学に通わせてもらった恩は忘れていない、というのがアスマンの台詞。
悪い子ではない……それはわかっている。わたしとしても、シヴァの遺伝子から勝手に作られた子供たちに、いつまでも意地悪などしていられない。
こうやって、世代交替が進んでいくのだ。
わたしたちは相変わらず、〝伝説のハンター〟だけれど……
司法局からの依頼は、だいぶ減っていた。事件はまだあるけれど、解決を〝リリス〟に頼る必要性が薄れてきたのだ。
今では辺境に違法都市《アグライア》という一大拠点ができ、若いジュン・ヤザキが総督として君臨している。
父親のヤザキ船長以上の豪傑らしいのは、遠くから見ているだけでもわかった。父親が軍や司法局から信頼されていることで、ジュン・ヤザキもまた、中央とのつながりを保っている。何といっても、真っ先に娼館廃絶を打ち出したおかげで、市民の人気も高い。
軍人や捜査官たちは交互に《アグライア》に派遣されてきて、辺境での経験を積んだり、事件解決に当たったりするようになっている。
惑星連邦軍では、市民の反応を測りながらも、少しずつ《アグライア》周辺に艦隊を派遣して、将兵たちを辺境に慣れさせようとしているから、いずれ、軍の行動範囲はもっと広がっていくだろう。どこかの時点で、〝連合〟が歯止めをかけない限り。
それにまた、百以上の違法都市に《ヴィーナス・タウン》の支部が置かれるようになり、そこも女性たちを保護する拠点になっている。
《ヴィーナス・タウン》というのは、当初は単なる女性用のファッション・ビルだった。各組織の女性幹部が、買い物したり、ホテル階で静養したりできる娯楽施設。辺境では初の試みだったので、あっという間に人気を博して支店が増えた。
それが途中から、『女性の聖域』として知られるようになってきたのは、〝連合〟の最高幹部会が肩入れを始めたからだ。
《ヴィーナス・タウン》の創業者、通り名でハニーと呼ばれる女性は、自分の店を『女性の駆け込み寺』にしてのけた。人間であろうとバイオロイドであろうと、保護を求める女性がそこに駆け込めば、たとえ有力組織であっても追跡をあきらめるのだ。
最高幹部会が、ハニーの後ろ盾であることを、世界に公言したから。
もっとも、これまで、六大組織からの逃亡者はいないと聞いている。おそらく、逃亡の必要などないのだろう。あるいは、逃亡しようとした瞬間、洗脳されるのか。
《アグライア》と《ヴィーナス・タウン》――この二つの新興勢力が、辺境の勢力地図をかなり塗り替えていた。中小組織は、何かあれば、彼女たちの出方を窺うようになっている。ジュンとハニーは互いに手を取り合い、同盟者であることを世界に宣言した。
期待の持てそうな展開に見える……それでも《ティルス》の総帥であるダイナは、まだ、様子見をしているところだ。
これまで、勢いのあった新興組織が、何かの具合であっという間に凋落したり、消滅したりするさまを、わたしたちの一族は幾度も眺めてきた。だから、慌てて接触したり、同盟を持ちかけたりすることはしない。
それが、古くから続いてきた一族の知恵。
問題は、最高幹部会がいつまで、この潮流を認め続けるかということ。
本当にこのまま、辺境が市民社会の道徳に染められていって構わないと思っているのだろうか?
それとも、この流れをうまく操り、自分たちの利益になるよう誘導している最中なのだろうか?
《アグライア》の総督ジュン・ヤザキも、《ヴィーナス・タウン》を率いるハニーも、最高幹部会が認めた人材なのだから、この潮流自体、最高幹部会の創り出したものではある。
ただ、どこまでが計算通りで、どこから計算以上なのか、そのあたりがわたしたちにはわからない。だからまだ、〝リリス〟の看板は下ろせない。
「やれやれ、元気なチビたちだ」
紅泉は花壇を見下ろす席に着き、紅茶のカップを取り上げた。
「ああやって寝てれば、天使なんだけどね」
わたしは手を伸ばして、紅泉の髪にからみついていた小枝を取り払った。美人だし、お洒落も好きな人なのに、何かに夢中になると、子供に戻ってしまう人。
すっかり貫禄のついたダイナは、シックな焦げ茶色のスーツ姿で、微笑んで座っている。首に巻いたエメラルドのネックレスは、シレールが贈ったものだという。
昔は自分も、紅泉にせがんで肩車をしてもらったこと、どのくらい覚えているかしら。蜂の巣に手を出して、蜂たちに追われて逃げたこともあった。ベッドの下に蛇の卵を隠していて、わたしに悲鳴を上げさせたこともあった。子供時代は、夢のように過ぎてしまう。
「ところでね。姉さまたちに、報告することがあるんだけど……通信では言いにくいので、姉さまたちが来てくれるのを待っていたの」
改まって、何だろう。
都市経営の上では、わたしも紅泉も、何の貢献もしていない。若い頃から市民社会に入り浸りで、故郷の《ティルス》や姉妹都市のことは、一族に任せきりだった。
「実は、しばらく前にね……シヴァ兄さまから、連絡があって」
突然、あたりの色彩がなくなった。
頭から、血の気が引くのがわかる。
なぜ、その名前が。
ああ、生きていたのね。どこかで死んでくれればと、願っていたのに。
ダイナの声が、どこか遠くから聞こえている。
「ずっと音信不通だったことを詫びて、一度、挨拶に来たいというの。伴侶ができたので、その人を紹介したいんですって」
詫びる?
伴侶?
あの男が、よくもそんな。
でも、ダイナはそれを認めたのだ。現在の総帥としては、当然の判断。
「シヴァ兄さまって、アスマンそっくりね。というか、アスマンがほぼクローンなんだから、似ていて当然なんだけど。そもそもあたしは初対面なので、シレール兄さまが確認してくれて、本物に間違いないだろうって保証してくれたの。もちろん、お祖母さまたちにも報告してあるわ」
手足が冷たくなり、頭の中で過去の記憶が再生される。堅い床に押し倒され、体重差と腕力差で押さえ込まれ、服が引き裂かれ……
わたしは、少女らしい夢や憧れを全て失った。それなのに平気な顔で、ここに戻ってくるつもりなの。
あなたの伴侶は、あなたがしたことを知っているの?
それでも構わない、平気だというくらい、あなたを愛してくれる人?
テーブルの上のわたしの手に、大きな温かい手が重なった。紅泉は、わたしがシヴァに会いたくないことを知っている。
でも、自分自身はずっと、彼を心配していたのだ。貴重な従兄弟だから。幼馴染みだから。
紅泉には、人を恨むなんて負の気持ちはわからない。自分をずたずたに切り刻むような思いも、きっとしたことがない。ミカエルから婚約解消を言い渡された時も、荒れたのは、ほんの少しの間だけ。今は彼の幸福を願うことだけで、満足している。だから負の感情を持ち続けるわたしを、神経質な病人としか思わない。
「――それはよかった。無事だったんだ。彼が戻ってくれるなら、一族も安泰だね」
と寛大に言う。すると、ダイナが説明する。
「ううん、ここに戻るつもりではないみたい。今は自分の組織があって、仕事で忙しくしているらしいから」
つまり、成功したから、凱旋したいのね。何という、身勝手な男。一族から逃げ出して、何十年も音沙汰なしでいて、今は歓迎されるとでも?
「でも、自分にもしものことがあった場合、伴侶や子供たちに、頼れる先があった方がいいからって……家族のために、顔つなぎしたいってことみたい」
「子供までできたのか」
と紅泉は素直に驚く。
「へえ、あいつが父親にねえ。まあ、それはめでたい」
「今回は、子供たちは置いてくるって言ってたけど」
それでもダイナの言い方からは、わたしに配慮していることが感じられた。ダイナにも、わかってはいるのだ。わたしがシヴァを嫌っていること。許すつもりがないこと。
でも、一族の総帥としては、貴重な人材の帰還を歓迎するしかない。それを、わたしに理解してくれと願っている。
「そうか。シヴァの家族なら、もちろん、あたしたちで守ってやればいい。アスマンたちを同席させるかどうかは、彼らにも意見を聞いてみなきゃだけど」
紅泉なら当然、そう言うだろう。心底から〝正義の味方〟なのだもの。
頼られれば、誰のことでも守る。頼られなくても、守りたければ守る。相手が犯罪者でも、悔い改めた者なら、寛大に受け入れる。
わたしはだめ。許せない。
アスマンと梨莉花はいいけれど、シヴァはだめ。
ああ、気持ちが悪い。気をゆるめたら、この場で吐いてしまいそう。かろうじて、みっともない真似はしたくない意地で、こらえているだけ。子供たちが、すぐ近くで寝ているのだもの。
「で、いつ来るって?」
「お互い、日程を調整して……シヴァが、姉さまたちが戻ってくる時に合わせることになって……つまり、明日ってことなんだけど……」
ダイナはそっと、わたしをうかがっている。わたしが泣いたり、叫んだりしないかどうか。ずっと、打ち明けるタイミングを図っていたのね。
「もちろん、嫌だったら、探春姉さまは会わなくていいんだし」
でも、一族の皆は、シヴァとその伴侶に会うつもりね。紅泉も、もちろん会うでしょう。
わたしが受けた傷なんか、もう半世紀以上も昔のこと。水に流せばいいと、皆、内心では思っている。
でも、皆がシヴァを迎える時に、わたしだけこそこそ、別室に隠れていろというの!?
それは違うわ。
遠慮するとしたら、向こうの方でしょう。
なぜわたしが、息を潜めて隠れていなくてはならないの。
「ダイナの予定の通りにすればいいわ。わたしは別に、構いません」
わたしが言うと、ダイナはほっと息を吐き、苦しい笑顔を浮かべた。
「それじゃ、明日のお昼、お祖母さまの屋敷の方で、会食の席を用意するから。子供たちは、挨拶だけさせて退席させます。シヴァお兄さまとハニーお姉さまは、そのまま屋敷に泊まりますから」
ハニーというのね、その女。
《ヴィーナス・タウン》の総帥も同じ通り名だけれど、まさか同じ人物ではないでしょう。あんな大物が、シヴァみたいなチンピラを相手にするはずがないもの。
いえ、シヴァも一時期、《フェンリル》のリザードと関わりがあったらしいから、それなりに、大物との付き合いはあるのかもしれないけれど……
「その、シヴァの相手って、どんな人?」
紅泉が、邪気のない顔で問う。ダイナもまた、楽しげに答えた。
「あたしもまだ、名前しか聞いてないの。遠距離通信では、あまり長く話せなかったから。だから、明日のお楽しみね」
ダイナもこれまで、シヴァの少年時代の写真くらいしか見ていなかったはず。でも、紅泉の語る思い出話を聞いて、憧れを持っていたらしく、そわそわしているのがわかる。
「ずっと家出していた人が帰ってくるって、ドラマチックよね」
と紅泉に話しかけ、ちらとわたしを気にしては、また話しかける。
「すっごい男前なんだもん、上ずっちゃった。あの低音、しびれるわ。女殺しよね」
紅泉は気軽に笑う。
「おやおや、シレールが聞いたら悩むよ」
シレールはダイナを妻にして子供たちを得、ようやく穏やかな日々を送れるようになった。泉という第二の妻も、ダイナの要望があってこそ、受け入れたようなもの。
ダイナは泉に借りがあると感じているから、彼女を追い払うことができなかったのだ。
わたしはミカエルを追い払ってしまったのだから、その点でも、ダイナには狭量だと思われて仕方ない……
いえ、違うわ。
シレールには、ダイナが最愛だった。だからダイナは、第二の女に対する余裕が持てるのよ。
でもわたしは、紅泉にとっては、いつか王子さまが現れるまでの〝預かり物〟のようなもの。
わたしにとっての王子さまか、あるいは、紅泉にとっての王子さま。
必死でしがみつかなければ、捨てられていた。紅泉に捨てられたら、わたしは生きていられない。そんな人生、想像することすらできない。
「もちろん、シレール兄さまが一番だけど、野性的な魅力っていうか……ほら、シレール兄さまって貴族的だから、色々と繊細でしょ。シヴァ兄さまの方が、荒波で鍛えられた感じ……アスマンのママが、片思いして子供を作ったっていうの、わかるわ。アスマンもいい男だけど、原型の方が一段と渋いわね」
男なんて、外見は立派でも、中身は多分に幼児的なのに。
「とにかく、生きていたんなら、よかった、よかった」
と、紅泉は安堵した様子で言う。
「アスマンと梨莉花には、これから話すわ。来るも来ないも、彼らの自由よ」
とダイナ。
もう、こうなったら、平気な顔をして通すしかない。
どちらさまでしたかしら、すっかり忘れていましたわ。
そんな顔をして、最低限の挨拶だけ交わせばいいのよ。
わたしには、紅泉がいてくれるのだもの。
その他のことは、全て、どうでもいいことなのだから。
その晩、ダイナの屋敷に設けられた、わたしたち用の寝室で、ベッドに座った紅泉は、わたしを膝の上に抱き上げた。
ミオの件があってから、紅泉は、長いこと自分に課していた、ある制限を外している。
ミオの心を癒すために、ミオを抱いてやれたなら、同じ親切を、従姉妹のわたしに向けても問題はない、と考えたのだ。
たとえ、そこに恋愛感情はないとしても。
わたしにとっては、十分に嬉しいことだった。ほんの、たまにでいいのだ。紅泉の負担にならない程度で。
唇にキスをしてもらい、全身を愛撫してもらえれば、わたしの飢えは癒される。そんなことを望んだら、紅泉に嫌悪され、遠ざけられるのではないかと、長い年月、悩んでいたのだ。
その壁を崩してくれたのだから、今はミオに感謝するしかない……彼女は彼女で、幸せでいてくれることを願えるようになった。
「今日は、びっくりしたね」
わたしの腰を抱き、髪を撫でてくれながら、紅泉は言う。何のことを言っているのか、疑問の余地はない。
「ええ」
「何年になるのかな。もう五十年……いや六十年? 七十年近いのか」
「そうね」
シヴァが家出してから何年かで、わたしたちも屋敷を出た。成人した紅泉が、修行と冒険を求めていたから。
幸いなことに、わたしたちはハンターとして市民社会に迎えられ、中央と辺境を行き来して暮らしてきた。でも、シヴァは一族の援護もなく、辺境でどうやって生き延びてきたのだろう。
自分たちの研究所にいるアスマンと梨莉花からは、こちらから会いに出向くつもりはない、という返答が来ていた。彼らは彼らで、身勝手な親に対して、苦い思いがあるのだろう。
シヴァに横恋慕したリナという女性が、彼の遺伝子情報を盗んで勝手に作った子供が、アスマンと梨莉花だ。
わたしたちはある時、シヴァそっくりの少年が、違法都市で腕試しに暴れ回っていることを知り、驚いた。昔の紅泉やシヴァと、そっくり同じことをしているなんて。
喧嘩相手にされたチンピラたちには、迷惑きまわりない話。
でも、紅泉が彼を捕獲し、鍛え直したおかげで、今ではすっかり落ち着いている。妹の梨莉花も兄を慕って、研究所の補佐に納まっていた。リナからは時々、会いに戻って来なさいという要請が届くとか。でも、子供たちが親離れするのは、自然なことだ。たまに通話していれば、親不孝とは言えないだろう。
「シヴァを愛する女性が、リナの他にもいたのね……」
それは、彼女たちの趣味を疑うという意味だけれど、紅泉は笑って応じた。
「そりゃあまあ、黙って立ってりゃ、いい男だから」
そして、わたしの頭を撫でてくる。
「探春は別に、無理しなくていいよ。別室にでもいれば。必要なことは、あたしから話しておくし」
彼がどんな風に、この七十年近い歳月を過ごしてきたのか、特に興味はない。ことさら、会う必要もない。ただ、わたしが臆して逃げた、と思われたら、それは悔しい。
あんなこと、ハンター稼業の中で見てきた地獄に比べれば、たいしたことではないと、今なら言える。
そもそも、あなたのことなんか、ほとんど忘れていたし。
それを思い知らせるためには、美しく毅然として、冷たい視線を投げてやらなくては。
明日は、わたしの肌を引き立てるサーモンピンクのドレスを着て、菫の香水を吹きかけておくわ。いえ、麗香お姉さま愛用の、梅花香がいいかもしれない。しんとした、冷たい香りだもの。
紅泉は、わたしが意固地になっていると思うらしい。わたしの額にキスをして、慰めてくれる。
「シヴァはもう、別な場所で生きているんだから、これでよかったよ。明日、顔合わせしたら、あたしたちは中央に帰ればいいし」
そう。名前や素顔は隠しているけれど、わたしたちは市民社会の英雄として、十分な尊敬を受けている。
全て、なるべくして、こうなったのだ。

翌朝、お祖母さまの屋敷へ顔を出すと、ミカエルが来ていた。
珍しい。いつもは麗香お姉さまの隠居用小惑星にいて、用事は大抵、通信で済ませているのに。
「あ、ぼく、一応、顔を出してくれって、ダイナさんに呼ばれたんです」
ミカエルは、言い訳に聞こえないような言い方で、にこやかに言う。白いシャツブラウスの襟元に細い紺のリボンを結び、柔らかい素材の紺のスーツを着て、相変わらず、天使のような美少年ぶり。
「泉さんと違って、ぼくはあなた方の〝一族〟に加わったわけではありませんから……居候か、使用人の分際だとわきまえていますよ」
とんでもない。
麗香お姉さまに信頼されて、今では一族の研究・開発部門を統括する実力者。
アスマンでさえ、ミカエルの采配の下にいることを認めている。ダイナもシレールも、何かあれば、ミカエルの知恵をあてにする。
〝リリス〟の活動も、ほとんどミカエルが援護してくれている。戦闘艦の新造や、新たな兵器の装備など、彼に頼りきり。
まして、紅泉は今でも、ミカエルのことを想っているのだから。婚約を破棄されても、紅泉とミカエルとの間にある心のつながりは、消えてはいない。
「ダイナがあなたを呼ぶのは、当然だわ。わたしたちも、あなたにはいつも助けられています」
厭味に聞こえないよう、努力して言った。
もしもいつか、わたしが紅泉を残して死んだら、その時は、ミカエルがわたしの位置に納まることは間違いない。
紅泉はひとしきり泣いたら、ミカエルに手を差し伸べ、胸に抱くだろう。そして、わたしのことを思い出にしてしまう。それを想像すると、わたしは生き抜く意欲を掻き立てられる。
ミカエルには、負けたくない。
心が歪んでいるのは、わたしなのかもしれないけれど。
「あ、ミカエル」
紅泉がやってきて、嬉しげにミカエルを抱きしめ、額にキスをした。ほうらね。ミカエルもまた、喜びで頬を紅潮させる。
「リリーさん、今日もお綺麗です。そのドレス、いいですね」
「そう? ありがと。きみも素敵よ」
紅泉は深い青のドレスを着て、金褐色の長い髪に、大粒の黒真珠のイヤリングがよく映えている。首には薄手の青紫のストールを巻いて、それが手首のタンザナイトの腕輪に合っている。
シヴァに会うのが楽しみで、いそいそお洒落をしてきたのだ。
女らしくて、素直でおおらかで、可愛い性格をしているのだけれど、見た目がきついから(怒った時は暴風だし)、なかなか他人に理解されないのが紅泉の悲劇。
いえ、もちろんミカエルは、ちゃんと理解しているわ。
だから、紅泉はミカエルが大好きなのよ。
「後でゆっくり話そうね。いま、お祖父さまたちに挨拶してくるから」
「はい」
紅泉が行ってしまうと、わたしたちはまた、探る視線で向き合う。
ミカエルの目に映るわたしは、明るいサーモンピンクのドレスを着て、三連の淡いピンクの真珠を首に巻いてはいるけれど、底意地の悪い魔女だろう。
「ヴァイオレットさんが何を考えているか、ぼく、大体わかる気がするんですけど」
と、柔らかい微笑みで言われた。こちらもまた、笑みを返す。
「わたしも、あなたが何を考えているか、大体わかると思うわ」
わたしが邪魔をしなければ、紅泉はミカエルと結ばれていた。二人は今でも、心の底で互いを欲している。ただ、〝気の毒な〟わたしに遠慮しているだけ。
「性格が悪いのは、お互い様ですよね」
と、ミカエルは澄ました微笑みを保って言う。
「でも紅泉は、あなたのことを天使と思っているわ」
「そういうリリーさんだから、ぼく、大好きなんです」
わたしも、そう。
紅泉は悪意がなくて、単純だ。この世の中から、理不尽に虐げられる者をなくしたいと、本気で思っている。
そんなこと、人間が全員、悟りを開かない限り、ありえないのに。
「でも、ぼくは、ヴァイオレットさんもまた、正義感の強い人だと思いますよ。ただリリーさんが好きなだけでは、何十年も戦いきれないでしょう」
素直でないわたしは、褒め殺しではないかと、警戒してしまう。
「ヴァイオレットさんは、この世が自分の思う通りでないことが、我慢ならないんでしょう。腐敗とか、裏切りとか、強欲とか、そういう醜悪なものを視野から消し去りたい……そうではないですか?」
「あら、そうなのかしら……」
確かにわたし、頭の悪い人間や、愚かな出来事を見ると、苛々するけれど。
それはきっと、ミカエルも同じだわ。この子は賢すぎるから。
「この世を理想の世に近づけたいというのが、貴女の戦う動機でしょう? ことによったら、リリーさんより純粋ですよ」
どんな皮肉を込めて、そう言っているのかしら。
「別に皮肉じゃなくて……」
ほら、わたしの心を読んでる。
「まあ、理想主義というのは、一歩間違うと怖いことになりますが……リリーさんがいれば、貴女の理想主義が暴走することもないでしょうし」
やっぱり、わたしを〝潔癖性の困り者〟だと言いたいのね。
「紅泉は、甘いから」
でも、多くの人間に好かれ、信頼されるには、その甘さが必要なのだ。世間では、それを人情と呼ぶ。
わたしには、その大らかさがない。つい、人を断罪したくなる。
「それで、シヴァについて、あなたの調査は?」
ミカエルのことだから、彼の過去を探り、この都市に危険はないか、紅泉に害は及ばないか、徹底的に調べたはずだ。
「ああ……ナギに資料を送っておきましたよ。色々なことが判明しました。ヴァイオレットさんには不愉快かもしれませんが、シヴァはずいぶんな大物になっているようです」
確かに、不快感が走り抜けた。ミカエルにそう言わせるほど、あの男が成功しているなんて。

シヴァが神経質になっている。
数日前から、隠しきれないほどそわそわしていたけれど、《ティルス》に接近するほど、それが顕著になっている。何度も鏡を見たり、髪や襟元を直したり、欲しくもないコーヒーを何杯も飲んだりして。
日頃、洋服や髪型にこだわる人ではないのに、今回だけは、
「これで大丈夫か、おかしくないか」
と何度もわたしに念押しする。
シヴァは冷淡で無愛想に見えて、実は愛情深くて繊細なのだとわかっているから、わたしは、自分こそが不安がっているというふりをした。
「わたしたちが〝連合〟に庇護されていること、あなたの一族に、どう受け止められるかしら」
とか、
「本当に〝リリス〟は、わたしたちを無事に帰してくれるかしら」
とか。
そうすれば、シヴァはわたしを慰めたり励ましたりすることになるから、自分の心配からは、少しでも気をそらせるはず。
本当は、ショーティから大丈夫だと保証されたので、身の安全という意味での心配はしていない。ただ、歓迎の度合いがわからないだけ。
だから、子供たちはショーティや部下たちに託して、《アヴァロン》に置いてきた。シヴァに罪があっても、わたしに罪があっても、子供たちには関係ない。
どうか、あまり冷淡な扱いを受けませんように。
さすがに、シヴァの初恋の女性には、避けられるか、罵られるかと、覚悟しているけれど。
少なくとも、シヴァが心底から後悔していることだけは、信じてもらえますようにと祈っている。
シヴァの息子のアスマンも、娘の梨莉花も、結局は《ティルス》に居着いてしまっている。彼らが面会してくれるかどうかは、まだわからない。リナがシヴァに断りなく作った子供たちだから、親に対しては、複雑な思いがあるだろう。
それでも、できるならば、いざという時のため、ペネロペとリュウに、信頼できる身内がいた方がいい。
わたしたちの《ヴィーナス・タウン》が、いつまで安泰か、保障はないのだ。明日にでも最高幹部会が、
『《ヴィーナス・タウン》は、〝人集め〟の役目を終えたな』
と決定すれば、すぐさま本部も支部も接収されてしまい、わたしたちは逃亡の旅に出なければならないかもしれないのだ。
ショーティが助けてくれると思いたいけれど、彼もまた〝連合〟の背後にいる超越体には、頭を押さえられているらしいから……
《ティルス》の外周桟橋には、出迎えの車が来ていた。本当は自分たちの車で目的の屋敷まで行きたいけれど、ここはもうシヴァの一族の掌だから、少しばかり抵抗しても無駄……とはわかる。
客人として、ゆったり振る舞わなくては。
万が一、シヴァの従姉妹がわたしたちを射殺するようなことになっても、ペネロペとリュウは安全圏にいる。
護衛車も含めた車の隊列が、ゆるやかに回転する都市の居住区に入った。
緑の樹海を貫く広い道路、花崗岩の島のようにそびえる繁華街、野花で覆われた丘、川で結ばれた幾つもの湖、緑地に点在するホテルや他組織の拠点。
わたしたちの車は途中から繁華街の地下通路に入り、深く密かに守られたトンネルの中を延々と通って、どこかの地下駐車場に停まった。一族の屋敷への出入りは、部外者にはわからないようになっているという。
広い駐車場に降り立つと、ふわふわの赤毛をショートカットにした、可愛いタイプの美人が待っていた。金のイヤリングと、エメラルド色のツーピースがよく似合う。瞳もまた、見事なエメラルド色。
横にいるのは、濃紺のスーツを着た、黒髪の理知的なハンサムで、これがダイナとシレールの総帥夫妻だとすぐわかる。もう何度か、シヴァが通話で話しているから、わたしもその記録を見ているのだ。彼らは一貫して、歓迎の態度を示してくれている。
「シヴァ、よく帰ってきたな。元気そうでよかった」
シレールと名乗った年上の従兄弟が、まず、シヴァを軽く抱いて背中を叩いてくれた。シヴァは、うう、とも、ああ、ともつかないうめきを洩らしただけ。
子供時代、勉強を教えてもらったという人なのだから、きちんと挨拶したらどうなのかしら。
こうやって不器用だから、誤解されるのよ。それがわたしには、可愛くてならないのだけれど。
それから、年下の従姉妹のダイナが――まるで無邪気な娘のようだけれど、既に二児の母で、《ティルス》を含む三都市を所有する組織の総帥だという――シヴァの両手を取って、上下にぶんぶん振る。
「シヴァ兄さま、お帰りなさい!! じかに会えて嬉しいわ!! 紅泉姉さまに繰り返し話を聞いていたから、ずっと会いたいと思っていたの!! さあ、来てちょうだい。みんな上で待っているから!!」
どうかすると、ぴょんぴょん跳ね上がりそうな歓迎ぶりだ。とても無邪気に愛らしく見えるけれど……辺境では、それが希有なことなのだとわかっている。途方もなく強くなくては、明るくなれない。
「きみがハニーだね。よろしく」
シレールがわたしと握手を交わし、その後でダイナが両手を広げ、ぎゅうと抱きついてきた。わたしより小柄なので、こちらが抱きとめる感じになる。
「ようこそ、よくいらっしゃいました。歓迎します。ハニーお姉さまって呼んでいいでしょう? あたしのことは、ダイナって呼んでくださいね!! これからは、妹と思って仲良くしてください!!」
こちらが戸惑ってしまうほど、開け広げで、親しげだ。本物の親しみなのか、社交上の演技なのか、まだわからない。わたしより十歳ほど年下になるので、姉扱いということになるらしい。
「ありがとう、ダイナさん。迎えていただいて、本当に嬉しいわ。感謝します」
シヴァの故郷とはいえ、およそ七十年も離れていたのだ。一族がどんな風に変わっているか、まだわからない。
案内されて階上に上がると、明るい玄関広間に出た。シヴァが子供時代を過ごした屋敷だ。階上への階段には古典絵画、二階と三階から玄関を見下ろせる回廊、左右に伸びる通路、背の高い扉。窓から見える中庭の薔薇は、色とりどりに咲き誇っている。
「食事の支度は、食堂にしてあるの。もうじき、みんな集まるわ。でもまず、シヴァ兄さまの部屋に行ってみたら? 懐かしいでしょ。昔のままに残してあるのよ」
ということで、三階にある部屋に上がってみた。シヴァが事件を起こして他の都市にやられるまで、ここで暮らしていたのだ。
当時の荷物が、そのままになっている。工具やバイクの部品、読み込んだ本(冒険物や歴史物、軍の戦闘マニュアルなどらしい)、わずかな衣類、文房具、チェス盤、トレーニング用品。歳月の経過はあっても、常に掃除され、きちんと管理されていたことがわかる。
「嘘だろ……」
シヴァは苦い顔だったけれど、わたしは安堵した。ここの人たちは、シヴァがいつか帰ってくるものと信じていたのだ。
「まあ、あなたの写真ね」
芝生に片膝をつき、ショーティの首を抱いている黒髪の少年の姿が、棚の上に飾ってある。ちょっと照れたような、むくれ気味の顔。今より短く刈られた髪。
「本当に、ここで暮らしていたのねえ」
子供の頃のシヴァがここにいたら、頭を撫でてあげたい。将来、わたしが愛してあげるから、すねなくていいのよ、と教えたい。
「来られてよかったわ。あなたの子供時代が、想像しやすくなったもの」
「想像しなくていい」
シヴァは照れてむっつり言うけれど、彼なりに感慨に浸っているのはわかった。古い工具を取り上げたり、書棚を眺めたりしているもの。
わたしもまた、劣等感に凝り固まって、頭でっかちで、ひねくれて、扱いにくい娘だった。両親や祖父母たちはさぞ、悩んでいたことだろう。ようやくこちらから連絡を取ることができて、本当によかった。
もし、わたしが普通に可愛い娘だったら、決して辺境へ出ることはなかった。醜かったから、そのことを気に病んでいたから、市民社会を捨て、シヴァに出会うことができたのだ。
あの頃のわたしを求めてくれたのは、マックスだけ。
今では、彼に感謝できる。
彼もまた、どこかで幸せでいてくれるといいのだけれど。
食堂に降りてから、一族の人々に紹介された。前の総帥夫妻、その補佐をしてきた同世代の人々。いずれも数百歳だというけれど、中年にしか見えない。長年、この違法都市を支えてきた人たちだ。
「よく、このこらえ性のない子の面倒を見てくれました。ありがとう」
というようなことを、口々に言われた。本当に歓迎されている……ように思える。彼らはシヴァがむっつりしていても、気にかけないようだ。彼は子供時代から、こういう態度だったのだろう。
「きみたちに子供がいるなんて、本当に素晴らしい」
とも言われた。次は是非、子供たちを連れてきてくれと。
「そうよ、うちの子たちと友達になれるわ」
とダイナが熱心に言う。
信じていいのかしら。
大丈夫なのかしら。
ここが子供たちの安全な基地になるのなら、どんなに素晴らしいか。
それからシレールのもう一人の妻、泉。黒髪に黒い目の落ち着いた美人で、中央から脱出してきたという。
シレールの子供たちは三人いた。ダイナが産んだ春と夏の双子、その下の梢は泉の子供。彼らはわたしたちに行儀よく挨拶した後、男女の家庭教師に連れられて帰宅した。シレールの屋敷は、同じ敷地内にあるという。といっても広大な土地なので、地下トンネルでの移動には、車が必要だとか。
栗色の髪をした、十二歳くらいの可愛い少年もいて、こちらは〝老化を止めた〟だけで、中身は大人だと説明された。このミカエルが、一族の研究・開発部門の責任者だという。
「ぼくはリリーさんに……つまり〝リリス〟に助けられて、市民社会から出てきたんです」
元は違法組織で作られたバイオロイドだと、話してくれた。
「最長老は……麗香さんは、後で少しだけ顔を出すそうです。近頃は、ぼくもあまり、お目にかかることがないんですよ」
一族を率いて地球から出てきたという神話的な人物は、最近では、ほとんど一族の前に姿を見せないらしい。シヴァの育ての親だと聞いていたから、今日は会えるものと期待していた。
「長く生きると、生きることに飽きるみたいですよ。ご自分の趣味の研究だけ、細々となさっているようです。その研究の中身は、ぼくにもわかりません」
このミカエルが、数世紀にわたる麗香さんの研究の成果を、かなり引き継いでいるという。けれど、ミカエルにも知らされない部分がまだあるようで、それは、
「どのくらい恐ろしいものか、想像がつきません」
という。
でも、その恐ろしさを吹き飛ばすくらい、〝リリス〟の二人は印象的だった。
「なんでもっと早く、連絡しないのよ!! みんな、心配してたんだからね!!」
紹介の順番が来るなり、シヴァのお腹に軽いパンチを入れたのは(親愛の表現であっても、シヴァは身を折り、いくらかよろめいた)、背の高い精悍な美女だ。
輝くような金褐色の髪に、青い瞳、よく通る声。
市民社会には〝リリス〟をモデルにした映画がたくさんあり、様々な女優がその役を演じてきたけれど、
(この人が、その大本なのね)
と納得できる、まばゆい存在だった。
コード名〝リリー〟は世界に知られているが、一族の間でだけ使う本当の名は紅泉。
彼女はシヴァの肩を掴んで揺さぶったり、背中をばしばし叩いたりして、思う存分、実在感を確かめている。
「いやあ、安心したわあ、よかった、よかった」
と、わたしまで抱きしめ、すりすりして歓迎してくれる。
服を通しても、体熱が感じられた。エネルギーに満ち溢れて、じっとしていられないような人。このパワーがあればこそ、世界の果てまで犯罪者を追い回すこともできるのだろう。
「シヴァと喧嘩したら、あたしに言えばいいよ。あいつの首を絞めてやるからね」
と笑ってわたしに言い、シヴァに〝大きなお世話だ〟という顔をさせている。
この人はたぶん、子供の頃から、ずっとこうだったのだろう。まっすぐで、てらいがない。怒る時は、きっと全力で怒る。
この人がいなかったら、きっと市民社会は、違法組織の脅威に対して、もっと打ちひしがれていたのではないかしら。
やはり、稀代の英雄なのだ。密かに抱えていたわたしの不安も、かなり薄らいだ。少なくとも、もう一人の従姉妹が、シヴァやわたしを害することは止めてくれるだろう。
その後ろにひっそりと立つ女性は、紹介されなくてもわかった。シヴァが片思いをしていた、その人だ。
〝リリス〟の片割れで、長く紅泉を補佐してきた人。コード名は〝ヴァイオレット〟、本当の名は探春。
美しいサーモンピンクのドレスを着て、長い茶色の髪を編み込みにしてまとめ、真珠のイヤリングとネックレスがよく似合い、春の妖精のように愛らしいけれど、金茶色の瞳には冷ややかな警戒の色しかない。
笑いを浮かべる途中で凍りついたような顔で、わたしに対して、
「初めまして。よくいらっしゃいました」
と言ったきり。他に、何もしゃべるつもりはないらしい。その分、紅泉やダイナが、シヴァをちやほやしているけれど。
とにかく後で、じっくり話をするつもりだった。
わたしたちが《ヴィーナス・タウン》の主宰者であること。〝連合〟との関係。今後の方針。
でも、とりあえずは、親戚としての関係を築くこと。それが、この訪問の最大の目的だ。歓迎されないようなら、余計なことは話さず、引き上げるつもりだったけれど。
ここまでは、うまくいっている。シヴァは、一族に待たれていたのだと納得できた。
「それから、一つ、打ち明けることがあるんだけど……ハニーには不愉快な話だと思うので、気分を害したら申し訳ない。でも、隠しておくわけにもいかなくて」
紅泉の遠慮がちな言い方で、わたしはぴんときた。
「もしかしたら、アスマンと梨莉香のことかしら? 二人はこちらにいると、母親のリナから聞いているわ」
紅泉は驚き、ほっとしたように肩の力を抜いた。
「知ってたのか!! ならよかった。あなたに泣かれるかと思った。今日は二人とも来てないけど、すぐ近くの小惑星にいるんだ。会いに行くなら、案内するから。いや、今日の集まりにも誘ったんだけど、来る気はないって言われてね」
やはり、反感を持たれているのだろう。シヴァが憮然として、打ち明けた。
「十年くらい前か。《フェンリル》のリナが泣きついてきて、初めてわかったんだ。俺の遺伝子を使った子供がいると。紅泉、おまえがアスマンを弟子にして、鍛えてくれたと聞いている。世話になったな……俺が言うのも変だが」
紅泉は苦笑し、肩をすくめつつ、手を広げてみせた。
「勝手に判断して悪かったけど、あの時点では、あんたは生死も不明だったからね。アスマンをあのまま暴れさせておいたら、成人前に死ぬと思ったから」
シヴァは、彼としては最大限、神妙な態度で答えた。
「申し訳なかった……世話をしてくれて、感謝する」
シヴァが会うつもりになれば、研究所を訪ねてきて構わないと、アスマンたちは言っているそうだ。
自分たちは、シヴァの意志に関係なく作られた子供だから、シヴァが責任を感じることはない。こちらはこちらで、幸せに暮らしているからと。
「寛大な子供たちね」
それでも、ここへ来ることは拒絶したのだ。母親に遠慮しているのか、父親に反感を持っているのか。きっと、その両方ではないか。
「まあ、クローンていうのは複雑な気分だろうしね。梨莉香の方は、お兄ちゃんがいれば、それで満足らしいし」
と紅泉は言う。
それでは、後で通話して、その様子で、訪問の約束を取り付ければいい。もし、シヴァがそれを望むなら、だけれど。
なまじ血がつながっているというのは、難しい。お互い、なかなか平静にはなれないだろう。今回は、伝言だけで引き下がった方がいいのかもしれない。《アヴァロン》に遊びに来てくれるなら、歓迎すると。
和やかな昼食会が終わると、仕事のある人々は、いったん引き上げていった。夕食の時に、また集まるという。残った者は温室に移動し、美しい花に囲まれながら、居心地のいいベンチで会話を続ける。
わたしはだいぶ、緊張がゆるんでいた。紅泉は、シヴァとの再会を心から喜んでくれている。ダイナはシヴァから放浪時代の話を聞きたがり、自分の仕事の話もしてくれる。
都市経営の苦労。
他組織との付き合い。
〝リリス〟に憧れ、市民社会で短期間だけ、護衛仕事をしたことも聞いた。その時、泉と知り合ったことも。
シヴァの顔からすると、その時に泉と接触したグリフィンは、もう二代目だったらしい。
グリフィンの仕事は、多くの人々の運命を左右したのだ。わたしたちは、現在のグリフィンについては、何も知らないけれど。
シヴァはシレールと、ぽつぽつ話をしている。無愛想な大男が、やけに神妙そうなのが可笑しかった。子供時代を知られている相手には、やはり大きな顔はできないのだ。
夕方になって、長い黒髪の女性が現れた。上品な濃紺のドレスを着て、首には真珠のネックレスを二重に巻いている。
姿は若いけれど、それでも四十歳以下に思われることはないだろう。数百年の歳月を生きてきた重みが、波立ちのない表情にも、ゆったりした挙措にも表れている。人類が明日、滅びるとわかっても、
『あら、そう』
で済ませることができそうな落ち着きだ。
「こちらが、麗香さんです」
とミカエルが改まって言う。
シヴァを育てた最長老。この一族を地球から導いてきたばかりか、本格的な人体強化や不老の技術も実用化したという。辺境の歴史の、生き証人のような人。
「シヴァ、久しぶりね。戻ってくれて、嬉しいわ」
彼女は長身のシヴァを見上げて言い、わたしには、真正面でにっこり微笑んで言う。
「ハニー、そう呼ばせてもらうわね。シヴァの伴侶なら、わたしには孫娘のようなものよ。これからは、ここを、あなたの家と思ってくださいね」
「ありがとうございます」
安心度が増した。この人の意思が、一族全体の行く末を左右するらしいから。
〝リリス〟が活躍してこられたのも、この人が一族に後援を命じてくれたからだ、と聞いている。
「こうしてあなたを迎えられて、とても嬉しいわ。シヴァが色々と困らせるでしょうけれど、許してやってちょうだいね。もうわかっていると思うけれど、言葉が足りない子なので」
シヴァは何も言わず、むっつりしたままだ。まだ、育ての親に対する反感が残っているらしい。
「麗香お姉さまと、呼ばせていただきますね」
あらかじめダイナに、それでよいと言われている。シヴァの伴侶なら、わたしも既に一族の一員なのだと。
本当にそう思ってもらえるのなら、有難い。うちの子供たちにとっては、大きな後ろ盾になる。
「お会いできて、本当に嬉しいと思っています。ここは本当に、シヴァの故郷なんですね」
「そうよ。これからは、あなたの里でもあるわ。何かあったら、頼ってくれていいのよ。何もなくても、遊びに来ればいいわ。アスマンたちとも、いずれは仲良くなれるでしょう」
よかった。麗香さんが底知れない人物なのは感じられるけれど、とりあえず、ここに足がかりができた。
「明日は、別の小惑星にある、わたしの屋敷にいらっしゃい。シヴァが小さい頃は、そこで育ったのよ。自分の腕力の調整ができるようになるまでね。わたしは用があるので、ミカエル、明日はあなたが案内してあげて。わたしの、地下の研究室もね。きっと、シヴァには興味があるでしょうから」
人間の肉体に宿った〝ぼく〟は数瞬、呼吸を忘れた。あの地下室を……シヴァに見せろというのか!?
真っ先に思ったことは、ただ一つ。
戦争を起こしたいのか、この人は。
隠居屋敷の地下室では、シヴァの愛した茜が冷凍にされたまま、もう何十年も時を過ごしている。
シヴァがそれを見て、真実を悟ったら、激怒するに違いない。
茜との出会いも別れも、全て麗香さんに演出されていたのだ。グリフィンに据えられたことも、その地位から追われたことも……
麗香さんにとって、自分以外の存在は、全て壮大な実験のための駒にすぎない。人間たちが泣こうが怒ろうが、周囲で羽虫が飛び回る程度のこと。
だが、シヴァが本気で怒ったら……親友のショーティすら、麗香さんの使い走りだったと知ったら……その怒りが、どれほどの破壊力を及ぼすか。
麗香さんは、シヴァを怒らせたいのか。
それが、超越体と人類との戦争にまで発展することを、望んでいるのか。
もし、麗香さんがそのつもりなら、ぼくが抵抗しても、無駄なことだろう。
せめて、超越体の仲間たちに知らせて、相談するしかない。
麗香さんの弟子として、ゆるい連携をとってはいるが、普段はそれぞれの意志で活動している。そして、何を大切に思うかが異なっている。
進化を続け、より高次の存在になりたい者。
純粋に、世界の謎を解き明かしたい者。
愛する人間を守りたい者。
人類の庇護者でありたい者。
だが、誰一人、ただの人間に(あるいは、ただの犬に)戻りたいとは思っていない。ぼく自身、生身の肉体のはかなさを思っただけで、身震いが生じるほどだ。進化できたことは、有難い。
ただ、人類との関わり方においては、まだ揺れ動いている。
対立が起きたら、ショーティはシヴァの味方をして、人類の側に立つかもしれない。マックスはハニーを守ろうとして、やはりそちらに立つかもしれない。ネピアやリエラは、ジュンとその仲間たちを守ろうとするかもしれない。アイリスのような新種族は、人類に怖れられることを嫌い、麗香さんの側に付くかもしれない。
だが、ぼくは……?
ぼくがあくまでも、リリーさんを守りたいと願うなら……そのために、力を保持しておきたいのなら……〝勝つ側〟に付くべきかもしれないのだ。
負けてしまえば、リリーさんと共に滅びることになる。
勝つ側にいれば、少なくとも、リリーさんだけを救うことはできるかもしれない。
リリーさんが、人間ではなくなったぼくを、どの程度信じてくれるかはわからないけれど。
これまで、麗香さんには人類を滅ぼす意図はない、と思っていた。人類にはまだ、進化の母胎としての価値があるからだ。
何百億という人間がいれば、その中には天才も異才も生まれる。切磋琢磨によって、新たな発明や発見もなしうる。
もし、麗香さんが人類の愚かさ、醜悪さに嫌気がさし、見切りをつけたのなら、とうに絶滅させているはず。
あるいは、自分は既に高みに在るのだから、停滞した種族など、わざわざ絶滅させる手間をかけるまでもない、というだけかもしれない。
だが、もしも進化の実験の一部として、人類に新たな試練を与えるつもりなら……そのために、超越体との戦争を経験させようというのなら……
自分は遠くへ引き下がり、ぼくらを前面に押し出して戦わせるだろう。自分が采配したら、戦争など一瞬で終結してしまうからだ。
そのために、ぼくたち若い超越体を育てたのか。
人類対超越体グループなら、勝敗は決まっている。
だが、ぼくたち若手の超越体が、人類の側と超越体の側に分かれれば、簡単には決着がつかなくなる。闘争が長引けば、そこから新たな変化が生じるかもしれない。麗香さんを喜ばせるような。
「わかりました……では、明日」
ミカエルの宿った肉体が、人間一同の前でそう答えた時、ぼくの一部は他の超越体に接触を図り、この出来事を伝えていた。
猶予は、明日の朝まで。
その時までに、ぼくらは態度を決めなければならないだろう。
今夜のうち、他の超越体から、ぼくの推測が間違っているという指摘が入ればいいのだが。

「ミカエル、あなたが案内してあげて。わたしの、地下の研究室もね」
黒髪の美女が、栗色の髪の美少年にそう言った時……異変が起きたことを、他の皆は悟らなかったかもしれない。
でも、あたしにはわかった。
怜悧なミカエルが、すぐに返事をせず、優に一秒以上、凍りついていたからだ。
ミカエルは、あたしに婚約解消を申し出た時でさえ、冷静だったのに。

何だろう? 何がそんなに、ミカエルを驚愕させ、あるいは恐怖させたのか?
あたしの知らない何かが、姉さまの研究室にある? そして姉さまは、それをシヴァに見せたいと思っている?
あたしや探春、ダイナやシレールにではなく、ようやく帰還してきたシヴァに?
麗香姉さまは、夕食会には参加せず、早々に自分の隠居屋敷へ引き上げた。せっかくの親睦の機会なのに、ずいぶんそっけない。
だが、まあ、それが〝俗世から去った〟人の、自然な在り方なのかもしれない。現役の人間たちの苦労や心配とは、距離を置きたいのだろう。
再び一族が集まった夕食会で、ハニーは重大な打ち明け話をした。
自分が《ヴィーナス・タウン》の主宰者であること。
シヴァはずっと、自分の良き守護者であったこと。
最高幹部会のリュクスとメリュジーヌが庇護者であり、そのおかげで順調に支店を増やしてこられたこと。
それでも一族の側は、ミカエルがナギに渡してくれた資料で予習できたから、ここで驚くことはなかった。
それでも、テーブルに満ちたため息は、
(よくも、あのシヴァが、こんな女性を射止めたもの)
という感嘆からだった。
「きちんとお話して頂いて、嬉しいです」
ダイナが一族を代表して、感謝を述べた。
「これまではわたしたち、過去の経験から色々と用心して、《アグライア》の改革や《ヴィーナス・タウン》の試みとは距離を置いていましたが、身内が関わっているとはっきりしたからには、前向きに協力できるのではないかと思います」
ハニーは自分が受け入れられたことを理解し、感謝の言葉を返してから、なおも真摯に言う。
「ただ、この先、わたしたちがいつまで庇護されるかは、予測がつきません。〝連合〟が何を利益と考えるかで、わたしたちの運命は変わってきます。もしもの時、わたしたちのせいで、こちらにご迷惑をかけることになるかもしれません」
「それは大丈夫です。わたしたちも、辺境に確実なことはないと承知しています」
とダイナ。
この《ティルス》と姉妹都市に《ヴィーナス・タウン》の支店はまだないが――シヴァが、故郷の三都市を避けていたからだろう――ダイナたちも、何人かの女性部下を《ヴィーナス・タウン》の顧客にさせて、様子はうかがっていたという。
「統括者としてのハニーお姉さまの評判は、聞いていました。お姿も承知していました。ただ、シヴァ兄さまと一緒に来る方が本当に同じ方なのか、それがはっきりしなかったので……」
「ごめんなさい。幾つかの支店には、わたしの影武者がいるので、紛らわしかったでしょうね」
「それはいいんです。当然の用心ですから。ハニーお姉さまからこうして打ち明けていただいて、理解が深まり、ほっとしました」
ダイナはすっかり、頼もしい総帥ぶりだ。もうじき四十歳に届くのだから、それで当然なのだが……あたしにはどうしても、子供時代のやんちゃな印象が強すぎて。
「わたしたちとしては、ハニーお姉さまの《ヴィーナス・タウン》と、ジュン・ヤザキ総督の《アグライア》が、辺境の新しい勢力になっていることを、望ましい変化だと思っています。わたしたちも長い年月、〝リリス〟の戦いを応援してきましたからね」
ダイナ自身はまだ若いので、これは、一族の総帥としての言葉だ。
「これまでは距離を置いて様子見をしていましたが、こうしてじかに会えたからには、今後は、三者で親しくお話できるのではないかしら」
ハニーは既に、ジュン・ヤザキと同盟している。ジュン・ヤザキは辺境にいても、軍や司法局から一定の信用を得ている。
そこに、うちの一族が加わるとしたら……これは、辺境の歴史の中でも大きな出来事だ。
三つの勢力が一つの陣営にまとまり、なおかつ市民社会からの支持も受けられるとすれば……今度こそ〝連合〟に対抗しうるかもしれない。
〝連合〟の陰に、謎めいた超越体がいるのなら、また別かもしれないが。
「もしも〝連合〟が方針を変えて、改革の動きを潰すことになるのなら、その時はこちらとしても、対処を考えることになるでしょう。戦う時は、一緒に戦うことになるのではないかしら」
ダイナは微笑んで、あたしを見る。
「それでいいですよね、紅泉姉さま?」
あたしも微笑み、シャンパンのグラスを持ち上げた。
「同盟に乾杯、だね」
シヴァとハニーは顔を見合わせ、深く安堵したように表情をゆるめた。
「ありがとうございます」
ハニーは声を震わせながら言い、シヴァもぼそりと付け加える。
「そう思ってもらえるなら、助かる……感謝する」
それでいい。個々に立ち向かっても敵わないのなら、こちらも同盟すればいいのだ。
夕食の後、シヴァとハニーは二階の客室に引き取り(屋敷内にあるシヴァの部屋は、二人で泊まるには向かなかったから)、ダイナたちも自分たちの屋敷へ引き上げた。大伯父や叔母たちも、それぞれセンタービルや、屋敷内にある自分の部屋に引き上げた。
ミカエルも桔梗屋敷へ帰ろうとしたが、あたしはそれを引き留めた。明日また会えるとはいえ、彼をこのまま一人にしたくはない。
探春はあたしの動きを見ていたが、何も言わずに自分の部屋へ引き上げた。あたしはミカエルを玄関脇の小部屋に連れ込み、壁に押しつけるようにして問い詰めた。
「夕方、姉さまに隠居屋敷の地下室を案内しろと言われた時、どうしてあんなに驚いたの? 何が、そんなに衝撃だったの?」
ミカエルは憂いを帯びた緑の目であたしを見上げたが、あたしが引かない構えなのを悟り、仕方なしのように微笑んだ。
「リリーさんには、隠せなかったんですね」
それはあたしが、いつもミカエルのことを気にかけているからだ。本当はもっと近くにいたいのに、たまにしか会えない。だから、会えた時には、なるべく長く見つめていたい。
「あたしは戦闘用強化体だからね。目はいいんだ」
ミカエルは視線を落とし、ぼそぼそと言う。
「ここへ来てから、リリーさんに言えないことが増えました。麗香さんの下で働くということは、それなりに、汚れ仕事を引き受けることでもあります」

その晩遅く、あたしは元の自分の部屋から出て、すぐ近くにある探春の部屋に行った。探春はまだ起きていて、微笑んで言う。
「ミカエルは、何も教えてくれなかったのね」
探春に隠し事はできない。あたしは子供時代のように、探春のベッドに座り、白状した。
「ミカエルがどんな重荷を抱えているのか、あたしにはわからないんだ。話してももらえない。姉さまの屋敷の地下に、何かあるらしいんだけど」
それからはっと気づいて、顔を上げた。
「ごめん。今日は、辛い一日だったよね」
探春はシヴァに会うことを心底厭がっていたのに、それは心の底にしまって、黙って同席してくれていた。ハニーに挨拶された時も、礼儀を守って受け答えしてくれた。
「疲れたでしょう。おいで」
あたしが腕を伸ばすと、探春はあたしの膝に横座りになった。薄いシルクの寝間着一枚だから、腕も脚もほとんどむきだしだ。そのなめらかな肌を、あたしはそっとさすり、細い躰を抱きしめ、前髪のかかる額にキスをする。
何が起きても、あたしにはこの従姉妹がいるのだ。
悩みは分け持ち、あたしが前の敵と戦う間、背後を守ってくれる。
ミカエルと出会うずっと前から、あたしの最大の味方であり、理解者だった。たぶんこの先も、ずっと側にいてくれる。
「色々と、神経が行き届かなくて、ごめん」
今日は、シヴァに再会できたことが嬉しくて、つい、はしゃいでしまったと思う。
「いいのよ。あなたに悪気がないこと、わかっているもの。ただ、迂闊なだけ」
探春がからかう口調なので、ほっとした。
シヴァにも今では、立派な伴侶がいる。大昔の失恋のことなど、もう薄れているだろう。
それよりも、明日だ。
ミカエルは、シヴァに何を見せるつもりなのだろう?
明け方、あたしが探春のベッドで目を覚ました時、探春は横にいなかった。トイレにでも起きたのかと思ったが、違った。浴室にも、クローゼットの中にもいない。
胸騒ぎがして、屋敷内で探春の位置を捜したら、地下室にいるという表示が出た。まだ暗いというのに、そんな所で何を!? あたしは毎朝、早起きして運動するのが普通だが、探春はいつも、あたしより二時間は余計に眠るのではないか。
階段を降りて、地下の貯蔵室に向かった。ワインや酒類の貯蔵室ではなく、食器や花瓶などの倉庫だ。
厚い扉を開いてみたら……派手な音がして、繊細な磁器が壁で砕け散ったところだった。既に床には、陶磁器の残骸が積み上がっている。薄い寝巻姿の探春は、壁一面の棚に並べてあった皿や茶碗を……あたり構わず、引き出しては、投げて叩き壊していた。黙って、しなければならない業務のように、荒い息をつきながら。
我慢が破裂したのだ、と思った。
自分自身が壊れないように、ものを壊してやり過ごそうとしている。
だったら、好きなだけ、させておくしかない。昨日はみんなして、探春の苦痛を見てみないふりしていたのだ。
表面上の平和を強いて、探春を窒息させようとしていた、と言ってもいい。探春の魂を。
探春は振り向いてあたしを見たが、破壊の動作は止めなかった。ティーカップを取り上げ、棚に投げつける。カップは他のカップを巻き添えにして、あたりに飛び散る。お祖母さまが大事にしていた本物のアンティークも混じっているはずだが(数百年前に地球から運んできた無傷の品には、天文学的な値段がつくはずだ)、仕方ない。品物など、いくらでも複製できる。
あたしは戸口に寄りかかり、黙って待つことにした。それしかできない。探春は広い貯蔵室の奥の方で、無事な皿を持ち上げては、投げて砕いた。ガラスの花瓶も、陶器の抹茶碗も、クリスタルのグラスも。入口に近いあたりから始めて、だんだん奥へ移動していったものらしい。
怪我さえしないでくれれば……いや、破片で怪我をしても、魂の呼吸の方が大事だ。
やがてとうとう、探春は疲れて壁にもたれた。足元は破片だらけなので、座る場所もない。
あたしは自分が怪我をしないよう、踏む場所を選びながら、ゆっくり探春に近づいた。そっと腕を差し出すと、崩れるようにあたしにもたれてくる。サンダルを履いただけの素足には、幾筋かの傷がついて、血が流れていた。
「手当てしよう」
あたしは探春を抱き上げ、スポーツシューズの足先で破片をよけながら、そろそろと貯蔵室から出た。通路には灰色の皮膚をしたアンドロイド侍女がいたので、
「片付けておいて」
と言い残して、部屋に戻る。屋敷の管理システムも、物品の破壊だけなら、止める必要はないと判断したのだろう。あるいは、お祖母さまかお祖父さまに報告が行き、放置するよう指示が出されたのかもしれないが。
幸い、客人たちはまだ起きていなかったから、一階にある医療室に行き着くまで、邪魔されることはなかった。傷口にかけらが食い込んでいないか調べてから、消毒して保護シールを貼る。
「ごめんね」
医療ベッドの端に腰かけてあたしが言うと、ベッドの上で足を伸ばしている探春は、静かに返してくる。
「あなたがなぜ、謝るの」

違法都市《ティルス》は、安定した恒星を巡る軌道上に存在する小惑星内部に建設されている。その周囲には、似たような周期で公転する幾つもの〝兄弟〟小惑星が存在する。相互の距離が開きすぎたら、ちょっと押しをくれて修正すればいい。
工業生産を行うもの、農地や牧場を抱えるもの、非常用の避難場所として用意されているもの。
防衛艦隊の基地になる小惑星もあり、いざという時には、ここが防衛戦争の中核になる。まあ、そんな時が来たら、《ティルス》を捨てて逃亡した方が早いかもしれないが。
そして、そういう小惑星の一つが、麗香姉さまの隠居場所になっている。
あたしたちは《ティルス》の防衛艦隊の船でそこへ向かい、待っていたミカエルと、秘書のセイラに迎えられた。
気密桟橋から車に乗って、広大な緑の中を、麗香姉さまの屋敷へ向かう。エアロダインに乗ればはるかに早いが、景色を楽しむには、地上を進む方がいい。
ポピーやアネモネ、パンジー、フリージア、ヒヤシンス、チューリップに撫子、たくさんの花が乱れ咲く野原、丘の麓を巡ってゆるやかに流れる川、遠くにきらめく湖。
何十万人もが暮らせる大空間に、住人は三人きりという贅沢。
しかも最近では、麗香姉さまは留守にしていることが多く、ミカエルやセイラでも、行く先は知らないという。
「昨日は、《ティルス》から直接、どこかへ行かれたようで、屋敷には戻っておられません。いつお戻りかも、わかりません。こちらから、麗香さまの予定をお尋ねすることはできませんので」
と紺のドレスのセイラが言う。
既にミカエルが、ここの主のようなものらしい。
あたしと探春には、子供の頃から繰り返し遊びに来ている場所だが、特にシヴァはここで幼年時代を過ごしている。車から野原や森を眺め、
「あの木が、まだあるんだな」
とか、
「丸木橋が、新しくなってる」
などとつぶやいては、上品な水色のドレスのハニーを微笑ませていた。昨日は濃紺のスーツで、今日はもう少しくだけた、青いジャケット姿――シヴァの服装が洗練されているのは、このハニーのおかげだろう。
「あなたの故郷なのね。見られて嬉しいわ」
彼女が心からシヴァを愛し、信頼していることがわかって、あたしも嬉しかった。まあ、これから何が起こるかは別として。
姉さまの屋敷は相変わらず、甘い香りのする薔薇の庭園に囲まれていた。ピンク、赤、薄紫、オレンジ、白、黄色。
ハンター稼業の合間に、よくここを訪れて、愚痴を聞いてもらったり、助言を受けたりしたものだ。
ここが、姉さまの永遠の安息所だと思っていたのに。
姉さまは、一族からも遠ざかって、何をしているのだろう?
せっかく不老長寿を得たのに、まさか、人生を終わらせたいわけではないだろう? それとも何か、新しい挑戦をしているのか? 不穏すぎて、あたしたちには打ち明けられないような?
「まずは、お茶をどうぞ」
セイラが用意してくれたテラス席で、薔薇の香りに包まれながら、抹茶と和菓子を楽しんだ。ハニーはあたしたちにあれこれ質問しては、シヴァの子供時代の思い出を引き出している。
愛犬のショーティと駆け回ったこと、森で焚火をして火事になりかけたこと、川で魚を獲り、石を投げて兎を仕留めたこと。菜園から掘り出したさつま芋を、焚火で焼いたこと。
淡いレモン色のドレスの探春は、セイラとハニーには普通に口をきいたが、シヴァに向かっては何も言わなかった。シヴァも決して、探春に話しかけることはない。会話は常に、他の誰かによってつながれる。
探春さえ耐えられるのだったら、これで構わないだろう。過去の事件など、知らん顔して、埋めてしまえばいいのだ。長い年月が流れて、それぞれ別の人生を確立してきたのだから。
シヴァだって、ハニーがいる今、新たな過ちは繰り返さないだろう。むしろ、その事件を心に刻んだからこそ、シヴァはハニーに愛される男になったのかもしれない……結果が良ければ、全て良し、だ。
「よくショーティと川で泳いで、その後は焚火をしたんだ。そのまま野宿することも、よくあった」
シヴァの口がほぐれてきたので、あたしも嬉しい。今日は白と黒のモノトーンのドレスを着て、大粒の黒真珠のネックレスをつけてきた。シヴァはあたしのお洒落なんか気にも留めないだろうが、ミカエルはいつも褒めてくれるから。
「あたしがショーティを連れ出して遊んでいると、あんたに怒られたわね。俺の犬を、勝手に連れていくなって」
あたしが笑うと、シヴァも苦笑いしたが、横でハニーがわずかに……困ったような顔をしている。これは何だろう?
「みなさん、そろそろ地下へ降りてみましょうか」
白いブラウス姿のミカエルが言って、椅子から立った。
問題の、地下の研究室か。
少女時代、何度か入らせてもらったことはある。昔の実験体が冷凍保存されていた。悪趣味な怪物、哀れな奇形、初期のバイオロイド。生かして野放しにするには危険すぎて、あるいは悲しすぎて、凍結するしかなかったと聞いている。
あたしには、それほど面白い場所ではなかった。実際にはもっと奥があり、あたしが見たのは、ごく一部に過ぎないのだろうが。
地下に降りたのは探春とあたし、ハニーとシヴァ、それに案内役のミカエルだけ。
ダイナやシレールたちは仕事があるし、お祖母さまたちは子守りだから、来なかった。セイラも日常の雑用があるからと、地上に留まった。
「ここは、麗香さんの個人的な研究施設です。都市経営から引退なさってから、ここで趣味的な研究をなさっていました」
とミカエルが言う。今ではここの管理も、ミカエルに任されているという。
あたしはここなら安心だと思って、ミカエルを姉さまに預けたのだ。その結果、ミカエルは脳腫瘍も完治して、姉さまの助手に落ち着いたけれど……
ここで本当に良かったのか、どうか。
違法都市の管理機構の一員として、ミカエルの知的能力を活かせるのはいいが、重い責任を負わせすぎたのではないだろうか。
ミカエルにはちゃんとした子供時代がなかったのだから、本当なら、もっと気楽な生活を楽しませ、その上で決心させるべきだったのでは。
もっとも今のミカエルは、一族にとって必要不可欠な存在になっている。やり直すことはできない。
「これは全部、人体改造の研究の成果……?」
冷凍保存のカプセルが並ぶ、ひんやりした部屋に入ると、ハニーが気味悪そうにあたりを見回した。無理もない。悪趣味なお化け屋敷のようなものだ。
空を飛べる鳥人。
水中生活に適応した半魚人。
何本もの触手を持つ軟体生物。
人間の形をしていない、悪夢の怪物のような生き物なのに、心は人間に近いという者もいる。彼らは矛盾に耐えきれず、自殺を図ったり、発狂したりしたという。
非道は確かだ。中央の市民たちが見たら、決して許してくれないだろう。
それでも、現在の人間を超える生き物を造ろうと、姉さまは何百年も研究してきた。
改造や育成に成功した者、つまり人間社会に適応できる者は、ここから外界に放たれたはずだから、冷凍カプセルに封じられたのは、精神が壊れた者、人間にとって危険な者ばかりのはず。
あたしたち一族は、その研究の上澄みから生まれている。これだけの犠牲がなかったら、あたしたちも生まれなかった。だから、あたしに姉さまを非難することはできない。
市民社会から石を投げられるとしたら、甘んじて受けるしかないだろう。
「さすがに小さい頃は、ここに入ることは禁止されていたよ。見学の許可を得られたのは、十代半ばになってからだ。あれからまた、怪物が増えたのか?」
シヴァはそう言い、ミカエルが説明して歩く後ろから、左右を眺めてついていく。
「失敗したバイオロイドも多かったのですよ。戦闘力を強化しようとして、殺戮狂になってしまった者とか。知能を高めようとして、発狂してしまった者とか。バランスのとれた強化は、難しかったようです」
そして姉さまは、シレールとダイナに言ったそうだ。人間を強化することは、もう限界に来ている。だからあなた方は、自然に子供を作りなさいと。
そのおかげで、ダイナは自然妊娠し、元気な子供たちを産むことができた。シレールと泉の子供だけは、強化体と普通人の子供になるため、姉さまが多少の遺伝子操作をして安定を図ったそうだけれど。
あたしだって、今の自分に満足している。強健で、知能もまずまずだ。
これ以上を望むなら、おそらく、人間であることを捨てなければならないだろう。
まだ、そこまで欲張るつもりはない。これから数百年生きれば、どうなるかわからないけれど……
ふと、シヴァの足が止まった。
けげんそうに、カプセルの一つを見下ろしている。
中にいるのは、人間型の実験体のようだ。内殻の奥で保存液に浸されているので、顔立ちははっきり見えないが、普通の若い女に思える。たぶん、何らかの改造処置に失敗したのだろう。
シヴァはそのカプセルの前から離れず、角度を変えては中を覗き込んでいたが、やがて、崩れるようにして床に膝をついた。
低くうめいてカプセルの外殻にすがりつき、何かの激情に身を震わせる。台座には小さなプレートが貼ってあり、そこに簡単な説明書きがあるようだ。
あたしも探春も、驚いてシヴァの背中を見守った。
深い悲しみと後悔、そして、溶岩のように噴き出す怒り。それが、彼を感情の間欠泉のように震わせている。
これか。
姉さまが、ミカエルに見せろと要求したものは。
ハニーが両手を顔に当て、目を閉じて背中を向けた。もしや、シヴァの昔の恋人なのか。
彼女が死んだと思ったか、それとも行方不明になったかして、何年も苦しんだ後で、シヴァはハニーと出会った……そんなところか。
しかし、その女がなぜ、この地下室に。
姉さまが、その件にどう関わったというのだ!?
「ショーティ、あなたも来ていたの!?」
ハニーが発した言葉で、あたしは振り向いた。
子供の頃に遊んだのとよく似た大型犬が、カプセルの間の通路に現れ、太い尻尾を振りながらやってくる。ふさふさの毛皮をまとった、寒冷地のソリ犬の子孫。
《ティルス》の屋敷には常に、ドーベルマンやシェパード、ロットワイラーのような精悍な警備犬がいたが、これは攻撃用の番犬とは違う。シヴァが子供時代に飼っていた犬にそっくりだ。
「クローンなの?」
あたしがそう言ったのは、シヴァが愛犬の細胞から、新しい犬を造ったのかと思ったからだ。男というのは寂しがりだから、そのくらい、おセンチなことをしかねない。
「いや、きみと遊んだショーティそのもの、だよ」
驚いたことに、犬がしゃべった。少しくぐもってはいるけれど、十分に聞き取れる声で。
すると、シヴァが愛犬を改造したのか?
「わたしが老衰死する前に、シヴァが凍結保存してくれた。そして、後からサイボーグ化と知能強化をしてくれ、復活させてくれた」
呆れた。究極のおセンチだ。
家出して、犬しか友達がいなかった時期が、長かったとみえる。
しかし、シヴァが血相を変えて犬に向き直った。
「ショーティ、きさま、これを知ってたのか!? 知っていて黙っていたのか!? これが本物なんだな!? 茜はすり替えられていたんだな!?」
そして、犬を蹴り殺しかねない勢いで前に出たが、ハニーが両手を広げて立ち塞がった。
「待って、落ち着いてちょうだい」
ハニーは顔に苦悩といたわりを浮かべていたが、それでも冷静だった。
「その人が、茜なのね。本物の茜なんでしょう。あなたが話してくれたこと、忘れていないわ」
既に夫婦になって何年も経つ、子供たちもいるという自信があるのだろう。過去の女が甦ったとしても、自分たちの今の幸福が破壊されることはないという確信を持っているようだ。
「この人がいれば、わたしと出会うことも……いえ、出会ったとしても、わたしを愛してはくれなかったわね。あなたはシレールさんと違って、女を何人も抱え込めるような人じゃないもの」
シヴァはかろうじて立ち止まり、肩を上下させて荒い息をした。怒っていようが悲しんでいようが、自分の激情をそのままハニーにぶつけてはいけないと、自制が働くらしい。
「いや、これもまた罠なのかもしれない。もし、俺を操りたい奴がいるのなら……俺の弱点は、茜とおまえ、子供たちくらいだ」
あたしと探春は、もう、そうではないのだろう。ちょっと寂しいが、仕方ない。シヴァの人生だ。
「ショーティ、あなたは何か、このことと関係あるの?」
ハニーは犬の横に膝をつき、両腕で太い首を抱いて話しかけた。その姿勢なら、シヴァが犬を蹴り殺すことはできないからだ。そんなことをしようとしたら、ハニーにまで大怪我をさせてしまう。
すると、犬は訥々と語る。
「わたしが真実に気づいたのは、茜を失って何年も経ってからだ。初恋の探春にそっくりの娘が、着物姿でシヴァの前に現れるという偶然が、本当に偶然かどうか確かめたくなった。茜の遺品を整理している時にね」
探春そっくり?
あたしはちらと、従姉妹に視線を走らせた。探春はあたしの斜め後ろで、唇をきゅっと結んだまま、立ち尽くしている。
シヴァが探春に執着していたことを知っているのは……一族の者だけのはず。それとも〝連合〟か?
「きみたちの出会いの場所で、周辺の娼館を調査したら、記録があった。その時期、同じ型のバイオロイドが、どの店にも配属されていたのだよ。しかも、着物を着るよう指示されて」
この娘は、娼館用のバイオロイドだったのか。でも、なぜ着物?
探春は少女の頃、一族の集いがあると、よく麗香姉さまに着物を着せてもらっていた。シヴァの、その記憶を利用しようとしたのか。
「つまり、シヴァが気紛れでどの店に立ち寄っても、似たような出会いが起こるように仕組まれていた。あの都市で会えなければ、他の都市で会うことになっていただろう」
探春に似た娘なら、シヴァを惹きつけられる、という意味か。
「そんなことを、わざわざ仕掛ける者がいるとしたら……きみのことをよく知る誰かだろうとは思ったよ」
つまり、麗香姉さまが?
「なんでわざわざ、そんなことを?」
あたしの疑問に、ミカエルが答えた。
「シヴァを刺激し、彼に動機を与えるためですよ」
「動機?」
ミカエルは知っているらしい。何もかも。
「家出したシヴァは、そこそこの成功が得られたことに満足してしまい、進歩を止めていた。なまじショーティが有能な相棒だっただけに、本人は、すっかりたるんでいたんです」
シヴァは苦い顔をしたが、否定しなかった。
姉さまは、どこまでミカエルを支配しているのだろう? ミカエルに、どこまでの責任を負わせているのだ?
「麗香さんとしては、せっかく育てたシヴァを、そんなチンピラで終わらせるつもりはなかった……愛する者を与えれば、意欲が出る。その愛を失えば、きっと復讐心が……」
シヴァが前に飛び出して、ミカエルの襟元を掴み上げようとしたのを、あたしがかろうじて止めた。手刀でシヴァの手を払い、ミカエルを背中にかばう。
「まだ治ってないのか、その幼稚さは!!」
あたしは低い声で、長身の従兄弟を怒鳴りつけた。本当は彼の方が強いが、それでもあたしに本気の暴力を向けるほど、トチ狂ってはいないだろう。
「話を聞く間くらい、じっとしてろ!! ミカエルに当たってどうする!! ミカエルこそ、姉さまに利用されてるだけなんだから!!」
そのはずだ。
昨夜のミカエルの動揺を、あたしは見ている。
シヴァは怒りで身を震わせたが、さすがに、あたしに殴りかかることはしなかった。もっとも、それをしたら、屋敷の警備システムが彼を止めるだろう。レーザーで手足を切断してでも。
「その小僧は、何なんだ!!」
と苛立つシヴァに、あえて冷淡に言った。
「説明したでしょ。ミカエルは、あたしが姉さまに預けたの。脳腫瘍を治してもらうためにね。ミカエルが、あんたを嵌めたわけじゃないよ。今はただ、姉さまの代弁をしているだけなんだから」
「あの女に、取り込まれているんだな」
やれやれだ。
昨日は穏やかに再会できて、溝が埋まったと思っていたのに。
「説明なら、あたしも聞きたい。ミカエル、何がどうなっているのか、わかるように話してくれるでしょ」
それがあたしを怒らせる話であっても、ミカエルは、話すつもりでこの場に臨んでいるはずだ。
やはり彼は、静かに言う。
「話しますよ。まず、上に戻りましょう。茜は何十年も眠っていたのだから、あと二、三時間待ってもらっても、変わりはないでしょう」
その言葉には、ハニーがいくらか不安の色を浮かべた。彼女にとっては、シヴァの愛情を奪い合うライバルということになる。
でも、ダイナと泉が一人の男を分け合っているように、ハニーと茜がシヴァをはさんで共存することもできるだろう。
あたしの場合は、探春とミカエルを両方抱えることは、できなかったけれど。
薔薇の花園を見渡す明るいテラスに戻ると、地下のカプセルの群れが悪夢だったような気がする。桃の香りに似た、甘い芳香に包まれると、いくらか気持ちが和らぐ。
でも、シヴァはすっかり凶悪な顔つきになっていて、セイラが一同にお茶を注いで廻る間さえ、苛立ちを隠せないでいる。
セイラは事情を理解しているようで、テーブルをセットして、静かに引き下がった。かつては可憐な少女だったが、今は妖艶とすらいえる美女になって、この屋敷を切り回している。
彼女がミカエルを愛していることは明らかだが、だからといって、あたしとセイラが反目しあうことはない。ミカエルは、あたしたちのどちらに対しても、一定の距離を置いているからだ。寂しくて辛いのは、あたしよりもセイラの方だろう。
「ショーティとミカエルは、前からお互いを知っていたのね?」
と切り出したのは、探春だ。
少年と犬は、静かに同意した。
「ぼくたちはどちらも、麗香さんの弟子のようなものですから。ショーティが兄弟子ですね」
「まあ、仕事仲間のようなものだ」
「ちょっと待て」
険悪に遮ったのは、シヴァだ。
「ショーティ、おまえ、いつからあの女の手下なんだ!?」
あの女、ときた。
他の場合なら、シヴァの言葉遣いを咎めるところだが、今はさすがに、やむを得ないとあたしも思う。
姉さまやミカエルは、あたしたちに秘密を持ちすぎている。悪意からではなくても、あまりに水臭いではないか。
大型犬は風の通るテラスに寝そべったまま、ゆるやかに太い尻尾を動かしている。
「いつかは言わなければと思っていた。いま話すのがいいだろう。わたしはそもそも、最長老の作品なのだ」
ショーティの言葉に、シヴァが、不意を突かれた顔をする。
「作品……?」
そうなのかもしれない。一族の第二世代以下は、全て麗香姉さまの作品のようなものだから。姉さまがシヴァに与えたペットにも、何らかの〝処置〟がしてあって不思議ではない。そもそも辺境では、警備犬の知能強化くらい当たり前だ。さすがに、しゃべる犬は珍しいが。
「シヴァ、きみがわたしを老衰死から救い、サイボーグ化してくれ、知能強化してくれた。それは事実だ。深く感謝している。だが、きみの知識や技術では、精々、賢い警備犬になる程度のものだったろう」
シヴァは屈辱で顔を歪めたが、自分でも納得したのだろう、無駄な反論はしなかった。ショーティは続けて言う。
「わたしが人間を超える知能を持てるように、最長老が、こっそり手を加えてくれていた。それは、わたしも後から悟ったことだ」
麗香姉さまは、シヴァが家出しても生きていけるように、ショーティという贈り物に、更なる武器を与えたわけか。
まあ、シヴァが盗んだ船は一族のものだから、姉さまが追尾し、管理システムに干渉することは、難しくなかったはず。
姉さまは長年、あえてシヴァを泳がせていたのだろう。あたしたちを、市民社会に放ったように。
「シヴァ、きみが最高幹部会に捕まった時、わたしは悟ったよ。自分で超越化に成功したと思っていたのは、とんでもない自惚れだったと。わたしは、うまく導かれていたのだ」
超越化?
え?
この犬が……ショーティが……ただの知能強化だけでなく……生物の限界を超えた存在になっているというの!? 人間ですら、超越化は滅多に成功しないと言われているのに?
しかも、姉さまの〝作品〟だというのなら!?
はっとして、あたしはミカエルを見た。
まさか。
そんな。
ミカエルまでが、姉さまの手で!?
でも。
それなら、わかる。ミカエルが、あたしとの婚約を解消した理由が。
自分が人間でなくなるのなら、もはや、人間との恋愛など無理だと考えたのだろう。そのふりをすることすら、不毛で不実だと。
ミカエルが、寂しい色を湛えた緑の瞳であたしを見返した。その目だけで、あたしにはわかってしまう。
こうなったことを、ミカエルも悲しんでいるのだと。そして今では、その運命を受け入れているのだと。
手を伸ばせば、届く距離にいるのに。
あたしとミカエルは、深い大河に隔てられたようなもの。
もう、とっくに運命は分かれていたのだ。
恐ろしくて震えがきたし、自分の甘さに腹も立ったが、隣にいる探春が、そっとあたしの腕に触れてきた。理解と同情を示すために。
だけどあたしは、自分の動揺だけで手一杯で、そのいたわりに答える余裕がない。
何もかも、姉さまが。
最初から、全て計画して、あたしたちを駒にしていた。
そんなことって。
それじゃ、あたしたちの自由意志は!?
それとも、そんなもの、あると思うのが間違いなのか!?
「最高幹部会は、シヴァを初代のグリフィンに据えました」
とミカエルが口を開いた。
話が飛んで、あたしは戸惑う。
いま、何て言ったの?
「もちろん、シヴァ自身の努力はありましたが、ショーティをお守り役にすることで、シヴァは大きな失敗なく、四分の一世紀、その任務を続けられたんです」
四分の一世紀……シヴァが、グリフィンだった!?
訳がわからない。でも、ハニーは静かに聞いている。とうに知っているのだ、その部分は。
「高額の懸賞金をかけて〝リリス〟を有名にし、市民社会の英雄に祭り上げることが、グリフィンの役目でした」
あ。
霧の海に光が射して、新しい風景が立ち上がる。
これまでばらばらだった断片が、一本の糸で貫かれ、ネックレスのようにつながっていく。
「それによって、市民社会に光明がもたらされるからです。違法組織が強大であればあるほど、市民たちが希望を持ち続けるために、辺境の悪党どもを恐れさせる存在が必要だった……」
それが、あたしたち。
悪党狩りのハンター〝リリス〟。
ミカエルの言う通りなら、あたしと探春は、スポットライトを当てられるために、舞台に上がらされたのだ。見えない演出家の手で。
「あたしが少女時代、いくらチンピラ退治をしても、麗香姉さまに叱られなかったのは……お祖母さまにはこってり叱られたけれど……そういう役目を果たすためだったの!?」
あたしが尋ねると、ミカエルははっきり頷いた。
「そうです。全て、麗香さんの指図によるものです。お祖母さまから叱られたことで、リリーさんは却ってやる気を起こしたでしょう?」
その通りだ。
もし、チンピラ退治を奨励されていたら、それこそ、うんざりして、やる気を失くしていただろう。
あたしはとにかく、反逆したくてたまらない子供だった。あたしのエネルギーの行く先は、姉さまに誘導されていたのか。
演出された〝正義の味方〟……
「リリーさんたちは知らないことでしたが、そもそも〝連合〟の最高幹部会というのは、麗香さんが世間から身を隠すための盾にすぎないのです。〝連合〟の大物幹部たちは大抵、麗香さんが選んで、育てた者ですから」
「ちょっと待って」
あたしは片手を上げた。
ここらで少し、整理させてほしい。
あたしが信じていた世界の区分けは……上辺の化粧に過ぎなかったのだと、ようやく、わかり始めている。
騙されていた怒りや恨み、無力感はあるけれど、それよりまず、謎を解明したい意欲の方が先に立つ。
ミカエルがここで何もかも暴露し、説明し始めたということには、意味があるのだ。
「ミカエル、あたし、よくわからないんだけど、最高幹部会の黒幕が、麗香姉さまだっていうことなの……?」
あたしたちが最大の敵だと思ってきた〝連合〟の後ろに、姉さまがいた……?
ミカエルが眉を曇らせ、気の毒そうに言う。
「リリーさん、ここが〝連合〟の最奥なんですよ。奥の院、とでも言いますか。だから今日まで、リリーさんたちは生き延びてこられたんです」
この屋敷が。
この屋敷を含む、違法都市《ティルス》の領宙が。
ここにいて、姉さまは辺境の宇宙を支配していたというのか。
いや、人類の居住圏全体を。
「貴女の一族は、六大組織に匹敵する、というか、六大組織の上に位置する、辺境で最初の大組織なんです。他の構造は、全て後から付け加えられたものです。麗香さんの構想でね。〝リリス〟もまた、麗香さんの持ち駒の一つなんですよ」
あたしは周囲の、美しい庭園を眺めた。薔薇の花園の向こうには、桜や楓や椿の木立、山吹やライラックやジャスミンの茂みが見える。更に遠くでは、ミカエルの桔梗屋敷が緑に埋もれている。
ここが〝連合〟の真の本拠地なら、あたしたちは、姉さまの望む役を演じるために育てられた役者なのか……
「お釈迦さまの掌の、孫悟空ね」
と冷ややかに言ったのは、探春だ。
探春も、静かに怒っている。あたしたちのこれまでの戦いが、筋書きに沿って演出された芝居だったと知って。
でも、あたしたちは知らなかった。いつでも本気で戦っていた。かろうじて死を免れたことも、少なくない。何から何まで脚本通りなんて、ありえない……それとも、超越体なら、それができるのか!?
「それなら、色々なことが説明できるわ。わたし、自分たちが、幸運だけで暗殺から逃れてこられたとは思えなかったもの……紅泉なんか、自分の正体を宣伝して歩いてきたようなものだから。あれで生き延びてこられたなんて、その方が不思議なのよ」
ええと。
つまり。
どういうことになるんだろ。あたしは頭が悪い。まだ混乱している。これからは、何が変わるのだ!?
ちょっと戻ろう。シヴァがグリフィンという話まで。
「グリフィンは、あたしたちの首に懸賞金をかけながら、同時に、あたしたちが生き延びられるよう配慮してきた……?」
あたしがシヴァを見ると、彼は苦い顔で言い訳した。
「俺は、好きでグリフィンになったわけじゃない。最高幹部会に捕まって、強要されたんだ。俺が引き受けなければ、他に誰が、そんなに真剣におまえたちを守れたか……」
探春を愛したシヴァだから、か。
彼もまた、望まない役で舞台に上がらされたらしい。
「初代のグリフィンって言った?」
グリフィンは今も活動し、懸賞金リストを更新し続けている。二代目、三代目がいるということか。
「シヴァの後釜は、ぼくです」
片手を上げて、遠慮がちにそう言ったのは、ミカエルだ。申し訳なさそうに、でも、平静に。
「ぼくが、グリフィン役を引き継ぎました。断る選択肢など、ありませんでしたから。他の誰が、リリーさんを守るために、休みない監視役を引き受けるでしょうか」
あたしは改めて、ミカエルを見た。
さらさらの髪をした、緑の目の美少年。
その頭脳は天才級で、心にはあたしへの愛情がある。
そして、姉さまの弟子。ショーティと同じ超越体。
この世界は既に、彼らの管理下にある。
「そういうことか……」
地面に沈み込むような、重い脱力感が染みてきた。
ずっと守られていたんだ、あたし。
ミカエルは、あたしに何も言わないまま、陰の役目を果たしていた。
もはや、恋愛感情なんかなくて当然だ。ミカエルは、あたしなんかよりはるかに高い所へ昇ってしまった。天使になってしまったようなものだ。あたしの守護天使。
けれど、天使は神の戦士でもある。神の命令次第で、人間を滅ぼすこともする。ミカエルは最終的には、麗香姉さまの意図に従い、人類の敵になるのか!?
それとも姉さまは、あくまでも人類を守り育ててくれるつもりなのか!? こうやってミカエルやショーティに告白させているのは、あたしたちをより内側に取り込むため!?
「おまえが俺の後釜だと!?」
シヴァは露骨に不機嫌な顔だ。そのことは、知らなかったのか。
「俺はショーティの補佐があって、かろうじて務められていたんだ。おまえが一人で負えるような仕事じゃない」
「ミカエルは天才なのよ。普通人より、はるかに優秀なの」
初めて探春が、シヴァの言葉に直接、反論した。シヴァは驚いて、息を呑む。あたしもまた、探春が、壁を破ったことに気がついた。自分を守るための壁。男を軽蔑し、自分の世界から締め出すための境界線。
「それに、ミカエルは、どこかの時点で超越化しているわ。あなたのショーティと同じようにね」
探春の指摘で、シヴァもハニーも、まじまじ美少年を見つめた。ミカエルは困ったように苦笑する。
「ぼくはショーティから、色々と教わりましたよ。超越化の先輩ですからね。ぼくがグリフィンの職務に馴染むまで、ずっと面倒を見てもらったんです」
シヴァは息を吐き、天を仰ぐ。
あたしも天を仰ぎたい。あたしの見てきた世界は、真実の世界ではなかったのだ。でも、それですっきりした部分もある。ミカエルの涼しいたたずまいは……そういう背景があればこそ。
「とにかく、俺たちが傀儡だということはわかった……世界は、おまえら超越体の掌にあるんだな」
ショーティが、低い位置から口をはさむ。
「自棄になるのは、やめてもらおう。きみたちがただの道具なら、わたしもミカエルも、わざわざこんな話はしない」
そうだといいけどな。
「でもまた、何かに利用しようとしているのかもしれないわね。わたしの《ヴィーナス・タウン》も、あなた方の計画の一部だからこそ、支援されてきたわけだし」
微笑んで言ったのは、ハニーだ。彼女はとうに、腹が決まっているらしい。
「わたしもシヴァも、子供を守り育てなければならないのだから、自棄なんか起こさないわ。みんなで幸せになりたいの」
さすが、強いな。
「そのために、できることは何でもするつもりよ。ここに来たのは、味方を増やしたいから。ミカエルが超越体だというのなら、それも結構よ。わたしたち、これまでずっと、ショーティに助けられてきたんですもの。ミカエルにも、助けてもらえるんでしょう?」
美少年は、それでいい、というように微笑んだ。
「ええ、そうですよ。ぼくはリリーさんを愛しているので、リリーさんの暮らす世界を守りたいのです」
その言葉を信じたい。いや、信じているけれど、ミカエルが思う〝愛〟とは、既に人間の考える〝愛〟から乖離しているかもしれない。
「ショーティが、シヴァを愛しているのと同じです。ぼくたちは、これからも協力し合っていけるはずですよ」
とてもすぐには消化しきれないが、この場が一族にとって、辺境全体にとって、大きな転換点だということだけはわかった。
彼らがこれだけの秘密を打ち明けたということは、ここから先は、今までとは違う演目の舞台になるということだ。
もしかしたら、人類の歴史の転換点なのかもしれない。
でも、どんな方向に向かって?
あたしたちには、どんな役目がある?
「麗香お姉さまは、あなたたち若い超越体を育てて、自分の補佐をさせていたのね。お姉さまこそ、〝連合〟の背後にいた、最も古い超越体なのね。そして、人類を自分の思う方向に導いてきた……〝連合〟すら道具にして。その道具の使用期限が、そろそろ切れるということなのかしら。ハニーさんの《ヴィーナス・タウン》や、ジュン・ヤザキの《アグライア》が、新たな権威になっていくということ?」
探春が、あたしにもわかるようにまとめてくれた。
なるほど、そういうことなのだ。
辺境に、新しい時代が来る。
「その二つの勢力に、これからは《ティルス》が加わりますよ」
とミカエル。
「これまで細く流れてきた三つの流れが、合流して大河になるんです」
ゆっくりとだが、納得が染みこんできた。
麗香姉さまはおそらく、人類社会で、最初に超越体になった成功者。そして、現在でも、圧倒的な優位を保っている。その絶大な能力で、新たな脚本を書き下ろした。〝連合〟は力を失っていき、新たな権力者が辺境を仕切る。たぶん、前よりもっと人道的に。
「超越体って、たくさんいるの?」
あたしの疑問に、ミカエルが答える。
「ぼくが知る限り、たくさんはいません。この銀河一つに、たくさんの超越体は収まりきれませんよ」
そういうものか。
「麗香さんは、おそらく、これと見込んだ者を使って、何十回か何百回、あるいは何千回、超越化の実験を行ってきたのでしょう。その中で、失敗した者や反逆した者は、抹殺されたと思います。発狂した者、野心にかられて暴走した者が、何百、何千といたのでしょう」
ミカエルも、麗香姉さまの過去の行動を、全て知っているわけではないという。それどころか、知りえないことの方がはるかに多いと。
「ぼくやショーティのように、従順で安定した者だけが残されて、要所に配置されたのだと思います。そして、人類を陰から監視したり、操ったりしているわけです。それも、麗香さんのグランドデザインに添う形で」
犬は水のボウルを近くに置いて、ゆったりと寝そべっている。この可愛いミカエルも、単なる端末の〝人形〟なのか。本体はあちこちの基地や船の奥に、分散して存在しているのか。
そうして、互いにネットワークでつながり、日々、拡大し続けているのか。
それならば、感じ方も考え方も、ただの人間だった頃とは、大きく違ってくるだろう。
あたしへの愛情も、どう変質するかわからない。
いや、そんなものはとうに、動物を観察する学者のような客観性に変貌しているのかも。
あるいは、生物全体に対する慈愛……
それでも、無関心にはまだ至っていない。そう信じたい。
「グランドデザインて、何なの。姉さまは、最終的には、何がしたいわけ」
と、あたしは尋ねた。
「辺境の権力交替は、構わないよ。人権が尊重されるようになる。市民社会との垣根が低くなり、行き来が盛んになる。それが、ハニーたちの望む方向でしょう。それなら、文句はない。でも、その次には何が来るわけ。たとえば、人類全体を超越化させるとか。それとも、わずかな超越体だけを残して、旧人類を抹殺するとか」
シヴァがひきつった顔をした。冗談じゃない、と低くつぶやく。
「それは、ぼくらにも、想像することしかできませんが……」
ミカエルが、苦笑にすらならない、寂しげな色を浮かべた。
「たぶん、麗香さんは、今もどこかで実験を続けているのでしょう。より優れた生命とか、高度な知性を発生させようとして……あるいは、新たな宇宙の創造とか……先に何があるのかは、きっとまだ、麗香さんにもわからないのではありませんか」
その言葉が、真実であればと思う。
「未来が決まっていないのなら、それであたしは少し、救われるな」
すると、
「決まった脚本をなぞるだけでは、面白くないものね」
と、皮肉な微笑みを浮かべた探春が言う。
「それにしても、破格の存在なのですね……あなた方の最長老という方は」
とハニーがしみじみ、歴史を振り返るように言う。
「仲間を集めて地球から脱出して、辺境で都市を築いて……不老処置にも成功して、超越化にも乗り出して……どれだけ強い人だったのでしょう」
シヴァが苦い口調で言う。
「この屋敷で俺を育てていた頃、既に人間じゃなかったんだろう。だから俺は、いつもどこか……違和感を感じていたんだ。目の前にいても、はるか遠くから口をきいているような」
「あなたにとっては、育ての親なんでしょう?」
とハニー。
「だが、母親と思ったことはなかった。母親は、写真を見せられて、別人だと……いや、親なんて、本当に存在したのか、まだ疑ってはいるな。俺はどうせ、人工の胚から育てられたんだろう」
シヴァがすねた様子なので、あたしは横から言った。
「あたしたちみんな、程度の差はあれ、姉さまの手で合成されたんだよ。あんただけじゃない。誰かに由来する遺伝子なんて、言い訳程度にしか使っていなかったかも……全然、使っていなかったとしても、問題じゃない。その時に考えうる、最高の遺伝子の組み合わせをもらったんだから」
ハニーが微笑んで、横に座るシヴァの腕に手を置いた。
「わたしが好きなのは、今のあなたよ。あなたを創ってくれた人には、感謝しかないわ」
シヴァが照れ隠しに苦い顔をするので、めでたいと思う。この世に生まれてきたことが、祝福なのだ。
「確かに姉さまは、とらえどころのない人だったね」
ここにいながら、はるか遠くを見ているような。
「あたしには優しかった印象が強いけど、それも、計算の上での寛大さだったんだろうし」
あたしが子供の頃でも、
『なぜ、世界はこんな風になっているの』
『なぜ、人間はバイオロイドを作り続けるの』
と疑問をぶつければ、何かしら答えてはもらえたが、それも、抽象的な話が多かったと思う。
世界は、あなたの覚悟次第で変えられるのよ、とか。
何を大切に思うかで、行動が決まるのよ、とか。
あたしは、ヴェーラお祖母さまとはよくぶつかったが、それは、お祖母さまとあたしが同じ現実世界にいて、日々、自分なりに格闘していたからだ。屋敷の警備について。外出時の注意事項について。チンピラと殺し合いをした後の始末について。
でも、長く一族を率いてきたはずの姉さまは……どこかで、その現実から抜けてしまった。それが、長く生きた成果なのか。
ミカエルは、思い巡らす態度で言う。
「超越体として、一年の年齢差があれば、大人と子供くらいの差ができてしまいます。いったん超越化すれば、眠らずに進歩し続けられますから。それに、自分というものが拡大するから、ある部分で他組織の動向を調べ、ある部分で自分の研究を進めるという風に、分業できます。そして、情報の整理や統合も容易です。だから、加速度的な進化が可能になるんです」
たぶん、そうなのだろう。
一人で大組織に匹敵する、ということだ。
いや、人間の作る組織など、問題にならないくらい有能になるということか。
「ぼくから見ればショーティも、数十年の先行がある分、把握できないほど巨大な存在です。ぼくの知るショーティは、ほんの表面的な部分だけでしょう」
元が犬でも、か。
ショーティは否定も肯定もせず、床に寝て目を閉じている。
「まして、麗香さんのように、既に百年か二百年先行している超越体なら……先駆者としての試行錯誤の日々を考慮し、最初の頃の進化速度が遅かったと仮定しても、今ではおそらく……神に近い存在といえるのではないでしょうか」
そんなの、あたしの手には負えない。誰の手も届かない。姉さまに逆らうことを考えたって、確かに無駄だろう。
「ねえ、姉さまには、特に悪意はないんじゃないの?」
はかない期待を込めて、言ってみた。
「茜のことだって、ただ、親切で、シヴァに返してやろうと思っただけかもしれない。もう、シヴァを操る必要がなくなったという理由でね。あたしたちはずっと、姉さまに守られて暮らしてきたのだし……今さら、姉さまの善意を疑わなくてもいいんじゃないの?」
ミカエルが、口許を皮肉な形に歪めた。
「確かに、悪意はないでしょうね。人間は、池のミジンコやメダカに対して、悪意なんか持たないでしょう」
改めて、力が抜けた。
「あたしたちは、ミジンコ程度の存在か……」
古い超越体にとっては、たとえ大組織であっても、メダカくらいにしか見えないのか。
「でも、そのミジンコをうまく刺激すれば、その中から、頭のいいミジンコが出てくるかもしれない。それを気長に育てれば、いずれ自分に近い存在にまで進化するかもしれない……そういうことでしょ?」
それは、科学者の業のようなものではないか。
世界の真理を知りたい。究極の存在になってみたい。そのためには、何を犠牲にしても構わない、という。
シヴァは冷笑を浮かべた。
「その刺激のために、何人殺しても構わないわけだ」
彼はそれだけ真剣に、茜という娘を愛したらしい。
「あの時、茜の身代わりに、同型のバイオロイドを使ったんだろう。俺には茜が死んだと思わせておいて、茜本人は、いつか何かの形で利用するために、取っておいたわけだ。それをようやく、俺に返してくれるという。何のためにだ!? 今度は俺に、何をさせたいんだ!? 茜の身代わりになった娘は、自分で自分の頭を吹き飛ばしたんだぞ!! そうするように、暗示をかけられていたんだ!! そんな悪魔に、何が期待できるっていうんだ!?」
だけど、姉さまの目論見なんて、ミカエルやショーティにだって、推測しかできないものだろう。
「何人殺しても構わないというなら、それはあたしも同じことだよ。自分の思う〝正義〟のために、どれだけ破壊し、殺してきたか、わからない。人を非難する資格はないな」
シヴァはいささか、ひるんだようだ。もちろん、シヴァだって手を汚してきているはず。
「麗香姉さまだって、最初から全知全能だったわけじゃない。自分が生き延びるため、一族を守るため、必死の思いで戦ってきたはずだ」
一人ずつ仲間を失い、落胆し、思い直しては新たな子供を誕生させて、世代は移り変わっても、姉さまは生き続けて。
「その結果、超人的な存在になってしまったとしても……責められることではないわね」
と探春。
「いずれは、わたしたち全員が、そこへ到達するのかもしれないし」
そんな未来、途方もない。想像するだけで疲れてしまいそうだ。
「もしも仮に……仮定の話として聞くんだけど……」
考えながら、あたしは言う。
「あたしたち人間と、あなたたち若手の超越体が手を結んで、姉さまに逆らったら、どういうことになる? 姉さまを、この銀河から追い払うことはできるの?」
別に、そうするべきだと思うわけではない。今、あたしたちが姉さまの掌の上に載せられているとしても、特に困ってはいないからだ。
それどころか、新しい潮流のおかげで、辺境は平和になりつつある。
このまま半世紀が経てば、バイオロイドの人権は守られ、一般市民も不老処置を受けることが普通になり、人間同士が争う必要はなくなっているだろう。
人類が夢みた理想郷まで、もう一歩のところにきている。
いや、その理想郷に満足できない者たちは、きっと逃亡していくのだろうが……
彼らを追って、市民社会の価値観を押しつけることまでは、あたしの仕事ではない気がする。
「もしも麗香さんが、人類に興味を失ったら、あっさり出ていってくれるでしょうね。わざわざ、ミジンコやメダカを殺して廻る必要なんてありませんから。お一人で、はるか遠くの銀河へでも行けば、数億年か数十億年は一人でいられるでしょう。人類が、あえてそこまで出ていかない限り」
とミカエルは言う。
「でも、逆に、隠れて人類を見守っていたければ、いくらでも隠れられますよ。たとえばショーティが、途中で麗香さんに乗っ取られていても、他の者にはわかりませんから」
なるほど。
既に神の段階まで進化した存在なら、あたしたちがどう逆らっても、逆らわなくても、同じことか。
「じゃあさ、あたしたちは姉さまの意図なんか忖度せず、自分たちの好きなようにしていればいいんじゃないの?」
少なくとも、あたしはそれで構わない。
神が存在しても、しなくても、人間は勝手に生きるものだ。
「それも、一つの対応ではある」
と床に寝そべったショーティが、顔を上げて言う。
子供の頃、シヴァとショーティと一緒に走り回ったことは、今から思うと夢か幻のようだ。
まだ百年も生きていないのに、ずいぶん老け込んだ気がする。
「昨夜のうち、他の超越体とも協議したが、彼らも大方、特に新たな行動は必要ないという意見だった。これまで、麗香さんが我々に何かさせたい時は、そう指示してきたからだ」
「おまえも、静観でいいと思うのか」
シヴァが尋ねると、ショーティは言う。
「一番怒っているのはきみなのだから、きみがどうするかが、まず先ではないのかな。他の者は、それに応じて態度を決めるだろう」
ハニーがシヴァの横から、そっと訴えた。
「あなたが麗香さんに対して怒るのは、当然だわ。あなたを育てた最長老だからといって、あなたの心を、道具みたいに扱っていいことにはならないもの。冷凍された茜さんも、茜さんの身代わりに自殺させられた娘さんも、本当に可哀想だったわ」
既に長くシヴァと暮らして、彼の気質を飲み込んでいるから、穏やかに話せるのだろう。
「でも、茜さんは返してもらえるんでしょう。冷凍状態から、復活させられるんでしょう。それなら、あとはあなたが、彼女を保護してあげれば……あなたとの関係は、またここから始められるでしょう」
ハニーの声には覚悟が表れていた。《ヴィーナス・タウン》に大勢の女たちを集め、指揮しているだけのことはある。最高幹部会の目は確かだ。いや、麗香姉さまの眼力か。
「あなたがいいようにしてくれれば、わたしは大丈夫だから……」
シヴァは顔を曇らせたが、改めてハニーの肩に腕を回して、優しくさすった。
「俺は、何であっても、きみのいいようにする。俺の一番は、きみだ」
シヴァの奴、大真面目にそんなこと、言えるようになったんだ。それは、よかった。探春はちょっと、苦い顔をしているようだけど。
あたしなんて……ミカエルと、少なくとも心は通じ合っていると思っていたけれど、それも怪しくなってきたものね。あたしが、ミジンコの一匹にしか見えないとしたら。ちょっとばかり、大きなミジンコだとしても。
「すまない。きみがいるのに、動揺して悪かった。茜のことは……たぶん、娘として考える。ショーティもいることだし、子育ての続きをすればいいことだ」
ハニーの肩から、いくらか残っていた緊張が抜けた。あたしもまた、ほっとしている。シヴァも大人になったのだ。彼らのことは、もう大丈夫。
さて、あたしはどうだろう。
英雄豪傑と呼ばれて、いい気になっていた面がある。それがインチキだったとわかった以上は……
「とりあえず、〝リリス〟は活動停止だな」
あたしは探春と視線を合わせてから、なるべく明るく言った。声に多少の刺が混じるのは、仕方ない。
「芝居の舞台に載せられていたとわかった以上、もう、〝正義の味方〟の役はやっていられない。あたしには、巧い演技なんかできないからね」
あたしは道化だったのかもしれない。
自分では、本気で理想の世界を目指して歩んできた道だった。
それが、誰かに用意された花道だったのなら、この先は、しばらく考えてからでないと、動けそうにない。
「紅泉」
探春が心配そうな声を出したが、あたしは努力して笑みを返した。元々、探春自身はハンターなんて望んでいなかったのだ。
「しばらく休もう。《ティルス》で子守りでもしていればいい。そのまま引退かもしれないし、先でまた復活するかもしれないけど」
力が抜けた、気がする。
たとえハンター稼業に戻るとしても、もう、今までと同じようには行動できない。きっと、余計なことを考えてしまう。どこまで、超越体の計算の範囲なのかと。
あたしこそ、根底から人生を考え直す時なのかもしれない。八十年以上……戦いの人生を走り続けてきた。立ち止まってもいい頃だ。
「もしかしたら、あたしと探春の両親も……」
あたしが言うと、みんなが注目した。いや、そんな、たいしたことを言うつもりじゃないんだけど。
「こんな風に道を見失って、悩んだ挙句、この銀河から出ていったのかもしれないね。どこか遠くで、最初からやり直そうとして」
超越体に支配された世界では、人間の意志や努力など、もう意味がないのかもしれないから。
探春が理解した顔で、悪戯っぽく言う。
「わたしたちだって、遠くへ旅立っても構わないのよ。あなたが行くなら、わたし、どこにでもついて行くから」
いや、まだ、そんなつもりは全然ない。あたしはこの世界に馴染んでいるし、未練も多い。やっとシヴァに再会できたし、ミカエルもいるし、ダイナと泉の子供たちもいるし。
「とりあえず、人生の〝中休み〟をもらうことにするよ。探春が、それでよければね」
シヴァとハニーは、茜の眠り続けるカプセルを船に積んで、自分たちの拠点に引き上げていった。
茜をいつ起こすか、彼女にどう話をするか、それは彼らが決めればいい。シヴァだけでは不安だけれど、ハニーがいれば、きっと大丈夫。
この世界はずっと、賢い女たちが築き、受け継いで、守ってきたのだ。男たちが、見当外れに威張る傍らで。
麗香姉さまも、その系譜に連なる一人。
あたしは探春と共に《ティルス》の屋敷に戻り、しばらく子守りをして暮らすことにした。
ダイナとシレール、泉には、あたしたちが聞いた話をそっくり伝えた。もう、ハンター稼業を続ける気が失せたことも。
司法局には、長期の休暇を取るとメッセージを送っておいた。どうしてもあたしたちでなければならない任務なんて、もうないのだ。
そもそも、懸賞金リストなんてものがあるから、それに釣られた馬鹿どもが、暗殺騒ぎを引き起こす。
リストの筆頭である〝リリス〟の姿が、市民社会から消えれば、そんな事件も減る。
他の賞金首の警備は、軍と司法局が責任を持てばいいだろう。
こうなってみると、英雄だの豪傑だの言われて、誇らしく思っていた自分が、自分で哀れになって、笑えてくる。
「あなたは実際に、たくさんの人を救ったのよ。あなたがお手本を見せたから、大勢の若者が希望を持って、軍や司法局に入ったのよ」
探春はそう慰めてくれるが、誘拐された一人の市民を救うために、百人の辺境の人間を殺すような真似だったではないか。
「あたしの自己満足だったよ……まあ、何もしないより、よかったとは思うけど」
もう、みんな勝手にしてくれと言いたい。
しばらくは、ミカエルとも会いたくない。
今のミカエルにあるのは、愚かな人間たちへの哀れみだけではないのか。
特別に愛されているなんて、あたしの側の勝手な幻想、思い込みかもしれないだろう……
鬱々とした気分を救ってくれたのは、ダイナと泉の子供たちだった。
双子の春と夏、半年遅れで生まれた梢。
三人で朝からどたばたと走り回り、花瓶や彫像を倒したり、二階の窓から外の木に飛び移ったり、飼っている犬の上に転んだりして、ダイナや泉やお祖母さまに叱られ、しゅんとしては、またすぐ走り出す。
子供というのは、人生の歓喜そのものだ。
食べる時は、無我夢中。
遊ぶ時は、全力疾走。
眠る時は、こてんと泥のような眠りに落ちる。
あたしもきっと、そうだったのだろう。もうあんまり昔のことなので、よく覚えていないけれど、ヴェーラお祖母さまに言わせると、
「あなたくらい、厄介な子供はいませんでしたよ。何度叱っても、懲りずに同じ間違いをするし。自分の体力が無限かどうか、毎日確かめないではいられないようだったし」
ということだ。
あたしがお祖母さまに叱られてもへこたれなかったのは、麗香姉さまがいつも、かばう側に立ってくれたからだ。
『紅泉には、悪気はないのよ』
『大きくなれば、もっと慎重になるわ』
『失敗はいずれ、糧になります』
あたしが夜中に屋敷を抜け出し、街でチンピラに喧嘩を売って廻るようになってからも……
そう、姉さまは、あたしを無鉄砲な冒険家に育てたかったのだ。いずれ、市民社会の英雄にするために。それが、市民社会の健全さを守ることにつながるから。
市民たちが未来に希望を持たなければ、子供を産み育てられない。
姉さまは、人間社会に期待していたはずだ。
その期待を、愛という名で呼んでも間違いではないだろう。
そうでなければ、あたしが姉さまの庇護を受けて、安心していられたはずがない……単なる実験動物で、いつでも使い捨てにするつもりだったとは……思いたくない。
ヴェーラお祖母さま、ヘンリーお祖父さま、マーカス大伯父さまたちとも、腹を割って話し合った。
第二世代の人々は、ある時点で、第一世代の生き残りである麗香姉さまが〝人間でなくなった〟ことを悟っていたという。
「《ティルス》を建設した頃は、まだ人間だったと思うわ。冷静で強靭な人だったけれど、それでも感情があった。本気で怒ったり、悲しんだりするのが感じられた」
それはもう、何百年も昔のことだ。
《ティルス》の建設当時、お祖父さまやお祖母さまたちの第二世代は、まだ生まれたかどうか、というあたり。都市と共に成長し、姉妹都市を築く時の戦力になった。
「でも、いつからか、あの方の喜怒哀楽が、表面だけのものになったような気がするの。はっきり、いつとは言えないけれど」
バイオロイドを使った不老長寿の実験。自分自身への応用。そして超越化の研究。
それでも、麗香姉さまは一族の生き残りために、着々と手を打っていた。二つの姉妹都市の建設。研究機関の設置。新人のスカウト。防衛艦隊の増強。
辺境に人間が増え、他の組織が育つにつれ、勢力争いも起きたけれど、姉さまは的確な指揮を執っていたという。
「わたしたちはすっかり、それに慣れていたから、麗香お姉さまの指示に従うことに、何の疑問もなかった。ご自分はずっと独身で、若く美しかったから、わたしたちも、自然にお姉さまと呼んでいたわ」
地球を知る第一世代は、やがて事故や事件で死に絶えたが、姉さま一人は幸運にも……生き残った。そのうち姉さまは、他の有力組織をも、陰から牛耳るようになっていったという。
「その頃には、わたしたちは、麗香姉さまがどうやって正確な情報を得たり、他組織に自分の手先を送り込んだりしているのか、わからなくなっていた。あなたたちは、一族の内部に集中しなさいと言われていたし」
大手の組織が集まり、〝連合〟を形成したことにも麗香姉さまは関わっていたらしいが、ヴェーラお祖母さまたちは《ティルス》や姉妹都市の運営に忙しく、対外工作は姉さまに任せる部分が大きかったという。
「気がついたら、六大組織が〝連合〟に君臨していて、中小の組織を傘下に集めるようになっていた。〝連合〟がみるみる巨大化していくので、恐ろしくなっていたわね。でも、姉さまは、うちは独立のままで大丈夫だと。その代わり、一族から何人か、こっそり〝連合〟に送り込むと言われたわ。送り込んだ時点で、表面的な関係は断ち切るようにと」
現在の〝連合〟最高幹部の一人、リュクスと呼ばれる女性は、ヴェーラお祖母さまの妹だという。他にも二人、対外的にはデュークとハヤテと呼ばれる一族の男性たちが、最高幹部会に入っているという。
「知らなかった。お祖母さまに、妹がいたなんて」
あたしも探春も、成人してからは、中央で暮らす時間が長かったから。
「それは、若い世代には、余計なことは教えるなと言われたから。離れてからも、たまに彼らと通話はしているのよ。だから、一族が守られることはわかっていたの」
〝連合〟そのものと、明確な条約を交わしていたわけではない。ただ、互いの領土を侵さなければ、共存していけるという暗黙の了解ができていた。必要があれば、リュクスたちから情報が流れてきたという。
「それは姉さまのおかげと思って、感謝していたわ。わたしたちは、自分たちの領宙を守ることに専念していた。ただ姉さまは、一族の基盤が固まると、実務から退いて、研究に打ち込むようになったわね」
新しい素材。新しい通信方法。より強力な艦船。優れたバイオロイドやアンドロイドの設計。色々な不老処置や強化処置。
「姉さまの研究は幅広くて、誰も全貌を把握できなかった。部分的に手伝う者はいたけれどね。あの頃、既に、超越化に成功して、安定していたのでしょう。姉さまは隠居すると言って、自分用の小惑星を用意したわ。一族の新しい世代は、姉さまが遺伝子操作で生み出すようになっていた」
その一人、シヴァは幼いうちは姉さまの元で育てられ、やがてあたしたちと合流した。腕力の制御を覚えないうちは、危険すぎて、あたしたちと接触させられなかったのだ。
「あなた方は、遺伝子操作の最高傑作なのだと思うわ。わたしたちもそれぞれ、強化処置や不老処置は受けてきたけれど、最初から完璧に設計された者には敵わない」
ヴェーラお祖母さまやヘンリーお祖父さまたちの第二世代、ヴァネッサ伯母さまやサーシャ叔母さまたち第三世代としては、あたしたち第四世代が育てば、三つの都市の経営を任せることができ、自分たちは引退して楽になれると期待していたという。
「それなのに、シヴァは家出するし、あなたたちは中央に行ってしまうし」
「すみません」
「そもそも、あなたたちの親が出ていってしまったのが、大きな損失なんだけど」
決して、一族に望まれた離脱ではなかったという。けれど、当時の辺境は今よりもっとひどい戦国時代で、組織同士の抗争が激しかった。毎日のように、流血の惨事が起きていた。この銀河に見切りをつけて、はるか遠くで理想郷を建設したいと願う一団を、あたしと探春の両親は率いて出ていったのだ。
あたしと探春には、同行するか、残留するかの自由があった。あたしは残ることに決め、探春もあたしといることを選んだ。子供時代、双方の両親は仕事に忙しく、あたしと探春はほとんど、お祖母さまの元に置き去りの状態だったから……また、遠くへ仕事に行くのね、という感覚だった。その頃はまだ、違法都市で冒険して楽しく過ごしていたし……
法のない違法都市は、あたしには、スリルのあるジャングルだったのだ。あたしは子供の頃から、意欲的なハンターだった。手頃な小悪党は、いくらでもいた。狩場である《ティルス》を離れて、何十年も狭い船の中に閉じ込められ、あてのない旅を続けるなんて……
「シレールとダイナが残ってくれて、本当によかったわ」
お祖母さまは、しみじみと言う。
「一夫多妻はどうかと思ったけれど、泉ともうまくやっているようだし。何が正しいのかなんて、人によって、時代によって違うんですものね」
そうだ。
あたしは、自分にできること、自分がしたいことをやってきた。それが正しいと信じて。
でも、それは麗香姉さまに、うまくおだてられ、誘導されたから。舞台監督の指図で、良い役を振られていただけのこと。
いや、監督はグリフィンか。姉さまは、劇場のオーナーと言うべきかもしれない。
そのオーナー様は、これから先、いったいどんな芝居がお望みなのだ。観客に、何を信じさせたいのだ。
それとも全てに飽きて、観客ごと、劇場を破壊したいのか。
これからあたしが、自分の勝手なアドリブで演技し始めたら、それはオーナーへの反逆になるのか。
それとも、あたしの頭の中身まで、姉さまはお見通しなのか。
まあ、あたしが悩んだところで、たいした意味はない。どうせあたしは、あたしがしたいと感じることしか、できないのだから。
ダイナは総帥業務の傍ら、《アヴァロン》のハニーや《アグライア》のジュン・ヤザキと連絡を取り合い、今後の方針を話し合うことに忙しいようだ。好きにやってくれて、構わない。もう、新たな世代に任せる頃合いだ。
あたしと探春は、ここでのんびりする。また何か、動きたい気持ちを感じるまでは。
後悔した。ずっとくよくよ、考え続けた。本当は、意地を張らずに会いに行けばよかったのだ。彼らが《ティルス》を訪問してきた時に。
でも、会いたいとは言えなかった。そんなことを望むのは、アスマン兄さんに対する裏切りのような気がして。
当時のあの人は……ママとの間に子供を持つ気など、少しもなかったのだ。ママはただの秘書で、恋人でも愛人でもなかったのだから。
彼がこちらに無関心なことは、覚悟していた。ハニーさんからは通話をもらい、よければ《ヴィーナス・タウン》の旗艦店に遊びに来て下さいと言われたけれど、お義理の誘いだと思っていた。向こうにはもう、望まれた子供たちがいるのだから。
わたしには、兄さんがいれば十分……そう思っていた。兄さんもまた、自分の元になった細胞の持ち主には、無関心に見えた。兄さんには紅泉叔母さんという師匠がいて、自分の仕事があって、精神の安定を保っていられるから。
だけど……いくら頼もしい兄さんがいても、わたしは、父親というものに憧れることを止められなかった。
会ってみたい。でも、怖い。
もしも迷惑そうな顔をされたら……お義理の愛想を言われるだけだったら……想像するだけで耐えられない。得られない愛情を欲しがるなんて、そんな惨めな自分を、自分で許せない。
わたしはママに愛されているし、兄さんにも守られている。《ティルス》では、一族のうちとして認めてもらっている。何の不足があるというの。
けれど、とうとう、迷い続けることに疲れてしまった。
実際に会ってみて、迷惑がられたら、それであきらめがつくではないか。無用な憧れは消え、元通り、兄さんの元で楽しく暮らせるはずだ。
わたしは兄さんに、《フェンリル》のママの所へ顔を出すからと言って、研究所を離れた。そして、ダイナさんにだけ事情を話して、《アヴァロン》へ向かった。
目的地が近づくにつれ、眠りが浅くなり、食欲がなくなったけれど、無理にでも栄養はとった。やつれた青白い顔で〝父親〟に会うなんて、恥ずかしすぎる。
そもそも向こうは、わたしの母に遺伝子を盗まれて無断使用されただけであって、父親だなんてつもりは、全くないかもしれない。ハニーさんが通話してきた時だって、画面に顔を出すこともなかったのだし。
あくまでも軽い好奇心で……お買い物旅行のついでに……ほんの気まぐれで……
それでも、《ヴィーナス・タウン》の旗艦店に足を踏み入れた時は、胃が焼けるようで、逃げ帰りたい気持ちで一杯だった。けれど、ダイナさんから連絡してもらっている以上、後へは引けない。車から降りると出迎えの職員が待っていて、すぐにハニーさんのオフィスへ通された。
「梨莉花さん、来てくれて嬉しいわ」
ブルーグレイの上品なドレスがよく似合い、同性でも、まばゆさで目がくらむほどの美しい人。
わたしだって、自分はそこそこ可愛くて魅力的だと自負しているけれど(兄さんの研究所の科学者たちは、半分くらいわたしの崇拝者だ)、この人の貫禄には、はるかに遠いと思う。わたしがこれだけ優雅に、威厳を持って振る舞えるのは、いつのことになるだろう。
「うちの子供たちを紹介しますね」
と言われ、同じ階にある私的エリアの子供部屋へ案内された時には、ほっとした。相手が子供なら、何とか笑顔になれる。小さなリュウは、抱っこされてにこにこするだけだけれど、長女のペネロペには、〝親戚のお姉さん〟と認識されているらしい。
「泊まっていけるの? 絵本読んでくれる?」
物怖じしないのは、このビルで働く女たちを全て〝お姉さん〟と思っているからだろう。
「ええ、あなたのママが許して下さったらね」
「ママ!! 梨莉花お姉さんに絵本読んでもらっていい?」
「ええ、後で時間があったらね」
ビル内のホテル階に部屋を取ってもらっているが、ハニーさんの私生活に入れてもらえるかどうかは……ここに来るまで、わからなかった。
「よかったら、後でまた遊んでやって下さいね」
とハニーさんに言われたことを、本気にしていいのだろうか。子供を落胆させたくない。できるなら、嘘もつきたくない。いつか、わたしが遺伝子を共有していることを告げてもいいだろうか?
それからハニーさんに広い店内を案内してもらい、各階で従業員たちとおしゃべりし、服や宝石を買い、平和に日が暮れた。ビル内の私的エリアでの夕食に招かれた時は、
(とうとう)
と処刑台に向かう気がした。子供たちは乳母や家庭教師と共に……犬のショーティも一緒に……子供部屋で食べるというので、食事はわたしとハニーさん、それに、あの人だけだという。
やはり、案内された部屋には、背の高い黒髪の男性がいた。軽い青のジャケット姿。ちらりと一目見ただけで、アスマン兄さんにそっくりなのがわかる。骨格も、筋肉の厚みも、顔立ちも。
あ、でも……
「やあ……初めましてと言うべきか。梨莉花……と呼んで構わないか」
その声は、兄さんによく似ているけれど、少し違う。ほとんど同じ骨格であっても、声の出し方の違い、言葉の選び方の違いがあるのだ。
表情も違う。兄さんはわたしに、開け放した素の顔を見せる。怒りも喜びも隠さない。
でもこの人は、用心深く構えていて、わたしの反応を見守っている。わたしのことを、未知の危険と思っているのだろうか。
とりあえずは、兄さんとの区別がつく、ということに安堵した。ほとんどクローンと聞いていたので、髪型くらいしか、区別のつけようがないかと思っていたのだ。その髪も、兄さんより、この人の方が短く整えている。
「初めまして……」
この人を何と呼べばいいのか、ここに来ても、まだ迷っている。ハニーさんには、好きに呼んで構わないと言われたけれど。
「あの……」
精一杯、明るいピンクのドレスでお洒落していたけれど、自信がなくて、回れ右して逃げ出したい。この人はわたしに、母の面影を見て、うんざりしないだろうか。わたしは兄さんよりずっと多く、母方の遺伝子を組み込まれている。
だめよ、ぶつかるのよ。ここまで来たのは、何のため。
「お父さん……と呼んだら、間違いですか……」
軽い驚きが、向こうの全身を走ったと思う。でも、すぐに大きな右手が差し出された。
「いや。構わない。間違ってはいない」
わたしの全身に、何かが走った。向こうの顔には、兄さんとは違う温かみがある……気がする。
「きみはリナの娘で、俺の娘でもある。俺が知らないうちに生まれた、という事情はあるが」
そう。ママが勝手に、この人の遺伝子を使った。ママは今でも、この人を愛している。片思いのまま。この人に愛されているのは、ハニーさん。
泣くなんて惨めなことは、したくなかった。わたしには、ママの片思いなんて関係ない。わたしはわたしで、望む人生を歩いている。なのに、どうしてこんな所まで来て、身がすくむ思いをしなければならないの。
差し出された手に向かって、手を伸ばそうとして、途中でためらい、止まってしまう。
「あの、わたしたち、やっぱり、迷惑、ですよね……?」
そうだと言われたら、すぐさまここを立ち去って、二度と来ない。わたしの人生から、この人たちを切り捨てられる。
なのに、長身の男性は、ぷっと吹き出した。笑いをこらえようとして、失敗している。横にいるハニーさんを見て、同意を求めるように言った。
「リナよりずっと、遠慮深いじゃないか。こんなにいい子に育っているとは、紅泉のおかげかな? あいつ、アスマンを相当厳しく躾け直したらしいから」
「それは、妹さんにも、いい影響を与えたでしょうね」
とハニーさんも笑っている。
引っ込めようとした手を、大きな手でぐっと握られた。そのまま軽く前に引かれて、もう片方の手で、そっと背中を叩かれる。まるで、小さな子供をあやすように。
「よく来てくれた。ありがとう。俺から会いに行く勇気がなくて、すまなかった。憎まれているかと思って、怖かったんだ」
怖い? グリフィンという権力者だった人が、わたしみたいな小娘を?
「憎む、なんて、まさか……」
ああ、確かにアスマン兄さんは、この人に反感を持っているかもしれない。だから、自分から動いて《ティルス》に行こうとしなかった。
でも、わたしは……両親が揃った家庭に、ずっと憧れていた。偏った性格の母親しかいないことを、引け目に感じていた。ママは有能な実務家かもしれないけれど……兄さんを偏愛して、兄さんに愛想を尽かされていた。わたしもまた、ママの檻から逃げ出したかった。だから兄さんを自分の王子さまと決めて、兄さんの元で、お姫さまのように振る舞おうとした。
兄さんはもちろん、わたしの面倒を見てくれたけど、最初のうちは仕方なしに、だったわ。兄さんが、わたしを望んで引き取ったわけじゃない。
わたし、無条件で父親に愛される、本当のお姫さまになりたかったのよ。
プリンセスというのは、王国を約束されて生まれる娘のこと。王国というのは、父親が用意してくれる場所のこと。それが粗末な小屋であっても、洞窟であっても、構わない。
気がついたらわあわあ泣いて、広い胸にすがりついていた。この胸に受け止めてほしくて、ずっと飢えていたのだと思う。勝気に振る舞っても、それには演技が入っていた。
二十五年もの間、ずっと、本物の承認が欲しかったのだ。ママの愛情では足りなかった。あの人は、自分の寂しさを埋めるために、わたしを人形にしたがったんだもの。
ママが悪いというのではない。ママは市民社会からさらわれてきて、本当の家族を失った人。リザードがママを育てたのは、自分に忠実な幹部にするためにすぎない。ママにとって、世界は過酷だった。せめて好きな人の子供を持とうとしたママを、責めることはできない。
でも、わたしはそこから踏み出したかった。だから、兄さんを追って《ティルス》に移った。広い世界で、わたしの人生を切り開くために。
ぐしゅぐしゅ泣いて、頭を撫でてもらい、何度も鼻をかんで、やっと収まった頃には、夕食の予定時間をかなり過ぎていたと思う。でも、ハニーさんは片隅の席で、様子を見にきたショーティと共に待っていてくれた。お父さんは、わたしの額に軽いキスをしてくれて、洗面所に送り出した。
「顔を洗っておいで。乾杯の用意をしておくから」
辛い時に、帰れる場所がある。頼れるお父さんがいる。それならば、わたしはもっと勇敢になれると思った。これまでだって、かなり勇敢だったと思うけど。
研究所に帰ったら、兄さんに話せるだろう。兄さんも、意地を張るのはやめて、お父さんに会えばいいのよって。
わたしたちはもう、時代遅れなのかもしれない。
肉体が若いから、心も若いつもりでいたけれど、本当はもう、新しい時代に適応できなくなっているのかも。
一族の第二世代であるヴェーラお祖母さまたちも、そう感じているのかどうか。今では〝相談役〟という名の引退生活に入り、現世の責任をダイナやシレール、泉に引き渡してしまっている。
第三世代の伯父さまや叔母さまたちも、徐々に権限を譲り渡していこうとしている。今ではアスマンと梨莉花がいるし、いずれは春と夏、梢も成長して、両親を助けるだろう。
まだ百年も生きていないわたしでさえも、いったん立ち止まってしまうと、足が地面にめり込むようで、容易には歩き出せない。
これまで〝リリス〟を陰から支えてきたのが、シヴァやミカエルだったなんて。
それでは、彼らを憎んでいたわたしは……視野の狭い、ひねくれた恩知らず?
こちらが求めた保護ではない。
でも、守られてきたことは、たぶん、間違いない。
特にミカエルは、涼しい顔をして、わたしたちを欺いてきた。とうに超越体になっていたくせに、清らかな少年のような顔をして。
麗香お姉さまは、〝現世に絶望して、なおかつ紅泉に最後の望みを託す人材〟が欲しかったのだ。
同じ可能性を秘めていたミカエルの兄弟たちは、紅泉に出会うこともできずに、狙撃や脳腫瘍で死んだ。
きっと他にも、大勢の素材が用意されていたに違いない。その中でたまたま、タイミングよく出会いを果たしたミカエルに、超越化の切符が差し出された。
それでもわたしは、ここまでの流れの中に、姉さまの〝感情〟を感じられる気がする。
単なる計算だけではない。
姉さまは、特定の個性を、他の個性よりも好んでいる。
それは、紅泉の剛胆な善良さだったり、ダイナの無邪気なひたむきさだったり。
わたしが許せなかったシヴァも、あれほどの女性が愛しているのなら、きっと良い面があるのだろう。もしかしたら、あの失敗が、彼の教訓になったのかもしれないし。
ミカエルだって……わたしは今も嫌いだけれど……紅泉に対しては、あれほど純粋な好意を持っている。
それは、たぶん超越化しても変わっていない。ショーティだって、シヴァに対する誠実はきっと失っていない。
〝特別な役〟のために、姉さまに選ばれた者たちには、共通する肌合いがあるのだ。
それならば、信じられるかもしれない……姉さまがまだ、人類の保護者でいることを。
ただ、もし、そうでないとしたら、わたしにできることは……紅泉を守るためにできることは……
わたし自身が、超越化すること?
でも、そのために、愛する心まで失ってしまったら? 今だって、紅泉以外はどうでもいいのに。
人間の肉体に束縛されなくなったら、わたしは、もっと冷淡になってしまうのではないかしら? 誰も愛さなくなって、なお、生きる意味があるのかしら?
わたし、紅泉に嫌われたくないから、優しいふりをしているのよ。
紅泉以外なら、誰が死んでも大丈夫。
ミカエルは、わたしのこの冷酷さを知っている。そして、黙っていてくれる。紅泉を悲しませるようなことは、言わないでいてくれるのよ。
彼に頭を下げるのはしゃくだったけれど、一度は謝っておくべきかもしれなかった。わたしが邪魔をして、彼を紅泉から引き離してしまったこと。
それもまた、姉さまのシナリオだったのだろうけれど……
「ヴァイオレットさんに謝ってもらうことなんか、何もありませんよ。確か前にも、そう言った気がしますね」
やはり、通話画面のミカエルは微笑んで言った。紅泉に向けるような、とろける笑みではなく、儀礼的なものだったけれど。
「結果的に、ぼくはリリーさんの守護天使になることができました。それが全てです」
わたしは《ティルス》の屋敷の自分の部屋にいて、映像のミカエルに向き合っている。
「たぶん、そんな風に言われるだろうと思っていたわ。ただ、わたしは自分の気が済むようにしたかっただけ。あなたに意地悪をしたことは、意地悪と認めます」
すると、ミカエルは面白そうに微笑む。
「了解しました。認めて下さって、有り難うと申し上げますよ」
それから、付け加えた。
「今では、わかっています。ヴァイオレットさんがいてくれたから、リリーさんが、今のリリーさんになったのです。今のぼくは、あなた方二人を守ることを使命にしていますよ」
それなら、それでいいわ。
「でも、紅泉はただの人間だから、いつか死ぬわよ」
超越化を望まない限りは。そしてわたしには、紅泉が、そんなことを望むとは思えない。
「ええ、わかっています……」
ミカエルの顔はこちらに向いているけれど、たぶん、わたしより遠くにあるものを見ている。
「その時は、その時です。ぼくには、リリーさんの思い出が残りますから」
でも、超越体は、おそらくは何億年、何十億年、あるいはもっと長く生きられる。おそらくは、この宇宙の終わりすら超えて。
超越化した最初のきっかけなど、いずれは、遠い記憶の一粒になってしまうだろう。
それが、永遠に生きるということだ。永遠の中では、どんな思い出も極小になってしまう。
「わたしは、紅泉と一緒に死ぬわ。もし後に残るとしても、ほんの後始末の時間だけよ」
「それも、了解しました」
「では、その時まで、紅泉をよろしくね」
これで、一つの義理は果たしたと思う。
自分たちがいつまで生きられるのか、わからないけれど、その時までは、紅泉と共に暮らす。
自分が死んだ後のことは、何も心配する必要がない。
わたしの宇宙は、わたしが生きている間だけ存在する。
わたしが、人を愛している間だけ。
あたしは二十代の終わり頃、ヴェーラお祖母さまから、一族の総帥の地位を引き継いだ。
「あなたはまだ若いけれど、わたしたちはもう、疲れたのよ。シレールがいれば、実務は問題ないでしょう」
と言われて。
もちろん、シレール兄さまが助けてくれる。泉もいる。おじさまたち、おばさまたちも支えてくれる。やるしかない。
一族を守る。三つの都市を経営する。子供たちを育てる。いくら強化体の体力でも、目一杯の忙しさだ。
だから、くよくよ悩む暇などない。紅泉姉さまたちがハンターを辞めても、ミカエルが人間でなくなっても、あたしたちの暮らしは続いていく。
〝連合〟が張りぼてとわかったのなら、それも別に構わない。
ジュン・ヤザキの《アグライア》と連携し、《ティルス》にも《ヴィーナス・タウン》の支店を出してもらう。この流れに沿って、勢力を伸ばしていくつもり。
ただ、春と夏、梢には、何をどう説明したらいいのだろう。
この世界は、超越体の実験場に過ぎないなんて。あたしたちは、彼らに飼われている実験動物だなんて。
それはシレール兄さまにも、泉にも、解決のつかない難問だ。少なくとも、子供たちが成人するまでは……真実を教える必要はないという点で、あたしたちは合意した。
まだ心の柔らかい子供のうちに、そんなことを教えたら……きっと、いい結果にならない。
子供は、明日に希望を持たなくては。
そのためには、世界は未知の方がいいのだ。自分の力で、少しずつ地平を広げていけば。
それでも、夜中や明け方、ふと目を覚まして、考えることがある。
人類に希望なんて、あるのか。
それとも、人類であることをやめて、次の段階に行くしかないのか。
人間であり続けることを選んだら、いつ超越体に抹殺されるか、怯え続けなければならないのか。
それとも超越体は、永遠に人間の友でいてくれるのか。あるいはいつか、はるかに進化した異星人が来て、あたしたちを滅ぼすのか。
わからない。
わからないから、明日も普通に起きて、普通に暮らすしかない。
これまで、お祖母さまたちがそうしてきたように。
仕事の合間、ミカエルとも、繰り返し話した。彼は、超越体になったことを悔やんでいないという。
でもそれは、彼が最初から、意図的にそこへ追い込まれていたからだ。
生きるための希望が、紅泉姉さまただ一人と思い込み、そのためなら何でもするという袋小路へ。
たぶん、彼と仲間たちが組織から脱出できたのも、麗香姉さまの見えない手が伸びていたから。
それでも構わないと、ミカエルは微笑んでいるけれど。
「だって、ぼくの兄弟たちは、リリーさんに出会うまで、生き延びられなかったんですから。ぼくは、奇跡的に幸運だったんですよ」
そんな状況を作ったのは、誰なのだ。
麗香姉さまが、一族を守ろうとしたのは確かだ。そのために〝連合〟という構造を作り、冷酷な悪役に仕立てた。そうすれば、一族はその陰に隠れ、ひっそりと繁栄できる。
そして〝連合〟が強大になりすぎ、市民を恐れさせすぎると、〝リリス〟という正義の味方を登場させた。
〝グリフィン〟は、〝リリス〟の引き立て役。
それを知った紅泉さまは、肩をすくめて〝主役〟から降りた。芝居と知らされて、それを続けられるほど器用な人ではない。
この先は、ジュン・ヤザキとハニーお姉さまが、わかりやすい〝正義〟の拠り所になる。市民たちが安心して、辺境に出てこられるように。保護を求めるバイオロイドたちが、駆け込めるように。
では、あたしは?
あたしはただ、一族を守るだけでいいのか。それとも、もっと何かしなければならないのか。若い超越体グループに、それを期待されているのか。
それとも、こんなことを考え続けること自体、麗香姉さまの術中に陥っているのか。
「悩むのはおやめ、ダイナ」
と紅泉姉さまは簡潔に言う。誰に演出されていようが、本質的に闘士であり、歴史に残る英雄の一人だとあたしは思う。
「あたしたちが何を悩んでも、無駄だよ。他人の思惑より、自分のしたいことを優先すればいい」
シヴァ兄さまはショーティを信じているらしいし、紅泉姉さまはミカエルを信じているようだ。いつか、信じた相手に裏切られる時が来たら、それは仕方ないと。
でも、あたしは……確信が持てず、揺れ動く。
自分だけのことなら、なるようになる、と思ってもいい。
でも、今のあたしには、責任があるのだ。
育ててくれた一族への責任、これから育つ子供たちへの責任。この都市で暮らす人々の安全もまた、無視できない。あたしが思考停止したことで、取り返しのつかないことになったら、どうするのだ。
「それが、現役の苦労というものよ」
既に大部分の業務から手を引いたヴェーラお祖母さまは、あっさりと言う。
「わたしとヘンリーは、あなたとシレールを選んで後を託したのだから、あとはあなたたちと運命を共にするわ。どうなっても恨まないから、自由にやってちょうだい」
そして、子供たちの世話や、新たに採用した新人の研修などで、昼間の時間を使っている。
子供たちの戦闘訓練は紅泉姉さまが引き受けてくれたし、勉強は探春姉さまが半分くらい見てくれるから、お祖父さまとお祖母さまの負担は軽くなった。その分、新婚時代に戻ったかのように、夫婦で楽しんでいる。
ドライブや音楽会に行ったり、レストラン巡りをしたり、温室でお茶の時間を過ごしたり。
うらやましいけれど、あたしとシレール兄さま、そして泉が現役の責任から卒業できるのは、たぶん二百年か三百年は先のことだ。
まあ、それまで、やるだけのことはやってみるつもり。
いざという時は、紅泉姉さまも、探春姉さまも、シヴァ兄さまもいるのだから。特に、姉さまたちだ。不老の強化体である人たちを、いつまでも遊ばせてなんか、おくものですか。
ほんの少しの休息時間は許すけれど、また、世界のために働いてもらうんだから。