
ブルー・ギャラクシー ジュニア編

最初は、ナギからの報告だった。
「ミス・リリー、これをご覧下さい。先ほど届いた情報です」
彼はあたしたちが秘書として使っている、美青年型の有機体アンドロイドの一体である。
任務と任務の間の待機時間だったので、あたしたちは中央の植民惑星のホテルにいた。不定期にネットを通じて、辺境からの連絡を受け取っている。
リリーというのはあたしのコード名のようなものだが、それすらも有名になりすぎてしまったので、変更した方がいいと思いつつ、面倒臭いのでそのまま使っている。他にもサンドラとかジャスミンとかいう偽名が幾つもあり、使い分けるのが厄介なのだ。
「これはおそらく、じかにご覧になるべきだと思いますので」
「そう? わかった」
あたしたちは、辺境のあらゆる違法都市に戦闘支援システム《ナギ》の末端を配置している。偵察鳥、監視虫、アンドロイド兵、有機体アンドロイド。
彼らは常時、都市内を行き来する人間たちのデータを集め、各組織の動向を分析している。その膨大な情報の中に注意を喚起すべき事象があると判定すれば、《ナギ》はあたしや探春に報告してくる。
「一緒に見る?」
「ええ、いま行くわ」
少女時代から続けているバレエの稽古を終えた探春が、シャワーを済ませてから来るのを待った。続き部屋の居間でソファに座り、その監視映像を見ることにする。
何でも、違法都市《サルディス》で、夜な夜な暴れ回っている男がいるらしい。ヘルメットをかぶって大型バイクを乗り回し、夜中の街をうろつく。あちらで街娼を買う男に喧嘩を売り、こちらでチンピラ集団を叩きのめし、死体やアンドロイド兵士の残骸を残して去る。
えらく腕が立ち、しかも凶悪らしい。まるで、少女時代のあたしみたい。街に暮らす者たちからは、
『あいつには近づくな』
『姿を見たら逃げろ』
と恐れられているようだ。
これまではヘルメットを脱がなかったので顔がわからなかったが、喧嘩で痛い目に遭わされた三流組織の連中が報復を企み、彼を罠にかけたのだ。
あたしたちが見た望遠の偵察映像では、バイクの男が炎に包まれていた。彼が通りかかった道路に、左右から化学燃料が降り注いだのだ。
バイクの男は燃えながらも走り続け、バイクごと川に飛び込んだ。それからバイクとヘルメットを捨てて川底を泳ぎ、かなり離れた地点に上陸した。たいした肺活量だ。
当然、そこにも罠を張った者たちが待ち構えていたが、激しい銃撃戦の後、生き残ったのは彼だけだった。
もしかして、あたしと同じくらい強いかも。
ずぶ濡れのまま撮影されたその顔を見て、あたしは息を呑んだ。横にいる探春も同様だ。
乱雑に切った黒髪、浅黒い肌、男らしい精悍な顔立ち。
黒焦げのライダースーツに包まれた、がっしりした長身。
これは、あたしたちの従兄弟のシヴァだ。
いや、シヴァの若い頃にそっくりだ。
体格は一人前に近いが、顔がまだ若い。動作にも、無駄な力みがある。おそらく、十五歳かそこらだろう。
本物のシヴァは、もしも生きているなら、五十代後半の立派な中年男のはずである。
あたしたちと同様、寿命の長い強化体なので、外見は若く保たれているだろうが、戦いの歳月はどうしても顔に出てしまうから、もはや若者には見えないはず。
この子はまだ、ほんの少年だ。
それにしても、シヴァにそっくり……彼が家出してからの姿は知らないので、あたしには、彼の二十歳前の姿しか記憶にないのだが……
「ねえ、探春、ひょっとして、この子……」
横を振り向いたあたしは、そこに誰もいないので驚いた。
いつの間にか、探春は奥の浴室にいる。洗面台に向かって頭を下げ、ざあざあと水を流している。長い茶色の髪は、手で横にまとめて。
吐いたのか?
それとも、頭を冷やしているのか?
探春は小柄で細いが、あたし同様、頑丈な強化体だ。病気なぞ、滅多にしない。歴戦の闘士だから、死体を見てもびくともしない。ずいぶん前、あたしが遊びで嵐の海に連れ出した時でさえ、船酔いで吐きそうになっても、こらえていたのに。
「気分悪いの? 大丈夫? 何か変なもの食べたかなあ」
支えてベッドへ連れていこうとしたら、身ぶりで断られた。顔は真っ青だ。元から色白だから、血の気が失せているのがわかる。
「まだ吐きそう? 医療システムで診断する?」
もしも重大な異変なら、あたしたちの主治医である麗香姉さまの所へ連れていかなくては。
あたしたちの遺伝子設計をし、研究室で胚を育成したのは姉さまである。遺伝子の欠陥が今頃になって発現したのなら、姉さまに相談するしかない。
けれど探春は、真っ青な顔のままで言う。
「病気じゃないの……少し休めば、治るわ」
ようやくあたしは、今の映像が、探春にショックを与えたのだと悟った。
でも、どうして。
従兄弟への手掛かりが掴めて、嬉しくないのか。
確かに探春は、前からシヴァの話題が出ると、露骨に嫌そうな顔をしていたけれど……それは、子供時代にいじめられていたせいかと……あれは単に、不器用な少年の愛情表現だったのだけれど……
間抜けなあたしは、ようやく真剣に考え始めた。
もしかして、探春とシヴァの間には、あたしの知らない、深刻な問題があったのではないかと。
(まさか? あいつ、片思いが昂じて……)
そんなにひどいことをするはずがないと思うが、でも、わからない。
あたしには、男女の関係の機微は全然わからない。
これまで、まともな恋愛をしたことがないのだ。恋愛に対する憧れはあるけれど、実際には縁がない。ほとんどの男は、あたしのようながさつな大女は、避けて通るから。
二日後、あたしたちは辺境へ向かう高速艦の中にいた。
司法局には断りを入れ、しばらく戻れないと伝えてある。シヴァそっくりの少年のことを、どうしても放置しておけないと思ったので。
他人の空似ならいい。
けれど、もしも、シヴァの息子だったら。
それならば、一族の一員だ。
おそらくはエネルギーを持て余しているのだろうが、あんな危険な暴れ方、放置しておくわけにはいかない。
このままではきっと、無駄に命を落とす。
同時に、世間の迷惑でもある。八つ当たりのようにして殺されるチンピラたちにとっては、ただの災厄だ。
そもそも、シヴァはどうしているのだ。
息子と一緒に暮らしていないのか。息子の教育に責任を持っていないのか。
シヴァが一族から逃げたことは、まあいい。探春に振られて辛かったのだろうと、想像することができる。
だが、息子ができたのなら、なぜきちんと導いてやらない。あんな、手当たり次第に喧嘩を売って回るような修行、無駄すぎるし危険すぎる。
それはまあ、あたし自身も似たようなことをやってきたから、絶対に駄目とは言えないが……
あの頃のあたしはまだ、一族にかばわれていた。まずいことをすれば、お祖父さま、お祖母さまが何とか始末してくれた。
しかし、シヴァの息子(既にもう、あたしの中では息子と決めてしまっている)はどうなのだ。
追跡映像では、シヴァそっくりの少年は、ずぶ濡れのまま手近の地下道に入り、迷路のような地下世界のどこかへ消えた。何らかの組織に守られてはいるのだろう。
けれど、それはシヴァの築いた組織なのか? シヴァはまだ、一族と連絡を取らないつもりか?
探春に振られたことなんて、もう遠い過去の話ではないか。あたしは彼に、あたしたちの味方になってほしいのに。
あたしと探春は、辺境を支配する〝連合〟に逆らい続け、命を狙われている。シヴァはあたしたちの側に立って、共に戦ってくれるべきだろう。
でも、探春はずっと暗い顔のままだ。シヴァそっくりの少年を捜す旅に、はっきり反対はしなかったけれど、それは、反対してもあたしが止まらないとわかっていたからだろう。
何度も確かめようとして、ためらった。
怖くて聞けない。
いったいシヴァに、どんな恨みがあるのだと。
何十年経っても、これほど残るしこりというのは、子供の頃、髪を引っ張られたり、虫や泥団子を投げ付けられたりしたから、程度のことではないだろう。
思えば、思春期のある時期、突然、シヴァは遠方の姉妹都市へやられたのだ。まだ基礎教育が終わるかどうかという年頃だったのに、実地研修とかいう名目で。
それ以後、あたしからシヴァに会いに行くことはあっても(彼は迷惑そうな顔をしたが、あたしにはいつもそういう態度だったから、別に気にしなかった)、シヴァが《ティルス》の屋敷に戻ってくることは、ついになかった。
大人たちが、あえてシヴァと探春を引き離したのか。
あれこれ思い合わせてみると、やはり、一つの結論にたどり着く。
シヴァは、探春に何かしたのだ。探春が決定的に、男嫌いになってしまうような何か。
当の探春が、親友のあたしにさえも、何が起きたか言えないようなこと。
まさか、と思う一方で、そう考えなければ説明がつかない、とも思う。
シヴァは、そこまで愚かだったのか。
強烈な欲望に振り回される疾風怒濤の年齢だったにしても、初恋の相手だった探春に、生涯消えない痛手を負わせるような真似をするなど。
しかし多分、それで間違いない。
だからシヴァは、一族から出ていったのだ。自分が生涯、探春に許されないと認識したから。
それでは、シヴァの息子を捜す旅は、探春には、古い傷跡をえぐるような行為になるのか。
その傷はまだ治りきってはいず、じくじく痛んで、いまだ探春を苦しめているというのに。
そうとわかっても、捜索をやめるわけにはいかない。
シヴァの息子なら、あたしには甥っ子のようなものだ。
父親がきちんと育てられないのなら、叔母同然のあたしが、教え導いてやらなくては。
そして、一族の戦力になってもらわなくては。
一族はこれから、あたしのせいで、〝連合〟と正面きって戦う羽目になるのかもしれないのだから。
あるいは、それより前に、あたしが死んでいるかもしれないが。
命を使い捨てにするような文明が、長く繁栄するべきではない。人を恐怖と武力で支配する〝連合〟の時代は、いい加減、終わらせなくてはならないのだ。

違法都市《サルディス》は、人口六十万の二級都市だ。ここに拠点を置く組織は数多い。六大組織も、それぞれ拠点ビルを持っている。
したがって、あたしたちは素顔をさらして歩き回ることはできない。ここまでの旅でも船を使い分け、迂回と偽装を繰り返した。
それでももしかしたら、悪党狩りのハンター〝リリス〟の行方は、追跡されているかもしれないけれど。
〝連合〟が本気なら、あたしも探春も、とうに殺されているだろう。それならば最高幹部会はまだ、あたしたちを、さほどの敵と思っていないのかもしれない。
それならそれで、一日でも長く生きて、活動させてもらうだけのこと。
あたしたちは繁華街の雑居ビルの一区画に腰を据えて、問題の少年が現れるのを待った。
これまでの記録では、少年は週に一度は街に現れている。もっとも、バイクごと焼かれてからは用心深くなったのか、あれから十日以上過ぎているというのに、まだ一度も姿を見せてはいない。
それなりの火傷もしただろうし、考えることもあるだろう。こんな無茶を、いつまで続けられるものかと。
まるきり考えなかったら、ただの馬鹿だ。
彼は――あたしはとりあえず、ジュニアと呼んでいるが――おそらく、自分がどう生きていったらいいのかわからず、無駄に足掻いているのだろう。
あたしも、思春期の頃はそうだった。
ここは、正義や良識が通じる市民社会ではない。強い者が弱い者を踏み付けにする、無法のジャングル。ここで自分の信念を通そうとしたら、敵対する者を殺していくしかない。
あたしも殺した。
夜の街をさまよい、手当たり次第に喧嘩を売って。
自分の強さを試したかった。何かにぶつかり、突破してみたかった。
そのうち一族から追放処分をくらい、あてのない旅に出て、司法局の捜査官と出会い、正義の側に立つことになって、ようやく方向が定まった。
それから今日まで、色々な失敗はしでかしたにせよ、市民社会を守る側にいることを悔やんだことはない。
『弱い者を守れる世界』が、あたしの生きたい世界。
シヴァそっくりのジュニアは、違法組織の一員となることに、満足できる少年なのか。
それとも、自分の力をもっと他のことに使いたくて、方法がわからず、もがいているのか。
できるなら、真剣に悩む少年であってほしい。それなら、あたしの側に引っ張れる。
〝リリス〟の一員になれとは言わないから(そんなこと、探春が耐えられないだろう)、あたしから何かを学んでくれればいい。それから、彼なりの道を見つければいいだろう。
待機生活の間、探春はよく我慢して過ごしていた。
あたしのために料理をしてくれ、お茶を淹れてくれ、ピアノを聞かせてくれた。あたしは室内のジムで運動し、外を走り回りたい気持ちを抑え付けていた。
本当はあたしもヘルメットをかぶって、バイクで外を走りたいのだけれど。それで余計な危険を招いたら、本末転倒だ。
やがて、とうとうジュニアが現れた。前と似たようなバイクに乗って、ヘルメットに顔を隠して、夜の街を走り出した。
ただし、アンドロイドかバイオロイドの替え玉かもしれない。前に待ち伏せを受けて死にかけたのだから、いくら無鉄砲な少年でも、少しは用心しているだろう。
あたしは手を出さなかった。少年は(あるいは様子見の偽者は)二時間ほど走り回ると、誰とも喧嘩せずに引き上げた。
これでいい。少しは安心しただろう。
もう一度待って、次にジュニアが現れた時、あたしは捕獲のための罠を動かした。数台のトレーラーを使い、走るバイクを包囲させたのである。
彼がいい位置に来た時を狙い、粘着弾を撃たせた。
大成功。
ジュニアはバイクごと、速度を合わせたトレーラーの側面に張り付けられた。それから、ジュニアをはさむ配置で、二台のトレーラーが接近した。
ジュニアはおそらく、バイクごと車に潰されるかと思っただろう。精々、冷や汗をかけばいいのだ。そうしたら、少しは知恵がつく。
それから、片方のトレーラーの壁面が開き、回転し、外壁に張り付けになったバイクを、内側へ取り込んだのである。

おふくろは最近、ヒステリーだ。俺がおふくろと呼ぶと、青筋立てて怒りだす。
「リナと呼びなさいって、言ったでしょ!!」
気色悪い。
母親を名前で呼ばせるなんて、異常だ。
おふくろで、いいではないか。ババアと呼ばれるより、はるかにましだろう。
それなのに、
「そんな呼び方したって、返事しないから!!」
まるで小娘みたいにわめく。
護衛を引き連れて外へ出れば、いっぱしの女幹部みたいな顔をしているくせに。
俺も小さい頃は、素直にリナと呼んでいた。リナは世界で一番綺麗で優しくて、賢い女だと思っていた。
それというのも、他に女を知らなかったからだ。
俺が育ったビルや基地の中には、男の護衛や家庭教師や料理人しかいなかった。たまに女を見るのは、リザードの暮らす船や拠点に連れて行ってもらった時くらいのものだ。
そこには男女の職員がいて、口説いたり、いちゃついたり、別れたり、逃げたりの小事件が発生していた。
違法都市に車で連れ出してもらうようになると、バイオロイドの娼婦が客引きをするさまも見られるようになった。
やがて映画や小説のおかげで知恵が付き、自力で動ける範囲が広がってくると、母親に甘えることがいかに恥ずかしいことか、わかってきた。
俺は男だ。
男は独立するものだ。
なのに、リナと呼べだと!?
俺を恋人の代用にしたいのか!?
俺の父親がどんな男だったのか、ろくに話してもくれないくせに。俺がバイクで外を走ることにも、ぎゃあぎゃあ文句をつける。
「走りたかったら、安全な基地内で走りなさいと言ってるでしょ!!」
くだらない。
安全な場所で走って、何の役に立つ。
俺は試したい。自分がどれほど強いのか。勇気があるのか。
銃の腕も空手の技術も、実戦でなくては試せない。三流組織に待ち伏せをかけられたって、俺は切り抜けた。火傷はしたが、そんなものはすぐ治る。
次の戦いが楽しみだ。俺はもっと強くなる。女なんかに、文句は言わせないくらい。
火だるまにされた待ち伏せ事件の後、俺が再びバイクで外出できるようになったのは、リザードがおふくろを説得してくれたからだ。
「リナ、男の子は、いずれ独り立ちしなければならない。きみが抱え込んで甘やかすと、良い結果にはならないぞ」
リザードは組織のボスだから、おふくろの上司ということになる。おふくろは当然、逆らえない。
俺には、父親代わりのような人だった。十五歳の誕生日にバイクをくれたのも、リザードだ。おふくろと喧嘩した後、俺の話を聞いてくれるのもリザードだ。
俺には、本当の父親はいない。
もしかしたら、どこかにいるのかもしれないが、教えてもらったことはない。
おふくろの態度からすると、どうやら、俺とおふくろを捨てた男らしい。あれこれ考え合わせると、気まぐれな風来坊のような奴だろう。一時だけ、おふくろを遊び相手にして、立ち去ったのか。
だが、そんなことはどうでもよかった。
父親なんかいなくても、俺はここまで育った。
問題は、俺がこれから、どんな男になるかだろう。
リザードはいずれ、俺を組織の幹部にしてくれると言う。今はそのための、修行の時期だと。
俺は何人もの家庭教師を付けられ、数学や物理学から、歴史、古典文学、料理やダンスまで幅広く仕込まれた。武道や射撃も仕込まれた。リザードの視察旅行にも、毎年のように連れていってもらった。
もう数年で、そういう基礎教育も終わる。
そうしたら、組織の一番下っ端として働くように、リザードから言われている。いきなり高い地位に就けるのはよくないから、最下層から実力で昇進してこいと。
それに文句はない。
すぐに昇進してやり、いずれはおふくろを追い越すつもりだ。
そうしたら、自分の好きな道が選べる。組織の中に居続けるか、それとも外へ出て、自分の組織を立ち上げるか。
ところがだ。
気がついた時は、走行するトレーラーの内壁に逆さ張り付けだ。標本にされる虫けらのように、粘着剤でバイクごと固められてしまった。
(今度は、どいつの仕返しだ)
これまで、喧嘩して叩きのめした相手はたくさんいる。だから、敵は特定できない。
俺は逆さ磔のまま、車の動きを感じていた。幹線道路から外れ、どこかの地下に入ったようだ。俺を他の車に積み替え、追跡を断ち切るつもりなのだろう。
だが、リザードの組織《フェンリル》は、この都市を支配する《キュクロプス》と親密だ。地下道は全て、《キュクロプス》の監視下にある。俺がどこへ連行されようと、リザードが手を回して助けてくれるはず。
そう思って、ひたすら待った。
いつ、救助の部隊が俺を解放してくれるか。
逆さのままだから、頭に血が集まってきて苦しい。ライダースーツの襟元から侵入した粘着剤のせいで、首の皮膚がひきつれる。無理に動こうとすると、皮膚が裂けて血が流れる。スーツの下の腹や背中もかゆい。
だが、そんなことより恐ろしいことが始まった。
空気が薄くなっている。
呼吸が苦しい。
トレーラー内の空気が、抜かれているのだ。気圧は下がり続ける。いくら俺が強化体でも、酸素がなくては生きられない!!
そうか、これが一番簡単なんだ。
俺を、真空中で干物にすること。
いくら手足に力を入れて引きちぎろうとしても、粘着剤はびくともしない。やがて、気が遠くなってきた。
そうか、これが気絶するということか。小さい頃、木から落ちて、ほんの短い時間、気絶して以来だな。
悔しいが、一つ、いいことを学んだ。
俺は、無敵でも不死身でもなかったんだ。
意識が薄れる中で、リザードの言葉を思い出した。
(きみはまだ子供だ。世の中の厳しさを知らない。成人するまでは、我々の指示に従いなさい)
だが、ここで死ぬなら、成人してから得られる自由には、永遠に届かない。
俺が馬鹿だった。
リザードの保護をあてにして、世間を甘く見ていたんだ。
はっと目覚めた時は、空気と水が一緒くたに気道に入った時だった。
慌ててもがき、水面を目指そうとした。
酸素が足りない。
溺れ死ぬ。
さんざん、がぼがぼ、ばしゃばしゃやって、ようやく、自分のいる場所がわかった。
深いプールの中だ。
俺は気絶したまま、水の中に放り込まれたのだ。
幸いなことに、手足は動く。咳き込みながら、プールサイドまで泳いだ。呼吸さえできれば、回復は早い。
ところが、俺が這い上がろうとした岸には、偉そうな仁王立ちの女がいた。青いミニドレスの上に黒革のジャケットを着た、知らない女だ。
おまけに、俺は素裸にされている。このまま上陸すると、男の弱点が剥き出しになってしまう。
ええい、今更。
俺を裸にしたのは、どうせこいつか、こいつの仲間だろう。
見たけりゃ、見ろ。
俺は水を滴らせながら、プールサイドに立って、女と睨み合った。
俺は百八十センチ近い身長があるが、向こうは、俺とほとんど変わらない大女だ。いや、俺より少し高いかもしれない。
長い金褐色の髪をゆるい三つ編みにして、背中に垂らしている。目は深い青。蜂蜜色の皮膚をした、なかなかの美人だが、いかにも冷酷で高慢そうだ。
どこかの組織の警備隊長か、それともフリーの殺し屋か何かか。
少し離れて控えている、灰色のスーツ姿の優男は、秘書か何かに見える。その背後には、灰色の皮膚をしたアンドロイド兵士の壁。濃紺の制服を着ているが、組織名がわかるような紋章は付けていない。
腰に手を当てた女が、深いアルトの声で言う。
「坊や、お姉さまに挨拶は?」
何を言ってやがる。誰がお姉さまだ。
「おまえが俺を誘拐したのか」
自分で言って、改めて自分で驚く。
俺は、まんまと誘拐されたのだ。《フェンリル》の保護が働かなかったということは、かなりの組織。ここは、その組織の基地なのか?
だが、殺されてはいない。
身代金と交換というわけか。
おふくろは、俺のためなら幾らでも出すだろう。リザードが認める範囲内でのことだが。
それともリザードは、こんな間抜けのことなど見捨てるか? 期待して育てたのに、ものにならなかったと?
「誘拐されたことは、わかっているのね。じゃあ、体内に爆弾を仕込まれたことも、わかるわね」
爆弾?
自分の肉体を見下ろした。どこかに変化があるか? 胸、腹、脚。
あった。左の手首の皮膚の下だ。長さ二センチ程度の、堅いカプセル状のものが埋め込まれている。これが爆弾?
「小型の爆弾だから、周囲の人間には被害を及ぼさない。それと同じものがもう一つ、きみの心臓の横に仕掛けられている。取り出そうとして皮膚を傷つけたら、手首の爆弾は何とかなっても、心臓の方が爆発するよ。いくら強化体でも、大量出血ですぐに死ぬ。すぐ横に、医療カプセルがあって、誰かがそこに入れてくれない限りね」
ふん、そうか。
こんな状況、珍しくもない。中央製の映画では、何度も見ている。主人公は、絶対助かるのだ。
俺の場合はどうやって助かるのか、まだわからないが。
「身代金に、何を要求した。金塊か、プラチナか。それとも技術情報か」
「身代金?」
女は面白そうな顔をする。
「あんたみたいな小僧のために、誰が身代金を払ってくれるの?」
何だと。
俺の母親が誰か、知らないというのか。
最高幹部会直属の代理人、リザードの配下として、一応、辺境では恐れられている存在だぞ。おふくろがトチ狂うのは、俺に関することでだけだ。
「はした金なんか、欲しくもない。それより、あんたはあたしの奴隷になるのよ」
何だって。
「あたしが這えと言ったら、四つん這いになってもらうわ。あたしが舐めろと言ったら、あたしの足の指を舐めてもらう。楽しみでしょ? あたしに触ることを許される男なんて、滅多にいないんだから」
かっとした。
誰がするか、そんな真似。
それが逆の立場になるなら、考えてみないこともないが。
もしかしたら、俺が殺したチンピラが、こいつの関係者だったのかもしれない。だとすると、さんざん侮辱され、痛めつけられてから、殺されるか、洗脳されるか。
さすがに腹が冷えたが、ここでひるんだら、こいつを喜ばせるだけだ。
「ちょっとばかり美人だと思って、図に乗るなよ。そのうち、俺の下でよがらせてやるからな。楽しみに待ってろ」
すると、妙な空白が流れた。
向こうはなぜか、きょとんとした顔をしている。怒るのでもなく、呆れるのでもなく、ただ、予想外、といったように。
俺が何か、場にそぐわないことを言ったのか? 映画で見たように、渋く決めたつもりだったのに?
それともまさか、童貞のハッタリだと見抜かれた!? おふくろの目が厳しくて、リザードの所の侍女にもうっかり手を出せないってこと、知られているのか!?
女は横を向いた。むせるような音を立てて。
何かと思えば、肩を震わせて笑っている。それも、笑いの発作が止まらないかのように、しつこく。
そのうち、むせび笑いが爆笑になった。身を折って、秘書らしき男の肩にもたれている。男の胸を、掌でばしばし叩く。
「ひー、ひー、ああ苦しい。傑作。女も知らないくせに、いっちょまえにさあ」
俺は耳まで熱くなった。
激しく馬鹿にされている。
「もお、嬉しくなっちゃう。出ておいでよ。隠れてないで」
女が呼びかけた相手は、俺ではない。壁際の柱の陰から、別の女が現れた。
こちらは小柄で細い。上品な美人だ。結い上げた茶色い髪に、白い肌。白いドレスに、プールの波紋がゆらゆら反射して青い影ができている。ただし、こちらの顔には笑いの影もない。
「もう、辺境に染まっているわ。殺した方がいいわ」
静かな白い顔で、さらりと恐ろしいことを言う。
ぞっとした。
威張りくさった大女より、この小さい女の方が怖い。俺のことをまるで、つまらない虫けらのように思っている。
なぜだ? 俺が何をした?
こいつらの関係者を喧嘩で殺したのかもしれないが、そんなこと、辺境では当たり前だ。戦って負けた方が悪いのだ。
……ということは、今は俺の方が悪い、ということになるが。
笑いを収めた大女は、むしろ慈悲深いと形容したくなる態度で言う。
「そうじゃないよ。ただのガキの突っ張り。これから躾け直せばいい」
そう言ってくれる大女に、ついすがりたくなる。どうやら、すぐに殺されることはなさそうだ。
だが、聞き捨てならない言葉が含まれていた。
「俺を躾ける、だと!? おまえが!?」
「そう。これまで一応の教育は受けてきたらしいけど、どうやら偏っているみたいだ。まともな男になれるように、あたしたちで教育し直してやる」
つまり、今の俺は、まともな男ではないというのか。まともな男の予備軍でもないと。
「大きなお世話だ!! 何の権利があって、そんなことを決められる!!」
「あんたの父親が聞いたら、あたしたちに頼むと思うな。息子をよろしくって」
俺が唖然とする番だった。
父親だって。
俺の父親が、息子を頼むって?
「俺に、父親なんか、いない……」
声が震えたのが、自分でわかった。情けないことに、膝まで震えだしている。
何度尋ねても、父親がどこの誰なのか、おふくろは教えてくれなかった。リザードも教えてくれなかった。知りたければ、成長してから自分で探せと言われたこともある。もし、単なる人工精子なら、ああいう態度にはならなかったはずだ。
「そうだね。あんたは聞いてなかったんでしょ」
青い目をした女は、どこか気の毒そうに言う。
「あたしたちは、あんたの遺伝子を検査してわかった。あんたの父親は、あたしたちの一族の一人に間違いない」
一族だって。
どこの一族だ。
「だからあんたも、あたしたちの一族の一員というわけ。一族の子供の教育には、あたしたち上の世代が責任を持たなきゃならない。あんたが父親を知らずに育ったんなら、余計にね」
責任。
辺境で、そんな言葉を聞くのは珍しい。
「あたしたちは、あんたの父親の従姉妹にあたるのよ。だから、あんたにとっては、まあ、親戚の叔母さんというところ」
嘘だ。
でたらめだ。
だが、この女たちがそんな嘘をついて、何の得があるのかわからない。
「俺を騙して、手下にしたいんだろ」
精一杯の反抗だったが、穏やかに苦笑された。
「こんな自惚れたガキ、使い物になりしゃしない。もう何年かは、厳しく躾け直さないとね」
俺は突進した。とりあえず、小柄な女を人質に取ろうとしたのだ。爆弾のことは本当だろうが、この場で爆破スイッチは押さない方に賭けた。この大女は、俺を生かして利用したそうだから。
しかし、その手前で大女に足をひっかけられたと思ったら、床に転がる手前ですくい上げられ、高く投げ飛ばされた。
まさか、この俺が。
この大女は、もしかして、俺より強い!?
俺は、おふくろやリザードの護衛の誰より強いのに!?
俺は大きな放物線を描いてプールに落下し、派手な飛沫を立てた。態勢を立て直してから水面に顔を出したら、女たちは兵の壁に囲まれ、もう去りかけている。
後には黒髪の優男が残っていて、プールサイドに泳ぎ着いた俺に、白いバスローブを差し出した。床には、サンダルも揃えてある。
「お部屋にご案内します、ジュニア」
それがどうやら、俺の呼び名らしいのだ。そういえば、あの女たちは、名前も名乗っていかなかった。
「わたしはナギと申します。何十体もいるアンドロイドの一体ですから、あなたが叩き壊しても支障ありません。壊さないで下さるなら、あなたの身の回りのお世話をいたします」
機械の召使なんか、八つ当たりで壊しても意味がない。
壊さないと約束すると、ナギと名乗ったアンドロイドは、俺を通路に連れ出した。
ここはどうやら、どこかの地球型惑星にあるリゾートホテルらしい。
窓の外には、波を立てた冷たそうな青い海と、いじけた緑の生えた灰色の海岸線が見えた。
意識のないうち、こんな所まで運ばれていたとは。
ここは大陸から離れた孤島で、島にある唯一のホテルは、俺たちが占有しているという。
俺を捕まえた女たちには、しっかりした背景があるらしい。何しろ《フェンリル》の警備網を破って、俺を拉致してのけたのだから。
おふくろは今頃、半狂乱で俺を捜させているだろう。それとも、父親の側の人間に、俺を拉致された可能性を考えているだろうか?
もしかしたら、本当は父親などどこにもいず、培養工場か実験室で組み上げられた人工遺伝子から誕生したのかもしれない、と考えたこともあるのだが。
俺はあてがわれた部屋で風呂に入り、じっくり温まりながら考えた。
もし、あの大女の言うことが本当なら……彼女たちが、俺を仲間に引き込もうとしているのなら……しばらくは、様子を見てもいいかもしれない。
わかるかもしれないのだ。俺の父親のことが。どんな奴なのか、まだ生きているのか、どこにいるのか。
そんなこと、わざわざ突き止めようとは……あまり、思っていなかったが。
風呂から上がると、鏡で自分をまじまじ見た。捕まった時にできた傷は、もうほとんど治っている。
黒髪、黒い眉、黒い目。黄みがかった浅黒い肌。
我ながら精悍なハンサムで、格好いいと思う。
リザードの所の女たちが、俺をちらちら見たり、遠くでくすくす笑っていたりしたのは、俺が一人前になったら口説こう、と思っていたからだろう?
背はまだ伸びるし、筋肉ももっとたくましくなるだろう。毎日、鍛えているからな。
おふくろは俺のことが自慢でならず、何かといえば、恋人のようにべたべたまとわりついてきた。
仕事の上では十分、有能で冷徹なのに、俺のこととなると、溺愛を反省しないのだ。
リザードが制止してくれなかったら、今でもまだ、俺を自分のベッドで寝かせようとしていただろう。
俺はもう、十五だぞ。
昔なら、元服している歳だ。
正しい母親なら、俺を独り立ちさせようとするはずではないか。
それならば……俺を甘えたガキだと断定し、躾け直すと宣告したあの大女の方が、まだ健全なのではないか?
用意されていた服を着ると(シンプルで上質だった。あの女たち、俺の好みがわかっているらしい)、居間からバルコニーに出てみた。
この部屋は、建物の三階の位置にある。建物のすぐ下は、切り立った崖と狭い砂浜。海から吹き上げてくる風が冷たい。冬に近い気候だ。しかし、おかげで頭が冴える。
おふくろはやはり、俺の父親に捨てられのか。
わかる気がする。べたべた甘えまくって、男をうんざりさせるタイプだからな。
捨てられて悔しくて、その分、親父そっくりの俺にまとわりついていたわけか。
俺を母親べったりのマザコン息子に仕立てたら、たぶん、おふくろの勝ちなのだ。
自分を捨てた男への、復讐のようなもの。
その想像は、過去にもしてきた。だが、確証がなかった。
今は、その想像の輪郭がはっきりしてきた感じだ。
だから、もしかしたら、これはチャンスなのかも。
リザードの部下になるのも悪くはないが、それでは、おふくろの影響下から抜けられないし、先が見えすぎていたからな。
これが何かの罠だとしても、乗ってみるのは面白いじゃないか。
山盛りのハンバーガーとコーヒーの差し入れを運んできたナギが、説明してくれた。
「この島の中でしたら、自由に歩かれて構いません。水泳も、沿岸ならばご自由に」
いや、この冷たそうな海で、長時間泳ぐ気はしない。泳いで逃げ出す気もないし。どうせ、途中で捕まるだろ。
「お食事は、ここへ運ぶこともできますし、下の食堂においでになっても結構です。とりあえず、自由にお過ごし下さい。着替えなど、必要なものは揃えてございます。足りないものがあれば、お申し付け下さい」
客人待遇の囚人か。
いいだろう。体内の爆弾があるから、無茶をするつもりはないが、散歩やランニングくらいはできるだろう。
翌朝、俺はまだ暗いうちに叩き起こされた。
「おいで、一緒に走ろう」
昨日の大女が、髪を一つに束ね、ジョギング姿で俺を待っている。彼方に見える岬の突端まで走って、戻ってきてから朝食にするそうだ。
追い立てられるようにして、ベッドから出た。いつもは裸で寝るのだが、用心のため、下着を着ていてよかったと思う。ナギが出してくれたトレーニングウェアを着て、ランニング用のシューズを履く。
海岸を走るのはいいが(昨日のうち、走って島を一周してきて、様子はわかっている。他に建物は一軒もない)、なぜ、この女の後に付いていかなけりゃならないんだ。
(見てろよ。本気で走ったら、どれだけ速いか)
俺は女を追い越し、前に出た。
快調だ。
顔に冷たい風を受けるのが、気持ちいい。
左手首と、心臓の横に仕掛けられた爆弾のことは、今は気にしない。俺が脱走や反抗をしなければ、それでいいのだろう。
岬にさしかかると砂浜は消え、波の打ち寄せる岩場になった。俺は岩から岩へ軽く飛び移り、突端を目指した。振り向きはしなかったが、女は、はるか後方に置き去りにしてきたはずだ。
ところが、岬の突端で振り向くと、女は、すぐ後ろに付いてきているではないか。そして、にやっと笑うと身を翻し、
「追い越してごらん!」
と言い残し、彼方のホテル目指して走っていく。
そんな馬鹿な。
俺は最高水準の強化体だ。
おふくろもリザードも、そう言っていた。さすがに銃弾には勝てないが、素手の戦闘なら、戦闘用アンドロイドだって叩き壊せる。
俺は本気で走った。岩から岩へ、最短距離で飛び移った。砂浜でも、疾走した。
なのに、前を行く女に追いつけない。
そんなことがあるのか。何かインチキがあるんじゃないのか。
追い付けないどころか、どんどん引き離された。
信じられない。
いや、待てよ。
もしかしたら、俺は自分で思っていたほど、たいした強化体ではないのか。おふくろやリザードは、俺を世間知らずのままにしておきたかったのか。
冗談じゃないぞ。
甘やかされて自惚れていたなら、大馬鹿だ。
俺が汗をかいてホテルに帰り着いた時には、大女は涼しい顔をして、海に面したサンルームで朝食のテーブルに着いていた。
小柄な女が料理を並べ、コーヒーを注いでいる。少なくとも、食べ物は潤沢にある。
「お腹空いたでしょ。そこへお座り。食事したら、勉強見てあげる」
と大女。
俺はかっとした。まるきり、子供扱いか。
しかし、空腹には勝てない。とりあえず、再勝負は食ってからだ。
席に着くと、ナギが給仕してくれた。トースト、パンケーキ、ベーコンエッグ、ソーセージ、海藻サラダ、ヨーグルト、果物、コーヒー。
俺も大食いだが、この大女も負けずに食うとわかった。かなりの強化体だ。甘く見るのは大間違いだと、ようやく腹に落ちてきた。
俺が脱走するとしても、こいつより強くなってからでないと、とても無理そうだ。
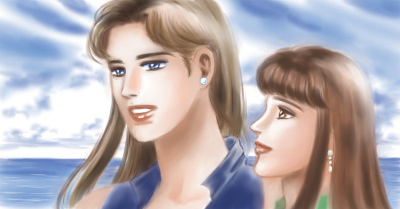
その後、俺に数学や物理や歴史などの試験問題を解かせ、採点し、新たな課題を出して寄越したのは、小柄な女の方だった。いかにも厭そうな、冷ややかな態度のまま。
子供が嫌いなのか、それとも俺個人が嫌いなのか。
「あなたの年齢なら、一日にこれくらいの量はこなせるでしょう。明日の朝食後に、また試験をします。合格したら、次の課題を出しますからね」
顔は綺麗だし、態度は上品だが、おかげで一層冷たく見える。性根が意地悪なのだろう。もし、今日中にこの課題をこなせなかったら、俺が馬鹿か怠け者みたいな言い方をする。
これならまだ、あの大女の方がましだ。
悔しいから、猛然と課題に取り組んだ。かなり高度な内容だ。本気でかからないと、終わらない。
夕方になって、やっと勉強から解放されると、俺は海岸に出た。
もう一回、走っておこう。これまであまり、砂地や岩場を走ったことがなかったからな。
明日も競争させられるなら、今度は負けない。少なくとも、今日よりは差を縮めてみせる。
岬まで走って戻ることを三回繰り返すと、ホテルの下の砂浜に大女がいた。俺を待っていたのか。
「負けず嫌いはいいことだわ」
と笑っている。
昼食時と同じ、紺のハイネックシャツとグレイのスパッツ。それに、革のジャケットを羽織っている。長い髪は束ねず、海からの風にそよがせている。客観的に見れば、かなりのいい女。
気に入らないのは、俺を〝可愛い子供〟みたいに見る点だ。
俺がこの女より強くなるには、あと何年あればいいのか。
「あのな、俺はまだ、あんたの名前を聞いてないぞ」
「あら、奇遇ねえ。あたしもまだ、きみの名前を聞いてないわ」
「俺のことは、とっくに調べたんじゃないのか」
「残念ながら、《フェンリル》がきみの後ろ盾だとわかっただけ。偶然、きみの姿がこちらの監視映像の中に映ったので、急いで飛んで来たのよ。きみの姿は、きみの父親そっくりだから」
そいつの名前は、シヴァだという。それだけは、俺に知る権利があると断言された。
シヴァ。
地球時代の神話に出てくる、神の名前だ。
そいつが本当に、俺の父親なんだろうか。おふくろとは、どの程度の期間、付き合っていたのだろう。
おふくろの態度からすると、相当、険悪な別れ方だったに違いない。
「きみの父親とあたしは、遺伝子的にかなり近いのよ。だから、あたしときみも、骨格が似てるでしょ」
そうかもしれない。男と女の違いはあるが。
「だけどあんたは、俺より強いな。俺より進歩した強化体なのか」
女に負けたと認めるのは悔しかったが、事実を否定しても始まらない。この女はおそらく、辺境で長い年月生き抜いてきた戦士だ。
「ううん。そうじゃない」
あっさり否定された。
「もう数年もすれば、きみの方が強くなるわ。ちゃんと修行をすればね。今はまだ、正しい修行を積んでいないだけ」
何だって。
俺はこれまで、最高の教育を受けてきたはずだ。
学問はもちろん、空手や剣道の修業もした。射撃だってできる。
実戦に関しては、確かに、最近、自己流で始めたばかりだが。
「あたしの指導を受ける気があるのなら、基礎から叩き直してあげるわ」
その言葉には、ただの〝親切〟しか含まれていない。砂浜に、がくりと膝を着いてしまいそうだった。
俺は、辺境の水準では、まだひよこクラスなのか。
「男なんだから、戦うことには、あたしより向いているはず。あたしには、戦闘の技術はあるけど、肉体そのものの強さは、きみの方が上よ」
大女の言葉が、ゆっくりと染みてきた。
素質はある、と言うんだな。
努力さえすれば、この女に追いつき、追い越せると。
「本当は、きみの父親がきみを鍛えてやるべきなんだけど、行方不明だから仕方ない」
希望が湧いてきた。反発もあるが、それより、強くなるのが優先だ。行方不明の父親なんか、どうでもいい。
「あんたの弟子にしてくれるってことか?」
女はにやりとした。
「お師匠さまに対する礼儀は?」
う。
礼儀を守らないガキと思われたら、この海に叩き込まれるのは間違いない。食事を抜かれるかもしれない。
「お……俺を、弟子に、してください。お師匠さま」
「よろしい」
くそ。今に見てろ。
俺は強くなる。
でないと、何も始まらない。
「あたしのことは、リリーと呼びなさい。本名じゃないけど、あんたはそれを知らない方がいいのよ。いずれ、《フェンリル》に戻るかもしれないんだし」
まあ、それは構わないが。
もう一人の小柄な女の方は、ヴァイオレットだという。
何か、どこかで聞いたことがあるような気がするが。
どちらも、女としてはよくある名前だ。
「リリー叔母さん、じゃないのか?」
と言ったら、大女は憮然とする。
「叔母さんと呼ばれると力が抜けるから、やめてちょうだい」
そういう点、何だか子供みたいだ。豪華な美人なのに。
「年増のくせに、年増だと認めたくないんだな」
小声でつぶやいたのに、速攻で、ごちんと頭に拳固をくらった。俺に逃げる隙を与えず拳固を命中させるなんて(しかも手加減して)、確かにすごい。
「礼儀作法は?」
「し……失礼しました。リリー……お姉さん、で、いいですか?」
「ただのリリーでいいわよ」
大人げない叔母さんだ。
しかし、頭をさすりながら、何だかひどく懐かしい気分になった。おふくろにもリザードにも、こんな真似をされたことはないのに。
リザードは冷静な書斎派で、俺にはいつも、静かに話をするだけだ。部下たちはみんな、その静けさを恐れていたし。
さて、俺はどう名乗るべきか。
本当の名前は、ごく親しい間柄だけで使うものだと、おふくろに言われて育った。リリーはある程度、信用していい相手だと思うが、今はまだ、本当の名前は言いたくない。
「俺は、ジュニアでいいよ。あんたたちにとっては、シヴァ・ジュニアなんだろ」
するとリリーは、長い髪を後ろに払って言う。
「別にあんたを、シヴァの代わりにしようとは思ってないけどね。あんたはあんたで、一族の役に立ってくれればいい。というより、それ以前に、あんたが何をしたいかによるんだけど。あんた、将来の夢とかあるの?」
俺が将来、何をしたいか?
それはまだ、よくわからない。
そもそも、俺に選択肢なんて、あるのか?
辺境では、戦って勝ち残る、それしかない。
どうやって戦うか、その方法を探ろうと思っていただけだ。
「俺はずっと《フェンリル》の中で育ったんだ。おふくろは、リザードの部下だから。俺としては、組織の中で出世して、いずれはナンバー2になる……つもりだった。これから《フェンリル》に戻れるなら、の話だけど。もしかしたら、独立の方向に行くかもしれない、とも思ってた。リザードのことは尊敬してるが、永遠に部下で満足かと言われたら、そうでもない」
空はもう暮れて、暗い紺碧になっていた。その中に、無数の星が輝き始める。あの星のどこかにおふくろがいるのだが、俺がここにいることを知らせる術はない。
やがて、リリーが言う。
「じゃあ、ジュニア、とりあえず、あたしとヴァイオレットの下で修行をしなさい。それが一段落したら、次を考えましょう」
一緒にホテルへ戻りながら、俺は確認した。
「リリー、あんたたちも、俺の父親の居場所を知らないのか?」
「そう。ずうっと捜してはいるんだけど、見付からないの。あたしとしては、きみが何か知らないか、期待していたんだけどね。でもまあ、少なくとも、きみの母親と出会った時には、生きていたんでしょ」
どうやら、ろくでもない男のような気がしてきた。
せっかく気にかけてくれる一族がいるのに、音信不通のまま、宇宙のどこかをさすらっているなんて、ひねくれすぎだ。
おふくろも決して、いい思い出を持っていないようだし。
「おふくろは、何も教えてくれない。教えたくないみたいだ」
「言いたくない事情があるんでしょうね」
いつか、俺が一人前の男になったら、教えてもらうことができるのだろうか。それとも、親父本人に、出会うことができるのだろうか。
夕食のために食堂に降りると、驚いた。
リリーは青紫のロングドレスで、ヴァイオレットは淡い金色のドレス。二人とも宝石のネックレスを巻いて、イヤリングを下げ、それがきらきら輝いている。
誰か客でも来るのかと、あたりを見回してしまった。リリーが苦笑して言う。
「ジュニア、あんたの部屋にもディナージャケットがあるよ。着替えてきなさい。今度から、夕食は正装でね。それが、一族のしきたりだから」
昨夜は部屋で食べたから、わからなかった。どうやら、旧家みたいな一族らしい。
俺のところでは、おふくろがいつも忙しかったからな。わざわざ夕食のために着替えるなんて、なかった。たまに、リザードに招かれての会食の時だけ、正装したくらいだ。
急いで着替えてきて、夕食の席に着いた。
ナギが何体か静かに動いて、給仕をしてくれる。叔母さんたちはワインを飲んだけど、俺はレモン水だった。いずれ成人したら、酒の飲み方も教えてやるという。
「あんたの肉体は、もうアルコールの悪影響を受けないと思うけど、精神の方は、まだ子供だからね。酒を習慣にするのは、もっと後でいい」
とリリーが言う。それは別にいい。リザードからも、早いうちに酒を覚えるのはよくないと言われていたし。
料理の間は、普通の世間話だけだった。
中央の何とか議員がどうしたとか、どこの会社が合併したとか、市民社会で流行りのサバイバル・ゲームとか。
市民社会のことは、よく知らない。中央でヒットした映画は、辺境でも話題になるから見るが、それだけだ。学校とか遊園地とかお祭りとか、特にうらやましいとは思わない。
しかし二人とも、市民社会に詳しいらしい。あの議員が引退して後継がどうだとか、どこの会社の経営が傾いているとか、学界で話題の新説とか、軍の人事がどうとか、見てきたように語る。
もしかしたら、辺境で独立して生きるためには、中央のことにも詳しくないといけないのかも。
確かにリザードからは、教養が大事だと言われてきたし。
もっと個人的な会話になったのは、デザートが出てからだ。
「ジュニア、修行が一段落したら帰してやってもいいけど、《フェンリル》は違法組織の一つに過ぎないよ。有力組織ではあるけどね。もっと広い世界を見たくないの?」
とリリーが言う。
「世界なら、見てきたよ。リザードのお供で、あちこち回った」
開発途中の地球型惑星とか。建設中の小惑星工場とか。組み立て中の戦闘艦とか。
「でも、きみが見たのは辺境だけでしょう」
「当たり前だろ。中央には入れないんだから」
「なぜ当たり前なの?」
俺は最初、リリーが馬鹿なのかと思った。
人類の文明は、何百年も前に二つに分裂して、それぞれ独自に繁栄している。
人権を守る市民社会。何でもありの辺境。
人体改造を認めない市民社会。自分で自分を進化させていく辺境。
奴隷制度を認めない市民社会。バイオロイドを製造して使い捨てる辺境。
二つの世界は相容れない。
しかしリリーは、その現状に疑問を持てと言いたいらしい。なぜ、文明は分裂したままなのか。融和は不可能なのか。
「例外がいるのは知ってる。〝リリス〟だろ」
悪党狩りのハンター。辺境生まれの強化体なのに、市民社会の側に付いた。
彼女たちの活躍を元にして、しょっちゅう新作の映画が作られるから、厭でも知ることになる。
女のペアとして描かれることが多いが、映画によっては女三人組のこともある。
それに、アンドロイド美青年のお供が付いている。
そう、そこのナギのような奴……
「辺境生まれなのに、連邦政府に雇われてハンターをやってるなんて、どこの物好きか知らないけど。リザードが、何回も仕事を邪魔されたことがあるって言ってた……」
俺は危うく、デミタスのカップを取り落とすところだった。
コード名は、リリーとヴァイオレット。
リリーは長身の美女で、戦闘の天才。パートナーのヴァイオレットは、小柄で可憐に見えるが、冷静な作戦参謀。
俺は古風なランプの明かりの下で、まじまじ二人を見た。宝石のイヤリングを下げ、和やかにデザートを楽しんでいる二人を。
「あの……?」
「やっと、わかったらしい」
リリーがリキュールのグラスを持ったまま、微笑んでヴァイオレットに言う。
「相当、鈍いわ」
と冷ややかなヴァイオレット。
仕方ないだろ。〝リリス〟の実像は不明で、映画は脚色されまくりなんだから。
「あんたたちが〝リリス〟なのか!?」
「そういうこと」
くそ、力が抜けた。
だったら、俺を捕まえられても不思議はない。
「それじゃ、俺の親父も、あんたたちと同じ側なのか……市民社会の味方?」
そうだったら、ちょっとは尊敬する……かもしれない。
「それはわからない。シヴァは若いうち一族から出ていって、それきりだから」
そうか。あてになりそうもない奴だな。
「でも、生きているなら、あたしたちの味方になってくれると思うよ。シヴァはね、ヴァイオレットが好きだったんだ」
この冷たい、気取ったフランス人形みたいな女が!?
「どこがよくて、好きになったんだ!?」
リリーはこちらを睨みつけ、俺は慌てて背筋を伸ばす。
「失礼しました、お師匠さま」
おかげで、拳固を受けずに済んだらしい。
「よろしい。ヴァイオレットも、あんたのお師匠さまだからね。勉強を教わるんだから、いい子にするんだよ」
よくわかった。どちらの女も、怒らせたら怖いということが。
しかし、それにしても、ヴァイオレットは食事の間中、ほとんど俺に話しかけてこなかったが。
あからさまに、俺を嫌っていないか?
俺の疑問が顔に出たのか、リリーが言う。
「子供の頃のシヴァは、よくヴァイオレットに意地悪してたからね。虫や蛙を投げるとか、ドレスに泥団子をぶつけるとか。まあ、男の子にはよくあることでね。好きな女の子に、振り向いて欲しいらしい」
なんて馬鹿な子供だったんだ、俺の親父は。
好きなら好きで、もっと違う態度があるだろう。
「俺は、違うよ。わざわざ人に、泥団子ぶつけたりはしない」
そこで、ヴァイオレットが冷ややかに言う。
「ただ、繁華街で暴れ回るだけよね」
ほら、やっぱりだ。俺を嫌ってる。
リリーが笑って言った。
「それは、あたしもやったことだよ。力試しをしたいんだ。ジュニアにはこれから、あたしが正しい力の使い方を教える。そうすればきっと、役立つ男になるはずだ」
ほっとした。嬉しかった。
この人は、俺に期待してくれている。天下の英雄が、俺のために時間を割いてくれるんだ。
「そう願うわ。さもないと、わたしたちが責任をとって、この子を始末することになるでしょうから」
俺が凍りついているうち、ヴァイオレットは席を立った。
「ごちそうさま。おやすみなさい。また明日ね」
呆然として見送っていたら、リリーが俺に合図した。俺が横の席に移ったら、声を低めて言う。
「あんたを引き取ることに、ヴァイオレットは反対だった。だから、態度が冷たいのは仕方ない。我慢しなさい。それも修行だと思って」
俺が不服な顔をしていると、リリーは更に声を低めて言う。
「問題は、あんたじゃなくて、あんたの父親なの。ちょうどあんたくらいの年齢の時に、シヴァがヴァイオレットに何かしたらしい……ということなんだ」
「何かって?」
リリーはじっと俺を見て、俺がどのくらい馬鹿か、推し量るような顔をする。
「若い男がやりそうなことで、その後、女の側に一生、心の傷が残るようなこと」
俺はショックを受け、沈黙した。
腹にずしんと、重いものを詰め込まれたようだ。
そういうわけか。
俺がしたことではないのに、ものすごく気持ちが沈んでしまった。
それでは、俺の父親は、まったくどうしようもないチンピラだったのではないか。だから、おふくろも、思い出を口にしないのだ。
いや、待てよ。まさか、まさか俺も……強姦の結果、できた子供じゃないだろうな。
頭の中が混乱した。
それにしてはおふくろは、俺をべたべたに可愛がってきたじゃないか。それとも、あれは、マイナスの思い出を打ち消したい反動だったのか。どんなにひどい男でも、子供に罪はないと。
何度も言葉を捜してから、やっとのことで質問した。
「じゃあ、ヴァイオレットは、俺のことも憎いんだな……もしかしたら、俺の食べ物に毒を入れたいくらい?」
「さすがに、それはしないと思うけど」
思う、だけかよ。
「あんたを見るだけで辛いのは、わかってやって。本当は、優しい性格なんだから」
そうかあ?
「あたしのわがままに付き合って、何十年もハンター稼業に付いてきてくれるんだからね」
優しいのはあんただ、と思った。
傷ついた相棒のことはもちろん、行方不明の俺の親父のことも、敵対する違法組織で育った俺のことも、まとめて心配してくれる。
だからだ。ハンターとして戦い続けて、世界の人々から尊敬されているのは。
本当に強いってことは、心底から優しいってことなんだ。
親父のことは、いったん脇にのけておこう。おふくろにも、しばらく我慢してもらおう。
俺は当面、この人について修行する。
そして、一人前の男になる。
そうしたら、きっと、進むべき道が見えてくるだろう。
その晩は、何時間も眠れずにいて、とうとう夜中の海岸に降りていった。真っ暗な中で波打ち際を歩き、冷気の中、降るような星空を見上げて考える。
あの星々のどこかに、俺の父親は隠れているのか。
あっちこっちで気に入った女を強姦して回り、子供を生ませるような奴なのか。
それじゃあ本当に、人間の屑じゃないか。
俺をその屑に似せないようにと、おふくろは必死だったのかもしれない。俺にいいものを見せ、いいもので取り囲み、時間があれば手料理を食べさせてくれ、これ以上はないというくらい俺を甘やかした。
リザードが時々、おふくろを制止してくれなかったら、俺はただの甘ったれの馬鹿息子になっていただろう。
いや、相当に馬鹿だった。街をバイクで走って、手当たり次第チンピラに喧嘩を売って、いい気になって。
これまでは幸運にも、本物の戦士にぶつからなかっただけだ。
最初にぶつかった強敵が〝リリス〟で、本当によかった。さもなければ、死体になって転がっていたところだ。
俺は服を脱いで暗い海に入り、ひとしきり泳いだ。海水はしびれるほど冷たかったが、おかげで頭がすっきりした。
俺は、親父のようにはならない。
もっと、ずっと、まともな男になってみせる。
おふくろには、いずれメッセージを届ければいい。しばらく修行の旅に出るから、心配しないでくれと。

「楽しそうね」
探春に厭味を言われた。
本人は厭味のつもりだろうけれど、あたしはちっともこたえない。事実、楽しいからだ。
子供を育てるって、こんなに楽しいことだったのね。
赤ん坊の頃から育てれば、苦労もあれこれあって、楽しいばかりではないのだろうけれど、あたしはいきなり、半完成品を引き取ったからなあ。
ジュニアはいっぱしの青年のつもりで大人ぶり、格好つけているけれど、十五歳の男の子なんて、まるっきり子供である。
あれもまだできない、これもまだだめ、と実地にわからせてやると、顔を赤くして悔しがって、一人でこっそり勉強したり、夜中まで練習したりして、可愛いったら。
あたしは空手を教え、剣道を教え、ナイフでの格闘術も、獲った魚や獣の捌き方も教えた。料理もさせた。目をつぶったまま、気配を頼りに戦うことも教えた。手作りの弓矢での狩り、草木で簡単な寝場所を作ること、小石と枯れ枝で火を熾すことも。
負けず嫌いの意地っ張りは、シヴァそっくり。
この子の母親が溺愛していたらしいのも、わかるなあ。
それはどうやら、シヴァ本人を逃がした反動のように思えるけれど(子供が出来たことを知ったら、いくらシヴァだって、逃げっ放しにはしないだろう)、どうやら近親相姦ぎりぎりの可愛がり方だったらしいので(ジュニアは十歳を過ぎてもまだ、母親のベッドで寝ていたとか!)、救い出して正解だったと思う。
昔なら元服の年頃なのだし、そろそろ母親から離れてもいいはず。
正確に言えば、ジュニアはシヴァの息子というより、クローンだ。
遺伝子検査の結果、シヴァ本人の遺伝子と、ほとんど変わらないことがわかった。
リナという女は、シヴァの細胞を手に入れ、それを使って子供を作ったのだ。
自分の遺伝子も混ぜたようだが、それはほんの気持ち程度。強化体の遺伝子を、下手に常人の遺伝子と混合しては、危険だからだ。
ジュニアがシヴァそっくりに育っているのも、クローンならば不思議はなかった。
遺伝子の発現には環境が影響するが、どちらも最高の生育環境を与えられたのだから、元のシヴァ同様、ジュニアの遺伝子も十全に発現した。
リナを庇護しているリザードというのは、最高幹部会の代理人の一人、すなわち辺境の超エリートだ。
シヴァとどんな関係があったのか知らないが、彼も色々、働いたり戦ったりしているのだろう。シヴァのクローンを育てれば、組織のために役立つと、リザードは思ったのではないか。
「好きにすればいいわ。どうせあなたは、いつでも自分の意志を通すんだもの」
探春はそっぽを向いて言うが、それでも辛抱強く、ジュニアの教師役を務めてくれていた。
本人もこれまで、母親の元で最高の教育を受けてきたようだが、まだもう少し伸びる余地がある。
ジュニア本人に何の罪もないことは、探春もよくわかっているのだ。ただ、彼があまりにもシヴァの少年時代そっくりなので、辛い記憶を刺激されるだけ。

一族が所有するリゾート惑星の離れ小島で、あたしたちはしばらく穏やかに暮らした。
あたしがジュニアに格闘技や射撃の稽古をつけ、探春が勉強を見る。
料理も掃除も洗濯もさせる。一緒に映画も見る。散歩もピクニックもサイクリングもする。
手首の爆弾は早々に取り去ったし、心臓の近くには、元々何も埋めてはいない。
あたしたちにとっても、思わぬバカンス。
あたしとジュニアが砂浜で走ったり、空手の稽古をしたりしている時、頭上の窓からはよく、探春の弾くピアノのメロディがこぼれてきたものだ。
夕食には正装で臨み、政治や経済の話をする。
その話題についていけないと悟ると、ジュニアはこっそり勉強して、知識を増やす。
あたしたちが〝正義の味方〟だと納得すれば、ジュニアはあっさり脱帽して、素直な弟子になった。
元が単純だから、何事にもストレートに反応してしまうのだ。
おかげでかなり、彼の育った《フェンリル》の内情がわかってきた。リザードが彼に期待をかけ、未来の幹部候補生として、自分の仕事に連れ歩いていたことも。
もちろん、こうしてジュニアの面倒を見るのは、ほんのしばらくのことだ。あたしたちはいずれ、仕事に戻らなければならない。
でも、その頃には、ジュニアも自分で決められるようになっているだろう。自分がこれから、どちらへ向かって歩いていくか。
《フェンリル》に戻って幹部を目指すも、あたしたちのように、市民社会の側に立つも、彼の自由だ。
先でいずれ戦うことになったとしても、それはやむを得ない。
もしかしたら、あたしたちの方こそ、歴史の流れに逆らっているのかもしれないのだから。
シヴァ・ジュニアを捕えたことを、あたしは《ティルス》にいるヴェーラお祖母さまに、事後報告だけして済ませた。遠距離の通信は傍受される危険があるので、ナギに手紙を持たせたのだ。
「あなたはまた、相談もなしに勝手なことをして」
と返信で叱られたが、それは覚悟の上。
事前に相談したら、止められるに決まっていた。一族の総帥であるお祖母さまも、最長老である麗香姉さまも、シヴァのことについては、最初から冷淡だったではないか。
あたしが何度捜索を頼んでも、
『捜させていますよ』
とだけ答える。そうして何年経っても、居場所は掴めないと言うだけ。

司法局に頼まれた潜入任務を一つ片付けると、あたしはジュニアに、グリフィンの懸賞金リストに載せられた女性政治家、ライサ・レイン議員の警護役を命じた。
これまでは通常の護衛チームが付いていたのだが、先月、その警備をかいくぐった刺客がいて、危機一髪の危ない目に遭ったばかりだったから。そこで司法局としては、しばらく警備を強化することになったのだ。
もちろん〝リリス〟に依頼された仕事だが、あたしが仕事の一部を弟子に任せても、司法局に文句を付けられるいわれはない。文句を言うなら、任務そのものを返上するだけだ。あたしと探春は、少し離れて見守ることにする。
「紅泉、男の子に女性の警護は無理よ」
と探春は反対したが、そんなことはない。
シヴァは女扱いが弱点だった。この子は、そういう弱点を持たない方がいい。
幸い、母親に甘やかされて育った坊やだ。どうしたら年上の女性が喜ぶか、怒るか、ちゃんと心得ている。
「いいこと。仕事なんだから、あんたの感情は引っ込めておきなさい。二十四時間、ひたすら番犬に徹すること」
とジュニアに厳しく言い渡した。
その上で、警護対象のレイン議員には、こう話した。
「男だと思わなくていいです。あなたの犬。ただの番犬。だから、着替えの時でも、お風呂の時でも、部屋の隅に置いておいて大丈夫です。眠る時も、ベッドの足元で転がしておいて大丈夫。殺しても死なないくらい頑丈だから、休憩も休日も要りません。注意散漫になっていたら、水をぶっかけても、蹴り飛ばしても結構です」
横に立って聞いていたジュニアは、不満げな仏頂面だったが、散々、躰に教え込んだので、師匠に逆らわないという覚悟はもうできている。黙って議員に頭を下げた。よろしい。
「まさか、ベッドの足元で寝かせるなんて」
と品格ある女性議員はためらう。
「もちろん、衝立てくらいは置いてもいいですよ。外出先でトイレに入る時でも、ドアのすぐ外で待たせて下さい。何か失敗したら、頭を叩いて躾けてくれて構いません」
彼女は不安げにジュニアを見た。図体は一人前で、地味なスーツを着せてはいるが、顔はまだ幼い。
「ミス・リリー、あなたが護衛して下さるわけにいかないの?」
「あたしも、弟子を育てなければならないんです。いつか、あたしが死んだ時、あるいは引退した時、次の世代が準備できていないと困る。どうか、新米を育てるのに協力して下さい」
それで、彼女は納得してくれた。さすが、懸賞金リストに載る人物だけのことはある。
辺境の宇宙を支配する〝連合〟の最高幹部会は、市民社会の弱体化を図るため、議員や軍人や科学者など、重要人物に懸賞金を懸けている。
その懸賞金制度の統括者は、グリフィンという名で知られているが、実際には、そういう特定の人物が存在するのか、それとも単なる持ち回りの役職名なのか、わからない。
ただ、これまであたしたちは、そのグリフィンにそそのかされた暗殺者やテロリストと、しばしばぶつかってきた。
ジュニアもまた、そういう連中と戦う中で、自分を鍛えていくだろう。
ジュニアはそれから毎日、付ききりでライサ・レインの護衛役を務めた。
出会う人間を警戒し、常に議員の盾となる位置にいる。彼女の口に入る食べ物は、自分で毒味する。議会にも、政財界のパーティにも、視察旅行にも付き添う。毎日、あたしたちに報告を入れる。
使い走りとして、ナギを二体付けておいたから、それでまず不自由はないはずだ。
もちろん、通常の護衛チームも、その外側に付いている。議員の行く先は二重、三重に調査され、警戒される。遠距離からの狙撃や、爆弾、毒ガスなどに対処することは、彼らの領分だ。
彼らの警備網を突破する刺客がいても、最後にジュニアが仕留めればいい。
彼の戦闘センスは文句ない。小石一つ、テーブルナイフ一本で、大抵の敵は止められる。
周囲の市民に巻き添えを出さないように配慮できたら、なおいい。
まあ、それはもっと経験を積んでいくうちに、注意できるようになっていくだろう。
そういう日々の中、レイン議員はとある大学に呼ばれて、講演会に行った。ジュニアは初めて大学のキャンパスを歩き、学生たちの楽しそうな様子を眺め、その活気に感動したらしい。
夜になってあたしに報告してきてから、ぼそりと言った。
「俺、いつか、大学に行けないかな」
「へえ?」
「少しでいいんだ。数か月とか」
「おやおや、ずいぶん遠慮深いこと」
あたしはからかった。
「可愛い女の子でもいたかな?」
「そんなんじゃない」
ぶすっとしているが、いいことだ。何か、したいことができたなら。
「いいよ。この仕事が終わったら、好きな大学に通えるように手配してあげる。何年いてもいいよ。それも修行だからね」
「本当か!?」
顔がはっきり明るくなった。そこは、シヴァよりずっと素直だ。母親に愛されて育ったからだろう。
「あんたに嘘なんかつかないよ。で、何を勉強したいの?」
「う、まだわからない。これから考える。でも、大学に入りたいんだ。学生になりたい」
「まあ、専攻は途中で何度変更してもいいからね」
そこで、あたしは彼に約束させた。大学では、辺境生まれの強化体だと知られないように振る舞うこと。
全力疾走しない。高く跳ばない。素手で石を割らない。三人前食べることは、まあ、仕方ない。
「努力するけど、もし、知られたら?」
「あんたが信頼できる友達数人になら、知られてもいい。尊敬する先輩とか、先生とかでもいい。友達に秘密を守ってもらうのも、あんたの力量だからね。でも、噂になるようだったら、逃げるしかなくなる。同じ大学に長くいたいのなら、用心すること」
ジュニアは真剣な顔で頷いた。
この子にとって一番いい勉強は、友達を作ることだ。恋をして、失恋するのもいい。
辺境ではできない経験をしてくれたら、それが、あたしたちにできる最上の贈り物ということになる。
「ここまではしっかり務めてるようだから、上出来だ。この調子で頼むよ」
と褒めてから通話を終えた。近くにいた探春は、複雑な顔をしている。
「確かにここまでは、よくやっているわ」
「少しは見直した?」
と笑いかけると、つんとしてみせる。
「元々、優秀な子だとは思っているわ。彼の遺伝子は、お姉さまの設計ですもの。ただ、どこまで続くか、わからなかっただけ。ちやほやされて育った男の子に、たいした忍耐力があるとは思えないもの」
探春としては、かなりの高評価だ。
「忍耐できるかどうかは、目標次第だね。あの子は何か、これっていう目標が欲しいんだよ。あれだけの頭脳と体力があったら、何でもできるもの。それを無駄にするより、何か、ましな目標を見つけた方がいい。違法組織で幹部になるより、もっと面白いこと……世界のためになるような」
「正義の味方?」
あたしは笑ってしまう。
「それは望まないよ」
それがましな生き方かどうか、わからない。もっと賢い生き方が、他にあるかも。
でも、邪悪に立ち向かうということは、誰かがやらなければならないことだ。
無駄でも戦う。あきらめない。
個人はいずれ死ぬが、人類はもっと長く続くのだから。
あたしたちが戦う姿を、下の世代が見てくれたら、きっと何か感じてくれるだろう。
「あの子、あなたを尊敬しているわ。このまま〝リリス〟の仲間になりたいと言うかもしれない」
「そうはならないよ。大学できっと、何か見付ける」
彼がいずれ自分で、母親に告げればいいのだ。俺は、自分で自分の道を選ぶと。
犬の暮らしには、すぐ慣れた。
自分にこんな修行者みたいな生活ができるとは、これまで考えたこともなかったが。
朝、暗いうちに起き出し、一運動してからシャワーを浴び、身支度をする。何種類かの武器を身に付け、食事を済ませる。
ライサが起きてきて食事をしているうち(最初はレイン議員と呼んでいたが、やがて、堅苦しいから名前でいいと言われた)、一日のスケジュールを確認し、警備体制について警備班と打ち合わせをしておく。
最高議会には議員用の警備要員がいるが、懸賞金リストに載っているライサの場合、それでは足りないので、司法局の専属チームが付いている。他星へ移動する時には、軍艦での護衛も付く。
あとは一日、彼女の行動に付き添う。
会議、視察、講演、調査、市民団体との会合。マスコミの取材も入る。
俺はもちろん、朝の運動だけでは足りないから、危険のなさそうな時、警備班に彼女の見張りを頼んでおいて、素早くあたりを走ってくる。空いている場所で、空手や剣道の稽古をする。
夜はライサが自室で寛いでいたり、翌日の準備をしたりしているうち、俺も自分の勉強をする。大学に入るまでに、これだけはやっておけという宿題をヴァイオレットから出されているから、それをこなしていく。
司法局の局員たちは、俺を〝リリス〟の弟子と思っているから、気がひけるくらい信頼してくれる。まだ何の経験もない、ほんの小僧だというのに。
何か失敗したら、リリーに迷惑をかけてしまう。それだけは、しなくて済むようにと祈った。
ライサは普段、惑星首都にある自分のアパートメントで暮らしているが、旅行先では警備のしやすい一流ホテルに泊まる。俺は大抵、彼女の寝室の隣室をもらい、そこで寝起きする。
彼女は最初、俺が一日中、視野の範囲にいることに緊張していたが、やがて、俺がひたすら番犬の役に没頭していることを理解してくれた。そして、緊張をゆるめてくれた。
それでいい。辺境の人間が、アンドロイドやバイオロイドの警備兵を気にしないのと同じことだ。
おふくろには幾度かメッセージを送り、心配するな、邪魔もするなと宣告してある。
向こうも俺が〝リリス〟に使われていることには驚いただろうが、おかげで十分なショックを与えられたようだ。
(あの子はもう、わたしの言うことは聞かない。わたしの勧める道は選ばない)
おふくろが、そう理解してくれればいい。
それは何も、おふくろに感謝していないとか、もう愛していないとかいうことではなくて、単に、
(俺は俺の人生を始める)
というだけのことだ。
リザードの下で働いたって、結局、リザードの部下で終わるだけ。それでは面白くない。
もっと何か、俺でなくてはできないことをやってみたい。
人の命令で動くのでは、絶対、満足できないに決まっている。
もちろん、この先、自分がどんな方向に進むのかは、まだ何もわからない。ようやく、人類社会の残り半分のことを学び始めたばかりだからだ。映画で見ただけでは、本当に市民社会を知ったことにはならない。
今はとにかくリリーやヴァイオレットの指図に従い、彼女たちから学べることを学んでおくつもりだ。戦うことにかけて、彼女たち以上の教師は、たぶんいない。
一緒にリゾート惑星で暮らした短い期間に、俺は自分が無敵でも、不死身でもないことを悟った。
何度もリリーに叩きのめされ、打ち負かされて、悟るしかなかったのだ。これまではただ、自分より弱い者としか戦ってこなかっただけだと。
教養の面でも、それなりの勉強はしてきたつもりだったが、ヴァイオレットの幅広い教養には、全然及びもつかないとわかった。
誰かと、何かと戦うためには、世界全体の成り立ちや、表面には出ない裏事情なども知っていなければならないのだ。
哲学、文学、歴史、政治、経済。
何も知らなくては、ライサが提出する議案にどんな意味があるのか、会う相手がどんな地位にいるのか、この会合にどんな意味があるのかもわからない。
自分がただの甘えたガキだと思い知らされて、最初はショックだったが、今はそのことに感謝している。
危うく、自惚れたまま世間に出ていって、大変な目に遭うところだった。
少なくとも、リリーより強くならなければ、そしてヴァイオレットに負けないくらい賢くならなければ、とても一人前とは言えない。
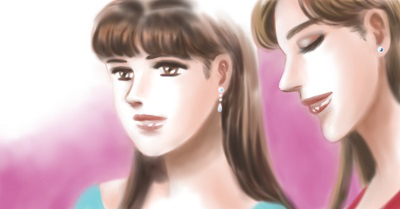
「はい、差し入れ」
目の前に差し出されたカップ入りのスープを見て、そこから立ち上るいい匂いの湯気を嗅いで、俺は顔を上げた。ダークスーツを着た、知らない女が立っている。
いや、顔は以前にも見ている。司法局員の一人だ。ただ、名前は知らない。今朝、今回の会議場の警備をしている班と紹介し合った時にいた。俺はライサが化粧室に入っている間、その前の通路で椅子に座っている。
「朝からずっと、交替もなしで、大変だと思って」
彼女は、自分が会議場の付属食堂で軽食を摂ったついでに、俺にもスープを持ってきてくれたらしい。俺は食べられる時に素早く食べるから、特に休憩時間は必要ないのだ。
「悪いが、要らない」
と答えた。
リリーに厳しく言われている。他人から勧められるものは、口にするな。自分が選んだものだけを食べろ。
いくら強化体でも、全ての毒物に耐性があるわけではない。死ななくても、行動を封じられたら、護衛の役に立たない。
「あんたを信用しないわけじゃないんだ。ただ、常に疑う姿勢でいないと、護衛は務まらない」
すると彼女はやや驚き、それから微笑んだ。
「まだ若いのに、偉いのね」
俺は、司法局には十八歳と言ってある。まだ十六歳になったばかりのガキと知られたら、いくらリリスの弟子でも、とても使ってもらえない。
「新米だから、言われた通りやるしかない」
「頼もしいわ。頑張ってね」
彼女はスープを持ったまま立ち去ったが、途中のロビーで、そのスープを自分で飲むのを見た。もちろん、毒入りなどではなく、ただの親切だったのだろう。気を悪くしていないといいが。
別の日には、別な女が来た。議員仲間の会合の後だ。
議員の一人が自分の秘書から離れ、俺に近づいてきた。美人だが、派手なスーツを着た、これ見よがしの美人なので、俺は内心で警戒する。どこか、おふくろに通じるものを感じるからだ。
「あなた、毎日ライサに付いているのね。休日はないの?」
そら、珍しい動物を見物に来たような態度。だが、こっちも護衛の立場はわきまえている。
「ありません」
「まあ、いくら司法局でも、若い人を、そんな無茶な使い方をしていいのかしら」
「俺は体力がありますから」
「そのようね。今度、時間ができた時、ゆっくりお話したいわ。司法局には、いずれ、わたしの護衛に回してくれるよう、お願いしておくわね」
「……?」
後から報告したら、ライサに笑われた。
「彼女、才能のある青年に目がないのよ。あなたが〝リリス〟の関係者だとわかったので、興味を持ったのね。うかうかしていると、味見されてしまうわよ。これまで、若手の俳優とか作家とか、司法局の新人とか、ずいぶん彼女に食い散らかされているんだから」
ぎょっとした。冗談ではない。俺にも好みというものがある。あんな毒々しい年増に〝味見〟されてたまるか。
俺の好みは……好みは……俺はいったい!?
わからない。
俺は、どんな女が理想なんだ。
身の周りに人間の女が少なかったから、映画に出てくる女優に憧れるのが精々だった。でも、リリーを師匠にした今となっては、その辺の女なんか比較にならない。
少なくとも、俺の母親のようなべたべた女は厭だ。ヴァイオレットのような冷たい女も(リリーにだけは笑顔を向けるが、あんまり露骨すぎるだろう)困る。
一緒にいて楽しくて、できれば頼りになる女がいい。俺の欠点や弱点を補ってくれるような。竹を割ったような気性で、明るくて豪快で……ということは、俺の理想ってのはリリーなのか!?
おいおいおい。
そりゃあ、尊敬できる相手となったら、真っ先にリリーだが。
しかし、彼女とどうこうというのは……ちょっと考えられない。恐れ多くて。
彼女を相手にして勃つ男なんて、世界にいるのか?
それでも、いつかは恋人が欲しいと思う。信頼で結ばれたカップルというものに、憧れる。
どんなに幸せだろう、愛し愛される相手がいたら。
(どこかで見付かるかな、好きな女)
それには、人間の女が少ない辺境よりも、人口の半分が女である市民社会の方が有利だと気がついた。
絶対、大学に通わせてもらおう。その間に、恋人になりうる女と出会えるかもしれない。
片思いでも構わない。誰も好きにならないより、ずっと張り合いがあるじゃないか。

次に〝彼女〟に会ったのは、別の会議場でのことだ。いつか、スープを差し入れてくれた女だ。
今度は、名前を覚えた。渚沙というのだ。
黒髪をショートカットにして、涼しい一重の目をしている。目立つ美人ではないが、頭の良さがわかる表情をしている。
司法局の捜査官で、ライサの護衛班ではないが、懸賞金リストの人物の警備に関して、各方面との連絡調整係として、他の捜査官と交代で勤務しているという。
「あなたはずっと、レイン議員の担当なのね」
俺個人に興味があるというより、〝リリス〟の弟子という噂を聞いたからだろう。
しかしもちろん、リリーたちの情報を他人に漏らすようなことはしない。リリーとヴァイオレットの二人こそ、最高金額の賞金首なのだ。
「本当に全然、自由時間がないの?」
と気の毒そうな微笑みで聞かれ、ちょっと恥ずかしくなった。俺より十歳は年上だろうから、可哀想な少年と思われているのだろう。
「ライサが寝室に引き取ったら、隣の部屋で寝る」
「それを、これから何年も続けるなんて、気が遠くなるわね」
だが、永遠にではないだろう。いずれリリーが、もういいと言ってくれるまでの辛抱だ。
「差し入れはできないとわかったから、代りにこれを」
渚沙が俺に渡した紙切れには、何本かの映画の題名が書いてある。
「わたし、映画好きなの。それ、まだ見ていなかったら、お薦めよ」
そして、手をひらひら振ってから、遠ざかった。
最初は、こんな風にして始まったのだ。それから何度か、別の会議場で顔を合わせた。そして、互いに、好きな小説や映画を教え合うようになった。彼女とは、好きなものが似ているとわかったのだ。
俺には、ライサの姿を見守る義務があるから、渚沙からのメールに目を通すのは、ほんの短時間のことだった。それでも、職務外で女性と交流が持てるのは、何となく嬉しいことだった。
世間の普通の少年が過ごすような、青春というものを、ちょっぴりだけ味わったような気がして。
もちろんリリーには、それも報告していた。メールの交換くらいなら、問題はないだろうと言われて、ほっとした。ただし、
「彼女があんたを篭絡して、議員の暗殺を狙う可能性もあるから、それは忘れないように」
と警告された。
「まさか」
とつい笑ったら、
「まさかで済んだら、軍も司法局も要らないことになるよ」
と脅され、しゅんとしてしまった。リリーとヴァイオレットは他星で別の任務に就いているから、ライサの安全は俺にかかっているのだ。いや、99パーセントまでは、通常の警備班で足りるはずだが。
次に渚沙に会った時は、最高議会の議場控室だった。議会で議員たちが議論している間、議場は、付属機関である護衛庁のものだ。司法局員は、控室までしか入れない。
片隅の椅子で大画面の中継映像を見ながら、議論の行方を追っていたら、隣に渚沙が来て言う。
「わたし、配置換えになるの。他星の支局に行くから、もう会えないと思うわ」
俺は思わず、振り向いて彼女を見てしまった。
「メールは構わないんだろ?」
渚沙はくすりと笑う。
「もちろんよ。きみにその暇があればね」
「そのくらい、隙間の時間はあるよ」
「ありがとう。お別れを言えて、よかったわ。元気で、お仕事しっかりね」
お別れ、なのか。
俺が言葉を見つけられないうち、渚沙がすっと手を伸ばして、俺の頬に当てた。そして、身を寄せてきて、唇に軽いキスをした。俺が呆然としているうち、彼女は立って、同僚の所へ行ってしまった。
周囲の捜査官たちは、誰一人、こちらを見ていなかった。いや、見ないふりだったらしいと、後で気付いたが。
後日、ライサが気の毒そうに言ったものだ。
「周囲には、何となくわかっていたのよ。彼女が、あなたを好きだってことはね。でも、あなたはまだ、子供だから。あれが最大限、彼女にできることだったのよ」
市民社会では、大人が子供に手出しをしたら、犯罪になる。
俺はまだ、子供として守られる立場でしかなかったのだ。

「シヴァ、悪いが、リナがそちらへ行く。話を聞いてやってほしい」
リザードから連絡があったことに、まず驚いた。俺がグリフィン役から降ろされて以来、交流は絶えていたからだ。
リザードの説明には、心底驚愕し、揺さぶられた。
俺に子供がいたというのだ。
それも、二人も。
「まさか」
最初は理解できなかった。俺に何の覚えもないのに、なぜ、そんなことになる。リナとは確か、手を握ったこともなかったはずだ。
しかし、通話画面の相手は淡々と言う。
「リナがきみの元を去る時、きみの髪の毛を持ち出した。その結果だ」
つまり、俺に内緒で、俺の遺伝子を使ったのか。
何ということだ。反則もいいところだ。俺が知らないうち、俺の遺伝子を受け継いだ子供が誕生していたなんて。
「なぜ、そんなことを」
当時、リナは俺の第二秘書だった。リザードの元から、俺の監視と護衛を兼ねて派遣されていたのだ。まだほんの小娘で、初めての仕事に張り切っていた。張り切りすぎて、何か勘違いしたのだ。
ある晩、裸で俺のベッドに潜り込み、俺を待っていた。俺は仰天して叱りつけ、リナを追い払った……と記憶している。
俺の目には、リナは背伸びしている子供にしか見えなかったのだ。
その翌日、リナはリザードの元へ逃げ帰り、それ以来、会っていない。今日まで、ほとんど忘れていた相手だ。当時の俺には、リアンヌという大事な女がいたから。
まして、そのリアンヌを失った後は(彼女は記憶を失い、市民社会に保護されて、俺とは別の人生を歩みだした)、何年も荒れ狂っていて、他の誰かを心配するどころではなかった。ハニーと出会ってからは、ハニーの補佐にかかりきりだし。
しかし、リザードはしゃあしゃあと言う。
「リナを責めてはいけない。きみが、乙女心を踏みにじったのが悪い。リナとしては、きみに傷つけられた心を癒すために、子供が必要だったのだよ」
何をぬかす。
「俺がいつ、リナを踏みにじった」
リザードに押し付けられた秘書だったが、ちゃんと仕事を任せ、公正に扱ったはずだ。
そう反論すると、リザードは愚か者を哀れむ顔で言う。
「きみは、リナの恋心を察知するべきだった。彼女なりに、本気の恋だったのだから」
おい。
あの時点で、リナはどうしたって、ピーチクパーチクさえずる、小雀にしか見えなかったぞ。
「しかし、それはまあ過去のことだから、いいとしよう。リナも息子を育てながら、組織の一員として働いてきた。今では立派な《フェンリル》の幹部だ」
そうかい。
「問題は、リナの息子が誘拐され、母親から引き離されたこと。絶望したリナは、改めて、もう一人子供を作ったが、その子もまた、母親から逃げ去るだろうと思われることだ」
誘拐?
逃げ去る?
「話が、よくわからんが……」
老舗組織である《フェンリル》が守っていた者なら、そう簡単に誘拐されたりしないはず。
「誘拐そのものは、既に過去のことだ。きみが〝リリス〟をきちんと監視していれば、わかったはずだと思うがね」
がんと頭を殴られた気がした。
〝リリス〟の仕業なのか。
「きみの息子が違法都市で暴れ回っていることを知って、捕獲に乗り出したのだ。彼は〝リリス〟に庇護され、鍛え直された。今は、きみの故郷の《ティルス》にいる。もう、《フェンリル》には戻るまい。まあ、母親に面会くらいはしているが」
ちょっと待て。頭が混乱する。俺の息子を、紅泉たちが庇護してくれたというのか。
知らないぞ、そんな話。
「リナが、俺に会いに来ると言ったか?」
「止めたが、聞かない。息子ばかりか、娘もきみの一族に奪われると思って、半狂乱になっている」
ぞっとした。
女のヒステリーほど、苦手なものはない。
リナはかつては、それなりに可愛い娘だったが、今では、どんな厚かましい中年女になっていることか。
そもそも、勝手に俺の遺伝子を使用したこと自体、かなり怖いぞ。思い込みが激しすぎるんだ。
「では、後はそちらで話し合ってくれたまえ」
「おい、おまえはそもそも、リナの子供たちをどうするつもりだったんだ!?」
「ゆくゆくは、わたしの元で幹部になってもらうつもりだったが、それはもはや無理だろう。〝リリス〟に奪われたのだからな。まずは、きみたちが話し合いたまえ。子供たちの両親なのだから」
冷静な他人面のリザードは通話画面から消え、俺は一人で取り残された。
何が両親だ。俺はついさっきまで、自分が親になっているなんて、知らなかったんだぞ。
女ってやつは、なんて卑怯なんだ。わがまま放題しやがって、困った時だけ男に泣きついて。悪いことは全部、男のせいにしやがる。
「ショーティ!!」
まずは相棒を呼んだ。奴は当然、リザードとの会話を聞いていたはずだ。
やはり、隣室からのそのそ、大型犬がやってきた。アラスカン・マラミュートのボディを使ったサイボーグ犬だ。立った耳、暗灰色の背中、白い腹、ふさふさの尻尾。
「リナの船は近くまで来ている。二時間もすれば、この街に上陸するだろう」
愕然とした。それしか猶予がないのか。
「おまえ、まさか、知ってたんじゃないだろうな!! そんなガキがいるってこと!!」
「きみにそっくりの少年が、バイクで違法都市を走り回っていることは知っていた。チンピラに喧嘩を売っては、叩きのめして回っていることも」
「なぜすぐ、俺に報告しない!!」
「グリフィン時代、きみがちゃんと報告書の束に目を通していれば、わかったことだ。〝リリス〟の行動についても、細かく注意を向けていれば、もっと早く気付いただろう」
俺は頭をかきむしった。
仕方ないだろう。毎日、あんなに報告の山が届くのだから、全部なんて把握できるわけがない。重要なことは、ショーティが把握して、俺に注意を促すはずだと思っていたし。
「俺が、知らなくてもいいと思ってたのか」
というか、知らない方がいいと思っていたのか。
「知らせてどうする。きみの知らないうちに作られた子供だ。きみに責任はない。なのに、父親らしいことをしたいのか? そもそも、きみの子供として認めるのか?」
くそ。相棒のくせに冷たい奴だ。少しは慰めてくれたり、励ましたりしてくれたらどうだ。
俺だってショックなんだぞ。いきなり、二人も子供がいるなんて知らされて。
「本当に、俺の子供なのか」
「子供と言うより、クローンと言うべきだろう。息子の方はな」
「もう一人は娘……なのか」
「兄とは二十歳ばかり離れた妹だ」
想像がつかない。俺の知らない息子と娘。
「息子には、きみの遺伝子にほとんど手を加えず、そのまま使っている。それで正解だ。きみは完成された強化体だから、そのバランスを崩すと、正常な生命活動ができなくなる。リナはそれがわかっていたから、自分の遺伝子は、気持ち程度にしか加えなかった」
ますます悪い。クローンとは。
ショーティめ。何もかも知っていたくせに、今日までよくも、黙り通しやがって。
俺そっくりの傲岸不遜な男が、この世にもう一人いるなんて、背筋がざわざわする。そんな奴、絶対に好きになれない。
「ただし娘には、リナの遺伝子をもう少し入れている。でないと、女の子にはならないからな」
ということは、リナに似ているのか。
ますます、げっそりしてきた。
そもそも、このことを、どうやってハニーに話せばいいのだ。

「シヴァ、お茶にしないこと?」
美しい紫紺のスーツを着たハニーが、優雅な足取りで入ってきた。
ここは、彼女の仕事場であるファッション・ビル《ヴィーナス・タウン》の一室だ。警備管制室と、その周辺の区画を、俺とショーティの居場所にしている。
ハニーの下で働く女の社員たちは、この区画に入ってくることはない。彼女たちが、警備責任者である俺の姿を見ることのないよう、注意を払っている。俺の姿は、人に見せてはまずい理由がある。
経営者であるハニーは、普段は別の階にある自分専用のオフィスにいて、時間ができた時だけ、俺と過ごすためにやってくる。
「ああ、うう……」
聡い女なので、苦りきった俺の顔と、床に寝そべるショーティを見て、何か察したらしい。
「何か困り事? わたしが聞いてはいけないことかしら?」
聞いてもらうしかない。ハニーに隠し事はできないからだ。猶予は、あと一時間しかない。リナが押しかけてくる前に、事態を把握しておいてもらわなくては。
だが、反応が怖い。ハニーは賢くて寛大な女だが、リナとは何もなかったと言って、信じてもらえるものだろうか。
「怒らないでくれるか?」
まず、卑屈に頼んだ。
「まあ、わたしが何を怒るというの? あなたが既に、懺悔の態勢なのに」
ハニーは灰色の瞳に理知の光をたたえ、薔薇色の唇で穏やかに微笑む。この世で最高の女だ。決して失いたくない。どうか、俺を軽蔑しないでくれ。
「今、リザードから知らせがあった……《フェンリル》のボスだ。昔、俺の秘書をしていた女が来る。俺がグリフィンになりたての頃、短期間だけの秘書だった」
ハニーは察しがいい。興味深い様子で尋ねてくる。
「あなたと、特別な関係だったのね?」
「違う!! 何もしてない。手も握らなかった」
「それじゃ、何が困るの?」
うう。
「彼女はシヴァに片思いしていて、こっそりシヴァの子供を作っていたのだ。シヴァの細胞を利用してね。息子と娘で、息子はとうに成人しているが、娘の方はまだ子供だ」
ようやくショーティが、助け舟を出してくれた。というか、俺を泥水に突き落として、面白がっているのかも。
「まあ」
ハニーは目を丸くする。頼むから、泣かないでくれ。
「それで、その人が子供を連れて、押し掛け女房になりにくるの?」
それではまるきり、ホラー映画だ。
「違う。子供を〝リリス〟に連れ去られたので、怒り狂っているらしい。たぶん、俺に子供を連れ戻せ、と言うんだろう」
ハニーは真剣な顔になった。ソファ席を示す。
「どうやら最初から、すっかり話してもらう方がいいようね」
これ以上、何を話せばいいのか、俺にはわからないのだが。
リナが少数の護衛を連れて《ヴィーナス・タウン》に到着した時、俺とハニーはホテル階の一室で待ち受けていた。正確に言うと、ハニーは俺のいる部屋の隣に控えていたのだ。
「一緒にいてくれ」
と頼んだのに、
「まさか、わたしの後ろに隠れるつもりではないわよね。わたしは、あなた方の会話が一段落したら出ていくわ」
と置き去りにされてしまった。
できることなら俺は、ハニーにうまく取りなしてもらいたかったのに。
くそ。蒔いた種は、自分で刈り取れということか。俺には、何も蒔いたつもりはないのに。
《ヴィーナス・タウン》は女しか入れないことで知られるビルなので、リナの護衛も女ばかりだった。その護衛たちも、こちらの護衛兵によって控え室に留められたので、俺たちのいる部屋に入ってきた時、リナは一人きりだった。
少しカールした短い黒髪、なめらかな小麦色の肌、負けん気に満ちた愛らしい顔立ち。
もう何十年も会っていなかったが、見た途端に記憶が蘇った。
ルワナが第一秘書で、リナが第二秘書だった頃。
当時の俺は、懸賞金制度の責任者であるグリフィンの仕事を押し付けられ、行動を制限されて鬱々としていた。リナはその不自由な生活の中で、俺を笑わせてくれた貴重な存在だったのだ。
もしかしたら、俺が(少しは)悪かったのかもしれない。
リナが裸で俺にぶつかってきた時、もう少し穏やかに受け止めていれば。あるいは、彼女が泣いて逃げ出した後、連れ戻していれば。
だが、あの頃の俺に、そんな余裕はなかった。従姉妹たちの命を心配するので手一杯だったし、《フェンリル》のナンバー2だった女と恋仲になってしまったから。
現在のリナは、リザードの元で経験を深めたようで、あの頃よりぐんと垢抜けて美しくなり、洒落たオレンジ色のスーツに身を包んで颯爽としていた。青紫の宝石のイヤリングも、よく似合う。
リナはハイヒールで威厳を持って歩いてくると、俺の前で立ち止まり、何か言おうとした。
「………」
そしてなぜか、言葉に詰まった。
言いたいことが多すぎて、順番が決まらないのか。
俺が見ているうちに、息が乱れ、顔がくしゃりと歪み、ぼろぼろと泣き出すではないか。
「シヴァ、あの子が……」
リナは体当たりのようにして、俺の胸に取りすがってきた。
「お願い、助けて。アスマンはもう、あきらめたわ。男の子なんて、全然言うことを聞かない。傲慢なのよ。あなたそっくり。でも、梨莉花まで奪われるなんて……!!」
あとはもう、言葉にならない。リナは彼にしがみついて、わあわあ泣きじゃくった。
まさか、こうくるとは。歳月を遡って、昔のやんちゃな小娘に戻ったかのようだ。
俺はどうしようもなく、
「わかった、わかった。もう泣くな」
とリナの背を撫でるしかない。
冷や汗が流れる気分だ。隣室のモニター画面で見ているハニーは、さぞ呆れているのではないか。これでは、男女の関係だったと誤解されても仕方ない。
俺はリナに胸を貸したまま、彼女が泣き止むのを辛抱強く待ち、肩をさすってなだめた。
「とにかく、子供たちの居場所はわかってるんだろう。俺の故郷にいるなら、心配することはない。〝リリス〟が保護してくれる」
リナはハンカチを握りしめ、しゃくり上げながら言う。
「だけど、ひどいわ。何の権利があって、人の子供を誘拐するの。あんまりよ」
奇妙な言い分だと思った。
他人を食い物にしてきた違法組織の幹部が、自分の権利だけは主張するのか。
だが、思い返せばリナ自身、子供の頃に市民社会から誘拐されてきて、違法組織に取り込まれた被害者である。
生きるためには、違法組織に適合するしかなかったのだ。俺には責められない。なるべく公平に聞こえるように言った。
「とにかく、俺にはまだ、事情がよく分かっていないんだ。説明してくれ」
子供の名前すら、いま聞いたばかりなのだから。

一時間ほどかけて、リナの話を聞いた。途中で泣いたり、怒ったり、俺との思い出話に飛んだりするので、話が何度も行きつ戻りつしたが。
息子のアスマンは《ティルス》で研究者として暮らしていて、妹の梨莉花は彼の元へ何度も遊びに行き、行くとなかなか帰ってこないという。
「あんまりだわ。息子ばかりか、娘まで取り込んだのよ。〝リリス〟は」
しかし、それは、彼らの選択だろう。違法組織よりも、〝正義の味方〟を信頼したのだ。
紅泉だって、これまでの年月、楽に過ごしてきたわけではない。犠牲者を出し、戦いに疲れ、市民たちから責められ、何度も『もうやめようか』と悩んだことを、俺は知っている。
だが、結局は〝正義の味方〟に立ち戻った。
無駄な戦いなどではない。
最初は違法強化体を信用しなかった市民たちも、やがて、〝リリス〟が本物であることを認めた。紅泉の粘り勝ちだ。
多くの若者が〝リリス〟に憧れ、軍に入ったり、司法局員になったりしているではないか。
俺の子供たちも……まだ子供と認めるのは抵抗があるが……紅泉の影響を受けたのだろう。
「最高幹部会は、まだ〝リリス〟に価値を認めている。正義の側で戦うのも、悪くはないだろう。いざとなったら、おまえが陰から守ってやればいい。俺も気を付けて見ているから」
しかし、リナの不満はそこではないらしい。
「わたしはいやよ!! 他の女が、あの子たちにあれこれ命令するなんて!!」
なんだ。つまり、嫉妬か。
「おいおい、子離れしたらどうだ」
と笑ってしまったら、怒りの矛先は俺に向いてきた。
「他人事だと思って、笑い話にしないで!! いいえ、そうよね、やっぱり他人なんだわ!! あなたは〝リリス〟ばかり大事にして、わたしのことなんか見てくれなかった!! だから子供を作ったのに!! わたしの息子まで〝リリス〟がさらっていくなんて、あんまりだわ!! このままでは、梨莉花まで取られてしまう!! 彼女たちは、何でも持っているじゃない!! どうしてわたしから、唯一の支えを取り上げるの!!」
まったく、女というやつは。どうして勝手に煮詰まって、勝手に怒るんだ。
泣きたいのはこっちだ。知らないうちに、子供なんか作られて。
再び泣かれるのは覚悟の上で、俺は冷たく言った。
「ヒスはやめろ。おまえだってもう、小娘じゃないはずだろう。わかっていないなら言うが、子供はおまえの持ち物じゃない。一時的に扶養を託されただけで、本来は天からの預かり物だ」
俺がこんな偉そうなことを言うなんて、ショーティの奴が、鼻先で笑っているだろうがな。
「アスマンはとっくに一人前なんだし、梨莉花だって、もう十三歳なら、少しは自由に行動させていい年齢だ」
ちゃんと勉強しているなら、兄の元に入り浸りになっても、問題あるまい。
「まだ早いわ。せめて十八までは、わたしの元にいるべきだわ」
だから、俺にしがみついてごねるな。まるで、別れた夫婦の再会みたいだろうが。
「二人が〝正義の味方〟に憧れるなら、仕方ない」
「だから困るのよ。わたしは違法組織の幹部なのに!!」
つい、笑いたくなってしまう。この性格で、どうやって部下たちをまとめているのだか。
まあ、背後にリザードが控えているからだろうな。
不思議なことは、なぜリザードがこいつを引き立てているかだ。リナには自分を裏切る意志も能力もないから、か?
「じゃあ、正義が勝つことを祈るんだな。それなら、めでたしめでたしだろう」
「遺伝子操作も不老不死も禁じられる世界なんて、ごめんだわ!! しわくちゃのお婆さんになるなんて、絶対いや!!」
その台詞は、いかにも女らしくていい。正直で可愛いではないか。
俺だって、ハニーには、今のままの美しい姿でいてほしい。
といっても、ハニーが白髪の老女になったら、それはそれで、いい風情のような気がするが。
ハニーなら、最上級の老女になることは間違いない。その時は、俺も枯れた老人になっていれば、釣り合いがいい。実際には、自分がいつまで若い姿でいられるか不明だが。
「だったら、市民社会がそれを認めるように、働きかければいい。法律は、暴力なしで変えられるんだ。中央と辺境の垣根が低くなるだけで、世界はだいぶましになる」
「何よ、あなたなんか、どっちつかずのコウモリのくせに!!」
拳固で肩をばしばし叩かれていては、苦笑するしかない。
「そうだな。狭間でうろうろしているだけだ。ろくでもない」
それでも、訴えを聞き、背中を撫でているうちに、リナは少しずつ落ち着きを取り戻していった。
ようやく俺から身を離すと、ハンカチで顔をこすりながら、やや照れたように言う。
「わたし、あなたに会ったら、うんと冷たく振る舞うつもりだったの。こんなにいい女になったのよって、見せつけてやるつもりだった。あなたが、わたしを相手にしてくれなかったこと、後悔するように」
助かった。
今の言葉、ハニーはきちんと聞いてくれただろうな。
俺としてはやはり、リナを背負わなくて済んで助かった、という気がしている。何かある都度、わあわあ泣かれ、辻褄の合わない愚痴をぶつけられたら、かなわない。
リナを好む男もいるだろうが、俺はやはりハニーのように、理知的で包容力のある女がいい。
改めて、ショーティの慧眼に感謝する気になった。よくぞハニーを選んで、他の男から取り上げた上、俺の元へ送り込んでくれたものだ。
そしてまた、ハニーが俺を認め、愛してくれるようになった。これはもしかしたら、途方もない奇跡だったのではないか。
リナは、何か悔しいことを認めるような様子で言う。
「なのに、あなたがあんまり変わらないから……わたしまで、つい、気持ちが過去に戻ってしまって」
「俺は変わってないか?」
つまり、進歩も老成もしていないんだな。これでも、少しはましになったつもりでいたのに。
すると、リナは照れ笑いのような顔になる。
「相変わらずハンサムで、かっこいいわ。わたしが夢中になった時のままね。いえ、やっぱり変わってる。昔だったら、こんなに気長に慰めてくれなかったわ。やっぱり、一緒にいる女性がいいのね」
う?
「あなたはその点、女性を選ぶセンスがいいわ。ジョルファさまは……やはり立派な方だった」
ジョルファ。本名はリアンヌ。
俺が夢中になって、うっかり妊娠させてしまった。普通人と強化体の間では、自然な妊娠や出産は無理だったのに。
「あの時のわたしでは、とても勝負にならなかった。それが、ようやく後から納得できるようになったの」
そうなのか?
「あの方があなたと引き離されたことは残念だったけれど、でも、市民社会で幸せに暮らしておいでのようだから、それはそれで良かったのよね。あなたはまた、素晴らしい女性を見付けたようだし」
俺はやや、驚いた。リナもやはり、小娘ではなくなっているらしい。
隣室でハニーが聞いているからといって、心にもないお世辞を言っているわけではないだろう。
「わたし、アスマンを宝物にして、一生懸命、あなたのように育てたつもりだったの。無口で無愛想で、でも男らしくて優しい子に。あの子があなたそっくりになっていくので、とても嬉しかった。毎日、毎日、楽しかったわ。でも、やっぱりあなたとは違うのね。あなたと会ったら、それがよくわかったわ。肉体的にそっくりでも、中身は別人。それでいいのね」
リナが納得してくれたのなら、それで話は解決だ。
「だいたい、あなただったら、母親に呼び戻されて、のこのこ帰るなんて真似、するわけないものね。少なくともアスマンは、たまには会いに来てくれるから」
わかってるじゃないか。
「梨莉花だって、わたしの言うことなんか聞かないの、当たり前なんだわ。あの子、お兄ちゃんが大好きなのよ。リザードにも、言われたの。子供が思う通りに育つことなんか、期待するなって」
俺には母親はいなかったが、育ての親の最長老には、ある時期から強い反発を感じるようになった。一族の勢力圏に閉じ込められ、あれは禁止これも禁止と指図されて、窒息しそうな気がしたのだ。
「子供たちには、リザードが父親代わりだったのか」
「彼は、とてもよくしてくれたわ。おかげで、安心して子育てできたの。あなたからも、お礼を言ってちょうだいね」
ますます、離婚した元夫婦みたいになってきた。ハニー、もうそろそろ助けてくれ。ショーティは引っ込んだまま、出てこないし。
そこへ、ようやくハニーが登場した。背後に、お茶のワゴンを押すアンドロイド侍女を従えて。
「ミス・リナ、わたくしのビルへようこそ。経営者のハニーと申します。こちらで、お顔を直されてはいかがですか。その間に、お茶を淹れますから。蜂蜜入りのハーブティでよろしいかしら」
プラチナブロンドを結い上げたハニーの美貌と、グレイがかった紫紺のスーツが似合う落ち着いた佇まいを見て、リナは改めて対抗心を燃やしたようだ。
ハニーのことは無論、前から知っていただろう。リナも《ヴィーナス・タウン》の顧客の一人だろうからな。
近頃では、辺境でそれなりの地位にある女は、ほとんど顧客になっている。リナが主に出入りしていたのは、この《アヴァロン》の本店ではなく、支店の方だろうから、ハニーとじかに会ってはいないかもしれないが。
「ありがとう。少し時間をいただきます」
リナは背筋を伸ばして、気取った声で言い、バッグを持って、いったん化粧室に消えた。ハニーは俺に悪戯な視線を向けて、
「おモテになること」
と柔らかく言う。
「勘弁してくれ。俺は無実だ」
「わかっています。あなたが彼女を弄んで捨てたなんて、思っていないわ」
「そうか」
それならいい。
「でも、あなたって、立っているだけで女を引き寄せるのよ」
「ああ?」
「自分では自覚がないらしいけれど、強烈に男性的で魅力的だから、あなたを間近で見た女が、片端から恋に落ちるのは、仕方のないことなの。罪作りな人なのよね」
そんなことを言われたら、どんな顔をしていいのかわからない。確かに、女に秋波を浴びせられたことはある……だが、遊び半分でそれに応じられるほど、俺は器用ではなかった。
「俺には、おまえだけいればいいんだ」
「それも本気で言っているから、困るのよねえ」
と、くすくす笑う。とにかく、よかった。ハニーは俺を怒っていない。冷静な女は有り難い。
リナは顔を洗って口紅を塗り直したようで、すまして戻ってきた。
「お待たせして、すみません」
いかにも出来る女のような態度で、勧められた席に腰を落ち着ける。女二人は向き合う形になり、俺はその横手に座った。ハニーもリナもにこやかに挨拶を交わし、穏やかに世間話をする。
ただし、リナが微笑んで、
「お幸せですわね。辺境一の男性を捕まえられて」
と言った時には、俺は内心で縮み上がってしまった。だが、ハニーは平静に受ける。
「ええ、とても幸運だと思います。おかげさまで、楽しく暮らしていますわ。ただ、今日はびっくりしましたのよ。この人に子供がいるなんて、つい数時間前までは知りませんでしたから……」
俺はとても口を出せない。リナもゆったり微笑んで言う。
「わたしだって、知らせるつもりはありませんでしたのよ。シヴァに横取りされては大変ですから、ずっと隠していましたの」
俺が横取り?
まさか。誰が欲しいものか、俺そっくりの生意気な小僧など。
娘と聞くと、ちょっと不思議な気はするが。まさか、紅泉のような、大柄で凶悪な娘ではあるまいな。
「でも、息子さんが《ティルス》にいるなら、心配はないでしょう。シヴァの故郷ですもの」
俺は絶縁したきりだが。
「貴女も幸運な方ですわ。リザードという後ろ盾を得られて、子供を育てられたのですもの。辺境では、滅多に望めない幸運でしょう」
「ええ、そうですね……これまでは、夢中で子育てしてきました。わたしは、シヴァには女として選んでもらえなかったけれど、それは仕方ないことですものね。彼の子供を育てるなら手助けすると、リザードが言ってくれましたから」
くそ、リザードめ。それもまた、持ち駒を増やす戦略だ。
リナはハニーをじっと見て、隠れた欠点や弱点を探ろうとしているかのようだった。しかし、ハニーは端然として隙がない。リナはそっと息を吐く。
「本当は、聞きたかったんですの。貴女がどうやって、この人に愛されるようになったのか。でも、もう、わかったような気がします。貴女はきっと、この人を包んであげられるんですね」
ハニーはにっこりした。これまで、何千人という部下を育ててきた貫禄だ。
「この人は不器用で、お人好しなので、誰かが支えてあげないといけないんですわ。その役を与えられて、とても嬉しいと思っていますの」
そうなのか?
「貴女の息子さんとお嬢さんのことは、こちらでも見守っていきます。きっと《ティルス》で、立派に働いていくと思いますわ。わたしたちも、楽しみにしていますから」
リナが護衛を連れて引き上げると、俺はがっくりしてしまい、見送った地下駐車場で、ハニーに後ろから抱きついた。
形としては俺が抱いているのだが、実質は、ハニーにすがっている。
ハニーがうまく対応してくれて、本当によかった。さもないと、修羅場になっていたかもしれない。
「艦隊戦をする方がましだった……」
すると、面白がるように笑われる。
「あなたより、彼女の方がずっと怖かったと思うわ。ここはあなたの領土だし、あなたが怒るかもしれなかったんだもの」
「いや、おまえの領土だ。それに、なんで俺が怒るんだ」
「勝手に遺伝子を使われた被害者でしょ?」
「だが、みんなして、俺が鈍いのが悪いって責めただろうが!!」
「そうよ。恋をされてもわからない、あなたが鈍いの。本当に、女心の通じない人なんだから」
「そういう時は、はっきり言ってくれないと困る」
「言われたって困るでしょ。あなたは一度に、一人の女しか愛せないんだから。ジョルファという人は、本当に偉い人だったのね」
ああ、久しぶりに、彼女のことを思い出した。
アマゾネス軍団の指揮官。
男優位の辺境で、女の地位を高めようとして、努力していた。
きっと、紅泉と話が合ったはずだ。もし、記憶を持ったままで会えていたら。
「だからこそ、〝連合〟としては、いずれ切り捨てなければならない人材だったんだ」
そうと理解したのは、後からだ。
ジョルファは――つまりリアンヌは――配下に女闘士を集め、男の論理を断罪し、内側から〝連合〟を変えようとしていた。それが、〝連合〟には脅威になっていた。
実質は、今のハニーも同じことをしようとしているのだが、ハニーのように穏健な方法ではなく、もっと力ずくの印象を与えていた。それが、男たちの反発を招いていた。
それで最高幹部会の連中は、〝リリス〟に追われた俺の身代わりとしてリアンヌを利用することに決め、うまく辺境から追い払ったのだ。
リアンヌが命まで取られなくて、本当によかった。
俺のことを忘れても、市民社会で幸せな母になってくれたのだから、それでいい。今では孫が何人もいて、立派なお祖母さんだ。
「可哀想に。辛かったわね。だからわたしに会った時、もう誰も愛さないと決めて、ぐれていたんでしょ」
「そんなに、ぐれてたか?」
「もう、手の付けようがないと思ったわ。あなたがまともに口をきいてくれるようになるまで、何週間かかったかしら?」
そういえば、そうだったかも。
「悪かった。俺も怖かったんだ」
「ええ、そうでしょ。あなたは女が怖いのよね。でも、それを認められるだけ、まだましよ」
よかった。ハニーは俺を見捨てず、愛してくれている。
ただし、ハニーは笑顔のまま、ぎゅうと俺の頬をつねってきた。爪が、爪が痛い。
「それはそうと、あなた、あの人を、一時間以上も抱いて慰めていたのよ。優しすぎるわ。そんなだから、うまく利用されるのよ」
やっぱり怒ってるじゃないか。
最後にハニーは、恐ろしい言葉を残して仕事に戻っていった。
「あなたが抱いて慰めてあげたから、あの人、満足して引き上げたのよ。もしかしたら、あなたの遺伝子を使って、次の子供を作るかもしれないわね。あなた、知らないうちに、一ダースくらい子供ができるわよ」
渚沙とは、数年間、ぽつぽつとメールのやりとりを続けた。中身は、映画や小説のことだけだ。それなら、子供を誘惑したと、渚沙がそしられることもないだろう。
二十歳を過ぎて、もう対等に付き合えるだろうと思ったので、彼女に会いに行った。そうしたら、既に渚沙は結婚していた。そして、子供が生まれるのだと、にこにこして教えてくれた。
まあ、こんなものだ。
結局、大学には五年いた。ライサの護衛任務を終了してから(二度、暗殺を阻止した)、リリーの元で更に二年間、助手を務めてからのこと。
その間、暗殺事件や誘拐事件も経験した。脅迫や洗脳の事件もあった。身近にいた司法局員の殉職も見た。そして、強化体の腕力なんて、組織の力に比べれば、たいして重要ではないと悟った。
体力があれば、何をするにも楽だし、無理も効くが、それだけのこと。
普通人より偉いわけでもないし、普通人が哀れなわけでもない。
約束通りに通わせてもらった大学では、毎日、楽しかった。思う存分勉強し、遊び、修行した。友達もできた。恋愛騒動も引き起こした。
俺から恋をしたというより、女から惚れられることが多かったため、あちこちで余計な恨みを買ってしまったからだ。決闘騒ぎまであった。もちろん、負けたふりでしのいだ。
まあ、おかげで、理想の女なんてものは、存在しないのだとわかった。
女には女の事情がある。
完璧でなくて当たり前。
自分の女神になってくれることを期待するよりも、友達として付き合う方が面白い。
そして、自分は意外にも、研究職に向いているとわかった。推理を重ねて謎を解明したり、実験装置を組み立てたり、まだこの世にない物を創り出したりするのが楽しいのだ。
最強の兵器とはどんなものか? 理想の戦闘艦隊は? 人間を超える人工の知性はありうるのか? バイオロイドはどこまで進化する?
俺は有利だった。疲れを知らない体力があれば、他人が寝ている間にも研究を続けられる。
大学で学ぶだけ学ぶと、リリーの口利きで、科学技術局に入れてもらった。
しかし、ここは二年しか続かなかった。あれこれと制限がありすぎるのだ。危険な兵器につながる研究は禁止。人体改造に通じる研究は禁止。精神操作もだめ。
望む分野の知識は、辺境でしか得られないとわかったり、せっかくの発見を、法律の制限のために封印しなければならなかったり。
何より、上司の命令というやつが一番気に入らない。なぜ、俺より頭の悪い連中に、研究の方向まで命令されなくてはならないのだ?
そこで、市民社会に別れを告げて、辺境に戻ることにした。
大学や科学技術局の友達とは、必要になれば連絡できるから、永遠の別れではない。彼らが辺境に亡命したいと望んだら、助けてやることもできる。
戻った先は、母親のいる《フェンリル》ではなかった。そこではどうしても、リザードの決めた枠内にはまるしかないからだ。俺は市民社会の制限も気に入らないが、辺境の違法組織の卑劣さも大嫌いだ。
中央で過ごした年月のおかげで、バイオロイドの製造と酷使がどれほど非道なことか、よくわかるようになった。
非道というのは、自分の気持ちが暗く不愉快になるということだ。
そんな世界は、長続きするはずがない。
そこで、リリーが自分の故郷である違法都市《ティルス》に連れて行ってくれ、一族の最長老に紹介してくれた。
俺の父親の遺伝子設計をし、手元で育てたという女性だ。長い黒髪の、麗しい貴婦人に見えるが、実際には、一族に君臨する絶対の指導者らしい。

しかし、俺が辺境に戻ったと知ると、おふくろが面会にやってきた。しかも、五歳になる俺の〝妹〟を連れて!!
やむなく《ティルス》のホテルで対面したが、こちらは唖然呆然である。
俺が大学を気に入り、市民社会に馴染み、《フェンリル》にはもう戻らないと判断した時に、おふくろは次の子供を〝創った〟のだ。
今度はいったい、誰の遺伝子を使ったのか。自慢そうにしているところを見ると、自信作らしいが、由来を説明してくれないのが困る。
「誰が父親でも、それはわたしの選択だから、あなたには関係ないわ」
とは、どういう意味だ。それなら、妹だなんて言って、俺に引き合わせるな。
俺の遺伝子には、おふくろの遺伝子はほとんど入っていないのだから、父親が違うのなら、この梨莉花との血縁関係なんて、ないに等しいじゃないか。
「さあ、梨莉花ですよ。抱っこしてあげてちょうだい」
子供は癖のある黒髪に黒い目で、健康な蜂蜜色の肌をし、とても可愛かったが、
「お兄ちゃん、お兄ちゃん」
と呼ばれるのには閉口した。
まとわりつかれるのは、まあ嬉しくないこともないが、どんな顔をすればいいのだ。本当に兄妹かどうかも怪しいのに。
おふくろはただ、自分が所有できる人形が欲しいだけではないのか。この子が成人して独立したら、また次の人形を創るのではないか。
そんな母親に、どんな教育ができるか怪しいものだ。
俺だって、自分で逃げなければ(リリーがさらってくれたから、楽に距離を取ることができたのだ)、まだ母親の支配下にあったことだろう。この子は女の子だから、余計、逃げにくいかも。
(すると、もしかして、俺がこの子のことを、気にかけてやらないといけないのか!!)
と気づいて愕然とした。おふくろが猫可愛がりにして甘やかしたら、どんなわがまま娘に育つか、わからないからだ。
わがまま娘が違法組織の中で地位と権力を握ったら、大変なことになる。何としても俺が、良い影響を与えてやらなくては。
リリーには、笑って言われた。
「いいじゃない。面倒見てやりなさいよ。人を育てて初めて、本当の大人になれるってもんよ」


「あいつの相手は、本当に疲れる」
俺の愚痴は、《ティルス》でできた友人、ミカエルが聞いてくれた。
彼は、最長老である麗香さんの元で、助手として暮らすようになったバイオロイドで、信じられないことだが、リリーと相思相愛の仲らしい。
俺にとっては師匠であるリリーが、ミカエルには、少女のように可愛い女に見えるというのだ。
「リリーさんに甘えられると、嬉しくて、ぞくぞくするんですよ。大きな虎が、子猫みたいに懐いてくるなんて、たまらない快感です」
