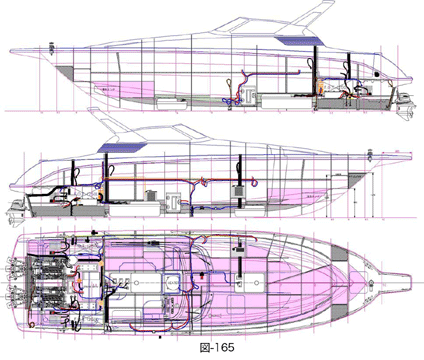連載-ボートデザイナーの仕事(第10回)

連載-ボートデザイナーの仕事(第10回)

■5章 基本設計 開発承認が得られると設計作業が本格化するが、開発手順は企画の中身にもよるが検 討項目は山ほどある。検討内容は相互に関係し合っている場合も多いのでいつまでも 検討しているとさっぱり開発が進展しない。 実は何を最初に決めねばならないかは 設計の都合ではなく試作現場の都合による場合も多い。FRP量産艇の開発は木型(オ ス型)→FRPメス型の順序で製作されるのでハルとデッキの木型の製作が先行するこ とになる。すなわちハルラインズとデッキラインズが優先となる。しかしボートデザ イナーとしてこれらのラインズを描けるようになるには経験と資質が必要である。プ レゼンテーションまでにかなり詳細に検討しているが、量産における製造工程を考え また原価意識を持ってラインズを描くのは大変である。例えば木型は全長を等分した セクションに外板を張るわけであるが、セクションを決める際、オフセット数値を細 かく決めるよりも、面の構成を単純な円を組合せて設計すると試作現図も楽である。 図-119は円弧を使用して形状を決めた例である。5-1ハルラインズ ハルラインズはボートの基本性能に関わる重要な作業であり、浮力、滑走性能、安定 性等を考慮し、完成状態の重量重心を予想しながら数回のシミュレーションの結果を 反映させた修正を加えて完成させる。これらの作業を効率的に行うには過去の類似艇 を参考にし、普段から自分が手がけたボートのデータを整理し応用できるようにすれ ば効率的である。プレジャーボートの設計で重要なことはハルラインズにも感性を持 つことである。デッキラインズほどではないにしてもボート全体の魅力や雰囲気に合 わせたラインズを作れるようになるには経験と資質(感性)が必要である。その為に はふだんから船舶に限らず多くの造形物を見て感性を養うように心掛けると良い。図- 120は23FTフィッシャーマンのハルラインズである。
5-1-1 適正機関出力の検討 ハルラインズで重要なことは企画で決めたエンジンが搭載可能かどうかである。安 全で適正な機関馬力であるかは試作艇のテストでも確認するがまずは小型船舶安全規 則の適正機関出力計算で確認を行う。船外機艇ではモーターウェルの高さも重要な要 素であるからトランサムにおける船底のV角度と全長、全幅、深さ、トランサムの計算 幅、モーターウェルの高さも規則を満たすよう検討しトランサム形状を決定する。図- 121は23FTフィッシャーマンのトランサム形状を示す。
上記23FTフィッシャーマンの例では全長7.5m、トランサムV角度が15°以上、トラ ンサムの計算幅が2.3m、モーターウェルの高さを64cmとし、計算を行なったのが表 -40である。 その結果、搭載馬力は船外機の場合250PS、船内外機の場合388PSま で許容されることを示している。
基本ハルラインズが決まると、FRPの積層も考慮しながら細部のRを指示するのであ る。FRP構造は剛性が小さいのでできるだけフラットな面を避け、曲面の形状の方が強 度の面でも有利である。 設計者は基本となるR定規(テンプレート)を使い、実際にオス型を作る現場も原寸の テンプレートを準備すると工数低減となる。またチャインやストライプのコーナーは 水切りを良くするためにできればピン角が良いがそれは無理なので最少Rを設定する。 実際の積層作業ではガラス繊維が曲がらないのでペーストなどを充填することにな る。海に浮かべてしまえばスタイリングは気にしない人も多いが、マリーナで陸上保 管の場合は船首付近のスタイリングや表面仕上げは乗用車と同じように気を使う顧客 も多いようである。
5-2 デッキラインズ 量産プレジャーボートは不特定多数の評価を受けるので外観のアピール度と性能や 機能の充実が求められる。機能や性能に詳しいデザイナーが一人で全体をまとめれば ベストだが、大企業でハルデザインとデッキデザインを分業する場合は企画に対し同 じ感性で統一することが重要だ。ラインズを木型作成段階の現場でチェックする際、 わずか数ミリのチャインラインの修正にこだわる場合もある。平面で作成したライン ズを立体で見るとイメージと異なることも多く、やはり実物(木型)で確認すること が重要である。最近はパソコンで3次元モデリング利用が多くなり、外観イメージをい ろんな角度から検証することが可能にはなったが、クレイモデルなどで形状を検討す るのも良い方法である。最近のデザイン検討は製図台からパソコンでの設計作業と変 わってしまったが手作業も捨てがたい。企画当初のイメージスケッチは開発ポリシー を見失わないためにもデザイナーは経験と知識と感性をフルに働かせてラインを決め ていかねばならない。 5-2-1 デッキラインズ検討例 量産釣りボートは釣り機能重視とは言え家族や友人を乗せることもあるし、快適な 遊びの空間が必要である。プレジャーボートも大衆化したが、やはり乗用車に比べる と愛好者が限定されており、魅力ある商品にするには工夫も必要である。低価格基本 モデルの大衆艇でも手抜きや検討不足が見えてはダメでオプション設定を充実させれ ば魅力的な商品になる。今後の量産ボートは最初から贅沢な装備は販売価格が高くな り一般ユーザーの購買意欲を満たすことはできないのでユーザーがオプションを選択 できるセミカスタムボートとして事業化するのも一考の価値があるかもしれない。 FRP量産ボートは1モデルで200隻程度販売できればFRP型投資は回収できるので、必 ずしも大量産にこだわる必要はない。販売が好調なRV車の仕様を参考としてセミカス タムボートの仕様を検討してみる。
表-45はRV車の仕様の例であるが車と船では使用環境も違い品質保証の面で慎重にな らざるを得ないが、車のオプション部品は品質も向上しているのでユーザーのリスク で試みるのは自由であり案外ユーザーの工夫図-123、124は多様化する遊びを多くの オプション設定を考慮した19FTフィッシャーマンのスケルトン図と外観図である。 デッキラインズを作成するに当たっては企画時のオプション設定にも充分に配慮をす ることが重要だ。
開発作業では木型が先行するのでデッキラインズの検討が中途半端であると後で修正 することはかなり困難である。下図は19FTカディーフィッシャーマンのデッキライン ズの例である。
5-3 一般配置の検討 一般配置の検討は始まりと終わりがはっきりしない。初期企画の時点で一般配置図 を作成するが限られた時間内で企画の要点を検討する十分な時間がないので作成者の 経験と技量によって作成する。一般配置図は重要な図面であるが詳細な検討の後に必 要な箇所は少しずつ修正される。図-126は一般配置図が開発プロセスで何度も修正さ れるのを示す。
5-3-1 一般配置図 開発プロセスでは一般配置図が当初からほとんど変らない場合も有るが、何度も修 正されかなり変化する場合もある。図-127は量産ボートではないが全長30mの観光船 の例であるが、開発当初と完成時ではかなり変化したのが分かる。
5-3-2 総トン数計算 総トン数は課税や船舶職員法他の判断基準として使用し、船舶の容積をベースに計 算する。総トン数の計算は、測度長24m以上と未満では計算方法が若干異なる。これ は日本独特の免許制度である。長年、小型船舶操縦士免許は総トン数20GTで制限を受 けていたが、最近小型船舶免許制度の一部改正により、小型船舶操縦士免許で操船可 能なサイズが全長24m未満へと緩和されたので総トン数20トン以上の小型船舶も増え ることが予想される。しかし、総トン数計算は従来の24m未満の小型船舶用の簡易計 算と24m以上の計算法では矛盾が生じることが分っている。そこで総トン数計算を測 度長24m未満と24m以上の両方の計算方法を比較してみた。 使用した主要目は次の通りである。 全長(Loa):24.00m 測度長(LT):23.60m 積量幅(DT):5.90m 積量深さ(DT):2.32m シヤー深さ(DS):2.89m カタ深さ(Dm):2.80m キャンバー(C):0.10m
(1)測度長24m未満の計算方法を用いた場合 ●船体主要部の容積 船体の容積は次の算式により求める。 Vu = 0.65 × LT × BT × Dm = 0.65 × 23.60 × 5.90 × 2.80= 258.417ɠ ●上甲板上の閉囲場所の容積及び除外場所の容積(上甲板上の容積計算は図-127参 照) 上甲板下の船体上部の容積=(最大の長さ) × (平均幅) × (平均深さ・高さ) 付加物の容積=(最大の長さ) × (平均幅) × (平均深さ・高さ) 閉囲場所の容積(上甲板上の閉囲場所及び除外場所の容積)=(最大の長さ)× (平均幅)× (平均深さ・高さ) 計算結果 合計容積V= 閉囲場所の合計容積+除外場所の合計容積 = 258.417ɠ + 207.572ɠ = 465.989ɠ 国際総トン数t = 118トン 総トン数 GT = 36トン (2)測度長24m以上の計算方法を用いた場合 24m未満の計算方法との違いは、船体容積と総トン数(GT)の計算方法である。 ●船体主要部の容積 船体主要部の容積はシンプソンの第1法則により計算する。ただしLppは垂線間長では なく上甲板の前端から後端までの長さとした。 ●上甲板 上の閉囲場所の容積及び除外場所の容積(上記と同じ計算法) 計算結果 合計容積V = 閉囲場所の合計容積+除外場所の合計容積 国際総トン数t =115トン 総トン数 GT =70トン (3)計算方法の比較 2方法による計算結果を表にして比較する。
計算結果は24m未満の計算方法による総トン数は36トン、24m以上の計算方法で70 トンと大きく異なる。この結果の違いは総トン数と国際総トン数計算に用いる係数の 取扱いにありそうである。この関連をグラフにして比較すると明確である。(図-129 参照) これによると国際総トン数が100トンの場合、総トン数は37トンとなりそれ以降は減 少し国際総トン数210トンで総トン数は0トンと奇妙な結果となってしまう。これらの 矛盾はいずれ法律の改正が行われると考えられる。 (現在20m未満は簡易積量測度で計算) 5-3-3 オプション艤装図 企画段階で標準価格とオプション価格を設定する。顧客が満足するよう低価格で高 品質を設定したいが、標準仕様を充実させ過ぎると製造原価が高くなり販売価格も高 くなってしまう。そこで艤装品をストリップダウンしてオプション設定とし標準モデ ルの販売価格を低く設定する場合が多いようだ。数十年前は乗用車の価格設定ではエ アコンもオプションとする廉価版もあったが、現在は極端な廉価版は消え失せた。残 念ながらプレジャーボートは乗用車ほど仕様の向上は実現していない。これはプレ ジャーボートの小さな市場規模と自然環境が厳しいので艤装品の技術開発が遅れてい るのも理由である。そこで顧客は購入後に高いオプション部品を取付けるのである が、ユーザーにとっても選択部品が多いと自分の好みにあったカスタムボートを持つ こともできる。例として小型量産ボートのオプション艤装図を示す。図-130
5-4 構造の検討 FRP量産ボートの場合、ラインズが完成すると試作現場では木型製作準備に入ること になる。一方、設計者は木型製作のフォローをしながら詳細設計に追われることにな る。木型、FRPメス型が完成し試作艇の積層が始まるまでの期間はボートの大きさに よって異なるが、いずれにしてもこの期間に構造図を始め試作に必要な図面の作成と 部品の手配を済ませねばならない。部品はパーツリストを基に手配し試作段階では変 更も多く、設計者はそのフォローに振り回される。同様に図面も修正を繰り返しなが ら作業を進める。どの図面を先行させるかは難しい判断だが試作工程を考えるとハル 構造図を優先するべきである。 5-4-1 ハル構造図 船舶設計ではどの分野が最も重要かは一概には言えない。船舶の種類により重要な ポイントが違うからである。しかし一般的に重要なのはハル構造であり、充分な強度 を持ち、且つ作りやすくコストを出来るだけ低減させる工夫が必要である。もちろん FRP船特殊基準を満たしているか確認をすることも重要である。長年のボート製造経験 のあるボートビルダーは独自のノウハウを持っている場合も多い。これらのノウハウ とは量産技術に関連する生産技術や過去の試作で発生した不具合点、市場からのク レーム等による品質改善などの集大成である。設計者はこれらの記憶をたどり、ノウ ハウ資料を読みながら設計作業を進め試作用ハル構造図を完成させる。ハル構造設計 の手順としてはハル外板の厚さすなわち積層構成を決めねばならない。滑走艇では速 力により船底圧力が変化するので最高速力でまず船底圧力を設定し、船底パネルが充 分な強度を持つように船底厚さを決定する。船底は単板だけで形状を保つことはでき ないので適当に補強材が追加する。補強材が少なければ当然船底外板の厚さは大きく なり重量も増すが補強材が少ない分、取付け工数は少なくなる。補強材を細かに配置 するとハル外板は薄く軽量化にもなるが組立工数は増すことになる。設計者は企画の 原点を考えながら総合的に構造を決定するが、量産数が多い場合は補強材も型による 一体構造としコストを低減している。図-151、152は補強材を型で一体構造とした場 合と合板を組合せた構造を示している。
図-153は最終的に完成したハル構造図(23FT)であるが大型艇では艤装品取付けの 為の補強材も追加され記載内容も複雑で図面も数枚になる場合もある。
5-4-2 ハル補強材一覧図 船体を製造するには補強材をすべて拾い出さねばならないがこれを一覧図にまとめた のが図-154である。この図面には原価や重量計算の要素である表面積、材料名、重心 位置などを記入する習慣を作ると後で技術計算やコスト計算が楽である。
5-4-3 デッキ構造図 ハル構造と同時にデッキ構造の検討も同時に行う。プレジャーボートはデッキ艤装品 配置の善し悪し(使い易さとなど)が商品性を左右するのでボートデザイナーにとっ て手腕の見せ所でもある。デッキ配置の概略が決まるとこれに関連してハル構造も当 然修正が加えられることになる。市場で評判の良いボートとなるには優れたデッキレ イアウトとこれをうまくまとめたハル構造の両立は不可欠である。デッキ構造設計は ハル設計と同様であるが、船舶設計の基本として安全性、安定性を考慮するとデッキ 構造は堅牢かつ軽量を両立させる必要がある。軽量化の有効な手段としてはサンド イッチ構造が代表的である。実際にほとんどのFRP艇レジャーボートが採用している。 FRPは引っぱり強度に優れているが剛性(曲げ剛性)が低い材料であるがサンドイッチ 構造には適している。例えば人や物を載せるパネル部分は適当なサンドイッチ構造に すべきである。ただ注意すべきはサンドイッチ構造に使用する芯材の選択である。芯 材としては合板、バルサ材、樹脂発泡材などがありそれぞれ利点があるがボートの商 品性を良く考慮して選択すべきである。一例として樹脂発泡材は芯材の比重が0.1以下 で軽量化の効果は抜群であるが表面材との接着が不確実だと剥離してしまいサンド イッチ構造が成り立たないのである。またサンドイッチ構造では剥離を防ぐ為に樹脂 を多く使う傾向にあり軽量化の効果が少し損なわれている。量産ボートではお客が購 入後オプション部品を取付ける場合を考慮して部品を取付けそうな場所の芯材は圧縮 強度に強い合板を部分的に採用しているが、釣り船のように改造する可能性の高い ボートでは多少軽量化をあきらめ芯材として合板や圧縮強度のあるコアマットなどを 採用する場合も多いようだ。 量産艇の軽量化で特に気をつけるべきことはガラス繊 維のオーバーラップである。強度的にはそれぞれのガラス繊維は25〜30mmラップし ていれば強度上問題はないが作業時間を重視する量産艇ではいちいちこのラップ寸法 を測りながら作業を進める訳にはいかない。作業者の技量にもよるがこのラップ代に 余裕をもって50mm以上にするとたちまち重量増加となるのである。ラップ率をでき るだけ下げることが軽量化を実現させまた材料使用量(材料費低減)を少なくするこ とになる。また材料使用量が減ると作業工数の低下にもなりコストダウンを実現させ 結果的に利益率の高い商品となる。このことは量産ボートデザインにおいては常に考 えておくべき重要なポイントである。ここで間違いのないように説明を加えておくが ラップ率を下げるには生産技術部門の存在を忘れてはならない。構造図に合わせてガ ラス繊維の型紙を作ったり歩止りを検討したりして設計者の考えを支えるこれらの部 門がないと魅力あるボートは完成しないのである。図-155は最終的に完成したデッキ 構造図である。
5-4-4 デッキ補強材一覧図 補強材組合せ構造の場合は補強材を拾い出さねばならないがこれを一覧図にまとめ たのが次図である。この図面には原価や重量計算の要素である表面積、材料名、重心 位置などを記入する習慣を作ると後で技術計算やコスト計算が楽である。
5-4-5 軽構造船暫定基準 舟艇の構造材料はアルミニウム合金とFRPが主流である。アルミで船体を設計する場 合は軽構造船暫定基準により各部材を検討しなければならない。部材の寸法を軽構造 船暫定基準で検討する場合にはパソコンで簡単なプログラムを作成すると便利であ る。以下は汎用ソフトエクセルに規則を入力し部材寸法を検討できるようにした簡単 な計算ソフトの例である。表-52は外板寸法の検討を示しているがこのようにして各部 材の検討を行うことが可能である。
5-4-6 FRP船特殊基準 舟艇の中でもプレジャーボートの構造材料はFRPが主流である。FRP船の場合、FRP 船特種基準により船体構造を検討する。軽構造船特殊基準と同じく各部材が基準値を 満たすように検討する。部材の配置とサイズを検討するにはパソコンで簡単なプログ ラムを作成すると便利である。以下は汎用ソフトエクセルに規則を入力し部材寸法を 検討できるようにした簡単な計算ソフトの例である。表-53は外板寸法の検討を示して いるがこのようにして各部材の検討を行うことが可能である。
5-4-7 中央断面の検討 滑走艇の強度検討はホギング、サギングといった縦曲げモーメントや静水圧による 外力ではなく走行中の波の衝撃荷重から検討すべきである。しかし、滑走艇の中央断 面における応力検討も比較を行う意味では有効であり断面係数の計算は是非行うべき である。図-157は80FTモーターヨットの計算例であるが縦曲げ強度の判定では材料 の耐力σγは船体の縦曲げ応力σに対し安全率が上甲板側では約8倍、船底側では約 12倍であることを示している。この結果は走行中の水圧を設計外力として計算した結 果が排水量型船舶の船体中央部における縦曲げモーメントと比較すると充分に強度が あることを示している。 M:船体の縦曲げモーメント(Ton-m)Z:船底側又は甲板側の船体中央断面係数(ɦ ×ʄ)
5-5 甲板艤装の検討 小型ボートのデッキ艤装品数はそれほど多くはない。係船装置としてクリート、 フェアリーダ、アンカー、ウインドラス、安全装置としてはバウレール、スターン レール、ホーン、航海灯他にハッチ、窓、釣り用艤装品、ベンチレ−タ等である。こ れらの艤装品は甲板艤装図に取付け位置を記入するが艤装品はそれぞれ機能を持って いるので良く検討し取付け位置を決定しなくてはならない。 5-5-1 係船揚錨装置 船舶は海上の船舶や岸壁に係留する機会があり、その際はロープをボートの係留装 置すなわちクリート、ビットボラード等に結わえなければならない。海面は穏やかな 場合ばかりではないので波浪中では係船装置に大きな力が加わることになる。そこで これらの係船装置はしっかりと甲板にボルトで固着しなければならない。FRP艇の甲板 剪断強度は弱いので係船装置等をボルトで甲板に固定する場合は甲板裏面に大きな座 金(ワッシャー)をセットして面圧を下げて固定している。図-146はクリートの取付 け詳細を示す。
プレジャーボートも洋上係留に備えてアンカーは備えているが例え5kg程度の軽量ア ンカーでも水深50mから1人で引き揚げると大変な作業である。特に釣り舟のように 多くの場所でアンカーリングするボートでは巻き上げ作業を人力で行なうと大変なの で大抵は揚錨装置(ウインドラス)を取付けている。これらの揚錨装置は係船ロープ とアンカーチェーンの両方を巻き取れるようになったウインドラスもあるが小型釣り 舟では横型の安価なウインチが多い様である。これらの揚錨装置は錨の重量や巻き上 げ速度および船体のサイズを考慮して仕様を決めるようだ。 図-147は比較的大型のプレジャーボート用の縦型揚錨装置の例である。
5-5-2 安全レール類 安全備品であるハンドレールなどの取付けは乗員が実際に掴まり易い位置となって いるかを考慮しなければならない。特に波浪中を走行時に暴露甲板を安全に移動する 為にハンドレールは是非必要であり、舷側に沿ったレールやキャビン側璧にも小型の ハンドレールを適当な数配置するべきである。レールの材質はステンレス製が良いが 量産艇では原価低減のためにサイズが標準化されたレールを使用するのが普通であ る。フライングブリッジがあるクルーザーでは昇降ラダーやFBレールは特に安全に留 意すべきである。 5-5-3 ハッチ、倉口 暴露甲板には係船ロープやアンカー、さまざまな備品を収納するロッカーが配置さ れる。釣り舟であればイケスなどのハッチも設置される。暴露甲板は波浪中に波をか ぶりハッチから海水が侵入するのでハッチのシール(水密)は重要である。 規則上も航行区域によりハッチコーミング高さは決められているがプレジャーボート ではハッチの上面が他の面と同じ高さのフラッシュハッチが多い。ハッチの裏には海 水の侵入を阻止する為にゴムパッキンが取り付けられている。パッキンが効果を持つ には適当な力でハッチを押さえるロックが必要である。図-148はフラッシュハッチ断 面の例を示す。
5-5-4 生簀(いけす) 釣り船には生簀を設ける場合が多い。小型釣り舟や漁船のように船底にスカッパー を取り付ける場合と大型スポーツフィッシングクルーザーのように循環式の生簀を装 備する場合がある。以前の釣り愛好者は釣った魚を生かして持ち帰れば新鮮との錯覚 があったが現在は魚の鮮度を保つ為には釣り上げてできるだけ早く絞めて血抜きを行 ない冷蔵する方が良いとの考えが普及しクーラーボックスやアイスボックスを装備す る船が増えている。生簀の役目も業務用漁船は別としてプレジャーボートでは生き餌 を運ぶために設備へと変わりつつあるようだ。しかし小型釣り舟でも相変わらず生簀 を装備する船も多く船底から海水を取り入れる場合の安全規則もあり生簀のサイズも 制限されている。図-149は小型釣り舟の生簀設置要件である。
5-5-5 甲板艤装図 図-150は23FT小型釣り舟の甲板艤装図である。量産艇では図面に取付け要領などは あまり記入しない場合が多い。これは量産では品質管理が重要であり取付け要領など は作業標準などで厳しく管理されているからである。それでも対象となるボートで特 に注意を喚起する必要が有る場合には取付けの詳細を記入することもある。(品質管 理や生産技術に関しては後述する。)また量産ボートではオプション部品の取付けに も考慮が必要だ。企画段階でオプションを設定するのだが購入者のオプション装着率 が高い艤装品はメーカーオプションとする方が無難である。この場合は事前に船体構 造に補強部品を準備しておくこともできる。しかしメーカーオプションは価格も高い ので購入者が市販品を取付ける場合も多いのでこれを予想して事前に対応しておくか は重要な課題である。
5-6機関艤装の検討 プレジャーボートの主機関の装備方法としては次の3種類が一般的である。 ●船外機(OUTOBOARD MOTOR) ●船内外機(STERNDRIVE) ● 船内機(INBOARD DRIVE) ● ポットドライブ(POD DRIVE) 代表的な主機関の装備方法で量産数が多いのは圧倒的に船外機であり次に多いのが船 内外機である。22〜28FTの小型艇ではどちらも搭載可能となるように開発初期段階 で検討しておくと開発投資を少なくしモデルバリエーションが増やすことができる。 ここではその両方を考慮した小型艇について解説する。 5-6-1 機関艤装図 機関艤装で重要なことは規則を満たすことは当然で、安全で取り扱い(保守点検) が容易なことである。もちろん主機関や機関関連機器が最高の性能を発揮できるよう 配慮した機関室の設計が重要である。図-131は23FTフィッシャーマンの機関艤装図 である。
●主機の取付け(エンジンセット) 船外機も船内外機も通常はエンジンメーカーの取付けマニュアルが準備されており 注意事項も記載されているのでこれらを参考に機関艤装設計を行う。船外機ではモー ターウェルの規則通りに設計するだけだが、船内外機は機関室(エンジンルーム)内 の換気やメンテナンスが容易となるようにエンジンハッチなどの大きさや形状を決め なければならない。船内外機ではエンジンルームの大きさを決める場合、メンテナン スの為にエンジンを取り外すことが可能な寸法とする。船外機も船内外機も推進ユ ニットは船尾から離れており急旋回や急加速など負荷がかかるとプロペラが空気を吸 い込むエアドローの現象が発生する。これらを防止する為にキャビテーションプレー トなるパーツが取り付けられているが、このセット高さ(エンジンセット高さ)は性 能に微妙な影響を与える。急旋回時にエアドローが発生するとプロペラは回転数が急 に上昇しスラストを失い船体は失速し座り込むような状態に陥ってしまうことがあ る。こうなると一時的に操縦不能になり危険なのでキャビテーションプレートを水中 に少し深めにセットし防止するよう設定すると付加物抵抗は増加してしまう。国産 ボートはこのエアドロー現象を気にする傾向にあるが米国のボートに試乗してみると 急旋回では結構エアドローが発生しても気にしていないようである。 ●艤装品の取り付け エンジン関連の艤装品としてはバッテリー、メインスイッチ、制御ケーブル、燃料 配管、電気関係配線他などであるが、機関艤装で留意すべき点は安全性、整備性であ る。バッテリー端子にはショート防止のキャップをかぶせ、ケーブルは無理な取り回 しは避け燃料配管も耐熱、耐油ホースを無理なく配管せねばならない。また最近は騒 音対策としてエンジンルームに遮音材や吸音材を張り付ける場合も多く、排気管など の高熱部と十分なクリアランスを確保することも重要である。 5-4-2 プロペラ直径及びピッチの検討 船外機艇や船内外機艇ではオリジナルのプロペラを設計することはほとんどなく、 エンジンメーカーで設定されている数種類のプロペラから最適となるピッチとダイヤ を選択する。一方、大型船内機艇は大馬力機関の搭載が多いので最適なプロペラを設 計する。プロペラ設計は推進効率が最適となる機関減速比、直径とピッチを選択す る。プロペラセッティングにより最高速力重視、加速重視などボートの性格が決ま る。初期企画ではプロペラ設計も考慮し、ギヤボックスの機関減速比を選択し、最良 な走行性能となることが大事である。しかしプレジャーボートの主機関配置は重心位 置に影響を与えるので必ずしも推進効率の良い直径の大きなプロペラを選ぶことはで きない場合もある。下表は最適プロペラを設計する簡単なプログラムの例である。こ れは高速艇用のガウンタイプの翼型で展開面積比0.65〜0.95のプロペラ性能特性カー ブをプログラムに組込み計算している。この方法を用いれば短時間に何種類ものプロ ペラを検討できるので機関配置の検討に便利である。
プロペラ直径とピッチを検討する際、最高速力が高いプロペラを選択するのは大事で あるが、加速特性の向上や滑走に移行しやすくするためプロペラピッチの特性も知っ ておいた方が良い。サンプルのグラフはピッチ比が異なるとプロペラ特性が大きく変 化することを示している。これはエンジンのトルク特性とも関連するので過給器付き ディーゼル機関では特に注意が必要である。新規開発のモデルで、エンジン開発も関 連するプロジェクトではエンジン特性の改善にもプロペラ特性は理解しておくべき だ。
5-6-3プロペラシャフト計算 船外機艇や船内外機艇ではプロペラシャフトを設計することはほとんどないが船内 機艇ではプロペラと共にオリジナルのシャフトを検討する必要がある。大型艇では捻 り振動の複雑な計算も必要であるがこれらの計算は専門メーカーに任せることも可能 で基本設計ではシャフト直径と材質およびシャフトベアリングのサイズを決めること が重要である。表は最適シャフトを設計する簡単なプログラの例である。ここでは機 関規則に合わせて直径を決めるが決定するシャフト径は市販されているシャフトベア リングのサイズに合わせて選択するように設定されている。
5-6-4 舵断面形状の特性について 舵断面は流線型舵、平板舵、楔形舵などがあり、高速艇の舵は楔形が良いとされて いる。しかし、大型の貨物船、軍艦や客船などと異なり、舟艇はコストや船価の低減 が重視され、多少舵の性能が悪くても採用される場合も多い。小型漁船などは、ほと んど平板舵が採用されている。これらの舵形状の差はあまり知られていないが舵直圧 力に付いて調べてみた。舵の効きは直圧力で決まるが意外にも操舵角15°未満では舵 断面形状の差はないことが判る。高速で走行中は緊急時を除いて大きな舵角をとるこ とはないので特別に高速を求めない限り、製造費の高い楔型舵は採用する必要はなさ そうである。
5-6-5 舵強度検討 舵の設計では旋回性を重視すれば舵面積が大きい方が当然良いが高速艇では付加物 抵抗が大きくなるので最小限にしたい。舵の軸径と舵取装置の能力計算は簡単なプロ グラムを使用して計算できる。以下は、舵に加わる力と舵トルクをJossel Beaufoyの 式による計算例である。
舵軸の強度計算は軽構造船規則とJossel Beaufoy式のどちらを採用するかは設計者 の判断によるが高速艇では後者の方が厳しい結果がでるようである。
5-6-6 換気計算書 機関室は機関が充分に性能を発揮するよう充分な空気量を取入れる必要がある。特 に過給器を備える最近のディーゼル機関は大量に空気を消費し、発生する熱量も大き いので機関室の換気は重要である。理想的には機関室温は40℃程度が良いが現実には 難しいようである。換気が不足すると機関自体が機関室の空気を吸い込み気圧が下が りキャビン床が沈むなどのトラブルも発生するので注意が必要である。次表は機関規 則による機関室の換気計算書の例である。
5-7 諸管艤装の検討 小型艇の諸管装置はビルジ配管、簡単なギャレー装置用の清水配管くらいであるが 大型のキャビンクルーザーになると一般家庭の諸設備は完備しておりシステムは結構 複雑である。最近は海洋環境対策で汚水の投棄が制限されており一時的に保管するタ ンクも装備せねばならない。配管自体は家庭用とさほど変わらないが海上で使用する ので材質は耐食性に優れたステンレスやプラスティックが多用されている。船舶の配 管で留意する点は多い。例えば温水系統にエンジンの冷却水を使用する場合は取付け と点検には注意を要するのである。 なぜなら温水機も熱源としてはエンジンの冷却用温水を耐熱ホースで導くのであるが 万一ホースが耐熱用でなければ破裂し冷却水が抜けてしまいエンジンはオーバーヒー トして航行不能になってしまうのである。また配管に使用するポンプの能力も良く理 解しておく必要がある。ポンプの吸上げ能力と押上げ能力をうまく考慮して取付け位 置を決めなければ必要な流量が得られないのである。また海水配管では船底に取付け るスルーハルの位置は操作がしやすいように注意が必要である。このように注意すべ き点は多々あるが造船所では作業マニュアルや設計マニュアルまたは技術基準等とし て整備されている。 5-7-1 諸管系統図 図-164は30FTキャビンクルーザーの諸管系統図を示す。表現法法としては電気系 統図のように系統重視の線図で表現する場合もあるが小型艇ではできるだけ判り易く 表現する為に管関連部品の図を表示すると判り易い。
5-7-2 諸管艤装図他 諸管艤装図は他の艤装図すなわち電気艤装図、室内配置図、機関艤装図、船体構造 図などとの関連も考慮し諸管艤装品の位置を決め諸管経路も整備性や安全性等も考慮 し決める。図-165は各種艤装関連をまとめて記入したスケルトン図である。このスケ ルトン図は作成すると諸管艤装図はもちろん他の艤装図との関連が良く判るので是非 作成したい検討図である。