連載-ボートデザイン開発編(第8回)

連載-ボートデザイン開発編(第8回)

4-3基本設計2(基本設計図決定:PHASE-3)4-4-1ヤード設計の流れ(構造、艤装、試作、予算、開発日程の検討) 建造開始に伴い設計部門が責任部署として関連部署と調整が必要。 特に艤装品納期が重要な資材部門とは密に情報確認。 製造部門へは製造工程に合わせて詳細構造図、補強材一覧図を作成して出図。 生産技術部門は製造部門のサポートとして作業要領書、治具等を準備する。 大型構造部品のハードトップ、ハルライナー、トイレユニット、ギャレーユニット、天井、家具、階段や市販品に ない専用艤装品は内作するか外注へ製造委託。 小型部品のハッチ、窓他や市販品にない専用艤装品は外注へ製造委託。 設計部門はできるだけ購入品を採用するよう努力する。 全体製造工数を低減のため主要なハルとデッキは個別に製造し、上向き作業を避ける ため可能な艤装は早期に済ませ、内装工事の前に配管、配線、防音工事は済ませてお くことが重要。(カップリングはできるだけ遅らせる。) 全体工程管理は設計と製造部門及び資材部門が密に連係して調整する。 重量管理を重視し可能な限り実際の重量を計測しカップリング直前の状態で重量重心を計 測する。(設計または品質管理立会い) 管理を確実に実施するには作業カード(JOBカード)を発行し作業内容を明確に 指示し、重要な場面では設計者が製造中立会いを密にし問題点の解決と不具合点 をフィードバックする。(問題点会議を開催し現状把握と問題点の解決を図る。) 初号艇が完成後、設計と品質管理が確認し手直しが必要な場合は指示する。 4-4-2ハル構造 図面には必要以上の指示は省き要点のみとするが安全に関する部分は特別に指示 し、工事作業者には標準作業要領書や現場管理者から注意を喚起する。
●ハル構造詳細 主要構造図が変更されることはほとんどないが承認図や製造に必要な現場工作 図を追加作成する場合もある。
●ハル補強材一覧図 詳細な工作図の例としては隔壁詳細図、補強材一覧図を示す。 量産する場合は型板(テンプレート)を作成し、2隻目以降のコスト低減を図る。 重要な型板作成には設計者も立ち会い確認する
●ハルフロア構造図 船体外殻に主要ロンジ補強材や隔壁やフレーム等及びフロアを固着する。 船内艤装が始まるとフレームやフロア面を基準として寸法を確認するので必要 ならば図面上に基準面となる数値を表示する。(データムポイント)
4-4-3上部構造 FRP艇の上部構造の製造管理は難しく重量が超過することが多い。 そこで構造図面には補強材のサイズ指定やFRP積層工事の重量管理注意喚起を記入 する。(可能ならば途中工程で重量計測を明記する。) FRP作業は現場監督者の技量に左右されるのでFRP作業マニュアルも作成する。
● 上部構造図 上部構造図はインテリアデザインと関連して補強材を配置するので最終図面の 完成には時間を要するので製造部門と情報交換を密にし先行できる図面は仮出図 で対応したり必要に応じて主要構造関連の補助図面も作成する。 FRP作業は現場監督者の技量に左右されるのでFRP作業マニュアルも作成する。
● 上部構造補強材一覧図 複雑な形状の上部構造部分は現場合わせを出来るだけ避ける為に設計段階で標準 型板が使用できるように設計すると現場作業コストを低減可能。 量産する場合は型板(テンプレート)を作成し、2隻目以降のコスト低減を図る。 重要な型板作成には設計者も立ち会い確認する。
●上部構造フロア構造図 大型インボード艇は機関室直上にメインキャビンを配置する場合が多いので 機関室からの騒音の遮断や防音および振動防止のフロア構造とする。 必要な場合はFRP艇でもたわみ量が小さい金属フレームも採用する。
4-4-4機関機器艤装 船舶の運用で故障発生は機関関係が多いので日常のメンテナンスが容易になるよ うな配置が求められる。
●機関機器艤装図(機関関連配管、排気装置、燃料装置他) 機関艤装で重要なことは規則を満たすことは当然で、安全で取り扱い(保守点検) が容易なことはもちろん主機関や機関関連機器が最高の性能を発揮できるよう 配慮した機関室の設計が重要で下図は53FT艇の機関艤装図である。
図-131は人が出入りできない23FTフィッシャーマンの機関艤装図の例である。
企画の見直しがない限り基本設計で決まった機関室内機器配置が変更されるこ とはまずない。 実際の使用操作や整備性を考慮して機器の詳細な取り付け図を作成する。 下図は53FT艇の機関艤装図である。 ●主機関の取付け(エンジンセット) 主機の搭載はメーカーの取付けマニュアルを参考に機関艤装設計を行う。 船外機では規則通りにモーターウェルを設計し、船内外機は機関室内の換気や メンテナンスが容易となるようにエンジンハッチを設計する。 船外機も船内外機もセット高さ(エンジンセット高さ)は速力性能や旋回性能に 微妙な影響を与えるので慎重に決定すべきだ。 国産ボートはエアドロー現象の旋回性能を重視するが米国製ボートは急旋回で 結構エアドローが発生しても気にしていないようである。 主機関は重要な発注品としては金額も大きく承認図や検査機関の予備検査を 受けて納入される
● プロペラ 大型インボード艇のプロペラ手配では承認図を交わして外注したプロペラ、プロペラ 軸、スターンチューブ等は検査証明書を添えて納入を受けることになる。 プロペラ承認図
●プロペラ軸、船尾管 インボード艇のプロペラ軸系はほとんどの部品は外注あるいは購入品である。 重要保安部品なので検査機関の予備検査証を添えて納入される。
●燃料タンク 重要保安部品なので内作する場合は検査機関の予備検査を受けること。 外注する場合は予備検査証を添えて納入されること。
●防音防熱装置図詳細 近年は環境や居住性が重視されるので機関室内の防音や防熱工事は重要だ。 機関室内の温度が高いと燃料温度も高くなり主機出力も影響を受けるので充分な 換気が必要である。 特に業務艇では主機関の耐久性にも配慮しエンジンメーカーが推奨する換気能力 を満たす方が無難である。 機関室温度を熱源の排気管のやエンジンの熱量が大きいので防熱対策をしても 理想的な40℃程度まで下げるのはかなり難しいのが現実である。 ●機関室換気計算 機関室は機関が充分に性能を発揮するよう充分な空気量を取入れる必要があり、特に 過給器を備える最近のディーゼル機関は大量に空気を消費し、発生する熱量も大きい ので機関室の換気は重要である。 理想的には機関室温は40℃程度が良いが現実には難しいようである。 換気が不足すると機関自体が機関室の空気を吸い込み気圧が下がりキャビン床が沈む などのトラブルも発生するので注意が必要である。 次表は機関規則による機関室の換気計算書の例である。
4-4-5操縦操舵装置詳細図(操舵装置、機関制御、航海機器制御) ●操舵及び機関制御装置図詳細 小型船舶の操舵および機関制御装置は手動ケーブル式や油圧式の他に自動操縦と 組み合せた電動油圧式もあり、大型艇や業務艇では2ヶ所以上に操舵装置を設け 場合が多い。
●救命および防火装置図詳細 船舶安全規則の設備規定に定められた備品の配置図。 検査官から備品配置を示すステッカーやシールを添付を要求される場合も多い。
4-4-6諸管艤装詳細(海水、清水、汚水配管) 小型艇の諸管装置はビルジ配管、簡単なギャレー装置用の清水配管くらいであるが 大型のキャビンクルーザーになると一般家庭の諸設備は完備しておりシステムは 結構複雑である。 近年は海洋環境対策で汚水の投棄が制限されており一時的に保管するタンクも装備 せねばならない。(ホールディングタンクの設置) 諸外国の汚水系統はシャワーや手洗いのグレーウォーターとトイレ汚物のブラック ウォーターと明確に区別されている場合も多い。 配管自体は家庭用とさほど変わらないが海上で使用するので材質は耐食性に優れた ステンレスやプラスティックが多用される。 配管で留意する点は多く、例えば温水系統にエンジン間接冷却清水を使用する場合 は取付けと点検には注意が必要で温水器の熱源としてエンジンの冷却用温水を耐熱 ホースでなく普通のゴムホースを使用すると破裂しエンジン冷却水が抜けてしまい エンジンはオーバーヒートして航行不能になる恐れがあるからだ。 また配管に使用するポンプの能力も良く理解し、ポンプの吸上げ能力と押上げ能力 をうまく考慮して取付け位置を決めなければ必要な流量が得られないのである。 海水配管では船底に取付けるスルーハルの位置は操作が容易になるよう配慮する。注 意すべき点は多々あるが造船所では作業マニュアルや設計マニュアルまたは技術 基準等を整備することが大事である。 居住区が充実した小型船舶は各種配管艤装が複雑になる傾向にある。 小型船舶は狭小空間なので諸管艤装は取付け作業や整備も考慮してレイヤー機能 のあるスケルトン図で検討しながら配管艤装図を作成すると良い。
●諸管艤装図詳細 図-165は各種艤装関連をまとめて記入したスケルトン図である。 このスケルトン図は作成すると諸管艤装図はもちろん他の艤装図との関連が良く 判るので是非作成したい検討図である。 全長10m以下の小型艇は海水、清水、汚水系統を1枚の諸管系統図で済ませるが 大型艇や業務艇では海水配管図、清水配管図、汚水配管図、ビルジ配管図を別図 として作成することもある。
4-4-7甲板艤装詳細 小型ボートのデッキ艤装品数はそれほど多くはない。 係船装置としてクリート、フェアリーダ、アンカー、ウインドラス、安全装置と してはバウレール、スターンレール、ホーン、航海灯他にハッチ、窓、釣り用艤 装品、ベンチレ−タ等である。 用途別の業務艇は専用の機器が配置されるので安全性や重量物配置には特に留意 すべきだ。 これらの艤装品は甲板艤装図に取付け位置を記入するが艤装品はそれぞれ機能を 持っているので良く検討し取付け位置を決定しなくてはならない。 ●小型艇の甲板艤装図の例 図-150は23FT小型釣り舟の甲板艤装図で、量産艇では図面に取付け要領などは 多くを記入しないが、その理由は量産では品質管理が重要で取付け要領などは 作業標準などで厳しく管理されているからである。 それでも対象となるボートで特に注意を喚起する必要が有る場合には取付けの 詳細を記入する。 また量産ボートではオプション部品の取付けには企画段階でオプションを設定す る段階で購入者のオプション装着率が高い艤装品はメーカーオプションとする 方が無難である。 この場合は事前に船体構造に補強部品を準備することになるが、メーカーオプシ ョンは価格も高いので購入者が市販品を取付ける場合も多いのでこれを予想して 事前に対応しておくかは重要な課題である。
●大型艇の甲板艤装図の例 小型船舶としては大型の53FT艇だが24m以上の船舶と比べると甲板艤装品は まだまだ小規模で安全性への配慮も割り切った配慮が求められる場合がある。 例えば係船装置や安全レールも業務艇に比べると簡素である。
●業務艇の甲板艤装図の例 漁船の甲板艤装図は操業で使用する操業機器の仕様に合せて配置する。
●係船揚錨装置 船舶は海上の船舶や岸壁に係留する機会があり、その際はロープをボートの係留 装置すなわちクリート、ビットボラード等に結わえなければならない。 海面は穏やかな場合ばかりではないので波浪中では係船装置に大きな力が加わる ことになるので係船ロープのサイズも余裕を持って搭載することが求められる。 これらの係船装置はしっかりと甲板にボルトで固着することが必要だが、FRP艇 の甲板剪断強度は弱いので係船装置等をボルトで甲板に固定する場合は甲板裏面 に大きな座金(ワッシャー)をセットして面圧を下げて固定している。 図-146はクリートの取付け詳細を示す。 プレジャーボートも洋上係留に備えてアンカーは備えているが例え5kg程度の 軽量アンカーでも水深50mから1人で引き揚げると大変な作業である。 特に釣り舟のように多くの場所でアンカーリングするボートでは巻き上げ作業を 人力で行なうと大変なので大抵は揚錨装置(ウインドラス)を装着している。 これらの揚錨装置は係船ロープとアンカーチェーンの両方を巻き取れるようにな ったウインドラスもあるが小型釣り舟では横型の安価なウインチが多い様である。 これらの揚錨装置は錨の重量や巻き上げ速度および船体のサイズを考慮して仕様 を決めるようだ。 図-147は比較的大型のプレジャーボート用の縦型揚錨装置の例である。
●安全レール類 ハンドレールなど安全備品の取付けは乗員が実際に掴まり易い位置となっている かを考慮し特に波浪中を走行時に暴露甲板を安全に移動する為にハンドレールは 是非必要であり、舷側に沿ったレールやキャビン側璧にも小型のハンドレールを 適当な数配置するべきである。 レールの材質はステンレス製が良いが量産艇では原価低減のためにサイズが標準 化されたレールを使用するのが普通である。 フライングブリッジがあるクルーザーでは昇降ラダーやFBレールは特に安全に 留意すべきである。
●ハッチ、倉口 暴露甲板には係船ロープやアンカー、さまざまな備品を収納するロッカーが配置 され、釣り舟はイケスなどのハッチも設置される。 暴露甲板は波浪中に波をかぶりハッチから海水が侵入するのでハッチのシール(水密)は重要である。 規則上も航行区域によりハッチコーミング高さは決められるがプレジャーボート ではハッチの上面が他の表面と同じ高さのフラッシュハッチが多い。 ハッチの裏には海水の侵入を阻止する為にゴムパッキンが取り付けられている。 パッキンが効果を持つには適当な力でハッチを押さえるロックが必要である。 図-148はフラッシュハッチ断面の例を示す。
●生簀(いけす)の詳細 釣り船に生簀を設ける場合は小型釣り舟や漁船のように船底にスカッパーを 取り付ける場合と大型スポーツフィッシングクルーザーのように循環式の生簀 を装備する場合がある。 以前の釣り愛好者は釣った魚を生かして持ち帰れば新鮮と考えていたが、現在は魚の 鮮度を保つ為には釣り上げてできるだけ早く絞めて血抜きを行ない冷蔵する方が良い との考えが普及しクーラーボックスやアイスボックスを装備する船が増えている。 生簀の役目も業務用漁船は別としてプレジャーボートでは生き餌を運ぶために設備へ と変わりつつあるようだ。 しかし小型釣り舟でも相変わらず生簀を装備する船も多く船底から海水を取り入れる 場合の安全規則もあり生簀のサイズも制限されている。 図-149は小型釣り舟の生簀設置要件である。
4-4-8室内艤装詳細 小型船舶の室内は狭小空間なので限られた空間を効率的に利用することが重要だ。 人間工学的な検討で広く見せる工夫、ボートの目的に合わせた室内配置は感性も 考慮して決定すべきだ。 室内家具に住宅家具や自動車部品を流用することもあるが海水面での使用を考える と耐久性の確認や塩害対策の確認が必要だ。 残念ながら日本製のマリン専用部品は少なく多くは輸入品に頼るしかない。 狭小空間をいかにデザインできるかはボートデザイナーの腕次第である。 魅力的なインテリアデザインは平面、側面、断面の寸法を数cmの単位で配置を 検討するのは乗用車やバス、鉄道のデザインにも通ずる考え方が必要である。 また優れたデザインを実現するには普段から関連するデザイン要素を貯えておくこ とが必要で、良いデザインを見つけたら資料として整理しておくと便利である。 (流用できそうな関連部品や人間工学的サンプルなどを整理すれば検討に役立つ。) ●スケルトン図 居住性を検討する場合、室内配置だけを考えれば良いのではなく、常に全体のバラ ンスを考えた配置検討が大事である。 機関室も整備性を考えれば広い方が良いのは当然であるが機関室の配置を優先する と居住区にしわ寄せが来てしまうのである。 そこで常に艤装品の配置や取付けを確認しながら検討を進めるにはレイヤー(画層) を使って艤装品の配置に無理がないかを確かめながら作業を進めると良い。 せっかく多くのレイヤーで検討を重ねても最後の段階で問題が発生すると再び最初 のレイヤーに戻り検討を繰り返さなければならないことも多い。 技術検討も可能な船舶専用ソフトもCAD機能を持つがパソコンには大きな処理能力 を求められる。 小型船舶の開発では少数のデザイナーで開発することが多いので船舶ソフトからの インターフェイスが可能な汎用CADソフトを使用することが望ましい。 図-141〜144は53FTスポーツフィッシャーマンの例である。
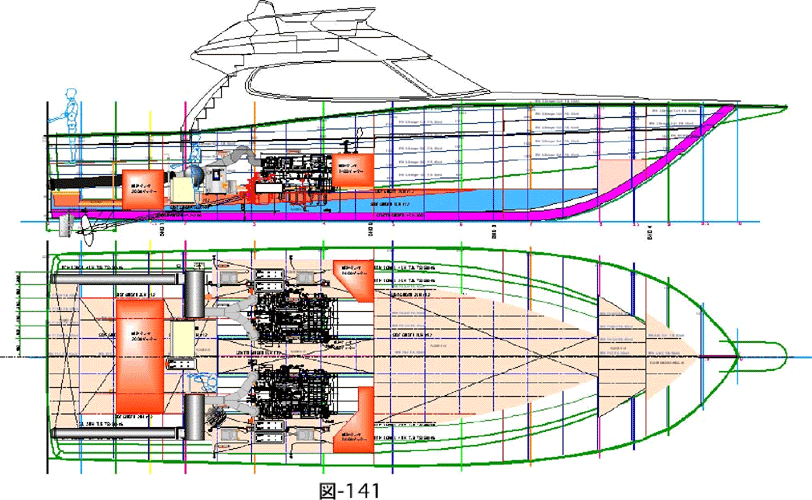
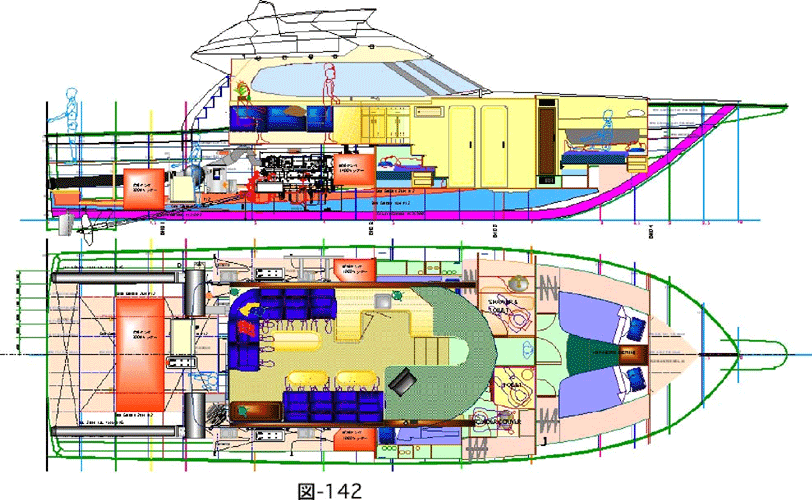
●インテリアデザインパネル 感性が求められる室内艤装では素材の選択重要だ。 小型船舶専門の内装会社は少ないが顧客の承認が必要な場合はインテリアデザイン パネルを製作する場合もある。
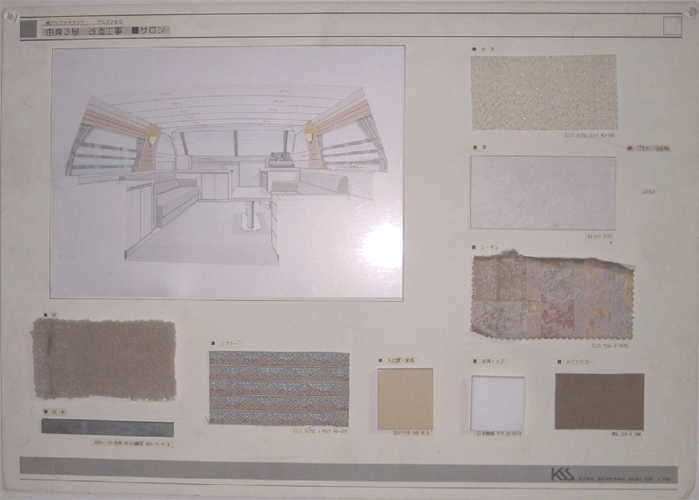
●室内艤装図1 室内配置はボートデザイナーの手腕が問われるが、狭小空間を如何に魅力的に配置 することは車両設計と似通っている。 更に量産では組立(艤装)に要する工数をいかに下げるかは車両生産ほどではなく ても1000台を超える量産数なら製造コストをいかに低減するかは重要な課題だ。 室内艤装が大型キャビンクルーザーの組立てプロセスの工夫が大事である。 人件費の高い日本で生産する場合、艤装工数を下げれば製造原価が下がり販売価格 も下がるので商品の競争力が高くなる。 量産数が増せば生産ラインのロボット化も投入されるがマーケット規模が小さいの で多機能ロボットが必要だ。 さて、室内艤装図は魅力有る室内配置とクオリティを検討し図面として表現する。 内装材の選択や仕上げなどの詳細は別に仕様書や作業要領書などを準備する。 スケルトン図で室内配置の総合的な検討が終了すると室内艤装図を作成する。 次図は室内配置を重視したスポーツクルーザーのスケルトン検討図の例である。
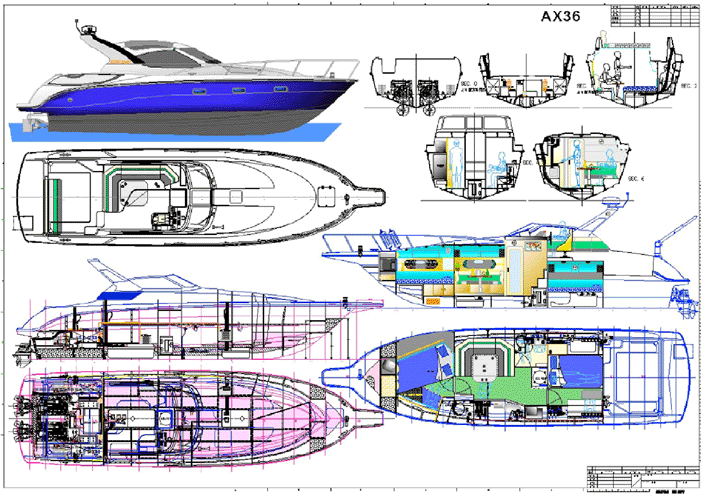
●室内艤装図2 30FT以上の小型船舶になると複数の居室を設けることが多く、居室ごとに検討し 詳細図面を作成することになる。 以下は33FTカタマラン艇の室内艤装図の例である。
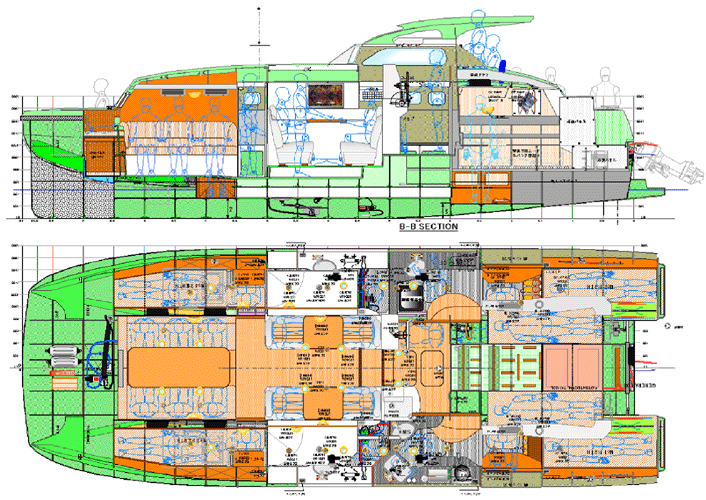
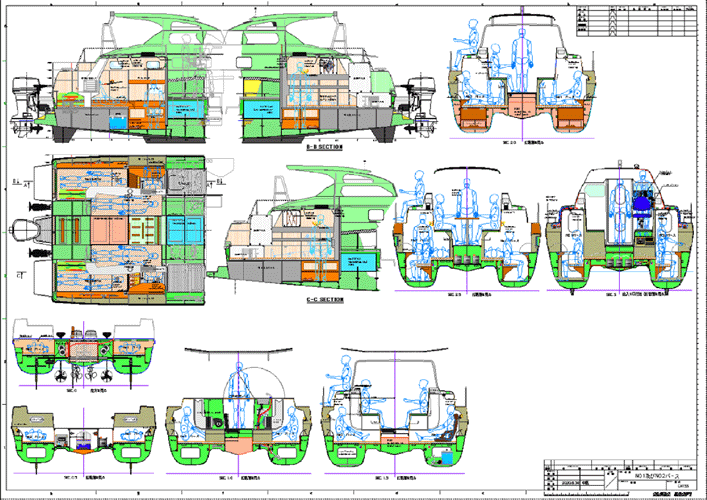
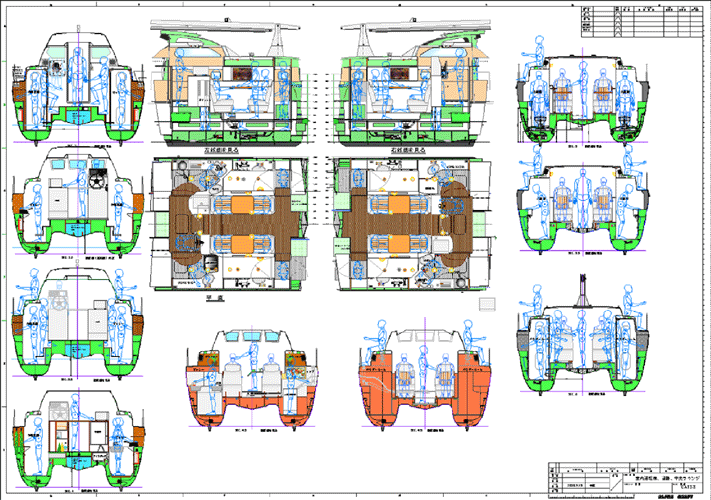
4-4-9電気艤装詳細 電気艤装は船舶の機能を制御し居住性空間の電装品に電源を供給するシステムである が近年は電子機器がますます増加し電気システムの重要性は増すばかりである。 船外機艇などの小型艇は電気を必要とする室内艤装品も少ないので比較的簡単である が30FT以上のキャビンを有するボートになると結構複雑なシステムとなる。 しかも発電機を装備し交流電源も搭載となると系統図、装置図や部品図も作成しなけ ればならない。 ●電気系統図詳細 電気系統の検討は極めて重要で電装品の消費電力を考慮し回路として間違いがなく 電線の太さを決めなければならない。 直流回路は比較的判り易いが大型艇の交流回路は複雑である。 DC-12V系統 7m未満の小型ボートは主機や電気艤装品の直流電源はほとんどDC-12Vである。 輸入の船舶用電気艤装品は豊富だが国産品は極めて少ないが最近は乗用車用の電気 艤装品も一部採用されるようになった。
DC-24V,DC-32V,DC-48V系統 大馬力ディーゼル主機を搭載した小型船舶の直流電源は主機の電源がDC-24Vを 採用している場合はDC-12V、DC-24V両方を搭載することが多い。 今後ハイブリッドエンジンの採用が増えると直流電源もDC-32V,DC-48Vの採用 も増えると考えられる。
AC-110V系統 大型艇の交流電源はAC-110V仕様で発電機や陸電および直流バッテリー電源から インバータを介して供給される。
●電力計算書 電力計算書で行う検討では運航状態により電装品の使用する割合が異なるので、これ らを考慮して直流、交流の電力使用量を検討し装備するバッテリーや発電機の 能力を決定するが大型船舶になるほどこの計算は複雑となるのは当然である。 表-54、55は直流電力計算書および交流電力計算書の例である。
●電気艤装図詳細1(船体内配線経路) 電気艤装図は室内配置図、機関艤装図、諸管配置図の電装品配置に合わせて作成 するが配線経路は整備性や安全性および船体構造も考慮し決めねばならない。 電気艤装図には電装品の配置を示す他に取付けの留意点なども記入する。
●電気艤装図詳細2(天井裏配線経路) 小型船舶の天井裏配線は作業困難な場合も多く作業工程の工夫や配線をワーヤー ハーネス化することも検討する
●配電盤 大型艇は電装品が多く電気回路をコントロールする配電制御盤で非常時に回路 を遮断するブレーカーパネルやスイッチ回路が取付けられている。 小型艇では1個所にまとめられる場合も有るが大型艇では必要個所に数カ所配置 し、豪華キャビンクルーザーの配電盤が機能重視は当然であるがで配電盤自体の 意匠デザインも重視されるので非常に高価である。 中小型プレジャーボート用の配電盤は輸入品の方が安く、また種類も多い。 図-161、162は50豪華キャビンクルーザーの直流配電盤と交流配電盤を示す。
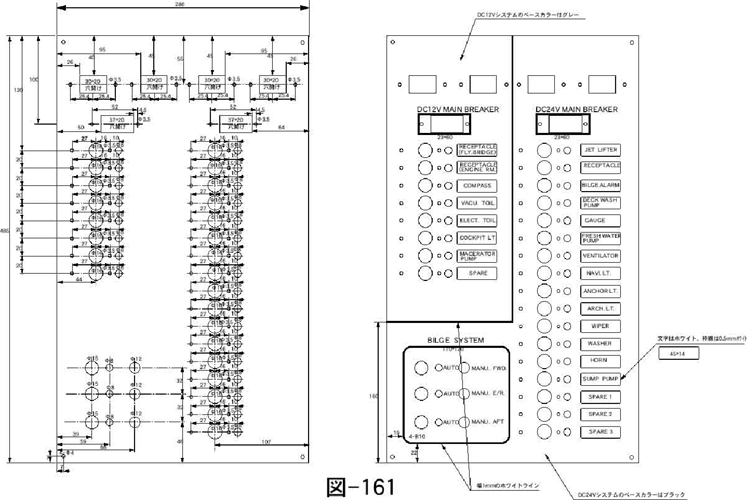
●ワイヤーハーネス 大型艇の配線は一般商船と同じように現場で配線するが小型艇は作業場所が狭く 作業性が悪く作業工程を工夫や配線はターミナルボックス経由や配線を車両製造と同 様にワイヤーハーネス(部品)として取り付ける。 ワイヤーハーネスの製作はまず図面上で長さを検討し試作品を製作し、試作艇の 組立の際に実際に取付けて寸法等を確認する。 図-163は23FTクラスのプレジャーボート用のワイヤーハーネスであるが図面の 他にワイヤーハーネスを組み立てる要領書や部品構成表も同時に作成すると良い。
4-4-10開発設計仕様最終確認(基本設計部門へフィードバック) ●船体構造重量重心集計(ハル構造、デッキ構造、艤装品) 金属艇の重量は基本設計で推定した船体重量は実際の完成重量とほとんど誤差は なく、溶接や表面塗装などの重量もある程度推定することは可能である。 FRP艇の場合はガラス繊維のラップ率で重量が大きく変化するので注意が必要。 FRP艇の安定した重量を管理するには生産技術部門の力量が問われ、試作工程で FRP部品重量の把握が極めて重要だ。 ● 室内艤装、電気艤装品の重量重心集計 最も重量誤差が発生するのは室内艤装や電気艤装であり、部品数が多く個々の 部品重量把握が難しいが、購入品などは必ず資材部門で重量を計測するように努める ことが求められる。 配管や電線の使用量は把握できてもシステムの重心位置を推定することは困難である が経験値として推定重量重心位置を決めると良い。 ● 完成、軽荷および重荷重量重心のまとめ 船舶の重量重心位置は性能や安全性に影響を与えるので開発過程では常に完成重量、 運用重量を把握することが求められる。 重量の集計は総合パーツリストを利用することが望ましい。 ● 安全性検討(浮き姿、復原性、GM値、定員、区画浸水) 重量集計の結果が基本設計で検討した重量重心位置と大きく異なる場合は浮き姿、復 原性、GM値、定員計算、区画浸水を再検討すべきだが実際にこのような事態が発生す ることは滅多にない。 ●耐久テスト、品質管理基準 顧客に引き渡す商品は製造者責任が発生するので必要なら艤装品等の耐久テスト や品質管理が必要となる。 特に新規開発の商品には配慮が必要となる。
