連載-ボートデザイン開発編(第7回)

連載-ボートデザイン開発編(第7回)

4-3基本設計2(基本設計図決定:PHASE-2)4-3-1基本設計2の流れ 開発プロジェクトが小規模な場合はPHASE-1とPHASE-2を明確に分ける 必要はない。 本稿では少し複雑なプロジェクトの場合を想定して検討を進める。 PHASE-1で外観形状が決まり全体の性能、機能、安全性、および艤装品の機能、 性能、サイズ、重量確認の目処がついたら本格的に検討を行う。 この段階ではハルラインズは90%程度の完成度で正式図面として配付しデッキラインズは 60%程度の完成度で参考図として配付する。(正式出図時期は開発者判断) 仕様検討として機関機器操縦系統、燃料系統、諸管系統、交直流電源系統を検討。 性能、機能、安全性の検討では喫水線、最大傾斜角、最高速力、航続距離、燃料及 び清水タンク容量、ビルジ、横安定、浸水区画、換気回数など検討項目は多い。 船体構造図で強度基準によりフレーム位置を決める。 機器配置と補強材と干渉する場合があるのでスケルトン図で確認しながら調整。 主機および推進軸系の設計は早急に決定し主機の発注と納期を確認する。 燃料タンク、清水タンク、汚水タンクの容量と位置をスケルトン図で確認。 室内配置を優先決定するが内装仕様は仮設定。 (顧客要望で仕様変更の可能性有り) スケルトン図で室内寸法を仮決定。 主な系統図は早急に仮決定しスケルトン図に書き込み問題点の有無を確認。 スケルトン図は最後まで完成しないので90%程度の完成度で各種図面を作成。 (理由:手配品の変更や仕様変更で決定事項に修正の可能性が発生。) 重量重心計算は単純で面倒な作業だが定期的に再確認する。 艤装品の重量及び価格情報は資材購入部門と共有しながらパーツリスト (部品表)で管理する。(表計算ソフトExcellを使用する。) 完成重量重心位置は速力性能や安定性に大きな影響がある。(フルード数で判断) 排水量船型の場合、浮心位置は水線長の半分の位置から数%船尾側。 高速領域の滑走船型はトランサムから水線長の33%〜35%。 中速領域の滑走船型はトランサムから水線長の35%〜40%。 半滑走船型はトランサムから水線長の38%〜45%。 万一修正が必要となったらスケルトン図で修正を加え再確認する。 基本設計2が終了し開発プレゼンテーションを実施し開発続行を確認 以下は53FTモーターヨットを例として紹介する。 4-3-2一般配置図、構造図作成 ●一般配置図 ほぼ最終段階の一般配置図が変更されることはほとんどない。 修正した場合は改定図として再配布することになる。
●ハル、デッキ、構造詳細図 主要構造図が変更されることはほとんどないが承認図や製造に必要な詳細構造図 を作成することになる。
ハル詳細構造図の例としては隔壁詳細図、フレーム詳細図、ロンジ詳細図、 補強材一覧図など様々だが例として隔壁詳細図、補強材一覧図を示す。
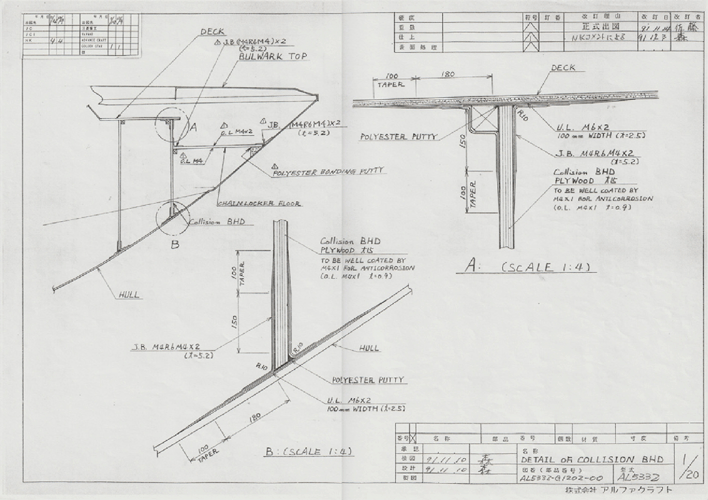
同様に上部主要構造図や室内家具配置に関連する補強材配置は室内仕様の変更により 上部構造図は修正が伴い最後まで手のかかる構造図である。 特に小型船舶では上部構造の重量が増える傾向にあるので面倒でも重量管理は確実に実施されるよう心がけが必要だ。
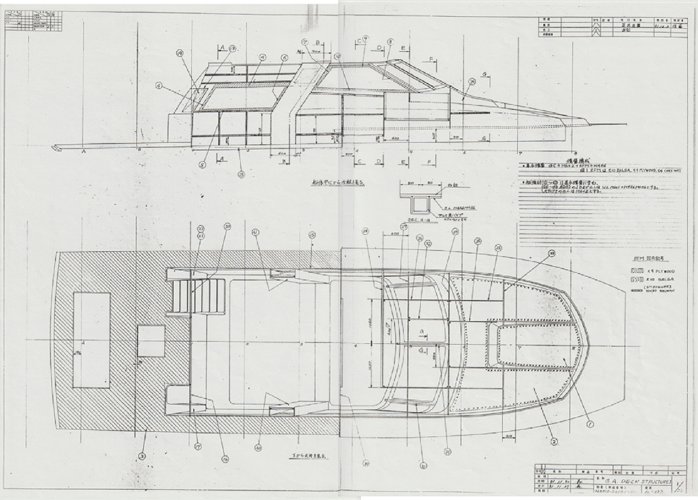
上部構造物には別に比較的大型な部品としてフライングブリッジ、バウスプリット、 ハッチなどの構造図も作成する。 例としてバウスプリットの構造図を示す。
4-3-3機関機器配置図、室内配置、配管、電気系統図作成 ●機関機器配置図(排気装置、燃料装置他、機関冷却排水装置) 機関室配置は整備性を重視して検討すべきだが小型船舶では人が機関室内で 作業するのに必要な空間を確保するのは極めて難しい。 下図は53FT艇なので比較的恵まれた空間が確保できているが30FT以下の船舶で は機関室に人が入ることはできないので通常のメンテナンスが必要な機器は手が 届く範囲内に配置するしかない。
● シャフトブラケット 高速艇のシャフトブラケットは抵抗の少ない形状とし青銅鋳物製を採用することが多 いがコストを重視する場合はステンレス製で組立型を採用した方が良い。 居住性を重視する場合はむしろ船底振動を防止する組立型のV型ブラケットも 方が良い。
● 舵配置検討(舵断面および舵取り装置) 舵断面 最高速力30KT以上の高速艇は舵断面形状に楔型を採用することが多いが舵効きに関しては漁船などで採用されている平板舵でも大差ないことが判っている。
舵取り装置 メンテナンスの都合上、舵軸の水密部分は係留状態の吃水線より上方となるよう留意すべきだ。
● 操縦操舵装置図(操舵装置、機関制御、航海機器) 操船個所を2カ所以上設ける小型船舶が増えたが、そのほとんどは油圧制御装置なので誤作動を防ぐエア抜きに配慮した配置が重要だ。
近年は自動操縦機能がある航海機器装置の発達が目覚ましく運転席付近の機器類 配置は視認性や使い易さに注意を払う必要が有る。
●諸管系統図(海水、清水、汚水、ビルジ) 船舶において故障が多いのは機関装置以外では配管系統や電気系統である。 設計段階ではメンテナンスが容易な配置検討が求められる。 近年は環境保全が求められるので汚水排出や汚物の一時貯蔵などにも配慮が必要 となった。
4-3-4室内配置図および艤装図 小型船舶の室内は狭小空間であり限られた空間を効率的に利用することが重要だ。 人間工学的な検討、広く見せる工夫、ボートの目的に合わせた室内配置は感性も 考慮して決定すべきでいかにデザインできるかはボートデザイナーの腕次第である。 室内配置の検討は数cmの単位で配置を検討するのは乗用車やバス、鉄道のデザイン にも通ずる考え方である。 ●人間工学的検討 室内配置設計は人間工学的配慮でドライビングポジションや居住性などの検討 を行うが何らかの基準(設計基準)を設ける必要がある。 図-137〜140はドライビングポジションやギャレーに関して決めた基準である。
●室内配置図、スケルトン図 居住性を検討する場合、室内配置だけを考えれば良いのではなく、常に全体の バランスを考えた配置検討が大事である。 そこで常に艤装品の配置を確認しながら検討を進めるにはレイヤー(画層)を 使って艤装品の配置に無理がないかを確かめながら作業を進めると良い。
4-3-5甲板艤装図(係船装置、ハッチ、窓、換気装置他) ●甲板艤装図 暴露甲板上の艤装品は塩害に強い材質(ステンンレスや黄銅)が多い。 窓ガラスは安全規則で決められているので窓サイズと板厚には留意する。
4-3-6電気艤装図(電源装置、充電装置、直流、交流他) ●電気系統図(交流、直流、充電) AC110V電気系統図
DC12V電気系統図
DC24V電気系統図
●電気艤装図(電装品配置、配線他) 近年はソーラーパネルなどからの外部電源からの充電回路や電子機器が複雑化す る傾向にあるので電気系統の設計は重要度が増している。 サンプルは33FT艇の床下と天井裏電線敷設図を示すが詳細検討はヤード設計であ るPHASE-3で実施する。
4-3-7製造仕様の決定 ●製造仕様書 企画段階の製造仕様書は基本設計も終了段階になるとより詳細な内容となり、 PHASE-3(ヤード設計)が詳細設計を行う際のベースとなる。 もちろん修正が必要な場合もあり改定通報と共に変更個所を関係部署に配布する ことになる。(客先の承認が飛鳥な場合もある。) ● 主要注文仕様書検討(船体材料、主機関等) 納期の長い発注品は早い段階で注文仕様書を発行することになるが製造仕様書がほぼ 完成すると納期に合せて個々の注文仕様書を作成し資材部門経由で発注することになる。 (納期の長い発注品としては主機、減速機、特殊な素材、輸入品など。) ●初期パーツリスト(寸法、重量、購入価格他) 小型船舶の資材や部品管理でパーツリスト(部品表)を作成すると便利なことは 前述した通りである。 資材や部品の納入に際しては重量、価格の情報をパーツリストなどへリンクする と次の開発などで役立つので徹底することが大事だ。 4-3-8重量重心計算2(完成重量、軽荷重量、重荷重量) PHASE-1、2で基本設計が終了段階になると高精度で開発艇の仕様が決まるので 検討して来た項目を再確認することが必要となる。 単純で面倒な重量重心計算だが企画が成功するか確認する重要な作業である。 試運転の結果、不都合が生じると対策が困難な場合もあるので事前に問題が発生 する可能性のある重量重心位置は確認しておくべきだ。
比較できる過去の企画や実例資料があれば進行中の開発に問題がないかチェックできる。 速力性能を重視する小型船舶ではインテリア重量には要注意である。 特に豪華なインテリアデザインを外注する場合は重量管理が抜け落ちて最終的に問題を抱え込むのは造船所である。
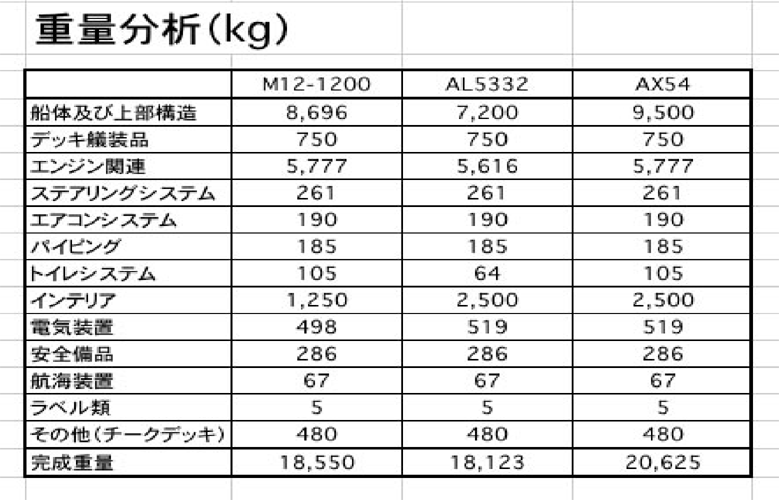
4-3-9主な確認項目 排水量等、重量重心、トリム、復原性、速力性能、定員、区画浸水、総トン数,機関出 力に余裕のある小型高速艇はあまり問題にならないが、半滑走の業務艇では適正な滑 走面荷重や重心位置でないと計画最高速力を達成できない場合が発生し、試運転の結 果これらが発生すると対策が不可能な場合も多い。 そこで過去の事例から最悪の事態を避ける意味で独自の“泥舟判別基準”や“半滑走 状態の検証“を実施することを提案する。
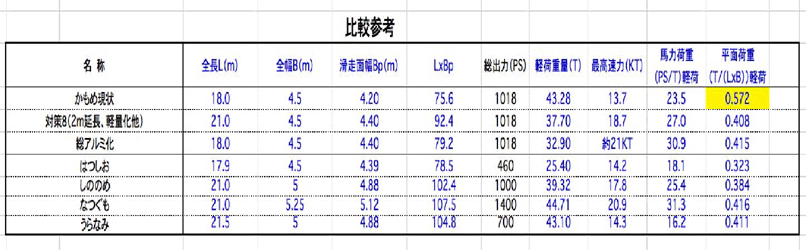
4-3-10発注仕様書、コスト検討 資材部門は開発艇の予定原価集計を実施し事業としての採算を確認する。
4-3-11開発大日程の決定 初期段階で大雑把に決めた開発日程が計画通りに進展することはまずない。 しかし組織で開発するプロジェクトでは関連部署と事前に調整し決定した開発大日程 は大変意義が有り責任と計画進捗管理に極めて有効である。 特に開発大日程を管理するプロジェクトリーダーには管理権限を託すべきである。
4-3-12プレゼンテーション資料の作成2 予定通りに計画を進展させるには関連部署の意思統一が重要であり、定期的に管理会 議やプレゼンテーションを実施して状況を把握できるようにすべきだ。 関連部署ではそれぞれ判り易い開発会議資料を準備することになる。
4-3-13開発会議(基本設計2確認、ヤード設計引継ぎ会議) 開発会議では企画と基本設計に問題がないか確認しヤード設計への引継ぎ準備に 入る。 4-3-14基本設計稟議(開発会議、稟議) 開発会議の報告を受け役員の承認を受け正式に次のステップ(PHASE-3)へ移行 する。
