![]()
六甲山頂より番匠屋畑尾根ル−トを通り有馬温泉へ!
●今回は、前回及び前々回に引き続き第三回目として六甲山の松やに採取跡を探索してきました。今回のル−トは番匠屋畑尾根で住吉道及び紅葉谷道と同じく六甲山頂より有馬温泉へと続いています。6年前には住吉道(いわゆる魚屋道=ととやみち)を歩いてきましたが、そのときの印象でも住吉道の反対側にある紅葉谷にも松やに採取跡が見られるのではないかと思っていました。そして1年前には、紅葉の美しい季節にハイキングをかねて紅葉谷道の松やに採取跡を探索してきました。二回の探索からみて、紅葉谷道の反対側にあたる番匠屋畑尾根ル−トにも松やに採取跡が残っているのではないかと考えておりましたが、丁度インタ−ネットで六甲山の情報を調べているときに、この番匠屋畑尾根ル−トにも松やに採取跡が残っているとの記事がありましたので、今回の訪問をしたわけです。この記事の筆者はこの番匠屋畑尾根ル−トの松やに採取跡の道を「松の道」として紹介しておりますが、私はこの道を少し気取ってト−ルロ−ド(Tall Road=Tallとはスエ−デン語で松を意味し、松の木からとれる油をト−ル油(Tall Oil)といっています。)と呼びたいと思います。戦時中であっても必死の思いで松やにを採取し、険しい道を通り神戸まで運んだ先人の努力に頭が下がります。
●六甲山頂のガ−デンテラスから番匠屋畑尾根道を通り有馬へと下ります。・・・約6Km(3時間)
前回歩いた紅葉谷道また住吉道から考えて、このル−トも比較的歩きやすく、有馬まで2時間もあれば十分と今回同行した妻にも説明してから出かけましたが、見通しの甘かったこと反省しております。途中までは比較的歩きやすく鼻歌交じりでしたが、湯槽谷山の手前の三角点の前後から急に険しくなり始め、下りばかりと考えていましたが急勾配の上りもあり、息が上がってしまい大変でした。また、下りは下りで何か山を垂直に下りているみたいで、足はがくがく腰はがたがたになってしまい、帰ってからも2−3日は歩くにも事欠き、特に階段の下りには大変な思いをしました。しかし、山を歩きながら平家物語の鵯越の逆落としを思い出し、きっと逆落としの場所もこのような急な坂であっとのだろうと思いました。義経はこの坂を下りるときに鹿が下りていることを聞き、鹿も四つ足ならば馬も四つ足、ならば馬でも下りられないことはないと思って鵯越を下ったとのことです。この番匠屋畑尾根ル−トの難所も鹿や猪は何の苦もなく上り下りしているのでしょうが、残念ながら筆者は2本足のため思うようには歩けず、その上途中の紅葉谷へ抜けるル−トが工事中のため通られず、灰形山回りとなってしまいよけいに時間がかかり、筆者の足では途中の休憩も入れて約3時間の行程となってしまいました。

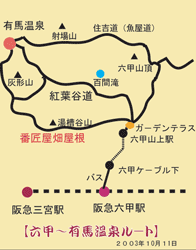
注:回る十国展望台は2002年11月24日をもって営業停止し、その後ガ−デンテラスとして開発されています。



左から湯槽谷山山頂(801M)および灰形山山頂(619M)の案内看板
●番匠屋畑尾根の松やに採取跡
ガ−デンレラスからしばらく歩くと、紅葉谷と番匠屋畑尾根ル−トの分かれ道に入ってきます。ここを左にはいると番匠屋畑尾根〜有馬温泉です。この地点から湯槽谷山頂の途中の地点にある三角点付近を中心として、松やに採取跡がぼつぼつ見られますが、本数的には多くなく精々10本程度です。松やに採取は戦前の一時期(多分昭和17−19年頃)松やにを採取して、軍需用の海底ケ−ブルの被覆材としたり、マッチや合成樟脳の原料をとるためにテレビン油を採取するなどの用途に使われたのではないかと考えられます。しかし、本数が非常に少ないのでとれる松やにの量も限られており、実際にはその目的はあっても実用的になったのかどうかは非常に疑問です。・・・この件については、松やに採取跡と六甲山と題して、このホ−ムペ−ジで以前にも紹介しています。今回、この番匠屋畑尾根で見つけた松やに採取跡ではやはり樹齢80年−110年(松やに採取時には樹齢30年−50年ぐらい)の赤松、黒松の両方があります。しかし、戦後50年以上経ち、その間の気候や雨風、台風、松食い虫などにより、大半の松やに採取跡の木は枯れつつあり、写真でもわかるように時の経過の長さを実感する次第です。



松やに採取は1−3年の期間にわたり採取されたと思われる。左から1年採取、2年採取、3年採取の跡。
松の木の直径は40cm(大きい物は80cmのものあり)で下から70−80cmのところを切り、切り幅は1年で
約20cm、3年では約60cmの切り幅となっている。


戦後50年以上経ち、倒れたり、枯死したりして放置されている物もある。朽ち果てた木に残る採取跡
●追記
過去3回にわたり、六甲山を歩いてきました。住吉道(魚屋道)と紅葉谷と番匠屋畑尾根です。いずれにも松やに採取跡が残っていましたが、当初住吉道を探索したときに想像した松やに採取跡として、2〜3千本は松の木としてあるのではないかと考えましたが、紅葉谷道、番匠屋畑尾根と探索するに従い、この推定は残念ながら間違っているようで、採取本数としてはこの十分の一くらいではないかと思います。住吉道の時は道筋から尾根にも採取跡が見られましたが、他のル−トでは道筋のそれも一部分しか採取跡がなく、戦後50年以上も経ち、風で倒れたり、伐採されたり、また枯死したりして本数も少なくなっていることを差し引いても数百本のオ−ダ−ではないかと思います。
今回の六甲山への松やに採取跡の探索のもう一つの理由は、健康面からのハイキングは勿論ですが、実はとあるインタ−ネットで有馬の温泉入浴券が2枚当たりましたので、妻を誘っての有馬温泉の金泉への入浴がその理由でした。番匠屋畑尾根のハイキングで疲れた体にはもってこいの温泉でした。疲れも吹き飛び明日からの仕事にズ−ムイン!