
●今回は、前回の六甲山の探索に引き続いて、六甲山の頂上より紅葉谷を通り、有馬へ下るル−トを歩いてきました。3年前には同じ有馬へ抜ける道でも住吉道(いわゆる魚屋道=ととやみち)を歩いてきましたが、そのときの印象でも住吉道の反対側にある紅葉谷にも松やに採取跡が見られるのではないかと思っていました。今回、紅葉の美しい季節にハイキングをかねて探索してきましたが、予想通りこの紅葉谷にも松やに採取跡が見つけられました。
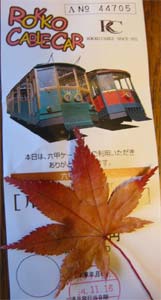


六甲ケ−ブル乗車券と有馬の紅葉
●六甲山から紅葉谷を通り有馬へと下ります。・・・約4Km(1時間)
紅葉谷は昭和7年(1932年)六甲ケ−ブルが開通した時に整備されて紅葉谷と名付けられた。名前の通り六甲山でも有数のも紅葉の美しいところです。紅葉谷はケ−ブルの六甲山上駅からバスで「回る十国展望台」で下車し、そこから有馬へ下っていく道で約4Kmの道のりです。道はよく整備されており、急な登り下りもありますが、比較的初心者にも歩きやすいコ−スです。

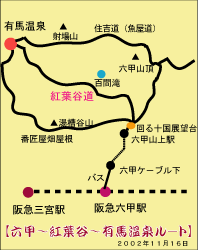
注:回る十国展望台は2002年11月24日をもって営業停止しています。


●紅葉谷の松やに採取跡
回る十国展望台からしばらく歩くと、紅葉谷と番匠屋畑屋根ル−トの分かれ道に入ってきます。ここを右にはいると紅葉谷〜有馬温泉です。石の案内が立っており、右が有馬とあります。
紅葉谷入り口から約20−30分歩くと、地図の通り百間滝付近に出ます。この付近まで来ると道の両横に松やにを採取した跡がぼつぼつと見られるようになります。松やに採取は戦前の一時期(多分昭和17−19年頃)松やにを採取して、軍需用の海底ケ−ブルの被覆材としたり、マッチや合成樟脳の原料をとるためにテレビン油を採取するなどの用途に使われたのではないかと考えられます。・・・この件については、松やに採取跡と六甲山と題して、このホ−ムペ−ジで以前にも紹介しています。今回、この紅葉谷で見つけた松やに採取跡ではやはり樹齢80年−110年(松やに採取時には樹齢30年−50年ぐらい)の赤松、黒松の両方があります。しかし、戦後50年以上経ち、その間の気候や雨風、台風、松食い虫などにより、大半の松やに採取跡の木は枯れつつあり、写真でもわかるように時の経過の長さを実感する次第です。



上部が切り取られ採取跡だけが残る切り株(左)、朽ち果てた木に残る採取跡(中)



紅葉谷の道脇に残る松やに採取跡



苔むした松やに採取跡の木と木に残る採取跡
●紅葉谷についての想い出


今回、松やに採取跡を訪ねて紅葉谷から有馬温泉へと歩いてきましたが、筆者にはこのル−トに大して非常に懐かしい想い出が残っています。筆者がまだ小さかった頃(小学生)両親と兄弟の家族全員で、紅葉谷から有馬温泉へ下り、ロッジを借りて一泊したことです。筆者にとっては家族そろっての旅行ということは記憶になく、これが記憶に残る唯一のものです。紅葉谷の途中で、父親が扇子を無くし非常に残念がっていたことを記憶しています。また、ロッジではトンボや蝉がたくさん捕れ、オニヤンマを捕まえて遊んだこと、有馬のわき水が炭酸入りで鼻にツ−ンときたことなど、懐かしい思い出として残っています。今は六甲も有馬もかなり変化してきて、いわゆる俗っぽくなってきていますが、この紅葉谷を通ったことにより、昔のことが懐かしく思い出されたわけで、松やに採取跡の探索も
思わぬ余得があったように気がします。
有馬温泉では金泉、銀泉の温泉につかり疲れも吹っ飛びました。
●追記
過去2度にわたり、六甲山を歩いてきました。住吉道(魚屋道)と紅葉谷です。いずれにも松やに採取跡が残っていて、満足した結果でした。次回は機会を見つけて3番目のル−トである番匠屋畑屋根のコ−スを探索してみたいと持っています。