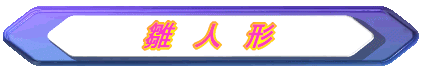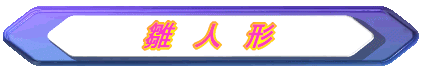

|
|

|
利根町(茨城県)でも、数箇所、雛人形が展示されているが、 |
| 私が足を運んだのは、「柳田國男記念公苑」である。 |
| この建物は、民俗学者柳田國男が滞在していた小川家の跡地に建て |
| られている。 |
| 柳田國男は、長兄の松岡鼎が当地で医院を開業していたので、 |
| 十三歳のときに生まれ故郷の兵庫県から移住したそうである。 |
| ここで三年ほど暮らした。腕白少年だった彼だが、家主の小川家の土 |
| 蔵にあった本を濫読する。 ここで運命的な出合いとなった本は、布川在 |
|
住で利根川流域を調べた医師・赤松宗旦の『利根川図志』だった。 |
 |
|
| 後年、柳田國男はこの本の復刻版の解題を書いている。 |
| 彼が民俗学へ興味をもつようになったきっかけは、『利根川図志』、 |
| 小川家の不思議な玉、徳満寺の「間引き絵馬」などで、少年期を過ごし |
|
|
|
| 雛飾りは商工会の女性部が中心になって企画し、今年で三年目との |
| ことである。 展示の段飾りの雛人形は、町の活性化にできるかぎり協力 |
|
したいと、住民が快く展示を申し出られたとか、日ごろ目にできない年代物 |
 |
もあり、絢爛豪華で、わが家の雛人形とは比較にならない。 |
| つるし雛は、、数ヶ月も前から女性部が無料の講習会を開き、 |
| 参加した約30名ほどの手作り作品である。 |
| つるし雛にはそれぞれ「いわれ」がある。 |
| 受付に置いてあるパンフレットには…… |
| ・ ほおずきは女性の守り神、安産や婦人病の薬効がある。 |
| ・ 巾着は、すべてのお金がわが子に集まって幸せが舞い込む。 |
| との親心とか。 |
|
忙しかった子育てのころは、つるし雛を作るゆとりがなかったが、今は |
|
充分に時間があるので、巾着やほおずき、桃の実、猿っ子、座布団など |

 |
型紙どおりに布を切り、縫い、綿を入れる。 |
| 最近、針を持つことが少なくなったが、講師がていねいに説明して、 |
| 材料までそろえてくださるので、それなりの物が出来上がる。 |
|
| 会場は、襖をはずした二十畳ほどの部屋が廊下を挟んで二箇所、 |
| 廊下にはつるし雛が所狭しと掛けられている。 |
| カメラを手に一体ずつ見ていると、時間を忘れてしまう。 |
|
| 一息つきたくなって反対の廊下を進むと、お茶席があった。 |
| 表千家の茶席だが、私がつるし雛の講習を受けたMさんがお点前をして |
| おられた。雛祭りにふさわしい特製の和菓子で、抹茶をいただく。 |
|
| 我が家でも毎年、2月の声を聞くと床の間に、40年前の木目込み人形を |
| 飾っている。長女のために買ったものだが、小学生の二人の孫は男子の |
| せいか関心がない。雛人形は実家に置いたままである。 |
| 娘自身も幼いころは雛段の前で歌ったり踊ったりして喜んでいたのに、 |
| 部活動が忙しくなった中学生からは、すべて母親任せになった。 |
|
| 今年も、昔のように桃の花を生け、雛あられや菱形の三色餅を飾った。 |
| 静かにお雛様をながめていると、脳裏には私の幼少時代が浮かび、若い |
| 父母、姉や兄が登場してくる。 |
| タイムスリップはささやかな楽しみである。 |
| |
|