
レディランサー アイリス編4

金髪の青年を寝かせた洞窟から、少し離れた暗闇の中で、わたしは偽者の肉体を育てていた。
今はまだ、桃色の肉塊にすぎない。青年の体細胞にわたしの細胞を加え、植物や小動物を溶かして、吸収させている。もう半日もすれば、人間の形になるだろう。
洞窟の外では昼が過ぎ、夕方に近づいている。保護した青年は、寝袋で昏々と眠っていた。起きていると思考漏れが煩いから、眠っていてくれる方がいい。
(他の雄に、先に交尾されるのではないか)
という憤怒と苛立ちが、いちいち放射されてくる。
それが、有性生殖の宿命らしい。繁殖に必要な雌を独占しようとする、雄の凶暴性。
わたし自身は、そういう破壊的な激情には縁がない。わたしは無性生殖だからだ。
それとも、融合性生殖に進化したと言うべきか。
とにかく、同盟は成立した。わたしは脱出のための船を手に入れ、彼は有性生殖の相手を取り戻す。
無限の可能性があるといっても、現在のわたしの力は、まだ不十分。もっと強くなり、有能になるまで、〝善意の人間たち〟との友好は保たねばならない。
もしも将来、わたしの増殖を、その人間たちが認めないとなれば、改めて決断することになる。
旧人類を滅ぼすか。
それとも、わたしたちがこの銀河を出ていくか。
あれはもう、遠い昔のことに思える。施設の職員たちに文字や計算を習い、人間世界の常識を教わっていた子供の頃。
仲間の実験体は、わたしが育つ横で、大勢死んでいった。付加された遺伝子の違い、投与される薬品の違いで、結果は大きく変わる。わたしは希少な成功例。
でも、わたしは聞いてしまった。人間たちの相談を。
わたしの知能が高すぎる。好奇心が強すぎる。薬で、それを鈍らせると。
わたしは、もっと学びたいのに。
この施設の外に出て、広い世界を見たいのに。
そういうわたしの心を、殺すというの。
では、こいつらはわたしの敵。
慎重に機会を待ったけれど、反逆は、やってみれば簡単だった。わたしが怒りを投射すれば、それを受けた人間たちは、神経が焼き切れ、発狂する。あるいは、痴呆化する。
無力になった人間たちを殺して、施設を破壊し、一人で逃げた。他の実験体を助ければよかったというのは、後から思いついたこと。
友情も協力も、最初は知らなかった。自分自身が分裂し、同族が増えるまで。
初期のわたしは、水もない荒野をさまよった。光合成をし、岩についた水滴を吸って生きた。
そこに、空から小惑星が降ってきた。
大地をえぐる激震。爆発に似た衝撃波。空を覆う塵の雲。
大量の氷が溶けて湖になり、川ができた。湿った風が吹き、雨が降る。
洞窟に隠れて暮らすうち、酸素を発生させる藍藻類が撒かれ、動物や植物が移植された。わたしは彼らを食って、生き延びた。
それでも、必要以上の殺しはしない。感知細胞を持つわたしは、彼らの苦痛や恐怖を、我が身で感じてしまうから。
やがて、食うのではなく、一体となることを覚えた。わたしの細胞を、動物の中枢神経に送り込むと、そこに新たな神経回路ができる。それが、わたしの意志を受信する回路となる。試行錯誤を繰り返せば、そこに、新たな自分が生まれる。
分裂することも覚えた。受信回路を持つ手足を脱落させれば、わたしの意志が、その肉塊を動かすようになる。手足は変形して、独立した生命体になる。
わたしは繰り返し分裂し、数を増やした。分離しても互いに感応できるのだから、全ての個体がわたしである。
環境が落ち着き、移民たちがやってくると、わたしは彼らを観察した。やがて、彼らを使い、実験を行うようになった。
人間に思考の投射を浴びせ、幻覚を見せる。食欲や性欲を刺激する。安堵や、恐怖の感覚を与える。
どの場合も、発覚を避けるため、実験は短時間で終え、利用した人間たちに傷は残さなかった。
それでも、人間たちは、何かを感じ取ったらしい。
『この星には、何かいる』
そして、潮が引くようにして、この星から撤退していった。
それなら、それでいい。
わたしは彼らの残した町で、勉強を続けた。何十体ものわたしが、手分けして勉強すれば、効率がいい。
数学、物理学、化学、生物学。
車や航空機の構造は、理解した。機械類を分解して、組み立てた。真似をして、新たに作った。もう少し時間があれば、自力で宇宙船を組み上げることもできただろう。
だが、その前に彼らが来た。
わたしを創った組織。
創造主の権利があるとでも思うのか、この星中の生き物を殺して回っている。わたしがどんな姿を持ち、どんな能力を育てているか、知らないまま。
愚かな人間たち。
おまえたちはもう、この銀河の覇者ではない。
新たな覇者を、自分たちで誕生させてしまったのではないか。

昼前になると、アンドロイド兵士がやってきて、あたしをシドのいる司令室に連行した。
「やあ、おはよう。よく眠れたかね」
黒髪の偉丈夫は、淡緑色のスーツを着て、健康そのものの顔だ。
「おかげさまで、ぐっすり」
あたしが冷ややかに言うと、にやりとする。
「へこたれないお嬢さんだ。今朝は、ベリルを尋問していたな。何か、いいことがわかったかね?」
あんたを殺せば、あたしが逃げる隙ができるってことかな……とは言わない。
「別に」
「ふうん。ところで、外でランチにしないかね。ずっと室内では、退屈するだろう」
あたしは驚いた。外に出られるのか。それは、シドの自信の表れなのだろうけど。
あたしが承諾すると、シドは部下に車を用意させた。兵に運転させて、近くの川原まで草地の中を走らせる。何度も往復したのだろう、草が倒されて道ができている。
エディが死んだというのに、嘘のような上天気だった。
高く澄んだ青い空、白い雲。遠くに連なる、緑の山並み。
川沿いの土手の上に降り立つと、素晴らしい眺めだった。幅広い砂利の川原にはさまれて、三十メートルほどの幅がある川が、ゆったりと流れている。
両岸は森や野原になっていて、赤いポピーや、白いマーガレット、青紫の矢車菊が点々と咲いていた。甘い香りが漂ってくるのは、ジャスミンの茂みがあるからだ。エディと一緒だったら、どんなに楽しいピクニックだったろう。
シドは自分の寛大さを見せたいのか、鷹揚に言う。
「気に入ったかい? 好きに歩いてきて構わないよ」
もちろん手錠付きだし、銃を構えたアンドロイド兵が四体、見張りに付いてくる。それでも、野原を探検するには困らない。
あたしはあたりを歩きながら、花を摘んでいった。白や紫のルピナス、ピンクのストック。芍薬の群生もあった。つぼみを付けた、百合の群れも。
どうせ、他には人間はいないのだから、好きに摘ませてもらうことにする。一人でこんなに花を集められるなんて、すごい贅沢。
本当は前から、密かに憧れていることがあった。好きな男性から、花を贈られること。できたら、赤かピンクの薔薇がいい。
でも、そんな甘ったるい夢想、人には絶対言えなかった。だって、誰が、賞金首の娘なんかと付き合いたい?
でも、そういえば……エディが来てから、《エオス》の食堂やラウンジで、センスよく生けられた花々を見るようになった。黄色や紫のパンジー。ピンクのミニ薔薇。赤いカーネーション。白や紫のトルコ桔梗。
バシムが言っていたっけ。いい雰囲気になったな、と。
山ほど抱えた花のうち、何輪か、そっと川に流したのは、エディに届きますように、という気持ちからだった。これ以上大袈裟なことは、できない。シドに気づかれたら、嘲笑されるだろうから。
ゆっくり歩いて、シドの元に戻った。彼は草地の木陰に敷いた、大きなシートの上に座っている。
メイド服の女性が、甲斐甲斐しくランチの支度をしていた。金髪のベリルではない。短い赤毛の美女だ。すべすべの白い肌、灰色の目、赤い唇。すらりと背が高く、抜群のスタイル。耳には、小さな真珠のイヤリング。
「おいで、ここにお座り」
まるで、あたしの保護者のように、シドはクッションを敷いた席を示す。とすると、ブーツを脱ぐ方が気持ちよかった。花束を横に置き、靴下だけになって、シートに上がる。
できれば、戦闘服の上着も脱ぎたい気温だったけれど、手錠が邪魔なので、無理だった。それに、下はTシャツ一枚だから、上着の前を開くのも、何となく不安である。シドが、妙に楽しげなので。
(まさか、あたしに対して、変な気は起こさないよね。だって、こんな美人の侍女が、二人もいるんだから)
シドも靴を脱ぎ、胡座をかいて寛いでいた。料理はみな、黒塗りの重箱に美しく盛られている。まるで、王侯貴族のピクニック。
「この花を、持って帰っていい?」
あたしが尋ねると、シドは親切そうに頷いた。
「それなら、水に浸けておくといい」
控えていたバイオロイド兵に指図して、花を川に持っていかせた。兵は少し考えてから、岸辺の細長い草を引き抜き、それで花束をまとめてから、茎を川の水に浸けた。そうすれば、花がばらばらに流されていくことはない。
(バイオロイドも、ちゃんと自分の頭で考えるんだ)
これは、いい発見だった。やはり、管理システムに制御される機械兵とは違う。それなら、反乱をそそのかすこともできる。
問題は、シドに対する、絶対の忠誠心を植え込まれていることだけど。
本人たちは、それをどの程度、束縛だと感じているだろう? もしかして、まるっきり疑いを持たないのか?
他にも七、八名のバイオロイド兵たちが、あちこちで見張りに立っていた。中の何人かは、立ったままハンバーガーらしきものをかじり、パック入りの飲み物を飲んでいる。立ち食いとは、気の毒な。もしかして、23号が奇襲してくるとでも?
「さ、どうぞ、好きなだけ」
シドに料理を勧められた。赤毛の美女が取り皿や箸を渡してくれ、ピクニック用らしい銅製のカップに、水筒からアイスティを注いでくれる。
シドはビールを飲んでいた。どんな場面でも、生活を楽しむ男らしい。たぶん、この星へは気晴らしの〝狩り〟に来たつもりなのだ。
「ありがとう。あなたの名前は?」
あたしが尋ねると、赤毛の美女は驚いたように、灰色の目を見開いた。ベリルと同じで、〝本物の人間の女〟に慣れていないようだ。あたしなんて、〝女〟の部類に入るかどうかも、怪しいもんだけど。
「ペトラと申します」
今度は、遺跡シリーズか。基地に戻れば、タニスとかパルミラとかいうお仲間がいるのかも。
「そう、よろしく、ペトラ。知ってるかもしれないけど、あたしはジュン。ジュン・ヤザキ」
「はい、存じております」
何といっても、親父は有名人だから。学校で何か行事がある時、よく来賓としてスピーチさせられていた。
ママが生きていた頃は、ニュース番組で親父の姿を見たものだ。
『ヤザキ船長、密輸船を追跡、拿捕』
『ヤザキ船長、乗っ取られた客船を奪回』
あたしが《エオス》に乗ってからは、あたしもニュースのネタにされている。軍人だったら当たり前の行動でも、小娘がするから、退屈している人々の話題になるのだ。
あたしが間違った自惚れを持たないよう、ジェイクたちが、厳しく見張っていてくれた……もう二度と、生きて会えないかもしれないと思うと、どんなしごきも懐かしい。
「ジュン、女たちは、そうやって話しかけられるのに慣れていない」
シドが警告してきた。
「きみの気晴らしになるならいいが、きみと対等に話せるような教養はないから、そのつもりで」
本人の前で、ずいぶんな言いようではないか。
「教養なら、あたしにだって、威張れるほどはないよ」
大学の通信講座のレポートだけで、四苦八苦しているんだもの。
「いや、普通に社会生活を送っているだけで、バイオロイドとは比較にならない知恵が身につくものだ」
「だったら、バイオロイドにも、もっと教育期間を与えたら。せっかく創って、五年で廃棄じゃ、勿体なさすぎるよ。命の無駄遣いもいいとこだ」
強く言うと、シドは苦笑した。
「反乱を煽るのは、やめてくれと言っただろう。人間に反逆したところで、勝ち目はゼロなんだから」
「そうだね。組織中のバイオロイドが、一斉に蜂起しない限りは」
「いや、それでも無駄だ。命令を下せる人間が一人でも生き残っていれば、管理システムがバイオロイドを皆殺しにできる」
この星では、現在、その人間はあんただけだよ、シド。人間の部下を連れてこなかったことが、きっと命取りになる。
でも、あたしはそこまでは言わない。
「いただきます」
シドに挨拶したのではない。準備してくれたベリルと、命をくれた動植物に感謝しただけのこと。
ローストビーフのサンドイッチ、塩焼きにした大きな海老、烏賊と貝柱のピラフ、赤身魚の胡麻フライ、ベーコンと夏野菜のパスタ、トマトとハーブのサラダ、何種類ものケーキやムース、甘い苺やさくらんぼ。パーティが開けるくらいの御馳走だ。
「いつもこんな、いいもの食べてるの?」
「食べることは、人生の大きな楽しみだからね」
それはいいけど、この量は二人分には多すぎる。
「ペトラ、あなたのお昼は?」
あたしが尋ねると、給仕の侍女は目をぱちくりする。
「わたくしは、後で……」
「いま、一緒に食べれば? どうせ余るよ、この料理」
すると、シドから再度、警告が来た。
「ジュン、召使いを困らせるものではない。彼女は今、勤務時間だ」
「それじゃ、休憩時間や休日は与えているわけ?」
あたしが追求すると、シドは一瞬、たじろいだ。バイオロイドには、休日も給料もないのが辺境の常識だというから。
「とにかく、組織の秩序を乱すことはやめてもらおう」
「わかったよ」
後でまた、ベリルやペトラ、警備のバイオロイド兵たちを惑わすことを言ってやろうっと。
エディが死んだというのに、こんなに食欲がある自分を、薄情だとは思ったけど、ここで絶食しても、自分の生存確率を下げるだけ。
あたしはまだ、死ぬわけにはいかない。親父が生きている限り。
デザートの、赤い宝石のようなさくらんぼをつまんでいる時、シドが言い出した。
「今朝、偵察鳥を経由した映像を見たがね。坊やの死体は、夜のうち、獣に引きずっていかれたようだ。三十キロ以下の狼や豹は、まだうろうろしているからね」
あたしは手が止まった。
エディの遺体が――埋葬もされず、獣に食い荒らされている?
一瞬、気が遠くなった。エディの笑顔と、血まみれの肉塊が重なって。
神さま。
でも、シドは、あたしを動揺させて楽しんでいるだけ。人間を見守ってくれる親切な神なんか、この宇宙にはいない。いるとしたら、弱肉強食を認める冷酷な神だけだ。
「埋葬くらい、してくれなかったの?」
と非難したが、黒髪の重量級ダンディは、澄ました顔である。
「獣に食われるのも、微生物に分解されるのも、同じことだろう。どちらでも無機物に還り、自然界で再利用される」
「それじゃ、あんたが死んだら、死体は獣にくれてやるよ」
あたしが怒りを込めて言っても、シドは平気だ。
「いいとも。きみが死んだら、全裸でガラスの棺に入れてあげよう。赤い薔薇で埋めてね。きっと素敵だよ。白馬の王子さまが通りかかって、買い取りたいと言うかもしれない」
白雪姫じゃあるまいし。
「死体愛好家の王子になんか、用はないね」
「同感だ。わたしも、生きているきみの方がいい」
にんまり眺められて、ぞっとした。こいつ、やっぱり、あたしに変な関心を持っている。
これは、男の子にラブレターをもらうとか、街でナンパされるとかいう平和な出来事とは、次元が違う。できるものなら、走って逃げたい。
それでも、
「わたしが怖いかね」
と見透かすように言われたことには、むっとした。
「あたしは、この世に怖いものなんかないよ」
身近な誰かを失うこと以外には。
「そうらしいな。だが、苦手なものはあるだろう。一度、きみの可愛い悲鳴を聞いてみたいな。その服の背中にムカデを入れるのと、ナメクジを入れるのと、どっちがいい?」
唖然とした。
この、変質野郎。
「あんた、あたしに喧嘩を売ってるの!? 他にすること、ないの!? わざわざ中央にまで侵入してきて、どれだけ暇人なの!?」
するとシドは、上体を反らせて笑った。
「そう、その調子だ。きみは、怒ると実に魅力的だね」
どういう趣味だ。
「暇は確かだ。いったん地位を固めてしまうと、組織のボスというのは、案外と退屈なものでね」
「他組織との抗争は?」
「小競り合い程度はあるが、本格的な戦闘は滅多にない。速攻で片付かない限り、他組織に付け込まれるのでね」
シドはビールのお代わりを飲みながら、機嫌よく話した。小惑星工場の建設。防衛艦隊の強化。違法都市でしている商売のあれこれ。これまでに潰してきた他組織の話。どうやって部下の裏切りを防ぎ、なおかつ、やる気を維持するか。
あたしは理解した。こいつは、本当に退屈しきっていたのだ。
無理もないかもしれない。周囲はおとなしいバイオロイドと、機械人形ばかり。人間の部下は、許容範囲内のお追従しか口にしない。だから、『対等な話相手』に飢えていた。
それなら、あたしの身は当面、安泰なのかもしれない。そう長いことではないにしても。
「あんたはそもそも、どうして違法組織に入ったの。辺境で生まれたわけではないんでしょ」
シドは、よくぞ聞いてくれた、という顔をする。
「ああ、元は中央の市民だった。惑星警察の警官だったんだよ。十年以上働いていた」
それはずいぶん、極端な転身だ。辺境には軍人崩れ、司法局員崩れが多いというけれど。
「それがどうして、辺境に?」
「どうしてと言われると……そうだな。警察に飽きたせいかな。どうせ、大きな事件は司法局に持っていかれる。パレードの時の交通整理や、酔っ払いの喧嘩の仲裁なんて、つまらないだろ」
「じゃ、司法局に入ればよかったじゃない。大事件を担当できるよ」
「そうすると、勤務地が選べない。その頃は、母の側にいたかったものでね。父を冬山登山の事故で亡くしてから、母は荒れていた」
「それは、お気の毒に……」
「いいや、きみの両親とは違う。元々、仲のいい夫婦じゃなかった。母は、つまらない結婚生活で、貴重な青春を無駄にしたと思っていたんだ。わたしが子供のうちは、まだ、いい母親をやろうと努力していたんだが」
よく、わからない。結婚に失敗したなら、さっさと別れればよかったろうに。
「父が死ぬと、母は、箍が外れたみたいになった。美容整形して、若作りして、男と遊び回るようになったのさ。今度こそ、ましな男を捕まえようってわけだ。で、入れ揚げた男に振られると、また整形に走る。もっと若く、もっと美人に。振られたのは顔や年齢のせいじゃなくて、そういう性格のせいなんだが、本人にはそれがわからない」
あたしはやや、違った目でシドを見るようになった。こいつ、もしかして、母親思いの息子だったのか?
荒れているお母さんを、何とかしようとしていた?
「わたしも途中までは、母を慰めたり、いさめたりしていたが、まあ、それにも飽きたんだな。馬鹿は、死ななきゃ治らない」
うわあ、言い切った。お母さんのことなのに。
「整形が害になるというのは、見ていて、よくわかったよ。自分の男が他の女を見たというだけで、母はこう、眉が吊り上がってね。鬼婆というのは、あのことだな」
今は笑いながらそう言うけれど、当時のシドは、母親のことで、ずいぶん思い悩んだのではないだろうか。彼を市民社会に留めていた糸が、そうやって、何本も切れていったのかも。
細い灰色の目があたしを見て、幾分優しく言う。
「きみならたぶん、年を食っても、そんな醜態はさらさないだろう。中身のある女性は、男に依存しなくても生きられる」
褒められたらしい。でも、見当違いだ。あたしは自分がエディに甘えたかったことを、自分でわかっているから、シドのお母さんを軽蔑できない。
「あたしだって、皺が出る歳になったら、美容整形に走るかも」
今はまず、その年齢まで生きられるかが問題だけど。
シドは、何かしんみりしたような、でも、期待をかけているような態度で、あたしに言う。
「どうだい、お嬢さん。不老処置を受けて、わたしと一緒に、末永く幸せに暮らすというのは。きみはきっと、辺境暮らしに向いているぞ」
へ!?
あんたと一緒に? 末永く?
何だかまるで、プロポーズの台詞みたい。新鮮なうちだけ遊び相手にして、飽きたら、最高幹部会にでも売り渡すくせに。
「ご親切に、ありがとう。参考までに聞くけど、あんたは幾つなの」
「そうだな、きみの祖父くらいの年齢かな」
ところが、あたしは、祖父母の年齢を知らない。会ったこともない。
親父はママとの結婚を反対されて以来、故郷の一族とは、縁を切ったままなのだ。友人たちが仲裁しようとしても、頑として断ってきた。
『見かけが女でも、本物の女じゃないだろ』
『深層心理に、破壊衝動や殺戮衝動が残っているかもしれない』
『戦闘兵器に、子供なんて育てられるの?』
というように、家族や親戚から、散々に言われた恨みがあるらしい。
親父はあまり語らないけれど、当時の騒ぎを知るバシムが教えてくれた。滅多に怒らない親父が怒って、自分から、一族に絶縁を宣言したこと。
ママは最後まで、それを気にしていた。自分のせいで、夫の家族に亀裂を入れたと。
でも、それは仕方ない。あたしだって、ママと会ってもくれなかった祖父母なんて、要らないし……ママのお葬式の時だって、あたしの手を握っていてくれたのは、バシムの奥さんのルカイヤさんだった……
ぼんやりして、警戒を忘れていたのだろう。顎に手をかけられて、びくっとした。こんな大きな手では、あたしの首なんか、簡単に絞められてしまう。
シドは身を乗り出して、灰色の目で、あたしの顔を覗き込んでいた。
「やはり、この美しさを失うのは惜しいよ、お嬢さん」
ええっ!?
「本気で考えてみないか? わたしの女になれば、不老処置を受けさせる。どんな贅沢でもさせる。庭園のある屋敷、ドレスに宝石。犬でも猫でも、虎でもライオンでも飼うといい。輸送船の下働きなんかより、ずっといいだろう」
あたしが唖然としていると、シドはにやりとした。
「といっても、武器になるものは渡せないがね。きみはそれで、わたしを殺そうとするだろう」
かっとした。やっぱり、からかわれてる。
「よくわかってるじゃない。あたしなら、あんたを殺して、自分が組織のボスになるよ」
シドは大笑いした。
「それが一番似合うな。きみなら、辺境中の違法組織を統合できるかもしれない」
ふん。
どうせもう、辺境中の違法組織は〝連合〟にまとめられている。二百年前ならまだあたしにも、辺境統一のチャンスがあったかもしれないけど。
「散歩してくる」
あたしはブーツを履き、再び川原に降りた。さっき水に浸けた花は、まだ元気だ。アンドロイド兵が付いてくるが、あたしの邪魔はしない。
しばらく野原と林を歩き、途中で彼らに命令した。
「全員、いいと言うまで、あたしに背中を向けていて」
いくら人間ではないと言っても、男の姿をしているのだから、見られていては落ち着かない。彼らの背中を見ながら、草むらの中で用を足した。
こういう時、エディは気を利かせて、遠くへ離れていてくれたものだ。野草を摘むとか、道を調べるとか、適当な理由をつけて。
いつでも優しく、完璧な紳士だった。あたしが温室に逃げ込んだ時は、追いかけてきて、違法ポルノの鑑賞を止めると言ってくれた。
あの時は信じなかったけれど、今は違う。エディなら、きっとそうしてくれたはずだ。あたしは何という、貴重な存在を失ったのだろう。
それにまた、一生、それを悔やみ続けるなんて、あまりにも無駄すぎる。
だって、悔やんだところで、エディは戻らないのだから。
もしも傲慢の罰だというのなら、天はあたしを死なせて、エディを生かすべきだった。
それとも、この世に生きること自体が、何かの罰なのだろうか。罪の少ない人間ほど、早く死んで、清らかな天上世界に戻れるのだろうか。ママもエディも、だから、早く死んだのだろうか。
でも、それでは、あまりにも悲しすぎる。
もちろんあたしは、神も天国も信じていないけど、そういうものを仮定しないと、考えが進まない。物理学で、実際には存在しない剛体を仮定するようなものだ。
ぼんやりと水辺をうろついていたら、シドが近づいてきた。
「暑かったら、泳いでもいいんだよ。昨日は、いい場面を見せてもらって、感謝しているんだ」
「えっ?」
感謝って、何に?
「朝、川で洗濯したり、水遊びしたりしただろう」
あたしは口を開いたまま、凍りつく。シドは、にんまりして言う。
「偵察鳥が撮影した映像、見せてあげようか?」
あたしは伸び上がるようにして、大男の顔に平手打ちを食らわせた。でも、シドは平然としてそれを受けてから、あたしの手首を捕まえる。手錠付きだから、こちらは身動きとれない。
「わたしをぶつなんて、他の者なら処刑室行きだぞ」
ぐいと引き寄せられ、唇にまともにキスされていた。太い腕にがっちり抱えられていて、逃げられない。
嘘でしょ。
ビール臭い。気持ち悪い。
なんであたしが、こんな目に。
ところが、キスだけでは済まなかった。シドのごつい手が、あたしの胸や腰を探ってくる。
あたしは恐怖でパニックを起こし、遮二無二もがいた。そして、何とかシドから離れると、逃げ出す素振りで、そこにあった岩に飛び乗った。
そこで、くるりと反転し、シドの頭に蹴りを浴びせた。直撃すれば、致命傷になったはずの蹴りだ。
ところが、シドは慌てもせず、あたしの足首を宙で捕まえ、ぶんと振り回した。
てっきり、砂利の地面に叩き付けられると思ったのだけれど、軽い人形のように、逆さ吊りにされただけ。
「まったく、生きのいい子で嬉しいよ。しかし、部下たちの手前、お仕置きだけはしておかないとな。しばらく、そのままで反省したまえ」
そのままって、まさか。
シドは兵に命じて、あたしを木の枝から逆さに吊るさせた。左右の足首にロープをかけられ、脚を少し開かされた態勢だ。とても、人には見せられない姿。
頭に血が下がってきて、苦しい。手錠もはまったままだから、有効な身動きができない。なのに、シドは呑気に言うのだ。
「いい子になると約束したら、降ろしてあげよう。約束する気にならなければ、明日の朝まで、そうしているといい」
逆さのまま眺めても、あたりは平和だった。銃を持った兵が、広く散っていることを別にすれば。
川はきらきら流れているし、野山は新緑に輝いている。自分が逆さに吊るされていることだけが、悪い冗談のよう。
シドのつもりでは、きっと冗談なのだ。あたしが泣いて謝れば、寛大に許すつもりなのだろう。そしてまた、ああいう真似をするつもりだ。
23号を狩り出すまでの、退屈しのぎに。
こん畜生。
この悔しさで、あいつを呪い殺せないものか。
ああ、でも、頭が破裂しそう。いつまで耐えられるだろう。さすがに、こんな訓練はしたことがない。
やがて、シドが砂利を踏んでやってきた。あたしの吊るされている枝は、草地から川原に張り出している。真下は石の川原だから、暴れて枝が折れたりしたら、頭から墜落してしまう。両手は手錠をかけられたままだから、頭を守る動作が難しい。
「反省する気になったかね。もう反抗しません、ごめんなさいと言えば、すぐに許してやるんだが」
言うもんか。
「そうか、まだ頑張るか。つくづく、誇り高いお嬢さんだな」
シドの手が、あたしの腰に触れた。思わず、びくっとしてしまう。その手がじわりと、あたしの腰や脇腹を撫でていく。
恐怖と怒りで、鳥肌が立った。ジェイクやエイジだって、訓練などの必要以外、あたしに触れることはない。あたしを叱るのに、加減して小突くことはあっても。
「タダであたしに触るな!! 図々しいぞ!!」
それがまた、シドを喜ばせたらしい。面白がっている声が言う。
「そうか、触られるのは嫌いか。おい、ナイフを寄越せ。果物ナイフじゃない。ハンティング用だ」
シドが兵に命じた言葉を聞いて、血が凍った。エディが料理した兎のように、あたしも動脈を切られ、腹を裂かれるのでは。
誰か助けて。
危うく、シドに哀願しそうになった。ごめんなさい、もう抵抗しないから許して。
でも、そんな泣き言を言うくらいなら、黙って切り裂かれて死ぬべきだ。
シドはナイフで、あたしのズボンの生地を切り裂いた。切れ端が川原に舞い落ち、腰の周囲に迷彩の布が垂れ下がる。
「さあ、どのへんを触られるのが一番嫌かな、お嬢さん」
そう言いながら、冷たいナイフの腹で、むきだしになったあたしの脚を、ぴたぴた叩く。こいつ、やっぱり変質者だ。
ジェイクたちがわざとらしく、ラウンジでああいう映画を見ていたのは、正しかったんだ。あたしは警告を受け止めて、《エオス》を降りるべきだった。そして、どこかの女子大の寮にでも……
いや、やっぱり違う。
大学の次は、実社会が待っているんだもの。
脅しを受けて逃げたら、自分の世界が狭くなるだけだ。逃げることを繰り返したら、最終的には、どこにも居場所がなくなってしまう。
いきなり、濡れたものが太腿に触れた。それが上下に移動するので、シドが舐めているのだ、とわかる。
もうだめ。もう少しで、悲鳴をあげてしまう。泣きわめいてしまう。
「強情なお嬢さんだな。まだ、降参しないのか」
あっと息を呑んだ。シドの太い指が、あたしの下着の脇部分に入ってくる。そこから、左右の肌をなぞる。その布一枚しか、あたしには残っていないのに。
「さあ、そろそろ謝った方がいいぞ。でないと、お仕置きがきつくなる」
それでもあたしが黙っていると、シドの指が、下着の中枢部分に降りてきた。そこを、前後にさするようにする。
だめ。そこはだめ。やめないと殺す。絶対殺す。
「まだ頑張るのか? それじゃ、少し痛い目に遭ってもらうか……」
次の瞬間、あたしは悲鳴をあげていた。絶叫と言っていい。シドの持っていたナイフの柄が、下着の上から、ぐいと押し込まれたからである。
止めようとしても、止まらない悲鳴だった。そもそも、声をあげようと思ってあげたのではない。我慢の限界を超えた、ヒステリー症状だったかもしれない。
周囲の兵たちが、急いで駆け付けてきた。
「シドさま、どうなさいました!?」
シド本人も驚いたらしく、ナイフを持って後ろへ下がった様子。
「おお、鼓膜が破れたかと思った……わかった、わかったよ。落ち着きたまえ。ちょっと脅かしただけだ。痛いほどは入れなかっただろ?」
殺す。殺す。殺す。
こいつだけは殺す。
あたしは逆さ吊りのまま、涙を流して呪っていた。確かに、それほど深い挿入ではなかったし、痛みというより驚きの方が強かったけれど。
悲鳴を謝罪に匹敵するものと受け取ったのか、シドは兵に命じて、あたしを地面に降ろさせた。あたしは激しくしゃくりあげていて、言葉にならない。
何が悔しいといって、この自分が〝女のような〟悲鳴をあげてしまったことが、我慢ならない。
せっかく、せっかく、強いふりをして、突っ張ってきたのに。男らしく、振る舞ってきたのに。本当は……ただの女の子だと、暴かれてしまった。
あたしはしばらく、草地に敷かれたシートの上で、身を伏せて泣き続けた。泣くのは恥の上塗りかもしれないけれど、神経がおかしくなったようで、泣き止むことができない。下半身はズボンがずたずたの惨めなさまだけれど、それを気にするゆとりもない。
それをまた、シドが他人事のように面白がっているのが、なお腹立たしい。
「可哀想に、びっくりしたんだな」
シドは他人の仕業のように言い、あたしの野戦服の背中を撫でる。その手が時々、脇や腰まで伸びる。
「よしよし、もう泣かなくていい。わたしの命を狙うような真似さえしなければ、いいんだよ。わたしは、きみを大事にしたいんだ。何しろ、〝本物の女の子〟なのだからね」
触るな、とシドの手を払いのけたかったけれど、もう、その気力がない。これ以上、何もされたくない。丸まって、小さくなって、消えてしまいたい。
自分は、こんなに弱虫だったのか。エディは、戦って死んだというのに。

シドさまは、嘘をついていた。
あれは真っ赤な嘘だったのだと、ようやくわかった。
『人間の女は、生意気になりすぎた。おまえたちのような優しい女こそ、男の理想だよ』
それなのに、ジュン・ヤザキを捕まえてからというもの、シドさまは、この娘のどんな憎まれ口にも、楽しそうに笑う。食事を共にして、何時間も話し込む。
わたしたちでは、絶対に有り得ないことだ。
バイオロイドなど、〝本物の女〟の前では、太陽の前の蝋燭のようなもの。
考えると、頭がおかしくなりそう。
いいえ、考えてはいけない。考えてしまったら、リマのようになる。基地の中央通路で、自分の頭を撃ち抜いたリマのように。
あの日、磨き上げられた通路に、真っ赤な血と肉片が飛び散った。まるで、大輪の花を咲かせたように。
『あの女は不良品だった。狂っていたのだ』
と人間の幹部に説明されたけれど、それは違う。リマはその直前まで、きちんと働いていた。そして、言葉巧みに、警備兵から銃を借り受けた。あの赤い花こそ、彼女の意志。
たぶん、ものを考えてしまったら、ああなるのだ。
培養工場からは、毎月、新しい女が送り出されてくる。いったん兵の相手に落とされた女は、二度と再び、シドさまの寝室に呼ばれることはない。
それでも今日までは、シドさまのお姿を間近で見られるだけで幸運、と思っていたけれど。
「さ、帰ろうか。そろそろ冷えてきた」
太陽が低く傾き、空の雲が紫と薔薇色に染まりだす頃、黒髪の娘はようやく泣きやんだ。シドさまは、大事そうに娘を抱き上げる。
「降ろせ、歩ける」
娘は、むきだしの脚をばたつかせて抵抗したけれど、それすらも、シドさまには愛しくてならない様子。
「いい子にしておいで。今日はもう、何もしないから……」
わたしは敷物を取り上げてはたき、きちんと畳んでから、車に戻ろうとした。その時、凄まじい羽音が襲ってきた。
どこから忍び寄っていたものか、視野一杯、小さなものがわんわんと飛び回る。まるで、黒い雲のよう。
肩や胸、手の甲、スカートに、色々な種類の虫が、びっしり張りついた。
黄色と黒の縞模様の虫。赤く細長い虫。黒や緑の艶やかな虫。
わたしは必死で払った。いったい、何事なの。
周囲で、男の兵たちが悲鳴をあげた。銃を取り落とし、地面に転がって苦しんでいる。どうやら、顔や手を刺されているらしい。背中に手を伸ばして、苦しむ兵もいる。服の下に潜り込まれたようだ。わたしはただ、たかられているだけなのに。
「焼き払え、撃退しろ!」
そう叫んだシドさまも、娘を地面に降ろして、身をよじっている。いったん車に逃げ込んだ兵も、ドアを開けて転がり出てきた。車内にも、虫が入り込んだらしい。
「川だ、水に飛び込め!」
シドさまが真っ先に走って、川に飛び込んだ。バイオロイド兵たちも、転がるようにして後に続く。しつこい虫も、水中では離れるのだろう。
心を持たず、苦痛を感じないアンドロイド兵のみ、火炎放射器を取り出して、虫の群れを焼いていた。何千匹、何万匹が焦げて落ちただろうか。燃えながら飛び回る虫もいた。それでもまだ、何十万の虫が残っている。
炎から逃れた虫は、茂みの奥へ避難した。おかげで、視野が晴れる。
その時、ボンという音がして、火炎放射器を持ったアンドロイド兵が一体、胸を吹き飛ばされて倒れた。誰かの銃を拾ったジュン・ヤザキが、身を翻して草地を走っていく。
いけない、逃がしては。
でも、バイオロイド兵たちは水中だし、アンドロイド兵は虫を追い払うのに忙しい。
わたしは落ちた火炎放射器を拾い、逃げる娘の後を追った。邪魔な茂みを飛び越え、彼女は森へ駆け込んでいく。
あれだけ軽々と走れるとうことは、彼女も刺されていないのか!?
燃料の詰まった重い銃を抱えて走るうち、スカートもペチコートもずたずたに裂けた。森の中を走るような格好ではないのだ。ストラップ付きの靴も、ヒールが高いので、走りにくい。石や木の根につまづき、何度も転びそうになる。
「待って、逃げないで!!」
前方の人影に向かって叫んだ。もちろん、止まるはずはない。向こうは手錠付きとはいえ、頑丈なブーツを履いている。ズボンは切り裂かれて、見る影もないけれど、脚力は鍛えてあるらしい。このままでは、見失う。
やむなく火炎放射器を構え、トリガーを引いた。こんなものを使うのは初めてだから、有効距離などわからない。夕闇の森に、凶悪なほど明るい火炎が伸びた。みるまに、乾いた草木が燃え上がる。
茂みに消えかけていた娘は、ぎょっとしたように振り向いた。炎は彼女の位置まで届かないけれど、火に照らされた姿はくっきり見える。
「そこで止まって!! でないと、焼け死にますよ!!」
けれど、彼女は再び走って消えた。森の奥に。それを追いながら、わたしはまた火炎を放射する。
風に吹かれ、炎が左右に広がった。大きな山火事になるかもしれないけれど、彼女を捕まえなくては。シドさまが、あれほどご執心なのだもの。
必死に後を追ったけれど、やはり脚力に差があった。風が吹いて草木がざわめき、彼女の気配を消してしまう。
流れてくる煙で、目が痛くなった。喉も苦しい。それに、ここはどこ。
その時、口の中に、何かが飛び込んだ。小さな虫らしい。はっとした時にはもう、喉を通過してしまっている。食道に気味悪い感触があったけれど、すぐに消えた。
ただの虫ならいいけれど。もし、23号が関わっているのだとしたら。
帰り道を探そうとして、何度も炎の壁に遮られた。熱風で肌がひりつき、火の粉で髪や服が焦げる。
重い火炎放射器は、途中で捨てた。応援の兵たちが来て、ジュンを捜索しているかもしれないけれど、わたしのことは、誰も気にしていないのではないだろうか。わたしはこのまま、焼け死ぬのかもしれない。
ふと、思った。
それなら、それでいいのかもしれないと。
戻ったところで、何があるの。果てしなく兵たちの要求の相手をして、最後には始末される。わたしには、あと一年の命しかない。
頭上を見上げると、木々の向こうの深い藍色の空に、金色の星が光っていた。この《タリス》に来てから、星を眺めたことなどあっただろうか。
野原を歩いて、花を摘むこともなかった。人間の娘には許される気晴らしが、わたしたちには有り得ない夢。
そうだわ、花を摘もう。腕に一杯。
そうしたら、あとは炎に飛び込んでもいい。崖から飛び降りてもいい。
帰らないと決めてしまうと、途方もなく身軽な気分になった。川に飛び込んで、海まで流れていってもいい。映像でしか見たことのない本物の海が、この星にはある。海の水は塩辛いって、本当かしら。
リマも、こういう気分だったのかもしれない。死のうと決めたら、何も怖いものはないのだわ。
ところが、前方の茂みが揺れたかと思うと、ばったり、黒髪の娘に出くわした。遠くに逃げたはずなのに、炎に追われて戻ってきたのだろうか。
向こうは、銃を構えた。わたしは何も持っていないので、突っ立ったまま。
それなのに、何秒過ぎても、撃たれなかった。彼女は銃口を下げ、苦い口調で言う。
「早く逃げないと、焼け死ぬよ。結構、火の回りが早い」
わたしがなおも立ったままでいると、怒ったように言う。
「それとも、あたしと一緒に逃げる!? どうせ、組織にいたって先はないでしょ。だったら、生きる方に賭けたらどう!? シドから逃げられたら、あなたは自由になれるんだよ!!」
あまり驚いて、しばらく口が利けなかった。
シドさまを裏切って、市民社会に助けてもらうの!?
そんなこと、出来るはずがない。あの艦隊と兵士の群れから、逃げられるはずはない。
それでも、頭の中がぐるぐる渦巻いた。もし、自由の身になって、五年ではなく、五十年生きられるとしたら!?
一瞬だけれど、夢を見た。
毛並みのいい犬を連れて、平和な街を歩く自分。花屋で好きな花を買い、通りを見渡すカフェで、ケーキとお茶を注文する。学校帰りの子供たちが、笑って通り過ぎていく。知り合いの子が、わたしを見て手を振ってくれる。
過去に見た何本もの映画が入り交じって、わたしの中に、そういう夢の街ができていた。
本当はわたしも、その街で暮らしたい。人間たちの仲間に入りたい。
バイオロイドは人間より丈夫だというのだから、百年か二百年、生きられるかもしれない。それだけの時間があったら、どれだけのことができるだろう!!
けれど、それはやはり夢だった。次の瞬間には、煙の中から、アンドロイド兵の一団が現れたから。

やはり、23号は存在する。そして、我々に逆襲を試みた。昆虫の大群を操って、わたしを殺そうとしたのだ。
おかげで、バイオロイド兵が四名死亡した。喉や鼓膜を食い破った虫が、脳内で大出血を起こしたのだ。
わたしも危なかった。川に飛び込むのがもう少し遅かったら、脳を食い荒らされていたに違いない。今度から外出時には、防護服か装甲服を着なくては。
他にも七、八名の兵が、蜂毒でショック症状を起こしていた。わたしは各地の部下に警告を飛ばし、待機させてある艦隊を応援に呼び、山火事の鎮火、負傷者の手当て、ジュンの捜索、キャンプ地の警備強化、あれこれと必要な指示を下した。
それから上陸艇に戻って、本格的な治療を受けた。わたしも蜂に刺され、あちこち赤く腫れ上がっている。自分で鏡を見ても、いかにも間抜けだ。
そこに、ジュンを確保したという報告が入ってきたので、安堵した。まったく、油断も隙もない。
それにしても、男しか刺されていないというのは、どういうわけだ?
「シドさま、お食事を」
留守番していたベリルが、司令室に遅い夕食を持ってきた。ジュンはもう怪我の手当てを受け、船室で休んでいるという。炎に追われて走り回ったので、軽い火傷や切り傷を負っていたそうだ。
「着替えを用意してやれ。それと、今日はペトラがよくやった。早目に休ませてやるといい」
「はい、そのようにいたします」
虫の襲撃はあったが、逆さ吊りのお仕置きは楽しかった。誇り高い乙女の悲鳴は、実に味わい深い。やはり、まだ処女だ。これから、あれこれ教えてやる甲斐がある。
ベリルに命じて、ブランディ入りの紅茶を持ってこさせた。23号は、次はどんな手でくるだろう。動物を操るのが特技だというのなら、次は、獣や猛禽類を使うかもしれないが、それは、銃や火炎で撃退できる。その程度で研究施設を破壊できるとは思えないから、もっと何か、特殊な能力があるはずだ。
虫のサンプルは集めさせたが、すぐに細胞のアポトーシスが始まってしまい、これといった手掛かりは得られていない。
だが、次の襲撃はまたあるはずだ。23号の奴、追い詰められて焦っている。待っていろ。我々の創った実験動物が、我々を出し抜けるはずがないと教えてやる。
体内にアドレナリンが満ち、気分が高揚していた。これでこそ狩りだ。奴を仕留め、ジュンを連れて凱旋してやる。ことによったら、ジュンは、最高幹部会に引き渡すことになるかもしれないが。あの子を使えば、父親をおびき寄せることができるだろうからな。
自分の船室に引き上げても、すぐには眠れそうにない。だが、明日のためには眠っておかないと。
そこでベリルを呼び、口でしてくれと命じた。すると、驚いた顔で言う。
「あの、わたしでよろしいのですか?」
そうか。一度、兵士の相手に格下げした女を、再びわたしが指名することはないからな。
だが、この星に降りるにあたっては、新米の女より、経験の長い女の方が都合がよかった。経験と言っても、五年に満たないが。
「構わない、おまえに頼む」
女たちは最後の日まで、わたしを愛する。そのように創ってある。
残酷なのはわかっているが、そうでなくては、組織は成立しない。
人間の部下なら、自分の野心が原動力になるが、バイオロイドの場合は、洗脳しかないのだ。恐怖、もしくは愛情。男の兵士たちには恐怖を持たせ、女たちには愛情を持たせる。それが一番、扱い易い。
最初に研修を受けているので、ベリルの愛撫は巧みだった。わたしの足の間に膝を付くと、たちまち、わたしを熱い嵐の中に沈めてくれる。
ただし、こういう場合でもコンドームは使わせる。感染症の予防のためだ。女たちは避妊処置を受けているから、何十人の兵士の相手をしても妊娠の心配はないが、外部からのウィルス攻撃の可能性は常にある。もしもの場合を考えると、感染経路は一つでも少ない方がいい。
わたしはすぐに果て、後始末も完璧にしてもらった。バイオロイドの女は、便利でいい。口説く手間も、面倒な前戯も要らない。血が騒いで落ち着かない時は、すぐに楽にしてくれる。
ただし、心底から楽しむためには、やはり本物の女だ。
ことに、純真で気の強い娘を手に入れ、じっくり調教するというのは、まさしく王侯貴族の楽しみ。
犯すのは、いつでもできる。
その前に、ありとあらゆる恥辱を与えてやり、悔しがって身悶えするさまを楽しみたい。あの娘なら、心身の限界まで突っ張り通してくれるだろう。
そうして限界に達し、泣き崩れたら、抱き寄せて慰めてやる。
今日奪ったキスは、蜜のように甘かった。やはり、女は強奪するものだ。明日はまた、違う趣向で苛めてやろう。どこまでやったら泣き出すか、それを思うだけでも、疼くではないか。
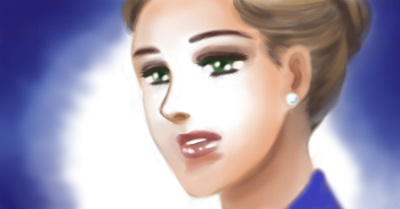
シドさまの部屋を出ると、通路にあるエアロックの一つに寄りかかった。
もちろん、ここから勝手に出ることはできない。外の野原では、兵たちが巡回している。23号は、また何か仕掛けてくるかもしれない。
それでも、勝手に出ていこうとして、兵たちに射殺される方が、ましなのではないだろうか。
惨めというのがどんなことか、今日、ようやくわかった。
これまでは、どんな格下げを受けても、自分なりにあきらめ、折り合いをつけてきたけれど。
今夜、シドさまに久しぶりの奉仕を命じられても、少しも嬉しくなかったのだ。その驚きを隠すために、より熱心に、務めを果たしたけれど。
シドさまはただ、排泄のために、わたしを利用しただけ。
愛され、求められているのは、人間の娘。
これ以上生きていて、何があるだろう。どうせ、あと半年で寿命なのだから。
その時、後ろから声をかけられた。
「ベリル、いまいいか?」
ぼんやり振り向くと、当直を終えたらしい兵が二人、期待にそわそわして立っている。彼らには、休憩時間があるのだ。侍女は睡眠時間以外、全て勤務時間なのに。
「ええ、どうぞ」
にこやかに応じる女でなければ、不良品として処分されてしまう。わたしより前から働いていた女たちは、もうほとんど見かけなくなった。もしかしたら、基地へ帰る途中で処分されてしまうかも。寿命ぎりぎりになったバイオロイドは、神経が不安定になると言われているから。
通路や物陰での〝処理行為〟は禁止されているので、兵たちの控え室の一つに行った。そこで下着を下ろし、彼らの要求に応えた。一度に二人までの処理なら、手慣れたもの。
彼らがわたしの肉体を使い、自分の快楽に夢中になっている間、わたしは冷静に考えていた。
(髪が短ければ、もっと楽なのに)
男たちが興奮してわたしの頭を掴み、結ってある髪を乱してしまうと、また結い直さなくてはならない。ペトラのような短い髪だったら、その手間がかからないのに。
男たちの動きに合わせ、わたしは適当に甘い声を上げていたけれど、演技にすぎない。そう毎日、何度も本気で相手ができるわけがない。
それでも、感じるふりをした方が兵たちは喜ぶし、彼らを興奮させた方が、結果として早く済む。
彼らがそれぞれ果ててしまうと、わたしは使用済みのコンドームをエプロンのポケットに入れ、すぐに自分の部屋に引き上げた。
他の兵に見つかって呼び止められる前に、侍女用の控え室に入れて、ほっとする。後の雑用は、管理システムが引き受けてくれる。睡眠時間だけは、邪魔されることがない。
ペトラはもう、二段ベッドの下段で、深い寝息を立てていた。虫の大群に襲われた挙句、ジュン・ヤザキを追って森を走り回り、火事に巻かれて死ぬところだったのだ。
この星に降りてきてから、侍女は二人だけなので、事務的な会話はよくしていた。でも、心を割った話はしたことがない。いつも管理システムに見張られているから、不忠を疑われるような言葉は口にできないのだ。
わたしより半年は若いけれど、ペトラも、死にたいと思うことがあるかしら?
積極的に死にたいというよりも、
(もういい、生きているのが面倒くさい)
という感じ。
でも、どうせ死ぬのなら、こんな狭い部屋ではなくて、高い青空の下がいい。花が一杯の野原の中。
それは、不可能な夢ではないだろう。油断している兵から銃を奪えば、即座に頭を撃ち抜ける。基地に血の花を咲かせた、あのリマのように。

ぼくは23号に連れられ、真っ暗な洞窟の中を移動していた。彼女の仄かな発光のおかげで、かろうじて足元が見える。
道があるわけではないので、水たまりに落ちそうになったり、濡れた斜面で滑って転んだりした。こんな悪路の中、彼女はよくも、ぼくをかついで運んでくれたものだ。
「おんぶしましょうか」
と提案されたが、それは固辞した。食べては眠り、を繰り返したので、だいぶ体力が戻っている。
今は裸ではなく、普通の男物の服を着ていた。靴も履いている。彼女の仲間がゴーストタウンから、古い缶詰やレトルト食品などの保存食料と共に、持ってきてくれたものだ。
眠っている時間が長かったので、ぼくはまだ、その仲間の姿を見てはいない。話の様子からすると、複数の仲間がいるらしいのだが……
やがて、外界への出口に着いた。人がやっとくぐれる程度の、岩の亀裂だ。
そこから見える世界は、青みがかった日暮れ時である。空には茜色の残照が残っているが、眼下の森は夕闇に沈みかけている。空気は冷えてきているが、服のおかげで寒さはしのげる。
「軌道上に監視衛星があるから、もっと暗くなるのを待ちましょう」
ということで、岩壁の内側に並んで座った。いい機会なので、昨日から考えていたことを言ってみる。
「あのう、ジュンの親父さんなんですが……若い頃、ジュンのお母さんに出会った時に、名前を進呈したというんです。人を番号で呼ぶのはあんまりだからといって、マリカという名前を。それでぼくも、あなたの名前を考えてみたんですが、もし、よかったら……」
23号は不思議そうな顔をした。これまで、名前の必要など感じなかったのだろうか。仲間同士、施設にいた時の番号で呼び合っていた?
しかし、彼女はすぐに微笑んでくれた。子供の思いつきを聞いた、寛大な大人のように。
「わたしに名前をくれるの? ありがとう」
歓喜する様子ではなかったが、迷惑という態度でもなかったので、ほっとした。聡明で勇敢なこの人には、優雅で毅然とした名前が相応しいと、あれこれ考えていたのだ。
「アイリス、という名は、どうでしょうか」
初夏の頃、すらりとした茎の上に、白や黄色や青紫の、気品ある花が咲く。それにまた、虹の女神の名前でもある。イメージとしては、青紫の花が、この人に似合う気がする。
そう話すと、23号は喜んでくれた……と思う。差し出された贈り物を吟味してみたら、悪くなかった、というように。
「アイリス……いい響きね。では、楽しみができたわ。その花を、じかに見なければ」
そして、ぼくの頬にキスしてくれた。くすぐったい。
できるものなら、ジュンからも、こういう感謝を受けたいものだ。生きたジュンに再会できるのなら、受けるものがびんたでも、文句はないが。
ジュンがどうしているかと思うと、またしても、ぎゅっと胸を絞られた。
違法組織の幹部だの、首領だのというのは、下劣な悪党に決まっている。それが、誇り高い美少女を捕まえたら、どうするか。
ジュンが自由を奪われ、服を引き裂かれ、細い躰を無理に押し開かれる無惨な光景が、目に浮かぶ。
こんな空想をする方も下劣かもしれないが、しかし、無事で済むとは思えないのだ。ぼくだったら絶対、ああいうことや、こういうことをしてしまう。他の男の下劣さが、ぼくよりましだという期待は持てない。
どうかジュンが、気を確かに持っていてくれますように。
命さえあれば、傷はいつか癒える。ぼくが一生付き添って、何でもするから。
「そろそろ出てもいいでしょうか」
ぼくが腰を浮かすと、23号、アイリスに止められた。
「まだよ。いま、仲間が来るわ」
そこへ、茶色い小鳥が飛び込んできた。アイリスの白い肩に止まり、細くさえずる。アイリスの口からも、口笛のような音が発せられた。小鳥はまたさえずり、それから外の暗闇に飛び立っていく。
「あなたたちの上陸艇は、ずっと北の土地に持っていかれたわ。そこに、彼らの前線基地がある。ジュンもそこにいる。わたしの仲間が、試しの攻撃をかけたわ。指揮官は倒せなかったけれど、〝仕掛け〟ができたから、攻撃の機会が生まれるでしょう」
ぼくはぽかんとした。
「あの、今の鳥が連絡係……?」
「わたしの仲間。わたしたちは、分裂して増えるの。どんな姿でもとることができる。この星中に、連絡網ができているのよ」
やっとわかった。
それが、この人の価値なのだ。違法組織がしつこく、狩り立てようとするだけのことはある。。
「この星はとうに、あなたの仲間で一杯だったんですね!?」
白い美女は、にっこりした。
「これから、この星中の仲間たちが、自分をアイリスだと名乗るようになるわ」
昆虫、獣、鳥、魚。
「わたしたちは電磁波で交信し、互いに融合と分裂を繰り返すから、全体で調和を保っているの。大型獣が狙われているとわかって、すぐに小さい生き物に分裂したから、まだ仲間は捕まっていない。向こうは、昆虫の死骸しか手に入れていない。わたしの細胞が多少入っていても、死骸はすぐ溶けるから、たいした手掛かりにはなっていないでしょう」
ぼくは、畏怖でしびれている。
「つまり、群体ということですか……惑星全土に散った群体だと」
孤立した、哀れな逃亡者などではない。
言うならば、アイリス一族。
もしもアイリス一族が他の星に降り立ったら、あっという間に、その星を覆い尽くしてしまうのではないか。
それから、一つのことに気づく。
「あなたを、女性と考えるべきではないんですね」
にっこり肯定された。
「そうね。もはや、有性生殖はしないから」
そんな重大なことを、あっさりと。性の区別を持たないならば、あらゆる情動が、人類とは違ってくるだろう。
アイリスがこれまで女性の姿をとっていたのは、ぼくを無駄に怯えさせないためだったという。
それでわかった。会話をしていて、微妙な違和感があったのは、アイリスが、女でないのに女のふりをしていたからだ。
ぼくらは普通、対面する相手が男か女かを真っ先に認識し、それによって対応を決める。現代では、あえて中性や両性の状態を選ぶ者もいるが、それでも対面者は、どちらかに寄せて解釈するのが普通だ。
人類はずっと有性生殖だったから、相手の性が決定できないと、態度にも言葉遣いにも困ってしまう。
だが、これからはたぶん、アイリスのような実験体と遭遇することも、増えてくるのだろう。
違法組織は、どんな新生物を創り出しているか、わからない。明日の文明の主役は、おそらく、ぼくたち人類ではなくなるのだろう。
多くの市民は、この冷厳な事実と、まだ向き合っていない。古い人類は、柔軟な新種族に追い散らされ、滅びていくのかもしれない。
だが、ぼくにももう、見切りというものがついていた。そんなことを心配するのは、戦って、ジュンを取り戻してからでいい。
「〝仕掛け〟というのは、何のことです?」
「兵たちの体内に、わたしの細胞が潜ったわ。神経回路と融合して、受信回路を作る。そうしたら、わたしが外から影響を与えられる」
はっとした。ぼくの胸に植え込まれた、アイリスの細胞。
「まさか、ぼくも?」
ぼくの恐怖を知ると、アイリスは笑った。
「あなたの脳は、乗っ取っていない。乗っ取っていたら、あなたはわたしになっているのだから、そんな心配も浮かばないでしょう。少しは体質が変わるかもしれないけれど、それは、後でゆっくり心配して」
では、やろうとすれば、できるのだ。アイリスは、簡単に他の生き物と融合し、アイリス一族に取り込むことができる。
この一族に宇宙船を与えるということは、巨大な災厄を、銀河に解き放つことになるのかも。
だとしたら、このぼくが、人類滅亡に手を貸すことになるのでは!?
だが、アイリスは明快に言った。
「あなたとジュンには、人間のまま、わたしの味方になってもらいたいの。将来、わたしが人類と正面対決することになったら。その時、あなたたちに、仲裁役をしてもらいたいのよ」
アイリスは、人類に危害を加えるつもりはないという。宇宙は広い。人類と新種族は、共存していけるはずだと。ただ、人類がアイリスを怖れ、滅ぼそうとするなら、戦って生き残るつもりだと。
そうなるかもしれない。ならないかもしれない。それは、後で心配しよう。ジュンを助け出してから、ゆっくりと。
衛星が頭上を通り過ぎた後、ぼくたちは崖を這い降り、暗い森に紛れた。アイリスは、肉体の発光を止めている。これまではただ、ぼくの便利のために、あえて発光していたのだそうだ。
森の中では、小柄な馬が二頭、待っていた。アイリスの仲間だという。
ぼくらがそれぞれ馬の背にまたがり、たてがみを軽く掴むと、彼らは森の下草を踏み分けて、静かに進んでいく。だが、徒歩よりずっと速い。
前の馬に乗るアイリスに言われた。
「眠りなさい。落ちないように、支えるから」
馬の背が変形して、椅子の背のような支えができ、横腹からは皮が垂れて、ぼくが足を入れる鐙のようなものができた。便利な能力だ。
規則的な揺れに身を任せているうち、強い眠気が襲ってきた。まだ、肉体が回復しきっていないからだ。
お言葉に甘えて、眠れるうち、眠っておこう。北方にある敵の集結地に接近したら、すぐに奇襲作戦を開始するのだから。

どうして、忘れていたんだろう。
わたし、空を飛べるんだわ。
最初は蜻蛉のように、身軽に風を切っていた。花に止まり、葉っぱに止まり、水面すれすれを滑る。
そのうち、気流に乗って、高く飛翔していた。鷹か鷲のような、大きな鳥になっている。
力強い翼を広げ、雲の上に出た。それでもまだ、余力がある。もっと飛べる。宇宙まで。
白い雲を散らした青い星が、目の下になった。美しいけれど、なんて無防備なのだろう。暗黒の中で、ただ独りだけ輝いて。
頭を上げると、わたしは無限の星の海を飛翔していた。赤い星、青白い星、金色の星。爆発する星、燃え尽きかけている星。長い尾を曳く彗星も、縞模様のガス惑星もある。
どこへ行こう。どこへ行ってもいいんだ。この世界全て、わたしのために差し出されている。なんて素敵。なんて楽しいの……
ふっと目覚めた時は、狭い二段ベッドの下だった。上の段では、ベリルが静かに眠っている。
夢だったことに落胆したけれど、いい夢だった。本当に、わたしも飛べたらいいのに。
そうしたら、こんな狭い艇は抜け出して、どこまでも飛んでいくんだわ。海も草原も山脈も、全て下に見て。
まだ早朝だったけれど、昨日は早く寝られたので、疲れは取れていた。そっと身支度して、厨房へ行く。
ひどく空腹だった。昨日、あんなに走ったからだ。
ああ、でも、また走りたい。
今朝はなぜか、内側から弾けそうな力が湧いている。たくさんの小さな切り傷も、火の粉にやられた火傷も、気にならない。
いつもの二倍食べて、自分の空腹を満たしてから、シドさまとジュンの朝食の支度をした。シドさまに給仕するのは、ベリルに任せよう。
ワゴンを押して囚人の部屋へ行き、見張りのアンドロイド兵に扉を開けてもらった。もうそろそろ、起こしてもいいはずだわ。
「ジュンさま、お食事を持って参りました……」
昨日、彼女は、わたしを撃たなかった。ほんの数分ながら、『自由になる』夢を見せてくれた。もちろん、シドさまを裏切ることなど、絶対にできないけれど、こうやって空想するだけならば……
絶対にできない?
どうして?
死のうと思ったこと自体、義務から逃れること、すなわち、シドさまへの裏切りなのではない?
その考えに、自分自身で驚いているうち、もぞもぞと身動きして、黒髪の少女がベッドから起き上がった。
「ふああ。早いね。おはよう」
オリーブ色の、何の装飾もない下着姿。わたしたちは常に、男の目を楽しませる、華美な下着を身に着けていなければならないのに。でも、ジュンの下着の方が心地よさそう。
「ちょっと待っててね」
ジュンは浴室に入り、シャワーを浴び、白いバスローブ姿で出てきた。わたしは狭いテーブルに、料理を並べている。
ベーコンとトマトとレタスのサンドイッチ、南瓜のポタージュ、蟹と胡瓜と玉葱のサラダ。ヨーグルト、苺とメロン、紅茶はダージリン。
食器は、忘れな草の模様の陶器。シドさまはこういう出先でも、本物の食器を使う。銀器も漆器も最上級品。ただし、わたしやバイオロイドの兵士たちには、縁のないもの。
文化というのは、人間のためにある。シドさまや幹部たち、科学者や技術者たち。
でも、ただ一人、この娘だけが、わたしたちに関心を払ってくれた。たとえ、自分が逃げるための下準備だとしても。
わたしは自分が何か、この娘に期待していることに気がついた。また何か、事件が起こらないだろうか。
いま思うと、森を火で焼いたのは面白かった。もしも、アンドロイド兵にナパームの炎を浴びせたら、どうなるだろう?
「ああ、昨日は惜しかったなあ。もう少しで、逃げられたのに」
ジュンは率直に言って席に着き、もりもり食べる。
「で、兵たちの被害はどんな?」
昨日のうち死んだ者の他は、皆、あらかた回復していた。待機していた艦隊がこの星の軌道上にやってきて、増援部隊を降ろしている。
わたしからそれを聞いて、ジュンは不満そうだった。
「衛星やブイがすり替えられているか、乗っ取られているかだと、《エオス》には異変が伝わらないな。星系外縁にいても、わからないかも。23号も、もう逃げられないかな。昨日の虫で、シドを仕留められなかったのは惜しかった」
食べ終わると、ジュンは片隅に積まれていた箱を開いた。昨夜のうち、ベリルが用意しておいたものだ。
「ジュンさまの着替えです。上空の船に注文して、届けてもらいました」
甘いサーモンピンクのワンピースを広げて、ジュンはなぜか凍りついていた。それから、それを投げ捨てて怒る。
「シドの奴、ふざけやがって!! 誰が、こんなもん着るか!!」
何を怒るのだろう。美しいドレスではないか。
「サイズは合うはずです。ベリルが、ジュンさまのために用意したのですわ」
「あたしは、元の服でいい。元の服と同じものを、仕立ててよ。できるでしょ」
あんな戦闘服よりも、このドレスの方がいいのに。
「それが駄目なら、こちらでは?」
もう一枚のワンピースを広げてみた。あっさりした白いミニドレスだ。ジュンはそれを見ても、不機嫌なまま。
「服自体は、いいよ。綺麗だと思う。でも、あたしは、女の服は着ないの」
「なぜですか? ジュンさまの船では、そういう決まりなのですか?」
「そういうわけじゃないけど……」
「好きな服を着られたら、いいですね。わたしたちには、これしかないのですから」
するとジュンは、驚いた顔になった。
「メイド服しか……持ってないってこと?」
「もちろんです。わたしたちには、自由時間はありませんから」
起きている間、ずっと勤務時間。休日もない。夏用の制服と、冬用の制服の切り替えがあるだけ。そう話すと、ジュンはベッドの端に座り込み、深刻な顔になる。
「ごめん。あたし、ちゃんと考えたことがなかった。バイオロイドの生活が、どんなものか」
何を謝るのだろう。わたしたちの境遇は、彼女の存在とは関係なく決まっている。
「シドさまに尽くすことが、わたしたちの全てです」
「あなたたちは……じゃあその……本当にシドが好きなの?」
「もちろんです」
今のわたしは、どうだか怪しいけれど。何だかむずむず、そわそわして、外に飛び出したい気分。走って、走って、どこかに行きたい。
「でもそれは、培養中に神経回路を固定されて、強引に植え込まれた感情でしょ? いつまでも、そんな無理は続かないでしょうに。あなたたちがどう尽くしても、シドはそれに報いてくれないじゃないの」
その通りだ。今朝のわたしには、ジュンの言う理屈がよくわかる。これまで頭にかかっていたもやが、強い風で吹き払われたような気分。
なぜ、シドさまに感謝する必要があるの。
どうして、五年で黙って死ぬ必要があるの。
どうせ死ぬとわかっているのなら、抵抗して失敗しても、損はしないのでは?
それでも、張り巡らされた管理システムの手前、模範解答をした。
「わたしたちには、他に生きる目的がありません。シドさまがいなければ、この世に生まれることもなかったのですから」
それから、ワゴンを押して部屋を出た。ジュンの元に、真新しいドレスを置いたまま。
厨房に戻ると、シドさまのワゴンがない。ベリルが給仕に行っているのだ。そこへ、二名の兵士がやってきた。
「ペトラ? 今、いいか?」
ここはシドさま専用の厨房だから、彼らが来るのは、わたしかベリルに用がある時だけ。いつもなら、
(まただわ。暇な男たち)
と苦々しく思うところが、今朝は渡りに船、という気がした。
さっきからずっと、むずむずしているのだ。生理の直前のように、胸が張って、感じやすくなっている。
「いいわよ。来て」
いつも使う彼らの控え室ではなく、狭い食料庫に誘い込んだ。服は着たまま、下着だけ脱ぎ降ろす。このためにいつも、ガーターベルトで吊るストッキングを履いている。
「どっちが先?」
棚に足をかけて、スカートの中身を彼らに見せびらかした。潤滑ゼリーを使わなくても済むくらい、わたしは潤っている。いつもは、ゼリーを塗られることすら苦痛なのに。
「おい、ここではまずいぞ。規則違反だ」
片方の男はひるんだけれど、もう一人が、強い腕でわたしを抱き上げた。
「いいさ、たまには。すぐ済むんだから」
わたしは濃紺の制服を着た男の腰を、太腿でぎゅっとはさんだ。あちこちの傷には、目立たない保護シールを張ってあるから、男たちの目には、さして気にならないだろう。
向こうはもう、興奮していた。目の色が違う。わたしは彼の首にしがみついて、舌を入れるキスをした。向こうも舌で応えてくる。やる気十分だ。
その時、舌から舌に、電流のようなものがびりっと流れた。それが脳天にまで突き抜けて、わたしを痺れさせる。
向こうも同様だったらしい。驚いて口を離し、互いの顔を覗き込む。
この刺激、何だろう。
何かが通じた、という感じ。
前に何度も〝慰労〟している男なのに、いつもと違うことが起きている。
「どうした?」
横で待つ兵士が、けげんそうに問う。
「何でもないわ」
「いいか、いくぞ」
「ええ」
脚を開いて抱き上げられた状態で、下から突き上げられた。気持ちいい。こんな風に感じるのは、本当に久しぶり。シドさま以外の男は、わたしたちにとって、ただの災厄にすぎないから……
自分で気づいた。今のわたしには、シドさまに対する未練がない。だから、他の男を新鮮に感じる。
そうだわ。
あの男が誰に夢中になろうが、もはや、どうでもいい。
それより、自分自身の生が先。
何と単純で、さわやかなのだろう。他の誰かがどう思うかではなく、自分がどう思うかが最優先になる、ということは。
「おい、コンドームをしてないぞ」
横で見ていた兵士が、止めてきた。
「規則違反だ。まずい」
「うるさいわね」
わたしの口から、勝手に言葉が飛び出した。
「どうせ殺されるのよ。何が怖いの」
止めた兵士はたじろいだ。けれど、わたしの腰を抱えている兵士は、不敵に笑って言う。
「おまえもやってみろよ。ナマは気持ちいいぜ」
狂っている。わたしもこの男も、どこかで狂った。
でも、それが何。
いま、自分が求めることをしたいのよ。
「そうだ。俺たちは生きてる。生きてるんだ」
止めた兵士は逃げた。自分まで、規則違反の仲間にされてはかなわない、と思ったのだろう。
わたしたちは構わず、結合を続けた。互いの目を見て、理解している。同じ発見、同じ興奮を共有しているのだと。
なぜかは分からないけれど、この男とは〝仲間〟。
身内に、原始的な力が荒れ狂っている。この力があれば、何でもできると思うくらいに。
潮が満ちるように、絶頂に達した。熱い体液が放出される。脳まで突き抜ける快感。強い脈動が起こり、甘い波紋が全身に広まっていく。
こんなこと、シドさまの担当を外されてからは、一度もなかったのに。
そっと下に降ろされた。向こうも満足したらしい。互いに無言のまま、何かを分け合っている。
その時、ベリルがワゴンを押して戻ってきた。
「あなたたち、何をしているの。ここは、シドさまのお食事を用意するところよ。ここではだめ」
もはや何も怖くなかったが、いま騒ぎを起こすのはまずい、と計算できた。
「わかってる。もうしないわ」
「じゃあな」
わたしと〝通じた〟兵士は、何かを胸に抱いたまま立ち去った。
わたしも下半身の後始末と、身支度を済ませてから、艇内を歩いてみる。行き交う兵士たちのおよそ半数が、〝仲間〟だと感じられた。見交わす視線で、向こうも、そう感じているとわかる。
ただしこの感覚は、〝仲間〟でない者には感知できないものらしい。他の兵士たちは、惨めな奴隷のままだ。23号について、ひそひそと、畏怖混じりの噂を交換し合っている。次はいったい、何が起こるのかと。
段々とわかってきた。昨日の虫たちの襲撃は、わたしたちを殺すためではなかったのだ。
これは、解放。
そして、飛翔。
わたしたちはこれから、世界を手に入れる。もう、一人ではないのだから。