
�_����H�Q
��10�́@�n�[�h�E�F�A�L�q����i���̂P�j
�@�@�|�v��@�Ƃ��̓����|
���V�@�T�i�@�@
�P�@�͂��߂�
- �{�͂ł́ALSI�̐v�E�J���ɍL���g�p����Ă���
�u�n�[�h�E�F�A�L�q����(HDL)�v
�ɂ��ĉ�����܂��B
- ����܂Ř_����H�̐v�́A
�^���l�\��J�ڕ\
���쐬���邱�Ƃ���n�܂�A
- �ŏI�I�ɂ�
��H�}
�����������ďI������悤�ɐ������Ă��܂����B
- �������A���݂ł�CPU���n�߂Ƃ��鑽����LSI�̐v�ɂ͉�H�}��p�����A
- �u�n�[�h�E�F�A�L�q����v�iHDL�GHardware�@Description�@Language�j
�Ƃ�����@���g�p����Ă��܂��B
- �{�͂ł́A����
�u�n�[�h�E�F�A�L�q����v
�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��A���̐v��@�Ɠ����𒆐S�ɐ������܂��B
�Q�@�_����H�v��@�̕ϑJ
- �O�͂܂ł́A�_����H�̐v�ڕW�͉�H�}���쐬���邱�Ƃɂ���܂����B
- ��H�}����������ƁA�v������H�}����
�Q�[�g��t���b�v�t���b�v
���A
- �Ⴆ��74�V���[�Y�̂悤��
�f�B�W�^��IC
�ɒu�������܂��B
- �����̃f�B�W�^��IC���A�v�����g�������Ŏg�p�����u���b�h�{�[�h���
- �������Ĕz������Θ_����H�̊����ł��B
- �������A���̂悤�Ș_����H�̐v�E������@�́A
�����⏬�K�͂Ȏ���̃��x���ł����p����ꂸ�A
- ���ۂ̐v�E�J����@�Ƃ͑傫����������Ă��܂��B
- ���̂悤�Ș_����H�̐v��@�́A�����̋Z�p�̐i���ɔ����A�傫���ω����Ă��܂����B
- ���̕ϑJ�ɂ��āA�ȒP�ɐ������Ă݂܂��傤�B
- (1)�@�f�B�W�^��IC�̕��y
- 1964�N�ɐ��E���̃f�B�W�^��IC�iTTL�j���o�ꂵ�A
�W�ω�H�iIC�j
�̎��オ�n�܂�܂����B
- �����̃f�B�W�^��IC�i�Ⴆ��74�V���[�Y��100�Ԃ܂Łj�́A
�P���ȃQ�[�g��t���b�v�t���b�v�����S�ł������A
- �����̋Z�p�̐i���ɔ����A
�J�E���^��V�t�g���W�X�^�A�Z���N�^��}���`�v���N�T�ȂǁA
- ��荂�@�\�Ŏg���₷���f�B�W�^��IC���J�������悤�ɂȂ�܂����B
- ��H�Z�p�҂́A���̂悤��IC�̃}�j���A�����Q�Ƃ��Ȃ���A
���p�I�Ș_����H��v����̂���ʓI�ł����B
- ���̂Ƃ��̎�Ȑv�菇�͈ȉ��̒ʂ�ł��B
- (1)�@�ڕW�Ƃ����H�̋@�\����������̂ɍł��ӂ��킵���f�B�W�^��IC��I�����A
- �@�@�@������g�ݍ����ĉ�H�}���쐬����B
- (2)�@�`�F�b�N�p�̊�����삵�ăf�o�b�O���s���A���Ȃ����삷�邱�Ƃ��m�F������A
- �@�@�@�v�����g����삵��IC����������B
- ���Ȃ킿�A�K�v�ȋ@�\�����f�B�W�^��IC�̑I�����A�ł��d�v�ȍ�Ƃ̂P�ł����B
- ���݂ł��A��r�I�P���Ȉꕔ�̘_����H�́A���̂悤�Ȏ菇�ɂ��J������Ă��܂��B
- (2)�@�}�C�N���v���Z�b�T�̓o��
- 1972�N�ɓo�ꂵ���}�C�N���v���Z�b�T�́A�₪�ăf�B�W�^����H�̐v��@�ɂ��傫�ȕϊv�������炵�܂��B
- �����̋Z�p�̐i���ɂ��A�����Ŏg���₷���}�C�N���v���Z�b�T������ł��A
�����삳����
- �\�t�g�E�F�A�̊J���������������ƁA
����܂Ńf�B�W�^���h�b�Ŏ������Ă����@�\�̈ꕔ�́A�@�\�̈ꕔ�́A
- ���̃v���Z�b�T�ɒu���������Ă䂫�܂����B
- ���ɁA���G�ȏ�ԑJ�ڐ}�ŕ\�킳��鐧���H�i�V�[�P���T�j���́A�v���Z�b�T�Ɏ��������
- �v���Z�b�T�Ɏ��������悤�ɂȂ�܂����B
- ����摜�����ȂǁA�}�C�N���v���Z�b�T�ł͎����ł��Ȃ������ȓ��삪�v�������̈悪���݂��܂��B
- ���̂悤�ȕ���ɂ́A��p�̂k�r�h��Ǝ��ɊJ��������A�ėp�̃f�B�W�^���k�r�h�ƈ�ʂ̃f�B�W�^��IC��
- �g�ݍ��킹���@���p�����܂����B
- (3)�@�f�B�W�^��IC��1�`�b�v��
- ������uMoore�̖@���v�ɂ��A1�N����2�{�Ƃ����w�����I�ȃX�s�[�h�ŁA�����̂̏W�ϓx��
- ���サ�Ă䂫�܂����B
- ����ɔ����A�f�B�W�^��IC��1�`�b�v����1�̑傫�ȗ���ɂȂ�܂����B
- �������̃f�B�W�^��IC���A1�̔����̃`�b�v�iLSI�j�Ɏ��߂邱�Ƃ��ł���A
���^�����}��邾���łȂ��A
- ���쑬�x�̌�������d�͂̒ጸ���������邱�Ƃ��ł��܂��B
- LSI�J���̏����R�X�g�͑����܂����A�ʎY�������1������̉��i��傫�������邱�Ƃ��\�ł��B
- ��H�̐v�ɂ�CAD�iComputer Aided Design�j�V�X�e������������A�@�\���ƂɊK�w�\��������
- �v�����@���p�����܂����B
- �܂��A��H�̃f�o�b�O�⌟�̂��߁ACAD�ɂ��_���V�~�����[�V�������L���p�����A
- �J�����Ԃ��Z�k�����悤�ɂȂ�܂����B
- �W�ϓx������قǍ����Ȃ����́A��H�v�ɉ�H�}���g�p����Ă��܂����B
- �������A���\���Q�[�g���z�����K��LSI�̎���ɂȂ�ƁA��H�}�̖������c��ȗʂɖc��オ��A
- ������CAD���͂�f�[�^�Ǘ����Ɏx������������Ⴊ�p�ɂɔ�������悤�ɂȂ�܂����B
- ����ɔ����A��H�}��p�����ɁA��K�͂�LSI�������I�ɐv�����@�ɂ��ėl�X�Ȍ������i�߂��A
- HDL���̋�̓I�Ȏ�@�Ƃ��Ē�Ă����悤�ɂȂ�܂����B
- (4)�@�v���O���~���O�\�ȐV���������̃f�o�C�X�̓o��
- �}�C�N���v���Z�b�T�̂悤�ɁA�i��͏��Ȃ��Ă���ʂɐ�������ꍇ�́A��p��LSI���J������̂��L���ł��B
- �������A���ʂ������Y���Ȃ��p�r�ł́A�c��ȊJ���R�X�g���������pLSI���J�����邱�Ƃ͌����I�ł͂���܂���B
- �����ŁA���̂悤�ȏ��ʑ��i��̉�H�ɂ��Ή��ł���悤�ɁA�v���O���~���O�\�ȐV���������̃f�o�C�X
- PLD�iProgrammable�@Logic�@Device�j
���J������܂����B
- ���̃f�o�C�X�̓����ɂ́AEEPROM��q���[�YROM�ASRAM�Ȃǂ̃���������������A�����̌�����ԓ���
- �����̃������ɕۑ����܂��B
- ��r�I���K�͂�PLD�́ACPU�̎��Ӊ�H�A�Ⴆ�������̃A�h���X�f�R�[�_���Ɏg�p����܂����B
- ����PLD�̃v���O���~���O�ɂ́A��H�}�ł͂Ȃ��A
PALASM��ABEL���̂悤�Ș_�����ɑ�������
- �ȒP�Ȍ��ꂪ�g���Ă��܂����B
- ���̌�A�����̋Z�p�̐i���ɔ����A����PLD�̍������A��e�ʉ��A���@�\�����i�݁A
- CPLD�iComplex PLD�j
��A
FPGA�iField Programmable�@Gate�@Array�j
�ւƔ��W���܂����B
- ����FPGA�́A��Ƃ��ď��ʑ��i��̐��i��A�{�i�I��
����p�r����LSI�iASIC�j
���J������܂ł̌q���Ƃ���
- ���p����Ă��܂����B
- �ŋ߂ł́AFPGA�̍������A��e�ʉ��A��R�X�g���ɔ����A
�Ɠd���i��ʐM������͂��߂Ƃ���
- �l�X�ȗ̈�ɓ�������Ă��܂��B
- (5)�@CAD�ɂ���H�v��@�@-��H�}����n�[�h�E�F�A�L�q����iHDL�j��-
- ��H�v����K�͉�����ɂ�āA
�R���s���[�^�ɂ���H�v�V�X�e���iCAD�F�@Computer�@Aided�@Design�j
- ���������Ȃ����̂ƂȂ�܂����B
- �Ƃ��낪�A�Q�[�g�������\���ɒB����悤�ɂȂ�ƁA
��H�}���x�[�X�Ƃ����v��@�Ɍ��E�������Ă��܂��B
- ��H�}�̖������c��ȗʂɖc��オ��A������CAD�ɓ��͂�����C�������Ƃ́A
- �K�����������̗ǂ����̂Ƃ͌����܂���ł����B
- �{���A��H�}�͐l�ԂɂƂ��Ē����I�ŕ�����₷���\����i�̂P�ł��B
- �������A���̖������ɒ[�ɑ�����ƁA�K�������g������̗ǂ����̂ł͂Ȃ��A
�R���s���[�^�����ɂ������Ă��Ȃ����Ƃ�
- ���炩�ɂȂ��Ă��܂����B
- �����ŁAPLD�Ȃǔ�r�I���K�͂Ș_���v�Ɏg�p����Ă�������
�iPALASM��ABEL���j
�����ڂ���A
- ���������ǂ��đ�K�͂�LSI�v�ɂ��Ή��ł���
�n�[�h�E�F�A�L�q����iHDL�j
���J�������悤�ɂȂ�܂����B
- ����ɁA���������_�����`�F�b�N���邽�߂̃V�~�����[�V�������@���ɂ��Ă��A
�ڍׂɋL�q�ł���悤�ɂȂ�܂����B
- ���ݍł����y���Ă���n�[�h�E�F�A�L�q����ɁA�č����h�Ȃ����S�ɂȂ��ĊJ������
VHDL
������܂����A
- ���̍����L�q�\�͂ɂ��g�b�v�_�E���̐v���\�ƂȂ�A
�J�����Ԃ̒Z�k�Ɍ��ʂ��グ�Ă��܂��B
�R�@�n�[�h�E�F�A�L�q����Ƃ�
�@3�D1�@�n�[�h�E�F�A�L�q����Ƃ́H
- �n�[�h�E�F�A�L�q����Ƃ́A�����ʂ�_����H��C����̂悤�ȃ\�[�X�R�[�h��p���ĕ\�����錾��ł��B
- �Ⴆ�A�ȉ��̂悤�ȉ�H�}���l���܂��傤�B
- ���͂� A �� B �A�o�͂� Z_OR �� Z_AND �ł��B
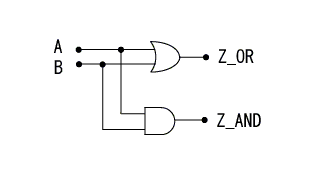
- Z_OR �͘_���a�iOR�j�AZ_AND �͘_���ρiAND�j�ɑ������܂��B
- �����̘_���L�����A�_������p���ĕ\�����Ƃ��\�ł��B
- ���Ȃ킿�A
- �@�@�@Z_OR �@= A + B
- �@�@�@Z_AND = A �E B
- �̂悤�ɂȂ�܂��B
- �n�[�h�E�F�A�L�q����̎�ނɂ��A��̓I�ȋL�q���@�͂��ꂼ��قȂ�܂����A
- ��{�I�ɂ͓����_�����ɑΉ�������o�͂̊W��\���Ă��܂��B
3.2�@�n�[�h�E�F�A�L�q����̓���
- �O�߂ŏq�ׂ��悤�ɁA�n�[�h�E�F�A�L�q����iHDL�j�́A��K�͂ȉ�H��v����ꍇ�̉�H�}��
- ���E���������邽�߂ɁA�l�Ă��ꂽ��@�ł��B
- ������x�A��H�}�̖��_�����Ă݂܂��傤�B
- (1) ��H�}�͒����I�ł͂��邪�ACAD�V�X�e���ւ̓��͍�Ƃ��ώG�ɂȂ�B
- (2) ��H�}�ł́A�ڍׂ��W���I�ȉ�H����̋L�q�͓���B
- (3) �R���s���[�^�ɂƂ��āA��H�}�͕K�������œK�ȕ\���`���ł͂Ȃ��B
- ���ɁA���ݍł��L���p�����Ă���VHDL�ɂ��āA���̓�������܂��B
- (1) �l�X�ȃ��x���ŋL�q�\
- �\�t�g�E�F�A�̕���ŁA�A�Z���u�����ꂩ�獂������ւƔ��W�����悤�ɁAHDL���A
- ���̓Q�[�g���x�������̓r�w�C�r�A���x���̋L�q�܂ŁA���L���Ή��ł���悤�ɂȂ�܂����B
- �Ⴆ�A�g�b�v�_�E���v�ŁA��ʂ̃r�w�C�r�A���x���̂L�q���邾���ŁA
- �S�̂�ʂ����f�o�b�O�𑁂��i�K�Ŏ��{���邱�Ƃ��ł��܂��B
- ��ʂ̃f�o�b�O������������A���̃��x�����L�q���邱�Ƃɂ��A�v���Ԃ̒Z�k���\�ƂȂ�܂����B
- (2)�@�_�������̃V�~�����[�V�������@�̋L�q
- ��H�̋L�q�����łȂ��A���������_���������邽�߂̃V�~�����[�V�������@���L�q���邱�Ƃ��ł��܂��B
- (3)�@�v�����̍ė��p
- HDL�̏ꍇ�A�p�����^���C�Y�̎�@�ɂ��A�v�����̍ė��p���ȒP�Ɏ����ł��܂��B
- ���̃p�����^���C�Y�Ƃ́A8�r�b�g�̃��W�X�^��16�r�b�g�̃��W�X�^��v����Ƃ��ɁA
- ���W�X�^���̃r�b�g�����p�����[�^�ŗ^���邱�Ƃɂ��A8�r�b�g�ł�16�r�b�g�̂ǂ���ł��g����悤��
- �ėp���̂����H��HDL�ŋL�q������@�ł��B
- ���̂悤�Ȏ�@�����p����A�r�b�g���ɂ�����炸�A�P�̃\�[�X�R�[�h�őΉ����邱�Ƃ��\�ɂȂ�܂��B
- �Ȃ��A��H�}�����S�ɔp�ꂽ�킯�ł͂���܂���B
- ��̓I�ȉ�H��HDL�ŋL�q���A��ʂ̊K�w�ł��̉�H���V���{���b�N�ȉ�H�}�ŕ\�������͐������p�����Ă��܂��B
3�D3�@�n�[�h�E�F�A�L�q����̎��
- �n�[�h�E�F�A�L�q����ɂ́A�������̎�ނ�����܂����A���̑�\�I�Ȃ��̂��ȉ��Ɏ����܂��B
- (1) VHDL�@�iVHSIC Hardware Description Language�j
- �č����h�Ȃ����S�ƂȂ��ĊJ�����ꂽ���̂ŁA���ݍł����y���Ă��錾��̂P�ł��B
- (2) Verilog�@HDL�@�iVerilog Hardware Description Language�j
- �č���Gateway Design Automation�Ђɂ��J�����ꂽ����ŁA20�N�ɂ킽��L���g�p����Ă��܂��B
- (3) AHDL�@�iAltera Hardware Description Language�j
- �č�ALTERA�Ђɂ��J�����ꂽ����B���Ђ��疳���̊J���c�[���iMAX-PLUS�U�j������Ă��܂��B
- (4) ���̑��iPALASM�AABEL���j
- PLD�ȂǁA��r�I���K�͂̉�H�Ɏg�p���ꂽ�ȈՌ^�̌���ł��B
- �Ȃ��A�����̊ȒP�ȗ�ɂ��ẮA���̑�4�߂ŏЉ�܂��B
3.4�@HDL�ƃ\�t�g�E�F�A�Ƃ̈Ⴂ�ɂ���
- �n�[�h�E�F�A�L�q����iHDL�j�ƈ�ʓI�ȃ\�t�g�E�F�A�Ƃ́A�{���I�ȈႢ������܂��B
- �Ⴆ��C����ŋL�q���ꂽ�v���O�����́A�����ꂽ���Ԃɏ]���ăV�[�P���V�����ɏ�������܂��B
- �\�t�g�E�F�A�ł́A�P���CPU�œ��삷�邽�߁A����ȗ�������ē����ɕ����̏��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ�����ł��B
- �������A�n�[�h�E�F�A���\�����邷�ׂĂ̕��i�́A���͐M�����^������A���ł����삵�܂��B
- ���̂悤�ɁAHDL�ŋL�q���ꂽ��H�́A�ʏ�R���J�����g�i�������s�I�j�ɓ��삷��̂Œ��ӂ��K�v�ł��B
- �ȉ��A��̓I�ȗ�ŕ⑫���܂��傤�B
- �Ⴆ��
- A = B and C
- D = C or E
- �̏ꍇ�A�M�� C ���ω�����ƁA�M�� A �ƐM�� D �͓����ɕω����܂��B
- �Ȃ��A
- A = B and C
- A = B or D
- �̓G���[�ɂȂ�܂��B
- 1�̐M�� A �ɁA�قȂ�2�̐M������͂��邱�Ƃ��ł��Ȃ����߂ł��B
�S�@�n�[�h�E�F�A�L�q����iHDL�j�ɂ��L�q��
- ����ł́A���ۂɃn�[�h�E�F�A�L�q����iHDL�j��p���ĊȒP�ȉ�H���L�q��������Љ�܂��傤�B
- �Ȃ��A�\�[�X�R�[�h�̑O�������o�͊W�A
�㔼�����̊Ԃ̘_���iAND��OR�j���L�q���Ă��܂��B
- VHDL�̏ꍇ�́A���o�͂̃C���^�t�F�[�X��\�� entity ���ƁA�����̓����\��architecture���ɕ������ċL�q���܂��B
- �ڍׂȐ����͏ȗ����܂����A��܂��ȍ\����A�����̑���_�ɂ��Ĕ�r���Ȃ��璭�߂ĉ������B
4�D1�@AND��H��OR��H
- (1)�@VHDL�̗�@�iAND��H��OR��H�j
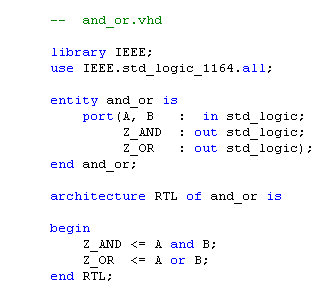
- (2)�@Verilog HDL�̗�
�@�iAND��H��OR��H�j
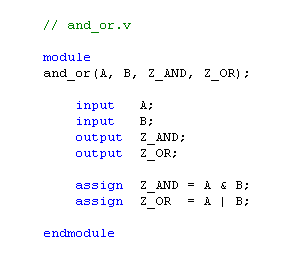
- (3)�@AHDL�̗�@�iAND��H��OR��H�j
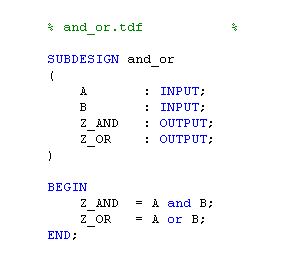
- (4)�@�^�C���`���[�g�̗�
�@�iAND��H��OR��H�j
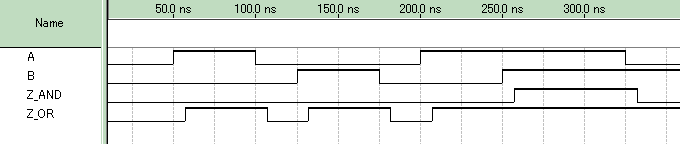
4�D2�@D�t���b�v�t���b�v
- D�t���b�v�t���b�v���A(1)VHDL�A(2)Verilog HDL�A(3)AHDL ��p���ċL�q��������ȉ��Ɏ����܂��B
- ��̗�Ɠ��l�A�\�[�X�R�[�h�̑O���͓��o�͊֘A�A�㔼�̓N���b�N CLK �̗������ŁA����
D �̒l���o�� Q �Ɍ���铮���\���Ă��܂��B
- (1)�@VHDL�̗�@�iD�t���b�v�t���b�v�j
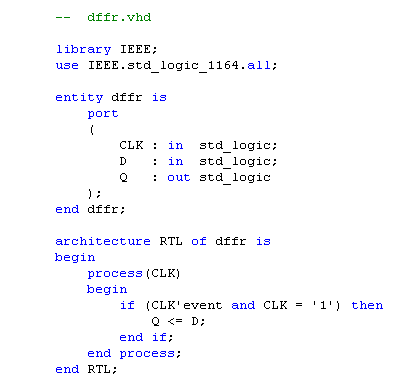
- (2)�@Verilog HDL�̗�@�iD�t���b�v�t���b�v�j
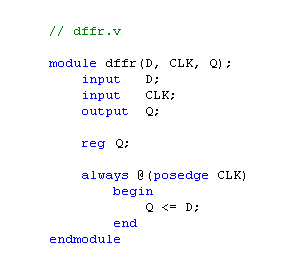
- (3)�@AHDL�̗�@�iD�t���b�v�t���b�v�j
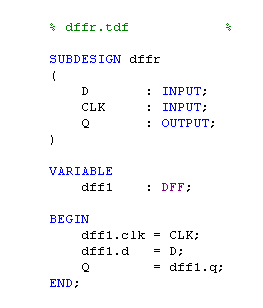
- (4)�@�^�C���`���[�g�̗�@�iD�t���b�v�t���b�v�j
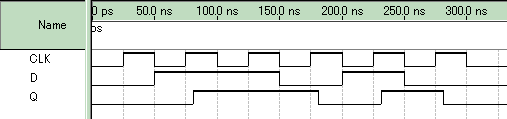
4�D3�@10�i�J�E���^��H�iVHDL�j
- ����ł́AVHDL��p���āA��5�͂Ő�������10�i�J�E���^��2�ʂ�̕��@�ŋL�q���Ă݂܂��傤�B
- (1)�@�Q�[�g�A�t���b�v�t���b�v���x���̋L�q
- (2)�@RTL(Register Transfer Level)�̋L�q
- �\�t�g�E�F�A�ɗႦ��ƁA(1)�̓A�Z���u������A(2)��C++�̂悤�ȍ�������ɑ������܂��B
- (1) �̏ꍇ�A�O���� D�t���b�v�t���b�v���L�q���A�㔼�ł�����4�g�ݍ����āA�J�E���^���\�����Ă��܂��B
- D�t���b�v�t���b�v��ʃt�@�C���Œ�`�����ꍇ�́A�O���͕s�v�ł��B
- (2) �ł́A�J�E���g�A�b�v�̓�����Acount = count + 1; �̍s�ŕ\���Ă��܂��B
- ���̏ꍇ�A��p�̃��C�u���� �iIEEE.std_logic_unsigned.all�j ���Ăяo���K�v������܂��B
- �����̏ڍׂȐ����͎��͂ōs���܂����A�����ł́A���҂��r���Ă��̈Ⴂ�ɒ��ڂ��ĉ������B
- (1)�@�Q�[�g�A�t���b�v�t���b�v���x���̋L�q
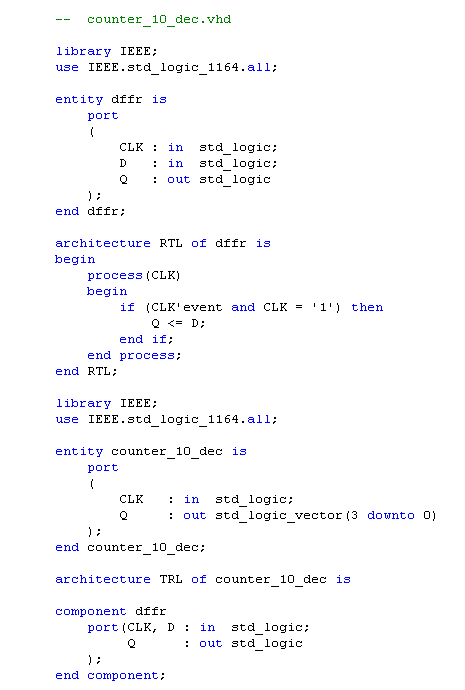
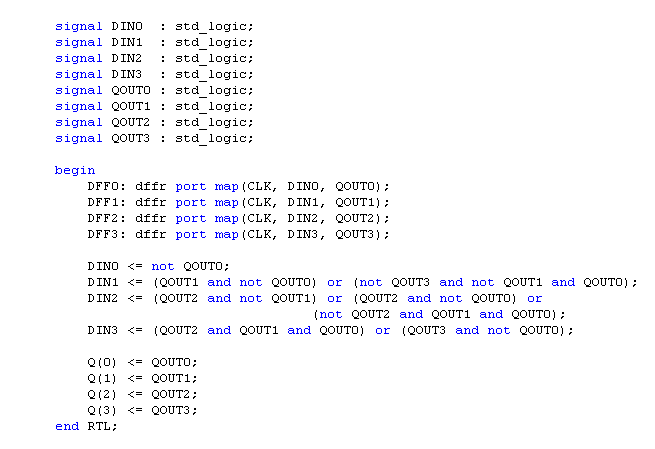
- (2)�@RTL�iRegister Transfer Level�j�̋L�q
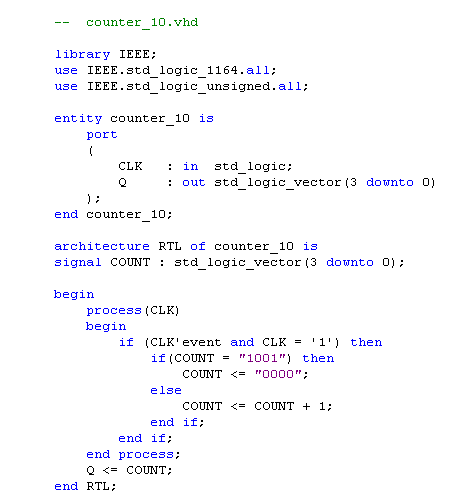
- (3)�@10�i�J�E���^�̃^�C���`���[�g
- �V�~�����[�V�����ɂ�苁�߂�10�i�J�E���^�̃^�C���`���[�g���A�ȉ��Ɏ����܂��B
- 10�i����0����9�܂ŌJ��Ԃ��J�E���g���Ă��邱�Ƃ�������܂��B
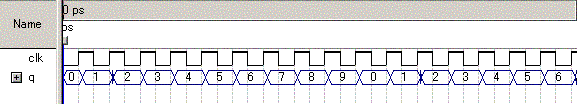
- ���̂悤�ɁAVHDL�ł́A���ʂ̃Q�[�g���x�������ʂ�RTL�܂ŁA���L�����x���ŋL�q�ł��邱�Ƃ������܂����B
- ���̂Ƃ��A��ʂ�RTL���g�p����A�Q�[�g���x���Őv����K�v�͑S���Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
- �������A�Q�[�g���x���̐v�ɂ́ARTL�ł͓����Ȃ����ʂ����҂ł��܂��B
- �\�t�g�E�F�A�̗̈�ŁA��������ł͂ǂ����Ă��L�q�ł��Ȃ������ɂ́A�A�Z���u�����ꂪ�p�����邱�Ƃ�����܂��B
- HDL�ɂ����Ă��A���������Ɍ��܂ŗv������镔���ɂ́A�ו��܂Őv�҂̈Ӑ}�����f�ł���
- �Q�[�g���x���ł̋L�q���������܂���B
- �܂��A�Q�[�g���x���̘_����H���v�ł��A�����̏ڍׂȓ��삪�C���[�W�ł���\�͂�o���A�����A
- ��ʂ�RTL�Őv������H�̃f�o�b�O�ɖ𗧂��Ƃ�����܂��B
- ���G��LSI�ɂȂ�ƁA�`�F�b�N���ׂ��̐M���̃p�^�[���͖����Ƃ����Ă悢�قǂ̐��ɖc��オ��܂��B
- ��ʂɊJ�����Ԃ͌����Ă��邽�߁A�`�F�b�N����M���̃p�^�[�����i�荞�ޕK�v�ɔ����܂��B
- �\�t�g�E�F�A�̏ꍇ�Ɠ����悤�ɁA�l�Ԃ������Ղ������ɂ́A���鋤�ʓ_������܂��B
- �Ⴆ�A���̐M���p�^�[�����J��Ԃ�����������ꍇ�A�����̏������J�n���镔���ƁA�I�����镔����
- �o�O����������m���������Ȃ�܂��B
- �`�F�b�N����p�^�[�����i�荞��A�o�O�̂���ꏊ����肷��Ƃ��ɁA�Q�[�g���x���̘_����H��v��������
- �o�����A���ɗ����Ƃ������̂ł��B
�T�@�܂Ƃ�
- �{�͂ł́A
�n�[�h�E�F�A�L�q����iHDL�j�̐v��@�Ƃ��̓���
�𒆐S�ɉ�����܂����B
- ���͂ł́A
�n�[�h�E�F�A�L�q����
�iVHDL�j��p������H�̋�̓I�ȋL�q�@�ɂ��ďЉ�܂��B
�_����H2�̃g�b�v�y�[�W�ɖ߂�

