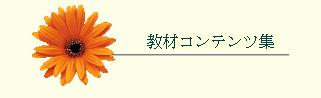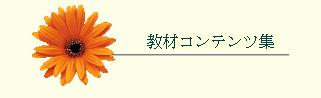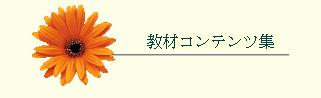
アナログ信号とディジタル信号
- アナログ量とディジタル量はどこが本質的に違うのでしょうか?上の図を用いて整理してみましょう。
-
- 左は、例えば音のようなアナログ信号です。横軸は時間、縦軸は信号の大きさに対応します。
- アナログ信号の性質として、時間軸を拡大すれば、いくらでも拡大することが可能です。
-
- 信号の大きさの軸についても同様です。(ただし、雑音等も拡大されます。)
-
- 一方の右側はディジタル信号を表しています。
- ディジタル信号は、記録や保存、圧縮、伝送等に適していることから、従来アナログ処理されていた分野にも
- 広く適用されるようになりました。
-
- ここで、横方向の時間軸について、ある間隔で観測する操作を、「サンプリング」(あるいは標本化)と言います。
- 例えば、コンパクトディスク(CD)では、44KHzの周波数でサンプリングされています。(周期はその逆数です。)
-
- また、信号の大きさについて、ある間隔で観測することを「量子化」と呼び、この間隔を「量子化ステップサイズ」
- と言います。
- この量子化された値は、2進数で表すことができ、CDの場合16ビット(216=65536レベル)で表現されています。
-
- また量子化の操作により、実際のアナログ信号との間に誤差が生じます。これを量子化雑音と呼びます。
-
- アナログ信号をアナログ処理すると、そのプロセスで雑音が混入し、処理が複雑になるほどSN比が劣化します。
-
- 一方のディジタル処理では、アナログ信号をディジタル信号に変換する部分で量子化雑音が発生しますが、
- その後はビット誤りが発生しない限り、同じSN比を確保することが可能です。
-
- 身近な電子機器の中から、アナログ信号がディジタル処理されている例を探してみましょう。
-
- ⇒ 教材コンテンツ集に戻る