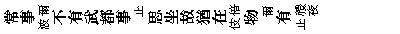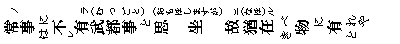テレビドラマのコメディなどを見てゐると、てつとりばやく中國人(あるいは歐米人)の感じを出す表現方法がある。たとへば、強盜が威して金を出せといふとき、かういつてゐる。「オマヘ、ハラマキ、カネある。それ出す、イノチ助ける。許す」
だいたい意味は通じるが、やはり變な日本語である。日本人なら「お前の腹卷きに金があるだらう。それを出せば、生命は助けてやる。許してやらう」となる。くらべてみると、「だらう」といふ推量や、「出せば」といふ條件や、「生命は」の「は」といふ「他と區別する氣持」などが表現しきれてゐない。つきつめてみると、助詞や助動詞が缺けてゐるうへに、いろいろな活用形といふものがなくて、終止形ばかりである。それがこの妙な日本語を作り出すコツである。日本語から助詞や助動詞を拔きとり、動詞や形容詞を終止形ばかりにすれば、外國人が話す下手な日本語となる。
この事實は興味深い。「オマヘ、ハラマキ……」式日本語のなかに、逆に日本語の特性がくつきりと浮び上がつてきてゐるからである。それを實に巧みに説明してくれる文法理論は、時枝誠記氏に始まる時枝文法であらう。
時枝文法については、多くの解説書があり、しだいに識者において一般化されつつあるすぐれた文法理論である。そしてその理論は、日本文法學においてのみではなくて、訓讀によつて漢文を讀む中國研究者にとつて非常に參考になる。そこではじめにその大要を紹介することにする。
鎌倉時代から江戸時代にかけて發展繼承されてきた言語に對する日本人の考へ方といふものがあつた。ところが、この傳統的な文法學説は、明治以後、忘れ去られるやうになつた。といふのは、明治になつてから、ヨーロッパの文法學説を模範として、それに基づいて日本文法が新しく組織された。しかも、さうして組織された日本文法を基礎とする學校文法なるものが生れ、日本の學校における文法の時間は、ヨーロッパの文法學説による日本文法が教へられることとなつてしまつたのである。日本の傳統的文法學説が學校教育からしめだされ、しだいに忘れ去られるやうになつたのはそのためである。
この忘れ去られた日本の傳統的文法學説に對して、近代的な言語研究の立場から、新たに息吹きを與へ、體系化したのが、時枝誠記氏であつた。
時枝文法は、言語過程説といふ言語理論に基づいてゐる。それは、ヨーロッパの言語學説、すなはち、意味とか思想といふ内容と、音声や文字といふ形式、この二つの要素が結合してできあがつたものを言語と考へる立場、いひかへれば言語構成説と對立的なものである。言語過程説は、言語は<物>ではなくて、自分自身の心を外部に表はす人間活動の一種と考へる。話し手と聞き手との全體場面を背景とする心の表現過程そのものである、とする。言語過程説は、言語を人間の働きと考へるので<事としての言語觀>であるが、言語構成説は、言語を物質と同じやうに、要素の結合から成りたつてゐると考へるので、<物としての言語觀>といふことができる。
このやうに兩者の立場は對立的である。當然、語の分類の基準が異なる。<物としての言語觀>、言語構成説では、語を物的に、すなはち形式面からのみ見て機械的に分けようとする。日本語の語を、まづ、自立語、附屬語に二大別する。その語が獨立して使はれるとき(「山」「走る」「美しい」など)自立語といひ、その語が獨立して使はれず、自立語にくつついて使はれるとき、(「が」「……ない」など)附屬語といふ。そして、その次に、自立語、附屬語のそれぞれにつき、活用するものと活用しないもの、とに分ける。といふやうな手續きで分類してゆく。それは、徹底的に語を物として見、形式や機能といふ外的な面から分類しようとする立場である。日本の學校で學ぶ文法は、かうした言語構成説によるものである。現在、普通の日本人の文法觀はほとんどこのやうな學校文法によつてゐるといつてよい。
さて、言語過程説では、どのやうに語を分類するのか。時枝誠記・増淵恒吉兩氏の『古典の解釋文法』(1950年・至文堂)から引用してみよう。
「おどろき」(驚き)といふ語と、驚いたときに表はす「おや」「まあ」などといふ語をとつて比較して見ませう。この兩者は、共に驚きの感情を表現する語であることで同じであると云へるのですが、前者の「おどろき」といふ語は、驚きの感情を、一旦、對象化し、話手の前に置いて、これを、指し表はすところの表現でありますが、後者の「おや」「まあ」は、驚きの感情をそのまま、直接に表現する語であります。前者に屬する語は、皆、何かを、指し表はしてゐるので、物そのものが既に客體的な存在である「山」「犬」「机」などは勿論のこと、主觀的な抽象的な「悲しみ」「雄大」「勇氣」「ほがらか」等の語も、同樣に皆何かを指し表はしてゐます。このやうな語を詞といひます。ところが、後者に屬する語は「雨だ」の「だ」、「櫻も咲いた」の「も」「た」のやうな語は、それによつて、何かを指し表はしてゐるものではなく、話手の判斷や立場や氣持ちを、直接に表はしてゐます。このやうな語を、辭といひます。(18頁)
すなはち、語には詞(し)と辭(じ)といふ二つの性質の違つた種類があるとする。いま私が「山」といふ、「静か」といふ、「走る」といふ。するとどの場合も、讀者はピンピンとそのことばのイメージを思ひ浮べるであらう。すなはち、話し手の私と、聞き手の讀者とに共通のイメージが起つたといふことである。それは客體としての事象を互ひに思ひ浮べたといふことである。かうした種類の語が詞(し)である。ところが、私が「山」といつた次に、「山よりも」といふか、「山よ」といふか、「山だらう」といふか、それは話し手である私の判斷や感情によつて定まる。かうした話し手の判斷や感情を表はす種類の語が辭(じ)である。いひなほすと、詞(「山」)に對する主體(私)の把握のしかたを直接に示すといふことである。
かうした詞・辭といふ分類のしかたは、ことばを話し手と聞き手との關係において分析した動的なものである(自立語・附屬語といふ分類は、ことばを物として見て分析した静的なものである)。そして、この辭が豐富に存在することこそ、日本語の特長中の特長といへる。
具體的にいへば、助詞、助動詞、接續詞といつたものである。さらにいへば、動詞や形容詞の活用された部分も辭的なものといへよう。なぜなら、「書かない」といふ場合、「書か」といふ未然形の活用は、「ない」といふ否定を表はす話し手の判斷に連動して生れてきたものであるから、「書か」の「か」にすでに話し手の否定の感情が託されてゐるといへよう。
さて、以上のやうな時枝文法の考へ方が、漢文讀解にどのやうに關はるであらうか。
時枝文法でいふ辭は、江戸時代の文法學説で使はれた述語である。それは「テニハ」とも「テニヲハ」ともいはれる。本居宣長は、詞を器物にたとへ、辭をその器物を使ひこなす手であるとたとへ、富士谷成章は、詞を胴體、辭を手足であるといふふうにたとへてゐる。宣長の弟子である鈴木朖は、詞を指し表はす語、辭を心の聲ともいつた。かうした區別は、ずつと遠く古代にさかのぼつて、祝詞や宣命にすでに表はれてゐるのである。すなはち、助詞・助動詞・活用語尾を小書きにした宣命體といふ表記法である。その例を擧げておかう。
この小書の部分はいはゆる萬葉假名(夜麻登など)であり、この部分を平がなに變へると次のやうに今日の日本文に近いものとなる。
この發想、すなはち辭にあたるものを補ふといふ發想が、漢文の訓讀にあてはめられたとき、訓點(ヲコト點、テニヲハ點)をつけるといふ發想と結びつく。訓點によつて、まさに「テニヲハ」の印をつけようとしたわけである。それが江戸時代になると、送りがなを補ふといふ形で完成したのである。
このことからもう明らかであるが、漢文には、日本語の辭にあたるものが少ない。いひかへると、漢文は詞が中心の言語なのである。そこで、日本人は、漢文の市と詞との間に辭を補ふといふ形で日本語化しようとしたのである。これが漢文の訓讀といふことの正體なのである。「オマヘ、ハラマキ……」式の日本語とは、詞ばかりを竝べた文章である。中國人が日本語を學んだとき、いちばん苦手なのは活用であり、次にその活用に續く助動詞の接續が苦手である。しぜんと「オマヘ、ハラマキ……」式に詞ばかりを竝べるやうになつてしまふ。
日本語と中國語との決定的な相違は、この、中國語が詞中心、日本語が辭中心、といふところにある。中國人の使ふ日本語には辭が少なく、日本人の使ふ中國語は<辭>的なものが多くてゴタゴタと説明的になり長くなるのはそのためである。
この辭中心の日本語を使ふ日本人には、さうした日本語に基づく思考樣式が生れてゐる。たとへば、日本人には、相手の身になつてとか、相手をやたらと優先する傾向がある。これなどは、辭が話し手のものであり、聞き手とくらべた場合、話し手の立場が優先する、といふ發想に基づいたものである。日本人の必要以上の謙遜も同じ基盤であらう。またたとへば、日本人は、ものごとを精緻なものにしたてあげる特性がある。これなども、辭による精緻ないはゆるキメこまかな表現といふ發想と深い關はりがあるだらう。またたとへば、日本人の思考には求道性がきはめて強い。日本人の思考の代表者でもある西田幾多郎や田邊元といつた哲學者たちの場合をみても、體系を作る、といふことよりも、一つの目標に到達したのち、さらに次の境地へと、奥へ奥へと眞理を求めてやまない。これは哲學者たちの場合にとどまらない。あらゆる「(技)術」が、はてしない「道」へと轉化し、深化されてゆくのは、日本人の思考の特性である。これなども、話し手が辭を使つて奧深な心のひだにわけ入つてゆくといふことと關はりなしとしない。
それと同じく、詞中心、いひかへれば、概念語中心の中國語を使ふ中國人には、さうした中國語の發想に基づくところの獨特の思考樣式があるはずである。それはいつたいどういふものであるのかといふ問題になつてくる。そしてこれが本書の中心問題である。このことを章を改めて次に論じてみたいと思ふ。