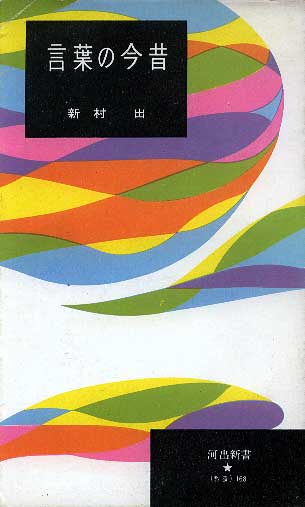
「序文」より
こんど昭和二十六年の春に出した所の、この語源漫談を、河出書房から新書版として改版して刊行することになったのは、老人として嬉しい極みである。善はいそげと、せいては事を仕損ずると聞く箴言との両方との間に迷ったあげくに、せっかちの老人は、ええ、ままよと、殆どすべてを書房の松木老人に、あなた任せと喜托してしまった。この晩春の広辞苑や五月富士の思切りによって、二度あることは三度あると、我慢し往生して、新仮名法の基準に、大体従順することに、諒めた。尚更、漢字法も和俗を寛容せざるを得なかった。それこそ京は清水の舞台から飛びおりる心持で。
……。
「序説」より
以上述べたところのものは、学問の側からであるが、今これを実際の問題の上から考察しなおしてみると、国語の音韻および文字のことが多分を占めておって、その内容たる意味あるいは意義に関することについてはあまり学界でも教育界でも実際界でもこれを対象として扱わぬように見える。等音的にOrthogpahyを改訂することの方に主力を注いで、内容の意義あるいは意味を確実に、また明瞭に教え、把握させるというような教授あるいは訓練というものはとかく怠られ勝ちである。これは平素私が非常に国語問題審査会に対して残念に思っておりおり注意を喚起したこともあった。ある少壮学者が「あまりに音韻的な」といって芥川龍之介の口調をもって皮肉を浴びせたこともあったくらい、近代の国語学界、あるいは国語問題界は音韻的に過ぎて内容の意義を疎かにしてしまったことは、争われないと思う。発音の矯正、アクセントの矯正というようなことは割合に行われ易いが、内容の意味のコントロールというようなことは難しい。その矯正指導とかいうようなことも難しい。それを把握してしっかり喰い止めることも発音の場合のようには出来難いので、音声方面の教育がかなり進みつつあるに反して、意義あるいは意味ないし語感という方面の調査を綿密に試みる人は極まれだといって差支えなかろう。少なくとも音声方面の細かい注意ほど意味の方の細かい注意は困難至極ではあるに違いないが、甚だ行きわたっていないのは事実である。これらの欠陥を補うためには、語史学あるいは意義学をもっと進めて行く必要が、日本の国語学界にはあると信ずるのである。
……。