

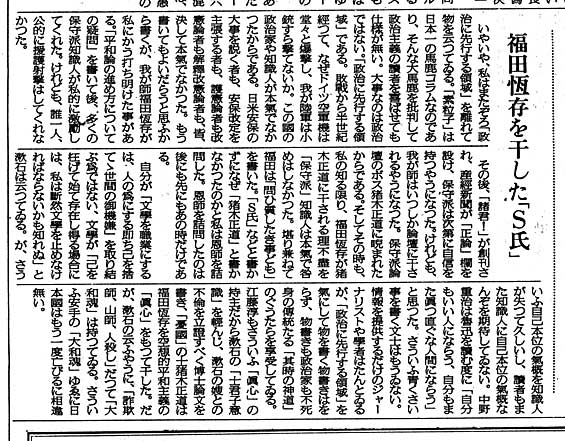
文學作品から讀みとつて良い事は、文學作品に書かれてゐる事だけである。江藤淳は、やつてはいけない推測に基いた「勝手讀み」に據つて漱石論を書いた。本書の著者・松原氏はさう云ふ「勝手讀み」を否定し、本當の文學の讀み方とはいかなるものかを實踐して見せる。論爭で敵なしだつた批評家による、本格的な作家論である。
昨今の漱石論には、漱石が何を書いたのか――漱石の「眞意」を探る形式をとりつつ、實は論者の心理を投影しただけで、漱石自身を全く描いてゐない漱石論が、極めて多い。しかし、さう云ふ「漱石を出しにして自分を語る」式の評論が、本當の評論だとはとても言へない。文學作品を論ずるならば、確固たる文學的な基準を設定し、それに基いて客觀的に判斷する事が必要である。
本書で著者は、漱石の或作品が、いかなる點で優れてをり、いかなる點で誤つてゐるかを、詳細に檢討し、論じてゐる。松原氏の『夏目漱石』は、日本で數少ない、純粹な文學評論である。
漱石の道徳的苦鬪の激しさを思ひやらぬ知的怠惰を痛烈に批判。江藤淳の漱石論がこれほど的確に批判された事は無い。西洋學問も封建道徳も信じ切れず、自己本位に徹して發狂寸前となり、なほも道義の文士たらんとする天才の偉大と悲慘を描く。類例のない漱石論
漱石にとつて自己は掛替へのないものであり、自己本位を貫いて生きるのでなければ、生きてゐる事はおよそ無意味であつた。けれども、自己本位に徹しようとして漱石は他者に愛される事を希求せずにゐられなくなる。その二つの慾求が齎す葛藤は我が近代文學至上類例の無いものだが、それこそが漱石の偉大であり悲慘なのである。「虞美人草」から「思ひ出す事など」まで、漱石の愛への慾求とその挫折とを丹念に描く待望の中卷、漸うここに上梓。
未刊。
江藤淳は、自分の思附きに基いて漱石の小説を解釋して見せてゐる。「嫂に漱石が懸想してゐた」と云ふ假定から、二人の關係について想像を逞しうし、漱石の作中から自分の想像した「關係」の痕跡を讀取らうとしてゐる。しかし、そのやうな江藤の方法は無意味である許りでなく邪道である。
大岡昇平が、「金太郎飴」の喩へを用ゐて、江藤の漱石論を批判した事がある。金太郎飴を切ると切り口から必ず金太郎の顏が出てくる。江藤が漱石の小説を切ると切り口からは必ず「嫂」が出てくる。金太郎飴は、切ると金太郎の顏が出て來るやうに作られてゐる。江藤の漱石論も、漱石の小説を切ると「嫂の顏」が出てくるやうに作られてゐる。
作者の生涯と、對象となる作品は、事實として存在する。そこから讀取つて良い事もあるのだし、解釋して良い事もある。だが、何でも讀取つて良い訣ではないし、解釋して良い訣ではない。根據として事實を擧げれば、解釋が事實になる訣ではない。
既に意見が出盡したシェイクスピア論の世界では「敢て誤讀する試み」が歐米でも廣まつてゐる、と大井邦雄氏は大學の講義で述べた。下手な鐵砲でも數を撃てば當る、と云ふ事は、慥かに言へるだらう。しかし、シェイクスピア論では現在までにオーソドックスな解釋が成立してゐる。
大學生相手にアヴァンギャルドな評論の存在を前提とした講義をするのは何うかと思はれるがそれはともかく、江藤の方法もやはりこの種の「試み」に屬すると言ふ事が出來るだらう。しかし、ここで疑問を呈したいのだが、漱石論にオーソドックスなものは既に存在すると言へるだらうか。と言ふよりは――そもそも、日本の文學論に、オーソドックスな方法があつたと言へるだらうか。
「過去の「漱石論」と呼ばれるものには見るべきものが皆無であつた」とするのは、慥かに妥當な評價とは言へない。その一方で、「感想文や、論者の個人的體驗と結び附けた印象記の域から脱した文學論が多數あつた」とする事も、やはり行き過ぎた考へ方だと言へよう。
漱石の思想を、日本における文藝の傳統の中で判斷し、全體の中に位置附ける、と云ふ試みは、例へば唐木順三に片鱗は見られる。が、殊にイデオロギーに基いた斷罪が評論であると屡々誤解される日本では、傳統の定義そのものが論者によつては怪しく、位置づけそのものに斷罪的な意義が籠められ勝ちである。
文學史の「權威」である吉田精一ですらも、漱石を論じて、「年表の中に位置づける」以上の事をなし得たと言へるか何うかは疑はしい。
西歐の文物が流入し、既存の日本的なものと衝突を起して始めてゐた明治と云ふ時代、日本人は傳統と近代との間で適應異常を起し、挌鬪を繰返した。それは文學者も例外ではない。そして、明治以來、現代まで、「西歐と日本との相克」は繼續してゐる。日本に於ては、西歐的なものと日本的なものとの對立と、壓倒的な西歐の勢力に據る日本の文化の壓倒が、現象として生じてゐるし、それは現在までに完了してゐない。
この状況に對して、イデオロギー的な視點からする政治的な斷罪――革新勢力に據る拜外主義、保守勢力に據る排外主義――が、政治とは異る筈の文學の世界でも「代替戰爭」のやうな形で行はれてゐる。さうでなければ、文化とか傳統とかと關係は無いが、單なる暴露趣味に基いた江藤式のスキャンダラスな「作家論」が出現する。日本には、政治的興味を離れた文化論、スキャンダル的關心に據らない作家論が、なかなか成立しない。
西歐の文學論も、時として論者の主義に據り偏つた内容となる事はある。しかし、その一方で、文學を論ずる方法論として、オーソドックスなものが成立してゐる。批評の方法が、既に西歐には「ある」と言ふ事が出來る。キリスト教とギリシャ哲學の傳統を前提とした議論が可能となつてゐる歐米の評論と、傳統の破壞と護持との相克が續いてゐる事を考へねばならない日本の評論とでは、當然、論じ方にも違ひは出て來る。だが、しかしその一方で、事實に接近する爲の一般的で客觀的な方法論は、文學の世界にも「ある」と考へる必要がある。
文藝は、專ら主情的なものとされる日本では信用され難い話となつてゐるが、論理の表明である言語によつて語られるものである以上、客觀的に判斷出來る客觀性を持つてゐる。日本語を、非論理的なものと看做したり、否、論理性なものであると主張したりする人がゐるが、「木」にしても「tree」にしても或種の植物を指示し、「1たす1は2」でも何でも或種の論理を指示する事は疑ひやうが無い。目的が感情の表現である事と、表現が客觀的である事とは、話が別である。
日本の文藝批評では從來、「目的としての感情の表現」と云ふ文藝の側面が極端に重視されて來た。さう云ふ前提で、例へば「漱石の目的」を主情的なものとして――ここで指摘したいのだが、「主情的なものである筈の文藝作品」を論者が主情的に讀取る、と云ふ方法を、「方法論」としてしまふ傾向が、日本にある。その一つの例が江藤の漱石論であると言ふ事が出來る。だが、茲には幾つかの飛躍が存在すると言はねばならない。言語の論理性と、言語に據る表現の論理性を、さう云ふ「方法論」は否定してゐる事になる。だが、それで「評論」と名乘る事は許されるか。
「評論」自體、criticismの譯語であり、西歐由來のものである。それを認めるのならば、西歐の客觀的な方法を採用する事は、論者に常に要請される事である。そこで「主情的な方法論」を採用しようと言ふのならば、逆にその妥當性を積極的に主張してゐなければならない。私の知る限り、積極的な主張に基いた「主情的な方法論」による作家論は、日本では皆無である。どちらかと言ふと「仕方がない」と云ふ考へ方に據る感想文や印象記が多いやうに、私には思はれる。
江藤の場合も、積極的と言ふよりは、解釋を事實と言換へる強引なやり口と言ひ、やけのやんぱちの開き直りか、或は、波江のやうな變な思ひ込みによる極端な自己の正義の主張に陷つたかのどちらかであると思はれ、一種、病的なものを感じさせられる。それもまた、日本人の西歐に對する適應異常の現象の一環であると指摘する事は可能である。
それに對して、松原氏は、文明論・文化論の立場をも理解しつゝ、公正な判斷を下さうとしてゐると言へる。例によつて自衞隊や國防の問題にも觸れる爲、文藝批評としては異色であるとされ、それは野嵜もその通りだとしか言ひやうが無い。しかし、漱石の文章を讀み取る仕方――と言ふよりも見方と云ふ點で、過去の漱石論の類に比べて、格段に異色の度合は強いと言ふ事が出來ると思ふ。寧ろ、「異色」であるのが過去の漱石論の方である、とすら言ひたい。
松原氏の漱石論については、完結してをらず、詳細に論じる準備も無いから、取敢ず野嵜を信用して讀者の方々には直かに當つていただきたいと御願ひするしかない。
一往、何も書かないのも何うかと思はれるので、少しだけ論じておく。
松原氏の漱石論では、「漱石の偉大と悲慘」の「悲慘」の側面――と言ふよりも、漱石の誤を指摘した部分が非常に目立つ。
「人の上の神」のやうには完璧でない「人の上の人」には缺點があり得る。だから、「人の上の人」を戴くやり方では屡々問題が起きる。漱石は人であり、「人の上の人」である。松原先生の漱石論で論じられる漱石にも、人としての限界が表はれてゐる。
既存の「漱石論」では、漱石を單に人として論ずるか、「人の上の人」として論ずる爲に漱石を神格化してしまつてゐるか、の、何れかの誤を抱へ込んでゐるものが幾つもある。松原氏の漱石論では、どちらにも偏らないやうな批評としての批評がなされてゐる――ゐる筈だが、下卷が未刊である以上、總體としての判斷は依然、控へる必要がある。
下卷が未刊である現状の二册でも、過去の「漱石論」の問題點を讀者に認識せしめるには有效性を持つとは思はれる。が、既刊に收録された文章は、數年前の文章である。その後の見解や、綜合的な結論までも含むであらう下卷の刊行が待たれる。


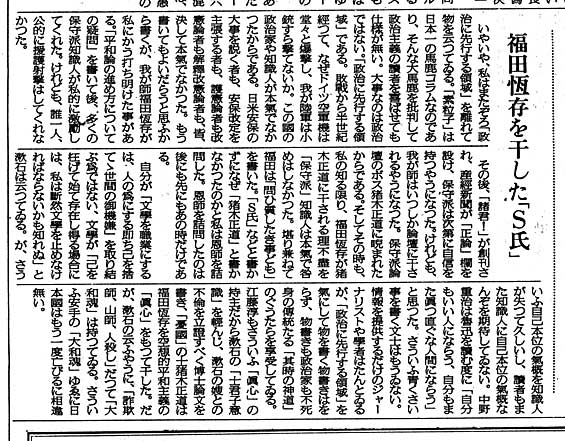
「月曜評論」(平成7年11月25日)掲載