

| 石塚龍麿・橋本新吉 日本上代の音韻(母音 ア・イ・ヰ・ウ・エ・ヱ・オ・ヲ 8音) 音韻 記紀万葉には973の万葉仮名が用いられている。 奈良時代の音節及び万葉仮名一覧 白川 静 [字訓] 岩波新書「漢字-生い立ちとその背景」 中公新書「漢字百話」 |
|||||||
| かみ[神] 乙類 |
かみ[上・頭] 甲類 |
かみ[帥・守] 甲類 |
かみ[髪] 甲類 |
やしろ[社] 乙類 |
もり[森・社・杜] | ||
| ゆふ[結] | いはふ[斎・忌・ 祝] |
いのる[祈・祷] | のる[宣・告] | のろふ[呪・ 詛] |
まつる[祭・祀] | ||
| まつろふ[伏・服] | いつ[厳] | いつく[斎] | はふり[祝] | はぶり[葬] | かむなぎ[巫] | ||
| うらなふ[占・卜] | ちかふ[盟・誓] | くかたち[盟神 探湯・誓湯・貞] |
うた[歌・謡] | さき[幸・福] | まらひと[客・賓] | ||
| にへ[贄] | にひ[新] | には[庭・場] | みる[見・視] | ものいみ[忌・ 斎] |
ある[生] みあれ神事 (下賀茂神社) |
||
| あり[有・在・存] | あらはす[顕・ 現] |
あらたし[新] | もの[物・者・ 鬼] |
もののふ[物 部・武士] |
こと[言・辞・詞] | ||
| こと[事] | こと[殊・異・別] | ことだま[言霊] | ことわざ[諺] | ことほく[寿・賀] | かがひ[嬥歌] | ||
| 白川 静 「字統」 | ||
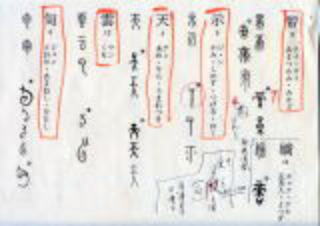 |
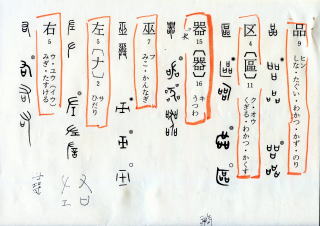 |
|
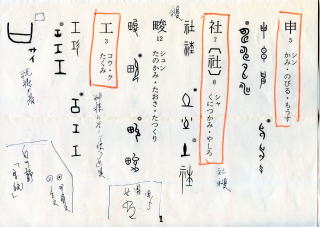 |
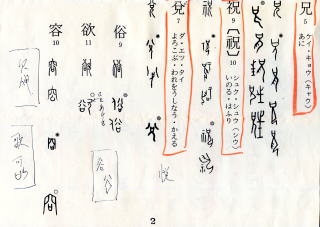 |
|
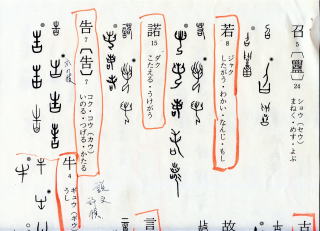 |
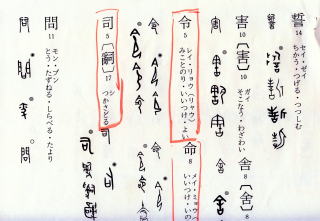 |
|
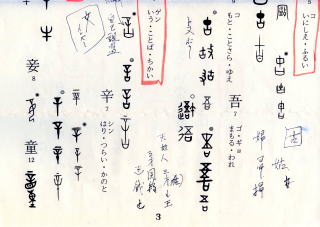 |
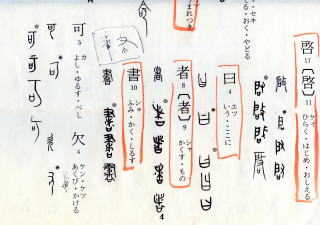 |
|
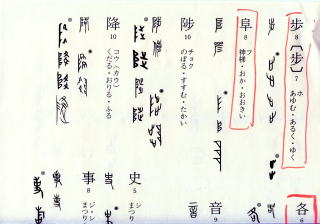 |
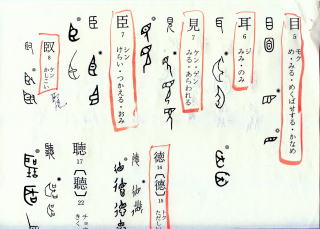 |
|
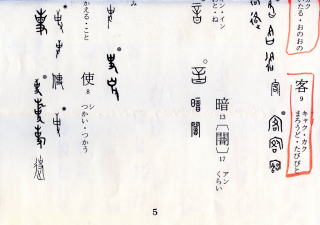 |
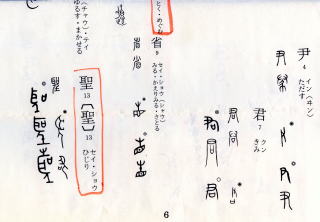 |
|
| 万葉歌人 大伴 旅人 大伴 家持 柿本人麻呂 「万葉集」 23首 |
382 筑波岳に登りて、丹比眞人国人の作る歌一首 并に短歌 383 反歌 |
| 1753 検税使大伴卿の、筑波山に登りし時の歌一首 短歌を并せたり 1754 反歌 |
|
| 1757 筑波山に登る歌一首 短歌を并せたり 1758 反歌 |
|
| 1759 筑波嶺に登りて 1760 反歌 右の件の歌は、高橋連蟲麿の歌集の中に出づ。 |
|
| 1838 右一首は筑波山にして作れり。 | |
| 3350、3351 右の二首は、常陸国の歌。 | |
| 3388~3397 右の十首は、常陸国の歌。 | |
| 4367 右の一首は、茨城郡の占部小龍のなり。 | |
| 4369、4370 右の2首は、那賀郡の |
|
| 4371 右の一首は、 |
|
| 1497 右の一首は、高橋連蟲麿の歌の中に出づ。 | |
| 1712 筑波山に登りて月を詠む一首 |
| 常陸国風土記 香島郡 | |
| 筑波郡 | みあれ神事 |
| 信太郡 | 御座替祭・御幸ヶ原 |
| 仏教文化 | 筑波山神社 | 筑波山 |
| 徳一大師 | ||
| 小田山 | 中禅寺 | 清龍寺 |
| 椎尾薬王寺 |