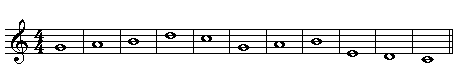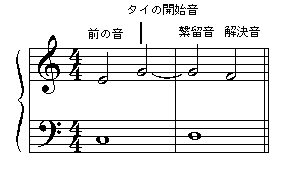
移勢対位法は弱拍から強拍にかけてタイで音を結び、シンコペーションのリズムを用いて声部を操作する練習である。便宜上、各音を次のように呼ぶこととする。
・タイで結ばれる2音のうちの前者(弱拍の音)を「タイの開始音」
・タイで結ばれる2音のうちの後者を「繋留音」(つながれた音)と呼び、
・繋留音が不協和音程(応用音程=2,4,7度)の場合、それに続く音(弱拍の音)を「解決音」と呼ぶこととする。
繋留音から解決音へは順次進行で進行する。
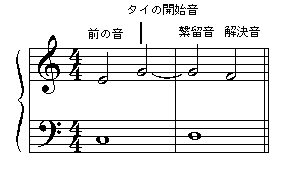
開始音(弱拍の音)が基本音程(1、3、5、6、8度)の場合
1.繋留音は出来るだけ応用音程(2、4、7度)であることが望ましい。繋留音から
解決音への進行は、既習の2分割対位法の「弱拍の音程が応用音程の場合」に準ずる。
すなわち、2度は3度へ、4度は3度又は5度へ、7度は6度へと進行する。
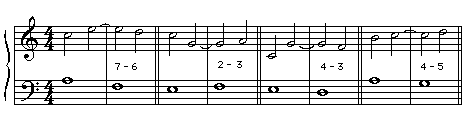
繋留音から解決音への進行が2度から1度、7度から8度へと進行することは次の条件の場合に許される。
・対旋律が開始音から解決音へと同一方向に順次進行し、
・対旋律と定旋律とが反進行している場合。
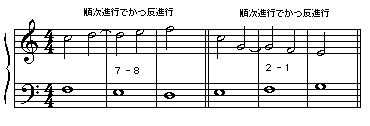
2.繋留音も基本音程(1、3、5、6、8度)であることは可能である。
しかし、前項のような繋留音が応用音程である場合に比べると、対位法的な緊張感が乏しいので、多用することは望ましくない。
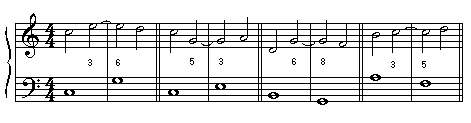
3.連続1度・5度・8度がタイによって時間的にずれただけの形は。連続進行と同等と見なし、禁止する。
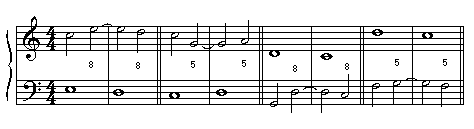
4.解決音(基本音程)がそのまま次の開始音となって、シンコペーションが連続する形をつくることができる。
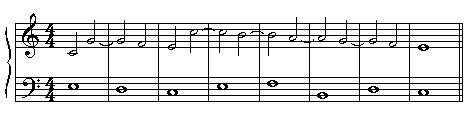
練習課題−7−
次の定旋律に対し、シンコペーションを含む2分割による対旋律をつけなさい。
この練習ではタイの開始音は必ず基本音程とすること。
<EX021>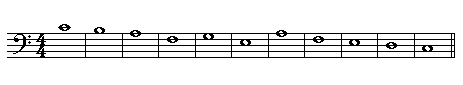
<EX022>