�悸���ȏЉ�������B����1943�i���a18�j�N�̐��܂�ŁA��w�ɐi�w���ē����ɏo��܂ł͐V�����ň�����u���V�����l�v�ł���B���̌�A1973 �N�A��������w�ɐE���̂ŁA�������ɗ��Ă��̂܂Z�ݒ����u���������l�v�ƂȂ����B���̍Ȃ�1942�i���a17�j�N�̐��܂�ŁA������͎̂��ꌧ�ł���B��l�͋��s
��w�ɋΖ����Ă����Ƃ��ɒm�荇���A1970 �N�Ɍ��������B
���̃y�[�W�̑�ꕔ�́u�z��ƎF���v�́u��r�n�敶���v���e�[�}�ł���B
���͂���܂ŁA�V���A�����A���s�A�������ƁA���j�A�����A�C��E���y���قȂ�y�n�������Ă����̂ŁA���ꂼ��̓y�n�̕������r���Č��邱�Ƃ��K�������Ă���B
���{���u���������v�Ɓu���������v�ɕ����錩�������邪�A�z��o�g�̎��Ƌߍ]�o�g�̍ȂƂ̌����́A�܂��Ɂu�ٕ����v�̏o��ł������B���̂��Ƃ����̂悤��
�e�[�}���l���邫�������ɂȂ��Ă���Ǝv���B���̃y�[�W�̓��e�͈ȉ��̒ʂ�ł���B
��ꕔ��1. �ł́A�z��ƎF���̋C��E���y���r���ď������B����2009 �N�ɑ�w���N�ސE�������A���̌�A���R�Ȏ��Ԃ��������̂ŁA�u���������̗��j�U���v�i�������������w�Z���j����ҁA�R��o�Łj�����߁A���̖{�ɓ�����ċ����������܂܂Ɏ����������̎j�Ղ�K�˕����Ă����B�����āA15 ���I�̒�����ɉz��܂ŗ��������F���l���������Ƃ�m�����B���ꂪ���������ŁA�F���Ɖz��̗��j�����̊W���𒆐S�ɒ��ׂ�悤�ɂȂ������A��ꕔ��2. �́A���̉ߒ��œ����m�����܂Ƃ߂����̂ł���B
�����̒����A�������ɂ���Ă��āu�F�������L�v�����A�{�x���l�Y�i1865 �|1912 �N�j�Ƃ����V�����l���������Ƃ�m�����̂́A�����������ɂĂ����̍��ŁA�n�����u����{�V���v�ɍڂ����L���ɂ���Ăł������B�u�F�������L�v�́A���j�w�A�n��j�A�����w�̌����҂ɂ͗ǂ��m��ꂽ�����ł���A2016 �N�Ɏ�������
�́u�����ېV150 ���N�L�O���Ɓv�Ƃ��ďo�ł��ꂽ�w�����ېV�Ƌ��y�̐l�X�x�ɂ́A���̓��e�̈ꕔ���Љ��Ă���B���̖{�x���l�Y�����̕�Z�A�V�������������Z�̑��y�ł���A�������������Z�̑O�g�̒����w�Z�A�����q�풆�w�Z�A�������w�Z�i�����j�̋��t�ł��������Ƃ�m�����̂�2000 �N�̂��Ƃł������B����ɁA�ނ��������ɂ���Ă����u�������v��m�����̂́A2020 �N�̂��Ƃł������B���l�Y���������Z�̑��Z�̂̎��̌���҂ł��邱�ƂɋC�t�����̂́A����ɂ��̌�ł������B�������Z�̑n��150 ���N�ɂ�����2022 �N���O�ɂ��̂悤�Ȃ��Ƃ����炩�ɂȂ������ƂɁA���͂Ȃɂ���������߂������̂��������̂ł���B�����ŁA�{�x���l�Y�ɂ��ĉ������珑���c���Ă��������Ǝv���A�������̂���ꕔ�̂R�D�̕��͂ł���B���������疾�����ɂ����ĎF���ɂ���ė����z��l�͑��ɂ��������A��ꕔ�̂S�D�́A���̈�l�ł���A�F���ˁE�J�����p�ꋳ���E���ޑ��i���O�����j�ɂ��ď��������̂ł���B��ꕔ�̂T�D�ł́A�u�����C���v��
�u���w�����v�𒆐S�ɁA�F���Ɖz��̔�r�u�n�敶���v�ɂ��ďq�ׂ��B��ꕔ�̂U.�́A�u�F���˂́A�Ȃ������ېV�̐��i�͂��蓾�����H�v�Ƃ����u�F���̕s�v�c�v�ɂ��āA�z�ォ�����ė��āA�ً��̒n��40�N�ȏ�Z�݁A�u�������l�v�ƂȂ������E�l�i�}�[�W�i���E�}���j�ł��邱�Ƃ����o���Ă��鎄�Ȃ�̌������܂Ƃ߂����̂ł���B
�{�x���l�Y�́A���������E�{�V��i���E���s�j�̉m�i�i��������j�q�퍂�����w�Z�̋����E�Z���Ƃ��ĂQ�N���قǎ������ɑ؍݂����B�u�F�������L�v�ɂ́A�F���l�m�̉Ȋw�E���w�ɑ���ԓx�ɂ��ď����Ă��镔��������A���w�̋���E�����҂ł��鎄�́A���̋L�q�ɓ��ɋ������������B�]�ˊ��̓��{�ɂ́A�u�a�Z�v�Ƃ����A��
�E�ɗނ��݂Ȃ��Ɠ��̐��w���������������A�����ېV�ɂ����{�̋ߑ㉻�������i�߂�ꂽ���Ƃɂ��A�u���m���w�v�ɒu��������Ă������ƂɂȂ�B���
�u���m���w�Ƙa�Z�v���e�[�}�ɂ��Ă���B�����A���̕����́u�z��l�E�{�x���l�Y�́w�F�������L�x����ю����g�́u�Ƒ��j�v��ʂ��ē��{�̋ߑ㉻���l����v���e�[�}�ɂ��ď�������ł������̂����A����͎��̋@��ɏ��邱�Ƃɂ���B�@�@�@
�@
�@�@�@�@ �@�@�@�@ �@
�@
�@�@�@�@
�͂��߂ɁA�z��ƎF���̎��R�A�C��A���y���r���邱�Ƃ���n�߂悤�B������42�N�O��1973�N�i���a48�N�j�t�ɁA���߂Ď������ɂ���ė����Ƃ��̑���ۂ́A
�u�������i�s�j�͍�̑��������Ȃ��v�Ƃ������̂ł������B�ŏ��ɏZ�̂́A�ɕ~�̎��������q���̂����߂��ɂ��������ƌ����������h�ɂł���B�Ȃƈ�ɂȂ��������
�������s�Ɏc���Ă̒P�g���C�ł������B��ɂȂ�Ɩ��a�����̋u�̎Ζʂɑ�R�̖����肪����A�L���L���P���̂��������B�V���ɂ������A5����18�܂ŏZ�����́A
4�L�����[�g�������ꂽ�Ƃ���܂ŁA500���[�g���`700���[�g�����̎R�X�i���R�u�ˁj�������Ă���Ƃ͂����A�����̂͋ɂ߂ĕ��Ȓn�`�̏�ɂ���A�ω��ɖR���������̂ŁA
�������̂悤�ȍ�̂��钬�͍D�܂����v�����B�u�̎Ζʂɔ�������悤�ɒ����L�����Ă��镗�i�ٍ͈���������������Ă��ꂽ�B���Ȃ����āA�������s�͕��n�����Ȃ��A
�l���̑����ƂƂ��ɁA�����̐V���Z��n���V���X��n�̋u�˂ɊJ������Ă��邱�Ƃ�m�����B��1974�N�i���a49�N�j�t�Ɍ����Z����A���N�x��Ŏ�������
����ė����ȂƖ��ƂƂ��ɏZ�ނ��ƂɂȂ�̂����A���������̂悤�ȐV���Z��n�̈�ł������B
�@
�ɕ~�̌������h�ɂ̒��ɂ́A����ނ��̖����m��ʑ��X�������ȉԂ��R���Ă����B���̐F�ʂ̖L�����ɁA�u�������ɓ썑�v�Ǝv�������̂ł���B
���̖u�J�C�R�E�Y�i�C�g���j�v
�i�A�����J�f�B�S�j �i�Ԍ��t�F���E���S�j
�i�Ԍ��t�F���E���S�j �A
�A
�u�[�Q���r���� �i�Ԍ��t�F��M�j
�i�Ԍ��t�F��M�j
 �A
�n�C�r�X�J�X�i�Ԍ��t�F�V�������E�E���j
�A
�n�C�r�X�J�X�i�Ԍ��t�F�V�������E�E���j ���̐F�N�₩�ȓ썑�̉ԁX��m��̂����Ȃ����Ƃł���B�����̉Ԃ̐F�̑N�₩���́A�썑���L�̂��̂ŁA�l�X�̐S����������
�������̂�����B�썑�̖��邳�͂��̕ӂ��痈�Ă���̂��Ǝv���B
���̐F�N�₩�ȓ썑�̉ԁX��m��̂����Ȃ����Ƃł���B�����̉Ԃ̐F�̑N�₩���́A�썑���L�̂��̂ŁA�l�X�̐S����������
�������̂�����B�썑�̖��邳�͂��̕ӂ��痈�Ă���̂��Ǝv���B
�@
�����A���M�ђn���ɂ��鎭�����ł́A�����n�����������l�G�̕ω��������邱�Ƃ͏��Ȃ��B�̂���ƋG�߂����ڂ���
�����悤�Ɋ�������B�܂��A���̋G�߁B�������ɂ����̖����͂���A�܂��A�X�H���Ƃ��Ă���R�A�����Ă���̂ŁA�t�ɂȂ�Ɛl�X�͂��Ԍ����y���ނ��A�������̍��͑�Ƃ����̂��قƂ�ǂȂ��B�����玭�����̍��̋G�߂͍T���߂ɉ߂�������
���܂��B�������̍��́A�C��E���Q���̊W�ő傫������Ƃ��o���Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���H�@���ɍg�t�̋G�߁B�������̒��̊X�H���̓N�X�m�L�A�N���K�l���`�A�C�k�}�L���̏�Ύ����������������邪�A
�X�S�̂��g�t�ɐF�Â��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B�Ƃ���ǂ��뉩�F�ɐF�Â�����ǂ̖͌������邪�A�g�F�ɐF�Â����X���X���Ō������邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��B����ȏ�ԂȂ̂ŁA�{�y�ň�ʓI��
�g�t�̋G�߂͎������ɂ͂Ȃ��ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��悤�Ɏv���B
�����������ɂ���ė���1973�N�����̍����͊������ɂ���A���X�������グ�A�D���������s�X�n�ɍ~�点�Ă����B�ɕ~�̏h�ɂ�����
���グ�Ă���ƁA�����_���������ʂ��炱����Ɍ������ė���ė����B���炭����ƁA�p���p���Ɖ��𗧂ĂĊD���~���ė��ĕӂ��ʔ��Â��Ȃ����B���̂悤�Ȃ��Ƃ������������B
���̍��A�������唚�����閲��ǂ��݂��B�����Ă������Ă��������ǂ��Ă��閲�ł���B���Ȃ����悤�ɂ��Ėڂ��o�܂��̂���ł������B���N����ƁA�������ɂ��̂悤�Ȗ��͂܂�����
���Ȃ��Ȃ����B���������܂ޓ��B�̓Ɠ��̌i�ς́A�����N�A���\���N�A���S���N�ɓn��ΎR���������グ�����̂ł���Ƃ������ƁA�ΎR�̋߂��ɏZ��Ő�����a���A������z���Ă���
�l�X�̗��j�Ɏv������悤�ɂȂ����̂͂��ŋ߂̂��Ƃł���B
�@
�x�O�ɏo���������̌i�ς́A�V���Ǝ������ł͑S���Ⴄ�̂����A�������ɂ͈ꂩ�������������܂������A�ӂ邳�ƐV�����v���N�������Ă����Ƃ��낪����B����͑�������̎�������
���R�������ɐi�̕t�여��̕��i�ł���B�Ȃ����낤���ƍl���Ă݂�ƁA����͐�Ɛ��c�Ɖ����Ɍ�����R���݂̂����ł��邱�ƂɋC�t�����B���ׂĂ݂�Ɗ̕t��͈ꋉ�͐�Ȃ̂ł���B
���������̈ꋉ�͐�͑��ɂ́A�����̖k�[�Ɍ����A���V�i�C�ɒ�������삵���Ȃ��B�����͎��������̖k���𗬂�Ă���̂ŁA�암�ɏZ�ގ�������@��͂قƂ�ǂȂ��̂ł���B
�傫�Ȑ삪���݂��邽�߂ɂ́A�����Ɛ��悪�K�v�ł���B���������ɑ傫�Ȑ삪���Ȃ��̂́A�����R�ƍL�����n�����Ȃ��������Ǝv���B���Ɍ��쐼���̎F�������͂����ł���B���j���Ђ�
�����ƁA�Ñ�A��a����̐��͂����B�ɓ��荞��ŗ����̂́A��������̊̕t�쉺���悩��ł����āA���̕ӂ�ɂ͌Õ�����������������Ă���B�����A�V�����ɂ͐M�Z��A������
�i�㗬�͑�����j�A�r��A��A�P��̌܂̈ꋉ�͐삪����B����͐V��������k�ɒ����A�w��ɍ��s�ȎR�����T���Ă��邱�Ƃɂ��B�V�����Ă̐��Y���Ƃ��Ĕ��W�����̂́A���̂悤��
���R�����ɋN�����Ă���̂ł���B���Ȃ݂ɁA����25�N�̂��āi����j�̓s���{���ʎ��n�ʂ́A664,300�g���ŐV�������S��1�ʁA����������114,900�g���ŁA���ꌧ�A���A�啪���ɂ���
�S��28�ʂł���B ���Ȃ݂ɁA���ׂ̋{�茧�́A93,600�g���őS��31�ʂł���B�l���͕���25�N�ŁA�V������233���l�A����������168���l�ł���B
�Ō�ɁA�Q�l�܂łɐV�����Ǝ��������̌��ʁA�~���ʁA�ō��A�Œ�A���ϋC���i���v���ԁF1981�N�`2010�N�j�������\���f�ڂ��Ă����B�V������11���A
12���A1���ɍ~���ʂ������͍̂~��A�܂��͐������̉J�ɂ��B����������6���A7���ɍ~���ʂ������͔̂~�J�O���̒�ƁA�삩�玼�C���܂�C����ʂɓ��荞��ŗ��邱�Ƃɂ����̂Ǝv����B�V�����̔N���ϋC����13.9���A�N�~���ʂ�1821.0mm�A
���������̔N���ϋC����18.6���A�N�~���ʂ�2265.7mm �ł���B
���}�@�V�����A�E�}�@���������@�i�����@�C���@�P�ʁ@���A�@�E���@�J�ʁ@�P�ʁ@mm�j
|
|
|
 |
 |
�Ńg�b�v��
�@
�������ɏZ�ݒ�����42�N�ɂȂ邪�A�c��������[���V���ʼn߂������������������Ă���̂́A�������ƊC�Ƃ�
�q����ɂ��Ăł���B�V���������{�C�ɐڂ��Ă��邵�A����5�̏t�܂ŏZ�V���s�́A�M�Z��̉͌��ɊJ�����`���ł��邪�A�C�Ƃ̌q�������Ɉӎ����邱�Ƃ�
�Ȃ������B���w�Z���ォ�獂�Z������߂����������s�́A�C�����R���ӎ�������y�n���ł������B
�����������ƊC�Ƃ̌q����������ӎ�����̂͂Ȃ����낤���H�@���l���Ă݂�ɁA���R�̈�́A�������͖k�̒n���i�k�F�n���j�������A�F�������A�������
�Ƃ�����̔�������Ȃ��Ă��邹���ł͂Ȃ����Ǝv���B�@�����͎O�����C�Ɉ͂܂�Ă��邱�Ƃ������āA�����ɏZ�ސl�X�ɊC��g�߂Ȃ��̂Ɋ��������Ă����B
�����Z��ł��鎭�����s�̃V���X��n����́A�����������ԋэ]�p�i���C�j�������邵�A�Ԃ�����30���قǂŁA���V�i�C�ɖʂ�������l�ɓ��B�ł���B�t�F���[�őΊ݂�
��������ɓn��ƁA�����m�݂܂ł͎Ԃ�1����30���قǂł���B
������̗��R�́A�������ɂ͑�R�̓������邹���ł͂Ȃ����낤���H�@�����Œn�}�����o���Ē��߂Ă݂�B
�������{�y�̓쐼�����ɑ召���܂��܂ȓ����ʂ�`���ĉ���{���܂ʼn��тĂ��邱�Ƃ��킩��B�������A���i�Ǖ����A��q���A���v���A�g�J���A�����哇�A���V���A
���i�Ǖ����A�^�_�����̓��X�ł���B����{���̐�́A�v�ē��A�{�Ó��A�Ί_���A�^�ߍ����Ƒ����A���{�Ő��[�̓��A�^�ߍ����Ƒ�p�Ƃ͖ڂƕ@�̐�ł���B��������
�C��̓����������{�y����쐼�����Ɍ������đ�p�܂ŐL�тĂ���悤�Ɍ�����B�����̑召���܂��܂ȓ��X���A�u���ׁi�Ƃ�����j�v�Ƃ����炵���B
�u���ׁi�Ƃ�����j�v�Ƃ������t�͎������ɗ��ď��߂Ēm�������t�ł������B
�����ŁA���炽�߂Đ��E�n�}�����o���Ē��߂Č���B����Ǝ����v���Ă���ȏ�ɁA��p�ƃt�B���b�s���Ƃ͂����߂��ł��邱�Ƃ�
�킩��B���̐�́A�C���h�l�V�A�̓��X�ƃ}���[�����ł���B�����ň͂܂ꂽ�C����V�i�C�ŁA��V�i�C�̓}���b�J�C�����o�ăC���h�m�ɒʂ��Ă���B
�ڂ��������̐�������іk���̊C�ɓ]���Ă݂�B����ƁA�����ɂ͍���������A����������B�����̂����ׂ͓V���ŁA�V���̓��X��
�k�シ��ƁA�ܓ��A���˓��A���A�Δn�A�ϏB���i�؍��j������B�����̓��X�́A����������k����B�A���N�����ɒʂ��������̊C�̓��Ƃ�����̂ł͂Ȃ����낤���H
���j�I�ɂ݂�ƁA�����̊C�̓��͐V���������̓`�d�o�H�ł������B�������ł́A�F�������u�T�c�}�C���v�Ƃ͌ĂȂ��B
�u�����i�J���C���j�v�������́u�������v�Ƃ��������ł���B�u�T�c�}�C���v�Ƃ����ď̂́A����A�������ȊO�̖{�y�̐l�X���g���Ă���ď̂Ȃ̂��B���̎������������ɗ���
���߂Ēm�������Ƃł������B���ׂĂ݂�ƁA�u�T�c�}�C���v�̌��Y�n�͓�A�����J�嗤�A�y���[�M�ђn���Ƃ����B�X�y�C���l�����̓|���g�K���l�ɂ�蓌��A�W�A��
�����炳��A���\�����i�t�B���s���j���璆�����o��1597�N�ɋ{�Ó��֓`���A17���I�̏��ߍ��ɗ����A�������A��B�A���̌�A���䓇�A�{�B�ւƓ`������Ƃ����B�u�T�c�}�C���v�́A
�������̓쐼�A�����A�k���ɉ��т�C�̓��ɂ��A���{�ɓ`�d�����T�^�I�ȃ��m�Ɏv����B
1543�N�A��q���ɕY�����������D�ɏ���Ă����|���g�K���l�ɂ���ēS�C���`�����A�퍑����̓��{�ɑ���ȉe����^�������Ƃ͒N�ł�
�m���Ă��邱�Ƃł��낤�B���V�i�C���q�s���Ă����D�͓x�X��j���A�������̓쐼�ɉ��т铇�X�ɕY�������̂ł���B�Ñ�ɂ����Ă��A�����̉�������{�ɓ`���������̑m�A�Ӑ^�́A
�x�X�̓n�C�̎��s�̌�A752�N�A�F���V�Â̏H�ڂɏ㗤���Ă���B�����A�V�Â͔����A�Ái�ɐ��j�ƕ��ԁA���{�O�Â̈�ł������B
���{�ɃL���X�g����`�����C�G�Y�X��̐鋳�t�A�t�����V�X�R�E�U�r�G���́A�}���b�J�ŏo�������F���̐l�A���W���E�A�|���W���[�A
�܂��͓����̉��C����A���W���E�i�A���W���[�Ƃ��j�A�m���ɃA���W�F���i�V�g�̈Ӂj�Ƃ�������| �̎�����ŁA1549�N�Ɏ������p���̌��E�������s�_���V�B�ɏ㗤���Ă���B
�����āA�ɏW�@��i��F��A���E�����������u�s�ɏW�@�����c�j�Ŏ��喼�̓��ËM�v�ɉy�����Ă���B���W���E�̑f���͒肩�ł͂Ȃ����A�U�r�G���������c�������̂ɂ��A
�F���������͑���̐l�ŁA����Đl���E�߁A�F�������œ�[�̎R��ɗ��Ă����|���g�K���D�ɏ���āA�}���b�J�ɍs���A�����ŃU�r�G���ɏo�������Ƃ����B����ɂ́A
���W���E�͖f�Ղɏ]������l�ł������Ƃ������B���̌�A�U�r�G���ɓ�����ăC���h�̃S�A�ɓn��A���̒n�œ��{�l�Ƃ��ď��߂Đ�������Ƃ����B
�Ō�ɁA�C�̓��ɂ�钩�N����̕����̓`�d�ɂ��ċL���Ă����B�������ɂ͎F���ĂƂ����Ă���������B
���F���ƍ��F���Ƃ���Ȃ��ŁA
���F���� ���n�ɍׂ₩�ȕ��l���g��������g���ĕ`�����₩�ȏĂ����ł���B���̏Ă����́A1598�N�A�L�b�G�g�̓�x�ڂ̒��N�o���i�c���̖��j�̋A���̍ۂɁA�F���̐퍑�喼�A
���Ë`�O�ɂ���ĘA�s���ꂽ���N�l���H�ɂ���Ă����炳�ꂽ���̂ł���Ƃ����B���̎q���̒��Ƃ́A���u�s���R�i�݂�܁j�ɍH�[���\���A���̋Z�����݂ɓ`���Ă���B
���n�ɍׂ₩�ȕ��l���g��������g���ĕ`�����₩�ȏĂ����ł���B���̏Ă����́A1598�N�A�L�b�G�g�̓�x�ڂ̒��N�o���i�c���̖��j�̋A���̍ۂɁA�F���̐퍑�喼�A
���Ë`�O�ɂ���ĘA�s���ꂽ���N�l���H�ɂ���Ă����炳�ꂽ���̂ł���Ƃ����B���̎q���̒��Ƃ́A���u�s���R�i�݂�܁j�ɍH�[���\���A���̋Z�����݂ɓ`���Ă���B
�×��A�������͊C�̓���ʂ��āA�����A����A�W�A�A���m�A���N���̊O���Ƃ̌𗬂��[���y�n���ł������ƌ������Ƃ��ł���ł��낤�B
���������{���ꂽ�]�ˎ���ɂ����Ă��A�F���˂͗����������x�z���ɂ����A������������Ē����i�����j�A����A�W�A�ƌ��Ղ��s���Ă����̂ł���B
�Ńg�b�v��
�@�@�@
�@
���݂͋x�~��Ԃɂ���悤�����A�u���������R��w�v�Ƃ������̂��L��A���N�O�A�����Łu�������l�͂ǂ����痈���̂��H�v�Ƃ����A���u����
�������̂Œ����ɍs�����B�@�����������i�����������ۑ�w�j�����j�w�̗��ꂩ��A8���I�̏��߁A���������ł����a����ɑ��Ĕ������N�������������̐�Z���A���l�i�͂�Ɓj�ɂ���
���ꂽ�B�܂��A�x�g�i���A���I�X�ɓx�X�������n�������s���Ă�������a�����i�t���يw�|���j���A�����w�̗��ꂩ��A�����̒n��ŕ�炷�l�X�Ɠ쐼�����i�����������q���A���v���A
�����哇�A����{�����o�đ�p�܂ő����召�l�X�ȓ��X�̂��ƁA�O�e�A�u�C�̓��v���Q�Ɓj�ŕ�炷�l�X�Ƃ̏K���A�����̗ގ����ɂ��Č��ꂽ�B��쎁�́A�����g�̌����Ɋ�Â��A�������l��
���̊C�̓���ʂ��ē삩�痈���ƐM���ċ^��Ȃ��Ƃ������Ƃł������B
�Ƃ���ŁA�u�������l�v�Ƃ������t�͓���A���܂莨�ɂ��邱�Ƃ͂Ȃ����A�����Ӗ�����̂ł��낤���H�@�펯�I�ɂ́A��c��X�������ɏZ�݂���
�����l�X�̖���Ƃ������Ƃł��낤�B�m���ɁA���ꂼ��́u�n��v�ɂ́A���ꂼ��̕��y�̒��Œ������Ԃ������Č`����Ă����Ɠ��̕���������B���ł������Ȃ̂́A�H�ו��⌾�t������K����
���낤�B�C���Ƃ������̂�����Ɋ܂܂�邩���m��Ȃ��B
�������A�l�ފw�I�A��`�w�I�ɂ݂��Ƃ��A�u�������l�v�ɓ��L�Ȍ`������肷�邱�Ƃ͉\�Ȃ̂ł��낤���H�@�ߔN�ADNA�Q�m����͂̋Z�p�͔���
�i�����Ă���悤�ł��邪�A���̂悤�Ȍ����ɂ��Ă͕��������Ƃ��Ȃ��B�@���������A��c��X�������ɏZ��ł���l�B�̒��ɁA�Ñ�́u���l�v�ɂ܂Ōq���錌�̐l�X�͂ǂꂭ�炢����̂�
���낤���H�@�f�p�ȋ^��ł��邪�A�����̋^��ɓ����邱�Ƃ͑�ϓ�����Ƃł��낤���Ƃ͏\���z���ł���B
1986�N�i���a61�N�j�ɁA�������p�i�э]�p�j���̊C��ڂ̑O�ɂ����A�����s�i���E�����s�j�̕W��250m�̃V���X��n�ɍH�ƒc�n�����A��K�͂�
�ꕶ����̏W���Ղ��������ꂽ�B���݂͐�������āA�u��V���ꕶ�̐X�v�����ƂȂ��Ă���A���ɂ̓~���[�W�A��������B
���̌�A10�N�������Ĕ��@�������s��ꂽ���ʁA���̈�Ղ͋ߐ�����ꕶ���㑁���O�t�܂ł̈�ՌQ���܂ޕ�����Ղł��邱�Ƃ��킩�����B����
��ՌQ�̍ʼn��w�ł���A9500�N�O�̍������̉ΎR�D�w�̉�����́A�����ɂ����ē��{�ōŌÂ̑�K�͂Ȓ�Z�W���Ձi�G�����Z����52���j���������ꂽ�B���̒n�w�͖�ꖜ�N�O����4000�N�ق�
�����ꕶ���㑁���̑O���Ɉʒu�Â�������̂ł���A�L�k���l�̓y��i�L���y��j�����A�W�Έ�\39��A�A���y���i�����t�F���j16��A���ՂQ�{���p���������B�W�Έ�\�͐Ώ��������ɁA
�A���y���͓��������ɗp����ꂽ�ƍl�����Ă���B
���̈�Ղł́A�����9500�N�O�̍����ΎR�D�w��7500�N�O�̍����ΎR�D�w�̊Ԃ̒n�w����A������10���_�̈╨���o�y�����B���̒��ɂ͑�������
�����ꂽ���l���������y���y��������A�y��A�ꊇ�������ꂽ�A�u�ۂ̂`�Ε��v�̋Z�@�����������Ε��召65�A�n�ʂɖ��߂�ꂽ��Ԃł̈�̚�`�y�퓙���܂܂�Ă���A������
�l�X�̖L���Ȑ��_���������̂����̂ł������B�����̔����́A�u�ꕶ�����͓����{�ʼnh���Đ����{�ł͒ᒲ�������v�Ƃ����A����܂ł̏펯�����ƂƂȂ����B
�����Łu�ۂ̂`�Ε��v�Ƃ́A�ۖ؏M�蔲���̂ɗp����ꂽ�Ǝv����Ί�ŁA�����������ł́A�ꕶ���㑐�n���i��ꖜ3000�N�O�`�ꖜ�N�O�j
�̈�ՂƂ��ėL���ȉ����c�s�i���E�삳�s�j�̞��m����Ղ⎭�����s�|���R��ՁC�u�z�u�������y�c��ՁC����ɓꕶ���㑁���㔼�i��7,000�N�O�j�ɑ������鎭���s�O����ՁC��q����
���V�\�s���R��ՁA�����{�����ŏo�y���Ă���B���ɂ���͉���{���A�k�͒��茧�ܓ��Ŕ�������Ă���A���̎���Ɂu�C�̓��v�ɉ����āA��̕����������݂��Ă������Ƃ����肳���B
�ŋ߁A���������̖{�ł͂��邪�A�uNHK���{�l�\�͂邩�ȗ��i�Q�j���啬�ɏ����������̖��\�삩�炫�����{�l�̑c��v
�i�n��I�j�E���c�Õv�ďC�ANHK�X�y�V�����E�u���{�l�v�v���W�F�N�g�ҏW�A�}���G�\���E���A�����ˏ��[�A2003�N���j�Ƃ����{�����邱�Ƃ�m�����B���̖{�ň����Ă���̂́A��q�̎�������
��쌴��n�ŕ�炵�Ă����ꕶ�l�̂��Ƃł���Ǝv����B�����ł����u���啬�v�Ƃ́A���悻7300�N�O�ɂ������A�S�E�J���f���i�F�������̓�50km�̊C��ɂ���J���f���ŁA���̖k���ɂ�
�F���������A�|��������j�̉ӗ����啬�̂��ƂŁA���̎��̉ΎR�D�i�A�J�z���ΎR�D�j�́A�����k���A���k�n���⒩�N�����암�ł��m�F�ł���Ƃ����B
�@�@�@
�������̐�Z���A���l���܂��A�삩��u�C�̓��v��ʂ��Ă���ė����C�m�����̖���Ȃ̂ł��낤���H�@���̉\���͏\������B
�Ńg�b�v��
�@
���{�����w�̕��ƌ�������c���j�i1875�|1962�j�̐��U�Ō�̖{�ɁA�u�C��̓��v�i�}�����[�A1961�N���j�Ƃ����{������B���݂͊�g�V���Ƃ��Ă�
�o�ł���Ă���B���c�́A�ŏ��̈ڏZ�͕Y���E�Y���ł������Ƃ��Ă��A��L�i�Ñ�A�ݕ���g��̍ޗ��Ƃ��Ē��d���ꂽ�R���X�K�C�A���R�E�K�C���̊��L�j�̖��͂ɂЂ���Ē����嗤����쐼�����ɂ����
�����l�X������A�����̐l�X�ɂ���ăC�l�����{�ɓ`����ꂽ�ƍl�����B�������C�l��`�����C�̓����������Ƃ����̂ł���B���{�����ƈ��Ƃ͕s���ȊW�ɂ���A�C�l���Ȃ����
���{�����͐������Ȃ��ƍl���A���̈��͓���������ė����Ƃ����m�M�́A���c�̐��U�ς��ʐM�ɋ߂����̂ł������Ƃ����B
�������A���̍l�����ɑ��ẮA����w�A���j�w�A�Ƃ�킯�l�Êw�̗��ꂩ�狭�������������Ƃ����B��앶���͖퐶�����ƌ��т��Ă���A
�퐶�����͈���I�ɋ�B���牫��{���ɂ܂œ쉺���Ă���A�t�ɖk�シ�镶���̍��Ղ͔F�߂��Ȃ��Ƃ����̂ł���B�����̏K�������{�j�ł��A�I���O3���I�����ɐ��c���̋Z�p���������l�X��
�����⒩�N��������k����B�ɂ���ė��āA�������琅�c��삪���{�S���ɍL�܂����Ƃ������Ƃł������Ǝv���B�����Ƃ��A���c���̊J�n�������Ė퐶����̎n�܂�Ƃ݂Ȃ��ƁA�퐶�����
�n�܂�͋I���O8���I�܂ők��Ƃ����ŋ߂̌����i�u�퐶����̗��j�v�A�����T��Y���A�u�k�Ќ���V���A2015�N���j������悤�ł���B����͈╨�Ɏc���ꂽ�Y�������̒Y�f14�̗ʂ�p�����N��̑��肪
��萸���ɂł���悤�ɂȂ������ƂƁA���̕��@�ɂ�蓱���ꂽ�Y�f�N�����������F���ł����N��Ɋ��Z����r���i���������j�N��@���i���������ʂł���Ƃ����B
���c�́u�C��̓��v�̊w���́A�w��Ŋ��S�ɔے肳�ꂽ���ɂ݂����B�ɂ�������炸�A���̌�̓W�J�͂��������Ⴄ�悤�ł���B
���c�̖��ӎ��́A�u���{�l�͂ǂ����痈���̂ł��낤���H�v�Ƃ������ƂƋ��ɁA�u���{�����ƕs���̊W�ɂ���C�l���ǂ����痈���̂��H�v��
�������Ƃł������Ǝv����B���̂��ƂɊ֘A���āA�uNHK ���{�l �͂邩�ȗ��i�S�j�|�C�l�A�m��ꂴ��ꖜ�N�̗��A�嗤���琅�c����`�����퐶�l�v
�i�n��I�j�E���c�Õv�ďC�ANHK�X�y�V�����u���{�l�v�v���W�F�N�g�ҏW�A�}�� �G�\���E���A�����ˏ��[�A2003�N���j�Ƃ����{������B�l�X�̊w�╪��ɂ�����A����܂ł̌������ʂ𑍍����āA
��̃X�g�[���[�Ƃ��ď�����Ă���̂ŁA���������̖{�ł͂���Ƃ͂����A�Ȃ��Ȃ���������������{�ł���B���̖{�ɂ��A���`�d�̗��j���T�ς��Ă������B�|�C���g�́u���c���v��
�u���v�͓����ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł���B
�C�l�ɂ̓W���|�j�J��ƃC���f�B�J�킪���邱�Ƃ͎����m���Ă����B�������A�W���|�j�J��ɔM�уW���|�j�J�Ɖ��уW���|�j�J�����邱�Ƃ́A���̖{
�ŏ��߂Ēm�����B�M�уW���|�j�J�͔w�������A������������̐��͏��Ȃ��B���уW���|�j�J�͔w���Ⴍ�A����Z������̐��������BDNA���͂ɂ��A�M�уW���|�j�J�̕������уW���|�j�J����
�Â����Ƃ��킩���Ă���Ƃ����B
�C�l�͋I���O1���N���A���]�i�g�q�]�j������ō͔|�����悤�ɂȂ����ƍl�����Ă���B���E�ŌẪ��~�́A���]������̋�巊�i���傭����j
��Ղł݂����Ă���B���]������A�������]�Ȃ̉͛G�n�i���ڂƁj��Ղ͋I���O5000�N���̈�Ղł��邪�A�����Ō��������Y���Ă͔M�уW���|�j�J�ł������B�͛G�n�i���ڂƁj�̖��͍�����
�Z���ɏZ�݁A�����s���ƂƂ��ɁA�C�ɏo�ċ������Ă����B�͛G�n�i���ڂƁj��Ղ���͈ړ����̂��܂ǂ��o�y���Ă���Ƃ����B�I���O3000�N���ɂ́A���]������̈��n�тŁA�V�R�̎��n��
�V���c�ɂ�����āA���c��������悤�ɂȂ�B���c�����ɂ́A�����y�؋Z�p�A�����Z�p���K�v�ł���B���c�Ƃ����V�������̂��ƂŁA�M�уW���|�j�J�̃C�l�́A��`�I�ɐV�����C�l
�i���уW���|�j�J�j�ɐ��܂�ς���Ă������ƍl�����Ă���B�I���O11���I����I���O10���I�ɂ́A���c���̋Z�p�͒��N������[�ɂ܂ŒB���Ă����B���傤�ǂ��̍��A���{�͊��≻��
�������A�H�Ɗ�@�Ɋׂ��Ă����B
���{�̑Δn�Ƀq�g���Z�ݎn�߂��̂́A�I���O10���I�̌㔼�i�ꕶ�������j�ȍ~�̂��Ƃł���B���݁A�Δn�̐_�c�ō͔|����Ă���Ñ�Ă͔M�уW���|�j�J��
���邪�A�����`�����̂́A�͛G�n�i���ڂƁj�̖��̂悤�ȁA���]������̓��V�i�C���݂̋����ł͂Ȃ��������ƍl�����Ă���B����ƁA�C�l�͋I���O10���I�̌㔼�ɂ͓��{�ɓ`�����Ă���
���ƂɂȂ�B�͛G�n�i���ڂƁj�̖����`������������Ȃ��������̓`���͍��ł��Δn�̐l�X�Ɏp����Ă���Ƃ����B
�؍��암�̌c���쓹�E���R�s�ɂ����ӓ��i�낭�Ƃ��j��Ղ���́A��B�k���ɏZ�ޓꕶ�l�Ƃ̌𗬂𗠕t����╨�i�ꕶ�y��j���o�y���Ă���B
�܂��A�؍����O���L�˂���́A��ʂ̓ꕶ�y��ƂƂ��ɁA���ꌧ�ɖ����s�Y�o�̍��j���݂����Ă���B�����̎����́A�ꕶ����ɂ����ċ�B�k���̓ꕶ�l�Ɗ؍��ɏZ�ސl�X�̊ԂɌ𗬂�
���������Ƃ𗠕t���Ă���B
�@�@�@
1979�N�ɁA�I���O600�N���̓ꕶ�ӊ��̈�Ղł���A���Îs�ؔ���Ղ��������ꂽ���A�����Ő��c�̈�Ղ����������B�����ɏZ��ł����ꕶ�l��
���N�암�ɓn��A���c���̋Z�p���w��Ŏ����A�������̂ƍl�����Ă���B�܂�A���c���͓ꕶ����̔ӊ��ɂ͍s���Ă������ƂɂȂ�B�����ł̃C�l�͉��уW���|�j�J�ł������B
�Ƃ���ŁA�u�v�����g�I�p�[�����͖@�v�Ƃ������̂�����B�v�����g�I�p�[���Ƃ́A�C�l���͂��߁A���M�A�q�G�A�A���A�g�E�����R�V�ȂǁA�C�l�Ȃ�
�A���Ɋ܂܂��K���X���i��_�́j�̍זE���̂��Ƃł���B�K���X���̂��߁A�C�l�Ȃ̐A���������ď����ĂȂ��Ȃ��Ă��A�y�̒��Ɏc��̂ł���B���̃v�����g�I�p�[����y�̒����猟�o���āA
���̌`�ɂ���āA�C�l�Ȃ̂ǂ̐A�����𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��A�u�v�����g�I�p�[�����͖@�v�Ƃ����B���̕��@�ɂ��A���R���A�������A���������ɂ���X�����̓ꕶ��ՂŃC�l�̃v�����g�I�p�[����
���������B���̂��Ƃ́A���{�̓ꕶ����ɁA�L���͈͂ŃC�l���͔|����Ă������Ƃ������Ă���B�����̓ꕶ��Ղ��猩�������C�l�̃v�����g�I�p�[���́A�M�уW���|�j�J�̂��̂ł������B
�C�l���ǂ̂悤�Ȍo�H��ʂ��ē��{�ɓ`������̂��ɂ��ẮA����܂ŁA���N�����o�R���A��������̒��ړn�����A
�C��̓����쓇�o�R���̎O�̐�������Ƃ����B�������A�����̐��́A�u���c���Ɛ���i���уW���|�j�J�j�v��O�����̂ŁA�u�Ĕ����ƔM�уW���|�j�J�v���ӎ��������̂ł�
�Ȃ��Ƃ����B�A����`�w�҂̍����m��Y���ɂ��A�u�M�уW���|�j�J�v���A�C��̓����쓇�o�R���œ��{�ɓn�������\���͋������̂́A�܂�����I�ȏ؋��͌������Ă��Ȃ��Ƃ����B
���̉\����⋭������̂Ƃ��āA���R�l�ފw�ҁA���֏�v�i1897�|1983�j�ɂ��A�u�쓇���Ӎk�i�ǂ������j�����_�v��A����������A
�����w�ҁA���X�؍������i1929�|2013�j�́u�쓇�_�k�����_�v������B�u�Ӎk�i�ǂ������j�v�Ƃ́A���_��L�i����j��p���Đl�͂ɂ��y�n���k���A�����Ƃ����n�I�ȍk����@�������B
�^���C����}�C���͔̍|�ɂ͞��_���p�����A�����͔̍|�ɂ͌L���p������B�@���X�ɂ��u�쓇�_�k�����v������Â�����̂́A�~��̍�G�A�A���ƃC���i�M�ьn�̃��}�m�C����
�T�g�C���j����앨�Ƃ��锨��Ɠ��k��q�R�o�G�琬�^�̈��Ƃ̋����A�Ɠ��̔_��A�Đ������͂��߂Ƃ���V���M�Ȃǂł���Ƃ����B
�@�@�@
���X�؍������́A�u�쓇�v�ł̎��g�̌��n�����Ɋ�Â��āA�u�쓇�_�k�����v�̊�b���`�����Ă���̂́A�u�I�[�X�g���l�V�A�^���v�ł����
�����Ă�����i���X�؍������F�u�삩��̓��{�����i��j�A�i���j�|�V�E�C��̓��v�ANHK �u�b�N�X980�A���{�����o�ŋ���A2003�N���j�B�����Łu�쓇�v�Ƃ̓I�[�X�g���l�V�A�̂��Ƃł���A
�I�[�X�g���l�V�A�Ƃ́A��p���瓌��A�W�A���ו��A�����m�̓��X�A�}�_�K�X�J���ȂǁA�u�I�[�X�g���l�V�A�ꑰ�v�ƌĂ��l�X����炷�n��������B���˂ẮA�u�}���[�E�|���l�V�A�ꑰ�v
�ƌĂ�Ă����l�X�̌���Ƒ�p���Z���̏���Ƃ̗މ������ؖ�����āA���݂͈ꊇ���Ă��̂悤�ɌĂ�Ă���Ƃ����B�I�[�X�g���l�V�A�ꑰ�͑�p����t�B���s���A�C���h�l�V�A�A
�}���[�����Ɠ쉺���A5���I���ɃC���h�m���z���ă}�_�K�X�J�����ɒB���A����ɓ��̑����m��̓��X�Ɋg�U�����ƌ����Ă���B
�@
�u�I�[�X�g���l�V�A�^���v�̃C�l�͔M�уW���|�j�J�ł���B���X�́A�u�쓇�v�ł̖L�x�Ȍ��n�����ɂ���āA���́u�I�[�X�g���l�V�A�^���v
���܂ށu�쓇�_�k�����v�̕��z�𖾂炩�ɂ����B�����Ă��́u���z�v�������Ƃ��āA���́u�����v���삩��k�ցu�C�̓��v�ɂ���ē`�d���邱�Ƃɔ����A�C�l�����{�ɓ`����ꂽ
�\��������Ǝ咣���Ă���̂ł���B
�Ńg�b�v��
�@
�썑�F���Ɋւ��u�C�̓��v�ɂ��ď������̂ŁA�k���z��Ɋւ��u�C�̓��v�ɂĂ������Ă������Ǝv���B�k���́u�C�̓��v�Ɋւ��āA�܂��A�v�������Ԃ̂́A
�ߐ��A�]�ˎ���ɂ�����u�k�O�D�v�Ɓu�R�O���Ձi���������j�v�̂��Ƃ���B
�u�k�O�D�v �Ƃ́A�]�ˎ��ォ�疾������ɂ����ē��{�C�C�^�Ŋ����A��Ɂu���ς݁v�́u���D�v�̂��Ƃł���B�u���ς݁v�Ƃ́A���i��a������
�^������̂ł͂Ȃ��A�D�厩�̂��D�̊�`��Ŕ������ė��v�邱�Ƃ�ړI�ɁA���i���Đςݍ��ނ��Ƃ������B�u���D�v�Ƃ́A�`����`�֏���D�̂��Ƃł���B�u�k�O�D�v�̍q�H�́A
���͑Δn�C���ɍR���āA�k���Ȗk�̏��`����A���ւ��o�R���Đ��˓��C��ʂ��đ��Ɍ������i����͂��̋t�j�B�u�k�O�D�v�̍Ŗk�[�̊�`�n�͉ڈΒn�i�k�C���j�̍]���ł���B�z��ł́A
��D�A�V���A���i���n�j�A�o�_��A����A�����i�����]�Áj�Ȃǂ��k�O�D�̎�Ȋ�`�n�ł������B�����^���Ƃ����ƁA����ׁi�k�����ʁj�ɂ́A�ڈΒn�̐l�X�ւ�
��ށE���H�i�ށE�ߕ��p�i�E�����Ȃǂ̓��퐶���i�A���˓��C�e�n�̉��i���l�������ɕs���j�A���A�����A�āA��琻�i�i��E���V���j�A�X�C�i���Y�n�͐��˓��j�Ȃǂł������B���ׁi�E�����ʁj�́A
�w�ǂ��C�Y���ŁA
���i�_�앨�͔|�̂��߂̔엿�ł����ה��A���̎q�A�g�����j�V���A�����i�}�R�A���z�A����Ȃǂł������B���ɍ��z�͑�₩��i�܂��͒��肩��j�F�����o�āA����o�R�Œ�����
�܂Ŗ��A�o���ꂽ�Ƃ����B�k�C���A�z���A�F���A�����i����j�A���i�����j�܂ł̃��[�g���u���z���[�h�v�Ƃ������Ƃ�����Ƃ������A�k�́u�C�̓��v�Ɠ�́u�C�̓��v���A�u���z�v��ʂ��Č݂���
�q����A�����܂ʼn��тĂ����Ƃ��������́A��ϋ����[�����ƂɎv�����B
�Ƃ́A�]�ˎ��ォ�疾������ɂ����ē��{�C�C�^�Ŋ����A��Ɂu���ς݁v�́u���D�v�̂��Ƃł���B�u���ς݁v�Ƃ́A���i��a������
�^������̂ł͂Ȃ��A�D�厩�̂��D�̊�`��Ŕ������ė��v�邱�Ƃ�ړI�ɁA���i���Đςݍ��ނ��Ƃ������B�u���D�v�Ƃ́A�`����`�֏���D�̂��Ƃł���B�u�k�O�D�v�̍q�H�́A
���͑Δn�C���ɍR���āA�k���Ȗk�̏��`����A���ւ��o�R���Đ��˓��C��ʂ��đ��Ɍ������i����͂��̋t�j�B�u�k�O�D�v�̍Ŗk�[�̊�`�n�͉ڈΒn�i�k�C���j�̍]���ł���B�z��ł́A
��D�A�V���A���i���n�j�A�o�_��A����A�����i�����]�Áj�Ȃǂ��k�O�D�̎�Ȋ�`�n�ł������B�����^���Ƃ����ƁA����ׁi�k�����ʁj�ɂ́A�ڈΒn�̐l�X�ւ�
��ށE���H�i�ށE�ߕ��p�i�E�����Ȃǂ̓��퐶���i�A���˓��C�e�n�̉��i���l�������ɕs���j�A���A�����A�āA��琻�i�i��E���V���j�A�X�C�i���Y�n�͐��˓��j�Ȃǂł������B���ׁi�E�����ʁj�́A
�w�ǂ��C�Y���ŁA
���i�_�앨�͔|�̂��߂̔엿�ł����ה��A���̎q�A�g�����j�V���A�����i�}�R�A���z�A����Ȃǂł������B���ɍ��z�͑�₩��i�܂��͒��肩��j�F�����o�āA����o�R�Œ�����
�܂Ŗ��A�o���ꂽ�Ƃ����B�k�C���A�z���A�F���A�����i����j�A���i�����j�܂ł̃��[�g���u���z���[�h�v�Ƃ������Ƃ�����Ƃ������A�k�́u�C�̓��v�Ɠ�́u�C�̓��v���A�u���z�v��ʂ��Č݂���
�q����A�����܂ʼn��тĂ����Ƃ��������́A��ϋ����[�����ƂɎv�����B
�u�R�O���Ձv�́u�R�O�v�Ƃ́A�R�U�A�R�Ƃ������A��ɃE�C���^���i�c���O�[�X�n�j�A�j�u�q���i�����S���C�h�j�A�I���`�������i�c���O�[�X�n�j�Ȃ�
���Z��ŋ����A�ɓ����V�A�̓��{�C���ݒn��������B�����̋��Z���ƃA�C�k�l�Ƃ̊ԂŁA��Ƃ��Ċ����i�T�n�����j�𒆌p�n�ƍs��ꂽ���Ղ��u�R�O���Ձv�ł���B
�R�O�l�́A����������渁i�e���j�����[�������ɁA�����c���艺�����ꂽ������z�n�A�h�̉H�A�ʂȂǂ����Q���Ċ����ɗ��q�����B�A�C�k�l��
�œ����є��A�a�l�������炳�ꂽ�S���i�A�āA���A�R�O�l���������i�ƌ��������B�A�C�k�l�̒��ɂ͎R�O���Ղ��������ł͂Ȃ��A�����ɒ��ڒ��v���Ă������̂������Ƃ����B
�R�O�l�ƃA�C�k�l�Ƃ̌��Ղɂ���Ă����炳�ꂽ�i�X�́A�A�C�k�l�ɂ���ĉڈΒn�̏��O�˂ɂ����炳�ꂽ�B����ɁA�����̕i�X�́A���O������{�C���́u�����q�H�v�Ƒ����m���́u�����q�H�v��
���{�̊e�n�ɉ^�ꂽ�B�@�����̌��Ղ��܂߂āu�R�O���Ձv�Ƃ������Ƃ�����B�u�R�O���Ձv�ł����炳�ꂽ�i�œ��ɗL���Ȃ̂��u�R�O���v
�Ȃ����u�ڈсv�Ə̂����ؗ�Ȏh�J�̎{���ꂽ���B����
�����̊��� �ł������B
�ł������B
�����ŁA������Ñ�ɂ܂ł����̂ڂ��Ă݂悤�B���{�̌Ñ�ɂ�����A�k�́u�C�̓��v�́A���}�g�������k���̉ڈi���݂��j���͂��߂Ƃ���u�ٖ����v��
�鉻�Ɛ����̂��߂ɑ�D�c�𑗂����u���v�ł������B�H��������́u�Ñ�ڈv�i�g��O���فA2011�N�A2000�N�̏��ő����̕����Łj�Ƃ����{�ɂ��ƁA�u���{���L�v�ɂ͎��̂悤�ȋL�q������Ƃ���
�i�����App.99�`100�j�B
�E658�N�`660�N�i�Ė��S�`�U�N�j�A���N�A�z���i�����̂��ɁA���݂̕��䌧�։�s
����R�`�������n���̈ꕔ�ɑ�������n��j�̍���A���{�䗅�v��180�`200�z�̑�
�D�c�𗦂��ē��{�C��k�シ�鉓�����s�����B
�E658�N�i�Ė��S�N�j7���A�ڈ�200�l�]�肪�s�ɂ̂ڂ蕨�����サ�A�\��ƒÌy�̌S�̂Ȃǂ��ʂ�^����ꂽ�B
�E����{�]�A���{�䗅�v���l�T�i���キ����j�Ɛ���ċA��A��49�l�����サ���B
�E660�N�i�Ė��U�N�j3���A���{�䗅�v��200�z�̑D�ŎO�x�ڂ̉����ɏo�����A����̓��{�C���̂ǂ����A�܂��͐Ύ��͌��܂ōs���A�����ŏl�T�Əo���������f�Ղ��������������������Ȃ������B
�܂��A544�N�i����5�N�j12���A�l�T�l�i�����͂��̂ЂƁ����キ����j�����n�ɓ��������Ƃ����L�q�����{���L�ɂ���Ƃ���
�i�c���\�ꑼ���A�u�V�����̗��j�v�A�R��o�ŁA1998�N���App.41�`50�j�B
�����ŁA�u�l�T�i���キ����j�v�Ƃ����̂́A�����A���݂̒������k���A�ɓ����V�A���{�C���݁i���C�B�j�A�����i�T�n�����j�ɏZ��ŋ����l�X�ŁA
�l��I�ɂ͓��{�̓ꕶ�l�Ɠ��n���ł���Ƃ�����������悤�ł���B�Ñ�ɂ����Ă����{�C�̑Ί݂ɏZ�ސl�X�Ƃ̊ւ��͂������̂ł���B
�@�@�@
�����܂ŏ����Ă��ċC�Â������̂́A�����A���N�̗��j�ɂ��ẮA������x�̒m���͂�����̂́A���N�ȊO�̓��{�C�Ί݂̒n��A���݂̒������k����
�ɓ����V�A�̓��{�C���ݒn��ɁA�ǂ̂悤�Ȑl�X���Z�݁A�ǂ̂悤�ȍ�������Ă����̂��A�����Ă����̍��X�Ɠ��{�͂ǂ̂悤�Ȋւ��������Ă������ɂ��ẮA�قƂ�lj����m��Ȃ��Ƃ������Ƃ�
����B����̉ۑ�Ƃ������B
�Ńg�b�v��
�@
�����������Ɂu�ĎR��t�v�Ƃ����ꏊ�����邱�Ƃ�m�����̂͂��̍��������낤���H�@����2009�N�ɑ�w���N�ސE������A�u���������̗��j�U���v�i�������������w�Z���j����ҁA�R��o�Łj�����߁A���̖{�ɓ�����ċ����������܂܂�
�����������̎j�Ղ�K�˕����Ă����B�����炭�A���́u���������̗��j�U���v�̖{�̒��́u���ǁE�����E����������v�̍��Ɂu�ĎR��t�v�̖��O��
���o�����̂��ŏ��ł������Ǝv���B
���͂��Ƃ��ƎR�������D���ŁA���w���̍����玄�̋����V���������s�̋ߕӂ̎R�X�ɓo���Ă����B�����́A
�M�B�̎R���ɒ[�������{�꒷����A�M�Z�삪�R�ԕ����ĕ��암�ɓ���A�앝���L���Ȃ����Ƃ���̉E�݂ɊJ�������ł���B���݂͕����̑升����
���s����g����l���������Ă��邪�A�������w�����������̐l����13���l�قǂł������B�����͓���ƕ���̑喼�q��Ƃ̏鉺���ł������B�s�̒��S��
���瓌�� 4km ���̂Ƃ���ɁA���R�u�˂ƌĂ��R�X�������Ă���B���̋u�˂̍ō���͕W��765m�̋��R�ł���B�ǂ����肵���A�`�̗ǂ��R�ł���A
���̖�����킩��悤�ɁA���̎R�̗Ő��͉������璭�߂�Ƌ��̎��̂悤�ɃM�U�M�U���Ă����B���̑z���ł��邪�A�×��A���R�͏C�����̏C�s�̏��
�������̂ł͂Ȃ��낤���B�������s�̖k���A�������ɂ��鑠�����i���E�����_�Ёj�ɁA�C�����̕��l�A�������������u����Ă��邱�Ƃ����̑z���͂�
�~�����Ă�B���̋��R�ɓo��ƍ���ߑO���ɁA�s���~�b�h�^�̌����ȎR�e�������R���ڂɔ�э���ł���B�C�̋߂����ނ����Ɨ���Ȃ̂ň��
�ڗ����Ă���B���ꂪ�����m���Ă���ĎR �ł���B�×������{�C���q�s����D�̖ڈ�ɂȂ��Ă������Ƃł��낤���A�l�X�̐M�̑ΏۂɂȂ��Ă�������
�ł��낤���Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B����قǖڗ��R�ŁA�_�X����������������R�ł���B�ĎR�̕W����992.5���ŏ�z�s�Ɣ���s�̋��E�ɒ������Ă���B���̕�����
�c���̎��Ƃ���������z�s������������ǂ�������B���Ȃ݂ɔ���s�͎��̋��������s�ׂ̗̎s�ł���B�����V�����ɏZ��ł������i��w�ɐi�w���ē�����
�o��܂ł�18�N�ԁj�A�ĎR�Ɉ�x�͓o���Ă݂����Ǝv���Ă��������ljʂ����Ȃ������B�ĎR�̒���ɂ͖�t��������A��t�@�����J���Ă���Ƃ����B
�����m���Ă��邱�́u�ĎR�v�Ǝ������́u�ĎR��t�v�͊W������̂ł��낤���H�@���ׂĂ݂�Ƌ��������Ƃɑ傢�ɊW������̂ł���B
�ł���B�×������{�C���q�s����D�̖ڈ�ɂȂ��Ă������Ƃł��낤���A�l�X�̐M�̑ΏۂɂȂ��Ă�������
�ł��낤���Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B����قǖڗ��R�ŁA�_�X����������������R�ł���B�ĎR�̕W����992.5���ŏ�z�s�Ɣ���s�̋��E�ɒ������Ă���B���̕�����
�c���̎��Ƃ���������z�s������������ǂ�������B���Ȃ݂ɔ���s�͎��̋��������s�ׂ̗̎s�ł���B�����V�����ɏZ��ł������i��w�ɐi�w���ē�����
�o��܂ł�18�N�ԁj�A�ĎR�Ɉ�x�͓o���Ă݂����Ǝv���Ă��������ljʂ����Ȃ������B�ĎR�̒���ɂ͖�t��������A��t�@�����J���Ă���Ƃ����B
�����m���Ă��邱�́u�ĎR�v�Ǝ������́u�ĎR��t�v�͊W������̂ł��낤���H�@���ׂĂ݂�Ƌ��������Ƃɑ傢�ɊW������̂ł���B
�������̕ĎR��t�́A�������p�i�э]�p�j�̘p���ɒ������ޕʕ{��i�͐�j�̉͌��������k����
���݂̍���125m�̊�R�̏�ɂ���B�Z���͈��ǎs��q�ł���B���̓�q�ɂ͖L�B�Ɠ��ÉƂ̕�n������A���̕�n�̕~�n�ɁA���đ��T���Ƃ�������
�������B�L�B�Ɠ��ÉƂ́A���喼�A���Ï@�ƂW�㓇�Ëv�L�i1375�N�|1425�N�j�̎O�j�A���ËG�v�i���܂� �����Ђ��A1413�N�|1477�N�j������Ƃ���
���Î��̕��Ƃł���B���㓇�ËG�v���L�����̂������Ƃ���u�L�B�Ɓv�ƌĂ�邱�ƂɂȂ����B���̑��T�����������Ă����u�ĎR��t�R���v�ɂ�
���̂悤�ɏ����Ă���Ƃ����i�ĎR��t�_�Ѓz�[���E�y�[�W���]�ځj�B
�w���̖�t�͑��T���J�R�N�@�a���̔���ɂ�錚���ł���B�N�@�a�������ՎQ�̎��A�z��̕ĎR����t��
���ł���Ƃ����̂ŁA�S���Q�Ă��Ă����B���鎞�����̘V�l������A�a���Ƌ��ɎQ�Ă����B�V�l�͋N�@�Ɂu���͕��t�ł���B�t�͖�t�ɋA���Ă���
�悤�Ȃ̂ŁA��t���荷���グ�܂��傤�B�v�ƌ������B�N�@�͑傢�Ɋ�т��肢�����B����҂������Ă��̘V�l�͎t�̌���K��A��t�̑���^�����B
�Z���Z���̍����ł���B�܂��N�@�Ɂu����t���̋��A�����炷���Ɏ����������A�l�X���ꂵ�݂���~���Ȃ����B�v�ƍ������B�N�@�͂��̖�t����
���݂̕��ł͂Ȃ����Ƃ�������A�V�l�̖���q�˂��̂����A���ɘV�l�͓����邱�ƂȂ������Ă��܂����B�ǂ��֍s�����̂���������Ȃ��B�N�@�͂����
�s�v�c�Ȏ��ł���Ǝv���A���锧�g������������h�炵���B
�N�@�͋��֎������ہA��t���t�Ɍ����邱�Ƃɂ����B�����������t�͋����u���̑��͐l�����������ł�
����܂���B����t�̖����A���̎O�������ɂ���l������A���̑������Ɍ����Ă����̂ł��B�v�ƌ������B����t�̖����Ƃ����A�V�l����t��������
�ĎR�ɗ������ł���B�N�@�͂܂��܂��s�v�c�ł���Ɗ������B
�N�@�͖{�˂ɋA��ƁA�����̊≪���܂�ʼnz��̕ĎR�̂悤�ł������̂ŁA���̑������u�����B�����ĕĎR��t�Ɩ��t�����̂ł������B����ȗ��̗쌱��
��������Ȃ��قǂł���x�B
�����ő��T�����J�R�����N�@�a���Ƃ́A�L�B�Ɠ��Î�����A���ËG�v�̎l�j�A���Î狻�̂��Ƃł���B
15���I�̒����A��������A�F���̕��Ƃ̎l�j�V���m�ƂȂ�A�������s�r���A���H�͂��z��̍��ɂ܂ő����̂��Ă������Ƃ�m�������Ƃ́A���̒�
�Ɉ���̊��S�������N�����ɏ\���ł������B
2011�N4���̖��A���͎������̕ĎR��t��K�˂��B�ĎR��t�̂��鈦�ǎs�́A�������A���ǒ��A�����ؒ���
�O�̒�����������2010�N�ɂł����V�����s�ł���A���݂͎������s�̃x�b�h�^�E���ƂȂ��Ă���B���͎����������w����JR���L�{���ɏ��A�����w��
�~�肽�B�����������w����܂ځA�������A�������A�d�x�A���ǂ̎��������ł���A��Ԏ��Ԃ�25���قǂł������B�����w�����̐��ʓ��H�����ɍs���A
��`�֒ʂ��鍂�����H���������Đi�ނ�25�����炢�ŕʕ{��ɂ����鋴�i�������j�ɂł�B���̋���n�����Ƃ��낪��q�̒n�ŁA���݁A�������w�Z������
�ꏊ�ɂ́A�]�ˎ���A�F���˂̒n���������������Ƃ����B�܂���O�̕ʕ{�썶�݁A�������̂����Ƃɂ͔[������q�������āA���̂�����̐����E�o�ς�
���S�n�ł������B�ĎR��t�͒������w�Z�̓�������ɂ����R�̒��� (�E�[�̎R�̏�̊��̕ӂ�)�ɂ���B��R����ւ̓o��́A���Ȃ�̋}�o�ł��邪�A���̂����o�R��������
�ݒu����Ă����肵�āA125m�̍�����o�肫��ɂ���قNj�J���邱�Ƃ͂Ȃ��B����ɂ͖�t�@�����J���t�����������B���ォ��̒��߂͗ǂ��A�����A
�������s�̋g���n�ɒʂ���d�x�̔����i���낪�˂����j���ʁA�ʕ{��㗬�������ʂ̎R�X���ǂ��������B�܂��k���̑����ɂ́A�ĎR��t����������
�N�@�a���i�L�B�Ɠ��Î����㓇�ËG�v�̎l�j�A���Î狻�j���J�R�����������Ձi���݂͖L�B�Ɠ��ÉƂ̕�n�j���������B���݂̕ʕ{��̐��ʂ͂���ق�
�����͂Ȃ����A�������ɂ͏㗬�̊������ʂ܂őD���������Ƃ����B�����̊ԁA�u���������͕ĎR��t�A�O�͔����̑���D�v�Ɨw��ꂽ�̓����ÂB
(�E�[�̎R�̏�̊��̕ӂ�)�ɂ���B��R����ւ̓o��́A���Ȃ�̋}�o�ł��邪�A���̂����o�R��������
�ݒu����Ă����肵�āA125m�̍�����o�肫��ɂ���قNj�J���邱�Ƃ͂Ȃ��B����ɂ͖�t�@�����J���t�����������B���ォ��̒��߂͗ǂ��A�����A
�������s�̋g���n�ɒʂ���d�x�̔����i���낪�˂����j���ʁA�ʕ{��㗬�������ʂ̎R�X���ǂ��������B�܂��k���̑����ɂ́A�ĎR��t����������
�N�@�a���i�L�B�Ɠ��Î����㓇�ËG�v�̎l�j�A���Î狻�j���J�R�����������Ձi���݂͖L�B�Ɠ��ÉƂ̕�n�j���������B���݂̕ʕ{��̐��ʂ͂���ق�
�����͂Ȃ����A�������ɂ͏㗬�̊������ʂ܂őD���������Ƃ����B�����̊ԁA�u���������͕ĎR��t�A�O�͔����̑���D�v�Ɨw��ꂽ�̓����ÂB
�������w�Z�̐������H��k�ɐi�ނƒ�����א_�Ђɍs�����B�S���Â�搂�ꂽ�퍑�������Ë`�O
�i1539�|1619�j�́A1596�N����1606�N�܂ŁA�����ɋ��ق������������Ƃ����B���̉��~�̐Ί_�������c���Ă���B���Ë`�O�����N�o�������̂́A
���\�̖��i1592�|1593�j�ƌc���̖��i1597�|1598�j�ł��邩��A�c���̖��͂�������o�w���Ă����ɋA���Ă������ƂɂȂ�B�܂��A�u���Â̑ނ����v
�ŗL���ȊփP���̐킢��1600�N�ł��邩��A��͂蓯�l�A��������o�Ă����ɋA���Ă������ƂɂȂ�B���Ë`�O�����N����A��A�������H���C
(�a��:���R����)�́A�`�O���ق̖k���ɉF�s�q��z���A�`�O�D�݂̒������Ă����Ƃ����B�����̍�i�͉����̌䗢�q�̐��i�ƂƂ��Ɂu�Ò����āv
�Ƃ��đ�ϒ��d����Ă����B�F�s�q�Ղ�1934�N (���a9�N)�ɔ�������A���݂͌��w��j�ՂƂȂ��Ă���B���̗q�Ղ͋`�O���ق�������Ă����̂Ƃ���
�Ȃ̂Ŏ����K�˂Ă݂��B
�F���˂̒n�������Ձi���݂̒������w�Z�j��A���Ë`�O���ِՁi���݂̒�����א_�Ёj�A�Ò�����
�F�s�q�ՂȂǂ������q�̕��n���̖k���ɂ́A�ĎR��t�������R�Ɠ������炢�̍����̏��R���A�Ȃ��Ă���B���̏��R�ɂ́A���ĕ��R��
�i������E�����{��E����Ƃ��]���j�ƍ�����Ƃ����R�邪�������B������͕��R��̎x��ł���Ƃ����B�E�C�L�y�f�B�A�ŕ��R��ɂ��Ē��ׂ�
�݂�Ǝ��̂悤�ɏ����Ă������F
�w�i���R��́j1282�N�i�O��5�N�j���A���s�̐ΐ��������{���牺�������P�@���@�����z�邵���B
�P�@���@���́A�ΐ��������{���K���̈ꑰ�ł��������A�����A�ΐ��������{�ƊW���[����������������{�i���݂̎������_�{�j�̂̒��������R��
�̗̉ƐE�Ƃ��āA�ΐ��������{�̐_����A����ő��A�m���A��ҁA��H�A���t�A�y��t��873�l�𗦂��A�D�Œ������������̍]�ɓ��������B�X��
�ʕ{�� ��k��A���N���o���Ă���܋��R�R����Вn�ɒ�߁A��q�����_�Ёi���݂̒��������_�Ёj��n�������B����������{�ɑ��āA�V����
�������������Ƃ������ƂŁA�u�V�������{�v�Ə̂����B�����́A�����̘e�ɁA�����R�����������@��ʓ����Ƃ��Č��������B�X�ɐ_�Ђ̐��ɕ��R���
�z���A�n�����畽�R���𖼏�����B������̎��ł��������Î��ƕ��R���͗{�q���g���s���Ă���A�����͍s�������ɂ��Ă������A����ɑΗ�����
�悤�ɂȂ�A�����N�ԁi1452�N - 1454�N�j�ɓ��Î���9�㓇�Ò����̒�A���ËG�v���A���R����9�㕽�R���L���Ē�������̗L�����B�s�ꂽ���R����
�w�h�ցA�ꑰ�͎������̕����ֈڂ��ꂽ�B�G�v�́A�ʕ{��̑Ί݂ɉZ�����i������j��z���ċ���Ƃ��A���R��ɂ͎��j�̒��N��z���A���R���̖���
���p���������B�܂��A�G�v�̎O�j�̖��v�͗��̉����؎��̗{�q�Ƃ��A�G�v�̈А��͋ߗׂɋy�B�x
���łɌ��y�������Ƃ����A���̓��ËG�v�i�����Ђ��A�L�B�Ɠ��ÉƏ���j�̎l�j�������ĎR��t��
�L�B�Ɠ��Î��̕���T����n�������N�@�a���i���Î狻�j�ł���B���͎R�̏�̕��R��Ղɂ��钟�������_�Ђ܂œo���Ă݂��B���������_�Ђ̒���
�̑O���͕��R��̓�邪�������Ƃ���ŁA���݂́u�������v�ƂȂ��Ă���B��������͍����ƕʕ{��͌����� ���ǂ��������B���������_�Ђ̋����ɂ�
�P�@�������i���R�鏉���啽�R�����j���A�����Ɠ`���������700�N�̑��ǂ��������B���́A������700�N�ȏ���O�ɋ��s����͂��ꑰ�Y�}
873�l�ƂƂ��ɁA���̒����̒n�Ɉڂ��Ă��āA���̒n��170�N�߂����߂����R���ꑰ�̋��S�Ɏv����y�����B
���ǂ��������B���������_�Ђ̋����ɂ�
�P�@�������i���R�鏉���啽�R�����j���A�����Ɠ`���������700�N�̑��ǂ��������B���́A������700�N�ȏ���O�ɋ��s����͂��ꑰ�Y�}
873�l�ƂƂ��ɁA���̒����̒n�Ɉڂ��Ă��āA���̒n��170�N�߂����߂����R���ꑰ�̋��S�Ɏv����y�����B
�Ńg�b�v��
�L�B�Ɠ��Î����㓇�ËG�v�̎�������ꐢ�I�قǎ��オ���邪�A��q�ɋ��ِՂ����铇�Ë`�O�ɂ͎O�l
�̌Z�킪�������B�`�v�A�v�A�Ƌv�ł���B���Îl�Z��Ɖ]���A�`�O���܂߂����̌Z��������B�`�v�����j�A�`�O�����j�A�v���O�j�A�Ƌv���l�j
�ł���B���̎l�Z��̕��e���u���Ẩp��v�Ə̂���ꂽ���Ö{�@�Ƒ�15�㓖��E���ËM�v�i1514�|1571�j�ł���B�M�v�͉i��11�N5��5��
�i1514�N5��28���j�A�F�����Î��̕��ƁA�ɍ�ƁE���B�Ɠ���̈ɍ쒉�ǂ̒��j�Ƃ��ēc�z�{�T����ɂĐ��܂ꂽ�B���̈ɍ쒉�ǂ͓��Î������̑c��
�]���A�B����͓��V�ցi���������j�Ɩ����A�u���V�ւ���͉́v����������ƂŒm���Ă���B���̒��ǁE�M�v�̍��A
���Î��͈��E���ƁE���l�O�̎��������i�݁A����ɂ͑�12�㓖��E���Ò����A��13�㓖��E���Ò������������A��14�㓖��E���Ï��v�͎�N�̂��߁A
���Ö{�@�Ƃ͎�̉����Ă����B�����ŏ��v�͑��B�Ƃ̒��ǂ𗊂�A��i6�N�i1526�N�j11���A�M�v�͏��v�̗{�q�ƂȂ��ē��Ö{�@�Ƃ̉Ɠ̌�p��
�ƂȂ����B��i7�N�i1527�N�j4���A���v�͒��ǂ̖{�̂ł���ɍ�ɉB�����A�M�v�͎������̐�����ɓ����Đ����ɉƓ��p�������B�����������c��
�o�������߂�F�B�Ɠ���E���Î��v�͂���ɕs���������A���Ï��v��S���Œ��ǁE�M�v�e�q�Ƃ̊Ԃɑ������N�������B���̑����𐧂��ĎF���̍���
���ꂵ���̂����ËM�v�ł���B���̌�A���ǁE�M�v�e�q�͎F���E����E�����O���̓�����ʂ������B����ɋM�v�͓��Îl�Z��ƂƂ��ɋ�B�����ڎw��
�R����k�ɐi�߂����A���ƈ���Ƃ����Ƃ���őS�������ڎw���L�b�G�g�̌R���ɉ����߂���s�k�����B�������F���E����̓��Ɠ����̈ꕔ
�i�����n���E���y���Ȃǁj�̗̗L���͈��g���ꂽ�B���Î���16�㓖��̍��͋M�v�̎q�A�`�v�Ɍp������A���̌�͋`�v�ɒj�q�����Ȃ������̂ŁA
�`�v�̒�̋`�O�ɁA����ɂ��̌�͋`�O�̎q�A���P�i��Ɂu�Ƌv�v�ɉ����j�Ɍp�����ꂽ�B���̒��P������̎F���˔ˎ�ł���i���F�ȏ�̋L�q�̓E�C�L�y�f�B�A�ɕ����Ƃ����ł���j�B
���́A���Ö{�@�Ƃ̋��邪���������݂̎������s�㒬�i����܂��j�n��̒n�`�����Ë`�O�̋��ِՂ�
���鈦�ǎs��q�̒n�`�Ɏ��Ă��邱�ƂɋC�Â����B�ǂ�����O���ɉ͌��ɋ߂��삪����A�w��ɂ͎R�邪����B���Ö{�@�Ƃ̋��ق͎������s�㒬��
�������w�Z�̒n�ɂ��������A���̑O���ɂ͋э]�p�ɒ�����א�i�͐�j������A����̏��R�̏�ɂ͐����邪�������B���Î��̋���͎R�̏�̏��
�[�̋��ق���̂ƂȂ������̂ł���A���Ö{�@�Ƒ�15�㓖�哇�ËM�v�͂��̐�����ɏZ�B�������苷�ɂȂ������߁A���C�ɋ߂��ꏊ�ɐV����
���z���Ĉڂ�Z�B���̏�́u����v�Ɖ]���A���݂̑嗳���w�Z�̒n�ɂ������B��l�߂̏�Ƃ��āA��א�����C���̏��R�̏�
�i���݂̑���R�����j�ɁA�������㖖�����瑱���Ă����������邪����A���鎩�̂͊ȒP�ȉ��`���̕���ł������Ǝv����B���̌�A����ɂ͓��Ö{�@��
��16�㓖�哇�Ë`�v���ݏ邵�A���\4�N�i1595�N�j�܂ŏZ��ł������A�L�b�G�g�̈��͂̂��߁A�x�G��i�����s�j�Ɉړ]�����B���̌�A����́A
�`�O�̎q�A���P�̋���ƂȂ������A���P�͒��N�o���ō����ɂ͂��炸�A�قƂ�ǂ��̏���g�����Ƃ͂Ȃ������Ǝv����B�������A�c��7�N�i1602�N�j�A
���P�̖��ɂ�蓇�Î��̖{�邪��������i�ߊۏ�j�Ɉڂ�ƁA����͔p��ƂȂ�A���̐Ղɂ͋M�v�A�`�v�̕�A�嗴�����������ꂽ�B�嗳���w�Z
�̖��O�͂��̎��̖��O�ɗR������i���F�ȏ�̋L�q���ꕔ�E�C�L�y�f�B�A�ɕ����Ă���j�B
�V�����̕ĎR�����锐��s�́A���̋��������s�ׂ̗̎s�ŁA���{�C�ɖʂ��Ă���A�������Z�Ȍ~�g�Ƃ���
�C�݂����������߁A���̗c���N���A���т��ъC������L�����v�ɏo�����Ă����ꏊ�ł���B�������A����s���̂ɂ��ẮA����܂ŏڂ����m��@���
�Ȃ������B���̂��ђ��ׂĂ݂��Ƃ���A���̒n�����ǎs��q�n��A�������s�㒬�n��Ǝ����悤�Ȓn�`�����Ă���A�����������ېV�ɂ�����
�k�z��C�푈�̕���ɂȂ��Ă��āA�V���{�R���̕��m�𑗂�o�����������Ƃ����Ȃ��炸��������y�n���ł��邱�Ƃ��킩�����̂ł��̂��Ƃ��������߂�
�������Ƃɂ���B����̐����疾���̐��ւ̈ڍs���A���{�����ł͐V���{�R���Ƌ����{�R���Ƃ̊ԂŐ푈���������B�푈�́A�c��4�N1��3���|6��
�i1868�N1��27���|30���j�̒��H�E�����̐킢�Ŏn�܂�A�������N10��21���\����2�N5��18���i1868�N12��4���\1869�N6��27���j�̔��ِ푈�ŏI������B
���̊ԁA���{�̂��������ŗ��w�c�̊ԂŐ킢���J��L����ꂽ���A�ĎR�̂��锐����A���̋������������̐킢�̕���ɂȂ����B�����̈�A�̐킢��
�s��ꂽ�N�̊��x����C�ł������̂ŁA���̐푈���C�푈�Ƃ����B�������A���ِ푈�̍Œ��Ɋ��x�͕�C����Ȗ��i�����j�ɕς���Ă���B
������s�͓��{�C�ɒ�����̐�A�L��A�I�ΐ�i��������͐�j�̉��ϕ���̏�ɑ��X�ł���B
�L��͕ĎR�R��̈ꕔ�ł�����_�x�i757m�j�������Ɏ����A�I�ΐ�͏\�����u�˂������Ɏ����Ă���B�㐙���M�i1530�|1578�j�A�㐙�i���i1556�|1623�j
���z��̓����҂ł������퍑���ォ��D�L����ɂ����āA�L��E�݂ɂ͔��f����Ƃ������邪�������B�I�ΐ�̉͌��ɂ͉z��L���̍`�p���薩��������
�̂ŁA���̎���A���̕ӂ�͐����E�o�ς̒��S�n�̈�ł������Ǝv����B���f����́A1598�N�A�L�b�G�g�ɂ��㐙�i���̉�Âւ̈ڕ��ɔ���
�p��ɂȂ����B
�Ńg�b�v��
�c��3�N�i1867�N�j�A��15�㏫�R����c��i1837�N-1913�N�j���吭��҂����A
�������Â�����A�F���ˁE���B�ˁE�y���ˁE��O�˂𒆐S�Ƃ���V���{���������ꂽ�B�V���{�͓���c��́u�[�n�[���v�i�y�n�Ɗ��E�̕Ԕ[�j��
���肵���B���̍��]�˂ł́A�u��p�}�v�Ɩ����Q�l�̈�h���Ή��u�m�̖����x���āA�]�ˎs���̗T���ȏ��Ƃ��P�����i�������グ�鋭�����l��
�s�ׂ��p�����Ă����B���̘Q�l�������O�c�̎F���˓@������ɂ��Ă��邱�Ƃ�˂��~�߂��]�˖��{�́A�����˂ɖ����ĎO�c�̎F���˓@���Ă������������B
���̎��������������ɁA�V���{�R���̎F���ˁE���B�˂̌R���Ƌ����{���̓��얋�{�E��ÔˁE�K���˂̌R�������s��x�̒��H�E�����ɂ����ďՓ˂����B
�킢�͕����ɏ���A�O���Ƃ̎���o��������V���{�������������B�s�ꂽ�����{���̏��R����c��A��Ôˎ叼���e�ہi��������A1836�|1893�j�A
�K���ˎ叼����h�i���������A1847�|1908�j��́A�؍݂��Ă�������𖧂��ɔ��������Ė��{�̌R�͂ō]�˂ɋA�����B����ȍ~�A�O�l�͒��G�Ƃ���A
�V���{�R�̒Ǔ��̑ΏۂƂ���邱�ƂɂȂ����B�����e�ۂƏ�����h������c��ƂƂ��ɒ��G�Ƃ��ꂽ���R�́A����܂ŁA�e�ۂ����s���E�A��h��
���s���i��̐E�ɂ���A���c���Δh�̎u�m�B���A���s�����g����ѐV��g��p�������܂闧��ɂ���������ł���B���Ȃ݂ɗe�ۂƒ�h��
�����x�ˁE���Z���{�˂̑�10��ˎ叼���`���i�܂�����悵���A1800�N-1862�j�̎��j�Ɣ��j�ł�����̌Z��ł���B�܂������̌������ɏd�v��
�������ʂ������ƂɂȂ铿���O�Ƃ̈�A�����ˑ�14��E��17�㓖�哿��c���������`���̎��j�ł���A�����e�ہE��h�ƌZ��ł���B�]�˂ɋA��������c��͓V�c��
�̋����̎p�����������߁A���̊��i���ɋސT�����B
�i�n�ɑ��Y�������u���v�ł��̐��U��`�����z�㒷���ˎm�͍��p�V���͒��H�E�����̐�̓����A�˂�
�ƘV�Ƃ��Ĕˎ�q�쒉�P�i�������ɁA1837�|1913�j�ƂƂ����ɂ��āA���\���̒����ˎm�Ƒ��̋ʒË��̌x�q�ɂ������Ă����B�ˎ�q�쒉�P�A�͍��p�V�����͂��߂Ƃ��钷���ˎm�́A���H�E������
�킢�ɂ͎Q�킵�Ă��炸�A�킢�I����͓Ǝ����[�g�ō]�˂ɋA�����B�͍��p�V���͍]�˂ɒ����Ɣˎ咉�P�������ɕԂ�����A�]�˔˓@�Ɏc��A������
�̑S���Y�����������B�����ăv���V�A�l���폤�l�G�h�����h�E�X�l�����瓖���̓��{�ɎO�����Ȃ��Ƃ����K�g�����O�C�i�ŐV���@�֖C�j���������B
�����ăv���V�A�D���ق��A�K�g�����O�C�ƍ]�˂ɂ��������˂̉Ɛb�c��150���ƂƂ��ɒÌy�C�����o�R���ĐV���ɋA�����B���̎��A�K���ˎ叼����h��s������
��\���o���̂ŌK���ˎm����щ�Ôˎm��200�����ꏏ�ɐV���ɍs�����B�K���˂͔ˎ�s�݂̂܂܌��_�̖��A�V���{�R�ւ̋��������߂����߁A������h�͌K���˂ɋA��Ȃ��Ȃ����̂ł���B
������h��s���V���ɍs�����͕̂ĎR�����锐��ɌK���˂̔�ђn�i6���j�Ɩ��{�̗a����́i5���j������������ł���B������h�Ɖ�Â�
�����e�ۂƓ��ɕ����ꂽ�����V���{�R�ɑ��Đ헪�I�ɗL���ł���Ƃ����v�f�����������炩���m��Ȃ��B�K���˂�����ɔ�ђn�������Ă����̂́A
�K����4��ˎ叼����d�i1644�|1717�j�����Ƒ����̂��߁A�z�㍂�c�˂Ɉڕ����ꂽ���ƂƊW����̂ł��낤���H�@��Ô˂��z��Ƃ͊W���[���A
�����S��5���A�����S��3���̔�ђn�������Ă����B����E�����ׂ̗̏���J�i������j�͉�Ô˗̂ł���A��Ô˕������Ԃ��Ă����B
�@�@�@
���͌K���˂ƒ����˂͋��s���i��̐E�������Ĉ������������B�O�E�����ˎ�q�쒉���i�����䂫�A1824�|1878�j�͏����e�ۂ����s���E�ł�����
�Ƃ��A���s���i��̐E�ɂ��������A��N���߂���A���p���͍��p�V���̐i���ɂ�莫�C�����B�q�쒉���̌�ɋ��s���i��̐E�ɏA�����̂��K���˂�
������h�ł������B
�@�@�@
�V���`�ɒ������K���ˎ叼����h��s�́A�V�����痤�H�A�K���˂̐w��������������Ɉړ������B
������h�i����21�j�͙���R��a�O�ɓ��邱�Ƃ�݂��ď��莛�ɋސT�����Ƃ����B�������A�֓����ʂ���O�������U�����ꂽ�ꍇ�A����͌Ǘ�����
���܂��̂Ŕˎ�̏��ݒn�Ƃ��Ă͕s�K�Ƃ���A�K���˗a����̂����������Ɉړ������B���́u���\���z���v�A�u�Ð���i������D�^�j�v�ɂ��
��ƒʂ��Ă����B
�@�@�@
�K���˂̔���w���ł́A���h�Ƌ����h�̊ԂŌ��_���������B�����Ď��h���哱�����������B���̍��A
���H�E�����Ő�����K���ˁA���{�������i���{���R�j�̒E�������V���{�ւ̍~��������ŁA�֓��e�n��]�킵����A�z��ɓ��荞��ł����B�K���ˎm
�����ӎO�Y�i1845�|1907�j�͂��̂悤�Ȏ҂̈�l�ł������B�K���˂̔���w���̌K���ˎm�����_�ɓ����̂ɗ����ӎO�Y�̉e���͑傫�������Ƃ����B
�V���{���͏��˂̋A���̂��߂ɓ����呍�{��ݒu���A�k�����ʂւ̎蓖�ĂƂ��Čc��4�N�i1868�N�j1��5���ɂ͖k�����������{��ݒu�����B3����
�����Ă���k������N���R���z�㍂�c�ɓ��������B�����ĉz��11�˂̏d�b���W�߂Ē���ւ̋A���𖽂����B�������A�S�R���w�����铌���呍�{��
�k������N���R�ɑ��č]�˂ւ̑����]�i�𖽂������Ƃɂ��A�z�ォ��V���{�R�͋����Ă��܂����B
4��14���ɂȂ��đ呍�{�͏��˂ɉz��o���𖽂��A19���ɖk������������ �� ��Ð������ɍ��q�i?�i��������Ȃ������A���Ɓj�A�Q�d�ɎF���ˎm���c����
�i�����j�ƒ��B�ˎm�R������i�L���j��C���ĉz��Đi�U�̑̐��𐮂����B�[4��17���A���c�E�R���ɗ�����ꂽ�V���{�R�͉z��i�U�̍����n�ł��鍂�c�ɎQ�W�����B
�܂��V��ɏ��݂��Ă������R�����R�̌R�ēy���ˎm�⑺����Y���Q�����Ėk�z����̌R�c���J����A�{���͊C�����ɔ���i�݁A�x���͏��V�R���o�R
�ŏ��o�����U�����Ă��珬��J�ɓ���A�M�Z���n���Ē�������U�����邱�ƂƂ����B�i���J�n��21���ƂȂ�A�C����i�ސV���{�R�{��
�i�F���A���B�A����Ȃ�6�ˁj��2,500�l�͍��c�E�R�����Q�d�̎w���̂��Ƃɂ������B��N�߂��͍̂��c�ˉƘV�A�V�|�\���q��ł������B���͓r����
�����A�`��ł͈ꕔ�A������i���E��z�s�`��捕��j�ցA����ł͈ꕔ�A�J�����i���E����s�J���j�ցA��͕͂ĎR����ʉ߂��ĐC��֓��������B
�����Ĕ���~�g�C�݂ŋ��K���˂�
�ՖN���̘A���R�Ƃ̊ԂŐ퓬���J�n���ꂽ�B�����Łu�ՖN���i���傤�ق������j�v�Ƃ́A���{���R�̕����w�}��
�É����v���q�傪�������������{��������Ȃ�g�D�ŁA�������͋����b�Ō��q�̍���M�Y�ł������B�����{���͂悭���������������A�R���͂̍��͔@��
�Ƃ�����A�����{���̔s�k�ł������B���������A����J�ł̐킢�A������U�h��ł������{���͔s�ꂽ�B
���Ȃ݂ɁA�F���˂̗��w�҂œ��Ðĕj�̏W���َ��Ƃ𐄐i���A�F���˂̐��R�����A�R�͌����A���˘F���݂��s���A�F���˂̋ߑ�C�R�̑b��z���������P���
������U�h��ŕ������A����a�@�ŖS���Ȃ��Ă���B�܂��A���������̒�A�����g��Y�i�����]���̌Z�A1833�|1868�j���A�k�z��C�푈�ɎQ��A�����s�̋߂��A
�O���s�\����t�߂̐킢�ŕ��������ꂪ���ƂŐ펀���Ă���B���̌�A������h�͓��k�e�n��]�킵����A�Ō�͔��ِ푈�ŐV���{���ɍ~�������Ƃ����B
�Ńg�b�v��
�@
�����̎���A����푈���I�����12�N���o�߂���1889�N�i����22�N�j�ɁA�������ɂ���Ă��Ă��炭
�؍݂��A���̂Ƃ��̌����E�̌������ƂɁu�F�������L�v�i1898�N�i����31�N�j�A�����E���z���x�X���j�����V�����l�������B�{�x���l�Y
�i�ق�Ղ₷���낤�A1865�|1912�j�Ƃ����B�������̐l�̑��݂�m�����̂́A1973�N�Ɏ������ɂ���ė��ĊԂ��Ȃ����̂��ƂŁA
�n�����u����{�V���v�ɍڂ����L���ɂ���Ăł������B�m���ȋL���͂Ȃ��̂����A���̋L���̃e�[�}�͎��������l�́u�������v�ɂ��ĂŁA
�V�����l�{�x���l�Y���u�F�������L�v�̒��Ŏ��������l�̐��i�E�C���ɂ��ď����Ă��镔�������p���A�����l���玭�����l���ǂ̂悤�Ɍ�����
���邩���Љ�Ă�����̂ł������悤�Ɏv���B���̌���A���̐V�����l�Ɋւ��邱�̎�̋L�������x�������V������Ō��������悤�ȋC������B
�������S�����̂́A�L���̕M�҂������{�x���l�Y���������u�F���l�C���i�������j�v�ɂ��Ă̋L�q���T�˓I���˂Ă�����̂Ƃ��Ď���Ă���
���Ƃł������B���͂����ƁA�u�F�������L�v�����V�����l�͂ǂ̂悤�ȑf���̐l�ŁA�ǂ̂悤�Ȍo�܂Ŏ�������
����Ă��āA�������ʼn�������Ă����l�Ȃ̂��낤���Ǝv���Ă����B
�������̐l�̌o����m�����̂́A�����������u�F�����O�x�z�̍\���|���㖯�O�ӎ��̊�w��T��|�v
�i����V�ЁA2000�N���j�ɂ���Ăł������B�����ɏ����Ă��������̐l�̌o���ɂ���āA���͏��߂Ă��̐l�����̕�Z�������Z�̑��y�ł���A
�������������Z�̑O�g�̒����w�Z�A�����q�풆�w�Z�A�������w�Z�i�����j�̋��t�ł��������Ƃ�m�����B
���Ȃ݂ɁA�{�x���l�Y�́u�F�������L�v�́A�����̎F����m����
�M�d�Ȏ����ł��邱�Ƃ͎������̋��y�j�����҂̊Ԃł͒m���Ă����悤�ŁA���a37�N�i1962�N�j�ɁA�������������w�Z���j����ɂ�蕜���ł����s�����
����B������͎������̕����Ђł���B�������̒����ɏ����Ă������{�x���l�Y�̌o���́A���́u�����Łv�̒��̖F�����i����� �̂�܂��A1915�|2012�j
���ɂ����̂ł���B�F���̓��T�[�������w�Z���@�A�����������}���ِE���A�ْ��A���������ېV�j�����Ҏ[�����A���������S���q�Z����w�����A
���ÏW���يْ��߂�ꂽ���ł���B�u�F�������L�v�́u�����Łv�����s���ꂽ�����A�F���͎������������w�Z���j����̉���Ń��T�[�������w�Z��
���@�ł��������̂Ǝv����B
�Ƃ���Ŏ��̕�Z�������Z�͖���5�N�i1872�N�j�n���̒����m�w�Z�������Ƃ���Â��w�Z�ŁA���̒����m�w�Z�a���̕�ق�
�Ȃ������������w�Z�ݗ��ɂ܂��u�ĕS�U�v�̌̎��́A2001�N�A���̑�����b�����Y������̏��M�\�������ŏЉ�����ƂŒm���Ă���B
�������Z�������������s�́A�]�ˎ���A����Ƃ̕���喼�q�쎁�i7���S��j�̏鉺���ł������B�i�n�ɑ��Y�������u���v�ŁA���̐��U��`����
�͈�p�V���́A��C�푈�����̒����˂̉ƘV��Ȍ��R�����ł������B�͈�͖k������i�R���Ă����V���{�R�ɑ��āA�����̗���ŐV���{����
�����{���Ƃ̘a�r���̒���̘J���Ƃ邱�Ƃ�\���o�������������ꂸ�A�ŏI�I�ɂ́A��C�푈�Œ��G�Ƃ��ꂽ�����e�ۂ�ˎ�Ƃ����Ôˋ~�ς�
���߂ɁA���ˁA�����˂𒆐S�Ɍ������ꂽ���H��˓����ɎQ�����Đ키���Ƃ����f����B���̌��ʁA�����鉺�Ƃ��̎��Ӓn��͐�Ɍ�������
���ƂɂȂ����B��C�푈�I����A�����˂͔p�˂����Ƃꂽ���̂́A����7���S�����2��4��Ɍ��炳�ꂽ���ߋ�����ɂ߂邱�ƂɂȂ�B���̎��A
����������˂��x�˂̎O���R�˂��瑗���Ă����̂��ĕS�U�ł������B�ˎm�����́A����Ő������y�ɂȂ�Ɗ���A�˂̑�Q�����ьՎO�Y�́A
�����Ă����Ă�ˎm�ɕ����^�����A���p�̏�Ŋw�Z�[���̔�p�ɏ[�Ă邱�Ƃ����肷��B�ˎm�����͂��̌���ɋ����������ČՎO�Y�̂��Ƃւ�
���������R�c���邪�A����ɑ��ՎO�Y�́A�u�S�U�̕Ă��A�H�������܂��Ȃ��Ȃ邪�A����ɂ��Ă�Ζ����̈ꖜ�A�S���U�ƂȂ�v�Ɨ@���A
����̐���������������B���̕ĕS�U�̔��p���̏�������č��ꂽ�̂��u���������w�Z�v�ł������B�R�{�L�O�i1887�|1974�j�́A���̂��Ƃ��ނɂ���
�Y�ȁu�ĕS�U�v�������Ă���B
�u���������w�Z�v�ɂ͗m�w�ǂƈ�w�ǂ����u����Ă����B���̊w�Z����ɐݗ����ꂽ�̂��u�����m�w�Z�v
�ŁA���ꂪ��̒������w�i�����j�ł���A���݂̒������Z�ł���B�������Z�ɂ́u���Z�́v�ƌĂ��Â��Z�̂ƁA�x����w�쎌�́u���Z�́v��
����B�u���Z�́v�́u�䂪���w�̑��̈ʒu�́A�\�͔����������́A���̏�Ɩ��������A����Ղ�O�Ɍ��āc�v�Ŏn�܂钷���̎�
�̉̂ł��邪�A���̕�Z�������Z�̑O�g�̒������w�i�����j�̍Z�̂ł���A���݂��̂��p����Ă���B�������Z���̂Ƃ��ɂ͉̂������A���݂ł��̂̈��
���炢�́A��ǂ݂Ȃ��̂����Ƃ��ł���B���́u���Z�́v�̎��̌���҂��u�F�������L�v�̒��Җ{�x���l�Y���̐l�ł��邱�ƂɋC�t�����̂͂���
�ŋ߂̂��Ƃł���B�������̕����ɂ���Ă킩�����{�x���l�Y�̐��U�͂��悻���̂悤�Ȃ��̂ł���B
���l�Y�͒�����150�Ύ��̒����ˎm�̎O�j�Ƃ��āA�c�����N�i1865�N�j2��15���ɐ��܂�Ă���B
�{�x�Ƃ͒����˂̑��n�����瑱���ƕ��i���p�Ɨw�Ȃ̎t�́j�ł������B�юs�������w�Z�E��V�㏬�w�Z���o�āA����13�N�i1880�N�j�����w�Z�i�����m�w�Z�̌�g�ɂ���
�������w�i�����j�̑O�g�j�ɓ��w�������A�݊w3�N�A����15�N�i1882�N�j12���Ɋw�Z������A����16�N�i1883�N�j1�����A19�ŕ�Z��V�㏬�w�Z��
�����ƂȂ����B���N�ɂ͒����w�Z�̋����ɓ]�g�B�g���́u���Ɛ��v�ŁA�S���́u���{�j�v�Ɓu�K���v�ł������B
����19�N�i1886�N�j4���A���l�Y�͐E�������ď㋞�A���������p��w�Z�ɓ��w�����B���l�Y������������Ă�������
�����w�Z�́A�V�����Îu�S�S���ƎO���S41�����̘A��������ɂ���Ĉێ����ꂽ�������̊w�Z�ł��������A����19�N�A��ꎟ�ɓ����t�i����18�N12��22���|
����21�N4��30���j�̕�����b�X�L��̂��ƂŎ��{���ꂽ����߂ɂ��A�����̒��w�Z�͂P����1�Z�Ƃ��ꂽ���߁A������ɂ�钆�w�Z�̐ݒu�͕s�\�ƂȂ����B
���̂��ߒ����w�Z�͑����̊�@�ɗ������ꂽ���A��������ю��Ӓ����̗����Ɗ�t���̒ɂ���āA���낤���Ē��������̎����w�Z�Ƃ��Ė�����ۂ��Ƃ��ł����B
�������A���̌サ�炭�́A�������w�Z�o�c���������邱�ƂɂȂ�B���l�Y�̎��E�E�㋞�͒����w�Z�̂��̂悤�ȏ̕ω������������Ƃ������̂ł������̂ł͂Ȃ��낤���H�@�����Ӗ璘�u�����M�����t��`�|�w�G�A�F���Ɋw�����̍��v�i�P���ЁA2000�N���j��57�Ł`59�łɂ́A���̏㋞�̗���`����
�u�V�w�v�Ƒ肷����l�Y�̕��́i�u�a����G���v5�C6���i����28�N���j�f�ځj�̈ꕔ���Љ��Ă���B���l�Y������҂ł��钷�����Z���Z�̂��q�ׂ邲�Ƃ��A
�u���ɑ�Ƃ𐬂������āc�v�Ƃ�����u������Ă̏㋞�ł������B
����19�N�̋���߂ɂ��A
5�N���̐q�풆�w�Z�ƍ������w�Z�i�������Z�̑O�g�j���ݗ����ꂽ�B�w�Z���ɈقȂ�̂����A�������w�Z�ɂ͖{�Ȃ�
��w�E�@�w�E�H�w�Ȃǂ̐��Ȃ�����A���Ȃ͊w���E�w�Ȃɂ��C�ƔN�����قȂ��Ă����B�܂����́u���v�v�ō����t�͊w�Z���ݗ����ꂽ�B
�����p��w�Z�ɂ͊����Ǝ����������ĕ���킵���̂����A���l�Y�����w���������̓����p��w�Z��
��w�\����i������ꍂ���w�Z�̑O�g�j�ɐi�w���邽�߂̕����p��ŋ�����\���Z�̂悤�Ȋw�Z�ł������Ƃ����B
���l�Y�͎��g�̌o�ϓI��������������߁A����20�N�i1887�N�j��w�Ȃɓ]�w���A���Ԃ͓����O�_�c�̖F�я��w�Z�ŋ����Ƃ��ē����Ȃ���w�B����22�N�i1889�N�j3���A
�����p��w�Z�𑲋Ƃ������l�Y�́A���̔N��10���A24�̎��A����������ɍ��S�{�V�鑺�m�i�i��������j�����q�포�w�Z�����Ƃ��ĕ��C����B
�����āA������23�N�i1890�N�j11���ɂ͓��Z�̍Z���ɏ��i�����B�������A����25�N�i1892�N�j4���A�E�������ď㋞�B���l�Y���������ɑ؍݂����̂�
2�N���قǂ̒Z�����Ԃł������B
���̌�A����27�N�i1894�N�j5������Ăђ����q�풆�w�Z�i�����w�Z�̌�g�j�̋����ɂȂ��Ă���B
����29�N�i1896�N�j1���A�����q�풆�w�Z�̐��k��g�D�ł���u�a����v�̋@�֎��u�a����G���v��7���ɎF���ł̌����E�̌������Ƃɂ����ꕶ�A
�u��F�َ��v����e�B�F���ɂ͎m���̎q��̂������Ő̂���s���Ă����Ɠ��̋���V�X�e���A�u�����i�����イ�j����v���������B����͐搶�����k�����炷��̂ł͂Ȃ��A�N���҂��N���҂��w��������̂ŁA���f�͂�{�����߂̖ⓚ�u�F�c�v�═�|�̌m�ÁA�u�Վ땨��v�� �u�O�B�{�N���́v�Ȃǂ̈Ï����s�����B����͎F�����m�c�̎m�C���ێ����A���߂邱�Ƃ��傽��ړI�ɂ������̂ł������B���l�Y���u�a����G���v�Ɋ�e�����ꕶ�̓��e�́A���́u��������v�̗�������ށA�n��ɂ�����N�������і�w�Z�ɂ��Ă̂��̂ł������B����29�N�A��̑����m�A���͑��i�ߒ����R�{�\�Z�i��������A�펀�㌳���ɏ��i�j��
���w�����Ƃ��A�{�x�����̒S�C�ł������Ƃ����B���̔N�A�{�x�͖{�����_����ł���ׂ����k��g�D�u�a����v�̉�ɐ��Ղ���Ă���B
���l�Y�͖���30�N�i1897�N�j10���A�����q�풆�w�Z�̐E�������ď㋞�B������31�N6���A
�_�c�擌�z���x�X�Ƃ̊ԂɁu�F�������L�v�o�ł̌_�������A����31�N�i1898�N�j8���ɏo�ł��ꂽ�B����32�N�i1899�N�j�A���{���������w�Z����
�ɂȂ�B����35�N�i1902�N�j6���A37�̂Ƃ��V�������������w�Z�i�����q�풆�w�Z�̌�g�ɂ��Ē������Z�̑O�g�j�ɍē]�C�B����͖{�x���2�Ή��ŁA
���Ĉꏏ�ɋΖ��������Ƃ̂����q�P�C���Z���ɏ��C�����̂��@�ɖ{�x�����ق������̂ł������Ƃ����B���Ȃ݂ɁA���̍�q�P�C�͟��̏��� �u�앪�v
�̎�l���̃��f���Ƃ��ꂽ�l���ł���B
�{�x�́u����E�����v�Ɓu���j�v��S������
�ƂƂ��ɁA�ɊĂƂ��ďm���i��h�ɂ̓��ɐ��j�̌P��ɂ��������B�܂����k��g�D�u�a����v�̍��V�̂��߂ɐs�͂����B����45�N�i1912�N�j1���A�ݕa�������B4��5���i���A���N47�B
���̑O���A4��4���t���������ĐV�����m�����狳��҂̖͔͂Ƃ��ĕ\�����ꂽ�B�R�{�\�Z�͌�N�A
���t�{�x �̂��Ƃ��u���t�������Ȃ���
�ތ����̂��̂̔@������̒��Ɏ����ݐ[�����������������v�Ɖ�z���Ă���Ƃ����B
�̂��Ƃ��u���t�������Ȃ���
�ތ����̂��̂̔@������̒��Ɏ����ݐ[�����������������v�Ɖ�z���Ă���Ƃ����B
�ȏ�̈��l�Y�̌o���ɂ��ĎQ�l�ɂ��������́A(1) �y�c���v���w���~���ɂ��u�����m�w�Z�a����v
�̐ݗ��Ƃ��̌�̓����x�i���~���Z���^�[�N��A21���A23 -49�A2012�N���A���m��w�w�p��|�W�g���j�A(2)�u���ܒ��l���`�v
�i���ܒ����y�j������A2015�N11�����j�A(3)�u�l���T�K20�@�{�x���l�Y�v�i�L�܁@2018�N11�����j�A(4)�u�ӂ邳�ƒ����̐l�X�v
�i�����s�A1989�N���j�A(5)�u�������Z�S�\���N�L�O���v�i2021�N���s�\��j�A�i6�j�����Ӗ璘�u�����M�����t�`�|�w�G�A�F���Ɋw�����̍��v
�i2000�N�A�P���Ёj�Ȃǂł���B
�Ƃ���ŁA�{�x���u�F�������L�v�̒��ŏ������Ƃ����A�u�F���l�C���v�̓����Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂�
�������̂ł��낤���H�@�܂����́u�����v�������炵�Ă���w�i��v����{�x�͂ǂ̂悤�ɍl���Ă����̂ł��낤���H�@�����{�x�̌o����m�邱�Ƃ�
�Ȃ����u�F�����O�x�z�̍\���|���㖯�O�ӎ��̊�w��T��|�v�̒��ҁA�����������͌Ñ㔹�l�̌����Œm������ł��邪�A���̖{�̒��Ŏ��́A
����܂œ��{�j�̂Ȃ��̒n��j�������ۑ�ɂ��Ă����W��A�u�������v�A�u�����C���v�Ƃ������̂ɂ��S�������Ă����Əq�ׂ��Ă���B
�����āA����Ɋ֘A����e�[�}�����ɂ����o�ŕ��Ƃ��āA�{�x�́u�F�������L�v�ɒ��ڂ��A�֘A������e�����̖{�̒��ŏڂ����Љ�ꂽ�̂ł���B
�ŋ߁A���́u�n����v�ւ̊S����A�F�����꒘�u�ߑ�̎������\21���I�ւ̓W�]�v�i���鏑�[�o�ŁA1990�N�j�Ƃ����{��ǂދ@����������A
���̖{�ł��{�x�́u�F�������L�v�̒��́u�F���l�C���v�ɂ��Ă̋L�q���Љ��Ă��邱�Ƃ�m�����B�u�F���l�C���v�̓����������炵�Ă���w�i��
�v���ɂ��ẮA������̕����Ȍ��ɂ܂Ƃ߂��Ă���̂ŁA�����ł͂��̊F�����̖{�Ɋ�Â��āA�{�x�́u�F�������L�v�̒��́u�F���l�C���v
�ɂ��Ă̋L�q���Љ�邱�Ƃɂ���B����ɐ旧���A�u�F�������L�v�ɂ�����{�x�̌����̈Ӑ}�𗝉����邽�߂̈ꏕ�ɁA�ނ��������ɂ���ė���
�O��̓��{�̐������T�ς��Ă����B
�����V���{�͎F���y��e�˂����l���̎Q�c�ɂ�鍇�c���ɂ���Đi�߂��Ă������A����6�N
�i1873�N�j�A���ؘ_�ɔs�ꂽ���F���ˏo�g�̐��������Ƌ��y���ˏo�g�̔_�ޏ������삷�邱�ƂɂȂ�B���̂Ƃ������ƂƂ��ɁA�������{�Ɏd���Ă���������
�F���o�g�̖�l�E�R�l�E�x�@�����E�������Ď������ɋA�����Ƃ����B����7�N�i1874�N�j�A�_�ޏ��͈������}��ݗ����A����c�@�ݗ��̌��������o�A
�����������ɎQ���ł��铹���J���ׂ����Ǝ咣�����B��������A���{�ɍ���J�݂����߂鎩�R�����^�� ���L�܂��Ă������ƂɂȂ����B����10�N
�i1877�N�j�A���������͎������̎m���𗦂��Đ���푈���N�������s�k�A��������R�ɂĎ����B�{�x��15�Œ������w�Z�i�����j�̑O�g�ł��钷���w�Z�ɓ��w�����̂�
����푈�I������3�N��̖���13�N�i1880�N�j�̂��Ƃł������B����푈�ɂ͒����˂̋��m������C�푈�̋w�����ƌ����āA
�V���{�R���̕��m�Ƃ��ėE��ŎQ�킵���Ƃ����B����11�N5��14���A�����̓�������v�ۗ��ʂ��I�����Ō�����ˎm���ɂ���ĈÎE�����B
����14�N�i1881�N�j�A�F���o�g�̖k�C���J��g���c���������L�����F���o�g�̎��Ɖƌܑ�F���Ɉ������������悤�Ƃ������������o���A
���{�ւ̔ᔻ�����܂����B������Đ��{�́A����J�݂̒��@�ɂ��A10�N��̍���̊J�݂�����B���̂悤�ȗ���̒��ŁA
�u����14�N�̐��ρv���N�����B����܂Ō��@����ɂ��Ă͐��{���ɂ����āA�N��匠���c���r�X�}���N���@���C�M���X�^�̋c�@���t���̌��@���������Ę_�����������B
�O�҂��x�������̂��ɓ������ƈ��]�ł���A��҂��x�������̂���G�d�M�ł��������A����J�݂̒��@�Ǝ��������āA���L���̕��������𐭕{�O�Ƀ��[�N�����^����
������Ă�����G�d�M�����{��������Ǖ�����Ă��܂����B�����ɑ�G�̃u���[���̌c��`�m�剺�������i��Ɍ��m�Ќn�j�����{����Ǖ����ꂽ�B������u����14�N�̐��ρv�Ƃ����B���̔N�A
�_�ޏ��͎��R�}�������B����ɂ́A�����y���o�g�̒��]�ĉ�i�����j��������Ă���B���N�ɂ͔�O�o�g�̑�G�d�M�����i�}�����������B����18�N
�i1885�N�j�A���{�́u���t���x�v������A������t������b�Ɉɓ��������A�C����i��ꎟ�ɓ����t�j�B�ɓ����t�ŕ�����b�߂��X�L��ɂ��
�A����15�N�i1872�N�j�ɒ�߂�ꂽ�u����߁v���p�~����A����19�N�i1886�N�j3������4���ɂ����āA�V���Ɂu�w�Z�߁v�����z���ꂽ�B�����
����т����w�Z���x����������邱�ƂɂȂ����B�{�x���l�Y�������w�Z�̐E�������ď㋞�A���������p��w�Z�ɓ��w�����̂�
����19�N�i1886�N�j4���ł��邩�璚�x���̍��̂��Ƃł���B
���āA�����Řb�����ɖ߂��ƁA�{�x���u�F�������L�v�̒��ŎF���l�̐����̓����Ƃ���
���������Ƃ͎��̂悤�Ȃ��Ƃł���B
�i�P�j�u���p�ɂ��ėE�ҁv�ł��邪�u�D�����S��v��L���Ă���B���̗F�b�S�̌����͎������
�����Ă͔��_�ł��邪�A������ɂ����Ă͌��_�ƂȂ��Ă���B�܂�A�e�ʁE���F�̗��g�o���̂��߂ɁA�������E�����E���A�Ȃ��Ă�����˔����
�̕a�������Ɏ��������Ƃ́A���Ԃ̔��U����Ƃꂴ��Ƃ���ł���B
�i�Q�j����̌��������Ƃ��܂��F���l�̓����ł���B�F���l�m���A��ʂɉȊw���D�܂��A���ɐ��w�ɕs����ł���̂́A��������C�Z���ŁA
�E�ςƗ��z�ɖR�����A��x���݂Đ������Ȃ���A���������͋y���Ƃ����Ă����������A���x���J��Ԃ��v�l���Ȃ����Ƃɂ����̂ł���B
���ɁA�F���l�́A�ꎖ��A���I�ɔ����������邱�ƁA����ш��s�ς̗��z��������A���_�I�ɔ��f���A�Njy���Ă����Ƃ������Ƃ́A����]�ނ��Ƃ�
�ł��Ȃ��B�ېV�ȗ��̎F�������l�̐l���ɂ��Ă݂Ă��A���̓_�������Ă��邱�Ƃ��F�߂���̂ł���B
�i�R�j�c���͂��������Ƃ́A�F���l�̓����Ƃ��čL�����Ԃɒm���Ă��邱�Ƃł���B���̌����Ƃ��čl�����邱�Ƃ́A���ɁA���l�i�͂�Ɓj
�Ƃ��āA�×�����̈��l�ł��������ƁA���ɁA�]���āA����A�����������ƈقȂ�A�ꕗ���Ȃ��Ă��邱�ƁA��O�ɁA�Ӌ��̒n�ɂ����āA
�����������V�R�̒n���ɂ���Ĉꍑ���`�����Ă��邱�ƁA��l�ɁA���S�N���A��Ɉ��i���Áj���Ȃ��ē������A�����I�ȕ������Ȃ��������ƁA
��܂ɁA�₦�������e�҂̑������Ă������߂ɁA���R�c�����Ă���ɔ�����K�v�����������ƁA��Z�ɁA���̐�������ɕx�݁A�����\���Ղ��A
�����Ђ������r���������ƁA�Ȃǂł���B
�i�S�j���̒c���͂̋����̌��ʂƂ��Ď��̂悤�ȓ���������������B���ɁA���d�p��ɕx��ł��邱�ƁA���ɁA��r�I�O�ɋ������āA�ǂɎカ���ƁB
��O�ɁA�e�l�Ɨ��̎v�z���B�����A�������R�̍l�����r���R�������ƁB�F���̈ꍑ�́A�S���R���I�g�D�ɂ��āA��Ӊ��B�����ŁA��l�̈ӌ���
���R�ɏq�ׂ邱�Ƃ͏o���Ȃ��B�������k�l�͌l�v�z�����B���āA�e�X�ǁX�U���ŁA�c���𐬂����Ƃ��ł��Ȃ��̂ɔ����A�F���l�m�͐ꐧ�I�c����
�r������Ȃ��߂ɁA�l�̈ӌ��͏�ɒc�̂̐��_�ɂ���Ĉ��|����A����ȏ�A���W���Ȃ��̂ł���B���������āA���_�ƌ����̂��܂��A������y�҂�
�ӌ��ɂ����Ȃ��̂ł���B
�͂Ȃ͂��茵�����w�E�ł���B�i�S�j�́i�F���l���j�u���d�p��ɕx��ł���v�Ƃ����̂́A
�������ɂ����āA�ŏ��A�F���˂͉�ÔˁA�K���˂ƈꏏ�Ɂu�������́v�𐄂��i�߂Ă����ɂ��ւ�炸�A�r�����璷�B�˂Ɩ��������Łu�����v��
�]�������Ƃ�A���H�E�����̐킢�̈������ƂȂ����A�����ˎm�ɂ��]�ˎF���˓@�P�������́A�����炪��������s�ׂɂ����̂ł���������
�Ȃǂ��O���ɂ��������̂Ǝv����B�u�F�������L�v�́A���a46�N�i1971�N�j�ɏo�ł��ꂽ�u���{���������j���W�� ��12���v�i�O�ꏑ�[�j��
���߂�ꂽ���Ƃɂ��A�����w�A�n��w�A���j�w�Ȃǂ̑����̌����҂̖ڂɐG��邱�ƂɂȂ������A�F�����̖{�ɂ��A�����A�������̗��j�w���
�傫�ȉe���͂������Ă��������Y���i1914�|1986�A����������w�����A���{�o�ώj�j�́A���̖{�́u�F�������L�v�́u���v�̒��Ŏ��ɂ悤�ɏq�ׂĂ���Ƃ����B
�u���k���˂Ɛ��쏔�˂Ƃ̌������Η��̊��ɂ́A���k���{�^�Ɛ�����{�^�̎Љ�ތ^�̑����
���������Ƃ��ł��Ȃ��B�{�x���̂悤�ȒB���̓��k�l������Y�ˌ^�̓T�^�F���̓����ɓ��藈����A�[�����ɂĂ̐��ׂȊώ@���₵�Ă��ꂽ���Ƃ́A
�w�⌤����̓V�S�Ƃ����ׂ����v
�@�@�@
�ō����̎^���ł͂Ȃ����B�ȏ�̖{�x������ь������̌����ɂ��Ă͎������낢��v���Ƃ��낪����̂����A����͕ʂɘ_���邱�Ƃɂ���
�i��������w���_�����̉�u������v�z�[���E�y�[�W �ihttps://www.kagoshima-u.ac.jp/shoujukai/�j �́u����̂Ђ�v�Ɍf�ڂ́y�z��l�E�{�x���l�Y�́w�F�������L�x�̒��́u�m�����v�ƎF���̐��w�z���Q�Ɓj�B���ɖ{�x���́u�F���l�m���A��ʂɉȊw���D�܂��A
���ɐ��w�ɕs����ł���c�v�̕����A�u�������k�l�͌l�v�z�����B���āA�e�X�ǁX�U���ŁA�c���𐬂����Ƃ��ł��Ȃ��c�v�̕����A�������́u���k���{�^��
������{�^�̎Љ�ތ^�̑�������������Ƃ��ł��Ȃ��B�c�v�̕����ɂ��Ă͂������ɋc�_������Ƃ���ł͂Ȃ��낤���B
�@�@�@
�{�x���́u�F�������L�v�ɂ͎F���l�̗e�e�E���̂ɂ��Ă̋L�q������̂ŁA���łȂ���
���̕������Љ�Ă����B����͎��̂悤�Ȃ��̂ł���B
�@�@�@
�u�l�\�{�����\�B�y�n���قȂ�ɏ]���āA���̐l���̗e�e�����ꂼ�ꑽ���̑���͂�����̂ł��邪�A
�F���l�͒��ł��������ʕ������Ă���B���Ɩڂ̊Ԃ͋߂��Ă��E�݁A��ۂ����Ċ�������ɉs���B�����̋C���������猻��Ă���B�ǂ��]���A
���љz�R�Ƃ��Ď��̂悤�ł��邪�A�����]���A���e�Ȃ����ĎE���i�ł���B�g�̂͋����ł͂��邪���N�Ƃ͉]���Ȃ��B���̊O�e�͐r���s���
�؍�痂����A����ȘJ���E����ɂ͊����邱�Ƃ��ł���ɂ�������炸�A�̓��̊�B�͈ӊO�Ɏキ�A���N���a�̐l�͐��ɋH�ł���B���̂��Ƃɂ��ẮA
���������������Ƃ��邲�ƂɎw�E���Ă���Ƃ���ł���v
�������̖{�Ŗ{�x���l�Y�������w�Z�i�����������w�̑O�g�j�̑��Ɛ��ł���A�����w�Z�ŋ����Ă������ƁA�����Ė���22�N�Ɏ������ɂ���ė��ċ�����
����Ă������Ƃ͂킩�����̂����A�ނ��������ɂ���Ă����������͓�̂܂܂ł������B�Ƃ��낪��N�i2020�N�j�̏��ߍ��A�C���^�[�l�b�g�Ō��������Ƃ���A
�����������ܒ��̍L�A�u�L�܁v�@2018�N11������
�u�l���T�K20�@�{�x���l�Y�v�Ƃ����L���ɍs��������A�����Ɉ��l�Y���������ɂ����
�����������������Ă��邱�Ƃ������B�u���ܒ��l���`�v�i���ܒ����y�j������A2015�N11�����j�ł́A���l�Y�͉m�i���w�Z�̍Z���搶�Ŗ����u�F�������L�v�̒��҂Ƃ��ďЉ��Ă���B
���ܒ��́A���l�Y�����C�����m�i���w�Z���������{�V�钬�Ƌߗׂ̒ߓc���C�F�����Ƃ��������ĕ���17�N�i2005�N�j�ɂł����V�������ł���B
�@
�{�x���l�Y�͖���19�N�i1886�N�j4���A�����w�Z�̋����������ď㋞�����������p��w�Z
�i����18�N�i1885�N�j�A��w�\����̍Z���ł��������Y�d���ɂ��n�݁j�ɓ��w���邪�A
�����ŋ����Ă����̂����������{�V��o�g�̉F�s�{����i1858�|1896�j�ł������B�F���˂͎������鉺�����ł͂Ȃ��̍����̕S�\�O�J����
�u�O��i�Ƃ��傤�j�v�Ƃ������̂�u���A�����ɔ��_���m�̕��m�i�O��m�����m�j���Z�܂킹�Ă����B�{�V��͂��̂悤�ȊO��̈�ŋ{�V�铇�ÉƂ̎���
�ł��������A�F�s�{��
�����̔��\�̎m���i�ƒ��m�j�̎q�ł���B�F�s�{�͖{�x�̎��Ώ�Ŗ���10�N�i1877�N�j�̐���푈�ɏ]�R���Ă���B�s���͍��Ɍq����邱�Ƃ͂Ȃ��A�ߖƂ����
�{�V��ɋA��A�m�i�q�포�w�Z�̑O�g�ł���{�V�鏬�w�Z�̋����ɂȂ����B�������A�F�s�{�͌��w�S�ɔR���ď㋞�A�y���̍������푾�Y���n�݂����O�H���Ɗw�Z��
���w���Čo�ϊw���w�B�O�H���Ɗw�Z�́A����@�g���n�݂����c��`�m�̕��Z�I���i���������w�Z�ł������Ƃ����B�{�x�͓����p��w�Z��22�N�i1989�N�j3���ɑ��Ƃ���ƁA���̔N��10���A
�F�s�{����̐��E�ɂ��A���ĉF�s�{�������Ă����m�i�����q�포�w�Z�ɋ����Ƃ��ĕ��C�����̂ł���B
�F�s�{���� �̏ڂ����o����
�u�L�܁v�@2018�N12�����́u�l���T�K 21 �F�s�{����v�A
�܂��́u���ܒ��l���`�v�i���ܒ����y�j������A2015�N11�����j�ɂ���Ēm�邱�Ƃ��ł���B�u���ܒ��l���`�v�ɂ��ƉF�s�{��14�̂Ƃ��ɕ��e��
�S�����Ă���B�F�s�{�́A�v���m���̎q�Ƃ��ċ��K�I�Ɍb�܂�Ȃ��ɂ���Ȃ����ɗ�Ò����A�N�q�R�Ƃ��Ă���{�x�������]�����Ă������̂Ǝv����B
��l�̊Ԃɂ͎t��̊W���z���ĐS���ʂ���Ƃ��낪�������̂ł͂Ȃ����Ƃ����̂����̐����ł���B�{�x��
�u�F�������L�v�͉F�s�{���S���Ȃ�����ɏo�ł���Ă��邪�A���́u�����v�ɂ́A�u�F���̒m�l�̉F�s�{����N�̍Z�{���o����v�̋L�q������B
�̏ڂ����o����
�u�L�܁v�@2018�N12�����́u�l���T�K 21 �F�s�{����v�A
�܂��́u���ܒ��l���`�v�i���ܒ����y�j������A2015�N11�����j�ɂ���Ēm�邱�Ƃ��ł���B�u���ܒ��l���`�v�ɂ��ƉF�s�{��14�̂Ƃ��ɕ��e��
�S�����Ă���B�F�s�{�́A�v���m���̎q�Ƃ��ċ��K�I�Ɍb�܂�Ȃ��ɂ���Ȃ����ɗ�Ò����A�N�q�R�Ƃ��Ă���{�x�������]�����Ă������̂Ǝv����B
��l�̊Ԃɂ͎t��̊W���z���ĐS���ʂ���Ƃ��낪�������̂ł͂Ȃ����Ƃ����̂����̐����ł���B�{�x��
�u�F�������L�v�͉F�s�{���S���Ȃ�����ɏo�ł���Ă��邪�A���́u�����v�ɂ́A�u�F���̒m�l�̉F�s�{����N�̍Z�{���o����v�̋L�q������B
�{�x���l�Y���{�V��̉m�i�����q�포�w�Z�����Ƃ��ĕ��C�����N�̗��N�A����23�i1890�N�j�N7��1����
�鍑�c��J�݂ɔ�����1��O�c�@�c���I�����s���Ă���B�F�s�{����͂��̑I���ɋ������琄����ė������R�}�i�����h�j�̌��Ƃ��Ď�����4��
���痧��₵�A����̖��A���I���Ă���B�������A���̗��X�N�i����25�N�j��2���A�鍑�c��̉��U�ɔ����s��ꂽ��2��O�c�@�c���I���ł́A
���{���̗��}�h�̑Η����ɋ͂�24�[���Ŕs��Ă��܂��B���̌�A�F�s�{�͌��N�����ꂸ�A����29�i1896�j�N12���ɕa�v�A���N38�ł������B
�F�s�{�͊��푾�Y�Ɍ����܂�A���̎q�v��̉ƒ닳�t������Ă������A�v��͉F�s�{�̗ՏI��������Ă��̉��ɕ��Ƃ����B
�F�s�{����v��A����34�i1901�j�N12���ɒǓ��W�u�ՎR���s�^�v�i�u�ՎR�v�͉F�s�{�̍��j�����s���ꂽ���A�{�x���l�Y�͂����Ɉꕶ���A
������ɂ߂���2��O�c�@�c���I���̗l�q�����ʂ��Ă���B���̕���ǂނƁA�{�x���l�Y�Ƃ����l�͑�σW���[�i���X�e�B�b�N�ȍ˔\���������l��
�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�F�s�{����̒Ǔ��W�u�ՎR���s�^�v�ɂ́A��G�d�M���Ǔ������Ă���B��G�d�M�͖����V���{�̎Q�c���呠���ł���A����14�N�̐��ςňꎞ���r�������̂́A���t���x�n��́A�����t�̊O����b�A
�_������b�A������b�Ȃǂ߁A�������̊O���E�����E�o�ςɑ傫�ȉe�����y�ڂ����l���ł���A����c��w�̑n�ݎ҂ł�����B����31�i1898�j�N�ɂ́A��G������i���}��
�_�����鎩�R�}���������Ăł��������}����ɁA���߂Ă̐��}���t�i�G���t�j�𑍗���b�Ƃ��đg�D���Ă���B�F�s�{�̒Ǔ��W�̑�G�d�M�̒Ǔ�����
�W���邱�Ƃ����A�u�L�܁v�@2018�N12�����́u�l���T�K21�@�F�s�{����v�ɂ��ƁA�F�s�{�͖���17�i1884�j�N�A26�̂Ƃ��ɁA
���R�����^���̓��m���]�ĉ�i�����j�炪���ď�C�ɑn�݂��ꂽ�����w�قɋ������ɊĂƂ��ď�����āA���̌o�c�ɎQ�����Ă���B
�ْ��̖��L�d�������n�ɕ������Ƃ��ł��Ȃ������̂ŁA�F�s�{���ْ��̖������ʂ�������Ȃ������B�������w�ق�
�o�c�͍s���l�܂�Z�B��G���F�s�{�̒Ǔ��W�Ŏv���o�Ƃ��ď������̂́A���̂Ƃ��ɕ������؋��̌�n�������A���{�ւ̋A���������Ă�������Ƃ�
�������B���]�����͉F�s�{�̒Ǔ��W�u�ՎR���s�^�v�����s����钼�O�ɖS���Ȃ��Ă���B
�F�s�{����ɊW���āA�t�����X�v���Ɏv�z�I��Ղ�^�����Ƃ���郋�\�[�́u�Љ�_��_�v����{��
�Љ�i�a��u����_�v�A����u�������v�j�A���m�̃��\�[�Ƃ��̂���ꂽ���]�����̖��O���o�Ă������Ƃ͎v���������Ȃ����Ƃł������B���R��Ԃɂ����Đl�Ԃ͎��R�ŕ����ȑ��݂ł���A�{���P�ǂȐl�Ԑ������邽�߂ɁA�����������Љ���̂ċ���A�Љ�_��ɂ���ė��z�I��
�����̂����v�Ƃ����̂����\�[�̎v�z�ł���B���Ȃ݂ɒ��]�������t�Ƃ����̂��A������u��t�����v�̎v�z�I�w���҂Ƃ��āA���ƌ��͂ɂ��A1911(����44�j�N�P���ɍi��Y�ɏ�����ꂽ�����{��`�ҁE�K���H���ł������B
���͖{�x�́u�F�������L�v�̒��ɁA�u�v�z�Ɓv�A�u���_�Ɓv�Ƃ��Ă̒��]�ĉ�i�����j�̖��O���o�Ă���̂ł���i�u�l���A����v�̍��j�B
���ɏq�ׂ��悤�ɁA�{�x�����w�Z���t�Ƃ��Ď������ɑ؍݂�������22�i1889�j�N10�����疾��25�i1892�N�j�N4���̊��Ԃ́A�鍑�c����J�݂���A��1��Ƒ�2��̏O�c�@�I�����s��ꂽ�����ł������B��1��̏O�c�@�I���ł́A���]�ƉF�s�{�́A���ꂼ����4��Ǝ�����4�悩�痧�����R�}�i�����h�j���痧��₵�ē��I���Ă���B��1��鍑�c��i�O�c�@�j�́A��ꎟ�R�p�L�����t�̂��ƂŁA1890�i����23�j�N11��29������1891�i����24�j�N3��7���܂ŊJ�Â��ꂽ�B�鍑�c��͋M���@�ƏO�c�@����Ȃ��@���ł��������A�O�c�@�ł͎��R�����^���̗�������ށu�����h�v����Α������߂Ă����B�R�p���t�͎{�����j�����Ŏ匠���i�����j�ƂƂ��ɗ��v���i���N�j�̖h�q�̂��߂̌R���͑������咣���A���̂��߂̗\�Z�Ă��c��ɒ�o�������A�����h�́u����ߌ��A���͋x�{�v���咣���Đ��{�Ɖs���Η������B���{�͖����h�̈ꕔ�i�y���h�j�ɑ��Đ�����H����s���A�͍��ňꕔ�\�Z�����������B����ɔ����������]�����͋c�������E���A�c��������x�ƍ���c���ɂȂ邱�Ƃ͖��������B
1891�N�i����24�j�N11��26���A��1���������`���t�̉��ŁA��2��鍑�c����W���ꂽ�B���̋c��ł́A��1��鍑�c��ƈقȂ�A�����h�͐��{�ɂ�邳�܂��܂Ȑ�����ɂ�����邱�ƂȂ��A�R�͌�����͂��ߗ��R����e����ǔ�A�C�䌚�ݔ�A���|���ݗ���A�S�����L���ĂȂǁA���{��Ă̌R���\�Z�Ă����Ƃ��Ƃ��ی������B���{�͓}�h���Ċ�]�̑����S�����݂⎄�S���L���̈Č��Ŗ����h�����_���A��������Ƃ����������ʂ��Ȃ������B�C�R�̗v�������邱�̏C���ĂɊC�R��b�E���R���I���������A12��22���̏O�c�@�{��c�ŎF���˔����{�̐��������咣����ƂƂ��ɖ����h�̊C�R�E���{�ᔻ�ɔ��_�����i������u�ؗE�����v�j�B���̌�A�����h�̐��{�ւ̔��������܂�A�O�c�@�ŏC���Ă����ĂƂ���\�Z�Ă��ی����ꂽ�B���̂��ߏ������`��12��25���ɏO�c�@���U�����߂čs�����ƂƂȂ����B���̉��U�ɔ����s��ꂽ�̂���2��O�c�@�I���ł������B���łȂ��珑���Ă����ƁA��2��鍑�c��ɂ����āA�{�M���́u���Q�����v�ł���u�������R�z�Ŏ����v�ɂ��āA�c���������������s���Ă���B
�{�x�́u�F�������L�v�ɂ́A�����̎������ɂ����鋌�m���ƕ����i�_���A�E�l�A���l�j�Ɋւ���L�q��
����������B����28�i2016�j�N�A�������ł́u�����ېV150���N�L�O���Ɓv�̈�Ƃ��āA�u�����ېV�Ƌ��y�̐l�X�v�Ƃ����{���o�ł��ꂽ���A
���̒��Łu�����ېV�Ǝs��̐l�X�|�����ېV��̏����̕�炵�v�A�u�����ېV�Ə����|���Ƃ̍ȁv�A�u�����ېV�Ǝq�ǂ��|�����̋���v�̍���
�{�x���l�Y�́u�F�������L�v�̋L�q���Љ��Ă���B���̂����A�����̕�炵�ɊW�����ԖڂƎO�Ԗڂ̍��ڂɉ�����L�q���ȉ��ɓ]�ڂ���B
�܂��A��Ԗڂ́u�����ېV�Ǝs��̐l�X�|�����ېV��̏����̕�炵�v�̍��ŏЉ��Ă���{�x�́u�F�������L�v�̒��̋L�q�͎��̒ʂ�ł���B
�� ���������ɂ����ẮC�����ېV��\���N���o���Ă��C�m�����c����������Ȃǂ̌��E���߂Ă���
�n��̎w���ғI�������ʂ����Ă����B
�� �����́C�����ꕔ�̎������s�̏��l�ȊO�͐��ɗ���ȏ�ԂŁC���Y���m�������͂��Ȃ��C�m���Ƃ̊Ԃɂ͑傫�Ȋi��������B�ېV����20�N���o���C
�����ł͎m���ƕ����̋�ʂ͌ːЏ�݂̂ɂȂ������C�������ł͖����ɖ��_�̏̍��Ƃ��ėL���ł������B
�� �������m���ɔ�אU���Ȃ����R�́C���̓���ƍl������B
�@1. �������Ȃ��B������������{�̂��ߏ��Ƃ����B�����C�_�����m�����n��ŋ����B
�@2. �m���̐l���������B�����ɔ�ׂĎ��������͎m�����������߁C�����̗͂��L�тȂ��B
���o�̒����������̒����ɂ��A�������͎l�l�Ɉ�l���m���Ƃ����y�n���ł������B
�S���I�Ȏm���̊�����6�����炢�ł��邩��A�������������ɓ���ȓy�n���ł��邩���킩��Ǝv���B�������Ɏm�����������R�͑O�ɂ��������悤�ɁA
�F���˂ł͎������鉺�����ł͂Ȃ��A�̍����̕S�\�O�J���Ɂu�O��i�Ƃ��傤�j�v�Ƃ������̂�u���A�����ɕ��m���Z�܂킹������ł���B
�O��ɏZ�ޕ��m�́u�O��m�v�ƌĂ�A�m�s�E�}�������Ȃ����߁A�_�k���c��Ŏ���������Ȃ������B�u�O��m�v�͍]�ˎ������ɂ́u���m�v��
�Ă��悤�ɂȂ�B���́u�O�鐧�x�v�ƕ���ŎF���ɂ́u�劄���x�v�Ƃ����_���x�z�̍\��������A�F���̔_���͋ߐ��Ɏ����Ă������I�Ȕ_�z��
�悤�ȏ�Ԃɒu����Ă����B�����Ƃ��������̔N�v������A���Z��������锪�����܂œ�������Ă����B���������Ď������ɂ͖����ɂȂ��Ă�����ߑ㉻���x���閯�O�w���\���Ɍ`������Ă��Ȃ������B�u�劄���x�v�̎��Ԃ�
���ẮA�������̖{�ŏڂ����q�ׂ��Ă���B
���̂��ƂɊ֘A���邪�A�{�x���l�Y�́u�F�������L�v�ɂ͑�ϋ����[���\���ڂ��Ă���B����́A
����20�N��O�����̌��ʂ̌���c�������m���ƕ����ʂɋL�������̂ł���B����ɂ��Ǝm���ƕ����̌���c�����́A�V������4��60�A����������
27��3�ł���B�m���̌���c�����̊������v�Z���Ă݂�ƁA�V��������6�p�[�Z���g�A����������90�p�[�Z���g�ł���B�V�����̎m���̌���c������
�����́A�S���I�Ȏm�����̊����Ƃقړ���������S���I�ȕ��ςɋ߂����̂Ǝv����B�Ƃ��낪���������̏ꍇ�́A�m���̊���25�p�[�Z���g�ɔ䂵��
�m�������c��ɐ�߂銄���ُ͈�Ȃقǂ̍����������Ă���B�{�x�́A���̂悤�Ȍ��ʂ������炵�Ă���v���ɂ��Ă��A�������̎Љ�̐[������
���荞��ʼns�����͂����Ă���B�{�x�̎������ł̒Z���؍݊��Ԃ��l����Ȃ�A����͋����ɒl���邱�Ƃł͂Ȃ��낤���B
���������́u�����ېV�Ƌ��y�̐l�X�v�́u�����ېV�Ǝq�ǂ��|�����̋���v�̍��ŏЉ��Ă���
�u�F�������L�v�̒��̖{�x�̋L�q�͎��̒ʂ�ł���B
�� ���������̏A�w�����̊����́A�S���Œ�ł���B�j�q�͏A�w�Ώێ����̔������z���Ă����x�ŁA
���q�͏A�w������8�`9���ɉ߂��Ȃ��B�ΐ쌧�́A�j�q��80�����A���q��60�����A�w���Ă���B
�� �������s���̏��w�Z�̒j�����2��1�����A�n���ł͍ō��ł��j���䂪3��1�Ŋw�Z�ɂ���Ă͏��q�͂��Ȃ��ꍇ������B
�� �����ł͈ېV�������20���N�o���Ă��邪�A���������͎�����A10���N�����o���Ă��Ȃ����ߏA�w�����Ⴂ�B�������̈ېV�͐���푈�ォ���
�����ėǂ��A����܂ł͕������x�������Ă����B����푈�ɂ���āA�������̐l�͐��̐i���ɒx�ꂽ���ƂɋC�t�����B
�� ����푈��Ɏ������ł͊e��w�Z�̐ݒu������ɂȂ�A����20�N�i1887�N�j���ɂ͏��w�Z�̐ϗ����i�L�͎҂���̌���������ɂ������̂ƍl������j
�͑S��3�ʁA�w�Z�̖ʐς͑S��2�ʂɂȂ����B
�F���ł͐̂���m���̎q��̂������Łu�����i�����イ�j����v�Ƃ����Ɠ��̋��炪�s���Ă������A
�{�x���V���ɋA������A�����q�풆�w�w�Z�̐��k��̋@�֎��u�a����G���v�Ɋ�e�����ꕶ�A�u��F�َ��v�́A���́u��������v�̗�������ށA
�n��ɂ�����N�������і�w�Z�ɂ��Ă̂��̂ł��������Ƃ͊��ɏq�ׂ��Ƃ���ł���B�{�x�ɂƂ��āA�������ɂ���ė��ď��߂Č���
���̋���̈�ۂ���قNj����������̂Ǝv����B�����A�{�x�͎��̂悤�ɂ������Ă���B
�u�F�l�������̕������シ��̂͂܂��ƂɌ��\�Ȃ��Ƃł��邪�A���̈���ŁA���̂��Ƃɂ̂ݕΏd���āA�w����̏���A
���ӂ����Ȃ��̂ŁA�q�����������ׂȂ��ƂŊw�Z���x��A�ƂɋA���Ă����K�����Ȃ��B�܂��w�Ɛ��т��s�ǂł����Ă����ڒ��ł���B���̂悤��
���Ƃł́A�q����������ԁA�ӑĂɗ���A���̓��]���R�l�I�e���ȒP�ƂȂ��āA�k���̎v�z�A�ϋv�̐��_�������A�w�����}���A���ɐ[���Ȃ�N���A
�����̌����ɑς��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�F�l�̋C���͂����܂ŌR�l�I�ŁA�D��ŗ��C�R�ɓ��낤�Ƃ���ɂ��W��炸�A�����ł́A�R�l�ƂȂ�҂��܂�
�������Ɋw�p��v����Ƃ��ł��邩��A����̕��w�Z�ɂ����ĎF�l���s���т�Ƃ�邱�Ƃ��o���Ȃ��̂͂��̗��R�ɂ����̂ł���B�v
�������{�V��ŋ����߂��{�x�̎����ł������̂��낤�B�{�x���l�Y�́A1894�i����27�j�N���̓c���K�g�i����@�g�ƕ��ԁA�����̉p�w�h���\���鎩�R��`�]�_�ƁE�W���[�i���X�g�j�́w�j�C�x�A31���\32���Ɂu�k�v�̖��Łu�F�P�Ɣ��l�v�Ƃ����_���\���Ă���B���̘_���͖{�x�̎F���؍ݒ��ɂ����鑫��p�������n�����ƁA�u���{���L�v�Ȃǂ̗��j������p�������j�̌�����萶�܂ꂽ���̂ł͂Ȃ��낤���B
<�NjL>
�i�P�j�������������w�Z���j����ɂ��A
�{�x�́u�F�������L�v�́u�����Łv�́A�����������}���قɏ�������Ă��đݏo�\�ł���B����31�N�ł́A���݁A
��������}���ق̃f�W�^���R���N�V���� ( https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1901155/1 �j�Ƃ��Č��J����Ă��āA�C���^�[�l�b�g�Ŏ��R��
���邱�Ƃ��ł���B�u���{���������j���W�� ��12���v�i�O�ꏑ�[�A���a46�N�i1971�N�j���j�����́u�F�������L�v�́A���́u���v�������������Y����
����āA����ɂ͂Ȃ���Ǔ_���{���Ă����ēǂ݂₷���B���̂����u�⒍�v���t���Ă��ĕ֗��ł���B
�i�Q�j�V�������������Z�L�O�����قɂ͏��a37�N�ɕ������ꂽ�u�F�������L�v���R���A����31�N���́u�F�������L�v�́u���v�̍e�{�A ����26�N�̍e�{�u�F�������v�i�Ƃ��Ɉ��l�Y�̒��j�A�{�x��Y���i���Q�n��w�����j�̊j�������E�W������Ă���B���̂��Ƃ�m�����̂́A2021�N�̂��ƂŁA�������Z��������ǒ��i�����j�̕������Y����ʂ��Ăł������B���́A2022�N��5���A���������w�Z�L�O�����ق�K�ˁA�������Y���̂����ӂɂ��A�e�{�u�F�������v������@������A���e���ڍׂɌ������邱�Ƃɂ��A���̍e�{���u�F�������L�v�̌��ɂȂ������Ƃ��m���߂�ꂽ�B�e�{�u�F�������v�̖ژ^�i�ڎ��j�́A�u�F���̖��́A�y�n�A�C��A���j�A�e�e�A�����A�����G�L�A�M���A��ʁA����A�@���A���}�A�_�ƎY���v�ƂȂ��Ă���A����Ɂu�����G�L�v���A�u�����A���o�A��A�V�Y�A�̕����ȁA�N�����s���A�����A���ŁA�K��C����C�����A�����A�H���A���h�A����A�Ɖ��A�m���A�����A�V�����A�z�X�A�����l�A���́A�n�x�A�J���A���V��m�����A����A�̌āA�����A�`�e��A�G��v�ƍׂ����������Ă���B����A1898�i����31�j�N�Ɋ��s���ꂽ�u�F�������L�v�̖ژ^�i�ڎ��j�́A�u�y�n�C�C��C���j�C�l���C�N�������C�����C�V�Y�C�̕����ȁC�K��C����C���H���C���X�C����C�n�x�C�M���C�m�����C��ʁC����C���V�C�@���C�_�ƎY���v�ł���B���҂��ׂ�ƁA�O�҂́u�F���̖��́v�Ɓu���}�v����҂ł͖����Ȃ��Ă��鑼�́A���e�I�ɂ́A�قړ������̂Ɖ]���Ă悢�B�O�҂́u�F���̖��́v�́A�Ñ㗥�ߐ��̋��ł́u�F�����v�́u�F���v�Ɩ��ˑ̐��̂��Ƃł̓��Î��̗̍��Ƃ��Ắu�F���v�̈Ⴂ���L�q�������̂ł���B
�i�R�j�e�{�u�F�������v�̖`���ɂ́u�����v������A�����ɂ́u�F�������v�������Ɏ������o�܂������ɏ�����Ă����ċ����[���B����ɂ́A�u��j�]�K�F�B�j�q�X�����P�j�ރm���j���e�]���X�x�L�Ɩ��m�A���^���o�i���B�]�n�P�j���m���ƃm�׃j�ރm���j���L�V�m�~�B���m���y�l���T�����j���v���q�k���K�@�L�n�Ń����]�K�����q�F�m��Ӄj��U���V�i���v�A�u�]�K�z�J����Ƀj�����i�K���X�j�����m�T���������Q�Y�胒��j�V�e�A�������V�n�^�j�Ƀ��x�L�R�g�j�e�A���V�i���B��䢃j�L�ڃZ���g�~�X�����m���n�]�K�ݎF�m�ԋ��R���ڃj���G�V�^������m�����j�߃M�Y�B�����~�j�V�����^�V�ȃe�]�V�m�L�O�g�i�V���ȉ�z�m���j���X���m�~�v�Ə����Ă���B����ɑ����āA�u����ł�����ɕt��������������ēǂ�ł����l�����邩������Ȃ��v�Ƃ������Ă���B
���֘A�_����
[1] �؈䏺�� :�u���Z�̌���ҁE�{�x���l�Y�́w�F�������L�x�ƒ����̐��w�v�A�������Z�������� ��76���i�ߘa3�N7��1�����s)�Ap.10
[2] �؈䏺�� :�u�z��l�E�{�x���l�Y�́w�F�������L�x�ƎF���̐��w�@�\���m���w��e�ߒ���ʂ��ē��{�̋ߑ㉻���l����|�v�A���{�Ȋw�҉�c�@�֎��u���{�̉Ȋw�ҁv�i2023�N8����)
�Ap.45-p.53
[3] �؈䏺�� :�u�z��l�E�{�x���l�Y�́w�F�������L�x�̒��́u�m�����v�ƎF���̐��w�v�A��������w���_�����̉�u������v�̃z�[���E�y�[�W �ihttps://www.kagoshima-u.ac.jp/shoujukai/�j �́u����̂Ђ�v�Ɍf��
���⑫��
�E[1] �́u���{�Ȋw�҉�c�������x���v�̃E�F�b�u�E�T�C�g �i http://jsa-kagoshima.sakura.ne.jp/�j �́u2021�N�x��2��Ȋw�̂Ђ�v
����_�E�����[�h�\
�E[2] �� Researchmap �̒��҂̃y�[�W�ihttps://researchmap.jp/shoji-tsuboi�j���_�E�����[�h�\
�Ńg�b�v��
�@
�O�����i�܂����܂Ђ����j�Ɖ]���A�u���{�X�ցi�X���j�̕��v�Ƃ��Ēm���Ă���l���ł���B���͂��̐l��
�z��E���c�i���E�V������z�s�j�̏o�g�ł��邱�Ƃ͈ȑO����m���Ă����B���̑O�����A�����ɎF���˂̗m�w�Z�u�J�����v�ʼnp�ꋳ���߂Ă������ޑ���
����l���ł��邱�Ƃ́A2016�i����28�j�N�ɁA�����������u�����ېV150���N�L�O���Ɓv�̈�Ƃ��Ċ��s�����A�u�����ېV�Ƌ��y�̐l�X�v�Ƃ������q�ɂ���Ēm�����B
�z��l�E�{�x���l�Y�ɂ��āA���낢�뒲�ׂĂ���Œ��̂��Ƃł������B�z��l�E�O�����́A�ǂ̂悤�Ȍo�܂ŎF���ˁE�J�����̉p�ꋳ���߂�悤�ɂȂ����̂��낤���H
�@���͑傢�ɋ�����������ꂽ�B
�O�����S���Ȃ������N�A1920�i�吳9�j�N�ɁA�O���Ƃ���u���܍��v�Ƃ����{�����s����Ă���B����́A�O���Ɛe���̂������s�����g����
����ĕҎ[���ꂽ���̂ŁA700�]�ł̑啔�Ȗ{�ł���B���̖{�̂����A����9�N�܂ł́u�����`�i����e�j�v�A�s�����g���ɂ�閾��9�N����I���Ɏ���܂ł́u�㔼���^�v�A
����сu�N���v���ꏏ�ɂ������̂��u�O�����|�O���������`�v�i�l�Ԃ̋L�^21�j�Ƃ��āA�u���{�}���Z���^�[�v����1997�N�Ɋ��s����Ă���B�ŋ߂ł́A2019�i�������j�N�ɁA
�����k�O���u�����ېV�̗��O���J�^�`�ɂ����|�O�����̍\�z�́v���u���⏑�X�v���犧�s����Ă���B���̉������̖{�ɂ́A�w�s���H�̂��邵�|�O�������a�S�\�N�L�O�o�Łx
�i���{�P�v�ďC�A�X��o�ŁA1986�N���j�����т��ш��p����Ă���B���́w���邵�x�́A1881�i����14�j�N�ɏ����ꂽ�O�����̎��M��e�W�炵�����A���͖����Ȃ̂ŁA
���ꂪ�u�O�����|�O���������`�v�i�l�Ԃ̋L�^21�j�Ɋ܂܂��u�����`�v�Ɠ������̂��ǂ����킩��Ȃ��B������ɂ���A�������̖{�ɂ͓����̑O��������芪��������
��̓I�ɏ�����Ă��đ�ώQ�l�ɂȂ�B�����̖{�ɕ`����Ă���A�������疾���ɂ����āA�u�������Č����̎�����������j�̎p�́A���ɐ[��������^���Ă��ꂽ�B�z�㒷���ˎm��
�����̗m���w�ҁA�L�a�c���Y�ƑO���Ƃ̈ӊO�Ȑړ_���A��q�́u�����`�v�ɂ���Ēm�邱�Ƃ��ł����B
�������{�o�d��̑O���ƁA��v�ۗ��ʁA��G�d�M�A�y���o�g�̍����A���푾�Y��Ƃ̌����������[���B�ȉ��A�����̖{�ɉ����āA�O�����̔�����ǂ��Ă݂悤�Ǝv���B
���ޑ��i�O�����j�̗c���͖[�ܘY�Ƃ����A1835�i�V��6�j�N1��7���i���z���2��4���j�ɁA�z�㍑���S���r�����̏�쏕�E�q��̎q�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B���E�q��͖����������ꂽ���_�ŁA
���������c��ł����B��́A�z�㍂�c�ˏ\�ܖ��̖ڕt���E�ɓ����V�̖��u�Ă��v�ŁA�ޏ��͏��E�q��̌�Ȃł���A�v�Ɛ�Ȃ̊Ԃɂ́A���łɈ�j�ꏗ���������B�[�ܘY�����܂��
���N���܂�ŕ����E�q�傪�S���Ȃ����B�[�ܘY��5�ɂȂ����N�A�u�Ă��v�͏��Ƃ�����A���Ƃ̂��������c�ŕ�q��l�̐������n�߂��B�u�Ă��v�̒�͎�����ˈꖜ�̈�ƁE�����
�p���ł��������i�Ԃイ�j�ł������B�����͗����Ȗ[�ܘY��������ŁA������ɌĂъA���w�A������w�Ȃǂ̊w��̏������w�����B11�ɂȂ����[�ܘY�́A
���c�˂̎�ҁE�q�g�E�|�i�Ƃ����j�̂��Ƃɓ��債�A��w���w��ł���B���̍��̖[�ܘY�͖��R�ƈ�w�̏C����ڕW�Ƃ��Ă���A
��w�͂��̊�b�Ƃ��Ă̂��̂ł������B��w�́A�����̒m���l�̈�ʋ��{�ł������B�[�ܘY�́A1847�i�O��4�j�N�A12�̂Ƃ��A��������u���Č̋�����ɂ��A�Ƃ�]�˂Ɍ��������B
�]�˂ɒ������[�ܘY�͂܂��A������ˁi�ˎ�E�������t�j�̉����~��K�˂����̖̂�O��������킳��Ă���B�����ŁA���P�̍�Ƃ��āA������ˎ�̎�w�̎t�߂��A
�s�i��֔ˎ�j�̂��Ƃ։��������A�Ȃ�Ƃ��m���ɂ��ĖႤ���Ƃ��ł����B�������A�������͂����ɒ�������B�[�ܘY�͏f���̕����Ɏ莆�������ċ����������A
��������f���Ă���B�����ŁA�w�l�Ƃ��Čق��Ă�����t��{���āA������`��𗊂��Ă��̈������˗����Ă܂�����B�����āA�^�悭�A�J�ƈ�̏��Lj��Ɖ]���l�̉ƂɁA
�w�l�Ƃ��ē��邱�Ƃ��ł����B�Ȍ�̔ނ̐l���͖��������̒��q�ł������B�ނ̐������܂́A�u�������Č����ɓw�͂���������A�N�������Ă����l������A
���͎����ƊJ������̂��Ƃ������Ƃ������Ă���Ă���悤�Ɏv����B
�[�ܘY�̊w�ѕ��́A������@��𑨂��Ċw�ԂƂ����ɂ߂Ď��H�I�Ȃ��̂ŁA�w�҃^�C�v�̐l�Ԃ̊w�ѕ��Ƃ͂܂������قȂ���̂ł������B
�ނ͎m���Ɣ_���̊Ԃ̊K�w�̏o�g�i���e�����_�A��e���m���̖��j�ŁA���̓_�A���Ԃ�n���Ă��������ł�痂�����g�ɂ��Ă����悤�Ɏv���B�Ⴆ�Η��w�̊w�ѕ��ł���B�����̓��{�ɂ́A
�܂���������͕��y���Ă��炸�A�����̑���������͖̂ؔō���ł��������A����ł������͏��Ȃ��A���̂��ߏ����͂�����������ŁA��ʂɂ͂�����菑���Ŏʂ��M�ʖ{�����y���Ă����B
�[�ܘY�͍]�ˋ��̂قƂ�́u�B�����v�ƒm���A�����ɖ{�̖M�̕M�k�̎d���𐿂������A�����Ȃ���A���m�̒m�����w��ł������B�Ȃ��ł��V�[�{���g�̖�m�Ŋw��
���쒷�p���M���w�O�����Òm��i�^�N�`�C�L�j�x�͑O��O��M�ʂ��A���ɂ͑��l�ɂ��̖{�̓��e���u�`�ł���܂łɂȂ����Ƃ����B���Ȃ݂ɁA�w�O�����Òm��x�́A�v���V�A��
�R���w���I�����_��ɖ|�����̂��A����ɓ��{��ɖ|�����̂ŁA�����E�R���E�H���i�C���j�́u�O���v�����Ắutakitek�i�^�N�`�C�L�j�v����p�i�^�N�e�B�N�X�j�ɂ���
�q�ׂ�������ł������B
�[�ܘY�̐l���̓]�@�́A1853�i�Éi6�j�N6���A�A�����J���C���h�͑��i�ߊ��y���[�����鍕�M�̗��q�ƂƂ��ɂ���ė����B���̍��A�A�����J��
�ߌ~�D�����{�̋ߊC�ɂ܂Ői�o���Ă���A�A�����J�́A�d�E���E�H����⋋���Ă����`�����߂Ă����B�y���[�͑��́C���C�t���Q�[�g�́u�T�X�P�n�i�v�Ɓu�~�V�V�b�s�v�C
�����X���[�v�́u�T���g�K�v�Ɓu�v���}�X�v����Ȃ��Ă����B���̂Ƃ��A���C�͂́u�T�X�P�n�i�v���u�T���g�K�v���A�u�~�V�V�b�s�v���u�v���}�X�v���g�q���ĉY��ɓ��`�����B�[�ܘY�́A
���b�ʼnY���s�̈�ːΌ���O�����A�y���[�̉��ڎg�Ƃ��ĉY��֕������ƁA���̐Ό��炪�s��̏��҂����߂Ă��邱�Ƃ�m���A�������ɗ��݂��݁A�z�i������j�Ƃ��Ă��̍s���
�����Y��ɕ����Ă���B�[�ܘY�A19�̂Ƃ��ł���B�@��ΑD��25�{�̋��D�A�������y�N�T���C�Ƃ����A�����̍ŐV�s�̑�C�𓋍ڂ����R�͂����āA���̓��ɗN���Ă������S��[�ܘY��
�̂��ɁA���̂悤�ɉ�z���Ă���B�u���m���q��L�m�������ƃm����m�ہ��j�����X�B毃j�k�i�������j���j���U����m���Z���ȃe�I���w�P�����B�{�i���ׂ���j�N�u���u���V�A
���̓����m�厖�j�s�X�x�V�������m�}���g�]�w���n�C�h��j�߃N���n�i�V���g�v�i�������O�f���Ap.42�j�B������u�]����u�~���̎u�m�v�ւ̕����]���ł������B
���̌�A�[�ܘY�͐��������闷�ɏo���B���̖ړI�͊C�h�̌�����킪�ڂŊm���߂�Ƃ������Ƃł������炵�����A��h��O��Ƃ������̂ŁA
���{�I�I�J�~��R���ɏP����댯��`���Ă̂��̂ł������B�]�˂���M�Z�H���Ƃ�A���������ɗ���������̂��A�k���H���A�R�A�n������n�ցi���ցj���o�āA�L�O���q�ɏ㗤�A
��������C�݉����ɒ���ցA�쉺���Ĕ�ォ������Ɏ���B���ւ̏o������������Ǘ����Ă����F���ɂ͓��炸�A�L�O����ցi���E�啪���啪�s����ցj�ɖ߂�A
��������l���E�ɗ\���i���E���Q���j�ցB�ɗ\����]��i���E���쌧�j�֏o�āA�D�ŋI�B�ɏ㗤�A�ɐ��H�������āA�O�͂Ɏ���A���C���ɓ����Ĉɓ����c�ɓ��B�A�D�ւō]�˂ɋA�����B
�]�˂ɖ߂����[�ܘY�́A���{�E�݊y�e���i�����炾�傤�j�̉��~�ɉ��l�Ƃ��ďZ�ݍ��ނ��Ƃ��ł����B���̒e���̎��Z���A�����ɂ��̊J���Ԃ��w��ꂽ�␣���k�i�����Ȃ�j�ł������B
�[�ܘY��1855�i����2�j�N�A20�̂Ƃ��ɁA���m���C�p�̑�ƁE���]�����O�Y�ɓ��債�Ă���B
���̉��]�����O�Y�́A���������m�C�p�̑n�n�ҁE�����H���̓�Ԓ�q�ŁA�H���̈�Ԓ�q���A���v�ԏێR�̐��m�C�p�̎t�ňɓ��B�R�̑㊯�E�]�쑾�Y���q��i�p���A�Ђł��j�ł������B
���D���q�̗��N�A1854�i�Éi7�j�N3���A���Ęa�e�����A���c�Ɣ��ق��J�`���ꂽ�B���{�͂���܂ŁA�]�˘p�ɂ�����C��i�����j��
���݂ɗ͂𒍂��ł������A�]�˘p�̖h���ɂ͋ߑ�I�ȌR�͂����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�Ɋ����C���̌��T�ԂقǂŔ����R�͂Ə��C���D���I�����_�ɔ������邱�Ƃ����߂��B
������āA����2�i1855�j�N6���A�I�����_���̏��C�D�X�[���C���O��������ɓ��`�i�I�����_��������̊j�A�䂩���p�D�ƂȂ�A�ό��ۂƖ������ꂽ�B���N10���A
���{�͒���ɊC�R�`�K����ݗ��B�ό��ۂ́A�q�C�p�A�@�֊w���w�Ԃ��߂̊C�R�`�K���̗��K�D�ƂȂ����B
�������疾���ɂ����Ċ��開�b�̏��C�M�A�|�{���g�͂��̓`�K���Ŋw��ł���B�������A�[�ܘY�ɂ͒���̊C�R�`�K���Ŋw�Ԏ��i���Ȃ������B
���{�́A����3�i1856�j�N6���A�z�n�Ɂu�u�����v��ݗ����A���{�̎t��ɗm�����p���w�����B����4�i1857�j�N�A�ό��ۂ肩��]�˂�
��q�B���̂Ƃ��A�ό��ۂ̉^�p���߂��̂����{�̒|���K�g�Y���ł������B���N4���A���{�͍u�����̒��Ɂu�R�͋������v�i��ɁA�u�R�͑������v�Ɖ��́j��݂��āA
�|���������ɔC�������B�|���͍����H���̂��ƂŐ��m�C�p���w�сA�������i1854�j�N�̎��_�ŁA
�C�R�`�K���̏����ɗ��������I�����_�C�R�̃w���n���h�D�X�E�t�@�r�E�X�����ɁA���˘F�g�p�@��D�D���c�@���w�̂�����C�R�`�K���ɓ��������o���̎�����ł������B
�����A���̉�q�̎������A���{��D�蓪�Ŏ��S�Ύ��̍]���\�����S������Ƃ̉��n�]���������B�����m�����[�ܘY�́A�]���@�ɂ����荞�݁A
�]�˂ɂ�����u�R�͋������v�Ɏ���������ĖႤ�ׂ��u�C���v���s���Ă���B�������A�]���̌R�͕�s�A�C�͗���A�[�ܘY�̓`�K���������Ȃ������B���̂Ƃ��[�ܘY�́A�]���@�ɂ���
�֏镽�ˎm�̖����V�i�ɁA�������R�w�̍u�`���A���̉��`�̓`���w���v�^�u�`�x��\���̕M�ʂ������Ė���Ă���B�]��ł��A�����ł͋N���Ȃ��̂��[�ܘY�̐M���ł������B
�[�ܘY�͒|���ɗ��ݍ��݁A�ό��ۂ��]�˘p���o�q���邽�߂̎��^�]�̍ۂɏ��C�@�ւ̌��K�����Ƃ��ď悹�ĖႤ���Ƃɐ��������B�[�ܘY�́A�@�֊w��q�C�p�Ɍg��鋳�t
�i�����͒���C�R�`�K���̈�����j�����ɁA�ϋɓI�ɘb�������A�^����������������B���̂Ƃ��A�[�ܘY�ɂƂ��ĈӊO�������̂́A�R�͋������̋�����C�R�m���������́A
���h�̗v�ł���C�R�����̂ɋ����K�v���Ƃ������Ƃ͂킩���Ă��Ă��A���̋��ݏo���ɂ͏��O���Ƃ̖f�Ղ��K�v�ł���Ƃ̔��z���S���Ȃ��������Ƃł������B�m�_�H���̐g�����̂��ƂŁA
�����͔ڂ������́A���m�����������̂ł͂Ȃ��Ƃ����펯���܂���ʂ��Ă�������ł���B
���̍��A���ق̖��{��s���̂��ƂɁA�u���p�����v���ݗ����ꂽ�Ƃ���������炳�ꂽ�B�����i�����j�͕��c��O�Y�i���₳�Ԃ낤�j
�i���́j�ł���Ƃ����B���c�͈ɗ\��F�ˎm�ŁA�����^���Ɋw���ƁA����3�i1856�j�N�A�]�˂ɏo�āA���v�ԏێR�ɓ��債�A�����Ő��m�C�p�ɉ����A���m���̒z��p��g�ɂ��Ă����B
����6�i1859�j�N�A���v�ԏێR�̐����Ŗ��b�ƂȂ�A�q�C�p���w�сA�����ڈΒn�ɔh������āA���V�A�̃v�`���[�`���A�A�����J�̃y���[�Ƃ̐Ղɂ������Ă���B���̂����A�ڈΒn�ł�
���قٓ̕V��C��A�T�c�̌ܗŊs�Ȃǂ�v�A���݂̎w���������Ă����B�u���p�����v�̋����͕��c������l�ł��������A�O���̎҂ɂ�����J���Ă���Ƃ����̂����������͂ł������B
����5�i1858�j�N3���A�u���p�����v�ɓ������ׂ��A�[�ܘY�͔��قɌ����A�]�˂���ɂ����B23�̂Ƃ��ł������B���̂Ƃ��A�[�ܘY�͖��O��
�u���ޑ��v�ɕς��Ă���B�w���f�͋�x�i��w�̌ÓT�w���f�x�̒��ߏ��j�̊����ɁA�w���f�x��������������肪����A�u���̏��͎n�߂Ɉꗝ�����ЁA������U���Ė����ƂȂ�A
���ɕ��i�܁j�������Ĉꗝ�ƂȂ�B�V����ĂΑ����Z���Ɏ��i�킽�j��A����������Α������ɑޑ����A���̖��킢�A���܂�Ȃ��v�Ƃ���B�u���ޑ��v�̖��O�͂����ɗR������Ƃ����B
�u�ޑ��v�Ƃ́u�ށi�Ёj���đ��i�����j���v�̈ӂł���B���̔N��6���A���{�́A��V��ɒ��J�̂��ƂŁA����̒����ʂ܂܁A���ďC�D�ʏ������n�߂Ƃ���A
�����̌܂������ɒ����B��13�㏫�R�E����ƒ�̌�̏��R�p�k��������݁A�����㗌�����ӂ��Ă����F���ˎ�E���Ðĕj���A�R�����K���w���A�{�����ɔ��a���A���N7��16���i�V�� 8��24���j�ɋ}�������B
���N50�i��49�j�ł������B
���قɂ����ޑ��́A���ٕ�s�������̎R�����O�Y�̉��~�Ɋ�����邱�ƂɂȂ����B����6�i1859�j�N�ɁA�ޑ��́u���p�����v��
������������Ă���B�������A�����̕��c�͑��Z�ł���A�u�`�͊J�X�x�Ƃ̏�Ԃł������B�ޑ��́u���p�����v����������Đl�{�[�f�b�e�B�̍q�C���ق��A�{���\�ȗm����Ɗw�ŕ������B
�킩��Ȃ��Ƃ���͐�y�ɐq�˂��B���̂����A�u���p�����v�ɂ́u���يہv�Ƃ����X�N�[�i�[�^���D�i2�`4�{�}�X�g�����A�c�����̗m�����D�j�����L���Ă��邱�Ƃ��m���B
���K��P�o�ł��Ȃ����߁A���̂܂܍`�Ɍq����Ă���̂��Ɖ]���B�����ŁA�m�Ɣ_�̐g���̍ہi����j�ň�����ޑ��̖{�̂����������B�ޑ��́A�u���يہv
���g���ĉڈΒn�̊C�Y������ɉ^��Ŕ��肳���A���v�������邱�Ƃc�Ɍ��c�����B�m���̕��c�ɂ́A���̂悤�Ȕ��z�͂܂��������������B�O���́u�����`�v�ɂ͎��̂悤�ɏ����Ă���B
�u�]�͂����ɂ����Č��c���ē����A�ڈΊC�Y���̉��͂����ɒႭ���đ��ӂɍ������ȂāA������^�����ė��v�ׂ��Ȃ�B
�����يۂ̋��`���ɒ�q����͐ɂ܂���ׂ��炸�B�C�Y���̉^���ɂ��Čo��������ɗ]�肠��ׂ��B�A�����D�Ȃ���ȂāA���l�Ɨ��𑈂����͈��͐��{�̋������鏊�Ȃ���
�m��ׂ��炴����ȂāA������{�C���ʂ��S��āA�ב��̂��߂ɊC�Y����ςނƂ��A�������ɋ�(����)���Ɓv
���c�͑ޑ��̌��c������A����6�i1859�j�N7���A���ٕ�s�������L���锠�يۂɏ��A�Y����ς�Ŏ���w�����A�剺���𗦂��āA
���n�]�B��]�n�ցi���ցj�|����]�d��]�ےÁ]��Ə��s���A����ɁA�㑍�A�������痤�����o�ē암�̋{�Âʼnz�~���A�����ŗo�z�F�����w�A������7�i1860�j�N1���A���قɋA���ė����B
�ޑ����g�́A���̍q�C�ɂ���āA�q�C���ʂƔ��D�̉^�]���w�Ԃ��Ƃ��ł����B����ɁA�����N�A���يۂɂ��2��ڂ̓��{����̍q�C���K���s���A����ɂ��ޑ��͑��ʖ��Ƃ��ď�荞��ł���B
�ޑ��́A2��ڂ̍q�C�͂��܂���C�ł͂Ȃ������悤�ł��邪�A���c�̐���������A�m���̊��߂������ď�D�����B���̌�A���D�≮�ɗ���ŁA���D�≮�̊C���̎������w�сA
����Ɋ�����݂܂ōq�s���Ă���B�ޑ��̓��̒��ɂ́A���̍��A���ɑD���g���Ėf�Ղ�����\�z���N���Ă����̂����m��Ȃ��B���̔N��3��3���ɁA�u���c��O�̕ρv���N����A
��ɑ�V���ÎE���ꂽ�B3��18�����N�����u�����v�ɕς�����B
�����������قł̐����͎��葽�����̂ł��������A�]�˂̗F�l����A��������Ȏ��A�]�˂ɋA��Ƃ̘A�������������߁A�]�˂ɋA�邱�Ƃɂ��āA
���ٕ�s���̎x�z�g�����R�h�ܘY�ɏ]���č]�˂ɋA���Ă����B�������N12���̂��Ƃł������B���̂Ƃ��A�ޑ����d�������R�h�ܘY�́A��ɓ���c��̖���Ƃ��āA�p������������ɎQ�����邽�߂Ƀp����
�n�q�������쏺���ɏ]���ēn�����Ă���l���ł���B�@�]�˂ɖ߂����ޑ��́A�����s���̒����ɔC����ꂽ���{�̏]�҂Ƃ��Ē���֕����Ă���B���̂Ƃ��̒���؍݂͒Z���������A�Z���Ёi����イ�͂��ށj
�Ƃ����l���ƒm�荇���ɂȂ����B�Z���͌�����ˎm�ŁA15�̂Ƃ��A�ː��̕s�ˎ��ɂ��A�������Y���ꂽ�B���̂��߁A��Ƃ͗��U�B�Ƃ苞�s�ɏ�����Z���́A�ޑ��Ɠ��l�A��w���痖�w�̓��ɐi�݁A
����Ɏ������l���ĉp�w�C�s���u���Ē���ɗV�w���Ă����B��ɑޑ����A����ɂ����āA����V�i���ꂢ���j�̉p��m�̏m���̂��߂̊�h�ɂƂ��č�����u�{�Ёv�̏������˗����邱�ƂɂȂ�j�ł���B
����2�i1861�j�N�A���V�A�R�́u�|�T�h�j�b�N�v�ɂ��Δn��̎������N�������B���{�́A�Ƃ��̊O����s�E���I�����i�����䂫�j������n��
�h���������A���V�A�R�͂͗e�Ղɑދ����悤�Ƃ��Ȃ��B�����ŁA���{�̓C�M���X�̗͂���A���߂ĊO����s�̖�X�R�O��猓���i���˂Ђ�j��h���B����ɊO����s�g���ɏ��i����
���R�h�ܘY�����s���邱�ƂɂȂ�A�ޑ��͂��̏]�҂Ƃ��ē��s���邱�ƂɂȂ����B���N8���A�]�˂��o�������s��́A���R�����m���m���Ɛi�B�������Δn�Ɍ������Đi�ނ����ɁA
�C�M���X�����V�A�R�͂�P�����Ă���邱�Ƃ����҂��Ă̂��Ƃł������B40���ȏ�������Ă悤�₭����ɓ���������s�́A�����ł����ׂɎ��Ԃ��₵�A10�����{�ɂȂ��Ă悤�₭�A
�F���˂́u�V�S�ہv����đΔn�Ɍ����������A�\�z�ʂ胍�V�A�R�͂͊��ɂ��Ȃ������B
�@�@�@
�Δn����̋A�H�A�ޑ��́u���A�����ɉ����ł��邩�v���l�������ɁA����ɗ��܂邱�Ƃɂ����B �]�ˎ���A�������̓��{�ɂ����āA����͐��m�����̎傽�闬�����ł��������A
���{�͈���5�i1858�j�N�ɁA���ďC�D�ʏ������͂��߁A���l�̏����C�M���X�A�t�����X�A�I�����_�A���V�A�Ƃ����сi�����܃J�����j�A����6�N�i1859�N�j�ɂ́A
���فA���l�A����i���c����j���J�`���A�{�i�I�Ȗf�Ղ��J�n����Ă����B���������āA����2�i1861�j�N���̒���́A���ۓs�s�Ƃ��Ċ�����悵�Ă����B�V���A�_�˂̊J�`�A
�]�˂���̊J�s���\�肳��Ă������A���Ή^���̍��܂�ɂ��A�����͑啝�ɉ������ꂽ�B�ޑ��́A���ɍq�C�p���C�����Ă������A�@�֊w���u�`�ł���܂łɂȂ��Ă����B
�o�_���]�˂�z�O����˂��D�D���w������ƁA����ɉ����đ��D�Z�p���������A�Ƃ��ɂ͉�q�̎�����S�����Ƃ��������B
�@�@�@
���̒���؍ݒ��ɁA�ޑ��͔����́w�č��A�M�u���x�Ƃ��������Əo����Ă���B��N�A�ޑ��́A���̏����̒��Ɂu�w���v�i�X�ցj�̂��Ƃ�
������Ă����Ɖ�z���Ă���B�ޑ��́A�L���X�g���̓`���̂������m�w���p��������Ă����A�����J�l�鋳�t�A�`���j���O�E���[�A�E�E�C���A���Y
�iChanning Moore Williams�A������: �ۗ��A1829 - 1910�j�ɁA�A�����J�̒ʐM���x�̂��Ƃ����₵���Ƃ����B���̃E�C���A���Y�́A�č�������ɑ����Ă���A�����ł̓`�������̂��ƁA
����6�i1859�j�N�A�W�����E���M���Y�ƂƂ��Ƀv���e�X�^���g�ŏ��̐鋳�t�Ƃ��Ē���ɂ���Ă����B���v2�i1862�j�N10���ɂ́A�E�B���A���Y�́A�W���[�W�E�X�~�X�勳�̊����
�����O���l�̌����ɂ���Ē���E���R�苏���n���i���R��11�Ԓn�j�Ɋ��������p���������i���{�ōŏ��̃v���e�X�^���g�̋���j�̏���`���v�����i�`���y���œ������E�ҁj�ƂȂ����B
���̎����A�E�B���A���Y�̂��Ƃ�K�ꂽ�����W��ɁA���Ď�����������Ă���B�܂��A��G�d�M�A���ޑ���ɉp��␔�w�Ȃǂ̉p�w���������B�E�B���A���Y�͂̂��ɗ�����w��
�n�݂��邪�A����c��w�n�ݎ҂̑�G�d�M�A�Z���ƂȂ銪�ޑ��ɂ��傫�ȉe����^�����B
�@�@�@
����ɋ��Â����ޑ��́A���v3�N�i1863�N�j�A���{�������g�ߒc���������Ă���Ƃ̏������ɋ��݁A���̒ʖ̌���
����V���i���ꂢ�̂����j�i�̂��̗�V�i�ꂢ���j�j�̖��O���������Ă��邱�Ƃ�l�`�ɒm�����B���̉���V���́A���ʎ��ŏZ��l�i�؋��j�̎q���ł��鉽�ÒJ�i�h�O�Y�j�Ƃ��āA
�V��11�i1840�j�N�ɁA����Ő��܂�Ă���B�V��15�i1845�j�N�A���̈��ނɔ����A5�ʼnƓ��p�����B15�̍���������C�߂��B���̍��A�O���͂����{�ߊC�ɔ���A�J�������߂铮����
�������Ă������߁A������̏K���̕K�v���������Ă����B���i���j�͍ݒ���̓��l����؉p���T�����߁A�Ɗw�ʼnp����w�Ƃ����B����5�N�i1858�N�j�ɓ��ďC�D�ʏ�����������ƁA
������J�`�n�ƂȂ�ʏ����J�n���ꂽ���߁A���{����ŊƖ��̏]���𖽂���ꂽ�B���N�V���A���{���ݗ���������p��`�K���ʼnp����w�сA��ɂ͋��t���߂Ă���B���̉p��`�K���́A
�p�ʎ��i�����j�̗{����ړI�ɁA����5�i1858�j�N�ɐݗ����ꂽ���̂ł���B�ŏ��͉p�E���E�I�̌�w�`�K���Ƃ��Ďn�܂�A�p��K������]���鐶�k�̑����ɂ��A�p��`�K���������A
�Ɨ������B�p��`�K���̐��k�͒ʎ���n��l�̎q��ł���A���t�͒���C�R�`�K���̃I�����_�C�R�R�l��A�p���l�̃��N�����E�t���b�`���[�iLachlan Fletcher�A��̉��l�̎��j�炪���߂��B
1859�N�ɃA�����J�l��D.J.�}�S�I���i�}�N�S�[���� Macgowan�j�ɉp����w��A�E�B���A���Y�i���o�j�A���M���Y�i���o�j�AR.J.�E�I���X�i�����V Walsh�j�A�t���x�b�L���A�{���̉p���
�w�сA����ɒʖ�E�Ǐ�����B���p��̒B�l�ƂȂ��Ă������B���v���i1861�j�N�́u���V�A�R�͑Δn��̎����v�̍ۂɂ́A�����s�̑ދ����ɒʖ�Ƃ��Đ��s���Ă���B�p��ʖ�̌��тɂ��A
���v3�N�i1863�j�N7���ɒ����s���x�z����i�ɔC�����A���b�ƂȂ����B���Œ����s���̉p��m�Ï��̊w���ƂȂ����B
���v3�i1863�j�N�A�F���V�c�ɝ���������{�́A12���ɕs�\�����m�̏�ʼn��l�`�̍ĕ����������邽�߁A�t�����X�֊O����s�E�r�c������S���Ƃ�����c��h�����邱�ƂɂȂ����B
���i���j���ʖ�Ƃ��Đ��s�𖽂���ꂽ�̂́A���̌����g�ߒc�ł���B�ޑ��͉��i���j�ɁA�u���������]�҂ɂӂ��킵���v�Ɣ��荞�B�u�����`�v�E�w���܍��x�Ɏ��̂悤�ɏ����Ă���B
�u���ɉ����Ĕލ��̎������T���������A�ƔM�]��������]�́A�ޒn�Ɏ���Ύ~�܂�ׂ��D�@�����o���ׂ���Ƃ̋�z�ɋ���A����A�����̏������������āA���]�҂����Ɛ������ɁA
���͔V�������v�B���N12���A��l�͒}�O�����˂̔��D�u�R�����r�A���v�i�M���E��Q�ہj�ɏ�D���č]�˂�ڎw�����B�Ƃ��낪�^�����A�r���A�D㣂̘R���Ȃǂ̌̏Ⴊ���o���A
�悤�₭�]�˂ɒ������Ƃ��ɂ́A���Ɏg�ߒc�͕i�쉫���o��������ł������i12��22���o���j�B
�@
����ɖ߂������i���j�́A�p��`�K���ɎE������J����Ȃ�����҂����e���ׂ��A���@�Ɏ��m���J�����ƂƂ��A���̏m���ɂ͑ޑ���C�������B
���̏m�ɂ́A�A�����J�l�鋳�t�t���x�b�L�Ȃǂ��Q�����A���e���[�����Ă��āA�m���͏u���Ԃ�300�������B�ޑ����m���Ƃ���p��m�͏����������Ǝv��ꂽ���A�ޑ����v�����č�����m���̂��߂�
��h�ɁA�u�|�Ёv�������������錋�ʂƂȂ����B�p��m�ɂ́A���̐g���̂܂܂̕n�����m������R�����B����Ɍ����˂��ޑ��́A��z�̔�p�ŐQ���܂�ł����h�ɁA�u�|�Ёv��
�J�݂����B�����́A�ȑO�m�荇�����Z���ЂɈ˗����A�����͌o�����������B�u�|�Ёv�́A�u���Ԃɖ��t�ɂȂ������A��h���̑唼�͒�z�̔�p���玝���Ȃ��l�X�ł���A���Ƃ��Ǝ��x��
�����Ă��Ȃ������B�Ԏ�����₤���߁A�ޑ���́A����܂ňȏ�ɁA���˂�����ōw�������D�D�̍q�C�m�A�@�֎m�Ƃ��Čق��āA���i�𑼋��ɉ^�сA
����Ŗ|�����|�����B�����������邤���ɁA�F���˂���m�w�̋����Ƃ��āA�ޑ��ɏ��و˗��������B�u�|�Ёv�̈�l�A�F���ˎm�E�L�������i恂͏��M�j�̈����ɂ����̂ł������B
���v���i1861�j�N9���ȍ~�A�ޑ����]�˂ɖ߂炸�A���̂܂ܒ���ɗ��܂��Ă����O��̎F���˂ł́A���x�A�����̓��������_�ɒB���悤�Ƃ��Ă���
�����ł������B���̍��̓��{�j�̔N�\�������o���Ă݂�ƁA���̂悤�ɂȂ�B
�E���v2�i1862�j�N3���A���Ðĕj�̌���p���ŎF���ˎ�ƂȂ����v�i�̂��̒��`�j�̕��A�v���́A�������̉^���𐄐i���邽�߁A���𗦂��ď㋞
�E���N4��23���A���c���������N����B�������c���Ɍ��W���Ă����L�n�V����F���˂̑������Δh�ߌ����q���A�v���̖��ɂ��l��
�E���N5��9���A����ɑ���v���̓��������ɂ��A�������v��v�����邽�ߒ��g���]�˂֑��邱�Ƃ�����B�v�������͎���3���ځF
�@�P�j���R�E�Ɩ̏㗌�A
�@�Q�j���C5��ˁi�F���E���B�E�y���E���E����j�ō\�������5��V�̐ݒu�A
�@�R�j�ꋴ�c��̏��R�㌩�E�A�O����ˎ�E�����t�Ԃ̑�V�E�A�C
�E���N5��21���A�v���͒��g�E�匴�d�M�ɐ��]���ċ��s���o���A6��7���A�]�˓����A7��6���A�c��̏��R�㌩�E�A�t�Ԃ̐������ِE�̏A�C������������B�i���v�̉��v�j
�E���N8��21���A�]�˂��o�����Ă̋A�H�A�����������N����B
�E���N12��24���A��Ôˎ�E�����e�ہA���s���E�Ƃ��ċ��s�ɓ���B
�E���v3�i1863�j�N7���i���z��8���j�A�F�p�푈������B
�E���N8��18���A8�E18�N�[�f�^�[�A�������̔h�̌����E��ÔˁE�F���˂����Δh�̌����E���B�ː��͂�r���A�����}�i�h���ƂV���̓s����
�E�������i1864�j�N3���A�F���˂̋v���̌��c�Ɋ�Â��Đ݂���ꂽ�Q�a��c���A�F���V�c����]���鉡�l���`���߂����āA���蝵�Θ_�i���`�x���j�̓���c��ƁA�����[���_�i���`���j��
���Ëv���E�����t�ԁE�ɒB�@��Ƃ̂������ɐ����I�Η������܂ꂽ�B���ʓI�ɋv����3�c��ɏ������A���{�̍��`���j�ɍ��ӂ������̂́A���҂̕s�a�͉������ꂸ�A�Q�a��c�͋@�\�s�S��
�ׂ��́B�F���˂����i�����������̉^���͓ڍ��B�v����3��14���ɎQ�a�����C�A�����ѓ����������Ɍ㎖������āA4��18���ɑދ����A5��8���Ɏ�������
�E���N4���A�K���ˎ�E������h�i���������A�����e�ۂ̎���j�A���s���i��ɏA�C
�E���N�i1864�j�N6��5���i7��8���j�A�r�c���������N����B���s�O��؉����̗��āE�r�c���ɐ������Ă������B�ˁE�y���˂Ȃǂ̑������Δh�u�m���A���s���E�z���̐V�I�g���P��
�E���N7��19���A�֖�i�����j�̕ρB�@���K�����i���R�㌩�E�E�ꋴ�c��A���s���E�E��Ôˎ叼���e�ہA���s���i��E�K���ˎ叼����h�i���������j�����S�ɂ����̂ŁA���̂悤��
�Ă��j���F���˂̏�������āA�㋞�o�����Ă������B�˕��Ɛ�������A�s��������B����ɂ��A���B�˂͒��G�ƂȂ�B
�E���N7��23���A��ꎟ���B�����i�`���N12���j�A�������������B�Ƃ̌��ɂ�����B
�E���N8��5���A�l���i�p�E�āE���E���j�A���͑��̉��֖C��
�F���˂́A���v3�i1863�j�N7���̎F�p�푈�Ŕs�҂ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��������A�R���Z�p�ʁA�Ƃ�킯�C�R�͂ł̐��m�Ƃ̍����v���m�炳��A
�푈��̘a�r�����o�ăC�M���X�Ƌ}�ڋ߂��邱�ƂɂȂ����B���̌��ʁA�F���˂́A1864�i�����j�N6���ɁA�m���ɂ��R���g�[�ƌR�������̐l�ޗ{����ړI�Ƃ���m�w�Z�u�J�����v���J�݂����B
���̉p�ꋳ���ɑޑ����X�J�E�g�����̂ł���B�������i1864�j�N10��17���A�ޑ��͏��ق�����āA�F���˂̌�ق��ƂȂ����B���̒���A�I�B�˂���A�˂�����ōw���������C�D�u�����ہv
�̋@�֎m�A�q�C�m�Ƃ��ċI�B�܂ŏ�荞��ʼn��D���Ăق����A�Ƃ̈˗��������̂ŁA���̎d����Еt���Ă���F���ɕ������Ƃɂ����B�u�����ہv�̋I�B�ւ̉��D�̎d�����I���āA
12�����ɒ���ɋA���Ă���ƁA�ޑ����o�c����u�|�Ёv�ɑ������N�����Ă����B�u�|�Ёv�̏����̉Z���Ђ��u�Ёv�̋����g�����݁A�u�Ёv�̊�h���ƑΗ����A������Ԃɂ������B�d���Ȃ��A
�ޑ��́u�|�Ёv�̕������f�����B
�c�����i1865�j�N�����A�ޑ��͎F���˂̑D�ŎF���Ɍ��������B�D���Ő����g�V���i�����j�̎p�������������A���t�����킷���Ƃ͂Ȃ������B
�F���˂̊J�����͗��w�Ɨm�w�̓�ɕ�����Ă����B�m�w�̐��k�̐��͓������ɑ����A�ޑ��Ƃ�ł͎J������Ȃ��Ȃ����̂ŁA�u�|�Ёv�̊�h���ł������ь��O�Ƌk�������ĂъA
����Ƃ��Ă���B�F���˂̑ޑ��ɑ���ҋ��͂�����������ł������B�͂��߂͋q�������ł��������A�F���˂͑ޑ��ɔˎm�g���i�����^�A�����傤���݁j��^����Ƃ����D�ӂ��������B
���鎞�A�ˎm�̓ޗnj��ɂ̉Ƃł̎��������ꂽ���Ƃ��������B���̂Ƃ����Ȃ�����v�ۗ��ʂ��ޑ��ɘb�������ė����B�u����͍q�C�p�Ƌ@�֊w���Ƃ���
�C�߂��ƕ��������A�{�����H�@�킪�˂͂��܊C�R�̌��݂��}���ł���B��킭�́A����̒m�����F���C�R�ɑ݂��Ă���Ȃ����v�B����ɑ���ޑ��̕ԓ��͎��̂悤�Ȃ��̂ł������B
�u�H���ہA�]�͊C�R�m�������~�����B���D���Ƃ̐��b������Ƃ���ӁB�ځi�����j�ӂɊC���i�C�R�j�̎��A���{�y�я���ˊF���ɔV�ɒ��ӂ���B�̂ɑ��̐l���Џo�ł��̗͑傢�ɐU�͂�B
�����ď��D�̎��Ɏ���Ă͖w�ǒ��ڂ���҂Ȃ����@���B����{�M�����̕�����Ďm�я���ڂނ̕��K�Ɉ���ׂ��B�]�͎���ʁi�͂��j�炸���̔ڏ��̕������i���j�߂�(��������)���ׂ߁A
���D���Ƃ̐��b�����Ɗ�]����̂݁v�B�������̑�v�ۂ����̎��_�ŁA���{�S�̂́u�x�������v�̂��߂ɁA�Y�Ƃ������A�f�Ղ�U������K�v���Ɏv�������Ă���킯�ł͂Ȃ������B
�ޑ��́A�F���ˉƘV�E�����ѓ��₻�̑��̎u�m�ɐڂ��Ĕˏ��₤�ƁA�˂̑吨���|���Ōł܂��Ă��邱�Ƃ�m�����B�ޑ����l���Ă����̂́A
���{���吭��ɕ�҂��A�����č������h�̔�p�ɋ����ׂ���̗̒n�����[���A���̕s�����͑��ɕ��ۂ��āA���X�ɍ��������v���Ă������ł������B�������������ɂ́A�����ɂł�
�]�˂ɋA��A���m�V�m�̗L�͎҂ɖd��A���̕����`�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��ƍl����悤�ɂȂ����B���x���̂Ƃ��A�ޑ��ٕ̈�Z�̏�얔�E�q��̑�a���A�F�l�����̎�ɂ���ē`����ꂽ�B
�ޑ��͂���K���ƁA�x�E����o���A�c�����i1865�j�N12��1���ɎF�����o�`���A�]�˂��o�R����12��21���A�����ɋA�����B�ޑ��͎F������ɂ���Ƃ��A�˖��������āA�����ɑ���ׂ��l��
���E���������ꂽ�̂ŁA�����ˎm�E�L�a�c���Y�𐄑E����ƁA�K�������̘J�����ׂ��Ɩ�����ꂽ�̂ŁA������A�����`���Ē����Ɏ���A�L�a������������A���ɂ��̖ړI��B����
���Ƃ͂ł��Ȃ������A�Ɓu�����`�v�ɏ����Ă���B�����ˎm�E�L�a�c���Y�́A���{�������̐��w�����߂Ă����m�w�҂ł���B�������i1984�j�N�A���{�̕����w����𖽂���ꂽ���A
�܂��Ȃ��a�Ə̂��Ď��E���A�����̒����ɋA���Ă����B
���́A�ޑ����F���ɑ؍݂��Ă����c�����i18965�j�N��2�����A���C�M�̐_�ˊC�R���������ɔ����A���̏m��20�����������ѓ��̐��b��
�������ɑؗ����Ă���A���̒��ɉL�a�c���Y�ٕ̈���A����x�n�i1847�|1911�j �������̂ł���B���̎����͋˖��l���́u���ܐl����151�v�i2010�N5��31���t�A����{�V���j�Œm�����B
������2������A����Ɉړ����A��{���n�𒆐S�ɁA�F���˂̉����̂��ƂŋT�R�В����N���������A�������ł̑؍݊��Ԃ��ޑ��Əd�Ȃ��Ă���̂ŁA�����炭�ޑ��Ɣ���͎������ʼn����
����̂ł͂Ȃ��낤���B����́A���̌�A����̉���V�̉p�ꎄ�m�ɎF���ˎm�Ƃ��ē��m���Ă���B����́A��{���n�́u�C�����v�̈���Ƃ��Ċ��A�����Ȃ��Ă���A�����J�ɓn��A���D�Ƃ��w�сA�_�ސ쌧�ؒ��i���E���l�s�ؒ��j�ɔ������D�����������B�������A���N��A�o�c�Ɏ��s���ē|�Y���Ă���B�ӔN�ɂ́u�����C�ہv�Ƃ����C�e�����ď��M����Ă���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�_�ˊC�R�������́A�������N�i1864�N�j5���ɁA���{�R�͕�s�̏��C�M�̌����ɂ��A���{���_�˂ɐݒu�����C�R�m���{���@�ցE�C�R�H����
���邪�A���N7��19���́u�֖�̕ρv�̐ӔC�����A���N11��10���A�������{�R�͕�s���Ƃ��ꂽ���Ƃɔ��������ꂽ�B�F���ˎm�Ō�̊C�R�叫�E�ɓ��S�����_�ˊC�R�������̏m����
���������A�����������}���ُ����́u�C�R�����ɓ��S���N�V���сv�ɂ��ƁA�������̕���A�ɓ��͍s�����킩��Ȃ��Ȃ����Ƃ����B��N�̈ɓ��̉�ڒk�ɂ��ƁA�ɓ��͂��̎��A�]�˂�
�����A���{�́u�R�͑������v�ɓ����������A�J�X�x�Ƃ̏�ԂŁA��ނȂ��A�����E�����ɋA���Ă����L�a�c���Y��K�ˁA�L�a�̎���Ɋ�h���A�q�C�p�̋��������Ƃ����B�L�a�̖��O��
���ꂾ���悭�m���Ă����Ƃ������Ƃł��낤�B�@�����1865�N2���ȍ~�̎��ł���A�ɓ����������玭�����ɋA�����̂́A1866�N4���ł��邩��A�ޑ����L�a��K�˂�1865�N12���ɂ́A
�ɓ��͉L�a�̎���Ɋ�h���Ă����̂ł���B��N�A�ޑ��́A���́A�L�a���F���˂̏��قɉ����Ȃ������̂��A���̗��R���A�ɓ��̉����k�i�u�W��lj��v�i�u�������w�ǖ{�v�l���ҏ����j���Q��
�j�ɂ���Ēm�����A�Ɓu�����`�v�ɏ����Ă���B�ޑ����K�˂����A�L�a�̂��Ƃɂ́A���ɖ��{����R�͖��i�ւ̏��������Ă��āA�L�a�͂���ɉ����邱�Ƃ����߂Ă����̂ł���B��ɁA
�L�a�́A���C�B�̐����ɂ��A���{�ڕt���ɏ��i���Ă���B���{������A�L�a�͒����ɋA��A�������i1867�j�N�A38�ŕa�v�����B�u���{�̐��w100�N�j�@��v
�i�u���{�̐��w100�N�j�v�ҏW�ψ���, ��g���X, 1983�N�j�Ɂu���w���ǂ��ł���l�v�Ƃ��Ė����c���قǂ̐l�ł������B
�]�˂ɋA�����ޑ��̂��ƂɁA���b�ŋ��s����g�̑O�������Y�Ƃ����l���A���l���c���ċ}�����A�Ռp�������Ȃ��A�Ƃ̘b�������炳�ꂽ�B
�c��2�i1866�j�N 3���A�ޑ��͑O���Ƃ̗{�q�ƂȂ�A�Ɠ��p���őO������Ɩ�������B�ޑ��͖��b�ƂȂ����̂ł���i�Ȍ�A�u�ޑ��v���u�O���v�ƋL���j�B���̔N1���A�������c��������
�N����A��{���n���P�����ꂽ�B���N8���A�O���́A���{�J��������̏��{�����v�̏Љ�ŁA�J�����̔���i�ق�₭�j�M�L���ɂȂ����B����́A�����������|�����e���C������
�M�L����Ƃ����d���ł������B���{�͑O���̎d���Ԃ�A���̊w�˂ɍ��ꍞ�݁A�c��3�N�i1866�N�j 5���ɁA�u�J�������w�����v�̃|�X�g��p�ӂ��A����ƂȂ����B�������A
�O���͂�������ނ����B�O���������̂́A���ɕ�s���̎�t���ł������B
����ɐ旧���A�c��2�N�i1866�j�N12���A����B�����̎��s�A14�㏫�R�Ɩ̋}�����āA���R�㌩���ł������ꋴ�c�삪15�㏫�R��
�A�C�����B�c��͍F���V�c�̕���ŁA�c��3�i1867�j�N����9���ɓV�c�ɂȂ���������̒����Ȃ��܂܁A���ĂɂȂ��Ă������ɂ̊J�`���Ƃ�i�߁A�J�`���̌��Ƃ�������āA5��29���A
�������B�����āA7���ɂ́A���ɕ�s�E�ēc�����獄���i�����Ȃ��j��h������Ɏ������i��㒬��s�Ƃ̌��C�j�B�O���ɂ́A�_�ˊJ�`�ɔ����ł�ېőq�ɂ̎������w�ԂƂ����Ӑ}��
�������B���̌�A���j�͑傫���������B���N10���A����c�삪�吭��ɕԊҁA11���A���s�ߍ]���ō�{���n�ƒ����T���Y���ÎE�����B12���A�������ẪN�[�f�^�[���N����A
����r���̐����̐����ł���B���c��4�i1868�j�N1���A���H�����̐킢���u���A5���A�܂����̌䐾�������z�����B4���A�]�ˏ閳���J��B���H�����̐킢���N�������Ƃ��A
�O���͕��ɕ�s���̎x�z�����Ƃ��Đ_�˂ɂ����B����ΓG�n�̐^���������ɁA���c���ꂽ�悤�Ȃ��̂ł��������A�������Q�Ă��A�Ŋւɋl�ߐ�Ŏc�������ɂ�����A���R�Ɖ�����
�F�����ɕ�s���������n���ۂɁA���������̈�R�������悤�ɐS�������Ƃ����B
�]�˂ɖ߂����O���̎��ɁA��v�ۈꑠ�i���ʁj���s�����s������ɑJ���l���ł���A�Ƃ̕��]���������Ă����B�������A�O���̍l���ł́A�J�s�̒n�͍]�˂łȂ���Ȃ�Ȃ������B
�����ŁA�O���͌��������v�ۂɓ͂��邱�Ƃɂ����B���̌������̑��Ă��{�l�̎苖�Ɏc���Ă����̂ŁA���̓��e��m�邱�Ƃ��ł���B�������ɂ͕������Y�����Ă��āA
�����ɏq�ׂ��Ă���A�J�s�̒n���]�˂łȂ���Ȃ�Ȃ����R�̗v�_�́A���悻���̒ʂ�ł���A�����������͂�����B
�i�P�j �吭�{���݂̒�s�́A�鍑�̒����̒n�łȂ���Ȃ�Ȃ��B�����̉ڈΒn�J��̂��Ƃ��l����ƁA�Q�͕s�ւł���A�]�˂����ӂ��킵���B
�i�Q�j �Q�͉^�A�֗̕��Ȓn�ł���Ƃ������A����́A�a�`���D�̎���̂��Ƃł���B���ꂩ��͑�^���C�D�̎���ł��邩��A���������邱�Ƃ��ł��A�܂��C�������
�֗��ȓy�n�ł���K�v������B���̓_�ŘQ�͂ӂ��킵���Ȃ��B����ɔ����āA�]�˂͊��ɒz���ꂽ�C��𗘗p���āA���S����^�D���q���`��e�Ղɑ��邱�Ƃ��ł���B�܂��A
���{��i���I�����̑n�Ƃ������S�E���D���j���߂��A�C�U���e�Ղł���B
�i�R�j �Q�͎s�O�A�l�ʂ̓��H����襂ōx�O�̕�����L���Ȃ��̂ŁA�����̑��s�Ƃ��Ă̔��W�͖]�߂Ȃ��B����ɔ����āA�]�˂̒n�͔����̓��H�͍L���A�l�ڂ̉_�R���͂邩
�����Ɍ�����قǍL���̂ŁA�����̔��W���]�߂�B
�i�S�j �Q�̎s�X�͋����ɂ��āA�Ԕn�𑖂点��̂ɓK���Ă��Ȃ��B��������z����ɂ́A�o��������݁A�����̖�����K�v�Ƃ���B����ƈقȂ�A�]�˂̎s�X�͓��H���L���A
��̍H�����K�v�Ƃ��Ȃ��B
�i�T�j �Q�ɑJ�s����ƁA�c���E�����E�v�l�̉��~�E�w�Z�ȂNJF�V�z����K�v������B
�������A�]�˂ɂ́A���ɁA�傫�Ȋw�Z�A����̔˓@�A�L�i�̓@�������Ă���̂ŁA�����𗘗p����H���̕K�v���Ȃ��B
�i�U�j �Q�͒�s�ɂȂ�Ȃ��Ƃ��A���ނ�S�z����K�v�͖����B�������A�]�˂͒�s�ƂȂ�Ȃ���A�s���͎l���ɗ��U���āA�������铌�C�̈ꊦ���ƂȂ��Ă��܂��ł��낤�B
��s���]�˂ɑJ���ƁA�S���̎s���͈��g���A�O���ɑ��ẮA���E�����̑�s��ۑ����邱�Ƃɂ��A�c���̈̑傳���������Ƃ��ł���B
���o�l�́A�u�]�ˊ��m�@�O������v�Ƃ������߂��B���̌������������ɂ��đ�v�ۗ��ʂɓ͂��邩�����ł������B����͍������Ă���A
�ʏ�̔�r�ւł́A�����ɓ͂����ǂ����ۏł��Ȃ������B���̂Ƃ��A�p�����g�p�[�N�X���������悷�邽�߂ɑ��ɍs���Ƃ�����������B�����őO���͎��������̒ʖ�̈����
�����ĖႨ���ƍl�����B�l����H���Ă����ƁA���{��ʖA�[�l�X�g�E�T�g�E�ɂ��ǂ蒅���B�T�g�E�͑O���ɍD��ۂ�����A�ނ̖]�݂��A�����̏��C�D�ɏ悹�āA���܂ʼn^��ł��ꂽ�B
�������A�p�[�N�X�̑��؍݂̊��Ԃ͒Z�������̂ŁA���̊Ԃɑ�ォ�狞�s�܂ő����^�сA��v�ۂɌ���������n���邩�ǂ����A�m�͂Ȃ������B�����ŁA��ނȂ��O���́u���g���A
�g���i�g���j�����i��j��āA����𑗒�v���A���s�։^�����B�������͊�ՓI�ɑ�v�ۂ̋��ɓ͂��A���̓��e���ᖡ�������ʂ��A�]�˂ւ̑J�s�ƂȂ����B����́A��N�A�O�����V���{�ɏo�d���A
��v�ۂƌ��t�����킷�@��K�ꂽ�Ƃ��Ɋm���߂�ꂽ���Ƃł���B
�]�ˏ邪�����J�邳�ꂽ����A�֓��A�k�z�A���k�A�ڈ̊e�n�ŐV���{�R�Ƌ����{�R�Ƃ̊Ԃ̐킢�͑������B�������i1868�j�N5��15���A
���̎R�ɗ����Ă����������b����Ȃ鏲�`���́A�킸�������ŕ���A�ב������B���N����24���A��O���̈�A�c���Ƃ̋T�V��������@�Ƃ𑊑����A�x�{�i���E�É��s�j��70���������āA
�V���ɗ��˂����B���̎��_�ŁA�����b�ɂ͎��̎O�̑I�������������B�P�j����i�V���{�j�Ɏg����A�Q�j�A�_����A�R�j�x�{�ւ̖��\�ڏZ�B�O�����I�������̂́A�R�j�ł������B
�O���͔˘V���C�M���A�x�͔˗��狏�Y���i�̂��ɗ��狏���ɏ��i�j�ɔC����ꂽ�B�s����r��ꂽ�O���́A���߂Ė���2�N��������A���B�����s�ɔC����ꂽ�B�V����ɉ����āA
�M�Z�̍����܂ł̖�8���̒n��������ł������B
����2�N6��17���A�F���E���B�E�y���E��O��4�˂��u�ŐЕ�ҁv�i�̓y�Ɛl����ɕԏ�j�A����ɂ��A�x�͔˂͐É��˂Ɩ��O��ς����B
��������A�V���{�͊������ʏ̂�p���邱�Ƃ��ւ��A恁i���݂ȁA�����̖��j���g�p����悤�A�ʒB���o�����B�����Ɏ����āA�����Ƃ��Ɂu�O�����v���a���������ƂɂȂ�B�u����v��
�ʏ̂ŁA�u���v���O����恂ł������B���˂̍s��������s���p�~����A�V���{�͒����W������ڎw���āA�n���s���̐l�ނ𒆉�����h������悤�ɂȂ����B�O���͒����s�̐E��������A
�É��ɖ߂�A���߂āu�J�Ɩ����Y�W�v�ɔC����ꂽ�B�˗��̕��Y��Ђ�n����ł������B���̒����ɒ��肵�Ă���Œ��A�V���{�̖����Ȃ���O���ɏo�d���߂��͂����B�㋞��
�Ė����ȋ㓙�o�d��q�������̂́A����2�N12��28���̂��Ƃł������B
���̍��̐V���{�����������́A���т��ѕς���Ă��Ă킩��ɂ����B�u�呠�v�Ɓu�����v�̓�Ȃ��A���̌����ɂ����ďd�Ȃ邱�Ƃ������A
���߂邱�Ƃ����������B����2�N8���A�����Ȃ͑呠�Ȃɕ�������邪�A���N��7���ɂ͍ĂсA�����A�����Ȃ͓Ɨ�����B�����Ȃ͂܂��a�����Ă��Ȃ������B�O�������������Ƃ��̖����Ȃ́A
�������呠�����ɗ\�F�a���ˑO�ˎ�E�ɒB�@�邪���߂Ă���A���̉��Ŏ�����̑S�����������Ă����̂����i�����Ӂj�̑�G�d�M�ł������B���̉��̏���i���傤�䂤�j��
���B�ˎm�E�ɓ������A���i�������傤�A�i���o�[4�j�����E���]�ł������B���������E��v�ۗ��ʁE�،ˍF�[�i�����悵�j�́u�ېV�̎O���v�́A�e�Ȃ̏�ɒ��R�Ƃ��Ă����B
�V���{���ōő�̎����͂�����A�s���̒������閯���Ȃł͂��������A�n���ȍs����r�Ɓu�\�z�́v���������l�ނ��s�����Ă����B���̌���O���̂悤�ȋ����b�����߂Ă����Ɖ]���Ă悢�B
�O���́A�����x�����߁A�V���x��n�邽�߂́u�����|�v�ɎQ�悵�Ďd���������B�������e�́A�d�Ő��x�A�w���̕���A�x�ʍt�̓���A�ݕ����x�A�\���̉��v�A�ːЕҐ��A�d�M�E�S���Ȃ�
����ɓn�����B��G�͑O����]�����A�����|�̂܂܁A�d�Ō����i����̂��݁A7���j�ɏ��i�������B�悤�₭�O���́u�t�C���v�ɂȂ����̂ł���B����3�N5��10���t�ŁA�d�Ō����̂܂�
�w�����������C���邱�ƂɂȂ����B
����4�N7���́u�p�˒u���v�ɑΉ����āA���N6���A��v�ۂ͎Q�c�����C���đ呠���ɏA�C�����B���N7��27���A
�呠�Ȃ������Ȃ��z���������邱�Ƃ����肳��A���̎��_�ŁA�呠���ł�������v�ۂ��O���̂͂邩�����̏�i�ƂȂ����B����4�N11��12���A�E��b�E��q���S����g�Ƃ��A
��v�ہA�ɓ��A�R�����F�i�Ȃ��悵�A�O������E����ˏo�g�j�g�Ƃ����50���̎g�ߒc���A���l�����Ƃɉ��ėւƗ��������B���̎g�ߒc�̖ړI�́A
�P�j���얋�{����������������X���K���āA����ɍ������悷��A�Q�j���Đ�i���̐��x�E�����̎��@�A�R�j�ڑO�ɔ����Ă������̉�������i����5�N5��26���j�Ɍ����āA
������̗\�������s���A���Ƃł������B
����6�N5�����A��v�ۂ������O�V���I���A������ƁA���琭�{��a�����Ă������������E�]���V���E�_�ޏ��炪���肵���������N�ւ�
�g�ߔh���̈ꌏ�\�����𑗂荞�݁A�J���𔗂�B�����]��Ȃ���Γ��\������u���ؘ_�v�������āA�A���g�̑�v�ہE�،ˍF�[�E��q���Ƃ̊Ԃő�_�����N�������B��v�ۂ�
������D�悵�A�܂����͂����߂�ׂ����Ƃ��咣�����B���̘_���͑�v�ۂ�A���g�̏����ɏI��������A���N10���A�s�ꂽ���琭�{���̐��ؘ_�h�A���������A�]���V���A�_�ޏ���́A
���������ɘA�Ԏ��C�����i����6�N�̐��ρj�B�����Ɏ����đ�v�ۂ́u�����ȁv�̐V�݂ɓ����A����Q�c���������ɂȂ����B�����Ȃ͊O���ƕ��������������̒����̌��͂����ɏW�߂��ȂŁA
���̂Ƃ���v�ۂ͖����Ƃ��ɐ��{�́u�ɑ��v�ƂȂ�A�ƍَ҂ɓ��������͂���ɓ��ꂽ�Ɖ]���Ă悢�B����7�N1��9���A���̓����ȂɁu�w�����v���ڂ���A
�O���́A�����ɏ��i���Ă����呠�ȎO���o�d�̖��͉����ꂽ���̂́A��C�̉w�����ɂȂ����B����29���A�O���́A�w���������������܂܁A�����Ȃ̃i���o�[4�ł���������ɔC����ꂽ�B
����7�N2���A�Q�c�����C�����]���������̍���ŗi������č���̗����N����A�s�ꂽ�]���͏��Y���ꂽ�B���N7�N4���A��p�o�����s��ꂽ�B
����́A�����̂ڂ邱�Ɩ���4�N10���A�����̓�������p�ɕY�������Ƃ���A50�]�������Z���ɎE���ꂽ�����ł������B���̓���O���ɂ������āA���{�n�́u����{�鍑�X�֏��C�D��Ёv��
�S���@�\���Ȃ������B�����������m�̍q�C�ɁA���̉�Ђ̑D�͖��ɗ����Ȃ������B�܂��A���{�n�ł��邪�䂦�ɔ���v�۔h���،˂璷�B���̑����������Ă���A��v�ۂ̓ƒf�œ��������Ƃ�
�ł��Ȃ������B���Ȃ݂ɁA�ېV�̎O���̈�l�A�،˂͑�p�o���ɔ����āA�Q�c�����C���Ă���B��Y�����v�ۂɁA�����݂ɋ߂Â����̂��A�y���o�g�̍����E���푾�Y�ł������B����ɂ�
��G�̒���A�O���̐i��������A��v�ۂ͐��{�����ď�������w�������D�D13�ǂ̉^�p�����̊�ƏW�c�E�O�H�Ɉϑ����邱�Ƃ����߂��B���͂��̌R���A���𐬌��ɓ����A��v�ۂ̐M�����l���A�����
����ȗ��v��������ƂƂ��ɁA���̍ɑ�����돂���邱�Ƃɐ��������B
��p�o���́A���������̒�E�]���i���݂��j���ƒf�ő�p�ɏ�荞�݁A���������Ď����̔��˒n�E���O���Ȃǂ��́B��v�ۂ̐����Ƃ�
���ɂ���āA������50�����𐴍����瓾�āA�P���������̂ł������B���̂Ƃ��A��v�ۂ́A�O���Ɂu�O�����@�̗X�ւ̂������ŁA
�����͊O���ŏ����\�����v�ƌ�����Ɖ]���B����́A�O�����n�����X���x���A�����ɁA���������{���̈ꕔ���邱�Ƃ�F�߂����邱�ƂɗL���ɓ��������Ƃ������Ă���̂ł���B
���������́A�c��14�i1609�j�N�A�F���˂̐N�U�ɂ��A�F���˂ƒ��v���]�@�卑�̊W��������A���̌�250�N�ȏ�ɂ킽���ē���Ƃ�
���߂���{�̎�����̎�s�ł���]�˂Ɉ�A�̎g�ߒc��h�����Ă����B���̈���ŁA�����Ƃ������i���v�j�W�𑱂��A�g�ߒc�̎���i�����g�j�Ɣh���i�i�v�g�j���s���Ă����B
���������́A��������{�ƒ����ւ́u�����v�̊W�ɂ������̂ł���B�������{�́A1872�N�i����5�N�j9���A���������̎g�ߒc�𓌋��ɔh�������A�����ېV�̐������j�����t��
�q�ׂ����Ă���B�V�c�͊O�����i�O����b�j�̕�����b�ɏُ���ǂݏグ�����A���̒��ŗ��������E���ׂ��u�����ˉ��v�ɏ��i�����A�ؑ��ɗ��B���A���R�̂��Ƃ��A�����͓��{��
���̑[�u�ɔ[������͂����Ȃ������B�����̓��{���ւ̋A���́A�����Ȗ����܂�ł����̂ł���B��p�o���ł̐����Ƃ̌��ߒ��ł��̂��Ƃ����ɂȂ����B����ɐ旧���A�O���͉w�����Ƃ��āA
���{���ق��̃A�����J�l�u���C�A���̏�������āA����6�N8���ɓ��ėX�������ɒ��Ă����B����ɂ��A���{�̐؎��\�����X�֕��́A���̂܂܃A�����J�֑��B����A
�A�����J���o�ē��������ۗX�֏�������ł��鏔�O���ɂ����t�����悤�ɂȂ����B�O���͐����̓�������悤�ɁA����6�N�A�w�����̊����𗮋��˒��֔h�����A���{���n�̗X�ւ�
�����Ԃł��ʂ���悤�A�Ղɓ����点���B����7�N1���ɂ́A���{�n�́u����{�鍑�X�֏��C�D��Ёv�ɖ����āA�����\�����ԂɈ�N6���̗X�֑D���J�ʂ������B���N3���ɂ́A
�A�ߔe�A���A�m�i�Ȃ�����j���Ȃ킿�^�V�`��4�����ɗX�։�������ݒu�A���̑��A����������9�����ɗX�֎戵���̊J�݂����s�����B�����ɏ�荞��v�ۂ́A���̗X�֕ғ���
���������̂������ŁA���������{�̂ł��邱�Ƃ��咣���邱�Ƃ��ł����̂ł���B
����9�N2���A�������{�́A���Ɨ\�Z��3�����߂Ă������m���̉Ƙ\�ƈېV�̌��J�҂ɑ���ܓT�\��p�~����u���\�����v��f�s�����B���N3���A
�ѓ��֎~�߂����z�B���N10���A�F�{���ł͔p���߂ւ̔��Ή^���Ƃ��Đ_���A�̗��A�ĉ����ĕ������ŏH���ˎm�{��ԔV���𒆐S�Ƃ���H���̗��A�R�����őO���ꐽ��ɂ�锋�̗��Ȃ�
�s���m���ɂ�锽���������A���ꂼ��������ꂽ�B����10�N1��29���ɁA���F���˂̎m�������S�ƂȂ�A����������叫�ɗi�����āA���{�����ł͍ő�K�͂̓���ƂȂ鐼��푈���N�������B
���������Ɍĉ�����`�ŕ����ł��������l�Y�狌�����ˎm���ɂ�蕟���̕ς��N�������B����푈�͐V���{���̏����ɏI���B9��24���A���������͎�������R���J�ł̍Ō�̐킢��
���Ƒ������ɏe�e���A�ʕ{�W��̉���ɂ���čŌ�𐋂����Ɖ]���Ă���B����푈�̍Œ��A�F�{��U�͂̊�@�ɍۂ��āA�Վ��ɏ����債�A�u���叄���v�Ɩ������A�V�I���c�Ȃ�
��c��h�����邱�ƂɂȂ������A���̐ӔC�҂ł����H��x������n�ɕ�������ł������̂ŁA�x���̎����������ɑ�����W��A���̒���̎������O���ɉ���Ă����B�O���́A
���̕�W���I�Ԃɂ������āA��Ƃ��āA10�N�O�̕�C�푈�̂Ƃ��ɁA�F���̂��߂ɎS�邽��J���ڂ��������k�A�k���̊e���ɂ����Ƃ���A���ꂪ����ɂ����āA�������Ɍ���t�����Ƃ����B
����푈����5��26���A�،ˍF�[���o����̋��s�ŕa���B������11�N�i1878�N�j5��14���A�n�Ԃōc���������Ă�����v�ۗ��ʂ��I�����t�߂�
�����J�i���E�����s���c��I���䒬�j�Ō�����ˎm��ɂ���ĎE�Q���ꂽ�B�����ɂ����āA�u�ېV�̎O���v�͂��ׂĖS���Ȃ����B
����14�N�i1881�N�j�A�F���o�g�̖k�C���J��g���c���������L�����F���o�g�̎��Ɖƌܑ�F���Ɉ������������悤�Ƃ������������o�A���{�ւ�
�ᔻ�����܂�A���{�́A����J�݂̒��@�ɂ��A10�N��̍���̊J�݂�����B���@����ɂ��ẮA���{���ɂ����āA�N��匠���c���r�X�}���N���@���A�C�M���X�^�̋c�@���t����
���@���A�������Ę_�����������B �O�҂��x�������̂��ɓ������ƈ��]�ł���A��҂��x�������̂���G�d�M�ł��������A����J�݂̒��@�Ǝ��������āA���L���̕��������𐭕{�O��
���[�N�����^���� ������Ă�����G�d�M����Ƃ��ꂽ�B�����ɑ�G�̃u���[���̌c��`�m�剺�������i��Ɍ��m�Ќn�j�����{����Ǖ����ꂽ�B������u����14�N�̐��ρv�Ƃ����B���̌��ʁA
���{�͌N��匠���c���ꐧ�^�̐����̐����Ƃ邱�ƂɂȂ����B
�O�������̂Ƃ��ꏏ�ɉ���A46�̂Ƃ��ł������B���{��ǂ�ꂽ��G�d�M�������߂��������i�}�ɑO�����Q�����Ă���B��G���o�c��
�J�Z�Ɏ������������w�Z�i���E����c��w�j�̍Z�����A����20�N8�����瓯21�N7���܂Ŗ��߂��B�����̂ڂ��āA����{�鍑���@���z�ɐ悪���āA����18�N12���ɓ��t���x���������A
������t������b�Ɉɓ��������A�C�����B���̂Ƃ��A�_�����Ȃ���w���E�ǑD�̓�ǂ��ڊǂ��A�p�~�����H���Ȃ���d�M�E����ɓ�ǂ������p���ŁA���M�Ȃ��V�݂��ꂽ�B
������M��b�͉|�{���g�ł��������A�O���́A�����āA����21�N11������24�N�܂ŁA���M�����߂Ă���B
�@
�@�n����̈���u�n��v�ɐl���Z�ݒ����������n�߂�ƁA�����Ɂu�����v�����܂��B����͔����ɂ����āA���́u�n��v�̋C��A�n�`�A�n���Ȃǂ̎��R�����ɋK�肳���ł��낤���A���̔��W�ɂ����āA���́u�n��v�̐l�̗��j�ɋK�肳���B������u�n�敶���v�Ƃ����B�����́u�n��v�Ő��܂ꂽ�u�����v�����́u�n��v�ɓ`�d���A���̐�������g�傷�邱�Ƃ����邵�A���Ƃ��Ƒ��̒n��ɂ������u�����v�ƗZ�����ĐV�����u�����v�ݏo�����Ƃ�����B����Ɂu�n��v�Ɖ]���Ă��A���̍L����ɂ����đ召���낤���A�����Ŗ��ɂ���̂́A���{���́u�z��v�Ɓu�F���v�̓�́u�n��v�́u�����v�ɂ��Ăł���B19���I���A���{�ɉ����Ă������ė̈��͂ɂ��A���{�͐��E�Ɍ����ĊJ������ƂƂ��ɁA����܂ő����Ă����������i���ˑ̐��j��p�~���A�V�c�_�Ƃ��钆���W���I���Ƃ�����A�ߑ㉻��i�߂��B���̉ߒ��œ����A���I�A�����A�����m�푈���o�����邱�ƂƂȂ������A����͓��{�̓��A�W�A�ւ̒鍑��`�I�g��̗��j�ł������B���ʂ́A�p�ă\����A�����ɑ��閳�����~���ƂȂ�A���́A�A�����J�̐�̉��Ŗ���I���v���i�߂�ꂽ�B�ȗ�80�N�߂��ɓn����{�̗��j�́A���̂���܂ł̐l���Əd�Ȃ��Ă���B�����ېV���猻�݂Ɏ���ߒ��ŁA���V�A�A�����ɋ��Y��`���������܂ꂽ���Ƃ����݂̐��E�ɑ傫�ȉe����^���Ă���B���V�A�𒆐S�Ƃ���\�A�i�\���B�G�g�Љ��`���a���A�M�j�́A1991�N���ɕ������A���V�A�͐��E�ɑ��ĈˑR�Ƃ��Ĉ��̉e���͂�ێ����Ă���A�����͌o�ϖʁE�R���ʂł̋ߑ㉻�𐬂������A���E�̑卑�ƂȂ����B2024�N���݁A���E�ɂ́A�푈�̕p���A���j��A�n�x�̊g��A�l�S�̍r�p�ȂǗl�X�Ȗ��������o������B���E�͑��ɉ����Ă���A��s���͐r���s�����ł���B���̂悤�Ȏ���ɂ����āA���݁A���E�̒��œ��{����߂�ʒu��m�邱�Ƃ͏d�v�Ȃ��Ƃł��낤�B�����u�z��v�Ɓu�F���v�́u�n�敶���v���r���čl����悤�ɂȂ����̂́A�܂������̋��R�ɂ����̂ł��邪�A�ŋ߁A���̓�̕�����m�邱�Ƃ́A�u���{�����v�̊�w��m�邤���ňӖ�������̂ł͂Ȃ����ƍl����悤�ɂȂ����B�Ȃ����Ƃ����ƁA�u�z��v�Ɓu�F���v�́u�n�敶���v�́A���ꂼ�ꂪ�A�ߑ㉻���n�܂�ȑO�̍]�ˊ��ɂ�����i�u�č��v���S�́j�u�_�v�̕����ƁA���m�𒆐S�Ƃ����u���v�̕������\���Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl����悤�ɂȂ�������ł���B���̌��݂̊�{�F���͎��̂悤�Ȃ��̂ł���B����̓��{�ł́u�s�s���v���i�݁A�u�s���v�𒆐S�Ƃ��镶�����������ɂ߂Ă��邪�A����́A�u�ߑ㉻�v�ɂ���Đ���ɂȂ����u���H�̕����v�̉�������ɂ��镶���ł���B�������A���̊�w�ɂ́u�_�̕����v�Ɓu���̕����v����������Ă���ƁB����ɌÑォ�瑱���u���Ƃ̕����v�Ɓu���Ђ̕����v�������邱�Ƃɂ��A���݂́u���{�����v�̏����𑽖ʓI�ɑ����邱�Ƃ��\�ɂȂ�ƁB�×��A�u�_�Ɓv�Ɓu���́i�R���́j�v�́A�u���Ɓv�̏d�v�ȍ\���v�f�ł������B
����푈���I�����12�N���o�߂���1889�i����22�j�N10���Ɏ������ɂ���ė��āA�{�V��E�m�i�q�퍂�����w�Z�̋����E�Z���Ƃ���2�N���؍݂������z�㒷���ˎm�̎q�i���j�j�A�{�x���l�Y�i1865�|1912�j�́A���̂Ƃ��̑̌��E��������ɁA�w�F�������L�x�����B���̒���ɂ́A���������̎F���̕����E�Љ�̗l�q��������Ă���̂ŁA�����w�E���j�w�̋M�d�Ȏ����Ƃ��Č㐢�̐l�X���璍�ڂ����悤�ɂȂ����B�w�F�������L�x�̖ژ^�i�ڎ��j�́A�u�y�n�C�C��C���j�C�l���C�N�������C�����C�V�Y�C�̕����ȁC�K��C����C���H���C���X�C����C�n�x�C�M���C�m�����C��ʁC����C���V�C�@���C�_�ƎY���v�ƂȂ��Ă���B�ŏ��́u�y�n�v�C�u�C��v�C�u���j�v�C�u�l���v�́A�F���̎��R�A���j�A�l�Ɋւ���L�q�ł���A�u�N�������v�ȍ~���A�F���̕����E�Љ�Ɋւ���L�q�ł���B�Љ�Ɋւ���L�q�ɂ��Ă͓��v�f�[�^�����p����Ă���̂������I�ł���B����͓����A���Ă�������Ă����u���v�w�v�̉e���ł���Ǝv����B�u�l���v�̍��ڂ́A�u��� �e�e���́v�A�u����v����Ȃ��Ă���B�������ɋ������������̂́A���́u����v�̕����ł���B�����ɂ͎��������l�́u�������v�A�u�����C��(������)�v��������Ă����B���������A�������߂Ė{�x���l�Y�́w�F�������L�x��m�����̂́A����1973�N�Ɏ������ɂ���ė��ĊԂ��Ȃ����̂��ƂŁA �n�����u����{�V���v�ɍڂ����L���ɂ���Ăł������B���̋L���̃e�[�}�͎��������l�́u�������v�ɂ��ĂŁA �{�x���w�F�������L�x�̒��ŁA���̂��ƂɊ֘A���ď����Ă��镔�������p���A�����l���玭�����l���ǂ̂悤�Ɍ����� ���邩���Љ�Ă�����̂ł������B���̌���A�w�F�������L�x�Ɋւ��邱�̎�̋L�������x��������Ō��������Ǝv���B ���̌�A2000�N�ɒn���̓���V�Ђ���A�w�F�����O�x�z�̍\���|���㖯�O�ӎ��̊�w��T��|�x�Ƃ����{���o�ł��ꂽ�B���҂́A���������ۑ�w�����i�����j�ŁA�u�Ñ㔹�l�̌����v�Œm��ꂽ�����������ł������B���{�j�̂Ȃ��̒n��j�������ۑ�Ƃ��Ă����������́A���̖{�̒��ŁA���������l�́u�������v�A�u�����C���v���l�@���A���̐�s�����̈��Ƃ��Ė{�x���l�Y�́w�F�������L�x�����グ��ꂽ�̂ł���B�l�X�́u�e�e�v�́A�l�ފw�I�A��`�w�I�ɋK�肳�����̂ł��낤���A�u�n��v�ɏZ�ސl�X�́u�C���v�́A���́u�n��v�̕��y�E���j�ɋK�肳��邩��A���́u�n��v�́u�����v��\�o�������̂ł���Ɖ]����̂ł͂Ȃ��낤���B�@�����u�������v�A�u�����C���v�ɋ������o����̂͂��̂��Ƃɂ��B�n��I�����Ƃ��Ắu�������v�́A�������j�I���Ԃ������Č`�����ꂽ���̂ł��邩��A���̕ω��͊ɖ��ł���A�u�n��v���z�����l�Ɛl�Ƃ̌𗬂�����ɂȂ�������ɂ����Ă��l�X�̈ӎ��̒�ɑ��݂��Ă���Ǝv����B
�{�x�́w�F�������L�x�̒��ɂ́u���k�l�C���v�Ɓu�F���l�C���v���r���ċL�q��������������B���̏ꍇ�A�{�x�́u���k�l�v�̒��Ɂu�z��l�v���܂߂čl���Ă��邱�Ƃ́A���Ɏ�����̎����ɂ��m���߂邱�Ƃ��ł���B�{�x�́w�F�������x���o�ł��ꂽ�̂́A1898�i����31�j�N�ł��邪�A���̌��ɂȂ����e�{�u�F�������v�́A�{�x����������������1892�i����25�j�N�̉Ă��痂�N�̏t�ɂ����ē����ɂ����Ď��M���ꂽ�B���̍e�{�́A���݁A�{�x�̕�Z�A�V���������������w�Z�̋L�O�����قɓW������Ă���B�����������Z�̏o�g�ŁA2022�N�A��������ǒ��E�������Y���̂����ӂŁA������{�����邱�Ƃ��ł����B���̍e�{��98�ł���99�łɂ����āA�u����c���j�݃��e�����N�i1891�i����24�j�N�̂��Ɓj���j���P�����k�����m��r�������o���j���m�@���v�̕����ɑ����āA�u���k�����v�̎m���ƕ����̌���c�����̈ꗗ���ڂ��Ă��邪�A�����ʼn]���u���k�����v�ɂ́A���݂̓��k�����A�u�X�A���A�H�c�A�R�`�A�{��A�����v�݂̂Ȃ炸�A�u�_�ސ�A��ʁA��t�A����A�V���A�Q�n�A�ȖA���v���܂܂ꂢ��B���������āA�����ʼn]���u���k�����v�́A�z����܂ށu���{�̓��k���Ɉʒu���鏔���v���Ӗ����Ă���B
�ŋ߂킩�������Ƃł��邪�A�{�x�́w�F�������x�̑��ɁA�w�n�����w�j�x�Ƒ肷��A�n������ΏۂƂ��铌���V�w�ē���1887�i����20�j�N6���ɏo�ł��Ă���B���ꂪ�o�ł��ꂽ�̂́A�{�x���A���t�����Ă����u�����w�Z�v�i�����������w�Z�A���E���������w�Z�̑O�g�j����߂ď㋞���A���������p��w�Z�ɓ��w�������N�̂��Ƃł���B���̏o�ŕ��́A���̕����ł��w�ߑ���{�N������p���A��V���E�i�w�ē� ��2���x�i���{�}���Z���^�[�A1992�N���j�ɏ�������Ă���̂Ō��݂ł��ǂނ��Ƃ��\�ł���B���̑��҉���33�łɁA�u���e�n�����C���m���v�Ɖ]����������A�����Ŗ{�x�́A���{���u���z���v�A�u�֓����v�A�u�������v�A�u��B���v�̎l�ɕ����A���ꂼ��̒n��̏����̋C���̓��������̂悤�ɋL�q���Ă���B
�u���z�m�l�n����ɖ��s�����j�V�e����@�j��W�����i�X�m�C�̓i�N���c�r�_���ۃj�a�N�c���e�a�m�͔��N�V�e������v�ȃe�����d���R�g�r�_��L�K�@�V�R���h������j���������m�Ǖ��A���e�σ��j�����X���R�g�i�N�\�N���d�j�e�������n�l��v�X���m�C���j�x�����v
�u�֓��l�n����y���j�߃M�e�����i���Y�����X���o�C�j�������j��Y�Ń������`��j�V�e�@���m���A���K�@�V�R���h�����q���圤�@�j�Ճ~���j�|�X���j�v���j�V�e���c�`���m���A���v
�u�����m�l�n�Ń��ِヒ�P�N�V�������ۃj���W����y���C�������j�V�e�����j�@�q�i���R���h�������c�X���σj���V�M�`���烉�Y��j�y���j�V�e�����m�C�ۃj�R�V�N�v�V�N���j�������\�n�U���K�@�V�v
�u��B�m�l�n�E�����B�M�b���N�F��[�N�C�����r�`�j�E�~�R�����d���Y�R���h���v�z�e���j�V�e�������n�l�X���R�g�\�n�Y��蛃j�V�e���J���d���W���ǎ�̃m�q�j�R�V�L�K�@�V�v
����ɁA�u�]���āA���z�̐l�͕����ɓK���A�֓������̐l�͂Ƃ��Ɉ�ʂ̎����ɓK���A��B�̐l�͕����ɓK����v�Əq�ׁA�����̋C���̈Ⴂ�������錴�������E�g�E�M�̋C���̈Ⴂ�ɋ��߂Ă���B�{�x���]���Ƃ���́u���k�l�v�́A�����ł́u���z�m�l�v�ɑ�������ƍl���Ă悢�Ǝv����B
���āA�u���k�l�C���v�Ɓu�F���l�C���v�̈Ⴂ�ł��邪�A�{�x�́w�F�������L�x�̒��ŁA�˓I�ɂ�����ԓx�̈Ⴂ��p���Ď��̗l�ɕ`�ʂ��Ă���B
�u���l�R(����)�ĕ]���ĞH���ނ̎˓I���ׂ�������ɓ��k�l�͊���x�ɂɂ��đ�ꔭ�Ɍ��������đ������I�X���X�����O���������ׂɌ�������x�����C�ɑ_����(�Ȃ�)���ǂ��F�l�Ȃ�Α�ꔭ�����Ⓖ�Ɋ����(����)�炵�є����t���ċC�}���r�k�Б_����߂����Ē��ɔV������O���������Č���������ŏe��n��ɝe(�Ȃ���)������v�B
�����āA�F���l�m�̊���̌����������̂Ƃ��āA���̈�b���ڂ��Ă���B�u��ɘD���c���q�̓��Î���K���Ƃ�������F�P�������ĘD�͂ɏ悶�Ď������ɋA������̐���(���܂т�)�������Ԃɏ��ւ�ꈽ���͌��p�������đ��^������҂���F�l�^�q���̎���_���H���������̍��������ׂ����Ȃ��Ƌq�������^���V���R�Ƃ��č����N�{�k�ɂ��ę̒��u�`�F�X�g�|�v��⋩������s�ĔV������Β䓁���ɂ��̍A��f�������v�z�̒P���ȈՂɂ��đ��s���̖��Ӗ��Ȃ��V���͐_�o���̐l�Ȃ��R�����V���ȂĎF�l��(��)���Β�(����)�炸�Ƃ��ւǂ��W�������炸�Ȃ�Ȃ�v�B����͖{�x�����ۂɑ��������o�����ł��낤���B�@�{�x���������ɑ؍݂��Ă�������24�N5��6���A���E���s�r���̃��V�A�鍑�E�j�R���C�c���q�i��̃j�R���C2���A���V�A�鍑�Ō�̍c��j���A���V�A�鍑�C�R�̊͑��������A��Ď�������K�₵���B�ŏI�ړI�n�̓E���W�I�X�g�b�N�ŁA�V�x���A�S���̋ɓ��n��N�H���T�ɏo�Ȃ��邽�߂ł������B���̂Ƃ��A�J�ɂ́A���������͐���푈�Ŏ��Ȃ��A���V�A�ɓ���܂������Ă���A���̃��V�A�̌R�͂ɏ���Ď������ɋA���Ă���Ƃ����\���������̂ł���B
�u���k�l�v��ʂɓ��Ă͂܂邩�ǂ����͂Ƃ������Ƃ��āA�z��l�́u�C���v�Ɋւ��ẮA��q�̖{�x�̋L�q�͊T�ˑÓ�����ł��낤���Ƃ́A�z��ɕ�炵�����Ƃ̂��鎄�Ƃ��Ă͎�m������Ȃ��B����́A�z�オ�ፑ�ł���A���N�߂�����ɕ����ꂽ�������������Ă������ƁA�Z���̑������P��̕č��v�̒��Ƃ����_���ł��邱�Ɠ��ɂ����̂ł���Ɖ]���邾�낤�B�����A�F���l�͌Ñォ��F�����l�̌ď̂Œm���Ă���悤�Ɂu�r�q���v�������Ēm���Ă����B�������邪�A���l�Ƃ͔��i�n���u�T�j�̂悤�Ȑl�̈ӂł���B���l�Y�͎F���l�m���������ɐS���h������Ċ���₩�ɗN���Ă��ė}���邱�Ƃ��o���Ȃ��Ȃ����Ƃ��ɔ�����u�`�F�X�g�|�v�Ɖ]���|�����ɎF���l�̊���̌������������Ă���B���͎F���l�́u�C�Z���v�Ƃ������́A�z��l�́u���v�́v�ɑ��ĎF���l�́u�u���́v��Δ䂳���������Ó��ł���悤�Ɏv���B���́u�u���́v�́A�u����点�č����v�ꌂ�K�E�̎F���̌��@�A�u�������v�ɂ悭����Ă���悤�Ɏv���B���̎F���l�̓����́i���j�M�ѐ��C��ƉΎR�����y�ɋN��������̂ł���Ǝv����B�F���͎R�n�������A�ꕔ�������z��̂悤�ȑ�K�͂Ȑ��c�͂Ȃ����A�ΎR����n��ɎF�����A�����ǂ���B
�b�x��B�����ō]�ˎ���ɂ�����u���w�����v�ɖڂ�]���悤�B�����]�ˎ���́u���w�����v�̒n��ɂ�����L��l�̈Ⴂ�ɊS�����悤�ɂȂ����̂́A�{�x�́w�F�������L�x�̂Ȃ��̎��̈ꕶ�ɂ��B�@�u�F���l�m���A��ʂɉȊw���D�܂��A���ɐ��w�ɕs����ł���̂́A��������C�Z���ŁA�E�ςƗ��z�ɖR�����A��x���݂Đ������Ȃ���A���������͋y���Ƃ����Ă����������A���x���J��Ԃ��v�l���Ȃ����Ƃɂ����̂ł���B ���ɁA�F���l�́A�ꎖ��A���I�ɔ����������邱�ƁA����ш��s�ς̗��z��������A���_�I�ɔ��f���A�Njy���Ă����Ƃ������Ƃ́A����]�ނ��Ƃ͂ł��Ȃ��B�v
�����ŁA���{�ɂ�����u���w�����v�̗��j���T�ς��Ă������B���{�ɂ����鐔�w�̋N���́A6 ���I�ɕS�ς��畧���ƂƂ��ɗ�`��������ɂ����̂ڂ�B�����A�����Ñ�̍ő�̐��w���ł���w��͎Z�p�x���A������Ă����B�ޗǎ���ɂȂ�ƁA�����̉ȋ����x�ɂȂ�������ߐ��������x�̎����ɂ����āA���w�����K�ȖڂƂ��Ď��グ����悤�ɂȂ����B���̌�A���{�́u���w�v�ɁA��������i�W�͂Ȃ��������A�퍑���ォ��M���E�G�g�̎�����o�āA�R���Z�p��z��p�̊v�V�A�z�R�J���⌟�n�Ȃǂ̎Љ�I�K�v����A���Ƃ̔��B�ɂ���āA�]�ˎ���ɓ���Ɠ��{�Ɠ��́u���w�����v���ԊJ�����B�]�ˎ���́u���w�v�́u�\���o���v�ɂ��v�Z�ƁA�Z��(�����)�ƎZ��(����)��p�����V���p����Ȃ��Ă����B�V���p�͈��̊��㐔�ł���A����̐����ɗp�����邱�Ƃ͂Ȃ��������A�V���E���p�ł͑㐔���������������Ƃ����߂��A���̌v�Z�ɕK�v�ł������B
�u�\���o���v�ɂ��v�Z�̏��́A�g�c���R�i1589�|1673 �N�j�́w�o���L�x�i1627 �N���j���L���ł���B���R�͎��D�f�Ղō����Ȃ��������p�q�Ƃ̈ꑰ�ł���B���R��15 ���I���A���N�o�R�œ��{�Ɉړ����ꂽ�����̐��w���w�Z�@���@�x�i1593 �N�A����̖��Ԑ��w�ҁA����ʂ̒��j����ɂ��āw�o���L�x���������Ɖ]���Ă���B�w�o���L�x�́u�\���o���v��p���Ă��낢��Ȍv�Z������{�ł���B�Ƃ������́A�u�\���o���v�ɏK�n���邽�߂ɂ��낢��Ȗ�肪���ׂ��Ă���Ɖ]���Ă悢�B���Ȃ݂Ɂw�o���L�x���������v�Z���́A�u�Ă̔����Ƃ���ɔ����v�Z�v�A�u���◼�ցv�A�u�K�̔����v�A�u�����v�A�u���z�̔����v�A�u���n�v�A�u�D���v�A�u���v�A�u���n�ƐŁv�A�u��X�̍H���v�A�u���ʁv�A�u�J�����v�A�u�J���@�v�ȂǑ���ɓn��B�o�ϐ��������W�����]�ˎ���͂��̂悤�Ȍv�Z��K�v�Ƃ��Ă���A���������āw�o���L�x�͍]�ˎ����ʂ��čL���ǂ܂ꂽ�B�܂��ޏ����������o�ł��ꂽ�B���R���S���Ȃ�1673�N�܂łɁA�w�o���L�x��21��ނ��o�ł��ꂽ���A���̂������R���g�ɂ����͎̂l��ނ���ނł���Ƃ����i���쑩��:�w�a�Z�\�]�˂̐��w�����x�A�����I��114�A2021 �N���Ap.35�j�B
�Z�ՂƎZ��p�����V���p�́A15 ���I���ɒ��N�o�R�œ��{�Ɉړ����ꂽ�����̐��w���w�Z�w�[�ցx�i1299 �N�A����̖��Ԑ��w�ҁA�鐢���̒��j�ɂ���Ă���B���̏��̓A���r�A��C���h�̉e����������Ƃ����B�㐢�A�u�a�Z�Ɓv�ƌĂ��悤�ɂȂ����l�X�̓\���o���Ōv�Z�����A�㐔��������V���p�ʼn������Ƃɂ���āA���낢��Ȑ��w�̖����������B�u�a�Z�Ɓv�Ƃ��ẮA�֍F�a�i1642�H�|1708 �N�j�Ƃ��̍���A�������O�i1664�|1739 �N�j���L���ł���B �F�a��25�̂Ƃ��A �ޗǂ̎��ɂ����������̐��w���u�k�P�Z�@�v�i������̓V���p�̏��A ���w,�A�s����������������Ă���j���ʖ{���������Ă���B �܂����̎���ɏ����ꂽ�u�������v�����A�����ꂽ��u�V���听�ljM(����)�S(���イ)�v(�悤)�v80����Ɨ͂œǂݐ����Ƃ����B�u�a�Z�v�́A ���w��m�I�V�Y�Ƃ��Ċy���ޕ����Ƃ��āA �����ԁE�����Ɠ����悤�ɏ����̂������ɂ��L�܂����B �u�֗��v�A�u�������v�A�u�ŏ�(�������傤)���v�Ȃǂ̃M���h���`�����Ƌ����x���Ƃ��Ă����B ���w���w��ł���l�̒��ɂ́A���w�̖������A ��肪������Ƃ��̓������G�n�̂悤�ɂ��Đ_�ЁE���t�ɕ�[����l�����ꂽ�B���̊G�n���u�Z�z�v�Ƃ����B���̂悤�ȕ����͐��E�ɗނ��݂Ȃ����̂ł���B
�]�ˎ���A���オ����ƁA�S���𗷂��Ȃ���A�n���̐��w���D�Ƃ�K�˂Đ��w��������A�V���Z�ƂƌĂ��l�X�����������悤�ɂȂ����B�u���w�����v�̒n���ւ̓`�d�ɂ́A�u���w���v�̗��ʂƂƂ��ɁA���̂悤�ȗV���Z�Ƃ̑��݂��^�����đ傫�������B���̗V���Z�Ƃ̈�l�ɁA�z��̔_���o�g�̎R���a (�H�]1850) �������B�R���͐V�����k�����S�������i���E�����s�j�̏o�g�ŁA�_�Ɓi���_�j�̎O�j�ł������B�֗��ܓ`�E����(������)���̒�q�̖]�����E�q�傩�琔�w���w�сA���̌�A�]�˂ɏo�āA�֗��̒��J�슰�i1782�]1838�j�̓���q�ɂȂ����B���J�슰�́A�]�˂̒��l�i�b�艮�j�̏o�g�ŁA�����A�g������Ȃ����w�m�Ƃ��ėL���������u���J�쓹��v����ɂ��Ă����l���ł���B�������꒘�w�a�Z�Ƃ̗����L�x�i�����ʐM�ЁA1988�N���j�ɂ��A�R���́A3��V���̗��ɏo�Ă���B�P��ځA�Q��ڂł́A�헤�A�����A���k������A�R��ڂł́A�k�z�A�R�z�A��B�A�R�A�������Ă���B��B�ł́A���q�A�����A����A�����A�V���A�F�{�A�v���āA�F��������A�����A�}�O���}�y�S���m���A�ɖ����A����ł͐��w�ҁA���w���D�Ƃɉ���Ă���B����ŎZ�z������ƕ����A���ꂪ�[�߂�ꂽ�_�ЁE���t��K�ˁA���w���D�Ƃ�����ƕ����ΖK�˂Đ��w���������B���O���m��ꂽ���w�҂ɂ͉�ɍs���A���w�Ɋւ���������������B�����������̒����A�w���{�l�Ɛ��|�]�ˏ����̐��w�x�i���m���X�A1994�N���j�A�w���{�l�Ɛ��|���E�a�Z�������������j�x�i���m���X�A2003�N���j�ɂ���āA���w��m�I�V�Y�Ƃ��Ċy���ޕ����́A���{�S���ÁX�Y�X�̏����i���l�A�_���j�̊ԂɍL���Z�����Ă������Ƃ�m�����B
�O�q�̖{�x���l�Y�̎F���l�m�̉Ȋw�E���w�ɑ���ԓx�Ɋւ���ꕶ��ǂ�ŁA�܂��l�������Ƃ́A�F���ɂ́u�a�Z�Ɓv�ƌĂ��悤�Ȑl�͂����̂��낤���Ƃ������Ƃł������B�����悸���ڂ����̂́A�u�Z�z�v�̑S���I�ȕ��z�ł���B�E�G�b�u��ɂ́u�a�Z�̊فv�Ƃ����T�C�g�i http://www.wasan.jp/ �j������, �����ɑS���́u�Z�z�v�̈ꗗ�\���ڂ��Ă���̂Ŕ`���Ă݂��B����ƁA�V�����܂ޓ��k�����ɂ́u�Z�z�v����r�I�������݂���̂Ƃ͑ΏƓI�ɁA�R��, ���m, ����, �F�{, �{��, �������̊e���́A��������u�Z�z�v�̋n�тł��邱�ƂɋC�t�����B ������, ����ɂ�2009�N��[�̎Z�z�����邪����͏����Ă���B�{�x�́w�F�������L�x�̒��ŁA�u��ʂɐ���n���͎m���̐��͉��������ł��邪�A�F���͂��̋ɓ_�ł���v�Əq�ׂĂ��邪�A���́u����n���v�Ɓu�Z�z�v�̋n�т��������Ă���悤�Ɏv��ꂽ�B ���͂��̎����Ɋ�Â��A�u���̒n��ɂ́A ��E���{�Ƃ��Đ��w���y���ޕ����A����ѐ��w��T�����镶���A������u�a�Z�v�̕����͑��݂��Ȃ������v�Ƃ��������𗧂Ă��B����̌���҂Ƃ���ł��邪�A�]�ˎ���́u���w�����v�ɂ��ẮA��ʘ_�Ƃ��Ď��̂��Ƃ��]����̂ł͂Ȃ��낤���B
�悸�A�]�ˎ���̕��ƎЉ�ł́A�\���o����p���Čv�Z����d���́u�����̏��Ɓv�Ƃ��ĕ̎�����Ă������Ƃ�m��K�v������i��c���j���F�w���m�̉ƌv��\�u����ˌ�Z�p�ҁv�̖����ېV�x�A�V���V���A2003�N���Ap.20�j�B�������A�×��A�����邱�Ƃ͌N��̎d���Ƃ��ďd�v�ł���������A�V���E���p�Ɋւ���u���w�v�͕ʂł���B�]�ˎ���́u���w���y���ޕ����v�́A�悸�A���s�A���A�]�˂ȂǁA�����̑�s�s�ɂ�����u���l�����v�̈ꕔ���Ƃ��ċN����A���ꂪ�n���̒����s�s����т��̎��ӂɏZ�ޔ_���̊ԂɍL�܂������̂ł��낤�B�����́u���w�v�i�u�Z�w�i�a�Z�j�v�܂��́u���m���w�v�j���w�ԕ��@�́A����Ɠ����悤�ɏo�ŕ��ɂ���Ď��w���K���邩�A�u�w�Z�v�ŏK�����̂����ꂩ�ł������B�����̊w�Z�́A�u�ˍZ�v�܂��́u���Z�v�i�n���m���̂��߂̊w�Z�j�A�u���m�v�A�u�������v�ł������B�u�ˍZ�v�A�u���Z�v�͎m���̂��߂̊w�Z�ł���A�u���w�v�A�u���w�v���������Ă�������A�u���w�v���������邱�Ƃ͂Ȃ������B�����̒��l�̐��w�Ɖ]���u�\���o���v�ł���A����͎�Ɂu�������v�ŋ������Ă����B�]�ˎ�����㔼�ɓ���Ɓu���w�i�Z�w�j�v�̗��h���m�����A�u���w�v����ɋ�����u���m�v�������悤�ɂȂ����B�ŋ߂̗��j�w�ł́A�]�ˎ���̒��l�����̃s�[�N���A�u���\�����v�i1668�]1704�j�A�u���E�V�������v�i1751�]1789�j�A�u���������v�i1804�|30�N�j�̎O�Ƃ���悤�ł���B�u���\�����v�͋��s�A���ȂǏ���𒆐S�Ƃ��镶���A�u���E�V�������v�͓c���ӎ���������U��������E���a�E���i�E�V�����̕����A�u���������v�͍]�˂𒆐S�Ƃ��镶���ł���B���\���ƕ��E�V�����̊ԂɁA�V�䔒�i1657�]1725�N�j�ɂ�镶�������i�����̎��A1711?16�N�j��8�㏫�R�g�@�ɂ��u���ۂ̉��v�v�i1736�]56�j������A���E�V�����Ɖ������̊Ԃɏ�����M�ɂ��u�����̉��v�v�i1787�]93�N�j�������āA�������̌�ɂ͐��쒉�M�ɂ��u�V�ۂ̉��v�v�i1830�`44�j���������B���ꂼ��̉��v�́A���I�l���A�Q�[��A�����I���Ē����A���Z�������߂Ȃǂ��Ӑ}�������̂ł������B���l�����̎O�̃s�[�N�Ƙa�Z�ƂƂ̊W�ʼn]���ƁA�֍F�a�͌��\���̐l�A�֗��l�`�̓��c�厑�ɍR���Ę_�w�����ŏ㗬�̎n�c�E��c�����i1747 �|1817�N�j�́A���E�V�������牻�����̐l�A�V���Z�ƁE�R���a�͉������̐l�ł���B
�F���˂ɂ�����u���w�����v�̏�m�邽�߂ɂ́A�F���˂ɂ�����u���w���v�̏o�ŁE���z�̏���ы���̏�m��K�v������̂����A�u���w���v�̏o�ŁE���z�Ɋւ��ẮA���̒m��Ƃ���ł́A1864�i�������j�N�ɑn�݂��ꂽ�F���˗m�w�Z�E�J�����̐}���ژ^�ɂ���u�w�A�P���h���A1827�N���v�݂̂ł���B����Ɋւ��ẮA1976�N�Ɂu������������j�E�����Łv�i��a�w�|�}���A������������ψ��ҁj�����s����Ă���A���ꂪ�Q�l�ɂȂ�B�]�ˎ���͐g�����̎���ł���A����Ɋւ��ẮA�u�m���v�Ɓu���l�v�A�u�_���v����ʂ��Č���K�v������B�F����8 ��ˎ�E���Ïd��(�����Ђ�)�i1744�|1833�N�j�́A���ȑ喼�ƌĂ��قǐ��m�̉Ȋw�E�Z�p�ɋ����������A�I�����_���و�V�[�{���g�ƍ��e�ȊW�ɂ��������ƂŗL���ł���B�d���͕�������������߁A�ˍZ�Ƃ��đ��m�فE�����فi1773�N�j�A��w�@�i1774�N�j��������B�퍑�̈╗���c�����e��Ȏm�������߂悤�ƁA������珤�l�A���ҁA�|�W�A���W�Ȃǂ��ĂъĂ���B�������s�ɂ͔ɉ؊X�̒��S�Ɂu�V���فv�Ƃ����ꏊ�����邪�A���Ă����ɂ́A�ȓV�V�A���ߕ\�A�]��������������A�����قƂ���������{�݂��������B�����n�����̂��d���ŁA1779�i���i8�j�N�̂��Ƃł������B�F���˂ł͏a��t�C���勝�����������ȗ��A������邽�тɔˎm��h�����җ���w���Ă������A���܂��� 1765�i���a 2�j�N�A���{���V������]�ˋ����ɑ���A�����ꏊ�ɐV������������Ƃ��A�F���˂��珕�肪�o�p���ꂽ�B�����ł��ĕ�����̂Ƃ�����߂����ԗǎ����h�����ꂽ���A���Ԃ͓V�������X�؏G���ɂ��Ă���������A8 �N��� 1772�i���i���j�N�ɋA�˂����B������_�@�ɎF���̓V����Ɨ�ǂ��ݒu���ꂽ�B���ꂪ�����قł���B�����قł͓V�̂̊ϑ��ƌv�Z�ɂ��V�̂̉^�s�̗\���A�Ȃ�тɗ�̕Ҏ[���s��ꂽ�B�d���͗��w�҂����ق��Ă������A�����������Ă����̂́A���w�Ƃ��Ă̈�w�E�V���w�E�n���w�E�{���w�ł���A�Ɛb�Ɂu���w�v���w���邱�Ƃ͂Ȃ������ł��낤�B�d���̂����ŁA�v�Z�⑪�ʋZ�p��K�v�Ƃ��銨����A�������A�d���Ȃǂ̉������m�́A���w�́u���s���v�ɂ�莩�w���K���邩�ƒ������ɂ���ĕK�v�Ȑ��w���w��ł������̂Ǝv����B
�{�x���l�Y�������E�Z���߂��{�V��̉m�i�����q�포�w�Z�́A�{�V�铇�É�15�㓖��E���Ëv���i1841�|1872�j��1858�i����5�j�N�ɐݗ������w�⏊�u�m�i�فv�Ɏn�܂�B�{�V�铇�ÉƂ́u����v�i�����A�����A�d�x�A���a��j�Ɏ����A�u��g���v�i���̎�j�̉ƕ��ł������B���Ëv���́A�������Ëv���̎��j�ŁA1863�i���v3�j�N�̎F�p�푈��1864�i�������j�N�֖̋�̕ςł͔ˎ�ɑ����ĕ����w�����Ă���B�u�m�i�فv�͓����̎F���˓��ɂ������u���Z�v�̂ЂƂł������B���́u�m�i�فv�łǂ̂悤�ȋ��炪�s���Ă������m�鎑���͂Ȃ����A�ˍZ�E���m�قɏ��������炪�s���Ă������̂Ǝv����B���Ȃ݂ɖ{�x���l�Y���m�i�����q�포�w�Z�̋����ɐ��E�����F���E�{�V��o�g�̉F�s�{����́A�Ⴋ���A�I��ĔˍZ�E���m�قɗ��w���Ă���B
�F���˂̎m���̊Ԃɂ́A�u��������v�Ƃ����Ɠ��̋��炪�������B�F���˂ł͐��\�˂�P�ʂƂ������(�ق�����)�ƌĂԋ抄��ɂ���Ĉ�̑g������Ă����B ���̑g�̒��̎��O���u����(�����イ)�v�ƌĂB�펞�ɂ͂��́u�g�v�����̂܂܌R���g�D�ɂȂ����B�u��������v�͐搶�����k���w������̂ł͂Ȃ��A�N���҂��N���҂��w��������̂ŁA ���f�͂�{�����߂̖ⓚ�u�F�c�v�═�|�̌m�ÁA �u�Վ땨��v��u�O�B�{�N���́v�Ȃǂ̈Ï����s�����B����͎F�����m�c�̎m�C���ێ����A ���߂邱�Ƃ��傽��ړI�ɂ�������ł������B�u��������v��ʂ��ĎF���̎m���̎�҂����̊ԂŐ�y�����y�ɋ������܂�Ă������̂Ƃ��āA���Ƀ����̑c�A���É�15�㓖��E���ËM�v�i1514�|1571�N�j�̕��A���Ò��ǁi1492�|1568�A36�Œ䔯���ē��V�ւƖ����B�ȗ��l�X�͓��V���ƌĂԁj��������u����͉́v�ƁA�փ�������̐��Ҏ҂ŁA���Ë`�O�̉Ɛb�E�R�c��(���傤)��(����)�i1578�|1668�N�j���o���O��̒n���ł������Ƃ��ɒ�߂��Ɖ]����u�o��(������)����(�ւ�)�C�{�|���v���������B�F���ɂ́A�j�������i1427�|1508�N�j��c�Ƃ����F�w�h�ƌĂ���q�w�̓`�����������B�����͎R���̐l�ŗՍϏ@�̑m�ł���A�����ɗ��w������A���É�11�㓖��E���Ò����i1463�|1508�N�j�ɏ�����ĎF���Ɏ���A��q�w���u����ƂƂ��ɁA�w��w�͋�x���o�ł��Ďm���̋����ɖ��߂��B���V���́u����͉́v�́A���̎�q�w��A���{�×��̐_���A�����̋��������ƂɁA�l�Ƃ��Ă̓���̋K�́A�������Ƃ�҂̐S�����A���l�Ƃ��Ă̐S���܂��Ȃ�47��̉̂ɂ������̂ł���B�u�o�������C�{�|�v�́A���Ƃ��Əo���O��́u��������v�̝|�ł��邪�A�Ό������̓������������̂ł���B�o���O��͔��ƍ���ڂ���n�ɂ���������C�����̎��Ƃ��āA�×�����ł������̒n�ł������B�u�o�������C�{�|�v���C���̋����̂���Ɣ�r���ėD��Ă����_�́C���E�̂ق��Ɂu���̂̈���v�����߂����Ƃł������B�F���˂ł́A�������A���É�28�㓖��E���Ðĕj�i1809�|1858�N�j�̎���ɁA�m���̍��V��ړI�Ƃ��ċ�������̑��_�����s��ꂽ�B1852�i�Éi5�j�N5���ɂ́A�e�����ɑ��đ��̎�������悤�������������Ă���B���̌����ɉ����ĐV���ɋ����|���߂ĕ������̂Ƃ��āu���r�c�����|�v���c���Ă��邪�A����10���ڂɁu�M�Z�V�V�͓��p�̋}���Ɍ�Ԍ��X�C�s�v���ׂ����v�Ƃ���̂͒��ڂ��ׂ����Ƃł���B����͎F���˂ɊJ�������ݗ�����m�w���炪�s����ȑO�̂��Ƃł��邩��A�����ʼn]���Ƃ���́u�M�Z�v�͐��m����10�i�ʎ��L���@�Ɋ�Â����̏�́u�M�Z�v�ł͂Ȃ��A�u���v�Ɓu�\���o���v�̂��Ƃł��낤�B
�F���˂ɂ�����u���l�v�A�u�_���v�̋���Ɋւ��ẮA�z����܂ޓ��k���˂Ƒ傫���قȂ��Ă����B�������������̋���@�ւł���u���q���v���F���˂ɂقƂ�ǖ��������B����͎F���˂ł͏����̏@���ł������@���֎~����Ă��������Ƃ��W���Ă�����̂Ǝv����B�܂��A�F���˂ɂ́A�z����܂ޓ��k���˂̂悤�ɁA�����_�Ƃ���_���̎����g�D���Ȃ������B�F���˂ɂ́A�u���m�v���܂ގm���K�����_�������������鐧�x�i�u�O�鐧�x�v�Ɓu�劄���x�v�j������A���_�����܂��]�n�͂Ȃ������B�n���́u���v�ɂ����Ă͎�����������{�Ƃ��Ă������珤�ƂɌg���l�������Ƃ��Ă����_�����ł���A�˂Ƃ̌q���肪�����ꕔ�̓����I���l�̑��ɍ��������܂��]�n�͂Ȃ������B�F���ł́u���w���y���ޕ����v�̒S����ł���u�����v�������B�ł������Ɖ]����B���̕ӂ̎���ɂ��ẮA�ڂ����́A�ٍe�w�z��l�E�{�x���l�Y�́w�F�������L�x�̒��́u�m�����v�� �F���̐��w�x�i https://www.kagoshima-u.ac.jp/shoujukai/re_tsuboi.pdf �j�́u3 �F���́u�M���v�Ɓu�啽���v�v���Q�Ƃ��ꂽ���B�����Łu�M���v�Ƃ͐����x�z�̍\���̂��Ƃł���B�F���˂͉���100���ɂ��V�����̗Y�˂ŁC��77���Ɖ]���邪�C����͖��i���݁j���ŁC���˂Ȃ݂ɕč��Ɍv�Z�����37���Β��x�ɂ����Ȃ炸�C�_�ƓI�ɂ݂�Ό����ėT���Ȕ˂ł͂Ȃ������B�{�x�́w�F�������L�x�i��3�Łj��38�łɂ́A�F���˂Ɠ��k���˂̎m���̌ː����r�����L�q�����邪�A����ɂ��ƁA�F���˂̎m���ː���46,529�˂ł���̂ɑ��āA�V���A�����A�{��A�R�`�A�H�c�A���A�X�̓��k7���i�V�����܂ށj�̎m���ː���49,252�˂ŁA�قڝh�R���Ă���B�F���˂̎m���́A���l���̖�4����1�őS���䗦�̖�5�{�ł���������A�����Ɏm���̐��������������������ł���ł��낤�B����́A�F���˂ł́A�������鉺�ɏZ�ޕ��m�����ł͂Ȃ��A�̍���113�J���́u�O��v�ɏZ�ޔ��_���m�̕��m�����ɓ���Ă��邩��ł���B�����̎m�������́u��������v�ɂ��A�m�C�A�̗́A���͂����߂鋳���₦���s���Ă����B���̂悤�ȁu�M���v���~����Ă����F���˂́A���ɂ͌Ñ�M���V���̌R���I�E�s�s���ƃX�p���^�ƃC���[�W���d�Ȃ��Č�����B
�w���{����j�����W�x�i�����ȁA����10�N��j�ɂ���āA�~���O���͂��̒��w�ߐ��̊w�Z�Ƌ���x�i�v���t�A1988�N���j�̑攪�͂ɂ����āA�]�ˎ���E�����ȍ~�ɋ敪���āA�e�{���̎��m�E���q���̕��z���E�W�v���Ă���B�����Ɏ����ꂽ�����́A�������{�ɂ��w�����v�ւ̊e�{�����ǂ̋��͎p�����e�����Ă���Ǝv����̂ŁA���̂܂ܐM����킯�ɂ͂����Ȃ����A���������̏ꍇ�A���{���ɔ�ׁA���m�E���q���̐����ɂ߂ĒႭ�A���m�͍]�ˊ��A�������A�����s�����A���ꂼ��A0�A1�A0�A�v1�A�@���q���́A19�A0�A0�A�v19�ƂȂ��Ă���B���������̒n�悲�Ƃ̓���́A�����݂̂��L���A�������S�i�s�j���A���m�E���q�������ꂼ��A1�C1�A��ӌS���A0�A13�A�哇�S���A0�A5�ł���B���̏W�v�͒n��I�ɕ��Ă���̂ŁA�����S��ɑ�ʂ̒����R�ꂪ���������Ƃ�z����������̂ł���B
�@�@�@
���m�E���q���̍��v������ԑ����̂͒��쌧�ŁA���m�͍]�ˊ��A�������A�����s�����A���ꂼ��117�A1�A7�A�v125�A�@���q���́A1196�A48�A97�A�v1341�ƂȂ��Ă���B���쌧�����̂悤�ɑ������R�ɂ��āA�C�����͎��̗l�ɏq�ׂĂ���B�u���쌧�ł́A�����˂̕����A�V�́E�m�s�n�̎U�݁A�X���̔��B�A���s�E�]�˕����̗����Ȃǂ̏�����������I�ɍ�p���āA��ʖ��O�̊ԂɍL�ĂȊw�K�v���ݏo���A�܂�����ɉ������鑽���̒m���l�����݂����Ƃ��������I���y���������B�v�܂��������̑����́A�R���i1304�Z�j�A���R�i1031�Z�j���������A����ɂ́u�ˎm����̔��˂≪�R�˓��ǂ����ʂɋ���M�S�ł��������Ƃ������Ă���悤�ł���v�i�O�f�̊C���������Ap.298�j�B�F���˂̔_���A���l�̏ɂ��ẮA�C�����͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B�u�i�F���˂́j�d�ł͎��n�̔����i�����j�A�����̂��Ƃ��́u���O�\�ܓ��v�Ƃ���ꂽ�悤�ɁA�z����₷��ߍ��ȕ��S���������Ă������A������Ƃ��������\�ɂ����̂́A�ق��Ȃ�ʋ��m���x�ł���B�������� �v����� (�F���̔_���ɂ�) ���q�����������u�J�l�v���u�q�}�v�ȂǁA�����������肦�Ȃ������Ƃ����킯�ł���B�v�A�u���q����������������؎��ɂ����͂��̒��l�K���͂ǂ��ł������̂��B�����ꔄ�ɂ݂���悤�ɁA�d�v�ȍ��Y�i�����ׂĔːꔄ�Ƃ��Ă����F���˂ł́A���Ǝ��{�̔��B�͂������邵���o�x��A���l�l�����̂��̂��Ǐ��ł��������A���̑唼�͗�ׂȏ����l�A���Ȃ킿�u�m���̌�p���i�B�j���v���߂�ނł����Ȃ���������A�ǂ݁E�����E�\���o���ւ̎��v�͂���߂ĕn��ł������B�v�i�����Ap.299�j
�@�@�@
����ɂ��Ă��]�ˎ���̐�����O�l�˂̒��ł��F���˂̓��ِ��͍ۗ����Ă���悤�Ɏ��ɂ͎v����B�F����1600�i�c��5�j�N�̊փ����̐킢�ɁA���É�15�㓖��E���ËM�v�̒��j�E���Ë`�O����1500���̕��𗦂��Đ��R�Ƃ��ĎQ�킵�Ă���B��w�̎ߌ���ɂ��Ă��炭�l�q�����Ă����`�O�R�́A���R�̔s�F���Z���Ƃ݂��A��300���̉Ɛb�ƂƂ��ɁA�ڂ̑O�̓G����˔j���Ė����炪��F���ɓ����A�����B�������҂ł����̂́A�`�O���܂ނ킸��80�����ł������Ƃ����B���ꂪ�L���ȁu���Â̑�(��)�����v�ł���B�ɂ��S��炸�A�`�O�̌Z�E�`�v�Ǝq�E���P��2�N�ɓn����̌��ʁA���Î��͑S���̂��ƍN�ɂ���Ĉ��g����Ă���B���łȂ���t�����Ă����ƁA���݂��������̎s���s���Ƃ��čs���Ă���u���~���w��v�́A���u�s�ɏW�@���ɂ���`�O���J�铿�d�_�Ёi�����~���j�ɎQ�q���邽�߁A�������鉺�̕��m�B���b�h�ɐg���ł߂Ċփ����̐킢�̑O��ɓ����鋌��9��14���̖�Ɏ������鉺���A������40�q�̓��̂���A���O���ĕ��������ƂɗR��������̂ł���B�ƍN��1606�i�c��11�j�N�A���̗L�͑喼�ɂ͎����Ȃ������u�Ɓv�̎����`�O�̎q�E���P�ɗ^���A�Ƌv�Ɖ��������Ă���B�����1609�i�c��14�j�N�ɂ́A�F���˂ɗ����o����F�߁A������12���𓇒Î��̏��̂ɉ��������Ă���B���̂悤�ȏ��u�͉ƍN�����Î���D�����Ă���悤�ɂ��������邪�A���̗��R��m�鎑���͂Ȃ��Ƃ����B
�@�@�@
�������̓��Î��ʓ@�E�匵���ɗאڂ���~���[�W�A���E���ÏW���يْ��̏�����Ύ��́A���Î��ƉƍN�Ƃ̓��ʂ̊W���A�������鎑���Ɋ�Â����̂悤�ɐ������Ă�����i2024�N2��15���t����{�V���w���E�j�̒��̎������i19�j�x�j�B�փ����̐킢�̒��O�A�ƍN�͓��Î���ʂ��A�����E���ɍ����������Ă������Ƃ���������������Ƃ����B�܂��A���N�o�����n��O�ɁA���Ë`�v�̒����l�Ɛb�E��(����)�V��(����)���A�o���J�n�Ɠ��Î����G�g�ɖd�����v�悵�Ă��邱�Ƃ�`���閾���̎���������A����ɂ́A���̖d���Ɂu���C���v�A�܂�ƍN���֗^���Ă���Ƃ���Ƃ����B������ĕ����R��̏����i�����j�E��(����)�t��(�ӂ���)�́A���{�̕����ɖd���𑣂��A�G�g�����҂��u���{�����v�ɕ����邱�Ƃ��c��ɏ�\����ƂƂ��ɁA���Ñ��Ɏg�҂�h�����A�ڐG�ɐ������Ă���B�����A���ƃp�C�v�����喼�͓��Î��������Ȃ������B�ƍN�͍]�˖��{���J������A�E���t���̒�Ă��������邽�߂ɓ��Î��𗘗p���悤�Ƃ��āA���Î������������A�D�������̂ł͂Ȃ����Ɖ]���̂�������Ύ��̐����ł���B�ƍN�ɂ͖��c�邩����{�����ɕ�������A�����͂��ՐɂȂ�Ƃ����v�����������̂ł͂Ȃ����Ƃ����B�F���ł͓��É�10�㓖��E���×��v�i1432�|1474�N�j�̍��́A�Ζ��f�Ղ̉Ԍ`�������������́u�����v�̂��A�Ŋ����f�Ղł��D�ʂɗ����A���s�Ŏn�܂������m�̗��i1467�|1477�N�j�̊O�ɂ��āA���Ȃ���Ɨ����Ƃ̊ς��������B�F���ł͌Â����疾�Ƃ̊W���[�������̂ł���B
�F���˂͕��N�ԁi1754�i���j4�N�|1755�i���j5�N�j�A�ؑ]�O��i�ؑ]��A���ǐ�A�K���j�̎����H���{���������Ȃǂ̎������Ȃ�����A����Ƃƈ��ʊW��z���Ȃǂ��Ė��{�Ƃ̗F�D�W��ۂ��A����̂̍����Ԏ�������Ȃ���������܂Ő������т��B�����Ē����L���i���q��j�i1776�|1849�N�j�ɂ��������v�ɂ��A�]������܂Œ~����Ɏ������B����ɂ͗�����������f�Ղ�쐼�������Y�́u�������v�̐ꔄ���^�����Ă����B���{�̓�́u�ǂ�l�܂�v�ɂ���F���˂��A�Ȃ������ېV�̒��j��S���������̐l�ނ�y�o����Ɏ��������́A�u�����ېV�̕s�v�c�v�ł��邪�A���͂��̗��R�́A�R�����ƁE�F�����x�����O�鐧�x�Ƌ�������A�����āA�C�m���ƁE�F������������čs���Ă��������Ƃ̒��v�f�ՂȂǁA���N�ɓn�鏔�O���Ƃ̐ڐG�̒��ň���ۊ��o�ɂ���ƍl���Ă���B�F���˂ɂ͐E���Ƃ��āA���ʎ��i�ʎ��j�A���N�ʎ��A����і����ɂ͐��m�ʎ��i���ʎ��A�m�ʎ��j���u����Ă����i���i�a�쒘�w�C�m���ƎF���x�A����V�ЁA2011�N���A��l�́A���߁j�B
�@
�u���܁v�́u�܁v�́u�������v�̂��ƂŁA�u���v�́A���S���i�����j�⑁�����i�����Ƃ߁j�́u���v�Ɠ������̂ł���Ƃ����i�w�F���̃L�Z�L�x�A�ҎҁE�F�������������u�`�F�X�g�v�A�����@�ߏo�ŎЁA2007�N���Ap.303�j�B�F���͕����ʂ�{�B�̋������A�n�ʂĂ�y�n�ł������B�������A�F���̓�ɂ͊C���J���A�������A���i�Ǖ����A��q���A���v���A�g�J���A�����哇�A���V���A ���i�Ǖ����A�^�_�����̓��X���o�āA����{���ɒʂ��Ă����B����{���̐�́A�v�ē��A�{�Ó��A�Ί_���A�^�ߍ����Ƒ����A���{�Ő��[�̓��A�^�ߍ����Ƒ�p�Ƃ͖ڂƕ@�̐�ł���B���̂悤�ɎF���́A�������{�y����쐼�����Ɍ������ĐL�т�C�̓��ɂ��A��p�A�����A�C(��)�v(�\��)�i�t�B���b�s���j�A����i�׃g�i���j�A��(�V��)��(��)�i�^�C�j�A�W�����i�C���h�l�V�A�j�ƌq�����Ă����B���̐�̃}���b�J�C�����o��ΓV���i�C���h�j�Ɏ���B�������̐�������іk���̊C�ɖڂ�]����ƁA�����A�����A�ܓ��A���˓��A���A�Δn�A�ϏB���i�؍��j���o�āA�k����B�A���N�����ɒʂ��������̊C�̓����������B�����̃T���S�ʂ̊����ł����������Ȃ��L�i�C���L�E�S�z�E���L�Ȃǁj�̘r�ւ��A�k����B�����łȂ��؍��암�̌Ñ��Ղ�ڈΒn�̌Ñ��Ղ�����o�y���Ă���悤�ɁA���Â̐̂��炱�̊C�̓���ʂ��čL���𗬂��s���Ă����B
���{�ɕ�����`���������̑m�A�Ӑ^���A���{�ɏ㗤�����͎̂F���V�Â̏H�ڂł���A752�N�̂��Ƃł���B�����A�V�Â͔����A�Ái�ɐ��j�ƕ��ԁA���{�O�Â̈�ł������B1543�N�A��q���ɕY�����������D�ɏ���Ă����|���g�K���l�ɂ���ēS�C���`�����A�퍑����̓��{�ɑ���ȉe����^�����B���V�i�C���q�s���Ă����D�͓x�X��j���A�������̓쐼�ɉ��т铇�X�ɕY�������̂ł���B���{�ɃL���X�g����`�����C�G�Y�X��̐鋳�t�A�t�����V�X�R�E�U�r�G���́A�}���b�J�ŏo�������F���̐l�A���W���E �̎�����ŁA1549�N�Ɏ������p���̌��E�������s�_���V�B�ɏ㗤���Ă���B �����āA�ɏW�@��i��F��A���E�����������u�s�ɏW�@�����c�j�Ŏ��喼�̓��ËM�v�ɉy�����Ă���B���{�ɂƂ��ẮA�F���͐V���������������Ă����̌����ł������B���ËM�v�̎q�E�`�v�́A��F�̗Ǎ`�E�R��`�𓇒Î��̒����n�ɂ��A���D�f�Ղ݂̂Ȃ炸��ؖf�Ղ��������āA�f�Ղɂ��o�ϗ͂̒~�ς��\�z���Ă����B�`�v�̎q�E���P�i�Ƌv�j�́A�\�z�ɂƂǂ܂炸�A���ہA���s�E���̏��l�B�ƌ��т��L��I�Ȗf�Ղ�W�J���Ă����i�O�f���i�a�쒘���Ap.22�|p.28�j�B�ƍN���]�˂ɖ��{���J���ƒ��P�́A�ƍN�������s���ĖႢ�A���Ƃ̊ԂŎ��D�f�Ղ��s�����B�����3�㏫�R�ƌ��ɂ���č����߂����߂����܂ő������B�C�m���ƁE�F���̖ʖږ��@�Ƃ����Ƃ���ł���B
�Ńg�b�v��
�@
�]�ˎ����ʂ��Đ��m���w�̒m���̗A���ɂ͎O�x�̑傫�Ȕg���������B��x�ڂ��A���m�̓V����@���g����������݂�ꂽ18���I���߁A8�㏫�R�g�@�̎���A��x�ڂ��O���D���p�ɂɓ��{�̎��ӂɌ����悤�ɂȂ���19���I�̏��߂��璆���ɂ����ĊC�h��Ƃ̊W�ŁA�O�x�ڂ�1854�N�i�Éi7�j�N�ɓ��Ęa�e�����A�J�����Ĉȍ~�̖������ł���B��x�ڂ͊�����ʂ��āA��x�ڂ͒���o���ɂ������ꂽ������ʂ��āA�O�x�ڂ����������͉p����ʂ��Ăł������B
�L���X�g���v�z�̗�����h�����߂ɁA1630�i���i7�j�N�A�u�֏��߁v����߂��Ă������A1720�i����5�j�N�A8�㏫�R��g�@�͉���̕K�v�ォ��u�֏��ɘa�߁v�߂����B����ɂ��w���������x�S�S�����A�����ꂽ�B�����g�p����Ă����勝���i5�㏫�R�j�g�̎���A��������̗�A�u�������v�����Ƃɏa��t�C(�͂��)���҂��́j�̕s�����w�E����Ă������߂ł���i[21]�Ap.109�j�B�w���������x�͖����̐�����̎��A�����[���A�_�����V���[����鋳�t�B���琼�m��@���w�сA����̂��߂Ɋ��s������ŁA����20���͐��w�A���Ɋw�Ɋւ�����e�ł������B�Ȍ�A��p�A���ʏp�A�q�C�p�ɊW���鐔�w�Ƃ��āA�O�p���\��@���ʎO�p�@�A����ɑΐ��Ȃǂ������Ă���B���̍��A�C�G�Y�X��̃L���X�g���鋳�t�}�e�I�E���b�`�i����⅁j�ɂ�郆�[�N���b�h�́w���_�x�̑�6�͂܂ł̊��w���{�x�͊��ɑ��݂��Ă������A���҂��L���X�g���̐鋳�t�ł���Ɖ]�����R�ɂ��A���͋֎~���ꂽ�B
18���I�I��肩��19���I���߂ɂ����āA�I�����_�ʎ���ʂ��ē����Ă������w���Ƃ��ẮA�u(��)�}(�Â�)���Y�i1760�|1806�N�j�ɂ��w��ېV���x�i��E���E���A1798�|1802�N�j������B���̖{�ɂ���āA�j���[�g�������w�����߂ē��{�ɏЉ�ꂽ�B���쒷�p�A��{�h��A�ɓ����p�A�˒ːÊC�炪����̃V�[�{���g�̖�m�i1824�|1828�N�j�Ŋw��ł���B���̍��A���{�̋ߊC�ɊO���D���p�ɂɌ����悤�ɂȂ������߁A1825�i����8�j�N�Ɂu�ٍ��D�ł������߁v���o����Ă���B
���А푈�i1840�|1842�N�j��̏�C�ɂ����āA�C�M���X�l�A���N�T���_�[�E�E�B���[�i���C���[�j�i�̗́A1815�|1887�N�A�鋳�t�j�𒆐S�Ƃ��Đ��m���w�̕��y������B�ނ̌������x�߂̊w�҂��M�L���āA�����̊������w�������q���͖|�ꂽ�B���̈�E���������A�w���w�[�ցx�i1853�N�j�A�w�㐔�w�x�i1859�N�A�h�E�����K���̏��̊���j�A�w����ϏE���x�i1858�N�A�A�����J�̃��[�~�X�̏��̊���j�A�w���{�x�i���[�N���b�h�́i�w���_�x�j��6���܂ł��A�}�e�I���b�`�i����⅁j�������[�̋��͂Ċ������̂ɁA�E�B���[���Ō�܂Ŋ������̂�t�������č��{�������́j�Ȃǂł���B�����̏��������v�N�ԁi1861�|1864�N�j�ɐ������A������Ă���B
\par
\bigskip
�@
���{�ɂ����Đ��m���w���ŏ��ɑg�D�I�ɋ�����ꂽ�̂́A�J�����1855�i����2�j�N�ɖ��{�ɂ���Đݒu���ꂽ�u����C�R�`�K���v�ɂ����Ăł������B�u����C�R�`�K���v�͊C�R�m����{������w�Z�ł������B�I�����_�R�l�����t�ɁA�q�C�p�E�^�p�p�E���D�w�E�@�֊w�E�D��w�E���ʊw�E�Z�p�E�C�p�E�C�����Ȃǂ̏��w�Ȃ��w�����B���{��1857�i����4�j�N�ɁA����C�R�`�K���̑������Ő��їD�G�Ȗ��b15���ʂ��]�˂ɌĂі߂��āA�z�n�̍u�������Ɂu�R�͋������v���J�����B�u�R�͋������v�͂��̌�A1864�i�������j�N�Ɂu�R�͑������v�Ɖ��̂���Ă���B1857�i����4�j�N�ɂ́A����t�O(�����)�i1832�|70�N�j���A�Z�p�����A�ʎ��L���@��p�����ŏ��̎Z�p���ł���w�m�Z�p�@�x���o�ł��Ă���B���̖���t�O�͐��w�҂Ƃ������͗m�w�҂ƌĂ��ׂ��l�ŁA��w�̍˔\�ɗD��Ă����B1862�i���v2�j�N�ɂ͔�������m�������ɉ��g���āA���̒��ɐ��w�ǂ��u���ꂽ�B1863�i���v3�j�N�ɗm�w�̋��猤���@�ւƂ��Ė��{�J������ݒu�B1864�i�������j�N�H�A�J�����K���𐧒肵�A�w�������Ă̊w�Z�ɂȂ炢�A�����Ȗڂ𗖁E�p�E���E�ƁE�I�̌�w�ƓV���E�n���E�����E���w�E���Y�E���w�E��B�E��w�E�����̏��ȂƂ��邱�ƂɂȂ����B����ɔ����A���{�J�����̐��w�����ł������_�c�F���ɂ���āw���w�����@�x���o�ł��ꂽ�B�@���{�J�����Ō�̓���ł���A�J�����̌�g�ł���J���w�Z�̏��㓪��߂��̂��A�w�m�Z�p�@�x��������t�O�ł������B
�Ńg�b�v��
�@
�������s�ɂ͔ɉ؊X�̒��S�Ɂu�V���فv�Ƃ����ꏊ������B���Ă����ɂ́A�ȓV�V�A���ߕ\�A�]��������������A�����قƂ���������{�݂��������B�����n�����͎̂F����8 ��ˎ�E���Ïd��(�����Ђ�)�i1744�|1833�N�j��1779�i���i8�j�N�̂��Ƃł���B�F���˂ł͏a��t�C���勝�����������ȗ��A������邽�тɔˎm��h�����җ���w���Ă������A���܂���1765�i���a2�j�N�A���{���V������]�ˋ����ɑ���A�����ꏊ�ɐV������������Ƃ��A�F���˂��珕�肪�o�p���ꂽ�B�����ł��ĕ�����̂Ƃ�����߂����ԗǎ����h�����ꂽ���A���Ԃ͓V�������X�؏G���ɂ��Ă���������A8�N���1772�i���i���j�N�ɋA�˂����B������_�@�ɎF���̓V����Ɨ�ǂ��ݒu���ꂽ�B���ꂪ�����قł���B�����قł͓V�̂̊ϑ��ƌv�Z�ɂ��V�̂̉^�s�̗\���A�Ȃ�тɗ�̕Ҏ[���s��ꂽ�B�d���͗��ȑ喼�ƌĂ��قǐ��m�̉Ȋw�E�Z�p�ɋ����������A�I�����_���و�V�[�{���g�ƍ��e�ȊW�ɂ��������ƂŗL���ł���B�d���͕�������������߁A�ˍZ�ł��鑢�m�فE�����فi1773�N�j�A��w�@�i1774�N�j���n���Ă���B�d���͐퍑�̈╗���c�����e��Ȏm�������߂悤�ƁA������珤�l�A���ҁA�|�W�A���W�Ȃǂ��ĂъĂ���B��������̎{��ɑ��锽�����傫�������B�˂̍����x�o�����傷��ƂƂ��ɁA�ł̕��S�҂ł���_�����敾��������ł���B�d����1787�i�V��7�j�N�A43�ʼnB�����A�ˎ�̒n�ʂ�15�̒��j�A�Đ�(�Ȃ�̂�)�ɏ������B�Đ�́w�ߋT�ⓚ�x���A�ߐb�ɔː����v�̈ӎv�����������A���̓��e�͒��F�����A�ߌ��m����������̂ł������B���̐Đ�̈ӎv�ɉ����ĉ��v��i�߂��̂́w�ߎv�^�x�i��q�w�̋��{�j�����ǂ��鎿�������̎F���l�m�B�ł������̂ŁA�u�ߎv�^�h�v�ƌĂ��B�������A�ނ�̎{��͕��ÐF�̔Z�����̂ŏd���������߂��J���I�A�i���I�Ȏ{��Ɛ^��������Η��������ߏd���̋t�ɐG�ꂽ�B���̌��ʁA���R�v���E�����G�ۗ��ƘV���͂��߂Ƃ���ߎv�^�h�̐l�тƂɌ���������������A�ː������|����邱�ƂɂȂ����i�ߎv�^����j�B�Đ��1809�i����6�j�N�A�����I�ɉB���������A�ˎ�̍��͐Đ�̒��j�E��(�Ȃ�)��(����)�Ɉ����p���ꂽ�B�d����1833�i�V��4�j�N�����A89�ŖS���Ȃ�܂ŁA�T�ᖳ�l�Ƃ���������̐��������т������A���ꂪ�\�������̂́A�����Đ��܂ꂽ�ˋC�ɉ����āA77���̊O�l�Y�˂̔ˎ�A�㌩���Ƃ��Ă̒n�ʂƁA11�㏫�R�ƐĂ̊x���i�ΕP�͉ƐĂ̐����j�Ƃ��Ă̈Ќ�������������ł���Ǝv����B
�F���˂������ېV�ɂ����ċɂ߂ďd�v�Ȗ������ʂ��������Ƃ͒N�����F�߂�Ƃ���ł��낤���A������\�Ƃ������R�́A��͂�u�R���́v�̗D�ʐ��ł��낤�B�u�R���́v�̗D�ʐ����������ẪN�[�f�^�[�𐬌������A��C�푈�������ɓ��������͂ɂȂ����B���̉e���͂́A����푈�ŎF�����s�҂ƂȂ�܂ő������B�F���˂ł͑��˂ɐ�삯�Ĕˍ����̗��Ē����ƌR���͂́u�ߑ㉻�v���}���Ă����B�d���E�Đ�̎���A�F���˂͔���Ȏ؋�������o�ϓI�ɍ������Ă����B�ˍ����̗��Ē����́A�d���̌䑤�p�l�E�����L���i���q��j�𒆐S�ɂ��Ă����߂�ꂽ���A�l�X�ȕ�����u���邱�Ƃɂ��A1840�i�V��11�j�N�ɂ́A�ˌɒ�����50�����̊O�ɏ��c�U��p200�����ɒB����܂łɂȂ����B
�F���˂�1609�i�c��14�j�N�A�������x�z���ɒu���ƂƂ��ɉ����ܓ����n�ɂ��A���{�̓����̂��Ƃŗ�����ʂ��Ē����Ɩf�Ղ��s���Ă����̂ŁA���̃��[�g���琼�m����Ɋւ���j���[�X�͂�����������ł����B1837�i�V��6�j�N�A�����\�����������N�������B�����\�����Ƃ́A�L���̃A�����J���ЃI���t�@���g����̑D�ŁA���{�l�C��D��7������{�ɑ��҂��A������@��ɓ��{�Ƃ̖f�ՂƃL���X�g���̕z���̒[�����J�����ƉY�ꉫ�ɗ������A�C�����ĖړI���ʂ������A�]���ĎF���E�R��`�ɐڋߒ┑�����B�F���˂ٍ͈��D�ŕ��߂Ɋ�Â��C���������A�����\�����͐ɓ��d�������œ����Ȃ������ɂ�������炸�A����̑�����^���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�����\�����́A���̂܂ܒE�o���L���ւƋA���Ă������B�]���̓��{�̖C�p�ł͒ʂ��Ȃ����Ƃ�m�����F���˂́A�ˎm��ɔh�����A�������C�p�����������������H���ɐ��m�C�p���w�����B���̂����A�F���˂͍����H���̒���Ő��m�̏e�C���w�����A1842�i�V��13�j�N�ɂ́A�������ٓV�z�n�Ő��m�e�C�̒������n�߂��B�ˎ�̐ċ�����C�ˌ����K�����{����틳�����s���Ă���B����ȗ��A�������C�p�����Éƌ䗬�V�ƂȂ����B
1844�i�O�����j�N�ȍ~�A�����E����։p�ĕ��̑D���O���E���Ղ����߂đ������œn������悤�ɂȂ������Ƃ�[���Ƃ��āA�F���˗̂̊�E���E���V���E�����哇�E�����ɂ����p�D�����q����悤�ɂȂ����B���̂悤�ȏɊ�@�����������F���˂ł́A1846�i�O��3�j�N�A�ˎ�E�ċ��͐��q�E��(�Ȃ�)�j(������)���A�������A�O���ɔ����C�ݖh���Ȃǂ̎w�������点�邱�Ƃ{�֊肢�o���B���{���A�����A���Q�ɊO������ɖ��邭�A�p�������ĕj�Ɋ��҂��A�V����˓@���킵������������B��3�N10��������R���͋����E�R�����v�̋�̓I���g�݂��n�܂����B�R���̊�ɂȂ鋋�n���̉����A�m�������ւ̈ڍs�A�m���e�C�����̂��߂̒������̐ݗ��A�C�p�ق̐ݗ��A�e�e�E�C�e�����ɕK�v�Ȍ������s������قƉΖ����̐ݗ��Ȃǂł���B�C�p�ق͗m���e�C�̉^�p�p����������Ƃ���ł��艉�K�{�݂ł������B�ٓ��ɂ́u���Е��v�A�u���ʕ��v�Ƃ����{�݂�����A�R���Ȋw���̕ۊǂƎʖ{�̍쐬���s���Ă����B
1851�i�Éi4�j�N2���A�ċ��̌���p���Ŕˎ�̍��ɂ����ĕj�́A���q����̍�����ێ悵�����Ă����m���z��p�E�h�q�p����ɋэ]�p�h���̂��߂̗m���C������������B����ɁA�m�����D�A���˘F�E�n�z�F�̌��݁A�n���E�����E�K���X�E�K�X���̐����Ȃǂ̏W���َ��Ƃ��������B1851�i�Éi4�j�N7���i���z���8�����j�ɂ́A�y���˂̕Y�����ŃA�����J����A���������l�����Y�i�W���������Y�j��ی삵�ˎm�ɑ��D�@�Ȃǂ��w�����B�y���[�����q�����̂͂��̒����1953�i�Éi6�j�N�̂��Ƃł������B1854�i�������j�N�A�m�����D�u����͊ہv�����������A���D�p���z���������邽�߂ɖؖȖa�ю��Ƃ��������B�����Đ��m���R�́u�����ہv�����������{�Ɍ��サ�Ă���B���D���q�ȑO������C�@�ւ̍��Y�������݁A���{�ŏ��̍��Y���C�D�u�_�s�ہv�Ƃ��Č����������B1855�i����2�j�N�ɖ��{�ɂ���ĊJ�݂��ꂽ����C�R�`�K���ɂ́A�ܑ�ˏ��i�F���j�A�쑺�o�\�Y�i���`�j��16���̎F���ˎm��`�K���Ƃ��đ��荞��ł���i[15]�Ap.942�j�B���R���i�C�R�j�n���̂��߂̕z�ł������B�܂��A���m�K���o�g�̐����������v�ۗ��ʂ�o�p���Ē���ł̐��ǂɊւ�����B�������A�������v���Ƃ��ɂ����߂��V���E�������O�̎���A��V�ɏA�C������ɒ��J�ɂ���Đĕj�͉��������Ă��܂����B1858�i����5�j�N�A����ɍR�c���邽�ߗ����㗌�����ӂ��邪�A�R�����K���w���A�{�����ɋ}�������B����ɔ�����ꌚ�݂͈ꎞ���f����邪�A�V�ˎ�E�v�ɂ���Čp�����ꂽ�B
�ˎ�E�v�̕��E���Ëv�����ĕj�̈ӎv���p���A���𗦂��č]�˂ɏo�����Ă̋A�r�A1862�N9��14���i���v2�N8��21���j�A�u���������v���N�����A���ꂪ���Ƃŗ�1863�N8���i���v3�N7���j�A�C�M���X�Ƃ̊ԂŐ푈���N�������B������u�F�p�푈�v�ł���B�F���˂͂��̐푈�Ŕs�҂ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��������A�R���Z�p�ʁA�Ƃ�킯�C�R�͂ł̐��m�Ƃ̍����v���m�炳��A�푈��̘a�r�����o�ăC�M���X�Ƌ}�ڋ߂��邱�ƂɂȂ����B���̌��ʁA1864�i�����j�N6���ɁA�m���ɂ��R���g�[�ƌR�������̐l�ޗ{����ړI�Ƃ���m�w�Z�u�J�����v���J�݂����B�܂��A�J���������E�Ή͊m���Y�̌����Ɋ�Â��āA���N�̐����A�C�M���X�ւ̗��w���𑗂�o���Ă���B��ɏ��㕶����b�Ƃ��ē��{�̋ߑ�I���琧�x�̐����ɐs�͂����X�L��i���V��j�i1847�|1889�N�j�́A���̊J�����ʼnp�w���w�сA�C�M���X���w���ɂ��I��Ă���B���́u�J�����v�̊w�ȖڂɁu�V���A�n���A���w�A���ʁA�q�C�v�Ƃ���B���̂����u���w�v�͎Z�p�E�E�㐔�A�u���ʁv�͕��ʎO�p�@�A�u�q�C�v�͋��ʎO�p�@���܂ނ��̂ł������Ɛ��������B�F���˂ɂ����āu���w�v�����ȂƂ��ċ�����ꂽ�̂͂��̎������߂Ăł������B�ċ��E�ĕj����ɑn�݂��ꂽ�u�C�p�فv�͂��̌�A�x�X���̂��ύX���ꂽ���A1867�i�c��3�j�N1���Ɂu���R���v�ƂȂ�A�����ɁA�V���ȌR���g�D���g�D���ꂽ�B
�Ńg�b�v��
�@�@�@
���{�ɂ����鐔�w�̋N���́A6���I�ɕS�ς��畧���ƂƂ��ɗ�`��������ɂ����̂ڂ�B�����A�����Ñ�̍ő�̐��w���w��͎Z�p�x���A������Ă����B�ޗǎ���ɂȂ�ƁA�����̉ȋ����x���܂˂����ߐ��������x�̎����ɂ����Đ��w�����K�ȖڂƂ��Ď��グ����悤�ɂȂ����B���̌�A���{�́u���w�v�ɁA��������i�W�͂Ȃ��������A�퍑���ォ��D�L������o�āA�R���Z�p��z��p�̊v�V�A�z�R�J���⌟�n�Ȃǂ̎Љ�I�K�v����A���Ƃ̔��B�ɂ���āA�]�ˎ���ɂ͓��{�Ɠ��̐��w�������ԊJ�����B
�@
�]�ˎ���́u���w�v�́u�\���o���v�ɂ��v�Z�ƎZ�ՂƎZ��p�����V���p�Ƃ����A���̊��㐔����Ȃ��Ă����B�u�\���o���v�ɂ��v�Z�͍]�ˎ����ʂ��čL���ǂ܂ꂽ�A�g�c���R�i1589�|1673�N�j�́w�o���L�x�i1627�N���j���L���ł���B���R�͎��D�f�Ղō����Ȃ��������p�q�Ƃ̈ꑰ�ł���B���R��15���I���A���N�o�R�œ��{�Ɉړ����ꂽ�����̐��w���w�Z�@���@�x�i1593�N�A����̖��Ԑ��w�ҁA����ʂ̒��j����ɂ��āw�o���L�x���������Ƃ����B���Ȃ݂Ɂw�o���L�x���������v�Z���́A�u�Ă̔����Ƃ���ɔ����v�Z�v�A�u���◼�ցv�A�u�K�̔����v�A�u�����v�A�u���z�̔����v�A�u���n�v�A�u�D���v�A�u���v�A�u���n�ƐŁv�A�u��X�̍H���v�A�u���ʁv�A�u�J�����v�A�u�J���@�v�ȂǑ���ɓn��B�Z�ՂƎZ��p�����V���p�́A������15���I���ɒ��N�o�R�œ��{�Ɉړ����ꂽ�����̐��w���w�Z�w�[�ցx�i1299�N�A����̖��Ԑ��w�ҁA�鐢���̒��j�ɂ���Ă���B���̏��̓A���r�A��C���h�̉e����������Ƃ����B������u�a�Z�Ɓv�ƌĂ�l�X�̓\���o���Ōv�Z�����A�㐔��������V���p�ʼn������Ƃɂ���āA���낢��Ȑ��w�̖����������B�u�a�Z�Ɓv�Ƃ��ẮA�֍F�a�i1642�H�|1708�N�j�Ƃ��̍���A�������O�i1664�|1739�N�j���L���ł���B�ւ�25�̂Ƃ��A�ޗǂ̎��ɂ����������̐��w���w�k�P�Z�@�x�A�i������̓V���p�̏��A���w�A�s����������������Ă���j���ʖ{���������Ă���B�܂����̎���ɏ����ꂽ�w�������x�����A�����ꂽ��w�V���听�ljM(����)�S(���イ)�v(�悤)�x80����Ɨ͂œǂݐ����Ƃ����B�ւ̐��U�ɂ��Ă͓�̕������������A�]�ˋl�̍b�{�ˎm�Ƃ��Č�d�A�䊨���l�߂����A���n�⑪�ʂɊւ���Ɩ��ɂ��g����Ă������ƁA��N�b�{�ˎ哿��j�L�i��ɉƐ�Ɖ����j���f���̏��R�j�g�̗{�q�ɂȂ��č]�ˏ鐼�̊ۂɓ������̂ɔ����A���ی�[�ˑg���ƂȂ��Ɛl�ƂȂ������ƁA����4�N��ɖv�������Ƃ͊m���Ȃ��Ƃł���B�ւ͈ꌳ�����㐔�������̋ߎ���@���J�������B����͓����̃��[���b�p�ɂ����ăz�|�i�|�iHorner�j�̕��@�Ƃ��Ēm���Ă�����̂Ɠ������̂ł������B�ւ͎Z��p����V���p�������łāu�T���@�v�Ƃ����M�Z�ɂ��㐔�v�Z�̑̌n���������Ă��B����́u�_�(�Ă�)�p�v�ƌĂ��B�����A���㐔�������̏����@�ɂ���@����s�̊T�O�ɒB�����B�~�����A�~�ʂƌ��̒����̊W�Ȃǂ����������B�����Č����͋t�������̃e�[���[�W�J�ɑ������鎮�������Ă���B�֗��a�Z�ƂƂ��Ă�18���I���Ɉ���(������)��(�Ȃ�)�~(�̂�)���o�ċȐ��̒�����Ȑ��ň͂܂ꂽ�����̖ʐς����߂邽�߁A�����̒�ϕ��ɑ���������̂��l�Ă��Ă���B�����̉~�Ɗւ�鐔�w�́u�~���v�ƌĂ��B�ցA������͐����̐��E�̖@��������������u���w�ҁv�Ɖ]���鑶�݂ł���B���{���w��ɂ�50��ڂ̔N����L�O����1995�N�ɂ��̓�l�̖��O���������w��܂�݂��Ă���B
�u�a�Z�v�́A���w��m�I�V�Y�Ƃ��Ċy���ޕ����Ƃ��āA�����ԁE�����Ɠ����悤�ɏ����̂������ɍL�܂����B�u�֗��v�A�u�ŏ�(�������傤)���v�A�u�������v�Ȃǂ̃M���h���`�����Ƌ����x���Ƃ��Ă����B���w�̖����������A��肪������Ɓu�Z�z�v������Đ_�Ђɕ�[�����B���́u�Z�z�����v���܂߂č]�ˎ���̐��w�����ɂ͎��̎O�̗��ꂪ�������Ɖ]����B
�i1�j ���p���w
�@�E�����i���l�A�E�l�A�_���j�̎��p���w�i�\���o���j
�@�E������l�i���m�j�̎��p���w�i�\���o���A�v�Z�p�A���ʏp�j
�@�E���̓����ҁi���m�j�Ƃ��Ă̎��p���w�|�V���E��p�ƌR���Z�p�i���w�A�C�p�A�z��p�A�q�C�p�A���D�i���C�D�j�p�A���e�C�i���e�E��C�j�p�j
�i2�j��E���{�Ƃ��Ă̐��w�i�Z�z�����j
�@�E�S����͏����i���l�A��w�_���j
�i3�j�a�Z�Ƃ̐��w�i�Z�ՂƎZ�A�_p�A�㐔�������A�~���j
�@�E�S����͎�Ƃ��ĉ������m�A��E���w�_���A���l
�����ɂȂ��č�������Ƃ��āu���m���w�v���������ꂽ�Ƃ��A���ꂪ�Z���Ԃʼn\�ł������͍̂]�ˎ���Ɂu�a�Z�v���L���s���Ă�������ł���ƍl������B�������A���[�N���b�h�́w���_�x�̊���{�A�w���{�x�������̕��v�N�ԁi1861�|1864�N�j�ɓ��{�ɓ����Ă����Ƃ��A�قƂ�ǂ̘a�Z�Ƃ͂��̈Ӌ`�𗝉����Ȃ������B�ނ�̐��w�͋Z�I�I�ɓ�������l���A������������߂̑����A���������𗧂āA�����V���p�܂��͖T���@�i�_ₖ@�j�ʼn����Ƃ������̂��قƂ�ǂł������B�ނ�̐��w�ɂ͏ؖ����Ȃ������B���w�ɂ�����_���L�����������悤�ɂȂ����̂́A�����ɂȂ��ă��[�N���b�h�w���藝�̏ؖ����܂߂ċ�������悤�ɂȂ��Ă���ł���B
���{�ɂ����āA���[�N���b�h�w�������n����o�����ďؖ��t���ŏ��߂ċ�����ꂽ�̂́A1871�i����4�j�N�ɗ������� �A�����J�l�����w���t�AW.E. �N���[�N�iEdward Warren Clark�A1849 -1907�N�j�ɂ���Ăł���A�É��˂̐É��w�⏊�ɉ����Ăł������B�����ېV�ɂ�蓿�얋�{������������A����@�Ƃ͏x�́E���]�E�O�͂�70����^������喼�ƂȂ������A���̔˂��É��˂ł���B�É��˂ɂ͖������ɖ��b�Ƃ��Đ����ɗ��w�����l��������R�����B�����̐l���������S�ƂȂ��đn��ꂽ�̂��É��w�⏊�ł���B�É��w�⏊�ł̃N���[�N�ɂ�郆�[�N���b�h�w�̍u�`�́A�w�w���b�x�i�N���[�N�搶�����A�R�{�����E ��k���� �T�A ���ѓ��j�Ƃ���1875�N�i����8�j�N�ɏo�ł��ꂽ�B���̖{�ɐ旧���A1873�i����6�j�N�Ɋ��ɁA�����Z�O�Y�ɂ���āA�ؖ��t���̊w���ȏ��Ƃ��ăf�B���B�X�iDavis�j�́w�w�����x���|�s����Ă���B���̖{�͕����Ȑ��E�}���i���ȏ��j�ƂȂ����i[23]�Ap.236�j�B�ؖ��t�����[�N���b�h�w�̕��y�ɂ́A�䂪���ŏ��̐��w�̑�w�����A�e�r��[(�����낭)�i�����Z�j�i1855�|1917�N�j�̊�^����Ƃ��낪�傫���B�e�r�͔؏������̕M�������E����薕�i1799�|1863�N�j�̖����E����H(���イ)��(�ւ�)�i1826�|1886�N�j�̓�j�ł���B1866�i�c��2�j�N�A��11�̂Ƃ��A���{�h���E��ꎟ�p�����w��14���i��2���͎�����j�̈�l�Ƃ��ĉp���ɗ��w�i���w�����A�ŔN���j�A�����h����w�̃��j�o�[�V�e�B�E�J���b�W�̕t�����Z�A���j�o�[�V�e�B�E�J���b�W�E�X�N�[���ɒʊw�������A1867�i�������j�N�A���{�����̂��ߋA���B1870�i����3�j�N�A�������{�̖����A2�x�ڂ̉p�����w�B�͂��߁A���j�o�[�V�e�B�E�J���b�W�E�X�N�[���ɒʂ�����A�P���u���b�W��w�̃Z���g�E�W���[���Y�E�J���b�W�ɓ��w�A���w���U�A���t�̒��ɂ̓g�h�n���^�[�iIsaac Todhunter�A1820�|1884�N. �wThe Element of Euclid�x�̒��ҁj�������B1877�i����10�j�N5���A�A���A���̔N��6���ɐݗ����ꂽ����́u������w���w���v�̋����ɏA�C�A���w�ƕ������������B���N�A�u�������w��Ёv�̐ݗ��ɎQ�����Ă���B
�����̏��߂ɂ́u���m���w�v�Ɓu�a�Z�v���������Ă������������������A����Ɂu�a�Z�v�́u���m���w�v�Ɏ���đ����A���w�j�̌����ΏۂƂȂ��Ă����B����͐��m���w�������E���w�E�H�w�ȂǁA�R���A�B�Y���ƂɕK�v�Ƃ��ꂽ���Ȋw�̊�b�Ƃ��Ă̈ʒu���߂�悤�ɂȂ������Ƃɂ����̂ł��낤�B���[���b�p�ɂ����Đ��w���R���E�Y�ƋZ�p�Ƃ̌��т������߂Ă����̂́A�s���v�����o�āu���{��`�o�σV�X�e���v���m������Ă����ߒ��ƋO����ɂ��Ă����B17���I�A�u�j���[�g���̗͊w�v�̒a�����_�@�ɐ��������u�����ϕ��w�v�́A18���I��ʂ��āAD.�x���k�[�C�i1700�|1782�N�j�A�I�C���[�i1707�|1783�N�j�A�_�����x�[���i1717�|1783�N�j�A���O�����W���i1736�|1813�N�j��嗤�̐����Ȋw�҂ɂ���āA�u��͊w�v�Ƃ��Đ�������Ă����i[44]�j�B�u�a�Z�v�̗��j�I�����͌��݂������ɍs���Ă��ĐV���Ȓm���������炳��Ă���悤�ł���i[26]�j�B�܂��u�a�Z�v������̐��w����ɐ��������Ƃ��鎎�݂��s���Ă���i[27]�j�B
�Ńg�b�v��
�u�ڏ؏p�͖��w�̊�{�Ȃ�v�Ƃ����A���v�ԏێR�̗L���Ȍ��t������B���̌��t�́w\ruby{��}{���傤}�P��\ruby{�^}{�낭}}�x�i��g���ɁA�u�P���v�̊����͌����j�̒��ɂ���B�u�ȃP���^�v�Ƃ́A����܂����Ȃ݂�L�^�̈ӂł��邪�A�ێR�������ɂ������Ƃ��̊�������ł܂Ƃ߂����̂ł���B�ێR�i1811�]1864�N�j�͖{���A��w�҂ł��������A��N�E�M�Z����ˎ�^�c�K�т����{�V���Ƃ��ĊC�h�|�ɂ����̂��@�ɁA���{���̊C�h�̂��߂̕�����������邱�Ƃ𖽂����A���m�̏���������Ȃ��ŁA���w�E���w�ɂ��ʂ���悤�ɂȂ����B�ێR�͍����_�ɑ��ĊJ���_�𑁂�����咣�����B�u�̏p�������Ĉ𐧂��v�Ƃ����̂��ނ̍l���ł������B1854�i�Éi7�j�N�A���̋g�c���A���ė��q�����y���[�̊͑��Ŗ��q����Ď��s����Ƃ����������N�������B�ێR�����̎����ɘA�����A�`�n���S���~�ɓ��������B���̌�A1862�i���v2�j�N�܂ŁA����ł�孋���]�V�Ȃ����ꂽ�B
�u�ڏ؏p�v�̓I�����_��� Wiskunde �̖�Ő��w�̂��Ƃł��邪�A�u�ڂ����ؖ�����p�v�̈Ӗ�����A���̕��͂������ďێR�����w�̉�㈓I�ؖ���m���Ă����Ɨ�������̂͌��ł��邱�Ƃ������C��w�����E��K�M�v���i�̐l�j�͎咣����Ă���i[21]�j�B��K���̐��ׂȌ����ɂ��A���̌��t���ŏ��Ɏg�����̂͘a�Z�ƁE���c�܊ρi1805 ? 1882�N�j�ł���A�ێR�͌܊ς���̎���ł���Ƃ����B�܊ς́u�ڏ؏p�v�ł͂Ȃ��u�ڏ؊w�v�Ƃ������t���g���Ă���̂����A���̌�́w���������x�ɍ̘^���ꂽ�A�v�g���}�C�I�X�́w�A���}�Q�X�g�x�ɗR������Ƃ����i[21]�Ap.127�j�B�܊ς�1805�i����2�j�N�A���b�E�{���s�Y�̓�j�Ƃ��č]�˂ɐ��܂ꂽ�B�c�����a�Z�̍˂����A1822�i����5�j�N�A18�Ŋ֗��U���@���̓`�������Ă���B�a�Z�ƕ��s���āA�m�E�߉~�ʂ���w���w�сA1822�i����5�j�N�A�܂���1828�i����11�j�N�ɁA����(�}�e�})��(�e)��(�J)�m���J���B����̐�y�A�a�c�J���A�~���̏p�̓`������B�������b�ɁA�~��歏p�W�������B��K���̌����ɂ��A�܊ς́i1�j�u �ڏ؊w�v�Ɖ]�����t���u�S�ȑS���h�v�̐��w�̍������M�����_�����x�[���ɂ��ł��L���Ӗ��ł̐��w�A�����������w�i���_�E�w�j�ƍ������w�i�͊w�E���w�E�V���w�E�n���w�E�N��w�E�R�����z�p�E���̐×͊w�E���͊w�E�q�C�p���j���܂ނ��̂Ƃ��Ďg���Ă���A�i2�j���[���b�p�̐��w�I���R�w�̊�b�ɂ���L���X�g���I���R�ρi�B��_��������n�����A���ׂĂ͐_�̈ӎu�̂��ƂɌ��肵�Ă���j�𗝉������B��l�́u�a�Z�Ɓv�ł���Ƃ����B
�Ńg�b�v��
�����̉���˂Ɋ��J�i1842�|1884�N�j�j�Ƃ����a�Z�Ƃ������B1856�i����3�j�N�A��14�̂Ƃ��A����ː��w�t�͎Z�p�҂Řa�Z�Ƃ̑�여�i�K�闬�j2���E���G���ɓ���B1864�i�������j�N�����A��여�a�Z�F�`����юw��Ƌ����擾���A1868�i�������j�N�ɂ͉���˔ˍZ�̗m�Z���t�ɍ̗p����Ă���B���͉���˂̊O������l���ɂ��ĉp����w�сA�m�Z�͎����Ŋw�K�����Ƃ����B���̌�A�����̗m���w�̖|�����B���������̍ő�̃x�X�g�Z���[���w���w�V��w�x�i22�����j�͔ނ̒���ł���B�F���˂ɂ́A���̂悤�ȁu�a�Z�Ɓv�͂����̂ł��낤���B�܂��F���̏����͘a�Z�Ƃ̎t���ɂ��āA���w����E���{�Ƃ��Ċy���ނ��Ƃ͂������̂ł��낤���B�w�F�������L�x�̒��̖{�x���l�Y�̎F���l�m�̉Ȋw�E���w�ɑ���ԓx�̋L�q��ǂ�ōŏ��Ɏv�����̂͂��̂��Ƃł������B�C���^�[�l�b�g��ɂ́u�a�Z�̊فv�Ƃ����T�C�g�i http://www.wasan.jp/ �j������A�����ɑS���́u�Z�z�v�̈ꗗ�\���ڂ��Ă����̂Ŕ`���Ă݂�ƁA�R���A���m�A����A�F�{�A�{��A�������̊e���͂�������u�Z�z�v�̋n�тł��邱�ƂɋC�t�����B�������A����ɂ͕���21�N��[�̎Z�z�����邪����͏����Ă���B���l�Y�́w�F�������L�x�̒��ŁA�u��ʂɐ���n���͎m���̐��͉��������ł��邪�A�F���͂��̋ɓ_�ł���v�Əq�ׂĂ��邪�A�����ɉ]���Ƃ���́u����n���v�Ɓu�Z�z�v�̋n�т��������Ă���悤�Ɏv����B���̂��Ƃ��炵�āA���́u���̒n��ɂ́A��E���{�Ƃ��Đ��w���y���ޕ����A����ѐ��w��T�����镶���A������u�a�Z�v�̕����͑��݂��Ȃ������v�Ƃ��������𗧂Ă����j���Ɋ�Â��Ď��ł����킯�ł͂Ȃ��B����̉ۑ�ł���B�F���˂ł͖������̔p���ʎ߂ɂ�莛�@���O��I�ɔj�ꂽ������l���ɓ����K�v������Ǝv����B��ʓI�ɂ́A���m�̐��͂������Ƃ���ł́A��E���{�Ƃ��Đ��w���y���ޕ����̒S����ł��钬�l�E�_���̗͂������B�ł��邩��ł���Ɖ]����B
���NjL��
2025�N7��4���t����{�V���́u�������ܒT���̉�v������a����ɂ��u����ς�Δ�D���v�Ƃ����L���ɂ��ƁA���Ðĕj���i�߂��u�W���َ��Ɓv�ɂ����āA�ĕj�̕Иr�Ƃ��ē����Ă����i�Ǝv����j�u��㏯���Y�i���b�j�v�ƌ����l���́A�]�˂Ő��w�m���J���Ă������J��O�i�Ђ�ށj�i1810�|1887�N�j�̍���ł������Ƃ����B���삳��Ɋm�F�����Ƃ���A���̂��Ƃ́A�u�a�Z�Ɛl�����T�i�S6���j�v�i���w�j�����p���A1964�N���j�́u6��1�v�i���̕����͍�������}���كf�W�^���R���N�V�����œǂ߂�j��A�u���C ���{���w�j�v�i��������⒘�A�O��`�v�ҁA���R������A�P���Ќ����t�A1981�N���A���Ȃ݂ɁA1918�i�吳7�j�N���̂��̂���������}���كf�W�^���R���N�V�����ɂ���j�ȂǂŊm�F�ł���Ƃ����B
�]�˂̒��J��m�i���w����j�Ƃ����A�֗��̒��J�슰�i1782�]1838�N�j���n�n�������w�m�ł���B���J�슰�́A�]�˂̒��l�i�b�艮�j�̏o�g�ŁA�ނ̏m�́A�����A�g���E���ʂ���Ȃ����w�m�Ƃ��ėL���������B���͐��U�A�q�������炸����q�̒��J��O�i�����o�ČS(�{�錧)�o�g�ŁA���̖��O�́A�����H�O�Y�ĐM�j��{�q�Ƃ��Ĉ�Ă��B�O�́A�{���̖v��A���J��m�����A2�㒷�J��P���q��𖼏�����B�O�q�̓�����a����̋L���ɂ́A�u�i��㏯���Y�́j1853�N����䏬�[�˂Ƃ��Ď�ɍ]�˂Őĕj�̂��Ŏg���Ă����悤���v�Ƃ����L�q������̂ŁA�����Y�́A�]�ˏZ�݂̂Ƃ��ɁA���J��m�ɓ��債�����̂Ǝv����B
�Ńg�b�v��
�@
���̘_�e�ŗp�����u���m���w�v�Ƃ������t�́A�����āu���m�v�Ő��܂�A�����ň�����u���w�v�݂̂��Ӗ����Ă���킯�ł͂Ȃ����Ƃ𒍈ӂ��Ă����B�u���w�v�̓C���^�[�i�V���i�������j�o�[�T���Ȃ��̂ŁA�����镶���́A�L����\�L�@�̈Ⴂ�͂����Ă��A���̔��˂����āu���w�v���Ƃ��Ċ܂�ł���̂���ʓI�ł���B�l�X�ȕ����ɂ�����u���w�v���݂��ɉe���������A�Z�����A���ꂳ��Č��݂́u���w�v���ł��Ă���B����������ƁA���݁A���������g�p���Ă���Z�p������10�i�ʎ��L���@�ł���B����͒x���Ƃ�7���I�ɂ̓C���h�ɂ����čL���g���Ă������Ƃ��킩���Ă���i[40]�Ap.57�j�B10�i�ʎ��L���@�ɂƂ��ẮA��ʂ�\�� �L��0���d�v�ł��邪�A���̋L���́A60�i�@�Ő���\���Ă����Ñ�M���V���̓V���w�ҒB�̋L�����痈�Ă���Ƃ�����������([40]�App.61�|62)�B���̃C���h�����ƈʎ��L���@��14���I����16���I�ɂ����ăA���r�A��ʂ��Đ����Љ�ɓ`������B10�i�����͌Ñ㒆���ɂ����������A���[���b�p�ŏ��߂Ďg�����̂�16���I�����̃I�����_�̃X�e���B���ł���B
�]�ˎ���̓��{�ɂ́A16���I���ɒ��N������{�ɓ����Ă��������̐��w������ɓƎ��ɔ��B�������w�������������B������u�a�Z�v�ƌĂԂ̂ɑ��āA16���I���ȍ~�A���[���b�p�l�̓��A�W�A�i�o�ɔ����A���{�ɂ����炳�ꂽ���w���u���m���w�v�ƌĂ�ł���B���������u���w�v�Ƃ������t�́A�䂪���ŏ��̊w��Ƃ������ׂ��u�������w��Ёv�̓����ψ���̌������o�āA1882�i����15�j�N��Mathematics�̖�Ƃ��č̗p���ꂽ���̂ł������BMathematics�̌�̂��ƂɂȂ����M���V����̌��`�́u�w��ׂ����́v�Ɖ]���Ӗ��ł���B�������A���[���b�p�Љ�ɂ����Ă��̌��t���Ӗ�������e�͎���ƂƂ��ɕς���Ă��邪�A�]�ˎ��������疖���ɂ����ē��{�Ŏg���Ă����u�Z�v�Ƃ��u�Z�p�v���Ӗ�������̂Ƃ́A���̍L����[���ɂ����ĈقȂ���̂ł������B
�u�����v�͉p��ł́A�ucivilization�v�ł��邪�A���̌�̓��e����́u���Ɓv���Ӗ�����u�V���B�^�X�v���痈�Ă���Ƃ����B�u���Ɓv�ƌĂׂ���ɔ��B�������G�ȎЉ�ł́A����p���Čv�Z������A�����A�ʐρA�̐ςȂǂ̗ʂ𑪒肷�邱�Ƃ͕K�{�Ȃ��Ƃł������B��������A���p�I�ȁu�Z�p�v�A�u�w�v�����܂ꂽ�B�u�Z�p�v���Ӗ�����p��́uarithmetic�v�́u����p���Čv�Z����Z�p�v�A�u�w�v���Ӗ�����p��́ugeometry�v�́u�n�ʁE�n���𑪂�v�Ƃ����Ӗ��ł���B���́u�Z�p�v�A�u�w�v�̑��ɐ��w�̌��ƂȂ��������Љ�ɋ��ʂ��������̂��̂́A�u�V���E��p�v�ł���B�_�ƂɂƂ��āA�G�߂̈ڂ�ς���m�邱�Ƃ͏d�v�Ȏ��ł������B�܂����̓����҂ɂƂ��āA�l�X�̎��Ԃ����邱�Ƃ͕K�v�Ȃ��Ƃł��������A���H�E���H��\�����邱�Ƃ͎���̌��Ђ����߂邤���Ŗ��ɗ������B�Ñ㒆���ɂ́A�c��͓V�̈ӎv���Đ������s�����̂ŁA�V�̈ӎv�͓V�����ۂɌ����Ƃ����v�z���������B������u�Ϗێv�Ƃ����B���̍l�����ɂ���ēV���ϑ��ɂ��萯�p�����B�����B���̂悤�Ȏ��͑����ꏭ�Ȃ���A������̕����ɂ����ʂ��邱�Ƃł���B�Ñ㗥�ߐ��̓��{�ɂ���������`���������̂ł͂��邪�A���̂悤�Ȏd���Ɍg���l�����������B�u��p�v�ɂ́A���̕��@�ɂ����āu���m�v�Ɓu���m�v�ł͈Ⴂ�������āA�u���m�v�ł́u�w�I���f���v��p���A�u���m�v�ł͖c��ȃf�[�^�����X�́u�V���萔�v�����߁A�����p���đ㐔�������𗧂ĉ����u�㐔�I�v�Z�v�ɂ���Ă����B�~�⋅��p�����w���f���ɂ��Ñ�M���V���E���[�}�����̓V���w�́A���[�}�鐭���̓V���w�ҁA�v�g���}�C�I�X�i�I��83�N�� �|168�N���A�p�̂̓g���~�[�j�́w�A���}�Q�X�g�x�S13���i�I��150�N�ȍ~�j�Ƃ��ē`����Ă���B
�����w���w�́A�Ñ�M���V���̃|���X���ƂƂ���ɑ����w���j�Y�����̍��X����ьÑネ�[�}�ɂ����鐔�w�����Ƃ�����̂ł����āA�u���[���b�p���w�v�ƌĂ�邱�Ƃ�����B���̐��w�ɂ�����u�Z�p�v�͎��p�I�Ȍv�Z�Ɋւ����̂ł͂Ȃ��A�u���v�̐��E�̖@�����i�Ⴆ�A���݁A�œ��̖��������Ƃ���Ă���A�f�����z�Ɋւ���u���[�}���\�z�v�Ȃǁj������������̂ŁA�u���_�v�ƌĂ��B�u�w�v�����p�I�ȑ��ʏp�ɌW�����̂ł͂Ȃ��A�u�C�f�A�v�Ƃ��Ă̊w�}�`�̐���������������̂ŁA�_���I�ȏؖ����d����B�s�s���ƃA�e�l�ɂ������v���g���i429�|347BC�j�̊w�Z�u�A�J�f�~�A�v�̓�����ɂ́A�u�w��m�炴��ғ���ׂ��炸�v�Ə����Ă������Ƃ������A����̓v���g���̓N�w�̒T���ɂ́u�w�v�ɕK�v�Ș_���I�ɋc�_��i�߂�d�������߂��Ă����Ƃ������Ƃł��낤�B�v���g���͐��w���s�^�S���X�i572�H�|492�HBC�j��c�Ƃ���w�h�̐��w�ҒB�Ɋw�Ɖ]���Ă��邪�A�s�^�S���X�̊w�h�́u���E�͐��Ȃ�v��M���Ƃ���閧���Ђ̂悤�Ȓc�̂ł������Ƃ����B���w�ɂ�����u�ؖ��v�́A�M���V�����w�ɓ��L�Ȃ��̂ł��邪�A�����I�F����ے肵�A�����v�҂̐��E�Ɍ��������Ƃ��咣�����G���A�w�h�̓N�w�ƃs�^�S���X�w�h�̐��w���o����Ƃɂ���Đ��܂ꂽ�Ƃ����i[41]�Ap.178�j�B�G���A�h�̓N�w�҂Ƃ��ẮA�p�����j�f�X�i515BC���j�A�[�m���i490BC���̐��܂�j���L���ł���B�v���g���̒�q�̃A���X�g�e���X�i384�|322BC�j�́A�t�̎���A�v���g���́u�A�J�f�~�A�v������A���̓r�ɂ����B�I���O342�N�A�}�P�h�j�A���s���b�|�X�̏������A���q�A���N�T���h���X�i�̂��̑剤�j�̗{��W�ɂȂ����B���̌�A�I���O335�N�ɃA�e�l�ɖ߂�A�ގ��g�̊w�Z�u�����P�C�I���v���J�����B�_���w�̊����ɂ���āA�w��̎x�z�������m�������̂̓A���X�g�e���X�ł���B�ނɂƂ��ẮA���o�Œm�o�ł���X�̎�������{�I���݂ł���A�t�v���g���́u�C�f�A�v�̊T�O�ɂ͔ᔻ�I������Ƃ����B�ނ́A�ώ@�Ɋ�Â����ؓI�Ȑ����w�̌������s���Ă���B�������[���b�p�ɂ����āA�A���X�g�e���X�̊w��̌n�́A�L���X�g���_�w�́u���Еt���v�ɗ��p����A�X�R���N�w�ނ��ƂɂȂ�B
���̌Ñ�M���V�����E�i�M���V�����p���镶�����j�ɂ����鐔�w�Ɋւ���m���́A�I���O300�N���̃G�W�v�g�E�A���L�T���h���A�̐��w�ҁA���[�N���b�h�ɂ���āA�w���_�x�i�w�X�g�C�P�C�A�x�j�S13���Ƃ��Ă܂Ƃ߂��Č㐢�ɓ`����ꂽ�B����́A�O������Ƃ��Ă̒�`�A�����A���ʊT�O����o�����Ę_����p���ĉ�㈓I�ɓ��o���ꂽ�藝�A����A�n����Ȃ�̌n�ł���B�Ȍ�A�w���_�x�̉�㈓I�L�q�̌`���̓��[���b�p�Љ�ɂ�����w�p���̋L�q�̎d���̃��f���ƂȂ����B
���[�N���b�h�́A�Ñ�M���V���Ɠ����̕������Z�������w���j�Y�����̃G�W�v�g�E�v�g���}�C�I�X���̐��w�҂ł��邪�A�����x��āA�V�`���A���̃C���N�T�ɃA���L���f�X�i287�H�|212BC�j���A���A�W�A�̃x���K�����ɃA�|����E�X�i262�H�|�HBC�j�����ꂽ�B�A���L���f�X�͒P�ɐ��w�҂ɂƂǂ܂炸�A�V���w�ҁA�����w�҂ł���A�Z�p�҂ł������B�ނ́A���q�╂�͂Ȃǒ��ځA�@�B�Ɋւ�邱�Ƃ���|���A���ۂɁA�u�R�N���A�X�i�����ނ�j�v�ƌĂ��A�������ݏグ��@�B�����Ă���B����́A���A�r���ɗ��p���ꂽ�B�܂��A���݂ł͐ϕ��ɂ���Čv�Z�����A��X�̋Ȑ��ň͂܂ꂽ���ʐ}�`�̖ʐρA���̐}�`�̕\�ʐς���ё̐ρA�����̗��̐}�`�̏d�S�����߂Ă���B�ނ������������w�́u�����v�ɁA�u���Ƃ���ɊO�ڂ���~���̑̐ς���ѕ\�ʐς̔�́A�Ƃ���2�F3�ƂȂ�v������B���w�̃m�[�x���܂Ƃ�����u�t�B�[���h�܁v�̃��_���̕\���ɂ́A�A���L���f�X�̏ё��ƃ��e����̖����A�u�Ȃ����߁A���E�𑨂���v���A���ʂɂ́A�u���Ƃ���ɊO�ڂ���~���v�����܂�Ă���B�A�|����E�X�́A�����w�~���Ȑ��_�x�̒��ŁA�㐢�ɓȐ��Ƃ��Ēm����悤�ɂȂ�A�������A�ȉ~�A�o�Ȑ��̐����𖾂炩�ɂ����B
�Ñ�M���V���E�w���j�Y�����̐��w�́A��ɑ������[�}�鍑�ɂ��p���ꂽ�B���[�}�鍑�́A395�N�ɓ������[�}�鍑�ɕ����̂��A�Q���}���l�̖k������̐N���ɂ��A476�N�Ƀ��[�}�𒆐S�Ƃ��鐼���[�}�鍑���łB���̌���A�v���g���A�A���X�g�e���X�����ꂼ��̑n�n�҂Ƃ���w�Z�A�u�A�J�f�~�A�v�Ɓu�����P�C�I���v�͓����[�}�鍑�i�r�U���`���鍑�j�ɂ����đ����������A529�N�A���X�e�B�j�A�k�X1���ɂ���ĕ����ꂽ�B����ɐ旧���A���[�}�鍑���ɂ̓L���X�g�������X�ɐZ�����Ă������A392�N�A�e�I�h�V�E�X1���ɂ���āA�u�O�ʈ�̔h�v�̃L���X�g�������[�}�鍑�́u�����v�ɒ�߂��Ă���B�u�A�J�f�~�A�v�Ɓu�����P�C�I���v�������ꂽ�̂́A�����ŋ������Ă������e���u�O�ʈ�̔h�v�̃L���X�g���̋��`�ɔ����鋰�ꂠ��Ƃ��ꂽ���߂ł���B�����̊w�Z�������̋��_�Ƃ��Ă����M���V���l�m���l�̒��ɂ́A�����[�}�鍑�̓G���ł��������̃T�T�����y���V���ɓ���A�z�X���[1���iKhusrau1�AKhosrow�A�݈ʁF531�|579�N�j�̕ی쉺�ɓ���҂����ꂽ�B�T�T�����y���V���̎�s�́A�`�O���X�쓌�݂̌Ñ�s�s�E�N�e�V�t�H���iCtesiphon�j�ł��邪�A���̓s�s�͒����ƒ��������ԁu�V���N���[�h�v�̗v�ՂƂ��ĉh�������ł������B
�����[�}�鍑�ƃT�T�����y���V���̊Ԃł́A���т��ѐ푈���N�������̂ŁA�A���r�A�����̐��C�݂ɉ����ĐV�������H���J���ꂽ���A���̌��H�ɂ������s�s�E���b�J�ɐ��܂ꂽ�}�z���b�g�i570�N���|632�N�j�ɂ���āA�C�X���������n�n���ꂽ�B�}�z���b�g�́A���Ƃ��Ƃ��̌��H�Œ��p�f�ՂɌg��鏤�l�ł������B�C�X�������̐��͂͏u���Ԃɐ������A�T�T�����y���V����|���A���݂̃g���R�A�C���N�A�C�����A�V���A�A�C�X���G���A�G�W�v�g�A�T�E�W�A���r�A�A�`���j�W�A�A�����b�R�A�X�y�C���Ɍׂ��鍑��z�����B����́u�C�X�����鍑�v�A�܂��́u�T���Z���鍑�v�ƌĂ��B�Ő����̓A�b�o�X���E�J���t�i750 �|1258�N�j�̎���ŁA�����ł́A�Ñ�G�W�v�g�����ƌÑ�o�r���j�A�����̊�b�̏�ɁA�A���r�A�A�y���V���A�M���V���A�C���h�A�����̕�����Z�������������h�����B762�N�A�J���t�A�A���E�}���\�[�iAl-Mansor�A�݈ʁF754�|775�N�j�́A�Ñ�o�r���j�A�̎�s�o�r�����̋߂��ɓs�s�o�N�_�[�g��z�������A���̒n�ɂ����āA���[�N���b�h�́w���_�x��v�g���}�C�I�X�́w�A���}�Q�X�g�x�Ȃǂ��A���r�A��ɖ|�ꂽ�B�w����镨��x�ŗL���ȃJ���t�A�n�[���[���E�A�b=���V�[�h�i763�|806�N�j���A�M���V���̉Ȋw���̃A���r�A��ւ̖|��𐄏���������ł���B�A�b=���V�[�h�̑��q�ő�8��J���t�̃A���E�}�A���[���́A803�N�Ɂu���҂̊فv�ƌĂ��w�p�����@�ւ����A�w�p�̋����ɐs�������B�Ñ�M���V���̐��w�Ƃ͈قȂ�^�C�v�̐��w�A�㐔�������̗��_�Ƒ㐔�w�����܂ꂽ�̂́A���̎���A���̒n��ɂ����Ăł���B820�N�Ƀo�N�_�[�g�̐��w�ҁA�A�����t���\���Y�~�[�́u�Ə���̌v�Z�̏��v�������A���̏��ɂ͑㐔�������̉�@�̋Z�@�Ƃ��āA�u�ڍ��i�W�F�u���[�A���W�F�u���j�v�Ɓu���ލ��Ȗ�v�̂��Ƃ�������Ă����B�㐔�w�i�A���W�F�u���j�̌�́A�u�ڍ��i�W�F�u���[�A���W�F�u���j�v���痈�Ă��邵�A�v�Z�菇�������u�A���S���Y���v�̌�́A�u�A�����t���\���Y�~�[�v�ɋA������B�������A��������\���L���́A���̎���ɂ͂܂��Ȃ������B���ꂪ�����̂́A16�A17���I�̐����[���b�p�ɂ����Ăł���B
�@�s�^�S���X�|�v���g���̊w���̊w�Z�A�u�A�J�f�~�A�v�ł�Mathematics�̓��e�́u���_�v�A�u�w�v�A�u���y�v�A�u�V���w�v�ł������B�u���_�v�A�u�w�v�́A���ꂼ��A�u�����w�v�i���̒����̔�Ɖ����Ƃ̊W�j�Ɓu�F���\���_�v�i�V���w�j�ƌ��т��Ă����B����Ɂu���@�v�A�u�C���w�v�A�u�ُ؏p�v�����������̂����R���w�|�Ƃ����A���[���b�p�������̋���E�C���@�t���̊w�Z���w�ɂ�����W���I�J���L�������ɂȂ����B12���I����n�܂�u���y�^���i���R���L�X�^�j�v��ʂ��āA8���I����12���I�ɂ����ĉh�����A���r�A�������C�x���A������ʂ��Đ����[���b�p�ɓ`����ꂽ�B���ɑ㐔�w�ƃA���r�A�����i=�C���h�����j��p�����v�Z�@�̗����͑傫�ȉe����^�����BMathematics �̓��e�ɕω��������̂́A���̍�����ł���B����͓����̐����[���b�p�ɂ�����s���K���̑䓪�ƌĉ����Ă����B���[�N���b�h�́w���_�x�����̃A���r�A�����̗�����ʂ��čĔ�������A�A���r�A�ꂩ�烉�e����ɖ|��ă��[���b�p�ɍL�܂����B�����ăA���r�A�������Ƃ���u�㐔�w�v�ƃ��[�N���b�h�́u���_�v�A�u�w�v�����т��āA17���I�Ƀf�J���g�́u��͊w�v�A�u�㐔�w�v�����܂ꂽ�B
�@���l�T���X���i14�|16���I�j�̎O�唭���Ɖ]���A�u�Ζ�v�A�u���j�Ձv�A�u���Ɗ��ň���p�v�ł��邪�A�����͂��ׂĒ����N���̂��̂ł���B�����̋Z�p�̓��[���b�p�ɂ����Ď��p������A���E��傫���ς��Ă������ƂɂȂ�B17���I�́u�Ȋw�v���v�́A1543�N�A�R�y���j�N�X�̒n�����̏��A�u�V���̉�]�ɂ��āv�̏o�łƂƂ��Ɏn�܂����Ɖ]���Ă悢�B���̌�A�e�B�R�E�u���|�G�A�K�����I�A�P�v���[���o�āA�j���[�g���i1642�|1727�N�j�̗͊w�Ɏ���B�e�B�R�E�u���|�G�̓f���}�[�N�̋M���ŁA�ɂ߂Đ��m����I�ȓV�̊ϑ����s���A�V�̂̉^�s�Ɋւ���ڍׂȋL�^���c�����B�P�v���[�̓e�B�R�̏���ł��������A�e�B�R�̓V���ϑ��f�[�^���g�p���ăP�v���[�̖@���������B�f���̉^���Ɋւ���P�v���[�̑ȉ~�O�����f���́A�u�j���[�g���̗͊w�v�̒a���ɏd�v�Ȗ������ʂ����Ă��邪�A���̃��f���̍���ɂ́A�Ñ�M���V���E���[�}�����̊w���f����p�����V���w�E��p�̓`�����������Ɖ]����̂ł͂Ȃ��낤���B1687�N�ɏo�ł��ꂽ�j���[�g���́u���R�N�w�̐��w�I�������i�v�����L�s�A�j�v�̋L�q�̎d���͋ɂ߂āu�w�I�v�Ȃ��̂ł���i[44]�j�B�u�ϗʂ̐��w�v�ł���u�����ϕ��w�v�̐����́A�u�V���w�v�ƒn��́u�͊w�i�^���w�j�v�ꂵ���u�j���[�g���̗͊w�v�̒a���i���L���͂Ɖ^���@���̔����j�Ɛ[�����т��Ă����B�����ŁA�u�����ϕ��w�v�́u�����v�Ƃ́A�����A�ϕ��́u�L���v�̑n�o�ƂƂ��ɁA���̔����A�ϕ��i�s��ϕ��j���A�݂��ɑ��̋t���Z�ɂȂ��Ă��邱�ƁA���Ȃ킿�A�u�����ϕ��w�̊�{�藝�v�́u�����v�ɂ���āA��X�́u�������v�Z�v���n���I�ɍs�����߂́u�A���S���Y���v���m�����ꂽ���Ƃ��Ӗ����Ă���B���݁A���������g���Ă���A�����E�ϕ��Ɋւ���L���ɂ��ẮA30�N�푈�i1618�|1648�N�j��̃h�C�c�����������̊w�ҁE�N�w�҂ł���A�O�����ł������A���C�v�j�b�c�i1646�|1716�N�j�ɕ����Ƃ��낪�傫���B
�Ńg�b�v��
[�P] �w���{���������j���W�� ��12���x�i�J�쌒��E�{�{���ҏW�A�O�ꏑ�[�A1971�N�j�����́u�F�������L�v�i����������w�����E�����Y���ɂ��u���v�A�u�⒍�v������j
[�Q] �w��������}���ق̃f�W�^���R���N�V���� �x�iURL: https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1901155/1�j�����́u�F�������L�v�i����31�N���s�̏��łƖ���35�N���s�̑�3�ł�����j
[�R] �u�F�����O�x�z�̍\���|���㖯�O�ӎ��̊�w��T��v�i�����������A����V�ЁA
2000�N�j
[�S] �u�����ېV�Ƌ��y�̐l�X�v�i�u�����ېV150���N�L�O���Ɓv�o�ŕ��A���������A2016�N�A�u�����ېV�Ǝs��̐l�X�|�����ېV��̏����̕�炵�v�A�u�����ېV�Ə����|���Ƃ̍ȁv�A�u�����ېV�Ǝq�ǂ��|�����̋���v�̍��j
[�T] �u�ՎR���s�^�v�i�F�s�{����Ǔ��W�A1901�N12���A��������}���كf�W�^���R���N�V�����j
[�U] �u�{�V�钬�j�v�i�{�V�钬�j�ҏW�ψ���ҁA�{�V�钬�A1974�N�i�ʂ�2000�N���̂��̂�����B����ɂ́u�ʍ������v�����Ă���j
[�V] �u���ܒ��l���`�v �i���ܒ����y�j������A2015�N11���j
[�W] �u���������̗��j�v�i���j�V���[�Y46�j�i�����Y���A�R��o�ŎЁA1973�N�j
[�X] �u���������̗��j�v�i���j�V���[�Y46�j�i������E�i�R�C��E���G����E������E�F�����꒘�A�R��o�ŎЁA1999�N�A2011�N���̑�2�ł�����j
[10] �u������������j�@��v�i�������������A1940�N�j
[11] �u������������j�@���v�i������������ψ���A1961�N�j
[12] �u���Ïd���v�i�F�������A�l���p���A�g��O���فA1980�N�j
[13] �u�����̎F���\�ߌ��̉��v�ҁA�������q��v�i�����Y���A�����V���A1966�N�j
[14] �u�����L���v�i�F�������A�l���p��191���A�g��O���فA1987�N�j
[15] �u�F�ˊC�R�j�@�㊪�v�i�����S�N�j�p����71���A��ݓ��ÉƕҎ[���ҁA�����[�A1968�N�j
[16] �u��v�ۗ������j����W5�|�����ېV�̗m�w�v�i�g��O���فA1986�N�j
[17] �u��v�ۗ������j����W�S�|�����ېV�Ƌ���v�i�g��O���فA1987�N�j
[18] �u�������F���˂̗m�w�ێ�ƊC�h�����ւ̎��H�v�i�R���E�P���A���ÏW���يw�|���A�u�����ېV150���N��茤���҈琬���ƌ������ʕ� ����28�N�x������30�N�x�v���������A2019�N�j
[19] �u�F���ˋ����m���Ɋւ����l�@�v�i�R���E�P���A���ÏW���ًI�v ��16���A
2017�N�j
[20] �u�F���l�ƃ��[���b�p�i����Łj�v�i�F�������A�������̗��j�V���[�Y�@�A����ЁA
1982�N�j
[21] �u�����ɂ����郈�[���b�p�w�p��e�̈�f�� �|���c�܊ςƍ��쒷�p�E���v�ԏێR�v
�i��K�M�v���A���C��w�o�ʼn�A1982�N�j
[22] �u�����E�������� ���w�ҌQ���i��j�����ҁv�i�������Y���A�g�����X�A1990�N�j
[23] �u�����E�������� ���w�ҌQ���i���j���������ҁv�i�������Y���A�g�����X�A1991
�N�j
[24] �u�L�a�t���v�i��������Y���A�k�z�V��ЁA1912�i�吳���j�N�A�L�a�͒����ˎm��
�������A�u���{�؏������v�̐��w�����߂��j�i���݂́uGoogle�u�b�N�X�v��
�������Ė����œǂނ��Ƃ��\�j
[25] �u�a�Z�\�]�˂̐��w�����v�i���쑩���A�����I��114�A2021�N�j
[26] �u����v�z�@���W�F�a�Z�̐��E�v�i�y�ЁAVol.49-8 �A2021�N�j
[27] �u���A�Ȃ��a�Z�Ȃ̂��v�i�c���O�Y�A���㐔�w�ЁA2015�N�j
[28] �u�X�L��v�i���ˍF�����A�l���p��188���A�g��O���فA1986�N�j
[29] �u�X�L��|�ߌ��ւ̏��́v�i�ђ|��W2�A�}�����[�A1986�N�j
[30] �u�����I�l�ԁv�i�ђ|��W6�A�}�����[�A1984�N�A�X�L��Ɠc������������
������j
[31] �u�O���@���|�O���������`�v�i�l�Ԃ̋L�^21�A���{�}���Z���^�[�A1997�N�j
[32] �u���w����j�\��̕����`�ԂɊւ�����j�I�����v�i���q���V�����A��g���X�A1932�N�j
[33] �u���{�̐��w100�N�j�@��v�i�u���{�̐��w100�N�j�v�ҏW�ψ���A��g���X, 1983.�N�j
[34] �u���ؒ厡�Ƃ��̎���|�����ߑ�̐��w�Ɠ��{�v�i�������m���A������w�o�ʼn�A2014�N�j
[35] �u���{�̐��w�@���m�̐��w�|��r���w�j�̎��݁v�i���c�S���A�����V��611�A1981�N�j
[36] �u�����_�V�T���i������j�v�i����@�g���A�ɓ����Y��A�c���w�o�ʼn�A2010�N�j
[37] �u���m�V���w�j�v�iMichael Hoskin���A�����@�m��AScience Palette�A�ۑP�o�ŁA2013�N�j
[38] �u���m�V���w�j�v�i�����@�m���AScience Palette�A�ۑP�o�ŁA2014�N�j
[39] �u�M���V�����w�̎n���v�i�A���p�b�h�E�T�{�[���A�����K�l�Y�E�������E���c�S���A�ʐ��w�o�ŕ��A1978�N�j
[40] �u���w���t���|�I���G���g����M���V���ցv�i���@���E�f���E���F���f�����A���c�S�E����������A�݂������[�A1984�N�j
[41] �u�M���V���l�̐��w�v�i�ɓ��r���Y���A�u�k�Њw�p���ɁA1990�N�j
[42] �u���[�N���b�h�w���_�x�̐����|�Ñ�̓`���ƌ���̐_�b�v�i�֓������A������w�o�ʼn�A1997�N�j
[43] �u�ߐ��̐��w�|�����T�O���߂����āv�i�����g���A�����܊w�|���ɁA2013�N�j
[44] �u�ÓT�͊w�̌`���|�j���[�g�����烉�O�����W���ցv�i�R�{�`�����A���{�]�_�ЁA1997�N�j
[45] �u�j�V�r���������w������`�i���R�@���i�̂ڂ�j���A�u�k�БI�����`�G168�A
1999�N�j
[46] �u�����M�����t��`�|�w�G�A�F���Ɋw�����̍��v�i�����Ӗ璘�A�P���ЁA
2000�N�j
[47] �w���m�̉ƌv��\�u����ˌ�Z�p�ҁv�̖����ېV�x�i��c���j���A�V���V���A2003�N�j
[48] �u�ߑ���{����F���̓�\���v�i�����A�W�W�ɁA2019�N�j
[49] �u�ߐ����{�̐l���\���v�i�֎R�����Y���A�g��O���فA1958�N�j
[50] �u�V�����̗��j�v�i���j�V���[�Y15�j�i�c���\��E�K�����j�E�����m��E���q�B�E�����`���E�{�Ԝ��꒘�A�R��o�ŎЁA1998�N�A2004�N���̑�3�ł�����j
[51]�u���Z�̌���ҁE�{�x���l�Y�́w�F�������L�x�ƒ����̐��w�v�i�؈䏺�A�������Z���������76 ���A2021 �N�Ap.10�j
[52] �u�z��l�E�{�x���l�Y�́w�F�������L�x�ƎF���̐��w�@�\���m���w��e�ߒ���ʂ��ē��{�̋ߑ㉻���l����|�v�i�؈䏺�A�u���{�̉Ȋw�ҁv2023�N8 �����Ap.45-p.53�j
[53]�u�z��l�E�{�x���l�Y�́w�F�������L�x�̒��́u�m�����v�ƎF���̐��w�v�i�؈䏺�A��������w���_�����̉�u������v�̃z�[���E�y�[�W�ihttps://www.kagoshimau.ac.jp/shoujukai/�j�u����̂Ђ�v�Ɍf�ځj
�ȏ�
�Ńg�b�v��
�@
�z��ň���������A�����甼���I���O�ɏ��߂ĎF���̒n�ɂ���ė������̑��
��ۂ́A�u�F�ʂ̑N�₩���v�A�u���ΎR�v�A�u��v�A�u�C�v�̎l��ɂ܂Ƃ߂���B�썑�̖��邢���z�̂��ƂŌ���A�n�C�r�X�J�X�A�u�[�Q���r���A�A�J�C�R�E�Y�i�C
�g���j�Ȃǂ̉Ԃ̐F�̑N�₩���͎��̐S���������Ă��ꂽ�B�܂��A�ߑ�I�s�s�̂����߂��Ɋ��ΎR�������グ�Ă��镗�i�ٍ͈��I�ł���A�E�s�ȎF���̋C��
���ے����Ă���悤�ł������B���������͕��n�����Ȃ��A���̂قƂ�ǂ������N�O�̉ΎR�����Ō`�����ꂽ�V���X��n�ł���B�������Ɂu��v�������̂͂��̂��ƂɗR������B����������X�Ɂu�C�v������������̂́A���͂��u�э]�p�v�Ƃ������C�ƁA�����m�A���V�i�C�̊O�C�Ɉ͂܂ꂽ�A�F���A����̓�̔�������Ȃ邹���ł���Ǝv���B�����𑽂������Ă��邱�Ƃ����̗��R�̈�ł��낤�B
�F���˂͖����ېV�ɂ����ďd�v�Ȗ������ʂ������B���̎F���̒n�ɕ�炵�Ă݂āA�F���ɂ́u���̕����v�����݂ł����X�Ɨ���Ă���Ɗ�����悤�ɂȂ����B�����ʼn]���u���̕����v�́A���ÉƂ𒆐S�Ƃ����������鉺�́u�鉺�m�v�́u���̕����v�����ł͂Ȃ��B�]�ˎ���̎F���ɂ́A�u���m�v�ƌĂ�锼�_���m�́u���m�v����R�������A����͎F���ɂ͕��n�����Ȃ��Ƃ����n���I�����Ɩ��W�ł͂���܂��B�u���m�v�͔˂���x�������\�͏��Ȃ��A����R������R�̏�̓y�n
���J�����ĎF�����⒃��������B�u���̕����v�Ƃ����Ƃ��A�������鉺�ȊO�̒n���ɏZ�ށu���m�v�w�́u���̕����v���܂߂čl����K�v������B
�F���˂͗��j�w�҂ɂ���āu�C�m���Ɓv�ƌĂ�邱�Ƃ�����B�F���˂͍]�ˎ���A���{���F�̂��Ƃɗ��������x�z���ɂ����A�����i���E���j�ƒ��v�f�Ղ��s�Ȃ��Ă����B����ɐ旧���A15 ���I�����̑Ζ��f�Ղ̉Ԍ`�������������́u�����v�̂��A�Ŋ����f�Ղł��D�ʂɗ����A���s�Ŏn�܂������m�̗��i1467 �| 1477�N�j�̊O�ɂ��āA���Ȃ���Ɨ����Ƃ̊ς��������Ƃ����B
���̌�A�z��ƎF���̗��j���w�Ԃ��Ƃɂ��A���j�̒��ŁA���̓�̒n�悪�ʂ�����������A�l�I�𗬂ɂ��ĊS�����悤�ɂȂ����B�V�����ɂ́A�M�Z��A������A�r��A��A�P��̌܂̈ꋉ�͐삪����B�����̉͐���������āA���̉�����̉��ϕ���ɟ��{�݂�����āA�č���ɂ����̂��z��
�ł���B�]�ˎ���̔_�Ƃ̒��S�́u�č��v�ł���������A���̈Ӗ��ŁA�z��́u�_�̕����v���\���Ă���Ɖ]���Ă悢�̂ł͂Ȃ����B�{�x���l�Y���������w�F�������L�x�́A�č�蒆�S�́u�_�̕����v������A���_���m�̋��m���Z�ށu���̕����v���ɂ���ė����A���m���ʼnz��l�́u�ٕ����̌��L�v�ł���Ɖ]����B
1990 �N��ɓ����āA�����p�ɂɊO���ɏo������悤�ɂȂ��Ă���́A���E�I���x���ł́u�ٕ��������v�A�u�ٕ����𗬁v�̑����F������Ɏ������B���̎������C�M���X�ݏZ�̃J�i�_�l�ƌ������A��l�̒j�q��݂����̂ŁA�v�X���̊���[�����Ă���B�l���Ă݂�A��l�̐l�ԂɂƂ��āA���l�́u�ٕ����I���݁v�ł�
��B���̈Ӗ��ŁA�l���x���ł̐l�Ɛl�Ƃ̌𗬂́u�ٕ����𗬁v�ł���A�u�ٕ��������v���O��ɂȂ��Ă���Ɖ]���Ă悢�B���A���E�ł͂��������Ő푈���J��
�L�����A�����̖��������Ă���B�푈������̂́u���v�ł��邪�A�u���v�Ɓu���v�Ƃ̐푈�́A�����ɂ�����~�߂���̂ł��낤���H�@���́A�u���v���z�������ԃ��x���ł̌𗬂�ɂ��A�l�Ɛl�Ƃ̘A�т��L���Ă��������Ȃ����낤�ƍl���Ă���B���̂��߂Ɂu�ٕ��������v�̐S��S�Ă̐l�����L����K�v������B�u�ٕ��������v�̐S�Ƃ́A�����𑊑Ή����A����̗���ɂȂ��čl���邱�Ƃł���B���́u�z��ƎF���v���A���̂悤�ȁu�ٕ��������v�̐S�œǂ�Œ������Ƃ��肤���̂ł���B�B�@�@�@
�Ńg�b�v��
 �i�Ԍ��t�F���E���S�j
�i�Ԍ��t�F���E���S�j �A
�A �i�Ԍ��t�F��M�j
�i�Ԍ��t�F��M�j
 �A
�n�C�r�X�J�X�i�Ԍ��t�F�V�������E�E���j
�A
�n�C�r�X�J�X�i�Ԍ��t�F�V�������E�E���j ���̐F�N�₩�ȓ썑�̉ԁX��m��̂����Ȃ����Ƃł���B�����̉Ԃ̐F�̑N�₩���́A�썑���L�̂��̂ŁA�l�X�̐S����������
�������̂�����B�썑�̖��邳�͂��̕ӂ��痈�Ă���̂��Ǝv���B
���̐F�N�₩�ȓ썑�̉ԁX��m��̂����Ȃ����Ƃł���B�����̉Ԃ̐F�̑N�₩���́A�썑���L�̂��̂ŁA�l�X�̐S����������
�������̂�����B�썑�̖��邳�͂��̕ӂ��痈�Ă���̂��Ǝv���B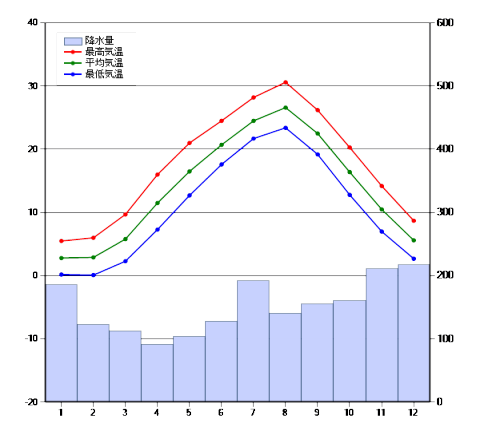
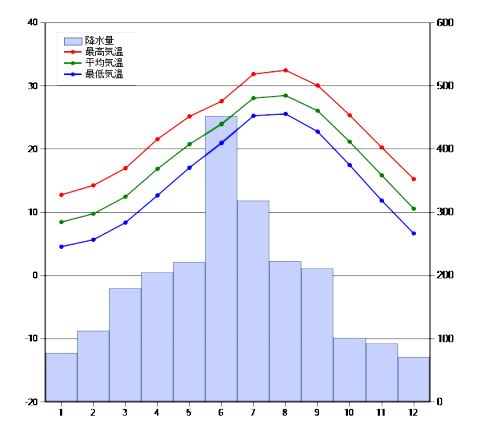
 ���n�ɍׂ₩�ȕ��l���g��������g���ĕ`�����₩�ȏĂ����ł���B���̏Ă����́A1598�N�A�L�b�G�g�̓�x�ڂ̒��N�o���i�c���̖��j�̋A���̍ۂɁA�F���̐퍑�喼�A
���Ë`�O�ɂ���ĘA�s���ꂽ���N�l���H�ɂ���Ă����炳�ꂽ���̂ł���Ƃ����B���̎q���̒��Ƃ́A���u�s���R�i�݂�܁j�ɍH�[���\���A���̋Z�����݂ɓ`���Ă���B
���n�ɍׂ₩�ȕ��l���g��������g���ĕ`�����₩�ȏĂ����ł���B���̏Ă����́A1598�N�A�L�b�G�g�̓�x�ڂ̒��N�o���i�c���̖��j�̋A���̍ۂɁA�F���̐퍑�喼�A
���Ë`�O�ɂ���ĘA�s���ꂽ���N�l���H�ɂ���Ă����炳�ꂽ���̂ł���Ƃ����B���̎q���̒��Ƃ́A���u�s���R�i�݂�܁j�ɍH�[���\���A���̋Z�����݂ɓ`���Ă���B
 �Ƃ́A�]�ˎ��ォ�疾������ɂ����ē��{�C�C�^�Ŋ����A��Ɂu���ς݁v�́u���D�v�̂��Ƃł���B�u���ς݁v�Ƃ́A���i��a������
�^������̂ł͂Ȃ��A�D�厩�̂��D�̊�`��Ŕ������ė��v�邱�Ƃ�ړI�ɁA���i���Đςݍ��ނ��Ƃ������B�u���D�v�Ƃ́A�`����`�֏���D�̂��Ƃł���B�u�k�O�D�v�̍q�H�́A
���͑Δn�C���ɍR���āA�k���Ȗk�̏��`����A���ւ��o�R���Đ��˓��C��ʂ��đ��Ɍ������i����͂��̋t�j�B�u�k�O�D�v�̍Ŗk�[�̊�`�n�͉ڈΒn�i�k�C���j�̍]���ł���B�z��ł́A
��D�A�V���A���i���n�j�A�o�_��A����A�����i�����]�Áj�Ȃǂ��k�O�D�̎�Ȋ�`�n�ł������B�����^���Ƃ����ƁA����ׁi�k�����ʁj�ɂ́A�ڈΒn�̐l�X�ւ�
��ށE���H�i�ށE�ߕ��p�i�E�����Ȃǂ̓��퐶���i�A���˓��C�e�n�̉��i���l�������ɕs���j�A���A�����A�āA��琻�i�i��E���V���j�A�X�C�i���Y�n�͐��˓��j�Ȃǂł������B���ׁi�E�����ʁj�́A
�w�ǂ��C�Y���ŁA
���i�_�앨�͔|�̂��߂̔엿�ł����ה��A���̎q�A�g�����j�V���A�����i�}�R�A���z�A����Ȃǂł������B���ɍ��z�͑�₩��i�܂��͒��肩��j�F�����o�āA����o�R�Œ�����
�܂Ŗ��A�o���ꂽ�Ƃ����B�k�C���A�z���A�F���A�����i����j�A���i�����j�܂ł̃��[�g���u���z���[�h�v�Ƃ������Ƃ�����Ƃ������A�k�́u�C�̓��v�Ɠ�́u�C�̓��v���A�u���z�v��ʂ��Č݂���
�q����A�����܂ʼn��тĂ����Ƃ��������́A��ϋ����[�����ƂɎv�����B
�Ƃ́A�]�ˎ��ォ�疾������ɂ����ē��{�C�C�^�Ŋ����A��Ɂu���ς݁v�́u���D�v�̂��Ƃł���B�u���ς݁v�Ƃ́A���i��a������
�^������̂ł͂Ȃ��A�D�厩�̂��D�̊�`��Ŕ������ė��v�邱�Ƃ�ړI�ɁA���i���Đςݍ��ނ��Ƃ������B�u���D�v�Ƃ́A�`����`�֏���D�̂��Ƃł���B�u�k�O�D�v�̍q�H�́A
���͑Δn�C���ɍR���āA�k���Ȗk�̏��`����A���ւ��o�R���Đ��˓��C��ʂ��đ��Ɍ������i����͂��̋t�j�B�u�k�O�D�v�̍Ŗk�[�̊�`�n�͉ڈΒn�i�k�C���j�̍]���ł���B�z��ł́A
��D�A�V���A���i���n�j�A�o�_��A����A�����i�����]�Áj�Ȃǂ��k�O�D�̎�Ȋ�`�n�ł������B�����^���Ƃ����ƁA����ׁi�k�����ʁj�ɂ́A�ڈΒn�̐l�X�ւ�
��ށE���H�i�ށE�ߕ��p�i�E�����Ȃǂ̓��퐶���i�A���˓��C�e�n�̉��i���l�������ɕs���j�A���A�����A�āA��琻�i�i��E���V���j�A�X�C�i���Y�n�͐��˓��j�Ȃǂł������B���ׁi�E�����ʁj�́A
�w�ǂ��C�Y���ŁA
���i�_�앨�͔|�̂��߂̔엿�ł����ה��A���̎q�A�g�����j�V���A�����i�}�R�A���z�A����Ȃǂł������B���ɍ��z�͑�₩��i�܂��͒��肩��j�F�����o�āA����o�R�Œ�����
�܂Ŗ��A�o���ꂽ�Ƃ����B�k�C���A�z���A�F���A�����i����j�A���i�����j�܂ł̃��[�g���u���z���[�h�v�Ƃ������Ƃ�����Ƃ������A�k�́u�C�̓��v�Ɠ�́u�C�̓��v���A�u���z�v��ʂ��Č݂���
�q����A�����܂ʼn��тĂ����Ƃ��������́A��ϋ����[�����ƂɎv�����B
 �ł������B
�ł������B
 �̂��Ƃ��u���t�������Ȃ���
�ތ����̂��̂̔@������̒��Ɏ����ݐ[�����������������v�Ɖ�z���Ă���Ƃ����B
�̂��Ƃ��u���t�������Ȃ���
�ތ����̂��̂̔@������̒��Ɏ����ݐ[�����������������v�Ɖ�z���Ă���Ƃ����B
 �̏ڂ����o����
�̏ڂ����o����