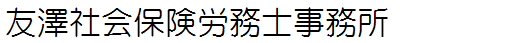| (56)特定業務委託事業者は、元委託者から元委託業務の対 |
| 価について、元委託業務に係る給付を行っている途中と、元 |
| 委託業務に係る給付を全て行った後とに分割して支払を受け |
| ます。この場合、特定業務委託事業者は、当該元委託業務に |
| ついて再委託を行った特定受託事業者に対し、対価が分割で |
| 支払われる各期日から30日以内に報酬を支払う必要があり |
| ますか。 |
| 特定業務委託事業者が、特定受託事業者との間で、再委託の場合における |
| 支払期日の例外の適用を受けることとした場合において、元委託者から特 |
| 定業務委託事業者に分割で対価が支払われるときは、元委託業務の対価の |
| 最後の支払日から30日以内に、当該特定受託事業者に対し報酬を支払う |
| 必要があります。また、特定業務委託事業者において、元委託業務の対価 |
| が特定業務委託事業者に分割で支払われる各期日から30日以内に特定受 |
| <託事業者に対して報酬を支払うことに特段の支障が無い場合には、当該特 |
| 定業務委託事業者は、元委託業務の対価が分割で支払われる各期日から3 |
| 0日以内に特定受託事業者に対し報酬を支払うことが望まれます。 |
| (57)特定受託事業者が請求書を提出してくれないので報酬 |
| の支払ができません。これは、「特定受託事業者の責めに帰 |
| すべき事由により支払うことができなかった」に該当します |
| か。 |
| 特定業務委託事業者は、特定受託事業者からの請求書の提出の有無にかか |
| わらず、給付を受領した日から起算して60日以内に定めた支払期日まで |
| に報酬を支払う必要があります。「特定受託事業者の責めに帰すべき事由 |
| により支払うことができなかったとき」とは、例えば、特定受託事業者が |
| 誤った口座番号を特定業務委託事業者に伝えていたため、特定業務委託事 |
| 業者は、支払期日までに報酬について払込みを実施していたにもかかわら |
| ず、口座番号の誤りのために支払期日までに特定受託事業者が実際には報 |
| 酬を受け取ることができなかったときが該当し、特定受託事業者が請求書 |
| を提出しないことは、これに該当しません。 |
| (58)本法の第5条では、特定受託事業者に対し業務委託をし |
| た場合に、特定業務委託事業者がしてはならない行為が定め |
| られています。具体的にどのような行為が禁止されているの |
| でしょうか。 |
| この規定では、以下のような7つの行為が禁止されています。 |
| ・「受領拒否」 |
| 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、発注した物品等の受領 |
| を拒否することです。発注の取消し、納期の延期などで納品物を受け取ら |
| ない場合も受領拒否に該当します。 |
| ・「報酬の減額」 |
| 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、発注時に決定した報酬 |
| を発注後に減額することです。協賛金の徴収、原材料価格の下落など、名 |
| 目や方法、金額にかかわらず、こうした減額行為が禁止されています。 |
| ・「返品」 |
| 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、発注した物品等を受領 |
| 後に返品することです。 |
| ・「買いたたき」 |
| 発注する物品・役務等に通常支払われる対価に比べ著しく低い報酬を不当 |
| に定めることです。通常支払われる対価とは、同種又は類似品等の市価で |
| す。 |
| ・「購入・利用強制」 |
| 特定受託事業者に発注する物品の品質を維持するためなどの正当な理由がな |
| いのに、特定業務委託事業者が指定する物(製品、原材料等)や役務(保険、 |
| リース等)を強制して購入、利用させることです。 |
| ・「不当な経済上の利益の提供要請」 |
| 特定業務委託事業者が自己のために、特定受託事業者に金銭や役務、その他 |
| の経済上の利益を不当に提供させることです。報酬の支払とは独立して行わ |
| れる、協賛金などの要請が該当します。 |
| ・「不当な給付内容の変更、やり直し」 |
| 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、発注の取消しや発注内容 |
| の変更を行ったり、受領した後にやり直しや追加作業を行わせる場合に、特 |
| 定受託事業者が作業に当たって負担する費用を特定業務委託事業者が負担し |
| ないことです。 |
| (59)特定業務委託事業者が特定受託事業者に対して行う業 |
| 務委託が1か月以上の期間行う業務委託に該当するかを判断 |
| する際、期間の始期と終期はどのように考えるのでしょうか。 |
| 単一の業務委託又は基本契約による場合の業務委託の期間の計算に当たって |
| の始期と終期の考え方は、それぞれ以下のとおりです。 |
| なお、業務委託の期間の計算に当たっては、始期となる日(初日)を算入し、 |
| 初日を1日目として算定します。 |
| <始期>次の日のいずれか早い日 |
| ①業務委託に係る契約を締結した日(3条通知により明示する業務委託をし |
| た日) |
| ②基本契約を締結する場合には、当該基本契約を締結した日 |
| <終期>次の日のいずれか遅い日 |
| ①3条通知により明示する「特定受託事業者の給付を受領し、又は役務の提 |
| 供を受ける期日」(ただし、期間を定めるものにあっては、当該期間の最終 |
| 日) |
| ②特定業務委託事業者と特定受託事業者との間で別途定めた業務委託に係る |
| 契約の終了する日 |
| ③基本契約を締結する場合には、当該基本契約が終了する日 |
| (60)特定業務委託事業者は、特定受託事業者との間で、2 |
| か月間有効となる基本契約を締結し、その2週間後に、給付 |
| を受領する期日を業務委託の日から10日後とする個別の業 |
| 務委託を行いました。この場合、当該個別の業務委託は、1 |
| か月以上の期間行う業務委託に該当するのでしょうか。 |
| 上記の事例において、個別の業務委託を行うより早く基本契約を締結してい |
| るため、業務委託の期間の計算に当たっての始期は、当該基本契約を締結し |
| た日となります。そして、当該個別の業務委託の給付を受領する日より後に |
| 基本契約の終了日が到来するため、当該業務委託の期間の計算に当たっての |
| 終期は、当該基本契約が終了する日となります。 |
| 当該基本契約を締結した日から終了する日までの期間は、1か月以上となり |
| ますので、当該個別の業務委託は、1か月以上の期間行う業務委託に該当し |
| ます。 |
| ※期間の算定方法の考え方については、問59を御参照ください。 |
| (61)特定業務委託事業者が、特定受託事業者に対して、給 |
| 付を受領する期日について業務委託をした日から25日後と |
| する業務委託を行い、3条通知による明示を行いました。し |
| かし、特定受託事業者のミスで作業が遅れた結果、給付を受 |
| 領した日が業務委託をした日から35日後になりました。こ |
| の場合、当該業務委託は、1か月以上の期間行う業務委託に |
| 該当するのでしょうか。 |
| 業務委託の期間の計算に当たって、終期を3条通知により明示する給付を受 |
| 領する期日として算定した場合、実際に給付を受領した日が、3条通知によ |
| り明示していた給付を受領する期日よりも前倒し又は後ろ倒しとなった場合 |
| であっても、業務委託の期間に変わりはありません。上記の事例において、 |
| 実際に給付を受領した日は後ろ倒しとなっていますが、業務委託の期間の計 |
| 算に当たっての終期は、3条通知により明示されていた「給付を受領する期 |
| 日」となります。そのため、当該業務委託は1か月以上の期間行う業務委託 |
| には該当しません。 |
| ※期間の算定方法の考え方については、問59を御参照ください。 |
| (62)特定業務委託事業者が、特定受託事業者に対して、給 |
| 付を受領する期日について業務委託をした日から20日後、 |
| 給付に係る検査期間を14日間、当該検査期間終了日を当該 |
| 業務委託に係る契約の終了する日とする業務委託を行い、3 |
| 条通知による明示を行いました。この場合、当該業務委託は、 |
| 1か月以上の期間行う業務委託に該当するのでしょうか。 |
| 3条通知により明示する給付を受領する期日より後の日に、業務委託に係る |
| 契約の終了する日を定めた場合には、業務委託の期間の計算に当たっての終 |
| 期は、給付を受領する期日ではなく当該業務委託に係る契約の終了する日と |
| なります。 |
| 上記の事例において、終期は、業務委託に係る契約の終了する日となります |
| ので、当該業務委託は1か月以上の期間行う業務委託に該当します。 |
| ※期間の算定方法の考え方については、問59を御参照ください。 |
| (63)契約の更新により継続して行うこととなる業務委託と |
| は、当該業務委託に係る前後の契約が、どのような関係にあ |
| るものをいうのでしょうか。 |
| 契約の更新により継続して行うこととなる業務委託というためには、当該業 |
| 務委託に係る前後の契約が |
| ①契約の当事者が同一であり、その給付又は役務の提供の内容が少なくとも |
| 一定程度の同一性を有すること |
| ②前の業務委託に係る契約又は基本契約が終了した日の翌日から、次の業務 |
| 委託に係る契約又は基本契約を締結した日の前日までの期間(空白期間)の |
| 日数が1か月未満であること |
| という2つの要件を満たす必要があります。 |
| (64)特定業務委託事業者であるA社が、ある特定受託事業 |
| 者に対して業務委託をしているところ、A社のグループ会社 |
| であるB社も、当該特定受託事業者に対して業務委託をする |
| ときは、A社の業務委託とB社の業務委託の時期が近接して |
| いる場合には、「契約の当事者が同一」であるといえるのでし |
| ょうか。 |
| 業務委託に係る前後の「契約の当事者が同一」であるかは、契約の当事者が |
| 法人である場合には、法人単位で判断します。 |
| 上記の事例においては、A社とB社はグループ会社であっても同一の法人で |
| はないため、業務委託に係る前後の契約の当事者は、同一とはいえません。 |
| したがって、A社とB社の業務委託の時期が近接していたとしても「契約の |
| 更新により継続して行うこととなる業務委託」には該当しません。 |
| (65)前後の業務委託に係る契約において「給付又は役務の |
| 提供の内容が少なくとも一定程度の同一性を有する」といえ |
| るのは、どのような場合でしょうか。 |
|
| 機能、効用、態様等を考慮要素として判断されます。その際は、原則として |
| 日本標準産業分類の小分類(3桁分類)を参照し、前後の業務委託に係る給 |
| 付等の内容が同一の分類に属するか否かで判断されます。 |
| なお、当事者間のこれまでの契約や当該特定業務委託事業者における同種の |
| 業務委託に係る契約の状況等に鑑み、通常、前後の業務委託は一体のものと |
| してなされている状況がある場合などは、上記の考慮要素から、個別に判断 |
| されます。 |