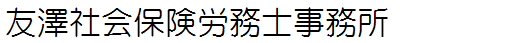| (21)業務委託の定義について、事業者が「その事業のため |
| 」に委託するとは、どのような場合が該当するのでしょうか。 |
| 法人である発注事業者については、法人が自身の事業の用に供するために |
| 行う委託行為は「事業のため」に委託する行為に該当します。ただし、法 |
| 人の事業は必ずしも定款に具体的に記載されている目的に限られるもので |
| はありません。 |
| また、個人である発注事業者については、事業者として契約の当事者とな |
| る場合も、消費者として契約の当事者となる場合もあり得るところ、個々 |
| の具体的な業務委託に応じて、当該個人が事業者として契約の当事者とな |
| っているといえる場合には「事業のため」に該当します。なお、発注事業 |
| 者(法人であるか個人であるかを問いません。)が純粋に無償の行為のた |
| めに行う委託は「事業のため」に委託する行為に該当しません。「事業者 |
| として契約の当事者となっているか」の判断の際には、 |
| ①契約締結の段階で、業務の内容が事業の目的を達成するためになされる |
| ものであることが客観的、外形的に明らかであるか、 |
| ②事業の目的を達成するためになされるか否かが客観的、外形的に明らか |
| でない場合には、消費者として当該業務委託に係る給付を受けることが想 |
| 定し難いものかを考慮します。 |
| (24)下請法上の製造・加工委託は同法第2条第1項において |
| 、業として行う販売の目的物たる物品等の製造、業として請 |
| け負う製造(加工を含む。)の目的物たる物品等の製造等を |
| 委託することであると規定されています。これに対して、本 |
| 法上の物品の製造・加工委託は、同法第2条第3項において |
| 「物品の製造(加工を含む。)…を委託すること」と規定さ |
| れていますが、両者の内容は異なるのでしょうか。 |
| 本法上の物品の製造・加工委託は、製造・加工を委託する目的物が、発注 |
| 事業者が業として行う販売の目的物又は業として請け負う製造の目的物に |
| 限定されないため、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120 |
| 号。以下「下請法」という。)上の製造・加工委託より広い範囲の製造委 |
| 託が対象となります。 |
| したがって、下請法においては、例えば、発注事業者が製造過程で用いる |
| 製造機械や工具の製造(自家製造している場合を除きます。)・加工を、 |
| 他の事業者に委託することは製造・加工委託に含まれませんが、本法にお |
| いては、発注事業者が事業のために他の事業者に物品の製造・加工を委託 |
| することは、全て物品の製造・加工委託に該当しますので、このような場 |
| 合も物品の製造・加工委託に該当することとなります。 |
| (29)発注事業者と受注事業者とのマッチングサービスを提供 |
| する事業者は、「業務委託事業者」に該当するのでしょうか。 |
| マッチングサービスを提供する事業者が、受注事業者との間で委託業務に |
| 係る業務委託契約を締結しておらず、実態としても発注事業者と受注事業 |
| 者との間の事務手続の代行(注文書の取次ぎ、報酬の請求、支払等)を行 |
| っているにすぎないような場合は、当該受注事業者に対して業務を委託し |
| ておらず単に仲介をしているだけであるため、当該受注事業者との関係で |
| は、マッチングサービスを提供する事業者は「業務委託事業者」とはなら |
| ず、発注事業者が「業務委託事業者」となります。 |
| 一方、マッチングサービスを提供する事業者が、受注事業者との間で委託 |
| 業務に係る業務委託契約を締結していない場合であっても、実質的に受注 |
| 事業者に対して業務委託をしているといえる場合は、当該受注事業者との |
| 関係では、発注事業者は「業務委託事業者」とはならず、マッチングサー |
| ビスを提供する事業者が「業務委託事業者」となります。 |
| 実質的に業務委託をしているといえるかは、委託の内容(物品、情報成果 |
| 物又は役務の内容、相手方事業者の選定、報酬の額の決定等)への関与の |
| 状況のほか、必要に応じて反対給付たる金銭債権の内容及び性格、債務不 |
| 履行時の責任主体等を、契約及び取引実態から総合的に考慮した上で判 |
| 断されます。 |
| (30)報酬は、現金以外でも支払うことができますか。 |
| 報酬は、できる限り現金(金融機関口座へ振り込む方法を含みます。)で |
| 支払わなければなりません。現金以外の方法で支払う場合には、当該支払 |
| 方法が、特定受託事業者が報酬を容易に現金化することが可能である等特 |
| 定受託事業者の利益が害されない方法でなければなりません。なお、金融 |
| 機関口座へ振り込む方法を採る場合、振込手数料を特定受託事業者に負担 |
| させることについて合意がないにもかかわらず、振込手数料の額を報酬の |
| 額から差し引くことや、振込手数料を特定受託事業者に負担させることに |
| ついて合意があったとしても金融機関に支払う実費を超えた振込手数料の |
| 額を報酬の額から差し引くことは、報酬の減額として本法上問題となるお |
| それがあります。 |